Of Grammatology
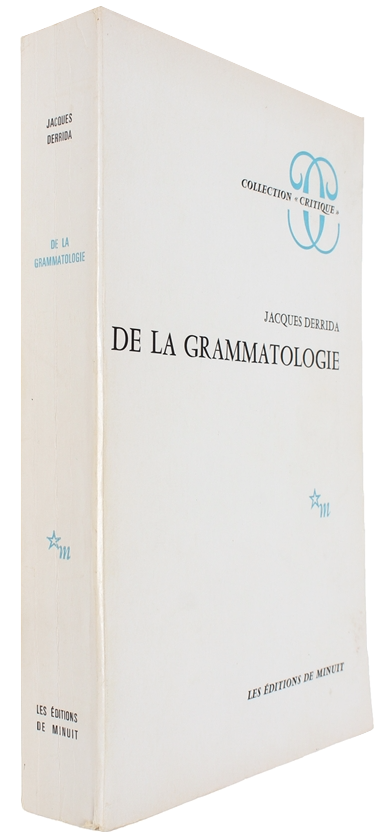
グラマトロジーについて
Of Grammatology
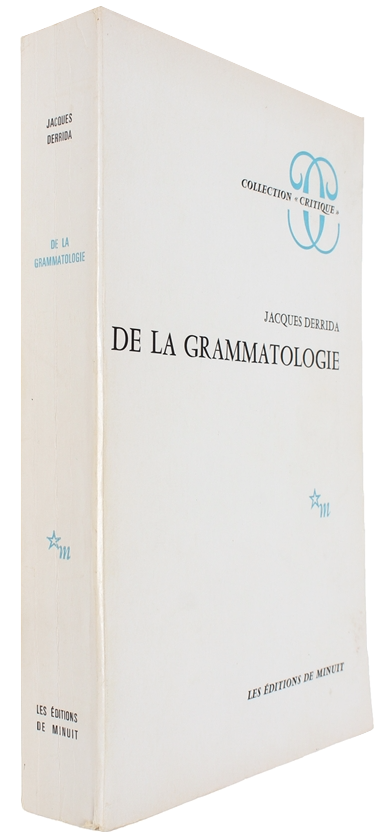
解説:池田光穂
『グラマトロジーについて』 (フランス語: De la grammatologie)は、フランスの哲学者ジャック・デリダによる1967年の著書である。脱構築の概念を生み出したこの著書では、大陸哲学全体において、特に言語や記号論の概念に携わる哲学者たちが、文字を音声から派生した ものとして誤って捉えてきたと主張している。文字は音声の真の「完全な存在」から「堕落」し、音声の独立した行為から「堕落」したものとなっている。
フランスの哲学者ジャック・デ リダ(1930~2004)は著書『グラマトロジーについて』の中で、ソシュールのロゴセントリックな論拠とされるものについて詳細に論じている。デリダ は、言語の表面的な内的な音韻論的システムを脱構築し、第2章「言語学とグラマトロジー」で、ソシュールの代表的な決定は、本質的理由から「...明示的 に機能する理想であり...決して完全に音声的ではない」と述べている。文字が音声的以外の機能を持ちうるという考えは、また、単に音声の表象以上のもの として機能するという考えは、デリダが「無限論的形而上学」と表現するものに帰結するロゴスの絶対的概念を可能にする。 ロゴス中心主義のプロジェクトのように、この存在の差異を実際に縮小することは決してできない。むしろ、意味の連鎖は存在と不在の痕跡となる。意味内容が もともと本質的に(そして、有限で創造された精神のみならず)痕跡であり、それが常にすでに記号の位置にあるという主張は、一見無害な命題であるが、ロゴ スの形而上学、存在と意識の形而上学は、その死と資源としての文章について熟考しなければならない。
☆ジャック・デリダのグラマトロジーにみられるエクリチュール論は、同時に技術論であり、発せられた声は、エクリチュールという技術のおかげて、拡張され、意味は遠隔地にまで運ばれる。つまりエクリチュールはテレコミュニケーションの一つである(林と廣瀬 2003:192)[→マーシャル・マクルーハン]
| Of
Grammatology (French: De la grammatologie) is a 1967 book by the
French
philosopher Jacques Derrida. The book, originating the idea of
deconstruction, proposes that throughout
continental philosophy, especially as philosophers engaged with
linguistic and semiotic ideas, writing has been erroneously considered
as derivative from speech, making it a "fall" from the real "full
presence" of speech and the independent act of writing. |
『グラマトロジーについて』(フランス語: De la
grammatologie)は、フランスの哲学者ジャック・デリダによる1967年の著書である。脱構築の概念を生み出したこの著書では、大陸哲学全体において、特に言語や記号論の概念に携わる哲学者たちが、文字を音声から派生した
ものとして誤って捉えてきたと主張している。文字は音声の真の「完全な存在」から「堕落」し、音声の独立した行為から「堕落」したものとなっている。 |
| Background The work was initially unsuccessfully submitted by Derrida as a Doctorat de spécialité thesis (directed by Maurice de Gandillac) under the full title De la grammatologie : Essai sur la permanence de concepts platonicien, aristotélicien et scolastique de signe écrit[1] (Of Grammatology: Essay on the Permanence of Platonic, Aristotelian and Scholastic Concepts of the Written Sign). |
背景 この論文は当初、デリダが専門博士論文(指導教官:モーリス・ド・ガンディヤック)として提出したが、不合格となった。論文の正式タイトルは次の通りであ る。De la grammatologie : Essai sur la permanence de concepts platonicien, aristotélicien et scolastique de signe écrit[1](「グラマトロジーについて:書かれた記号におけるプラトン的、アリストテレス的、スコラ哲学的概念の永続性に関する試論」)。 |
| Summary In Of Grammatology, Derrida discusses writers such as Claude Lévi-Strauss, Ferdinand de Saussure, Jean-Jacques Rousseau, Étienne Condillac, Louis Hjelmslev, Emile Benveniste, Martin Heidegger, Edmund Husserl, Roman Jakobson, Gottfried Wilhelm Leibniz, André Leroi-Gourhan, and William Warburton. In the course of the work he deconstructs the philosophies of language and the act of writing given by these authors, identifying what he calls phonocentrism, and showing the myriad aporias and ellipses to which this leads them. Derrida avoids describing what he is theorizing as a critique of the work of these thinkers, but he nevertheless calls for a new science of "grammatology" that would explore the questions that he raises about how to theorize the act of writing.[2] Of Grammatology introduced many of the concepts which Derrida would employ in later work, especially in relation to linguistics and writing.[3] |
概要 『グラマトロジーについて』において、デリダはクロード・レヴィ=ストロース、フェルディナン・ド・ソーシュール、ジャン=ジャック・ルソー、エティエン ヌ・コンディヤック、ルイ・イエルムスレー、エミール・ベンヴェニスト、マルティン・ハイデガー、エドムント・フッサール、ロマン・ヤコブソン、ゴットフ リート・ヴィルヘルム・ライプニッツ、アンドレ・レロワ=グーラン、ウィリアム・ウォーバートンといった作家について論じている。その作業の中で、彼はこ れらの著者が提示した言語哲学と書記行為を脱構築し、彼がフォノセントリズムと呼ぶものを特定し、それが無数のアポリアと省略につながることを示した。デ リダは、これらの思想家の業績に対する批判として、自身の理論を説明することを避けているが、それでもなお、彼が提起した「書く」という行為を理論化する 方法についての疑問を探究する「グラマトロジー」という新たな科学を求めている。 『グラマトロジーについて』では、デリダが後の著作で用いることになる概念の多くが紹介されている。特に、言語学や「書く」こととの関連で紹介されてい る。 |
| Publication history Of Grammatology was first published by Les Éditions de Minuit in 1967. The English translation by Gayatri Chakravorty Spivak was first published in 1976. A revised edition of the translation was published in 1997. A further revised edition was published in January 2016.[12] |
出版履歴 『グラマトロジー』は、1967年にレ・エディシオン・ド・ミニュイ社から初版が出版された。 ガヤトリ・C・スピヴァクによる英語訳は、1976年に初版が出版された。 改訂版は1997年に出版された。 さらに改訂された版は2016年1月に出版された。[12] |
| Reception Of Grammatology is one of three books which Derrida published in 1967, and which served to establish his reputation. The other two were La voix et le phénomène, translated as Speech and Phenomena, and L'écriture et la différence, translated as Writing and Difference. It has been called a foundational text for deconstructive criticism.[13] The philosopher Iain Hamilton Grant has compared Of Grammatology to the philosopher Gilles Deleuze and the psychoanalyst Félix Guattari's Anti-Oedipus (1972), the philosopher Luce Irigaray's Speculum of the Other Woman (1974), the philosopher Jean-François Lyotard's Libidinal Economy (1974), and the sociologist Jean Baudrillard's Symbolic Exchange and Death (1976), noting that like them it forms part of post-structuralism, a response to the demise of structuralism as a dominant intellectual discourse.[14] |
レセプション 『グラマトロジーについて』は、1967年にデリダが発表した3冊のうちの1冊であり、彼の名声を確立するのに役立った。他の2冊は、『声と現象』と訳さ れた『声と現象』と、『書記と差異』と訳された『書記と差異』である。この本は脱構築批評の基礎となるテキストと呼ばれている。 哲学者のイアン・ハミルトン・グラントは、『グラマトロジーについて』を、哲学者のジル・ドゥルーズと精神分析家のフェリックス・ガタリの『アンチ・オイ ディプス』(1972年)、哲学者のルース・イリガライの『他者の鏡』(1974年)、哲学者のジャン=フランソワ・リオタールの『リビドー経済』 (1974年)、社会学者のジャン・ボードリヤールの『象徴交換と死』(1976年)と比較し、それらと同様にポスト構造主義の一部を形成していると指摘 している。 フランソワ・リオタールの『リビドーの経済学』(1974年)、社会学者のジャン・ボードリヤールの『象徴交換と死』(1976年)などと同様に、支配的 な知的言説としての構造主義の終焉に対するポスト構造主義の一部をなすものとして位置づけられている。[14] |
| Editions De la grammatologie (Paris: Les Éditions de Minuit, 1967). Of Grammatology (Baltimore & London: Johns Hopkins University Press, 1976, trans. Gayatri Chakravorty Spivak). Of Grammatology (Baltimore & London: Johns Hopkins University Press, 1997, corrected edition, trans. Gayatri Chakravorty Spivak). |
エディション・ ドゥ・ラ・グラマトロジー(パリ:レ・エディシオン・ドゥ・ミニユ、1967年)。 グラマトロジーについて(ボルティモア&ロンドン:ジョンズ・ホプキンス大学出版、1976年、ゲイターリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク訳)。 グラマトロジーについて(ボルティモア&ロンドン:ジョンズ・ホプキンス大学出版、1997年、修正版、ゲイターリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク 訳)。 |
| Différance Logocentrism |
差延 ロゴセントリズム |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Of_Grammatology | |
|
Saussure and structuralism The book begins with a reading of Saussure's linguistic structuralism as presented in the Course in General Linguistics, and in particular signs, which for Saussure have the two separate components of sound and meaning. These components are also called signifier (signifiant) and signified (signifié).[4] Derrida quotes Saussure: "Language and writing are two distinct systems of signs; the second exists for the sole purpose of representing the first."[5] Highlighting the imbalanced dynamic between speech and writing that Saussure uses, Derrida instead offers the idea that written symbols are in fact legitimate signifiers on their own, and should not be considered as secondary, or derivative, relative to oral speech.[6] |
ソシュールと構造主義 この本は、ソシュールが『一般言語学講義』で提示した言語構造主義の解釈から始まり、特にソシュールが音と意味という2つの別個の要素を持つとした記号に ついて論じている。これらの要素は、シニフィアン(signifiant)とシニフィエ(signifié)とも呼ばれる。[4] デリダはソシュールの言葉を引用している。「言語と文字は、それぞれ独立した記号の体系である。文字は、言語を表現するという唯一の目的のために存在す る」[5] ソシュールが用いた音声と文字の間の不均衡な力学を強調する代わりに、デリダは文字の記号が実際にはそれ自体で正当なシニフィアンであり、口頭の音声に比 べて二次的、派生的なものとみなすべきではないという考えを提示している。[6] |
|
Reading of Rousseau Much of the second half of Of Grammatology consists of a sustained reading of Jean-Jacques Rousseau, especially his Essay on the Origin of Languages. Derrida analyzes Rousseau in terms of what he calls a "logic of supplementarity,"[7] according to which "the supplement is exterior, outside of the positivity to which it is super-added, alien to that which, in order to be replaced by it, must be other than it."[8] Derrida shows how Rousseau consistently appeals to the idea that a supplement comes from the outside to contaminate a supposedly pure origin (of language, in this case). This tendency manifests in many different binaries that Rousseau sets up throughout the Essay: writing supplements speech, articulation supplements accent, need supplements passion, north supplements south, etc.[9] Derrida calls these binaries a "system of oppositions that controls the entire Essay."[10] He then argues that Rousseau, without expressly declaring it, nevertheless describes how a logic of supplementarity is always already at work in the origin that it is supposed to corrupt: "This relationship of mutual and incessant supplementarity or substitution is the order of language. It is the origin of language, as it is described without being declared, in the Essay on the Origin of Languages."[11] |
ルソーの読解 グラマトロジーの後半の大部分は、ジャン=ジャック・ルソー、特に『言語の起源』の持続的な読解から構成されている。デリダは、彼が「補足性の論理」と呼 ぶ観点からルソーを分析している。[7] それによると、「補足物は外部にあり、それが付加される肯定性から外にあり、それによって置き換えられるためにはそれ以外の何者かでなければならないもの とは異質である」[8]。デリダは、ルソーが常に、補足物は外部からやって来て、本来は純粋であるはずの起源(この場合、言語の起源)を汚染するという考 えに訴えていることを示している。この傾向は、ルソーが『エクリチュール』全体を通じて設定する多くの異なる二項対立に表れている。すなわち、文字は音声 に補足され、発音はアクセントに補足され、必要性は情熱に補足され、北は南に補足される、などである。[9] デリダは、これらの二項対立を「『エクリチュール』全体を支配する対立の体系」と呼んでいる。[10] そして、ルソーはそれを明示的に宣言することなく、しかしながら、本来は汚染されるはずの起源において、補足性の論理が常にすでに作用していることを描写 していると論じている。「相互補完性または代替性の絶え間ない関係は、言語の秩序である。それは宣言されることなく、『言語起源論』で説明されているよう に、言語の起源である」[11] |
| References 1. Alan D. Schrift (2006), Twentieth-Century French Philosophy: Key Themes And Thinkers, Blackwell Publishing, p. 120. 2. Derrida 1997 3. Derrida 1997 4. Derrida 1997 5. Derrida 1997 6. Derrida 1997 7. Bernasconi, Robert. "Supplement". In Colebrook, Claire (ed.). Jacques Derrida : key concepts. Abingdon, Oxon. ISBN 9781844655892. OCLC 898081003. 8. Jacques, Derrida (1998). Of grammatology (Corrected ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. pp. 145. ISBN 0801858305. OCLC 39348029. 9. Rousseau, Jean-Jacques (1986). Essay on the Origin of Languages. Chicago, IL: University of Chicago Press. pp. 30–48. ISBN 978-0226730127. 10. Jacques., Derrida (1998). Of grammatology (Corrected ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. pp. 202. ISBN 0801858305. OCLC 39348029. 11. Jacques., Derrida (1998). Of grammatology (Corrected ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. pp. 235. ISBN 0801858305. OCLC 39348029. 12. "Of Grammatology". jhupbooks.press.jhu.edu. Retrieved 2016-04-11. 13. Rabinowitz, Nancy Sorkin (2008). Greek Tragedy. Malden, MA: Blackwell Pub. ISBN 978-1-4051-2160-6. p. 5: "Jacques Derrida's Of Grammatology, a foundational text for deconstructive criticism, works closely with Plato". 14. Jean-François Lyotard] and Iain Hamilton Grant (1993), Libidinal Economy, Indiana University Press, p. xvii. |
参考文献 1. アラン・D・シュリフト(2006)『20世紀フランス哲学:主要テーマと思想家』ブラックウェル出版、120頁。 2. デリダ 1997 3. デリダ 1997 4. デリダ 1997 5. デリダ 1997 6. デリダ 1997 7. バーナスコーニ、ロバート。「補遺」。コールブルック、クレア(編)。ジャック・デリダ:主要概念。アビンドン、オクソン。ISBN 9781844655892。OCLC 898081003。 8. ジャック・デリダ (1998). 『文法学について』 (修正版). ボルチモア: ジョンズ・ホプキンズ大学出版局. pp. 145. ISBN 0801858305. OCLC 39348029. 9. ルソー、ジャン=ジャック (1986). 『言語の起源に関するエッセイ』. イリノイ州シカゴ: シカゴ大学出版局. pp. 30–48. ISBN 978-0226730127. 10. ジャック、デリダ (1998). 『文法学について (修正版)』. ボルチモア: ジョンズ・ホプキンズ大学出版局. pp. 202. ISBN 0801858305. OCLC 39348029. 11. Jacques., Derrida (1998). Of grammatology (Corrected ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. pp. 235. ISBN 0801858305. OCLC 39348029. 12. 「文法学について」 jhupbooks.press.jhu.edu 2016-04-11 取得。 13. Rabinowitz, Nancy Sorkin (2008). Greek Tragedy. Malden, MA: Blackwell Pub. ISBN 978-1-4051-2160-6. p. 5: 「脱構築批評の基礎となるテキストであるジャック・デリダの『文法学』は、プラトンと密接に関連している」。 14. ジャン=フランソワ・リオタール] および イアン・ハミルトン・グラント (1993)、『リビディナル・エコノミー』、インディアナ大学出版、p. xvii。 |
| Sources Derrida, Jacques (1997). Of Grammatology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-5830-5. Further reading Bradley, Arthur. Derrida's Of Grammatology (Edinburgh: University of Edinburgh Press, 2008). Culler, Jonathan. On Deconstruction (Ithaca: Cornell University Press, 1982). de Man, Paul. "The Rhetoric of Blindness: Jacques Derrida's Reading of Rousseau," in Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983, second edition) 102-41. Harris, Roy. Interpreters of Saussure (Edinburgh: University of Edinburgh Press, 2001) 171-188. https://en.wikipedia.org/wiki/Of_Grammatology |
出典 デリダ、ジャック (1997). 『文法学について』. ボルチモア: ジョンズ・ホプキンズ大学出版局. ISBN 0-8018-5830-5. 追加文献(さらに読む) ブラッドリー、アーサー。『デリダの「文法学」について』(エディンバラ:エディンバラ大学出版、2008年)。 カラー、ジョナサン。『脱構築について』(イサカ:コーネル大学出版、1982年)。 デ・マン、ポール。「盲目のレトリック:ジャック・デリダのルソーの読み方」、『盲目と洞察:現代批評のレトリックに関するエッセイ』(ミネアポリス:ミネソタ大学出版、1983年、第2版)102-41。 ハリス、ロイ。『ソシュールの解釈者たち』(エディンバラ:エディンバラ大学出版局、2001年)171-188頁。 |
| "Logocentrism" is
a term
coined by the German philosopher Ludwig Klages in the early 1900s.[1]
It refers to the tradition of Western science and philosophy that
regards words and language as a fundamental expression of an external
reality. It holds the logos as epistemologically superior and that
there is an original, irreducible object which the logos represent.
According to logocentrism, the logos is the ideal representation of the
Platonic ideal. |
「ロゴセントリズム」とは、1900年代初頭にドイツの哲学
者ルートヴィヒ・クラゲスが作った造語である。[1]
これは、言葉や言語を外部の現実の根本的な表現とみなす西洋の科学と哲学の伝統を指す。ロゴスを認識論的に優れているとし、ロゴスが表現する元来の還元不
可能な対象があるとする。ロゴセントリズムによれば、ロゴスはプラトニックな理想の理想的な表現である。 |
| In linguistics According to Jacques Derrida, with the logos as the site of a representational unity, linguistics dissects the structure of the logos further and establishes the sound of the word, coupled with the sense of the word, as the original and ideal location of metaphysical significance. Logocentric linguistics proposes that "the immediate and privileged unity which founds significance and the acts of language is the articulated unity of sound and sense within the phonic."[2] As the science of language, linguistics is a science by way of this semiotic phonology. It follows, therefore, that speech is the primary form of language and that writing is secondary, representative, and, importantly, outside of speech. Writing is a "sign of a sign"[3] and, therefore, is basically phonetic. Jonathan Culler in his book Literary Theory: A Very Short Introduction says: Traditionally, Western philosophy has distinguished "reality" from "appearance," things themselves from representations of them, and thought from signs that express it. Signs or representations, in this view, are but a way to get at reality, truth, or ideas, and they should be as transparent as possible; they should not get in the way, should not affect or infect the thought or truth they represent. In this framework, speech has seemed the immediate manifestation or presence of thought, while writing, which operates in the absence of the speaker, has been treated as an artificial and derivative representation of speech, a potentially misleading sign of a sign (p. 11). This notion that the written word is a sign of a sign has a long history in Western thought. According to Aristotle (384 BC – 322 BC), "Spoken words are the symbols of mental experience and written words are the symbols of spoken words."[4] Jean-Jacques Rousseau similarly states, "Writing is nothing but the representation of speech; it is bizarre that one gives more care to the determining of the image than to the object."[5] Derrida’s critique of logocentrism examines the limitations of linguistic systems that prioritize speech over writing and assume a direct, stable connection between language and meaning. He argues that traditional linguistics fails to be "general" as it remains bound by rigid distinctions—between inside and outside, essence and fact—which prevent a complete understanding of language's structure. For Derrida, writing isn't merely a secondary "image" or representation of speech; rather, it challenges the very notion of a pure linguistic core. He suggests that if signs always refer to other signs, then writing is inherent within language itself, not a detached representation. This concept undermines the idea of language as a transparent tool for representing a stable reality. Derrida identifies this bias, logocentrism, as central to Western metaphysical thought, which privileges "presence" and direct expression in speech. This bias has stifled deeper inquiry into writing's origin and role, reducing it to a mere technical tool rather than acknowledging it as fundamental to meaning-making. Consequently, logocentrism restricts linguistic theory, making it impossible to fully explore the complex, interconnected nature of language and writing. [6] |
言語学において ジャック・デリダによると、ロゴスを表現の統一の場として、言語学はロゴスの構造をさらに細分化し、言葉の意味と結びついた言葉の音を、形而上学的意義の 原初的かつ理想的な場所として確立する。ロゴセントリック言語学は、「言語の意味と行為を基礎づける即時的かつ特権的な統一性は、音声内の音と意味の明確 な統一性である」と提案している[2]。言語学は言語の科学であり、この記号論的音声学による科学である。したがって、音声が言語の第一形態であり、文字 は第二形態であり、代表的なものであり、そして重要なのは、音声の外にあるということになる。文字は「記号の記号」であり[3]、したがって基本的に音声 記号である。 ジョナサン・カラーは著書『文学理論:超入門』で次のように述べている。 伝統的に西洋哲学では、「現実」と「外見」、物事そのものとそれらの表現、思考とそれを表現する記号を区別してきた。この見解では、記号や表現は現実、真 実、あるいは考えに近づくための手段にすぎず、可能な限り透明であるべきであり、思考や真実を表現する際に邪魔になったり、影響を与えたり、感染したりし てはならない。この枠組みでは、話し言葉は思考の即時的な顕在化または存在であると考えられてきた。一方、話し手の不在の中で機能する書き言葉は、話し言 葉の人工的で派生的な表現であり、誤解を招く可能性のある記号の記号であるとみなされてきた(11ページ)。 文字は記号の記号であるという考え方は、西洋思想において長い歴史を持っている。 アリストテレス(紀元前384年 - 紀元前322年)は、「発話された言葉は精神経験の象徴であり、文字は発話された言葉の象徴である」と述べている。[4] ジャン=ジャック・ルソーも同様に、「文字は発話の表現に他ならない。対象よりもイメージの決定に多くの注意を払うのは奇妙なことだ」と述べている。 [5] デリダのロゴセントリズム批判は、言語を音声よりも文字を優先し、言語と意味の間に直接的な安定したつながりがあるとする言語システムの限界を検証するも のである。 デリダは、従来の言語学は「一般」たり得ていないと主張する。その理由は、言語の構造を完全に理解することを妨げる、内側と外側、本質と事実といった硬直 した区別に縛られているからだ。 デリダにとって、文字は単に言語の二次的な「イメージ」や表現ではなく、むしろ純粋な言語の核という概念そのものを問い直すものなのである。 デリダは、記号が常に他の記号を参照するものであるならば、文字は言語そのものに内在するものであり、切り離された表現ではないと主張している。 この概念は、安定した現実を表現するための透明な道具としての言語という考え方を否定するものである。 デリダは、このバイアス、ロゴセントリズムを西洋形而上学思想の中心に位置づけ、言語における「プレゼンス」と直接的な表現を優先するものとしている。こ のバイアスは、文字の起源と役割に関するより深い探究を妨げ、文字を意味の創造に不可欠なものとして認めず、単なる技術的なツールに還元してきた。その結 果、ロゴセントリズムは言語理論を制限し、言語と文字の複雑に絡み合った相互関係の性質を十分に探究することを不可能にしてきた。[6] |
| Saussure Ferdinand de Saussure (1857–1913), it is claimed by Derrida, follows this logocentric line of thought in the development of his linguistic sign and its terminology. Where the word remains known as the whole sign, the unification of concept and sound-image becomes the unification of the signified and the signifier respectively.[7] The signifier is then composed of an indivisible sound and image whereby the graphic form of the sign is exterior. According to Saussure in his Course in General Linguistics, "The linguistic object is not defined by the combination of the written word and the spoken word: the spoken form alone constitutes the object."[8] Language has, he writes, "an oral tradition that is independent of writing."[9] |
ソシュール フェルディナン・ド・ソシュール(1857年~1913年)は、言語記号とその用語法の発展においてロゴ中心的な思考を貫いていると、デリダは主張してい る。言葉が全体としての記号として知られている場合、概念と音像の統一は、それぞれ意味内容と記号の統一となる。[7] 記号は、不可分の音とイメージから構成され、記号の視覚的形態は外部にある。 ソシュールは『一般言語学講義』の中で、「言語の対象は、書かれた言葉と話された言葉の組み合わせによって定義されるものではない。話された形のみが対象 を構成する」と述べている。[8] また、ソシュールは「言語には、文字とは独立した口頭伝承がある」とも述べている。[9] |
| Derrida French philosopher Jacques Derrida (1930–2004) in his book Of Grammatology responds in depth to what he believes is Saussure's logocentric argument. Derrida deconstructs the apparent inner, phonological system of language, stating in Chapter 2, Linguistics and Grammatology, that in fact and for reasons of essence Saussure's representative determination is "...an ideal explicitly directing a functioning which...is never completely phonetic".[10] The idea that writing might function other than phonetically and also as more than merely a representative delineation of speech allows an absolute concept of logos to end in what Derrida describes as infinitist metaphysics.[11] The difference in presence can never actually be reduced, as was the logocentric project; instead, the chain of signification becomes the trace of presence-absence.[12] That the signified is originarily and essentially (and not only for a finite and created spirit) trace, that it is always already in the position of the signifier, is the apparently innocent proposition within which the metaphysics of the logos, of presence and consciousness, must reflect upon writing as its death and its resource.[13] |
デリダ フランスの哲学者ジャック・デリダ(1930~2004)は著書『グラマトロジーについて』の中で、ソシュールのロゴセントリックな論拠とされるものにつ いて詳細に論じている。デリダは、言語の表面的な内的な音韻論的システムを脱構築し、第2章「言語学とグラマトロジー」で、ソシュールの代表的な決定は、 本質的理由から「...明示的に機能する理想であり...決して完全に音声的ではない」と述べている。[10] 文字が音声的以外の機能を持ちうるという考えは、 また、単に音声の表象以上のものとして機能するという考えは、デリダが「無限論的形而上学」と表現するものに帰結するロゴスの絶対的概念を可能にする。 [11] ロゴス中心主義のプロジェクトのように、この存在の差異を実際に縮小することは決してできない。むしろ、意味の連鎖は存在と不在の痕跡となる。[12] 意味内容がもともと本質的に(そして、有限で創造された精神のみならず)痕跡であり、それが常にすでに記号の位置にあるという主張は、一見無害な命題であ るが、ロゴスの形而上学、存在と意識の形而上学は、その死と資源としての文章について熟考しなければならない。 |
| In literary theory Inherent in Saussure's reasoning, a structuralist approach to literature began in the 1950s [14] to assess the literary text, or utterance, in terms of its adherence to certain organising conventions which might establish its objective meaning. Again, as for Saussure, structuralism in literary theory is condemned to fail on account of its own foundation: '...language constitutes our world, it doesn't just record it or label it. Meaning is always attributed to the object or idea by the human mind, and constructed by and expressed through language: it is not already contained within the thing'.[15] There is no absolute truth outside of construction no matter how scientific or prolific that construction might be. Enter Derrida and post-structuralism. Other like-minded philosophers and psychoanalysts who have notably opposed logocentrism are Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger and Freud, as well as those who have been influenced by them in this vein.[16] Literary critic Roland Barthes (1915–1980), with his essay The Death of the Author (1968), converted from structuralism to post-structuralism. For the post-structuralist the writer must be present in a kind of absence, or 'dead', according to Barthes; just as the reader is absent in a kind of presence at the 'moment' of the literary utterance. Post-structuralism is therefore against the moral formalism of the Western literary tradition which maintains only The Greats should be looked to for literary inspiration and indeed for a means of political control and social equilibrium. Modernism, with its desire to regain some kind of lost presence, also resists post-structuralist thought; whereas Post-modernism accepts the loss (the loss of being as 'presence') and steps beyond the limitations of logocentrism. |
文学理論において ソシュールの論理に内在する構造主義的アプローチは、1950年代に始まり、文学的なテキスト、すなわち発話を、その客観的な意味を確立する可能性のある 特定の組織化の慣例への準拠という観点から評価するようになった。 ソシュールの場合と同様に、文学理論における構造主義は、その基礎自体が原因で失敗に終わる運命にある。「...言語は我々の世界を構成するものであり、 それを記録したり、ラベル付けするだけのものではない。意味は常に人間の心によって対象や概念に付与され、言語によって構築され、表現される。それは物事 の中にすでに含まれているものではない。[15] 構築物以外の場所に絶対的な真実など存在しない。その構築物がどれほど科学的であろうと、またどれほど多産であろうと。デリダとポスト構造主義が登場す る。 ロゴセントリズムに明確に反対した思想家や精神分析家には、ニーチェ、ウィトゲンシュタイン、ハイデガー、フロイトなどがおり、また、彼らから影響を受け た思想家もいる。[16] 文学評論家のロラン・バルト(1915-1980)は、著書『作者の死』(1968年)で構造主義からポスト構造主義へと転向した。 ポスト構造主義者にとって、作家は一種の不在、すなわち「死」でなければならないとバルトは主張する。文学的表現の「瞬間」において、読者は一種の存在で あるが不在であるのと同様に。したがって、ポスト構造主義は、偉大な作家だけが文学的インスピレーションの源であり、政治的統制や社会の均衡を保つ手段で あると主張する西洋の文学的伝統の道徳的形而上学に反対する。 モダニズムは、失われた存在感を何らかの形で取り戻そうとするが、ポスト構造主義的な思考にも抵抗する。一方、ポストモダニズムは、その喪失(「プレゼン ス」としての存在の喪失)を受け入れ、ロゴセントリズムの限界を乗り越える。 |
| In non-Western cultures Some researchers consider that logocentrism may not be something which exists across all cultures, but instead has a particular bias in Western culture. Dennis Tedlock's study of stories in the Quiché Maya culture[17] leads him to suggest that the development of alphabetic writing systems may have led to a logocentric perspective, but this is not the case in all writing systems, and particularly less prevalent in cultures where writing has not been established. Tedlock writes, "The voice is linear, in [Derrida's] view; there is only one thing happening at a time, a sequence of phonemes,"[18] and this is reflected in writing and even the study of language in the field of linguistics and what Tedlock calls "mythologics (or larger-scale structuralism)",[19] "are founded not upon a multidimensional apprehension of the multidimensional voice, but upon unilinear writing of the smallest-scale articulations within the voice."[20] This one-dimensionality of writing means that only words can be represented through alphabetic writing, and, more often than not, tone, voice, accent and style are difficult if not impossible to represent. Geaney,[21] in writing about ming (names) in early Chinese reveals that ideographic writing systems present some difficulty for the idea of logocentrism, and that even Derrida wrote of Chinese writing in an ambivalent way, assuming firstly that "writing has a historical telos in which phonetic writing is the normal 'outcome'",[22] but also "speculat[ing] without irony about Chinese writing as a 'movement of civilization outside all logocentrism'".[23] |
西洋以外の文化では 一部の研究者は、ロゴセントリズムはすべての文化に共通するものではなく、むしろ西洋文化に特有の偏見であると考える。デニス・テッドロックによるキ チェ・マヤ文化の物語の研究[17]では、アルファベットの文字体系の発展がロゴセントリックな視点につながった可能性を示唆しているが、これはすべての 文字体系に当てはまるわけではなく、特に文字が確立されていない文化ではあまり見られない。テッドロックは、「デリダの見解では、声は直線的であり、一度 に起こることは1つだけで、音素の連続である」[18]と記している。これは、言語学の分野における文章や言語の研究、さらにはテッドロックが「神話学 (または大規模な構造主義)」と呼ぶものにも反映されている。 9] 「多声の多次元的な把握ではなく、声の中の最小規模の分節化を一次元的に書き表すことに基づいている」[20] 文字による表現の一次元性は、アルファベット文字では単語しか表現できないことを意味し、多くの場合、トーン、声、アクセント、スタイルは表現が不可能で あるか、表現が困難である。ゲーニー(Geaney)[21]は、初期の中国における名(名前)について書いている中で、表意文字の文字体系はロゴセント リズムの考え方にとっていくらか困難であることを明らかにし、デリダでさえも、まず「 表音文字が通常の『結果』である歴史的な目的を持つ」と仮定しているが、同時に「『あらゆるロゴセントリズム(言語中心主義)を超越した文明の運動』とし ての中国文字について、皮肉を込めずに思索している」[23]。 |
| Metaphysics of
presence Deconstruction Différance Phallogocentrism Phonocentrism Apollonian and Dionysian |
プレゼンスの形而上学 脱構築 差延 男根中心主義 音声中心主義 アポロ的とディオニュソス的 |
| Metaphysics of presence (German:
Metaphysik der Anwesenheit) is a view held by Martin Heidegger in Being
and Time that holds the entire history of Western philosophy is based
on privileging presence over absence.[1][2] https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysics_of_presence |
存在の形而上学(ドイツ語:Metaphysik der
Anwesenheit)は、マルティン・ハイデガーが『存在と時間』で唱えた見解であり、西洋哲学の歴史全体は、不在よりも存在を優先することに基づい
ているというものである。[1][2] |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Logocentrism |
★差 延 (さえん、différance)について
| 差 延 (さえん、différance) とは、哲学者ジャック・デリダによって考案された「語でも概念でもない」とされる造語。 およそ何者かとして同定されうるものや、自己同一性が成り立つためには、必ずそれ自身との完全な一致からのズレや違い・逸脱などの、常に既にそれに先立っ ている他者との関係が必要である。このことを示すために、差延という方法が導入された。 論理を簡略に述べれば、同定や自己同一性は、主語になるものと述語になるものの二つの項を前提とする(「AはAである」)。そのため主体や対象は反復され 得なければならない。「同じである」ということは二つの項の間の関係であり、自己同一性においてもその事情は変わらない。自己自身が差異化することによっ て初めてそれが複数の「同じ」であるが「別の」項として二重化しうる。そして初めて、同定や自己同一性が可能となる。 このことはそれ自身に完全に一致し、他を成立のために必要とせず、他に制約されておらず自己充足した根本的で特権的なもの、「他のもののうちにあり、他の ものによって考えられるのではないもの(スピノザ『エチカ』実体の定義)」というのは、たとえ概念の世界だけであっても副次的に構築された名目的概念とし てよりほかにはありえない、ということを意味する。 差延は、再帰的な性質を持つが、このとき、この再帰を媒介する他の項は、あくまでも不在の形で、自己の側に残された、自己の側の対応する痕跡から遡及的に 確認されるにすぎない。しかし他方でこの痕跡はそうした不在の媒介項を前提とし、痕跡の刻まれた項が自己充足することを許さない。 原・痕跡、あるいは原・エクリチュールとも表現される。 |
|
| 表記 フランス語の名詞 différence (差異)は動詞 différer に由来する。この動詞には「異なる」という意味のほかに、「遅らせ、先延ばしにし、留保する」という意味もある。そこで、eをaに変えることで、 différer の現在分詞形である différant を経由して名詞化した形となり、 différence で失われた「遅らせ、先延ばしにし、留保し、後にとっておく」という意味を担わされた名詞として différance が得られる。 また、デリダは-anceの形からの名詞化であることから、ギリシア語でいう中動態のように、能動態と受動態の間で宙吊りにされた、再帰的なニュアンスを 持つ名詞であることを示唆している。(différanceは能動・受動の差異の手前にあってその前提をなす自己差異化の運動を指す) また、この二つの形は発音の上では区別がつかない。そのことによって、この区別が声の次元ではなく、文(エクリチュール)の次元に存在することが示唆され る。(différanceは声(フォーネー)が直接性において文に優越するというモデルに依拠する音声中心主義(en:Phonocentrism、こ の言葉は en:Logocentrism(ロゴス中心主義、とも)を意識している)であるとしてそれへの批判を伴い、そうした直接性をその不可避な前提として予め 成り立たせている間接性・媒介性を指す) |
|
| 前史 différance は差異についての20世紀に入って再び活発になった哲学的な思考の流れの中に位置する。 ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは「AはAである」の同一性の判断について、この判断は同一性だけではなく非同一性をも意味している、と 述べた。「Aは」のAと「Aである」のAは、少なくとも概念的には異なるものとして識別されている。すなわち、同定においてすら、Aは二重化され、自己自 身に対して差異化されなければならない。ヘーゲルにおいては、この差異化が弁証法を駆動するが、その差異化は止揚において総合されることが、あらかじめ展 望されている。 また、ヘーゲルは、さまざまな多様性をなす諸々の差異が構成されていく起源には、もはや何者にも媒介も規定もされない、根源的な直接性である一者があると 考えた。この一者が、あたかも生物学的な卵割のように区分されて差異が生じて行き、弁証法的な運動によって多様化し、歴史が進展していく。 こうした、ヘーゲルによってひとつの完成に達した、同一性の支配に服した差異の概念と、それに依拠した「形而上学」を批判する哲学的な傾向が、20世紀に入って、フリードリッヒ・ニーチェ、フェルディナン・ド・ソシュールなどの影響のもとに発生した。 ニーチェは、ショーペンハウアーとは異なり、意志の単一性を肯定せず、これを根源的な矛盾と捉えており、差異を価値と意志と力の観点から考え、差異を必然 的に価値的な、還元できない複数の力の拮抗として捉えることで、そこに安定した同一性への収束の保証も、同一性による支配の根拠も存在しない、と主張し た。また、力は、二つの量の間の差異としてのみ現れえるもので、それ自体として力は把握できない。この原因のない効果としてのみ存在するという点で、 différanceへと力としての差異は繋がっている。 ソシュールはその1906年から1911年に行った一般言語学に関する講義のなかで「言語には差異しかない」と述べた。彼によれば、記号の意味は、他の記 号との違いによってしか規定されていない。ひとつの記号は他の諸記号が「不在において」介在している限りで意味しうる。しかも、その他のものは、その記号 それ自体においては不在であるから、あらかじめどういうものかは決して規定されない。 このことは言語論的転回を参照するまでもなく、それ自体ひとつの記号であるところの哲学的な概念、とりわけ、他のすべての概念がそこから意味を汲み取っており、他の概念には依存していないとされる、形而上学的で超越的な観念やそこからなる体系にも波及せざるを得なかった。 |
|
| 概要 デリダはこのソシュール的な差異のあり方を痕跡として捉え、そこに時間的な遅れ、ずれを見出した。 言語においてある語が何かを意味するとき、その語は、意味されているものの代わりに、我々に対してたち現れて意味する。代理・代表・表象する (represent)するということは、一方では代理なしでは現前(present)しないものを現前させることだが、他方では直接には現前させない、 ということでもある。代理するということは、不在の形で現前させるということでもある。 したがって、意味のあるところには、つねにすでに、他への参照、あるいは、他による媒介が働いている。そして、そこで不在の形で介在する他のものは、しか し、あくまでも、その記号とは異なるものである限りで、その記号自身によってはコントロールできないものであることから、そうした根源的な媒介性の関係、 基本的な差異化の運動には、必然的にずれと遅れが孕まれざるを得ない。 このことは別の形で言い換えるとむしろ順番は逆であって、意味がそこにあるためには、その記号は、他との関係を必要とする。そして、そのためには、他と異 なることが必要になる。そこで、或る他との差異化の運動がまずはじめに必要となる。しかしこの差異化は、必然的に、時間的な差異化でもある。この、他との 差異化の側面が「ずれ」であり、時間的な差異化の側面が「遅れ」である。意味を為すためには異ならねばならないのだから、形而上学が想定するような、「透 明でずれも遅れもない関係」=「直接性」というのは幻想に過ぎない。 また、およそ何かあるものが、それとして同定(アイデンティファイ)できるということは、それが反復可能性を有していなければならない。繰り返されうる記 号だけが、同定するものと、同定されるものとの二つに二重化されうる。識別可能な二つのものだけが同定可能であり、そこにはまずはじめに差異がなければな らない。したがって、何か同一性を保ち、何らかの体系の支えになるような根源的な概念を考えたとしても、それがまさしく同一性を保ち、現前するものである かぎりで、その手前にあらかじめ差異化の運動、différance が存在して、内的な同一性を引き裂いている。 ただし、デリダは差異化という表現に対しては、それが、その主語である何かの実体を想定させてしまう能動性を意味するという点で、次善の表現であるとして 留保している。différance は、ひとつの効果、あるいは効果を生む作用であるが、その主語、主体、原因は持たない。 こうして、「つねにすでに」いかなる記号や表現、概念、存在、同一者においても、他への参照と他からの遅れ、他なるものの痕跡としての、不在のものとの関 係、不可避で還元不可能な「ずれ」があらかじめ働いていて、そうした何ものも、根源的なものとして立てることはできない、というのが、 différance によってデリダが思考しようとしたことである。 |
|
| フッサールの現象学との関係 フッサール現象学は、経験される現象を、純粋に意識に直接与えられている、いわば疑いようのない確実なものだけにいったん還元して、そこから現象を再構成することで、認識の不確実性やそれにまつわる哲学的問題を克服しようという、デカルト的な試みであった。 そのためには、そこからすべての現象が構成される「根源」として、純粋かつ直接的に意識に与えられた現在(現前 present)というものが考えられなければならない。ここで、現象学にとって、時間性というものがアポリアとして現れる。意識に直接与えられているの は、あくまでも現在の瞬間であって、そこから他の時間を引き出すことはできない。そこでフッサールは過去と未来は独立した、現在と対等の何かではなく、唯 一存在する「現在」が持っているひとつのモードであるとした。こうしてフッサール現象学において、根源的かつ自己充足した現在の、意識への純粋な自己現前 という、絶対的な位置づけが成立する。 このような現在のあり方は他を必要とせず自らを、余すところなく提示するということであり、デリダは「声」がそのようなありようのモデルとしてフッサール だけでなく過去の形而上学を規定してきたと批判する。音声中心主義。声は直接的に意味を伝え、文書はそうした生き生きとした「声」の間接的な反響に過ぎな いとされてきた。これに対して提出されるのがエクリチュールの概念である。 差延 (différance)はデリダによるこの絶対的な現在への批判に関係する。(以下、主として『声と現象』ISBN 4480089225 による)彼の批判によれば、意識は現在を純粋かつ直接的に経験することはない。デリダはこうした、自己自身に直接的に、何ら媒介をともなわず、明晰に意味 が現前( present )する、届くという想定を指して『自分が-話すのを-聞く』と表現する。「直観」や「明証」、また透明な理想的コミュニケーションとは、『自分が-話すの を-聞く』かのごとき概念なのである。しかし、聞く自己と話す自己の差異=差延が、またそれに加えて話される言葉の話されなかった他の言葉との差異=差延 が、聞くことの条件である限りで、この直接性も実際には汚染されている。つねにすでに現在は、過去によって不在の形で、つまりその痕跡の形で取りつかれて おり、過去に間接的に媒介されない直接的な現在というものはない。現在は不可避的にすでに過去によって痕跡という形で汚染されている。 言い換えると、過去の痕跡との関係によってはじめて現在は意味を為すことができるのだが、痕跡の形で現在と関係している当の過去は、あくまでも痕跡の形で しか現在に含まれていないため現在にとっては不在であり、フッサールの受動的総合のように、現在にその一部として所有されているわけではない。こうして、 現在はその自己充足性を失い、つねに欠如をはらんだ動的な時間性を帯びることとなる。現在は独立して存在することができず、その外部である過去とのひらか れた関係を必要とする。 現在を構成する記号や表現は、それが意味を成すためには、それ自身とは別の記号や表現を指し示すことが必要であるが、この参照は無時間的なものではなく、 必然的に時間的な「遅れ」を伴う。記号は別の記号への参照によってはじめて記号として機能するのだが、この参照に不可避的に孕まれる「遅れ」によって、指 し示す記号と指し示される記号は、同一の現在の内部にあることができない。こうして、現在において不在の記号が過去として、現在の記号に痕跡として憑依す るのである。 デリダはこの事実から、根源的なものは、そもそも存在し得ない「意識に直接与えられた純粋な現在」ではなく、こうして不在の過去と現在とを引き裂きつつ関 係付ける差異、記号参照において孕まれる「遅れ」「ずれ」としての痕跡の働きであるとみなし、これを、差延 (différance)と名づけた。 |
|
| ハイデッガーの存在論的差異との関係 ものが存在するという出来事をハイデッガーは、存在する対象として語りうるものとは、どうあっても異なるものであると考え、この違いを存在論的差異(Ontologische Differenz)と呼んだ。 この還元できない根源的な違いにこだわる限り、「ものが存在するということは、そのもののこれこれこういう性質である」という形式の説明は一切できない。 性質や属性は、「これこれの性質が存在する」という形で語りうる対象だからである。存在することは、ものの属性ではない。また「ものが存在するということ は、より基本的な何かの在り方のモードや振る舞いである」という形の説明も解決にならない。その基本的な何かは、依然として存在する何かなので、その存在 がやはり問題として残るからである。 ハイデッガーは、従来の哲学はこのように存在する何かでもって存在するということを説明してきたとみなし、この存在論的差異の忘却によって、存在するとい うことの意味を把握し損ねてきたと考えた。ハイデッガーに依れば、何かが「存在する」ということは、現に「いまここ」というものが不断に存在する、という こととの係わりでしか理解できない。そして、この、「いまここが現に不断に存在する」という出来事は、近似的にいえば、現象の場としての<私>の存在のこ とであり、これを現存在と呼ぶ。 この現存在の概念は、認識論的なフッサールの超越論的主観性の概念を存在論的に作り変えたものと見ていい。フッサールの生ける現在(=現前 present)はここでは現存在として捉えなおされる。存在者(存在する主体や対象)に存在(存在するという出来事)が不在なものとして必然的に介在す るということは、現在に決して現在にはならない(現前しない)過去(の、あるいは、としての)痕跡がその前提を為して介在しているという事態と類比的な事 態なのである。 このとき、ハイデッガーの存在論的差異は、思惟や行為の対象からなるものの総体の外部がつねに存在するということを示すという方法的意義を持っている。あ らゆるものが思惟や行為の対象になりうるが、そのような思惟や行為の対象は、決して、その思惟や行為の対象をそういうものとして成り立たせているものとは 同一ではない。 デリダは、この存在するものに不在という形で(すなわち対象化から不可避的に逃れる剰余として)取り憑く存在するという出来事を、それ自体としては決して 現れないが、そういうもの(まったき他者)として存在するものに係わっているものとして、一種の痕跡とみなす。存在は、それ自体として存在者の世界(思惟 や行為の対象の世界)に出現しない。現れてしまったら、それはもはや存在者だからである。 われわれが主題的に思惟する対象にできるのは存在者だけである。あるいは、対象として思惟したとき、それはもはや存在者としてわれわれの前に現れている。 即ち、存在する何かとして語りうるものになっている。存在という概念によって存在するという出来事を主題化し対象として思惟することは確かにできるが、そ のとき、存在するという出来事の特性を、この存在という概念、すなわち存在を意味する存在者を見つめることによっては把握できない。 そういう意味で、存在は、存在者の世界には不在である。しかし、存在者は、存在することによってはじめて存在者なのだから、そこには存在が、やはり或る形で介在している。不在であるがそこにある形で介在しているという意味で、やはりそれを痕跡として規定することができる。 デリダは、この差異、存在するものとその存在との間のずれから、より一般的にあらゆる同一者が前提として経なければならない内的な差異化の運動 différance を引き出す。存在論的差異は、それが存在という形式によって限定されて現れた姿として捉え直される。 しかし存在論的差異や存在は現存在から或る意味で派生するものであり、現存在に先立たれている。それに対して、différance は、存在や現存在に先立っており、それよりも「年老いて」いる。différance は何らかの存在や存在者や主体の作用ではなく、そのような「主体」などの、主語になりうるようなものを成立させ、そのようなものに先立つ。 |
存在論的差異(Ontologische Differenz)とは、一般的にハイデガーが主張する、存在と存在者の明確に区分することである。 |
| La voix et le phenomene (初版1967年 3版2003年) 日本語訳 林好雄『声と現象』ちくま学芸文庫 La Différance (1968年1月27日フランス哲学会における講演) 日本語訳 高橋允昭「ラ・ディフェランス」(『理想』1984年11月号 「デリダ特集号」) |
|
| 高橋哲哉(1998)『デリダ―脱構築』講談社 | |
| ジル・ドゥルーズ ドゥルーズはヘーゲル的な差異への批判をニーチェと
アンリ・ベルクソンを範例としてデリダとは異なる形で遂行した。そこでは差異は微分(differenciation)と関係付けられ、自らを自己差異化
する生産的な力、充溢した多様な強度として把握された。 |
|
| https://x.gd/AZY4z |
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆