ジャック・デリダ
Jacques
Derrida, 1930-2004


ジャック・デリダ
Jacques
Derrida, 1930-2004


★
ジャック・デリダ(/ˈdɛrɪdə/、フランス語: ジャック・デリダ(Jacques Derrida、[ʒak
dɛʁida]、本名ジャック・エリー・デリダ、Jackie Élie Derrida、1930年7月15日 -
2004年10月9日)はフランスの哲学者である。彼は脱構築の哲学を発展させ、自身の多くの著作で活用した。脱構築は、フェルディナン・ド・ソーシュー
ルやフッサール、ハイデガーの現象学の言語学を詳細に読み解くことで発展したものである。[7][8][9]
彼はポスト構造主義およびポストモダン哲学の主要人物の一人であるが[10][11][12]、ポスト構造主義からは距離を置き、「ポストモダン」という
言葉も否定している。
デリダは、40冊以上の著書と数百の論文や発表物を発表した。
彼の影響は、哲学、文学、法学、人類学、歴史学、応用言語学、社会言語学、精神分析、音楽、建築、政治理論など、人文科学や社会科学の分野に多大な影響を
与えた。
2000年代に入っても、彼の研究はアメリカ合衆国、ヨーロッパ大陸、南アメリカ、および大陸哲学が優勢であったその他の国々において、特に存在論、認識
論(特に社会科学に関する)、倫理学、美学、解釈学、言語哲学に関する議論において、主要な学術的影響力を維持していた。分析哲学が優勢なアングロサクソ
ンのほとんどの地域では、デリダの影響は、彼が長年にわたって言語に関心を抱き、イエール大学在学中から著名な文学評論家たちと交流していたことから、現
在では文学研究において最も強く感じられる。また、デリダは(脱構築主義という形で)建築、音楽[23](特にハウントロジー=憑在論的な音楽の雰囲気に
おいて)、美術[24]、美術評論[25]にも影響を与えた。
特に晩年の著作では、デリダは自身の作品において倫理的・政治的なテーマを取り上げた。一部の批評家は『声と現象』(1967年)を彼の最も重要な作品で
あるとみなしているが、一方で『グラマトロジーについて』(1967年)、『筆記と差異』(1967年)、『哲学の余白』(1972年)を挙げる者もい
る。これらの著作は、さまざまな活動家や政治運動に影響を与えた。[26]
彼は著名な影響力のある公人となったが、哲学へのアプローチや難解な作品で物議を醸すこともあった。[26][27]
★
ジャック・デリダ(英語ウィキペディア)
| Jacques Derrida
(/ˈdɛrɪdə/; French: [ʒak dɛʁida]; born Jackie Élie Derrida;[6] 15 July
1930 – 9 October 2004) was a French philosopher. He developed the
philosophy of deconstruction, which he utilized in a number of his
texts, and which was developed through close readings of the
linguistics of Ferdinand de Saussure and Husserlian and Heideggerian
phenomenology.[7][8][9] He is one of the major figures associated with
post-structuralism and postmodern philosophy[10][11][12] although he
distanced himself from post-structuralism and disavowed the word
"postmodernity".[13] During his career, Derrida published over 40 books, together with hundreds of essays and public presentations. He has had a significant influence on the humanities and social sciences, including philosophy, literature, law,[14][15][16] anthropology,[17] historiography,[18] applied linguistics,[19] sociolinguistics,[20] psychoanalysis,[21] music, architecture, and political theory. Into the 2000s, his work retained major academic influence throughout the United States,[22] continental Europe, South America and all other countries where continental philosophy has been predominant, particularly in debates around ontology, epistemology (especially concerning social sciences), ethics, aesthetics, hermeneutics, and the philosophy of language. In most of the Anglosphere, where analytic philosophy is dominant, Derrida's influence is most presently felt in literary studies due to his longstanding interest in language and his association with prominent literary critics from his time at Yale. He also influenced architecture (in the form of deconstructivism), music[23] (especially in the musical atmosphere of hauntology), art,[24] and art criticism.[25] Particularly in his later writings, Derrida addressed ethical and political themes in his work. Some critics consider Speech and Phenomena (1967) to be his most important work, while others cite Of Grammatology (1967), Writing and Difference (1967), and Margins of Philosophy (1972). These writings influenced various activists and political movements.[26] He became a well-known and influential public figure, while his approach to philosophy and the notorious abstruseness of his work made him controversial.[26][27] |
ジャッ
ク・デリダ(/ˈdɛrɪdə/、フランス語: ジャック・デリダ(Jacques Derrida、[ʒak
dɛʁida]、本名ジャック・エリー・デリダ、Jackie Élie Derrida、1930年7月15日 -
2004年10月9日)はフランスの哲学者である。彼は脱構築の哲学を発展させ、自身の多くの著作で活用した。脱構築は、フェルディナン・ド・ソーシュー
ルやフッサール、ハイデガーの現象学の言語学を詳細に読み解くことで発展したものである。[7][8][9] 彼は
ポスト構造主義およびポストモダン哲学の主要人物の一人であるが[10][11][12]、ポスト構造主義からは距離を置き、「ポストモダン」という言葉
も否定している。 デリダは、40冊以上の著書と数百の論文や発表物を発表した。 彼の影響は、哲学、文学、法学、人類学、歴史学、応用言語学、社会言語学、精神分析、音楽、建築、政治理論など、人文科学や社会科学の分野に多大な影響を 与えた。 2000年代に入っても、彼の研究はアメリカ合衆国、ヨーロッパ大陸、南アメリカ、および大陸哲学が優勢であったその他の国々において、特に存在論、認識 論(特に社会科学に関する)、倫理学、美学、解釈学、言語哲学に関する議論において、主要な学術的影響力を維持していた。分析哲学が優勢なアングロサクソ ンのほとんどの地域では、デリダの影響は、彼が長年にわたって言語に関心を抱き、イエール大学在学中から著名な文学評論家たちと交流していたことから、現 在では文学研究において最も強く感じられる。また、デリダは(脱構築主義という形で)建築、音楽[23](特にハウントロジー=憑在論的な音楽の雰囲気に おいて)、美術[24]、美術評論[25]にも影響を与えた。 特に晩年の著作では、デリダは自身の作品において倫理的・政治的なテーマを取り上げた。一部の批評家は『声と現象』(1967年)を彼の最も重要な作品で あるとみなしているが、一方で『グラマトロジーについて』(1967年)、『筆記と差異』(1967年)、『哲学の余白』(1972年)を挙げる者もい る。これらの著作は、さまざまな活動家や政治運動に影響を与えた。[26] 彼は著名な影響力のある公人となったが、哲学へのアプローチや難解な作品で物議を醸すこともあった。[26][27] |
| Early life and education Derrida was born on 15 July 1930, in a summer home in El Biar (Algiers), Algeria,[6] to Haïm Aaron Prosper Charles (known as "Aimé") Derrida (1896–1970), who worked all his life for the wine and spirits company Tachet, including as a travelling salesman (his son reflected the job was "exhausting" and "humiliating", his father forced to be a "docile employee" to the extent of waking early to do the accounts at the dining-room table),[28] and Georgette Sultana Esther (1901–1991),[29] daughter of Moïse Safar.[30] His family was Sephardic Jewish, (originally from Toledo) and became French in 1870 when the Crémieux Decree granted full French citizenship to the Jews of Algeria.[31][32] His parents named him "Jackie", "which they considered to be an American name", although he would later adopt a more "correct" version of his first name when he moved to Paris; some reports indicate that he was named Jackie after the American child actor Jackie Coogan, who had become well known around the world via his role in the 1921 Charlie Chaplin film The Kid.[33][34][35] He was also given the middle name Élie after his paternal uncle Eugène Eliahou, at his circumcision; this name was not recorded on his birth certificate unlike those of his siblings, and he would later call it his "hidden name".[36] Derrida was the third of five children. His elder brother Paul Moïse died at less than three months old, the year before Derrida was born, leading him to suspect throughout his life his role as a replacement for his deceased brother.[33] Derrida spent his youth in Algiers and in El-Biar. On the first day of the school year in 1942, French administrators in Algeria—implementing antisemitism quotas set by the Vichy government—expelled Derrida from his lycée. He secretly skipped school for a year rather than attend the Jewish lycée formed by displaced teachers and students, and also took part in numerous football competitions (he dreamed of becoming a professional player). In this adolescent period, Derrida found in the works of philosophers and writers (such as Rousseau, Nietzsche, and Gide) an instrument of revolt against family and society.[37] His reading also included Camus and Sartre.[37] In the late 1940s, he attended the Lycée Bugeaud [fr], in Algiers;[38] in 1949 he moved to Paris,[7][27] attending the Lycée Louis-le-Grand,[38] where his professor of philosophy was Étienne Borne.[39] At that time he prepared for his entrance exam to the prestigious École Normale Supérieure (ENS); after failing the exam on his first try, he passed it on the second, and was admitted in 1952.[27] On his first day at ENS, Derrida met Louis Althusser, with whom he became friends. A professor of his, Jan Czarnecki, was a progressive Protestant who would become a signer of the Manifesto of the 121.[40] After visiting the Husserl Archive in Leuven, Belgium (1953–1954), he completed his master's degree in philosophy (diplôme d'études supérieures [fr]) on Edmund Husserl (see below). He then passed the highly competitive agrégation exam in 1956. Derrida received a grant for studies at Harvard University, and he spent the 1956–57 academic year reading James Joyce's Ulysses at the Widener Library.[41] |
幼少期と教育 デリダは1930年7月15日、アルジェリアのアルジェにあるエル・ビアール地区の別荘で生まれた。[6] 父親のハイム・アーロン・プロスパー・シャルル(通称「エメ」)デリダ(1896年 - 1970年)は、ワイン・蒸留酒会社タシェの社員として生涯を過ごし、その中には出張販売員としての仕事も含まれていた(息子のデリダは、その仕事を「 「屈辱的」で、父親は「従順な従業員」として、早朝に起きてダイニングテーブルで帳簿をつけることを強いられていたと述べている。[28] また、モーゼ・サファールの娘であるジョルジェット・スルタナ・エステル(1901年 - 1991年)[29]もいた。[30] 彼の家族はセファルディム系ユダヤ人であり、(もともとはトレド出身) 1870年にクレミュー勅令がアルジェリアのユダヤ人にフランス国籍を付与したことにより、フランス人となった。[31][32] 両親は彼を「ジャッキー」と名付けたが、これは「アメリカ風の名前」だと考えていた。しかし、後にパリに移住した際には、より「正しい」ファーストネーム に改名している。一部の報道によると、彼はアメリカの子供俳優ジャッキー・クーガンにちなんで「ジャッキー」と名付けられたという 。1921年のチャールズ・チャップリンの映画『キッド』で世界的に有名になった子役のジャッキー・クーガンにちなんで名付けられたという説もある。 [33][34][35] また、割礼の際に父方の叔父であるユージン・エリアフにちなんでエリーというミドルネームも与えられた。この名前は兄弟姉妹の名前とは異なり出生証明書に は記載されておらず、後に「隠された名前」と呼ぶようになった。[36] デリダは5人兄弟の3番目であった。彼の兄であるポール・モイーズは、デリダが生まれる前年のこと、生後3か月足らずで死亡した。このことが、デリダは生 涯にわたって、亡くなった兄の身代わりとしての自分の役割を疑うことにつながった。[33] デリダはアルジェとエル・ビアで青春時代を過ごした。 1942年の新学期初日、ヴィシー政権が定めた反ユダヤ主義の割当枠を実行するアルジェリアのフランス人行政官が、デリダをリセから退学させた。 デリダは、避難してきた教師や生徒たちによって形成されたユダヤ人リセに通うことを避け、1年間ひそかに学校をさぼり、また、数々のサッカー大会にも参加 していた(プロ選手になることを夢見ていた)。この思春期の時期に、デリダは哲学者や作家(ルソー、ニーチェ、ジイドなど)の著作から、家族や社会に対す る反抗の手段を見出した。[37] 彼の読書にはカミュやサルトルも含まれていた。[37] 1940年代後半、彼はアルジェのビュジョー高校に通っていた。[38] 1949年にパリに移り、ルイ=ル=グラン高校に通った。[38] そこで哲学の教授を務めていたのはエティエンヌ・ボルヌであった。[39] 彼は名門エコール・ノルマル・シュペリウール(ENS)の入学試験の準備をした。1回目の受験では不合格だったが、2回目の受験で合格し、1952年に合 格した。ENSでの初日、デリダはルイ・アルチュセールと出会い、友人となった。彼の教授のジャン・チャルネツキは進歩的なプロテスタント信者であり、後 に「121人宣言」の署名者の一人となった。[40] ベルギーのルーヴェンにあるフッサール文書館を訪問した後(1953年から1954年)、彼はエドムンド・フッサール(下記参照)の哲学修士号 (diplôme d'études supérieures)を取得した。その後、1956年に競争率の高いアグレガシオン試験に合格した。デリダはハーバード大学での研究のための助成金を 受け取り、1956年から57年の学年度は、ワイデナー図書館でジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』を読んだ。[41] |
| Career During the Algerian War of Independence of 1954–1962, Derrida asked to teach soldiers' children in lieu of military service, teaching French and English from 1957 to 1959.[citation needed] Following the war, from 1960 to 1964, Derrida taught philosophy at the Sorbonne, where he was an assistant of Suzanne Bachelard (daughter of Gaston Bachelard), Georges Canguilhem, Paul Ricœur (who in these years coined the term hermeneutics of suspicion), and Jean Wahl.[42] His wife, Marguerite, gave birth to their first child, Pierre, in 1963. In 1964, on the recommendation of Louis Althusser and Jean Hyppolite, Derrida got a permanent teaching position at the ENS, which he kept until 1984.[43][44] In 1965 Derrida began an association with the Tel Quel group of literary and philosophical theorists, which lasted for seven years.[44] Derrida's subsequent distance from the Tel Quel group, after 1971, was connected to his reservations about their embrace of Maoism and of the Chinese Cultural Revolution.[45] With "Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences", his contribution to a 1966 colloquium on structuralism at Johns Hopkins University, his work began to gain international prominence. At the same colloquium Derrida would meet Jacques Lacan and Paul de Man, the latter an important interlocutor in the years to come.[46] A second son, Jean, was born in 1967. In the same year, Derrida published his first three books—Writing and Difference, Speech and Phenomena, and Of Grammatology. In 1980, he received his first honorary doctorate (from Columbia University) and was awarded his State doctorate (doctorat d'État) by submitting to the University of Paris ten of his previously published books in conjunction with a defense of his intellectual project under the title "L'inscription de la philosophie : Recherches sur l'interprétation de l'écriture" ("Inscription in Philosophy: Research on the Interpretation of Writing").[38][47] The text of Derrida's defense was based on an abandoned draft thesis he had prepared in 1957 under the direction of Jean Hyppolite at the ENS entitled "The Ideality of the Literary Object"[47] ("L'idéalité de l'objet littéraire");[48] his 1980 dissertation was subsequently published in English translation as "The Time of a Thesis: Punctuations". In 1983 Derrida collaborated with Ken McMullen on the film Ghost Dance. Derrida appears in the film as himself and also contributed to the script. Derrida traveled widely and held a series of visiting and permanent positions. Derrida became full professor (directeur d'études) at the École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris from 1984 (he had been elected at the end of 1983).[47] With François Châtelet and others he in 1983 co-founded the Collège international de philosophie (CIPH; 'International college of philosophy'), an institution intended to provide a location for philosophical research which could not be carried out elsewhere in the academia. He was elected as its first president. In 1985 Sylviane Agacinski gave birth to Derrida's third child, Daniel.[49] On 8 May 1985, Derrida was elected a Foreign Honorary Member of the American Academy of Arts and Sciences, to Class IV – Humanities, Section 3 -Criticism and Philology.[50] |
経歴 1954年から1962年にかけてのアルジェリア独立戦争中、デリダは兵役の代わりに軍人の子供たちにフランス語と英語を教えることを志願し、1957年 から1959年にかけて教鞭をとった。[要出典] 戦争後、1960年から1964年にかけて、デリダはソルボンヌ大学で哲学を教え ソルボンヌ大学で哲学を教え、ガストン・バシュラールの娘であるスザンヌ・バシュラール、ジョルジュ・カンギレム、ポール・リクール(この時期に「疑いの 解釈学」という用語を考案した)、ジャン・ヴァールらの助手を務めた。[42] 1963年、妻のマルグリットが最初の子供であるピエールを出産した。1964年、ルイ・アルチュセールとジャン・イポリットの推薦により、デリダは ENSの常勤講師となり、1984年までその職を務めた。[43][44] 1965年、デリダは 文学・哲学理論家のグループであるテルケル・グループと関わりを持ち、それは7年間続いた。[44] 1971年以降、テルケル・グループから距離を置いたデリダは、彼らの毛沢東主義や中国文化大革命への傾倒に疑問を抱いていた。[45] 「人間の科学の言説における構造、記号、遊び」という、1966年にジョンズ・ホプキンス大学で開催された構造主義に関する会議への寄稿により、彼の作品 は国際的に注目を集めるようになった。同会議で、デリダはジャック・ラカンとポール・ド・マンと出会った。後者は、その後の数年間における重要な対話者で あった。[46] 1967年には次男のジャンが生まれた。同年、デリダは最初の3冊の著書、『筆記と差異』、『声と現象』、『グラマトロジーについて』を出版した。 1980年には初の名誉博士号(コロンビア大学)を受け、パリ大学にそれまでに出版した10冊の著書を提出し、自身の知的プロジェクトの擁護を 「L'inscription de la philosophie : Recherches sur l'interprétation de l'écriture」(「哲学への刻印:文字の解釈に関する研究」)というタイトルで提出し、国家博士号(doctorat d'État)を授与された。 38][47] デリダの弁明の文章は、1957年にENSでジャン・イポリットの指導の下で準備した「文学的対象の観念性」[47](「L'idéalité de l'objet littéraire」)[48]という題名の放棄された草案論文に基づいている。1980年の論文はその後、「論文の時間:句読点」として英語に翻訳さ れて出版された。。1983年、デリダはケン・マクマレンと共同で映画『ゴーストダンス』を制作した。デリダは映画の中で本人役として出演し、脚本にも参 加している。 デリダは広く旅をし、客員教授や常勤職を歴任した。1984年より、デリダはパリの高等社会科学研究学院の正教授(directeur d'études)となった(1983年末に選出されていた)。[47] フランソワ・シャトレらとともに、 シャトレらとともに、1983年に「国際哲学コレージュ」(Collège international de philosophie、CIPH)を共同設立した。これは、学問の場では実施できないような哲学研究を行うための機関である。彼は初代会長に選出され た。1985年、シルヴィアン・アガシンスキーはデリダの三番目の子供、ダニエルを出産した。 1985年5月8日、デリダはアメリカ芸術科学アカデミーの外国人名誉会員に選出された。第4部門 - 人文科学、第3部 - 批評と文献学である。[50] |
| In
1986 Derrida became Professor of the Humanities at the University of
California, Irvine, where he taught until shortly before his death in
2004. His papers were filed in the university archives. When Derrida's
colleague, Dragan Kujundzic, was accused of sexual assault, Derrida
wrote a letter to then-Chancellor Cicerone saying "if the scandalous
procedure" against Kujundzic was not "interrupted or cancelled," he
would end all his "relations with UCI." Regarding his archival papers,
there would be "another consequence: since I never take back what I
have given, my papers would of course remain the property of UCI and
the Special Collections department of the library. However, it goes
without saying that the spirit in which I contributed to the
constitution of these archives (which is still underway and growing
every year) would have been seriously damaged. Without renouncing my
commitments, I would regret having made them and would reduce their
fulfillment to the barest minimum."[51] After Derrida's death, his
widow and sons said they wanted copies of UCI's archives shared with
the Institute of Contemporary Publishing Archives in France. The
university had sued in an attempt to get manuscripts and correspondence
from Derrida's widow and children that it believed the philosopher had
promised to UC Irvine's collection, although it dropped the suit in
2007.[52] Derrida was a regular visiting professor at several other major American and European universities, including Johns Hopkins University, Yale University, New York University, Stony Brook University, The New School for Social Research, and European Graduate School.[53] He was awarded honorary doctorates by the University of Cambridge (1992), Columbia University, The New School for Social Research, the University of Essex, Katholieke Universiteit Leuven, the University of Silesia, the University of Coimbra, the University of Athens, and many others around the world. In 2001, he received the Adorno-Preis from the University of Frankfurt. Derrida's honorary degree at Cambridge was protested by leading philosophers in the analytic tradition. Philosophers including Quine, Marcus, and Armstrong wrote a letter to the university objecting that "Derrida's work does not meet accepted standards of clarity and rigour," and "Academic status based on what seems to us to be little more than semi-intelligible attacks upon the values of reason, truth, and scholarship is not, we submit, sufficient grounds for the awarding of an honorary degree in a distinguished university".[54] Late in his life, Derrida participated in making two biographical documentaries, D'ailleurs, Derrida (Derrida's Elsewhere) by Safaa Fathy (1999),[55] and Derrida by Kirby Dick and Amy Ziering Kofman (2002).[56] On 19 February 2003, with the 2003 invasion of Iraq impending, René Major [fr] moderated a debate entitled "Pourquoi La Guerre Aujourd'hui?" between Derrida and Jean Baudrillard, co-hosted by Major's Institute for Advanced Studies in Psychoanalysis and Le Monde Diplomatique. The debate discussed the relation between terrorist attacks and the invasion.[57][58] |
1986年、デリダはカリフォルニ
ア大学アーバイン校の人文科学の教授となり、2004年に亡くなる直前まで同校で教鞭をとった。彼の論文は大学のアーカイブに保管された。デリダの同僚で
あるドラガン・クジュンジッチが性的暴行容疑で告発された際、デリダは当時の学長チセロネに宛てて「クジュンジッチに対するこの不祥な手続きが中断または
取り消しされない場合、私はUCIとの関係をすべて断つ」と書いた。私のアーカイブ資料については、「別の結果が起こるだろう。私は一度提出したものを決
して取り下げることはしないので、私の資料は当然ながらUCIおよび図書館の特別コレクション部門の所有物として残るだろう。しかし、言うまでもなく、私
がこれらのアーカイブ(これは現在も進行中で、毎年拡大している)の設立に貢献した精神は、深刻なダメージを受けるだろう。自分の義務を放棄しないとして
も、私はそれを後悔し、その履行を最低限に抑えるだろう」[51]
デリダの死後、彼の未亡人と息子たちは、UCIのアーカイブのコピーをフランスの現代出版アーカイブ研究所と共有したいと述べた。同大学は、デリダの未亡
人と子供たちがアーバイン大学に寄贈する約束をしていたと考えた原稿や書簡を入手しようと訴訟を起こしたが、2007年に訴えを取り下げた。[52] デリダは、ジョンズ・ホプキンス大学、イェール大学、ニューヨーク大学、ストーニーブルック大学、ニュースクール・フォー・ソーシャルリサーチ、ヨーロピ アン・グラジュエート・スクールなど、アメリカとヨーロッパの主要大学で定期的に客員教授を務めていた。[53] 彼はケンブリッジ大学(1992年)、コロンビア大学、ニュースクール・フォー・ソーシャルリサーチ、エセックス大学、ルーヴェン・カトリック大学、シレ ジア大学、コインブラ大学、アテネ大学など、世界中の多くの大学から名誉博士号を授与された。2001年にはフランクフルト大学からアドルノ賞を授与され た。 ケンブリッジ大学でデリダに名誉学位が授与された際には、分析哲学の伝統を重んじる著名な哲学者たちから抗議が寄せられた。クワイン、マーカス、アームス トロングなどの哲学者たちは、デリダの業績は「明確性と厳密性の基準を満たしていない」ことや、「理性、真理、学識の価値に対する半ば理解不能な攻撃にす ぎないと思われるものを基盤とする学術的地位は、著名な大学が名誉学位を授与するに足る十分な根拠とは言えない」と大学側に異議を申し立てる書簡を送っ た。[54] 晩年、デリダは2本の伝記ドキュメンタリー映画の制作に参加した。1999年の『D'ailleurs, Derrida (Derrida's Elsewhere)』(監督:サファ・ファティ)と、2002年の『Derrida』(監督:カービー・ディックとエイミー・ジリング・コフマン)であ る。 2003年2月19日、間近に迫った2003年のイラク侵攻を前に、ルネ・メジャー(René Major)は、メジャーの精神分析高等研究所とル・モンド・ディプロマティークの共催で、「Pourquoi La Guerre Aujourd'hui?」と題されたデリダとジャン・ボードリヤールとの討論会を司会した。討論会では、テロ攻撃と侵攻の関係について議論された。 [57][58] |
| Personal life and death In June 1957, he married the psychoanalyst Marguerite Aucouturier in Boston. Derrida was diagnosed with pancreatic cancer in 2002.[27] He died during surgery in a hospital in Paris in the early hours of 9 October 2004.[59][26][60] At the time of his death, Derrida had agreed to go for the summer to University of Heidelberg as holder of the Gadamer professorship,[61] whose invitation was expressed by the hermeneutic philosopher himself before his death. Peter Hommelhoff, Rector at Heidelberg by that time, would summarize Derrida's place as: "Beyond the boundaries of philosophy as an academic discipline he was a leading intellectual figure not only for the humanities but for the cultural perception of a whole age."[61] |
私生活と死 1957年6月、彼はボストンで精神分析医のマルグリット・オークチュリエと結婚した。 2002年に膵臓癌と診断された。[27] 2004年10月9日未明、パリの病院で手術中に死去した。[59][26][60] 死の直前、デリダはガダマー教授職の保有者として、夏の間ハイデルベルク大学で過ごすことに同意していた。[61] その招待は、解釈学の哲学者自身が死の前に表明していた。当時ハイデルベルク大学の学長であったペーター・ホンメルホフは、デリダの地位を次のように要約 している。「学問としての哲学の境界を越え、人文科学のみならず、全時代の文化認識における第一人者であった」と述べている。[61] |
| Philosophy Main article: Deconstruction Derrida referred to himself as a historian.[62][63] He questioned assumptions of the Western philosophical tradition and also more broadly Western culture.[64] By questioning the dominant discourses, and trying to modify them, he attempted to democratize the university scene and to politicize it.[65] Derrida called his challenge to the assumptions of Western culture "deconstruction".[64] On some occasions, Derrida referred to deconstruction as a radicalization of a certain spirit of Marxism.[66][67] With his detailed readings of works from Plato to Rousseau to Heidegger, Derrida frequently argues that Western philosophy has uncritically allowed metaphorical depth models[jargon] to govern its conception of language and consciousness. He sees these often unacknowledged assumptions as part of a "metaphysics of presence" to which philosophy has bound itself. This "logocentrism", Derrida argues, creates "marked" or hierarchized binary oppositions that have an effect on everything from the conception of speech's relation to writing to the understanding of racial difference. Deconstruction is an attempt to expose and undermine such "metaphysics". Derrida approaches texts as constructed around binary oppositions which all speech has to articulate if it intends to make any sense whatsoever. This approach to text is, in a broad sense, influenced by the semiology of Ferdinand de Saussure.[68][69] Saussure, considered to be one of the fathers of structuralism, posited that terms get their meaning in reciprocal determination with other terms inside language.[70] Perhaps Derrida's most quoted and famous assertion,[68] which appears in an essay on Rousseau in his book Of Grammatology (1967),[71] is the statement that "there is no outside-text" (il n'y a pas de hors-texte).[71] Critics of Derrida have been often accused of having mistranslated the phrase in French to suggest he had written "Il n'y a rien en dehors du texte" ("There is nothing outside the text") and of having widely disseminated this translation to make it appear that Derrida is suggesting that nothing exists but words.[72][73][74][75][76] Derrida once explained that this assertion "which for some has become a sort of slogan, in general so badly understood, of deconstruction ... means nothing else: there is nothing outside context. In this form, which says exactly the same thing, the formula would doubtless have been less shocking."[72][77] |
哲学 詳細は「脱構築」を参照 デリダは自らを歴史家と称していた。[62][63] 彼は西洋哲学の伝統の前提を疑い、より広く西洋文化も疑った。[64] 支配的な言説を疑い、それを修正しようとすることで、彼は大学の場面を民主化し、 政治化しようとした。[65] デリダは西洋文化の前提に対する自身の挑戦を「脱構築」と呼んだ。[64] デリダは脱構築をマルクス主義の特定の精神の急進化であると表現したこともある。[66][67] プラトンからルソー、ハイデガーに至る作品を詳細に読み解く中で、デリダは西洋哲学が比喩的な深層モデル[専門用語]を批判することなく、言語や意識の概 念を支配させてきたと頻繁に主張している。彼は、これらのしばしば認められない前提を、哲学が自らを縛り付ける「存在の形而上学」の一部と見なしている。 デリダは、この「ロゴセントリズム」が「マーク付き」または階層化された二項対立を生み出し、それは言語と文字の関係の概念から人種差異の理解に至るま で、あらゆるものに影響を及ぼしていると主張する。脱構築とは、このような「形而上学」を暴露し、弱体化させる試みである。 デリダは、あらゆる言語が意味をなすためには、二項対立の概念を軸として構築されなければならないというアプローチでテキストを扱う。このテキストへのア プローチは、広義ではフェルディナン・ド・ソーシュールの記号論の影響を受けている。[68][69] 構造主義の父の一人とされるソーシュールは、用語は言語内の他の用語との相互決定によって意味を獲得するという仮説を立てた。[70] おそらく最も引用され、有名なデリダの主張は、著書『グラマトロジーについて』(1967年)のルソーに関する論文に登場する「テクストの外側などない」 (il n'y a pas de hors-texte)というものである。[71] デリダの批判者たちは、しばしばこのフレーズを誤訳し、デリダが「Il n'y a rien en dehors du texte」(「テクストの外側には何もない」)と書いたかのように示唆したと非難されている。また、この翻訳を広く流布し、デリダが言葉以外には何も存 在しないと示唆しているかのように見せかけたとも非難されている。[72][73][74][75] y a rien en dehors du texte"(「テキストの外には何もない」)と書いたと示唆し、広くこの翻訳を流布して、デリダが言葉以外には何も存在しないと示唆しているかのように 見せかけたという非難を受けている。[72][73][74][75][76] デリダはかつて、この主張について「一部の人々にとってはスローガンのようなものとなり、一般にはひどく誤解されているが、脱構築とは... それ以外には何も意味しない。文脈の外には何もない。この形では、まったく同じことを言っているが、この公式は間違いなくそれほど衝撃的ではなかっただろ う。」[72][77] |
| Early works Derrida began his career examining the limits of phenomenology. His first lengthy academic manuscript, written as a dissertation for his diplôme d'études supérieures and submitted in 1954, concerned the work of Edmund Husserl.[78] Gary Banham has said that the dissertation is "in many respects the most ambitious of Derrida's interpretations with Husserl, not merely in terms of the number of works addressed but also in terms of the extraordinarily focused nature of its investigation."[79] In 1962 he published Edmund Husserl's Origin of Geometry: An Introduction, which contained his own translation of Husserl's essay. Many elements of Derrida's thought were already present in this work. In the interviews collected in Positions (1972), Derrida said: In this essay the problematic of writing was already in place as such, bound to the irreducible structure of 'deferral' in its relationships to consciousness, presence, science, history and the history of science, the disappearance or delay of the origin, etc. ...this essay can be read as the other side (recto or verso, as you wish) of Speech and Phenomena. — Derrida, 1967, interview with Henri Ronse[80] Derrida first received major attention outside France with his lecture, "Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences," delivered at Johns Hopkins University in 1966 (and subsequently included in Writing and Difference). The conference at which this paper was delivered was concerned with structuralism, then at the peak of its influence in France, but only beginning to gain attention in the United States. Derrida differed from other participants by his lack of explicit commitment to structuralism, having already been critical of the movement. He praised the accomplishments of structuralism but also maintained reservations about its internal limitations;[81] this has led US academics to label his thought as a form of post-structuralism.[10][11][82] The effect of Derrida's paper was such that by the time the conference proceedings were published in 1970, the title of the collection had become The Structuralist Controversy. The conference was also where he met Paul de Man, who would be a close friend and source of great controversy, as well as where he first met the French psychoanalyst Jacques Lacan, with whose work Derrida had a mixed relationship. |
初期の作品 デリダは、現象学の限界を研究することからキャリアをスタートさせた。 1954年に提出された、高等研究課程の学位論文として書かれた最初の長編学術論文は、エドムンド・フッサールの研究に関するものであった。[78] ゲイリー・バンハムは、この論文について「多くの点で、デリダによるフッサール解釈の中で最も野心的なものであり、 扱われた作品の数だけでなく、その調査の非常に集中的な性質という観点からも、である」と述べている。[79] 1962年には、エドマンド・フッサールの論文の自身の翻訳を収録した『エドマンド・フッサール著『幾何学原論:序説』』を出版した。この著作にはすで に、デリダの思想の多くの要素が含まれていた。『ポジション』(1972年)に収録されたインタビューの中で、デリダは次のように述べている。 この論文では、すでに「書くこと」の問題が、意識、現在、科学、歴史、科学史との関係における「先送り」という不可還元的な構造に結びついた形で存在して いた。起源の消失や遅延など...この論文は、『声と現象』の裏側(表裏どちらでもお好きな方)として読むことができる。 — デリダ、1967年、アンリ・ロンセとのインタビュー[80] デリダがフランス国外で初めて注目を集めたのは、1966年にジョンズ・ホプキンス大学で行った講演「人間科学の言説における構造、記号、遊び」(後に 『書記と差異』に収録)がきっかけであった。この論文が発表された会議は構造主義に関するもので、当時フランスでは構造主義が絶大な影響力を誇っていた が、アメリカではまだ注目され始めたばかりであった。デリダは他の参加者とは異なり、構造主義に明確にコミットしていないことで際立っていた。彼は構造主 義の功績を称賛したが、その内部的な限界についても懸念を示していた。[81] これが米国の学者たちに、彼の思想をポスト構造主義の一形態と位置づけさせた。[10][11][82] デリダの論文の影響により、1970年に会議の議事録が出版されたときには、その論文集のタイトルは『構造主義論争』となっていた。また、この会議でポー ル・ド・マンと知り合った。ド・マンはデリダの親しい友人となり、大きな論争の相手ともなった。また、この会議でデリダはフランスの精神分析家ジャック・ ラカンと初めて会った。ラカンの仕事とデリダとの関係は複雑であった。 |
| Phenomenology vs structuralism
debate (1959) In the early 1960s, Derrida began speaking and writing publicly, addressing the most topical debates at the time. One of these was the new and increasingly fashionable movement of structuralism, which was being widely favoured as the successor to the phenomenology approach, the latter having been started by Husserl sixty years earlier. Derrida's countercurrent take on the issue, at a prominent international conference, was so influential that it reframed the discussion from a celebration of the triumph of structuralism to a "phenomenology vs structuralism debate". Phenomenology, as envisioned by Husserl, is a method of philosophical inquiry that rejects the rationalist bias that has dominated Western thought since Plato in favor of a method of reflective attentiveness that discloses the individual's "lived experience"; for those with a more phenomenological bent, the goal was to understand experience by comprehending and describing its genesis, the process of its emergence from an origin or event.[83] For the structuralists, this was a false problem, and the "depth" of experience could in fact only be an effect of structures which are not themselves experiential.[84] In that context, in 1959, Derrida asked the question: Must not structure have a genesis, and must not the origin, the point of genesis, be already structured, in order to be the genesis of something?[85] In other words, every structural or "synchronic" phenomenon has a history, and the structure cannot be understood without understanding its genesis.[86] At the same time, in order that there be movement or potential, the origin cannot be some pure unity or simplicity, but must already be articulated—complex—such that from it a "diachronic" process can emerge. This original complexity must not be understood as an original positing, but more like a default of origin, which Derrida refers to as iterability, inscription, or textuality.[87][88] It is this thought of originary complexity that sets Derrida's work in motion, and from which all of its terms are derived, including "deconstruction".[89] Derrida's method consisted in demonstrating the forms and varieties of this originary complexity, and their multiple consequences in many fields. He achieved this by conducting thorough, careful, sensitive, and yet transformational readings of philosophical and literary texts, to determine what aspects of those texts run counter to their apparent systematicity (structural unity) or intended sense (authorial genesis). By demonstrating the aporias and ellipses of thought, Derrida hoped to show the infinitely subtle ways in which this originary complexity, which by definition cannot ever be completely known, works its structuring and destructuring effects.[90] |
現象学〈対〉構造主義論争(1959年) 1960年代初頭、デリダは当時最も話題となっていた論争を取り上げて、公の場で発言し、執筆活動を始めた。その一つが、当時ますます流行しつつあった新 しい構造主義の運動であった。構造主義は、60年前にフッサールによって始められた現象学アプローチの継承者として広く支持されていた。デリダが著名な国 際会議で示した逆説的な見解は、非常に大きな影響力を持ち、構造主義の勝利を祝う議論を「現象学対構造主義の論争」へと方向転換させた。 フッサールが構想した現象学は、プラトン以来西洋思想を支配してきた合理主義的偏見を否定し、個人の「生活体験」を明らかにする反省的注意力の方法を支持 する哲学的探究の方法である。現象学に傾倒する人々にとって、その目的は 経験を理解するには、その起源、つまり起源や出来事から生じる過程を理解し、記述することが必要である。構造主義者たちにとって、これは誤った問題であ り、経験の「深さ」は、実際には経験そのものではない構造の影響でしかない。 その文脈において、1959年にデリダは次のように問いかけた。「構造」には起源があるはずであり、何かが「起源」となるためには、その「起源」となる時 点がすでに「構造化」されていなければならないのではないか?[85] 言い換えれば、あらゆる構造的または「共時的」現象には歴史があり、 その起源を理解することなしには構造を理解することはできない。[86] 同時に、運動や潜在的可能性があるためには、起源は純粋な統一や単純性であってはならず、すでに「共時的」なプロセスが生まれるような、複雑な構造を持っ ていなければならない。この原初的複雑性は、原初的な仮定として理解されるべきではなく、むしろデリダが反復可能性、刻印、テクスト性と呼ぶような原初の 既定値として理解されるべきである。[87][88] デリダの仕事を動かすのは、この原初的複雑性の思考であり、そこから「脱構築」を含むすべての用語が派生している。[89] デリダの方法は、この原初的複合性の形態と多様性、およびさまざまな分野におけるその多様な帰結を明らかにすることにあった。彼は、哲学や文学のテキスト を徹底的かつ注意深く、繊細に、そしてなおかつ変容的に読み解くことによって、これらのテキストのどのような側面が、その明白な体系性(構造的統一性)や 意図された意味(作者の創始)に反するかを明らかにした。デリダは、思考のジレンマや省略を示すことで、定義上、決して完全に知ることができない起源的な 複雑性が、その構造化と脱構築の効果をどのように作用させるかという、無限に微妙な方法を示すことを望んでいた。[90] |
| 1967–1972 Derrida's interests crossed disciplinary boundaries, and his knowledge of a wide array of diverse material was reflected in the three collections of work published in 1967: Speech and Phenomena, Of Grammatology (initially submitted as a Doctorat de spécialité thesis under Maurice de Gandillac),[38] and Writing and Difference.[91] On several occasions, Derrida has acknowledged his debt to Husserl and Heidegger, and stated that without them he would not have said a single word.[92][93] Among the questions asked in these essays are "What is 'meaning', what are its historical relationships to what is purportedly identified under the rubric 'voice' as a value of presence, presence of the object, presence of meaning to consciousness, self-presence in so called living speech and in self-consciousness?"[91] In another essay in Writing and Difference entitled "Violence and Metaphysics: An Essay on the Thought of Emmanuel Levinas", the roots of another major theme in Derrida's thought emerge: the Other as opposed to the Same[94] "Deconstructive analysis deprives the present of its prestige and exposes it to something tout autre, "wholly other", beyond what is foreseeable from the present, beyond the horizon of the "same"."[95] Other than Rousseau, Husserl, Heidegger and Levinas, these three books discussed, and/or relied upon, the works of many philosophers and authors, including linguist Saussure,[96] Hegel,[97] Foucault,[98] Bataille,[97] Descartes,[98] anthropologist Lévi-Strauss,[99][100] paleontologist Leroi-Gourhan,[101] psychoanalyst Freud,[102] and writers such as Jabès[103] and Artaud.[104] This collection of three books published in 1967 elaborated Derrida's theoretical framework. Derrida attempts to approach the very heart of the Western intellectual tradition, characterizing this tradition as "a search for a transcendental being that serves as the origin or guarantor of meaning". The attempt to "ground the meaning relations constitutive of the world in an instance that itself lies outside all relationality" was referred to by Heidegger as logocentrism, and Derrida argues that the philosophical enterprise is essentially logocentric,[105] and that this is a paradigm inherited from Judaism and Hellenism.[106] He in turn describes logocentrism as phallocratic, patriarchal and masculinist.[106][107] Derrida contributed to "the understanding of certain deeply hidden philosophical presuppositions and prejudices in Western culture",[106] arguing that the whole philosophical tradition rests on arbitrary dichotomous categories (such as sacred/profane, signifier/signified, mind/body), and that any text contains implicit hierarchies, "by which an order is imposed on reality and by which a subtle repression is exercised, as these hierarchies exclude, subordinate, and hide the various potential meanings."[105] Derrida refers to his procedure for uncovering and unsettling these dichotomies as deconstruction of Western culture.[108] In 1968, he published his influential essay "Plato's Pharmacy" in the French journal Tel Quel.[109][110] This essay was later collected in Dissemination, one of three books published by Derrida in 1972, along with the essay collection Margins of Philosophy and the collection of interviews entitled Positions. |
1967年~1972年 デリダの関心は学問分野の境界を越えており、多種多様な事柄に関する彼の知識は、1967年に出版された3つの著作集に反映されている。『声と現象』、 『グラマトロジーについて』(当初はモーリス・ド・ガンディヤックのもとで博士論文として提出された)[38]、『筆跡と差異』である。 デリダは何度か、フッサールとハイデガーに対する負債を認め、彼らがいなければ自分は一言も発しなかっただろうと述べている。[92][93] これらの論文で問われた問題には、「『意味』とは何か、また、それが『声』という名目で特定されたものとの歴史的な関係は何か 存在の価値、対象の存在、意識における意味の存在、いわゆる生きた言葉における自己存在、自己意識における自己存在として「声」という見出しで特定されて いるものとの歴史的な関係は何か?」という問いがある。[91] 『書くことと差異』の別の論文「暴力と形而上学: エマニュエル・レヴィナスの思想に関する試論」と題された、デリダの思想におけるもうひとつの主要テーマのルーツが現れる。「脱構築的分析は、現在からそ の威信を奪い、まったく異なるもの、現在から予測可能なもの、 。」[95] ルソー、フッサール、ハイデガー、レヴィナス以外にも、これらの3冊の本は、言語学者ソシュール[96]、ヘーゲル[97]、フーコー[98]、バタイユ [ イル、デカルト、人類学者のレヴィ=ストロース、[99][100] 古生物学者のレロワ=グーラン、[101] 精神分析家のフロイト、[102] そしてジャベスやアルトーといった作家の作品を論じ、またそれらの作品に依拠している。 1967年に出版されたこの3冊の本のコレクションは、デリダの理論的枠組みを詳細に説明している。デリダは西洋の知的伝統の核心に迫ろうとし、この伝統 を「意味の起源または保証者となる超越的存在の探求」と特徴づけている。「世界を構成する意味の関係を、それ自体がすべての関係性から外れた事例に根拠づ ける」という試みは、ハイデガーによってロゴセントリズムと呼ばれたが、デリダは、この哲学的企ては本質的にロゴセントリックであり、これはユダヤ教とヘ レニズムから受け継いだパラダイムであると主張している。[106] デリダは、ロゴセントリズムを 男根主義、家父長制、男性原理主義であると述べている。[106][107] デリダは「西洋文化における特定の奥深くに隠された哲学的仮定や偏見の理解」に貢献した。[106] デリダは、哲学の伝統全体が恣意的な二分法カテゴリー(神聖/世俗、記号/意味、心/身体など)に基づいていると主張し、 あらゆるテキストには暗黙のヒエラルキーが含まれており、それによって現実に対して秩序が課され、微妙な抑圧が行使される。なぜなら、これらのヒエラル キーは様々な潜在的な意味を排除し、従属させ、隠してしまうからだ」と主張している。[105] デリダは、これらの二分法を明らかにし、不安定にするための自身の手法を、西洋文化の脱構築と呼んでいる。[108] 1968年、彼はフランス語の学術誌『テル・ケル』に、影響力のある論文「プラトンの薬局」を発表した。[109][110] この論文は後に、1972年にデリダが出版した3冊の著書の1つ『ディサミナシオン』に収録された。他の2冊は、論文集『マルガンス・ドゥ・フィロゾ フィー』とインタビュー集『ポジシオン』である。 |
| 1973–1980 Starting in 1972, Derrida produced on average more than one book per year. Derrida continued to produce important works, such as Glas (1974) and The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond (1980). Derrida received increasing attention in the United States after 1972, where he was a regular visiting professor and lecturer at several major American universities. In the 1980s, during the American culture wars, conservatives started a dispute over Derrida's influence and legacy upon American intellectuals,[64] and claimed that he influenced American literary critics and theorists more than academic philosophers.[105][111][need quotation to verify] |
1973年~1980年 1972年から、デリダは毎年平均して1冊以上の本を出版した。デリダは『グラス』(1974年)や『ポストカード:ソクラテスからフロイト、そしてその 先へ』(1980年)など、重要な作品を次々と発表した。 1972年以降、デリダは米国でますます注目を集めるようになった。米国の主要大学で定期的に客員教授や講師を務めていたからである。1980年代、米国 の文化戦争のさなか、保守派はデリダが米国の知識人に与えた影響と遺産をめぐって論争を開始し、デリダは学術的な哲学者よりも米国の文学評論家や理論家に 影響を与えたと主張した。[105][111][検証のため引用文が必要] |
| Of Spirit (1987) On 14 March 1987, Derrida presented at the CIPH conference entitled "Heidegger: Open Questions", a lecture which was published in October 1987 as Of Spirit: Heidegger and the Question. It follows the shifting role of Geist (spirit) through Heidegger's work, noting that, in 1927, "spirit" was one of the philosophical terms that Heidegger set his sights on dismantling.[112] With his Nazi political engagement in 1933, however, Heidegger came out as a champion of the "German Spirit", and only withdrew from an exalting interpretation of the term in 1953. Derrida asks, "What of this meantime?"[113] His book connects in a number of respects with his long engagement of Heidegger (such as "The Ends of Man" in Margins of Philosophy, his Paris seminar on philosophical nationality and nationalism in the mid-1980s, and the essays published in English as Geschlecht and Geschlecht II).[114] He considers "four guiding threads" of Heideggerian philosophy that form "the knot of this Geflecht [braid]": "the question of the question", "the essence of technology", "the discourse of animality", and "epochality" or "the hidden teleology or the narrative order."[115] Of Spirit contributes to the long debate on Heidegger's Nazism and appeared at the same time as the French publication of a book by a previously unknown Chilean writer, Victor Farías, who charged that Heidegger's philosophy amounted to a wholehearted endorsement of the Nazi Sturmabteilung (SA) faction. Derrida responded to Farías in an interview, "Heidegger, the Philosopher's Hell" and a subsequent article, "Comment donner raison? How to Concede, with Reasons?" He called Farías a weak reader of Heidegger's thought, adding that much of the evidence Farías and his supporters touted as new had long been known within the philosophical community.[116] |
精神について(1987年) 1987年3月14日、デリダはCIPH会議で「ハイデガー:未解決の問題」と題する講演を行い、その講演は1987年10月に『精神について:ハイデ ガーと問い』として出版された。この講演では、ハイデガーの著作におけるガイスト(精神)の役割の変遷を追っており、1927年には「精神」はハイデガー が解体を試みた哲学用語のひとつであったと指摘している。[112] しかし、1933年にナチスと政治的に関わったことで、ハイデガーは「ドイツ精神」の擁護者として名乗りを上げ、この用語の賛美的な解釈から撤退したのは 1953年になってからであった。デリダは「その間のことはどうなるのか?」と問いかけている。[113] 彼の著書は、ハイデガーとの長年にわたる関わり(例えば、1980年代半ばにパリで行われた哲学上の国民性とナショナリズムに関するセミナー『哲学の余 白』の「人間の終わり」や 1980年代半ばにパリで開かれた哲学上の国民性とナショナリズムに関するセミナー、および英語で『Geschlecht』および『Geschlecht II』として出版された論文集などである。[114] 彼は、ハイデガー哲学の「4つの指針となる糸」が「この織り目(Geflecht)の結び目」を形成していると考える。すなわち、「問いの問い」、「テク ノロジーの本質」、「動物性に関する言説」、そして「時代性」または「隠された目的論または物語の秩序」である。[115] 『精神について』は、ハイデガーのナチズムに関する長年の論争に一石を投じ、それと同時期に、それまで無名だったチリの作家、ビクトル・ファリアスの著書 がフランスで出版された。ファリアスは、ハイデガーの哲学はナチスの突撃隊(SA)派閥を全面的に支持するものに等しいと主張した。デリダはファリアスに 対してインタビュー「ハイデガー、哲学者の地獄」と、その後の記事「どうやって理由を挙げて認めるか?」で応じた。彼はファリアスをハイデガー思想の読解 力の乏しい人物と呼び、ファリアスとその支持者たちが新しいと主張する証拠の多くは、哲学界では以前から知られていたものだと付け加えた。[116] |
| 1990s: political and ethical
themes Some have argued that Derrida's work took a political and ethical "turn" in the 1990s. Texts cited as evidence of such a turn include Force of Law (1990), as well as Specters of Marx (1994) and Politics of Friendship (1994). Some refer to The Gift of Death as evidence that he began more directly applying deconstruction to the relationship between ethics and religion. In this work, Derrida interprets passages from the Bible, particularly on Abraham and the Sacrifice of Isaac,[117][118] and from Søren Kierkegaard's Fear and Trembling. However, scholars such as Leonard Lawlor, Robert Magliola, and Nicole Anderson (philosopher)[119] have argued that the "turn" has been exaggerated.[120][additional citation(s) needed] Some, including Derrida himself, have argued that much of the philosophical work done in his "political turn" can be dated to earlier essays.[121] Derrida develops an ethicist view respecting to hospitality, exploring the idea that two types of hospitalities exist, conditional and unconditional. Though this contributed to the works of many scholars, Derrida was seriously criticized for this.[122][123][124] Derrida's contemporary readings of Emmanuel Levinas, Walter Benjamin, Carl Schmitt, Jan Patočka, on themes such as law, justice, responsibility, and friendship, had a significant impact on fields beyond philosophy. Derrida and Deconstruction influenced aesthetics, literary criticism, architecture, film theory, anthropology, sociology, historiography, law, psychoanalysis, theology, feminism, gay and lesbian studies and political theory. Jean-Luc Nancy, Richard Rorty, Geoffrey Hartman, Harold Bloom, Rosalind Krauss, Hélène Cixous, Julia Kristeva, Duncan Kennedy, Gary Peller, Drucilla Cornell, Alan Hunt, Hayden White, Mario Kopić, and Alun Munslow are some of the authors who have been influenced by deconstruction. Derrida delivered a eulogy at Levinas' funeral, later published as Adieu à Emmanuel Lévinas, an appreciation and exploration of Levinas's moral philosophy. Derrida used Bracha L. Ettinger's interpretation of Lévinas' notion of femininity and transformed his own earlier reading of this subject respectively.[125] Derrida continued to produce readings of literature, writing extensively on Maurice Blanchot, Paul Celan, and others. In 1991 he published The Other Heading, in which he discussed the concept of identity (as in cultural identity, European identity, and national identity), in the name of which in Europe have been unleashed "the worst violences," "the crimes of xenophobia, racism, anti-Semitism, religious or nationalist fanaticism."[126] At the 1997 Cerisy Conference, Derrida delivered a ten-hour address on the subject of "the autobiographical animal" entitled The Animal That Therefore I Am (More To Follow). Engaging with questions surrounding the ontology of nonhuman animals, the ethics of animal slaughter and the difference between humans and other animals, the address has been seen as initiating a late "animal turn" in Derrida's philosophy, although Derrida himself has said that his interest in animals is present in his earliest writings.[127] |
1990年代:政治的・倫理的主題 デリダの作品は1990年代に政治的・倫理的な「転回」を迎えたという意見もある。そのような転回を示す証拠として引用されるテキストには、『法の力』 (1990年)や『マルクスの亡霊』(1994年)、『友愛の政治』(1994年)などがある。また、『死の贈与』を、倫理と宗教の関係に脱構築をより直 接的に適用し始めた証拠として挙げる者もいる。この作品で、デリダは聖書、特にアブラハムとイサクの犠牲に関する箇所[117][118]、そしてセーレ ン・キルケゴールの『畏れとおののき』を解釈している。 しかし、レナード・ローラー、ロバート・マグリオラ、ニコル・アンダーソン(哲学者)などの学者は、「転回」が誇張されていると主張している。[120] [追加の引用(複数可)が必要] デリダ自身を含む一部の者は、彼の「政治的転回」で行われた哲学的な仕事の多くは、それ以前の論文に遡ることができると主張している。[121] デリダは、もてなしに関する倫理学者の視点を発展させ、条件付きのもてなしと無条件のもてなしという2つのタイプのもてなしが存在するという考えを探究し た。これは多くの学者の研究に貢献したが、デリダはこれについて深刻な批判を受けた。[122][123][124] デリダによるエマニュエル・レヴィナス、ヴァルター・ベンヤミン、カール・シュミット、ヤン・パトチカなどの同時代的な解釈は、法、正義、責任、友情と いったテーマについてであり、哲学以外の分野にも大きな影響を与えた。 デリダと脱構築は、美学、文学批評、建築、映画理論、人類学、社会学、史学、法、精神分析、神学、フェミニズム、ゲイ・レズビアン研究、政治理論に影響を 与えた。ジャン=リュック・ナンシー、リチャード・ローティ、ジェフリー・ハートマン、ハロルド・ブルーム、ロザリンド・クラウス、エレーヌ・シクスー、 ジュリア・クリステヴァ、ダンカン・ケネディ、ゲイリー・ペラー、ドルシラ・コーネル、アラン・ハント、ヘイデン・ホワイト、マリオ・コピッチ、アルン・ マンズローなどは、脱構築の影響を受けた作家の一部である。 デリダはレヴィナスの葬儀で弔辞を読み、後に『アデュー・ア・エマニュエル・レヴィナス』として出版された。デリダはブラハ・L・エッティンガーによるレ ヴィナスの女性性の概念の解釈を用い、このテーマに関する自身の以前の解釈をそれぞれ変えた。 デリダは文学の解釈を続け、モーリス・ブランショ、パウル・ツェランなどについて幅広く執筆した。 1991年には『もうひとつの見出し』を出版し、その中でアイデンティティの概念(文化的なアイデンティティ、ヨーロッパのアイデンティティ、国民のアイ デンティティなど)について論じている。ヨーロッパでは、その名のもとに「最悪の暴力」、「外国人排斥、人種主義、反ユダヤ主義、宗教的またはナショナリ スト的狂信主義の犯罪」が引き起こされてきたと述べている。 1997年のセリシー会議で、デリダは「自伝的動物」というテーマで10時間にわたる講演を行った。題名は『それゆえ我あり(More To Follow)』である。人間以外の動物の存在論、動物の屠殺の倫理、人間と他の動物との違いといった問題を取り上げたこの講演は、デリダの哲学における 後期の「動物回帰」の始まりと見なされているが、デリダ自身は、動物への関心は初期の著作にも見られると述べている。[127] |
| The Work of Mourning (1981–2001) Beginning with "The Deaths of Roland Barthes" in 1981, Derrida produced a series of texts on mourning and memory occasioned by the loss of his friends and colleagues, many of them new engagements with their work. Memoires for Paul de Man, a book-length lecture series presented first at Yale and then at Irvine as Derrida's Wellek Lecture, followed in 1986, with a revision in 1989 that included "Like the Sound of the Sea Deep Within a Shell: Paul de Man's War". Ultimately, fourteen essays were collected into The Work of Mourning (2001), which was expanded in the 2003 French edition, Chaque fois unique, la fin du monde (literally, "Unique each time, the end of the world"), to include essays dedicated to Gérard Granel and Maurice Blanchot. |
喪の仕事(1981年~2001年) 1981年の「ロラン・バルトの死」に始まり、デリダは友人や同僚の死をきっかけに、喪と記憶に関する一連のテクストを制作した。その多くは、彼らの仕事 との新たな関わりであった。『ポール・ド・マンへの追悼の辞』は、イェール大学で最初に発表され、その後アーバイン大学でウェーレック講座として行われた 講演シリーズをまとめた書籍である。1986年に出版され、1989年に改訂版が出版された。最終的に、14編のエッセイは『The Work of Mourning』(2001年)にまとめられ、2003年のフランス語版『Chaque fois unique, la fin du monde』(直訳すると「毎回唯一無二、世界の終わり」)では、ジェラール・グラネルとモーリス・ブランショに捧げられたエッセイが追加された。 |
| 2002 film In October 2002, at the theatrical opening of the film Derrida, he said that, in many ways, he felt more and more close to Guy Debord's work, and that this closeness appears in Derrida's texts. Derrida mentioned, in particular, "everything I say about the media, technology, the spectacle, and the 'criticism of the show', so to speak, and the markets – the becoming-a-spectacle of everything, and the exploitation of the spectacle."[128] Among the places in which Derrida mentions the Spectacle, is a 1997 interview about the notion of the intellectual.[129] |
2002年の映画 2002年10月、映画『デリダ』の劇場公開時に、彼は、多くの点で、ギー・ドゥボールの作品にますます親近感を抱くようになり、その親近感が『デリダ』 のテキストに現れていると語った。とりわけ、デリダは「私がメディア、テクノロジー、スペクタクル、そしていわば『見世物の批判』、市場について語るすべ てのこと、つまり、あらゆるもののスペクタクル化、スペクタクルの搾取について」言及している。[128] デリダがスペクタクルについて言及している場所のひとつに、1997年の知識人についてのインタビューがある。[129] |
| Politics Derrida engaged with a variety of political issues, movements, and debates throughout his career. In 1968, he participated in the May 68 protests in France [and met frequently with Maurice Blanchot]?.[130] However, he expressed concerns about the "cult of spontaneity" and anti-unionist euphoria that he observed.[131] He also registered his objections to the Vietnam War in a lecture he gave in the United States. Derrida signed a petition against age of consent laws in 1977,[132] and in 1981 he founded the French Jan Hus association to support dissident Czech intellectuals.[133] In 1981, Derrida was arrested by the Czechoslovakian government for leading a conference without authorization and charged with drug trafficking, although he claimed the drugs were planted on him. He was released with the help of the Mitterrand government and Michel Foucault.[134] Derrida was an advocate for nuclear disarmament,[135] protested against apartheid in South Africa, and met with Palestinian intellectuals during a visit to Jerusalem in 1988. He also opposed capital punishment and was involved in the campaign to free Mumia Abu-Jamal.[citation needed] Although Derrida was not associated with any political party until 1995, he supported the Socialist candidacy of Lionel Jospin, despite misgivings about such organizations.[136] In the 2002 French presidential election, he refused to vote in the run-off election between far-right candidate Jean-Marie Le Pen and center-right Jacques Chirac, citing a lack of acceptable choices.[137] Derrida opposed the 2003 invasion of Iraq and was engaged in rethinking politics and the political itself within and beyond philosophy. He focused on understanding the political implications of notions such as responsibility, reason of state, decision, sovereignty, and democracy. By 2000, he was theorizing "democracy to come" and thinking about the limitations of existing democracies.[citation needed] |
政治 デリダは、そのキャリアを通じて、さまざまな政治問題、運動、論争に関わっていた。1968年には、フランスにおける5月革命に参加し、モーリス・ブラン ショと頻繁に会っていた。[130] しかし、彼は「自発性の崇拝」と、彼が観察した反組合主義の陶酔状態について懸念を表明した。[131] また、アメリカ合衆国で行った講演では、ベトナム戦争に反対する意見を述べた。1977年には、デリダは同意年齢法に反対する請願書に署名し[132]、 1981年には、チェコの反体制派知識人を支援するフランス・ヤン・フス協会を設立した[133]。 1981年、デリダは許可なく会議を主宰したとしてチェコスロバキア政府に逮捕され、麻薬密売の容疑をかけられたが、麻薬は自分に仕掛けられたものだと主 張した。彼はミッテラン政権とミシェル・フーコーの助力により釈放された。[134] デリダは核軍縮の提唱者であり[135]、南アフリカのアパルトヘイトに抗議し、1988年のエルサレム訪問時にはパレスチナの知識人たちと会合した。ま た、死刑にも反対し、ムミア・アブ・ジャマール釈放運動にも関与していた。[要出典] 1995年まではどの政党にも所属していなかったが、デリダは社会党のリオネル・ジョスパン候補を支持した。このような組織に対する疑念を抱きながらも、 である。[136] 2002年のフランス大統領選挙では、 極右のジャン=マリー・ル・ペン候補と中道右派のジャック・シラク候補による決選投票には、受け入れられる選択肢がないことを理由に棄権した。[137] デリダは2003年のイラク侵攻に反対し、政治や政治そのものを哲学の枠内および枠外で再考する活動に従事していた。彼は、責任、国家の理由、決定、主 権、民主主義といった概念の政治的意味合いを理解することに重点を置いていた。2000年までに、彼は「来るべき民主主義」を理論化し、既存の民主主義の 限界について考えていた。[要出典] |
| Influences on Derrida Crucial readings in his adolescence were Rousseau's Reveries of a Solitary Walker and Confessions, André Gide's journal, La porte étroite, Les nourritures terrestres and The Immoralist;[37] and the works of Friedrich Nietzsche.[37] The phrase Families, I hate you! in particular, which inspired Derrida as an adolescent, is a famous verse from Gide's Les nourritures terrestres, book IV.[138] In a 1991 interview Derrida commented on a similar verse, also from book IV of the same Gide work: "I hated the homes, the families, all the places where man thinks he'll find rest" (Je haïssais les foyers, les familles, tous lieux où l'homme pense trouver un repos).[139] Other influences upon Derrida are Martin Heidegger,[92][93] Plato, Søren Kierkegaard, Alexandre Kojève, Maurice Blanchot, Antonin Artaud, Roland Barthes, Georges Bataille, Edmund Husserl, Emmanuel Lévinas, Ferdinand de Saussure, Sigmund Freud, Karl Marx, Claude Lévi-Strauss, James Joyce, Samuel Beckett, J. L. Austin[62] and Stéphane Mallarmé.[140] His book, Adieu à Emmanuel Lévinas, reveals his mentorship by this philosopher and Talmudic scholar who practiced the phenomenological encounter with the Other in the form of the Face, which commanded human response.[141] The use of deconstruction to read Jewish texts – like the Talmud – is relatively rare but has recently been attempted.[142] |
デリダへの影響 青年期におけるデリダの重要な読書は、ルソーの『孤独な散歩者の夢想』と『告白』、アンドレ・ジイドの日記『狭き門』、『地上の養育』、『不道徳な者』、 そしてフリードリヒ・ニーチェの著作であった。[37] 特に、 特に「家族よ、お前たちを憎む!」というフレーズは、青年期のデリダにインスピレーションを与えたもので、ギドの『地上の養育』第4巻からの有名な一節で ある。[138] 1991年のインタビューで、デリダは同じくギドの作品第4巻からの類似した一節について次のようにコメントしている。「私は家庭や家族、人間が安らぎを 見出せると考えるあらゆる場所を嫌っていた」(Je haïssais les foyers, les familles, tous lieux où l'homme pense trouver un repos)と述べている。[139] デリダに影響を与えたその他の人物としては、マルティン・ハイデガー[92][93]、プラトン、セーレン・キルケゴール、アレクサンドル・コジェーヴ、 モーリス・ブランショ、アントナン・アルトー、ロラン・バルト、ジョルジュ・バタイユ、エドマンド・フッサール エル、エマニュエル・レヴィナス、フェルディナン・ド・ソーシュール、ジークムント・フロイト、カール・マルクス、クロード・レヴィ=ストロース、ジェイ ムズ・ジョイス、サミュエル・ベケット、J.L. オースティン[62]、ステファヌ・マラルメ[140] 著書『Adieu à Emmanuel Lévinas』では、この哲学者でありタルムード学者であるレヴィナスが、他者との現象学的出会いを「顔」という形で実践し、人間の反応を導いていたこ とについて、彼の指導者としての役割が明らかにされている。[141] ユダヤ教のテキスト(タルムードなど)を読み解くために脱構築を用いることは比較的まれであるが、最近では試みられている。[142] |
| Peers and contemporaries This section needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources in this section. Unsourced material may be challenged and removed. Find sources: "Jacques Derrida" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2022) (Learn how and when to remove this message) This section possibly contains original research. Please improve it by verifying the claims made and adding inline citations. Statements consisting only of original research should be removed. (December 2022) (Learn how and when to remove this message) Derrida's philosophical friends, allies, students and the heirs of Derrida's thought include Paul de Man, Jean-François Lyotard, Louis Althusser, Emmanuel Levinas, Maurice Blanchot, Gilles Deleuze, Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe, Sarah Kofman, Hélène Cixous, Bernard Stiegler, Alexander García Düttmann, Joseph Cohen, Geoffrey Bennington, Jean-Luc Marion, Gayatri Chakravorty Spivak, Raphael Zagury-Orly, Jacques Ehrmann, Avital Ronell, Judith Butler, Béatrice Galinon-Mélénec, Ernesto Laclau, Samuel Weber, Catherine Malabou, and Claudette Sartiliot. |
同世代の人物 この節には検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。 出典の無い内容は、異議申し立てにより削除される場合があります。「ジャック・デリダ」 – ニュース · 新聞 · 書籍 · 学者 · JSTOR (2022年12月) (Learn how and when to remove this message) この節には独自研究の内容が含まれている可能性があります。 その主張が正しいことを検証し、適切な形で引用を追加するなどして、改善してください。 独自研究のみに依拠する内容は削除すべきです。 (2022年12月) (Learn how and when to remove this message) デリダの哲学的友人、同盟者、弟子、そしてデリダの思想の継承者には、ポール・ド・マン、ジャン=フランソワ・リオタール、ルイ・アルチュセール、エマ ニュエル・レヴィナス、モーリス・ブランショ、ジル・ドゥルーズ、ジャン=リュック・ナンシー、フィリップ・ラクー=ラバルト、サラ・コフマン、エレー ヌ・シクスー、ベルナール・スティグレール 、アレクサンダー・ガルシア・デットマン、ジョセフ・コーエン、ジェフリー・ベニントン、ジャン=リュック・マリオン、ガヤトリ・C・スピヴァク、ラファ エル・ザグリ・オルリ、ジャック・エールマン、アヴィタル・ロネル、ジュディス・バトラー、ベアトリス・ガリノン=メレネック、エルネスト・ラクラウ、サ ミュエル・ウェーバー、キャサリン・マラブー、クロデット・サルトリオ。 |
| Nancy and Lacoue-Labarthe Jean-Luc Nancy and Philippe Lacoue-Labarthe were among Derrida's first students in France and went on to become well-known and important philosophers in their own right. Despite their considerable differences of subject, and often also of a method, they continued their close interaction with each other and with Derrida, from the early 1970s. Derrida wrote on both of them, including a long book on Nancy: Le Toucher, Jean-Luc Nancy (On Touching—Jean-Luc Nancy, 2005). |
ナンシーとラクー=ラバルト ジャン=リュック・ナンシーとフィリップ・ラクー=ラバルトは、フランスにおけるデリダの最初の学生の一人であり、やがてそれぞれに著名で重要な哲学者と なった。主題や方法においてかなりの相違があったにもかかわらず、1970年代初頭から、彼らは互いに、そしてデリダと緊密な交流を続けた。 デリダは、ナンシーに関する長編『Le Toucher, Jean-Luc Nancy(触れることについて—ジャン=リュック・ナンシー、2005年)』を含む、両者に関する著作を残している。 |
| Paul de Man Main article: Paul de Man Derrida's most prominent friendship in intellectual life was with Paul de Man, which began with their meeting at Johns Hopkins University and continued until de Man's death in 1983. De Man provided a somewhat different approach to deconstruction, and his readings of literary and philosophical texts were crucial in the training of a generation of readers. Shortly after de Man's death, Derrida wrote the book Memoires: pour Paul de Man and in 1988 wrote an article in the journal Critical Inquiry called "Like the Sound of the Sea Deep Within a Shell: Paul de Man's War". The memoir became cause for controversy, because shortly before Derrida published his piece, it had been discovered by the Belgian literary critic Ortwin de Graef that long before his academic career in the US, de Man had written almost two hundred essays in a pro-Nazi newspaper during the German occupation of Belgium, including several that were explicitly antisemitic. Critics of Derrida have argued that he minimizes the antisemitic character of de Man's writing. Some critics have found Derrida's treatment of this issue surprising, given that, for example, Derrida also spoke out against antisemitism and, in the 1960s, broke with the Heidegger disciple Jean Beaufret over Beaufret's instances of antisemitism, about which Derrida (and, after him, Maurice Blanchot) expressed shock. |
ポール・ド・マン 詳細は「ポール・ド・マン」を参照 デリダの知的生活において最も著名な交友関係はポール・ド・マンとのもので、ジョンズ・ホプキンス大学での出会いから始まり、ド・マンの1983年の死ま で続いた。ド・マンは脱構築に対してやや異なるアプローチを提供し、文学や哲学のテキストの彼の解釈は、読者世代の育成において極めて重要な役割を果たし た。 ド・マンの死後まもなく、デリダは『追憶:ポール・ド・マンに捧ぐ』を著し、1988年には『クリティカル・インクワイアリー』誌に「貝殻の奥深く響く海 の音のように:ポール・ド・マンの戦争」という論文を発表した。この回顧録は論争の的となった。というのも、デリダがこの論文を発表する少し前に、ベル ギーの文学評論家オルトウィン・ド・グラーフが、デ・マンが米国で学術的なキャリアを積むずっと以前に、ドイツによるベルギー占領下で親ナチス新聞に 200本近いエッセイを寄稿しており、その中には明白な反ユダヤ主義的な内容のものも含まれていたことを発見していたからだ。 デリダの批判者たちは、ド・マンの著作の反ユダヤ主義的な性格をデリダが軽視していると主張している。デリダが反ユダヤ主義に反対の立場を表明し、 1960年代にはハイデガーの弟子ジャン・ボーフレが反ユダヤ主義的言動を理由に師と決別したことについて、デリダもショックを表明していたことを考える と、この問題に対するデリダの対応は意外であると指摘する批評家もいる。 |
| Michel Foucault Derrida's criticism of Foucault appears in the essay Cogito and the History of Madness (from Writing and Difference). It was first given as a lecture on 4 March 1963, at a conference at Wahl's Collège philosophique, which Foucault attended, and caused a rift between the two men that was never fully mended.[43] In an appendix added to the 1972 edition of his History of Madness, Foucault disputed Derrida's interpretation of his work, and accused Derrida of practicing "a historically well-determined little pedagogy [...] which teaches the student that there is nothing outside the text [...]. A pedagogy which inversely gives to the voice of the masters that infinite sovereignty that allows it indefinitely to re-say the text."[143] According to historian Carlo Ginzburg, Foucault may have written The Order of Things (1966) and The Archaeology of Knowledge partly under the stimulus of Derrida's criticism.[144] Carlo Ginzburg briefly labeled Derrida's criticism in Cogito and the History of Madness, as "facile, nihilistic objections," without giving further argumentation.[144] |
ミシェル・フーコー フーコーに対するデリダの批判は、エッセイ『コギト』と『狂気の歴史』(『書記』と『差異』より)に示されている。 1963年3月4日、フーコーが出席したワル・コレージュ・フィロソフィックの会議で初めて講演が行われ、このことが2人の間に決定的な亀裂を生み、その 後完全に修復されることはなかった。 1972年の『狂気の歴史』の増補版で、フーコーは自身の著作に対するデリダの解釈に異議を唱え、デリダが「歴史的に十分に決定された小さな教育」を実践 していると非難した。「この教育は、学生にテキストの外側に何もないと教えるものである。逆に師の声に無限の主権を与え、テキストを際限なく再解釈するこ とを許すような教育法」であると非難した。[143] 歴史家のカルロ・ギンズブルクによると、フーコーは『物事の秩序』(1966年)と『 デリダの批判に刺激されて書いた部分もあるかもしれないと述べている。[144] カルロ・ギンズブルクは、『狂気の歴史と「我思う」』におけるデリダの批判を「安易で虚無的な異議申し立て」と簡単に表現し、それ以上の論証は示さなかっ た。[144] |
| Derrida's translators Geoffrey Bennington, Avital Ronell and Samuel Weber belong to a group of Derrida translators. Many of Derrida's translators are esteemed thinkers in their own right. Derrida often worked in a collaborative arrangement, allowing his prolific output to be translated into English in a timely fashion. Having started as a student of de Man, Gayatri Spivak took on the translation of Of Grammatology early in her career and has since revised it into a second edition. Barbara Johnson's translation of Derrida's Dissemination was published by The Athlone Press in 1981. Alan Bass was responsible for several early translations; Bennington and Peggy Kamuf have continued to produce translations of his work for nearly twenty years. In recent years, a number of translations have appeared by Michael Naas (also a Derrida scholar) and Pascale-Anne Brault. Bennington, Brault, Kamuf, Naas, Elizabeth Rottenberg, and David Wills are currently engaged in translating Derrida's previously unpublished seminars, which span from 1959 to 2003.[145] Volumes I and II of The Beast and the Sovereign (presenting Derrida's seminars from 12 December 2001 to 27 March 2002 and from 11 December 2002 to 26 March 2003), as well as The Death Penalty, Volume I (covering 8 December 1999 to 22 March 2000), have appeared in English translation. Further volumes currently projected for the series include Heidegger: The Question of Being and History (1964–1965), Death Penalty, Volume II (2000–2001), Perjury and Pardon, Volume I (1997–1998), and Perjury and Pardon, Volume II (1998–1999).[146] With Bennington, Derrida undertook the challenge published as Jacques Derrida, an arrangement in which Bennington attempted to provide a systematic explication of Derrida's work (called the "Derridabase") using the top two-thirds of every page, while Derrida was given the finished copy of every Bennington chapter and the bottom third of every page in which to show how deconstruction exceeded Bennington's account (this was called the "Circumfession"). Derrida seems to have viewed Bennington in particular as a kind of rabbinical explicator, noting at the end of the "Applied Derrida" conference, held at the University of Luton in 1995 that: "everything has been said and, as usual, Geoff Bennington has said everything before I have even opened my mouth. I have the challenge of trying to be unpredictable after him, which is impossible... so I'll try to pretend to be unpredictable after Geoff. Once again."[147] |
デリダの翻訳者 ジェフリー・ベニントン、アヴィタル・ローネル、サミュエル・ウェーバーは、デリダの翻訳者グループに属している。デリダの翻訳者の多くは、それぞれが著 名な思想家である。デリダは共同作業を頻繁に行い、その多作な著作をタイムリーに英訳することを可能にした。 ド・マンの学生としてスタートしたガヤトリ・スピヴァクは、キャリアの初期に『グラマトロジーについて』の翻訳を手がけ、その後、第2版に改訂した。バー バラ・ジョンソンの翻訳した『ディシプリン』は、1981年にアスローン・プレス社から出版された。アラン・バス(Alan Bass)は初期のいくつかの翻訳を担当し、ベニントンとペギー・カムフは20年近くにわたって彼の作品の翻訳を続けている。近年では、マイケル・ナース (Michael Naas)とパスカル=アンヌ・ブラウ(Pascale-Anne Brault)による翻訳が多数出版されている。 ベニングトン、ブラウル、カムフ、ナース、エリザベス・ロッテンバーグ、デイヴィッド・ウィルズは現在、1959年から2003年にかけて行われたデリダ の未発表セミナーの翻訳に取り組んでいる。[145] 『野獣と主権者』の第1巻と第2巻( 2001年12月12日から2002年3月27日、および2002年12月11日から2003年3月26日)のセミナーを収録した『野獣と主権者』第1巻 と第2巻、および『死刑制度』第1巻(1999年12月8日から2000年3月22日)が英訳されている。現在、このシリーズで予定されているその他の巻 には、『ハイデガー:存在の問いと歴史』(1964年~1965年)、『死刑、第2巻』(2000年~2001年)、『偽証と恩赦、第1巻』(1997年 ~1998年)、『偽証と恩赦、第2巻』(1998年~1999年)がある。[146] ベニントンとともに、デリダは『ジャック・デリダ』という課題に取り組み、ベニントンは各ページの上3分の2を使ってデリダの著作の体系的な説明(「デリ ダベース」と呼ばれる)を試み、デリダにはベニントンの各章の完成版と各ページの下3分の1が渡され、脱構築がベニントンの説明をどのように超えるかを示 した(これは「Circumfession」と呼ばれた)。デリダは特にベニントンをラビの解説者のような存在と捉えていたようで、1995年にルートン 大学で開催された「応用デリダ」会議の最後に次のように述べている。「すべては語り尽くされた。そして、いつものように、私が口を開く前にジェフ・ベニン トンがすべてを語ってしまった。私は彼に続いて予測不可能であろうとするという課題に直面しているが、それは不可能だ...だから、ジェフに続いて予測不 可能であろうとするふりをしてみる。もう一度」[147] |
| Marshall McLuhan Derrida was familiar with the work of Marshall McLuhan, and since his early 1967 writings (Of Grammatology, Speech and Phenomena), he speaks of language as a "medium,"[148] of phonetic writing as "the medium of the great metaphysical, scientific, technical, and economic adventure of the West."[149] He expressed his disagreement with McLuhan in regard to what Derrida called McLuhan's ideology about the end of writing.[150] In a 1982 interview, he said: I think that there is an ideology in McLuhan's discourse that I don't agree with because he's an optimist as to the possibility of restoring an oral community which would get rid of the writing machines and so on. I think that's a very traditional myth which goes back to... let's say Plato, Rousseau... And instead of thinking that we are living at the end of writing, I think that in another sense we are living in the extension – the overwhelming extension – of writing. At least in the new sense... I don't mean the alphabetic writing down, but in the new sense of those writing machines that we're using now (e.g. the tape recorder). And this is writing too.[151] And in his 1972 essay Signature Event Context he said: As writing, communication, if one insists upon maintaining the word, is not the means of transport of sense, the exchange of intentions and meanings, the discourse and "communication of consciousnesses." We are not witnessing an end of writing which, to follow McLuhan's ideological representation, would restore a transparency or immediacy of social relations; but indeed a more and more powerful historical unfolding of a general writing of which the system of speech, consciousness, meaning, presence, truth, etc., would only be an effect, to be analyzed as such. It is this questioned effect that I have elsewhere called logocentrism.[152] |
マー
シャル・マクルーハン デリダはマーシャル・マクルーハンの著作に精通しており、1967年初頭の著作(『グラマトロジーについて』、『声と現象』)以来、彼は言語を「媒体」 [148]、音声表記を「西洋の偉大な形而上学的、科学的、技術的、経済的冒険の媒体」[149]と表現している。 デリダが「書記の終焉」についてマクルーハンの思想と呼んだことについて、彼はマクルーハンに反対の意見を述べた。[150] 1982年のインタビューで、彼は次のように述べた。 マクルーハンはオーラル・コミュニティを復興させる可能性について楽観的であり、私はそれに同意できない。なぜなら、彼はオーラル・コミュニティが文字機 械などを駆逐するだろうと考えているからだ。私は、それは非常に伝統的な神話であり、その起源は... 例えばプラトンやルソーまで遡ると思う。文字の終焉を迎えていると考えるのではなく、文字の延長線上、文字の圧倒的な延長線上に私たちは生きているのだと 思う。少なくとも新しい意味において... 私が言っているのは、アルファベットによる文字の書き留めではなく、今私たちが使っている文字機械(テープレコーダーなど)の新しい意味においてだ。これ も文字である。[151] また、1972年のエッセイ『署名の出来事の文脈』では、次のように述べている。 「もし言葉の維持に固執するならば、コミュニケーションや記述は、意味の伝達手段ではなく、意図や意味の交換、言説や「意識の伝達」である。マクルーハン の思想的な表現に従うならば、社会関係の透明性や即時性を回復するような文字の終焉を目撃しているわけではない。しかし、実際には、音声、意識、意味、存 在、真実などのシステムが単なる効果にすぎず、そのように分析されるべきであるという、一般的な文字の歴史的な展開がますます強まっている。私が他の場所 でロゴセントリズムと呼んだのは、まさにこの疑わしい効果である。[152] |
| Architectural thinkers Derrida had a direct impact on the theories and practices of influential architects Peter Eisenman and Bernard Tschumi towards the end of the twentieth century. Derrida impacted a project that was theorized by Eisenman in Chora L Works: Jacques Derrida and Peter Eisenman.[153] This design was architecturally conceived by Tschumi for the Parc de la Villette in Paris, which included a sieve, or harp-like structure that Derrida envisaged as a physical metaphor for the receptacle-like properties of the khôra. Moreover, Derrida's commentaries on Plato's notion of khôra (χώρα) as set in the Timaeus (48e4) received later reflections in the philosophical works and architectural writings of the philosopher-architect Nader El-Bizri within the domain of phenomenology. Derrida used "χώρα" to name a radical otherness that "gives place" for being. El-Bizri built on this by more narrowly taking khôra to name the radical happening of an ontological difference between being and beings.[154] El-Bizri's reflections on "khôra" are taken as a basis for tackling the meditations on dwelling and on being and space in Heidegger's thought and the critical conceptions of space and place as they evolved in architectural theory (and its strands in phenomenological thinking),[155] and in history of philosophy and science, with a focus on geometry and optics.[156] This also describes El-Bizri's take on "econtology" as an extension of Heidegger's consideration of the question of being (Seinsfrage) by way of the fourfold (Das Geviert) of earth-sky-mortals-divinities (Erde und Himmel, Sterblichen und Göttlichen); and as also impacted by his own meditations on Derrida's take on "χώρα". Ecology is hence co-entangled with ontology, whereby the worldly existential analytics are grounded in earthiness, and environmentalism is orientated by ontological thinking[157][158][159] Derrida argued that the subjectile is like Plato's khôra, Greek for space, receptacle or site. Plato proposes that khôra rests between the sensible and the intelligible, through which everything passes but in which nothing is retained. For example, an image needs to be held by something, just as a mirror will hold a reflection. For Derrida, khôra defies attempts at naming or the either/or logic, which he "deconstructed". |
建築思想家 デリダは、20世紀末に活躍した著名な建築家ピーター・アイゼンマンとベルナール・チュミの理論と実践に直接的な影響を与えた。デリダは、アイゼンマンが 『Chora L Works』で理論化したプロジェクトに影響を与えた。ジャック・デリダとピーター・アイゼンマンによるもの。[153] この設計は、デリダがコーラの容器のような性質を物理的な比喩として想定したふるい、あるいはハープのような構造を含み、ツクミがパリのヴィレット公園の ために建築的に構想したものである。さらに、ティマイオス(48e4)で示されたプラトンのコーラ(χώρα)の概念に関するデリダの論評は、現象学の領 域において、哲学者であり建築家でもあるナデル・エル=ビズリの哲学作品や建築作品に後々まで影響を与えた。 デリダは「χώρα」という用語を用いて、存在の「場」となる根源的な他者性を表現した。エル・ビズリは、khôraをより狭義に解釈し、存在と存在者間 の本質的な差異の根源的な出来事を表現した。[154] エル・ビズリの「khôra」に関する考察は、ハイデガーの思想における住居と存在と空間に関する思索、 建築理論(および現象学的な思考の諸潮流)において発展した空間と場所に関する批判的な概念、幾何学と光学に焦点を当てた哲学と科学の歴史において、ハイ デガーの思想と 大地-天空-人間-神々(Erde und Himmel, Sterblichen und Göttlichen)の4つの要素(Das Geviert)による存在の問題(Seinsfrage)の考察を拡張したものとして、また、デリダの「χώρα」に関する考察に影響を受けたものとし て、エル=ビズリの「エコロジー」の捉え方を説明している。したがって、生態学は存在論と絡み合っており、世俗的な実存分析は土着性に根ざし、環境主義は 存在論的思考によって方向づけられている[157][158][159]。デリダは、主観はプラトンのコーラ(khôra)に似ていると主張した。コーラ はギリシャ語で空間、容器、場所を意味する。プラトンは、khôraは知覚できるものと知覚できないものの間に位置し、あらゆるものがそこを通過するが、 そこには何も留まることはできないと主張している。例えば、鏡が反射を保持するように、イメージは何かによって保持される必要がある。デリダにとって、 khôraは命名や二元論の論理を拒否するものであり、彼はそれを「脱構築」した。 【追記】 コーラとは、プラトンがいうイデア的なかたちを受け入れる場所のことをさす。プラトンのティマイオスでは、造化の神でミウルゴスは、あらゆるマチエールに永久不変のイデアに基づいた、理想的かたちを与えることで、造化をこころみる。 |
| Criticism Criticism from Marxists In a paper entitled Ghostwriting,[160] Gayatri Chakravorty Spivak—the translator of Derrida's De la grammatologie (Of Grammatology) into English—criticised Derrida's understanding of Marx.[161] Commenting on Derrida's Specters of Marx, Terry Eagleton wrote "The portentousness is ingrained in the very letter of this book, as one theatrically inflected rhetorical question tumbles hard on the heels of another in a tiresomely mannered syntax which lays itself wide open to parody."[162] |
批判 マルクス主義者からの批判 ゴーストライティングと題された論文[160]において、デリダの『グラマトロジーについて』の英訳者であるガヤトリ・C・スピヴァクは、デリダのマルク ス解釈を批判した。 テリー・イーグルトンは「この本の文字には、芝居がかった修辞的な質問が、退屈なまでにわざとらしい構文で次から次へと続くように、重大さが染み込んでい る。それは、パロディに完全にさらけ出されている」と書いた。[162] |
| Criticism from Anglophone
philosophers Though Derrida addressed the American Philosophical Association on at least one occasion in 1988,[163] and was highly regarded by some contemporary philosophers like Richard Rorty, Alexander Nehamas,[164] and Stanley Cavell, his work has been regarded by other analytic philosophers, such as John Searle and Willard Van Orman Quine,[165] as pseudophilosophy or sophistry. Some analytic philosophers have in fact claimed, since at least the 1980s, that Derrida's work is "not philosophy". One of the main arguments they gave was alleging that Derrida's influence had not been on US philosophy departments but on literature and other humanities disciplines.[105][111] In his 1989 Contingency, Irony, and Solidarity, Richard Rorty argues that Derrida (especially in his book, The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond, one section of which is an experiment in fiction) purposefully uses words that cannot be defined (e.g., différance), and uses previously definable words in contexts diverse enough to make understanding impossible, so that the reader will never be able to contextualize Derrida's literary self. Rorty, however, argues that this intentional obfuscation is philosophically grounded. In garbling his message Derrida is attempting to escape the naïve, positive metaphysical projects of his predecessors.[166] Roger Scruton wrote in 2004, "He's difficult to summarise because it's nonsense. He argues that the meaning of a sign is never revealed in the sign but deferred indefinitely and that a sign only means something by virtue of its difference from something else. For Derrida, there is no such thing as meaning – it always eludes us and therefore anything goes."[167] On Derrida's scholarship and writing style, Noam Chomsky wrote "I found the scholarship appalling, based on pathetic misreading; and the argument, such as it was, failed to come close to the kinds of standards I've been familiar with since virtually childhood. Well, maybe I missed something: could be, but suspicions remain, as noted."[168] Paul R. Gross and Norman Levitt also criticized his work for misusing scientific terms and concepts in Higher Superstition: The Academic Left and Its Quarrels With Science (1994).[169] Three quarrels (or disputes) in particular went out of academic circles and received international mass media coverage: the 1972–88 quarrel with John Searle, the analytic philosophers' pressures on Cambridge University not to award Derrida an honorary degree, and a dispute with Richard Wolin and the NYRB. |
英語圏の哲学者からの批判 デリダは1988年に少なくとも一度はアメリカ哲学協会で演説を行い[163]、リチャード・ローティ、アレクサンダー・ネハマス[164]、スタン リー・カヴェルといった現代の哲学者たちからは高く評価されていたものの、ジョン・サールやウィラード・ヴァン・オーマン・クワイン[165]といった他 の分析哲学者たちからは、彼の仕事は偽哲学や詭弁であるとみなされてきた。 実際、少なくとも1980年代以降、デリダの仕事は「哲学ではない」と主張する分析哲学者もいた。彼らの主な主張のひとつは、デリダが影響を与えたのはア メリカの哲学科ではなく、文学やその他の人文科学分野であったという主張であった[105][111]。 リチャード・ローティは1989年の『偶発性、アイロニー、連帯』の中で、デリダ(特にその著書『ポストカード』において)は、「ソクラテスからフロイ ト、そして連帯へ」と主張している: ソクラテスからフロイトへ、そしてその先へ』(その一節はフィクションの実験である)において、デリダは意図的に定義できない言葉(例えば差延)を使い、 以前は定義できた言葉を、理解を不可能にするほど多様な文脈で使うことで、読者がデリダの文学的自己を文脈化することができないようにしていると論じてい る。しかしローティは、この意図主義的な難読化には哲学的な根拠があると主張する。デリダは自分のメッセージを文字化することで、先人たちのナイーブでポ ジティ ブな形而上学的プロジェクトから逃れようとしているのである[166]。 ロジャー・スクルー トンは2004年に「彼はナンセンスなので要約するのが難しい」と書いている。デリダは、記号の意味は記号の中で明らかにされることはなく、無限に先延ば しされるものであり、記号は他の何かとの差異によってのみ何かを意味すると主張している。デリダにとって、意味などというものは存在せず、それは常に私た ちから逃れ、したがって何でもありなのである」[167]。 デリダの学問と文体について、ノーム・チョムスキーは「私はその学問が、哀れな誤読に基づく、ひどいものであると感じた。まあ、私が何かを見落としていた のかもしれない。そうかもしれないが、前述のように疑念は残る」[168]。 ポール・R・グロスとノーマン・レヴィットもまた、『Higher Superstition』の中で、科学用語や概念を誤用していると批判している: The Academic Left and Its Quarrels With Science』(1994年)[169]。 1972年から88年にかけてのジョン・サールとの論争、分析哲学者たちがデリダに名誉学位を授与しないようケンブリッジ大学に圧力をかけたこと、そして リチャード・ウォリンとNYRBとの論争である。 |
| Searle–Derrida debate Main article: Searle–Derrida debate |
|
| Cambridge honorary doctorate In 1992 some academics at Cambridge University, mostly not from the philosophy faculty, proposed that Derrida be awarded an honorary doctorate. This was opposed by, among others, the university's Professor of Philosophy Hugh Mellor. Eighteen other philosophers from US, Austrian, Australian, French, Polish, Italian, German, Dutch, Swiss, Spanish, and British institutions, including Barry Smith, Willard Van Orman Quine, David Armstrong, Ruth Barcan Marcus, and René Thom, then sent a letter to Cambridge claiming that Derrida's work "does not meet accepted standards of clarity and rigour" and describing Derrida's philosophy as being composed of "tricks and gimmicks similar to those of the Dadaists". The letter concluded that: ... where coherent assertions are being made at all, these are either false or trivial. Academic status based on what seems to us to be little more than semi-intelligible attacks upon the values of reason, truth, and scholarship is not, we submit, sufficient grounds for the awarding of an honorary degree in a distinguished university.[170] In the end the protesters were outnumbered—336 votes to 204—when Cambridge put the motion to a formal ballot;[171] though almost all of those who proposed Derrida and who voted in favour were not from the philosophy faculty.[172] Hugh Mellor continued to find the award undeserved, explaining: "He is a mediocre, unoriginal philosopher — he is not even interestingly bad".[173] Derrida suggested in an interview that part of the reason for the attacks on his work was that it questioned and modified "the rules of the dominant discourse, it tries to politicize and democratize education and the university scene". To answer a question about the "exceptional violence", the compulsive "ferocity", and the "exaggeration" of the "attacks", he would say that these critics organize and practice in his case "a sort of obsessive personality cult that philosophers should know how to question and above all to moderate".[174] |
ケンブリッジ名誉博士号 1992年、ケンブリッジ大学の一部の学者(その多くは哲学部出身者ではない)が、デリダに名誉博士号を授与することを提案した。これに反対したのは、と りわけ同大学のヒュー・メラー哲学教授であった。その後、バリー・スミス、ウィラード・ヴァン・オーマン・クワイン、デイヴィッド・アームストロング、 ルース・バルカン・マーカス、ルネ・トムを含む、米国、オーストリア、オーストラリア、フランス、ポーランド、イタリア、ドイツ、オランダ、スイス、スペ イン、英国の18人の哲学者がケンブリッジ大学に書簡を送り、デリダの研究は「明晰さと厳密さにおいて受け入れられている基準に達していない」と主張し、 デリダの哲学は「ダダイストのものと同様のトリックや仕掛け」で構成されていると述べた。書簡は次のように結んでいる: 首尾一貫した主張がなされている場合、それは虚偽か些細なものである。理性、真実、学問という価値観に対する半可通の攻撃に過ぎないと思われるものに基づ く学問的地位は、著名な大学において名誉学位を授与する十分な根拠にはならないと我々は提出する」[170]。 しかし、デリダを推薦し、賛成票を投じた者のほぼ全員が哲学部出身ではなかった[172]。 ヒュー・メラーは引き続き、この授与はふさわしくないと考えており、次のように説明している: 「彼は凡庸で独創性のない哲学者であり、興味深いほど悪いわけでもない」[173]。 デリダはインタビューの中で、彼の著作が攻撃される理由のひとつは、「支配的な言説のルールに疑問を投げかけ、それを修正することであり、教育や大学の現 場を政治化し、民主化しようとすることである」と示唆している。攻撃」の「例外的な暴力性」、強迫的な「獰猛さ」、「誇張」についての質問に答えるため に、彼はこれらの批評家たちが、彼の場合「哲学者が疑問を投げかけ、とりわけ穏健化する方法を知るべき、一種の強迫的な人格崇拝」を組織し、実践している と述べている[174]。 |
| Dispute with Richard Wolin and
the NYRB Richard Wolin has argued since 1991 that Derrida's work, as well as that of Derrida's major inspirations (e.g., Bataille, Blanchot, Levinas, Heidegger, Nietzsche), leads to a corrosive nihilism. For example, Wolin argues that the "deconstructive gesture of overturning and reinscription ends up by threatening to efface many of the essential differences between Nazism and non-Nazism".[175] In 1991, when Wolin published a Derrida interview on Heidegger in the first edition of The Heidegger Controversy, Derrida argued that the interview was an intentionally malicious mistranslation, which was "demonstrably execrable" and "weak, simplistic, and compulsively aggressive". As French law requires the consent of an author to translations and this consent was not given, Derrida insisted that the interview not appear in any subsequent editions or reprints. Columbia University Press subsequently refused to offer reprints or new editions. Later editions of The Heidegger Controversy by MIT Press also omitted the Derrida interview. The matter achieved public exposure owing to a friendly review of Wolin's book by the Heideggerian scholar Thomas Sheehan that appeared in The New York Review of Books, in which Sheehan characterised Derrida's protests as an imposition of censorship. It was followed by an exchange of letters.[176] Derrida in turn responded to Sheehan and Wolin, in "The Work of Intellectuals and the Press (The Bad Example: How the New York Review of Books and Company do Business)", which was published in the book Points....[177] Twenty-four academics, belonging to different schools and groups – often in disagreement with each other and with deconstruction – signed a letter addressed to The New York Review of Books, in which they expressed their indignation for the magazine's behaviour as well as that of Sheenan and Wolin.[178] |
リチャード・ウォリンとNYRBとの論争 リチャード・ウォリンは1991年以来、デリダの仕事、およびデリダの主要な触発者(バタイユ、ブランショ、レヴィナス、ハイデガー、ニーチェなど)の仕 事は、腐敗的なニヒリズムにつながると主張してきた。例えば、ウォリンは「転覆と再記述という脱構築的な身振りは、ナチズムと非ナチズムとの間の本質的な 差異の多くを消し去る脅威によって終わる」と論じている[175]。 1991年、ウォリンがハイデガーに関するデリダのインタビューを『The Heidegger Controversy』(ハイデガー論争)の初版に掲載した際、デリダはこのインタビューが意図的に悪意を持って行われた誤訳であり、「明白に実行不可 能」で「弱く、単純で、強迫的に攻撃的」であると主張していた。フランスの法律では、翻訳には著者の同意が必要であり、この同意が得られなかったため、デ リダはこのインタビューを以後の版や再版に掲載しないよう主張した。コロンビア大学出版局はその後、再版や新版の提供を拒否した。MIT出版社による『ハ イデガー論争』(The Heidegger Controversy)の後の版でも、デリダのインタビューは省かれている。この問題は、ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックスに掲載されたハイデ ガー研究者トーマス・シーハンによるウォリンの本の友好的な批評によって公になった。その後、手紙のやりとりが続いた[176]。デリダは今度はシーハン とウォリンに反論し、「知識人の仕事と報道(悪い例:ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス社によるビジネスのやり方)」として、 『Points......』に掲載された[177]。 さまざまな学派やグループに属する24人の学者が、しばしば互いに、また脱構築とも意見を異にしているが、『ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス』誌 に宛てた書簡に署名し、その中で、同誌の行動とシーナンとウォーリンの行動に対する憤りを表明している[178]。 |
| Critical obituaries Critical obituaries of Derrida were published in The New York Times,[26] The Economist,[179] and The Independent.[180] The magazine The Nation responded to the New York Times obituary saying that "even though American papers had scorned and trivialized Derrida before, the tone seemed particularly caustic".[64][181] A second obituary by deconstruction scholar and Derrida's friend Mark C. Taylor was published by the Times a few days after the first one.[182] |
批判的な追悼記事 デリダに対する批判的な追悼記事は、ニューヨーク・タイムズ紙[26]、エコノミスト誌[179]、インディペンデント誌に掲載された[180]。 雑誌『ナショナリズム』は、ニューヨーク・タイムズ紙の追悼記事に対して、「アメリカの新聞はこれまでもデリダを軽蔑し、矮小化してきたにもかかわらず、 その論調はとりわけ苛烈に思われた」と反論している[64][181]。 |
| Major works Main article: Jacques Derrida bibliography Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences (1966), it was published in 1967 as Chapter 10 of Writing and Difference. Of Grammatology (1967) Translated by Gayatri C. Spivak in 1976 Speech and Phenomena : And Other Essays on Husserl's of Sign (1967) Or, Voice and Phenomena: Introduction to the Problem of the Sign in Husserl's Phenomenology (1967) Writing and Difference (1967) Trans. in 1978 Margins of Philosophy (1972) Signature Event Context (1972) Positions (1972) |
主な作品 主な記事 ジャック・デリダ文献目録 人間科学の言説における構造、記号、戯れ』(1966年)。1967年に『書くことと差異』の第10章として出版された。 文法学について』(1967年)1976年にガヤトリ・C・スピヴァクによって翻訳された。 音声と現象:フッサールの記号論に関するその他の論考』(1967年 あるいは『音声と現象:フッサールの現象学における記号の問題への序論』(1967年) 書くことと差異 (1967) 1978年翻訳 哲学の余白(1972年) シグネチャー・イヴェント・コンテクスト(1972年) 立場(1972年) |
| Gadamer–Derrida debate Difference (poststructuralism) |
ガダマーとデリダの論争 差延(ポスト構造主義) |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida |
以 下の年譜はウィキペディア「ジャック・デリダ」などによる。
1870 デリダの家族の祖先はセファルディム であり、この年にフランス国市民権を取得したという。
1930 エルビアールという町で、ピエ・ノワール と呼ばれるユダヤ系フランス人家庭に生まれた。父はジェオルジェット・エメ・デリダ、母はスルタナ・エステル・サファ。五人兄弟の三男で両親はハリウッド の映画俳優にちなんでジャッキーと名付ける。のちパリに出て、「正し い読み」としての「ジャック」に本人が変更した
1951 エコール・ノルマル・シュペリウール(高 等師範学校)に入学
1953
-1954 Le Problème
de la genèse dans la philosophie de Husserl
1954 Agrégation →1990年に 『フッサール現象学における発生の問題』
1956 アグレガシオンに合格
1957 精神分析を研究していたマルグリット・ オークチュリエとボストンで結婚
-1959 アルジェリア独立戦争中、軍事学校で兵 士たちにフランス語や英語を教える。
1960 ソルボンヌ大学で哲学講師(-1964)
1962 フッサールの『幾何学の起源』に長大な序 文をつけ翻訳出版;Introduction (et traduction) à L'origine de la géométrie
1963 長男ピエール誕生
1964 高等師範学校の哲学史講師、後教授(- 1984)
1966 ジョンズ・ホプキンス大学。ポール・ド・ マンやジャック・ラカンと知り合う
1967 次男ジャン誕生
1967 La Voix et le phenomene: introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl 『声と現象―フッサール現象学における記号の問題への序論 』、De la grammatologie、L'ecriture et la différence
1972 Marges, de la philosophie、Positions、La Dissémination、Éperons. Les styles de Nietzsche
1973
L'archéologie du
frivole
1974 4月、この問題に対処するための「哲学教 育研究グループ」(Groupe de Recherches sur l’Enseignement PHilosophique・GREPH)を結成。Glas
1978 12月、仏語および英語圏アフリカ哲学者 連合国際コロキウムで「哲学教育の危機」を講演。La vérité en peinture.
1979 6月、ソルボンヌで公開討論会「哲学の三 部会」
1980
La Carte postale,
de Socrate Freud et au delà
1981 ミッテラン政権
1983 「国際哲学コレージュ」初代議長に就任。D'un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie
1984 パリの社会科学高等研究院(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales:EHESS)で研究ディレクター。Otobiographies. L'enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre.
1986 カリフォルニア大学アーバイン校 (UCI)人文学教授。Schibboleth : pour Paul Celan. Parages.
1987 Ulysse gramophone、Feu la cendre 、Psyché, Inventions de l'autre
1988
Mémoires, pour
Paul de Man、Signéponge
1990 『哲学への権利について/法から哲学へ』
1990 Le Problème de la genèse dans la philosophie de Husserl (1953-1954)。Limited Inc.' De l'esprit Heidegger et la question, Mémoires d'aveugle. L'autoportrait et autres ruines, Du droit à la philosophie
1991
Donner le
temps、Circonfession" in Jacques Derrida 、L'autre cap
1992 Donner la mort、Points de suspension
1993
Passions、Khôra、Sauf
le nom、Spectres de Marx(→憑在論)
1994 Force de loi 、Politiques de l'amitié 、
1995
Moscou
aller-retour、Mal d'archive
1996 Apories、 Résistances, de la psychanalyse 、Le monolinguisme de l'autre、Échographies – de la télévision
1997 Adieu à Emmanuel Lévina、Cosmopolites de tous les pays, encore un effort、Le droit à la philosophie du point de vue cosmopolitique、Marx en jeu、De l'hospitalité
1998
Demeure, Maurice
Blanchot、Voiles、Le
Toucher, Jean-Luc Nancy
1999 Feu la cendre、Sur parole
2000 États d'âme de la psychanalyse
2001
Tourner les mots.
Au bord d'un film、Foi et Savoir、L'université sans condition、Papier
Machine 、Le siècle et le pardon
2002 映画『デリダ』Le concept du 11 septembre、Au-delà des apparences、Artaud le Moma、Fichus、H.C. pour la vie, c'est-à-dire...、Voyous: Deux essais sur la raison 、Marx & Sons、
2003 すい臓がんに罹患がわかる。2月20日にM・ブランショ、Maurice Blanchot (1907-2003) が死去、葬儀で弔辞を読む。
2003 Chaque fois unique, la fin du monde, présenté par Pascale-Anne Brault et Michael Naas、De quoi demain...、Voyous、Béliers、Genèses, généalogies, genres et le génie、
2004 10月9日パリで膵臓がんで死去。
2005 Apprendre à vivre enfin. Entretiens avec Jean Birnbaum, Galilée / Le Monde
2006 L'animal que donc je suis
2008,2010 Séminairevol. 1、vol. 2
2009 Demeure, Athènes
2010 Politique et amitié
2012 Les yeux de la langue. L'abîme et le volcan、Histoire du mensonge. Prolégomènes、Pardonner、Séminaire La bête et le souverain
2013
A dessein, le
dessin、Heidegger : la question de l'Être et l'Histoire
★
★
デリダ哲学集(ジェフ・コリンズによる)
| 1 |
デリダとは誰か? |
|
| 2 |
脱構築とはなにか |
|
| 3 |
さまざまな境界線 |
|
| 4 |
哲学の批判 |
|
| 5 |
デリダという人物 |
|
| 6 |
エクリチュールを読む |
|
| 7 |
ウイルス・マトリクス |
|
| 8 |
決定不可能性 |
|
| 9 |
生と死の中間 |
|
| 10 |
さまざまな対立 |
|
| 11 |
非決定性というホラー |
|
| 12 |
プラトンによる哲学の創始 |
|
| 13 |
プラトンのパルマケイアー |
|
| 14 |
薬剤師のための治療薬 |
|
| 15 |
代補 | |
| 16 |
ジョーカー | |
| 17 |
呪術師と身代わりの山羊 | |
| 18 |
音声言語と文字言語 | |
| 19 |
音声中心主義 | |
| 20 |
文字言語は無益で危険なものなのか? |
|
| 21 |
形而上学とロゴス中心主義 | |
| 22 |
基礎の捉え方 |
|
| 23 |
デリダと形而上学 |
|
| 24 |
転覆 |
|
| 25 |
ずらすこと |
|
| 26 |
現前の形而上学 |
|
| 27 |
現前と音声言語 |
|
| 28 |
文字言語の抑圧 |
|
| 29 |
1960年代の争点 |
|
| 30 |
鍵となる現象学者の顔ぶれ |
|
| 32 |
鍵となる構造主義者の顔ぶれ |
|
| 32 |
純粋現象学に固有の諸理念 |
|
| 33 |
ソシュールの言語学 |
|
| 34 |
痕跡 |
|
| 35 |
構造主義と現象学——デリダの作戦 |
|
| 36 |
戦略01:エクリチュール |
|
| 37 |
戦略02:差延 |
|
| 38 |
差延(Différance)
の4つの場 |
|
| 39 |
コミュニケーションにおける混乱要素 |
|
| 40 |
コンテクストの保証 |
|
| 41 |
出来事 |
|
| 42 |
言語活動の黄化 |
|
| 43 |
文字言語の教え——反復可能性 |
|
| 44 |
引用と接木 |
|
| 45 |
失敗可能則 |
|
| 46 |
それでもコミュニケーションは起こる? |
|
| 47 |
署名と花押 |
|
| 48 |
脱構築だって? |
|
| 49 |
脱構築とは……である? |
|
| 50 |
それは人が考えているものではない? |
|
| 51 |
〜イズム? |
|
| 52 |
エクリチュールと文学 |
|
| 53 |
文学テクスト、哲学テクスト |
|
| 54 |
汚染 |
|
| 55 |
極限のエクリチュール |
|
| 56 |
単語の分解 |
|
| 57 |
マラルメを読む |
|
| 58 |
ユリシーズ——グラモフォン |
|
| 59 |
その他のさまざまなイエス |
|
| 60 |
ジョイスの名の下に |
|
| 61 |
批評のなすべきこと |
|
| 62 |
テキストを開=折(open up)する |
|
| 63 |
「弔鐘」 |
|
| 64 |
文学的アートとしての哲学 |
|
| 65 |
建築 |
|
| 66 |
脱構築的建築 |
|
| 67 |
ラ・ヴィレット公園 |
|
| 68 |
公園で脱構築 |
|
| 69 |
機能をもつフォリー |
|
| 70 |
哲学と建築の共同作業 |
|
| 71 |
「コーラル・ワーク」 |
|
| 72 |
制限と機能 |
|
| 73 |
再=記入 |
|
| 74 |
ポストモダニズム |
|
| 75 |
視覚芸術 |
|
| 76 |
ジャスパー・ジョーンズ |
|
| 77 |
「絵画における真実」 |
|
| 78 |
カントの美学論 |
|
| 79 |
内部/外部 |
|
| 80 |
パレルゴン |
|
| 81 |
盲者の記憶 |
|
| 82 |
ブタデス、または素描の起源 |
|
| 83 |
政治と学校 |
|
| 84 |
政治をめぐるエクリチュール |
|
| 85 |
連合と忠誠 |
|
| 86 |
ハイデガー論争 |
|
| 87 |
ポール・ド・マン論争 |
|
| 88 |
脱構築とフェミニズム |
|
| 89 |
コレオグラフィー |
|
| 90 |
マルクスと様々なマルクス主義 |
|
| 91 |
マルクスの亡霊たち |
|
| 92 |
脱構築の結論? |
"With Derrida, you can hardly misread him, because he's so obscure. Every time you say, "He says so and so," he always says, "You misunderstood me." But if you try to figure out the correct interpretation, then that's not so easy. I once said this to Michel Foucault, who was more hostile to Derrida even than I am, and Foucault said that Derrida practiced the method of obscurantisme terroriste (terrorism of obscurantism). "- John Searle, Reality Principles: An Interview with John R. Searle. Feb. 2000.
デ リダの業績とはなんだろうか? 思いつくだけで も、1)ヒューマニズム批判、2)解釈学を解体するグラマトロジーとエクリチュールの理論、3)(文章単体の)意味の決 定不能論、4)読解方法としての「散種」、5)政治的立場、など多岐にわたる。特にエクリチュールの理論は、パロールとエクリチュールの二元論から出発 し、「ロゴセントリズム(ロゴス中心主義)」「現前の形而上学」「痕跡」「原=エクリチュール」「差延作用」などからなる。
★
デリダリアン・マトリクス(ジェフ・コリンズによる)
| デリダとは誰か? |
脱構築とはなにか |
さまざまな境界線 |
哲学の批判 |
デリダという人物 |
エクリチュールを読む |
ウイルス・マトリクス |
決定不可能性 |
生と死の中間 |
さまざまな対立 |
| 非決定性というホラー |
プラトンによる哲学の創始 |
プラトンのパルマケイアー |
薬剤師のための治療薬 |
代補 |
ジョーカー |
呪術師と身代わりの山羊 |
音声言語と文字言語 |
音声中心主義 |
文字言語は無益で危険なものなのか? |
| 形而上学とロゴス中心主義 | 基礎の捉え方 |
デリダと形而上学 |
転覆 |
ずらすこと(差延?) |
現前の形而上学 |
現前と音声言語 |
文字言語の抑圧 |
1960年代の争点 |
鍵となる現象学者の顔ぶれ |
| 鍵となる構造主義者の顔ぶれ |
純粋現象学に固有の諸理念 |
ソシュールの言語学 |
痕跡 |
構造主義と現象学——デリダの作戦 |
戦略01:エクリチュール |
戦略02:差延 |
戦略02:差延 |
コミュニケーションにおける混乱要素 |
コンテクストの保証 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 出来事 |
言語活動の黄化 |
文字言語の教え——反復可能性 |
引用と接木 |
失敗可能則 | それでもコミュニケーションは起こる? |
署名と花押 |
脱構築だって? |
脱構築とは……である? |
それは人が考えているものではない? |
| 〜イズム? |
エクリチュールと文学 | 文学テクスト、哲学テクスト | 汚染 |
極限のエクリチュール |
単語の分解 |
マラルメを読む |
ユリシーズ——グラモフォン |
その他のさまざまなイエス |
ジョイスの名の下に |
| 批評のなすべきこと |
テキストを開=折(open up)する |
「弔鐘」 |
文学的アートとしての哲学 |
建築 |
脱構築的建築 |
ラ・ヴィレット公園 |
公園で脱構築 |
機能をもつフォリー |
哲学と建築の共同作業 |
| 「コーラル・ワーク」 |
制限と機能 |
再=記入 |
ポストモダニズム |
視覚芸術 |
ジャスパー・ジョーンズ |
「絵画における真実」 |
カントの美学論 |
内部/外部 |
パレルゴン |
| 盲者の記憶 |
ブタデス、または素描の起源 |
政治と学校 |
政治をめぐるエクリチュール |
連合と忠誠 | ハイデガー論争 |
ポール・ド・マン論争 |
脱構築とフェミニズム |
コレオグラフィー |
マルクスと様々なマルクス主義 |
| マルクスの亡霊たち |
脱構築の結論? |
リ ンク
文 献
そ の他の情報

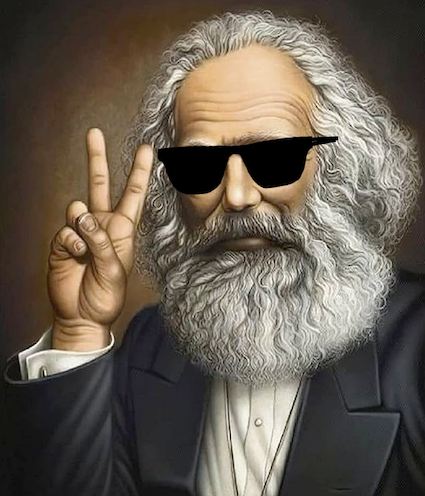
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆