
池田光穂(oxlajuuj tijaax)
「文明人は語り、野蛮人は沈黙する。語る者はつねに 文明人である。より正確に言えば、言語が文明の表現ある限りにいて、暴力は沈黙的である。言語と文明が世界を構成するとすれば、暴力が文明からのみなら ず、人間自身からも(なぜなら人間と言語は同じものだから)追放されるのは必至であろう」澁澤龍彦(1989:89)
「彼女の論文「サバルタンは語ることができるか?」(1988年)は、女性につ いて考える際に歴史、地理、階級を考慮するフェミニストの仲間入りをするきっ かけとなった。「サバルタンは語ることができるか?」の中でスピヴァクは、サティの慣習についての説明の欠如について論じ、サバルタンは語ることもできる のかどうかについて考察している。[18] スピヴァクは、その過程について、表象の問題を否定するようなヨーロッパ中心主義的な主体に焦点を当てて書いている。ヨー ロッパの主体を呼び起こすこと で、これらの知識人はサバルタンを「ヨーロッパの他者」として匿名で無口な存在として構成している。彼女のすべての著作において、スピヴァクの主な努力 は、調査対象者の主観に近づく方法を見つけようとするものであった。彼女は、サバルタン(アントニオ・グラムシが、市民権へのアクセスを持たない、一般化 できない社会の周縁集団を表現する際に用いた言葉)の立場を考慮し、脱構築哲学を女性化し、グローバル化した批評家として賞賛されている」(→「スピバック」)。
「1980年代初頭には、ポストコロニアリズムの共同創始者としても称賛されたが、彼女はこれを全面的に受け入れることを拒否した。1999 年に出版された 著書『ポストコロニアル理性批判』では、ヨーロッパの形而上学の主要な作品(カント、ヘーゲルなど)が、サバルタンを議論から排除する傾向にあるだけでな く、非ヨーロッパ人が完全に人間としての主体となることを積極的に妨げていることを探求している。[19] この作品でスピヴァクは、「植民地主義的構造の再生産と封鎖」のための「容認された無知(sanctioned ignorance)」という概念を打ち出した。この概念は、「特定の文脈を無関係とし て退ける」ことによる意図的な沈黙を意味し、制度化されイデオロギー的な世界の見せ方を示すものである」(→「スピバック」)。
★G.C.スピヴァク1998『サバルタンは語ることができるか』上村忠男訳、東京 : みすず書房の内容紹介——14のテーゼ(竹中 2002:314-316)
|
1)研究者の主権的な主体は、その研究対象と対峙したときに、危機に晒される 2)まず、西洋世界で「主体を問題化する」時に、いったい、(研究者は)どのような努力(=つまり自己反省)を試みているのだろうか? 3)つぎに、第三世界の主体が、「西洋の言説」のなかでどのように表象されているのかについて考えよう(→これはサイードの「オリエンタリズム」の問題系でもある) 4)第三世界の主体は、その主体が脱中心化されている、と考えるのがノーマルな視点である。そうでないという立場は(近代西洋の)「普遍主義」であり、その立場を採用すれば、第三世界の主体である「サバルタンは(西洋の主体とともに)語れる」ということになる。 5)主体が脱中心化するという批判的な立場を表明している思想家として、マルクスとデリダを取り上げてみよう。 6)マルクスとデリダによれば、主体が脱中心化する(=マージナライズされる)とは、国際経 済的な利害や階級的諸関係において、主体がみずからを認識し、自らの欲望をふくめて自覚的に表明できない状態におかれていることである。マルクスなら疎外 の概念が、デリダならヨーロッパの主体が理想とする〈透明な主体〉など、そもそも存在しない/できないことを論じるだろう(=主体概念の虚構性)。 7)サバルタンの女性は、サバルタンであること、そして女性であることで、二重 の疎外状況におかれている。そのなかで、(a)サバルタンの女性について[あなたという発話主体が]語ることができるのか?そして、(b)[あなたという 発話主体が]サバルタンの女性に代わって(つまり表象して) 語ることができるのか?について、言明することが求められる。 8)そのための分析材料としての、サティー(寡婦の殉死)の慣習と、1829年の大英帝国におけるサティーの禁止/廃止について考える 9)サティーを禁止=抑圧する言説の構造を考えてみよう。(a)まずは帝国主義的言説:「白 い白人[=大英帝国]が茶色い肌の女性を茶色い肌の男性から救い出す」(人種的/ジェンダー的救済の物語)。次に(b)現地の土着的説明「(ヒンドゥー主 義では)女性たちは死ぬことを望んでいる」という文化主義的説明[=イデオロギー]から救い出す(民族的文化的な陋習からの救済の物語)。 10)(a)は、植民者による自身の社会の法的な整備、パターナリズム、サティーはローカルで私的なものではなくて、国家が管理対象にしなければならない「犯罪」であるという法理の導入——ポストコロニアルな状況にも引き継がれる。 11)(b)は、土着主義的な正当化があるのか、スピバックは『リグ・ヴェーダ』と『ダル マ・シャーストラ』を精査する。哲学上の自己破壊という主張はあるものの、それらは自殺については禁止していることを確認する。つまり、サティーは、女性 の主体的な自殺が要請されていないなかでの、例外として設定されているのだ。 12)コロニアルな状況のなかでは、サティーを「実践する主体」はダブルバイン ド(池田の用語)な状況におかれている。(a)では自由な意思決定する主体として決意をしても思いとどまることが期待される。(b)の土着主義的なジェン ダー圧力のもとでは、自己犠牲することが見事な女性の文化的モデルとして体現する。つまり(自死という)儀礼の実践者として報酬を受け、帝国主義は法的な 犯罪者としてそれを取り締まる。 13)この相互に矛盾する権力の交差するところに、社会の秩序を維持するコロニ アリズムの実態である。このダブルバインドは、(a)では女性は救い出される客体として構築され自己決定に身を委ねる主体性というものがない。(b)で は、自殺(殉死)の時だけ主体が認められる——それは自己決定とは無関係に死ぬことを強制される死すべき主体——つまり裁判抜きの処刑を待つ死刑囚である ことの押し付けである。 14)これが植民地状況ならびにポスト植民地状況のなかでも、サティーを通した「主体なき」 女性の構築である。このような言説あるいはイデオロギーが支配する社会空間のなかで、女たちの声=意識(voice-cousciousness)を証言 したものに出会うことは、決してない。これがサバルタン=寡婦/女性が「語れない」ということの根拠である。 |
このページは「スピバックの『サバルタンは語れない』」の命題をめぐっての、断片的なノート 集です。全体を把握するために、小見出しのリストを以下に示します。リンクなどはしません。
- 1. 遡上的読解(running-up reading)に よる『サバルタンは語れるか』
- 2. 論文中の「わたした ちのなかの他者の声である内なる声にうわ言をいわせること」は重要(そ れまでにも最低1回はこの表現がある)(スピバック 1998:116)
- 3. アイデンティティからエー ジェンシーへ (スピバッ クの場合)
- 4. 忘却の問題
- 5. スピバックからの出発
- 6. 透明な主体
- 7. 欲望と主体
- 8. 表象の2つの意味
- 9. スピバックはサイードのフーコー批判の尻馬に乗る
- 10. フェミニズムとポストコロニアリズム.
- 11. サバルタンは語れない
- 12. ポストモダンにおける他者問題
- 13. サバルタンは聞き取られない
- 14. アイデンティティからエージェンシーへ(繰り返しか?)
- 15. スピバックのエージェンシーのマルクス主義的アイディア?
- 16. サバルタンはどこから語るのか
- 17. スピバックさんはどんな人か?
- →「ポストコロニアル理性批判=消え去りゆく現在の歴史のために」
++++++++++++++++++++++++
1.0 ■遡上的読 解に よる『サバルタンは語れるか』
「サバルタンは語ることができない。グローバル・ランドリー・リスト〔世界各地の 国際空港のホテルなどに置いてある洗濯可能品目を長々と列記した表〕に恭しく「女性」という項目を記載したところで、こんなものにはなんの値打ちもない。 表象 =代表(representation) の作用はいまだ衰えて はいない。女性知識人には知識人としてひとつの限定された任務が課せ られているのであって、それを彼女は自分のものではないと麗々しく言い募って否認するようなことはすべきではないのである」(スピバック 1998:116)。
冒頭に、ドゥールズとフーコーの対談のエピソードが ある。
「今日西洋から生じてきているもっともラディカルな 批評のいくつかは、西洋という主体あるいは 主体としての西洋を保持しようという、あるひとつの利害にもとづいた欲望の所産である。複数形 で表示された「主体効果(subkect-effects)」の理論はあたかも主体の主権性を掘り崩そうとするもの であるかのような幻想をあたえるが、実際には大概の場合、この知の主体を隠蔽するた めの覆いを 提供している。主体としてのヨーロッパの歴史は西洋の法、経済、イデオロギーによって物語化さ れたものであるにもかかわらず、この隠蔽された主体はそれが「地政学的規定をもたない」と言い つくろう。主権的主体についての広く喧伝されている批判は、このようなしかたでもって現実には ひとつの主体を立ち上げているのだ。わたしは、その批判の二人の偉大な実践家によって書かれた ひとつのテクストを考察することをとおして、この結論を論証しようとおもう。「知識人と権力 ——ミシェル・フーコーとジル・ドゥルーズとの対談」〔一九七二年三月四日。『アルク』誌第四九号に 掲載〕がそれである」(スピヴァク 1998:3 上村忠男訳)。
本論文の終焉の部分に、フーコー&ドゥールズの諸戦 術よりも「デリダの形態学」のほうがましだと、デリダの脱構築、自民族中心主義批判などの利点を 並べる。すなわち、この論文全体が、デリダへの教護論になっている。
「かれ(=デリダ)は起源におけるカタクレーシス 〔Catachresis; 濫喩〕を読みとっている。かれはユートピア主義 的な構造的衝動を「わたしたちのなかの他者の声である内なる声にうわ言をいわせるこ と」という ように書き直すことを要求している。ここでわたしは『性の歴史』と『千のプラトー』の著者たち にはもはや見いだせないようにおもわれる長期にわたっての有用性をジャック・デリダのうちに認 めないわけにはいかない」(スピバック 1998:116)。
※カタクレーシス 〔Catachresis; 濫喩〕:カタクレシス(ギリシャ語のκατάχρησις「乱用」から)とは、本来は意味上の誤用や誤りを意味する、 例えば、「militate 」を 「mitigate 」に、「chronic 」を 「severe 」に、「travesty 」を 「tragedy 」に、「anachronism 」を 「anomaly 」に、「alibi 」を 「excuse 」に、といった具合である。ジャック・デリダは、カタクレシスとは、あらゆる意味体系の一部である元来の不完全性を指す。彼はメタファーとカタクレシスは 哲学的言説の根拠となる用語であると提唱している。ここでのガヤトリ・スピヴァクは、「女性」や「プロレタリア」の「真の」例が存在しないにもかかわら ず、ある集団、例えば女性やプロレタリアートを代表すると主張する「マスター・ワード」にこの言葉を適用している。同様に、人々に押し付けられ、不適切と みなされる言葉は、このようにカタクレシス、つまりその意味と恣意的なつながりを持つ言葉を示すと、みなされるのである(→ポストコロニアル )。
J. Derrida, Margins of Philosophy, trans., Alan Bass, Brighton: Harvester Press 1982, 255. 3 Ibid., 256.
彼女は別のところで、重要なことは「誰が語るべきか」という問いよりも「誰が聞くか」というほうが重要であるという(スピバック 1999:108)
2.0 ■論文中の「わ たした ちのなかの他者の声である内なる声にうわ言をいわせること」は重要(そ れまでにも最低1回はこの表現がある)(スピバック 1998:116)
論文は、4部構成で、4部(pp.74- )の後半からは、サティ(=インドの亡夫への妻の殉死)——それ自体問題含みの表現であることが後で明かされるが——をめぐる議論である。
第1部は、第三世界の労働者の表象をめぐる権力問題 についての議論。
第2部(pp.30- )は、インドのサバルタンの表象をめぐる議論である。後半は、フーコー批判、ドゥールズ批判についての言及がある。
第3部(Pp.63- )は、デリダによる他者論である。論文末で再登場する「わたしたちのなかの他者の声 である内なる声にうわ言をいわせること」が、70ページに初出する。デリダによると「他者」たちに自分で語らせるようにすることは、ヨー ロッパ[知識]人による自民族中心主義であることが、仄めかされる。
「ポストコロニアルの批評家や知識人は、そのテクストに書きこまれた(text-
inscribed)空白を前提として
はじめて、自分たち自身の生産活動を転位させることを試みることができるのである。これとは対
照的に、思考ないし思考主体を透明または自に見えない存在にしてしまうことは、同化による他者の
のお構いなしの認知がなされていることを隠蔽してしまうもののようにおもわれる。デリダが「他
者(たち)に自分で語らせる」ことをもとめず、むしろ、「まったき他者」(自己をうち固めるため
の他者とは対立する関係にあるものとしてのtout-autre)への「呼びかけ」をおこなって、「わたし
たちのなかの他者の声である内なる声にうわ言をいわせる」ことをもとめているのは、こういった
ことを用心してのことにほかならない。/
デリダは、17世紀末期から18世紀初期にかけてのヨーロッパのエクリチュールの学における
自民族中心主義をヨーロッパ的意識の一般的な危機の徴候であると呼んでいる」(スピバック 1998:70)。
承前であるが、4部(pp.72- )は、いよいよ「女性」の声というものについての考察から始まる(下記)。そして、その後半からは、サティ(=インドの亡夫への妻の殉死)——それ自体問 題 含みの表現であることが後で明かされるが——をめぐる議論となる。
「サバルタンは語ることができるのか。サバルタンの
連続的な構築がおこなわれることにたいして
警戒を怠らないためにエリートはなにをしなければならないのか。このコンテクストにおける問題
点がもっともよくあらわれているのは「女性」についての問いではないかとおもわれる。いかにも、
もしあなたが貧乏人で、黒人で、そして女性であれば、あなたはサバルタンであるとの規定を三様
のしかたで手に入れることになる。しかしながら、この定式が第一世界のコンテクストからポスト
コロニアルのコンテクスト(これは第三世界のコンテクストとは同一ではない)に移されたならば、
その途端に「黒人」または「有色」という要素は説得力を失ってしまう。資本主義的帝国主義の第
一段階において横民地的主体構成がなされたとき、そこでは必然的に階層化もまた同時に起きてい
たのであって、「有色」という要素はすでにその段階で解放のためのシニフイアンとしては役にた
たないものになってしまっていたのである」(スピバック 1998:72)。
3.0 ■アイデンティティからエージェン
シーへ
(スピバッ
クの場合)
・スピバック「サバルタンは語れない」
"identity claims are political manipulations of people who seem to share one characteristic and therefor it is a sort of roll-call concept. / Now it seems to me that agency relates to accountable reason. The idea of agency comes from the principle of accountable reason, that one acts with responsibility, that one has to assume the possibility of intention, one has to assume even the freedom of subjectivity in order to de responsible. That's where agency located. "(Spivak 1996:p.294)
【アイデンティティが要求するものは、一つの性格をシェアすると思われる人々による政治的操作であり、それはすなわち役割を召喚する概念*(roll- call concept)のひとつである。他方エージェンシーは説明責任のある理性に関係しているように私には思える。エージェンシーの理念は、説明責任ある理性 という原理から出たものであり、各人は説明責任を持って行動するということ、意図の可能性を引き受けなければならないこと、応答責任を持つためには主体性 の自由さえ想定されなければならないということである。それがエイジェンシーが位置してきた場所なのである】(Spivak 1996, p.294.)。
※スピバックは、それがロマン主義的行為者であるという批判には、さほど耳を貸す必要を感じていないようだ。
※アイデンティティが役割を召喚する概念であるという指摘は、高木(1999)におけるLPPのAA(断酒会)のメンバーが、固有名性を失って(マスク
されて?)不断にAAのメンバーとしてアイデンティティを注入されているという批判を想起する。そしてウェンガーのいう<非参加のアイデンティティ>とそ
れを共有するメンバーによる隙間共同体は、かりに抵抗の実践と呼ぼうと呼ぶまいと、(古典的な)権力関係の布置においては、ウェンガーのいうとおり疎外の
一形態に他ならない。
"When one posits an agency from the miraculating ground of identity, the question that should come up is, "What kind of agency?" Agency is a blank word. So the shift from "identity" to "agency" in itself does not assure that the agency is good or bad, it simply entails seeing that the idea that calling everything a social construction is anti-essentialist entails a notion of the social as an essense".(Spivak 1996, p.294.)
【アイデンティティの驚くべき(miraculating)地点からひとつのエージェンシーを措定した時に、すぐに浮かぶことは『エージェンシーとはい
かなる類のものか?』という問いであろう。エージェンシーは、白紙の(空の)用語である。つまり、アイデンティティからエージェンシーへの移行それ自体
は、エージェンシーの善し悪しを保証するものではなく、全てを社会構築であると呼ぶためには、社会をひとつの本質とすることが必然として伴う、というアイ
ディアを単純にも必要としていることなのである】(Spivak 1996, p.294.)。
※スピバックは、エージェンシーを動員する理由は、アイデンティティの社会構築という立場を批判する(社会という本質=係留点を不可欠にする)以上の、
強い動機がないことを示している。
4.0 ■忘却の問題
・想起と忘却、あるいは占有化について
<組織化された忘却>(Milan Kundera, 『笑いと忘却の書』1992)が一方にある。それに対抗するのが<専有化する実践 appropriate practice>と考えられている。
・「権力にたいする人間の闘いとは忘却にたいする記憶の闘いにほかならない」(クンデラ、p.7)
・発話できないことがら、をめぐって
「ピエール・マシュレーは、イデオロギーを解釈するための次のような定式を提供している。「ある作品において重要なのは、それが言っていないことがらであ る。これはしばしば不用意にそう表示されているような『それが言うことを拒絶していることがら』とは同じものではない。『それが言うことを拒絶しているこ とがら』というのもこれはこれで興味深い問題であるにしてもである。それについてはひとつの方法がうち建てられてもよいだろう。それと認められているもの であれ認められていないものであれ沈黙を測定するという仕事を遂行することによってである。だが、これよりもむしろ、作品が言うことができないでいること がらのほうが重要である。なぜなら、そこでは発話の練り上げが遂行されるのは、沈黙への旅とでもいうべきもののなかにあってであるからである」。」(スピ バック1998:47-8)。
スピバックは、マシュレーとは反対に「それが言うことを拒絶していることがら」への関心を喚起する。「それは、植民地での慣習を法典化しようとする帝国
主義の法律的実践のためには、なにか集合的なイデオロギー的拒絶のたぐいを診断することを可能にしてくれるのだ。このことは、政治経済的およびマルチ学問
的な見地から地勢のイデオロギー的な書きこみ直し(reinscription)をおこなうための地平を開くであろう。これは抽象の第二次的なレヴェルに
おいての「世界の世界化(worlding of the
world)」である。したがって、拒絶という概念は、ここでは十分採用されるに足るだけの蓋然性のあるものになる。ここにかかわってくる資料収集、歴史
叙述、学問的批判といった仕事、不可避的に介入主義的(interventionist)なものであらざるをえないそのような仕事は、まさしく「沈黙を測
定する」ことを任務としたものにほかならない」(スピバック1998:47-8)(→「サバルタンは語ることができるか」)。
5.0 ■スピバックからの出発
【文献】Spivak, Gayatri Chakravory. 1988. Can Subaltern Speak ? in
"Colonial Discourses and Post-colonial Theory: A reader",
William, P and L. Chrisman eds.. pp.66-111, New York: Columbia
University Press.[ガヤトリ・C・スピバァク『サバルタンは語ることができるか』上村忠男訳、みずす書房、1998年]
6.0 ◆透明な主体
「今日西洋から生じてきているもっともラディカルな批評のいくつかは、西洋という主体あるいは主体としての西洋を保持しようという、あるひとつの利害に もとづいた欲望の所産である」(スピバック1998:3)。
その究極の形態が<透明化された主体>である。「主体としてのヨーロッパの歴史は西洋の法、経済、イデオロギーによって物語化されたものであるにもかか わらず、この隠蔽された主体はそれが「地政学的規定をもたない」と言いつくろう」(スピバック1998:3)。→マルクス主義的な隠蔽あるいは錯認を暗示 する。彼女はその俎上にフーコーとドゥルーズの対談をあげる。
告発されるのは彼らの権力意識と権力観の密接な関係だ。「権力を破壊したいという欲望はそれがどんな権力についてのどんな破壊欲望であっても単純に価値 のあるものとして認めようとすることに根拠を置いているようにみえる」(スピバック1998:6)。スピバックはベンヤミンによるボードレール批判の上 に、彼女の批判の論理をなぞる。
スピバックの批判の対象は、ドゥルーズ、ガタリ、フーコーらのポスト構造主義にあり、これは竹村のいう<社会構成論>(社会構築論)的な枠組の中の(強
いてラベルを貼ればアナーキスティクな——「もはやルプレザンタシオンといったものは存在しません。行動……以外のなにものも存在しないのです(ドゥルー
ズ)」)主体形成の論理につらなるものだろう。
(アルチュセールの託宣)
「労働力の再生産は、それの資格条件の再生産だけでなく、同時に、……労働者たちにたいしては支配するイデオロギーに労働力を従属させることの再生産と、
そして搾取の担い手たちにたいしては支配するイデオロギーに労働力を従属させることの再生産と、そして搾取と抑圧の担い手たちに対しては支配するイデオロ
ギーを正しく操作し、支配階級の支配を『言葉によってpar la
parole』も保証することができるようにする能力の再生産を要求する」アルチュセール(スピバック1998:9)。
——(スピバックのフーコー批判)「フーコーは、イデオロギーについて発達した理論がみずから物質的生産の場を「知の形成と蓄積のための効果的な諸道具」
(PK,102)のうちにと同様、制度性のうちにも見いだすことができない。これらの哲学者たち(フーコー他、ドゥルーズ、ガタリ——池田)は、どうやら
イデオロギーという概念を口にするあらゆる議論をテクスト論的というよりはむしろたんに図式的にすぎないものとして拒絶することを余儀なくされているよう
である。そのため、利害と欲望とのあいだに機械的に図式的な対立を措定することも余儀なくされるのである。こうしてかれらはイデオロギーの占めるべき場所
を実体的内容を付与された「無意識」や準主体的な資格を与えられた「文化」でもって埋め合わせようとするブルジョア社会学者たちと連携する羽目におちい
る」(スピバック1998:9-10)。
7.0
◆欲
望と主体
「欲望の名において、かれらは権力についての言説のなかにふたたび未分割の主体を導入する。フーコーはしばしば「個体[分割できないもの]」と「主体」と
を混同的に使用している」(スピバック1998:11)。
「問わなければならないのは、自民族中心主義的な<主体>があるひとつの<他者>を選択的に定義することで自己を確立してしまうのを避けるにはどうすれば
よいか、ということである。これは<主体>そのもののための企てではない。むしろ善意にみちた西洋知識人のための企てである」(スピバック1998:
65)
8.0
◆表
象の2つの意味
「もはやルプレザンタシオンといったものは存在しません。行動……以外のなにものも存在しないのです(ドゥルーズ)」に対するスピバックの批判を池田がパ
ラフレーズすると以下のようになる。
表象には、政治における代弁/代表と、芸術・哲学における表象の2つの意味がある。ドゥルーズによれば理論は「行動」だから、理論が被抑圧者たちを代弁 することはできない。また主体は意識を表象するものでもない。2つの表象は、権利主体と権利表現という主語−述語関係のもとにあるゆえに、一方が他方へ包 摂されるということはありえない。多様なものからなりたっているものを表象化することは不能である。その「非連続性」を覆い隠すために考え出された/機能 しているのがヨーロッパ的<透明な主体>なのだ。
しかし、国民経済システムにあるイデオロギー的主体への批判や意識の変革への企図が断念すべきでないとすれば[——それを問う根拠についてスピバックは
言わない]、「一方における国家と国民経済の内部にあってのrepresentationと他方における<主体>[原文ゴチ]に関する理論の内部にあって
のrepresentationとのあいだを移動しつつ存在している区別は抹消されてはならない」(スピバック1998:15)。
「ラディカルな実践は権力と欲望の概念を全体化することをつうじて個人的な主体を再導入するのではなくて、むしろ、このような
reperesentationのダブル・セッションこそ留意すべきであろうというのが、わたくしの意見である。また、階級的実践の領域を第二次的な抽象
のレヴェルに保ちつづけることによって、マルクスは実際上、行為の<作因者>[強調は池田]としての個人的な主体についての(カント的かつ)ヘーゲル的な
批判を展開しつづけていたのだというのが、わたしの意見である」(スピバック1998:25)。
9.0
◆ス
ピバックはサイードのフーコー批判の尻馬に乗る
「エドワード・T・サイードはフーコーにおける権力 概念を批判して、それはフーコーにあっては魅力的でいっさいを神秘化してしまうようなカテゴリーと化し ており、「階級の役割、経済の役割、蜂起と反乱の役割を隠蔽する」結果を招いていると指摘しているが、この批判はいまの場合にはきわめて適切である (24)。わたしはサイードの分析に付け加えてさらにひとつ、そこでは権力と欲望の密やかな主体の存在が知識人の透明性によってマークされているという点 を指摘しておきたい」(スピバック1998:27-8)。
「この奇妙なことにも否認の言葉によって[知識人 の]透明性のなかにいっしょに縫いこまれてしまっている<主体>/主体は、労働の国際的分業の搾取者の側 に属している」(スピバック1998:28)。この種の西洋的主体に関するラカン的解説で第1節がしめくくられ、第2節は次のような言葉ではじめる。
第2部の冒頭は次のような文章からはじまる
「そ のような認識の暴力(epistemic violence)についての利用可能なもっとも明確な実例は、植民地的主体(colonial subject)を他者として構成しようとする、遠く隔たったところで編成された、広範囲におよぶ、そして異種混交的な企図である。この企図はまた、当の 他者が危うくも主体−性を獲得するかにみえるときには、これとは非対称的に、その痕跡を抹消しようともする」(スピバック1998: 30)。
スピバックのフーコー批判はかなり言いがかり的なと ころもあるが、スピバックが、引用するペリー・アンダーソンが次のように質問する時、ヨーロッパ以外 の<人間>の視点は確かにフーコーすっぽり抜けているように思える。
「フーコーは1966年に例の預言者ぶった口調で 『言語という存在がわれわれの地平の上でますます明るく輝きつづけている一方で、人間は死滅しつつあ る』と宣言した。しかし、そのような地平を認知ないし所有する『われわれ』とはだれなのか」(P・アンダーソン、引用はスピバック1998:63)
******************************************
・英文批評系の基本的語り口(竹村和子・本橋哲也)
スピバックのサバルタンと、それに対するベニタ・パリーの批判(=語れないことをもって終わるのではなく、身振りなどを通して声を聞けるはずだ、という
スピバックの発話中心主義に対する批判)、ベニタ・バリーに対するレイ・チョウのスピバック擁護(=スピバックによる批判の要衝は発話のヘゲモニー構造な
のだ)。そして、ホミ・バーバの二項対立を超えるエージェントの模倣行為の評価、などなど(e.g. 本橋1999「応答するエイジェンシー」論文)。
**************竹村エージェンシー論(はじめ)
******************
【文献】竹村和子、責任あるエイジェンシー——ポストモダニズム、ポストコロニアリズム、
フェミニズム、『差異化と同一化:ポストコロニアル文学論』山形
和美編、pp.65-81、研究社出版、1997年
10.0 ●フェミニズムとポストコロニアリズム.
(1)西洋フェミニズムの功罪
チャンドラ・モハンティの"Colonial Discourses and Post-colonial Theory: A reader"中の論文「西洋の眼差しのもとで——フェミニズム研究とコロニアル言説」(1984):欧米の白人中産階級のフェミニズムが、第三世界の女 性を植民地化するという批判であり、問題は第三世界という差異のもとに、女性の闘争を同質化、組織化した(Mohanty, Chandra Talpade. 1984. p.198)。
(2)フランツ・ファノン:植民地主義における人種の他者性
西洋は、<自分たちのもつ過剰性>をネイティヴの属性として押しつけることを通して近代主体を保とうとする(Black Skin, White Masks)とファノンは主張。そのために——他者の排除と抑圧の代償として——「黒人の価値の賃貸対照票を作成」しているという。例えば、白人音楽に拮 抗するものとして、黒人音楽を擁護するようなメンタリティである(竹村は英語訳p.226-9から引用)。竹村はこれを「他者排除」のメカニズムであると 解説して、他者=女性に対する男性社会(「男根主義」者たち—イリガライの用語?)の排除メカニズムと[次のような留保をしながらも]同等のものであると している。
セクシズムとコロニアリズムは、その作用の様式が似ているだけではなく、作働の仕方がより重層的であるとバーバを引きながらする(「コロニアル体制を盤 石のものとする抑圧構造」)。バーバ曰く「人種や文化の差異にかかわる問題は、セクシュアリティやジェンダーの問題に重なりあっている」(Bhabha, p.175)。また竹村も「コロニアル言説そのもののなかに構造化されているジェンダーやセクシュアリティの概念を検討する必要がある」(竹村1997: 66)。
[論文のねらい]植民地主義と性差別主義が二重に作用する場にいる、植民地の「他者」=植民地の女性の発話の可能性、その条件について考察する。
11.0 ●サバルタンは語れない
スピバックの1988年論文「サバルタンは語れるか」。サバルタンとは、「ネグリチュード的な民族解放を訴える被植民者」ではなく「むしろ、そういった
『大きな物語』の対立図式に隠れて、反乱の契機さえ巧妙に剥奪された、根源的な意味での被抑圧者」である(竹村1997:67)。
・ポストモダン(PM)における他者問題
主体を脱中心化するPMの理論は「権力と欲望の働きだけを分析し(本当は分析していない)、誰をも、何をも代表/表象しない(non-
represented)主体というものに頼ってしまう」=これを主体を「透明化」するという(Spivak,
p.74、引用は竹村1997:67)。この透明化により、「歴史的現実として、いま、ここにいる主体」について議論することが困難になる。それだけでな
く、主体形成に関わる「複雑なイデオロギー操作を論じる議論」を遮るという積極的な弊害もあるという。
では他者はどこにいるのか? スピバックによると、それは「作品が語ることができないもの」にある。しかし、以下のことを区分しなければならない。
(α)語られない沈黙と(β)語ることを拒否すること、である。前者は、それがもつシステムへの抵抗が、外部からそれを統合するテクストに翻訳されない
ものであり、「『世界の世界化』という手続きから完全に追放されているもの」である。つまり反乱の主体にもならず「歴史も、語る声も、奪われて、なお深い
陰のなかに沈み込む植民地の女」である(Spivak,
pp.82-3引用は竹村1997:68)。後者は、集合的でありイデオロギー的であり、「帝国主義の法の実践」を支える巧妙なシステムの手先にとなる
(竹村1997:67-8)。[※これはスピバック翻訳pp.47-8を見れば一目瞭然P・マシュレーの文学作品におけるイデオロギー解釈についての解説
に由来するのである]。
ベニタ・パーリィのスピバック批判[これは省略](竹村1997:68)——蛇足だが、この引用は次節で引かれるレイ・チョウからの孫引用であることが
レイ・チョウ『ディアスポラの知識人(Writing Diaspora)』の本文(本橋訳、pp.62-3)からわかる。
12.0 ●サバルタ
ンは聞き取
られない
スピバックの狙いは第三世界の女性を一括してカテゴライズすることではない。1933年のインタビューで次のように語る。
「『サバルタンが語れない』という意味は、たとえどんなに必死になってサバルタンが語ろうとしても、聞き取ってもらえないということです。というのも、語
る行為は、語ることと、聞くことの二つから成り立つものだからです。これが、私の言おうとしたことであり、苦悩こそ、その地点の明確な特徴なのです」
(Spivak, p.292. 竹村1997:67)。
ここでは<語ることができない状況>を特定化することをやめなければならない。というのは、そのような位置を同一化(=本質化する)からである。
※語ることができない状況を特定することは、語ることを保証することで解消済みの問題になるからだ。言葉遊びのようではあるが「もしサバルタンが語るこ
とができるなら、ありがたいことに、その人はもう被抑圧者ではないのです」(Spivak , The New
Historicism...,p.1990:158)。レイ・チョウは次のようにつづける。「サバルタンは語ることができないという事実を認めることで
はじめて、私たちはネイティブの同一化のプロセスについて、これまでとは異なった考え方をするようになるだろう」(『ディアスポラの知識人』p.64)。
「イメージにより同一化する」(レイ・チョウの用語、p.63)という表現もある。
・同一化(アイデンティティ)が批判の対象になる——「耐え難いのは差異ではない。耐え難いのは、ある意味で差異がないことだ」(ジジェク
1996:13)『快楽の転位』青土社。
スピバックの戦略的本質主義の発想は、イリガライの本質論の批判からはじまる。イリガライたちは、男性をおなじ地平で女性の解放を説いたのではない。し
かし、「男性言語」(※ここでも<言語>なんですわ、ルート・メタファーは!)の外側へ女性性を打ち立てることが、男性言語の外側という本質主義を生んで
しまったと批判する。これに対するスピバックの作戦は竹村によると次のようなことである。「スピバックは、一方で、システムから決定的に放逐されたサバル
タンの存在を強力に主張しながらも、もう一方では、そのような他者を自己同一的な属性に還元せず、システムの所産とみなした」。これは竹村によると社会構
築主義のひとつである。
他方、社会構築主義をつきつめると、「動く主体」を前提とするので、それじたいもまた「表象しない(non-represented)主体」つまり透明
なものになる。一般には社会構築は本質主義から自由になっていると思われがちだが、スピバックは、社会構築主義の議論の前提になる社会を本質化していると
批判する。
「あらゆるものが社会構築されたものだとみなすことは、本質主義ではないと思われがちですが、それは社会そのものを本質と見ていることです」。「もし社会
を本質と見てしまった場合、資本主義をある種の本質として、すなわち社会一般とみなして、何の検討も加えないことになります」(Spivak 1993,
p.294. 竹村1997:70-1)。
※これをパラフレーズすると、構築主義は、非本質主義(=理論的にはあらゆるものが構築可能)ではなく、主体の構築する場=係留点として確固としたコテ
コテの本質として<社会>を想定しなければその議論が不能になる。さらに悪いことに、社会構築主義では、その本質化された社会に対する批判のメスを入れる
ことができないという(=構築主義の議論では、社会が批判の対象から免疫されているということなのだろうか、たぶん)。竹村の次の言葉に耳を傾けよう。
[**]「社会構成論の弱点は、パフォーマティヴィティによって主体が構築されるというとき、目の前の抑圧/被抑圧の二項対立はずらすことができても、そ
れはつねに抑圧/非[ママ]抑圧というパラダイムの中でしかずれないことだ。たしかに社会構成論で議論を進める者(たとえばジュディス・バトラー)はパ
フォーマティヴにシステムを反復する儀式が、一方でシステムを固定化すると同時に、他方で、そのシステムがいかに虚構であるかをあらわにすると述べてはい
る。だが長年のパフォーマティヴな反復の成果として、かりに現在のシステムが解体したとしても、そのシステムを成り立たせていた抑圧/被抑圧の対立図式が
消滅するという保証はない。差別の場所が移動しただけで、差異を差別とするメカニズムは不問に付されたままだ。というのも、社会構成論そのものが、そのよ
うなヒエラルキーが消滅するユートピア的地点——つまり理念的、牧歌的な本質——を拒否しているからだ」( 竹村1997:71-2)。
14.0 アイデンティティからエージェンシーへ
スピバックの社会構築主義批判は、社会構築の概念
の中にある主体形成概念、つまり透明で移動する主体が、身につける(置き換え可能な)ことのできるメタ
ファーとして確立されたアイデンティティ=同一化への批判へと展開する。彼女はそのような透明な主体に対して、「歴史的現実として、いま、ここにいる主
体」を中心に据えようとするのだ。その主体形成概念として考え出されたのがエージェンシーである。彼女は次のように言う。
「エイジェンシーという概念は、責任ある理性という原則[幻想?—池田]から出たものです。つまり責任を持って行動するということ——意図を持つ可能性を
引き受けなければならないということ——責任を持つためには主体性の自由さえ想定されなければならないということ——なのです。そこにエイジェンシーの位
置があるのです」(Spivak 1993, p.294. 竹村1997:71)。
(竹村はこの引用につづけて、スピバックの主張が「矛盾に満ちた、きわめて危なっかしい論理に見えるが、現在のコロニアリズムの文脈では、不可欠の批判主
体の位置である」と弁護しつつ、返す刀で社会構築論を批判する——上掲の[**]の部分)。社会構築論は、ポストコロニアリズム(PC)の文脈の中では、
コロニアリズム批判たり得ても、ネオコロニアリズムに対しては「御用理論」になり、「ボーダーレスの後期資本主義社会では、境界を生きる<主体/他者>の
イメージは、国境を越えて労働力やマネーた情報を動かす多国籍企業の理論的補完物となるからだ」(
竹村1997:72)と主張。だから、責任あるエージェンシーのという概念が必要になるという。
※しかし、これは無茶な議論だ。彼女の主張は社会構築論の限界の指摘はそれなりの意味をもつ。しかし社会構築論の無能がスピバックによって救済されると
いう論拠が何も示されていないのだ。彼女に従えば、本質論的議論はすでに限界が露呈している。社会構築論はその外見とは異なり実際その深層では社会本質論
と変わらない(=本質論である)。他方スピバックは本質論ではない。だからスピバックの議論は有効だ、というふうになってしまう。まったく論証になってい
ない。
——だから、スピバックを擁護するためには、社会構築主義の限界を「責任あるエージェンシー」の概念が、どのように有効に乗り越えているのかを、論証し
なければならない。
15.0 ■スピバックのエージェンシーのマルクス主義的アイディア?
マルクスの新社会創造のアイディアを<欲求>の観点から捉え直すAgnes Hellerは次のようにいう。
「マルクスは『反プルードン』の中で、資本主義の「悪い面」を棄て「良い面」を守らなければならないとするプルードンの考えを、皮肉をこめて撥ねつけてい
る。「組織体」の諸構造は相互に措定しあっていて、一方を棄て他方を保持するということは不可能である【だが今日日そのようなことを信じるものがいるだろ
うか?—池田】。すなわち、必然にたいして二律背反的関係にあるあの必然は、偶然にたいして二律背反的関係にない必然と同じではない。因果律にたいして二
律背反的関係にあるあの目的論は、因果律の二律背反をもたない目的論と同じではない。そして最後に、自分の客体にたいして二律背反的関係に立ちながら発展
するあの主体もまた、自分の客体を自己のうちに「取り返す」主体、主体—客体の同一性を生みだす主体と同じではない」(ヘラー『欲求理論』p.106)
16.0 ●サバルタンはどこから語るのか
竹村は、この節でチカーナ作家のグロリア・アンサルドゥア(Gloria
Anzaldu'a)を引く——これはスピバックからの孫引きと思われる。そこで評価されるのは、様々な主体を担うメスティサヘ的主体の多重・多層性であ
る(Spivak 1985:13)。バーバ(Bhaba
p.185)によりながら竹村は、そこに見られるのは超越的で透明なエージェンシーではなく、ひとつの単位をなす、有機体の、自律的なエイジェンシーであ
る。
(バーバーの長い引用)「発話の不連続な現在を強調することによって、歴史家は、サバルタンの意識を二項対立的に捉えたり、肯定的または否定的に
捉えたりすることから免れる。むしろそれによって、サバルタンというエイジェンシーの声は、再定位とか再記述として登場できることになる。……社会の象徴
秩序を保
持する同時性の概念には異議申し立てがおこなわれるのは、その約定[何じゃこれ——池田]の内部においてである。しかし約定の基盤をずらしてきたものは、
約定を超えてゆく代補の運動であった。これこそカムフラージュとしての、記号/象徴の時差の内部で働く、抵抗するエイジェンシーとして、ハイブリッドの歴
史的運動なのである。時差とは、すなわち約定のルールの間隙に存在するスペースである」(Bhaba, Location of Culure.
p.193:引用は竹村p.74)
——バーバのこの見解は、歴史家の方法や認識論的視点が、その作品の中でサバルタンを表象することについて言及しているのではないか。ズラすことで、見え
ないものを見えるようにするというのは伝統的な人類学の手法ではないはないのか?。引用文そのものが不明瞭で、解説がわかりにくい。前節のスピバックの議
論であるところの「サバルタンは語れない」という結論を受けると、「サバルタンが語る」という命題がいかにして可能になるのか不明瞭である。竹村は「サバ
ルタンは語れる」と信じている、あるいはそのように定義できると主張する根拠は次の一文である。「サバルタンとは、多くの環境によって決定された位置から
語る者である」(竹村 1997:74)
またエイジェンシーが発話する存在であることも、次の引用からも明らかだ。
「その複数の声[メスティサヘのように重層的な主体がさまざまな声を発話していると想像すべきだろう——竹村のアンサルドゥアの引用から推察すれば(池
田)]が、歴史的現実の網の目を形成する「撚り糸」それぞれに係留されているがゆえに、被植民者の「抵抗」の「責任あるエイジェンシー」として機能するこ
とになるのだ。責任あるエイジェンシーという概念は、何かひとつの立場を代弁することではない。数多くの環境が歴史的現実として交差する地点
(positionality)から語るということなのだ」(竹村 1997:74-5)。
17.0 ★スピバックさんとは、どんな人か?
| Gayatri
Chakravorty Spivak (IPA:
gaĕòttri t͡ʃɔkkròbòr(t)ti) FBA (born 24 February 1942) is an Indian
scholar, literary theorist, and feminist critic.[1] She is a University
Professor at Columbia University and a founding member of the
establishment's Institute for Comparative Literature and Society.[2] Considered one of the most influential postcolonial intellectuals, Spivak is best known for her essay "Can the Subaltern Speak?" and her translation of and introduction to Jacques Derrida's De la grammatologie.[3][4] She has also translated many works of Mahasweta Devi into English, with separate critical notes on Devi's life and writing style, notably Imaginary Maps and Breast Stories. Spivak was awarded the 2012 Kyoto Prize in Arts and Philosophy for being "a critical theorist and educator speaking for the humanities against intellectual colonialism in relation to the globalized world."[5][6][7] In 2013, she received the Padma Bhushan, the third highest civilian award given by the Republic of India.[8] Although associated with postcolonialism, Spivak confirmed her separation from the discipline in her book A Critique of Postcolonial Reason (1999), a position she maintains in a 2021 essay titled "How the Heritage of Postcolonial Studies Thinks Colonialism Today", published by Janus Unbound: Journal of Critical Studies.[9] |
ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク(IPA:
gaĕòttri
t͡ʃɔkkròbòr(t)ti)FBA(1942年2月24日生まれ)は、インドの学者、文学理論家、フェミニズム批評家である。[1]
彼女はコロンビア大学の特別教授であり、同大学の比較文学・文化研究所の創設メンバーでもある。[2] 最も影響力のあるポストコロニアルの知識人の一人と考えられているスピヴァクは、エッセイ「サバルタンは語ることができるか?」とジャック・デリダ著『グ ラマトロジーについて』の翻訳と序文で最もよく知られている。[3][4] また、マハシュヴェタ・デヴィの多くの作品を英語に翻訳しており、デヴィの人生と文体に関する個別の評論注釈を付けている。特に『イマジナリー・マップ』 や『ブレスト・ストーリーズ』などがある。 スピヴァクは、「グローバル化された世界における知的植民地主義に反対する人文科学の代弁者である批判理論家および教育者」として、2012年の京都賞 (思想・芸術部門)を受賞した。[5][6][7] 2013年には、インド共和国から与えられる民間人向け賞としては3番目に高いパドマ・ブーシャン賞を受賞した。[8] ポストコロニアリズムと関連付けられているものの、スピヴァクは著書『ポストコロニアリズムの批判的考察』(1999年)で、その学問分野から自らを切り 離していることを確認している。この立場は、彼女が2021年に『Janus Unbound: Journal of Critical Studies』誌に発表した「ポストコロニアリズム研究の遺産が今日のコロニアリズムをどう考えるか」と題するエッセイでも維持されている。[9] |
| Life Early life Spivak was born Gayatri Chakravorty in Calcutta, India, to Pares Chandra and Sivani Chakravorty.[10] After completing her secondary education at St. John's Diocesan Girls' Higher Secondary School, Spivak attended Presidency College, Kolkata under the University of Calcutta, from which she graduated in 1959.[10] Spivak has been married twice—first to Talbot Spivak, from 1964 to 1977, and then to Basudev Chatterji.[11] She has no children.[11] 1960s and 1970s In 1959, upon graduation, she secured employment as an English tutor for forty hours a week. Her MA thesis was on the representation of innocence in Wordsworth with M.H. Abrams. In 1961, Spivak joined the graduate program in English at Cornell University in the United States, traveling on money borrowed on a so-called "life mortgage". In 1962, unable to secure financial aid from the department of English, she transferred to a new program called Comparative Literature, although she had insufficient preparation in French and German. Her dissertation was under the guidance of the program's first director, Paul de Man, titled Myself Must I Remake: The Life and Poetry of W.B. Yeats.[10] In 1963–1964, she attended Girton College, Cambridge, as a research student under the supervision of Professor T.R. Henn, writing on the representation of the stages of development of the lyric subject in the poetry of Yeats. She presented a course in the summer of 1963 on "Yeats and the Theme of Death" at the Yeats Summer School in Sligo, Ireland. (She returned there in 1987 to present Yeats' position within post-coloniality.)[citation needed] In the Fall of 1965, Spivak became an assistant professor in the English department of the University of Iowa. She received tenure in 1970. She did not publish her doctoral dissertation, but decided to write a critical book on Yeats that would be accessible to her undergraduate students without compromising her intellectual positions. The result was her first book, written for young adults, Myself I Must Remake: The Life and Poetry of W.B. Yeats.[12] In 1967, on her regular attempts at self-improvement, Spivak purchased a book, by an author unknown to her, entitled De la grammatologie. She decided to translate this book, and wrote a long translator's preface. This publication was immediately a success, and the "Translator's Preface" began to be used around the world as an introduction to the philosophy of deconstruction launched by the author, Jacques Derrida, whom Spivak met in 1971.[13] In 1974, at the University of Iowa, Spivak founded the MFA in Translation in the department of Comparative Literature.[14] The following year, she became the Director of the Program in Comparative Literature and was promoted to a full professorship. In 1978, she was National Humanities Professor at the University of Chicago. She received many subsequent residential visiting professorships and fellowships. In 1978, she joined the University of Texas at Austin as professor of English and Comparative Literature. 1980s to present In 1982, she was appointed as the Longstreet Professor in English and Comparative Literature at Emory University. In 1986, at the University of Pittsburgh, she became the first Mellon Professor of English. Here, she established the Cultural Studies program. From 1991, she was a member of faculty at Columbia University as Avalon Foundation Professor in the Humanities, where, in 2007, she was made University Professor in the Humanities. Since 1986, Spivak has been engaged in teaching and training adults and children among the landless illiterates on the border of West Bengal and Bihar/Jharkhand. This sustained attempt to access the epistemologies damaged by the millennial oppression of the caste system has allowed her to understand the situation of globality as well as the limits of high theory more clearly. In 1997, her friend Lore Metzger, a survivor of the Third Reich, left her $10,000 in her will, to help with the work of rural education. With this, Spivak established the Pares Chandra and Sivani Chakravorty Memorial Foundation for Rural Education; to which she contributed the majority of her Kyoto Prize. |
生涯 幼少期 スピヴァクは、インドのカルカッタで、パレシュ・チャンドラとシヴァニ・チャクラボルティーの間に、ガヤトリ・チャクラボルティーとして生まれた。 [10] セント・ジョーンズ教区女子高等学校で中等教育を修了した後、スピヴァクはカルカッタ大学の下部組織であるプレジデンシー・カレッジ・コルカタに入学し、 1959年に卒業した。[10] スピヴァクは2度結婚しており、最初は1964年から1977年までタルボット・スピヴァクと、次にバースデヴ・チャタジーと結婚した。[11] 彼女には子供はいない。[11] 1960年代と1970年代 1959年、卒業と同時に週40時間、英語の家庭教師として職を得た。修士論文のテーマは、M.H.アブラムズとの共著で、ワーズワースにおける無垢の表 現についてであった。1961年、スピヴァクは「生活担保」で借りたお金でアメリカのコルネル大学の英語学大学院に入学した。1962年、英語学科から経 済的支援を得ることができなかったため、フランス語とドイツ語の準備が不十分であったにもかかわらず、比較文学という新しいプログラムに転校した。彼女の 博士論文は、比較文学プログラムの初代ディレクターであるポール・ド・マンの指導の下で執筆され、タイトルは『Myself Must I Remake: The Life and Poetry of W.B. Yeats』であった。1963年から1964年にかけて、彼女はケンブリッジ大学のギルトン・カレッジで研究生としてT.R.ヘン教授の指導を受け、 イェーツの詩における叙事的主体の成長段階の表現について研究した。1963年夏には、アイルランドのスライゴで開催されたイェーツ・サマースクールで 「イェーツと死のテーマ」という講座を担当した。(1987年には再び同地を訪れ、ポストコロニアリズムにおけるイェーツの位置づけについて発表してい る。)[要出典] 1965年秋、スピヴァクはアイオワ大学英語学部の助教授となった。1970年に終身在職権を得た。彼女は博士論文を公表することはなかったが、自身の知 的立場を妥協することなく、学部学生にも理解できるようなイェーツに関する評論を書くことを決意した。その結果が、彼女の最初の著書であり、若い大人向け に書かれた『Myself I Must Remake: The Life and Poetry of W.B. Yeats』である。 1967年、自己改善を試みる中で、スピヴァクは、著者不明の『De la grammatologie』という本を入手した。彼女はこの本を翻訳することを決意し、長い訳者序文を書いた。この本はたちまち成功を収め、この「訳者 序文」は、著者のジャック・デリダが打ち出した脱構築の哲学の入門書として、1971年にスピヴァクが彼と出会って以来、世界中で使用されるようになっ た。 1974年、アイオワ大学でスピヴァクは比較文学科に翻訳修士課程(MFA in Translation)を創設した。[14] 翌年、彼女は比較文学科の学科長となり、正教授に昇進した。1978年、彼女はシカゴ大学の全米人文科学教授となった。その後も、多くの客員教授職やフェ ローシップを授与された。1978年にはテキサス大学オースティン校の英米文学および比較文学の教授に就任した。 1980年代から現在まで 1982年にはエモリー大学で英文学および比較文学のロングストリート教授に任命された。1986年にはピッツバーグ大学で初のメロン英文学教授に就任 し、ここでカルチュラル・スタディーズのプログラムを立ち上げた。1991年からはコロンビア大学で人文科学のアバロン財団教授を務め、2007年には人 文科学のユニバーシティ・プロフェッサーに任命された。 1986年より、スピヴァクは西ベンガル州とビハール州/ジャールカンド州の州境に住む土地を持たない文盲の人々、大人や子供たちに教育やトレーニングを 行っている。こうした千年にわたるカースト制度の抑圧によって傷ついた認識論へのアクセスを試みる継続的な取り組みにより、彼女はグローバリゼーションの 状況とハイ・セオリーの限界をより明確に理解することができた。1997年には、第三帝国の生き残りである友人ロア・メッツガーが、農村教育の活動支援の ために遺言で1万ドルを彼女に残した。これを受けてスピヴァクは、農村教育のためのパレシュ・チャンドラ・シヴァーニ・チャクラヴォルティー記念財団を設 立した。この財団には、彼女が京都賞の大半を寄付した。 |
| Work Gayatri Spivak  Spivak speaking on “The Strength of Critique: Trajectories of Marxism–Feminism” at the Internationaler Kongress Spivak rose to prominence with her translation of Derrida's De la grammatologie, which included a translator's introduction that has been described as "setting a new standard for self-reflexivity in prefaces".[15] After this, as a member of the "Subaltern Studies Collective", she carried out a series of historical studies and literary critiques of imperialism and international feminism. She has often referred to herself as a "practical Marxist-feminist-deconstructionist".[16] Her predominant ethico-political concern has been for the space occupied by the subaltern, especially subaltern women, both in discursive practices and in institutions of Western cultures. Edward Said wrote of Spivak's work, "She pioneered the study in literary theory of non-Western women and produced one of the earliest and most coherent accounts of that role available to us."[17] "Can the Subaltern Speak?" Her essay, "Can the Subaltern Speak?" (1988), established Spivak among the ranks of feminists who consider history, geography, and class when thinking about women. In "Can the Subaltern Speak?", Spivak discusses the lack of an account of the Sati practice, leading her to reflect on whether the subaltern can even speak.[18] Spivak writes about the process, the focus on the Eurocentric Subject as they disavow the problem of representation; and by invoking the Subject of Europe, these intellectuals constitute the subaltern 'Other of Europe' as anonymous and mute. In all her work, Spivak's main effort has been to try to find ways of accessing the subjectivity of those who are being investigated. She is hailed[by whom?] as a critic who has feminized and globalized the philosophy of deconstruction, considering the position of the subaltern (a word used by Antonio Gramsci as describing ungeneralizable fringe groups of society who lack access to citizenship). In the early 1980s, she was also hailed as a co-founder of postcolonial theory, which she refused to accept fully. Her A Critique of Postcolonial Reason, published in 1999, explores how major works of European metaphysics (e.g., Kant, Hegel) not only tend to exclude the subaltern from their discussions, but actively prevent non-Europeans from occupying positions as fully human subjects.[19] In this work, Spivak launched the concept of "sanctioned ignorance" for the "reproducing and foreclosing of colonialist structures". This concept denotes a purposeful silencing through the "dismissing of a particular context as being irrelevant"; an institutionalized and ideological way of presenting the world.[20] Spivak coined the term "strategic essentialism", which refers to a sort of temporary solidarity for the purpose of social action. For example, women's groups have many different agendas that potentially make it difficult for feminists to work together for common causes. "Strategic essentialism" allows for disparate groups to accept temporarily an "essentialist" position that enables them able to act cohesively and "can be powerfully displacing and disruptive."[21] However, while others have built upon the idea of "strategic essentialism", Spivak has been unhappy with the ways the concept has been taken up and used. In interviews, she has disavowed the term, although she has not completely deserted the concept itself.[22][23] In speeches given and published since 2002, Spivak has addressed the issue of terrorism and suicide bombings. With the aim of bringing an end to suicide bombings, she has explored and "tried to imagine what message [such acts] might contain", ruminating that "suicidal resistance is a message inscribed in the body when no other means will get through".[24] One critic has suggested that this sort of stylised language may serve to blur important moral issues relating to terrorism.[25] However, Spivak stated in the same speech that "single coerced yet willed suicidal 'terror' is in excess of the destruction of dynastic temples and the violation of women, tenacious and powerfully residual. It has not the banality of evil. It is informed by the stupidity of belief taken to extreme."[24] Apart from Derrida, Spivak has also translated the fiction of the Bengali author, Mahasweta Devi, the poetry of the 18-century Bengali poet Ramprasad Sen, and A Season in the Congo by Aimé Césaire, a poet, essayist, and statesman from Martinique. In 1997, she received a prize for translation into English from the Sahitya Akadami from the National Academy of Literature in India.[26] Academic roles and honors She has been a Guggenheim fellow, has received numerous academic honours including an honorary doctorate from Oberlin College,[27] and has been on the editorial board of academic journals such as Boundary 2. She was elected to the American Philosophical Society in 2007.[28] In March of that same year, Columbia University President Lee Bollinger appointed Spivak University Professor, the institution's highest faculty rank. In a letter to the faculty, he wrote: Not only does her world-renowned scholarship—grounded in deconstructivist literary theory—range widely from critiques of post-colonial discourse to feminism, Marxism, and globalization; her lifelong search for fresh insights and understanding has transcended the traditional boundaries of discipline while retaining the fire for new knowledge that is the hallmark of a great intellect. Spivak has served on the advisory board of numerous academic journals, including Janus Unbound: Journal of Critical Studies published by Memorial University of Newfoundland, differences, Signs: Journal of Women in Culture and Society, Interventions: International Journal of Postcolonial Studies published by Routledge, and Diaspora: A Journal of Transnational Studies.[29][30][31] Spivak has received 11 honorary doctorates from the University of Toronto, University of London, Oberlin College, Universitat Rovira Virgili, Rabindra Bharati University, Universidad Nacional de San Martín, University of St Andrews, Université de Vincennes à Saint-Denis, Presidency University, Yale University, and University of Ghana-Legon. In 2012, she became the only Indian recipient of the Kyoto Prize in Arts and Philosophy in the category of Arts and Philosophy, while in 2021 she was elected a corresponding fellow of the British Academy.[32] Spivak has advised many significant post-colonial scholars. Professors Jenny Sharpe and Mark Sanders are among her former students.[19]: xxiii [33] |
仕事 ガヤトリ・スピヴァク  スピヴァクは「批判の力:マルクス主義フェミニズムの軌跡」について、インターナショナル・コングレスで講演した スピヴァクは、デリダの『グラマトロジーについて』の翻訳で一躍有名になった。この翻訳には「序文における自己言及性の新たな基準を打ち立てた」と評され る翻訳者による序文が含まれていた。[15] その後、「サバルタン研究集団」のメンバーとして、帝国主義と国際フェミニズムに関する一連の歴史研究と文学批評を行った。彼女はしばしば自らを「実践的 マルクス主義フェミニスト・脱構築主義者」と称している。[16] 彼女の倫理的・政治的関心は、西洋文化における言説の実践と制度の両方において、サバルタン、特にサバルタン女性が占める空間に向けられている。エドワー ド・サイードはスピヴァクの業績について、「彼女は文学理論における非西洋の女性研究の先駆者であり、その役割について、我々が利用できる最も初期かつ最 も首尾一貫した説明のひとつを生み出した」と述べている。[17] 「サバルタンは語ることができるか? 」 彼女の論文「サバルタンは語ることができるか?」(1988年)は、女性について考える際に歴史、地理、階級を考慮するフェミニストの仲間入りをするきっ かけとなった。「サバルタンは語ることができるか?」の中でスピヴァクは、サティの慣習についての説明の欠如について論じ、サバルタンは語ることもできる のかどうかについて考察している。[18] スピヴァクは、その過程について、表象の問題を否定するようなヨーロッパ中心主義的な主体に焦点を当てて書いている。ヨーロッパの主体を呼び起こすこと で、これらの知識人はサバルタンを「ヨーロッパの他者」として匿名で無口な存在として構成している。彼女のすべての著作において、スピヴァクの主な努力 は、調査対象者の主観に近づく方法を見つけようとするものであった。彼女は、サバルタン(アントニオ・グラムシが、市民権へのアクセスを持たない、一般化 できない社会の周縁集団を表現する際に用いた言葉)の立場を考慮し、脱構築哲学を女性化し、グローバル化した批評家として賞賛されている。 1980年代初頭には、ポストコロニアリズムの共同創始者としても称賛されたが、彼女はこれを全面的に受け入れることを拒否した。1999年に出版された 著書『ポストコロニアル理性批判』では、ヨーロッパの形而上学の主要な作品(カント、ヘーゲルなど)が、サバルタンを議論から排除する傾向にあるだけでな く、非ヨーロッパ人が完全に人間としての主体となることを積極的に妨げていることを探求している。[19] この作品でスピヴァクは、「植民地主義的構造の再生産と封鎖」のための「容認された無知」という概念を打ち出した。この概念は、「特定の文脈を無関係とし て退ける」ことによる意図的な沈黙を意味し、制度化されイデオロギー的な世界の見せ方を示すものである。 スピヴァクは「戦略的本質主義」という用語を考案した。これは、社会活動の目的のため の一時的な連帯を意味する。例えば、女性グループには多くの異なる議題があり、フェミニストが共通の目的のために協力して活動することが困難になる可能性 がある。「戦略的本質主義」は、一時的に「本質主義」の立場を受け入れることを異質なグループに許容し、団結して行動することを可能にする。「それは強力 に転換し、混乱を引き起こす可能性がある」[21] しかし、他の人々が「戦略的本質主義」の考えを基にしている一方で、スピヴァクは、この概念がどのように受け入れられ、利用されてきたかについて不満を抱 いている。彼女はインタビューでこの用語を否定しているが、この概念自体を完全に放棄しているわけではない。 2002年以降のスピーチや出版された著作において、スピヴァクはテロリズムと自爆テロの問題を取り上げている。自爆テロを終わらせることを目的として、 彼女は「そのような行為がどのようなメッセージを含んでいるのか想像しようと試みた」と述べ、「自殺的抵抗は、他の手段が通じない場合に身体に刻み込まれ るメッセージである」と考察している。ある批評家は、このような このような様式化された表現は、テロリズムに関する重要な道徳的問題をぼやかしてしまう可能性がある」と指摘している。[25] しかしスピヴァクは、同じスピーチの中で「強制されながらも自らの意思で選んだ単独の自殺的『テロ』は、王朝時代の寺院の破壊や女性への暴力よりも、はる かに根強く、強力な破壊力を持っている。それは悪の平凡さとは無縁である。それは、極端な信念の愚かさによって生み出されたものなのだ」と述べている。 [24] デリダ以外にも、スピヴァクはベンガル人作家マハシュヴェタ・デーヴィーの小説、18世紀のベンガル人詩人ラムプラサード・センの詩、そしてマルティニー ク出身の詩人、エッセイスト、政治家であるエメ・セゼールの『コンゴの季節』を英訳している。1997年には、インドの文学アカデミーである Sahitya Akadamiから英訳作品に対して賞を授与された。 学術的な役割と栄誉 彼女はグッゲンハイム奨学生であり、オベリン大学から名誉博士号を含む数々の学術的栄誉を受けている。また、学術誌『Boundary 2』の編集委員も務めている。2007年にはアメリカ哲学協会の会員に選出された。同年3月、コロンビア大学学長リー・ボリンジャーはスピヴァクを同校の 最高職位である大学教授に任命した。学内向けの手紙の中で、ボリンジャーは次のように述べている。 彼女の世界的に有名な研究は、脱構築主義の文学理論を基盤としており、ポストコロニアルの言説の批判からフェミニズム、マルクス主義、グローバリゼーショ ンまで、幅広い分野にわたっている。また、彼女は生涯を通じて、新たな洞察と理解を求めており、偉大な知性の特徴である新しい知識への飽くなき探究心を維 持しながら、学問の伝統的な境界を超越してきた。 スピヴァクは、ニューファンドランドメモリアル大学出版の『Janus Unbound: Journal of Critical Studies』、Routledge出版の『differences』、『Signs: Journal of Women in Culture and Society』、『Interventions: International Journal of Postcolonial Studies』、ディアスポラ研究誌『Diaspora: トロント大学、ロンドン大学、オベリン大学、ロヴィラ・ビルジリ大学、ラビンドラ・バーラティ大学、サン・マルティン国立大学、セント・アンドルーズ大 学、ヴァンセンヌ・サン・ドニ大学、プレジデンシー大学、イェール大学、ガーナ大学レゴン校から11の名誉博士号を授与されている。2012年には、芸術 および哲学部門における京都賞の唯一のインド人受賞者となり、2021年には英国学士院の通信会員に選出された。 スピヴァクは、多くの重要なポストコロニアル学者に助言を与えてきた。ジェニー・シャープ教授とマーク・サンダース教授は、彼女の元学生である。 |
| Criticism This article's "criticism" or "controversy" section may compromise the article's neutrality. Please help rewrite or integrate negative information to other sections through discussion on the talk page. (March 2022) Spivak has often been criticized for her cryptic prose.[34][35] Terry Eagleton laments that If colonial societies endure what Spivak calls 'a series of interruptions, a repeated tearing of time that cannot be sutured', much the same is true of her own overstuffed, excessively elliptical prose. She herself, unsurprisingly, reads the book's broken-backed structure in just this way, as an iconoclastic departure from 'accepted scholarly or critical practice'. But the ellipses, the heavy-handed jargon, the cavalier assumption that you know what she means, or that if you don't she doesn't much care, are as much the overcodings of an academic coterie as a smack in the face for conventional scholarship.[36] Writing for the New Statesman, Stephen Howe complained that "Spivak is so bewilderingly eclectic, so prone to juxtapose diverse notions without synthesis, that ascribing a coherent position to her on any question is extremely difficult."[11] Judith Butler, in a response critical of Eagleton's position, cited Adorno's comment on the lesser value of the work of theorists who "recirculate received opinion", and opined that Spivak "gives us the political landscape of culture in its obscurity and proximity", and that Spivak's supposedly "complex" language has resonated with and profoundly changed the thinking of "tens of thousands of activists and scholars", and continues to do so.[37] In May 2024, Spivak was involved in a controversy where she repeatedly corrected the pronunciation of a dalit graduate student Anshul Kumar who asked her a question as part of a discussion at an event in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Anshul Kumar shared in a dalit blog about feeling humiliated and insulted during the incident.[38] Spivak remarked in an interview that Anshul Kumar "had not identified himself as a Dalit".[39] Dalit scholar Anilkumar Payyappilly Vijayan called the student's reaction "a strategy of counter-violence" against "the structural violence built into the very edifice of postcoloniality on which many dominant class intellectuals [like Spivak] have been comfortably placed".[40] |
批判 この記事の「批判」または「論争」の節は、記事の客観性を損なっている可能性がある。否定的な情報は、トークページでの議論を通じて、他のセクションに書 き直したり、統合したりするよう協力してほしい。 (2022年3月) スピヴァクはしばしば、難解な散文について批判されている。[34][35] テリー・イーグルトンは次のように嘆いている。 植民地社会がスピヴァクが「一連の中断、縫合できない時間の裂け目の繰り返し」と呼ぶものを耐え忍ぶのであれば、彼女自身の詰め込みすぎで過度に省略され た散文も同様である。彼女自身も、驚くことではないが、この本の破綻した構造を「学術的または批評的慣習として受け入れられているもの」からの異端的離脱 として、まさにそのように読んでいる。しかし、省略、大げさな専門用語、読者は彼女の言わんとすることが分かるはずだという思い上がり、あるいは、分から なくても彼女はあまり気にしないという態度は、従来の学術研究に対する一撃であると同時に、学術的仲間内の過剰なコーディングでもある。 ニュー・ステーツマン誌に寄稿したスティーブン・ハウは、「スピヴァクはあまりにも困惑するほど折衷主義的であり、統合することなく多様な概念を並置する 傾向が強いため、いかなる問題についても彼女に首尾一貫した立場を帰属させることは極めて困難である」と不満を述べている。 ジュディス・バトラーは、イーグルトンの立場を批判的に論じた論文の中で、アドルノが「既成の意見を再循環させる」理論家の作品の価値の低さを指摘したコ メントを引用し、スピヴァクは「 その不明瞭さと親密さにおいて、文化の政治的風景を私たちに示してくれている」と述べ、スピヴァクの「複雑」な言語は「何万人もの活動家や学者」の考えに 共鳴し、その考えを深く変え、今も変え続けていると主張した。[37] 2024年5月、スピヴァクは、ニューデリーのネルー大学でのイベントでの議論の最中に質問をしたダリット出身の大学院生、アンシュル・クマール (Anshul Kumar)の発音を繰り返し訂正したことで物議を醸した。アンシュル・クマールは、この出来事について、ダリットのブログで屈辱と侮辱を感じたと述べ た。[38] スピーヴァクはインタビューで、アンシュル・クマールは「自分がダリットであると名乗っていなかった」と述べた。[39] ダリットの学者であるアニルクマール・パイ 「ポストコロニアリティの基盤に組み込まれた構造的暴力」に対する「カウンター・バイオレンス(暴力への対抗策)」であると述べた。この構造的暴力は、ス ピヴァクのような支配階級の知識人たちが安住してきたものだ。[40] |
| Avital Ronell controversy In May 2018, Spivak signed a collective letter to New York University to defend Avital Ronell, a colleague of Spivak, against the charge of sexual abuse from NYU graduate student Nimrod Reitman. Spivak and the other signatories called the case a "legal nightmare" for Ronell and charged Reitman with conducting a "malicious campaign" against her. More specifically, the letter suggested that Ronell should be excused on the basis of the significance of her academic contributions. Many signatories were also concerned of the utilisation of feminist tools, like Title IX, to take down feminists.[41] Judith Butler, the chief signatory, subsequently apologized for certain aspects of the letter.[42][43] NYU ultimately found Ronell guilty of sexual harassment and suspended her for a year. |
アヴィタル・ロネル論争 2018年5月、スピヴァクは、NYUの大学院生ニムロッド・レイトマンによる性的虐待の告発に対して、スピヴァクの同僚であるアヴィタル・ロネルを擁護 する集団書簡に署名した。スピヴァクと他の署名者は、この件をロネルにとって「法的な悪夢」と呼び、レイトマンが彼女に対して「悪意のあるキャンペーン」 を行っていると非難した。より具体的には、この書簡は、ロネルの学術的貢献の重要性を理由に、彼女を免責すべきだと主張した。また、多くの署名者は、フェ ミニストを陥れるために、タイトルIXのようなフェミニストのツールが利用されることを懸念していた。[41] 署名者の筆頭であるジュディス・バトラーは、その後、この書簡の特定の側面について謝罪した。[42][43] NYUは最終的に、ロネルをセクハラ有罪と認定し、1年間の停職処分とした。 |
| Publications Academic books Myself Must I Remake: The Life and Poetry of W.B. Yeats. Crowell. 1974. ISBN 9780690001143. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. Routledge. 2006 [1987]. ISBN 9781135070816. This is a collection of previously published essays. Selected Subaltern Studies. Oxford University Press. 1988. ISBN 9780195052893. This collection was edited by Ranajit Guha and Spivak, and includes an introduction by Spivak. The Post-Colonial Critic – Interviews, Strategies, Dialogues. Routledge. 1990. ISBN 9781134710850. This collection of interviews was edited by Sarah Harasym. Outside in the Teaching Machine. Routledge. 2009 [1993]. ISBN 9781135070571. The Spivak Reader. Routledge. 1995. ISBN 9781135217129. Spivak, Gayatri Chakravorty (1999). A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-17764-2. Death of a Discipline. Columbia University Press. 2003. ISBN 9780231503235. Conversations with Gayatri Chakravorty Spivak. Seagull Books. 2012 [2006]. ISBN 9781905422289. These conversations were conducted with Swapan Chakravorty, Suzana Milevska, and Tani E. Barlow. Who Sings the Nation-State?: Language, Politics, Belonging. Seagull Books. 2007. ISBN 9781905422579. This book was co-authored by Spivak and Judith Butler. Other Asias. Wiley. 2008. ISBN 9781405102070. Nationalism and the Imagination. Seagull Books. 2010. ISBN 9780857423184. An Aesthetic Education in the Era of Globalization. Harvard University Press. 2012. ISBN 9780674051836. Harlem. Seagull Books. 2012. ISBN 9780857420848. This book engages with photographs by Alice Attie. Readings. Seagull Books. 2014. ISBN 9780857422088. Selected essays "Translator's Preface" in Of Grammatology, Jacques Derrida, trans. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore & London: Johns Hopkins University Press. ix-lxxxvii. 1976. Spivak, Gayatri Chakravorty (1985). "Three Women's Texts and a Critique of Imperialism". Critical Inquiry. 12 (1): 243–61. doi:10.1086/448328. S2CID 143045673. Spivak, Gayatri Chakravorty (1985). "The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives". History and Theory. 24 (3): 247–72. doi:10.2307/2505169. JSTOR 2505169. S2CID 147694151. "Speculations on Reading Marx: After Reading Derrida" in Post-Structuralism and the Question of History, eds. Derek Attridge, et al. Cambridge: Cambridge University Press. 30–62. 1987. "Can the Subaltern Speak?" in Marxism and the Interpretation of Culture, eds. Cary Nelson and Lawrence Grossberg. Basingstoke: Macmillan. 271–313. 1988. "Woman in Difference: Mahasweta Devi’s ‘Douloti the Bountiful’" in Nationalisms and Sexuality, eds. Andrew Parker et al. New York: Routledge. 96–120. 1992. Spivak, Gayatri Chakravorty (1994). "Responsibility". Boundary 2. 21 (3): 19–64. doi:10.2307/303600. JSTOR 303600. "Ghostwriting". Diacritics. 25 (2): 65–84. 1995. Spivak, Gayatri Chakravorty (2001). "A Note on the New International". Parallax. 7 (3): 12–6. doi:10.1080/13534640110064084. S2CID 144501695. "Scattered Speculations on the Subaltern and the Popular". Postcolonial Studies. 8 (4): 475–86. 2006. Translations Derrida, Jacques (2016) [1967]. Of Grammatology. The Johns Hopkins University Press. ISBN 9781421419954. This translation includes a lengthy critical preface by Spivak. Devi, Mahasweta (1995) [1993]. Imaginary Maps. Routledge. ISBN 9780415904636. This translation includes a critical introduction of the three stories. Devi, Mahasweta (1997). Breast Stories. Seagull Books. ISBN 9788170461401. This translation includes a critical introduction of the three stories. Mazumdar, Nirode; Sena, Rāmaprasāda (2000). Song for Kali: A Cycle. Seagull Books. ISBN 9788170461555. This translation includes an introduction to the story. Devi, Mahasweta (2002) [1999]. Old Women. Seagull Books. ISBN 9788170461449. This translation includes a critical introduction of the two stories. Devi, Mahasweta (2002) [1980]. Chotti Munda and His Arrow. Seagull Books. ISBN 9780857426772. This translation includes a critical introduction of the novel. Césaire, Aimé (2010) [1966]. A Season in the Congo. Seagull Books. ISBN 9781905422944. This translation includes a critical introduction of the novel. Red Thread (forthcoming) Gramsci and the Schucht Sisters (forthcoming, in collaboration with Ursula Apitzsch, et al.) In popular culture Phire Esho, Chaka, a 1961 book of love poems by Binoy Majumdar, was addressed and dedicated to her.[44] Her name appears in the lyrics of the Le Tigre song "Hot Topic".[45] |
出版物 学術書 Myself Must I Remake: The Life and Poetry of W.B. Yeats. Crowell. 1974. ISBN 9780690001143. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. Routledge. 2006 [1987]. ISBN 9781135070816. これは以前に出版されたエッセイのコレクションである。 Selected Subaltern Studies. オックスフォード大学出版局. 1988. ISBN 9780195052893. このコレクションはラナジット・グハとスピヴァクが編集し、スピヴァクによる序文が含まれている。 The Post-Colonial Critic – Interviews, Strategies, Dialogues. ルートレッジ. 1990. ISBN 9781134710850。このインタビュー集はサラ・ハラシムが編集した。 『ティーチング・マシンの外側』。Routledge。2009年[1993年]。ISBN 9781135070571。 『スピヴァク・リーダー』。Routledge。1995年。ISBN 9781135217129。 スピヴァク、ガヤトリ・チャクラヴォルティ(1999年)。『ポストコロニアル理性批判:消えゆく現在史に向けて』ハーバード大学出版局。ISBN 978-0-674-17764-2。 『学問の死』コロンビア大学出版局。2003年。ISBN 9780231503235。 スピーヴァクとの対話。シーガルブックス。2012年[2006年]。ISBN 9781905422289。これらの対話は、スワパン・チャクラヴォルティ、スザナ・ミレフスカ、タニ・E・バーロウとの対話である。 国家を歌うのは誰か?言語、政治、帰属。シーガルブックス。2007年。ISBN 9781905422579。本書はスピヴァクとジュディス・バトラーの共著である。 Other Asias. Wiley. 2008. ISBN 9781405102070. ナショナリズムと想像力. Seagull Books. 2010. ISBN 9780857423184. グローバル化時代の美的教育。ハーバード大学出版局。2012年。ISBN 9780674051836。 ハーレム。シーガルブックス。2012年。ISBN 9780857420848。この本はアリス・アッティーの写真と関わっている。 リーディングス。シーガルブックス。2014年。ISBN 9780857422088。 選集 「訳者まえがき」ジャック・デリダ著『グラマトロジーについて』ガヤトリ・C・スピヴァク訳。ボルチモア&ロンドン:ジョンズ・ホプキンス大学出 版。ix-lxxxvii。1976年。 スピヴァク、ガヤトリ・チャクラヴォルティ(1985年)。「3人の女性のテクストと帝国主義批判」。『クリティカル・インクワイアリー』12(1): 243-61。doi:10.1086/448328。S2CID 143045673。 スピヴァク、ガヤトリ・チャクラヴォルティ (1985年). 「シリムール藩王夫人:アーカイブを読む試論」. 『History and Theory』. 24 (3): 247–72. doi:10.2307/2505169. JSTOR 2505169. S2CID 147694151. 「マルクスを読むことについての思索:デリダを読んで」『ポスト構造主義と歴史の問題』編:デレク・アトリッジ他。ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版 局。30-62頁。1987年。 「サバルタンは語ることができるか?」『マルクス主義と文化の解釈』編:キャリー・ネルソン、ローレンス・グロスバーグ。ベージングストーク:マクミラ ン。271-313頁。1988年。 「差異のなかの女性:マハシュヴェタ・デーヴィの『ドルーロティ・ザ・バウンティフル』」『ナショナリズムとセクシュアリティ』アンドリュー・パーカー他 編、ニューヨーク:ルートレッジ、96-120ページ、1992年。 スピヴァク、ガヤトリ・チャクラヴォルティ(1994年)。「責任」。『バウンダリー2』21巻3号:19-64ページ。doi: 10.2307/303600。 JSTOR 303600。 「ゴーストライティング」。『ダイアクリティクス』25巻2号:65-84ページ。1995年。 スピヴァク、ガヤトリ・チャクラヴォルティ (2001年). 「『ニュー・インターナショナル』についての覚書」. パララックス. 7 (3): 12–6. doi:10.1080/13534640110064084. S2CID 144501695. 「サバルタンと大衆に関する散逸した思索」. Postcolonial Studies. 8 (4): 475–86. 2006. 翻訳 デリダ、ジャック (2016) [1967]. グラマトロジーについて. ジョンズ・ホプキンス大学出版. ISBN 9781421419954. この翻訳にはスピヴァクによる長大な批判的序文が含まれている。 デヴィ、マハシュヴェタ (1995) [1993] 『想像上の地図』。 ルートレッジ。 ISBN 9780415904636。 この翻訳には3つの物語の批評的な序文が含まれている。 デヴィ、マハシュヴェタ (1997) 『胸の物語』。 シーガルブックス。ISBN 9788170461401。この翻訳には3つの物語の批評的序文が含まれている。 マジュムダル、ニロデ、セナ、ラーマプラサーダ(2000年)。『カーリーへの歌:サイクル』。シーガルブックス。ISBN 9788170461555。この翻訳には物語の序文が含まれている。 デヴィ、マハシュヴェタ(2002年)[1999年]。『老女たち』。Seagull Books。ISBN 9788170461449。この翻訳には2つの物語の批評的序文が含まれている。 デヴィ、マハシュヴェタ(2002年)[1980年]。『チョッティ・ムンダと彼の矢』。Seagull Books。ISBN 9780857426772。この翻訳には小説の評論的な序文が含まれている。 セゼール、エメ(2010年)[1966年]。コンゴの季節。Seagull Books。ISBN 9781905422944。この翻訳には小説の評論的な序文が含まれている。 赤い糸(近刊) グラムシとシュクート姉妹(共同執筆者:ウルスラ・アピッツシュ他) 大衆文化において ファイア・エショ、チャカ(Phire Esho, Chaka)は、ビノイ・マジュムダールによる1961年の愛の詩集であり、彼女に捧げられている。[44] 彼女の名前は、バンド「レ・ティグレ」の楽曲「ホット・トピック」の歌詞にも登場する。[45] |
| List
of deconstructionists Postcolonialism Postcolonial feminism Subaltern Studies Comparative literature |
脱構築主義者の一覧 ポストコロニアリズム ポストコロニアリズム・フェミニズム サバルタン研究 比較文学 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Gayatri_Chakravorty_Spivak |
★旧クレジット:ガヤトリ・スピバァク(スピバック)の「サバルタンは語れるか」入門
(Agency and Re-Imaginating of "Society")
リンク
- ︎先住民の視点からグローバル・スタディーズを再構築する領 域横断研究▶︎知識の脱植民地化▶︎︎脱植民地化▶︎戦略的本質 主義▶︎︎
- 脱植民地化の方法論▶︎エージェンシー▶︎︎政治的アイデンティティ▶︎政治的アイデンティティとしての先住民▶
- カント流植民地主義︎︎▶ポストコロニアリズム︎▶︎︎戦略的本質主義▶︎先住民の視点からグローバル・スタディーズを再構築する▶︎︎
- オリエンタリズム(サイード)▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎
文献
- Bhabha, Homi K. 1994. The Location of Culture. London: Routledge.
- Fanon, Frantz. 1967[1952] Black Skin, White Masks. trans. C. Porter. New York: Grove Weidenefeld.
- Mohanty, Chandra Talpade. 1984. Under Western Eyes. in "Colonial Discourses and Post-colonial Theory: A reader", William, P and L. Chrisman eds. pp.196-220, New York: Columbia University Press.
- Spivak, Gayatri Chakravory. 1988. Can Subaltern Speak ? in William, P and L. Chrisman eds. pp.66-111. [ガヤトリ・C・スピバック『サバルタンは語ることができるか』上村忠男訳、みずす書房、1998年]
- Spivak, Gayatri Chakravory. 1993. Subaltern Talk. in "The Spivak Reader". D. Landry et al. eds., pp.287-308. London: Routledge.
- Abercrombie, N., S. Hill, and B.S. Turner eds. 1994.The Dictionary of Sociology, London: Penguin Books.(丸山哲央監訳、1996『社会学中辞典』ミネルヴァ書房)。
- ヘラー、アグネス1982『マルクスの欲求理論』良知力・ 小箕俊介訳、法政大学出版局。
- 池田光穂2000「「医療と文化」再考—グアテマラにおける医療人類学の再想像—」『思想』第908号,Pp.199-218
- ミンスキー、マーヴィン1990『心の社会』安西祐一郎訳、東京 : 産業図書。
- 本橋哲也1999「応答するエイジェンシー」『現代思想』27(7):207-217.
- 太田好信1998『トランスポジションの思想 : 文化人類学の再想像』、京都 : 世界思想社。
- 太田好信1998「存在しえなかったものを回復する:スピバックの論文「サバルタンは語ることができるか」が人類学へ投げかける問題と可能性」『現代思 想』12(12):200-207
- 太田好信1999「未来から語りかける言語—中米グアテマラにおけるマヤ系言語とマヤ運動—」『思想』第902号、pp.20-41
- 太田好信2000「人類学とサバルタンの主体的関与——『私の名はリゴベルタ・メンチュ』における表象の問題」『現代思想』28(2):8-23.
- G.C.スピヴァク1998『サバルタンは語ることができるか』上村忠男訳、東京 : みすず書房
- 竹村和子1997「責任あるエイジェンシー——ポストモダニズム、ポストコロニアリズム、フェミニズム」『差異化と同一化:ポストコロニアル文学論』山形 和美編・所収、pp.65-81、研究社出版
- 田辺繁治1998「儀礼的暴力とその身体的基礎——北タイの供犠と憑依について」『暴力の文化人類学』田中雅一編、京都大学出版会
- ポスト植民地主義の思想 / G.C.スピヴァック著 ; S.ハレイシム編集 ; 清水和子, 崎谷若菜訳, 再版. - 東京 : 彩流社 , 1999.10
- サティー論 : スピヴァク『サバルタンは語ることができるか』をどう読むか(pp.311-348) / 竹中千春,
以下に所収:ポストコロニアルと非西欧世界 / 神奈川大学評論編集専門委員会編、東京 : 御茶の水書房 , 2002.9. -
(神奈川大学評論叢書 / 神奈川大学評論編集専門委員会編 ; 第10巻)
その他の情報


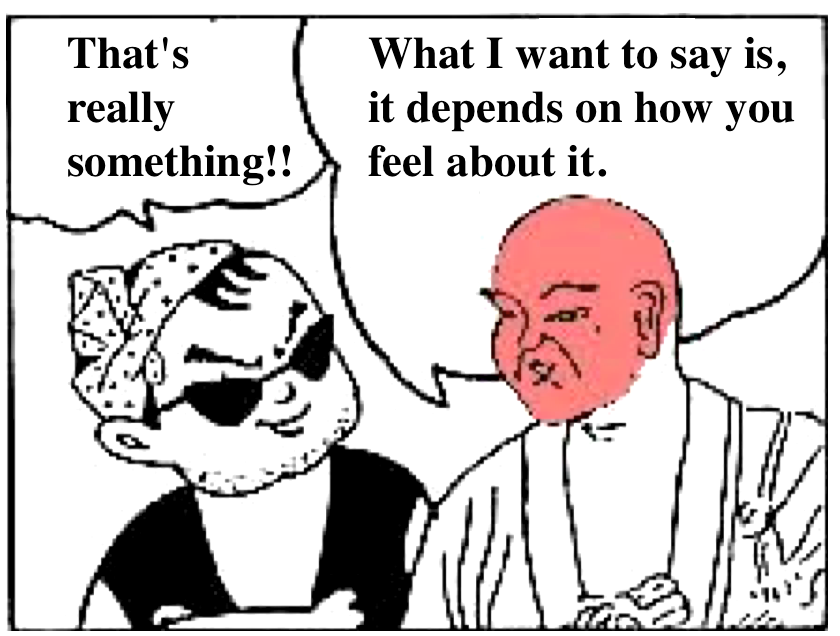

 ☆
☆