
ラファエル・トルヒージョ
Rafael Leónidas Trujillo Molina, 1891-1961, ラファエル・トルヒーヨとも

Rafael
Trujillo (right) and guest
Anastasio Somoza (left) at the
inauguration of Héctor Trujillo as president in 1952
★ラファエル・レオニダス・トルヒーヨ・モリーナ(/truːˈ, Spanish: [rafaː leˈjoʊ/ troo-HEE-yoh]; 1891年10月24日から1961年5月30日)、エルヘフェ(スペイン語:Elˈɾ moˈ、邦名:「ボス」)のニックネームで呼ばれる。el ˈxefe]、「長」または「ボス」の愛称)、は、1930年2月から1961年5月に暗殺されるまでドミニカ共和国を支配したドミニカの独裁者である。
★マリオ・ バルガス・ジョサ『チボの狂宴』作品社、 2011年についての要約や背景情報は、この行でリンクします。
★メ
レンゲ音楽(Merengue
music)については、この行でリンクします。
| Rafael
Leónidas Trujillo Molina (/truːˈhiːjoʊ/ troo-HEE-yoh, Spanish: [rafaˈel
leˈoniðas tɾuˈxiʝo moˈlina]; 24 October 1891 – 30 May 1961), nicknamed
El Jefe (Spanish: [el ˈxefe], "The Chief" or "The Boss"), was a
Dominican dictator who ruled the Dominican Republic from February 1930
until his assassination in May 1961.[2] He served as president from
1930 to 1938 and again from 1942 to 1952, ruling for the rest of the
time as an unelected military strongman under presidents.[Note 1] His
rule of 31 years, known to Dominicans as the Trujillo Era (Spanish: El
Trujillato or La Era de Trujillo), is considered one of the bloodiest
and most corrupt regimes in the Western hemisphere, and centered around
a personality cult of the ruling family. Trujillo's security forces,
including the infamous SIM, were responsible for perhaps as many as
50,000 murders, including between 12,000 and 30,000 Haitians in the
infamous Parsley massacre in 1937, which continues to affect
Dominican-Haitian relations to this day. During his long rule, the Trujillo government's extensive use of state terrorism was prolific even beyond national borders, including the attempted assassination of Venezuelan President Rómulo Betancourt in 1960, the abduction and disappearance in New York City of the Basque-Dominican exile Jesús Galíndez in 1956, and the murder of Spanish writer José Almoina in Mexico, also in 1960.[3] These acts, particularly the presumed murder of Galindez, a naturalized US citizen, and the murder of the Mirabal sisters in 1960, eroded relations between the Dominican Republic and the international community and ushered in OAS sanctions and economic and military assistance to Dominican opposition forces. After this momentous year large segments of the Dominican establishment, including the military, turned against him. By 1960, Trujillo had amassed a net worth of $800 million ($8.02 billion today). On 30 May 1961, he was assassinated by conspirators sponsored by the Central Intelligence Agency (CIA). In the immediate aftermath, Trujillo's son Ramfis took temporary control of the country, exterminating most of the conspirators. By November 1961, the Trujillo family was pressured into exile by the titular president Balaguer, whole introduced reforms to open up the regime. The murder ushered in civil strife which concluded with the Dominican Civil War and a US intervention, eventually stabilised under a multi-party system in 1966. The Trujillo era unfolded in a Hispanic Caribbean environment particularly susceptible to dictators.[Note 2] In the countries of the Caribbean Basin alone, his dictatorship overlapped with those in Cuba, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela, and Haiti. In perspective, the Trujillo dictatorship has been judged more prominent and more brutal than its contemporaries.[5] Trujillo remains a polarizing figure in the Dominican Republic, as the longevity and profound importance of his rule makes a detached evaluation difficult. While his supporters credit him for bringing long-term stability, economic growth and prosperity, doubling life expectancy of average Dominicans and multiplying the GDP,[6] critics denounce the heavy-handed and violent rule of his 30 years in power, including the murder of tens of thousands, his open racism and xenophobia towards Haitians, as well as the Trujillo family's nepotism, widespread corruption and looting of the country's natural resources. |
ラ
ファエル・レオニダス・トルヒーヨ・モリーナ(/truːˈ, Spanish: [rafaː leˈjoʊ/ troo-HEE-yoh];
1891年10月24日から1961年5月30日)、エルヘフェ(スペイン語:Elˈɾ moˈ、邦名:「ボス」)のニックネームで呼ばれる。el
ˈxefe]、「長」または「ボス」の愛称)、は、1930年2月から1961年5月に暗殺されるまでドミニカ共和国を支配したドミニカの独裁者である
[2]。
[1930年から1938年までと1942年から1952年まで大統領を務め、それ以外の期間は大統領の下で選挙で選ばれない軍の強権者として統治した
[注 1] 彼の31年間の統治は、ドミニカ人にトルヒーリョ時代(スペイン語:El TrujillatoまたはLa Era de
Trujillo)として知られ、西半球で最も流血と腐敗した政権の一つとされ、支配家族の個人崇拝が中心であった。悪名高いSIMを含むトルヒーヨの治
安部隊は、1937年の悪名高いパセリの大虐殺での12000人から3万人のハイチ人を含む、おそらく5万人もの殺人に責任があり、これは今日までドミニ
カとハイチの関係に影響を与え続けています。 トルヒーリョの長期政権時代には、1960年のベネズエラ大統領ロムロ・ベタンクール暗殺未遂、1956年のバスク・ドミニカ人亡命者ヘスス・ガリンデス のニューヨークでの誘拐・失踪、同じく1960年のスペイン作家ホセ・アルモイナのメキシコでの殺害など、国境を越えた国家テロが盛んに行われた[3]. [3] これらの行為、特に米国に帰化したガリンデスの殺人と推定される行為と1960年のミラバル姉妹の殺害は、ドミニカ共和国と国際社会の関係を損ない、 OAS制裁とドミニカの反対勢力への経済・軍事援助の始まりとなった。この重要な年以降、軍部を含むドミニカの多くの組織が彼に反旗を翻した。 1960年、トルヒーヨは8億ドル(現在の80億2千万ドル)の純資産を築いた。1961年5月30日、中央情報局(CIA)の陰謀により暗殺された。そ の直後、トルヒーヨの息子ラムフィスが一時的に国を掌握し、共謀者のほとんどを駆逐した。1961年11月、トルヒーリョ一家はバラゲル大統領に圧力をか けられ亡命し、全政権が開放的な改革を行った。この殺人事件をきっかけに内戦が始まり、ドミニカ共和国内戦とアメリカの介入を経て、1966年に複数政党 制のもとで安定した。 トルヒーヨ時代は、カリブ海のヒスパニック系という独裁者の影響を受けやすい環境で展開された[注 2] 。カリブ海盆地の国々だけでも、彼の独裁はキューバ、ニカラグア、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ベネズエラ、ハイチの独裁と重なっている。 トルヒーリョはドミニカ共和国において、その支配の長さと重要性から冷静な評価が難しく、両極端の人物である[5]。彼の支持者は、彼が長期的な安定と経 済成長、繁栄をもたらし、ドミニカ共和国の平均寿命を2倍にし、GDPを倍増させたと評価しているが[6]、批判者は、数万人の殺害、ハイチ人に対する公 然の人種差別と排外主義、トルヒーヨ家の縁故主義、広範囲の汚職、国の天然資源の略奪など彼の30年の権力による強引かつ暴力的支配を糾弾している。 |
| Early life Rafael Leónidas Trujillo y Molina was born on 24 October 1891 in San Cristóbal, Dominican Republic, into a lower-middle-class family.[7] His father was José Trujillo Valdez, the son of Silveria Valdez Méndez of colonial Dominican origin and José Trujillo Monagas, a Spanish sergeant who arrived in Santo Domingo as a member of the Spanish reinforcement troops during the annexation era. Trujillo's mother was Altagracia Julia Molina Chevalier, later known as Mama Julia, the daughter of Pedro Molina Peña, also of colonial Dominican origin, and the teacher Luisa Erciná Chevalier, whose parents were part of the remaining French descendants in Haiti: Trujillo's maternal great-grandfather, Justin Víctor Turenne Carrié Blaise, was of French descent, while his maternal great-grandmother, Eleonore Juliette Chevallier Moreau, was part of Haiti's mulatto class.[8][9] Trujillo was the third of eleven children;[7][Note 3] he also had an adopted brother, Luis Rafael "Nene" Trujillo (1935–2005), who was raised in the home of Trujillo Molina.[8] In 1897, at the age of six, Trujillo was registered in the school of Juan Hilario Meriño. One year later, he transferred to the school of Broughton, where he became a pupil of Eugenio María de Hostos and remained there for the rest of his primary schooling. As a child, he was obsessed with his appearance and would place bottle caps on his clothes that mimicked military decorations. At the age of 16, Trujillo got a job as a telegraph operator, which he held for about three years. Shortly after Trujillo turned to crime: cattle stealing, check counterfeiting, and postal robbery. He spent several months in prison, which did not deter him, as he later formed a violent gang of robbers called the 42.[10][11][12] |
幼少期 ラファエル・レオニダス・トルヒーヨ・イ・モリーナは1891年10月24日にドミニカ共和国のサン・クリストバルで中流階級の家庭に生まれた[7]。父 親はホセ・トルヒーヨ・バルデスで、シルベリア・バルデス・メンデスの息子であり、彼は植民地時代のドミニカ人である。トルヒーヨの母親はアルタグラシ ア・ジュリア・モリーナ・シュバリエ(後にママ・ジュリアと呼ばれる)で、ペドロ・モリーナ・ペニャ(同じく植民地時代のドミニカ人)とルイサ・エルシ ナ・シュバリエ(両親はハイチ残留フランス人の一部)の娘であった。トルヒーヨの母方の曽祖父であるジャスティン・ビクトル・トゥレンヌ・カリエ・ブレー ズはフランス系で、母方の曽祖母であるエレオノール・ジュリエット・シュバリエ・モローはハイチのマルチーズ階級に属していた[8][9]。 [8][9] トルヒーヨは11人兄弟の3番目であった[7][注3]。また、養子の弟ルイス・ラファエル・「ネネ」・トルヒーヨ(1935-2005)がいて、トル ヒーヨ・モリーナ宅で育てられる[8]。 1897年、6歳の時、トルヒーヨはフアン・ヒラリオ・メリーニョの学校に籍を置いた。1年後、ブロートン校に転校し、エウヘニオ・マリア・デ・ホストス の教え子となり、残りの初等教育期間はそこに留まった。幼少の頃、彼は自分の外見にこだわり、軍隊の装飾を模したボトルキャップを服につけていた。16歳 の時、電信技師の仕事に就き、3年ほど勤めた。その後、牛泥棒、小切手偽造、郵便強盗などの犯罪に手を染めた。彼は数ヶ月間刑務所で過ごしたが、後に42 と呼ばれる暴力的な強盗団を結成したため、その抑止力とはならなかった[10][11][12]。 |
| Rise to power In 1916, the United States began its occupation of the Dominican Republic following 28 revolutions in 50 years.[13] At the time, Trujillo was twenty-five and worked as a guardacampestre, controlling sugar cane workers at a plantation in Boca Chica.[12] The occupying force soon established a Dominican army constabulary to impose order. Trujillo joined the National Guard in 1918 with the help of his employer along with US Major James J. MacLean, who was his maternal uncle Teódulo Pina Chevalier's friend, immediately receiving the rank of second lieutenant and training with the US Marines.[14][12] Allegations of forgery were ignored when Trujillo applied and he was later acquitted by a panel of Marines following plausible accusations of rape and extortion.[12] Colonel Richard Malcolm Cutts trained Trujillo further and many Marine leaders praised his abilities at the time, approving his rise among the ranks.[12] President Horacio Vásquez named Trujillo the commander of the Dominican National Police in 1925, he was named brigadier general in 1927 and in 1928, Trujillo reconstituted the police into the army and created it as an independent armed body under his control.[12] A rebellion or coup d'état against President Vásquez broke out in February 1930 in Santiago.[15][16] Trujillo secretly cut a deal with the rebel leader Rafael Estrella Ureña. In return for Trujillo letting Estrella take power, Estrella would allow Trujillo to run for president in new elections. As the rebels marched toward Santo Domingo, Vásquez ordered Trujillo to suppress them. However, feigning "neutrality", Trujillo kept his men in barracks, allowing Estrella's rebels to take the capital virtually unopposed. On 3 March, Estrella was proclaimed acting president, with Trujillo confirmed as head of the police and of the army. As per their agreement, Trujillo became the presidential nominee of the Patriotic Coalition of Citizens (Spanish: Coalición patriotica de los ciudadanos), with Estrella as his running mate.[17] The other candidates became targets of harassment by the army. When it became apparent that the army would allow only Trujillo to campaign unhindered, the other candidates pulled out. Ultimately, the Trujillo-Estrella ticket was proclaimed victorious with an implausible 99 percent of the vote.[18] In a note to the State Department, American ambassador Charles Boyd Curtis wrote that Trujillo received far more votes than actual voters.[19] |
権力の台頭 1916年、アメリカは50年間で28回の革命を経てドミニカ共和国の占領を開始した[13] 当時、トルヒーヨは25歳で、ボカチカの農園でサトウキビ労働者を管理するガードアカンペストレとして働いた[12] 占領軍はすぐにドミニカ軍の治安部隊を設立し、秩序を強制していた。トルヒーヨは1918年に雇用主の援助で、母方の叔父テオドゥロ・ピナ・シュバリエの 友人であったアメリカ少佐ジェームズ・J・マクリーンと共に州兵になり、直ちに少尉の階級を得てアメリカ海兵隊で訓練を受けた。 [14][12] トルヒーヨの申請時には偽造の疑惑は無視され、後に海兵隊の審査会でレイプと恐喝のもっともな告発を受けて無罪となった[12]。リチャード・マルコム・ カッツ大佐はトルヒーヨをさらに訓練し、当時多くの海兵隊指導者が彼の能力を賞賛し、彼の階級が上がることを承認した[12]。 1925年にオラシオ・バスケス大統領がトルヒーヨをドミニカ国家警察の司令官に任命し、1927年には准将に任命され、1928年には警察を軍隊に改組 し、彼の支配下に独立した武装組織として創設した[12] 1930年2月にサンティアゴでバスケス大統領に対する反乱(クーデター)が勃発し、トルヒーヨは反乱軍リーダー、ラファエル・エストレーラ・ウレーニャ と密かに取引している[15][16]. トルヒーリョはエストレージャに政権を任せる代わりに、新たな選挙でトルヒーリョが大統領に立候補することを認めるというものであった。反乱軍がサント・ ドミンゴに向かって進軍してくると、バスケスはトルヒーリョに鎮圧を命じた。しかし、トルヒーリョは「中立」を装って兵舎に兵を待機させ、エストレヤの反 乱軍は事実上無抵抗で首都を奪取することができた。3月3日、エストレージャは大統領代理に就任し、トルヒーリョは警察と軍隊のトップとして承認された。 この合意により、トルヒーリョは市民愛国連合(Coalición patriotica de los ciudadanos)の大統領候補となり、エストレージャはその候補者となった[17]。軍隊がトルヒーリョにだけ選挙運動を自由にさせることが明らか になると、他の候補者は撤退した。最終的に、トルヒーリョとエストレヤの組み合わせ が99%というありえない得票率で勝利を宣言した[18]。アメリカ大 使のチャールズ・ボイド・カーティスは国務省へのメモで、トルヒーリョは実際の投票者よりはるかに多くの票を得たと記している[19]。 |
| In government Three and a half weeks after Trujillo ascended to the presidency, the destructive Hurricane San Zenon hit Santo Domingo and left 2,000 dead. As a response to the disaster, Trujillo placed the Dominican Republic under martial law and began to rebuild the city. He renamed the rebuilt capital of the Dominican Republic Ciudad Trujillo ("Trujillo City") in his honor and had streets, monuments, and landmarks to honor him throughout the country.[20] On 16 August 1931, the first anniversary of his inauguration, Trujillo made the Dominican Party the nation's sole legal political party. However, the country had effectively become a one-party state with Trujillo's inauguration. Government employees were required by law to "donate" 10 percent of their salaries to the national treasury,[21][22] and there was strong pressure on adult citizens to join the party. Members had to carry a membership card, nicknamed the "palmita" since the cover had a palm tree on it, and a person could be arrested for vagrancy without one. Those who did not join or contribute to the party did so at their own risk. Opponents of the régime were mysteriously killed.[citation needed] In 1934, Trujillo, who had promoted himself to generalissimo of the army, was up for re-election. By then, there was no organized opposition left in the country, and he was elected as the sole candidate on the ballot. In addition to the widely rigged (and regularly uncontested) elections, he instated "civic reviews", with large crowds shouting their loyalty to the government, which would in turn create more support for Trujillo.[21] |
政府において トルヒーヨが大統領に就任して3週間半後、ハリケーン「サンゼノン」がサントドミンゴを襲い、死者2,000人を出す大災害が発生した。この災害への対応 として、トルヒーヨはドミニカ共和国を戒厳令下に置き、都市の再建に取り掛かった。彼は再建されたドミニカ共和国の首都を自分の名誉のためにシウダー・ト ルヒーヨ(「トルヒーヨ市」)と改名し、国中に彼を称える通りやモニュメント、ランドマークが設けられた[20]。 就任1周年の1931年8月16日、トルヒーリョはドミニカ共和国を国内唯一の合法政党とした。しかし、トルヒーヨの就任により、国は事実上一党独裁国家 となった。政府職員は給与の10%を国庫に「寄付」することが法律で定められており[21][22]、成人した国民には党に加入するよう強い圧力がかけら れていた。メンバーは、表紙にヤシの木が描かれていることから「パルミタ」と呼ばれる会員証を携帯しなければならず、それがないと浮浪者として逮捕される こともあった。党に加入しない者、党に貢献しない者は自己責任であった。政権に反対する者は謎の死を遂げた[citation needed]。 1934年、陸軍大将に昇進したトルヒーリョは再選を目指した。このとき、国内には組織的な反対勢力は残っておらず、彼は唯一の候補者として投票に参加 し、当選した。広く不正な(そして定期的に無投票になる)選挙に加えて、彼は「市民審査」を導入し、大群衆が政府への忠誠を叫び、その結果トルヒーヨへの 支持をより高めることになった[21]。 |
| Personality cult In 1936, at the suggestion of Mario Fermín Cabral, the Congress of the Dominican Republic voted overwhelmingly to change the name of the capital from Santo Domingo to Ciudad Trujillo. The province of San Cristóbal was renamed to "Trujillo" and the nation's highest peak, Pico Duarte, to Pico Trujillo. Statues of "El Jefe" were mass-produced and erected across the Dominican Republic, and bridges and public buildings were named in his honor. The nation's newspapers had praise for Trujillo as part of the front page, and license plates included slogans such as "¡Viva Trujillo!" and "Año Del Benefactor De La Patria" (Year of the Benefactor of the Nation). An electric sign was erected in Ciudad Trujillo so that "Dios y Trujillo" could be seen at night as well as in the day. Eventually, even churches were required to post the slogan "Dios en cielo, Trujillo en tierra" (God in Heaven, Trujillo on Earth). As time went on, the order of the phrases was reversed (Trujillo on Earth, God in Heaven). Trujillo was recommended for the Nobel Peace Prize by his admirers, but the committee declined the suggestion.[23] Trujillo was eligible to run again in 1938, but, citing the United States example of two presidential terms, he stated, "I voluntarily, and against the wishes of my people, refuse re-election to the high office."[24] In fact, a vigorous re-election campaign had been launched in the middle of 1937 but the international uproar that followed the Haitian massacre later that year forced Trujillo to announce his "return to private life."[25] Consequently, the Dominican Party nominated Trujillo's handpicked successor, 61-year-old vice-president Jacinto Peynado, with Manuel de Jesús Troncoso his running mate. They appeared alone on the ballot in the 1938 election. Trujillo kept his positions as generalissimo of the army and leader of the Dominican Party. It was understood that Peynado was merely a puppet, and Trujillo still held all governing power in the nation. Peynado increased the size of the electric "Dios y Trujillo" sign and died on 7 March 1940, with Troncoso serving out the rest of the term. However, in 1942, with US President Franklin Roosevelt having run for a third term in the United States, Trujillo ran for president again and was elected unopposed. He served for two terms, which he lengthened to five years each. In 1952, under pressure from the Organization of American States, he ceded the presidency to his brother, Héctor. Despite being officially out of power, Rafael Trujillo organized a major national celebration to commemorate 25 years of his rule in 1955. Gold and silver commemorative coins were minted with his image.[citation needed] |
人格崇拝 1936年、マリオ・フェルミン・カブラルの提案により、ドミニカ共和国議会は圧倒的多数で首都の名前をサント・ドミンゴからシウダッド・トルヒーヨに変 更することを決定した。サン・クリストバル県は「トルヒーリョ」に、国の最高峰ピコ・ドゥアルテは「ピコ・トルヒーリョ」に改名された。エル・ヘフェ」の 像は大量生産されてドミニカ共和国中に建てられ、橋や公共施設には彼にちなんだ名前が付けられた。新聞は一面トップでトルヒーヨを称え、ナンバープレート には「¡Viva Trujillo!」「Año Del Benefactor De La Patria」(国家の恩人の年)などのスローガンが書かれていた。シウダード・トルヒーヨには電光掲示板が建てられ、昼だけでなく夜も「Dios y Trujillo」を見ることができるようになった。やがて教会でも「Dios en cielo, Trujillo en tierra」(天の神、地のトルヒーヨ)のスローガンを掲示することが義務づけられた。やがて、「地上の神、天上の神」と順番が逆転していく。トルヒー リョは、彼の崇拝者たちによってノーベル平和賞に推薦されたが、委員会はその提案を辞退した[23]。 トルヒーヨは1938年に再出馬の資格を得たが、大統領を2期務めた米国の例を引き合いに出し、「私は自発的に、国民の意向に反して、高位公職への再選を 拒否する」と表明した[24]。 「24] 実際、1937年半ばには精力的な再選運動が展開されていたが、同年末のハイチの大虐殺に伴う国際的な騒動により、トルヒーヨは「私生活への復帰」を表明 せざるを得なかった[25]。その結果、ドミニカ党はトルヒーヨが選んだ後継者の61歳の副大統領ハシント・ペイナドと候補者にマヌエル・デ・ヘス・トロ ンコソを指名した。1938年の選挙では、この二人が単独で投票用紙に載った。トルヒーヨは陸軍総司令官とドミニカ共和国党首の地位を維持した。ペイナド は傀儡にすぎず、トルヒーリョは依然として国家の全権を握っていると理解されていた。ペイナドは「Dios y Trujillo」という電光掲示板を大きくし、1940年3月7日に死去し、トロンコソが残りの任期を務めることになった。しかし、1942年、アメリ カではフランクリン・ルーズベルト大統領が3期目に出馬したため、トルヒーヨは再び大統領選に出馬し、無投票当選した。彼は2期務め、それぞれを5年に伸 ばした。1952年、米州機構からの圧力により、大統領の座を弟のエクトルに譲る。1955年、ラファエル・トルヒーヨは、公式には権力の座から降りてい たにもかかわらず、統治25周年を記念する大規模な国民的行事を組織した。彼の肖像が入った金銀の記念硬貨が鋳造された[要出典]。 |
| Oppression Brutal oppression of actual or perceived members of the opposition was the key feature of Trujillo's rule from the very beginning in 1930 when his gang, "The 42", led by Miguel Angel Paulino, drove through the streets in their red Packard "carro de la muerte" ("car of death").[26] Trujillo also maintained an execution list of people throughout the world who he felt were his direct enemies or who he felt had wronged him. He even once allowed an opposition party to form and permitted it to operate legally and openly, mainly so that he could identify those who opposed him and arrest or kill them.[27] Imprisonments and killings were later handled by the SIM, the Servicio de Inteligencia Militar, efficiently organized by Johnny Abbes, who operated in Cuba, Mexico, Guatemala, New York, Costa Rica, and Venezuela.[28] Some cases reached international notoriety such as the disappearance of Jesús de Galíndez and the murder of the Mirabal sisters, which further eroded Trujillo's critical support by the US government. After Trujillo approved an assassination attempt on the Venezuelan President Rómulo Ernesto Betancourt Bello, the Organization of American States and the United States blocked Trujillo's access to US sugar quota profits.[29] |
弾圧 1930年、ミゲル・アンヘル・パウリノ率いる彼のギャング「42」が赤いパッカード「死の車」で通りを走ったときから、反対派の実際のメンバーまたはそ う思われるメンバーに対する残忍な弾圧はトルヒーリョの支配の主要な特徴であった[26]。トルヒーリョはまた、自分の直接の敵または自分を裏切ったと感 じた世界中の人々の処刑リストを持っていました。彼はかつて野党の結成を許可し、合法的かつ公然と活動することを許可したが、それは主に彼に反対する人々 を特定し、逮捕または殺害するためであった[27]。 投獄と殺害は後に、キューバ、メキシコ、グアテマラ、ニューヨーク、コスタリカ、ベネズエラで活動するジョニー・アベスが効率的に組織したSIM(軍事情 報部)が担当した[28]。ヘスス・デ・ガリンスの失踪やミラバル姉妹の殺害など一部の事件は国際的に有名になり、アメリカ政府によるトルヒーヨの重要な 支持をさらに損ねた。トルヒーヨがベネズエラ大統領ロムロ・エルネスト・ベタンクール・ベロの暗殺未遂を認めた後、米州機構とアメリカはトルヒーヨのアメ リカ砂糖割り当て利益へのアクセスをブロックした[29]。 |
| Immigration Trujillo was known for his open-door policy, accepting Jewish refugees from Europe, Japanese migration during the 1930s, and exiles from Spain following its civil war. At the 1938 Évian Conference the Dominican Republic was the only country willing to accept many Jews and offered to accept up to 100,000 refugees on generous terms.[30] In 1940 an agreement was signed and Trujillo donated 26,000 acres (110 km2) of his properties for settlements. The first settlers arrived in May 1940; eventually, some 800 settlers came to Sosúa and most moved later on to the United States.[30] Refugees from Europe broadened the Dominican Republic's tax base and added more whites to the predominantly mixed-race nation. Trujillo’s government favored white refugees over others while Dominican troops expelled illegal immigrants, resulting in the 1937 Parsley Massacre of Haitian migrants.[citation needed] |
移民政策 トルヒーリョは、ヨーロッパからのユダヤ人難民、1930年代の日本人 移民、内戦後のスペインからの亡命者を受け入れるなど、門戸開放政策で知られた人物 である[30]。1938年のエヴィアン会議では、ドミニカ共和国が唯一多くのユダヤ人を受け入れ、最大10万人の難民を寛大な条件で受け入れると申し出 た[30]。 1940年に協定が結ばれ、トルヒーヨは26000エーカー(110km2)を入植地として寄贈することになった。最初の入植者は1940年5月に到着 し、最終的に約800人の入植者がソスーアにやってきて、そのほとんどが後にアメリカへ移住した[30]。 ヨーロッパからの難民はドミニカ共和国の課税基盤を拡大し、混血の多い国家に白人を増やした。トルヒーリョ政権は他の難民よりも白人を優遇し、ドミニカ軍 は不法移民を追放したため、1937年にハイチ人移民のパセリ虐殺事件が発生した[要出典]。 |
| Environmental policy The Trujillo regime greatly expanded the Vedado del Yaque, a nature reserve around the Yaque del Sur River. In 1934 he banned the slash-and-burn method of clearing land for agriculture, set up a forest warden agency to protect the park system, and banned the logging of pine trees without his permission. In the 1950s the Trujillo regime commissioned a study on the hydroelectric potential of damming the Dominican Republic's waterways. The commission concluded that only forested waterways could support hydroelectric dams, so Trujillo banned logging in potential river watersheds. After his assassination in 1961, logging resumed in the Dominican Republic. Squatters burned down the forests for agriculture, and logging companies clear-cut parks. In 1967, President Joaquín Balaguer launched military strikes against illegal logging.[22] Trujillo encouraged foreign investment in the Dominican Republic, particularly from Americans. He gave a concession with mineral rights in the Azua Basin to Clem S. Clarke, an oilman from Shreveport, Louisiana.[31] |
環境政策 トルヒーリョ政権は、ヤケ・デル・スル川周辺の自然保護区「ヤケの谷(Vedado del Yaque)」を大幅に拡張した。1934年には焼畑による農地開拓を禁止し、公園を保護するための森林監視局を設置し、許可なく松の木を伐採することを 禁じた。1950年代、トルヒーヨ政権はドミニカ共和国の水路にダムを建設し、水力発電の可能性を調査することを依頼した。その結果、森林に覆われた水路 のみが水力発電ダムを支えることができると結論づけられ、トルヒーリョは水路となりうる場所での伐採を禁止した。1961年にトルヒーヨが暗殺された後、 ドミニカ共和国では伐採が再開された。不法占拠者が農業のために森林を焼き払い、伐採業者が公園を切り開いた。1967年、ホアキン・バラグエル大統領は 違法伐採に対する軍事攻撃を開始した[22]。 トルヒーヨはドミニカ共和国への外国投資、特にアメリカからの投資を奨励した。彼はルイジアナ州シュリーブポート出身の石油業者クレム・S・クラークにア ズア盆地の鉱業権付き租界を与えた[31]。 |
| Foreign policy Trujillo tended toward peaceful coexistence with the United States government. During World War II, Trujillo symbolically sided with the Allies and declared war on Germany, Italy and Japan on 11 December 1941. While there was no military participation, the Dominican Republic thus became a founding member of the United Nations. Trujillo encouraged diplomatic and economic ties with the United States, but his policies often caused friction with other nations of Latin America, especially Costa Rica and Venezuela. He maintained friendly relations with Franco of Spain,[32] Perón of Argentina, and Somoza of Nicaragua. Towards the end of his rule, his relationship with the United States deteriorated. |
外交政策 トルヒーリョはアメリカ政府と平和的共存を志向した。第二次世界大戦中、トルヒーリョは象徴的に連合国側に付き、1941年12月11日にドイツ、イタリ ア、日本に対して宣戦布告を行った。軍事的な参加はなかったが、ドミニカ共和国は国際連合の創設メンバーになった。トルヒーリョはアメリカとの外交・経済 関係を重視したが、コスタリカやベネズエラをはじめとするラテンアメリカ諸国とはしばしば摩擦を引き起こした。スペインのフランコ、アルゼンチンのペロ ン、ニカラグアのソモサとは友好的な関係を保った[32]。統治末期には、アメリカとの関係が悪化した。 |
| Hull–Trujillo Treaty Early on, Trujillo determined that Dominican financial affairs had to be put in order, and that included ending the United States's role as collector of Dominican customs—a situation that had existed since 1907 and was confirmed in a 1924 convention signed at the end of the occupation. Negotiations started in 1936 and lasted four years. On 24 September 1940, Trujillo and the American Secretary of State Cordell Hull signed the Hull–Trujillo Treaty, whereby the United States relinquished control over the collection and application of customs revenues, and the Dominican Republic committed to deposit consolidated government revenues in a special bank account to guarantee repayment of foreign debt. The government was free to set custom duties with no restrictions.[33] This diplomatic success gave Trujillo the occasion to launch a massive propaganda campaign that presented him as the savior of the nation. A law proclaimed that the Benefactor was also now the Restaurador de la independencia financiera de la Republica (Restorer of the Republic's financial independence).[34] |
ハル=トルヒーリョ条約 トルヒーリョは早くからドミニカの財政問題を整理する必要があると考え、1907年から続いていたドミニカの税関の徴収者としての米国の役割を終了させる ことを含め、占領末期の1924年に締結された条約で確認されたものである。 交渉は1936年に開始され、4年間続いた。1940年9月24日、トルヒーヨとアメリカのコーデル・ハル国務長官はハル・トルヒーヨ条約を締結し、アメ リカは関税収入の徴収と使用に関する統制を放棄し、ドミニカ共和国は政府の統合収入を対外債務の返済を保証するための特別銀行口座に預金することを約束し た。政府は何の制限もなく自由に関税を設定することができた[33]。 この外交的成功は、トルヒーリョを国家の救世主として紹介する大規模なプロパガンダキャンペーンを開始する機会を与えた。法律は、恩人が今や Restaurador de la independencia financiera de la Republica(共和国の財政的独立の回復者)でもあることを宣言した[34]。 |
| Haiti Haiti had historically occupied what is now the Dominican Republic from 1822 to 1844. Encroachment by Haiti was an ongoing process, and when Trujillo took over, specifically the northwestern border region had become increasingly "Haitianized".[35] The border was poorly defined. In 1933, and again in 1935, Trujillo met the Haitian President Sténio Vincent to settle the border issue. By 1936, they reached and signed a settlement. At the same time, Trujillo plotted against the Haitian government by linking up with General Calixte, Commander of the Garde d'Haiti, and Élie Lescot, at that time the Haitian ambassador in Ciudad Trujillo (Santo Domingo).[35] After the settlement, when further border incursions occurred, Trujillo initiated the Parsley Massacre. |
ハイチ ハイチは1822年から1844年まで現在のドミニカ共和国を歴史的に占領していた。ハイチによる侵攻は継続的なものであり、トルヒーリョが政権を取った とき、特に北西部の国境地帯はますます「ハイチ化」していた[35]。1933年、そして1935年、トルヒーヨは国境問題を解決するためにハイチ大統領 ステニオ・ヴィンセントと会談した。1936年までに和解に至り、調印した。同時にトルヒーヨはハイチ軍司令官カリクテ将軍や当時シウダー・トルヒーヨ (サント・ドミンゴ)のハイチ大使エリー・レスコと連携し、ハイチ政府への攻撃を企てた[35]。 和解後、さらなる国境の侵犯が起こるとトルヒーヨはパセリの虐殺を開始した。 |
| Parsley massacre Known as La Masacre del Perejil in Spanish, the massacre was started by Trujillo in 1937. Claiming that Haiti was harboring his former Dominican opponents, he ordered an attack on the border that slaughtered tens of thousands of Haitians as they tried to escape. The number of dead is still unknown, but it is now calculated between 12,000 and 30,000.[36][Note 4][Note 5][Note 6] The Dominican military used machetes to murder and decapitate many of the victims; they also took people to the port of Montecristi, where many victims were thrown into the sea to drown with their hands and feet bound.[40] The Haitian response was muted, but its government eventually called for an international investigation. Under pressure from Washington, Trujillo agreed to a reparation settlement in January 1938 of US$750,000. By the next year, the amount had been reduced to US$525,000 (US$9.9 million in 2023); 30 dollars per victim, of which only two cents were given to survivors because of corruption in the Haitian bureaucracy.[24][41] In 1941, Lescot, who had received financial support from Trujillo, succeeded Vincent as President of Haiti. Trujillo expected that Lescot would be his puppet, but Lescot turned against him. Trujillo unsuccessfully tried to assassinate him in a 1944 plot and then published their correspondence to discredit him.[35] Lescot fled into exile in 1946 after demonstrations against him.[42] |
パセリの大虐殺 スペイン語でLa Masacre del Perejilと呼ばれるこの大虐殺は、1937年にトルヒーヨによって始められた。ハイチがかつてのドミニカの敵対勢力をかくまっていると主張し、国境 への攻撃を命じ、脱出しようとした数万人のハイチ人を虐殺したのである。死者の数はまだ不明だが、現在では12,000人から30,000人と計算されて いる[36][注釈 4][注釈 5][注釈 6] ドミニカ軍は多くの犠牲者を鉈で殺害し首を切った。また彼らは人々をモンテクリスティ港に運び、多くの犠牲者は手足を縛られて海に投げ込まれ溺れさせた [40]。 ハイチの反応は鈍かったが、その政府は最終的に国際的な調査を要求した。ワシントンからの圧力により、トルヒーヨは1938年1月に75万米ドルの賠償金 に合意した。翌年までにその額は52万5000米ドル(2023年には990万米ドル)に減額された。犠牲者一人当たり30ドルで、ハイチ官僚の腐敗のた めに、そのうち生存者には2セントしか与えられなかった[24][41]。 1941年、トルヒーヨから資金援助を受けていたレスコットがヴィンセントの後を継いでハイチ大統領に就任した。トルヒーヨはレスコットが自分の傀儡にな ることを期待したが、レスコットはトルヒーヨに反旗を翻した。1944年にトルヒーヨが暗殺を企てたが失敗し、その後、彼の信用を落とすために二人の書簡 を公開した[35]。 1946年、レスコは反対デモの後、亡命した[42]。 |
| Cuba In 1947, Dominican exiles, including Juan Bosch, had concentrated in Cuba. With the approval and support of Cuba's government, led by Ramón Grau, an expeditionary force was trained with the intention of invading the Dominican Republic and overthrowing Trujillo. However, international pressure, including from the United States, made the exiles abort the expedition.[43] In turn, when Fulgencio Batista was in power, Trujillo initially supported anti-Batista supporters of Carlos Prío Socarrás in Oriente Province in 1955; however, weapons Trujillo sent were soon inherited by Fidel Castro's insurgents when Prío allied with Castro; Dominican-made Cristóbal carbines and hand grenades became the rebels' standard weapons. After 1956, when Trujillo saw that Castro was gaining ground, he started to support Batista with money, planes, equipment, and men. Trujillo, convinced that Batista would prevail, was very surprised when Batista showed up as a fugitive after he had been ousted. Trujillo kept Batista until August 1959 as a "virtual prisoner".[44] Only after paying US$3–4 million could Batista leave for Portugal, which had granted him a visa.[44] Castro made threats to overthrow Trujillo, and Trujillo responded by increasing the budget for national defense. A foreign legion was formed to defend Haiti, as it was expected that Castro might invade the Haitian part of the island first and remove François Duvalier as well. A Cuban plane with 56 fighting men landed near Constanza, Dominican Republic, on Sunday, 14 June 1959, and six days later more invaders brought by two yachts landed at the north coast. However, the Dominican Army prevailed.[44] In turn, in August 1959, Johnny Abbes attempted to support an anti-Castro group led by Escambray near Trinidad, Cuba. The attempt, however, was thwarted when Cuban troops surprised a plane he had sent when it was unloading its cargo.[45] |
キューバ 1947年、フアン・ボッシュを含むドミニカ共和国の亡命者がキューバに集結していた。ラモン・グラウ率いるキューバ政府の承認と支援のもと、ドミニカ共 和国に侵攻しトルヒーリョを打倒するための遠征隊が編成された[43]。しかし、アメリカなどの国際的圧力により遠征は中止された[43]。一方、フルヘ ンシオ・バティスタが政権を握っていた1955年、トルヒーリョは当初オリエンテ州のカルロス・プリオ・ソカラを反バティスタ支持者として支援したが、プ リオはカストロと同盟し、トルヒーリョが送った武器をフィデル・カストロの反乱軍がすぐに受け継ぎ、ドミニカ製のクリストーバル銃と手りゅう弾は反乱軍が 標準装備した武器となった。 1956年以降、カストロの台頭を見たトルヒーリョは、資金、飛行機、装備、人員などでバティスタを支援するようになる。バチスタが勝つと確信していたト ルヒーリョは、追放されたバチスタが逃亡者として現れたとき、非常に驚いた。トルヒーヨはバティスタを1959年8月まで「仮想囚人」として拘束した [44]。 300万〜400万米ドルを支払った後でのみ、バティスタはビザを与えていたポルトガルへ出国することができた[44]。 カストロはトルヒーリョを打倒すると脅迫し、トルヒーリョは国防予算を増額して対応した。カストロが先にハイチへ侵攻し、フランソワ・デュバリエも排除す ることが予想されたため、ハイチを防衛するために外国人部隊を編成した。1959年6月14日(日)、56人の戦闘員を乗せたキューバ機がドミニカ共和国 のコンスタンツァ付近に着陸し、その6日後には2隻のヨットが運んできたさらなる侵略者が北海岸に上陸した。しかし、ドミニカ軍が勝利した[44]。 翻って1959年8月、ジョニー・アベスはキューバのトリニダッド付近でエスカンブレイが率いる反カストロ派を支援しようとした。しかし、この試みは、彼 が送った飛行機が荷物を降ろしている時にキューバ軍が奇襲したため、阻止された[45]。 |
| Assassination
attempt of Rómulo Betancourt. By the late 1950s, opposition to Trujillo's regime was starting to build to a fever pitch, especially among a younger generation who had no memory of the poverty and instability that had preceded the dictatorship. Many clamored for democratization. The Trujillo regime responded with greater repression. The Military Intelligence Service (SIM) secret police, led by Johnny Abbes, remained as ubiquitous as before. Other nations ostracized the Dominican Republic, compounding the dictator's paranoia. Trujillo began to interfere more and more in the domestic affairs of neighboring countries. He expressed great contempt for Venezuela's president Rómulo Betancourt; an established and outspoken opponent of Trujillo, Betancourt associated with Dominicans who had plotted against the dictator. Trujillo developed an obsessive personal hatred of Betancourt and supported numerous plots by Venezuelan exiles to overthrow him. This pattern of intervention led the Venezuelan government to take its case against Trujillo to the Organization of American States (OAS), a move that infuriated Trujillo, who ordered his agents to plant a bomb in Betancourt's car. The assassination attempt, carried out on Friday, 24 June 1960, injured but did not kill the Venezuelan president. The Betancourt incident inflamed world opinion against Trujillo. Outraged OAS members voted unanimously to sever diplomatic relations with his government and impose economic sanctions on the Dominican Republic. The brutal murder on Friday, 25 November 1960, of the three Mirabal sisters, Patria, María Teresa and Minerva, who opposed Trujillo's dictatorship, further increased discontent with his repressive rule. The dictator had become an embarrassment to the United States, and relations became especially strained after the Betancourt incident. |
ロムロ・ベタンクール暗殺未遂事件 1950年代後半になると、トルヒーヨ政権への反発は、独裁政権以前の貧困や不安定さを知らない若い世代を中心に、熱を帯び始める。特に、独裁以前の貧困 や不安定さを知らない若い世代が、民主化を強く望んでいた。これに対し、トルヒーリョ政権は弾圧を強めた。ジョニー・アベスが率いる秘密警察SIMは、以 前と同じようにどこにでもいるような状態であった。他国はドミニカ共和国を排斥し、独裁者のパラノイアをさらに強めた。 トルヒーヨは、近隣諸国の内政に干渉するようになった。ベネズエラ大統領ロムロ・ベタンクールは、トルヒーリョの敵として知られ、独裁者に謀反を企てたド ミニカ人と関わりを持っていたため、非常に軽蔑していた。トルヒーリョはベタンコールを執拗に憎悪し、ベネズエラ人亡命者による打倒計画を何度も支援し た。このような介入により、ベネズエラ政府は米州機構(OAS)にトルヒーヨを提訴し、トルヒーヨは激怒し、ベタンクールの車に爆弾を仕掛けるよう工作員 に命じた。1960年6月24日(金)に行われたこの暗殺未遂は、ベネズエラ大統領を負傷させたが、死亡には至らなかった。 このベタンクール事件は、トルヒーリョに対する世界の世論を煽った。憤慨したOAS加盟国は、全会一致で彼の政府との外交関係を断絶し、ドミニカ共和国に 経済制裁を科すことを決定した。1960年11月25日金曜日、トルヒーヨの独裁に反対したミラバル三姉妹、パトリア、マリアテレサ、ミネルバが残忍にも 殺害され、彼の圧政に対する不満がさらに高まった。この独裁者はアメリカにとって厄介な存在となり、特にベタンクール事件以降、関係が緊迫化した。 |
| Personal life Trujillo's "central arch" was his instinct for power.[46] This was coupled with an intense desire for money, which he recognized as a source of and support for power. Up at four in the morning, he exercised, studied the newspaper, read many reports, and completed papers before breakfast. At the office by nine, he continued his work, and took lunch by noon. After a walk, he continued to work until 7:30 pm. After dinner, he attended functions, held discussions, or was driven around incognito in the city "observing and remembering."[46] Until Santo Domingo's National Palace was built in 1947, he worked out of the Casas Reales, the colonial-era Viceregal center of administration. Today the building is a museum; on display are his desk and chair, along with a massive collection of arms and armor that he bought. He was methodical, punctual, secretive, and guarded; he had no true friends, only associates and acquaintances. For his associates, his actions towards them were unpredictable.[citation needed] Trujillo and his family amassed enormous wealth. He acquired cattle lands on a grand scale, and went into meat and milk production, operations that soon evolved into monopolies. Salt, sugar, tobacco, lumber, and the lottery were other industries which he or his family members dominated. Family members also received positions within the government and the army, including one of Trujillo's sons who was made a colonel in the Dominican Army when he was only four years old.[Note 7][Note 8] Two of Trujillo's brothers, Héctor and José Arismendy, also held positions in his government. José Arismendy Trujillo oversaw the creation of the main radio station, La Voz Dominicana, and later the television station, the fourth in the Caribbean.[citation needed] By 1937 Trujillo's annual income was about $1.5 million ($28 million in 2021);[48] at the time of his death the state took over 111 Trujillo-owned companies. His love of fine and ostentatious clothing was displayed in elaborate uniforms and suits, of which he collected almost two thousand.[49] Fond of neckties, he amassed a collection of over ten thousand. Trujillo doused himself with perfume and liked gossip.[50] His sexual appetite was rapacious, and he preferred mulatto women with full bodies. Trujillo was married three times and kept other women as mistresses. On 13 August 1913, Trujillo married Aminta Ledesma Lachapelle, with whom he had 2 daughters, Julia, who died as an infant, and Flor de Oro, who died of lung cancer in 1978. On 30 March 1927, Trujillo married Bienvenida Ricardo Martínez, a girl from Monte Cristi and the daughter of Buenaventura Ricardo Heureaux. A year later he met María de los Angeles Martínez Alba (nicknamed "la españolita", or "the little Spanish girl"), and had an affair with her. He divorced Bienvenida in 1935 and married Martínez. A year later he had a daughter with Bienvenida, named Odette Trujillo Ricardo.[citation needed] Trujillo's three children with María Martínez were Rafael Leónidas Ramfis, who was born on 5 June 1929, María de los Ángeles del Sagrado Corazón de Jesús (Angelita), born in Paris on 10 June 1939, and Leónidas Rhadamés, born on 1 December 1942. Ramfis and Rhadamés were named after characters in Giuseppe Verdi's opera Aida.[citation needed] In 1937, Trujillo met Lina Lovatón Pittaluga,[51] an upper-class debutante with whom he had two children, Yolanda in 1939, and Rafael, born on 20 June 1943.[citation needed] In spite of Trujillo's indifference to the game of baseball, the dictator invited many black American players to the Dominican Republic, where they received good pay for playing on first-class, un-segregated teams. The great Negro league star Satchel Paige pitched for Los Dragones of Ciudad Trujillo, a team organized by Trujillo. Paige later claimed, jokingly, that his guards positioned themselves "like a firing squad" to encourage him to pitch well. Los Dragones won the 1937 Dominican championship at Estadio Trujillo in Ciudad Trujillo.[52] Trujillo was energetic and fit. He was generally quite healthy but suffered from chronic lower urinary infections and, later, prostate problems. In 1934, Dr. Georges Marion was called from Paris to perform three urologic procedures on Trujillo.[53] Over time Trujillo acquired numerous homes. His favorite was Casa Caobas, on Estancia Fundacion near San Cristóbal.[54] He also used Estancia Ramfis (which, after 1953, became the Foreign Office), Estancia Rhadames, and a home at Playa de Najayo. Less frequently he stayed at places he owned in Santiago de los Caballeros, Constanza, La Cumbre, San José de las Matas, and elsewhere. He maintained a penthouse at the Embajador Hotel in the capital.[55] While Trujillo was nominally a Roman Catholic, his devotion was limited to a perfunctory role in public affairs; he placed faith in local folk religion.[46] He was popularly known as "El Jefe" ("The Chief") or "El Benefactor" ("The Benefactor") but was privately referred to as Chapitas ("Bottlecaps") because of his indiscriminate wearing of medals. Dominican children emulated Trujillo by constructing toy medals from bottle caps. He was also known as "El Chivo" ("The Goat"). |
個人生活 トルヒーリョの「中心的アーチ」は権力への本能であった[46]。 これは金銭への強い欲求と結びついており、彼はそれを権力の源であり支えであると認識していた。朝4時に起床し、運動し、新聞を読み、多くのレポートを読 み、朝食前に論文を完成させた。9時には出社して、仕事を続け、昼には昼食をとる。散歩をした後、午後7時半まで仕事をする。1947年にサント・ドミン ゴの国立宮殿が建設されるまでは、植民地時代の副王庁であるカサス・レアレスで仕事をした。現在、この建物は博物館となっており、彼の机と椅子、そして彼 が購入した大量の武器と鎧のコレクションが展示されている。几帳面で、時間に正確で、秘密主義で、警戒心が強く、真の友人はおらず、友人と知人だけであっ た。また、彼の仲間にとって、彼らに対する彼の行動は予測不可能であった[citation needed]。 トルヒーヨとその一族は莫大な富を築き上げた。トルヒーヨとその一族は莫大な富を築き、大規模な畜産業の買収、食肉や牛乳の生産、独占的な事業へと発展し ていった。塩、砂糖、タバコ、木材、宝くじなども彼やその一族が支配した産業である。トルヒーヨの息子の1人は、わずか4歳でドミニカ軍の大佐になった [注釈 7][注釈 8]。トルヒーヨの2人の兄弟、エクトルとホセ・アリスメンディも政府で役職に就いていた。ホセ・アリスメンディ・トルヒーヨは主要なラジオ局であるラ・ ボス・ドミニカナの設立を監督し、後にカリブ海で4番目となるテレビ局を設立した[要出典]。 1937年までのトルヒーヨの年収は約150万ドル(2021年には2800万ドル)であった[48] 。高級で派手な服装を好み、凝った制服やスーツを2,000着近く集めた[49]。トルヒーリョは香水をつけ、ゴシップを好んだ[50]。性欲は旺盛で、 豊満な体のマルチーズの女性を好んだ。 トルヒーヨは3回結婚し、他の女性も愛人にしていた。1913年8月13日、アミンタ・レデスマ・ラチャペルと結婚し、ジュリア(幼児で死亡)とフロー ル・デ・オロ(1978年に肺癌で死亡)の2人の娘をもうけた。1927年3月30日、トルヒーヨは、モンテ・クリスティ出身でブエナベンチュラ・リカル ド・ヒューロックスの娘であるビエンベニダ・リカルド・マルティネスと結婚する。1年後、彼はマリア・デ・ロス・アンヘレス・マルティネス・アルバ(愛称 「ラ・エスパニョリータ」、「小さなスペイン娘」)と出会い、彼女と関係を持つようになった。1935年、ビエンベニダと離婚し、マルティネスと結婚し た。1年後、ビエンベニダとの間にオデット・トルヒーヨ・リカルドと名付けられた娘をもうけた[要出典]。 マリア・マルティネスとの間に生まれた3人の子供は、1929年6月5日に生まれたラファエル・レオニダス・ラムフィス、1939年6月10日にパリで生 まれたマリア・デ・ロス・アンヘレス・デル・サグラード・コラソン・デ・ヘスス(アンジェリータ)、1942年12月1日に生まれたレオニダス・ラダメス である。ラムフィスとラダメスはジュゼッペ・ヴェルディのオペラ『アイーダ』の登場人物にちなんで名付けられた[citation needed]。 1937年、トルヒーヨは上流階級出身のリナ・ロバトン・ピッタルガと出会い[51]、1939年にヨランダ、1943年6月20日にラファエルという2 人の子供をもうけた[citation needed]。 トルヒーヨは野球に無関心であったが、独裁者は多くのアメリカの黒人選手をドミニカ共和国に招待し、彼らは差別のない一流のチームでプレーすることで高い 報酬を得ていた。ニグロリーグの大スター、サチェル・ペイジは、トルヒーヨが組織したロス・ドラゴネス・オブ・シウダ・トルヒーヨでピッチャーを務めた。 ペイジ氏は後に、護衛が「銃殺隊のように」配置され、好投を促したと冗談交じりに語っている。ロス・ドラゴネスはシウダー・トルヒーヨのエスタディオ・ト ルヒーヨで1937年にドミニカ選手権を制した[52]。 トルヒーヨはエネルギッシュで健康な人だった。健康そのものであったが、慢性的な下部尿路感染症に悩まされ、後に前立腺にも問題が生じた。1934年、 ジョルジュ・マリオン医師がパリから呼ばれ、トルヒーリョに3つの泌尿器科手術を施した[53]。 やがてトルヒーヨは多くの邸宅を手に入れた。また、エスタンシア・ラムフィス(1953年以降、外務省になる)、エスタンシア・ラダメス、プラヤ・デ・ナ ジャヨの家も使われた。サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロス、コンスタンツァ、ラ・クンブレ、サン・ホセ・デ・ラス・マタスなどに所有する場所に滞在す ることは少なかったが、サン・ホセ・デ・ラス・マタスにはペントハウスがあった。首都のエンバハドルホテルのペントハウスを維持していた[55]。 トルヒーリョは名目上ローマ・カトリック教徒であったが、その信仰は公務での形式的な役割に限られ、地元の民間宗教に信頼を置いていた[46]。 一般には「エル・ヘフェ」(「首長」)または「エル・ベネファクター」(「恩人」)として知られていたが、無差別にメダルを身につけることから、プライ ベートでは「チャピタス」(「ボトルキャップ」)と呼ばれていた。ドミニカの子供たちは、ボトルキャップでおもちゃのメダルを作ってトルヒーヨを見習っ た。また、「エル・チボ」(「山羊」)とも呼ばれた。 |
| Assassination On Tuesday, 30 May 1961, Trujillo was shot and killed when his blue 1957 Chevrolet Bel Air was ambushed on a road outside the Dominican capital.[56] He was the victim of an ambush plotted by a number of men, such as General Juan Tomás Díaz, Pedro Livio Cedeño, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero and General Antonio Imbert Barrera.[57] The plotters, however, failed to take control as the later-executed General José René Román Fernandez ("Pupo Román") betrayed his co-conspirators by his inactivity, and contingency plans had not been made.[58] On the other side, Johnny Abbes, Roberto Figueroa Carrión, and the Trujillo family put the SIM to work to hunt the members of the plot and brought back Ramfis Trujillo from Paris to step into his father's shoes. The response by the SIM was swift and brutal. Hundreds of suspects were detained, many tortured. On 18 November the last executions took place when six of the conspirators were executed in the "Hacienda María Massacre".[59] Imbert was the only one of the seven assassins who survived the manhunt.[60] A co-conspirator named Luis Amiama Tio also survived.[citation needed] US President John F. Kennedy learned of Trujillo's death during a diplomatic meeting with French President Charles de Gaulle.[61] Trujillo's funeral was that of a statesman with the long procession ending in his hometown of San Cristóbal, where his body was first buried. Dominican President Joaquín Balaguer gave the eulogy. The efforts of the Trujillo family to keep control of the country ultimately failed. The military uprising on 19 November of the Rebellion of the Pilots and the threat of US intervention set the final stage and ended the Trujillo regime.[62] Ramfis tried to flee with his father's body aboard his boat Angelita, but was turned back. Balaguer allowed Ramfis to leave the country and to take his father's body to Paris. There, the remains were interred in the Cimetière du Père Lachaise on 14 August 1964, and six years later moved to Spain, to the Mingorrubio Cemetery in El Pardo on the north side of Madrid.[63] The role of the CIA in the killing has been debated. Imbert insisted that the plotters acted on their own.[60] However, Trujillo was certainly murdered with weapons supplied by the CIA.[64][60][65] In a 1975 report to the Deputy Attorney General of the United States, CIA officials described the agency as having "no active part" in the assassination and only a "faint connection" with the groups that planned the killing.[66] US involvement appears to go deeper than supplying weapons. In the 1950s, the CIA gave José Figueres Ferrer money to publish a political journal, Combate and to found a left-wing school for Latin American opposition leaders.[67] Funds passed from a shell foundation to the Jacob Merrill Kaplan Fund; then to the Institute of International Labor Research (IILR) headed by Norman Thomas, six-time US presidential candidate for the Socialist Party of America; and finally to Figueres, Sacha Volman, and Juan Bosch.[68][67][65] Sacha Volman, treasurer of the IILR, was a CIA agent.[67] Cord Meyer was a CIA official responsible for manipulating international groups.[67] He used the contacts with Bosch, Volman, and Figueres for a new purpose, as the United States moved to rally the Western Hemisphere against Cuba's Fidel Castro, Trujillo had become expendable.[67] Dissidents inside the Dominican Republic argued that assassination was the only certain way to remove Trujillo.[67] According to Chester Bowles, the Undersecretary of State, internal Department of State discussions in 1961 on the topic were vigorous.[69] Richard N. Goodwin, Assistant Special Counsel to the President, who had direct contacts with the rebel alliance, argued for intervention against Trujillo.[69] Quoting Bowles directly: The next morning I learned that in spite of the clear decision against having the dissident group request our assistance Dick Goodwin following the meeting sent a cable to CIA people in the Dominican Republic without checking with State or CIA; indeed, with the protest of the Department of State. The cable directed the CIA people in the Dominican Republic to get this request at any cost. When Allen Dulles found this out the next morning, he withdrew the order. We later discovered it had already been carried out.[69] An internal CIA memorandum states that a 1973 Office of Inspector General investigation into the murder disclosed "quite extensive Agency involvement with the plotters." The CIA described its role in "changing" the government of the Dominican Republic "as a 'success' in that it assisted in moving the Dominican Republic from a totalitarian dictatorship to a Western-style democracy."[70][67] Juan Bosch, the earlier recipient of CIA funding, was elected president of the Dominican Republic in 1962 and was deposed in 1963.[68] Even after the death of Trujillo, the unusual events continued. In November 1961, Mexican police found a corpse they identified as Luis Melchior Vidal, Jr., godson of Trujillo.[65] Vidal was the unofficial business agent of the Dominican Republic while Trujillo was in power.[65] Under the cover of the American Sucrose Company and the Paint Company of America, Vidal had teamed up with an American, Joel David Kaplan, to operate as arms merchants for the CIA.[65] Joel David Kaplan was the nephew of the previously mentioned Jacob Merrill Kaplan.[71] The older Kaplan earned his fortune primarily through operations in Cuba and the Dominican Republic. In 1962, the younger Kaplan was convicted of killing Vidal, in Mexico City.[65] He was sentenced to 28 years in prison.[65] Kaplan escaped from a Mexican prison using a helicopter. The dramatic event was the basis for the Charles Bronson action film Breakout.[72][73] The Mexican police requested for the FBI to arrest and remand Joel Kaplan on 20 August 1971.[65] Kaplan's attorney claimed that Kaplan was a CIA agent.[65] Neither the FBI nor the US Department of Justice has pursued the issue.[65] The Mexican government never initiated extradition proceedings against Kaplan.[73] |
暗殺 1961年5月30日火曜日、トルヒーヨはドミニカの首都郊外の道路で1957年製の青いシボレー・ベルエアが待ち伏せされ、撃たれて死んだ[56]。彼 はフアン・トマス・ディアス将軍、ペドロ・リビオ・セデーニョ、アントニオ・デ・ラ・マザ、アマド・ガルシア・ゲレロおよびアントニオ・インベルト・バレ ラ将軍など、多くの人物により計画された待ち伏せ事件の犠牲者であった。 [しかし、後に処刑されたホセ・レネ・ロマンフェルナンデス将軍(「プポ・ロマン」)が無為無策で共謀者を裏切ったことや、不測の事態への対策がなされて いなかったことから、謀議者は主導権を握れなかった[58]。一方、ジョニー・アベス、ロベルト・フィゲロア・カリオン、トルヒーヨ一家は、謀議のメン バーを追うために SIM を働かせ、ラムフィス・トラヒーヨが父親の後任としてパリから連れ戻されてきた。SIMの対応は迅速かつ残忍であった。何百人もの容疑者が拘束され、その 多くが拷問を受けた。11月18日、最後の処刑が行われ、6人の共謀者が「ハシエンダ・マリアの虐殺」で処刑された[59] インベールは7人の暗殺者の中で唯一、捜索から生き残った。 ルイス・アミア・ティオという共謀者も生き残った[60][要出典]。 アメリカのジョン・F・ケネディ大統領は、フランスのシャルル・ド・ゴール大統領との外交会談でトルヒーヨの死を知った[61]。 トルヒーヨの葬儀は政治家のものであり、長い行列は彼の故郷であるサン・クリストバルで終わり、彼の遺体はそこに最初に埋葬された。ドミニカ共和国大統領 ホアキン・バラゲルが弔辞を述べた。トルヒーリョ一族による国の支配を維持するための努力は、最終的に失敗に終わった。11月19日の「操縦士たちの反 乱」による軍の反乱とアメリカの介入の脅威が最終段階となり、トルヒーリョ政権を終わらせた[62]。 ラムフィスは父の遺体とともに船アンヘリータに乗って逃げようとしたが、追い返された。バラゲールは、ラムフィスが国を出ることを許可し、父の遺体をパリ に運ぶことを許可した。そこで遺体は1964年8月14日にペール・ラシェーズ墓地に埋葬され、6年後にスペインに移り、マドリード北側のエルパルドにあ るミンゴルビオ墓地に移された[63]。 この殺害におけるCIAの役割については議論がなされてきた。インベールは計画者が独自に行動したと主張した[60]が、トルヒーヨはCIAから供給され た武器で殺害されたことは確かである[64][60][65]。 1975年の米国司法省副長官への報告書において、CIA職員は、暗殺において「積極的な役割はなく」、殺害を計画したグループとは「かすかなつながり」 しかなかったと述べている[66]。 アメリカの関与は武器の供給よりも深いようである。1950年代、CIAはホセ・フィゲレス・フェレールに政治雑誌『コンバテ』の出版とラテンアメリカの 野党指導者のための左翼学校を見つけるための資金を与えた[67]。 67] 資金はシェル財団からジェイコブ・メリル・カプラン基金に渡り、次にアメリカ社会党の大統領候補として6度選出されたノーマン・トーマスが率いる国際労働 研究所(IILR)に渡り、最後にフィゲレス、サシャ・ヴォルマン、フアン・ボスに渡った[68][67][65] IILRの会計係であるサシャ・ヴォルマンはCIAエージェントだった[67][65]。 コード・マイヤーは国際的なグループの操作を担当するCIA職員だった[67]。 彼はボッシュ、ボルマン、フィゲレスとの接触を新しい目的のために使った。アメリカがキューバのフィデル・カストロに対して西半球を結集しようと動いてお り、トルヒーヨは消耗品になっていた[67] ドミニカ共和国内のディシデント達は暗殺だけがトルヒーヨを取り除く確かな方法だと主張した[67]...。 国務次官であるチェスター・ボウルズによれば、1961年のこのテーマに関する国務省内部の議論は活発であった[69]。反乱同盟と直接接触していた大統 領特別顧問補佐官のリチャード・N・グッドウィンは、トルヒーヨに対する介入を主張していた[69]。 ボウルズの言葉を直接引用する。翌朝、反体制派に我々の援助を要請させないという明確な決定にもかかわらず、ディック・グッドウィンは会議の後、国務省や CIAに確認することなく、ドミニカ共和国のCIA職員に電報を送ったことが分かった。その電報は、ドミニカ共和国にいるCIA職員に、この要請を何とし てでも勝ち取るよう指示した。翌朝これを見つけたアレン・ダレスは、その命令を撤回しました。後に、それがすでに実行されていたことがわかった[69]。 CIAの内部メモによると、1973年の監察官室による殺人事件の調査で、「計画者たちに対するかなり広範なCIAの関与」が明らかにされたとのことであ る。CIAはドミニカ共和国の政府を「変える」役割を「ドミニカ共和国を全体主義の独裁国家から西洋スタイルの民主国家に移行させることを支援したという 点で『成功』であった」と述べている[70][67]。 先にCIAの資金提供を受けたフアン・ボスは、1962年にドミニカ共和国の大統領に選出され、1963年に退陣させられている[68]。 トルヒーヨの死後も、異常な出来事は続いていた。1961年11月、メキシコの警察はトルヒーヨの名付け子であるルイス・メルチョール・ビダル・ジュニア と確認した死体を見つけた[65]。 ビダルはトルヒーヨが政権を握っていた間、ドミニカ共和国の非公式のビジネスエージェントだった[65] アメリカのスクロース社とアメリカのペイント社を隠れ蓑に、ビダルはアメリカ人のジョエル・デヴィッド・カプランと組み、CIA向けの兵器商として営業を 行っていた[65]. ジョエル・デイヴィッド・カプランは、先に述べたジェイコブ・メリル・カプランの甥であった[71]。年長のカプランは、主にキューバとドミニカ共和国で の事業を通して財産を得ていた。 1962年、若いカプランは、メキシコシティで、ビダルを殺害した罪で有罪判決を受けた[65]。 彼は28年の懲役を言い渡された[65]。カプランはヘリコプターを使ってメキシコの刑務所から脱走した。この劇的な出来事は、チャールズ・ブロンソンの アクション映画『ブレイクアウト』の元ネタとなった[72][73]。 メキシコ警察は1971年8月20日にFBIにジョエル・カプランを逮捕・拘束するよう要請した[65]。カプランの弁護士はカプランがCIAのエージェ ントであると主張した[65]。 FBIもアメリカ司法省もこの問題を追求していない[65]。メキシコ政府はカプランに対して引き渡し手続きを開始することはなかった[73]。 |
| General bibliography Block, Maxine (1941). E. Mary Trow (ed.). Current Biography Who's News and Why. The H. W. Wilson Company. ISBN 978-9997376671. Capdevilla, Lauro (1998). La dictature de Trujillo, République dominicaine, 1930–1961. Paris; Montreal: L'Harmattan. Crassweller, Robert D. (1966). The Life and Times of a Caribbean Dictator. New York: The Macmillan Company. de Galindez, Jésus (1962) [1956]. L'Ère de Trujillo. Paris: Gallimard. Diamond, Jared (2005). Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. Penguin (Non-Classics). ISBN 978-0143036555. Diederich, Bernard (1978). Trujillo, The Death of the Goat. Little, Brown, and Co. ISBN 978-0316184403. Pack, Robert; Parini, Jay (1997). Introspections. University Press of New England. ISBN 978-0874517736. Roorda, Eric (1998). The dictator next door : the good neighbor policy and the Trujillo regime in the Dominican Republic, 1930–1945. Durham: Duke University Press. ISBN 978-0822321231. |
一般書誌 Block, Maxine (1941). E. Mary Trow (ed.). Current Biography Who's News and Why. H. W. Wilson Company. ISBN 978-9997376671. Capdevilla, Lauro (1998). La dictature de Trujillo, République dominicaine, 1930-1961. Paris; Montreal: L'Harmattan. Crassweller, Robert D. (1966). The Life and Times of a Caribbean Dictator. New York: The Macmillan Company. de Galindez, Jésus (1962) [1956]. L'Ère de Trujillo. Paris: Gallimard. Diamond, Jared (2005). 崩壊: How Societies Choose to Fail or Succeed. Penguin (Non-Classics). ISBN 978-0143036555. Diederich, Bernard (1978). Trujillo, The Death of the Goat. リトル・ブラウン社。ISBN 978-0316184403. Pack, Robert; Parini, Jay (1997). Introspections. ニューイングランド大学出版局。ISBN 978-0874517736. Roorda, Eric (1998). The dictator next door : the good neighbor policy and the Trujillo regime in the Dominican Republic, 1930-1945. Durham: Durham: Duke University Press. ISBN 978-0822321231. |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Rafael_Trujillo |
https://www.deepl.com/ja/translator |
●La fiesta del Chivo (novela) por
Mario Vargas Llosa
| La fiesta del Chivo
es una novela publicada en el año 2000 del escritor peruano-español
Mario Vargas Llosa. El libro tiene lugar en República Dominicana y se
centra en el asesinato del dictador Rafael Trujillo, y los hechos
posteriores, desde dos puntos de vista con una diferencia generacional:
durante la planificación y después del asesinato en sí mismo, en mayo
de 1961; y treinta y cinco años después, en 1996. A través de la
historia, se encuentra una intensa reflexión del apogeo de la
dictadura, en los años 1950, y su significado para la isla y sus
habitantes.1 La historia sigue tres historias entrecruzadas. La primera concierne a una mujer, Urania Cabral, que se encuentra de regreso a República Dominicana, tras una larga ausencia, para visitar a su enfermo padre; ella había abandonado el país, para marcharse a Estados Unidos, y de regreso recordaba incidentes de su juventud y revela un secreto largo tiempo oculto a su tía y a sus primas. La segunda historia hace foco en los últimos días de la vida de Trujillo, desde el momento en que se despierta en adelante, y muestra el círculo íntimo del régimen, del cual el padre de Urania alguna vez formó parte. La tercera es sobre los asesinos de Trujillo, algunos de los cuales había sido leales al gobierno, que se encuentran esperando el coche del dictador la noche del atentado; luego la historia se concentra en su persecución. Cada aspecto del libro revela a diferentes puntos de vista del ambiente social y político dominicano, tanto en el pasado como en el presente.Y las repercusiones de la dictadura en la isla y el mundo . El lector se encuentra en una historia con un espiral descendente, el asesinato de Trujillo y los eventos posteriores bajo la visión de su círculo íntimo, conspiradores y los recuerdos de una mujer de mediana edad contemplando su pasado. La novela tiene una técnica narrativa múltiple (caleidoscópica) acerca del poder dictatorial, incluyendo sus efectos psicológicos y su impacto a largo plazo. La novela es, pues, un retrato del poder dictatorial, incluidos sus efectos psicológicos, y su impacto a largo plazo. Los temas de la novela incluyen la naturaleza del poder y la corrupción, y su relación con el machismo y la perversión sexual en una sociedad rígidamente jerárquica con papeles de género rígidos. La memoria, y el proceso de recordar, es también un tema importante, sobre todo en la narrativa de cómo Urania recuerda su juventud en la República Dominicana. Vargas Llosa entrelaza elementos ficticios con históricos: es libro no es documental y la familia Cabral, verbigracia, es completamente ficticia. Por otro lado, los personajes de Trujillo y sus asesinos fueron creados basados en registros históricos; Vargas Llosa teje una historia estructurada con capítulos que se alternan entre los recuerdos de la protagonista, el propio general Trujillo y las personas que cometieron el atentado. En palabras de Vargas Llosa, "esta es una novela, no un libro de historia, entonces me tomé muchas, muchas libertades. [. . .] Tuve que respetar los hechos básicos, pero cambié y deformé muchas cosas para hacer a la historia más persuasiva; y no he exagerado." |
La fiesta del
Chivoは、ペルーとスペインの作家、マリオ・バルガス・リョサが2000年に発表した小説である。本書はドミニカ共和国を舞台に、独裁者ラファエル・
トルヒーヨの暗殺とその後の事件を、暗殺計画中と暗殺後の1961年5月、そして35年後の1996年と、世代差のある二つの視点から取り上げている。物
語全体を通して、1950年代の独裁政権の全盛期と、島とそこに住む人々にとってのその意義が強烈に映し出されている。 物語は、3つの物語が織りなす展開で進んでいく。アメリカに渡っていたウラニア・カ ブラルは、久しぶりにドミニカ共和国に戻ってきた。彼女は帰国後、若い頃の出来事を思い出し、叔母やいとこに長い間隠していた秘密を打ち明ける。 第2話では、トルヒーリョの晩年、目覚めた瞬間から以降に焦点を当て、ウラニアの父 親がかつて所属していた政権の側近の姿を映し出す。3つ目は、トル ヒーリョの暗殺者たち(その中には政府に忠誠を誓った者もいる)が、暗殺未遂の夜、独裁者の車を待っているところを発見され、その追跡劇に集中する物語で ある。それぞれの側面から、過去と現在のドミニカの社会・政治環境、そして独裁政権が島と世界に及ぼした影響について、さまざまな見解が明らかにされてい る。 読者は、トルヒーヨの暗殺とその後の出来事を、彼の側近や陰謀者たち、そして自分の過去に思いを馳せる中年女性の記憶の幻影のもとで、下降線を描く物語の 中に身を置いていることに気づく。この小説は、独裁的な権力について、その心理的影響や長期的な影響など、多重(万華鏡)のような物語技法を持っていま す。このように、この小説は独裁的な権力について、その心理的影響や長期的な影響も含めて描いたものである。この小説のテーマは、権力と腐敗の本質、そし て厳格な性役割の階層社会におけるマチズモや性的倒錯との関係である。特にウラニアがドミニカ共和国での青春時代を回想する物語では、記憶、そして記憶の プロセスも重要なテーマとなっている。 バルガス・リョサはフィクションと歴史の要素を織り交ぜている。この本はドキュメンタリーではなく、例えばカブラル一家は完全にフィクションである。一 方、トルヒーヨと暗殺者たちのキャラクターは史料に基づいて作られている。バルガス・リョサは、主人公であるトルヒーヨ将軍自身の記憶と暗殺未遂を行った 人々の記憶を交互に章立てして、構成された物語を紡いでいる。バルガス・リョサの言葉を借りれば、「これは小説であって、歴史書ではないので、多くの自由 を得た」。[中略)私は基本的な事実を尊重しなければならなかったが、ストーリーをより説得力のあるものにするために、多くのことを変更し、歪曲した。 |
| Contexto La fiesta del chivo es la segunda novela de Vargas Llosa que trascurre totalmente fuera del Perú (la primera había sido La guerra del fin del mundo). Es también algo inusual para el autor el hecho de que por primera vez tiene una protagonista mujer: Lynn Walford escribió sobre la personaje central de la novela, y del siguiente libro de Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina, «ambas son en gran medida distintas a cualquiera de otras personajes femeninas en sus novelas previas». La novel examina el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo Molina en República Dominicana. Trujillo fue, en las palabras del historiador Eric Roorda, «de una imponente influencia en la historia dominicana y del Caribe», el cual fue «uno de los más estables regímenes del siglo XX», durante sus treinta y un años en que ejerció poder desde 1930 hasta su asesinato en 1961.6 Trujillo había sido entrenado con el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la ocupación estadounidense del país, y se graduó de la Academia Militar de Haina en 1921.6 Tras la partida de los estadounidenses en 1924, se convirtió en la cabeza de la Policía Nacional dominicana, la cual, bajo su comandancia, se transformó en el Ejército Nacional Dominicano y la «base autónoma del poder» personal de Trujillo. Trujillo fue oficialmente el dictador durante 1930 y 1938, y nuevamente entre 1942 y 1952, pero conservó poder efectivo. El pensamiento del régimen fue generalmente nacionalista, aunque Daniel Chirot comentó que no tuvo «ninguna ideología particular» y sus políticas sociales y económicas fueron básicamente progresistas. La novela toma su título del popular merengue dominicano Mataron al chivo, que refiere al asesinato del Trujillo el 30 de mayo de 1961.9 Merengue es un género musical creado por Ñico Lora en los años 1920, que fue activamente promovido por el mismísimo Trujillo. En la actualidad es considerado la música nacional.10 Los críticos culturales Julie Sellers y Stephen Ropp consideran sobre este merengue en particular, que fantasea con el dictador convertido en un animal que podría ser convertido en un guisado (plato frecuente en la gastronomía dominicana), la canción «da a aquellos que están cantando, escuchando y bailando este merengue un sentimiento de control sobre sí mismos, que no han tenido la experiencia de vivir durante esos treinta años». Vargas Llosa cita la letra de Mataron al chivo al inicio de la novela. |
コンテキスト バルガス・リョサの2作目の小説で、舞台はすべてペルー国外である(1作目は『La guerra del Fin del mundo』)。また、著者が初めて女性を主人公にしたのも珍しい。リン・ウォルフォードは、この小説の中心人物と、バルガス・リョサの次作『El paraíso en la otra esquina』について、「どちらも彼のこれまでの小説のどの女性キャラクターとも全く異なっている」と記している。 ドミニカ共和国のラファエル・レオニダス・トルヒーヨ・モリーナの独裁政権を検証した小説である。トルヒーヨは、1930年から1961年に暗殺されるま での31年間、「20世紀で最も安定した政権のひとつ」であり、歴史家エリック・ロルダによれば、「ドミニカとカリブ海の歴史に屹立する影響力を持つ」人 物であった。 6 トルヒーヨは、アメリカの占領下でアメリカ海兵隊で訓練を受け、1921年にハイナ陸軍士官学校を卒業した。6 1924年にアメリカが去った後、彼はドミニカ国家警察のトップとなり、その指揮下でドミニカ国軍となりトルヒーヨ個人の「自治的権力基盤」となったの だ。 トルヒーリョは1930年から1938年まで、そして1942年から1952年まで、公式に独裁者となったが、実効的な権力を保持した。ダニエル・チロ氏 は「特定のイデオロギーはない」とコメントしているが、政権の考え方はおおむねナショナリストであり、社会・経済政策も基本的には進歩的であった。 この小説のタイトルは、1961年5月30日のトルヒーヨ暗殺にちなんで、ドミニカのポピュラーなメレンゲ「Mataron al chivo」から取られている9 。メレンゲとは、1920年代にニニコ・ロラによって作られた音楽ジャンルで、トルヒーヨ自身によって積極的に推進されたものである。文化批評家のジュ リー・セラーズとスティーブン・ロップは、独裁者が動物に変えられてギサド(ドミニカの美食によく登場する料理)にされることを空想したこの特別なメレン ゲについて、「このメレンゲを歌い、聞き、踊る人々は、あの30年間に経験しなかった自分に対する支配感を得られる」と語っている。 バルガス・リョサは、小説の冒頭で「Mataron al chivo」の歌詞を引用している。 |
| El pueblo celebra con gran entusiasmo La fiesta del Chivo El treinta de mayo. — Extracto de Mataron al chivo, merengue dominicano, en el principio de la novela. |
国民が祝う 意気揚々と 山羊の祭り 5月30日のことだ。 - 小説冒頭のドミニカのメレンゲ「Mataron al chivo」から抜粋。 |
| Trama La narrativa de la novela está dividida en tres hilos distintos. Una está centrada en Urania Cabral, dominicana, totalmente ficticia; los asuntos con los conspiradores en el asesinato de Trujillo; y el tercero en el mismo Trujillo. La novela se va alternando entre estas tres historias, y va dando saltos entre 1961 a 1996, con frecuentes flashbacks sobre los inicios del régimen de dictador. La fiesta del Chivo comienza con el regreso de Urania a su casa natal en Santo Domingo, una ciudad que había sido renombrada como Ciudad Trujillo durante los tiempos del dictador en el poder. Este hilo es una larga introspección y narración de hechos de la memoria de Urania y su confusión interna sobre los eventos que precedieron a su salida de República Dominicana hace 35 años. Urania escapó durante del régimen en 1961, bajo el tutelaje de unas monjas que la llevaron a estudiar a Míchigan. En las siguientes décadas, se convirtió en una prominente y exitosa abogada de Nueva York. Finalmente regresa a su país en 1996, un anhelo, y se encuentra compelida a confrontar a su padre y los elementos del pasado que había ignorado durante un largo tiempo. Mientras Urania habla a su enfermizo padre, Agustín Cabral, ella recuerda más y más de su enojo y disgusto que llevaron a sus treinta y cinco años de silencio. Va recordando la caída de su padre en desgracia en el ámbito político, hasta revelar el engaño que une su hilo narrativo con el de Trujillo. El segundo y tercer hilo tienen lugar en 1961, las semanas previas al asesinato de Trujillo el 30 de mayo. Cada asesino tiene su propia historia de fondo, que explica los motivos por los que deciden formar parte en el complot. Cada uno de ellos se había sentido atacado por Trujillo y su régimen, por las torturas o su brutalidad, por golpes al orgullo, religiosidad, moralidad y, en un caso, un asunto referido al amor. Vargas Llosa teje la historia del dictador a manera de memorias recordadas la noche de su asesinato, cuando los conspiradores esperan por el Chivo. Interconectadas con estas historias se encuentran, la de uno de los trujillistas más famosos de aquel tiempo, Joaquín Balaguer, el presidente títere; Johnny Abbes García, el despiadado líder de Servicio de Inteligencia Militar (SIM); y varios otros; algunos reales, algunos inspirados parcialmente en figuras históricas y otros puramente ficticios. El tercer hilo concierne al mismo Rafael Leónidas Trujillo Molina, en cuanto a sus acciones y pensamientos. Los capítulos centrados en el Chivo recuerdan los eventos más destacados de su tiempo, incluyendo el asesinato de miles de haitianos en 1937. Se destacan también las relaciones internacional del país durante las tensiones de la Guerra Fría, especialmente con los Estados Unidos bajo la presidencia de John F. Kennedy, y de Cuba bajo el dominio de Fidel Castro. Vargas Llosa especula sobre los pensamientos de Trujillo y recrea la imagen de un hombre cuyo cuerpo le está comenzando a fallar. Trujillo es atormentado por incontinencia e impotencia sexual. Eventualmente, este hilo se conecta con la narración de Urania cuando revela que fue abusada sexualmente por el dictador. Este, no logra una erección con Urania, y, en su frustración, la viola con sus manos. Este es el hecho clave que avergüenza a Urania y que la llevaría a detestar a su propio padre. Además, esta es la causa que mantiene iracundo a Trujillo, ya que la «muchachita desabrida» fue testigo de su impotencia y de sus emociones, y es la razón que lo motiva a ir a verse con otra mujer, para acostarse con ella, la noche de su asesinato. En el capítulo final de la novela, los tres hilos narrativos se van tocando con frecuencia. El tono de estos últimos capítulos es especialmente oscuro y se enfocan principalmente en la tortura y muerte de los asesinos en manos del SIM, el golpe de Estado fallido, la violación de Urania, y las concesiones de los más duros simpatizantes de Trujillo permitiéndoles llevar a cabo su horrorosa venganza y luego escapar del país. El libro finaliza con Urania preparándose para regresar a casa, resuelta a mantenerse en contacto con la familia que le queda en la isla. |
プロット この小説の物語は、3つの糸に分かれている。一つはドミニカ人のウラニア・カブラルが主人公の完全なフィクション、もう一つはトルヒーヨ暗殺の共謀者、そ してもう一つはトルヒーヨ自身である。小説はこの3つの物語を交互に繰り返し、1961年と1996年を行き来しながら、独裁者政権の初期に頻繁にフラッ シュバックしている。 ウラニアが生家のあるサント・ドミンゴに帰るところから、La fiesta del Chivoは始まる。この街は、独裁者の政権時代にシウダー・トルヒーヨと改名されていた。このスレッドは、35年前にドミニカ共和国を出発する前の出来 事について、ウラニアの記憶と内心の動揺を長い内省と事実のナレーションで綴ったものである。ウラニアは、1961年に政権を脱し、修道女の手引きでミシ ガンに留学した。その後、彼女はニューヨークで著名な弁護士となり、成功を収めた。1996年、念願かなって故郷に戻った彼女は、父や長い間無視してきた 過去の要素と向き合わざるを得ないことに気づく。ウラニアは、病床の父アグスティン・カブラルに語りかけるうちに、35年間の沈黙につながった怒りと嫌悪 をどんどん思い出していく。彼女は、父が政治の舞台で失脚したことを思い出す。そして、自分の物語の糸をトルヒーヨの糸と結びつける欺瞞を明らかにするの である。 第2、第3話は1961年、5月30日にトルヒーヨが暗殺されるまでの数週間が舞台である。暗殺者にはそれぞれ背景の物語があり、なぜその計画に参加する ことになったのかが説明されている。拷問や残虐行為、プライドや宗教心、道徳心、そしてある場合は恋愛感情など、トルヒーリョとその政権から攻撃されたと 感じている人たちばかりだった。バルガス・リョサは、独裁者暗殺の夜、共謀者たちがエル・チーボを待ち受けるときに回想する手記という形で、独裁者の物語 を紡いでいるのだ。これらの物語は、当時最も有名なトゥルージリスタの一人で、傀儡大統領ホアキン・バラゲール、軍事情報局(SIM)の冷酷なリーダー、 ジョニー・アベス・ガルシア、その他、実在の人物、歴史上の人物から一部インスピレーションを得た人物、純粋にフィクションの作品とが相互に関連するもの である。 3つ目は、ラファエル・レオニダス・トルヒーヨ・モリーナ自身の行動と思考である。エル・チーボに焦点を当てた章では、1937年の数千人のハイチ人暗殺 など、彼の時代の最も重要な出来事を回想している。また、冷戦期の緊張の中で、特にジョン・F・ケネディ大統領時代の米国と、フィデル・カストロ統治下の キューバとの国際関係も取り上げている。バルガス・リョサはトルヒーヨの思考を推測し、身体が衰え始めた男のイメージを再現するのである。トルヒーリョは 失禁と性的不能に悩まされている。やがてこの糸は、ウラニアが独裁者から性的虐待を受けたことを明かしたときに、ウラニアの物語とつながる。独裁者はウラ ニアで勃起に失敗し、悔しさのあまり両手で彼女を犯してしまう。これがウラニアを辱め、実の父親を憎むようになる重要な出来事である。さらに、このこと が、トルヒーリョが自分の無力さと感情を「不親切な少女」に目撃され、殺された夜に他の女性に会いに行き、その女性と寝ようとする動機となり、怒り続ける 原因となっているのだ。 小説の最終章では、3つの物語の糸が頻繁に触れ合う。この最終章のトーンは特に暗く、主にSIMの手による暗殺者の拷問と死、クーデターの失敗、ウラニア のレイプ、トルヒーヨの最も過酷なシンパの譲歩によって彼らが恐ろしい復讐を実行し、国外に脱出することに焦点が当てられている。最後に、ウラニアは島に 残された家族と連絡を取り合いながら、帰国の準備をするところで本書は終わる。 |
| Personajes Presente Urania Cabral y su padre Agustín Cabral son presentados ambos tanto en tiempo presente como pasado. En el año 1996, Urania regresa a República Dominicana por primera vez desde que abandonó el país con 14 años. Ella es ahora una importante abogada radicada en Nueva York y que ha pasado los últimos 35 años tratando de olvidar traumas de su niñez, algo que busca con una fascinación académica de la cultura dominicana y de la historia durante la era trujillista. Urania está profundamente acomplejada por los eventos de su pasado, y se decidió a enfrentar a su padre Agustín con respecto a su participación en tales hechos. Urania visita a su padre, y lo encuentra débil por la edad y por un grave accidente, tanto que apenas puede notar su presencia y está incapacitado de responderle, dejándola hablar como si fuera un monólogo. Agustín escucha, sin poder hacer nada, a Urania rememorar su pasado como «Cerebrito Cabral», un importante miembro del círculo íntimo de Trujillo, y su caída en desgracia. Urania detalla el papel de Agustín en los eventos que llevaron a ella a ser violada por Trujillo, y su subsecuente trauma emocional y celibato.13 El personaje de Agustín en el presente de la novela sirven como caja de resonancia para los recuerdos de Urania sobre la era de Trujillo y los eventos que rodearon la desgracia Agustín Cabral y el escape de ella. Sus únicas respuestas son mínimas y no vocales, a pesar del fervor acusativo de Urania y de la enormidad de los hechos durante la era de Trujillo. Trujillismo El dictador dominicano, figura central de La fiesta del chivo, Rafael Leónidas Trujillo. Rafael Trujillo, conocido como el Chivo, el Jefe y el Benefactor, es un personaje con elementos ficticios pero basado en el verdadero dictador de República Dominicana entre 1930 y 1961, oficialmente como Presidente de la República sólo entre 1930 y 1936, y, nuevamente, de 1943 y 1952.14 En La fiesta del Chivo, Vargas Llosa imagina los pensamientos del dictador y cuenta las últimas horas de El Chivo desde su propia perspectiva.15 Trujillo lucha contra el envejecimiento y problemas de incontinencia e impotencia de origen psicológico.16 A través de eventos ficticios y un narrador en primera persona, el lector se encuentra inmerso en el hombre que, durante sus «treinta y un años de crímenes políticos horribles»,9 modernizó la infraestructura del país y sus fuerzas armadas, pero que sus ataques a enemigos en el extranjero (particularmente el intento de asesinato de Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela) llevaron a la imposición de sanciones económicas contra la República Dominicana por parte de la Organización de Estados Americanos en la década de 1950.17 El resultado fue una debacle económica que, junto con otros factores, llevaron a la CIA a apoyar el complot que acabó con la vida de Trujillo el 30 de mayo de 1961.14 Trujillo tiene como figura y simpatizante a Johnny Abbes García, la cabeza del Servicio Inteligencia Militar (SIM), un hombre brutal al que se lo indica como responsable de «desapariciones, ... ejecuciones, ... súbitas caídas en desgracia».18 Abbes y sus oficiales de inteligencia son conocidos por su crueldad, particularmente por el hábito de matar disidentes arrojándolos al mar para que sean devorados por los tiburones.19 El coronel Abbes «...puede ser un demonio; pero al Jefe le sirve: todo lo malo se lo atribuye a él y Trujillo sólo lo bueno».20 El hijo de Trujillo, Ramfis Trujillo, es un leal servidor de su padre. Luego de intentar fallidamente estudiar en Estados Unidos, Ramfis regresa al país para servir en el ejército. Es un reconocido mujeriego. Luego de la muerte de Trujillo, Ramfis se encarniza en buscar venganza, incluso llegando al extremo de torturar a su tío político, el general José Román, por su participación en el complot del asesino. Joaquín Balaguer, el presidente títere de Trujillo, es uno de los simpatizantes del régimen, e inicialmente mostrado como un personaje inocuo sin poder real. Tras la muerte de Trujillo, la calma y serenidad de Balaguer dan un giro, y el General Román comenta sobre él que es un hombre insignificante, visto como un empleado, una figura puramente decorativa, que comienza a adquirir sorpresivamente autoridad.21 Esta es la figura de Balaguer en los últimos capítulos del libro. |
キャラクター 現在 ウラニア・カブラルとその父アグスティン・カブラルは、現在形と過去形の両方で描かれています。1996年、ウラニアは14歳でドミニカ共和国を離れて以 来、初めてドミニカに戻る。彼女は現在、ニューヨークを拠点とする著名な弁護士である。彼女はこの35年間、幼少期のトラウマを忘れようと、トルヒーヨ時 代のドミニカの文化と歴史に学術的な魅力を感じながら、それを追及している。ウラニアは過去の出来事に深く悩み、父アグスティンがその出来事に関与してい たことを突き止めようと決意する。ウラニアが父を訪ねると、彼は年齢と大きな事故によって衰弱しており、彼女の存在にほとんど気づかず、声もかけられず、 まるで独白のように話すだけだった。アグスティンは、ウラニアがトルヒーリョの側近であった「セレブリート・カブラル」としての過去と、その転落を回想す るのを、なすすべもなく聞いていた。ウラニアは、トルヒーヨにレイプされるに至った出来事におけるアグスティンの役割と、その後の心の傷と独身生活につい て詳述する13。小説の現在におけるアグスティンの人物は、ウラニアのトルヒーヨ時代の記憶とアグスティン・カブラルの不名誉と彼女の脱出に関わる出来事 の相談相手として機能している。ウラニアの告発的な熱意とトルヒーリョ時代の出来事の重大さにもかかわらず、彼女は最小限の反応しかせず、声も発しない。 トルヒーヨ主義 『山羊の饗宴』の中心人物であるドミニカの独裁者、ラファエル・レオニダス・トルヒーリョ。ラファエル・トルヒーヨは、「エル・チボ」、「ヤギ」、「ボ ス」、「恩人」として知られる架空の人物だが、1930年から1961年までドミニカ共和国の独裁者として活躍し、1930年から36年まで、1943年 から52年まで再び大統領として公式に就任した14。「La fiesta del Chivo」では、独裁者の考えを想像して、彼自身の視点からエル・チボの最後の数時間を語っている15 。トルヒーヨは老化と心理的原因による失禁とインポテンツという問題を抱えて苦しんでいる16。 読者は、フィクションの出来事と一人称の語り手を通して、「31年間の恐ろしい政治犯罪」9の間に、国のインフラと軍隊を近代化したが、海外の敵への攻撃 (特にベネズエラ大統領ロムロ・ベタンコート暗殺未遂)により、1950年代に米州機構からドミニカ共和国に対する経済制裁を受けた男に没頭している。 17 その結果、経済が破綻し、その他の要因もあって、CIA は 1961 年 5 月 30 日にトルヒーヨの命を絶つ計画を支援することになった。 トルヒーリョの象徴であり同調者であるジョニー・アベス・ガルシアは、軍事情報局(SIM)の長官で、「失踪、...処刑、...突然の失脚」に責任があ ると言われる残忍な男である。 アッベスとその諜報部員は残虐なことで知られ、特に反体制派を海に投げ込んでサメに食べさせるという習慣がある。 アッベスは「悪魔かもしれないが、彼はボスに仕え、すべての悪は彼に、トルヒーリョは善に帰する」。トルヒーリョの息子、ラムフィス・トラヒーリョは父に 忠実に仕えている。米国留学に失敗したラムフィスは、兵役のために帰国する。彼は悪名高い女たらしだ。トルヒーヨの死後、ラムフィスは復讐を決意し、暗殺 計画に加担した義理の叔父であるホセ・ロマン将軍を拷問するまでになる。 トルヒーリョの傀儡大統領ホアキン・バラゲルは、政権のシンパの一人であり、当初は実権を持たない無邪気な人物として描かれていた。トルヒーヨの死後、バ ラゲールの冷静沈着さは一転し、ロマン将軍は、従業員として、純粋に装飾的な存在として見られていたバラゲールが、驚くべき権威を持ち始めるとコメントし ている。 これが、本書の終章におけるバラゲールの姿なのである。 |
| Conspiradores La línea narrativa que concierne al asesinato primariamente sigue a los cuatro conspiradores que participaron directamente en la muerte de Trujillo. Antonio Imbert Barrera es uno de los cuatro conspiradores que sobreviven a las violentas represalias del asesinato. Imbert es un político que está desilusionado por la crueldad y decepción del régimen de Trujillo. Su primer plan para matar a Trujillo fue frustrado por el intento de fuerzas paramilitares cubanas de derrocar el régimen. Convencido de la dificultad de la tarea, Imbert debe unirse a los otros conspiradores de la muerte de Trujillo, como Antonio de la Maza, uno de los guardias personales de Trujillo. El hermano de Antonio es asesinado como parte de un montaje llevado a cabo por el gobierno y Antonio jura venganza contra Trujillo; Salvador Estrella Sadhalá, conocido como «Turco», es un devoto católico quien, indignado por los crímenes trujillistas ofensivos al catolicismo, promete atacar a Trujillo. La preocupación de Turco pasa a ser luego que el régimen no torture a su familia como respuesta al asesinato. Tanto Turco como su hermano inocente, son torturados durante un mes. Su padre permanece fiel al trujillismo y reprocha personalmente a Turco. A pesar de todo, Turco rehúsa suicidarse y no pierde la fe en Dios. Es posteriormente ejecutado por Ramfis y otros sujetos de importancia del gobierno. El amigo íntimo de Turco, Amado García Guerrero, conocido como Amadito, en un teniente del ejército que debe abandonar a su prometida como una prueba de lealtad hacia Trujillo, y luego es forzado a matar al hermano de su amada, en ese mismo sentido. El disgusto de Amadito consigo mismo y la desilusión con el régimen lo llevan a colaborar en la conspiración. Luego del asesinato, se esconde con de la Maza y muere durante un enfrentamiento. Posteriormente al asesinato, Amadito y Antonio de la Maza eligen enfrentarse a los miembros del SIM que los persiguen para arrestarlos, optando por morir combatiéndolos que ser capturados y luego torturados. |
共謀者 暗殺をめぐるストーリーラインは、主にトルヒーヨの死に直接関与した4人の共謀者を追っている。アントニオ・インベル・バレラは、暗殺の激しい報復を生き 延びた4人の共謀者のうちの1人である。インベールはトルヒーリョ政権の残酷さと欺瞞に幻滅した政治家である。最初のトルヒーヨ殺害計画は、キューバの準 軍事組織による政権転覆の企てによって頓挫した。その困難さを確信したインベールは、トルヒーヨの護衛の一人であるアントニオ・デ・ラ・マザら、トルヒー ヨ殺害の他の共謀者たちに加勢しなければならない。アントニオの兄は政府の陰謀で殺され、アントニオはトルヒーヨへの復讐を誓う。「トゥルコ」と呼ばれる サルバドール・エストレージャ・サダハラは敬虔なカトリック信者で、トルヒーヨのカトリックに反する犯罪に怒り、トルヒーヨを攻撃することを誓う。そし て、トゥルコの関心は、暗殺に対して政権が自分の家族を拷問しないかということに移っていく。ターコと無実の弟は共に1ヶ月間拷問を受ける。父親はトル ヒーリョに忠誠を誓い、個人的にトゥルコを非難する。それでもターコは自殺を拒み、神への信仰を失わなかった。その後、ラムフィスをはじめとする政府要人 によって処刑された。トゥルコの親友アマド・ガルシア・ゲレロ、通称アマディトは陸軍中尉だが、トルヒーリョへの忠誠心を試すために婚約者を捨てなければ ならず、さらに愛する者の兄を同じように殺さなければならない。アマディトは自分への嫌悪感と体制への幻滅から、陰謀に協力するようになる。暗殺後、デ・ ラ・マザと共に潜伏し、対決の末に死亡する。暗殺後、アマディートとアントニオ・デ・ラ・マザは、自分たちを逮捕しようと追ってきたSIMのメンバーと対 決し、捕まって拷問されるよりも、彼らと戦って死ぬことを選ぶのである。 |
| Temas principales Los temas principales de La fiesta del Chivo incluyen corrupción, machismo, memorias, y poder y escritura. Olga Lorenzo, crítica del The Melbourne Age, señala que todos estos componentes han ayudado a Vargas Llosa a revelar fuerzas irracionales que ha dado acicate al despotismo en los países latinoamericanos. Corrupción La estructura de la sociedad dominicana es jerárquica, con roles de género fuertemente definido. Rafael Trujillo, el líder, es un cruel dictador que aterró al país durante 35 años hasta su muerte. Es un verdadero caudillo, gobernando bajo brutalidad y corrupción. Ha creado un culto a la personalidad en una sociedad capitalista y acrecienta la decadencia en su régimen. Para lograr un ascenso y conseguir mayores responsabilidades, un oficial o alguno de sus servidores debe pasar por una «prueba de lealtad». Pese a todo sus partidarios se muestran leales a todo costo, siendo sometidos a censuras y humillaciones públicas, haciendo esto aún que la deslealtad sea inusual. Trujillo viola mujeres y niñas como expresión de su poder político y sexual, y ha habido casos donde toma la esposa o la hija de alguno de sus tenientes, la mayoría ciegamente leales. Incluso la Iglesia y las instituciones militares son usadas para proveer de mujeres al dictador. Casi todos los asesinos han estado vinculados directamente al régimen de Trujillo o han sido fervientes partidarios, y solo han encontrado que el régimen los usaba para cometer crímenes contra la población. En una entrevista, Vargas Llosa describe la brutalidad y la corrupción del régimen de Trujillo: «Tenía más o menos todos los rasgos que tienen en común todos los dictadores de Latinoamérica, pero llevado al extremo. En crueldad, creo que fue mucho más lejos que el resto; y en corrupción, también.» Machismo Según el especialista literario Peter Anthony Niessa, dos comportamientos significativos del machismo son un comportamiento agresivo e hipersexualidad. El comportamiento agresivo se demuestra en exhibiciones de poder y de fuerza, mientras que la hipersexualidad a través de actividad sexual con todas las personas cuantas sean posibles. Estos dos componentes dan forma al retrato de Trujillo y de su régimen en La fiesta del Chivo. Como Lorenzo destaca, Vargas Llosa «revela tradiciones de machismo, padres abusivos, y prácticas de la crianza de los niños que se repiten y avergüenzan a los niños, de modo que cada generación lega un marchitamiento del alma a la subsiguiente.» Reflejando ambos aspectos del machismo, Trujillo reclamaba a sus ayudantes y a su gabinete que le brinden acceso sexual a sus esposas e hijas. Mario Vargas Llosa escribió acerca del machismo de Trujillo y su trato con las mujeres, «[él] va a la cama con las esposas de sus ministros, no sólo para mostrar que le gustan esas mujeres, sino también para probarlos. Quería saber si ellos estaban preparados para soportar la extrema humillación. Principalmente los ministros estaban preparados para desempeñar ese grotesco papel; y se mantuvieron leales a Trujillo incluso hasta después de su muerte.»Las conquistas sexuales del dictador y las humillaciones públicas de sus enemigos también sirven para reafirmar su poder político y su machismo. En palabras de Niessa, «La implicación es que la máxima virilidad es igual al dominio político.» El deseo de conquista sexual de Trujillo sobre Urania es un ejemplo de manipulación política sobre Agustín Cabral y de poder sexual sobre una niña. Sin embargo, el falo de Trujillo se mantiene flácido a pesar del encuentro sexual y se siente humillado frente a ella, no pudiendo satisfacer su machismo. Memoria Todos los hilos de la novela novela refieren a la memoria en algún otro sentido. La confrontación más aparente con la memoria es con Urania Cabral, quien regresa a territorio dominicano por primera vez en 30 años, y es forzada a confrontar a su padre y los traumas que la llevaron a abandonar el país a los 14 años. Fue víctima de un abuso sexual por parte del mismísimo dictador, un sacrificio que su padre debió hacer para ganarse nuevamente la confianza del dictador, un hecho al cual ella alude a lo largo de todo el libro, pero solo se revela completamente al final: la obra finaliza cuando se lo cuenta a su tía y a sus primas, haciendo memoria, quienes nunca supieron los motivos reales de por qué abandonó el país. Cuando su tía se ver sorprendida por detallismo de esa noche, ella responde que, a pesar de que olvida muchas cosas, «Recuerdo todo sobre esa noche.»31 Para Urania, olvidar las atrocidades cometidas por el régimen es inaceptable.32 Su padre, por otro lado, no es capaz de unirse a ese proceso, ya que ha sufrido un accidente cerebrovascular; sin embargo, Urania está enojada de que él haya optado por olvidar cuando aún tenía capacidad para recordar. La memorias es importante también en los pasajes de la novela concerniente al asesinato. Cada recuerdo lleva a los conspiradores a tomar parte en el asesinato de Trujillo. Algunos de estos hechos incluyen el secuestro y el asesinato de Jesús Galíndez en 1956, el asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal y la ruptura de 1961 con la Iglesia católica. Estos eventos históricos son usados por Vargas Llosa para conectar a los perpetradores con momentos históricos que reflejan la violencia del régimen. Trujillo, además, recuerda su pasado, no menos importante fue su formación y su entrenamiento con los marines estadounidenses. Por sobre todo Mario Vargas Llosa usa a la ficticia Urania para facilitar en la novela el recuerdo del régimen. La novela comienza y se cierra con la historia de Urania, efectivamente fragmentada en su narración bajo la forma de recordar el pasado y su comprensión con el presente. Además, gracias a su estudio académico de la historia dominicana bajo Trujillo, ella confronta en el presente lo que fue para el país en su conjunto aquel gobierno. Este es uno de los propósitos del libro, el cual es asegurar que las atrocidades de la dictadura y los peligros del poder absoluto sean recordados por las nuevas generaciones. |
主要なテーマ "La fiesta del Chivo" の主なテーマは、腐敗、マチズモ、回想録、権力と文章などである。メルボルン・エイジ誌の評論家、オルガ・ロレンソは、これらの要素がバルガス・リョサが ラテンアメリカ諸国の専制政治を煽る非合理的な力を明らかにするのに役立ったと指摘する。 汚職(腐敗) ドミニカの社会構造は階層的で、性別の役割分担が強く決められている。指導者のラファエル・トルヒーヨは、死ぬまでの35年間、この国を恐怖に陥れた残虐 な独裁者である。彼は、残忍さと腐敗の下で支配する、真のカウディーロである。彼は資本主義社会でカルト的な人格を作り上げ、政権の退廃を進めているので す。昇進してより大きな責任を果たすためには、将校や使用人の一人は「忠誠心テスト」に合格しなければならない。しかし、彼の支持者は、世間の非難と屈辱 にさらされながら、何としても忠誠心を保ち続け、不忠実は異常でさえある。トルヒーヨは自分の政治的、性的権力の表現として女性や少女をレイプし、ほとん ど盲目的に忠実な部下の妻や娘を連れ去ったケースもある。教会や軍の機関までもが、独裁者のために女性を提供するために利用される。 暗殺者のほぼ全員がトルヒーヨ政権に直接関係しているか、熱烈な支持者であり、政権が住民に対する犯罪に利用したことがわかっただけだ。 バルガス・リョサはインタビューの中で、トルヒーヨ政権の残虐性と腐敗について、「ラテンアメリカのすべての独裁者が共通して持っている特徴を多かれ少な かれ持っていたが、極限に達した」と述べている。残酷さでは、他の人よりもずっと進んでいたと思うし、腐敗の面でもそうだ」。 マチズモ 文学者のピーター・アンソニー・ニーサによれば、マチズモの2つの重要な行動は、攻撃的行動とハイパーセクシュアリティである。 攻撃的行動は力と強さを誇示し、ハイパーセクシュアリティはできるだけ多くの人と性的行為を行うことで発揮される。この2つの要素が『La fiesta del Chivo』におけるトルヒーリョとその政権の肖像を形作っているのだ。ロレンソが言うように、バルガス・リョサは「マチズモ、虐待する父親、繰り返され て子供を辱める育児法などの伝統を明らかにし、各世代が魂の枯渇を次の世代に遺すこ とになる」。 マチズモの両面を反映して、トルヒーヨは側近や閣僚に自分の妻や娘と性的な関係を持つことを要求した。マリオ・バルガス・リョサは、トルヒーヨのマチズモ と女性の扱いについて、「彼 は大臣の妻とベッドインし、彼女らが好きであることを示すだけでなく、彼女らを試すためでもある。極限の屈辱に耐える覚悟があるかどうかを知りたかったの だ。独裁者の性的征服と敵への公然の屈辱は、彼の政治的権力とマチズモを再確認させるものであった。ニーサの言葉を借りれば、「最大限の活力は政治的な支 配に等しいという意味合い」である。 トルヒーヨのウラニアに対する性的征服欲は、アグスティン・カブラルに対する政治的操作と少女に対する性的権力の例である。しかし、トルヒーヨの陰茎は性 行為にもかかわらず弛緩したままであり、彼は彼女の前で屈辱を感じ、自分のマチズモを満足させることができないのだ。 記憶 この小説のすべての糸は、別の意味での記憶に言及している。30年ぶりにドミニカに戻ったウラニア・カブラルは、父親や14歳のときに国を離れることに なったトラウマと向き合わざるを得ない。彼女は独裁者自身による性的虐待の被害者であり、独裁者の信頼を取り戻すために父親が犠牲にならなければならな かった。この事実は、彼女が本書を通して暗示するが、最後に初めて完全に明らかになる。本書は、彼女が国を離れた本当の理由を知らない叔母といとこに、記 憶の中で伝えるところで終わっているのである。ウラニアにとって、政権の残虐行為を忘れることは許されないことである32。 また、小説の中で殺人に関わる箇所では、記憶が重要な意味を持つ。あらゆる記憶が、陰謀家たちをトルヒーリョ暗殺への参加へと導いていく。1956年のヘ スス・ガリンデスの誘拐・殺害、1960年のミラバル姉妹の暗殺、1961年のカトリック教会との断絶などがその例である。バルガス・リョサはこれらの歴 史的事件を利用して、犯人を政権の暴力を反映する歴史的瞬間と結びつけているのである。さらに、トルヒーヨは、自分の過去、特にアメリカ海兵隊での教育や 訓練を思い出している。 とりわけ、マリオ・バルガス・リョサは、架空のウラニアを使って、この小説の体制についての回想を容易にしている。小説はウラニアの物語で始まり、過去へ の追憶と現在との理解という形で、彼女の語りの中で効果的に断片化されながら幕を閉じる。また、トルヒーリョ政権下のドミニカの歴史を学術的に研究してい るおかげで、その政権が国全体にとってどのようなものであったかを現在に対峙させている。 これは、独裁政権の残虐性と絶対権力の危険性を新しい世代に記憶させるという、本書の目的の1つである。 |
| Recepción El estilo realista de La fiesta del chivo es reconocido por algunos críticos como una ruptura con las aproximaciones alegóricas de las obras del género novela del dictador. La obra recibió mayoritariamente críticas positivas, muchas de las cuales se mostraron complacientes en el sacrificio de la exactitud histórica por una sobresaliente narración. Un comentario habitual sobre la novela es acerca de la naturaleza gráfica de los actos de tortura y asesinato que son descritos en la obra. Vargas Llosa ofrece al lector las realidades de un régimen opresivo con un grado de detalle que no son usados habitualmente por otros autores latinoamericanos, en ese sentido Michael Wood sugirió en London Review of Books: «Vargas Llosa ... nos cuenta más allá de una intriga del día a día, y las sórdidas, sádicas minucias de tortura y asesinato.» Walter Kirn, de The New York Times, comentó que esas «escenas espeluznantes de los interrogatorios en las mazmorras y las sesiones de tortura» dejan a los otros aspectos de la novela en una luz pálida, drenándolos de su importancia e impacto. De igual manera, para Kirn implica que la «maquinaria narrativa» mencionada por Wood se vuelva un tanto inmanejable, produciendo un argumento superfluo. El hilo narrativo centrado en Urania Cabral es descrito por Sturrock como el centro emocional en que hace foco la novela, y Wood concuerda en que las confrontaciones de ella con sus demonios logran captar la atención del lector. En contraste, la visión de Kirn es que los segmentos de Urania son «hablados y atmosféricos... [y] parecen haber sido tomados prestados de otro tipo de libro.» La gran mayoría de las críticas hacen referencia, directa o indirectamente, a la relación entre sexualidad y poder. La analista de Salon Laura Miller, el escritor de The Observer, Jonathan Heawood, Kirn, y Wood cada uno detalla que ello está conectado con la pérdida progresiva del poder de Trujillo, desde su cuerpo hasta sus seguidores. La alegoría de que Trujillo refuerza su poder político a través de actos sexuales, y comienza a perder convicción a medida que el cuerpo de le falla, es algo de frecuente discusión en la crítica. En 2011 Bernard Diederich, autor del libro histórico de 1978 Trujillo. La muerte del Chivo, acusó a Vargas Llosa de plagio. |
受容(と批判) この作品は、独裁者の小説ジャンルの作品に見られる寓話的なアプローチとは一線を画す、現実的なスタイルであると一部の評論家は認めている。 この作品はほぼ好意的に受け入れられたが、その多くは、優れたストーリーテリングのために歴史の正確さが犠牲になったことに満足している。 よく言われるのは、作中で描かれる拷問や殺人行為の生々しさについてだ。バルガス・リョサは、他のラテンアメリカの作家が通常使用しない程度の詳細さで、 圧政の現実を読者に提供する。ロンドン・レビュー・オブ・ブックスでマイケル・ウッドが示唆したように、「バルガス・リョサは・・・過去の興味深い物語を 越えて・・・我々に語る。ニューヨーク・タイムズ紙のウォルター・カーン記者は、この「地下牢での尋問や拷問の悲惨なシーン」は、小説の他の側面を淡白に し、その重要性とインパクトを奪っていると評している。 同様に、キルンにとっては、ウッドの言う「物語の機械」がやや扱いにくくなり、余分なプロットを生み出すことを意味する。ウラニア・カブラルを中心とした 物語の流れは、スターロックが小説の感情的な焦点であると述べ、ウッドも彼女の悪魔との対決が読者の注意を引くことに成功していると同意している。 これに対してカーンは、ウラニアのセグメントは「饒舌で雰囲気のある...」という見方をしている。[別の種類の本から借用したようだ] 批判の大半は、直接的または間接的に、セクシュアリティと権力の関係に言及している。SalonのアナリストLaura Miller、ObserverのライターJonathan Heawood、Kirn、Woodはそれぞれ、これがトルヒーヨの身体から信奉者まで、徐々に失われる権力と結びついていると詳述している。トルヒーヨ が性行為によって政治的権力を強化し、肉体の衰えとともに信念を失い始めるという寓話は、批評の中でもよく取り上げられるものだ。 2011年、1978年の歴史書『トルヒーヨ』の著者であるベルナルド・ディーデリックが登場した。『山羊の死』では、バルガス・リョサの盗作を非難し た。 |
| Adaptaciones En 2005 se realizó una adaptación fílmica en inglés, dirigida por Luis Llosa, primo de Mario Vargas Llosa. Se destacan Isabella Rossellini como Urania Cabral, Paul Freeman como su padre Agustín, Stephanie Leonidas como Uranita y Tomas Milian como Rafael Leónidas Trujillo. Fue filmada tanto en República Dominicana, como en España. En la crítica de la cinta realizada por la revista Variety, el crítico Jonathan Holland opinó que era «poco menos que un banquete de tres platos, hecho apresuradamente, pero completamente agradable», comentando que la principal diferencia con el libro fue el sacrificio de los matices psicológicos. La novela ha sido también llevada al teatro, versión dramática realizada por Jorge Alí Triana y su hija Verónica Triana, y dirigida por Jorge Triana: tuvo su estreno —en idioma español, pero con traducción simultánea en inglés— en el teatro Repertorio Español de Nueva York en 2003; la producción fue llevada a Lima en 2007. Un cambio destacable de la versión teatral es que es el mismo actor quien interpreta a Agustín Cabral y Rafael Trujillo. Para el analista Bruce Weber, esto significaría que «el poder de Trujillo sobre la nación depende de sus cobardes colaboradores». |
翻案や適用作品 2005年には、マリオ・バルガス・リョサのいとこであるルイス・リョサ監督によって英語版の映画化もされた。ウラニア・カブラル役にイザベラ・ロッセ リーニ、父アグスティン役にポール・フリーマン、ウラニータ役にステファニー・レオニダス、ラファエル・レオニダス・トルヒーヨ役にトマス・ミリアンが出 演しています。バラエティ誌の批評では、評論家のジョナサン・ホランドが「急ごしらえの3コースディナーに過ぎないが、十分に楽しめる」と評し、「本との 大きな違いは、心理的ニュアンスが犠牲になっていることだ」とコメントしている。 この小説は、ホルヘ・アリ・トリアーナとその娘ベロニカ・トリアーナによって劇化され、ホルヘ・トリアーナが演出した。 2003年にニューヨークのレパートリー・エスパニョールで初演(スペイン語、英語同時通訳)、2007年にリマで上演。 劇場版で注目すべき点は、同じ俳優がAgustín CabralとRafael Trujilloを演じていることだ。アナリストのブルース・ウェーバーは、「トルヒーヨの国家に対する権力は、臆病な協力者に依存している」ということ になる。 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/La_fiesta_del_Chivo_(novela) |
https://www.deepl.com/ja/translator |
|
Merengue was developed in the middle of the 1800s, originally played with European stringed instruments (bandurria and guitar). Years later, the stringed instruments were replaced by the accordion, thus conforming, together with the güira and the tambora, the instrumental structure of the typical merengue ensemble. This set, with its three instruments, represents the synthesis of the three cultures that made up the idiosyncrasy of Dominican culture. The European influence is represented by the accordion, the African by the Tambora, which is a two-head drum, and the Taino or aboriginal by the güira. The genre was later promoted by Rafael Trujillo, the dictator from 1930 to 1961, who turned it into the national music and dance style of the Dominican Republic. In the United States it was first popularized by New York-based groups and bandleaders like Rafael Petiton Guzman, beginning in the 1930s, and Angel Viloria y su Conjunto Típico Cibaeño in the 1950s. It was during the Trujillo era that the merengue "Compadre Pedro Juan", by Luis Alberti, became an international hit and standardized the 2-part form of the merengue.[5] Famous merengue artists and groups include Juan Luis Guerra, Wilfrido Vargas,[6] Milly Quezada, Toño Rosario, Fernando Villalona, Los Hermanos Rosario, Bonny Cepeda,[7] Johnny Ventura,[8] Eddy Herrera, Sergio Vargas, Grupo Rana, Miriam Cruz, Las Chicas Del Can, Kinito Mendez, Jossie Esteban y la Patrulla 15, Pochy y su Cocoband,[9] Cuco Valoy, Ramón Orlando, Alex Bueno,[10] The New York Band, Elvis Crespo, Olga Tañón, Gisselle, and Grupomanía. The popularity of merengue has been increasing in Venezuela. Venezuelan Merengueros include Roberto Antonio, Miguel Moly, Natusha, Porfi Jiménez, Billo's Caracas Boys, and Los Melodicos. Merengue is also popular in the coastal city of Guayaquil in Ecuador. The new line of merengue created in New York City has become very popular amongst younger listeners. Known as "Merengue de Mambo," its proponents include Omega, Oro 24, Los Ficos, Los Gambinos, Alberto Flash, Mala Fe, Henry Jimenez, and Aybar. Although the etymology of merengue can be disputed, there are a few theories about where the word might have derived from. One suggestion is that the term derives from meringue, a dish made from egg whites that is popular in Latin-American countries. The sound made by the whipping of eggs supposedly resembles the guiro used in merengue. |
メレンゲは1800年代半ばに開発され、当初はヨーロッパの弦楽器(バンドゥリアとギター)を使って演奏されていた。その後、弦楽器はアコーディオンに 取って代わられ、グイラとタンボラと合わせて、典型的なメレンゲのアンサンブルの楽器構成となった。この3つの楽器のセットは、ドミニカ文化の特異性を構 成する3つの文化の統合を象徴している。ヨーロッパ系はアコーディオン、アフリカ系はタンボラ(2つの頭を持つ太鼓)、タイノ系はグイラで表現されてい る。 その後、1930年から1961年まで独裁者だったラファエル・トルヒーヨが奨励し、ドミニカ共和国の国民音楽・ダンススタイルになった。アメリカでは、 1930年代からラファエル・プティトン・グスマン、1950年代にはアンヘル・ビロリア・イ・ス・コンジュント・ティピコ・シバエーニョといったニュー ヨークのグループやバンドリーダーによって普及が始まった。トルヒーヨ時代には、ルイス・アルベルティによるメレンゲ「Compadre Pedro Juan」が世界的にヒットし、メレンゲの2部形式が標準化された[5]。 有名なメレンゲのアーティストやグループには、フアン・ルイス・ゲーラ、ウィルフリッド・バルガス、[6] ミリー・ケサダ、トーニョ・ロサリオ、フェルナンド・ビラロナ、ロス・エルマノス・ロサリオ、ボニー・セペダ、[7] ジョニー・ベンチュラ[8] エディ・エレラ、セルジオ・バルガス、グルーポ・ラナ。ミリアム・クルス、ラス・チカス・デル・カン、キニト・メンデス、ジョシー・エステバン・イ・ラ・ パトルージャ15、ポーチー・イ・ス・ココバンド、クコ・バロイ、ラモン・オーランド、アレックス・ブエノ、ニューヨーク・バンド、エルヴィス・クレス ポ、オルガ・タニョン、ジセル、グルポマニアなど。 メレンゲの人気はベネズエラでも高まっている。ベネズエラのメレンゲには、Roberto Antonio、Miguel Moly、Natusha、Porfi Jiménez、Billo's Caracas Boys、Los Melodicosなどがいる。メレンゲはエクアドルの海岸沿いの都市グアヤキルでも人気がある。 ニューヨークで生まれた新しいメレンゲのラインは、若いリスナーの間でとても人気がある。メレンゲ・デ・マンボ」と呼ばれるその支持者には、オメガ、オロ 24、ロス・フィコス、ロス・ガンビーノ、アルベルト・フラッシュ、マラフェ、ヘンリー・ヒメネス、アイバーなどがいる。 メレンゲの語源については異論もあるが、その語源がどこから来たのかについてはいくつかの説がある。そのひとつは、中南米諸国で人気のある卵白を使った料 理、メレンゲに由来するというものだ。卵を泡立てるときの音が、メレンゲに使われるギロと似ているのだという。 |
| History The origins of the music are traced to the land of El Cibao, where merengue cibaeño and merengue típico are the terms most musicians use to refer to classical merengue. The word Cibao was a native name for the island, although the Spanish used it in their conquest to refer to a specific part of the island, the highest mountainous range. The term merengue cibaeño is therefore partially native and so merengue might also be a derivation of a native word related to song, music, dance, or festival. Another theory includes Western African words related to dance and music, based on the presence of African elements in merengue. An early genre with similarities to merengue is the carabiné originating in the southern region of the territory of what is now the Dominican Republic, during the time of the French occupation. The name "carabiné" derives from the weapons called carbines (in French carabinier) that the soldiers did not dare to leave when a dance arrived, proceeding to dance with them on their shoulders. From the French word, the Spanish name of the new rhythm was derived, accentuating its pronunciation sharply on the "e". Merengue was first mentioned in the mid 19th century with the earliest documented evidence being newspaper articles. Some of the articles inform about a "lascivious" dance, and also highlight merengue displacing the Tumba. The genre had originated within the rural, northern valley region around the city of Santiago called the Cibao. It later spread throughout the country and became popular among the urban population.[11] The oldest form of merengue was typically played on string instruments. When the accordion came to the island in the 1880s, introduced by German traders, it quickly became the primary instrument, and to this day is still the instrument of choice in merengue típico. Later, the piano and brass instruments were introduced to the genre. |
歴史 音楽の起源はエル・シバオという土地に遡り、メレンゲ・シバエーニョやメレンゲ・ティピコは、クラシックなメレンゲを指す言葉としてほとんどのミュージ シャンが使っている。シバオという言葉は先住民の名前であったが、スペイン人が征服の際に島の特定の部分、最も高い山々を指す言葉として使われた。した がって、メレンゲ・チバエーニョという言葉は部分的にネイティブであるため、メレンゲも歌、音楽、踊り、祭りに関連するネイティブの言葉が派生したものか もしれない。また、メレンゲにアフリカの要素があることから、ダンスや音楽に関連する西アフリカの単語を含むという説もある。 メレンゲと類似した初期のジャンルとして、フランス統治時代の現在のドミニカ共和国の領土の南部地域で生まれたカラビネがある。カラビネ」という名前は、 カービン銃(フランス語でcarabinier)と呼ばれる武器を、兵士が踊りが来てもあえて離さず、肩に担いで踊っていたことに由来している。このフラ ンス語から、スペイン語の「e」の発音を強調した新しいリズムの名称が生まれたのである。 メレンゲは19世紀半ばに初めて言及され、最も古い文献は新聞記事である。その記事の中には、「淫らな」ダンスについて書かれたものもあり、また、メレン ゲがトゥンバを置き換えたことも強調されています。このジャンルは、サンチアゴ市周辺のシバオと呼ばれる北部の谷間の農村地帯で生まれた。その後、国中に 広がり、都市部の人々の間で人気を博すようになった[11]。 最も古いメレンゲの形態は、通常、弦楽器で演奏されていた。1880年代にドイツ人商人によってアコーディオンが持ち込まれると、すぐに主要な楽器とな り、現在でもメレンゲティピコではこの楽器が選ばれている。その後、ピアノや金管楽器がこのジャンルに導入された。 |
| Musical style Three main types of merengue are played in the Dominican Republic and Puerto Rico today. Merengue típico, which is usually called perico ripiao, is the oldest style commonly played. The other two types are merengue de orquesta (big-band merengue) and merengue de guitarra (guitar merengue). Rhythm Merengues are fast arrangements with a 2/4 beat. The traditional instrumentation for a conjunto típico (traditional band), the usual performing group of folk merengue, is a diatonic accordion, a two–sided drum, called a tambora, held on the lap, and a güira. A güira is a percussion instrument that sounds like a maraca. It is a sheet of metal with small bumps on it (created with hammer and nail), shaped into a cylinder, and played with a stiff brush. The güira is brushed steadily on the downbeat with an "and-a" thrown in at certain points, or played in more complex patterns that generally mark the time. Caballito rhythm, or a quarter and two eighths, is also common. The double-headed drum is played on one side with a stick syncopation and on the other side with the palm of the hand. The traditional (some say fundamental) signature rhythm figure of merengue is the quintillo, which is essentially a syncopated motif whose pattern is broken by five successive drumhead hits at the transition between every second and third beat, alternating between the hand and the stick. To purists, a merengue without quintillo is not truly a merengue, a viewpoint that has gradually disappeared as other alternate figures are used more frequently (as the one traditionally called jaleo, also known as merengue bomba, wrongly identified as a mixture of merengue and Puerto Rican bomba music, and which actually also has its roots in traditional merengue). Three main types of merengue are played in the Dominican Republic today. Merengue típico, which is usually called perico ripiao, is the oldest style commonly played. In English perico ripiao means "ripped parrot", which suggests controversy but which is said to be the name of a brothel where the music was originally played. The other two types are merengue de orquesta (big-band merengue) and merengue de guitarra (guitar merengue). Stylistic changes At first, merengue típico was played on stringed instruments like the tres and cuatro, but when Germans came to the island in the late 19th century trading their instruments for tobacco, the accordion quickly replaced the strings as lead instrument. Típico groups play a variety of rhythms, but most common are the merengue and the pambiche. In the 1930s–50s a bass instrument was also often used. Called marimba, it resembles the Cuban marímbula, and is a large box-shaped thumb piano with 3-6 metal keys. The main percussion instruments, güira and tambora, have been a part of the ensemble since the music's inception, and are so important that they are often considered symbolic of the whole country. The güira is a metal scraper believed to be of native Taíno origin, while the tambora is a two-headed drum of African origin. Together with the European accordion, the típico group symbolizes the three cultures that combined to make today's Dominican Republic. One important figure in early merengue was Francisco "Ñico" Lora (1880–1971), who is often credited for quickly popularizing the accordion at the turn of the 20th century. Lora was once asked how many merengues he had composed in his lifetime and he answered "thousands", probably without much exaggeration, and many of these compositions are still a standard part of the típico repertoire. He was a skilled improviser who could compose songs on the spot, by request. But he has also been likened to a journalist, since in his precomposed songs "he commented on everything with his accordion" (Pichardo, in Austerlitz 1997:35). His compositions discussed current events such as Cuban independence, World War I, the arrival of the airplane, and US occupation of the Dominican Republic. Among Lora's contemporaries are Toño Abreu and Hipólito Martínez, best remembered for their merengue "Caña Brava". This popular song was composed in 1928 or 1929 as an advertisement for the Brugal rum company, who were then selling a rum of the same name. Brugal paid Martínez $5 for his efforts. Típico musicians continued to innovate within their style during the latter half of the twentieth century. Tatico Henríquez (d.1976), considered the godfather of modern merengue típico, replaced the marimba with electric bass and added a saxophone (it was used before, but infrequently) to harmonize with the accordion. A prolific composer, Tatico's influence cannot be overestimated: nationally broadcast radio and television appearances brought his music to all parts of the country, leading to widespread imitation of his style and dissemination of his compositions. Today, these works form the core of any típico musician's repertoire. Other innovations from this period include the addition of the bass drum now played by the güirero with a foot pedal, a development credited to Rafael Solano. Many of today's top accordionists also began their careers during this period, including El Ciego de Nagua, Rafaelito Román, and Francisco Ulloa. Arrangements In the 1990s, most groups maintained the five-man lineup of accordion, sax, tambora, güira, and bass guitar, though a few new innovations have been made. Some modern band leaders have also added congas, timbales (played by the tamborero), and keyboards to their groups in an attempt to reach a wider audience and narrow the gap between the típico and orquesta styles. The most popular artist at present is El Prodigio, a young accordionist who is respected among típico musicians of all ages. Though he has become famous for recording his own compositions in a modern style, he is also able to perform all the "standards" of the traditional típico repertoire and is a talented, jazzy improviser. New York–based groups like Fulanito have experimented with the fusion of típico accordion with rap vocals. Young artists such as these have been able to bring merengue típico to new audiences. Merengue típico songs are generally composed in two parts. The first section is rhythmically straightforward and is used to introduce the song's melodic and lyrical material; here, verses are sung and the only improvisation occurs at the end of song lines, when the accordion or saxophone fills in. The second section is dominated by improvisation, more complex rhythms, and hard-driving mambo, or the part of the song where melody instruments (sax and accordion) unite to play catchy, syncopated riffs or jaleos which help motivate and stimulate dancers. Típico rhythms include merengue derecho, or straight-ahead merengue, which is the kind of fast-paced 2/4 time merengue most of us are used to hearing, usually used in the first section. Pambiche or merengue apambichao is similar but usually slower, and can be recognized by the double slap rhythm on the tambora. Guinchao is a third rhythm combining the first two that is commonly heard in the second section of a merengue. Típico groups do not have to limit themselves to merengue as they can also play other traditional rhythms from the Dominican Republic and elsewhere, though this was more common in the past than at present. Mangulina and guaracha are now seldom heard; the latter is a clave-based style in 4/4 originally from Cuba, while the former is a 6/8 dance native to the Dominican Republic. Paseo was a slow introduction to a merengue song during which couples would promenade around the dance floor in stately fashion. Orquesta or big-band merengue became the merengue of choice for the urban Dominican middle and upper classes in the twentieth century. Although merengue had been played in upper-class salons as early as the 1850s, moralists like then-president Ulises Espaillat succeeded in banning the dance from such locations only two decades later, causing the merengue to effectively die out in the cities. Still, it was kept alive by rural musicians such as accordionist/composer Nico Lora, and it began to reappear in towns of the Cibao during the 1910s. During that decade, several composers, including Julio Alberto Hernández, Juan Espínola of La Vega and Juan Francisco García of Santiago, tried to resuscitate the dance by creating orchestrated, written scores based on folk merengue melodies. One of these was García's 1918 work titled "Ecos del Cibao." Composer Luis Alberti later reported that such pieces, especially the famous tune known as the Juangomero, were frequently played at the end of an evening's program that otherwise featured imported styles like waltzes, mazurkas, polkas, danzas, danzones, and one- and two-steps. While these early efforts in orchestrated merengue generally succeeded only in scandalizing their audiences, the political changes that occurred in the Dominican Republic over the next few years made a resurgence of the merengue possible. The resented North American invasion of 1916 seems to have made the general public more disposed to support autochthonous rhythms over imported ones, though the raucous rural accordion sound was still unacceptable to high-society tastes. Nevertheless, when Rafael Leonidas Trujillo took power in 1930, he imposed the merengue upon all levels of society, some say as a form of punishment for the elites that had previously refused to accept him. The soon-to-be dictator must also have realized the symbolic power of the rural folk music and its potential for creating support among the masses, since he took accordionists with him around the Republic during his campaign tours from the very beginning. |
音楽スタイル 現在、ドミニカ共和国とプエルトリコでは、主に3種類のメレンゲが演奏されている。メレンゲ・ティピコは通常ペリコ・リピアオと呼ばれ、一般に演奏される 最も古いスタイルである。他の2つのタイプは、メレンゲ・デ・オルケスタ(ビッグバンドメレンゲ)とメレンゲ・デ・ギタラ(ギターメレンゲ)です。 リズム メレンゲは2/4拍子の速いアレンジである。民謡メレンゲの演奏グループであるコンヌント・ティピコ(伝統的な楽団)の楽器は、ダイアトニックアコーディ オン、膝に乗せるタンボーラと呼ばれる二面性の太鼓、グイラが一般的である。グイラとは、マラカのような音を出す打楽器である。ハンマーと釘で小さな凹凸 をつけた金属板を円筒形に成形し、硬いブラシで叩く。グイラは、下拍に安定してブラシをかけ、あるポイントで "and-a "を入れたり、一般に時間を示すより複雑なパターンで演奏される。カバリートのリズム、つまり4分の1と8分の2もよく使われる。双頭の太鼓は、片方はス ティックのシンコペーションで、もう片方は手のひらで演奏する。 メレンゲの伝統的(基本的)な特徴的リズム図形はクインティージョで、これは基本的にシンコペーションのモチーフで、そのパターンは2拍目と3拍目ごとの 切り替えでドラムヘッドを5回連続して叩くことで壊れ、手とスティックが交互に使われる。メレンゲとプエルトリコのボンバが混ざった音楽として間違って認 識されているが、実はこれも伝統的なメレンゲにルーツがある)。 現在ドミニカ共和国では、主に3種類のメレンゲが演奏されている。通常perico ripiaoと呼ばれるMerengue típicoは、一般に演奏される最も古いスタイルである。英語でperico ripiaoは「裂かれたオウム」を意味し、論争を示唆するが、これはこの音楽がもともと演奏されていた売春宿の名前であると言われている。他に、メレン ゲ・デ・オルケスタ(ビッグバンド・メレンゲ)とメレンゲ・デ・ギタラ(ギター・メレンゲ)がある。 スタイルの変化 当初、メレンゲ・ティピコはトレスやクアトロなどの弦楽器で演奏されていたが、19世紀後半にドイツ人がタバコと楽器を交換して島にやってきたため、すぐ にアコーディオンが弦楽器に代わってリード楽器として使われるようになった。ティピコのグループは様々なリズムを演奏するが、最も一般的なのはメレンゲと パンビシェである。1930年代から50年代にかけては、低音楽器もよく使われた。マリンバと呼ばれるこの楽器は、キューバのマリンブラに似ており、大き な箱型の親指ピアノで、3~6個の金属製の鍵盤がある。主な打楽器であるグイラとタンボラは、音楽が始まって以来、アンサンブルの一部となっており、国全 体の象徴とされることもあるほど重要な楽器である。グイラはタイノ族が起源とされる金属製のスクレイパーで、タンボラはアフリカ系の双頭の太鼓である。 ティピコはヨーロッパのアコーディオンとともに、今日のドミニカ共和国を形成する3つの文化を象徴している。 初期のメレンゲの重要人物の一人に、20世紀初頭にアコーディオンを急速に普及させたとされるフランシスコ・"ニイコ"・ロラ(1880〜1971年)が いる。ロラは生涯で何曲のメレンゲを作曲したかと聞かれ、「数千曲」と答えたが、おそらくそれほど誇張していないはずで、これらの曲の多くは今でもティピ コのレパートリーとして定番となっている。彼は即興演奏に長けており、リクエストに応じてその場で作曲することができた。しかし、事前に作曲した曲の中で 「彼はアコーディオンで何にでもコメントした」(ピカルド、アウステルリッツ1997:35)ため、ジャーナリストにも例えられる。彼の曲は、キューバの 独立、第一次世界大戦、飛行機の到着、アメリカによるドミニカ共和国の占領といった時事問題を論じている。ロラと同時代の作曲家には、メレンゲ「カー ニャ・ブラバ」で有名なトニョ・アブレウとヒポリート・マルティネスがいる。この人気曲は、1928年か1929年に、当時同じ名前のラム酒を販売してい たBrugal社の広告として作られたものである。ブルガルはマルティネスに5ドルを支払った。 ティピコの音楽家たちは、20世紀後半、そのスタイルを革新し続けた。現代メレンゲ・ティピコの名付け親とされるタティコ・ヘンリケス(1976年没) は、マリンバをエレクトリックベースに置き換え、アコーディオンと調和するサクソフォーンを加えた(以前は使われていたが、頻度は少なかった)。全国放送 のラジオやテレビに出演したことで、タティコの音楽は全国に広まり、彼のスタイルを模倣し、彼の作曲した曲は広く知られるようになりました。今日、これら の作品はティピコ音楽家のレパートリーの中核を成している。また、この時代、バスドラムを足で踏むグイレロが登場したが、これはラファエル・ソラーノが開 発したものであるとされている。エル・シエゴ・デ・ナグア、ラファエリート・ロマン、フランシスコ・ウジョアなど、今日のトップクラスのアコーディオン奏 者もこの時期にキャリアをスタートさせた。 編曲 1990年代には、アコーディオン、サックス、タンボーラ、グイラ、ベースの5人編成が主流となったが、いくつかの新しい試みもなされている。また、コン ガ、ティンバレス(タンボレロで演奏)、キーボードなどを加え、ティピコとオルケスタの垣根を取り払い、より多くの人に楽しんでもらえるよう工夫している バンドリーダーもいる。現在、最も人気のあるアーティストは、ティピコ・ミュージシャンの間で幅広い年齢層から尊敬されている若手アコーディオン奏者、エ ル・プロディジオです。自作曲をモダンなスタイルで録音していることで有名ですが、ティピコの伝統的なレパートリーである「スタンダード」もすべて演奏で き、ジャジーな即興演奏の才能も持ち合わせています。ニューヨークを拠点とするフラニートのようなグループは、ティピコ・アコーディオンとラップ・ヴォー カルの融合を試みている。このような若いアーティストたちは、メレンゲ・ティピコを新しい聴衆に届けることができました。 メレンゲ・ティピコの曲は一般的に2つのパートで構成されています。最初のセクションはリズムが単純で、曲のメロディと歌詞を紹介するために使われる。こ こでは詩が歌われ、唯一の即興演奏は曲の行末にあるアコーディオンやサックスが補うときに起こる。第2部では、即興演奏、より複雑なリズム、ハードなマン ボ、またはメロディ楽器(サックスとアコーディオン)が一体となってキャッチーでシンコペーションの効いたリフやジャレオを演奏し、ダンサーのモチベー ションを高めるのに役立ちます。ティピコのリズムには、メレンゲ・デレチョ(ストレート・アヘッド・メレンゲ)と呼ばれる、私たちが聞き慣れている2/4 拍子の速いメレンゲがあり、通常は最初のセクションで使われる。PambicheまたはMerengue apambichaoはこれに似ているが、通常はより遅く、タンボラのダブルスラップのリズムで見分けることができる。Guinchaoは最初の2つを組 み合わせた第3のリズムで、メレンゲの第2セクションでよく聞かれる。ティピコのグループはメレンゲに限らず、ドミニカ共和国やその他の国の伝統的なリズ ムを演奏することもあるが、これは現在よりも昔の方が一般的であった。マングリーナやグアラチャは今ではあまり聞かれないが、後者はキューバ発祥の4/4 のクラーベをベースにしたスタイルで、前者はドミニカ共和国原産の6/8のダンスである。パセオは、メレンゲの曲の序奏で、カップルが堂々とダンスフロア をプロムナードするようにゆっくり踊るものである。20世紀には、オルケスタやビッグバンドのメレンゲが、ドミニカの都市部の中流階級や上流階級に好まれ るメレンゲになった。メレンゲは1850年代にはすでに上流階級のサロンで演奏されていたが、当時の大統領ウリセス・エスパイラットのような道徳主義者が わずか20年後にそうした場所でのダンスを禁止することに成功し、メレンゲは都市部で事実上消滅してしまった。しかし、アコーディオン奏者で作曲家のニ コ・ロラなどの地方のミュージシャンによって存続され、1910年代にはシバオの町でも再び見られるようになった。 この10年間に、フリオ・アルベルト・エルナンデス、ラ・ベガのフアン・エスピノラ、サンティアゴのフアン・フランシスコ・ガルシアなどの作曲家が、民謡 メレンゲのメロディーを基にしたオーケストラの楽譜を作り、ダンスの復活を図ったのです。そのひとつがガルシアの1918年の作品 "Ecos del Cibao" である。作曲家のルイス・アルベルティは後に、このような作品、特にフアンゴメロとして知られる有名な曲は、ワルツ、マズルカ、ポルカ、ダンザス、ダンソ ン、ワンステップやツーステップなどの輸入様式を特集した夜のプログラムの最後によく演奏されたと報告している。 このような初期の組織的なメレンゲの試みは、概して聴衆を顰蹙させることにしかならなかったが、その後数年の間にドミニカ共和国で起こった政治的変化に よってメレンゲの復活が可能になったのである。1916年の北米侵攻に憤慨した一般市民は、輸入リズムよりも自国のリズムを支持する傾向が強まったようだ が、田舎の騒々しいアコーディオンの音は上流社会の好みにはまだ受け入れがたいものであった。しかし、1930年にラファエル・レオニダス・トルヒーヨが 政権を握ると、それまで自分を受け入れようとしなかったエリート層に対する罰として、社会のあらゆる階層にメレンゲを押し付けるようになった。独裁者と なったトルヒーヨは、農村民謡の持つ象徴的な力と大衆の支持を生み出す可能性に気づいたのだろう、当初から選挙遊説の際にアコーディオン奏者を連れて共和 国を回っていた。 |
| Rafael Leonidas Trujillo Until the 1930s, the music was considered "immoral" by the general population. Its more descriptive and colorful name, perico ripiao (literally "ripped parrot" in Spanish), was said to have been the name of a brothel in Santiago where the music was played. Moralists tried to ban merengue music and the provocative dance that accompanied it, but with little success.[12] Merengue experienced a sudden elevation of status during dictator Rafael Leonidas Trujillo's reign from 1930 to 1961. Although he was from the south rather than the Cibao, he did come from a rural area and from a lower-class family, so he decided that the rural style of perico ripiao should be the Dominican national symbol. He ordered numerous merengues to be composed in his honor. With titles like "Literacy", "Trujillo is great and immortal", and "Trujillo the great architect", these songs describe his virtues and extol his contributions to the country. Trujillo's interest in and encouragement of merengue helped create a place for the music on the radio and in respectable ballrooms. Luis Alberti and other musicians began to play with "big band" or orquesta instrumentation, replacing the accordion with a horn section and initiating a split between this new, mostly urban style and mostly rural perico ripiao. New York City Latino radio is still dominated by orquesta merengue.[13] Following his election, Trujillo ordered musicians to compose and perform numerous merengues extolling his supposed virtues and attractiveness to women. Luis Alberti and other popular bandleaders created a style of merengue more acceptable to the urban middle class by making its instrumentation more similar to the big bands then popular in the United States, replacing the accordion with a large brass section but maintaining the tambora and güira as a rhythmic base. They also composed lyrics free of the rough language and double-entendres characterizing the folk style. The first merengue to attain success at all levels of society was Alberti's famous 1936 work, "Compadre Pedro Juan." This was actually a resetting of García's "Ecos," itself based on earlier folk melodies, and thus it upheld a long-standing tradition in merengue típico of creating songs by applying new words to recycled melodies. The new, popular-style merengue began to grow in quite different directions from its predecessor, merengue típico. It became ever more popular throughout the country through its promotion by Petán Trujillo, the dictator's brother, on his state-sponsored radio station, La Voz Dominicana. Musicians like Luis Senior and Pedro Pérez kept listeners interested by inventing new variations like the "bolemengue" and "jalemengue."[14] Merengue does not have as plainly strong African origins as other forms of Dominican music, and therefore did not conflict with Trujillo's racist ideology. Trujillo promoted the music for political gain as a focus of national solidarity and political propaganda. It helped his efforts to unify a Dominican identity.[15] After Trujillo's assassination in 1961, the merengue orquesta underwent great change. During that decade, Johnny Ventura's Combo Show drove crowds wild with their showy choreography, slimmed-down brass section, and salsa influences. In the 1970s, Wilfrido Vargas sped up the tempo and incorporated influences from disco and rock. (The term "orquesta," simply meaning a large musical ensemble, is now used to describe the pop merengue groups based on Ventura's and Vargas's models as well as the older Alberti style.) In addition, a new rhythm called "merengue a lo maco" appeared and was popularized by groups including Los Hermanos Rosario and Cheche Abreu. Far less complicated than other merengue rhythms, it was particularly useful for adapting songs from other styles like bachata, Colombian vallenato, Mexican rancheras, and North American pop. This process of remaking is called fusilamiento and continues to be a source for many merengue hits to this day. |
ラファエル・レオニダス・トルヒーリョ 1930年代まで、この音楽は一般市民から「不道徳」だと思われていた。より分かりやすくカラフルな名前であるペリコ・リピアオ(スペイン語で「裂かれた オウム」)は、この音楽が演奏されていたサンティアゴの売春宿の名前だと言われている。道徳主義者はメレンゲの音楽とそれに伴う挑発的なダンスを禁止しよ うとしたが、ほとんど成功しなかった[12]。 メレンゲは1930年から1961年までの独裁者ラファエル・レオニダ ス・トルヒーリョの統治下で急激に地位を高めた。彼はシバオではなく南部出身であったが、農村部出身で下層階級の家庭であったため、農村部のスタイルであ るペリコ・リピアオをドミニカの国の象徴とすることを決めたのであった。彼は、自分の名誉のために数多くのメレンゲを作曲するよう命じた。文学」「トル ヒーヨは偉大で不滅」「偉大な建築家トルヒーヨ」などのタイトルで、彼の美点を述べ、国への貢献を讃える歌である。トルヒーリョはメレンゲに関心を持ち、 それを奨励したことで、ラジオや立派な社交場でこの音楽の居場所を作ることができた。ルイス・アルベルティや他のミュージシャンは、アコーディオンをホー ンセクションに置き換え、「ビッグバンド」や「オルケスタ」という楽器編成で演奏するようになり、この新しい、主に都市部のスタイルと主に地方のペリコ・ リピアオとの間に分裂が起こりました。ニューヨークのラテン系ラジオは今でもオルケスタ・メレンゲが主流である[13]。 トルヒーヨは当選後、音楽家たちに自分の美徳や女性への魅力を謳った数 々のメレンゲを作曲し演奏するよう命じた。ルイス・アルベルティや他の人気バンドリーダーたちは、アコーディオンを大きなブラスセクションに置き換え、タ ンボラとグイラをリズムのベースとしながら、楽器編成を当時のアメリカのビッグバンドに近づけ、都会の中流階級に受け入れられるメレンゲのスタイルを作り 上げた。また、歌詞も民謡にありがちな乱暴な言葉遣いや二枚舌のないものが作られた。メレンゲが社会的に成功したのは、1936年のアルベルティの有名な 作品 "Compadre Pedro Juan "が最初である。これはガルシアの "Ecos "を改作したもので、それ以前は民謡のメロディーをベースにしていた。つまり、メレンゲ・ティピコの長い伝統である、リサイクルされたメロディーに新しい 言葉をつけて曲を作るという伝統を守っているのだ。この新しい大衆的なメレンゲは、前身であるメレンゲ・ティピコとは全く異なる方向へ発展していった。独 裁者の弟ペタン・トルヒーヨが国営ラジオ局「ラ・ボス・ドミニカーナ」で宣伝し、全国的に人気が高まった。ルイス・シニアやペドロ・ペレスのようなミュー ジシャンは、「bolemengue」や「jalemengue」のような新しいバリエーションを考案してリスナーの興味を引き続けた[14]。 メレンゲはドミニカ音楽の他の形態ほど明白に強いアフリカ起源を持たな いため、トルヒーヨの人種差別的イデオロギーと対立することはなかった。トルヒーヨは国民的連帯と政治的プロパガンダの焦点として、政治的利益のためにこ の音楽を推進した。それはドミニカのアイデンティティを統一するための彼の努力に役立った[15]。 1961年にトルヒーヨが暗殺された後、メレンゲオルケスタは大きな変化を遂げた。この10年間、ジョニー・ベンチュラのコンボ・ショーは、派手な振り付 け、スリムなブラスセクション、サルサの影響などで観衆を熱狂させた。1970年代には、ウィルフリッド・バルガスがテンポを速め、ディスコやロックの影 響を取り入れた。(オルケスタという言葉は、単に大きな音楽アンサンブルという意味だが、現在ではベンチュラやバルガスをモデルとしたポップなメレンゲグ ループや、古いアルベルティスタイルを指す言葉として使われている)。さらに、「メレンゲ・ア・ロ・マコ」と呼ばれる新しいリズムが登場し、ロス・エルマ ノス・ロサリオやチェチェ・アブレウなどのグループによって人気を博した。他のメレンゲのリズムに比べてはるかに複雑ではなく、バチャータ、コロンビアの バレナート、メキシコのランチェラ、北アメリカのポップスなど、他のスタイルの曲をアレンジする際に特に使われた。このリメイクのプロセスは fusilamientoと呼ばれ、今日に至るまで多くのメレンゲのヒット曲の源であり続けている。 |
| Merengue around the world Merengue has been heard in New York since the 1930s, when Eduardo Brito became the first to sing the Dominican national music there before going on to tour Spain. Salcedo-born, Juilliard-educated Rafael Petitón Guzmán formed the first Dominican-led band in the city with his Orquesta Lira Dominicana, which played in all the popular ballrooms in the 1930s and 1940s, while at the same time Angel Viloria played popular tunes on accordion with his "conjunto típico cibaeño" for Big Apple fans. However, it wasn't until the massive migration of Dominicans in the 1960s and 1970s that the music reached a mass audience. In 1967, Joseíto Mateo, Alberto Beltrán, and Primitivo Santos took merengue to Madison Square Garden for the first time. Later, New York–based groups like La Gran Manzana and Milly, Jocelyn y los Vecinos, a group unusual for being fronted by women, gained a following in the diaspora as well as back on the island. By the 1980s merengue was so big it was even beating out salsa on the airwaves. That decade was also notable for a boom in all-female orchestras, and Las Chicas del Can became particularly popular. Since then, musicians like Juan Luis Guerra, trained at Boston's Berklee school, Toño Rosario and former rocker Luis Díaz have brought merengue even further abroad, truly internationalizing the music. Guerra collaborated with African guitarists, experimented with indigenous Caribbean sounds, and explored Dominican roots music with típico accordionist Francisco Ulloa, while Díaz (an innovator since his work with 1970s folklore group Convite) fused merengue, rock, merengue típico, and bachata in his productions. In the 21st century, orquesta musicians began to voice concern that their style would be eclipsed in popularity by bachata and merengue típico. Perhaps for this reason, some pop merengue singers have gone to extreme lengths to attract attention, such as Tulile and Mala Fe's excursions into women's wear. But even without such antics, recordings by groups like Los Toros Band, Rubby Pérez, Alex Bueno, Sergio Vargas, and the ever-popular Los Hermanos Rosario continue to sell well. Pop merengue also has a remarkably strong following on the neighboring island of Puerto Rico, which has produced its own stars, like Olga Tañón and Elvis Crespo. In more urban settings, merengue is played with all manner of instrumentation, but the tambora and the güira are signatures. Today, merengue de orquesta is most popular. It uses a large horn section with paired saxophones, piano, timbales, hi-hat, backup singers, and conga, in addition to tambora, güira, and bass. In modern merengue típico a saxophone is an addition to the accordion, along with electric bass guitar. A proof of the great adaptability of the music can be found in the Dominican National Symphony's presentation in 2003 of a concert series entitled "Symphonic Merengue", in which the Symphonic Orchestra consisting of woodwinds, brass, strings, and the like played popular tunes.[16] |
世界のメレンゲ メレンゲは1930年代からニューヨークで聴かれるようになった。エドゥアルド・ブリトがスペイン公演の前に、このドミニカの民族音楽を初めてニューヨー クで歌ったのである。サルセド出身でジュリアードで教育を受けたラファエル・ペティトン・グスマンは、ニューヨークで最初のドミニカ人主導のバンド、オル ケスタ・リラ・ドミニカーナを結成し、1930年代と1940年代に人気のボールルームで演奏し、同時期にアンヘル・ビロリアは、ビッグアップルのファン のために「コンジュント・ティピコ・シバエーニョ」というアコーディオンの演奏で人気の曲を演奏していた。しかし、この音楽が大衆に受け入れられるように なったのは、1960年代から1970年代にかけてのドミニカ人の大移動がきっかけであった。1967年、ホセイト・マテオ、アルベルト・ベルトラン、プ リミティボ・サントスの3人は、マディソン・スクエア・ガーデンで初めてメレンゲを披露した。その後、ニューヨークを拠点とするラ・グラン・マンサナやミ リー、ジョセリン・イ・ロス・ベシーノスといったグループが、女性中心の珍しいグループとして、ディアスポラだけでなく島でも支持されるようになった。 1980年代には、メレンゲはサルサをしのぐほどの大ブームとなった。この年代は女性だけのオーケストラがブームとなり、特にラス・チカス・デル・カンは 人気を博した。その後、ボストンのバークリー音楽院で学んだフアン・ルイス・ゲラ、トニョ・ロサリオ、元ロッカーのルイス・ディアスなどのミュージシャン が、メレンゲをさらに海外に広め、音楽を国際化させた。ゲーラはアフリカのギタリストとコラボレートし、カリブ海の土着的なサウンドで実験し、ティピコ・ アコーディオンのフランシスコ・ウロアとドミニカのルーツ音楽を探求し、ディアス(1970年代のフォークロアグループ、コンバイトでの活動以来革新者) はメレンゲ、ロック、メレンゲティピコ、バチャータを自分の作品に融合させたのである。 21世紀に入ると、オルケスタのミュージシャンたちは、自分たちのスタイルがバチャータやメレンゲ・ティピコに人気を奪われることを懸念するようになっ た。そのためか、ポップなメレンゲ歌手の中には、TulileやMala Feが女性服に身を包むなど、注目を集めるために極端な手段を取る者もいる。しかし、そんなことをしなくても、ロス・トロス楽団、ルビー・ペレス、アレッ クス・ブエノ、セルジオ・バルガス、そして不動の人気を誇るロス・エルマノス・ロサリオといったグループの録音は売れ続けているのである。隣国のプエルト リコでもポップなメレンゲは根強い人気があり、オルガ・タニョンやエルビス・クレスポといったスターを輩出している。 都市部では、あらゆる楽器を使って演奏されるが、タンボラとグイラが代表的な楽器である。現在、最も人気があるのはメレンゲ・デ・オルケスタである。タン ボラ、グイラ、ベースに加えて、ペアのサックス、ピアノ、ティンバレス、ハイハット、バックシンガー、コンガを含む大規模なホーンセクションが使われる。 現代のメレンゲ・ティピコでは、アコーディオンに加えてサックスが入り、さらにエレクトリックベースが加わる。2003年にドミニカ共和国交響楽団が「シ ンフォニック・メレンゲ」と題したコンサートシリーズを開催し、木管楽器、金管楽器、弦楽器などからなるシンフォニック・オーケストラが人気曲を演奏した ことが、この音楽の大きな適応性を証明しているといえる[16]。 |
| Distribution Merengue music found mainstream exposure in other areas of Latin America in the 1970s and '80s, with its peak in the 1990s. In the Andean countries like Peru and Chile, merengue dance lost the characteristic of being danced close together, instead being danced separately while moving the arms.[17] Women in merengue Merengue, from its conception and through time, has classically been a male-dominated genre. In recent times, however, the genre has experienced a change in this situation. Several female artists and all-female bands have risen to relative stardom. This upheaval was influenced by the contributions of singer/bandleader Johnny Ventura’s modernization of the sound of merengue in 1960, modernizing the sound from its “big-band”-esque setup with a quickening of tempo and inclusion of a visually-appealing element, with glitzy costumes and choreography. In the early 1970s, trumpeter and singer Wilfrido Vargas furthered the modernization of merengue by including electronic elements and strengthening the focus of a visual stage presence. These two men modernized the merengue stage, thereby increasing the palatability of a female merengue presence.[18] One of the most influential women in merengue is Fefita La Grande. Her birth name was Manuela Josefa Cabrera Taveras. She performed for Petán Trujillo, the brother of the Dominican Republic's president, convincing him to give her father a home and a job she could earn money from. Her rise to fame led to a great demand for her performances in New York, the Dominican Republic, and even Europe. Fefita's efforts forced men to work alongside women in merengue and accept that there is a place for them. Female merengue bands began to emerge in the 1970s, with examples such as Gladys Quero's "Orquesta Unisex", but started gaining popularity in the early 1980s with Aris García's "La Media Naranja", "Las Chicas del País" and, principally, pianist Belkis Concepcion's band, Las Chicas del Can. They are known by their fans as Las Reinas del Merengue, or in English, The Queens of Merengue. The band currently consists of eleven members, including horns, rhythm, dancers, and singers. After Belkis Concepcion left the band in 1985, Miriam Cruz took over as lead vocalist and led the band on tours through Europe. Soon after Concepcion followed the “mother figure” of merengue—Milly Quesada. She led the group Los Vecinos, which includes her sister Jocelyn and cousins Rafael and Martin, based in New York City. In reference to this female-merengue phenomena, Jocelyn Quesada states, You know, if you wear a dress, and you have to open your legs and hold the tambora, that’s kind of awkward. And also the brass instruments ... that’s like macho territory. They never thought a woman could do that. They could play a violin, flute. They got up there, and they played those instruments, and people were shocked, and they were mostly curious to see if it works. The audience was not too thrilled; they thought, "Nah, well, a female group is not going to sound kosher."[19] Yet another notable all-female merengue group is the trio Chantelle. The women are Puerto Rican, not Dominican, and both this and their gender testify to merengue's growing popularity.[20] Las Chicas del Can was the first all-female band from the Dominican Republic, formed in 1981, which paved the road for other Latina artists. Known as “Las Reinas de Merengue”, which means “The Queens of Merengue”, they not only sang and danced, but also played a variety of instruments such as the trumpet, conga drums and the guitar. Las Chicas del Can were extremely successful, earning several platinum and gold records. Their hit single “El Negro No Puede” was later remade by Shakira, in her song “Waka Waka”. Milly Quezada was born as Milagros Quezada Borbon on May 21, 1955. She is a singer in Latin America. Her hometown is Dominican Republic. She graduated from New York City College with a communications degree. Then she was known as the Queen of Merengue, or La Reina de Merengue. She had a group with her two brothers and sister called Milly, Y Los Vecinos. The band would write songs about women's independence and freedom of choice. |
流通 メレンゲ音楽は1970年代と80年代にラテンアメリカの他の地域で主流となる露出を見つけ、1990年代にピークを迎えた。ペルーやチリなどのアンデス 諸国では、メレンゲのダンスは近くで踊るという特徴を失い、代わりに腕を動かしながら別々に踊られるようになった[17]。 メレンゲにおける女性 メレンゲはその構想から時代を通して、古典的に男性優位のジャンルであった。しかし、近年ではこの状況に変化が生じている。女性アーティストや女性だけの バンドがスターダムにのし上がったのである。1960年に歌手兼バンドリーダーのジョニー・ベンチュラがメレンゲのサウンドを近代化し、テンポを速め、華 やかな衣装と振り付けで視覚的に訴える要素を取り入れたことが、この激変に影響を与えた。1970年代初頭には、トランペット奏者で歌手のウィルフリッ ド・ヴァルガスが、電子的な要素を取り入れ、視覚的なステージングを重視することでメレンゲの現代化をさらに推し進めた。この2人はメレンゲのステージを 近代化し、それによって女性のメレンゲの存在感を高めた[18]。 メレンゲで最も影響力のある女性の一人はフェフィータ・ラ・グランデである。彼女の出生名はマヌエラ・ホセファ・カブレラ・タベラスである。彼女はドミニ カ共和国大統領の弟であるペタン・トルヒーヨのためにパフォーマンスを行い、父親に家を与え、彼女が稼げる仕事を与えるようにと説得した。彼女の名声は、 ニューヨーク、ドミニカ共和国、そしてヨーロッパにまで広がり、彼女のパフォーマンスは大きな需要を持つようになった。フェフィタの努力によって、男性は メレンゲで女性と共に働き、女性のための場所があることを受け入れざるを得なくなった。 女性メレンゲバンドは1970年代に登場し、グラディス・ケロの「オルケスタ・ユニセックス」などが有名だが、1980年代初頭にはアリス・ガルシアの 「ラ・メディア・ナランハ」、「ラス・チカス・デル・パイス」、主にピアニストのベルキス・コンセプシオンのバンド、ラス・チカス・デル・カンで人気を集 めはじめた。ファンの間では、Las Reinas del Merengue、英語ではThe Queens of Merengueとして知られている。バンドは現在、ホーン、リズム、ダンサー、シンガーを含む11人のメンバーで構成されている。1985年にベルキ ス・コンセプシオンが脱退した後、ミリアム・クルスがリード・ボーカリストとしてバンドを率い、ヨーロッパ・ツアーに参加した。コンセプシオンは、メレン ゲの "母 "ミリー・ケサダを追った。彼女は、妹のジョセリン、いとこのラファエルとマーティンを加えたグループ、ロス・ベシーノスを率いてニューヨークを拠点に活 動している。この女性メレンゲの現象について、ジョセリン・ケサダはこう語る。 ドレスを着て、足を開いてタンボーラを持たないといけないとなると、ちょっと気まずいわね。それに、金管楽器も......あれはマッチョの領域みたいな ものです。金管楽器はマッチョの領域で、女性が演奏できるなんて思ってもみませんでした。バイオリンやフルートは演奏できるのに。観客はショックを受けま したが、それがうまくいくかどうか知りたかったのです。観客はあまり興奮しませんでした。「いや、まあ、女性グループはコーシャルの音にはならないだろ う」と思ったのです[19]。 さらにもう1つの注目すべき女性だけのメレンゲグループは、トリオのChantelleです。彼女たちはドミニカ人ではなくプエルトリコ人であり、このこ とと彼女たちの性別の両方がメレンゲの人気が高まっていることを証明している[20]。 ラス・チカス・デル・カンは、1981年に結成されたドミニカ共和国初の女性だけのバンドで、他のラテン系アーティストへの道を切り開いた。メレンゲの女 王」を意味する「ラス・レイナス・デ・メレンゲ」として知られる彼女たちは、歌い踊るだけではなく、トランペット、コンガドラム、ギターなど様々な楽器を 演奏した。ラス・チカス・デル・カンは大成功を収め、プラチナやゴールドのレコードをいくつも獲得した。彼らのヒット曲「El Negro No Puede」は、後にシャキーラの曲「Waka Waka」でリメイクされた。 ミリー・ケサーダは1955年5月21日、ミラグロス・ケサーダ・ボルボンとして生まれた。ラテンアメリカの歌手である。出身地はドミニカ共和国。彼女は ニューヨーク・シティ・カレッジのコミュニケーション学科を卒業した。その後、メレンゲの女王(La Reina de Merengue)と呼ばれるようになる。彼女は2人の兄と姉と一緒にMilly, Y Los Vecinosというグループを持っていた。このバンドは、女性の自立と選択の自由をテーマにした曲を作っていた。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Merengue_music |
https://www.deepl.com/ja/translator |

El dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo inspiró el best seller literario “La fiesta del chivo”, de Mario Vargas Llosa. "Mataron al chivo"
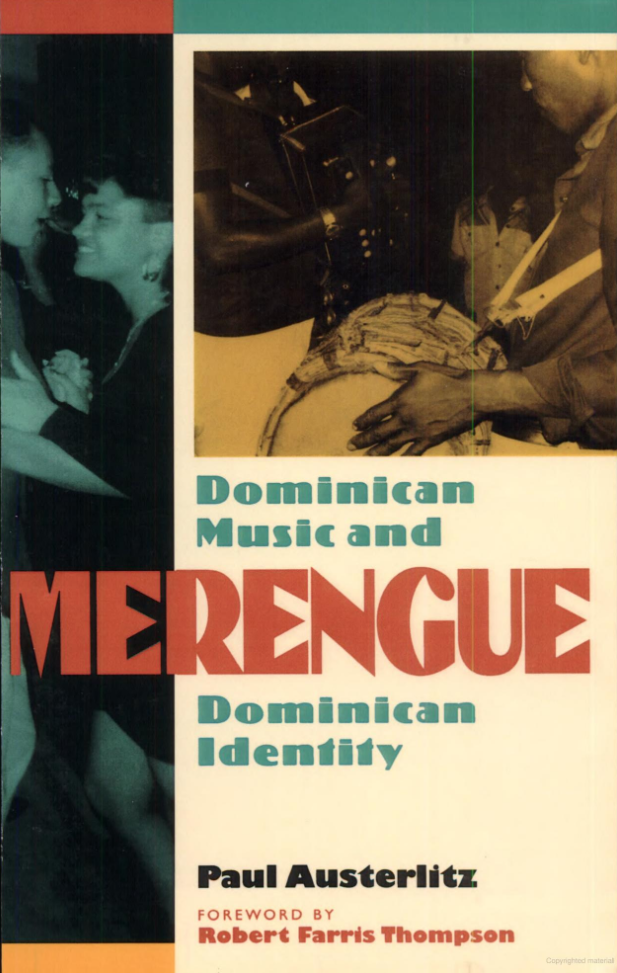
「ドミニカのダンスミュージックの真髄ともいえるメレンゲは、島とニューヨークの大規模な移 民コミュニティの両方において、長く複雑な歴史を持っている。本書は、メレンゲのルーツであるアフリカとイベリア半島の歴史を紐解き、独裁者ラファエル・ トルヒーヨの時代に成長し、国際的な音楽として再び人気を博すまでの軌跡をたどった意欲作である。豊富なインタビューと解説書を使って、メレンゲが演奏さ れ踊られる歴史的・現代的な文脈、その象徴的意義、社会的機能、音楽・振付の構造などを検証している。メレンゲの政治的機能、階級的・人種的な意義につい ても語っている。彼は、このイベリア・アフリカの芸術形式の様々な民族的起源を探るだけでなく、一部のドミニカ人がいかにそのアフリカのルーツを否定しよ うとしてきたかも指摘する。今日のグローバル社会では、大衆文化が民族のアイデンティティを示すことが多い。メレンゲはドミニカ共和国の国内外を問わず、 ドミニカ人のアイデンティティを示す代表的な音楽である。著者はこのダンス音楽を語ることで、現代のエスニシティにおける大衆と民衆の表現の意味、地域、 国民、移民文化の関係、農村・地域と都市・大衆文化の関係をとらえている。アウステルリッツはまた、移民やグローバルな文化が、すでに自国のメレンゲの形 式と活発に混ざり合っている自国の音楽に与えた影響も追跡している。農村の民謡から国境を越えた大衆音楽まで、メレンゲは長く華やかなキャリアを歩んでき た。本書は、現代音楽に関心を持つ人にとって必読の書であると同時に、カルチュラル・スタディーズに関心を持つ人にとっても、その複雑な歴史は同様に欠く ことのできないものとなるだろう。」。Austerlitz, Paul, 1997. Merengue : Dominican music and Dominican identity. foreword by Robert Farris Thompson. Temple University Press.
【章立て】
Foreword - Robert Farris Thompson
Preface
1. Introduction
Part I: The History of Merengue, 1854-1961
2. Nineteenth-Century Caribbean Merengue
3. Merengue Cibaeno, Cultural Nationalism,
and Resistance
4. Music and the State: Merengue during
the Era of Trujillo, 1930-1961
Part II: The Contemporary Era, 1961-1995
5. Merengue in the Transnational community
6. Innovation and Social Issues in Pop
Merengue
7. Merengue on the Global Stage
8. Enduring Localism
Conclusion
Notes
Bibliography
Interviews
Index
+++
Links
リンク
文献
その他の情報



++
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099