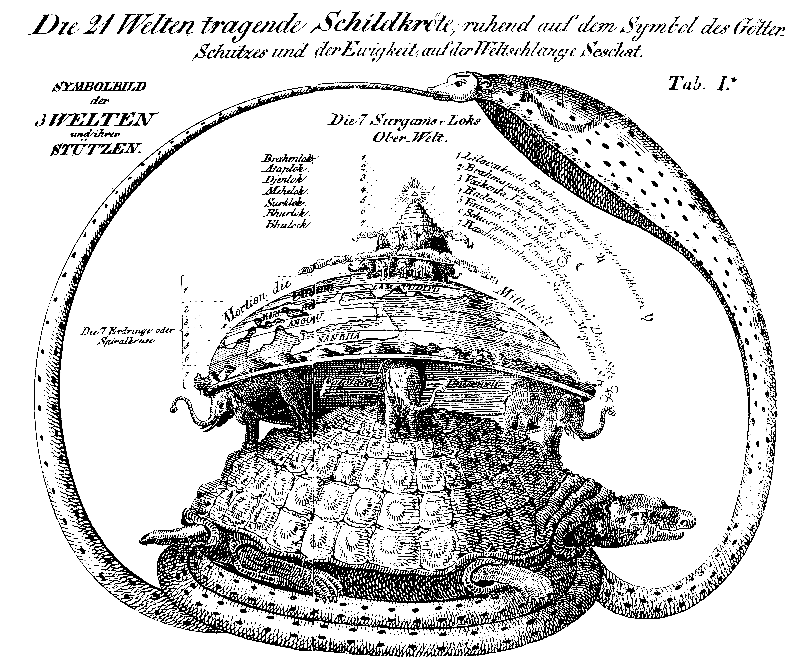
「厚い記述」
Thick description
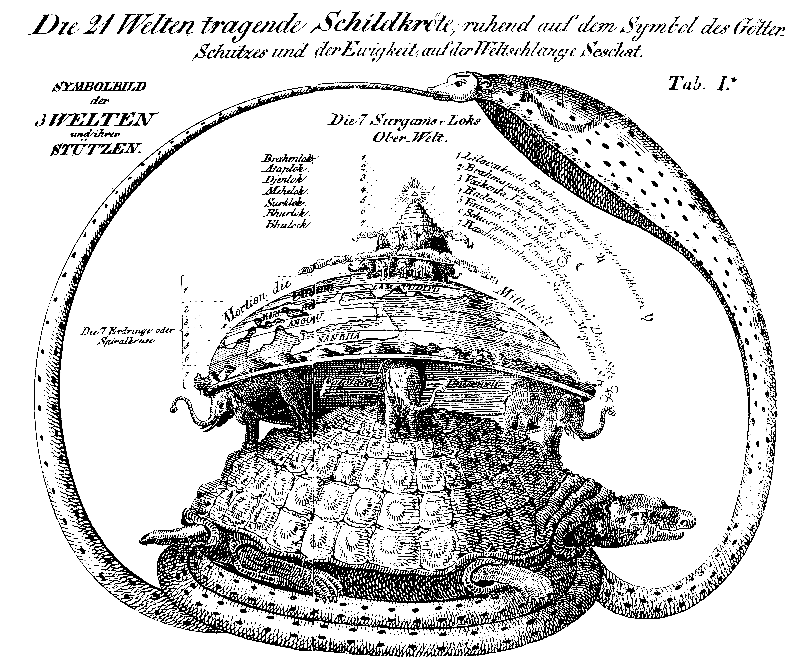
解 説:池田光穂
あ:「厚い記述」 (thick description):厚い記述あるいは分厚い記述とは、米国の文化人 類学者クリフォード・ギアーツ(1926-2006)が同名の論文で提 唱したも のであるが、元々は英国の哲学者ギルバート・ライルによる。人類学者はフィールドワークをするときに、現地の人と仲良くなり、情報を提供してもらう人を探 し、関連文書を写し、系譜関係をとり、付近の地図をつくり、活動の日記などを書く。これらの一連の行為を厚い記述と呼ぶ。そして反対に、薄い記述とは、 「少年が瞬きした」というようにそれ以外に情報のないシンプルな記述をいう。瞬きは、付近にいる誰かに合図したのか、それとも目にゴミが入ったのか、ある いは以前に読んだ小説の感動的な部分を思い出して涙ぐんだのか、などの情報の収集、などの記録の積み重ねにより、少年の瞬きを描いてゆくことを厚い記述と 呼ぶ。フィールドワークではそれだけ記述を重ねることの重要なのだが、事情はそれほど簡単ではない。レヴィ=ストロースは『悲しき熱帯』(1955)で何 日もかけて奥地の住民を探し出したが、必要とする情報が手に入らず、系譜関係の収集などわずか数十分で終わることがあり、そんな徒労の積み重ねがフィール ドワークだという。つまりフィールドワークと厚い記述とは直接の関係性がない。他方で、多くの人類学者は、文化人類学の方法論を知らない時代や人が書いた 旅行記や事件記録などに触れて、自分が積み重ねてきた厚い記述が一瞬にして瓦解するぐらいインパクトがある(=より厚い)ことを感じる。厚い記述は単に自 分のフィールドノートの記録を厚くしてゆくことではない。だからと言って、厚い記述はフィールドワーカーの精神性が可能にするものでもない。逆に厚い記述 をフィールドワークの精神論としてのみ理解するだけでは、決してそのような記述(=厚い記述)が常に可能になるわけではない。
★論文「厚い
記述」研究ノー
トはこちらです.
●テキスト分析
| Thick
Description: Toward an Interpretive Theory of Culture. by Clifford Geertz |
私が支持し、以下のエッセイでその有用性 を示そうとしている文化の概念は、本質的に記号論的なものである。マックス・ウェーバーとともに、人間は自分自身が紡ぎ出した意味の網にぶらさがっている動物であると信じている私は、文化とはその網のこと であり、それを分析することは、したがって、法則性を求める実験科学で はなく、意味を求める内省的で解釈的なものであると考えている。私が 求めているのは、表面上は不可解な社会的表現を解釈するための説明である。しかしながら、この宣言は、一節の中に位置づけられる教義であり、それ自体が何らかの説明を必要とする。 |
| I In her book, Philosophy in a New Key, Susanne Langer remarks that certain ideas burst upon the intellectual landscape with a tremendous force. They resolve so many fundamental problems at once that they seem also to promise that they will resolve all fundamental problems, clarify all obscure issues. Everyone snaps them up as the open sesame of some new positive science, the conceptual center-point around which a comprehensive system of analysis can be built. The sudden vogue of such a grande ideÈ, crowding out almost everything else for a while, is due, she says, "to the fact that all sensitive and active minds turn at once to exploiting it. We try it in every connection, for every purpose, experiment with possible stretches of its strict meaning, with generalizetions and derivatives." After we have become familiar with the new idea, however, after it has become part of our general stock of theoretical concepts, our expectations are brought more into balance with its actual uses, and its excessive popularity is ended. A few zealots persist in the old key-to-the-universe view of it; but less driven thinkers settle down after a while to the problems the idea has really generated. They try to apply it and extend it where it applies and where it is capable of extension; and they desist where it does not apply or cannot be extended. It becomes, if it was, in truth, a seminal idea in the first place, a permanent and enduring part of our intellectual armory. But it no longer has the grandiose, all-promising scope, the infinite versatility of apparent application, it once had. The second law of thermodynamics, or the principle of natural selection, or the notion of unconscious motivation, or the organization of the means of production does not explain everything, not even everything human, but it still explains something; and our attention shifts to isolating just what that something is, to disentangling ourselves from a lot of pseudoscience to which, in the first flush of its celebrity, it has also given rise. Whether or not this is, in fact, the way all centrally important scientific concepts develop, I don't know. But certainly this pattern fits the concept of culture, around which the whole discipline of anthropology arose, and whose domination that discipline has been increasingly concerned to limit, specify, focus, and contain. lt is to this cutting of the culture concept down to size, therefore actually insuring its continued importance rather than undermining it, that the essays below are all, in their several ways and from their several directions, dedicated. They all argue, sometimes explicitly, more often merely through the particular analysis they develop, for a narrowed, specialized, and, so I imagine, theoretically more powerful concept of culture to replace E. B. Tylor's famous "most complex whole," which, its originative power not denied, seems to me to have reached the point where it obscures a good deal more than it reveals. The conceptual morass into which the Tylorean kind of pot-au-feu theorizing about culture can lead, is evident in what is still one of the better general introductions to anthropology, Clyde Kluckhohn`s Mirror for Man. In some twenty-seven pages of his chapter on the concept, Kluckhohn managed to define culture in turn as: "the total way of life of a people"; "the social legacy the individual acquires from his group"; a "way of thinking, feeling, and believing"; an "abstraction from behavior"; a "theory on the part of the anthropologist about the way in which a group of people in fact behave"; a "storehouse of pooled learning"; a "set of standardized orientations to re-current problems"; "learned behavior"; a "mechanism for the normative regulation of behavior"; a "set of techniques for adjusting both to the external environrnent and to other men"; "a precipitate of history"; and turning, perhaps in desperation, to similes, as a map, as a sieve, and as a matrix. In the face of this sort of theoretical diffusion, even a somewhat constricted and not entirely standard concept of culture, which is at least internally coherent and, more important, which has a definable argument to make is (as, to be fair, Kluckhohn himself keenly realized) an improvement. Eclecticism is self-defeating not because there is only one direction in which it is useful to move, but because there are so many: it is necessary to choose. The concept of culture I espouse, and whose utility the essays belowattempt to demonstrate, is essentially a semiotic one. Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search of law but an iterpretive one in search of meaning. It is explication I am after, construing social expressions on their surface enigmatical. But this pro- nouncement, a doctrine in a clause, demands itself some explication. |
I スザンヌ・ランガーは著書『哲学の新鍵』の中で、ある考えが知的風景に突如として現れ、途方もない勢いで広がることを指摘している。 それらの考えは、多くの根本的な問題を一度に解決し、すべての不明瞭な問題を明らかにし、すべての根本的な問題を解決することを約束しているように見え る。 誰もがそれらを新しいポジティブな科学の「開けゴマ」として受け入れ、分析の包括的なシステムを構築できる概念上の中心点として捉える。こうした壮大な理 念が突如として流行し、しばらくの間は他のほとんどのものを駆逐してしまうのは、「敏感で活発な頭脳がすべて、一斉にそれを活用しようとするからだ」と彼 女は言う。私たちはあらゆる関連性において、あらゆる目的のためにそれを試し、厳密な意味の可能な範囲、一般化や派生形を実験する。 しかし、新しい考えに慣れ、それが理論的概念の一般的なストックの一部となった後、私たちの期待は実際の使用とより釣り合うようになり、過剰な人気は終焉 を迎える。少数の狂信者は、依然として「宇宙の鍵」という古い考え方に固執しているが、あまり熱心でない思想家は、しばらくすると、その考え方が実際に生 み出した問題に落ち着く。彼らは、それが適用できる場所や拡張可能な場所では、それを適用し、拡張しようとする。そして、適用できない場所や拡張できない 場所では、それをやめる。 もしそれが真実であれば、それはそもそも、私たちの知的武器庫における恒久的で永続的な一部である、画期的なアイデアとなる。 しかし、それはもはや、かつてのように壮大で、すべてを約束するような範囲、見かけ上の無限の多様性を持つものではない。 熱力学第二法則や自然淘汰の原理、無意識の動機づけの概念、生産手段の組織化などは、すべてを説明しているわけではない。人間に関することですらすべてを 説明しているわけではないが、それでも何かを説明している。そして、私たちの関心は、その「何か」が何なのかを突き止めること、そして、その「何か」が脚 光を浴びた当初に、多くの似非科学を生み出したことから私たち自身を解き放つことに移っている。 これが実際に、すべての重要な科学的概念が発展する過程であるかどうかはわからない。しかし、このパターンは、人類学という学問全体が生まれた文化の概念 に当てはまる。そして、その学問は、文化の支配を制限し、特定し、焦点を絞り、内包することにますます懸念を抱いている。したがって、以下の論文はすべ て、さまざまな方法で、さまざまな方向から、文化の概念を縮小することに専念している。彼らは皆、時に明示的に、より頻繁には彼らが展開する特定の分析を 通じて、E.B.タイラーの有名な「最も複雑な全体」に取って代わる、狭く特化した、そして理論的により強力な文化概念を主張している。その創造力は否定 しないが、私には、明らかにするよりも多くのことを覆い隠しているように見える。 文化に関するタイラー流の寄せ集め理論が陥る概念上の泥沼は、今でも優れた人類学の入門書であるクライド・クルックホーン著『人間を映す鏡』に明らかであ る。クルックホーンは、概念に関する章の27ページで、文化を次のように定義している。 「ある民族の生活様式の総体」、 「個人が所属する集団から獲得する社会的遺産」、 「思考、感情、信念のあり方」、 「行動の抽象化」、 「人類学者が、実際の人々の集団の行動様式について論じた理論」、 「蓄積された知識の宝庫」、 「再発する問題に対する標準化された一連の方向付け」、 「学習された行動」、 「行動の規範的規制のメカニズム」、 「外部環境と他者への適応技術」、 「歴史の沈殿物」、そして、絶望のあまり、地図、ふるい、マトリックスといった比喩に頼る。 このような理論の拡散を前にして、少なくとも内部的に首尾一貫しており、さらに重要なのは、明確な主張を持つ、ある程度限定された標準的ではない文化概念 でさえも(公平に見て、クルックホーン自身も痛感していたように)改善される。折衷主義が自己矛盾に陥るのは、進むべき方向が一つしかないからではなく、 あまりに多くの方向があるからである。選択が必要なのだ。 私が支持する文化の概念、そしてその有用性については、以下の論文で明らかにしようとしているが、それは本質的には記号論的なものである。マックス・ ウェーバーと同様に、人間は自ら紡ぎ出した意味の網に捕らわれた動物であると信じている私は、文化をその網と捉え、その分析は、法則を求める実験科学では なく、意味を求める解釈科学であると考える。私は、その表面的な表現が謎めいている社会的表現を解釈し、その解釈を求めているのだ。しかし、この宣言、つ まり条項の教義は、それ自体に何らかの説明を求めている。 |
| II Operationalism as a methodological dogma never made much sense so far as the social sciences are concerned, and except for a few rather toowell-swept corners--Skinnerian behaviorism, intelligence testing, and so on--it is largely dead now. But it had, for all that, an important point to make, which, however we may feel about trying to define charisma or alienation in terms of operations, retains a certain force: if you want to understand what a science is, you should look in the first instance not at its theories or its findings, and certainly not at what its apologists say about it; you should look at what the practitioners of it do. In anthropology, or anyway social anthropology, what the practioners do is ethnography. And it is in understanding what ethnography is, or more exactly what doing ethnography is, that a start can be made toward grasping what anthropological analysis amounts to as a form of knowledge. This, it must immediately be said, is not a matter of methods. From one point of view, that of the textbook, doing ethnography is establishing rapport, selecting informants, transcribing texts, taking genealogies, mapping fields, keeping a diary, and so on. But it is not these things, techniques and received procedures, that define the enterprise. What defines it is the kind of intellectual effort it is: an elaborate venture in, to borrow a notion from Gilbert Ryle, "thick description." Ryle's discussion of "thick description" appears in two recent essays of his (now reprinted in the second volume of his Collected Papers addressed to the general question of what, as he puts it, "Le Penseur" is doing: "Thinking and Reflecting" and "The Thinking of Thoughts." Consider, he says, two boys rapidly contracting the eyelids of their right eyes. In one, this is an involuntary twitch; in the other, a conspiratorial signal to a friend. The two movements are, as movements, identical; from an l-am-a-camera, "phenomenalistic" observation of them alone, one could not tell which was twitch and which was wink, or indeed whether both or either was twitch or wink. Yet the difference, however unphotographable, between a twitch and a wink is vast; as anyone unfortunate enough to have had the first taken for the second knows. The winker is communicating, and indeed communicating in a quite precise and special way: (1) deliberately, (2) to someone in particular, (3) to impart a particular message, (4) according to a socially established code, and (5) without cognizance of the rest of the company. As Ryle points out, the winker has not done two things, contracted his eyelids and winked, while the twitcher has done only one, contracted his eyelids. Contracting your eyelids on purpose when there exists a public code in which so doing counts as a conspiratorial signal is winking. That's all there is to it: a speck of behavior, a fleck of culture, and--voilý!--a gesture. That, however, is just the beginning. Suppose, he continues, there is a third boy, who, "to give malicious amusement to his cronies," parodies the first boy's wink, as amateurish, clumsy, obvious, and so on. He, of course, does this in the same way the second boy winked and the first twitched: by contracting his right eyelids. Only this boy is neither winking nor twitching, he is parodying someone else's, as he takes it, laughable, attempt at winking. Here, too, a socially established code exists (he will "wink" laboriously, over-obviously, perhaps adding a grimace--the usual artifices of the clown); and so also does a message. Only now it is not conspiracy but ridicule that is in the air. If the others think he is actually winking, his whole project misfires as completely, though with somewhat different results, as if they think he is twitching. One can go further: uncertain of his mimicking abilities, the would-be satirist may practice at home before the mirror, in which case he is not twitching, winking, or parodying, but rehearsing; though so far as what a camera, a radical behaviorist, or a believer in protocol sentences would record: he is just rapidly contracting his right eyelids like all the others. Complexities are possible, if not practically without end, at least logically so. The original winker might, for example, actually have been fake-winking, say, to mislead outsiders into imagining there was a conspiracy afoot when there in fact was not, in which case our descriptions of what the parodist is parodying and the rehearser is rehearsing of course shift accordingly. But the point is that between what Ryle calls the "thin description" of what the rehearser (parodist, winker, twitcher . . .) is doing ("rapidly contracting his right eyelids") and the "thick description" of what he is doing ("practicing a burlesque of a friend faking a wink to deceive an innocent into thinking a conspiracy is in motion") lies the object of ethnography: a stratified hierarchy of meaningful structures in terms of which twitches, winks, fake-winks, parodies, rehearsals of parodies are produced, perceived, and interpreted, and without which they would not (not even the zero-form twitches, which, as a cultural category, are as much non-winks as winks are non-twitches) in fact exist, no matter what anyone did or didn't do with his eyelids. Like so many of the little stories Oxford philosophers like to makeup for themselves, all this winking, fake-winking, burlesque-fake-winking, rehearsed-burlesque-fake-winking, may seem a bit artificial. In way of adding a more empirical note, let me give, deliberately unpreceded by any prior explanatory comment at all, a not untypical excerpt from my own field journal to demonstrate that, however evened off for didactic purposes, Ryle's example presents an image only too exact of the sort of piled-up structures of inference and implication through which an ethnographer is continually trying to pick his way: "The French (the informant said) had only just arrived. They set up twenty or so small forts between here, the town, and the Marmusha area up in the middle of the mountains, placing them on promontories so they could survey the countryside. But for all this they couldn't guarantee safety, especially at night, so although the mezrag (trade-pact-system) was supposed to be legally abolished it in fact continued as before. One night, when Cohen (who speaks fluent Berber) was up there (at Marmusha) two other Jews who were traders to a neighboring tribe came by to purchase some goods from him. Some Berbers--from yet another neighboring tribe--tried to break into Cohen`s place, but he fired his rifle in the air. (Traditionally, Jews were not allowed to carry weapons; but at this period things were so unsettled many did so anyway.) This attracted the attention of the French and the marauders fled. The next night, however, they came back, and one of them disguised as a woman who knocked on the door with some sort of a story. Cohen was suspicious and didn't want to let "her" in, but the other Jews said: "oh, it's all right, it's only a woman." So they opened the door and the whole lot came pouring in. They killed the two visiting Jews, but Cohen managed to barricade himself in an adjoining room. He heard the robbers planning to burn him alive in the shop after they removed his goods, and so he opened the door and--laying about him wildly with a club--managed to escape through a window. He went up to the fort (then) to have his wounds dressed, and complained to the local commandant, one Captain Dumari, saying he wanted his "ar-ie", four or five times the value of the merchandise stolen from him. The robbers were from a tribe which had not yet submitted to French authority and were in open rebellion against it, and he wanted authorization to go with his mezrag-holder, the Marmusha tribal sheikh, to collect the indemnity that, under traditional rules, he had coming to him. Captain Dumari couldn`t officially give him permission to do this--because of the French prohibition of the mezrag relationship--but he gave him verbal authorization saying, "If you get killed, it's your problem." So the sheikh, the Jew, and a small company of armed Marmushans went off ten or fifteen kilometers up into the rehellious area, where there were of course no French, and, sneaking up, captured the thief-tribe's shepherd and stole its herds. The other tribe soon came riding out on horses after them armed with rifles and ready to attack. But when they saw who the "sheep thieves'` were, they thought better of it and said, "all right, we'll talk." They couldn`t really deny what had happened--that some of their men had robbed Cohen and killed the two visitors--and they weren`t prepared to start the serious feud with the Marmusha, a scuffle with the invading party would bring on. So the two groups talked, and talked, and talked, there on the plain amid the thousands of sheep, and decided finally on five-hundred-sheep damagee. Thc two armed Berber groups then lined up on their horse at opposite ends of the plain with the sheep herded between them, and Cohen, in his black gown, pillhox hat, and flapping slippers, went out alone among the sheep, picking out, one hy one and at his own good speed, the best ones for his payment. So Cohen got his sheep and drove them back to Marmusha. The French, up in their fort, heard them coming from some distance ("Ba, ba, ba" said Cohen, happily, recalling the image) and said, ''What the hell is that?" Cohen said "That is my 'ar'." The French couldn't believe he had actually done what he said he had done, and accused him of being a spy for the rebellious Berbers, put him in prison, and took his sheep. In the town, his family, not having heard from him in so long a time, thought he was dead. But after a while the French released him and he came back home, but without his sheep. He then went to the Colonel in the town, the Frenchman in charge of the whole region, to complain. But the Colonel said, "I can't do anything about the matter. It's not my problem." Quoted raw, a note in a bottle, this passage conveys, as any similar one similarly presented would do, a fair sense of how much goes into ethnographic description of even the most elemental sort--how extraordinarily "thick" it is. In finished anthropological writings, including those collected here, this fact--that what we call our data are really our own constructions of other people's constructions of what they and their compatriots are up to--is obscured because most of what we need to comprehend a particular event, ritual, custom, idea, or whatever is insinuated as background information before the thing itself is directly examined. (Even to reveal that this little drama took place in the highlands of central Morocco in 1912--and was recounted there in 1968--is to determine much of our understanding of it. There is nothing particularly wrong with this, and it is in any case inevitable. But it does lead to a view of anthropological research as rather more of an observational and rather less of an interpretive activity than it really is. Right down at the factual base, the hard rock, insofar as there is any, of the whole enterprise, we are already explicating: and worse, explicating explications. Winks upon winks upon winks. Analysis, then, is sorting out the structures of signification--what Ryle called established codes, a somewhat misleading expression, for it makes the enterprise sound too much like that of the cipher clerk when it is much more like that of the literary critic--and determining their social ground and import. Here, in our text, such sorting would begin with distinguishing the three unlike frames ofinterpretation ingredient in the situation, Jewish, Berber, and French, and would then move on to show how (and why) at that time, in that place, their copresence produced a situation in which systematic misunderstanding reduced traditional form to social farce. What tripped Cohen up, and with him the whole, ancient pattern of social and economic relationships within which he functioned, was a confusion of tongues. I shall come back to this too-compacted aphorism later, as well as to the details of the text itself. The point for now is only that ethnography is thick description. What the ethnographer is in fact faced with--except when (as, of course, he must do) he is pursuing the more automatized routines of data collection--is a multiplicity of complex conceptual structures, many of them superimposed upon or knotted into one another, which are at once strange, irregular, and inexplicit, and which he must contrive somehow first to grasp and then to render. And this is true at the most down-to-earth, jungle field work levels of his activity: interviewing informants, observing rituals, eliciting kin terms, tracing property lines, censusing households ... writing his journal. Doing ethnography is like trying to read (in the sense of "construct a reading of') a manuscript--foreign, faded, full of ellipses, incoherencies, suspicious emendations, and tendentious commentaries, but written not in conventionalized graphs of sound but in transient examples of shaped behavior. |
II 方法論上の教義としてのオペレーショナリズムは、社会科学に関して言えば、これまであまり意味をなさなかった。そして、スキナー派の行動主義や知能テスト など、ごく一部の例外を除いては、今ではほぼ死語となっている。しかし、それは重要な指摘を含んでいた。カリスマ性や疎外感を操作という観点から定義しよ うとする際に、私たちがどう感じるかに関わらず、それは依然として一定の力を保っている。科学とは何かを理解したいのであれば、まずその理論や発見に目を 向けるべきであり、その擁護者が語る内容に目を向けるべきではない。科学の実践者が何を行っているかに目を向けるべきである。 人類学、あるいは社会人類学において、実践者が行うことは民族誌学である。民族誌学とは何か、より正確に言えば民族誌学を行うとは何かを理解することか ら、人類学的分析が知識の形態として何を意味するのかを把握するための第一歩が始まる。これは、すぐに言っておかなければならないが、方法の問題ではな い。教科書的な見方をするならば、エスノグラフィーを行うということは、信頼関係を築き、情報提供者を選び、文章を書き起こし、系図を作成し、フィールド をマッピングし、日記をつける、といったことである。しかし、この事業を定義するのは、これらの事柄や技術、定石の手順ではない。 この事業を定義するのは、その知的努力の種類である。ギルバート・ライルの考え方を借りるならば、それは「厚みのある記述」という緻密な事業である。 ライルの「厚い記述」に関する議論は、彼の最近の2つのエッセイに記載されている(現在は、彼の論文集第2巻に再録されている)。その論文では、彼が言う ところの「考える人」が何をしているのかという一般的な問題について、「思考と反省」と「思考の思考」という2つのテーマが扱われている。彼は、右目のま ぶたを素早く閉じる2人の少年について考えている。一方では不随意のまばたきであり、もう一方では友人への共謀的な合図である。この2つの動きは、動きと しては同一である。「現象学的」な観察から、どちらがまばたきでどちらがウィンクなのか、あるいはどちらもまばたきでどちらもウィンクなのかさえも区別す ることはできない。しかし、写真では区別できないとはいえ、まばたきとウインクの違いは大きい。ウインクをする人はコミュニケーションを図っているのだ。 しかも、かなり正確で特別な方法でコミュニケーションを図っている。(1)意図的に、(2)特定の誰かに、(3)特定のメッセージを伝えるために、(4) 社会的に確立された規範に従って、(5)他の人々の存在を意識せずに。ライルが指摘するように、ウィンカーは2つのことをしていない。まぶたを閉じてウィ ンクをしたわけではない。一方、ツイッチャーは1つのことしかしていない。まぶたを閉じただけだ。ウィンクとは、そうすることが共謀の合図として数えられ る公共の規範が存在する中で、意図的にまぶたを閉じることを指す。それだけだ。ほんのわずかな行動、文化の断片、そして――なんとまあ!――ジェスチャー だ。 しかし、それはほんの始まりに過ぎない。もし3人目の少年がいて、その少年が「取り巻きたちに悪意のある楽しみを与えるため」、1人目の少年のウインクを パロディー化し、素人くさく、不器用で、あからさまなウインクをしたとしよう。もちろん、彼は2人目の少年がウィンクをし、1人目の少年がまばたきをした のと同じ方法で、つまり右のまぶたを閉じることでそれを表現する。この少年だけはウィンクもまばたきもしていない。彼は、自分では笑えると思っている他人 のウィンクの真似をしているのだ。ここにもまた、社会的に確立された暗黙のルールが存在する(彼は苦心して、あからさまに、おそらくは不自然な顔をしなが らウィンクするだろう。道化師の常套手段である)。そして、メッセージも存在する。ただし、今や空気中には陰謀ではなく嘲笑が漂っている。もし他の人々が 彼が実際にウィンクしていると考えるなら、彼の計画は完全に失敗するだろう。ただし、他の人々が彼がまばたきしていると考える場合とは、多少異なる結果に なるだろう。さらに踏み込んで言えば、もしも彼が物まねの能力に自信がない場合、風刺作家志望の彼は自宅で鏡の前で練習するかもしれない。その場合、彼は ぴくぴく動いたり、ウィンクをしたり、パロディ化したりしているのではなく、リハーサルをしていることになる。しかし、カメラや過激な行動主義者、あるい はプロトコル文の信奉者が記録する限りにおいては、彼は他の人々と同じように右のまぶたを素早く動かしているだけである。複雑なことは、実際には際限なく とはいかないまでも、少なくとも論理的にはあり得る。 例えば、最初のウインカーは、実際には偽のウインカーだったかもしれない。つまり、陰謀が企てられていると外部の人間に想像させるために、実際には陰謀が 企てられていないのに、陰謀が企てられていると想像させるためにウインカーをしたのかもしれない。その場合、パロディストがパロディしているもの、リハー サーがリハーサルしているものの記述は、当然ながらそれに応じて変化する。しかし、重要なのは、ライルが「薄い記述」と呼ぶ、リハーサルを行う者(パロ ディスト、ウィンカー、ツイッチャーなど)が何をしているかについての記述(「右のまぶたを素早く閉じる」)と、「厚い記述」と呼ばれる、彼が何をしてい るかについての記述(「友人がウインクのふりをして無実の人を欺き、陰謀が進行中であると思わせるという茶番劇の練習」)との間にある、民族誌学の対象で ある。それによって、まばたき、ウインク、偽ウインク、パロディ、パロディのリハーサルが作り出され、認識され、解釈される。そして、それなしには、まば たきもウインクも存在しない(文化カテゴリーとして、まばたきはウインクではないのと同様に、ウインクはまばたきではない)。誰がまぶたをどうしようと、 それは変わらない。 オックスフォードの哲学者たちが好んで作り出す多くの小さな物語と同様に、ウィンク、偽ウィンク、パロディの偽ウィンク、リハーサルされたパロディの偽 ウィンクなど、すべてが少し人工的に思えるかもしれない。より実証的な注釈を加えるために、意図的にこれまでの説明的なコメントとは全く異なる、私自身の フィールド・ジャーナルから典型的な抜粋を提示しよう。教訓的な目的のために平準化されているとはいえ、ライルの例は、民族誌学者が常にその道を選びなが ら進んでいくような、推論と暗示の積み重なった構造を正確に表現している。 「フランス人(情報提供者によると)は、ちょうど到着したばかりだった。彼らは、この場所と町、そして山の中腹にあるMarmusha地域との間に、20 ほどの小さな砦を設置した。それらの砦は、半島に設置され、周辺の状況を監視できるようにしていた。しかし、これだけのことをしても、特に夜間は安全を保 証することはできなかったため、mezrag(貿易協定システム)は法律上廃止されたはずだったが、実際には以前と同様に継続されていた。 ある夜、ベルベル語を流暢に話すコーエンがマルムーシャにいたところ、近隣の部族と取引をする2人のユダヤ人がやって来て、彼から商品をいくつか購入し た。別の近隣の部族から来たベルベル人の一部がコーエンの家に押し入ろうとしたが、彼はライフルを空に向けて発砲した。(伝統的に、ユダヤ人は武器の携帯 を許されていなかったが、この時代は非常に不安定な状況であったため、多くの人が武器を携帯していた。) これにフランス軍が目を付け、略奪者たちは逃げ去った。しかし翌晩、彼らは戻ってきて、そのうちの一人が女に変装し、何か用事があると言ってドアをノック した。コーエンは疑い、その「女」を家に入れたくなかったが、他のユダヤ人たちは「大丈夫、ただの女だ」と言った。そこで彼らはドアを開け、全員が押し 入ってきた。彼らは訪問していた2人のユダヤ人を殺したが、コーエンはなんとか隣の部屋に立てこもった。彼は強盗たちが商品を運び出した後、店の中で彼を 生きたまま焼くつもりであることを聞き、ドアを開け、棍棒を振り回しながら、なんとか窓から逃げ出した。 彼は傷の手当てを受けるために砦に向かい、地元の司令官であるデュマリ大尉に、盗まれた商品の4~5倍の価値がある「アーリー」が欲しいと訴えた。強盗犯 はフランス当局に服従していない部族の一員であり、公然と反旗を翻していた。彼は、伝統的なルールに従って彼に支払われるべき損害賠償金を集めるために、 メズラグホルダーであるマルムーシャ族の族長と共に外出する許可を求めた。デュマリ大尉は、メズラグ関係を禁じるフランス軍の規則を理由に、彼に公式に許 可を与えることはできなかったが、「もし殺されても、それは君の問題だ」と口頭で許可を与えた。 そこで、その首長とユダヤ人、そして武装した少数のマームシャン族の一団は、10キロか15キロ奥地にある、もちろんフランス人のいない地獄のような地域 へと向かい、忍び寄って盗賊の一族の羊飼いを捕らえ、その群れを奪った。 他の一族はすぐにライフル銃を携行して馬で追いかけてきて、攻撃の構えを見せた。しかし、彼らは「羊泥棒」が誰なのかを知ると、考えを変え、「わかった、 話し合おう」と言った。彼らは、自分たちの仲間がコーエンを襲い、訪問者2人を殺したという事実を否定することはできなかった。また、彼らは、マームー シャとの深刻な対立、つまり侵略者たちとの争いを始める準備ができていなかった。そこで、2つのグループは羊数千頭が草を食む平原で話し合い、話し合い、 話し合い、最終的に500頭の羊の損害賠償で合意した。武装したベルベル人の2つのグループは、平原の両端に馬を並べて立ち、その間に羊を追い込んだ。そ して、黒いガウンと山高帽、はき古したスリッパ姿のコヘンは、羊の群れの中に一人で入り、自分の報酬にふさわしい羊を一匹ずつ、自分のペースで選び出し た。 こうしてコヘンは羊を手に入れ、マルムーシャまで羊を追い立てて戻った。フランス兵たちは砦に上り、遠くから羊の足音を聞いた(「バ、バ、バ」とコヘンは 楽しそうに言い、その様子を思い出した)。そして、「一体何だ?」と言った。コヘンは「それは私の羊だ」と答えた。フランス兵たちは、彼が本当に自分が 言ったことをしたとは思えず、反乱を起こしたベルベル人のスパイだと彼を非難し、牢屋に入れ、彼の羊を奪った。町では、彼の家族は長い間彼から連絡がな かったため、彼が死んだと思っていた。しかししばらくしてフランス軍は彼を釈放し、彼は家に戻ってきたが、羊はもういなかった。彼は町の大佐のもとへ行 き、その地域全体を統括するフランス人に対して苦情を申し立てた。しかし大佐は「私はこの件について何もできない。私の問題ではない」と言った。 引用された生のままの、ボトルに入れられたメモ、この一節は、同様のものが提示される場合と同様に、最も基本的な種類の民族誌的記述にどれほどの労力が費 やされるか、すなわち、それがいかに「厚み」のあるものかを、十分に伝えている。ここに集められたものも含め、完成した人類学の著作では、私たちがデータ と呼ぶものは、実際には自分たちが他の人々について構築したものを、さらにその人々が自分たちや同胞について構築したものだという事実が隠されている。な ぜなら、特定の出来事、儀式、習慣、考え、あるいはその他のものを理解するために必要なもののほとんどは、そのもの自体が直接的に調査される前に、背景情 報としてほのめかされるからだ。(この小さなドラマが1912年にモロッコ中央部の高地で起こり、1968年にそこで語られたことを明らかにするだけで も、それに対する我々の理解の多くが決まってしまう。これ自体は特に問題があるわけではなく、いずれにしても避けられない。しかし、それは人類学的研究 を、実際よりも観察的で解釈的でない活動として捉える見方につながる。 事実の基盤、すなわち、この事業全体における硬い岩、それが存在する限りにおいて、私たちはすでに説明している。さらに悪いことに、説明の説明をしてい る。ウィンクにウィンクを重ねてウィンク。分析とは、すなわち、ライルが「確立されたコード」と呼んだもの、つまり、いくらか誤解を招きやすい表現である が、それは、この事業が暗号解読者のそれのように聞こえるが、実際には文芸評論家のそれにより近いという意味で、意味の構造を整理し、その社会的基盤と重 要性を決定することである。このテキストでは、まずユダヤ人、ベルベル人、フランス人という、状況における3つの異なる解釈の枠組みを区別することから始 め、次に、なぜ、そしてどのようにして、その時代、その場所で、それらの共存が体系的な誤解によって伝統的な形式が社会的な茶番劇へと変質する状況を生み 出したのかを明らかにする。彼を、そして彼が機能していた社会経済関係の全体的な古代のパターンを混乱させたのは、言語の混乱であった。 この簡潔な格言については、また後で、テキストの詳細についても触れることにする。ここで重要なのは、民族誌学は詳細な記述であるということだけだ。民族 誌学者が実際に直面するものは、より自動化されたデータ収集のルーチンを追及している場合(もちろん、そうしなければならない)を除いて、複雑な概念構造 の多様性であり、それらの多くはお互いに重なり合ったり、絡み合ったりしている。それらは同時に奇妙で、不規則で、曖昧であり、民族誌学者はまずそれを把 握し、次に表現する方法を考え出さなければならない。これは、彼が実際に現地で行う最も地に足のついたジャングルでのフィールドワーク、すなわち情報提供 者へのインタビュー、儀式の観察、親族関係の聞き取り、所有権の追跡、世帯調査、そして日記の執筆といった活動においても同様である。 民族誌学を行うことは、原稿を(「解釈を構築する」という意味で)読もうとするようなものだ。原稿は、外国語で書かれており、色あせており、省略や矛盾、 疑わしい修正、偏った論評が満載だが、音の定型化されたグラフではなく、形作られた行動の一時的な例として書かれている。 |
| III Culture, this acted document, thus is public, like a burlesqued wink or a mock sheep raid. Though ideational it does not exist in someone's head; though unphysical is not an occult entity. The interminable, because unterminable, debate within anthropology as to whether culture is "subjective" or "objective," together with the mutual exchange of intellectual insults ("idealist!"--"materialist!"; "mentalist!"--`'behaviorist!"; "impressionist!"--"positivist!") which accompanies it, is wholly misconceived. Once human behavior is seen as (most of the time; there are true twitches) symbolic action which, like phonation in speech, pigment in painting, line in writing, or sonance in music, signifies, the question as to whether culture is patterned conduct or a frame of mind, or even the two somehow mixed together, loses sense. The thing to ask about a burlesqued wink or a mock sheep raid is not what their ontological status is. It is the same as that of rocks on the one hand and dreams on the other--they are things of this world. The thing to ask is what their import is: what it is, ridicule or challenge, irony or anger, snobbery or pride, that in their occurrence and through their agency, is getting said. This may seem like an obvious truth, but there are a number of ways to obscure it. One is to imagine that culture is a self-contained "super-organic" reality with forces and purposes of its own; that is, to reify it. Another is to claim that it consists in the brute pattern of behavioral events we observe in fact to occur in some identifiable community or other; that is, to reduce it. But though both these confusions still exist, and doubtless will be always with us, the main source of theoretical muddlement in contemporary anthropology is a view which developed in reaction to them and is right now very widely held--namely, that, to quote Ward Goodenough, perhaps its leading proponent, "culture [is located] in the minds and hearts of men." Variously called ethnoscience, componential analysis, or cognitive anthropology (a terminological wavering which reflects a deeper uncertainty), this school of thought holds that culture is composed of psychological structures by means of which individuals or groups of individuals guide their behavior. "A society's culture," to quote Goodenough again, this time in a passage which has become the locus classsicus of the whole movement, "consists of whatever it is one has to know or believe in order to operate in a manner acceptable to its members." And from this view of what culture is follows a view, equally assured, of what describing it is --the writing out of systematic rules, an ethnographic algorithm, which, if followed, would make it possible so to operate, to pass (physical appearance aside) for a native. In such a way, extreme subjectivism is married to extreme formalism, with the expected result: an explosion of debate as to whether particular analyses (which come in the form of taxonomies, paradigms, tables, trees, and other ingenuities) reflect what the natives "really" think or are merely clever simulations, logically equivalent but substantively different, of what they think. As, on first glance, this approach may look close enough to the one being developed here to be mistaken for it, it is useful to be explicit as to what divides them. If, leaving our winks and sheep behind for the moment, we take, say, a Beethoven quartet as an, admittedly rather special but, for these purposes, nicely illustrative sample of culture, no one would, I think, identify it with its score, with the skills and knowledge needed to play it, with the understanding of it possessed by its performers or auditors, nor, to take care, en passant, by the view of the reductionists and reifiers: with a particular performance of it or with some mysterious entity transcending material existence. The "no one" is perhaps too strong here, for there are always incorrigibles. But that a Beethoven quartet is a temporally developed tonal structure, a coherent sequence of musical sound--in a word, music--and not anybody's knowledge c-f or belief about anything, including how to play it, is a proposition to which most people are, upon reflection, likely to assent. To play the violin it is necessary to possess certain habits, skills, knowledge, and talents, to be in the mood to play, and (as the old joke goes) to have a violin. But violin playing is neither the habits, skills, knowledge, and so on, nor the mood, nor (the notion believers in "material culture" apparently embrace) the violin. To make a trade pact in Morocco, you have to do certain things in certain ways (among others, cut, while chanting Quranic Arabic, the throat of a lamb before the assembled, undeformed, adult male members of your tribe) and to be possessed of certain psychological characteristics (among others, a desire for distant things). But a trade pact is neither the throat cutting nor the desire, though it is real enough, as seven kinsmen of our Marmusha sheikh discovered when, on an earlier occasion, they were executed by him following the theft of one mangy, essentially valueless sheepskin from Cohen. Culture is public because meaning is. You can't wink (or burlesque one) without knowing what counts as winking or how, physically, to contract your eyelids, and you can't conduct a sheep raid (or mimic one) without knowing what it is to steal a sheep and how practically to go about it. But to draw from such truths the conclusion that knowing how to wink is winking and knowing how to steal a sheep is sheep raiding is to betray as deep a confusion as, taking thin descriptions for thick, to identify winking with eyelid contractions or sheep raiding with chasing woolly animals out of pastures. The cognitivist fallacy--that culture consists (to quote another spokesman for the movement, Stephen Tyler) of "mental phenomena which can [he means"should"] be analyzed by normal methods similar to those of mathematics and logic"--is as destructive of an effectivc use of the concept as are the behaviorist and idealist fallacies to which it is a misdrawn correction. Perhaps, as its errors are more sophisticated and its distortions subtler, it is even more so. The generalized attack on privacy theories of meaning is, since early Husserl and late Wittgenstein, so much a part of modern thought that it need not be developed once more here. What is necessary is to see to it that the news of it reaches anthropology; and in particular that it is made clear that to say that culture consists of socially establishcd structures of meaning in terms of which people do such things as signal conspiracies and join them or perceive insults and answer them, is no moreto say that it is a psychological phenomenon, a characteristic of someone's mind, personality, cognitive structure, or whatever, than to say that Tantrism, genetics, the progressive form of the verb, the classification of wines, the Common Law, or the notion of "a conditional curse" (as Westermarck defined the concept of 'ar in terms of which Cohen pressed his claim to damages) is. What, in a place like Morocco, most prevents those of us who grew up winking other winks or attending other sheep from grasping what people are up to is not ignorance as to how cognition works (though, especially as, one assumes, it works the same among them as it does among us, it would greatly help to have less of that too) as a lack of familiarity with the imaginative universe within which their acts are signs. As Wittgenstein has been invoked, he may as well be quoted: "We ... say of some people that they are transparent to us. It is, however important as regards this observation, that one human being can be a complete enigma to another. We learn this when we come into a strange country with entirely strange traditions; and. what is more, even given a mastery of the country's language. We do not understand the people. (And not because of not knowing what they are saying to themselves.) We cannot find our feet with them." |
III 文化、この行為された文書は、したがって、パロディ化されたウィンクや模造羊の襲撃のように、公的なものである。観念的なものではあるが、誰かの頭の中に あるわけではない。非物質的なものではあるが、隠れた実体があるわけでもない。文化が「主観的」なのか「客観的」なのかという人類学における果てしない (そして終わりのない)議論、そしてそれに伴う知的侮辱の応酬(「観念論者!」、「唯物論者!」、「精神論者!」、「行動主義者!」、「印象論者!」、 「実証主義者!」)は、まったく見当違いである。人間の行動が(ほとんどの場合、真の奇癖もあるが)音声における発声、絵画における顔料、文章における 行、音楽における音高のように象徴的な行動であると見なされれば、文化が型にはまった行動なのか、あるいは心のあり方なのか、あるいはその両方が何らかの 形で混ざり合っているのかという疑問は意味をなさなくなる。茶化されたウィンクや模造の羊襲撃について問うべきことは、それらの存在論的な地位が何である かではない。それは一方では岩であり、他方では夢であることと同じである。問うべきことは、それらの意味合いが何であるかということだ。すなわち、嘲笑な のか挑戦なのか、皮肉なのか怒りなのか、俗物根性なのか誇りなのか、それらが引き起こす出来事や、それらを通じて語られる言葉が何であるかということだ。 これは自明の理のように思えるかもしれないが、それを不明瞭にする方法は数多くある。そのひとつは、文化とは独自の力と目的を持つ自己完結した「超有機 的」現実であると想像すること、つまり文化を実体化することである。 もうひとつは、文化とは、実際にある特定のコミュニティやその他の場所で起こっていると観察される行動の出来事の、単純なパターンで構成されていると主張 すること、つまり文化を還元することである。 しかし、こうした混乱はいまだに存在しており、今後も常に付きまとうだろうが、現代の文化人類学における理論的な混迷の主な原因は、それらへの反動として 発展し、現在では広く受け入れられている見解である。すなわち、おそらくその主唱者であるウォード・グッドイナフの言葉を引用すれば、「文化は人間の心と 精神の中にある」というものである。 この学派は、文化は個人または個人の集団が自らの行動を導くための心理的構造から成り立っていると考える。この学派は、エスノサイエンス、コンポーネン シャル・アナリシス、または認知人類学など、さまざまな名称で呼ばれている(用語の揺れは、より深い不確実性を反映している)。グッドイナフの言葉を再び 引用すると、「社会の文化」とは、「その社会の構成員が受け入れるやり方で活動するために、知っておくべきことや信じていることのすべてから構成される」 のである。そして、文化とは何かというこの見解から、文化を記述するとはどういうことかという、同様に確かな見解が導かれる。体系的な規則を書き出すこ と、民族誌的アルゴリズムに従うこと、そうすれば、その文化で活動し、通過(外見はともかく)することが可能になる。このように、極端な主観主義と極端な 形式主義が結びつき、期待通りの結果がもたらされる。すなわち、特定の分析(分類、パラダイム、表、ツリー、その他の工夫を凝らした形式)が、ネイティブ が「本当に」考えていることを反映しているのか、それとも、彼らが考えていることの論理的に等価だが本質的に異なる巧妙なシミュレーションに過ぎないの か、という点について、議論が沸騰するのだ。 一見したところ、このアプローチはここで展開されているアプローチと十分に似ているように見えるため、混同される可能性がある。それらを区別する点を明確 にしておくことは有益である。ウィンクや羊はひとまず置いておいて、例えばベートーベンの四重奏曲を、確かにかなり特殊ではあるが、この目的のためには文 化をうまく例示するサンプルとして取り上げる。誰もそれを楽譜や、演奏に必要なスキルや知識、 演奏に必要なスキルや知識、演奏者や聴衆の理解力、さらには、一応言っておくと還元論者や実体論者の見解とも関連するが、特定の演奏や物質的存在を超越し た神秘的な存在とも関連付けることはないだろう。「誰も」というのは、おそらく言い過ぎかもしれない。なぜなら、救いようのない人も常に存在するからだ。 しかし、ベートーヴェンの四重奏曲は、時間とともに展開する調性構造であり、音楽的な音の首尾一貫した連続体であり、つまり一言で言えば音楽であり、演奏 方法を含め、誰の知識や信念でもないということは、ほとんどの人が考えれば同意するであろう命題である。バイオリンを演奏するには、ある種の習慣、スキ ル、知識、才能、そして演奏する気分になること、そして(古いジョークにあるように)バイオリンを持っていることが必要だ。しかし、バイオリン演奏は、習 慣、スキル、知識などでもなく、気分でもなく、(「物質文化」の信奉者が抱く考えのように)バイオリンでもない。モロッコで貿易協定を結ぶには、特定の事 柄を特定の方法で行わなければならない(例えば、コーランの教えに従ってアラビア語を唱えながら、集まった部族の成人男性たちの前で子羊の喉を切り裂くな ど)。また、特定の心理的特性(例えば、遠く離れたものへの欲望)も必要である。しかし、貿易協定は喉を切ることでも、欲望でもない。しかし、それは十分 に現実的なことである。以前、マームーシャ族の族長が、コーエン族から一匹の痩せこけた、実質的には価値のない羊の皮を盗んだとして、彼を処刑した際、彼 らの7人の親族がそれを発見した。 文化が公共的なのは、意味が公共的なからだ。ウィンク(またはそのパロディ)をするには、ウィンクと見なされるものや、物理的にどのようにまぶたを閉じる かを知らなければならない。また、羊泥棒(またはそのパロディ)をするには、羊を盗むとはどういうことか、また、実際的にどのように行うかを知らなければ ならない。しかし、そのような真実から、ウィンクの仕方を理解することがウィンクであり、羊を盗む方法を理解することが羊の強奪であるという結論を導き出 すことは、ウィンクをまぶたの収縮と同一視したり、羊の強奪を牧草地から羊毛の動物たちを追い出すことと同一視したりするような、同様に根深い混乱を招く ことになる。認知論の誤謬、すなわち文化とは(この運動の別のスポークスマンであるスティーブン・タイラーの言葉を引用すれば)「数学や論理学と同様の通 常の方法で分析できる(すべきである)」精神現象であるという誤謬は、行動主義や観念論の誤謬が誤った修正であるのと同様に、概念の有効な使用を破壊する ものである。おそらく、その誤謬はより洗練され、その歪曲はより巧妙であるため、さらにその傾向が強い。 意味のプライバシー理論に対する一般的な攻撃は、初期のフッサールや後期のウィトゲンシュタイン以来、現代思想の一部となっているため、ここで改めて展開 する必要はない。必要なのは、そのニュースが人類学に届くようにすることであり、特に、文化が社会的に確立された意味の構造から成り立っているということ が、人々が共謀の合図を察知してそれに加わる、あるいは侮辱を察知してそれに答えるといったことを行う際の基準である、ということが、心理的な現象、つま り、 タントリズム、遺伝学、動詞の進行形、ワインの分類、コモン・ロー、あるいは「条件付きの呪い」という概念(ウェスターマルクが「ar」という概念を定義 したように、コーエンが損害賠償請求を主張した際の条件)がそうであるというよりも、誰かの心、性格、認知構造、あるいはその他の特性であるというより も、文化であるという方がより適切である。モロッコのような場所で、私たちが他者と目配せを交わしたり、他の羊の群れに加わったりして育った場合、人々が 何を企んでいるのかを理解するのを妨げるのは、認知の仕組みに関する無知ではない(ただし、特に彼らの間でも私たちと同じように認知が機能していると仮定 するならば、その無知もかなり役立つだろう)。ウィトゲンシュタインが引用されたように、次のように引用してもよいだろう。 「我々は...ある人々について、彼らは我々に対して透明であると言う。しかし、この観察に関して重要なのは、ある人間が別の人間にとって完全な謎である 可能性があるということだ。我々は、まったく見知らぬ伝統を持つ見知らぬ国に来たときに、このことを学ぶ。さらに、その国の言語を完全に習得していたとし ても、我々は彼らを理解できない。(彼らが自分自身に何を言っているのか知らないからではない。)我々は彼らと一緒にいると、自分の足場を見失うのだ。」 |
| IV Finding our feet, an unnerving business which never more than distantly succeeds, is what ethnographic research consists of as a personal experience; trying to formulate the basis on which one imagines, always excessively, one has found them is what anthropological writing consists of as a scientific endeavor. We are not, or at least I am not, seeking either to become natives (a compromised word in any case) or to mimic them. Only romantics or spies would seem to find point in that. We are seeking, in the widened sense of the term in which it encompasses very much more than talk, to converse with them, a matter a great deal more difflcult, and not only with strangers, than is commonly recognized. "If speaking for someone else seems to be a mysterious process," Stanley Cavell has remarked, ''that may be because speaking to someone does not seem mysterious enough". Looked at in this way, the aim of anthropology is the enlargement of the universe of human discourse. That is not, of course, its only aim--instruction, amusement, practical counsel, moral advance, and the discovery of natural order in human behavior are others; nor is anthropology the only discipline which pursues it. But it is an aim to which a semiotic concept of culture is peculiarly well adapted. As interworked systems of construable signs (what, ignoring provincial usages, I would call symbols), culture is not a power, something to which social events, behaviors, institutions, or processes can be causally attributed; it is a context, something within which they can be intelligibly--that is, thickly--described. The famous anthropological absorption with the (to us) exotic Berber horsemen, Jewish peddlers, French Legionnaires--is, thus, essentially a device for displacing the dulling sense of familiarity with which the mysteriousness of our own ability to relate perceptively to one another is concealed from us. Looking at the ordinary in places where it takes unaccustomed forms brings out not, as has so often been claimed, the arbitrariness of human behavior (there is nothing especially arbitrary about taking sheep theft for insolence in Morocco), but the degree to which its meaning varies according to the pattern of life by, which it is informed. Understanding a people's culture exposes their normalness without reducing their particularity. (The more I manage to follow what the Moroccans are up to, the more logical, and the more singular, they seem.) It renders them accessible: setting them in the frame of their own banalities, it dissolves their opacity. It is this maneuver, usually too casually referred to as "seeing things from the actor's point of view," too bookishly as "the verstehen approach," or too technically as "emic analysis," that so often leads to the notion that anthropology is a variety of either long-distance mind reading or cannibal-isle fantasizing, and which, for someone anxious to navigate past the wrecks of a dozen sunken philosophies, must therefore be executed with a great deal of care. Nothing is more necessary to comprehending what anthropological interpretation is, and the degree to which it i.s interpretation, than an exact understanding of what it means--and what it does not mean--to say that our formulations of other peoples' symbol systems must be actor-oriented.1 '"Not only other peoples": anthropology can be trained on the culture of which it is itself a part, and it increasingly is; a fact of profound importance, but which, as it raises a few tricky and rather special second order problems, I shall put to the side for the moment. What it means is that descriptions of Berber, Jewish, or French culture must be cast in terms of the constructions we imagine Berbers, Jews, or Frenchmen to place upon what they live through, the formulae they use to define what happens to them. What it does not mean is that such descriptions are themselves Berber, Jewish, or French--that is, part of the reality they are ostensibly describing; they are anthropological --that is, part of a developing system of scientific analysis. They must be cast in terms of the interpretations to which persons of a particular denomination subject their experience, because that is what they profess to be descriptions of; they are anthropological because it is, in fact, anthropologists who profess them. Normally, it is not necessary to point out quite so laboriously that the object of study is one thing and the study of it another. It is clear enough that the physical world is not physics and A Skelton Key to Finnegan's Wake is not Finnegan's Wake. But, as, in the study of culture, analysis penetrates into the very body of the object--that is, we begin with our own interpretations of what our informants are up to, or think they are up to, and then systematize those--the line between (Moroccan) culture as a natural fact and (Moroccan) culture as a theoretical entity tends to get blurred. All the more so, as the latter is presented in the form of an actor's-eye description of (Moroccan) conceptions of everything from violence, honor, divinity, and justice, to tribe, property, patronage, and chiefship. In short, anthropological writings are themselves interpretations, and second and third order ones to boot. (By definition, only a "native" makes first order ones: it's his culture.)2 They are, thus, fictions; fictions, in the sense that they are "something made," "something fashioned"--the original meaning of fictiÙ--not that they are false, unfactual, or merely "as if" thought experiments. To construct actor-oriented descriptions of the involvements of a Berber chieftain, a Jewish merchant, and a French soldier with one another in 1912 Morocco is clearly an imaginative act, not all that different from constructing similar descriptions of, say, the involvements with one another of a provincial French doctor, his silly, adulterous wife, and her feckless lover in nineteenth century France. In the latter case, the actors are represented as not having existed and the events as not having happened, while in the former they are represented as actual, or as having been so. This is a difference of no mean importance; indeed, precisely the one Madame Bovary had difficulty grasping. But the importance does not lie in the fact that her story was created while Cohen's was only noted. The conditions of their creation, all "the point of it (to say nothing of the manner and the quality) differ. But the one is as much a fictiÙ--a making"--as the other. Anthropologists have not always been as aware as they might be of this fact: that although culture exists in the trading post, the hill fort, or the sheep run, anthropology exists in the book, the article, the lecture, the museum display, or, sometimes nowadays, the film. To become aware of it is to realize that the line between mode of representation and substantive content is as undrawable in cultural analysis as it is in painting; and that fact in turn seems to threaten the objective status of anthropological knowledge by suggesting that its source is not social reality but scholarly artifice. It does threaten it, but the threat is hollow. The claim to attention of an ethnographic account does not rest on its author's ability to capture primitive facts in faraway places and carry them home like a mask or a carving, but on the degree to which he is able to clarify what goes on in such places, to reduce the puzzlement--what manner of men are these?--to which unfamiliar acts emerging out of unknown backgrounds naturally give rise. This raises some serious problems of verification, all right--or, if "verification" is too strong a word for so soft a science (I, myself, would prefer "appraisal"), of how you can tell a better account from a worse one. But that is precisely the virtue of it. If ethnography is thick description and ethnographers those who are doing the describing, then the determining question for any given example of it, whether a field journal squib or a Malinowski-sized monograph, is whether it sorts winks from twitches and real winks from mimicked ones. It is not against a body of uninterpreted data, radically thinned descriptions, that we must measure the cogency of our explications, but against the power of the scientific imagination to bring us into touch with the lives of strangers. It is not worth it, as Thoreau said, to go round the world to count the cats in Zanzibar. |
IV 足場を固め、成功とは言えない不安な事業を経験することが、個人的な経験としての民族誌学調査である。そして、その基盤を構築しようと試みることが、科学 的努力としての人類学的な記述である。我々は、少なくとも私は、現地人になること(いずれにしても妥協的な言葉である)や、彼らを模倣することを求めてい るわけではない。そこに意義を見出すのは、ロマン主義者かスパイくらいだろう。私たちは、会話というよりもはるかに多くのことを包含する広義の言葉の意味 において、彼らと会話することを求めている。それは、一般的に認識されているよりもはるかに困難なことであり、見知らぬ人との会話だけにとどまらない。 「他者の代弁が不可解なプロセスであるように見えるなら、それは他者との会話がそれほど不可解ではないからかもしれない」とスタンリー・キャヴェルは述べ ている。 このように考えると、人類学の目的は、人間の談話の世界を拡大することである。もちろん、人類学の目的はそれだけではない。教育、娯楽、実用的な助言、道 徳的向上、人間行動における自然秩序の発見なども目的である。また、人類学が唯一それを追求する学問というわけでもない。しかし、記号論的文化概念が特に 適している目的である。解釈可能な記号(地方の慣習を無視して私が「シンボル」と呼ぶもの)の相互に作用するシステムとして、文化は力ではなく、社会的出 来事、行動、制度、またはプロセスに因果関係を帰属させることができるものでもない。文化とは文脈であり、その中でそれらは理解可能に、つまり濃密に記述 できるものである。 有名な人類学における、私たちにとってエキゾチックなベルベルの騎馬民族、ユダヤ人の行商人、フランス外人部隊への関心は、本質的には、私たちがお互いを 洞察力を持って理解し合う能力の神秘性が私たちから隠されている、鈍感な親近感を置き換えるための手段である。非日常的な場所で日常的なものを見ると、こ れまで何度も主張されてきたように、人間の行動の恣意性が明らかになるわけではない(モロッコで羊の盗難を無礼とみなすことに特に恣意性はない)。そうで はなく、その意味が、その意味が伝えられる生活様式のパターンによってどの程度変化するかが明らかになるのだ。ある民族の文化を理解することは、その特殊 性を損なうことなく、その普通さを明らかにする。(モロッコ人が何をしようとしているのかを理解しようとすればするほど、彼らはより論理的で、より特異に 思える。)彼らを身近に感じられるようにする。彼らを彼ら自身の平凡さの枠組みに位置づけることで、彼らの不可解さを解消する。 この手法は、通常、「役者の視点から物事を見る」というあまりにも安易な表現で、あるいは「理解するアプローチ」というあまりにも学術的な表現で、あるい は「エマティック分析」というあまりにも専門的な表現で言及されることが多い。このため、人類学は遠距離での読心術や人食い人種の島での空想の類であると いう考えにつながることが多い。そして、1ダースもの沈没した哲学の残骸を乗り越えようとする人にとっては、人類学は細心の注意を払って実行されなければ ならない。人類学的な解釈とは何か、またそれがどの程度解釈であるかを理解する上で、他者の象徴体系の解釈は行為者志向的でなければならないということが 何を意味し、何を意味しないのかを正確に理解することほど必要なことはない。1 「他民族」だけでなく:人類学は、それ自体がその一部である文化を研究対象とすることができる。そして、ますますそうなりつつある。これは非常に重要な事 実であるが、いくつかの厄介でかなり特殊な二次的な問題を引き起こすため、ここではひとまず脇に置いておく。 つまり、ベルベル人、ユダヤ人、フランス人の文化についての記述は、彼らが経験したことや、彼らに起こったことを定義するために彼らが用いる公式を、我々 が想像するベルベル人、ユダヤ人、フランス人の構築物という観点から捉えなければならないということだ。 つまり、そうした記述自体がベルベル人、ユダヤ人、フランス人であるということではない。つまり、それらは表面的に記述されている現実の一部であり、人類 学的なものである。つまり、科学的な分析の体系の一部である。なぜなら、それらは特定の宗派の人々が自らの経験を解釈したものであるからだ。なぜなら、そ れらを公言しているのは人類学者だからだ。通常、研究対象と研究とは別物であることをこれほどまでに骨を折って指摘する必要はない。物理的世界は物理学で はないし、『フィネガンズ・ウェイク』のスケルトン・キーは『フィネガンズ・ウェイク』ではないことは明らかである。しかし、文化研究においては、分析が 対象の核心にまで入り込んでいく。つまり、情報提供者が何をしようとしているのか、あるいは何をしようとしていると思っているのかについて、まず自分なり の解釈から始め、それを体系化していく。そのため、(モロッコの)文化という自然的事実と(モロッコの)文化という理論上の存在との境界線は曖昧になりが ちである。後者が、暴力、名誉、神性、正義から部族、財産、庇護、首長制に至るまで、あらゆるものに対するモロッコ人の概念を俳優の視点で描写した形式で 提示されると、その傾向はさらに強まる。 つまり、人類学的な記述はそれ自体が解釈であり、さらに二次的、三次的な解釈でもある。(定義上、一次的な解釈を行うのは「土着の人々」だけである。それ は彼らの文化である。)2 したがって、それらはフィクションである。フィクションとは、「何かが作られたもの」、「何かが形作られたもの」という意味であり、fictiÙの本来の 意味である。それらは偽りであるとか、事実無根であるとか、あるいは単に「もし~ならば」という思考実験であるという意味ではない。1912年のモロッコ におけるベルベル人の族長、ユダヤ人の商人、フランス人兵士の相互関係を、登場人物中心の描写で構成することは明らかに想像力に富んだ行為であり、例えば 19世紀のフランスにおける地方のフランス人医師、愚かな不倫妻、そして彼女の無責任な愛人たちの相互関係を描写する行為とそれほど変わらない。後者の場 合、登場人物は実在しなかったとされ、出来事も起こらなかったとされるが、前者の場合は、登場人物は実在した、あるいは、そうであったとされる。これは些 細な違いではない。実際、まさにこの点が『ボヴァリー夫人』の理解を難しくしていた。しかし、重要なのは、彼女の物語が作られた一方で、コーエンの物語は 注目されただけだったという事実ではない。それらが作られた状況、つまり「その要点(方法や質については言うまでもなく)」は異なる。しかし、どちらも同 様にフィクションであり、作り話である。 文化は交易所や丘の砦、あるいは羊の群れの中にも存在するが、人類学は本や記事、講義、博物館の展示、あるいは時には最近では映画の中にも存在する。この 事実を認識することは、文化分析において、表現の方法と実質的な内容の境界線は、絵画と同様に、引くことができないということを理解することである。そし て、この事実は、その源は社会的現実ではなく学術的な人為であることを示唆することで、人類学的知識の客観的な地位を脅かすように思われる。 確かにそれは脅威ではあるが、その脅威は根拠のないものだ。民族誌的記述が注目を集めるのは、著者が遠い地で原始的な事実を捉え、それを仮面や彫刻のよう に持ち帰る能力があるからではなく、そうした場所で何が起こっているのかを明らかにし、未知の背景から生じる未知の行為に対して自然に生じる「彼らはどん な人間なのか?」という困惑を軽減する能力があるからだ。これは、検証に関する深刻な問題を提起する。つまり、検証という言葉が、あまりに強すぎる表現で あるならば、より良い説明と悪い説明を見分ける方法について、である。しかし、それこそがまさにその長所である。民族誌学が詳細な記述であり、民族誌学者 がその記述を行う人々であるとすれば、フィールド・ジャーナルの稚拙な記述であれ、マリノフスキーの単行本のような大著であれ、そのいずれの例において も、決定的な問題は、まばたきと引きつり、本物のまばたきと真似されたまばたきを区別できるかどうかである。解釈されていないデータの集合体や、大幅に簡 略化された記述に対して、私たちの説明の妥当性を測る必要はない。そうではなく、科学的な想像力が、私たちに他人の生活を理解させるのだ。ソローが言った ように、ザンジバルの猫の数を数えるために世界を一周する価値はない。 |
| V Now, this proposition, that it is not in our interest to bleach human behavior of the very properties that interest us before we begin to examine it, has sometimes been escalated into a larger claim: namely, that as it is only those properties that interest us, we need not attend, save cursorily, to behavior at all. Culture is most effectively treated, the argument goes, purely as a symbolic system (the catch phrase is, "in its own terms"), by isolating its elements, specifying the internal relationships among those elements, and then characterizing the whole system in some general way--according to the core symbols around which it is organized, the underlying structures of which it is a surface expression, or the ideological principles upon which it is based. Though a distinct improvement over "learned behavior" and "mental phenomena" notions of what culture is, and the source of some of the most powerful theoretical ideas in contemporary anthropology, this hermetical approach to things seems to me to run the danger (and increasingly to have been overtaken by it) of locking cultural analysis away from its proper object, the informal logic of actual life. There is little profit in extricating a concept from the defects of psychologism only to plunge it immediately into those of schematicism. Behavior must be attended to, and with some exactness, because it is through the flow of behavior--or, more precisely, social action--that cultural forms find articulation. They find it as well of course, in various sorts of artifacts, and various states of consciousness; but these draw their meaning from the role they play (Wittgenstein would say their "use") in an ongoing pattern of life, not from any intrinsic relationships they bear to one another. It is what Cohen, the sheikh, and "Captain Dumari" were doing when they tripped over one another's purposes--pursuing trade, defending honor, establishing dominance--that created our pastoral drama, and that is what the drama is, therefore, "about." Whatever, or wherever, symbol systems "in their own terms" may be, we gain empirical access to them by inspecting events, not by arranging abstracted entities into unified patterns. A further implication of this is that coherence cannot be the major test of validity for a cultural description. Cultural systems must have a minimal degree of coherence, else we would not call them systems; and, by observation, they normally have a great deal more. But there is nothing so coherent as a paranoid's delusion or a swindler's story. The force of our interpretations cannot rest, as they are now so often made to do, on the tightness with which they hold together, or the assurance with which they are argued. Nothing has done more, I think, to discredit cultural analysis than the construction of impeccable depictions of formal order in whose actual existence nobody can quite believe. If anthropological interpretation is constructing a reading of what happens, then to divorce it from what happens--from what, in this time or that place, specific people say, what they do, what is done to them, from the whole vast business of the world--is to divorce it from its applications and render it vacant. A good interpretation of anything--a poem, a person, a history, a ritual, an institution, a society--takes us into the heart of that of which it is the interpretation. When it does not do that, but leads us instead somewhere else--into an admiration of its own elegance, of its author's cleverness, or of the beauties of Euclidean order--it may have its intrinsic charms; but it is something else than what the task at hand--figuring out what all that rigamarole with the sheep is about--calls for. The rigamarole with the sheep--the sham theft of them, the reparative transfer of them, the political confiscation of them--is (or was) essentially a social discourse, even if, as I suggested earlier, one conducted in multiple tongues and as much in action as in words. Claiming his 'ar, Cohen invoked the trade pact; recognizing the claim, the sheikh challenged the offenders' tribe; accepting responsibility, the offenders' tribe paid the indemnity; anxious to make clear to sheikhs and peddlers alike who was now in charge here, the French showed the imperial hand. As in any discourse, code does not determine conduct, and what was actually said need not have been. Cohen might not have, given its illegitimacy in Protectorate eyes, chosen to press his claim. The sheikh might, for similar reasons, have rejected it. The offenders' tribe, still resisting French authority, might have decided to regard the raid as "real" and fight rather than negotiate. The French, were they more habilÈ and less dur (as, under Mareschal Lyautey's seigniorial tutelage, they later in fact became), might have permitted Cohen to keep his sheep, winking--as we say--at the continuance of the trade pattern and its limitation to their authority. And there are other possibilities: the Marmushans might have regarded the French action as to great an insult to bear and gone into dissidence themselves; the French might have attempted not just to clamp down on Cohen but to bring the sheikh himself more closely to heel; and Cohen might have concluded that between renegade Berbers and Beau Geste soldiers, driving trade in the Atlas highlands was no longer worth the candle and retired to the better-governed confines of the town. This, indeed, is more or less what happened, somewhat further along, as the Protectorate moved toward genuine sovereignty. But the point here is not to describe what did or did not take place in Morocco. (From this simple incident one can widen out into enormous complexities of social experience.) It is to demonstrate what a piece of anthropological interpretation consists in tracing the curve of a social discourse; fixing it into inspectable form. The ethnographer "inscribes" social discourse; he writes it down. ln so doing, he turns it from a passing event, which exists only in its own moment of occurrence, into an account, which exists in its inscriptions and can be reconsulted. The sheikh is long dead, killed in the process of being, as the French called it, "pacified"; "Captain Dumari," his pacifier, lives, retired to his souvenirs, in the south of France; and Cohen went last year, part refugee, part pilgrim, part dying patriarch, "home" to Israel. But what they, in my extended sense, "said" to one another on an Atlas plateau sixty years ago is--very far from perfectly--preserved for study. "What," Paul Ricoeur, from whom this whole idea of the inscription of action is borrowed and somewhat twisted, asks, "what does writing fix?" Not the event of speaking, but the ''said" of speaking, where we understand by the "said" of speaking that intentional exteriorization constitutive of the aim of discourse thanks to which the 'Sagen'--the saying--wants to become the 'Aussage': the enunciated. In short, what we write is the noema ["thought", ''content,'' "gist''] of the speaking. It is the meaning of the speech event, not the event as event. This is not itself so very "said"--if Oxford philosophers run to little stories, phenomenological ones run to large sentences; but it brings us anyway to a more precise answer to our generative question, "What does the ethnographer do?"--he writes.3 This, too, may seem a less than startling discovery, and to someone familiar with the current "literature," an implausible one. But as the standard answer to our question has been: "He observes, he records, he analyzes"--a kind of "veni-vidi-vici"-conception of the matter--it may have more deep-going consequences than are at first apparent,--not the least of which is that distinguishing these three phases of knowledge-seeking may not, as a matter of fact, normally be possible; and, indeed, as autonomous "operations" they may not in fact exist. The situation is even more delicate, because, as already noted, what we inscribe (or try to) is not raw social discourse, to which, because save very marginally or very specially, we are not actors, we do not have direct access, but only that small part of it which our informants can lead us into understanding.4 This is not as fatal as it sounds, for, in fact, not all Cretans are liars, and it is not necessary to know everything in order to understand something. But it does make the view of anthropological analysis as the conceptual manipulation of discovered facts, a logical reconstruction of a mere reality, seem rather lame. To set forth symmetrical crystals of significance, purified of the material complexity in which they were located, and then attribute their existence to autogenous principles of order, universal properties of the human mind, or vast, a priori weltanschauungen is to pretend a science that does not exist and imagine a reality that cannot be found. Cultural analysis is (or should be) guessing at meanings, assessing the guesses, and drawing explanatory conclusions from the better guesses, not discovering the Continent of Meaning and mapping out its bodiless landscape. |
V さて、人間の行動を調査する前に、我々にとって興味深いその特性を漂白してしまうことは我々にとって利益にならないというこの命題は、時にさらに大きな主 張へとエスカレートする。すなわち、我々にとって興味深いのはその特性だけであるため、行動にはまったく注意を払う必要はないという主張である。文化は、 その要素を分離し、それらの要素間の内部関係を特定し、そしてそのシステム全体をある一般的な方法で特徴づけることによって、純粋に象徴体系として最も効 果的に扱われる(キャッチフレーズは「そのものとして」)という主張である。すなわち、それが組織化される中心的な象徴、その表面的表現である基礎構造、 またはその基盤となるイデオロギー的原則に従ってである。文化とは何か、また現代の文化人類学における最も強力な理論的アイデアの源である「学習行動」や 「精神現象」の概念をはるかに凌ぐ明確な改善ではあるが、この物事に対する閉鎖的なアプローチは、文化分析をその本来の対象である実際の生活における非公 式な論理から遠ざけてしまう危険性があるように私には思える。心理主義の欠陥から概念を救い出したとしても、すぐに図式主義の欠陥に陥るだけである。 文化形態は、行動の流れ、より正確に言えば社会的行動を通じて、明確な形をとる。もちろん、文化形態はさまざまな人工物やさまざまな意識状態においても明 確な形をとるが、それらは、生活の継続的なパターンの中で果たす役割(ウィトゲンシュタインは「用途」と言うだろう)から意味を引き出すのであって、互い に内在的な関係性から引き出すのではない。貿易、名誉の擁護、優位性の確立といった目的を追求する中で、コーエン、族長、そして「ドゥマリ族長」がお互い の目的を妨害したときに、私たちの牧歌的なドラマが生まれたのだ。そして、そのドラマこそが「本質」なのである。 記号システムが「それ自身の言葉で」どのようなものであれ、またそれがどこにあろうとも、私たちは抽象化された存在を統一されたパターンに配置することで はなく、出来事を調査することによって、それらに対する経験的なアクセスを得る。 このことのさらなる含意は、文化の記述における妥当性の主要な基準として首尾一貫性を挙げることはできないということである。文化システムには最低限の首 尾一貫性があるはずであり、そうでなければそれをシステムと呼ぶことはできない。そして、観察によれば、通常ははるかに多くの首尾一貫性がある。しかし、 偏執狂の妄想や詐欺師の作り話ほど首尾一貫したものはない。私たちの解釈の力は、しばしばそうであるように、その解釈がどれほど首尾一貫しているか、ある いはどれほど論証されているかという点に依存してはならない。実際の存在を誰も信じることができない形式的な秩序の非の打ちどころのない描写を構築するこ とほど、文化分析の信頼性を失墜させるものはないと私は考える。 人類学的な解釈が「何が起こっているか」についての解釈を構築しているとすれば、「何が起こっているか」からそれを切り離すことは、つまり、この時代やあ の場所で特定の人々が何を言い、何を行い、彼らに何が行われたか、世界の広大な営みのすべてからそれを切り離すことは、その応用からそれを切り離し、それ を空虚なものにしてしまうことになる。詩、人物、歴史、儀式、制度、社会など、何であれ優れた解釈は、私たちをその解釈の対象の核心へと導いてくれる。そ うではなく、別の場所へと導く場合、つまり、その作品の優雅さや作者の巧妙さ、あるいはユークリッド的秩序の美しさへの感嘆へと導く場合、それ自体は魅力 的であるかもしれないが、目の前の課題、つまり羊に関するあれこれの真意を解明するという課題とは別のものだ。 羊をめぐる騒動、つまり羊の偽装窃盗、羊の補償的移送、羊の政治的没収は、私が先に述べたように、言葉だけでなく行動でも行われたとしても、本質的には社 会的な議論である。 自分の「権利」を主張したコーエンは通商協定を呼び起こし、その主張を認めた首長は違反者の部族に異議を唱え、責任を引き受けた違反者の部族は賠償金を支 払い、首長や行商人たちに誰が今この地を支配しているかをはっきりと示すことに躍起になったフランスは、帝国の手腕を示した。あらゆる言説と同様に、規範 が行動を決定するわけではない。実際に何が言われたかは、必ずしもそうである必要はない。コーエンは、保護領の目から見てその主張が正当性を欠いていたた め、主張を押し通すことを選ばなかったかもしれない。首長も同様の理由から、それを拒否したかもしれない。フランス人の権威に依然として抵抗していた犯罪 者の部族は、その襲撃を「本物」と見なし、交渉よりも戦うことを決めたかもしれない。フランス人(彼らが後に実際そうであったように、マレスシャル・リヤ ウテーの封建的な指導の下で、より有能で、かつ頑固でなかった場合)は、コヘンに羊を飼うことを許可し、貿易形態の継続と、その権限の制限を黙認したかも しれない。そして、他にも可能性がある。フランス人の行動をあまりに侮辱的だと受け止め、マームシャン族自身が反旗を翻したのかもしれない。フランス人 は、ただコヘンを締め上げるだけでなく、首長自身をより従順にさせようとしたのかもしれない。そして、コヘンは、背教者のベルベル人とボー・ジェストの兵 士の間では、アトラス高地での交易を続ける価値はないと判断し、より統治の行き届いた町へと退いたのかもしれない。これは、事実、ある程度までは、保護領 が真の主権へと向かっていく中で、やや時間が経ってから起こったことである。しかし、ここで重要なのは、モロッコで起こったこと、あるいは起こらなかった ことを描写することではない。(この単純な出来事から、社会経験の巨大な複雑性にまで広げることができる。)ここで示したいのは、人類学的な解釈が、社会 的な言説の曲線をたどり、それを検証可能な形に固定することによって成り立つということである。 民族誌学者は社会的な談話を「記述」する。つまり、それを書き留めるのだ。そうすることで、その談話は、発生したその瞬間にのみ存在する一過性の出来事か ら、記述として存在し、再調査が可能な記録へと変わる。シェイクは、フランス人が「pacified(鎮圧)」と呼ぶ過程で殺され、とうの昔に亡くなって いる。「キャプテン・ドゥマリ」という名の彼の鎮圧者は、思い出の中に身を引いて南仏で暮らしている。そして、コーエンは昨年、難民、巡礼者、そして死に かけた家長の一部として、イスラエルに「帰郷」した。しかし、私の広義の感覚で言えば、60年前にアトラス山脈の高原で彼らが互いに「語り合った」こと は、完璧とは程遠いものの、研究用に保存されている。「書くことによって何が修正されるのか?」と、行為の刻印という考えを借用し、多少ひねったポール・ リクールは問いかける。 話すという出来事ではなく、話すという「言われたこと」である。話すという「言われたこと」によって、談話の目的を構成する意図的な外化が理解される。そ れによって、「Sagen(言われる)」が「Aussage(言明)」になりたいと望む。つまり、私たちが書くものは、発話のノエマ(「思考」、「内 容」、「要点」)である。それは発話の出来事の意味であり、出来事そのものではない。 これはそれ自体はそれほど「言われた」ものではない。オックスフォードの哲学者が小さな物語に走るなら、現象学者は大きな文章に走る。しかし、いずれにし ても、生成に関する我々の質問「民族誌学者は何をするのか?」に対するより正確な答えに我々を導く。3 これもまた、驚くほどの発見ではないように思えるかもしれないし、現在の「文学」に精通している人にとっては、ありそうもない発見に思えるかもしれない。 しかし、我々の質問に対する標準的な答えが「 「彼は観察し、記録し、分析する」という、この問題に関する「veni-vidi-vici(来た、見た、勝った)」的な考え方であるが、それは一見した 以上に深い影響を及ぼす可能性がある。その影響のひとつとして、知識を求めるというこの3つの段階を区別することは、実際には通常不可能であるかもしれな いということである。そして、実際には、それらは自律的な「活動」として存在していない可能性もある。 すでに述べたように、私たちが書き記す(あるいは記そうとする)のは、生の社会的な言説ではない。その言説には、ごく限られた場合や特別な場合を除いて、 私たちは当事者ではないため、直接アクセスすることはできず、 情報提供者によって理解に導かれるそのごく一部だけである。4 これは、聞こえほど致命的なものではない。なぜなら、実際にはクレタ島民が皆嘘つきというわけではないし、何かを理解するためにすべてを知る必要はないか らだ。しかし、人類学的な分析を、発見された事実の概念操作であり、単なる現実の論理的な再構成であると見なすことは、かなり見当はずれである。意味の対 称的な結晶を、それが置かれていた物質的な複雑性から浄化し、その存在を、自己生成的な秩序原理、人間の精神の普遍的特性、あるいは広大な先験的な世界観 に帰属させることは、存在しない科学を装い、見出すことのできない現実を想像することである。文化分析とは、意味を推測し、その推測を評価し、より優れた 推測から説明的な結論を導き出すものであり、意味の大陸を発見し、その実体のない風景を地図化するものではない。 |
| VI So, there are three characteristics of ethnographic description: it is interpretive; what it is interpretive of is the flow of social discourse; and the interpreting involved consists in trying to rescue the "said" of such discourse from its perishing occasions and fix it in perusable terms. The kula is gone or altered; but, for better or worse, The Argonauts of the Western Pacific remains. So far as it has reinforced the anthropologist's impulse to engage himself with his informants as persons rather than as objects, the notion of "participant observation" has been a valuable one. But, to the degree it has lead the anthropologist to block from his view the very special, culturally bracketed nature of his own role and to imagine himself something more than an interested (in both senses of that word) sojourner, it has been our most powerful source of bad faith. Western Pacific remains. But there is, in addition, a fourth characteristic of such description, at least as I practice it: it is microscopic. This is not to say that there are no large-scale anthropological interpretations of whole societies, civilizations, world events, and so on. Indeed, it is such extension of our analyses to wider contexts that, along with their theoretical implications, recommends them to general attention and justifies our constructing them. No one really cares anymore, not even Cohen (well ... maybe, Cohen), about those sheep as such. History may have its unobtrusive turning points, "great noises in a little room"; but this little go-round was surely not one of them. It is merely to say that the anthropologist characteristically approaches such broader interpretations and more abstract analyses from the direction of exceedingly extended acquaintances with extremely small matters. He confronts the same grand realities that others--historians, economists, political scientists, sociologists--confront in more fateful settings: Power, Change, Faith, Oppression, Work, Passion, Authority, Beauty, Violence, Love, Prestige; but he confronts them in contexts obscure enough --places like Marmusha and lives like Cohen's--to take the capital letters off them. These all-too-human constancies, "those big words that make us all afraid," take a homely form in such homely contexts. But that is exactly the advantage. There are enough profundities in the world already. Yet, the problem of how to get from a collection of ethnographic miniatures on the order of our sheep story--an assortment of remarks and anecdotes--to wall-sized culturescapes of the nation, the epoch, the continent, or the civilization is not so easily passed over with vague allusions to the virtues of concreteness and the down-to-earth mind. For a science born in Indian tribes, Pacific islands, and African lineages and subsequently seized with grander ambitions, this has come to be a major methodological problem, and for the most part a badly handled one. The models that anthropologists have themselves worked out to justify their moving from local truths to general visions have been, in fact, as responsible for undermining the effort as anything their critics--sociologists obsessed with sample sizes, psychologists with measures, or economists with aggregates--have been able to devise against them. Of these, the two main ones have been: the Jonesville-is-the-USA "microcosmic" model; and the Easter-Island-is-a-testing-case "natural experiment" model. Either heaven in a grain of sand, or the farther shores of possibility. The Jonesville-is-America writ small (or America-is-Jonesville writ large) fallacy is so obviously one that the only thing that needs explanation is how people have managed to believe it and expected others to believe it. The notion that one can find the essence of national societies, civilizations, great religions, or whatever summed up and simplified in so-called "typical" small towns and villages is palpable nonsense. What one finds in small towns and villages is (alas) small-town or village life. If localized, microscopic studies were really dependent for their greater relevance upon such a premise--that they captured the great world in the little--they wouldn't have any relevance. But, of course, they are not. The locus of study is not the object of study. Anthropologists don't study villages (tribes, towns, neighborhoods ...); they study in villages. You can study different things in different places, and some things--for example, what colonial domination does to established frames of moral expectation you can best study in confined localities. But that doesn't make the place what it is you are studying. ln the remoter provinces of Morocco and Indonesia I have wrestled with the same questions other social scientists have wrestled with in more central locations--for example, how comes it that men's most importunate claims to humanity are cast in the accents of group pride? and with about the same conclusiveness. One can add a dimension--one much needed in the present climate of size-up-and-solve social science; but that is all. There is a certain value, if you are going to run on about the exploitation of the masses in having seen a Javanese sharecropper turning earth in a tropical downpour or a Morrocan tailor embroidering kaftans by the light of a twenty-watt bulb. But the notion that this gives you the thing entire (and elevates you to some moral vantage ground from which you can look down upon the ethically less privileged) is an idea which only someone too long in the bush could possibly entertain. The "natural laboratory" notion has been equally pernicious, not only because the analogy is false--what kind of a laboratory is it where none of the parameters are manipulated?--but because it leads to a notion that the data derived from ethnographic studies are purer, or more fundamental, or more solid, or less conditioned (the most favored word is "elementary") than those derived from other sorts of social inquiry. The great natural variation of cultural forms is, of course, not only anthropology's great (and wasting) resource, but the ground of its deepest theoretical dilemma: how is such variation to be squared with the biological unity of the human species? But it is not, even metaphorically, experimental variation, because the context in which it occurs varies along with it, and it is not possible (though there are those who try) to isolate the y's from x's to write a proper function. The famous studies purporting to show that the Oedipus complex was backwards in the Trobriands, sex roles were upside down in Tchambuli, and the Pueblo Indians lacked aggression (it is characteristic that they were all negative--"but not in the South"), are, whatever their empirical validity may or may not be, not "scientifically tested and approved" hypotheses. They are interpretations, or misinterpretations, like any others, arrived at in the same way as any others, and as inherently inconclusive as any others, and the attempt to invest them with the authority of physical experimentation is but methodological sleight of hand. Ethnographic findings are not privileged, just particular: another country heard from. To regard them as anything more (or anything less) than that distorts both them and their implications, which are far profounder than mere primitivity, for social theory. Another country heard from: the reason that protracted descriptions of distant sheep raids (and a really good ethnographer would have gone into what kind of sheep they were) have general relevance is that they present the sociological mind with bodied stuff on which to feed. The important thing about the anthropologist's findings is their complex specificness, their circumstantiality. It is with the kind of material produced by long-term, mainly (though not exclusively) qualitative, highly participative, and almost obsessively fine-comb field study in confined contexts that the mega-concepts with which contemporary social science is afflicted--legitimacy, modernization, integration, conflict, charisma, structure, ... meaning--can be given the sort of sensible actuality that makes it possible to think not only realistically and concretely about them, but, what is more important, creatively and imaginatively with them. The methodological problem which the microscopic nature of ethnography presents is both real and critical. But it is not to be resolved by regarding a remote locality as the world in a teacup or as the sociological equivalent of a cloud chamber. It is to be resolved--or, anyway, decently kept at bay--by realizing that social actions are comments on more than themselves; that where an interpretation comes from does not determine where it can be impelled to go. Small facts speak to large issues, winks to epistemology, or sheep raids to revolution, because they are made to. |
VI つまり、民族誌的記述には3つの特徴がある。それは解釈的であり、解釈の対象は社会的な談話の流れであり、解釈とは、そうした談話の「言われたこと」を消 滅の危機から救い出し、読み返せる形で固定することである。クラは消滅したか、あるいは変化した。しかし、良くも悪くも、『西太平洋のアルゴ号乗組員た ち』は残っている。 人類学者が情報提供者と関わる際に、彼らをモノとしてではなく、一人の人間として関わるという衝動を強化するという意味において、「参与観察」という概念 は価値のあるものだった。しかし、文化的に括られた自身の役割の特殊性を視野から遮断し、単なる興味本位の滞在者以上の存在であると想像するほど、人類学 者を欺瞞の最も強力な源泉へと導いてきた。 西太平洋の残存。しかし、少なくとも私が実践する限りにおいて、このような記述には4つ目の特徴がある。それは、ミクロ的であるということだ。 これは、社会全体、文明、世界的な出来事などに対する大規模な人類学的解釈が存在しないという意味ではない。実際、分析をより広い文脈に拡張することは、 理論的な含意とともに、一般的な関心を呼び、それらを構築することの正当性を裏付ける。もはや、コーエン(まあ、コーエンかもしれないが)でさえ、それら の羊そのものについて気にかける人はいない。 歴史には目立たない転換点、「小さな部屋での大きな騒音」があるのかもしれないが、この小さな一巡りは、それらには当てはまらない。 人類学者は、極めて小さな事柄について極めて広範な知識を持っているという特徴から、このようなより広範な解釈やより抽象的な分析にアプローチする。 彼は、歴史家、経済学者、政治学者、社会学者といった他の人々が、より運命的な状況において直面するのと同じ壮大な現実と向き合う。権力、変化、信仰、抑 圧、労働、情熱、権威、美、暴力、愛、威信などである。しかし、彼はそれらを、マルムーシャのような場所やコーエンのような生活といった、大文字を外して もおかしくないほど不明瞭な文脈で扱っている。こうしたあまりにも人間的な普遍性、すなわち「私たちを皆おびえさせる大きな言葉」は、このような平凡な文 脈において平凡な形を取る。しかし、それこそがまさに利点なのである。世界にはすでに十分な深みがある。しかし、羊の話のような民族誌的な小話の集まり、 つまり、さまざまな発言や逸話から、国民、時代、大陸、文明といった壁一面の文化景観にどうやって到達するかという問題は、具体性や現実的な思考の美徳に ついて漠然とほのめかすだけでは簡単に乗り越えられるものではない。インドの部族、太平洋諸島、アフリカの系譜で生まれ、その後より壮大な野望を抱くよう になった科学にとって、これは主要な方法論上の問題となり、ほとんどの場合、不適切に扱われている。 人類学者が自ら考案した、ローカルな真実から一般的なビジョンへと移行することを正当化するためのモデルは、実際、サンプルサイズにこだわる社会学者、測 定にこだわる心理学者、集計にこだわる経済学者といった批判者たちが彼らに対して考案したものと同様に、その努力を損なう原因となっている。 そのうちの主なものは2つある。ジョーンズビルがアメリカである「縮図」モデル、そしてイースター島がテストケースである「自然実験」モデルである。砂粒 の中の天国か、あるいは可能性の果てしない地平線か。ジョーンズビルがアメリカを縮小したものだという誤謬(またはアメリカがジョーンズビルを拡大したも のだという誤謬)はあまりにも明白であるため、説明が必要なのは、人々がそれを信じ、他人にもそれを信じさせることを期待してきた理由だけである。国民社 会、文明、偉大な宗教、またはその他何であれ、いわゆる「典型的な」小さな町や村に集約され単純化された本質を見出すことができるという考えは、明らかな ナンセンスである。小さな町や村で見つかるのは、残念ながら、小さな町や村の生活である。 もし局所的でミクロな研究が、より関連性を持つために本当にそのような前提に依存しているとしたら、つまり、小さな世界に大きな世界が凝縮されているとい う前提に依存しているとしたら、それらの研究には関連性はないだろう。 しかし、もちろん、そうではない。研究の対象は研究の中心ではない。人類学者は村(部族、町、近隣など)を研究するのではなく、村で研究する。異なる場所 では異なるものを研究できるし、例えば植民地支配が確立された道徳的期待の枠組みにどのような影響を与えるかといったことは、閉ざされた地域で最もよく研 究できる。しかし、それによってその場所が研究対象となるわけではない。モロッコやインドネシアの辺境の州で、私は他の社会科学者がより中心的な場所で取 り組んできたのと同じ問題について考えを巡らせてきた。例えば、男性が人間性に対して最もしつこく主張することが、集団の誇りのアクセントで表現されるの はなぜか? といった問題について、ほぼ同じ結論に達した。社会科学の現状において、評価と解決を求めるという観点から、非常に必要とされている次元を追加することは できる。しかし、それだけだ。熱帯の豪雨の中で土を耕すジャワ人の小作農や、20ワットの電球の光でカフタンに刺繍を施すモロッコ人の仕立屋を目撃したか らといって、大衆の搾取についてあれこれと語るのであれば、それなりの価値はある。 しかし、この考え方によって全体像が把握でき(倫理的に恵まれない人々を見下ろすことのできる道徳的な優位に立つことができる)、という考え方は、あまり にも長く現地に滞在した人だけが抱く可能性のある考え方である。 「自然の実験室」という概念も同様に有害である。なぜなら、その類推が誤っているからだ。すなわち、パラメータが操作されていない実験室などあり得るだろ うか? また、この概念は、民族誌学的研究から得られたデータは、他の種類の社会調査から得られたデータよりも純粋、あるいはより根本的、より確固とした、あるい は条件付けられていない(最も好まれる言葉は「素朴」)という考えにつながるからだ。 文化形態の大きな自然変動は、もちろん、人類学の大きな(そして無駄な)資源であるだけでなく、その最も深い理論的ジレンマの根拠でもある。すなわち、そ のような変動を、生物学的観点から見た人類の統一性とどのように折り合いをつけるか、というジレンマである。しかし、それは比喩的にさえも実験的な変化で はない。なぜなら、それが起こる文脈も同時に変化するからであり、xからyを分離して適切な機能を記述することは不可能だからだ(試みる者はいるが)。 トロブリアンド諸島ではエディプス・コンプレックスが逆転し、チャンブリでは性役割が逆転し、プエブロ・インディアンには攻撃性が欠如しているという有名 な研究(いずれも「南ではそうではない」という否定形であるのが特徴的である)は、その実証的な妥当性があるかないかに関わらず、「科学的に検証され、承 認された」仮説ではない。それらは、他の解釈や誤った解釈と同様に、他の解釈と同じ方法で導き出されたものであり、他の解釈と同様に本質的に結論の出ない ものであり、物理的な実験の権威を付与しようとする試みは、単に方法論的なごまかしに過ぎない。民族誌学的な調査結果は、特別なものではなく、単に特殊な ものである。別の国からの意見だ。それらをそれ以上のもの(あるいはそれ以下のもの)とみなすことは、それらと、社会理論にとってはるかに深い意味を持つ それらの含意の両方を歪めることになる。 別の国からの声:遠く離れた場所での羊の略奪に関する長々とした記述(優れた民族誌学者であれば、それらの羊がどのような種類なのかにも踏み込んでいるだ ろう)が一般的な関連性を持つ理由は、社会学的な思考に、それを養うための身体的な素材を提供しているからである。人類学者の調査結果で重要なのは、その 複雑な特殊性、状況性である。現代の社会科学が抱える巨大な概念、すなわち正当性 、近代化、統合、紛争、カリスマ、構造、... 意味などといった、現代の社会科学が抱える巨大な概念に、現実的かつ具体的に考えるだけでなく、さらに重要なこととして、それらを創造的に、想像的に考え ることを可能にするような、感覚的な現実性を与えることができる。 エスノグラフィーのミクロな性質がもたらす方法論上の問題は、現実的かつ重大である。しかし、遠く離れた地域を「お茶碗の中の宇宙」や「雲室の社会学的な 同等物」と見なすことでは解決できない。社会的な行動はそれ自体以上のものに対するコメントであるという認識によって解決されるべきである。つまり、解釈 がどこから来たかによって、それがどこに向かうかが決まるわけではない。小さな事実が大きな問題を語り、認識論にウィンクし、革命に羊の群れが襲いかかる と警告する。なぜなら、そうさせられるからだ。 |
| VII Which brings us, finally, to theory. The besetting sin of interpretive approaches to anything--literature, dreams, symptoms, culture--is that they tend to resist, or to be permitted to resist, conceptual articulation and thus to escape systematic modes of assessment. You either grasp an interpretation or you do not, see the point of it or you do not, accept it or you do not. Imprisoned in the immediacy of its own detail, it is presented as self-validating, or, worse, as validated by the supposedly developed sensitivities of the person who presents it; any attempt to cast what it says in terms other than its own is regarded as a travesty--as, the anthropologist's severest term of moral abuse, ethnocentric. For a field of study which, however timidly (though I, myself, am not timid about the matter at all), asserts itself to be a science, this just will not do. There is no reason why the conceptual structure of a cultural interpretation should be any less formulable, and thus less susceptible to explicit canons of appraisal, than that of, say, a biological observation or a physical experiment--no reason except that the terms in which such formulations can be cast are, if not wholly nonexistent, very nearly so. We are reduced to insinuating theories because we lack the power to state them. At the same time, it must be admitted that there are a number of characteristics of cultural interpretation which make the theoretical development of it more than usually difficult. The first is the need for theory to stay rather closer to the ground than tends to be the case in sciences more able to give themselves over to imaginative abstraction. Only short flights of ratiocination tend to be effective in anthropology; longer ones tend to drift off into logical dreams, academic bemusements with formal symmetry. The whole point of a semiotic approach to culture is, as I have said, to aid us in gaining access to the conceptual world in which our subjects live so that we can, in some extended sense of the term, converse with them. The tension between the pull of this need to penetrate an unfamiliar universe of symbolic action and the requirements of technical advance in the theory of culture, betwecn the need to grasp and the need to analyze, is, as a result, both necessarily great and esentially irrcmovable. Indecd, the further theoretical development goes, the deepcr the tension gets. This is the first condition for cultural theory: it is not its own master. As it is unseverable from the immediacies thick description presents, its freedom to shape itself in terms of its internal logic is rather limited. What generality it contrives to achieve grows out of the delicacy of its distinctions, not the sweep of its abstractions. And from this follows a peculiarity in the way, as a simple matter of empirical fact, our knowledge of culture (cultures, a culture) grows: in spurts. Rather than following a rising curve of cumulative findings, cultural analysis breaks up into a disconnected yet coherent sequence of bolder and bolder sorts. Studies do build on other studies, not in the sense that they take up where the others leave off, but in the sense that, better informed and better conceptualized, they plunge more deeply into the same things. Every serious cultural analysis starts from a sheer beginning and ends where it manages to get before exhausting its intellectual impulse. Previously discovered facts are mobilized, previously developed concepts used, previously formulated hypotheses tried out; but the movement is not from already proven theorems to newly proven ones, it is from an awkward fumbling for the most elementary understanding to a supported claim that one has achieved that and surpassed it. A study is an advance if it is more incisive--whatever that may mean--than those that preceded it; but it less stands on their shoulders than, challenged and challenging, runs by their side. It is for this reason, among others, that the essay, whether of thirty pages or three hundred, has seemed the natural genre in which to present cultural interpretations and the theories sustaining them, and why, if one looks for systematic treatises in the field, one is so soon disappointed, the more so if one finds any. Even inventory articles are rare here, and anyway of hardly more than bibliographical interest. The major theoretical contributions not only lie in specific studies--that is true in almost any field--but they are very difficult to abstract from such studies and integrate into anything one might call "culture theory" as such. Theorctical formulations hover so low over the interpretations they govern that they don't make much sense or hold much interest apart from them. This is so, not because they are not general (if they are not general, they are not theoretical), but because, stated independently of their applications, they seem either commonplace or vacant. One can, and this in fact is how the field progresses conceptually, take a line of theoretical attack developed in connection with one exercise in ethnographic interpretation and employ it in another, pushing it forward to greater precision and broader relevance; but one cannot write a "General Theory of Cultural Interpretation." Or, rather, one can, but there appears to be little profit in it, because the essential task of theory building here is not to codify abstract regularities but to make thick description possible, not to generalize across cases but to generalize within them. To generalize within cases is usually called, at least in medicine and depth psychology, clinical inference. Rather than beginning with a set of observations and attempting to subsume them under a governing law, such inference begins with a set of (presumptive) signifiers and attempts to place them within an intelligible frame. Measures are matched to theoretical predictions, but symptoms (even when they are measured) are scanned for theoretical peculiarities--that is, they are diagnosed. In the study of culture the signifiers are not symptoms or clusters of symptoms, but symbolic acts or clusters of symbolic acts, and the aim is not therapy but the analysis of social discourse. But the way in which theory is used--to ferret out the unapparent import of things--is the same. Thus we are lead to the second condition of cultural theory: it is not, at least in the strict meaning of the term, predictive. The diagnostician doesn't predict measles; he decides that someone has them, or at the very most clincially decides that someone is rather likely shortly to get them. But this limitation, which is real enough, has commonly been both misunderstood and exaggerated, because it has been taken to mean that cultural interpretation is merely post facto: that, like the peasant in the old story, we first shoot the holes in the fence and then paint the bull's-eyes around them. It is hardly to be denied that there is a good deal of that sort of thing around, some of it in prominent places. It is to be denied, however, that it is the inevitable outcome of a clinical approach to the use of theory. It is true that in the clinical style of theoretical formulation, conceptualization is directed toward the task of generating interpretations of matters already in hand, not toward projecting outcomes of experimental manipulations or deducing future states of a determined system. But that does not mean that theory has only to fit (or, more carefully, to generate cogent interpretations of) realities past; it has also to survive--intellectually survive--realities to come. Although we formulate our interpretation of an outburst of winking or an instance of sheep-raiding after its occurrence, sometimes long after, the theoretical framework in terms of which such an interpretation is made must be capable of continuing to yield defensible interpretations as new social phenomena swim into view. Although one starts any effort at thick description, beyond the obvious and superficial, from a state of general bewilderment as to what the devil is going on--trying to find one's feet--one does not start (or ought not) intellectually empty-handed. Theoretical ideas are not created wholly anew in each study; as I have said, they are adopted from other, related studies, and, refined in the process, applied to new interpretive problems. If they cease being useful with respect to such problems, they tend to stop being used and are more or less abandoned. If they continue being useful, throwing up new understandings, they are further elaborated and go on being used.5 Such a view of how theory functions in an interpretive science suggests that the distinction, relative in any case, that appears in the experimental or observational sciences between "description" and "explanation" appears here as one, even more relative, between "inscription" ("thick description") and "specification" ("diagnosis")--between setting down the meaning particular social actions have for the actors whose actions they are, and stating, as explicitly as we can manage, what the knowledge thus attained demonstrates about the society in which it is found and, beyond that, about social life as such. Our double task is to uncover the conceptual structures that inform our subjects' acts, the "said" of social discourse, and to construct a system of analysis in whose terms what is generic to those structures, what belongs to them because they are what they are, will stand out against the other determinants of human behavior. In ethnography, the office of theory is to provide a vocabulary in which what symbolic action has to say about itself--that is, about the role of culture in human life--can be expressed. Aside from a couple of orienting pieces concerned with more foundational matters, it is in such a manner that theory operates in the essays collected here. A repertoire of very general, made-in-the-academy concepts and systems of concepts--"integration?" "rationalization," "symbol," "ideology," "ethos," "revolution," ''identity," "metaphor," "structure," "ritual," "world view," "actor," "function," "sacred," and, of course, "culture" itself--is woven into the body of thick-description ethnography in the hope of rendering mere occurrences scientifically eloquent.6 The aim is to draw large conclusions from small, but very densely textured facts; to support broad assertions about the role of culture in the construction of collective life by engaging them exactly with complex specifics. Thus it is not only interpretational that goes all the way down to the most immediate observational level: the theory upon which such interpretation conceptually depends does so also. My interest in Cohen's story, like Ryle's in winks, grew out of some very general notions indeed. The "confusion of tongues" model the view that social conflict is not something that happens when, out of weakness, indefiniteness, obsolescence, or neglect, cultural forms cease to operate, but rather something which happens when, like burlesqued winks, such forms are pressed by unusual situations or unusual intentions to operate in unusual ways--is not an idea I got from Cohen's story. It is one, instructed by colleagues, students, and predecessors, I brought to it. Our innocent-looking "note in a bottle" is more than a portrayal of` the frames of meaning of Jewish peddlers, Berber warriors, and French proconsuls, or even of their mutual interference. It is an argument that to rework the pattern of social relationships is to rearrange the coordinates of the experienced world. Society's forms are culture's substance. |
VII 最後に、理論について述べる。文学、夢、症状、文化など、あらゆるものに対する解釈的アプローチの最大の欠点は、概念的な明確化に抵抗する傾向にある、あ るいは抵抗することを許される傾向にあるため、体系的な評価の方法から逃れてしまうことである。解釈を理解するかしないか、その要点を理解するかしない か、受け入れるか受け入れないか、である。その詳細の即時性に囚われ、それは自己正当化として提示されるか、あるいはさらに悪いことに、それを提示する人 物の、おそらくは発達した感受性によって正当化される。その主張を、その主張自身の言葉以外の言葉で表現しようとする試みは、すべて茶番として見なされ る。 しかし、臆病にも(私自身はまったく臆病ではないが)、科学であると主張する学問分野にとって、これはまったく受け入れがたい。文化解釈の概念構造が、例 えば生物学的な観察や物理的な実験のそれよりも、定式化が難しく、評価の明確な規範に当てはまりにくいという理由はない。そのような定式化が可能な用語 が、全く存在しないわけではないにしても、ほとんど存在しないという理由以外には。私たちは、理論をほのめかすことしかできない。なぜなら、それを明確に 表現する力が欠如しているからだ。 同時に、文化解釈には、その理論的発展を通常よりも困難にするいくつかの特徴があることを認めなければならない。第一に、想像力に富んだ抽象化に没頭でき る科学分野ではそうなる傾向にあるが、理論はより現実的である必要がある。 人類学においては、短時間の推論が効果的である傾向があり、長時間の推論は論理的な夢想や、形式的な対称性に関する学術的な困惑へと漂流してしまう傾向が ある。文化に対する記号論的アプローチの要点は、私がすでに述べたように、私たちの主題が生きている概念的世界へのアクセスを可能にすることであり、そう することで、その言葉の拡張された意味において、それらと対話することができる。この、記号的な行動の未知の世界に踏み込む必要性と、文化理論における技 術的進歩の要件との間の緊張、把握する必要性と分析する必要性との間の緊張は、結果として、必然的に大きく、本質的に動かしがたいものとなる。理論がさら に発展すればするほど、この緊張は深まる。これが文化理論の第一条件である。厚みのある記述が提示する即時性から切り離すことができないため、その内部論 理に従って自らを形作る自由はかなり限られている。文化論が達成しようとする一般性は、その区別の繊細さから生じるものであり、抽象化の広がりから生じる ものではない。 そして、このことから、文化(文化、文化)に関する我々の知識が成長する仕方には、単純な経験的事実として、独特の性質があることが導かれる。文化分析 は、累積的な発見の増加曲線に従うのではなく、断続的ではあるが、より大胆な一連の連続として行われる。研究は他の研究の上に築かれるが、それは他の研究 が残した課題を引き継ぐという意味ではなく、より多くの情報を得て、より明確な概念を構築し、同じ事柄にさらに深く掘り下げていくという意味である。真剣 な文化分析は、すべてゼロから始まり、知的な衝動が尽きる前に到達できる地点で終わる。すでに発見された事実が動員され、すでに開発された概念が用いら れ、すでに定式化された仮説が試される。しかし、その動きはすでに証明された定理から新たに証明された定理へと向かうものではなく、最も初歩的な理解を模 索するぎこちない試行錯誤から、それを達成し、それを超えたという裏付けのある主張へと向かうものである。研究は、それが先行する研究よりも鋭い洞察力を 持っている場合(それが何を意味するにせよ)、進歩である。しかし、それは先行する研究の上に立つというよりも、先行する研究に挑戦し、先行する研究に挑 戦しながら、先行する研究の横を走るものである。 この理由から、30ページであろうと300ページであろうと、エッセイは文化的な解釈やそれを支える理論を提示するのに自然なジャンルであると思われてき た。体系的な論文をこの分野で探そうとすれば、すぐに失望させられる。在庫目録でさえもここでは珍しく、いずれにしても、書誌的な関心以上のものはない。 主要な理論的貢献は、特定の研究にのみ存在するわけではないが、ほとんどの分野でその傾向がある。しかし、そのような研究から理論を抽出して、「文化理 論」として統合することは非常に難しい。理論的定式化は、支配する解釈よりもはるかに低く位置しているため、それらから離れてはあまり意味をなさず、また 興味も持たれない。これは、理論が一般化されていないからではなく(一般化されていないのであれば、それは理論ではない)、応用とは別に述べられた場合、 ありふれたものか、中身のないものに見えるからである。 実際、この方法で概念的に研究が進展している。ある民族誌解釈の実践に関連して開発された理論的アプローチを、別の実践に適用し、より高い精度とより幅広 い関連性へと発展させることは可能である。しかし、「文化解釈の一般理論」を書くことはできない。いや、できるかもしれないが、それにはほとんど利益がな いように思われる。なぜなら、ここで理論構築の重要な課題は、抽象的な規則性を体系化することではなく、厚みのある記述を可能にすることであり、事例を一 般化することではなく、事例内での一般化を行うことだからである。 事例内での一般化は、少なくとも医学や深層心理学では、臨床的推論と呼ばれることが多い。一連の観察から出発し、それらを支配する法則の下に包括しようと するのではなく、このような推論は、(推定上の)記号群から出発し、それらを理解可能な枠組みの中に位置づけようとする。測定値は理論上の予測と照合され るが、症状(測定値が得られた場合でも)は理論上の特異性をスキャンされる。つまり、診断されるのだ。文化研究における記号は症状や症状の集合ではなく、 象徴行為や象徴行為の集合であり、目的は治療ではなく、社会的な言説の分析である。しかし、理論の用いられ方、すなわち物事の明白でない含意を明らかにす るという点では同じである。 したがって、文化理論の第二の条件に導かれる。それは、少なくとも厳密な意味では予測的ではないということである。診断医は麻疹を予測するわけではない。 誰かが麻疹にかかっていると判断する、あるいはせいぜい臨床的に、誰かが間もなく麻疹にかかる可能性が高いと判断する。 しかし、この限界は十分に現実的なものであるにもかかわらず、一般的に誤解され、誇張されてきた。なぜなら、文化的な解釈は単に事後的なものだという意味 に捉えられてきたからだ。昔話に出てくる農民のように、まずフェンスに穴を開け、その周りに的を描くように、というような解釈である。そのようなことがか なりあることは否定できないし、中には目立つ場所にあるものもある。しかし、それが理論の使用に対する臨床的なアプローチから必然的に生じる結果であると 否定することはできない。 理論の臨床的な定式化では、概念化はすでに手元にある事柄の解釈を生み出すという課題に向けられるのであって、実験操作の結果を予測したり、決定されたシ ステムの将来の状態を推論したりすることに向けられるわけではない。しかし、理論が過去の現実を適合させる(あるいは、より慎重に言えば、説得力のある解 釈を生み出す)だけでよいということにはならない。理論は、来るべき現実を生き残らせる(知的には生き残らせる)ものでもある。私たちは、ウインクの噴出 や羊泥棒の事例について、それが発生した後、時にはかなり時間が経ってから解釈を構築するが、そのような解釈が為される理論的枠組みは、新たな社会現象が 現れるたびに、擁護可能な解釈を継続的に生み出すものでなければならない。厚い記述の努力は、明白なことや表面的なことを超えたところから、いったい何が 起こっているのかまったくわからない状態から始まる。自分の足で立とうとするのだ。しかし、知的には手ぶらで始めるわけではない(あるいは、手ぶらで始め るべきではない)。理論的な考えは、各研究において完全に新たに生み出されるわけではない。すでに述べたように、それらは他の関連研究から採用され、その 過程で洗練され、新たな解釈上の問題に適用される。それらがそのような問題に関して有用でなくなれば、それらは使われなくなり、多かれ少なかれ放棄される 傾向にある。それらが有用であり続け、新たな理解をもたらすのであれば、それらはさらに洗練され、使われ続ける。 解釈科学における理論の機能に関するこのような見解は、実験科学や観察科学において「記述」と「説明」の間に見られる相対的な区別が、ここでは「記述」 (「厚い記述」)と「仕様 特定の社会的行為が、その行為者にとってどのような意味を持つかを明らかにすることと、そうして得られた知識が、それが発見された社会について、さらには 社会生活そのものについて、何を明らかにしているかを、できる限り明確に述べることを意味する。私たちの2つの課題は、被験者の行為を導く概念構造、すな わち社会的な談話における「言われたこと」を明らかにし、その構造に一般的なもの、つまり、それがそれであるがゆえにそれらに属するものを、人間の行動の 他の決定要因に対して際立たせる分析の体系を構築することである。民族誌学において、理論の役割は象徴的行為がそれ自身について、つまり人間の生活におけ る文化の役割について語ることを可能にする語彙を提供することである。 より基礎的な問題に関するいくつかの方向づけとなる論文を除いて、本書に収められた論文では理論はこのような形で機能している。非常に一般的な、アカデ ミックな概念や概念体系のレパートリー――「統合? 「合理化」、「象徴」、「イデオロギー」、「エートス」、「革命」、「アイデンティティ」、「隠喩」、「構造」、「儀式」、「世界観」、「行為者」、「機 能」、「神聖」、そしてもちろん「文化」そのものといった、非常に一般的なアカデミックな概念や概念体系が、 単なる出来事を科学的に雄弁に表現することを目的として、厚みのある民族誌の記述に織り込まれている。6 その目的は、小さな事実から大きな結論を導き出すこと、つまり、集団生活の構築における文化の役割に関する幅広い主張を、複雑な詳細事項と正確に照らし合 わせることである。 したがって、解釈は最も直接的な観察レベルにまで至るだけでなく、その解釈の概念的基盤となる理論もまた同様である。ライルのウィンクのように、コーエン の話に対する私の関心は、ごく一般的な考えから生まれた。「舌の混乱」モデルは、社会的葛藤とは、弱さ、曖昧さ、時代遅れ、あるいは無視などから文化形態 が機能しなくなったときに起こるものではなく、むしろ、茶番化されたウィンクのように、そうした形態が異常な状況や異常な意図によって異常な方法で機能す るように迫られたときに起こるものだという見解である。これは、私がコーエンの話から得た考えではない。これは、同僚や学生、先人たちから教わったもの で、私がそれに取り入れたものだ。 一見無邪気な「ボトルメール」は、ユダヤ人の行商人、ベルベル人の戦士、フランスの執政官たちの意味の枠組み、あるいは彼らの相互干渉を描写したもの以上 のものだ。社会関係のパターンを再構築することは、経験された世界の座標を再配置することであるという主張である。社会の形式は文化の実質である。 |
| VIII There is an Indian story--at least I heard it as an Indian story--about an Englishman who, having been told that the world rested on a platform which rested on the back of an elephant which rested in turn on the back of a turtle, asked (perhaps he was an ethnographer; it is the way they behave), what did the turtle rest on? Another turtle. And that turtle ? "Ah, Sahib, after that it is turtles all the way down." Such, indeed, is the condition of things. I do not know how long it would be profitable to meditate on the encounter of Cohen, the sheikh, and "Dumari" (the period has perhaps already been exceeded); but I do know that however long I did so I would not get anywhere near to the bottom of it. Nor have I ever gotten anywhere near to the bottom of anything I have ever written about, either in the essays below or elsewhere. Cultural analysis is intrinsically incomplete. And, worse than that, the more deeply it goes the less complete it is. It is a strange science whose most telling assertions are its most tremulously based, in which to get somewhere with the matter at hand is to intensify the suspicion, both your own and that of others, that you are not quite getting it right. But that, along with plaguing subtle people with obtuse questions, is what being an ethnographer is like. There are a number of ways to escape this--turning culture into folklore and collecting it, turning it into traits and counting it, turning it into institutions and classifying it, turning it into structures and toying with it. But they are escapes. The fact is that to commit oneself to a semiotic concept of culture and an interpretive approach to the study of it is to commit oneself to a view of ethnographic assertion as, to borrow. B. Gallie's by now famous phrase, "essentially contestable." Anthropology, or at least interpretive anthropology, is a science whose progress is marked less by a perfection of consensus than by a refinement of debate. What gets better is the precision with which we vex each other. This is very difficult to see when one's attention is being monopolized by a single party to the argument. Monologues are of little value here, because there are no conclusions to be reported; there is merely a discussion to be sustained. Insofar as the essays here collected have any importance, it is less in what they say than what they are witness to: an enormous increase in interest, not only in anthropology, but in social studies generally, in the role of symbolic forms in human life. Meaning, this elusive and ill-defined pseudoentity we were once more than content to leave philosophers and literary critics to fumble with, has now come back into the heart of our discipline. Even Marxists are quoting Cassirer; even positivists, Kenneth Burke. My own position in the midst of all this has been to try to resist subjectivism on the one hand and cabbalism on the other, to try to keep the analysis of symbolic forms as closely tied as I could to concrete social events and occasions, the public world of common life, and to organize it in such a way that the connections between theoretical formulations and descriptive interpretations were unobscured by appeals to dark sciences. I have never been impressed by the argument that, as complete objectivity is impossible in these matters (as, of course, it is), one might as well let one's sentiments run loose. As Robert Solow has remarked, that is like saying that as a perfectly aseptic environment is impossible, one might as well conduct surgery in a sewer. Nor, on the other hand, have I been impressed with claims that structural linguistics, computer engineering, or some other advanced form of thought is going to enable us to understand men without knowing them. Nothing will discredit a semiotic approach to culture more quickly than allowing it to drift into a combination of intuitionism and alchemy, no matter how elegantly the intuitions are expressed or how modern the alchemy is made to look. The danger that cultural analysis, in search of all-too-deep-lying turtles, will lose touch with the hard surfaces of life--with the political, economic, stratificatory realities within which men are everywhere contained--and with the biological and physical necessities on which those surfaces rest, is an ever-present one. The only defense against it, and against, thus, turning cultural analysis into a kind of sociological aestheticism, is to train such analysis on such realities and such necessities in the first place. It is thus that I have written about nationalism, about violence, about identity, about human nature, about legitimacy, about revolution, about ethnicity, about urbanization, about status, about death, about time, and most of all about particular attempts by particular peoples to place these things in some sort of comprehensible, meaningful frame. To look at the symbolic dimensions of social action--art, religion, ideology, science, law, morality, common sense--is not to turn away from the existential dilemmas of life for some empyrean realm of deemotionalized forms; it is to plunge into the midst of them. The essential vocation of interpretive anthropology is not to answer our deepest questions, but to make available to us answers that others, guarding other sheep in other valleys, have given, and thus to include them in the consultable record of what man has said. |
VIII インドの物語がある。少なくとも私はそれをインドの物語として聞いた。世界は台の上にあり、その台は象の背中にあり、その象は亀の背中にあり、その亀は台 の上にある、と聞いたイギリス人が、亀はさらに何の上に載っているのかと尋ねた(おそらく彼は民族学者だったのだろう。それが彼らの振る舞い方なのだか ら)。別の亀だ。その亀は?「ああ、旦那様、それ以降はずっと亀です」 まさに、このような状況なのだ。コーエン、首長、そして「ドゥマリ」の出会いを考察することがいつまで有益であるかはわからないが(おそらくすでにその期 間は過ぎている)、どれだけ長く考察を続けても、その本質に近づくことはできないだろう。また、これまでに書いたことについても、以下のエッセイでも、他 の場所でも、本質に近づいたことは一度もない。文化分析は本質的に不完全である。さらに悪いことに、深く掘り下げれば掘り下げるほど、その不完全性は増し ていく。文化分析は奇妙な学問であり、最も説得力のある主張は最も震えるような根拠に基づく。そして、目の前の問題について何らかの結論を出すことは、自 分自身と他者の双方の疑念を強め、自分が正しく理解していないという疑いを深めることになる。しかし、それは、繊細な人々を鈍い質問で悩ませることと並ん で、文化人類学者の仕事とはそういうものなのだ。 この状況から逃れる方法はいくつかある。文化を民俗学に変えて収集する、文化を特徴に変えて数える、文化を制度に変えて分類する、文化を構造に変えてあれ これいじくり回す、などである。しかし、これらはあくまで逃げである。実際には、記号論的な文化概念と解釈的な研究アプローチに身をゆだねることは、B. ギャリーの有名な表現を借りれば、文化人類学的な主張を「本質的に議論の余地がある」ものとして捉えることに身をゆだねることを意味する。 B. ギャリーの有名なフレーズを借りれば、「本質的に議論の余地がある」ということになる。人類学、少なくとも解釈人類学は、その進歩がコンセンサスの完成よ りも議論の洗練によって示される科学である。より良くなるのは、お互いを悩ませる精度である。 これは、議論の一方の当事者に注意が独占されていると、非常に見えにくくなる。結論を報告するわけではないので、独白にはほとんど価値がない。ここで収集 されたエッセイが重要であるとすれば、それは内容よりも、証言したことによる。人類学だけでなく、社会研究全般において、人間の生活における象徴形式の役 割に対する関心が大幅に高まったことである。つまり、かつては哲学者や文学評論家に任せておけばいいと私たちが考えていた、この捉えどころのない曖昧な疑 似実体は、今や私たちの学問の中心に舞い戻ってきたのだ。マルクス主義者でさえカッシーラーを引用し、実証主義者でさえケネス・バークを引用している。 こうした状況の中で、私は主観主義とカバラ主義の双方に抵抗しようと努めてきた。象徴形式の分析を、具体的な社会的出来事や機会、公共の場である共通の生 活にできるだけ密接に結びつけ、理論的定式化と記述的解釈の間のつながりが、闇の科学への訴えによって曇らないように整理しようとしてきた。私は、このよ うな問題では完全な客観性は不可能である(もちろん、不可能である)から、自分の感情の赴くままにすればよいという議論に感銘を受けたことは一度もない。 ロバート・ソローが述べたように、それは、完全な無菌環境は不可能であるから、手術は下水道で行えばよいと言っているようなものだ。また、構造言語学やコ ンピュータ工学、あるいはその他の高度な思考形態によって、人間を知らずに人間を理解できるという主張にも感銘を受けない。直観主義と錬金術の組み合わせ に文化記号論を流してしまうことほど、そのアプローチを否定するものはない。直観がどれほど優雅に表現され、錬金術がどれほど現代的に見せられようとも、 である。 文化分析が、あまりにも奥深くに潜む亀を探し求めるあまり、政治、経済、階層化された現実、つまり人間がどこにでも包含されている現実、そしてそれらの現 実の基盤となる生物学的および物理的な必要条件といった、人生の厳しい現実から乖離してしまうという危険性は、常に存在する。それに対する唯一の防御策、 そして、文化分析を一種の社会学的観念論に変えることに対する防御策は、そもそも、そのような分析をそのような現実や必要条件に適用することである。私 は、ナショナリズム、暴力、アイデンティティ、人間の本性、正統性、革命、民族、都市化、地位、死、時間について、そして何よりも、これらの事柄をある種 の理解可能な、意味のある枠組みに位置づけようとする特定の民族による特定の試みについて書いてきた。 芸術、宗教、イデオロギー、科学、法律、道徳、常識といった社会行動の象徴的な側面を考察することは、人生の存在論的なジレンマから目を背けることではな く、むしろその真っ只中に身を投じることである。解釈的人類学の本質的な使命は、私たちの最も深い問いに答えることではなく、他の谷で他の羊の群れを守る 他の人々が与えた答えを私たちに利用できるようにし、それによって、人類が語ったことの参照可能な記録にそれらを含めることである。 |
| 1 Not only other peoples': anthropology can be trained on the culture of which it is itself a part, and it increasingly is; a fact of profound importance, but which, as it raises a few tricky and rather special second order problems, I shall put to the side for the moment. 2 The order problem is, again, complex. Anthropological works based on other anthropological works ( LÈvi-Strauss', for example) may, of course, be fourth order or higher, and informants frequently, even habitually, make second order interpretations--what have come to be known as "native models." In literate cultures, where "native" interpretation can proceed to higher levels--in connection with the Maghreb, one has only to think of Ibn Khaldun; with the United States, Margaret Mead--these matters become intricate indeed. 3 Or, again, more exactly, "inscribes." Most ethnography is in fact to be found in books and articles, rather than in films, records, museum displays, or whatever; but even in them there are, of course, photographs, drawings, diagrams, tables, and so on. Self-consciousness about modes of representation (not to speak of experiments with them) has been very lacking in anthropology. 4 So far as it has reinforced the anthropologist's impulse to engage himself with his informants as persons rather than as objects, the notion of "participant observation" has been a valuable one. But, to the degree it has lead the anthropologist to block from his view the very special, culturally bracketed nature of his own role and to imagine himself something more than an interested (in both senses of that word) sojourner, it has been our most powerful source of bad faith. 5 Admittedly, this is something of an idealization. Because theories are seldom if ever decisively disproved in clinical use but merely grow increasingly awkward, unproductive, strained, or vacuous, they often persist long after all but a handful of people (though they are often most passionate) have lost much interest in them. Indeed, so far as anthropology is concerned, it is almost more of a problem to get exhausted ideas out of the literature than it is to get productive ones in, and so a great deal more of theoretical discussion than one would prefer is critical rather than constructive, and whole careers have been devoted to hastening the demise of moribund notions. As the field advances one would hope that this sort of intellectual weed control would become a less prominent part of our activities. But, for the moment, it remains true that old theories tend less to die than to go into second editions. 6 The overwhelming bulk of the following chapters concern Indonesia rather than Morocco, for I have just begun to face up to the demands of my North African material which, for the most part, was gathered more recently. Field work in Indonesia was carried out in 1952-1954, 1957-1958, and 1971; in Morocco in 1964, 1965-1966, 1968-1969, and 1972. |
1 他者のものだけでなく、人類学は、それ自体がその一部である文化を研究対象とすることができる。これは非常に重要な事実であるが、いくつかの厄介でかなり 特殊な二次的な問題を引き起こすため、ここではひとまず脇に置いておく。 2 この順序の問題は、またしても複雑である。他の人類学的研究(例えばレヴィ=ストロース)に基づく人類学的研究は、もちろん4次またはそれ以上のレベルの ものであり、情報提供者は頻繁に、あるいは習慣的に2次レベルの解釈を行う。文字文化圏では、「ネイティブ」な解釈がより高いレベルに進むことができる。 マグレブ地域との関連ではイブン・ハルドゥーン、米国との関連ではマーガレット・ミードを思い浮かべればよい。 3 あるいは、より正確に言えば、「記述する」である。ほとんどの民族誌は、映画やレコード、博物館の展示物などではなく、書籍や記事で見つけることができ る。しかし、それらにももちろん、写真、絵、図表などがある。表現方法についての自覚(それらに関する実験については言うまでもない)は、人類学では非常 に欠如している。 4 「参与観察」という概念は、人類学者が情報提供者と関わる際に、対象としてではなく一人の人間として関わるという衝動を強化する限りにおいては、非常に価 値のあるものだった。しかし、人類学者が自身の役割が持つ文化的に括られた特別な性質を視野から遮断し、単なる(この言葉の2つの意味における)興味本位 の滞在者以上の存在であると想像するよう導く程度であれば、それは最も強力な不誠実さの源であった。 5 確かに、これはある種の理想化である。理論は臨床の場で決定的に否定されることはほとんどなく、単にますます厄介で非生産的でぎこちない、あるいは中身の ないものになっていくだけなので、ごく一部の人々(彼らはしばしば最も熱心であるが)がほとんど興味を失ってしまった後も、理論は長く生き残ることが多 い。実際、人類学に関して言えば、生産的な考えを文献に取り入れることよりも、陳腐な考えを文献から取り除くことの方がはるかに問題であり、望ましいより も批判的な理論的議論がはるかに多く、死にかけている概念の終焉を早めることにキャリア全体が費やされてきた。分野が進歩するにつれ、この種の知的雑草駆 除が私たちの活動の目立たない部分になることを期待したい。しかし、今のところ、古い理論は滅びるよりもむしろ改訂版として生き延びる傾向にあることは事 実である。 6 以下の章の大部分は、モロッコよりもインドネシアに関するものである。なぜなら、私は北アフリカの資料の要求に直面し始めたばかりであり、その資料のほと んどは最近になって収集されたものだからだ。インドネシアでの現地調査は1952年から1954年、1957年から1958年、1971年に行われ、モ ロッコでは1964年、1965年から1966年、1968年から1969年、1972年に行われた。 |
| Thick description: toward an
interpretive theory of culture, in: The interpretation of
cultures: selected essays. New-York/N.Y./USA etc. 1973: Basic Books,
pp. 3-30 http://hypergeertz.jku.at/GeertzTexts/Thick_Description.htm |
リンク先
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099
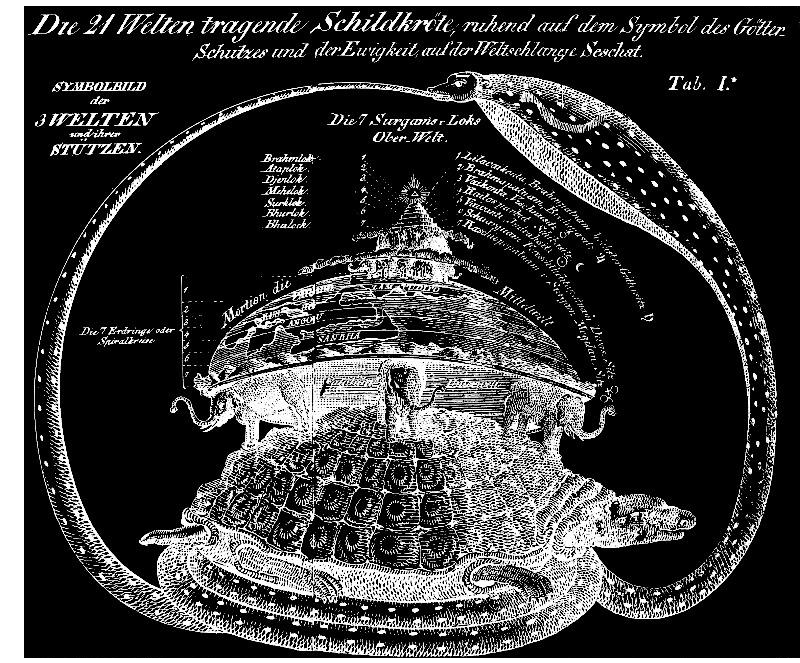
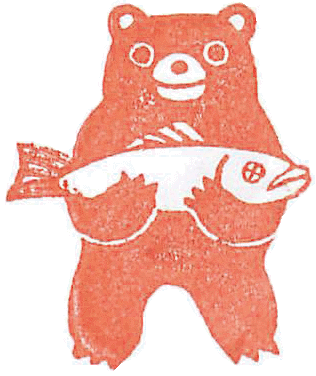




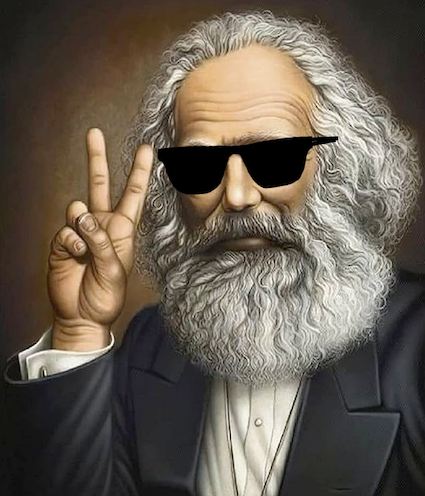
++
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099