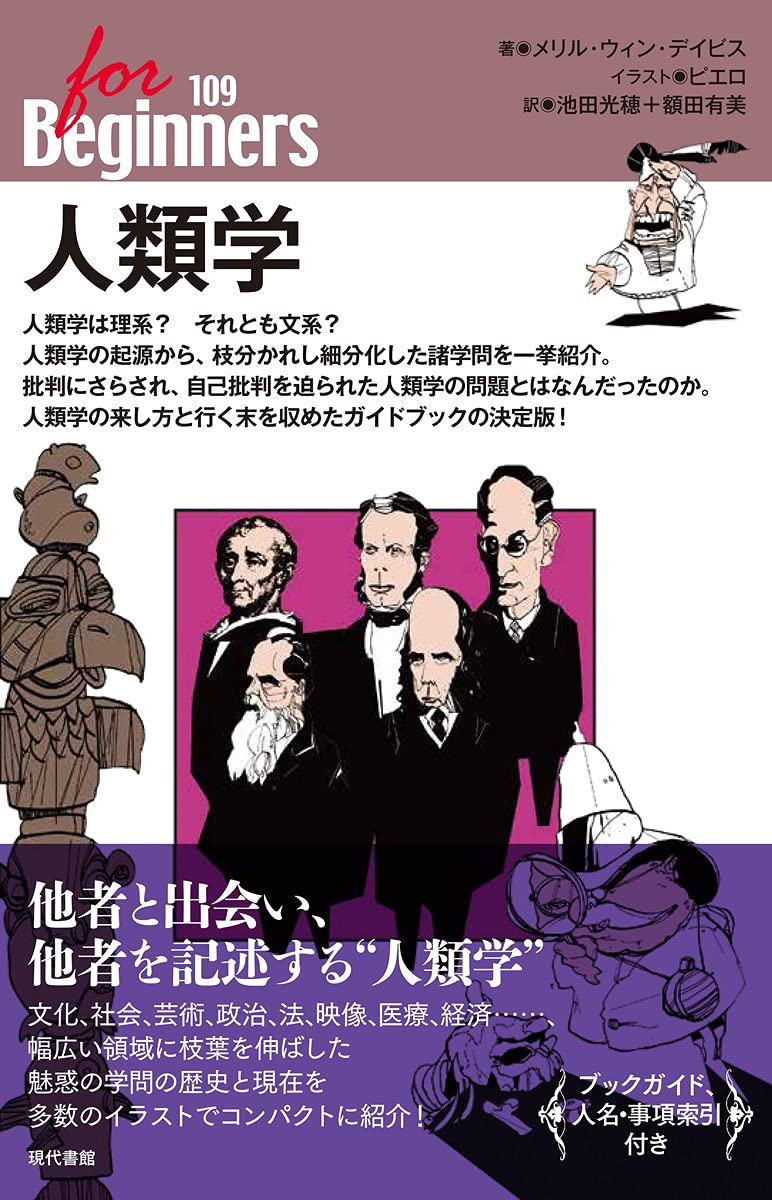
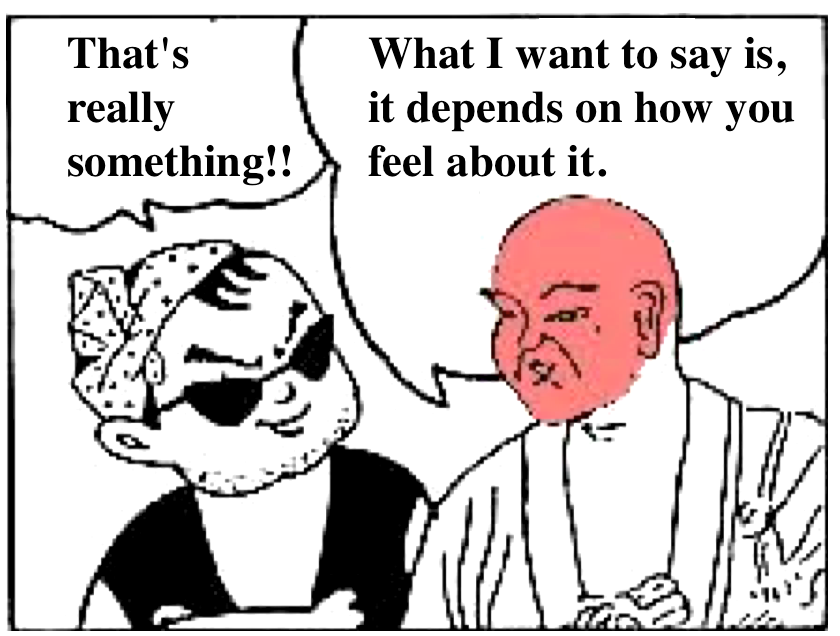

古きものへの忠誠
"Fidelity to the Old":
A Graphic Guide 011
■
教科書(Cultural Anthropology Remix 協賛):今回の教科書は Merryl Wyn Davies
が著者、Piero がイラストレーターによる、その名も『人類学を紹介する(Introducing Anthropology)』出版社は
Icon Books, 2002 です。8年後に改定されて、Merryl Wyn Davies and PIERO, Introducing
Anthropology: A Graphic Guide, Icon Books Ltd.,
2010.となりました。いわゆる啓蒙のためのイラスト・ブックです。カルスタもとい、カ
ルチュラル・スタディーズのものは日本語に翻訳されているのでな
いだろうか。とってもおもしろい本です。文化人類学の現代の問題系
にまでしっかり踏み込んでい ますが、そのことを
明確するために、人類学の歴史的ルーツに遡り考察するという姿
勢が貫かれています。つまり、骨太の人類学史の教科書ともいえるべきものです。それが、な、なんと邦訳されました!!!
メリル・ウィン・デイビス『人類学』池田光穂+額田有美訳、現代書館、2021年10月 ISBN-13 : 978-4768401095
| 011 |
【II】人類学史 Part
1:「古きものへの忠誠」 ("Fidelity to the Old") |
11.
〈古き時代への忠誠〉 |
11. 〈古き時代への忠誠〉 ハリスが厳しく非難し除外しようとするのは、マーガレット・ハッジェンの主張である。ハッジェンは著書『16世紀から17世紀の初期人類学』(1964) において、手ごたえのある2つの点を指摘した。 まず第2に、人間の起源、生活様式や多様性についての推論は、古くからあるもので、相互作用し連続している。古代ギリシア、中世の作家、〈リコナサンス時 代〉、モンテーニュ、そしてそれ以外の多くの概念と着想が、啓蒙主義思想と19世紀の人類学の知的伝統に情報を与えこれらを構築している。 【台詞】マーガレット・ハッジェン「そして第2に、このような古臭い推測に折り重ねられた組織化の原理と理論的着想は、何度も蒸し返されて、モダン人類学 のなかで生き永らえているということね」 【台詞】アナザシ「ハッジェンは、これを〈人類学に今なお残る古代への忠誠心〉と呼んだのさ」 ハッジェンが人類学とのつながりを指摘する初期の作品の特徴は何だろうか?1つの要素は、ローマの作家プリニウスが『博物誌』(A.D.77)の1節でそ う呼んだ、〈プリニウスの野蛮人〉への信仰である。『博物誌』は、知られざる世界の縁に暮らす怪物のような人種(犬の頭をした民族や頭のない食人種)につ いての莫大なコレクションを記録したものである。これらの怪物のような人種は、古代そして中世の文学作品の標準的特徴であった。これ以外の要素は、聖書的 な説明の枠組みである。 【台詞】マーガレット・ホッゲン「怪物のような民族への期待は、認められている人類学の歴史が始まった19世紀にはまだ誰もが抱いていて、ベストセラーの 書籍を生み出していたのよ」 【台詞】学者(人類学者)「そして食人種は生き続けているのじゃ」 食人種という見出し(ヘッドライン)を生み出す人類学者の最後の1人が1980年代に確認されている。しかし、人類学者ウィリアム・アレンス(1979) は、互いの共通言語が存在しないときに西洋人が発見しようとしたものが食人種であったと示しつつ、それが西洋人による過度な想像の産物であると説得力を もって主張した。その存在が期待されていたので、どんなに不合理であっても、食人種に関する報告は受け入れられていたのだ。 (原著15ページ) |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099