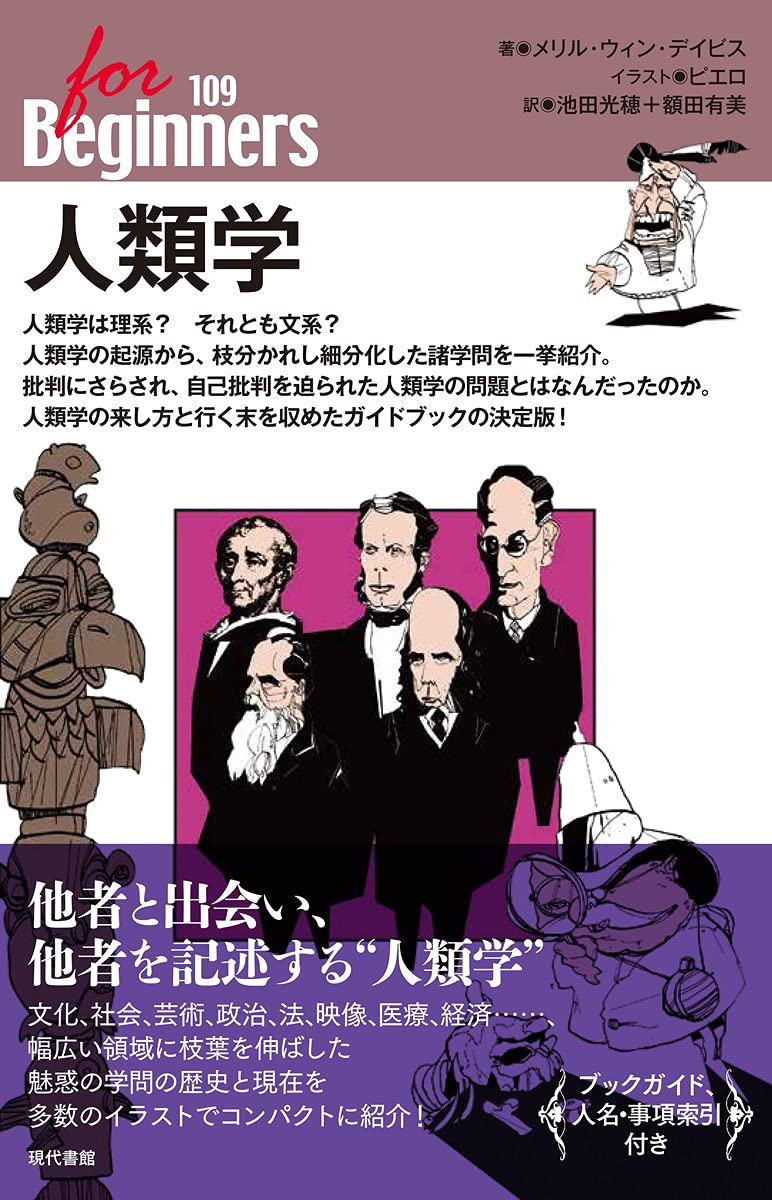
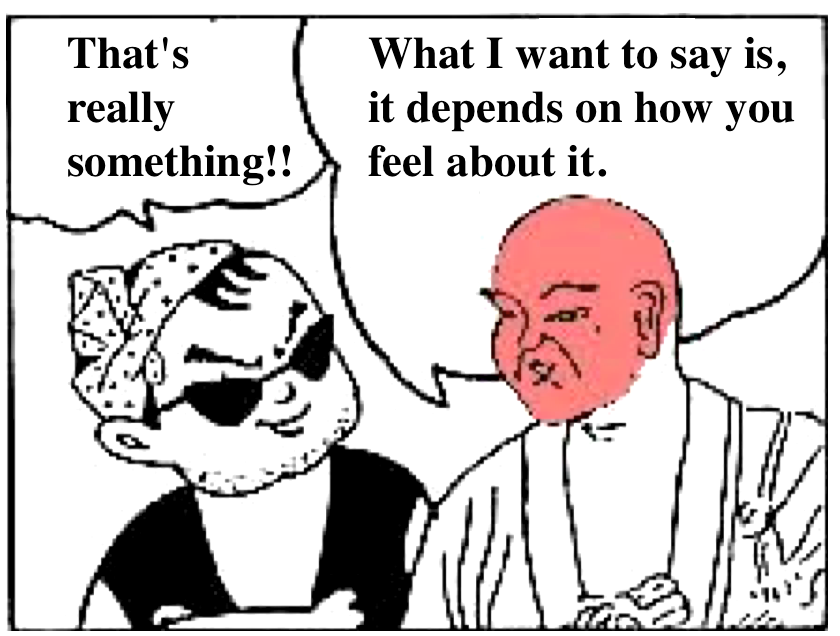

人権という問い
The question of human
rights:
A Graphic Guide 012
■
教科書(Cultural Anthropology Remix 協賛):今回の教科書は Merryl Wyn Davies
が著者、Piero がイラストレーターによる、その名も『人類学を紹介する(Introducing Anthropology)』出版社は
Icon Books, 2002 です。8年後に改定されて、Merryl Wyn Davies and PIERO, Introducing
Anthropology: A Graphic Guide, Icon Books Ltd.,
2010.となりました。いわゆる啓蒙のためのイラスト・ブックです。カルスタもとい、カ
ルチュラル・スタディーズのものは日本語に翻訳されているのでな
いだろうか。とってもおもしろい本です。文化人類学の現代の問題系
にまでしっかり踏み込んでい ますが、そのことを
明確するために、人類学の歴史的ルーツに遡り考察するという姿
勢が貫かれています。つまり、骨太の人類学史の教科書ともいえるべきものです。それが、な、なんと邦訳されました!!!
メリル・ウィン・デイビス『人類学』池田光穂+額田有美訳、現代書館、2021年10月 ISBN-13 : 978-4768401095
| 012 |
【II】人類学史 Part
1:人権の問題 |
12.
人権という問い |
12. 人権という問い スペイン人の〈新世界〉についての思想研究を専門とする、ケンブリッジ大学の歴史学者アンソニー・パグデンも、同様の議論をしている。 パグデンは、まず最初の重要点を指摘する。1550年にスペインのバリャドリードで開かれ、1570年代まで何度も繰り返された、アメリカインディアンが 人間か否かをめぐってのカトリック教会の公開討論が、人類学的思考と議論が作動するなかでの主要因(パラメーター)であるというのだ。 【台詞】征服者「その起訴案件は、スペイン王国の司祭兼公設史家であったフアン=ヒネス・デ・セプルベダによって示されたんだ」 【台詞】フアン=ヒネス・デ・セプルベダ「我は、古代ギリシアの哲学者アリストテレスを引き合いに出し、非西洋人は生来の野蛮人であるか、そうでなければ 自然奴隷であり幼児であると示したのである」 ドミニコ会の聖職者バルトロメ=デ・ラス=カサス(1474-1566)は、『インディアスの破壊についての簡潔な報告』として、これと相反する主張を提 示した。ラス=カサスは自身の主張を身をもって知っていた。 【台詞】バルトロメ=デ・ラス=カサス「私は、1502年からアメリカ大陸に滞在しておった 私自身がインディアンの奴隷を有し、彼らを搾取することで富を得ていたのだ。これは、私の著書『インディアス史(1566)』に詳しく記述したとおりであ る」 【台詞】アナザシ「1515年以降、ラス=カサスはその人生をインディアンの権利を弁護するのために費やしたのさ。ラス=カサスの貢献は、専門的職業上の 人類学者たちが行った以上のものだし、これは1950年代や1960年代に人類学者がアドヴォカシーを話題にし始めてからにもいえることだね」 |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099