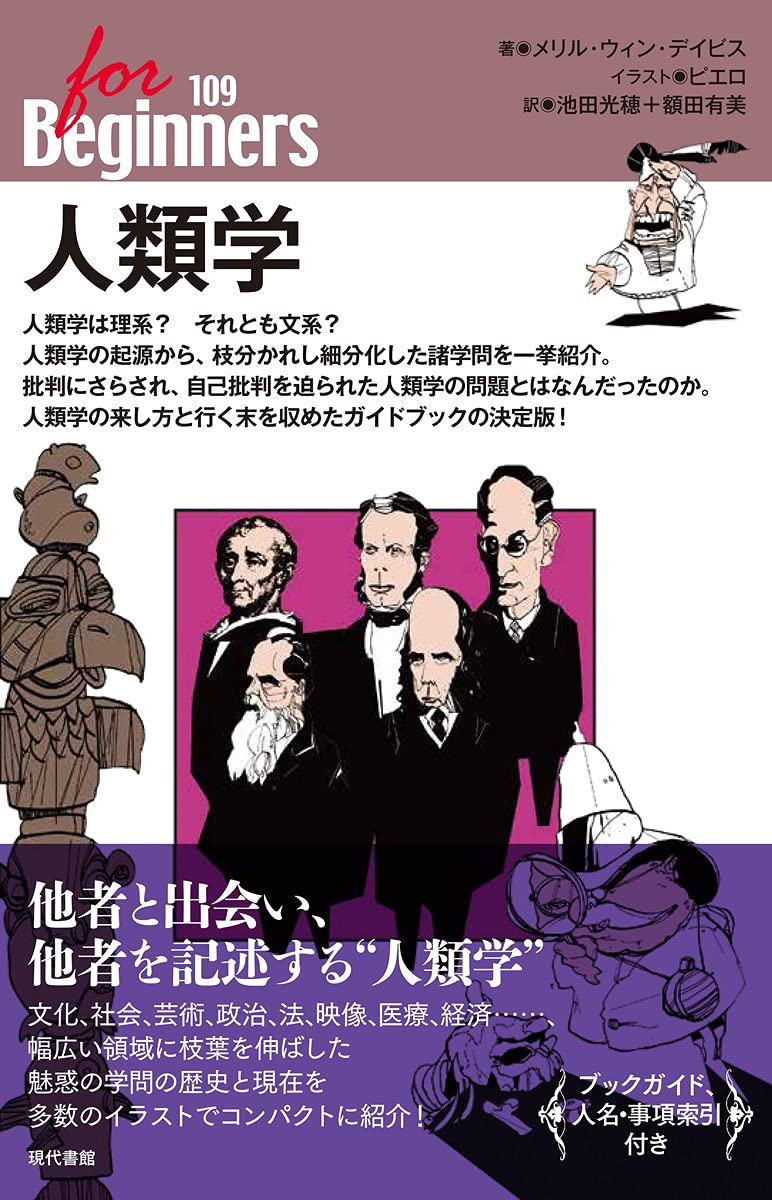
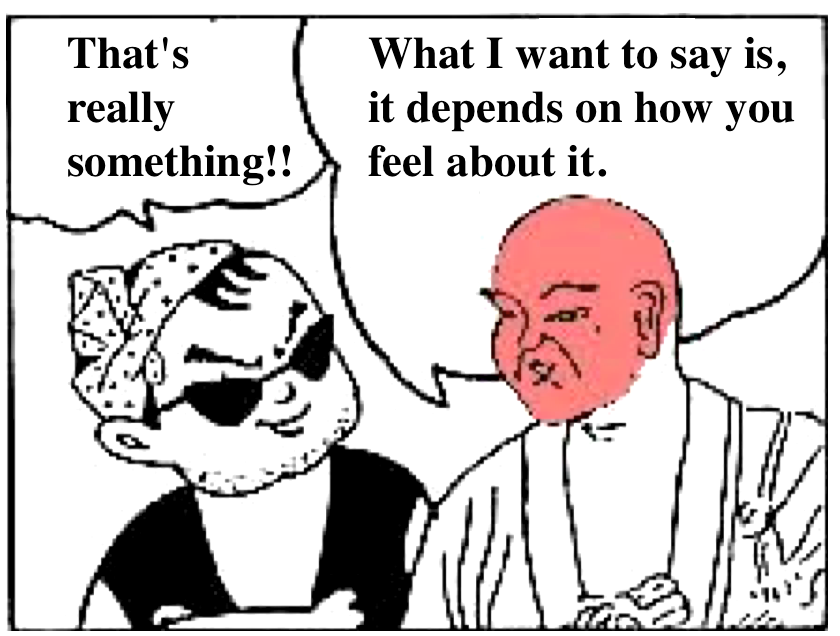

シンボリズムと新たな視点
Symbolism and a new
perspective;
A
Graphic
Guide 101
| 101 |
シンボリズムと新しい見解 |
101.
象徴主義と新たな視点 |
101. シンボリズムと新たな視点 シンボリズムの研究は、人類学の近年の展開において重要である。 ■デビッド・シュナイダー(1918-95)の象徴人類学(symbolic anthropology)は、文化を意味とシンボル(象徴)の全体的体系だと考える。シンボル(象徴)体系は、細々とした二項対立の部分に分割されるべ きではなく、経済、政治、親族、宗教といった社会組織の具体的な側面とつながっている。したがって、それは全体として研究されなければならない。 ■認知人類学は、2つの音を峻別する、つまり音声学(phonetics)と音素論(phonemic)を区別する考え方を言語学から借用している。言語 学のこの考え方が、普遍的要素を強調するエティックと、ある固有の文化で意味を持つ要素であるエミックと区別することになった。エティックが、〈客観的 な〉観察者にとって明らかな普遍的基準である一方、エミックは、特定の言語ないし文化のなかで意味を持つ対照基準である。このように考えると、文化は、概 念化の体系、つまり知識と概念の体系とされる。 ■解釈人類学は、エヴァンズ=プリチャードによるアザンデの妖術とヌアーの宗教についての研究から始まり、アメリカ合衆国の人類学者クリフォード・ギアー ツ(1926-2006)の研究と最も関連する。ギアーツは、テキストないしは為された文書としての文化体系の研究を提唱した。この研究は、エスノグラ フィーを実践する方法論である厚い記述として文化生活を細部にまでつくり上げることによって研究しようとするものである。 ■ギアーツは、レヴィ=ストロースの(「野生の思考」を批判しつつ)「頭でっかちの野蛮人」だとみなして、シンボル(象徴)を、社会的素材からつくられた テキストとしてではなく、むしろ閉じた構造として分析するレヴィ=ストロースのやり 方を「解読的」アプローチとして批判した。 【台詞】(学者)「意味は、目的から生じるのであり、公式の構造から生まれるのではないのじゃ。レヴィ=ストロースがシンボル的要素の内的な関係へ焦点を 当てたことで、実際の生活の非公式な論理が見過ごされているのじゃ」 1966年の論文「文化システムとしての宗教」において、ギアーツは、宗教を次のように定義した:「シンボルの体系であり、人間の中に強力な、広くゆきわ たった、永続する情緒と動機づけを打ち立てる。それは、一般的な存在の秩序の概念を形成し、そしてこれらの概念を事実性の層をもっておおい、そのために動 機づけが、独特な形で現実であるようにみえる」とした※。 【台詞】アナザシ「私にはギアーツが〈厚い記述〉をもって何を言わんとしているのかがわかるよ!」 ※“Religion as a Cultural System”, Geertz defined religion as: “a system of symbols which acts to establish powerful, pervasive and long-lasting moods and motivations in men by formulating conceptions of a general order of existence and clothing these conceptions with such an aura of factuality that the moods and motivations seem uniquely realistic.” 吉田禎吾ほか訳『文化の解釈学 I』Pp.150-151、岩波書店、1987年 ★「象徴人類学」→「文化要素を比較したり、象徴で置き換えたり、現地人の視点 を強調することの意味につ いて」→「クリフォード・ギアーツ」→「記号・表象・象徴」 ★「解釈人類学」→「意味のパターンと意味ある象徴の体系」→「捉え難い真理への探求と、人類学の研究倫理」→「クリフォード・ギアツの 文化人類学」 ★「エヴァンズ=プリチャード」→「エドワード・エヴァン・エヴァンズ=プリチャード」→「エヴァンズ=プリチャードのマレット講演(1950)」→「妖 術を信じなくても妖術を理解することは可能である」 ★「人類学リテラシー」 ★「野生の思考」→「ブリコラージュという概念について」→「自然と文化とそれらのハイブリッド」→「クロード・レヴィ=ストロース」 ★「文化システム(体系)としての宗教」 ★「厚い記述」→「ギアーツの「厚い記述」のメタファー」→「火掻き棒事件をめぐる〈熱い〉記述」 ★「《厚い記述》とは、さまざまな情報の積み重ねを多角的に検討すること で、エスノグラフィーの解釈をより正確にしていこうという挑戦のことをさす。決定的な記述などはなく、複雑な権力関係の中で記述が成立することから後のポ ストモダン人類学にも大きな影響を与えた。」 ▷ギアーツは、『野生の思考』を書いたレヴィ=ストロースを「頭でっかちの野蛮人」だと批判した。なぜなら、レヴィ=ストロースの方法が、現実の社会的事 実から理論を構築するのではなく、彼の頭の中だけで「暗号解きゲーム」をしているにすぎないからだと彼は論じた。 【設問:01】 「なになに人類学」という分野が鬼のようにあるのは、1)その学問が歴 史的に厚みをましてきたこと、2)専門家同士がさらに細かい下位分野を競ってつくり「偉そうに第一人者になりたがる」という2つの側面がある。どうして、 学問の専門家たちは、「偉そうに第一人者になりたがる」のだろうか?みんなで考えてみよう。 |
■ 教科書(Cultural Anthropology Remix 協賛):今回の教科書は Merryl Wyn Davies (1949-2021) が著者、Piero がイラストレーターによる、その名も『人類学を紹介する(Introducing Anthropology)』出版社は Icon Books, 2002 です。8年後に改定されて、Merryl Wyn Davies and PIERO, Introducing Anthropology: A Graphic Guide, Icon Books Ltd., 2010.となりました。いわゆる啓蒙のためのイラスト・ブックです。カルスタもとい、カ ルチュラル・スタディーズのものは日本語に翻訳されているのでな いだろうか。とってもおもしろい本です。文化人類学の現代の問題系 にまでしっかり踏み込んでい ますが、そのことを 明確するために、人類学の歴史的ルーツに遡り考察するという姿 勢が貫かれています。つまり、骨太の人類学史の教科書ともいえるべきものです。それが、な、なんと邦訳されました!!! メリル・ウィン・デイビス『人類学』池田光穂+額田有美訳、現代書館、2021年10月 ISBN-13 : 978-4768401095 [総合目次]
★ 著者紹介:Merryl Wyn Davies (1949-2021)
メ
リル・ウィン・デービス(1949年6月23日 -
2021年2月1日)は、ウェールズのイスラム教徒の学者、作家、放送作家でした。イスラム教を専門とし、ジアウディン・サルダールと共同で書籍や記事を
執筆しました。イスラム人類学の権威であり、ロンドンのムスリム研究所の所長も務めた。メリル・ウィン・デービスは、1949 年 6 月 23
日、ウェールズのマーサー・ティドフィルで生まれた。サイファースファ・グラマースクールで A
レベルを取得。ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジで人類学を学んだ後、放送局やジャーナリズムの分野でのキャリアをスタート。ウェールズの地方紙、
BBC ラジオを経て、BBC テレビの宗教番組で 10 年間働き、「Everyman」、「Heart of the
Matter」、「Global Report」[4] などの受賞番組や、シリーズ番組「Encounters with
Islam」に携わった。1981 年、31
歳でイスラム教に改宗。1985年にBBCを退職し、フリーライターとして、ロンドンを拠点とするイスラム教徒の雑誌「Inquiry」で働き始めた。
1990年代には、マレーシアの元副首相で、後に野党党首となったアンワル・イブラヒム氏の顧問およびスピーチライターを務め、マレーシアのテレビ局
TV3で「Faces of
Islam」シリーズを制作した。イブラヒム氏が逮捕されると、ウィン・デイヴィスは逃亡し、シンガポールに移住した。1996年に英国に戻り、英国イス
ラム教徒評議会のメディア担当官に就任した。2010年にロンドン・ムスリム研究所に入所し、所長に就任した。2018年に「第二の故郷」であるマレーシ
アに戻ったメリル・ウィン・デーヴィスは、2021年2月1日、クアラルンプールのペタリンジャヤで、長年の病気のため心臓発作で71歳の生涯を閉じた。
英語ウィキペディア"Merryl
Wyn Davies (1949-2021)"より
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099