On iyomante ritual of the Ainu, northern Japan, Part 1.
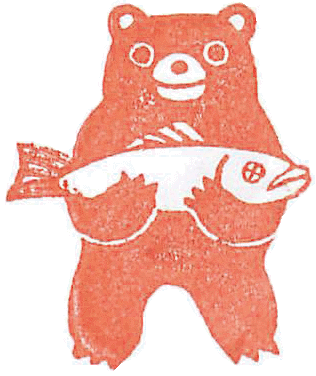
熊送りの諸相(1)
On iyomante ritual of the Ainu, northern Japan, Part 1.
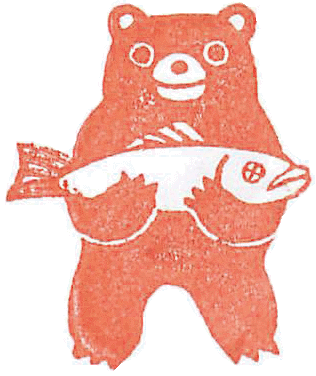
解説:池田光穂
——「そんなコタンの学校では、当時、運動会の綱引
きになると、綱が切れ、ひっくり返るまでひっぱりあったものだという。どうしても切れない時、誰かがこっそりと小刀で切ったものだという。/熊祭りの風習
である。神の国へ還る熊の霊が土産話をするためには、どうしても、綱が切れ、人間どもがひっくり返らねば面白くなかったのである。今、どこの小学校にも、こ
んなアイヌの心が伝えられているだろう」——向井豊明(1971:184-185)
動物の供犠のあり方について、パースペクティヴィ ズムという観点からアイヌのイオマンテ(クマ送り・クマ祭り:カムイを御送りする儀礼)に関するともにアイヌ社会に溶け込んだ対照的な2人の異邦 人の立場 について考えてみよう。
下図は、多気志楼主人(松浦武四郎)著『蝦夷漫画』安政六年
■動物実験;■ナグアル;■セ
リオフィリー(動物優越論):■ハゲタカと怠惰農夫の寓意
ここで取り扱われるものは1931年頃のアイヌのク マ送りである。英国のフィールド人類学ならびに医療人類学の歴史に名を残すアルフレッド・ハッドン (Alfred C. Haddon, 1855-1940)が指揮したトレス海峡探検調査(1898年)に参加したチャールズ・セリグマン(Charles G. Seligman, 1873 - 1940)は1930年以来、二風谷においてアイヌに対して診療活動する傍ら民族誌調査をしていたニール・マンロー(Neil Gordon Munro, 1863 -1942)の研究の支援者と支えることになる。マンローはそれまでに自分の書物や論文をセリグマンに送付しており、それが彼の死の20年後に人類学者と して夫と共にスーダンでも調査経験のあるセリグマン夫人(Brenda Z. Seligman, 1882-1965)が編集した『アイヌの信仰とその儀式(Ainu Creed and Cult)』として出版されることになる。
しかし奇妙なことにアイヌの熊祭りに関しては、アイ ヌの伝統的な宗教実践としてこれまで数多くの民族誌家および民族史家によって記録・言及されてきた熊 祭りについては、マンローは1931年に記録映画を撮影した以外にはまとまった記述を残していない。その直接の理由は明らかではないが、映画の公開当時、 聖公会宣教師で1877年からアイヌ地域の伝道に携わっていたジョン・バチェラー(John Batchelor, 1854-1944)が熊送りという「残酷野蛮な行事」映画の公開をアイヌの「一民族の恥」を晒すものと批判し、それに対してマンローがアイヌの信仰を擁 護して反論した経緯が背景にあった可能性があった。この確執はバチェラーが皮膚の腫瘍の切開のために1938年にマンローを訪れるまで続いたと言われてい る[桑原 1983:222-223]。(桑原千代子『わがマンロー伝』新宿書房、1983年)。次の記録は、マンローが先のセリグマンの論集の中に「追録」として 収載されている先に触れたセリグマン夫人が、マンローによる映画の説明部分から彼女自身が編集したものである。
「熊がしばらくの間みんなの前で引き廻される と、何人かの男たちが特別に作った飾り矢(花矢)を熊目がけて射かけます。この飾り矢は先端がとがっていないので、熊を傷つけるようなことはありません。 この後熊は、広場の中心に打ち込まれた杭につながれます。この行事が進められて行く中で、最後に選ばれた一人の射手が、自分の放つ本当の矢が迅速に熊に命 中してすぐに射斃(たお)すことができるように、と〈カムイ〉に向かって祈ります。竹の先端をとがらせて作った一本、時には二本の矢は、熊の身体からその 霊魂を送り出してやるために適切なやり方であると考えられています。射た熊の身体から出る血を地面にこぼすことは禁じられており、またその血がほんのわず かな雪で汚れることも許されていません。一人の長老が、去り行く熊の霊魂の無事を祈ります。前に熊の遺体を安置した祭壇を越えて何本かの霊力のある矢が空 に放たれることで、熊の霊魂が去って行ったことが確認されます」[セリグマン 2002:242-243])[原文は英語でありこの書物の翻訳者はマンローの文章を常体、セリグマン夫人の文章を敬体と訳し分けてい る]。
日本語の翻訳にして二段組みでわずか4ページほど のテキストであるが、「北極圏から亜北極圏にかけて住む多くの民族と同じように、アイヌの人びとも仕留めたあらゆる獣の身体に対しては大そう敬虔な態度で 臨んで」いたことを示すことを簡潔ながら見事に表現するものとなっている。「仔熊は〈カムイ〉であるために檻の中で仔熊は崇められながら育てられ」「また 優しく扱われて今でもかなり人に慣れて」いる。供儀にされる直前の熊に「一人の長老が祈りを唱えながら、この〈カムイ〉である熊の身体に酒のしずくを振り かけ」られ、「熊は唸り声をあげながら、それでも凶暴というよりはむしろ不意をつかれて驚いたような表情を見せながら、自らの終焉の場所へと導かれて」ゆ くわけだが供儀にする人たちはあまねく「こうすることで熊は幸せになれるだと信じ」ている[セリグマン 2002:241-242]。この熊に対する敬虔な態度は、熊の生物学的な生命が朽ち果てた後にも続く。
「雌の熊を送る儀式の場合には、その遺体に首飾 りをかけて飾ってやります。熊の霊魂に向かっては、敬意をこめた挨拶の儀を行い、人ぴとに恵みを与えてくれたことに讃辞を述べ、その霊魂を先祖のもとに 送ってやる約束の言葉を唱えて捧酒を行います。こうすることで、その霊魂を満足させてやるのです。熊の毛皮を紳いだり解体する作業は、伝統密な儀式の約束 にもとづいて行われることになっています。人びとは敬虔な態度で熊の生き血を飲むことにしていますが、この生き血は神聖な薬であるとされています(セリグマン 2002:243)。
もし民族誌家に学問的な感情移入という精神的性向と いうものがあり、その力能を我々が働かすことができれば、ここには動物の殺害に伴う凄惨な情景という ものが微塵もなく、むしろ美的なエロティシズムすら感じることができるかもしれない。「犠牲になった動物は聖なる存在になったが、しかし動物であるがゆえ に、その前からすでに聖なる存在だった。……原初の人間の眼には、動物は根本的な掟を知っているはずだと映っていた。そして動物は、自分を突き動かしてい る衝動、すなわち暴力が、この根本的な掟への侵犯であるということを知っているはずだと映っていた」[バタイユ 2004[1957]:132]。ジョルジュ・バタイユによる供儀論は、人間を供儀に使うようになった後で、時に動物がその代用として用いられるように なったが、それはそれまでも含めてもともと最古の供儀の対象は動物だったから代用できると考える。そして生命を絶つという暴力、それ自体は残虐ではない が、暴力を組織する者が登場することがそれを残虐にするという(「残虐さは、組織化された暴力の諸形態の一つ」)[バタイユ 2004[1957]:129; 131]。
このバタイユ的な残虐の概念が、アイヌという集合的 な表象「(アイヌ)民族の恥」として独り歩きすることについて、キリスト教道徳の体現者であったバ チェラーは(その根源的な理解はともかくとして)十分に感じていたと思われる。ただしバチェラーは、多少なりとも父権主義的なところはあったが植民地主義 のメンタリティを完全に体現していたとは言いがたい。彼はクマ送りの記述を抹消すべきだとは考えず、欧米の読者に対しては少なくともアイヌの文化のレパー トリーとして詳細に記述している[Bachelor 1908:239-252, 1932]。マンローの上記の記述は、バチェラーの『宗教と倫理の百科事典』[1908]に収載されたアイヌの項目のなかの「熊祭り(The bear festival)」[Bachelor 1908:249-250]を踏襲したものと言えるほど共通性があり。つまりバチェラーのマンローの記録映画に対する反発は、クマ送りの表象が日本人にア イヌの偏見を助長することを危惧することが主目的であり、儀礼の存在的価値を過小評価するものではなかった可能性がある。他方、クマ送りの儀礼をアイヌ文 化の内面から理解しようとしていたマンローは、それが少数先住民の「野蛮な」表象として統治者の日本人にどのように映るのかということに関してじつはほと んど無理解であったように思われる。にもかかわらず日本の読者には疎遠な英語で記載についても行わなかったことは依然として謎のままである。それは日本に おけるアイヌ研究において膾炙している、クマ送りとアイヌの当事者性をめぐる両者の間の確執であれば、なぜバチェラーがクマ送りの記述を残し、儀礼に対し てアイヌの内面から理解しようとした——セリグマン夫人の語り口を通してではあるが——マンローがその記述を残さなかったことは疑問のまま残され、この事 実そのものは——古典的民族誌記述にはつきものではあるが——皮肉な結果と言わざるを得ない[Rosaldo 1993](Rosaldo, Renato. Culture & Truth: The Remaking of Social Analysis. Boston: Beacon Press. 1993)。
いずれにせよエキゾチックなイヨマンテの儀礼は、日 本の社会においても歌謡曲の題名になり有名になればなるほど、アイヌと日本社会の差異性を強調する文 化表象として流通するようになる。しかし、他方、それは旧土人保護法以来、アイヌの同化をすすめる日本の統治者にとっては厄介な障壁として機能する。また アイヌの観光化に伴いパフォーマンスとしての熊祭りの挙行に関して日本動物愛護協会からの抗議などが北海道に提出された。これを象徴する事件が1955年 におこる。同年(昭和30)年3月15日に田中敏文(当時)北海道県知事名で「生きた熊を公衆の面前に引き出して殺すことは信仰上相当な理由があるにせよ 同情博愛の精神にもとり野ばんな行為であるから廃止されなければならない」等を理由に「熊祭の行事中にある熊のさらし首についても廃止」も含めて北海道内 の支庁長と市町村長に禁止の通達(文書名「昭和30年3月10日付け30畜第471号」)が送られた。
しかし、アイヌの民族に対する文化的な抑圧の象徴を 示すこの事件の文書には次のような言葉も記載されている。「生きものを憐れみ殺すに忍びない気持ちが 熊祭の形式の上にも表れるよう指導して下さい」[この通達は後に『北海道公報』6638号82ページに収載される](北海道ウタリ協会 1989:955)。
このような措置にもかかわらず少なくとも半世紀後に なってこの通達が廃止されるまでにも、すくなくとも3度の儀礼が、それぞれ1985(昭和60)年1 月に旭川市近文で、1989(平成元)年1月と2月に白老町アイヌ民族博物館で実施され、詳細に記録に残されている(池田 2009:28)。前者では写真記録が、また後者では長老・日高善次郎の伝承による儀礼の再現が試みられた。これらはアイヌの代表的な儀礼への行政からの 禁止に対する、アイヌからの応答(あるいは抵抗)であることは言うまでもない。この当時1985年にいわゆるアイヌ肖像権裁判が始まり、1988年に和解 に到っている(現代企画室編集部 1988)。
そのような歴史的経緯もあり、北海道ウタリ協会 (現、アイヌ協会)は2005年にこの儀礼禁止の通達の撤回を求めた。北海道は国に対して「動物の愛護及 び管理に関する法律」(1963(昭和48)年制定)との関連性について照会し、同年10月に環境省は動物を利用した祭式儀礼について「正当な理由をもっ て適切に行われる限り法律に抵触しない」ことを示し、道庁は2007年3月に環境省は「イヨマンテは祭式儀礼に該当する」と回答をした。それを受けて同年 4月2日付で先の通達の廃止を北海道に通知した。
このようにアイヌのクマ送りの近代化の歴史は、人類 学者に対しては一種のメタ知識としてのアイヌのコスモロジーを理解するための儀礼装置を提示してく れ、また儀礼に参加する当事者にとってはクマの〈カムイ〉と交流する始原的世界の体験とそれがもたらす感情の多声的空間からの後退を意味するものであっ た。またアイヌ自身にとっては、道庁が禁止する以前は、観光化のなかでその始原的な意味が形骸断片化することで急速に生きた意味を失い、他方、禁止以降 は、抑圧されるアイヌ文化のよりどころ、あるいは民族文化のアイデンティティとして、急速にその文化の記録と再構成が「民族再生」のための喫緊の課題に なっていく。
このようなクマ送りの復元の政治化は、「クマ送りの 儀礼は(もともと本来は)どのような意味をもっていたのか?」という本質主義的な人類学の関心から遠 ざけることになった。近代のクマ送りの文献を子細に検討した煎本孝は、このような状況に研究上の不足を覚え、次のように述べる。「昭和に入ってからの熊送 り儀礼は、その詳細な記録にもかかわらず、狩猟採集生活の実際の経験の少ない、あるいは全くない参加者により行われたものであると考えられ、したがって、 これら熊送り儀礼が実際にはどの時代にまでさかのぼり得、またどのような歴史的脈絡の中で位置づけられるのかということを検討しなければならない」[煎本 1986:53]。煎本の主張を敷延すれば「採集狩猟生活の実際の経験」のない人たちが再演したクマ送りの記録や彼ら自身の体験は、アイヌが歴史的時間の 中で経験してきた儀礼の内容を反映しておらず、同じ儀礼手続きを執行しているとしても、儀礼の行為者や参加者に去来する感覚はそれぞれまったく別物である ということになる。
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099