On comparative methods, symbolic representation tactics, and remarks
on "native point of view"
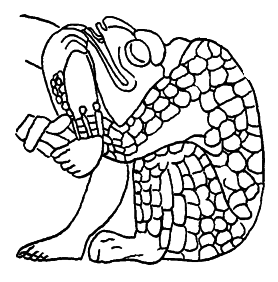
文化要素を比較したり、象徴で置き換えたり、現地人の視点を強調することの意味
On comparative methods, symbolic representation tactics, and remarks
on "native point of view"
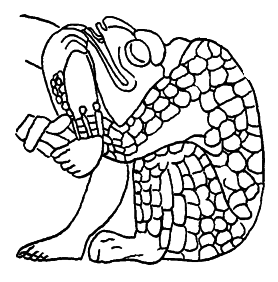
池田光穂
文化の要素を単純に比較して(例えば、日本では縦書 き(箸)だが、西洋は横書き(ナイフとフォーク))、その差異がわかったということはできない。ただ、単に異なったものどうしを併置して「違うと指摘して 満足している」からである。文化人類学を研究するものにとって、問題の本質は、その違いは〈なぜ〉あるのかという、ほとんど解答不能なことを探究すること ではない。〈どのように〉違うのかを適切に説明することである。箸とフォークの例えで言うならば、そもそも食べている料理が違い、それらの料理の種類の違 いに、食器用具の違いが対応しているからである。また、料理の違いとは、それらがたべられる情景・情況な、その場におけるテーブルマナーや、一緒に食事す る人たちの社会的属性の違いなども違いがある。箸とフォークの違いは、それが使用されるさまざまな違いの一連の連鎖のなかのひとつにすぎない。このよう に、一つの違いを検討するときには、その要素の周辺に比較可能な要素をさらに拡大していって、それらがどのような社会的脈絡(=文脈ともいう)の中で意味 をなすのかを子細に検討することが必要だ。
文化人類学者のクリフォード・ギアーツは、そのよう な文化の理解のための、比較という方法論も、子細に文脈を追ってゆくと(=文脈化という)、それを説明する文化的要素そのものが、その文化にとって固有の 要素からなりたっていることを指摘した。文化の説明には、例えでの表現(隠喩や提喩、寓意=アレゴリー、皮肉、あてこすり等等)が豊富にある。それらが、 どのような説明から成り立っているのかを詰めて考えてみようと、ギアーツは提唱している。それは、文化分析の専門家にとって、なにも超絶技巧の修業を要求 することではない。その社会の中にはいって、人びとの「肩越し」にのぞかせてもらい、「彼/彼女らが考える」ように、自分の思考法を相手の社会のなかでく り返しくり返し、経験を通して学んでゆくことだ。
これらは、やってもやってもきりがないこともある。
しかし、自分が、その調査している社会から離れ、資料を整理する過程のなかで、「再度その文化のなかでおこった出来事」を説明しようと試みることの中に、
地と図が逆転するように、見えてくることもあることを指摘している。そして、多くの人類学者は、そのような経験を持ったことがあると、同意してくれるであ
ろう。
■さまざまな疑問
「……住民の視点」についてわれわれに何を語るか、 ないしは適当なやり方をすれば語るはずなのか……象徴の使用についてわれわれが描写するときには、知覚や感情や展望や経験について描写しているのであろう か。それはどのような意味においてであろうか。われわれが、この事例では人が相互に定義される際の記号論的手段を理解すると主張するとき、われわれは何を 主張しているのであろうか。言葉の理解であろうか、心の理解であろうか」(ギアーツ 1999:120)。
[L]et us return
to the question of what all this can tell us, or could if it were done
adequately, about "the native's point of view" in Java, Bali, and
Morocco. Are we, in describing symbol uses, describing perceptions,
sentiments, outlooks, experiences? And in what sense? What do we claim
when we claim that we understand the semiotic means by which, in this
case, persons are defined to one another? That we know words or that we
know minds?
■処方せん=解釈者自身による解釈知の行為を反省実 践(=批判)すること
「この疑問に答える際に必要であると私が思うのは、 まず第一に、これらの分析のそれぞれに、事実マリノフスキーを含めてこの種の分析に常にみられる知の特徴的な動き方、内なる概念のリズムに注意を払うこと である——すなわち、地方固有(ローカル)の細部中の細部と、包括的な上にも包括的な構造とが、双方とも同時的に見えてくるようなかたちで継続的弁証法的 に引き寄せられているという点である。ジャワやバリやモロッコの自己の感触を見出すために、最良の民族誌をも読み難くするような異邦の些事の類い(対比的 語葉、図式的範曙化、語形的日音素的変形)と、ごく当たり前のことでもない限りどこか受け容れ難いところのある荒っぽい特徴づけの類い(「静謐主義」、 「演劇主義」、「文脈主義」)との間を、休く揺れ動くのである。全体を実現する部分を通じて概念化された全体と、部分を動かす全体を通じて概念化された部 分との間を行きつ戻りつすることによって、われわれは部分と全体を、一種の知の永続的運動により互いを明らかとするものに転じようとするのである」(ギ アーツ 1999:120)。
In answering this
question, it is necessary, I think, first to notice the characteristic
intellectual movement, the inward conceptual rhythm, in each of these
analyses, and indeed in all similar analyses, including those of
Malinowski--namely, a continuous dialectical tacking between the most
local of local detail and the most global of global structure in such a
way as to bring them into simultaneous view. In seeking to uncover the
Javanese, Balinese, or Moroccan sense of self, one oscillates
restlessly between the sort of exotic minutiae (lexical antitheses,
categorical schemes, morphophonemic transformations) that make even the
best ethnographies a trial to read and the sort of sweeping
characterizations ("quietism," "dramatism," "contextualism") that make
all but the most pedestrian of them somewhat implausible. Hopping back
and forth between the whole conceived through the parts that actualize
it and the parts conceived through the whole that motivates them, we
seek to turn them, by a sort of intellectual perpetual motion, into
explications of one another.
■解釈学的循環(ディルタイ)
「こうしたことすべては、言うまでもなく今ではよく 知られているように、ディルタイが解釈学的循環と呼んだものの軌跡をたどることであり、私のここでの議論とはそのような循環が、文学、歴史、学、精神分 析、聖書における解釈の場合と同じように、あるいはまたわれわれが〈常識〉と呼ぶような、日常経験に対するインフォーマルな註釈の場合と同じように、民族 誌における解釈の場合にも、つまり他の人々の思考様式に入り込もうとする場合にも、やはり中心的であるということにすぎない」(ギアーツ 1999:121)。
All this is, of course,
but the now familiar trajectory of what Dilthey called the hermeneutic
circle, and my argument here is merely that it is as central to
ethnographic interpretation, and thus to the penetration of other
people's modes of thought, as it is to literary, historical,
philological, psychoanalytic, or biblical interpretation, or for that
matter to the informal annotation of everyday experience we call common
sense.
■現地人のジョークが理解できること
「要するに、他の人々の主観性についての説明は、自 己を滅却し他人に仲間意識を抱くことについての並はずれた能力を持つことを装わなくても可能であるということである。こうしたことについて並程度の能力を 持つことはもちろん本質的に重要であるし、もし人々の生活へ侵入することをそもそも許容され、話をするに値する人物として受容されるととをわれわれが期待 するなら、そうした能力を伸ばすことも重要である。言うまでもなく私は、他人への感受性が鈍くてよいと言っているのではないし、そうした鈍さをここで私が 示さなかったことを望みたい。しかしわれわれのインフォーマントが、よく使われる言い方では〈本当のところどんな〉人々なのかについて、どれほどまで正確 な、ないし半ば正確な感触を得るにしても、そのような感触はわれわれが受容されること自体から来るのではない。受容されたことは、彼らの伝記ではなくわれ われの伝記に記すべき事柄である。そのような感触は、彼らの表現様式を読みとる能力、私が象徴体系と呼ぼうとするものを読みとる能力から来るのであり、こ の能力を伸ばすことは、そうした受容があってはじめて可能となるのである。いま一度だけあの危ない言葉を使えば、〈住民の内面生活〉におけるかたちや力を 理解するとは、心を交えることよりは、諺を解したり、のめかしに気づいたり、冗談がわかったり——あるいはここで示唆してきたように、詩を読んだり——す ることに近いということである」(ギアーツ 1999:122-123)。
In short, accounts of
other peoples' subjectivities can be built up without recourse to
pretensions to more-than-normal capacities for ego effacement and
fellow feeling. Normal capacities in these respects are, of course,
essential, as is their cultivation, if we expect people to tolerate our
intrusions into their lives at all and accept us as persons worth
talking to. I am certainly not arguing for insensitivity here, and hope
I have not demonstrated it. But whatever accurate or half-accurate
sense one gets of what one's informants are, as the phrase goes, really
like does not come from the experience of that acceptance as such,
which is part of one's own biography, not of theirs. It comes from the
ability to construe their modes of expression, what I would call their
symbol systems, which such an acceptance allows one to work toward
developing. Understanding the form and pressure of, to use the
dangerous word one more time, natives' inner lives is more like
grasping a proverb, catching an allusion, seeing a joke--or, as I have
suggested, reading a poem--than it is like achieving communion.
文献
リンク・文献

