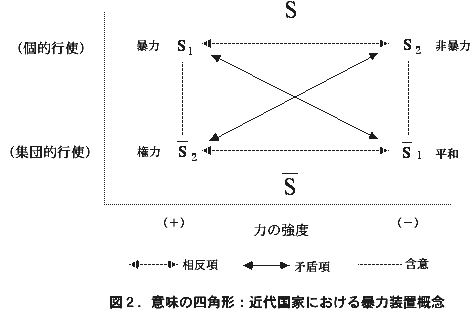
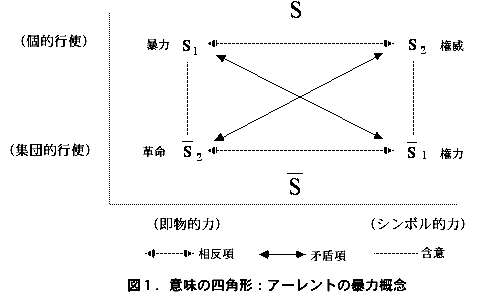
暴力の文化
The Culture of Violence
暴力と権力を対極のものとするアーレントの理念(→政治的暴力の概念)とは裏腹 に、現実の近代国家の暴力装置はその行使を常態的に逸脱してきたことは歴史的に明白である。それを国家によるテラーの行使と位置づけたワルターは、その先 駆的な研究『恐怖と抵抗(Terror and Resistance)』において、国家が濫用する暴力の特長をつぎの三点にまとめている[WALTER 1969]。
(I)まず、国家テロは、文化によってさまざまな形態がみられる一方で、通文化的共通点もみられること。[→テロリズム]
(II)次に、通常の国家がテロ行為を行うことは、それほど珍しい現象ではないし、現実にすべての国家においてそれを準備できる能力をもっ ている。
(III)そして最後に、テラーの行使はいつも「最後の手段(ultima ratio)」と思われているが、実際には「優先手段(prima ratio protestatis)」として使われている。
つまり、近代国家を生きる我々にとって、テラーとは日常生活からかけ離れた非日常な出来事ではない。むしろテラーとは、我々の生活空間と壁一枚 隔てたところで進行している事態であり、それらは局所的な特殊事象でありながら同時にかつグローバルな一般的事象である。したがって政治的暴力の意味を社 会的現実に押し戻して人類学的に考えることの意義がここで浮上する。
では政治的暴力の研究について、人類学者は今までどのような貢献をしてきたのだろうか。
スルカによれば、この種の研究領域は「恐怖の文化(culture of terror)」という言葉でまとめられる[SLUKA 2000]。
タウシグは、政治的拷問や殺人が局所的(endemic)に流行すれば、そこに恐怖の文化が繁茂するという[TAUSSIG 1992]。このような文化が「存在」したのが、ラテンアメリカでは、一九七〇年代後半から八〇年代初頭のアルゼンチン、ピノチェト政権時代(一九七三— 八九年)のチリ、そして内戦期のグアテマラであるというのだ。
実際グリーンはグアテマラの内戦時の状況を「恐れの常套化(routinization of fear)」と呼んでいる[GREEN 1995]。恐怖の文化とは、恐怖つまりテラーを統治手段として採用することにともなう、一種の共同幻想の産物である。いささかスキーマ的になるが、それ をまとめると次のような社会的経過をたどる。
これらの事態が起こるとそれに連鎖して事後的に社会の人びとの中に次のような意味が形成、共有される。つまり,
「貧困の文化」概念が登場した時と同じように、このような主張は文化概念に ついての理解を矛盾する二極に分解化してしまう[LEWIS 1966; LEACOCK 1971]。
つまり「暴力の文化」において、一方では政治的暴力の発動のプロセスを普遍的メカニズム(作用機序)として説明する。しかし、他方では、この概 念化によって政治的暴力が生起した社会の特殊状況に還元するという本質主義的説明に回収してしまう。これらは一度に両立することができないために「貧困の 文化」論争と同様の問題を抱えてしまう。暴力の文化を措定した際に、普遍主義に立つ説明では、ある政治的暴力が生起した歴史的社会的状況における偶然的諸 条件についての考察を過小評価してしまう危険性があるからだ。
また個別還元主義では、アーレントのいうところの「権力」を政治的暴力が無力化した際には、アルゼンチン、チリ、グアテマラのように「恐怖の文 化」は社会の固有の文化状況に強く結びつけて説明されてしまう。しかしながら、暴力あるいは暴力後の世界を生きる人間にとって重要なことは、このような用 語法と概念を通して、どのような経路を通って、それが不可避となったのか、ならなかったのか、ある歴史的時点における、より適切な防止策とはなんだったの か、ということを具体的に知ることにある。その審問の動機は、歴史現象から教訓を得るということよりも、同時代的あるいは対位法的に暴力と暴力の対照事象 を見ることにある[例えば、サイード 一九九八、二〇〇一]。
他方、政治的暴力についての人類学調査にともなう具体的困難も指摘されている。
まず政治的暴力の「現場」という問題である。それは、実際に暴力が行使される現場に居合わせるという機会に遭遇することの困難である。現実に拷 問の現場に参与観察が可能であるとは思われないし、待ち伏せ攻撃の最中で質問票を回すことなど考えることはできまい。より多くの研究が結果的に暴力的状況 に巻き込まれてしまった結果の産物である[NORDSTROM and ROBBEN 1995]。もちろん、この現場というのは狭義の政治的暴力のことを指している。
広義の政治的暴力とは、たんに暴力が行使される現場だけで知り得るものではないし、むしろそのような暴力的状況は日常性の中に組み込まれ、身体 的経験をともなう「記憶」として、我々の前に投げ出されている。また裁判や集会さらには宗教儀礼の現場において様々な形で表出する集合的な想起行為を含ん でいる。
したがって政治的暴力の研究は、最初から対象を刮目することにともなう困難がある。隠喩的に言えば、政治暴力についての人類学的現場は、当事者 ならびに人類学者が抱えている恐怖というシートに覆われていて見ることができない。とすれば、先のタウシグのいう恐怖の文化とは、暴力の現場を覆い隠そう とする隠喩的暴力(=恐怖)、つまり政治的暴力に対して沈黙を強いようとする恐怖に対抗する研究領域であるとも言える[TAUSSIG 1992]。
また直接的暴力が行使された場合、被害者と加害者の対立構図というのは、その原因や社会的背景とは別個に比較的明確になる(この問題点は次節で 検討する)。
このようなはっきりした枠組の中で、いわゆる文化相対主義をとる調査というものは苦境に立たざるを得ない。特に加害者についての調査研究の場合 は、調査者は微妙な立場に立たされることになる。
ロビン[ROBIN 1996]は、アルゼンチンの「汚い戦争」時における、拷問や超法規的処刑に携わった軍関係者へのインタビューを続けてゆく過程で、加害者たちは、しばし ば我々がステレオタイプするような残忍な性格の持ち主ではなく、高い教養をもつ紳士たちであったことを感じた。それゆえ加害者に対してある種の好意的な感 情移入をしてしまう危険性を彼は危惧している。同様に、政治的暴力をめぐって、加害者と被害者の相互の調査を続けてゆくうちに、そのギャップに苛まれると いうストレスも感じる。彼はこのような民族誌学調査にまつわるストレス状況を民族誌的誘惑(ethnographic seduction)と呼んでいる[ROBIN 1996:72]。
このストレスの原因は、研究対象を純粋に客体化することや、逆に人権擁護を前提に調査をおこなうことが、研究者自身の道徳的距離のとり方を自動 的に決定してしまうことに起因する。ここから通常の状態ではなかなか遭遇しないような恐怖の事例を、民族誌的に構成することが、いかに異例のことであるか がわかる。そのような研究対象について人類学の民族誌記述の方法論がいまだ十分に検討されていないことも明らかだ。
このようなジレンマに対して研究者に一種の避難場所を与えるのが心理学的解釈を動員することである。
一九七〇年代後半のアルゼンチンの政治的暴力の被害者である失踪者(desaparecido)の家族についてロスアンゼルスで調査研究したス ウァレス=オロスコは、犠牲者の家族と加害者に心理学的テストを含めた民族誌的作業を通して「声なき声に我々がどのように声を与えることができるか」を研 究課題として掲げている[SUARES-OROZCO 1990:354]。
しかし、彼の分析には「精神病的(psychotic)」「ヒステリー的拒絶(hysterical denial)」「幻想(fantasies)」「幻覚(hallucination)」「集合的誤認(collective delusion)」「偏執的エトス(paranoid ethos)」など定義不明確な精神病理的隠喩表現に満ちあふれており、声を与えると言っておきながら、実際には心理学パラダイムの用語によって声を代弁 する。また用語の解釈の妥当性においては、それ自体が論争的なものになっている。
政治的暴力の意味を日常の社会的次元に還元して論争をより公共的なものにするためには、心理学的説明は、失われる声の代価が高すぎるように私に は思える。
■ リンク
■ 文献
■その他の情報:暴力と権力を対極のものとするアーレントの理念(→政治的暴力の概念)
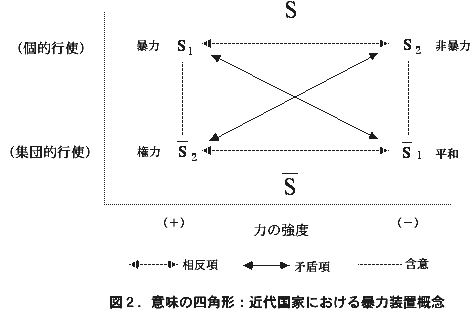
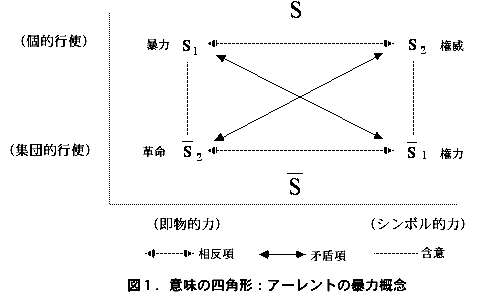
■クレジット:池田光穂「政治的暴力と人類学を考える:グアテマラの現在」,『社会人類学年報』,第 28 巻,.
Pp.27-54,2002 年 8 月
(いけだ・みつほ 大阪大学COデザインセンター 社会イノベーション部門 教 授)