
斎藤成也
Nariya SAITO, b.1957

☆ 斎藤 成也(さ いとう なるや、1957年〈昭和32年〉1月14日 - )は、日本の遺伝学者。国立遺伝学研究所教授、総合研究大学院大学生命科学研究科遺伝学専攻教授、東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻教授。日本学術 会議会員。福井県出身。専門は、ゲノムの進化,特にヒトのゲノム進化を、コンピュータ解析とゲノム配列決定の研究。主要な研究テーマ:(1)現代人と古代 人のゲノム解析、(2)哺乳類を中心とした多様な生物ゲノムの配列決定とその解析、(3)分子進化研究で有用な系統解析法の開発、など。2022年3月末 に国立遺伝学研究所を退職。2022年4月からは、ジェネシスヘルスケア社との共同研究費用により特任教授に就任。http://www.saitou-naruya-laboratory.org/
| 斎藤 成也(さいとう
なるや、1957年〈昭和32年〉1月14日 -
)は、日本の遺伝学者。国立遺伝学研究所教授、総合研究大学院大学生命科学研究科遺伝学専攻教授、東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻教授。日本学術
会議会員。福井県出身。 中立進化論を主張している。アイヌと琉球人の近縁性についての研究結果を定期的に発表している[1][2]。 経歴 1972年福井大学教育学部附属中学校卒業、1975年福井県立藤島高等学校卒業、1979年東京大学理学部生物学科人類学課程卒業、1987年同大学院 理学系研究科博士課程人類学中退、1986年テキサス大学ヒューストン校生物医科学大学院修了(Ph.D.)。 1989年2月より東京大学理学部生物学科人類学教室にて助手を経て、1991年1月、国立遺伝学研究所進化遺伝研究部門助教授。翌1992年10月より 総合研究大学院大学生命科学研究科遺伝学専攻助教授を併任。 1994年3月、「分子レベルにおけるヒト科の進化 (Hominoid Evolution at the Molecular Level)」により東京大学より理学博士の学位を取得。1995年、国際日本文化研究センター助教授を1998年まで併任。同年、日本遺伝学会奨励賞を 受賞。 2002年、国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門教授に就任、および総合研究大学院大学教授を併任。2004年木原記念横浜生命科学振興財団より第12回木 原記念財団学術賞受賞、2005年10月より日本学術会議第20期会員、2006年には東京大学理学系研究科生物科学専攻教授就任、同年、京都大学大学院 理学研究科生物科学専攻教授を併任。 |
●日本人の源流 : 核DNA解析でたどる /
斎藤成也著, 河出書房新社 , 2023 . - (河出文庫, [さ47-1]) ●【書肆解説】アフリカを出た人類の祖先は、いかにして日本列島にたどりつき「ヤポネシア人」となったのか?中国人や東南アジア人ともかけ離れた、縄文人 のDNAの特異性とは?また、縄文人・弥生人とも異なる集団は存在したのか?さまざまな証拠を組み合わせて導かれる日本人の実像とは?先端科学を駆使し て、日本列島人20万年の旅のミステリーに挑む!
|
| 著書 『遺伝子は35億年の夢を見る―バクテリアからヒトの進化まで』大和書房、1997年。ISBN 9784479390855。 『ワードマップ ゲノムと進化 ――ゲノムから立ち昇る生命』新曜社。ISBN 978-4788509122。 『DNAから見た日本人』ちくま新書、2005年。ISBN 978-4480062253。 『ゲノム進化を考える 系統樹の数理から脳神経系の進化まで』サイエンス社 臨時別冊・数理科学 SGCライブラリ 2007 『ゲノム進化学入門』共立出版 2007 『自然淘汰論から中立進化論へ 進化学のパラダイム転換』NTT出版 叢書コムニス 2009 『ダーウィン入門 現代進化学への展望』ちくま新書 2011 『日本列島人の歴史』岩波ジュニア新書〈知の航海〉シリーズ) 2015 『核DNA解析でたどる 日本人の源流』河出書房新社 2017 共編著 『遺伝子とゲノムの進化』藤博幸,小林一三,川島武士,佐藤矩行,植田信太郎,五條堀孝共著 岩波書店 シリーズ進化学 2006 『ゲノムはここまで解明された』編著 ウェッジ選書 「地球学」シリーズ 2007 『絵でわかる人類の進化』編 海部陽介,米田穣,隅山健太著 講談社 絵でわかるシリーズ 2009 『生物学者と仏教学者七つの対論』佐々木閑共編著 ウェッジ選書 2009 『岩波生物学辞典』第5版 巌佐庸,倉谷滋,塚谷裕一共編集 岩波書店 2013 『最新DNA研究が解き明かす。日本人の誕生』河合洋介, 木村亮介, 松波雅俊, 鈴木留美子共著 秀和システム 2020 翻訳 根井正利『分子進化遺伝学』五条堀孝共訳 培風館 1990 ジョンジョー・マクファデン『量子進化 脳と進化の謎を量子力学が解く!』監訳 十河和代,十河誠治訳 共立出版 2003 https://x.gd/1ZjrH |
●ゲノム進化学 / 斎藤成也著、共立出版 , 2023 第1部 進化は生物学を統合する 1. DNAからゲノムへ 2. DNAからタンパク質へ 3. 生物界の階層構造 4. 生命の歴誌 第2部 ゲノム進化のメカニズム 5. 突然変異 6. 系統樹 7. 集団の遺伝 8. ゲノムの長期進化 第3部 ゲノム進化の研究法 9. ゲノム配列の決定とデータベースの利用 10. 整列と置換数の推定 11. 系統関係の復元 12. 集団進化史の解析 13. ゲノムと表現型をつなぐ |
| When I was sophomore in the
University of Tokyo, 19 years old in 1976, I came to know the neutral
theory of evolution by reading a Japanese review article written by Dr.
Kimura Motoo (ref. 1). I
immediately fell in love with this theory, and started to learn
population genetics theory and
molecular evolution. When I was senior at Department of Biology,
majoring in physical
anthropology, I decided to study genetical anthropology under Professor
Omoto Keiichi. I carefully
read one paper on molecular phylogeny written by Cavalli-Sforza and
Edwards in 1967 (ref. 2). I
was asked to explain this paper by Omoto laboratory members including
Dr. Horai Satoshi, who
later joined NIG. This experience gave me a great hint when I developed
the neighbor-joining
method (ref. 3). In my master course, I estimated the age of mutants found in Philippine Negrito populations by Professor Omoto’s group, applying a branching process. This was my master thesis, but my first academic paper was estimation of migration pattern in Japan using surname data collected through telephone books. This paper, written in Japanese, was published in 1983 (ref. 4), when I was in Houston, Texas. After visiting Negrito villages in the Philippines from December 1981 to January 1982, I joined Professor Masatoshi Nei’s Laboratory in University of Texas, Houston in the summer of 1982. Nei Laboratory was a stronghold of the neutral theory at that time. Drs. Wen-Hsiung Li and Ranajit Chakaraborty were faculty members, Drs. Gojobori Takashi and Chung-I Wu were postdoc, and Drs. Tajima Fumio and Dan Graur were graduate students. During four years in Houston, I worked pretty hard, and my Ph.D thesis consisted of three chapters including proposal of the neighbor-joining method. I also analyzed influenza A virus gene sequence data, and published two papers, but did not combine these with my Ph.D. thesis. I returned to Japan in fall of 1986, and did two years of JSPS postdoctoral fellow. During that period, I visited ethnic minorities in Hainan Island, China with Professor Omoto. I then became an assistant professor at Department of Anthropology, Faculty of Science, the University of Tokyo in 1989. I visited indigenous peoples in Taiwan with Dr. Horai Satoshi in 1990 and 1991. Professor Gojobori Takashi, who became head of DDBJ at NIG at that time, asked me to join DDBJ. I was very pleased with this offer, and joined NIG as associate professor at Division of Evolutionary Genetics on January 16th, 1991. Therefore, I have been at NIG for slightly more than 31 years, though I worked for DDBJ until 2008. During this period, I published 233 papers and books. Among them, 23 are single-authored ones (mainly review articles) and 9 are first-authored ones. I am corresponding author of 45 papers that were first-authored by my former students and postdocs. Papers that were mainly produced by SAITOU Lab members are very heterogenous. For example, Satoshi OOta, my first Ph.D. student, estimated the phylogeny of muscle tissues (ref. 5). This work was mentioned by Nick Lane’s book (ref. 6) for general audience. One of my nephews who went to law school read its Japanese translation, and he was surprised by finding my name in that book. Though this paper was cited only 93 times according to Google Scholar, I am happy with this episode. When I moved to NIG, I just started to analyze human ABO blood group gene sequences. I contacted Dr. Fumiichiro Yamamoto, who determined the nucleotide sequences of human ABO genes for collaboration. I suggested him to determine non-human ABO blood group sequences, and he did. Therefore, when Takashi Kitano, my second Ph.D student, joined my laboratory in 1996, I suggested him to study orthologs of human Rh blood group genes and its paralogous genes. We collected bone marrow samples from mice, rat, and crab-eating macaque, and determined Rh and Rh50 gene sequences (ref. 7). In 2000, determination of the draft human genome sequences was announced. Area of molecular evolution should also move to evolutionary genomics. I thus started Ape Genome Project, nicknamed Silver, for atomic symbol of silver is Ag. With the help of Dr. Fujiyama Asao, Dr. Kim Chun-Gong produced gorilla fosmid library (ref. 8). My laboratory was also involved in the international chimpanzee chromosome 22 sequencing project headed by Dr. Sakaki Yoshiyuki. However, I was also interested in gene hunting, and focused on ear wax gene. Ear wax has a long history of research in Japan. Dr. Takahashi Aya, who just received Ph.D. in University of Chicago under Professor Chung-I Wu, joined my lab as a post-doc in 2000, and I suggested her to hunt for ear wax gene. In one day in 2002, I found a surprising news in a Japanese weekly magazine; Nagasaki University group discovered the ear wax gene. I was shocked, but found the corresponding paper and was relieved to know that they only narrowed down the chromosome region for the ear wax gene. I quickly contacted Professor Niikawa Norio at Nagasaki University Medical School, and my laboratory joined the ear-wax hunting team. Eventually, four years later, ABCC11 was found to be the gene for ear wax (ref. 9). My former student Ishibashi Minaka, as well as Takahashi Aya and myself, were coauthors of this paper. When Takahashi (now Ueda) Mahoko joined my lab as the 11th Ph.D. student in 2005, I suggested her to study CNSs (Conserved Noncoding Sequences) among primates and rodents. Matsunami Masatoshi, my 12th Ph.D. student, also studied CNSs, but he first focused on Hox gene clusters, and his paper (ref. 10) was the first CNS related paper published from Saitou Laboratory. Later, three students from Nigeria (Isaac Babarinde), Sri Lanka (Nilmini Hettiarachchi), and Iran (Mahmoudi Saber Morteza), as well as Inoue Jun, who constructed dbCNS (http:// yamasati.nig.ac.jp/dbcns/), also studied CNS evolution. Meanwhile, Timothy A. Jinam joined my laboratory as Ph.D. student in 2008. He already had experience of analyzing genome-wide SNP data of modern human populations in Malaysia. I thus suggested him to study similar data of Japanese populations. He has been very productive, and after doing postdoc at Division of Human Genetics, NIG, he became assistant professor of my laboratory after Dr. Sumiyama Kenta moved out to Riken Center for Biosystems Dynamics Research. Tim is an important member of our “Yaponesia Genome Project” (http:// www.yaponesian.jp). Kanzawa Hideaki became Ph.D student of my laboratory in 2009, and he wanted to study ancient DNA. I managed to find some grant from Indus Project at Research institute for Humanity and Nature to set up a primitive aDNA working space in my laboratory, and he eventually obtained partial genome sequence of Jomon people, and we published a paper in 2016 (ref. 11). In 2020 A.D. (or in my year, year 0020), I started a new online journal “iDarwin” (http:// idarwin.org) on the birthday of Charles Darwin (ref. 12). At this moment, not many articles are published in this journal, however, I do hope that this journal will become an important asset for evolutionary studies. |
私
が東京大学2年生の1976年、19歳の時に、木村資生博士の総説(文献1)を読んで、中立進化説を知った。私はすぐにこの理論に魅了され、集団遺伝学と
分子進化の勉強を始めた。 大学4年の時に、生物学科の物理人類学を専攻していた私は、大本圭一教授の下で遺伝人類学を研究することにした。
1967年にCavalli-SforzaとEdwardsが発表した分子系統学に関する論文(参考文献2)を注意深く読み、
この論文について、大本研究室のメンバー(後に国立遺伝学研究所に入られた蓬莱尚幸先生を含む)に説明を求められた。この経験は、私がNeighbor-
Joining法(参考文献3)を開発する際に大きなヒントとなった。 修士課程では、大本研究室でフィリピンのネグリト族で見つかった突然変異体の年齢を推定する研究を、分岐過程を応用して行った。これが修士論文だったが、 最初の学術論文は、電話帳から集めた苗字データを使って日本の移動パターンを推定したものだった。この論文は日本語で書かれ、1983年にテキサス州 ヒューストンにいたときに発表された(参考文献4)。1981年12月から1982年1月にかけてフィリピンのネグリトの村々を訪問した後、1982年の 夏にテキサス大学ヒューストン校のネイ教授の研究室に加わった。ネイ研究室は当時、中立説の拠点であった。ウェン・シオン・リー博士とラナジット・チャカ ラブォルティー博士が教員、五條堀 孝博士とチョン・イ・ウー博士がポスドク、田島 文雄博士とダン・グラール博士が大学院生であった。 ヒューストンでの4年間はかなりハードに働いた。私の博士論文は、隣接結合法の提案を含む3つの章から構成されていた。また、インフルエンザAウイルスの 遺伝子配列データの解析も行い、2本の論文を発表したが、これらは博士論文には盛り込まなかった。1986年秋に帰国し、日本学術振興会特別研究員として 2年間を過ごした。その間、大本教授と中国海南島の少数民族を訪ねた。1989年には東京大学理学部人類学科の助教授に就任した。1990年と1991年 には、蓬莱尚志博士とともに台湾の先住民を訪ねた。 当時、NIGのDDBJのセンター長となられた五條堀孝先生からDDBJへの参加を依頼された。 私はこの申し出を非常に喜んで、1991年1月16日に進化遺伝研究部門の助教授としてNIGに加わった。 したがって、私は2008年までDDBJで働いていたが、NIGには31年余り在籍していることになる。この間、論文や著書を233件発表した。そのうち 単著は23件(主に総説)、筆頭著者は9件である。私の元の学生やポスドクが筆頭著者の論文45件の責任著者を務めている。 サイトウ研のメンバーが主に執筆した論文は、非常に多様性に富んでいる。例えば、私の最初の博士課程学生である太田聡は、筋肉組織の系統樹を推定した(参 考文献5)。この研究は、一般読者向けのニック・レーンの著書(参考文献6)で言及された。法学部に進学した私の甥の一人がその日本語訳を読み、その本に 私の名前を見つけて驚いた。この論文はGoogle Scholarによると93回しか引用されていないが、私はこのエピソードを嬉しく思っている。 NIGに移ったばかりの頃、私はちょうどヒトABO血液型遺伝子の塩基配列の解析を始めたところだった。共同研究のためにヒトABO遺伝子の塩基配列を決 定した山本史郎博士に連絡を取った。私は彼にヒト以外のABO血液型遺伝子の塩基配列を決定することを提案し、彼はそれを行った。そのため、1996年に 私の研究室に2人目の博士課程学生として北野誉が加わったとき、私は彼にヒトRh血液型遺伝子のオルソログとそのパラログ遺伝子を研究するよう勧めた。私 たちはマウス、ラット、カニクイザルから骨髄サンプルを採取し、Rh遺伝子とRh50遺伝子の塩基配列を決定した(参考文献7)。 2000年にはヒトゲノムのドラフト配列の決定が発表された。分子進化の分野も進化ゲノム学に移行すべきである。そこで、私は「シルバー」という愛称で 「サルゲノムプロジェクト」を始めた。銀の原子記号はAgである。藤山秋佐夫博士の協力により、キム・チュングン博士がゴリラのフォスミドライブラリーを 作製した(参考文献8)。私の研究室は、酒井義行博士が率いる国際的なチンパンジーの第22染色体シーケンスプロジェクトにも参加していた。 しかし、私は遺伝子ハンティングにも興味があり、耳垢の遺伝子に注目していた。耳垢は日本では研究の歴史が長い。2000年にシカゴ大学のチョン・ウー教 授のところで博士号を取得したばかりの高橋彩博士がポスドクとして私の研究室に加わったので、私は彼女に耳垢の遺伝子をハンティングするよう提案した。 2002年のある日、日本の週刊誌で驚くべきニュースを見つけた。長崎大学のグループが耳垢遺伝子を発見したというのだ。私はショックを受けたが、対応す る論文を見つけ、彼らが耳垢遺伝子の染色体領域を絞り込んだだけだと知り、安心した。私はすぐに長崎大学医学部の新川典雄教授に連絡し、私の研究室も耳垢 探索チームに加わった。そして4年後、耳垢の遺伝子はABCC11であることが判明した(参考文献9)。この論文には、私の元学生である石橋美奈加、高橋 彩、そして私の3人が共著者として名を連ねている。 2005年に11人目の博士課程学生として高橋(現・上田)真帆子が研究室に加わったとき、私は彼女に霊長類と齧歯類のCNS(保存非コード配列)の研究 を提案した。私の12人目の博士課程学生である松浪正俊もCNSの研究を行ったが、彼はまずHox遺伝子クラスターに焦点を当て、彼の論文(参考文献 10)は斎藤研究室から発表されたCNS関連の最初の論文となった。その後、ナイジェリア(アイザック・ババリンデ)、スリランカ(ニルミニ・ヘッティア ラッチ)、イラン(マフムディ・サバー・モルテザ)出身の3人の学生と、dbCNS(http:// yamasati.nig.ac.jp/dbcns/)を構築した井上純も、CNSの進化について研究した。 一方、2008年に博士課程の学生として私の研究室に加わったTimothy A. Jinamは、すでにマレーシアの現生人類集団のゲノムワイドSNPデータの解析経験があった。そこで私は彼に、同様の日本人の集団のデータも研究するよ うに勧めた。彼は非常に生産的であり、人間遺伝学部門(NIG)でポスドク研究員として勤務した後、住山健太博士が理研生命システム研究センターに移籍し たため、私の研究室の助教となった。ティムは、私たちの「ヤポネシア・ゲノム・プロジェクト」(http:// www.yaponesian.jp)の重要なメンバーである。 2009年に神澤秀明が私の研究室の博士課程の学生となり、古代DNAの研究をしたいと言い出した。私は、総合地球環境学研究所のインダスプロジェクトか ら何とか研究費を獲得し、私の研究室に原始的なaDNAの作業スペースを設置した。そして、彼は最終的に縄文人のゲノム配列の一部を取得し、2016年に 論文を発表した(参考文献11)。西暦2020年(私の年号では0020年)、私はチャールズ・ダーウィンの誕生日に、オンラインジャーナル 「iDarwin」(http:// idarwin.org)を創刊した(参考文献12)。現時点では、このジャーナルに掲載された論文は多くはないが、このジャーナルが進化研究にとって重 要な資産となることを願っている。 |
| References Ref. 1. 木村資生 (1976) 分子進化論および集団遺伝学における中立説の立場. 科学, 46巻, 528-535頁. Ref. 2. Cavalli-Sforza L. L. and Edwards A. (1967) Phylogenetic analysis. Models and estimation procedures. American Journal of Human Genetics, vol. 19, pp. 233–257. Ref. 3. Saitou N. and Nei M. (1987) The neighbor-joining method: A new method for reconstructing phylogenetic trees. Molecular and Biological Evolution, vol. 4, pp. 406–425. Ref. 4. 斎藤成也 (1983) 苗字資料による国内の移住パターン推定の試み. 人類学雑誌, 第91巻3号, 309-322頁. Ref. 5. OOta S. and Saitou N. (1999) Phylogenetic relationship of muscle tissues deduced from superimposition of gene trees. Molecular and Biological Evolution, vol. 16, pp. 856–867. Ref. 6. Lane N. (2009) Life ascending — The ten great inventions of evolution. Profile Books Ltd. {日本語訳:ニッ ク・レーン著、斉藤隆央訳 (2010) 生命の跳躍‒進化の10大発明‒. みすず書房} Ref. 7. Kitano T., Sumiyama K., Shiroishi T., and Saitou N. (1998) Conserved evolution of the Rh50 gene compared to its homologous Rh blood group gene. Biochemical and Biophysical Research Communications, vol. 249, pp. 78-85. Ref. 8. Kim C.-G., Fujiyama A., and Saitou N. (2003) Construction of a gorilla fosmid library and its PCR screening system. Genomics, vol. 82, pp. 571-574. Ref. 9. Yoshiura K. et al. (2006) A SNP in the ABCC11 gene is the determinant of human earwax type. Nature Genetics, vol. 38, pp. 324-330. Ref. 10. Matsunami M., Sumiyama K., and Saitou N. (2010) Evolution of conserved non-coding sequences within the vertebrate Hox clusters through the two-round whole genome duplications revealed by phylogenetic footprinting analysis. Journal of Molecular Evolution, vol. 71, pp. 427-436. Ref. 11. Kanzawa-Kiriyama H. et al. (2016) A partial nuclear genome of the Jomons who lived 3000 years ago in Fukushima, Japan. Journal of Human Genetics (Advance online). Ref. 12. Saitou N. (0020) iDarwin: Quixotic idea? iDarwin, vol. 0, pp. 1-6. |
|
| 中立進化
説(ちゅうりつしんかせつ、英語: neutral
theory of molecular evolution)
とは、分子レベルでの遺伝子の変化は大部分が自然淘汰に対して有利でも不利でもなく(中立的)、突然変異と遺伝的浮動が進化の主因であるとする説。分子進
化の中立説、あるいは単に中立説ともいう。国立遺伝学研究所の木村資生 (きむらもとお)
によって1960年代後半および1970年代前半に発表されて、センセーションを巻き起こした説である。[1][2][3][4]中立説は自然選択説との
間で論争を引き起こした。 中立突然変異の幅広い存在を示唆した者は以前からいた。Sueoka (1962)[5]もその一人である。しかし、木村資生(1968)は中立進化を一貫した理論として初めて定式化した。これに続いてすぐJack L. KingとThomas H. Jukesによる『非ダーウィン進化』(1969)[6]というセンセーショナルな論文が発表された。 この説には以下の二つの重要な主張が含まれる。 第一に、現存種のゲノムを比較すると分子レベルでの違いの大部分は自然選択に「中立」である。つまり分子レベルでの違いの大部分は生物個体の適応度に何ら 影響を及ぼさない。この結果中立説は、ゲノムの分子レベルでの変化が、自然選択を受けないし、また、自然選択によって説明されない、とする。この見解をも たらした根拠の一つに遺伝子コードの縮退がある。遺伝子コードの3塩基は、異なるものが同じアミノ酸をコードする場合がある(例えばGCCとGCAはどち らもアラニンをコードする)。その結果単一塩基での変化の多くはその効果がサイレントでありアミノ酸変化をもたらさない(コドン#遺伝コードの縮重あるい は非表現突然変異を参照)。このような変化は生物学的な効果がほとんどあるいは全くないと考えられる。ただし、中立説の初版はアミノ酸変化率の一定性に基 づいたもので、これら(アミノ酸)変化の大部分も中立であると仮定していた。 中立説の第2の主張あるいは仮定は、進化的変化の大部分は中立遺伝子に働く遺伝的浮動の結果であるとする。遺伝子の塩基配列中の1塩基に自然突然変異が起 こって新しい対立遺伝子が生ずると、単細胞生物ではこのような変化は直ちに新規の遺伝子として集団に寄与し、以後の存亡は遺伝的浮動にゆだねられる。両性 生殖を行う多細胞生物では、個体中の性細胞の一つに塩基置換が起こらなければならない。さらにこの性細胞が胚発生、続いて個体発生に係わって、初めてこの 突然変異が集団中に新規遺伝子として寄与する。塩基置換が中立であれば新しい対立遺伝子も中立である。 これら新対立遺伝子は遺伝的浮動によって集団中に広がっていく。あるものは消失するであろうし、まれに集団中に固定される(新しい遺伝子が集団中で古い遺 伝子と完全に置き換わる)ものもあるだろう。 遺伝的浮動の数学的原理により互いに多様な変化を遂げた集団を比較してみると、1塩基置換の大部分は突然変異をもった個体が生じる率と同じ率で集積してき たと考えられた。この率はDNA複製酵素のエラー率から予想できるという議論が行なわれた。DNA複製酵素はよく研究されておりあらゆる種を超えてきわめ てよく保存されている。こうして中立説は分子時計技術の基礎を与えている。分子進化生物学者は、種が共通祖先から分岐してからどれ位の年月が経過したかを 測るのにこれを用いる。突然変異率は一定とは考えられないが、様々な複雑な分子時計が考案されている。 木村[7]のほかに、分子生物学者や集団遺伝学者の中で中立説の発展に貢献した研究者は数多くいる。このことについては現代進化学の統合の流れの中で概観 されるだろう。[8] 有利な変異は自然選択によって選択され、不利な変異は排除されるという点では選択説と共通する。「有利な変異」とは表現型に影響し、生物の住む環境におい て、その突然変異が生じた遺伝子をもつ個体の適応度(生存率や繁殖率)を高める変化のことである。自然選択が関わるのは生物の表現型である。 中立進化説では、突然変異の大部分が、表現型に影響せず、生物にとって有利でも不利でもない中立的な変化であるという事実に注目する。中立的な突然変異が 起きても子孫を残せる確率の期待値は変わらないが、個体によってはたまたま多くの子孫を残すものもいれば、残せないものもいる。そのなかで、中立的な突然 変異を起こした遺伝子は、運がよければ子孫の個体に残るだろうし、悪ければ消えてしまうだろう。この運良く子孫の個体に残った中立的な突然変異が集団のな かに広がって定着していく。つまり、遺伝子に起きた中立的な突然変異が、全くの偶然によって広がることでも進化が起きると考える。この過程を遺伝的浮動と 呼ぶ。自然選択による進化が適応を生み出すのに対して、中立的な進化は前適応や遺伝的な多様性の原因になると考えられている。 自然選択説との関係 分子レベルでの遺伝子の突然変異は、そのほとんどが自然選択に対し有利でも不利でもない中立なもので、それが集団中に広まるのは偶然によって決まる。すな わち、遺伝子の広まりの決定要因には、運のよさ(サバイバル・オブ・ザ・ラッキスト)と適者生存(サバイバル・オブ・ザ・フィッテスト)が関係している。 木村は「中立説は適応進化の決定要因として自然選択の役割を否定するものではない」[9]としたが、この考えは、ダーウィンの自然選択説と、それに基づく 進化の総合説を否定していると誤解され、当初は大きな反発を受けた。 その後、様々な証拠が集まるとともに、中立説と自然選択説は並立する概念であることがわかり、大部分の進化生物学者が、両説は両立できるものであるとして 受け入れるに至った。 中立説派-選択説派論争 木村説が初めて発表されるや、白熱した論争が起こり、多くはゲノム中の中立遺伝子と非中立遺伝子の割合に関して展開された。[10]論争を遠目に見ていた 多くの研究者の認識とは反対に、論争は、自然選択が働いているのかどうかということに関してではなかった。木村は分子進化には中立進化が幅を利かせている が、表現型レベルの形質の変化にはサンプリングの偶然による遺伝的浮動よりも自然選択が働いているほうが多いだろうと論じた。[11] 太田朋子は木村の学生で、一時的に微小有害突然変異がかなり一般的に存在しているかも知れないという考えに迷い込んだこともあったが、[12]中立説に、 「ほぼ中立な」選択性という概念を取り入れるという重要な一般化を行った。[13][14][15]つまり遺伝子が大部分浮動による影響を受けるか、選択 による影響を受けるかは、交配集団の有効な大きさによって決まるとする。中立説派-選択説派の喧噪は沈静化したが、中立遺伝子と非中立遺伝子の割合に関す る問題はまだ続いている。GraurとLi (2000)[16]は次のように言っている。『分子進化の将来についてわれわれが予言したいことは2つしかない。1つはかつての論争に関係している。中 立説派-選択説派の論争やイントロンの起源の古さというような問題に関する論争は続くだろう。その際「中立説は死んだ」とか「中立説よ永遠なれ」というよ うな叫びは凶暴性の帯びかたに程度の差はあれ1つの論文のタイトルに鳴り響くことは時々あるだろう』 中立進化説の証拠 それまでの現存生物や化石として残っている古生物の形態を調べる従来の進化の研究に、分子生物学の進歩によって遺伝子の塩基配列進化やタンパク質のアミノ 酸配列進化を分子レベルで調べることが可能になった。こうして調べると、予想以上に多くの中立的な突然変異が起きていることが判明した。 ヘモグロビン偽遺伝子 偽遺伝子とは、正常遺伝子から重複によって生じた後、何らかの理由によって遺伝子としての機能を失った、いわば遺伝子の残骸である。正常遺伝子に起こった 突然変異は、自然淘汰により排除される可能性があるが、偽遺伝子には表現型効果がないため、ここに生じた突然変異は自然淘汰にかからない(すなわち中立な 突然変異)。マウスのヘモグロビン偽遺伝子の研究から、正常遺伝子に比べて偽遺伝子の進化速度は非常に速いことがわかったが、これは中立進化説の予測どお りである。 プロインスリン インスリンの前駆体プロインスリンは3つの部分(A-C-B)から構成されており、タンパク質として合成された後、中央部分のC領域が切り出され、残りの AとBがインスリンを構成することでホルモンとして作用するようになる。A・B領域のアミノ酸置換率に比べてC領域のアミノ酸置換率は6倍になっている。 これは、C領域は切り捨てられる部分なので、ここでの突然変異は自然淘汰に対して中立である場合が多いが、A・B領域はホルモン本体を構成するので、この 領域における突然変異は致命的になりやすい、と考えれば容易に理解できる。 アルギニノコハク酸合成酵素偽遺伝子 アルギニノコハク酸合成酵素(AS)遺伝子は9番染色体上に位置しているが、ASの偽遺伝子が多数存在しており、7番染色体とY染色体に存在している2つ の偽遺伝子(これをφ-7、およびφ-Yとする)の塩基配列が調べられた。φ-7、φ-Yはいずれも共通の祖先偽遺伝子(これをφ-aとする)に由来して いる。φ-a→φ-Yの進化の過程における塩基置換率は、φ-a→φ-7の塩基置換率の2.2倍であることが判明した。これは、オスの生殖細胞形成の際の 分裂回数がメスに比べてはるかに多く、その結果複製ミスによる塩基の置換が発生しやすいことを反映している。つまり、7番染色体は平均して2世代につき1 世代をオスの中で過ごすが、Y染色体は必ずオスの体にしか存在しないため、Y染色体の複製ミス発生率は7番染色体の2倍になるのであると考えればよい。こ のように複製ミスの発生率と塩基の置換率が単純に比例していることは、塩基の置換による突然変異が、自然淘汰に対して中立であることを示している。 中立進化説からの発展 中立説を理論的根拠とする分子時計によって種分化の起きた時期や、生物種間の系統関係などが調べられる。 さらに進んで、相同な2つの遺伝子の塩基配列を比較したとき、配列に変化の少ない部分があると、この部分は遺伝子が機能する上で重要な部分である(つま り、生存に不利な突然変異は自然選択により排除される)と考え、変化の大きい部分は重要でない部分である(つまり、その部分は表現型に発現されず中立であ るため、変異が多数蓄積している)と考えることができる。 2000年代の初め以降中立説は、帰無仮説検定のいわゆる「帰無モデル」として広く用いられるようになっている。研究者は多くの場合すでに2種の分岐ある いは系統分岐のあとの年月の推定値をもっていて、この検定に応用することがよく行われる。(Tajima's D、en:HKA test等) 例えば化石採掘現場の放射性炭素からの年代測定あるいはヒト科の場合は歴史記録からの推定など。2種の塩基配列間の変異数の実測値と、独立して推定される 分岐後の時間内に中立説が予想する変異数を比較し検定を行う。もし実測値が予想値よりかなり小さいものであれば、帰無仮説は棄却される。この場合研究者 は、問題の塩基配列に自然選択が働いていることを合理的に推定することができるだろう。[疑問点 – ノート]このような検定は、分子進化がどれ位中立かどうかを研究するのにも貢献している。[17] また定説とは言えない論争中の議論ではあるが、生態系における多様性の進化についても中立理論が適用されるケースがある(中立理論 (生態学))。 https://x.gd/orWt9 |
|
| The neutral theory of molecular evolution
holds that most evolutionary changes occur at the molecular level, and
most of the variation within and between species are due to random
genetic drift of mutant alleles that are selectively neutral. The
theory applies only for evolution at the molecular level, and is
compatible with phenotypic evolution being shaped by natural selection
as postulated by Charles Darwin. The neutral theory allows for the possibility that most mutations are deleterious, but holds that because these are rapidly removed by natural selection, they do not make significant contributions to variation within and between species at the molecular level. A neutral mutation is one that does not affect an organism's ability to survive and reproduce. The neutral theory assumes that most mutations that are not deleterious are neutral rather than beneficial. Because only a fraction of gametes are sampled in each generation of a species, the neutral theory suggests that a mutant allele can arise within a population and reach fixation by chance, rather than by selective advantage.[1] The theory was introduced by the Japanese biologist Motoo Kimura in 1968, and independently by two American biologists Jack Lester King and Thomas Hughes Jukes in 1969, and described in detail by Kimura in his 1983 monograph The Neutral Theory of Molecular Evolution. The proposal of the neutral theory was followed by an extensive "neutralist–selectionist" controversy over the interpretation of patterns of molecular divergence and gene polymorphism, peaking in the 1970s and 1980s. Neutral theory is frequently used as the null hypothesis, as opposed to adaptive explanations, for describing the emergence of morphological or genetic features in organisms and populations. This has been suggested in a number of areas, including in explaining genetic variation between populations of one nominal species,[2] the emergence of complex subcellular machinery,[3] and the convergent emergence of several typical microbial morphologies.[4] Origins While some scientists, such as Freese (1962)[5] and Freese and Yoshida (1965),[6] had suggested that neutral mutations were probably widespread, the original mathematical derivation of the theory had been published by R.A. Fisher in 1930.[7] Fisher, however, gave a reasoned argument for believing that, in practice, neutral gene substitutions would be very rare.[8] A coherent theory of neutral evolution was first proposed by Motoo Kimura in 1968[9] and by King and Jukes independently in 1969.[10] Kimura initially focused on differences among species; King and Jukes focused on differences within species. Many molecular biologists and population geneticists also contributed to the development of the neutral theory.[1][11][12] The principles of population genetics, established by J.B.S. Haldane, R.A. Fisher, and Sewall Wright, created a mathematical approach to analyzing gene frequencies that contributed to the development of Kimura's theory. Haldane's dilemma regarding the cost of selection was used as motivation by Kimura. Haldane estimated that it takes about 300 generations for a beneficial mutation to become fixed in a mammalian lineage, meaning that the number of substitutions (1.5 per year) in the evolution between humans and chimpanzees was too high to be explained by beneficial mutations. Functional constraint The neutral theory holds that as functional constraint diminishes, the probability that a mutation is neutral rises, and so should the rate of sequence divergence. When comparing various proteins, extremely high evolutionary rates were observed in proteins such as fibrinopeptides and the C chain of the proinsulin molecule, which both have little to no functionality compared to their active molecules. Kimura and Ohta also estimated that the alpha and beta chains on the surface of a hemoglobin protein evolve at a rate almost ten times faster than the inside pockets, which would imply that the overall molecular structure of hemoglobin is less significant than the inside where the iron-containing heme groups reside.[13] There is evidence that rates of nucleotide substitution are particularly high in the third position of a codon, where there is little functional constraint.[14] This view is based in part on the degenerate genetic code, in which sequences of three nucleotides (codons) may differ and yet encode the same amino acid (GCC and GCA both encode alanine, for example). Consequently, many potential single-nucleotide changes are in effect "silent" or "unexpressed" (see synonymous or silent substitution). Such changes are presumed to have little or no biological effect.[15] Quantitative theory Kimura also developed the infinite sites model (ISM) to provide insight into evolutionary rates of mutant alleles. If 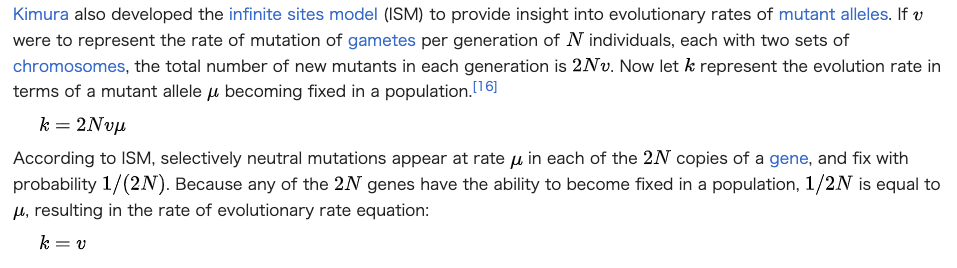 This means that if all mutations were neutral, the rate at which fixed differences accumulate between divergent populations is predicted to be equal to the per-individual mutation rate, independent of population size. When the proportion of mutations that are neutral is constant, so is the divergence rate between populations. This provides a rationale for the molecular clock, which predated neutral theory.[17] The ISM also demonstrates a constancy that is observed in molecular lineages. This stochastic process is assumed to obey equations describing random genetic drift by means of accidents of sampling, rather than for example genetic hitchhiking of a neutral allele due to genetic linkage with non-neutral alleles. After appearing by mutation, a neutral allele may become more common within the population via genetic drift. Usually, it will be lost, or in rare cases it may become fixed, meaning that the new allele becomes standard in the population. According to the neutral theory of molecular evolution, the amount of genetic variation within a species should be proportional to the effective population size. The "neutralist–selectionist" debate See also: History of evolutionary thought and History of molecular evolution A heated debate arose when Kimura's theory was published, largely revolving around the relative percentages of polymorphic and fixed alleles that are "neutral" versus "non-neutral". A genetic polymorphism means that different forms of particular genes, and hence of the proteins that they produce, are co-existing within a species. Selectionists claimed that such polymorphisms are maintained by balancing selection, while neutralists view the variation of a protein as a transient phase of molecular evolution.[1] Studies by Richard K. Koehn and W. F. Eanes demonstrated a correlation between polymorphism and molecular weight of their molecular subunits.[18] This is consistent with the neutral theory assumption that larger subunits should have higher rates of neutral mutation. Selectionists, on the other hand, contribute environmental conditions to be the major determinants of polymorphisms rather than structural and functional factors.[16] According to the neutral theory of molecular evolution, the amount of genetic variation within a species should be proportional to the effective population size. Levels of genetic diversity vary much less than census population sizes, giving rise to the "paradox of variation" .[19] While high levels of genetic diversity were one of the original arguments in favor of neutral theory, the paradox of variation has been one of the strongest arguments against neutral theory. There are a large number of statistical methods for testing whether neutral theory is a good description of evolution (e.g., McDonald-Kreitman test[20]), and many authors claimed detection of selection.[21][22][23][24][25][26] Some researchers have nevertheless argued that the neutral theory still stands, while expanding the definition of neutral theory to include background selection at linked sites.[27] Nearly neutral theory Tomoko Ohta also emphasized the importance of nearly neutral mutations, in particularly slightly deleterious mutations.[28] The Nearly neutral theory stems from the prediction of neutral theory that the balance between selection and genetic drift depends on effective population size.[29] Nearly neutral mutations are those that carry selection coefficients less than the inverse of twice the effective population size.[30] The population dynamics of nearly neutral mutations are only slightly different from those of neutral mutations unless the absolute magnitude of the selection coefficient is greater than 1/N, where N is the effective population size in respect of selection.[1][11][12] The effective population size affects whether slightly deleterious mutations can be treated as neutral or as deleterious.[31] In large populations, selection can decrease the frequency of slightly deleterious mutations, therefore acting as if they are deleterious. However, in small populations, genetic drift can more easily overcome selection, causing slightly deleterious mutations to act as if they are neutral and drift to fixation or loss.[31] Constructive neutral evolution Further information: Constructive neutral evolution The groundworks for the theory of constructive neutral evolution (CNE) was laid by two papers in the 1990s.[32][33][34] Constructive neutral evolution is a theory which suggests that complex structures and processes can emerge through neutral transitions. Although a separate theory altogether, the emphasis on neutrality as a process whereby neutral alleles are randomly fixed by genetic drift finds some inspiration from the earlier attempt by the neutral theory to invoke its importance in evolution.[34] Conceptually, there are two components A and B (which may represent two proteins) which interact with each other. A, which performs a function for the system, does not depend on its interaction with B for its functionality, and the interaction itself may have randomly arisen in an individual with the ability to disappear without an effect on the fitness of A. This present yet currently unnecessary interaction is therefore called an "excess capacity" of the system. However, a mutation may occur which compromises the ability of A to perform its function independently. However, the A:B interaction that has already emerged sustains the capacity of A to perform its initial function. Therefore, the emergence of the A:B interaction "presuppresses" the deleterious nature of the mutation, making it a neutral change in the genome that is capable of spreading through the population via random genetic drift. Hence, A has gained a dependency on its interaction with B.[35] In this case, the loss of B or the A:B interaction would have a negative effect on fitness and so purifying selection would eliminate individuals where this occurs. While each of these steps are individually reversible (for example, A may regain the capacity to function independently or the A:B interaction may be lost), a random sequence of mutations tends to further reduce the capacity of A to function independently and a random walk through the dependency space may very well result in a configuration in which a return to functional independence of A is far too unlikely to occur, which makes CNE a one-directional or "ratchet-like" process.[36] CNE, which does not invoke adaptationist mechanisms for the origins of more complex systems (which involve more parts and interactions contributing to the whole), has seen application in the understanding of the evolutionary origins of the spliceosomal eukaryotic complex, RNA editing, additional ribosomal proteins beyond the core, the emergence of long-noncoding RNA from junk DNA, and so forth.[37][38][39][40] In some cases, ancestral sequence reconstruction techniques have afforded the ability for experimental demonstration of some proposed examples of CNE, as in heterooligomeric ring protein complexes in some fungal lineages.[41] CNE has also been put forwards as the null hypothesis for explaining complex structures, and thus adaptationist explanations for the emergence of complexity must be rigorously tested on a case-by-case basis against this null hypothesis prior to acceptance. Grounds for invoking CNE as a null include that it does not presume that changes offered an adaptive benefit to the host or that they were directionally selected for, while maintaining the importance of more rigorous demonstrations of adaptation when invoked so as to avoid the excessive flaws of adaptationism criticized by Gould and Lewontin.[42][3][43] Empirical evidence for the neutral theory Predictions derived from the neutral theory are generally supported in studies of molecular evolution.[44] One of corollaries of the neutral theory is that the efficiency of positive selection is higher in populations or species with higher effective population sizes.[45] This relationship between the effective population size and selection efficiency was evidenced by genomic studies of species including chimpanzee and human[45] and domesticated species.[46] In small populations (e.g., a population bottleneck during a speciation event), slightly deleterious mutations should accumulate. Data from various species supports this prediction in that the ratio of nonsynonymous to synonymous nucleotide substitutions between species generally exceeds that within species.[31] In addition, nucleotide and amino acid substitutions generally accumulate over time in a linear fashion, which is consistent with neutral theory.[44] Arguments against the neutral theory cite evidence of widespread positive selection and selective sweeps in genomic data.[47] Empirical support for the neutral theory may vary depending on the type of genomic data studied and the statistical tools used to detect positive selection.[44] For example, Bayesian methods for the detection of selected codon sites and McDonald-Kreitman tests have been criticized for their rate of erroneous identification of positive selection.[31][44] |
分
子進化の中立説は、進化の変化のほとんどは分子レベルで起こり、種内および種間の変異のほとんどは、選択的に中立的な突然変異対立遺伝子のランダムな遺伝
的浮動によるものであるとする。この理論は分子レベルでの進化のみに適用され、チャールズ・ダーウィンが仮定した自然淘汰によって形作られる表現型の進化
と矛盾しない。 中立説では、ほとんどの突然変異は有害である可能性を認めているが、それらは自然淘汰によって急速に排除されるため、分子レベルでの種内および種間の変異 にはほとんど寄与しないと主張している。中立突然変異とは、生物の生存や繁殖能力に影響を与えない突然変異である。 中立説では、有害ではない突然変異のほとんどは、有益な突然変異ではなく中立的な突然変異であると仮定している。 種の各世代では、配偶子の一部のみがサンプリングされるため、中立説では、突然変異対立遺伝子は集団内で偶然に生じ、選択的優位性によってではなく固定に 至る可能性があるとしている。 この理論は、1968年に日本の生物学者である木村資生によって、また1969年にはアメリカの生物学者であるジャック・レスター・キングとトーマス・ ヒューズ・ジュークスによってそれぞれ独立に提唱され、1983年に木村が著した単行本『分子進化の中立理論』で詳細に説明された。中立説の提唱後、分子 の分岐や遺伝子多型のパターン解釈をめぐって「中立説派と選択説派」の広範な論争が起こり、1970年代と1980年代にピークを迎えた。 中立説は、生物や個体群における形態学的または遺伝的特徴の出現を説明する際に、適応説に対する帰無仮説として頻繁に用いられる。中立説は、1つの名目上 の種における個体群間の遺伝的変異の説明[2]、細胞内の複雑な機械装置の発生[3]、およびいくつかの典型的な微生物形態の収斂進化[4]など、多くの 分野で提案されている。 起源 フリーゼ(1962年)[5]やフリーゼと吉田(1965年)[6]などの一部の科学者は、おそらく中立変異は広範囲にわたって存在していると示唆してい たが、この理論の数学的導出は、1930年にR.A.フィッシャーによって初めて発表された[7]。しかし、フィッシャーは、 実際には、中立遺伝子の置換は非常にまれであるという根拠を示した。[8] 中立進化の首尾一貫した理論は、1968年に Motoo Kimura によって初めて提案され[9]、1969年には King と Jukes が独自に提案した。[10] Kimura は当初、種間の相違に焦点を当てていたが、King と Jukes は種内の相違に焦点を当てていた。 また、多くの分子生物学者や集団遺伝学者も中立説の発展に貢献した。[1][11][12] J.B.S. ハルデン、R.A. フィッシャー、ソール・ライトらによって確立された集団遺伝学の原理は、遺伝子頻度を分析するための数学的アプローチを生み出し、それがキムラの理論の発 展に貢献した。 ハルデーンの選択のコストに関するジレンマは、木村の動機づけとして利用された。ハルデーンは、有益な突然変異が哺乳類の系統で固定されるには約300世 代が必要であると推定した。これは、ヒトとチンパンジーの進化における置換の数(年間1.5)は、有益な突然変異によって説明するには高すぎることを意味 する。 機能的制約 中立説では、機能的制約が減少するにつれ、突然変異が中立である確率が高まり、配列の分岐速度も速くなるはずであると主張している。 さまざまなタンパク質を比較すると、フィブリノペプチドやプロインスリン分子のC鎖などのタンパク質では、活性分子と比較して機能性がほとんどないにもか かわらず、極めて高い進化速度が観察された。また、木村と太田は、ヘモグロビン蛋白質の表面にあるα鎖とβ鎖は、内部ポケットよりも約10倍速い速度で進 化していると推定している。これは、ヘモグロビンの分子構造全体よりも、鉄を含むヘム基が存在する内部の方が重要ではないことを示唆している。 ヌクレオチド置換の速度は、機能上の制約がほとんどないコドンの第3位置で特に高いという証拠がある。[14] この見解は、3つのヌクレオチド(コドン)の配列が異なっていても同じアミノ酸をコードする場合がある縮退遺伝暗号に基づいている(例えば、GCCと GCAはどちらもアラニンをコードする)。その結果、多くの可能性のある一塩基の変化は、事実上「サイレント」または「発現しない」ものとなる(同義置換 またはサイレント置換を参照)。このような変化は、生物学的な影響はほとんど、あるいはまったく無いと推定されている。[15] 量的理論 また、キムラは突然変異対立遺伝子の進化速度に関する洞察を得るために、無限サイトモデル(ISM)を開発した。 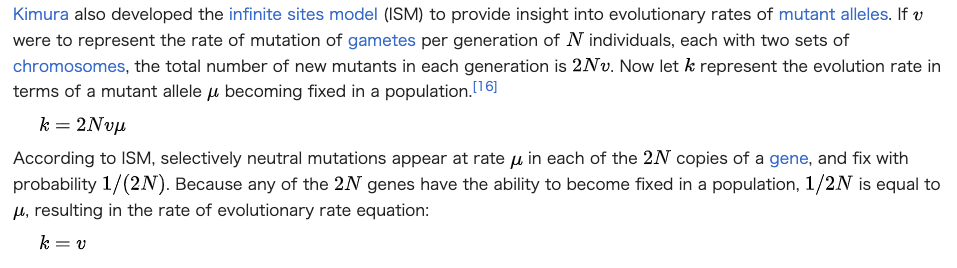 これは、すべての突然変異が中立的な場合、固定された差異が分岐した集団間で蓄積する速度は、集団の規模に関係なく、個体あたりの突然変異率と等しくなる ことが予測されることを意味する。中立的な突然変異の割合が一定である場合、集団間の分岐速度も一定である。これは、中立理論に先立つ分子時計の理論的根 拠となる。ISMはまた、分子系統で観察される一定性を示す。 この確率過程は、例えば非中立対立遺伝子との遺伝的連鎖による中立対立遺伝子のヒッチハイクではなく、サンプリングの偶然によるランダムな遺伝的ドリフト を説明する方程式に従うと仮定されている。突然変異によって出現した後、中立対立遺伝子は遺伝的ドリフトによって集団内でより一般的になる可能性がある。 通常は失われるが、まれに固定される場合があり、その場合はその新しい対立遺伝子が集団内で標準となる。 分子進化の中立説によると、種内の遺伝的多様性の量は有効集団のサイズに比例するはずである。 中立説と選択説の論争 参照:進化論の歴史、分子進化の歴史 木村の理論が発表されると、激しい論争が巻き起こった。その論争は主に、「中立」対「非中立」の多型対立遺伝子と固定対立遺伝子の相対的なパーセンテージ を巡るものであった。 遺伝的多型とは、特定の遺伝子、ひいてはその遺伝子が作り出すタンパク質の異なる形態が、同一の種内で共存していることを意味する。選択説の支持者は、こ のような多型は均衡選択によって維持されていると主張しているが、中立説の支持者は、タンパク質の変異は分子進化の一時的な段階であると見なしている。 [1] リチャード・K・コーエンとW・F・イーンズによる研究では、多型と分子サブユニットの分子量との間に相関関係があることが実証されている。[18] これは、大きなサブユニットは中立変異の割合が高いはずだという中立説の想定と一致する。一方、選択説の支持者は、多型の主な決定要因として、構造や機能 的要因よりも環境条件を挙げる。 分子進化の中立説によると、種内の遺伝的多様性の量は有効個体数に比例するはずである。 遺伝的多様性のレベルは、国勢調査による個体数よりもはるかに変動が少ないため、「多様性のパラドックス」が生じる。[19] 遺伝的多様性のレベルの高さが中立説を支持する当初の論拠のひとつであったが、多様性のパラドックスは中立説に対する最も強力な論拠のひとつとなってい る。 中立説が進化をうまく説明できるかどうかを検証する統計的手法は数多く存在し(例えば、マクドナルド・クリートマン検定[20])、多くの著者が選択の検 出を主張している[21][22][23][24][25][26]。しかし、一部の研究者は、中立説の定義を拡大して連鎖部位での背景選択を含めること で、中立説は依然として有効であると主張している[27]。 ほぼ中立説 太田朋子もまた、特にわずかに有害な突然変異であるほぼ中立突然変異の重要性を強調している。[28] ほぼ中立説は、中立説の予測である、選択と遺伝的浮動のバランスが有効個体群サイズに依存するという考え方に基づいている。[29] ほぼ中立突然変異は、選択係数が有効個体群サイズの2倍の逆数よりも小さい突然変異である。[30] ほぼ中立突然変異の個体群動態は、 選択係数の絶対値が1/Nより大きい場合を除いて、中立突然変異の個体群動態とほとんど変わらない。ここでNは選択に関する有効個体群サイズである。 [1][11][12] 有効個体群サイズは、わずかに有害な突然変異が中立突然変異として扱われるか、有害突然変異として扱われるかに影響を与える。[31] 大きな個体群では、選択によってわずかに有害な突然変異の頻度が低下し、有害突然変異として作用する。しかし、小さな集団では、遺伝的浮動が選択をより容 易に打ち消し、わずかに有害な突然変異が中立であるかのように作用し、固定または喪失へと向かう。 建設的ニュートラル進化 さらに詳しい情報:建設的ニュートラル進化 建設的ニュートラル進化(CNE)理論の基礎は、1990年代に発表された2つの論文によって築かれた。[32][33][34] 建設的ニュートラル進化は、中立的な変遷を通じて複雑な構造やプロセスが出現しうることを示す理論である。中立進化説とは全く別の理論であるが、中立対立 遺伝子が遺伝的浮動によってランダムに固定されるプロセスとしての中立性に重点を置くという点では、進化における中立性の重要性を唱えた中立進化説の初期 の試みから着想を得ている。概念的には、2つの構成要素AとB(2つのタンパク質を表す可能性もある)が互いに相互作用する。Aはシステムに対して機能を 発揮するが、その機能性はBとの相互作用に依存するものではなく、相互作用自体は個体においてランダムに生じたものであり、Aの適応度に影響を与えること なく消滅する可能性もある。この現在ではまだ不要な相互作用は、したがって、システムの「余剰能力」と呼ばれる。しかし突然変異が起こり、Aが単独で機能 を果たす能力が損なわれる可能性もある。しかし、すでに現れているA:B相互作用は、Aが当初の機能を果たす能力を維持している。したがって、A:B相互 作用の出現は突然変異の有害な性質を「前提」としており、それはゲノムにおける中立的な変化であり、ランダムな遺伝的浮動によって集団全体に広がる可能性 がある。したがって、AはBとの相互作用に依存するようになった。[35] この場合、BまたはA:B相互作用の喪失は適応度に悪影響を及ぼすため、そのようなことが起こった個体は純化選択によって排除される。これらの各段階はそ れぞれ可逆的であるが(例えば、Aは独立して機能する能力を取り戻す可能性があるし、A:Bの相互作用が失われる可能性もある)、突然変異のランダムな順 序は、Aが独立して機能する能力をさらに低下させる傾向があり、依存性の空間におけるランダムウォークは、Aが機能的に独立した状態に戻る可能性がほとん どないような構成になる可能性が非常に高い 。CNEは一方向または「ラチェットのような」プロセスである。CNEは、より複雑なシステム(全体に寄与するより多くの部分と相互作用を含む)の起源に 適応メカニズムを適用しないが、スプライソソームの進化起源、真核生物の複合体、RNA編集、コア以外のリボソームタンパク質の追加 コア以外のリボソームタンパク質、ジャンクDNAからの長鎖ノンコーディングRNAの出現などである。[37][38][39][40] 場合によっては、祖先配列再構成技術によって、いくつかの真菌の系統におけるヘテロオリゴマーリングタンパク質複合体のように、CNEのいくつかの例が実 験的に実証されている。 CNEはまた、複雑な構造を説明する帰無仮説としても提示されており、したがって、複雑性の出現に対する適応説の説明は、受け入れられる前に、この帰無仮 説に対して個別に厳密に検証されなければならない。CNEを帰無仮説として採用する根拠としては、変化が宿主に適応上の利益をもたらした、あるいは方向性 を持って選択されたと仮定しないこと、一方で、グールドとレウォンティンが批判した適応説の過剰な欠陥を避けるために採用される場合には、適応のより厳密 な実証の重要性を維持することが含まれる。[42][3][43] 中立説の経験的証拠 中立説から導き出された予測は、分子進化の研究において概ね支持されている。[44] 中立説の帰結のひとつは、実効個体サイズが大きい個体群や種では、正の選択の効率性が高いということである。[45] この実効個体サイズと選択効率の関係は チンパンジーやヒトを含む種や家畜種のゲノム研究によって、実効集団サイズと選択効率の関係が証明されている[45][46]。小さな集団(例えば、種分 化の過程における集団のボトルネック)では、わずかな有害突然変異が蓄積するはずである。さまざまな種のデータは、この予測を裏付けている。種間の非同義 置換と同義置換のヌクレオチド置換の比率は、一般的に種内よりも高いからである。[31] さらに、ヌクレオチド置換とアミノ酸置換は一般的に、中立説と一致する線形の形で、時間とともに蓄積する。[44] 中立説に対する反論は、ゲノムデータにおける広範囲にわたる正の選択と選択的掃き集めの証拠を挙げている 。中立説を支持する実証的根拠は、研究対象のゲノムデータのタイプや、正の選択を検出するために使用される統計的手法によって異なる可能性がある。 [44] 例えば、選択されたコドン部位の検出のためのベイズ法やマクドナルド・クリートマン検定は、正の選択の誤った識別率が高いという批判を受けている。 [31][44] |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Neutral_theory_of_molecular_evolution |
|
リンク(関連研究者)
リ ンク(サイト内リンク)
★「日本人の源流」でCiNiiで検索すると次の35文献が検索された(2024年9月21日)※斎藤の書物は太字
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆