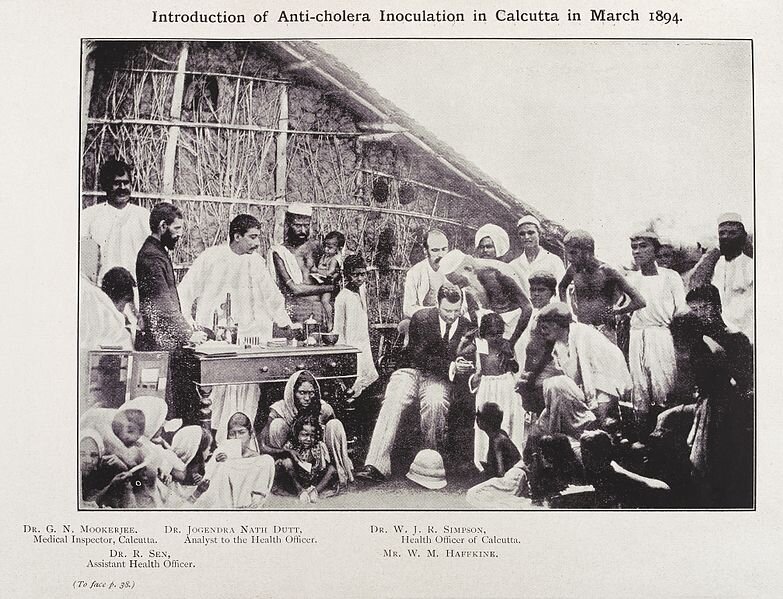70年代から80年代の末期までの応用医療人類学の隆盛を象徴するものがアルマアタ宣言であり、戦略理念として採用されたプライマリヘル
スケア(PHC)であることは論を待たない。PHCは、1978年にWHOとユニセフがカザフスタン共和国のアルマ・アタで宣言した保健の理念と施策であ
る。これがそれまでの公衆衛生理念と異なる点は、健康の達成には、(1)政治経済の安定や、(2)住民の自助努力が不可欠としたことにある。実践面では
「保健上の問題を克服する教育とその問題を予防しコントロールする方法、食糧供給と適正な栄養の増進、安全な水と基本的な衛生の適切な供給、家族計画を含
む母子保健、主要な感染症に対する免疫付与、局地的な流行病の予防とコントロール、通常の傷病への適切な治療、基本医薬品の支給」(宣言文)が目標とさ
れ、おびただしいマニュアルが公的、私的保健セクターから出版された。このあらゆる角度からの、しかし漠然とした政策はのちに包括的
(comprehensive)PHCと呼ばれることになる。
この理念がどのような過程を経て生まれたのかは明らかではない。すでに60年代末から70年代の中頃には世界各地の低開発地域でこのよう
な施策がすでに試みられていた。たとえば、中国の文化大革命期に制度化された赤脚医生(はだしの医者)、WHOによる抗マラリア剤の投与と疫学資料収集の
出先機関となる保健普及員の制度、ユニセフによる伝統的出産介助者(産婆)の能力養成講座、ユネスコによる栄養改善と保健教育の普及運動など、地域をベー
スにした住民参加の保健運動があった。より広い文脈では70年代中頃から国連経済特別総会などで議論された「内発的発展」やシュマッハーらの代替技術論な
どとPHCは思想的にも施策的にも通底するものがある。1973年の石油危機以降の援助条件の悪化という経済的背景のなかで、住民参加という名をもったプ
ライマリヘルスケアは援助の効率を援助される住民の側から内発的にうながすイデオロギーとして機能した。PHCをめぐる政策論争をあとづけて、このことを
検証してみよう。
宣言の翌年、ロックフェラー財団のワルシュとワレンは包括的PHCの非現実性を批判して、選択的(selective)PHCを提唱し
た。この戦略は包括的PHCへの暫定的な戦略として、より具体的に効率良く保健衛生の状態を改善するために特定の保健政策を選択的に行う。つまり、地域の
死亡率を著しく下げる乳幼児死亡対策(麻疹、およびジフテリア・百日咳・破傷風の三種混合ワクチン接種、下痢に対する経口補水療法)、効果が顕著に現われ
るといわれているマラリア対策、母親への破傷風ワクチン接種や母乳推奨をおこなう(Walsh
and Warren 1979)。彼らはPHCの遂行に際して、効果性を重視し、技術が確立されたものから着手すべきであると主張した。
提唱から6年後「包括的PHCと選択的PHC」をめぐる国際会議がベルギーのアントワープで開催され、1988年に『社会科学と医療』誌
の特集として公刊された(Rifkin
and Walt
1988)。選択的的PHC側のワレンは、ユニセフがとったPHC戦略、コスタリカや中国などの事例の検討を通して選択的PHCの成功を宣言する
(Warren
1988)。他方、包括的PHCによる選択的PHCへの批判はより政治経済的色彩がつよい。すなわち、選択的な戦術への偏重は、政府あるいは援助機関から
住民への医療の主導権の移行を実現させず、工業医薬品、医療産業などへの依存という医療化(medicalization)を押し進めると言うのである。
現実の医療体制とPHCの関係の中でも選択的PHCは批判される。スミスらは、医療システムを下部構造という枠組みにおける時間的な変遷の中で考察した。
それによると選択的PHCを実施する際に、母子保健、マラリア対策などの縦割の専門業務集団に分れる傾向があり、それらは国家レベルでは協調関係にあるも
のの、地方や共同体のレベルになるとバラバラになり、横の連携がとれていないという欠陥が生じるという(Smith
and Bryant 1988)。
この選択的および包括的PHCが相互に排除的に批判することに対して、折衷的な意見もある。モズレイの主張によると、重要なことは特定の
疾病対策ではなく、存在する問題全体にアプローチすることである(Mosley
1988)。選択的PHCが成功を収めるには、包括的で社会変化を巻き込むことが不可欠だという。アフリカのザイールやマリの事例研究においても、選択的
PHCの有効性を評価する一方で、国家と共同体の利益誘導の相違などによるマイナスの効果も指摘され、包括的PHCが理想とする統合の問題に深い関心が寄
せられた。
しかしPHCに対するもっと手厳しい批判もある。カメルーンにおける実態を検討したバン・デル・ゲーストは、中央政府、制度的医療の推進
者、および住民の三つの次元を通して、はからずも生物医学が中心を占め、PHC政策は理念とは裏腹に歪んで運用され、否定的機能すらみられることを描写す
る(Van
der Geest
1982)。政治的安定や経済的発展は健康に寄与するという論法をPHCが採るならば、第一に解決しなければならないのは政治だ、と彼はいう。池田はホン
ジュラスの共同体をターゲットにしたPHC計画について調査し、外部から操作的にかつ多様に定義される共同体概念の曖昧さを指摘し、人びとがPHCそのも
のを無力化してゆくことを指摘した(池田
1990;1992)。
選択的PHCを提唱したワルシュとワレンの論文の冒頭には、先に述べた当時の世銀総裁マクナマラによる1978年次報告からの引用があ
り、その理念の影響はその論文にも色濃く表れている。ケネディ政権下の国防長官であり、米国の多角的な核戦略論の構想者であるマクナマラは、同時に肥大化
する軍事財政を「計画的科学的に管理し、合理的かつ効果的に予算編成する」手法をペンタゴンに導入したことでも知られている(カウフマン
1968)。技術論的批判としての選択的PHCのいう保健施策の「効率」とは、死亡率で代表される指標の変化で「可視化」されるものに還元された。これは
投下された資本がどれだけの利潤を引き出すかという計算の合理性を「健康」の中にみることにほかならない。
プライマリヘルスケア論争の最大の意義は、援助する側とされる側の社会的背景が問題視されたことで、する側からされる側への「援助」の論
理が相対化されたことである。これによって19世紀末以来の援助する側(開発国)がされる側(低開発国)に投影してきたさまざまな前提が崩壊に向かったこ
とも確かである。また異なった政治体制下におけるPHCの分析が、普遍的な保健計画がどこにでも通用するのではなく、むしろ政治経済状況下で恣意的に形成
させられることを明らかにした。例えば、社会主義混合経済下にあった中央アメリカのニカラグアの保健教育のなかで「健康」が社会体制や経済に還元されるの
に対して、政治的軍事的に合衆国の多大なる影響下にあったその隣国ホンジュラスで「健康」とは家族内における安寧と平和と強く結びつけられてPHCの教育
に組み込まれるからである(池田
1989)。