Ideology As a Cultural System, from Introduction to Geertz' Interpretation of Culture, 1973
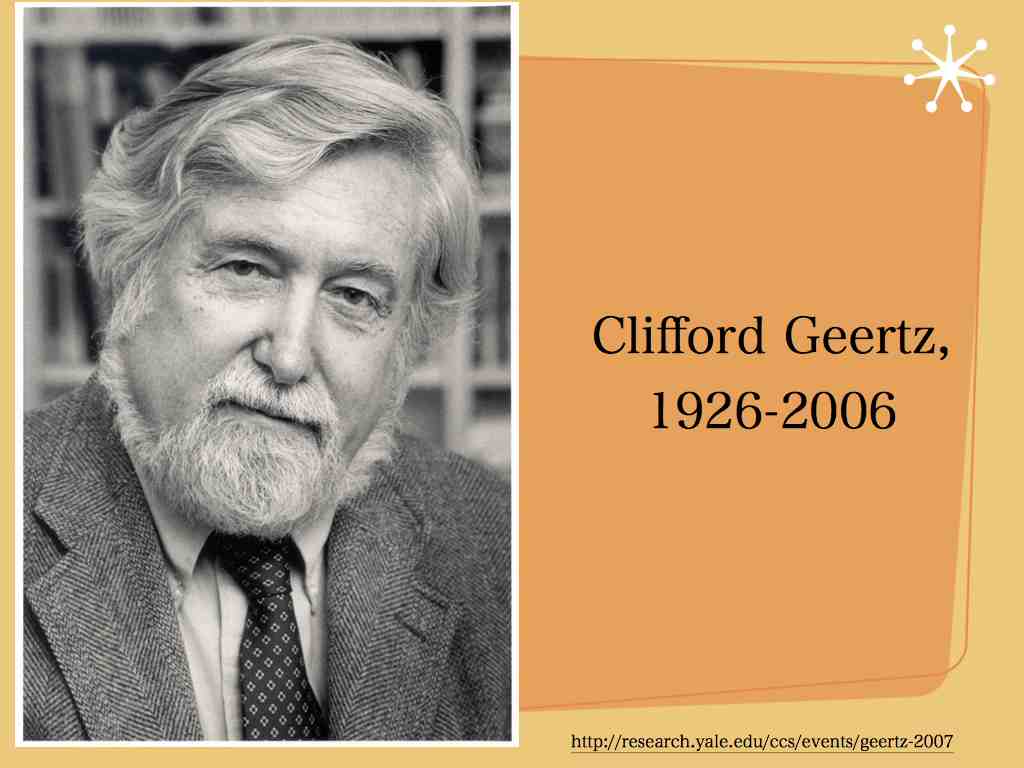
文化体系としてのイデオロギー
Ideology As a Cultural System, from Introduction to Geertz' Interpretation of Culture, 1973
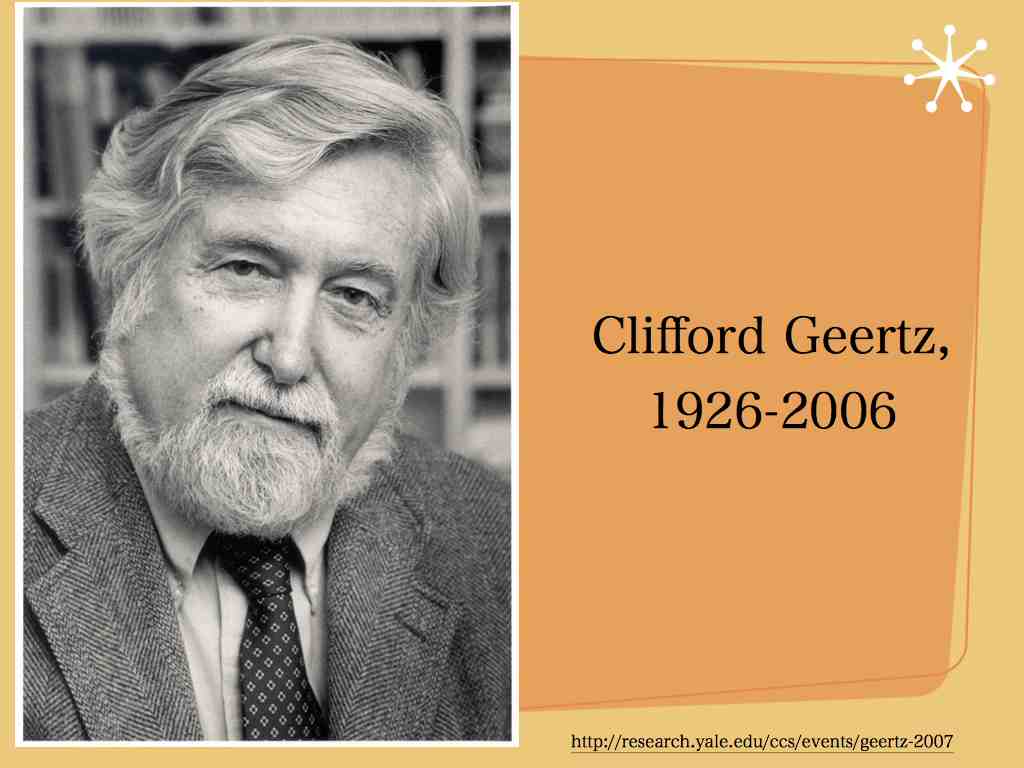
解説:池田光穂
『文化の解釈』(邦訳:文化の解釈学)[The Interpretation of Cultures, 1973.]は、1973年のクリフォード・ギアーツの著書、から「文化としての政治」について考える
8.文化体系としてのイデオロギー(邦
訳, pp.3-) Ideology As a Cultural System
| I | 3 |
・イデオロギーが「おとろしい」用語と
して使われてきたわけ ・イデオロギーの言わば自己言及性(マンハイム) ・それゆえマンハイムは「価値判断を含まないイデオロギー概念」の探求(構築)に着手する、pp.4-5 ・ゼノンのパラドクスと、マンハイムのパラドクスとの類似(脱色しても脱色しても無垢の差は縮まらない) ・イデオロギーのイデオロギー概念を解消しようと努力するマンハイム、または「イデオロギーの終焉」終焉。 ・イデオロギー抜きの社会科学は「客観性」への到達願望か? ・イデオロギー抜きの社会科学は、自分の探求している内容や手法が「洗練」されていない、というコンプレックスによるのか?(7) ・イデオロギーが社会学的分析を拒む(分析が不適切だから?) +++++++++++++++++++++++++++ 1)社会科学は、価値判断を含まないイデオロギー概念を手にしてない 2)その理由は方法論的な欠如ではなく、理論的な不備による 3)社会的心理的文脈を吟味するのではなく、イデオロギーを象徴的に取り扱うときに、このようなジレンマが生じる 4)意味というものを巧妙に扱う概念装置を完成させるべき 5)研究対象をより正確にとらえること(そうでないと)「おとなしい嫁」を探せと言われて死骸をもちかえる愚かな少年(ジャワの民話)にならないように (7) +++++++++++++++++++++++++++ |
| II |
・イデオロギー概念のほとんどは価値判
断的=侮蔑的である(8)。 ・スタークの議論を引きながら、イデオロギーという用語にはさまざまなマイナスのイメージが付与されていることを指摘。 ・つまり、イデオロギー研究とは、知識社会学とは異なり、その知的誤謬をしてきすることにあると認識されている(9) ・シルズにおいても、その扱いは同様(10) ・あの慎重なタルコット・パーソンズも同じような路線を主張する(11)——有害な「二次的」選択性—— ・社会科学の分析に、イデオロギーほど中傷されているのに、なぜそれが残留しているのかは謎のまま(12) ・レイモン・アーロンの「知識人の阿片」でも同様 ・シルズのイデオロギーに対する病理的な嫌悪は、異端審問官の異端に対する態度に通底する(13) ・イデオロギーがもつ先験的な虚偽性の意味を保持させるのは、論点先取的な誤 りにも覚える(14) |
|
| III |
14 |
・イデオロギーの病理解剖的な様相にス
トーリーはすすむ。とりわけ、社会心理的な説明。 ・イデオロギーの社会的決定要因は、利益説と緊張説(15) ・利益説には多くを踏み込まない(15) ・利益説の問題は、心理的には貧困であり、社会学的には骨太すぎること(16) ・果てしのない闘争史観(17) ・利益説も、緊張説も、両方とも、心理的であり、社会的説明でもある(18) ・緊張説の出発点は、社会の「慢性的な不統合状態」からはじまる(18-19) ・社会的摩擦が個人的摩擦に反映される(19)そして絶望状態を産む(20) ・イデオロギー的思想は、この絶望に対する(ある種の)反応である(20)——象徴的はけ口など ・この表現は、病理的(医学的)に説明=表現される(20) ・以下、洗浄(カタルシス)論的、意欲論的、団結論的、弁護論的 ・洗浄=カタルシス論は、安全弁論的で、スケープゴート的(21) ・意欲論 ・団結論(21) ・弁護論(22) +++++++++ ・緊張説とそのの限界(24-25) ・いずれせよ、社会と心理の関連を関連づけて説明するイデオロギー説明説の問題点が列挙されている(26) |
| IV |
26 |
・社会科学理論は、マルクス主義、ダー
ウィニズム、功利主義、観念論、フロイト学説、行動主義、実証主義、操作主義など、主知的な運動から影響をうけてきた(26) ・(他方)生態学、動物行動学、比較心理学、ゲーム理論、サイバネティクス、統計学の方法論的革新から影響をうけてこなかった。 ・例外のひとつバークの「象徴行為」論。 ・哲学者の仕事も、文芸批評家の仕事も影響を与えていない(26)。 ・比喩言語を理解できないので、イデオロギーの手の込んだ苦痛の叫びに還元してみることとなる(27) ・サットンの「タフト・ハートレー法」の理解。組織労働者は「奴隷労働法」とラベル(28)。 ・奴隷労働者を見下すような見解が(事例引用)には含まれている。(29-) ・それは比喩の企て(30-) ・奴隷労働という表現は、複雑な象徴的行為であることを示唆(33-34) |
| V |
34 |
・人間の思考は公共的活動であり……
(34) ・思考が外にあるアプローチ=外在説 ・象徴モデルと世界の状態の過程と付き合わせる活動(35) ・引用、想像的思考とは……(35) ・引用、象徴モデルとは……(37) ・人間を政治的動物とするのは(41) ・イデオロギーの説明に(41-) ・エドマンド・バークのイデオロギー論(批判) ・「教えられざる感性の人」(42)——エドマンド・バーク ・【イデオロギーは大衆の政治的緊張への反応だ】 「イデオロギーの機能とは、政治 を意味あるものとするような権威ある概念を与えることによって、すなわち政治を理解し得るような 形で把握する手段としての説得力あるイメージを与えることによって、自律的な政治を可能とするこ とである。事実ある政治体系が、受け入れられてきた伝統の無媒介的支配から、すなわち一方で宗教 的ないし哲学的規律の直接的で細部にまでわたる導きから、他方で慣習的道徳の省みられることのな い教えからまさに自らを解放し始めるとき、形式化されたイデオロギーが最初に現われ根を張る傾向 にある。自律的政体が分佑することは、政治的行為について、独立しった文化的モデルが分化す ることをも意味する。なぜなら政治的行為に特定しない古いモデルは、そうした政治体系が要請する ようなたぐいの導きを与えるには、あまりに包括的にすぎるか、具体的にすぎるか、だからである。そう/ したモデルは、超越的な意味を負わせて政治的行動を束縛するか、習慣的判断のうつろな現実主義に 縛り付けて政治的理念を窒息させるかである。ある社会の最も広汎な文化的方向付けも、最も実際的 で「実用的な」方向付けも、ともに政治過程の妥当なイメージを与えるに充分でなくなったときに、 イデオロギーは社会的政治的な意味と姿勢の源泉として決定的重要性を帯び始める」(42-43) ・イデオロギーの積極的解釈(44)★ |
| VI |
45 |
・イデオロギーの醸成の場はどこにあ
る?(45)——イデオロギーの跋扈は途上国(=ギアツの言葉では「新生国家」)にある ・ラマルティーヌの詩(46)——このあたりの解説はベネディクト・アンダーソンの表現に似ている? ・インドネシア近代国家における適応と失敗のプロセス(47) ・ヒンドゥ時代のジャワ(48) ・イスラムとヒンドゥ(49) ・パンチャシラ(51) ・マニポル・ウスデク(54) ・イデオロギーとリアル・ポリテークが混乱したインドネシアの分析(56-57) ・インドネシアは政治的実験の場 ・ ・イデオロギーの科学的研究の出発点(58) |
| VII |
58 |
・なぜ、ケネス・バークの引用からこの
セクションははじまるのか?(58-59) ・【批判的想像的作品】 「批判的想像的作品とは、それが生まれた状況により提示された問題に対する解答である。それは単 なる解答ではなく、戦略的解答であり様式化された解答である。というのは同じ「はい」と言うにし ても、「よかった!」を意味する調子の時と「残念!」を意味する調子の時とでは、様式や戦略に違 いがあるからである。そこで私はさしあたっての作業上、「戦略」と「状況」の間に区別を設けるこ とによって、批判的ないし想像的性格の作品とは……状況を包囲するために様々な戦略を用いること である……と考えることにしたい。こうした戦略は状況を測り、状況の構造とその目立った内容物に// 名前を付けるが、それらに対する姿勢を含むような形で名前を付けるのである。/ このような見方をしても、いかなる意味でも個人的ないし歴史的主観主義にくみすることにはなら ない。こうした状況は本物である。それらを処理するための戦略には公共の内容がある。状況が個人 と個人の間で、あるいはある時代と時代の間で重なり合う限り、その戦略には普遍的意味がある ——ケネス・バーグ『文学形式の哲学(Philosophy of Literary Form)』」(58-59) ・科学とイデオロギーの差異の解説(60-61) ・「ヒットラーが自国民の悪魔的自己嫌悪を、聖書に依拠して呪術的に腐敗するユダヤ 人像に映し描 いたとき、彼はドイツ人の意識を歪めていたのではなかった。彼は単にそれを客体化していたのであ る——広くみられた個人的神経症を、強力な社会的力へと変容させていたのである」(ギアーツ(下)1987:62)。 ・言説により人を動員させる機能がイデオロギーであるが、それを働かせるためには、言説のシンボル的操作が必要だということか?(62-63) ・【科学とイデオロギーの関係】——イデオロギーと「科学(あるいは常識)の共犯関係?を最後に描写するギアーツ。でも科学を信じているギアーツの別の姿 がある。 +++++++ ・「しかし、科学とイデオロギーが相異なる企てであったとしても、相互に関連してい ないわけではな い。イデオロギーは確かに社会の条件と方向について経験に基づく主張 を行なうが、評価を行なうの は科学の(そして科学的知識が欠如する場合には常識の)役目である。イデオロギーに対するものとし ての科学の社会機能とは、まずイデオロギ——それが何であるか、それがどのように機能するか、 それを生むものは何か——を理解すること、次にそれを批判し、それに現実との妥協(必ずしも降伏/ ではない)を強いることである。社会問題の科学的分析という欠くべからざる伝統が存 在することは、 極端なイデオロギーを生まない保証として最も効果が大きいものの一つである。なぜなら科学的分析 というものには、政治的理念が依存し尊重すべき実証的知識の源泉として、比類のない信頼性がある からである。科学的分析はそうした阻止機構として唯一のものではない。既に述べたように、当該社 会の他の強力な集団が奉ずる競合的イデオロギーの存在もまた、少なくとも同じくらい重要である。 また全体的権力の夢がそこでは明らかに幻想としかなり得ない自由な政治体系も、また伝統的期待が 常に裏切られるわけではなく伝統的思想が根源的に無能力であるわけでもない安定した社会条件も、 同じくまた重要である。しかし自らの見解については静かに妥協を拒む科学的分析は、おそらくその どれよりも不屈である」(62-63) |
●追記:マイケル・オークショット——こ
れには、ギアーツ先生がいう否定的な意味は込められていない。具体的な経験とは別物であるという定義が
素晴らしい。
「私の理解するかぎりでは、政治的イデオロギーとは、ある抽象的な原理または諸原理の関連せる組合せを意味し、 あらかじめ個々の経験から独立に考案されたものである。それは、社会を整序することに関わる行動に先んじて、追 求されるべき目的を定式化し、そうすることによって、いっそう鼓舞されるべき諸要求と抑圧または修正されるべき ものとを、区別する手段を提供してくれる」(翻訳 p.134)
"As I understand it, a political ideology purports to be an
abstract
principle, or set of related abstract principles, which has been
independently
premeditated. It supplies in advance of the activity of
attending to the arrangements of a society a formulated end to be
pursued, and in so doing it provides a means of distinguishing
between those desires which ought to be encouraged and those
which ought to be suppressed or redirected." (Oakeshott 1962:116)
| Ideology
as a Cultural System. Clifford Geertz I. It is one of the minor ironies of modern intellectual history that the term "ideology" has itself become thoroughly ideologized. A concept that once meant but a collection of political proposals, perhaps somewhat intellectualistic and impractical but at any rate idealistic--"social romances as someone, perhaps Napoleon, called them--has now become, to quote Webster's, "the integrated assertions, theories, and aims constituting a politico-social program, often with an implication of factitious propagandizing; as, Fascism was altered in Germany to fit the Nazi ideology"--a much more formidable proposition. Even in works that, in the name of science, profess to be using a neutral sense of the term, the effect of its employment tends nonetheless to be distinctly polemical in Sutton, Harris, Kaysen, and Tobin's in many ways excellent The American Business Creed, for example, an assurance that "one has no more cause to feel dismayed or aggrieved by having his own views described as 'ideology' than had Moliere's famous character by the discovery that all his life he had been talking prose,"1 is followed immediately by the listing of the main characteristics of ideology as bias, oversimplification, emotive language, and adaption to public prejudice No one, at least outside the Communist bloc, where a somewhat distinctive conception of the role of thought in society is institutionalized, would call himself an ideologue or consent unprotestingly to be called one by others. Almost universally now the familiar parodic paradigm applies: "I have a social philosophy; you have political opinions; he has an ideology." The historical process by which the concept of ideology came to be itself a part of the very subject matter to which it referred has been traced by Mannheim; the realization (or perhaps it was only an admission) that sociopolitical thought does not grow out of disembodied reflection but "is always bound up with the existing life situation of the thinker" seemed to taint such thought with the vulgar struggle for advantage it had professed to rise above.2 But what is of even more immediate importance is the question of whether or not this absorption into its own referent has destroyed its scientific utility altogether, whether or not having become an accusation, it can remain an analytic concept. In Mannheim's case, this problem was the animus of his entire work--the construction, as he put it, of a "nonevaluative conception of ideology.' But the more he grappled with it the more deeply he became engulfed in its ambiguities until, driven by the logic of his initial assumptions to submit even his own point of view to sociological analysis, he ended, as is well known, in an ethical and epistemological relativism that he himself found uncomfortable. And so far as later work in this area has been more than tendentious or mindlessly empirical, it has involved the employment of a series of more or less ingenious methodological devices to escape from what may be called (because, like the puzzle of Achilles and the tortoise, it struck at the very foundations of rational knowledge) Mannheim's Paradox. As Zeno's Paradox raised (or, at least, articulated) unsettling questions about the validity of mathematical reasoning, so Mannheim's Paradox raised them with respect to the objectivity of sociological analysis. Where, if anywhere, ideology leaves off and science begins has been the Sphinx's Riddle of much of modern sociological thought and the rustless weapon of its enemies. Claims to impartiality have been advanced in the name of disciplined adherence to impersonal research procedures of the academic man's institutional insulation from the immediate concerns of the day and his vocational commitment to neutrality, and of deliberately cultivated awareness of and correction for one's own biases and interests. They have been met with denial of the impersonality (and the effectiveness) of the procedures, of the solidity of the insulation, and of the depth and genuineness of the self-awareness. "I am aware," a recent analyst of ideological preoccupations among American intellectuals concludes, somewhat nervously, "that many readers will claim that my position is itself ideological."3 Whatever the fate of his other predlctions, the validity of this one is certain. Although the arrival of a scientific sociology has been repeatedly proclaimed, the acknowledgment of its existence is far from universal even among social scientists themselves; and nowhere is resistance to claims to objectivity greater than in the study of ideology. A number of sources for this resistance have been cited repeatedly in the apologetic literature of the social sciences. The valueladen nature ot the subject matter is perhaps most frequently invoked: men do not care to have beliefs to which they attach great moral significance examined dispassionately, no matter for how pure a purpose; and if they are themselves highly ideologized, they may find it simply impossible to believe that a disinterested approach to critical matters of social and political conviction can be other than a scholastic sham. The inherent elusiveness of ideological thought, expressed as it is in intricate symbolic webs as vaguely defined as they are emotionally charged; the admitted fact that ideological special pleading has, from Marx forward, so often been clothed in the guise of "scientific sociology"; and the defensiveness of established intellectual classes who see scientific probing into the social roots of ideas as threatening to their status, are also often mentioned. And, when all else fails, it is always possible to point out once more that sociology is a young science, that it has been so recently founded that it has not had time to reach the levels of institutional solidity necessary to sustain its claims to investigatory freedom in sensitive areas. All these arguments have, doubtless, a certain validity. But what--by a curious selective omission the unkind might well indict as ideological--is not so often considered is the possibility that a great part of the problem lies in the lack of conceptual sophistication within social science itself, that the resistance of ideology to sociological analysis is so great because such analyses are in fact fundamentally inadequate; the theoretical framework they employ is conspicuously incomplete. I shall try in this essay to show that such is indeed the case: that the social sciences have not yet developed a genuinely nonevaluative conception of ideology; that this failure stems less from methodological indiscipline than from theoretical clumsiness; that this clumsiness manifests itself mainly in the handling of ideology as an entity in itself --as an ordered system of cultural symbols rather than in the discrimination of its social and psychological contexts (with respect to which our ana Iytical machinery is very much more refined); and that the escape from Mannheim's Paradox lies, therefore, in the perfection of a conceptual apparatus capable of dealing more adroitly with meaning. Bluntly, we need a more exact apprehension of our object of study, lest we find ourselves in the position of the Javanese folk-tale figure, "Stupid Boy," who, having been counseled by his mother to seek a quiet wife, returned with a corpse. |
イデオロギーとしての文化システム クリフォード・ギアーツ I. 「イデオロギー」という用語自体が徹底的にイデオロギー化されてしまったことは、現代の知的歴史における些細な皮肉のひとつである。かつては政治的提案の 集合体を意味していた概念、おそらくはいくらか観念的で非現実的ではあるが、いずれにせよ理想主義的な概念――「社会的なロマン主義」と、おそらくナポレ オンは呼んだ――は、現在ではウェブスターの言葉を引用すれば、「政治的社会的なプログラムを構成する統合された主張、理論、目的であり、しばしば人為的 なプロパガンダの含みを持つ。例えば、ファシズムはドイツでナチスのイデオロギーに合うように変化した」という、より強力な命題となっている。科学の名の もとに、用語を中立的に使用していると主張する作品においても、その使用が論争的な効果をもたらす傾向にあることに変わりはない。サットン、ハリス、ケイ セン、トビンの『The American Business Creed』は、多くの点で優れた作品である。例えば、「自分の意見が『イデオロギー』と表現されたからといって落胆したり、不当に扱われたと感じる理由 は、モリエールの 「自分の生涯をかけて散文を語っていたことを発見したモリエールの有名な登場人物よりも、自分の意見が『イデオロギー』と表現されたことで落胆したり不当 に扱われたりする理由などない」という主張が続きます。1 そのすぐ後に、イデオロギーの主な特徴として、偏見、単純化、感情的な表現、そして大衆の偏見への順応が挙げられています。少なくとも社会における思想の 役割について、ある程度独特な概念が制度化されている共産圏以外の地域では、自らをイデオローグと称する者や、他人からそう呼ばれることに異議を唱えない 者はいないでしょう。今ではほぼ世界中で、おなじみのパロディ的なパラダイムが適用されている。「私は社会哲学を持っている。あなたは政治的意見を持って いる。彼はイデオロギーを持っている」 イデオロギーという概念が、それ自体がまさにその概念が指し示す主題の一部となるに至った歴史的過程は、マンハイムによって明らかにされている。社会政治 思想は、身体から切り離された思索から生じるのではなく、「常に思想家の既存の生活状況と結びついている」という認識(あるいは、それは単なる承認にすぎ なかったかもしれない)は、 。しかし、より差し迫った問題は、この参照対象への吸収が科学的実用性を完全に破壊してしまったかどうか、告発の対象となってしまった以上、分析的概念で あり続けることができるかどうかという問題である。マンハイムの場合、この問題は彼の全作品の動機となった。すなわち、彼が言うところの「価値判断を伴わ ないイデオロギーの概念」の構築である。しかし、彼がこの問題に取り組めば取り組むほど、その曖昧さに深く巻き込まれていった。そして、当初の仮定の論理 に駆られて、自身の視点さえも社会学的分析に委ねるようになった彼は、周知の通り、自らを不快に感じた倫理的・認識論的相対主義に陥った。この分野におけ るその後の研究が、偏見に満ちたものや、無分別な経験主義的なものに留まらない限り、それは、マンハイムのパラドックスと呼ばれるもの(アキレスと亀のパ ズルのように、合理的知識の根幹を揺るがすもの)から逃れるために、さまざまな独創的な方法論的工夫を駆使したものとなっている。 ゼノンのパラドックスが数学的推論の妥当性について不安を掻き立てるような疑問を提起した(あるいは少なくとも明確にした)ように、マンハイムのパラドッ クスは社会学分析の客観性について同様の疑問を提起した。イデオロギーがどこで終わり、科学が始まるのかは、近代社会学思想の多くにおけるスフィンクスの 謎であり、その敵の錆びない武器であった。公平性への主張は、学術的な人間の、その時代の差し迫った関心事から隔離された制度上の非個人的研究手順への規 律ある厳守、および職業上の中立性への献身、そして、自らの偏見や利害に対する意識を意図的に養い、修正するという名目で進められてきた。これらは、手順 の非個人的性質(および有効性)、隔離の堅固さ、自己認識の深さと真実性の否定に直面してきた。「私は自覚している」と、最近のアメリカ知識人のイデオロ ギー的関心についての分析者は、やや神経質な調子で結論づけている。「多くの読者は、私の立場自体がイデオロギー的であると主張するだろう」3。彼の他の 予測の運命がどうであれ、この予測の妥当性は確実である。科学的社会学の到来は繰り返し宣言されてきたが、その存在の認知は社会科学者自身の間でも普遍的 とは程遠い。そして、客観性への主張に対する抵抗は、イデオロギーの研究において最も大きい。 この抵抗の要因については、社会科学の弁明的な文献で繰り返し挙げられている。この主題の価値を伴う性質は、おそらく最も頻繁に引き合いに出されるもので ある。人間は、いかに純粋な目的であっても、道徳的に大きな意義を付与した信念を冷静に検証されることを望まない。また、もし人間自身が高度にイデオロ ギー化されている場合、社会や政治的な信念の重要な問題に対して、利害関係のないアプローチが学問的な偽善以外の何者でもないと考えることは、単に不可能 であるかもしれない。感情を揺さぶるようなあいまいな定義の複雑な象徴の網として表現されるイデオロギー的思考の本質的な捉えどころのなさ、マルクス以 降、イデオロギー的特別弁護が「科学的社会学」という仮面を被ることが非常に多かったという認められた事実、そして、アイデアの社会的ルーツを科学的に探 ることを自分たちの地位を脅かすものとして捉える確立された知識階級の防衛的な姿勢も、よく言及される。そして、他に手段がない場合には、社会学はまだ歴 史の浅い学問であり、最近になってようやく確立されたばかりであるため、デリケートな分野における調査の自由を主張し続けるために必要な制度的な強固さを 獲得するだけの時間がなかった、ということを再び指摘することが常に可能である。これらの議論には、確かに一定の妥当性がある。しかし、興味深い選択的省 略によって、不親切な人々からイデオロギー的だと非難される可能性があるが、あまり考慮されていないのは、問題の大部分が社会科学自体の概念的な洗練度の 欠如にあるという可能性である。社会学的な分析に対するイデオロギーの抵抗が非常に大きいのは、そのような分析が実際には根本的に不適切であるためであ り、彼らが用いる理論的枠組みは著しく不完全である。 本稿では、社会科学がまだイデオロギーに対する真に評価的でない概念を発展させていないこと、この失敗は方法論の無規律さよりも理論的な不器用さから生じ ていること、この不器用さは主にイデオロギーをそれ自体の存在として取り扱う際に現れること --社会や心理的文脈の区別(これに関しては、私たちの分析的機械ははるかに洗練されている)よりも、むしろ文化的なシンボルの秩序あるシステムとして、 というように。そして、マンハイムのパラドックスからの脱却は、意味をより巧みに扱うことのできる概念的装置の完成にある。端的に言えば、私たちは研究対 象をより正確に把握する必要がある。さもなければ、ジャワの民話に登場する「愚かな少年」の立場に立たされることになる。母親から「おとなしい妻をめとる ように」と助言された愚かな少年は、死体を抱えて戻ってきた。 |
| II. That the conception of ideology now regnant in the social sciences is a thoroughly evaluative (that is, pejorative) one is readily enough demonstrated. " [The study of ideology] deals with a mode of thinking which is thrown off its proper course," Werner Stark informs us; "ideological thought is . . . something shady, something that ought to be overcome and banished from our mind." It is not (quite) the same as lying, for, where the liar at least attains to cynicism, the ideologue remains merely a fool: "Both are concerned with untruth, but whereas the liar tries to falsify the thought of others while his own private thought is correct, while he himself knows well what the truth is, a person who falls for an ideology is himself deluded in his private thought, and if he misleads others, does so unwillingly and unwittingly."4 A follower of Mannheim, Stark holds that all forms of thought are socially conditioned in the very nature of things, but that ideology has in addition the unfortunate quality of being psychologically "deformed" ("warped," "contaminated," "falsified," "distorted," "clouded") by the pressure of personal emotions like hate, desire, anxiety, or fear. The sociology of knowledge deals with the social element in the pursuit and perception of truth, its inevitable confinement to one or another existential perspective. But the study of ideology--an entirely different enterprise--deals with the causes of intellectual error: Ideas and beliefs, we have tried to explain. can be related to reality in a double way: either to the facts of reality, or to the strivings to which this reality, or rather the reaction to this reality, gives rise. Where the former connection exists, we find thought which is, in principle, truthful; where the latter relation obtains, we are faced with ideas which can be true only by accident. and which are likely to be vitiated by bias. the word taken in the widest possible sense. The former type of thought deserves to be called theoreticai; the latter must be characterized as paratheoretical. Perhaps one might also describe the former as rational, the latter as emotionally tinged--the former as purely cognitive, the latter as evaluative. To borrow Theodor Geiger's simile . . . thought determined by social fact is like a pure stream. crystal-clear, transparent; ideological ideas like a dirty river, muddied and polluted by the impurities that have flooded into it. From the one it is healthy to drink; the other is poison to be avoided.5 This is primitive, but the same confinement of the referent of the term "ideology" to a form of radical intellectual depravity also appears in contexts where the political and scientific arguments are both far more sophisticated and infinitely more penetrating. In his seminal essay on "Ideology and Civility," for example, Edward Shils sketches a portrait of "the ideological outlook," which is, if anything, even grimmer than Stark's.6 Appearing "in a variety of forms, each alleging itself to be unique"--Italian Fascism, German National Socialism, Russian Bolshevism, French and Italian COmmunism, the Action Francaise, the British Union of Fascists, "and their fledgling American kinsman, 'McCarthyism,' which died in infancy"--this outlook "encircled and invaded public life in the Western countries during the 19th century and in the 20th century. . . threatened to achieve universal domination." It consists, most centrally, of "the assumption that politics should be conducted from the standpoint of a coherent, comprehensive set of beliefes which must override every other consideration." Like the politics it supports, it is dualistic, opposing the pure "we" to the evil "they," proclaiming that he who is not with me is against me. It is alienative in that it distrusts, attacks, and works to undermine established political institutions. It is doctrinaire in that it claims complete and exclusive possession of political truth and abhors compromise. It is totalistic in that it aims to order the whole of social and cultural life in the image of its Ideals, futuristic in that it works toward a utopian culmination of history in which such an ordering will be realized. It is, in short, not the sort of prose any good bourgeois gentleman (or even any good democrat) is likely to admit to speaking. Even on more abstract and theoretical levels, where the concern is more purely conceptual, the notion that the term "ideology" properly applies to the views of those "stiff in opinions, and always in the wrong" does not disappear. In Talcott Parsons's most recent contemplation of Mannheim's Paradox, for example, "deviations from [social scientific objectivity" emerge as the "essential criteria of an ideology": "The problem of ideology arises where there is a discrepancy between what is believed and what can be [established as] scientifically correct."7 The "deviations" and "discrepancies" involved are of two general sorts. First, where social science, shaped as is all thought by the overall values of the society within which it is contained, is selective in the sort of questions it asks, the particular problems it chooses to tackle, and so forth, ideologies are subject to a further, cognitively more pernicious "secondary" selectivity, in that they emphasize some aspects of social reality--that reality, for example, as revealed by current social scientific knowledge--and neglect or even suppress other aspects. "Thus the business ideology, for instance, substantially exaggerates the contribution of businessmen to the national welfare and underplays the contribution of scientists and professional men. And in the current ideology of the 'intellectual,' the importance of social pressures to conformity' is exaggerated and institutional factors in the freedom of the individual are ignored or played down." Second, ideological thought, not content with mere overselectivity, positively distorts even those aspects of social reality it recognizes, distortion that becomes apparent only when the assertions involved are placed against the background of the authoritative findings of social science. "The criterion of distortion is that statements are made about society which by social-scientific methods can be shown to be positively in error, whereas selectivity is; involved where the statements are, at the proper level, 'true,' but do not constitute a balanced account of the available truth." That in the eyes of . the world there is much to choose between being positively in error and rendering an unbalanced account of the available truth seems, however, rather unlikely. Here, too, ideology is a pretty dirty river. Examples need not be multiplied, although they easily could be. Nlore important is the question of what such an egregiously loaded concept is doing among the analytic tools of a social science that, on the basis of a claim to cold-blooded objectivity, advances its theoretical mterpretations as "undistorted" and therefore normative visions of social reality. If the critical power of the social sciences stems from their disinterestedness, is not this power compromised when the analysis of political thought is governed by such a concept, much as the analysis of religious thought would be (and, on occasion, has been) compromised when cast in terms of the study of "superstition"? The analogy is not farfetched. In Raymond Aron's The Opium of the Intellectuals, for example, not only the title--ironically echoic of Marx's bitter iconoclasm--but the entire rhetoric of the argument ("political myths," "the idolatry of history," "churchmen and faithful "secular clericalism," and so forth)8 reminds one of nothing so much as the literature of militant atheist Shils's tack of invoking the extreme pathologies of ideological thought -- Nazism, Bolshevism, or whatever --as its paradigmatic forms is reminiscent of the tradition in which the Inquisition, the personal depravity of Renaissance popes, the savagery of Reformation wars, or the primitiveness of Bible belt fundamentalism Is offered as an archetype of religious belief and behavior. And Parsons's view that ideology is defined by its cognitive insufficiencies vis-a-vis science is perhaps not so distant as it might appear from the Comtean view that religion is characterized by an uncritically figurative conception of reality, which a sober sociology, purged of metaphor, win soon render obsolete: We may wait as long for the "end of ideology" as the positivists have waited for the end of religion. Perhaps it is even not too much to suggest that, as the militant atheism of the Enlightenment and after was a response to the quite genuine horrors of a spectacular outburst of religious bigotry, persecution, and strife (and to a broadened knowledge of the natural world), so the militantly hostile approach to ideology is a similar response to the political holocausts of the past halfcentury (and to a broadened knowledge of the social world). And, if this suggestion is valid, the fate of ideology may also turn out to be similar -- isolation from the mainstream of social thought.9 Nor can the issue be dismissed as merely a semantic one. One is, naturally, free to confine the referent of the term "ideology" to "something shady" if one wishes; and some sort of historical case for doing so can perhaps be made. But if one does so limit it, one cannot then write works on the ideologies of American businessmen, New York "literary" intellectuals, members of the British Medical Association, industrial laborunion leaders, or famous economists and expect either the subjects or interested bystanders to credit them as neutral.'10 Discussions of sociopolitical ideas that indict them ab initio, in terms of the very words used to name them, as deformed or worse, merely beg the questions they pretend to raise. It is also possible, of course, that the term "ideology" should simply be dropped from scientific discourse altogether and left to its polemical fate--as "superstition" in fact has been. But, as there seems to be nothing at the moment with which to replace it and as it is at least partially established in the technical lexicon of the social sciences, it seems more advisable to proceed with the effort to defuse it.11 |
II. 社会科学で現在支配的なイデオロギーの概念が徹底的に評価的な(つまり、軽蔑的な)ものであることは、容易に証明できる。「イデオロギーの研究は、本来の 道筋を逸脱した思考様式を扱うものである」と、ヴェルナー・シュタールは私たちに教えている。「イデオロギー的な思考は...何か怪しげなものであり、克 服し、私たちの心から追放すべきものである。」 それは(まったく)嘘と同じではない。なぜなら、嘘つきは少なくともシニシズムを獲得するが、イデオローグは単なる愚か者のままであるからだ。「両者とも 虚偽に関わるが、嘘つきは他人の考えを改ざんしようとする一方で、自分の個人的な考えは正しい。一方で、彼自身は真実が何であるかをよく理解している。一 方、イデオロギーに陥った人は、自分の個人的な考えを誤解しており、他人を欺く場合でも、不本意かつ無意識のうちにそうしている。」4 マンハイムの信奉者であるスタークは、あらゆる思考形態は物事の本質において社会的に条件付けられているが、イデオロギーにはさらに、憎悪、欲望、不安、 恐怖などの個人的な感情の圧力によって心理的に「変形」(「ゆがむ」、「汚染される」、「偽造される」、「歪曲される」、「曇る」)するという不運な性質 がある、と主張している。知識社会学は、真実の追求と認識における社会的要素、すなわち、真実が必然的に存在論的観点のひとつに限定されることを扱う。し かし、イデオロギーの研究は、まったく異なる分野であるが、知的誤りの原因を扱う。 我々は、思想と信念について説明しようとしてきた。思想と信念は、現実に対して2つの方法で関連している可能性がある。すなわち、現実の事実、または現 実、あるいは現実への反応が生み出す努力のいずれかである。前者の関係が存在する場所では、原則として真実である思考が見出される。後者の関係が存在する 場所では、偶然にのみ真実となりうる考えに直面する。そして、それは偏見によって台無しにされる可能性が高い。この言葉は、可能な限り広い意味で捉えられ る。前者の思考は理論的と呼ぶにふさわしく、後者は傍論的と特徴づけられるべきである。おそらく、前者は合理的、後者は感情的と表現することもできるだろ う。前者は純粋に認識的、後者は評価的である。テオドール・ガイガーの例えを借りれば、社会的事実によって決定づけられた思考は、澄んだ小川のようなもの である。一方、思想は、不純物が流れ込み濁って汚染された汚い川のようなものである。前者は健康に良いので飲むことができるが、後者は避けるべき毒であ る。 これは原始的であるが、「イデオロギー」という用語の参照対象が急進的な知的堕落の一形態に限定されていることは、政治的および科学的議論がはるかに洗練 され、はるかに深く突き刺さるような文脈においても見られる。例えば、エドワード・シールズは「イデオロギーと礼節」に関する画期的な論文の中で、「イデ オロギー的展望」の肖像を描いているが、それはスタークのそれよりもさらに陰鬱なものである。6 「それぞれが唯一無二であると主張する、さまざまな形態で現れる」――イタリアのファシズム、ドイツの国民社会主義、ロシアのボリシェヴィズム フランスおよびイタリアの共産主義、フランス行動党、イギリスのファシスト同盟、「そして、その未熟なアメリカ人の親戚である『マッカーシズム』」が挙げ られる。この見解は、「19世紀から20世紀にかけて、西洋諸国の公共生活を包囲し、侵略した。... 普遍的な支配を達成しようと脅かした。」それは、最も中心的な部分では、「政治は、あらゆる他の考慮事項を上回る、首尾一貫した包括的な信念体系の観点か ら行われるべきである」という前提から成り立っている。それを支える政治と同様に、それは二元論的であり、純粋な「私たち」と邪悪な「彼ら」を対立させ、 「私」に同調しない者は「私」の敵であると宣言する。それは、既存の政治制度を不信し、攻撃し、弱体化させようとするという点で疎外的なものである。政治 的真理の独占的な所有を主張し、妥協を嫌うという点で、それは教条主義的である。社会生活と文化的生活のすべてをその理想のイメージ通りに秩序立てること を目指すという点で、全体主義的である。そのような秩序が実現される歴史のユートピア的な集大成に向けて活動するという点で、未来志向的である。つまり、 それは、良きブルジョワ紳士(あるいは良き民主主義者)が口にするような言葉ではない。 より抽象的で理論的なレベル、つまりより純粋に概念的な関心事においても、「頑固な意見を持ち、常に間違っている」人々の見解に「イデオロギー」という用 語が適切に当てはまるという考え方は消えない。例えば、タルコット・パースンズがマンハイムのパラドックスについて最近考察した中で、「社会科学的な客観 性からの逸脱」が「イデオロギーの本質的な基準」として浮上している。「イデオロギーの問題は、信じられていることと科学的に正しいとされることとの間に 食い違いがある場合に生じる」7。関与する「逸脱」と「食い違い」には、一般的に2つの種類がある。まず、社会科学は、それが含まれる社会全体の価値観に よって形作られるため、問いかける質問の種類、取り組む特定の問題などにおいて選択的になるが、イデオロギーは、社会の現実のいくつかの側面を強調し、他 の側面を無視したり、場合によっては抑圧するという、さらに認知的に有害な「二次的」選択性を帯びる。「例えば、ビジネス思想は、ビジネスマンが国民の福 祉に貢献している度合いを実際以上に誇張し、科学者や専門家の貢献を過小評価する。そして、現在の「知識人」のイデオロギーにおいては、社会的な同調圧力 の重要性が誇張され、個人の自由に関する制度的な要因は無視されたり、軽視されたりしている。」 第二に、イデオロギー的な思考は、単なる選択の偏りだけでは満足せず、認識している社会の現実の側面さえも積極的に歪曲する。この歪曲は、関連する主張が 社会科学の権威ある調査結果を背景に置かれた場合にのみ明らかになる。「歪曲の基準は、社会についてなされた主張が、社会科学的手法によって間違いである ことが証明できる場合である。一方、選択性は、主張が適切なレベルで『真実』であるものの、利用可能な真実のバランスの取れた説明を構成しない場合に含ま れる。」しかし、世界の見方では、間違いであることと、利用可能な真実のバランスの取れていない説明をすることの間には、多くの選択肢があるように思われ る。ここでも、イデオロギーはかなり汚い川である。 例を挙げる必要はないが、簡単に挙げることができる。それよりも重要なのは、このようなひどく偏った概念が、冷酷な客観性を主張し、理論的解釈を「歪みの ない」ものとして、したがって社会現実の規範的なビジョンとして提示する社会科学の分析ツールの中で、どのような役割を果たしているかという問題である。 社会科学の批判力がその無関心さから生じているとすれば、政治思想の分析がそのような概念によって支配されている場合、その批判力は損なわれるのではない か。宗教思想の分析が「迷信」の研究という観点から損なわれることがあるように(そして、時には実際に損なわれているように)。 この類推は的外れではない。例えば、レイモンド・アロン著『知識人のアヘン』では、皮肉にもマルクスの辛辣な偶像破壊主義を想起させるタイトルだけでな く、論旨全体(「政治的迷信」、「歴史の偶像崇拝」、「聖職者と敬虔な信者による世俗的聖職者主義」など)が、8 。ナチズム、ボルシェビズム、その他、イデオロギー思想の極端な病理を典型的な形態として引き合いに出すという、好戦的な無神論者シルズの手法は、宗教的 信念と行動の典型として、異端審問、ルネサンス期の教皇の個人的堕落、宗教改革戦争の残虐性、聖書ベルトの原理主義の原始性といった伝統を想起させる。そ して、科学に対する認識の不十分さによってイデオロギーが定義されるというパーソンズの考え方は、宗教が現実を批判的に考えずに比喩的に捉えるという特徴 を持つというコントの考え方と、それほどかけ離れたものではないかもしれない。宗教は、比喩を排除した冷静な社会学によってすぐに時代遅れになるだろう。 「イデオロギーの終焉」を待つのは、実証主義者が宗教の終焉を待っていたのと同じくらい長い時間になるかもしれない。啓蒙主義以降の過激な無神論が、宗教 的偏見、迫害、争いの大規模な勃発という極めて深刻な恐怖(および自然界に関する知識の拡大)への反応であったように、イデオロギーに対する過激な敵対的 アプローチも、過去半世紀の政治的ホロコースト(および社会世界に関する知識の拡大)への同様の反応であると主張するのは、おそらく行き過ぎではないだろ う。そして、この提案が妥当であるならば、イデオロギーの運命もまた同様である可能性がある。すなわち、社会思想の主流から孤立することである。9 また、この問題を単に意味論的なものとして片付けることもできない。もちろん、必要であれば「イデオロギー」という用語の参照対象を「怪しげなもの」に限 定することは自由である。そして、そうする歴史的な事例もある程度は作れるだろう。しかし、もしそう限定するならば、アメリカのビジネスマン、ニューヨー クの「文学的」知識人、英国医師会の会員、産業労働組合のリーダー、あるいは著名な経済学者のイデオロギーに関する著作を書いたとしても、その主題や 彼らを中立的なものとみなすことを、主題や利害関係者から信用されることを期待することはできない。10 彼らを非難する社会政治的な考えについて、それらを指名するために使われる言葉そのものについて、当初から議論することは、単に彼らが提起しようとしてい る問題を先送りするだけである。もちろん、「イデオロギー」という用語を科学的な議論から完全に排除し、その論争的な運命に委ねることも可能である。実 際、「迷信」という用語はそう扱われてきた。しかし、現時点ではそれに代わる用語は見当たらないし、少なくとも部分的には社会科学の専門用語として定着し ているため、この用語を廃止する努力を続ける方が望ましいと思われる。11 |
| III. As the flaws hidden in a tool show up when it is used, so the intrinsic weaknesses of the evaluative concept of ideology reveal themselves when it is used. In particular, they are exposed in the studies of the social sources and consequences of ideology, for in such studies this concept is coupled to a highly developed engine of social--and personalitysystem analysis whose very power only serves to emphasize the lack of a similar power on the cultural (that is, the symbolsystem) side. In investigations of the social and psychological contexts of ideological thought (or at least the "good" ones), the subtlety with which the contexts are handled points up the awkwardness with which the thought is handled, and a shadow of imprecision is cast over the whole discussion, a shadow that even the most rigorous methodological austerity cannot dispel. There are currently two main approaches to the study of the social determinants of ideology: the interest theory and the strain theory.12 For the first, ideology is a mask and a weapon; for the second, a symptom and a remedy. In the interest theory, ideological pronouncements are seen against the background of a universal struggle for advantage; in the strain theory, against the background of a chronic effort to correct sociopsychological disequilibrium. In the one, men pursue power; in the other, they flee anxiety. As they may, of course, do both at the same time--and even one by means of the other -- the two theories are not necessarily contradictory; but the strain theory (which arose in response to the empirical difficulties encountered by the interest theory), being less simplistic, is more penetrating, less concrete, more comprehensive. The fundamentals of the interest theory are too well known to need review; developed to perfection of a sort by the Marxist tradition, they are now standard intellectual equipment of the man-in-the-street, who is only too aware that in political argumentation it all comes down to whose ox is gored. The great advantage of the interest theory was and is its rooting of cultural idea-systems in the solid ground of social structure, through emphasis on the motivations of those who profess such systems and on the dependence of those motivations in turn upon social position, most especially social class. Further, the interest theory welded political speculation to political combat by pointing out that ideas are weapons and that an excellent way to institutionalize a particular view of reality -- that of one's group, class, or party--is to capture political power and enforce it. These contributions are permanent; and if interest theory has not now the hegemony it once had, it is not so much because it has been proved wrong as because its theoretical apparatus turned out to be too rudimentary to cope with the complexity of the interaction among social, psychological, and cultural factors it itself uncovered. Rather like Newtonian mechanics, it has not been so much displaced by subsequent developments as absorbed into them. The main defects of the interest theory are that its psychology is too anemic and its sociology too--muscular. Lacking a developed analysis of motivation, it has been constantly forced to oscillate between a narrow and superficial utilitarianism that sees men as impelled by rational calculation of their consciously recognized personal advantage and a broader, but no less superficial, historicism that speaks with a studied vagueness of men's ideas as somehow "reflecting," "expressing," "corresponding to," "emerging from," or "conditioned by" their social commitments. Within such a framework, the analyst is faced with the choice of either revealing the thinness of his psychology by being so specific as to be thoroughly implausible or concealing the fact that he does not have any psychological theory at all by being so general as to be truistic. An argument that for professional soldiers "domestic [governmental] policies are important mainly as ways of retaining and enlarging the military establishment [because] that is their business; that is what they are trained for" seems to do scant justice to even so uncomplicated a mind as the military mind is reputed to be; while an argument that American oil men "cannot very well be pure-and-simple oil men" because "their interests are such" that "they are also political men" is as enlightening as the theory (also from the fertile mind of M. Jourdain) that the reason opium puts you to sleep is that it has dormitive powers13 On the other hand, the view that social action is fundamentally an unending struggle for power leads to an unduly Machiavellian view of ideology as a form of higher cunning and, consequently, to a neglect of its broader, less dramatic social functions. The battlefield image of society as a clash of interests thinly disguised as a clash of principles turns attention away from the role that ideologies play in defining (or obscuring) social categories, stabilizing (or upsetting) social expectations. maintaining (or undermining) social norms, strengthening (or weakening) social consensus, relieving (or exacerbating) social tensions. Reducing ideology to a weapon in a guerre de plume gives to its analysis a warming air of militancy, but it also means reducing the intellectual compass within which such analysis may be conducted to the constrictcd realism of tactics and strategy. The intensity of interest theory is --to adapt a figure from Whitehead--but the reward of its narrowness. As "interest," whatever its ambiguities, is at one and the same time a psychological and sociological concept--referring both to a felt advantage of an individual or group of individuals and to the objective structure of opportunity within which an individual or group moves--so also is strain," for it refers both to a state of personal tension and to a condition of societal dislocation. The difference is that with "strain" both the motivational background and the social structural context are more systematically portrayed, as are their relations with one another. It is, in fact, the addition of a developed conception of personality systems (basically Freudian), on the one hand, and of social systems (basically Durkheimian) on the other, and of their modes of interpenetration-- the Parsonian addition--that transforms interest theory into strain theory.14 The clear and distinct idea from which strain theory departs is the chronic malintegration of society. No social arrangement is or can be completely successful in coping with the functional problems it inevitably faces. All are riddled with insoluble antinomies: between liberty and pohtical order, stability and change, efficiency and humanity, precision and flexibility, and so forth. There are discontinuities between norms in different sectors of the society --the economy, the polity, the family, and so on. There are discrepancies between goals within the different sectors -- between the emphases on profit and productivity in business firms or between extending knowledge and disseminating it in universitics. for example. And there are the contradictory role expectations of which so much has been made in recent American sociological literature on the foreman, the working wife, the artist, and the politician. Social friction is as pervasive as is mechanical friction--and as irremovable. Further, this friction or social strain appears on the level of the individual personality--itself an inevitably malintegrated system of conflicting desires, archaic sentiments, and improvised defenses--as psychological strain. What is viewed collectively as structural inconsistency is felt individually as personal insecurity, for it is in the experience of the social actor that the imperfections of society and contradictions of character meet and exacerbate one another. But at the same time, the fact that both society and personality are, whatever their shortcomings, organized systems, rather than mere congeries of institutions or clusters of motives, means that the sociopsychological tensions they induce are also systematic, that the anxieties derived from social interaction have a form and order of their own. In the modern world at least, most men live lives of patterned desperation. Ideological thought is, then, regarded as (one sort of) response to this desperation: "Ideology is a patterned reaction to the patterned strains of a social role."15 It provides a "symbolic outlet" for emotional disturbances generated by social disequilibrium. And as one can assume that such disturbances are, at least in a general way, common to all or most occupants of a given role or social position, so ideological reactions to the disturbances will tend to be similar, a similarity only reinforced by the presumed commonalities in "basic personality structure" among members of a particular culture, class, or occupational category. The model here is not military but medical: An ideology is a malady (Sutton, et al., mention nail-chewing, alcoholism, psychosomatic disorders and "crotchets" among the alternatives to it) and demands a diagnosis. "The concept of strain is not in itself an explanation of ideological patterns but a generalized label for the kinds of factors to look for in working out an explanation."16 But there is more to diagnosis, either medical or sociological, than the identification of pertinent strains; one understands symptoms not merely etiologically but teleologically--in terms of the ways in which they act as mechanisms, however unavailing, for dealing with the disturbances that have generated them. Four main classes of explanation have been most frequently employed: the cathartic, the morale, the solidarity, and the advocatory. By the "cathartic explanation" is meant the venerable safetyvalve or scapegoat theory. Emotional tension is drained off by being displaced onto symbolic enemies ("The Jews," "Big Business," "The Reds," and so forth). The explanation is as simpleminded as the device; but that, by providing legitimate objects of hostility (or, for that matter, of love), ideology may ease somewhat the pain of being a petty bureaucrat, a day laborer, or a small-town storekeeper is undeniable. By the "morale explanation" is meant the ability of an ideology to sustain individuals (or groups) in the face of chronic strain, either by denying it outright or by legitimizing it in terms of higher values. Both the struggling small businessman rehearsing his boundless confidence in the inevitable justness of the American system and the neglected artist attributing his failure to his maintenance of decent standards in a Philistme world are able, by such means, to get on with their work. Ideology bridges the emotional gap between things as they are and as one would have them be, thus insuring the performance of roles that might otherwise be abandoned in despair or apathy. By the "solidarity explanation" is meant the power of ideology to knit a social group or class together. To the extent that it exists, the unity of the labor movement, the business community, or the medical profession obviously rests to a significant degree on common ideological orientation; and the South would not be The South without the existence of popular symbols charged with the emotions of a pervasive social predicament. Finally, by the "advocatory explanation" is meant the action of ideologies (and ideologists) in articulating, however partially and indistinctly, the strains that impel them, thus forcing them into the public notice. "Ideologists state the problems for the larger society, take sides on the issues involved and 'present them in the court' of the ideological market place."17 Although ideological advocates (not altogether unlike their legal counterparts) tend as much to obscure as to clarify the true nature of the problems involved, they at least call attention to their existence and, by polarizmg issues, make continued neglect more difficult. Without Marxist attack, there would have been no labor reform; without Black Nationalists, no deliberate speed. It is here, however, in the investigation of the social and psychological roles of ideology, as distinct from its determinants, that strain theory itself begins to creak and its superior incisiveness, in comparison with interest theory, to evaporate. The increased precision in the location of the springs of ideological concern does not, somehow, carry over into the discrimination of its consequences, where the analysis becomes, on the contrary, slack and ambiguous. The consequences envisaged, no doubt genuine enough in themselves, seem almost adventitious, the accidental byproducts of an essentially nonrational, nearly automatic expressive process initially pointed in another direction --as when a man stubbing his toe cries an involuntary "ouch!" and incidentally vents his anger, signals his distress, and consoles himself with the sound of his own voice; or as when, caught in a subway crush, he issues a spontaneous "damn!" of frustration and, hearing similar oaths from others. gains a certain perverse sense of kinship with fellow sufferers. This defect, of course, can be found in much of the functional analysis in the social sciences: a pattern of behavior shaped by a certain set of forces turns out, by a plausible but nevertheless mysterious coincidence, to serve ends but tenuously related to those forces. A group of primitives sets out, in all honesty, to pray for rain and ends by strengthening its social solidarity; a ward politician sets out to get or remain near the trough and ends by mediating between unassimilated immigrant groups and an impersonal governmental bureaucracy; an ideologist sets out to air his grievances and finds himself contributing, through the diversionary power of his illusions, to the continued viability of the very system that grieves him. The concept of latent function is usually invoked to paper over this anomalous state of affairs, but it rather names the phenomenon (whose reality is not in question) than explains it; and the net result is that functional analyses --and not only those of ideology--remain hopelessly equivocal. The petty bureaucrat's anti-Semitism may indeed give him something to do with the bottled anger generated in him by constant toadying to those he considers his intellectual inferiors and so drain some of it away; but it may also simply increase his anger by providing him with something else about which to be impotently bitter. The neglected artist may better bear his popular failure by invoking the classical canons of his art; but such an invocation may so dramatize for him the gap between the possibilities of his environment and the demands of his vision as to make the game seem unworth the candle. Commonality of ideological perception may link men together, but it may also provide them, as the history of Marxian sectarianism demonstrates, with a vocabulary by means of which to explore more exquisitely the differences among them. The clash of ideologists may bring a social problem to public attention, but it may also charge it with such passion that any possibility of dealing with it rationally is precluded. Of all these possibilities, strain theorists are, of course, very well aware. Indeed they tend to stress negative outcomes and possibilities rather more than the positive, and they but rarely think of ideology as more than a faute de mieux stopgap--like nailchewing. But the main point is that, for all its subtlety in ferreting out the motives of ideological concern, strain theory's analysis of the consequences of such concern remains crude, vacillatory, and evasive. Diagnostically it is convincing; functionally it is not. The reason for this weakness is the virtual absence in strain theory (or in interest theory either) of anything more than the most rudimentary conception of the processes of symbolic formulation. There is a good deal of talk about emotions "finding a symbolic outlet" or "becoming attached to appropriate symbols" -- but very little idea of how ffi the trick is really done. The link between the causes of ideology and its | effects seems adventitious because the connecting element--the autono| mous process of symbolic formulation--is passed over in virtual silence. Both interest theory and strain theory go directly from source analysis to consequence analysis without ever seriously examining ideologies as systems of interacting symbols, as patterns of interworking meanings. Themes are outlined, of course; among the content analysts, they are even counted. But they are referred for elucidation, not to other themes nor to any sort of semantic theory, but either backward to the effect they presumably mirror or forward to the social reality they presumably distort. The problem of how, after all, ideologies transform sentiment into significance and so make it socially available is short-circuited by the crude device of placing particular symbols and particular strains (or interests) side by side in such a way that the fact that the first are derivatives of the second seems mere common sense--or at least post-Freudian, post-Marxian common sense. And so, if the analyst be deft enough, it does.18 The connection is not thereby explained but merely educed. The nature of the relationship between the sociopsychological stresses that incite ideological attitudes and the elaborate symbolic structures through which those attitudes are given a public existencc is much too complicated to be comprehended in terms of a vague and unexamined notion of emotive resonance. |
III. 道具に隠された欠陥が使用される際に明らかになるように、評価的な観念としてのイデオロギーの本質的な弱点も、それが使用される際に明らかになる。特に、 イデオロギーの社会的源泉と結果の研究において、それらは露呈する。なぜなら、そのような研究では、この概念は高度に発達した社会分析および性格分析のエ ンジンと結びついているが、そのエンジンが持つ力は、文化(すなわち、記号体系)の側における同様の力の欠如を強調するだけだからである。イデオロギー思 想の社会的・心理的背景(少なくとも「良い」もの)を調査する際、その背景が扱われる際の繊細さによって、その思想が扱われる際のぎこちなさが浮き彫りに なり、議論全体に不正確さの影が投げかけられる。その影は、最も厳格な方法論的厳格さをもってしても払拭することはできない。 イデオロギーの社会的決定要因の研究には現在、主に2つのアプローチがある。関心理論と緊張理論である。12 前者は、イデオロギーを仮面と武器と見なし、後者は、症状と治療法と見なす。関心理論では、イデオロギー的宣言は、普遍的な優位性獲得競争を背景として見 られる。緊張理論では、社会心理的不均衡を是正しようとする慢性的努力を背景として見られる。一方では、人間は権力を追い求め、他方では不安から逃れよう とする。もちろん、同時に両方を行うことも、一方を他方の手段として行うこともあり得るが、この2つの理論は必ずしも矛盾するものではない。しかし、緊張 理論(これは利害理論が経験的に直面する困難に対応して生まれたもの)は、より単純化されておらず、より洞察力に富み、より具体的ではなく、より包括的で ある。 利害理論の基礎は周知の事実であり、再検討する必要はない。マルクス主義の伝統によってある種の完成度にまで発展したこの理論は、今では一般市民の標準的 な知的装備となっている。一般市民は、政治的な議論においては、すべてが「どちらの牛が角で突かれたか」という問題に帰着することをよく理解している。利 害理論の大きな利点は、そのシステムを信奉する人々の動機や、その動機が社会的な地位、特に社会階級に依存していることを強調することで、文化的な思想体 系を社会構造という確固たる基盤に根付かせたことである。さらに、利益理論は、思想は武器であり、特定の現実の捉え方(自分のグループ、階級、政党のそ れ)を制度化する優れた方法とは、政治権力を掌握し、それを強制することであると指摘することで、政治的思索と政治闘争を結びつけた。これらの貢献は永続 的なものであり、もしも関心理論がかつての覇権を現在も保持していないとすれば、それはその理論が誤りであることが証明されたからというよりも、その理論 的装置が、関心理論自身が明らかにした社会的、心理学的、文化的な要因の相互作用の複雑さに対処するにはあまりにも初歩的すぎることが判明したからであ る。むしろニュートン力学のように、関心理論はそれ以降の進展によって駆逐されたというよりも、それらに吸収されたのである。 関心理論の主な欠点は、その心理学が貧弱すぎ、社会学が強すぎることである。動機に関する発展した分析を欠いているため、人間を意識的に認識された個人的 利益の合理的な計算によって動かされていると見る狭く表面的な功利主義と、人間の考え方を「反映」、「表現」、「対応」、「発生」、あるいは「条件付け」 するものとして、わざと曖昧に語るより広範だが、これまた表面的な歴史主義との間で、常に揺れ動かざるを得なかった。そのような枠組みの中で、分析者は、 あまりにも特定しすぎてまったくありそうもないものにしてしまうことで、その人物の心理の薄っぺらさを明らかにするか、あまりにも一般化しすぎてありふれ たものにしてしまうことで、その人物が心理理論をまったく持っていないという事実を隠蔽するか、という選択に直面する。職業軍人にとって「国内政策は、軍 事組織を維持し拡大する方法として重要である。なぜなら、それが彼らの仕事であり、そのために訓練されているからだ」という主張は、軍人の心はそれほど単 純ではないにもかかわらず、その心に正当な評価を与えていないように思われる。一方、「 アメリカの石油業界の人間は「純粋な石油業界の人間であるはずがない」という主張は、「彼らの利益がそうだから」であり、「彼らは政治的な人間でもある」 という主張は、アヘンが人を眠らせるのは、それが催眠作用を持つからだという理論(これもM. Jourdainの豊かな発想から生まれたもの)と同様に、啓発的である。 一方、社会運動とは本質的に終わりのない権力闘争であるという見方は、イデオロギーを高度な策略の一形態とみなす行き過ぎたマキャベリズム的な見方につな がり、その結果、より広範で劇的ではない社会機能が軽視されることになる。社会を、利益の衝突を理念の衝突と見せかけた戦場と見なすことは、イデオロギー が社会的カテゴリーの定義(または曖昧化)、社会的期待の安定化(または混乱)、社会的規範の維持(または弱体化)、社会的合意の強化(または弱体化)、 社会的緊張の緩和(または悪化)において果たす役割から目を背けさせる。イデオロギーを「筆による戦争」における武器に還元することは、その分析に好戦的 な雰囲気を与えるが、同時に、そのような分析が実施される知的コンパスを、戦術と戦略の狭いリアリズムに還元することでもある。関心理論の強度は、ホワイ トヘッドの言葉を借りれば、その狭さの報酬である。 「利害」は、その曖昧さに関わらず、同時に心理学的および社会学的な概念である。すなわち、個人または個人の集団が感じる優位性と、その個人または集団が 動く機会の客観的構造の両方を指す。「緊張」も同様である。なぜなら、それは個人の緊張状態と社会的な混乱状態の両方を指すからだ。違いは、「緊張」では 動機づけの背景と社会構造の文脈の両方がより体系的に描かれ、両者の関係も描かれていることである。実際、パーソンズ理論の追加によって、関心理論は緊張 理論へと変化する。14 緊張理論の出発点となる明確かつ明瞭な考えは、社会の慢性的な機能不全である。社会のあらゆる仕組みは、必然的に直面する機能上の問題に対処する上で、完 全に成功しているわけではないし、また、完全に成功することはありえない。自由と政治的秩序、安定と変化、効率性と人間性、正確性と柔軟性など、あらゆる ものに解決不能な二律背反が存在する。社会の異なる分野、すなわち経済、政治、家族などにおける規範の間には不連続性がある。異なる分野における目標の間 にも相違がある。例えば、企業における利益や生産性の重視、あるいは大学における知識の拡大と普及などである。そして、最近アメリカ社会学の文献で多く取 り上げられている、監督者、働く妻、芸術家、政治家などに対する矛盾した役割期待もある。社会的摩擦は機械的摩擦と同じくらい広範囲に広がっており、取り 除くことができない。 さらに、この摩擦や社会的緊張は、個人の人格レベルで現れる。人格自体が、相反する欲求、古風な感情、即興的な防御という、必然的に統合不良を起こすシス テムである。構造的不整合として総体的に捉えられるものは、個々人にとっては個人的な不安として感じられる。なぜなら、社会の不完全さと性格の矛盾がぶつ かり合い、互いに悪化するのは、社会的な行動者の経験においてだからである。しかし同時に、社会も個性も、その欠点が何であれ、単なる制度の集合体や動機 の集まりではなく、組織化されたシステムであるという事実がある。つまり、社会心理的な緊張は体系的なものであり、社会的な相互作用から生じる不安には独 自の形と秩序があるということである。少なくとも現代社会では、ほとんどの人は型にはまった絶望的な生活を送っている。 したがって、イデオロギー思想は、この絶望に対する反応(の一種)とみなされる。「イデオロギーとは、社会的な役割の型にはまった緊張に対する型にはまっ た反応である。」15 イデオロギーは、社会的不均衡によって生じる感情的な混乱に対して「象徴的な出口」を提供する。そして、こうした障害は少なくとも一般的な意味では、特定 の役割や社会的地位にある人々のすべてまたはほとんどに共通していると想定できるため、障害に対するイデオロギー的な反応も同様のものになる傾向がある。 この類似性は、特定の文化、階級、職業カテゴリーに属する人々の「基本的な性格構造」に共通性があるという想定によって、さらに強調される。ここでモデル となるのは軍事ではなく医学である。イデオロギーとは病である(Sutton らは、その代替案として、爪を噛む、アルコール依存症、心身症、そして「クローチェット」を挙げている)。そして、診断を必要とする。「緊張の概念は、そ れ自体がイデオロギーのパターンを説明するものではなく、説明を導き出すために探す要因の種類を一般化したラベルである。」16 しかし、医学的であれ社会学的であれ、診断には関連する緊張の特定以上のものがある。人は症状を単に病因論的にではなく、目的論的に理解する。つまり、そ れらが、たとえ役に立たないとしても、それらを生み出した障害に対処するためのメカニズムとして作用する方法という観点から理解する。最も頻繁に用いられ てきた説明は、主に4つのカテゴリーに分類される。すなわち、浄化、モラル、連帯、提唱である。「下剤的説明」とは、由緒ある安全弁理論またはスケープ ゴート理論を意味する。感情的な緊張は、象徴的な敵(「ユダヤ人」、「大企業」、「赤」など)に転嫁されることによって解消される。この説明は、その手法 と同様に単純である。しかし、敵意の正当な対象(あるいは愛情の対象)を提供することで、イデオロギーが、小役人や日雇い労働者、あるいは小さな町の店主 の苦痛をいくらか和らげる可能性があることは否定できない。「士気に関する説明」とは、イデオロギーが慢性的なストレスに直面する個人(または集団)を支 える能力を意味する。それは、ストレスを全面的に否定するか、より高い価値観の観点からそれを正当化することによってである。アメリカというシステムの必 然的な正しさを信じて疑わない小規模事業主も、俗世の中でまともな基準を維持しようとして挫折した芸術家も、そうした手段によって仕事を続けることができ る。イデオロギーは、あるがままのものとそうあってほしいものとの間の感情的なギャップを埋める。それによって、さもなければ絶望や無気力によって放棄さ れてしまうかもしれない役割の遂行が保証される。「連帯の説明」とは、イデオロギーが社会集団や階級を結びつける力を意味する。労働運動、企業、医療業界 などの団結は、その存在の程度において、明らかに共通のイデオロギー的志向に大きく依存している。また、広範な社会的な苦境の感情を担う大衆的なシンボル が存在しなければ、南部は南部ではなくなってしまうだろう。最後に、「擁護的説明」とは、イデオロギー(およびイデオローグ)が、部分的であれ不明瞭であ れ、それらを推進する要因を明確に表現する行為を意味し、それによってそれらを公に認知せざるを得ない状況に追い込む。「イデオローグは、より大きな社会 の問題を提起し、関連する問題について立場を明らかにし、イデオロギー市場という『法廷』にそれを提示する」17。イデオロギーの擁護者(法律上の擁護者 とまったく同じではないが)は、問題の真の性質を明らかにするのと同じくらい、それを不明瞭にする傾向があるが、少なくともその存在に注意を喚起し、問題 を二極化することで、継続的な無視をより困難にしている。マルクス主義者の攻撃がなければ労働改革は起こらなかっただろうし、ブラック・ナショナリストが いなければ意図的なスピードは実現しなかっただろう。 しかし、決定要因とは異なるイデオロギーの社会的および心理的役割の調査において、緊張理論そのものが軋み始め、利害理論と比較してその優れた洞察力が消 え失せる。イデオロギー的関心の源泉の特定精度が向上しても、その帰結の識別には何らかの形でそれが反映されるわけではなく、むしろ分析は緩慢で曖昧なも のとなる。想定される帰結は、それ自体は疑いなく十分に本物であるが、ほとんど偶発的であり、本質的に非理性的でほぼ自動的な表現プロセスの副産物である ように思われる。このプロセスは、当初は別の方向を向いていた。例えば、つま先をぶつけて思わず「痛っ!」と叫び、ついでに怒りをぶちまけ、 苦痛を訴え、自分の声の響きに自らを慰める。あるいは、地下鉄の押しつぶされそうになる混雑に巻き込まれたとき、自発的に「ちくしょう!」と不満を口に し、他の人々からも同じような悪態を耳にする。そして、苦痛を共有する人々との間に、ある種の歪んだ親近感を覚える。 もちろん、この欠陥は社会科学における機能分析の多くに見られる。ある特定の力によって形作られた行動パターンが、もっともらしいが不可解な偶然によっ て、その力とはほとんど関係のない目的を果たすことになる。原始人の一団が、正直に雨乞いをしようとして、結局は社会的な連帯感を強めることになる。区の 政治家が、権力の近くに行こうとして、あるいは権力の近くに留まろうとして、結局は未同化移民グループと非人格的な政府官僚機構との仲介役を担うことにな る。イデオローグが、自分の不満を訴えようとして、幻想の転換力によって、自分自身が、自分を悩ませているまさにそのシステムの存続に貢献していることに 気づく。 潜在機能という概念は、通常、この異常な状態を覆い隠すために持ち出されるが、それは現象を説明するのではなく、現象を名指すだけである(その現実性は疑 いの余地がない)。そして、最終的な結果は、機能分析(イデオロギーの機能分析に限らない)が絶望的に曖昧なままであるということだ。小役人の反ユダヤ主 義は、彼が知的劣等者とみなす人々に対して常にへつらうことで彼の中にたまった怒りを何かにぶつけることができ、その怒りの一部を解消できるかもしれな い。しかし、それは単に、彼に無力な苦々しさを感じる別の対象を与えることで、彼の怒りを増大させるだけかもしれない。無視された芸術家は、自身の芸術に おける古典的な規範を引用することで、自身の人気喪失をよりうまく耐えることができるかもしれない。しかし、そのような引用は、自身の環境の可能性と自身 のビジョンが求めるものとの間のギャップを、その芸術家にとって劇的に強調し、そのゲームがろうそくの火に似て価値がないと思わせるかもしれない。イデオ ロギーの認識における共通性は、人々を結びつけるかもしれないが、同時に、マルクス主義の宗派主義の歴史が示すように、人々の間の相違をより繊細に探求す るための語彙をも提供するかもしれない。イデオロギー論者の衝突は、社会問題を人々の注意に訴えるかもしれないが、同時に、その問題に情熱を注ぎ込み、理 性的に対処する可能性を排除してしまうかもしれない。これらの可能性について、もちろん、緊張理論の論者はよく理解している。実際、彼らは肯定的なものよ りも否定的な結果や可能性を強調する傾向があり、イデオロギーを一時しのぎの策以上のものとして考えることはほとんどない。しかし、重要なのは、イデオロ ギー的関心の動機を突き止めるための繊細な手法とは裏腹に、その関心の結果に対するストレイン理論の分析は粗野で、不安定で、回避的であるということだ。 診断としては説得力があるが、機能的にはそうではない。 この弱点の理由は、緊張理論(あるいは利害理論でも)には、象徴的定式化のプロセスに関する最も初歩的な概念以上のものがほとんど見られないことにある。 感情が「象徴的な出口を見つける」とか「適切な象徴に結びつく」といった話はたくさんあるが、そのトリックが実際にどのように行われるのかについての考え はほとんどない。イデオロギーの原因と影響の間のつながりは、その結合要素である象徴的定式化の自律的プロセスがほとんど無視されているため、偶発的なも ののように思われる。関心理論も緊張理論も、相互作用する象徴の体系、相互に作用する意味のパターンとしてイデオロギーを真剣に検討することなく、原因分 析から結果分析へと直接進む。テーマは、もちろん概説される。内容分析家の間では、テーマの数が数えられることさえある。しかし、それらは解明のために参 照されるのであって、他のテーマや意味論の類に参照されるわけではない。参照されるのは、おそらく反映しているであろう影響を遡って、あるいはおそらく歪 めているであろう社会的現実を前方に参照するのである。結局のところ、イデオロギーが感情を意義へと変え、社会的に利用可能にする方法の問題は、特定のシ ンボルと特定の系統(または利害)を並置するという粗野な手法によって回避される。その手法では、前者が後者の派生物であるという事実が、単なる常識であ るかのように見える。少なくとも、フロイトやマルクス以降の常識であるかのように見える。したがって、分析者が十分に巧妙であれば、そのように見える。 18 そのつながりは説明されているわけではなく、単に導き出されているだけである。イデオロギー的態度を煽り立てる社会心理的ストレスと、そうした態度に公的 な存在意義を与える精巧な象徴構造との関係性は、感情的な共鳴という漠然とした未検証の概念で理解するにはあまりにも複雑である。 |
| IV. It is of singular interest in this connection that, although the general stream of social scientific theory has been deeply influenced by almost every major intellectual movement of the last century and a half-- Marxism, Darwinism, Utilitarianism, Idealism, Freudianism, Behaviorism, Positivism, Operationalism--and has attempted to capitalize on virtually every important field of methodological innovation from ecology, ethology, and comparative psychology to game theory, cybernetics, and statistics, it has, with very few exceptions, been virtually untouched by one of the most important trends in recent thought: the effort to construct an independent science of what Kenneth Burke has called "symbolic action." 19 Neither the work of such philosophers as Peirce, Wittgenstein, Cassirer, Langer, Ryle, or Morris nor of such literary critics as Coleridge, Eliot, Burke, Empson, Blackmur, Brooks, or Auerbach seems to have had any appreciable impact on the general pattern of social scientific analysis.20 Aside from a few more venturesome (and largely programmatic) linguists--a Whorf or a Sapir-- the question of how symbols symbolize, how they function to mediate meanings has simply been bypassed. 'The embarrassing fact," the physician cum novelist Walker Percy has written, "is that there does not exist today-- a natural empirical science of symbolic behavior as such.... Sapir's gentle chiding about the lack of a science of symbolic behavior and the need of such a science is more conspicuously true today than it was thirty-five years ago."21 It is the absence of such a theory and in particular the absence of any analytical framework within which to deal with figurative language that have reduced sociologists to viewing ideologies as elaborate cries of pain. With no notion of how metaphor, analogy, irony, ambiguity, pun, paradox, hyperbole, rhythm, and all the other elements of what we Iamely call "style" operate -- even, in a majority --of cases, with no recognition that these devices are of any importance in casting personal attitudes into public form, sociologists lack the symbolic resources out of which to construct a more incisive formulation. At the same time that the arts have been establishing the cognitive power of "distortion" and philosophy has been undermining the adequacy of an emotivist theory of meaning, social scientists have been rejecting the first and embracing the second. It is not therefore surprising that they evade the problem of construing the import of ideological assertions by simply failing to recognize it as a problem.22 In order to make explicit what I mean, let me take an example that is, I hope, so thoroughly trivial in itself as both to still any suspicions that I have a hidden concern with the substance of the political issue involved and, more important, to bring home the point that concepts developed for the analysis of the more elevated aspects of culture--poetry, for example--are applicable to the more lowly ones without in any way blurring the enormous qualitative distinctions between the two. In discussing the cognitive inadequacies by which ideology is defined for them, Sutton et al. use as an example of the ideologist's tendency to "oversimplify" the denomination by organized labor of the Taft-Hartley Act as a "slave labor law": Ideology tends to be simple and clear-cut. even where its simplicity and clarity do less than justice to the subject under discussion. The ideological picture uses sharp lines and contrasting blacks and whites. The ideologist exaggerates and caricatures in the fashion of the cartoonist. In contrast, a scientific description of social phenomena is likely to be fuzzy and indistinct. [n recent labor ideology the Taft-Hartley Act has been a "slave labor act." By no dispassionate examination does the Act merit this label. Any detached assessment of the Act would have to consider its many provisions individually. On any set of values, even those of trade unions themselves, such an assessment would yield a mixed verdict. But mixed verdicts are not the stuff of ideology. They are too complicated, too fuzzy. Ideology must categorize the Act as a whole with a symbol to rally workers, voters and legislators to action.23 Leaving aside the merely empirical question of whether or not it is in fact true that ideological formulations of a given set of social phenomena are inevitably "simpler" than scientific formulations of the same phenomena, there is in this argument a curiously depreciatory--one might even say "oversimple"--view of the thought processes of laborunion leaders on the one hand and "workers, voters and legislators" on the other. It is rather hard to believe that either those who coined and disseminated the slogan themselves believed or expected anyone else to believe that the law would actually reduce (or was intended to reduce) the American worker to the status of a slave or that the segment of the public for whom the slogan had meaning perceived it in any such terms. Yet it is precisely this flattened view of other people's mentalities that leaves the sociologist with only two interpretations, both inadequate, of whatever effectiveness the symbol has: either it deceives the uninformed (according to interest theory), or it excites the unreflective (according to strain theory). That it might in fact draw its power from its capacity to grasp, formulate, and communicate social realities that elude the tempered language of science, that it may mediate more complex meanings than its literal reading suggests, is not even considered. "Slave labor act" may be, after all, not a label but a trope. More exactly, it appears to be a metaphor or at least an attempted metaphor. Although very few social scientists seem to have read much of it, the literature on metaphor--"the power whereby language, even with a small vocabulary, manages to embrace a multimillion things"-- is vast and by now in reasonable agreements.24 In metaphor one has, of course, a stratification of meaning, in which an incongruity of sense on one level produces an influx of significance on another. As Percy has pointed out, the feature of metaphor that has most troubled philosophers (and, he might have added, scientists) is that it is "wrong": "It asserts of one thing that it is something else." And, worse yet, it tends to be most effective when most "wrong."25 The power of a metaphor derives precisely from the interplay between the discordant meanings it symbolically coerces into a unitary conceptual framework and from the degree to which that coercion is successful in overcoming the psychic resistance such semantic tension inevitably generates in anyone in a po8: sition to perceive it. When it works, a metaphor transforms a false identification (for example, of the labor policies of the Republican Party and of those of the Bolsheviks) into an apt analogy; when it misfires, it is a mere extravagance. That for most people the "slave labor law" figure was, in fact, pretty: much a misfire (and therefore never served with any effectiveness as "a symbol to rally workers, voters and legislators to action") seems evident enough, and it is this failure, rather than its supposed clear-cut simplicity, that makes it seem no more than a cartoon. The semantic tension between the image of a conservative Congress outlawing the closed shop and of the prison camps of Siberia was--apparently--too great to be resolved into a single conception, at least by means of so rudimentary a stylistic device as the slogan. Except (perhaps) for a few enthusiasts, the analogy did not appear; the false identification remained false. But failure is not inevitable, even on such an elementary level. Although, a most unmixed verdict, Sherman's "War is hell" is no social-science proposition, even Sutton and his associates would probably not regard it as either an exaggeration or a caricature. More important, however, than any assessment of the adequacy of the two tropes as such is the fact that, as the meanings they attempt to spark against one another are after all socially rooted, the success or failure of the attempt is relative not only to the power of the stylistic mechanisms employed but also to precisely those sorts of factors upon which strain theory concentrates its attention. The tensions of the Cold War, the fears of a labor movement only recently emerged from a bitter struggle for existence, and the threatened eclipse of New Deal liberalism after two decades of dominance set the sociopsychological stage both for the appearance of the "slave labor" figure and--when it proved unable to work them into a cogent analogy--for its miscarriage The militarists of 1934 Japan who opened their pamphlet on Basic Theory Or National Defense and Suggestions for Its Strengthening with the resounding familial metaphor, "War is the father of creation and the mother of culture," would no doubt have found Sherman's maxim as unconvincing as he would have found theirs.26 They were energetically preparing for an imperialist war in an ancient nation seeking its footing in the modern world; he was wearily pursuing a civil war in an unrealized nation torn by domestic hatreds. It is thus not truth that varies with social, psychological, and cultural contexts but the symbols we construct in our unequally effective attempts to grasp it. War is hell and not the mother of culture, as the Japanese eventually discovered--although no doubt they express the fact in a grander idiom. The sociology of knowledge ought to be called the sociology of meaning, for what is socially determined is not the nature of conception but the vehicles of conception. In a community that drinks its coffee blacks Henle remarks, to praise a girl with "You're the cream in my coffee would give entirely the wrong impression; and, if omnivorousness were regarded as a more significant characteristic of bears than their clumsy roughness, to call a man "an old bear" might mean not that he was crude, but that he had catholic tastes.27 Or, to take an example from Burke, since in Japan people smile on mentioning the death of a dose friend, the semantic equivalent (behaviorally as well as verbally) into American English is not "He smiled," but "His face fell"; for, with such a rendering, we are "translating the accepted social usage of Japan into the corresponding accepted social usage of the West."28 And. closer to the ideological realm, Sapir has pointed out that the chairmanship of a committee has the figurative force we give it only because we hold that "administrative functions somehow stamp a person as superior to those who are being directed"; "should people come to feel that administrative functions are little more than symbolic automatism th. chairmanship of a committee would be recognized as little more than a petrified symbol and the particular value that is now felt to inhere in it would tend to disappear."29 The case is no different for "slave labor law." If forced labor camps come, for whatever reasons, to play a lesprominent role in the American image of the Soviet Union, it will not be the symbol's veracity that has dissolved but its very meaning, its capacity to be either true or false. One must simply frame the argument--that the Taft-Hartley Act is a mortal threat to organized labor--in some other way. In short, between an ideological figure like "slave labor act" and the social realities of American life in the midst of which it appears, there exists a subtlety of interplay, which concepts like "distortion," "selectivity," or "oversimplification" are simply incompetent to formulated Not only is the semantic structure of the figure a good deal more complex than it appears on the surface, but an analysis of that structure forces one into tracing a multiplicity of referential connections between it and social reality, so that the final picture is one of a configuration of dissimilar meanings out of whose interworking both the expressive power and the rhetorical force of the final symbol derive. This interworking is itself a social process, an occurrence not "in the head" but in that public world where "people talk together, name things, make assertions, and to a degree understand each other."31 The study of symbolic action is no less a sociological discipline than the study of small groups, bureaucracies, or the changing role of the American woman; it is only a good deal less developed. |
IV. この点において特筆すべきは、社会科学理論の一般的な流れは、過去1世紀半のほぼすべての主要な知的運動――マルクス主義、ダーウィニズム、功利主義、観 念論、フロイト主義、行動主義、実証主義、操作主義――に深く影響を受け、 生態学、動物行動学、比較心理学からゲーム理論、サイバネティクス、統計学に至るまで、方法論の革新におけるほぼすべての重要な分野を活用しようとしてき たが、ごく一部の例外を除いて、最近の思想における最も重要な傾向のひとつである、ケネス・バークが「象徴的行為」と呼ぶものの独立した科学を構築する試 みには、ほとんど手をつけていない。19 ピアス、ウィトゲンシュタイン、カッシーラー、ランガー、ライル、モリスといった哲学者の業績も、コールリッジ、エリオット、バーク、エンプソン、ブラッ クマー、ブルックス、オーエブリーといった文学評論家の業績も、 社会科学的分析の一般的なパターンに著しい影響を与えた人物はいない。20 ウォーフやサピアのような、より大胆な(そしてほとんどがプログラム的な)言語学者を除いては、記号がどのように記号化するか、意味を媒介する機能として どのように機能するかという問題は、単純に回避されてきた。医師であり小説家でもあるウォーカー・パーシーは、「恥ずべき事実」として、「今日、記号行動 に関する自然な経験科学は存在しない」と書いている。記号行動の科学が存在しないこと、そしてそのような科学が必要であることについて、サピアが優しく叱 責していることは、35年前よりも今日の方がより顕著に真実である。」21 このような理論の欠如、特に比喩的な言語を扱うための分析的枠組みの欠如が、社会学者をイデオロギーを痛切な叫び声として捉えるように追いやってきた。た とえ大半のケースにおいて、比喩、類推、皮肉、曖昧性、ダジャレ、逆説、誇張、リズム、そして私が「スタイル」と呼ぶものの他のすべての要素がどのように 作用するのかについての概念がなく、また、これらの手法が個人の態度を公的な形に定着させる上で重要であるという認識がないために、社会学者は、より鋭い 定式化を構築するための象徴的なリソースを欠いている。芸術が「歪曲」の認知力を確立し、哲学が感情論的な意味論の妥当性を損なってきたのと同時に、社会 科学者は前者を拒絶し、後者を受け入れてきた。したがって、彼らがイデオロギー的主張の含意を解釈するという問題を、単にそれを問題として認識しないこと によって回避しているとしても、驚くには当たらない。 私が言わんとすることを明確にするために、私は、私が政治問題の本質について隠された関心を持っているのではないかという疑いを晴らすと同時に、より重要 なこととして、文化のより高尚な側面(例えば詩)の分析のために開発された概念が、より卑しいものにも適用可能であり、両者の間に存在する質的な大きな違 いをぼやかせることは一切ないという点を理解してもらうために、完全に些細な例を挙げてみようと思う。サットンらは、イデオロギーが認知上の不十分さに よって定義されることを論じる中で、労働組合による「タフト・ハートレー法」を「奴隷労働法」として「単純化しすぎる」イデオロギー論者の傾向を例として 挙げている。 イデオロギーは単純かつ明確である傾向がある。その単純性や明瞭性が、議論の対象に対して正当な評価を下していない場合でもである。イデオロギー的な描写 は、鋭い線と黒と白のコントラストを使用する。イデオロギー論者は、漫画家の手法で誇張や風刺を行う。それに対して、社会現象の科学的描写は、あいまいか つ不明瞭である傾向がある。最近の労働イデオロギーでは、タフト・ハートレー法は「奴隷労働法」である。この法律がこのレッテルに値するかどうかは、冷静 な検討によっては判断できない。この法律を客観的に評価するには、その多くの規定を個別に検討しなければならない。どのような価値観に照らしても、労働組 合自身でさえ、そのような評価は賛否両論となるだろう。しかし、賛否両論はイデオロギーの対象ではない。それはあまりにも複雑で、あいまいすぎる。イデオ ロギーは、労働者、有権者、議員を結集して行動を起こさせるシンボルとともに、この法律全体を分類しなければならない。 特定の社会現象をイデオロギー的に定式化することは、同じ現象を科学的に定式化するよりも「より単純」であるということが実際に真実であるかどうかとい う、単に経験的な問題はさておき、この議論には、労働組合のリーダーと「労働者、有権者、議員」の思考プロセスに対する、奇妙なほどに否定的な見方、ある いは「単純すぎる」とさえ言える見方がある。このスローガンを考案し広めた人々が、法律が実際にアメリカの労働者を奴隷の地位にまで引き下げる(あるいは 引き下げる意図がある)と信じていた、あるいは他の誰かが信じることを期待していたとは、なかなか信じがたい。また、このスローガンが意味を持つ人々も、 それをそのような言葉で捉えていたとは思えない。しかし、他者の心理をこのように単純化して見ることこそが、そのシンボルが持つ効果について、社会学者が 2つの不適切な解釈しか持てない原因となっている。すなわち、無知な人々を欺く(利害理論による)か、思慮のない人々を刺激する(緊張理論による)か、の どちらかである。実際には、科学の洗練された言語では捉えきれない社会の現実を把握し、体系化し、伝達する能力からその力が引き出されている可能性がある こと、また、その文字通りの意味よりも複雑な意味合いを媒介している可能性があることについては、まったく考慮されていない。「奴隷労働行為」は、結局の ところ、レッテルではなく修辞法であるのかもしれない。 より正確に言えば、それは比喩であるか、少なくとも比喩の試みであるように見える。社会科学者のほとんどがこの文献をあまり読んだことがないようだが、比 喩に関する文献は膨大であり、今では妥当な合意が得られている。24 比喩には、もちろん、意味の層がある。あるレベルでの意味の不調和が、別のレベルでの意義の流入を生み出す。パーシーが指摘しているように、哲学者(そし て、彼が付け加えるなら科学者)を最も悩ませてきた比喩の特徴は、「誤り」である。「あるものを、それとは別のものだと主張する」ということである。さら に悪いことに、比喩は最も「間違っている」場合に最も効果的になる傾向がある。25 比喩の力は、まさに、比喩が象徴的に単一の概念的枠組みに無理やり押し込める不調和な意味の相互作用と、その強制が、比喩を認知する立場にある誰もが必然 的に生み出す意味論的な緊張から生じる心理的抵抗を克服する上で成功する度合いから生じる。うまく機能すれば、隠喩は誤った同一視(例えば、共和党の労働 政策とボルシェビキの労働政策の同一視)を適切な類似性に変える。しかし、誤った場合には、単なる贅沢に過ぎない。 ほとんどの人々にとって、「奴隷労働法」という表現は、実際にはかなり見当はずれであった(したがって、「労働者、有権者、議員を行動に駆り立てるシンボ ル」として有効に機能することは決してなかった)ことは明らかである。そして、この失敗こそが、その明快な単純性という想定よりも、この表現を単なる漫画 のように見せているのだ。クローズドショップを違法とする保守的な議会とシベリアの強制収容所のイメージの間の意味論的な緊張は、少なくともスローガンと いう初歩的なスタイルの手法では、ひとつの概念に解決するにはあまりにも大きすぎた。熱狂的な一部の人々を除いて、その類似性は見出されなかった。誤った 同一視は誤ったままであった。しかし、このような初歩的なレベルにおいても、失敗は避けられないわけではない。 純粋な評決を下すならば、シャーマンの「戦争は地獄だ」は社会科学的な命題ではないが、サットンや彼の仲間たちも、おそらくそれを誇張や風刺とは見なさな いだろう。 しかし、この2つの表現の適切さの評価よりも重要なのは、これらの表現が互いに呼び起こそうとする意味が結局は社会的に根ざしているという事実であり、そ の試みの成否は、用いられた表現上のメカニズムの力だけでなく、まさに緊張理論が注目するそれらの要因にも相対的なものとなる。冷戦の緊張、苦しい生存競 争からようやく脱した労働運動の不安、そして20年にわたって支配的であったニューディール自由主義が失墜の危機に瀕していたことが、社会心理的な舞台を 整え、「奴隷労働」という概念の登場を促した。そして、その概念が説得力のある類推として機能しないことが明らかになると、その概念は頓挫した。1934 年の日本の軍国主義者たちは、 あるいは国防とその強化に関する提言』というパンフレットを「戦争は創造の父であり、文化の母である」という衝撃的な家族的な比喩で開いた1934年の日 本の軍国主義者たちは、シャーマンの格言を自分たちのものと同じくらい説得力のないものと感じたに違いない。26 彼らは、近代世界での足場を模索する古代の国家で帝国主義戦争に精力的に備えていた。一方、彼は、国内の憎悪に引き裂かれた未開の国家で、内戦を疲れ果て て追っていた。したがって、真実が社会、心理、文化の文脈によって変化するのではなく、真実を把握しようとする私たちの不均等な試みの中で構築されるシン ボルこそが変化するのだ。戦争は地獄であり、文化の母ではない。日本人は最終的にこの事実を発見したが、彼らは間違いなく、この事実をより壮大なイディオ ムで表現するだろう。 社会的に決定されるのは概念の本質ではなく、概念の手段であるため、知識社会学は意味社会学と呼ぶべきである。コーヒーをブラックで飲むようなコミュニ ティでは、ヘンレは「君は僕のコーヒーのクリームだ」と褒めるのはまったく間違った印象を与えると述べている。また、雑食性が熊の不器用な粗野さよりも重 要な特徴であるとみなされる場合、「年取った熊」という表現は、その人が粗野であるという意味ではなく、趣味が幅広いという意味になるかもしれない。27 あるいは、バークの例を挙げると、 日本では友人の死を聞いて人々が微笑むことから、アメリカ英語における意味上の同等物(行動上および言語上)は「He smiled(彼は微笑んだ)」ではなく「His face fell(彼の顔が曇った)」となる。なぜなら、このような表現では「日本の社会で受け入れられている慣習を、西洋の社会で受け入れられている慣習に翻訳 している」ことになるからだ。28 そして、イデオロギーの領域により近いところで、サピアは、委員会の委員長という役職が比喩的な力をもつのは、 「管理機能が、管理される人々よりも優れた人物であることを何らかの形で刻印する」という考え方があるからこそ、私たちは委員会の議長職に比喩的な力を与 えている。「もし人々が管理機能が象徴的な自動的なものにすぎないと考えるようになった場合、委員会の議長職は単なる象徴の固まりとして認識され、今では そこに内在すると感じられている特別な価値は消え去る傾向にあるだろう」29。「奴隷労働法」の場合も事情は変わらない。強制労働収容所が、どのような理 由であれ、ソ連に対するアメリカのイメージの中でより目立つ役割を果たすようになった場合、そのシンボルの真実性が失われるのではなく、その意味、つまり 真実であるか偽りであるかの能力が失われることになるだろう。タフト・ハートレー法は組織労働者にとって致命的な脅威であるという主張を、別の方法で展開 しなければならない。 つまり、「奴隷労働法」のような観念的な概念と、それが現れるアメリカ社会の現実との間には、微妙な相互作用が存在する。「歪曲」、「選択」、「単純化」 といった概念では、それを表現することはできない。この概念の持つ意味構造は 表面的に見えるよりもはるかに複雑であるだけでなく、その構造の分析は、その象徴と社会的現実との間の参照関係の多様性をたどることを余儀なくさせる。そ の結果、最終的な象徴の表現力と修辞力は、その相互作用から生じる異質な意味の構成の1つとなる。この相互作用自体が社会的プロセスであり、それは「頭の 中」ではなく、「人々が共に話し、物事を名指し、主張し、ある程度お互いを理解する」31公共の世界で起こるものである。象徴的行為の研究は、小集団、官 僚制、あるいはアメリカ女性の役割の変化の研究に劣らず社会学的な分野である。しかし、その発展度はかなり劣る。 |
| V. Asking the question that most students of ideology fail to ask--what, precisely, do we mean when we assert that sociopsychological strains are "expressed" in symbolic forms?--gets one, therefore, very quickly into quite deep water indeed; into, in fact, a somewhat untraditional and apparently paradoxical theory of the nature of human thought as a public and not, or at least not fundamentally, a private activity.32 The details of such a theory cannot be pursued any distance here, nor can any signifieant amount of evidence be marshaled to support it. But at least its general outlines must be sketched if we are to find our way back from the elusive world of symbols and semantic process to the (apparently) more solid one of sentiments and institutions, if we are to trace with some circumstantiality the modes of interpenetration of culture, personality, and social system. The defining proposition of this sort of approach to thought en plein air--what, following Galanter and Gerstenhaber, we may call "the extrinsic theory"--is that thought consists of the construction and manipulation of symbol systems, which are employed as models of other systems, physical, organic, social, psyehologieal, and so forth, in such a way that the structure of these other systems-- and, in the favorable ease, how they may therefore be expected to behave--is, as we say "understood."33 Thinking, conceptualization, formulation, eomprehension, understanding, or what-have-you, consists not of ghostly happenings in the head but of a matching of the states and processes of symbolie models against the states and processes of the wider world: Imaginal thinking is neither more nor less than constructing an image of the environment, running the model faster than the environment, and predicting that the environment will behave as the model does.... The first step ill the solution of a problem consists in the construction of a model or ima2c of the "relevant features" of the [environment]. These models can be constructed from many things including parts of the organic tissue of the body and, by man, paper and pencil or actual artifacts. Once a model has been constructed it can be manipulated under various hypothetical conditions and constraints. The organism is then able to "observe" the outcome of these manipulations, and to project them onto the environment so that prediction is possible. According to this view, an aeronautical engineer is thinking when he manipulates a model of a new airplane in a wind tunnel. The motorlst is thinking when he runs his finger over a line on a map, the finger serving as a model of the relevant aspects of the automobile, the map as a model of the road. External models of this kind are often used in thinking about complex [environments]. Images used in covert thinking depend upon the availability of the physieo-chemieal events of the organism which must be used to form models.34 This view does not, of course, deny consciousness: it defines it. Every conscious perception is, as Percy has argued, an act of recognition, a pairing in which an object (or an event, an act, an emotion) is identified by placing it against the background of an appropriate symbol: It is not enough to say that one is conscious of something; one is also eonseious of something being something. There is a difference between the apprehension of a gestalt (a chicken perceived the Jastrow effect as well as a human) and the grasping of it under its symbolic vehicle. As I gaze about the room. I am aware of a series of almost effortless acts of mate hmg: seeing an object and knowing what it is. If my eye falls upon an unfamiliar something. I am immediately aware that one term of the match is missing, I ask what [the objects is--an exceedingly mysterious question.35 What is missing and what is being asked for are an applicable symbolic model under which to subsume the "unfamiliar something" and so render it familiar: If I see all object at some distance and do not quite recognize it, I may see it, actually see it, as a succession of different things, each rejected by the criterion of fit as I come closer. until one is positively certified. A patch of sunlight in a field I may actually see as a rabbit--a seeing which goes much further than the guess that it may be a rabbit; no, the perceptual ges talt is so construed. actually stamped by the essence of rabbitness: I could have sworn it was a rabbit. On coming closer. the sunlight pattern changes enough so that the rabbit-cast is disallowed. The rabbit vanishes and I make another cast: it is a paper bag. and so on. But most significant of all. even the last. the "correct" recognition is quite as mediate an apprehension as the incorrect ones; it is also a cast, a pairing, an approximation. And let us note in passing that even though it is correct. even though it is borne out by all indices. it may operate quite as effectively to conceal as to discover. When I recognize a strange bird as a sparrow. I tend to dispose of the bird under its appropriate formulation: it is only a sparrow.36 Despite the somewhat intellectualist tone of these various examples, the extrinsic theory of thought is extendable to the affective side of human mentality as well.37 As a road map transforms mere physical locations into "places," connected by numbered routes and separated by measured distances, and so enables us to find our way from where we are to where we want to go, so a poem like, for example, Hopkins's "Felix Randal" provides, through the evocative power of its charged language, a symbolic model of the emotional impact of premature death, which, if we are as impressed with its penetration as with the road map's, transforms physical sensations into sentiments and attitudes and enables us to react to such a tragedy not "blindly" but "intelligently." The central rituals of religion--a mass, a pilgrimage, a corroboree--are symbolic models (here more in the form of activities than of words) of a particuiar sense of the divine, a certain sort of devotional mood, which their continual re-enactment tends to produce in their participants. Of course, as most acts of what is usually called "cognition" are more on the level of identifying a rabbit than operating a wind tunnel, so most of what is usually called "expression" (the dichotomy is often overdrawn and almost universally misconstrued) is mediated more by models drawn from popular culture than from high art and formal religious ritual. But the point is that the development, maintenance, and dissolution of "moods," "attitudes," "sentiments," and so forth are no more "a ghostly process occurring in streams of consciousness we are debarred from visiting" than is the discrimination of objects, events, structures, processes, and so forth in our environment. Here, too, "we are describing the ways in which . . . people conduct parts of their predominantly public behavior."38 Whatever their other differences, both socalled cognitive and socalled expressive symbols or symbol-systems have, then, at least one thing in common: they are extrinsic sources of information in terms of which human life can be patterned--extrapersonal mechanisms for the perception, understanding, judgment, and manipulation of the world. Culture patterns--religious, philosophical, aesthetic, scientific, ideological--are "programs"; they provide a template or blueprint for the organization of social and psychological processes, much as genetic systems provide such a template for the organization of organic processes: These considerations define the terms in which we approach the problem of "reductionism" in psychology and social science. The levels we have tentatively discriminated [organism, personality, social system, culture] . . . are . . . levels of organization and control. The lower levels "condition," and thus in a sense "determine" the structures into which they enter, in the same sense that the stability of a building depends on the properties of the materials out of which it is constructed. But the physical properties of the materials do not determine the plan of the building; this is a factor of another order, one of organization. And the organization controls the relations of the materials to each other, the ways in which they are utilized in the building by virtue of which it constitutes an ordered system of a particular type ---looking downward" in the series, we can always investigate and discover sets of "conditions" in which the function of a higher order of organization is dependent. There is, thus, an immensely complicated set of physiological conditions on which psychological functioning is dependent, etc. Properly understood and evaluated, these conditions are always authentic determinants of process in the organized systems at the next higher levels. We may, however also look "upward" in the series. In this direction we see "structures ' organization patterns, patterns of meaning, programs," etc., which are the focus of the organization of the system at the level on which we have concentrated our attention.39 The reason such symbolic templates are necessary is that, as has been often remarked, human behavior is inherently extremely plastic. Not strictly but only very broadly controlled by genetic programs or models--intrinsic sources of information--such behavior must, if it is to have any effective form at all, be controlled to a significant extent by extrinsic ones. Birds learn how to fly without wind tunnels, and whatever reactions lower animals have to death are in great part innate, physiologically preformed.40 The extreme generality, diffuseness, and variability of man's innate response capacities mean that the particular pattern his behavior takes is guided predominantly by cultural rather than genetic templates, the latter setting the overall psychophysical context within which precise activity sequences are organized by the former. The toolmaking, laughing, or lying animal, man, is also the incomplete--or, more accurately, self-completing--animal. The agent of his own realization, he creates out of his general capacity for the construction ol symbolic models the specific capabilities that define him. Or--to return at last to our subject--it is through the construction of ideologies, sche matic images of social order, that man makes himself for better worse a political animal. Further, as the various sorts of cultural symbol-systems are extrinsic sources of information, templates for the organization of social and psychological processes, they come most crucially into play in situations where the particular kind of information they contain is lacking, where institutionalized guides for behavior, thought, or feeling are weak or absent. It is in country unfamiliar emotionally or topographically that one needs poems and road maps. So too with ideology. In polities firmly embedded in Edmund Burke's golden assemblage of "ancient opinions and rules of life," the role of ideology, in any explicit sense, is marginal. In such truly traditional political systems the participants act as (to use another Burkean phrase) men of untaught feelings; they are guided both emotionally and intellectually in their judgments and activities by unexamined prejudices, which do not leave them "hesitating in the moment of decision, sceptical, puzzled and unresolved." But when, as in the revolutionary France Burke was indicting and in fact in the shaken England from which, as perhaps his nation's greatest ideologue, he was indicting it, those hallowed opinions and rules of life come into question, the search for systematic ideological formulations, either to reinforce them or to replace them, flourishes. The function of ideology is to make an autonomous politics possible by providing the authoritative concepts that render it meaningful, the suasive images by means of which it can be sensibly grasped.41 It is, in fact, precisely at the point at which a political system begins to free itself from the immediate governance of received tradition, from the direct and detailed guidance of religious or philosophical canons on the one hand and from the unreflective precepts of conventional moralism on the other, that formal ideologies tend first to emerge and take hold.42 The differentiation of an autonomous polity implies the differentiation, too, of a separate and distinct cultural model of political action, for the older, unspecialized models are either too comprehensive or too concrete to provide the sort of guidance such a political system demands. Either they trammel political behavior by encumbering it with transcendental significance, or they stifle political imagination by binding it to the blank realism of habitual judgment. It is when neither a society's most general cultural orientations nor its most down-to-earth, "pragmatic" ones suffice any longer to provide an adequate image of political process that ideologies begin to become crucial as sources of sociopolitical meanings and attitudes. In one sense, this statement is but another way of saying that ideology is a response to strain. But now we are including cultural as well as social and psychological strain. It is a loss of orientation that most directly gives rise to ideological activity, an inability, for lack of usable models, to comprehend the universe of civic rights and responsibilities in which one finds oneself located. The development of a differentiated polity (or of greater internal differentiation within such a polity) may and commonly does bring with it severe social dislocation and psychological tension. But it also brings with it conceptual confusion, as the established images of political order fade into irrelevance or are driven into disrepute. The reason why the French Revolution was, at least up to its time, the greatest incubator of extremist ideologies, "progressive" and "reactionary" alike, in human history was not that either personal insecurity or social disequilibrium were deeper and more pervasive than at many earlier periods--though they were deep and pervasive enough --but because the central organizing principle of political life, the divine right of kings, was destroyed.43 It is a confluence of sociopsychological strain and an absence of cultural resources by means of which to make sense of the strain, each exacerbating the other, that sets the stage for the rise of systematic (political, moral, or economic) ideologies. And it is, in turn, the attempt of ideologies to render otherwise incomprehensible social situations meaningful, to so construe them as to make it possible to act purposefully within them, that accounts both for the ideologies' highly figurative nature and for the intensity with which, once accepted, they are held. As metaphor extends language by broadening its semantic range, enabling it to express meanings it cannot or at least cannot yet express literally, so the head-on clash of literal meanings in ideology--the irony, the hyperbole, the overdrawn antithesis--provides novel symbolic frames against which to match the myriad "unfamiliar somethings" that, like a journey to a strange country, are produced by a transformation in political life. Whatever else ideologies may be--projections of unacknowledged fears, disguises for ulterior motives, phatic expressions of group solidarity--they are, most distinctively, maps of problematic social reality and matrices for the creation of collective conscience. Whether, in any particular case, the map is accurate or the conscience creditable is a separate question to which one can hardly give the same answer for Nazism and Zionism, for the nationalisms of McCarthy and of Churchill, for the defenders of segregation and its opponents. |
V. イデオロギーの学生のほとんどが尋ねない質問、すなわち、社会心理的な緊張が象徴的な形態で「表現される」と主張するとき、私たちは正確に何を意味してい るのか、という質問を尋ねると、すぐに非常に深い水域に到達する。実際、それは 公的なものであり、少なくとも本質的には私的な活動ではない人間の思考の本質に関する、伝統的とは言えない、一見すると逆説的な理論である。32 このような理論の詳細をここで追求することはできないし、それを裏付けるに足る量の証拠を提示することもできない。しかし、もし私たちが、つかみどころの ない記号や意味のプロセスから、より確かな情緒や制度の世界へと戻る道を見つけたいのであれば、また、文化、人格、社会システムの相互浸透の様式をある程 度正確にたどりたいのであれば、少なくともその大まかな輪郭を描く必要がある。 この種の屋外での思考へのアプローチを定義する命題、すなわち、ギャランターとゲルステンハーバーにならって「外在理論」と呼ぶかもしれない命題は、思考 は記号システムの構築と操作から成り立っており、それらの記号システムは、物理的、有機的、社会的、心理学的など、他のシステムのモデルとして用いられる というものである。 そして、望ましい状況においては、それらがどのように振る舞うかが「理解」される。思考、概念化、定式化、理解、理解、またはその他何であれ、頭の中で起 こる幽霊のような出来事ではなく、シンボルのモデルの状態とプロセスを、より広い世界の状態とプロセスに一致させることである。 想像的思考とは、環境のイメージを構築し、そのモデルを環境よりも高速で実行し、環境がモデルと同じように振る舞うと予測することに他ならない。問題解決 の第一歩は、環境の「関連する特徴」のモデルまたはイメージを構築することである。これらのモデルは、身体の有機組織の一部や、人間、紙と鉛筆、または実 際の人工物など、多くのものから構築することができる。いったんモデルが構築されれば、さまざまな仮説上の条件や制約のもとで操作することができる。する と、生物はこれらの操作の結果を「観察」し、予測を可能にするために環境に投影することができる。この見解によれば、航空エンジニアは風洞で新型飛行機の モデルを操作しているときに考えていることになる。地図上の線に指を沿わせるとき、指は自動車の関連する側面のモデルとなり、地図は道路のモデルとなる。 このような外部モデルは、複雑な環境について考える際にしばしば用いられる。隠れた思考で用いられるイメージは、モデルを形成するために用いられるべき生 物の物理化学的イベントの可用性に依存する。 もちろん、この見解は意識を否定するものではない。意識とは定義されたものである。パーシーが主張するように、あらゆる意識的な知覚は認識の行為であり、 対象(あるいは出来事、行為、感情)を適切なシンボルの背景に置くことで識別する行為である。 何かを意識していると言うだけでは十分ではない。何かが何かであることを意識しているのだ。ゲシュタルト(鶏は人間と同様にジャストロー効果を認識してい る)を把握することと、象徴的な手段によってそれを理解することの間には違いがある。私は部屋を見回しながら、 私は、対象を見てそれが何であるかを知るという、ほとんど努力を必要としない一連の行為に気づく。もし私の目が慣れない何かにとまったら、私はすぐに、一 致する項目の1つが欠けていることに気づく。私は、その対象が何であるかを尋ねる。これは非常に不思議な質問である。 35 欠けているもの、そして求められているものは、「慣れない何か」を包含し、それを馴染みのあるものにするための、適用可能な象徴モデルである。 もし私がすべての対象をある距離から見ていて、それが何なのかよくわからない場合、近づくにつれて、それぞれが適合の基準によって拒絶される、異なるもの の連続として、それを実際に見るかもしれない。 それが何なのかがはっきりと証明されるまで。 畑に差し込む一筋の光を、私は実際にウサギとして見るかもしれない。 それは、ウサギかもしれないという推測よりもはるかに先を行くものだ。 いいや、知覚のゲシュタルトはそう解釈される。 実際にウサギらしさの本質によって刻印される。私はそれがウサギであると確信した。近づいてみると、光のパターンが変化し、ウサギであるという判断は覆さ れる。ウサギは消え、私はもう一度判断する。それは紙袋だ。そして、また同じことが起こる。しかし、最も重要なのは、最後のことさえも、「正しい」認識 は、不正確な認識と同じように、媒介された理解であり、判断であり、近似であるということだ。そして、正しい認識であっても、あらゆる指標によって裏付け られているとしても、発見するのと同じくらい効果的に隠蔽する働きをする可能性があることを、ここで簡単に指摘しておこう。私が奇妙な鳥をスズメだと認識 したとき、私はその鳥を適切な名称で片付けがちになる。つまり、それはただのスズメにすぎないのだ。 これらのさまざまな例は、やや観念論的なトーンを含んでいるが、思考の外延理論は人間の精神の情動的な側面にも適用できる。37 道路地図が単なる物理的な場所を「場所」に変え、番号付きのルートでつなぎ、距離を測って区切ることで、現在地から目的地までの道順を見つけられるように するのと同様に、 例えばホプキンスの「フェリックス・ランドール」のような詩は、その感情を揺さぶる言葉の力によって、早すぎる死が感情に与える影響の象徴的なモデルを提 供している。もし私たちがその詩の洞察力に地図と同じくらい感銘を受けるならば、物理的な感覚は感情や態度へと変化し、そのような悲劇に対して「盲目的」 ではなく「理性的」に反応できるようになる。宗教の中心的な儀式であるミサ、巡礼、コロボリーは、特定の神聖な感覚、ある種の敬虔な雰囲気の象徴的なモデ ル(ここでは言葉よりも活動の形をとる)であり、その継続的な再現は参加者の中にそれを生み出す傾向がある。もちろん、通常「認識」と呼ばれる行為のほと んどは、風洞を操作するよりもウサギを識別するレベルのものであるように、通常「表現」と呼ばれるもののほとんど(この二分法はしばしば行き過ぎであり、 ほぼ普遍的に誤解されている)は、高尚な芸術や形式的な宗教儀式よりも大衆文化から引き出されたモデルによって媒介されている。しかし、重要なのは、「気 分」、「態度」、「感情」などの発達、維持、解消は、環境における物体、出来事、構造、プロセスなどの識別と同様に、「意識の流れの中で起こる幽霊のよう なプロセスであり、我々は立ち入ることができない」ものではないということだ。ここでも、「我々は、人々が主に公的な行動の一部をどのように行うかを説明 している」38。 認知シンボルと表現シンボル、あるいはシンボル体系と呼ばれるものには、その他の相違点があるにせよ、少なくとも1つの共通点がある。それは、人間の生活 をパターン化できる外在的な情報源であるということだ。すなわち、世界を認識し、理解し、判断し、操作するための、個人を超えたメカニズムである。宗教、 哲学、美学、科学、イデオロギーなどの文化パターンは「プログラム」であり、遺伝システムが有機的プロセスの組織化にテンプレートや青写真を提供するのと 同様に、社会心理的プロセスの組織化のためのテンプレートや青写真を提供する。 これらの考察は、心理学や社会科学における「還元主義」の問題へのアプローチを定義する。我々が暫定的に区別したレベル(有機体、人格、社会システム、文 化)は、組織化と制御のレベルである。下位のレベルは「条件」であり、それゆえ、ある意味では、それらが組み込まれる構造を「決定」する。これは、建物の 安定性が、その構成材料の特性に依存しているのと同じ意味である。しかし、材料の物理的特性が建物の設計図を決定するわけではない。これは、別の要因、す なわち組織化の要因である。そして、組織は、材料同士の関係、建物でそれらがどのように利用されるか、それによって建物が特定のタイプの秩序あるシステム を構成するかを制御する。「下位」の系列を常に調査し、より高次の組織の機能が依存する「条件」の集合を発見することができる。このように、心理的機能が 依存する生理学的な条件の集合は非常に複雑である。適切に理解され評価されれば、これらの条件は常に、より上位のレベルにある組織化されたシステムにおけ るプロセスの真の決定要因となる。しかし、私たちは「上位」にも目を向けることができる。この方向では、「構造」「組織パターン」「意味のパターン」「プ ログラム」などが見られる。これらは、私たちが注意を集中しているレベルにおけるシステムの組織化の焦点である。 このような象徴的なテンプレートが必要とされる理由は、よく言われるように、人間の行動は本質的に極めて可塑性が高いからである。遺伝子プログラムやモデ ル(すなわち、本質的な情報源)によって厳密にではなく、非常に大まかに制御されているだけである。そのような行動が何らかの効果的な形を持つためには、 外的な要因によってかなりの程度制御されなければならない。鳥は風洞なしで飛ぶ方法を学ぶし、下等動物が死に対して示す反応は、大部分が生まれつき備わっ ている生理学的にあらかじめ形成されたものである。40 人間の生まれつき備わっている反応能力の極めて一般的な性質、拡散性、可変性は、人間の行動がとる特定のパターンは、遺伝的テンプレートよりも文化的なテ ンプレートによって主に導かれることを意味する。後者は、前者が正確な活動シーケンスを組織化する心理物理学的コンテクスト全体を設定する。道具を作り、 笑い、嘘をつく動物である人間は、不完全な動物でもある。より正確に言えば、自己を完成させる動物である。人間は、象徴モデルを構築する一般的な能力か ら、人間を定義する特定の能力を作り出す。あるいは、ようやく本題に戻ると、人間は、社会秩序の概略図であるイデオロギーを構築することで、良くも悪くも 政治的な動物となる。 さらに、さまざまな種類の文化的な象徴体系は、外的な情報源であり、社会的および心理的プロセスの組織化のためのテンプレートであるため、それらが含む特 定の種類の情報の欠如、行動、思考、感情の制度化された指針が弱い、あるいは存在しない状況において、最も重要な役割を果たす。感情的にも地理的にも見慣 れない土地では、詩やロードマップが必要となる。 イデオロギーも同様である。エドマンド・バークの「古代の意見と人生のルール」という黄金の集合体にしっかりと組み込まれた政治体制においては、イデオロ ギーの役割は、明示的な意味では限定的である。このような真に伝統的な政治体制においては、参加者は(バークの別の表現を借りれば)「教えられていない感 情を持つ人々」として行動する。彼らは、判断や行動において、感情と知性の両面から、吟味されていない偏見によって導かれる。その結果、「決断の瞬間にた めらい、懐疑的になり、困惑し、解決できない」状態に陥ることはない。しかし、革命期のフランスにおいて、そして事実、揺れ動くイングランドにおいて、お そらく国民の最大のイデオローグとして、聖なる意見や生活のルールが疑問視されるようになったとき、それらを強化するか、あるいは置き換えるか、体系的な イデオロギーの形成を求める動きが盛んになった。イデオロギーの機能は、それを意味あるものとする権威ある概念、つまり感覚的に把握できる説得力のあるイ メージを提供することで、自律的な政治を可能にすることである。41 実際、政治システムが、一方では宗教的または哲学的規範の直接的かつ詳細な指導から、他方では型にはまった道徳主義の思慮のない教えから、受け継がれた伝 統の直接的な統治から自らを解放し始めるまさにその時点で、 一方では、宗教的または哲学的規範の直接的かつ詳細な指導から、他方では、型にはまった道徳主義の思慮のない教えから、政治体制が自らを解放し始める時点 において、形式的なイデオロギーが最初に現れ、定着する傾向がある。42 自律的な政治体制の分化は、政治行動の別個かつ明確な文化的モデルの分化も意味する。なぜなら、古い未分化なモデルは、包括的すぎたり、具体的すぎたりし て、そのような政治体制が求めるような指針を提供できないからである。超越的な意義を政治的行動に付加することで政治的行動を妨げたり、習慣的な判断の白 紙のリアリズムに政治的想像力を縛り付けることで政治的想像力を抑えつけたりする。社会の最も一般的な文化的志向性も、最も現実的な「実用的」志向性も、 政治過程の適切なイメージを提供するにはもはや十分ではなくなったときに、イデオロギーが社会政治的な意味や態度の源泉として重要になり始める。 ある意味では、この主張はイデオロギーが緊張への反応であるという別の言い方でしかない。しかし、今や私たちは文化的、社会的、心理的な緊張も含めるよう になった。方向感覚を失うことが、最も直接的にイデオロギー的活動を生み出す。使用可能なモデルがないために、自分が置かれている市民としての権利と責任 の全体像を理解できないことである。分化した政治体制(あるいは、そのような政治体制内のより大きな内部分化)の発展は、深刻な社会的混乱と心理的緊張を 伴う可能性があり、実際、そうなることが多い。しかし、それはまた、確立された政治秩序のイメージが関連性を失って消え去ったり、信用を失ったりすること によって、概念上の混乱ももたらす。フランス革命が少なくとも当時においては、人類史上において「進歩的」および「反動的」な過激思想の最大の温床となっ た理由は、個人的な不安や社会的不均衡がそれ以前の多くの時代よりも深くて広範にわたっていたからではない。それらは十分に深くて広範であったが、 政治生活の中心的な組織原則である王の神聖な権利が破壊されたからである。43 体系的な(政治的、道徳的、あるいは経済的な)イデオロギーが台頭する舞台が整うのは、社会心理的な緊張と、その緊張を理解するための文化的資源の欠如が 重なり合い、それぞれが他方を悪化させるという状況である。 そして、それは、さもなければ理解不能な社会的状況に意味を持たせ、その状況の中で目的を持って行動できるように解釈しようとするイデオロギーの試みであ る。このことが、イデオロギーの高度に比喩的な性質と、いったん受け入れられると強く信じられるようになる理由の両方を説明している。比喩が言語の意味の 範囲を広げ、文字通りに表現できない、あるいは少なくともまだ表現できない意味を表現することを可能にするように、イデオロギーにおける文字通りの意味の 正面衝突(皮肉、誇張、誇張された対立概念)は、政治生活の変化によって生み出される、未知の国への旅のような無数の「見知らぬ何か」を照らし合わせるた めの、新しい象徴的な枠組みを提供する。イデオロギーが何であれ、すなわち、認められていない恐怖の投影、下心のための偽装、集団の連帯を示すフェティッ クな表現などであるが、それらは最も明確に、問題のある社会の現実の地図であり、集団的良心を生み出すための母体である。特定のケースにおいて、その地図 が正確であるか、あるいはその良心が信頼に足るものであるかは、ナチズムとシオニズム、マッカーシーとチャーチルの国民主義、人種隔離政策の擁護者と反対 派など、それぞれに異なる問題であり、同じ答えを出すことは難しい。 |
| VI. Though ideological ferment is, of course, widespread in modern society, perhaps its most prominent locus at the moment lies in the new (or renewed) states of Asia, Africa, and some parts of Latin America, for it is in these states, Communist or not, that the initial steps away from a traditional politics of piety and proverb are just now being taken. The attainment of independence, the overthrow of established ruling classes, the popularization of legitimacy, the rationalization of public administration, the rise of modern elites, the spread of literacy and mass communications, and the propulsion willy-nilly of inexperienced governments into the midst of a precarious international order that even its older participants do not very well understand all make for a pervasive sense of disorientation, a disorientation in whose face received images of authority, responsibility, and civic purpose seem radically inadett,: quate. The search for a new symbolic framework in terms of which to formulate, think about, and react to political problems, whether in the form of nationalism, Marxism, liberalism, populism, racism, Caesarism, ecclesiasticism, or some variety of reconstructed traditionalism (or, most commonly, a confused melange of several of these) is therefore tremendously intense. Intense--but indeterminate. For the most part, the new states are still groping for usable political concepts, not yet grasping them; and the outcome in almost every case, at least in every non-Communist case, is uncertain not merely in the sense that the outcome of any historical process is uncertain but in the sense that even a broad and general assessment of overall direction is extremely difficult to make. Intellectually, everything is in motion, and the words of that extravagant poet in politics, Lamartine, written of nineteenth century France, apply to the new states with perhaps even greater appropriateness than they did to the dying July Monarchy: These times are times of chaos; opinions are a scramble; parties are a jumble; the language of new ideas has not been created; nothing is more difficult than to give a good definition of oneself in religion, in philosophy, in politics. One feels, one knows, one lives, and at need. one dies for one's cause, but one cannot name it. It is the problem of this time to classify things and men.... The world has jumbled its catalog.44 This observation is no truer anywhere in the world right now [1964] than it is in Indonesia, where the whole political process is mired in a slough of ideological symbols, each attempting and so far each failing to unjumble the Republic's catalogue, to name its cause, and to give point and purpose to its polity. It is a country of false starts and frantic revisions, of a desperate search for a political order whose image, like a mi rage, recedes more rapidly the more eagerly it is approached The salv ing slogan amid all this frustration is, "The Revolution Is Unfinishedt And so, indeed, it is. But only because no one knows, not even those who cry most loudly that they do, precisely how to go about the job of finishing it.45 The most highly developed concepts of government in traditional Indonesia were those upon which the classic Hinduized states of the fourth to fifteenth centuries were built, concepts that persisted in somewhat revised and weakened form even after these states were first Islamicized and then largely replaced or overlaid by the Dutch colonial regime. And of these concepts the most important was what might be called the theory of the exemplary center, the notion that the capital city (or more accurately the king's palace) was at once a microcosm of the supernatural order--"an image of . . . the universe on a smaller scale"--and the material embodiment of political order.46 The capital was not merely the nucleus, the engine, or the pivot of the state; it was the state. In the Hindu period, the king's castle comprehended virtually the entire town. A squared-off "heavenly city" constructed according to the ideas of Indic metaphysics, it was more than a locus of power; it was a synoptic paradigm of the ontological shape of existence. At its center was the divine king (an incarnation of an Indian deity), his throne symbolizing Mount Meru, seat of the gods; the buildings, roads, city walls, and even, ceremonially, his wives and personal staff were deployed quadrangularly around him according to the directions of the four sacred winds. Not only the king himself but his ritual, his regalia, his court, and his castle were shot through with charismatic significance. The castle and the life of the castle were the quiddity of the kingdom, and he who (often after meditating in the wilderness to attain the appropriate spiritual status) captured the castle captured the whole empire, grasped the charisma of office, and displaced the no-longer-sacred king.47 The early polities were thus not so much solidary territorial units as loose congeries of villages oriented toward a common urban center, each such center competing with others for ascendency. Whatever degree of regional or, at moments, interregional hegemony prevailed depended, not on the systematic administrative organization of extensive territory under a single king, but on the varying abilities of kings to mobilize and apply effective striking forces with which to sack rival capitals, abilities that were believed to rest on essentially religious--that is, mystical--grounds. So far as the pattern was territorial at all, it consisted of a series of concentric circles of religio-military power spreading out around the various city-state capitals, as radio waves spread from a transmitter. The closer a village to a town, the greater the im pact, economically and culturally, of the court on that village. And, conversely, the greater the development of the court--priests, artisans, nobles, and king--the greater its authenticity as an epitome of cosmic order, its military strength, and the effective range of its circles of outward-spreading power. Spiritual excellence and political eminence were fused. Magical power and executive influence flowed in a single stream outward and downward from the king through the descending ranks of his staff and whatever lesser courts were subordinate to him, draining out finally into the spiritually and politically residual peasant mass. Theirs was a facsimile concept of political organization, one in which the reflection of the supernatural order microscopically mirrored in the life of the capital was in turn further and more faintly reflected in the countryside as a whole, producing a hierarchy of less and less faithful copies of an eternal, transcendent realm. In such a system, the administrative, military, and ceremonial organization of the court orders the world around it iconically by providing it with a tangible paragon.48 When Islam came, the Hindu political tradition was to some extent l weakened, especially in the coastal trade kingdoms surrounding the Java Sea. The court culture nevertheless persisted, although it was overlaid and interfused with Islamic symbols and ideas and set among an ethnically more differentiated urban mass, which looked with less awe on the classical order. The steady growth--especially on Java--of Dutch administrative control in the mid-nineteenth and early twentieth centuries constricted the tradition still further. But, since the lower levels of the bureaucracy continued to be manned almost entirely by Indonesians of the old upper classes, the tradition remained, even then, the matrix of supravillage political order. The Regency or the District orfice remained not merely the axis of the polity but the embodiment of it. a polity with respect to which most villagers were not so much actors as audience. It was this tradition with which the new elite of republican Indonesia was left after the revolution. That is not to say that the theory of the exemplary center persisted unchanged, drifting like some Platonic archetype through the eternity of Indonesian history, for (like the society as a whole) it evolved and developed, becoming ultimately perhaps more conventional and less religious in general temper. Nor does it mean that foreign ideas, from European parliamentarianism, from Marxism, from Islamic moralism, and so forth did not come to play an essential role in Indonesian political thought, for modern Indonesian nationalism is very far from being merely old wine in a new bottle. It is simply that, as yet, the conceptual transition from the classic image of a polity as a concentrated center of pomp and power, alternately providing a cynosure for popular awe and lashing out militarily at competing centers, to one of a polity as a systematically organized national community has, for all these changes and influences, still not been completed. Indeed, it has been arrested and to some extent reversed. This cultural failure is apparent from the growing, seemingly unquenchable ideological din that has engulfed Indonesian politics since the revolution. The most prominent attempt to construct, by means of a figurative extension of the classic tradition, an essentially metaphoric reworking of it, a new symbolic framework within which to give form and meaning to the emerging republican polity, was President Sukarno's famous Pantiasila concept, first set forth in a public speech toward the end of the Japanese occupation.49 Drawing on the Indic tradition of fixed sets of numbered precepts--the three jewels, the four sublime moods, the eightfold path, the twenty conditions of successful rule, and so forth--it consisted of five (pantja) principles (sila) that were intended to form the "sacred" ideological foundations of an independent Indonesia. Like all good constitutions, the Pantjasila was short, ambiguous, and Impeccably high-minded, the five points being "nationalism," "humanitarianism," "democracy," "social welfare," and (pluralistic) "monotheism." Finally, these modern concepts, set so nonchalantly in a medieval frame, were explicitly identified with an indigenous peasant concept, gotong rojong (literally, "the collective bearing of burdens"; figuratively, "the piety of all for the interests of all"), thus drawing together the "great tradition" of the exemplary state, the doctrines of contemporary nationalism, and the "little traditions" of the villages into one luminous image.50 The reasons why this ingenious device failed are many and complex, and only a few of them --like the strength in certain sectors of the popi ulation of Islamic concepts of political order, which are difficult to rect oncile with Sukarno's secularism --are themselves cultural. The Pantjaif sila, playing upon the microcosm-macrocosm conceit and upon the [traditional syncretism of Indonesian thought, was intended to contain within it the political interests of the Islamic and Christian, gentry and peasantry, nationalist and communist, commercial and agrarian, Jarvanese and "Outer Island" groups in Indonesia --to rework the old facsimile pattern into a modern constitutional structure in which these various tendencies would, each emphasizing one or another aspect of the doctrine, find a modus vivendi at each level of administration and party struggle. The attempt was not so totally ineffective or so intellectually fatuous as it has sometimes been painted. The cult of the Pantjasila (for that is what it literally became, complete with rites and commentaries) did provide for a while a flexible ideological context within which parliamentary institutions and democratic sentiments were being soundly, if gradually, forged at both local and national levels. But the combination of a deteriorating economic situation, a hopelessly pathological relationship with the former metropole, the rapid growth of a subversive (in principle) totalitarian party, a renascence of Islamic fundamentalism the inability (or unwillingness) of leaders with developed intellectual and technical skills to court mass support, and the economic illiteracy administrative incapacity, and personal failings of those who were able (and only too willing) to court such support soon brought the clash of factions to such a pitch that the whole pattern dissolved. By the time of the Constitutional Convention of 1957, the Pantjasila had changed from a language of consensus to a vocabulary of abuse, as each faction used it more to express its irreconcilable opposition to other factions than its underlying rules-of-the-game agreement with them, and the Convention ideological pluralism, and constitutional democracy collapsed in a single heap.51 What has replaced them is something very much like the old exemplary center pattern, only now on a self-consciously doctrinaire rather than an instinctive religion-and-convention basis and cast more in the idiom of egalitarianism and social progress than in that of hierarchy and patrician grandeur. On the one hand, there has been, under President Sukarno's famous theory of "guided democracy" and his call for the reintroduction of the revolutionary (that is, authoritarian) constitution of 1945, both an ideological homogenization (in which discordant streams of thought--notably those of Moslem modernism and democratic socialism-- have simply been suppressed as illegitimate) and an accelerated pace of flamboyant symbolmongering, as though, the effort to make an unfamiliar form of government work having misfired, a desperate attempt to breathe new life into a familiar one was being launched. On the other hand, the growth of the political role of the army, not so much as an executive or administrative body as a backstop enforcement agency with veto power over the whole range of politically relevant institutions, from the presidency and the civil service to the parties and the press, has provided the other--the minatory--half of the traditional picture. Like the Pantjasila before it, the revised (or revivified) approach was introduced by Sukarno in a major speech--"The Rediscovery of Our Revolution"--given on Independence Day (August 17) in 1959 a speech that he later decreed, along with the expository notes on it prepared by a body of personal attendants known as The Supreme Advisory Council, to be the "Political Manifesto of the Republic": There thus came into existence a catechism on the basis, aims and duties of the Indonesian revolution; the social forces of the Indonesian revolution, its nature. future and enemies; and its general program, covering the political, economics social, mental, cultural, and security fields. Early in 1960 the central message of the celebrated speech was stated as consisting of five ideas --the 1945 constitution, Socialism a la Indonesia, Guided Democracy, Guided Economy, and Indonesian Personality--and the first letters of these five phrases were put together to make the acronym USDEK. With 'Political Manifesto' becoming "Manipol," the new creed became known as "Manipol-USDEK."52 And, as the Pantjasila before it, the ManipolUSDEK image of political order found a ready response in a population for whom opinions have indeed become a scramble, parties a jumble, the times a chaos: Many were attracted by the idea that what Indonesia needed above all was men with the right state of mind, the right spirit, the true patriotic dedication. "Returning to our own national personality" was attractive to many who wanted to withdraw from the challenges of modernity, and also to those who wanted to believe in the current political leadership but were aware of its failures to modernize as fast as such countries as India and Malaya. And for members of some Indonesian communities, notably for many [lndic-mindedl Javanese, there was real meaning in the various complex schemes which the President presented in elaboration of Manipol-USDEK, explaining the peculiar signifieanee and tasks of the current stage of history. [But] perhaps the most important appeal of Manipol-USDEK, however, lay in the simple fact that it promised to give men a pegangan--somethmg to which to hold fast. They were attracted not so much by the content of this pegangan as by the fact that the President had offered one at a time when the lack of a sense of purpose was sorely felt. Values and cognitive patterns being in flux and in conflict, men looked eagerly for dogmatic and schematic formulations of the political good.53 While the President and his entourage concern themselves almost entirely with the "creation and recreation of mystique," the army concerns itself mainly with combating the numerous protests, plots, mutinies, and rebellions that occur when that mystique fails to achieve its hoped-for effect and when rival claims to leadership arise. Although involved in some aspects of the civil service, in the managing o, the confiscated Dutch enterprises, and even in the (nonparliamentary) cabinet, the army has not been able to take up, for lack of training, internal unity, or sense of direction, the administrative, planning, and organizational tasks of the government in any detail or with any effectiveness. The result is that these tasks are either not performed or very inadequately performed, and the supralocal polity, the national state, shrinks more and more to the limits of its traditional domain, the capital city--Djakarta--plus a number of semi-independent tributary cities and towns held to a minimal loyalty by the threat of centrally applied force. That this attempt to revive the politics of the exemplary court will long survive is rather doubtful. It is already being severely strained by its incapacity to cope with the technical and administrative problems involved in the government of a modern state. Far from arresting Indonesia's decline into what Sukarno has called "the abyss of annihilation," the retreat from the hesitant, admittedly hectic and awkwardly functioning parliamentarianism of the Pantjasila period to the Manipol-USDEK alliance between a charismatic president and a watchdog army has probably accelerated it. But what will succeed this ideological framework when, as seems certain, it too dissolves, or from where a conception of political order more adequate to Indonesia's contemporary needs and ambitions will come, if it does come, is impossible to say. Not that Indonesia's problems are purely or even primarily ideological and that they will-- as all too many Indonesians already think--melt away before a political change of heart. The disorder is more general, and the failure to create a conceptual framework in terms of which to shape a modern polity is in great part itself a reflection of the tremendous social and psychological strains that the country and its population are undergoing. Things do not merely seem jumbled--they are jumbled, and it will take more than theory to unjumble them. It will take administrative skill, technical knowledge, personal courage and resolution, endless patience and tolerance, enormous selfsacrifice, a virtlially incorruptible public conscience, and a very great deal of sheer (and unlikely) good luck in the most material sense of the word. Ideological formulation, no matter how elegant, can substitute for none of these elements; and, in fact, in their absence, it degenerates, as it has in Indonesia, into a smokescreen for failure, a diversion to stave off despair, a mask to conceal reality rather than a portrait to reveal it. With a tremendous population problem; extraordinary ethnic, geographical, and regional diversity; a moribund economy; a severe lack of trained personnel, popular poverty of the bitterest sort; and pervasive, implacable social discontent, Indonesia's social problems seem virtually insoluble even without the ideological pandemonium. The abyss into which Ir. Sukarno claims to have looked is a real one. Yet, at the same time, that Indonesia (or, I should imagine, any new nation) can find her way through this forest of problems without any ideological guidance at all seems impossible.55 The motivation to seek (and, even more important, to use) technical skill and knowledge, the emotional resilience to support the necessary patience and resolution, and the moral strength to self-sacrifice and incorruptibility must come from somewhere, from some vision of public purpose anchored in a compelling image of social reality. That all these qualities may not be present, that the present drift to revivalistic irrationalism and unbridled fantasy may continue; that the next ideological phase may be even further from the ideals for which the revolution was ostensibly fought than is the present one; that Indonesia may continue to be, as Bagehot called France, the scene of political experiments from which others profit much but she herself very little; or that the ultimate outcome may be viciously totalitarian and wildly zealotic is all very true. But whichever way events move, the determining forces will not be wholly sociological or psychological but partly cultural--that is, conceptual. To forge a theoretical framework adequate to the analysis of such three-dimensional processes is the task of the scientific study of ideology--a task but barely begun. |
VI. もちろん、現代社会では思想的な混乱が蔓延しているが、おそらく現在最も顕著なのはアジア、アフリカ、ラテンアメリカの一部の地域における新たな(あるい は再興された)国家である。これらの国家では、共産主義であるか否かに関わらず、伝統的な信心深い政治から離れるための第一歩が今まさに踏み出されようと している。独立の達成、既得権益層の打倒、正統性の一般化、公共行政の合理化、近代的エリートの台頭、読み書き能力とマス・コミュニケーションの普及、そ して、経験不足の政府が否応なく その古い参加者たちでさえもよく理解していない不安定な国際秩序の真っ只中に、経験の浅い政府を否応なく突き進ませることは、すべてにわたって広範な方向 感覚の喪失感を生み出す。その方向感覚の喪失感に直面すると、権威、責任、市民としての目的といった既成概念は根本的に不適切であるように思える。政治問 題を定義し、考え、反応するための新たな象徴的枠組みを求める動きは、ナショナリズム、マルクス主義、自由主義、ポピュリズム、人種差別主義、シーザー主 義、教会主義、あるいは再構築された伝統主義(あるいは、最も一般的な、これらのいくつかの混乱した混合)の形をとるかどうかに関わらず、それゆえに非常 に激しいものとなっている。 激しいが、不確定である。ほとんどの場合、新生国家はまだ使える政治的概念を模索している段階であり、それを把握しているわけではない。そして、ほぼすべ てのケースにおいて、少なくとも非共産主義のケースにおいては、結果が不確実であるという意味は、歴史的プロセスにおける結果が不確実であるという意味に とどまらず、全体的な方向性に関する広範かつ一般的な評価でさえも極めて困難であるという意味である。知的には、すべてが流動的であり、政治の世界の贅沢 な詩人、ラマルティーヌが19世紀のフランスについて書いた言葉は、滅びゆく七月王政について述べたものよりも、おそらく新しい国家によりふさわしく当て はまる。 「この時代は混沌の時代である。意見は錯綜し、党派は入り乱れ、新しい思想の言語はまだ生まれていない。宗教、哲学、政治において、自己を適切に定義する ことは何よりも難しい。人は感じ、知り、生き、必要に応じて死ぬ。しかし、その大義を名指すことはできない。物事や人間を分類することが、この時代の課題 である。世界は、そのカタログを混乱させた。 この観察は、1964年現在、世界中のどこよりもインドネシアで真実である。インドネシアでは、政治プロセス全体がイデオロギーの記号の泥沼にはまり込ん でおり、それぞれが共和国のカタログを解読しようと試み、そして今のところは失敗している。その原因を明らかにし、政治体制に目的と意義を与えるために。 それは、誤ったスタートと必死の修正、そして、近づけば近づくほど急速に遠ざかっていくイメージのような政治的秩序を必死に探し求める国である。こうした フラストレーションのなかで、唯一の救いは「革命は未完成」というスローガンである。そして、まさにその通りである。しかし、誰もがそれを知っているわけ ではない。最も大きな声で「知っている」と叫ぶ人々でさえ、それを完成させるための具体的な方法を知っているわけではないのだ。 インドネシアの伝統的な政府の概念で最も高度に発展したものは、4世紀から15世紀にかけての古典的なヒンドゥー教化された国家が築かれたものであり、こ れらの国家が最初にイスラム化され、その後、オランダの植民地体制にほぼ置き換えられ、あるいは覆い隠された後も、多少修正され弱体化した形で存続した概 念である。そして、これらの概念の中で最も重要なものは、模範的中心地論と呼ばれるかもしれないものであり、首都(より正確には王宮)は、超自然的秩序の 小宇宙であると同時に、「より小規模な宇宙のイメージ」であり、政治的秩序の物質的な体現であるという考え方である。46 首都は単に国家の中核、原動力、あるいは枢軸というだけではなく、国家そのものであった。 ヒンドゥー教の時代には、王の城は事実上、町全体を包含していた。 インド哲学の考え方に基づいて建設された正方形の「天上の都市」は、単なる権力の拠点という以上の存在であった。それは、存在の形相の全体論的パラダイム であった。その中心には神聖な王(インドの神の化身)がおり、その王座は神々が住むメルー山の象徴であった。建物、道路、城壁、そして儀式においては妻や 側近までもが、4つの神聖な風の方向に従って王の周囲に四角形に配置されていた。王自身だけでなく、その儀式、王権の象徴、宮廷、城には、カリスマ的な意 味が浸透していた。城と城での生活は王国の真髄であり、城を占領した者は(しばしば荒野で瞑想して適切な精神状態に達した後で)帝国全体を占領し、職務の カリスマ性を把握し、もはや神聖ではない王を追い落とした。 初期の政治体制は、連帯した領土単位というよりも、共通の都市中心部に向かう緩やかな村落の集合体であり、各都市は優位性を求めて互いに競い合っていた。 地域的な、あるいは時には地域間の覇権がどの程度優勢であったかは、単一の王の下で広大な領土を体系的に管理する組織の有無ではなく、ライバルの首都を略 奪する効果的な攻撃部隊を動員し、適用する王の能力の差によるものであった。このパターンが領土的なものである限り、それは、送信機から広がる電波のよう に、さまざまな都市国家の首都の周囲に広がる宗教的・軍事的権力の同心円の連なりから成っていた。都市に近ければ近いほど、その都市の宮廷がその村に与え る経済的・文化的な影響は大きかった。そして逆に、宮廷(司祭、職人、貴族、王)が発展すればするほど、宇宙の秩序の縮図としての真実味が増し、軍事力も 増し、外に向かって広がる権力の輪の有効範囲も広がった。精神的な卓越性と政治的な高潔さが融合していた。魔法の力と行政上の影響力は、王からその部下た ち、そして王に従属するその他の小規模な宮廷へと、単一の流れとなって外側に向かって下へと流れていき、最終的には精神面でも政治面でも農民の集団へと流 れ込んでいく。彼らの政治組織の概念は、超自然的秩序の反映が首都の生活に顕微鏡的に映し出され、それがさらに田舎全体に、よりぼんやりと反映されるとい うもので、永遠で超越的な領域の忠実度の低いコピーのヒエラルキーを作り出していた。このような体制では、宮廷の行政、軍事、儀式の組織が、有形の模範を 提供することで、象徴的に周囲の世界を支配していた。 イスラム教が到来した際、ヒンドゥーの政治的伝統は、特にジャワ海周辺の沿岸貿易王国において、ある程度弱体化した。しかし、宮廷文化は依然として根強く 残った。ただし、イスラムのシンボルや思想と重なり合い、融合し、民族的により分化した都市圏に位置づけられ、古典的な秩序をそれほど畏敬の念を持って見 なくなっていた。19世紀半ばから20世紀初頭にかけて、特にジャワ島におけるオランダの行政支配が着実に拡大したことで、伝統はさらに狭められた。しか し、官僚機構の下層部は依然としてほぼすべてが旧上流階級のインドネシア人によって占められていたため、その伝統は存続し、村落共同体政治秩序の母体と なった。 摂政や郡役所は、単に政治体制の軸であるだけでなく、その体現でもあった。 ほとんどの村民は、その政治体制において、俳優というよりも観客であった。 革命後、インドネシア共和国の新しいエリート層が受け継いだのは、この伝統であった。模範的中心という理論がインドネシアの歴史の永遠の中で、プラトニッ クな原型のように変化することなく漂い続けたというわけではない。なぜなら、それは(社会全体と同様に)進化し、発展し、最終的にはおそらくより一般的 で、全体的な傾向としてはより宗教色が薄くなったからである。また、ヨーロッパの議会制、マルクス主義、イスラム道徳主義など、外国の思想がインドネシア の政治思想において重要な役割を果たさなかったというわけではない。なぜなら、現代のインドネシア民族主義は、単に古い考え方が新しい瓶に入れられただけ というものではないからだ。それは単に、威光と権力の集中した中心として、民衆の畏敬の的となり、競合する中心に対して軍事的に攻撃を仕掛ける国家という 古典的な国家像から、体系的に組織された国民共同体としての国家像への概念の転換が、これらの変化や影響にもかかわらず、まだ完了していないということに 過ぎない。実際、この転換は阻止され、ある程度は逆行している。 この文化的な失敗は、革命以来インドネシアの政治を覆っている、消えることのないように見えるイデオロギーの騒乱の拡大から明らかである。古典的伝統の比 喩的延長、本質的に比喩的な再解釈、そして、新たに登場しつつある共和制政治に形と意味を与えるための象徴的な枠組みを構築しようとする最も顕著な試み は、スカルノ大統領の有名なパンティアシラ概念であり、それは日本占領の終わり頃に初めて公の演説で発表された。 49 インドの伝統である、番号付きの戒律の固定セット(三宝、四つの崇高な気分、八正道、20の統治成功条件など)を参考に、独立したインドネシアの「神聖 な」イデオロギーの基礎を形成することを意図した5つの(pantja)原則(sila)から構成されていた。優れた憲法の例に漏れず、パンチャシラは簡 潔で曖昧なものであり、非の打ちどころのないほど高邁なものであった。5つの原則は、「ナショナリズム」、「人道主義」、「民主主義」、「社会福祉」、そ して(多元的な)「一神教」であった。最後に、これらの近代的概念は、中世の枠組みに淡々と据えられ、土着の農民概念である「ゴントン・ロジョン」(文字 通りには「集団的な負担」、比喩的には「すべての人々の利益のためのすべての人々の信心」)と明確に同一視され、模範的な国家の「偉大な伝統」、現代ナ ショナリズムの教義、そして村々の「小さな伝統」を1つの輝かしいイメージへとまとめ上げた。 この巧妙な手法が失敗した理由は数多く複雑であるが、そのうちのいくつか、例えばイスラムの政治秩序概念が国民の一部に根強く残っていることなど、その理 由の一部は文化的なものである。パンチャシラは、小宇宙と大宇宙という概念と、インドネシアの伝統的なシンクレティズム(折衷主義)を基盤としており、イ スラム教徒とキリスト教徒、地主と農民、民族主義者と共産主義者、商業と農業 インドネシアのジャルヴァ人や「外島」グループなど、さまざまな傾向を持つ人々――教義の1つまたは別の側面を強調する人々――が、行政や政党間の闘争の 各レベルにおいて、互いに妥協点を見出すことができるような、現代的な憲法構造に古い模造パターンを再構築することを目的としていた。この試みは、時に描 かれるほど、まったく効果のないものでも、知的に愚かなものでもなかった。パンチャシラ(文字通り、儀式や解説を伴うものとなった)の崇拝は、議会制度と 民主主義の感情が、地方と国家の両レベルで、健全に、しかし徐々にではあるが、形成されていく柔軟なイデオロギー的背景を、しばらくの間は提供した。しか し、経済状況の悪化、旧宗主国との絶望的な病的な関係、急成長する(原則的には)破壊的な全体主義政党、イスラム原理主義の復活、 知的・技術的能力を備えた指導者たちが大衆の支持を取り付けることができなかった(あるいは、その意思がなかった)こと、そして、そのような支持を取り付 けることができた(そして、その意思も十分にあった)人々の経済的な無知、行政能力の欠如、個人的な欠点が、すぐに派閥間の対立を極限まで高め、そのパ ターン全体が崩壊した。1957年の憲法制定会議の頃には、パンチャシラは合意の言語から罵りの言葉へと変化していた。各派閥がパンチャシラを、他の派閥 との妥協できない対立を表現するために用いることが多くなり、ゲームのルールや、憲法制定会議の理念の多元主義、立憲民主主義は、一挙に瓦解したのであ る。 それに取って代わったものは、かつての模範的な中心パターンに非常に似たもので、本能的な宗教と慣例に基づくものではなく、自覚的に教義主義的なものであ り、階層と貴族的な壮大さよりも平等主義と社会進歩のイディオムに傾倒している。一方では、スカルノ大統領の有名な「誘導民主主義」理論と、1945年の 革命的(すなわち権威主義的)憲法の再導入を求める呼びかけの下、イデオロギーの均質化(不調和な思想潮流、特に イスラム近代主義や民主的社会主義など)が単に非合法として弾圧された)と、きらびやかな象徴主義の加速化の両方が見られた。それは、見慣れない政治形態 を機能させるための努力が失敗したため、見慣れた政治形態に新しい息吹を吹き込もうとする絶望的な試みが開始されたかのようであった。一方、軍の政治的役 割の拡大は、大統領や公務員から政党や報道機関に至るまで、政治に関連するあらゆる機関に対する拒否権を持つ強力な執行機関として、行政機関や行政組織と いうよりも、脅威的なもう一つの側面を伝統的な図式に与えた。 パンチャシラ以前と同様に、この修正(または復活)されたアプローチは、1959年の独立記念日(8月17日)にスカルノが「我々の革命の再発見」と題し た主要演説で導入した。この演説は、後にスカルノが「共和国の政治宣言」と定めたもので、 こうして、インドネシア革命の基礎、目的、義務に関するカテキズムが誕生した。インドネシア革命の社会的勢力、その性質、未来、敵。そして、政治、経済、 社会、精神、文化、安全保障の分野をカバーするその一般的なプログラム。1960年初頭、この有名な演説の主要なメッセージは、1945年憲法、インドネ シア流社会主義、誘導民主主義、誘導経済、インドネシア的個性の5つの理念から構成されると述べられ、この5つのフレーズの頭文字を組み合わせた USDEKという頭字語が作られた。「政治宣言」が「マニポル」となったことで、この新しい信条は「マニポル-USDEK」として知られるようになった。 そして、パンチャシラがそうであったように、政治秩序に関するマニポル・USDEKのイメージは、意見がまさに乱立し、政党がごちゃ混ぜになり、時代が混 沌としていた人々から、すぐに反応を得た。 インドネシアが何よりも必要としているのは、正しい精神状態と正しい精神、真の愛国心を持つ人々であるという考えに多くの人が惹きつけられた。「自らの国 民性を再認識する」という主張は、近代化の課題から撤退したいと考える多くの人々にとって魅力的であり、また、現在の政治指導者を信じたいが、インドやマ ラヤなどの国々よりも近代化が遅れていることを認識している人々にとっても魅力的であった。そして、インドネシアのいくつかのコミュニティのメンバー、特 に多くのインドネシア系ジャワ人にとっては、大統領がマニポール・USDEKを詳しく説明した際に提示した、さまざまな複雑な計画には、歴史の現段階にお ける独特な意味と課題を説明する真の意義があった。しかし、マニポール・USDEKの最も重要な訴えは、おそらく、人々にペガンガン(揺るぎない拠り所と なるもの)を与えるという単純な事実にある。人々は、このペガンガンの内容というよりも、目的意識の欠如がひどく感じられていた時に大統領がそれを提示し たという事実により強く惹きつけられた。価値観や認識パターンが流動的で対立している中、人々は政治的な善の教条的な図式化を熱心に求めた。 大統領と側近が「神秘性の創造と再生」にほぼ専念する一方で、軍は主に、神秘性が期待された効果を上げられず、指導権を巡る対立が生じた際に発生する、数 多くの抗議、陰謀、反乱、暴動の鎮圧に専念した。 軍は、徴用されたオランダ企業や(非議会制の)内閣の運営など、行政の一部に関与していたが、訓練不足、内部の結束、方向感覚の欠如により、政府の行政、 計画、組織に関する詳細かつ効果的な業務を遂行することができなかった。その結果、これらの任務は遂行されないか、非常に不十分な形で遂行されることとな り、超国家的統治機構である国民国家は、その伝統的領域である首都ジャカルタと、中央政府による武力行使の脅威によって最低限の忠誠心を維持しているいく つかの準独立的な従属都市や町という限界に、ますます縮小していくことになる。 模範的な宮廷政治を復活させようとするこの試みが長く生き残ることは、かなり疑わしい。近代国家の統治に関わる技術的および行政的な問題に対処できないと いう理由で、すでに大きな負担となっている。スカルノが「消滅の淵」と呼んだものへのインドネシアの衰退を食い止めるどころか、パンチャシラ時代の躊躇 し、確かに慌ただしくぎこちなく機能していた議会制から、カリスマ的な大統領と監視役の軍隊によるマニポル・USDEK同盟への後退は、おそらくその衰退 を加速させた。しかし、このイデオロギー的枠組みが崩壊した際、それに取って代わるものは何なのか、あるいは、インドネシアの現代のニーズと野望により適 した政治秩序の概念はどこから生まれるのか、もし生まれるとしても、それは不可能である。 インドネシアの問題が純粋に、あるいは主としてイデオロギー的なものであり、政治的な意識改革が起こる前に、すでに多くのインドネシア人が考えているよう に、それらの問題が解決するわけではない。この混乱はより全般的なものであり、近代的な政治体制を形作るための概念的枠組みを構築できないことは、この国 と国民が経験している途方もない社会的・心理的緊張の反映である。物事は単に混乱しているように見えるだけではなく、実際に混乱している。そして、それを 整理するには理論以上のものが必要である。行政手腕、技術的知識、個人的な勇気と決断力、果てしない忍耐と寛容、多大な自己犠牲、事実上汚職とは無縁の公 共の良心、そして、文字通り非常に多くの幸運が必要である。いかに洗練されたものであっても、イデオロギーの定式化はこれらの要素のどれにも代用できな い。実際、これらの要素が欠如している場合、インドネシアで起こったように、失敗の煙幕、絶望を先延ばしにするための陽動作戦、現実を覆い隠す仮面とな り、それを明らかにする肖像画とはならない。途方もない人口問題、並外れた民族、地理、地域的多様性、死にかけた経済、深刻な熟練労働者の不足、最も苦し い種類の貧困、そして広範囲に蔓延する容赦ない社会的不満により、イデオロギーの混乱がなくても、インドネシアの社会問題は事実上、解決不可能であるよう に思われる。 スカルノ氏が覗き見たと主張する深淵は、現実のものである。 しかし同時に、インドネシア(あるいは、私が想像するに、いかなる新生国家も)がイデオロギー的な指針をまったく持たずに、この問題の森を切り抜けられる とは考えられない。55 技術的な技能や知識を求め(さらに重要なのは、それらを 技術的スキルや知識を求め(さらに重要なのは、それらを実際に活用する)こと、必要な忍耐と決意を支える感情的な回復力、そして自己犠牲と清廉潔白さとい う道徳的強さは、どこからか、つまり、社会の現実を説得力のあるイメージで表現した公共目的のビジョンから生まれるに違いない。これらの資質がすべて揃っ ているわけではないかもしれない。現在の復興主義的で非合理的な、そして抑制のきかない空想主義的な流れが続くかもしれない。次のイデオロギーの段階は、 革命が表向きには戦われた理想から、現在よりもさらに遠いものになるかもしれない 、インドネシアが、ベイゴットがフランスを評したように、政治的実験の場であり続け、そこから他国は多くの利益を得るが、インドネシア自身はほとんど利益 を得られない、あるいは、最終的な結果が、悪辣な全体主義と狂信的な熱狂に陥る可能性がある、という可能性はすべて非常に高い。しかし、いずれの方向に事 態が展開しようとも、決定要因は完全に社会学的または心理学的というわけではなく、部分的に文化的、つまり概念的なものとなるだろう。このような三次元的 なプロセスを分析するのにふさわしい理論的枠組みを構築することが、イデオロギーの科学的調査の課題である。しかし、その課題はまだ始まったばかりであ る。 |
| VII. Critical and imaginative works are answer to questions posed by the situation in which they arose. They are not merely answers, they are strategicanswers, styalized answers. For there is a difference in style or strategy, if one says "yes" in tonalities that imply "thank God!" or in toanlities that imply "alas!" So I should propose an initial working distinction between "strategies" and "situations" whereby we think of . . . any work of critical or imaginative cast . . . as the adopting of various strategies for the encompassing of situations. These startegies size up the situations, name their structure and outstanding ingredients, and name them in a way that contains an attitude toward them. This point of view dies not, by any means, vow us to personal or historical subjectivism. The situations are real; the strategies for handling them have public content; in so far as situations overlap from individual to individual, or from one historical period to another, the strategies possess universal relevance. Kenneth Burke, The Philosophy of Literary Form As both science and ideology are critical and imaginitive "works" (that is symbolic structures), an objective formulation both of the marked differences between them and of the nature of their relationship to one another seems more likely to be achieved by proceeding from such a concept of stylistic strategies than from a nervous concern with comparative epistomological or axiological status of the two forms of thought. No more than scientific studies of religion ought to begin with unneccessary questions about the legitimacy of the substantive claims of such questions. The best way to deal with Mannheim's, as with any true paradox, is to circumvent it by reformulating one's theoretical approach so as to avoid setting off yet once more down the well-worn path of argument that led to it in the first place. The differentiae of science and ideology as cultural systems are to be sought in the sorts of symbolic strategy for encompassing situations that they respectively represent. Science names the structure of situations in such a way that the attitude contained toward them is one of disinterestedness. Its style is restrained, spare, resolutely analytic: by shunning the semantic devices that most effectively formulate moral sentiment, it seeks to maximize intellectual clarity. But ideology names the structure of situations in such a way that the attitude contained toward them IS one of commitment. Its style is ornate, vivid, deliberately suggestive: by objectifying moral sentiment through the same devices that science shuns, it seeks to motivate action. Both are concerned with the definition of a problematic situation and are responses to a felt lack of needed information. But the information needed is quite different, even in cases where the situation is the same. An ideologist is no more a poor social scientist than a social scientist is a poor ideologist. The two are--or at least they ought to be--in quite different lines of work, lines so different that little is gained and much obscured by measuring the activities of the one against the aims of the other.56 Where science is the diagnostic, the critical, dimension of culture, ideology is the justificatory, the apologetic one--it refers "to that part of culture which is actively concerned with the establishment and defense of patterns of belief and value." 57 That there is natural tendency for the two to clash, particularly when they are directed to the interpretation of the same range of situations, is thus clear; but that the clash is j inevitable and that the findings of (social) science necessarily will undermine the validity of the beliefs and values that ideology has chosen to defend and propagate seem most dubious assumptions. An attitude at once critical and apologetic toward the same situation is no intrinsic contradiction in terms (however often it may in fact turn out to be an empirical one) but a sign of a certain level of intellectual sophistication. One remembers the story, probably ben trovato, to the effect that when Churchill had finished his famous rally of isolated England, "We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills . . . ," he turned to an aide and whispered, "and we shall hit them over the head with soda-water bottles, because we haven't any guns." The quality of social rhetoric in ideology is thus not proof that the vision of sociopsychological reality upon which it is based is false and that it draws its persuasive power from any discrepancy between what is believed and what can, now or someday, be established as scientifically correct. That it may indeed lose touch with reality in an orgy of autistic fantasy--even that, in situations where it is left uncriticized by either a free science or competing ideologies well-rooted in the general social structure, it has a very strong tendency to do so --is all too apparent. But however interesting pathologies are for clarifying normal functioning (and however common they may be empirically), they are misleading as prototypes of it. Although fortunately it never had to be tested, it seems most likely that the British would have indeed fought on the beaches, landing grounds, streets, and hills--with soda-water bottles too, if it came to that --for Churchill formulated accurately the mood of his countrymen and, formulating it, mobilized it by making it a public possession, a social fact, rather than a set of disconnected, unrealized private emotions. Even morally loathsome ideological expressions may still catch most acutely the mood of a people or a group. Hitler was not distorting the German conscience when he rendered his countrymen's demonic self-hatred in the tropological figure of the magically corrupting Jew; he was merely objectifying it-- transforming a prevalent personal neurosis into a powerful social force. But though science and ideology are different enterprises, they are not unrelated ones. Ideologies do make empirical claims about the condition and direction of society, which it is the business of science (and, where scientific knowledge is lacking, common sense) to assess. The social function of science vis-a-vis ideologies is first to understand them--what they are, how they work, what gives rise to them--and second to criticize them, to force them to come to terms with (but not necessarily to surrender to) reality. The existence of a vital tradition of scientific analysis of social issues is one of the most effective guarantees against ideological extremism, for it provides an incomparably reliable source of positive knowledge for the political imagination to work with and to honor. It is not the only such check. The existence, as mentioned, of competing ideologies carried by other powerful groups in the society is at least as important; as is a liberal political system in which dreams of total rower are obvious fantasies; as are stable social conditions in which conventional expectations are not continually frustrated and conventional Ideas notradically incompetent. But, committed with a quiet intransigence to a vision of its own, it is perhaps the most indomitable. |
VII. 批判的かつ想像力に富んだ作品は、それが生じた状況によって提起された問いに対する答えである。それらは単なる答えではなく、戦略的な答えであり、定型的 な答えである。なぜなら、スタイルや戦略には違いがあるからだ。「神に感謝!」という意味合いを持つトーンで「イエス」と言う場合と、「残念!」という意 味合いを持つトーンで「イエス」と言う場合では、 そこで私は、「戦略」と「状況」の間に、当初の作業上の区別を提案したい。すなわち、私たちが考えるあらゆる批判的または想像的な作品は、状況を包括する ためのさまざまな戦略を採用したものとしてである。これらの戦略は状況を評価し、その構造と顕著な要素を特定し、それらに対する態度を含んだ形でそれらを 特定する。 この視点は、決して個人的または歴史的な主観主義を誓うものではない。状況は現実であり、それらに対処するための戦略は公共的な内容を持っている。状況が 個人から個人へ、またはある歴史的時代から別の時代へと重複する限り、戦略は普遍的な関連性を持つ。 ケネス・バーク著『文学形式の哲学 科学とイデオロギーは、どちらも批判的かつ想像力に富んだ「作品」(すなわち象徴構造)であるため、両者の顕著な相違点と相互関係の本質を客観的に定式化 するには、2つの思考形態の比較認識論的または価値論的地位に対する神経質な懸念よりも、文体戦略の概念から出発する方がより実現可能性が高いと思われ る。宗教に関する科学的調査は、そのような質問の実質的な主張の正当性に関する不必要な問いから始めるべきではない。マンハイムのパラドックスに対処する 最善の方法は、他の真のパラドックスと同様に、そもそもそのパラドックスにつながった議論の陳腐な道筋を再びたどることのないよう、理論的アプローチを再 構築して回避することである。 科学とイデオロギーという文化システムの違いは、それぞれが表象する状況を包括する象徴的な戦略の種類に求められる。科学は、状況の構造を、それらに対す る態度が利害関係のないものであるように名付ける。そのスタイルは抑制的で簡潔、断固として分析的である。道徳的感情を最も効果的に形成する意味論的装置 を避けることで、知的明瞭性を最大限に高めることを目指している。しかし、イデオロギーは状況の構造を、それらに対する態度がコミットメントの1つである ように名付ける。そのスタイルは、装飾的で生き生きとしており、意図的に暗示的である。科学が忌避するのと同じ手段によって道徳的感情を客観化すること で、行動を促そうとする。両者は問題状況の定義に関心があり、必要な情報の欠如を感じたことへの反応である。しかし、必要な情報は状況が同じ場合でも、 まったく異なる。イデオローグが貧弱な社会科学者であることはなく、社会科学者が貧弱なイデオローグであることもない。この2つは、少なくともそうあるべ きであるが、まったく異なる分野の仕事であり、一方の活動を他方の目的に照らして測定しても、ほとんど何も得られず、多くのことが不明瞭になるほどに異な る。 科学が文化の診断的、批判的な側面であるとすれば、イデオロギーは正当化的、弁明的な側面である。すなわち、「信念や価値のパターンを確立し、それを擁護 することに積極的に関わる文化の一部」を指すのである。57 両者が衝突する傾向にあることは明らかであり、特に両者が同じ状況の範囲の解釈をめぐって対立する場合には、その傾向は顕著である。しかし、衝突は不可避 であり、社会科学の知見は必然的にイデオロギーが擁護し、普及しようとする信念や価値の妥当性を損なうという考え方は、最も疑わしい仮定である。同じ状況 に対して批判的かつ弁明的な態度を取ることは、本質的な矛盾ではない(ただし、実際には経験則であることが判明する可能性は高いが)。それは、ある程度の 知的洗練の証である。おそらく、チャーチルが孤立した英国の有名な演説を終えたとき、「我々は海岸で戦い、上陸地点で戦い、野原や街で戦い、丘で戦 う...」と述べた後、側近に振り向いて「そして、銃がないから炭酸水のボトルで頭を殴るんだ」と囁いたという、おそらく愉快な逸話を思い出すだろう。 このようにイデオロギーにおける社会的なレトリックの質は、その基盤となる社会心理学的現実のビジョンが誤りであることの証明にはならず、また、その説得 力は、信じられていることと、今現在またはいつか科学的に正しいと証明されることとの間のいかなる食い違いからも引き出される。自閉症的な空想にふけり、 現実との接点を失う可能性があることは明らかである。しかし、正常な機能の解明に病理学がどれほど興味深いものであっても(また、それが経験的にどれほど 一般的であったとしても)、正常な機能の原型としては誤解を招くものである。幸いにも、それを試す必要はなかったが、英国人が実際に海岸、上陸地点、通 り、丘で戦った可能性は高いと思われる。ソーダ水のボトルも使っただろう。なぜなら、チャーチルは自国民の気分を正確に表現し、それを表現することで、ば らばらで実現されていない個人的な感情の集合体ではなく、公有財産、社会的事実として動員したからだ。道徳的に嫌悪すべきイデオロギー的表現であっても、 人々や集団の雰囲気を最も鋭く捉えている場合がある。ヒトラーは、同胞の悪魔的な自己嫌悪を、魔法のように堕落したユダヤ人のトロピカルな姿に表現したと き、ドイツ人の良心を歪めていたわけではない。彼はそれを客観視していただけなのだ。つまり、蔓延する個人的な神経症を強力な社会的勢力へと変えたのだ。 しかし、科学とイデオロギーは異なる事業であるが、無関係なものではない。イデオロギーは社会の状態や方向性について経験則に基づく主張を行うが、それを 評価するのは科学(そして、科学的知識が欠如している場合は常識)の役割である。イデオロギーに対する科学の社会的機能は、まず第一に、それらを理解する こと、すなわち、それらが何であり、どのように機能し、何がそれらを生み出すのかを理解することであり、第二に、それらを批判し、現実と折り合いをつけさ せることである(ただし、必ずしも現実を受け入れる必要はない)。社会問題を科学的に分析する重要な伝統の存在は、イデオロギー的過激主義に対する最も効 果的な保証のひとつである。なぜなら、それは政治的想像力が活用し、尊重する上で、他に類を見ないほど信頼性の高い肯定的な知識の源となるからだ。このよ うな抑制はこれだけではない。先に述べたように、社会の他の強力なグループが掲げる競合するイデオロギーの存在も、少なくとも同様に重要である。また、リ ベラルな政治体制も重要である。そこでは、完全な平等という夢は明らかに空想であり、従来の期待が絶えず裏切られず、従来の考え方が根本的に無能ではない 安定した社会状況も重要である。しかし、独自のビジョンに静かな不屈の決意で献身する政治体制は、おそらく最も不屈の体制である。 |
| NOTES 1 F. X. Sutton, S. E. Harris, C. Kaysen, and J. Tobin, The American Business Creed (Cambridge, Mass., 1956), pp. 3-6. 2 K. Mannheim, Ideology and Utopia, Harvest ed. (New York n d.), p 59--83; see also R. Merton, Social Theory and Social Structure (New York; 3 W. White, Beyond Conformity (New York, 1961), p. 211. 4 W. Stark, The Sociology of Knowledge (London, 1958), p. 48. 5 Ibid., pp. 90-91. Italics in the original. For approximation of the same argument in Mannheim, formulated as a distinction between "total" and "particular" ideology, see Ideology and Utopia. 6 E. Shils, "Ideology and Civility: On the Politics of te Intellectual," The Sewanee Review 66 (1958): 450-480. 7 T. Parsons, "An Approach to the Sociology of Knowledge," Transactions of e Fourth World Congress of Sociology (Milan and Stressa, 1959), pp. 25-49. Italics in original. 8 R. Aron, The Opium of the Inrellectuals (New York, 1962). 9 As the danger of being misinterpreted here is serious, may I hope that my criticism will be credited as technical and not political. I note that my own general ideological (as I would frankly call it) position is largely the same as that of Aron, Shils, Parsons, and so forth; that I am in agreement with their plea for a civil, temperate, unheroic pohtics? Also it should he remarked that the demand for a nonevaluative concept of ideology is not a demand for the nonevaluation of ideologies, any more than a nonevaluative concept of religion imphes religious relativism. 10 Sutton, et al., American Business Creed; White, Beyond Conformity; H. Eckstem, Pressure Croup Politics: The Case of the British Medical Association (Stanford, 1960); C. Wright Mills, The New Men of Power (New York, 1948); J. Schumpeter, "Science and Ideology", American Economic Review 39 (1949). 11 There have been, in fact, a number of other terms used in the literature for the general range of phenomena that ideology "denotes, from Plato's noble lies" through Sorel's "myths" to Paretos "Derivations"; but none of them has managed to reach any greater level of technical neutrality than has Ideology." See H. D. Lasswell, "The Language of Power," in Lasswell, N. Leites, and Associates, Language of Politics (New York, 1949), pp. 3--19. 12 Sutton, et al., American Business Creed pp. I l-12, 303--310. 13 The quotations are from the most eminent recent interest theorist, A. Wright Mills, The Causes of World War Three (New York, 1958), pp. 54, 65. 14 For the general schema, see Parsons, The Social System (New York, 1951), especially Chaps. I and 7. The fullest development of the strain theory is in Sutton et al.. American Business Creed, especially Chap. 15. 15 Sutton, et al., American Business Creed, pp. 307-308. 16 Parsons, "An Approach." 17 White, Beyond Conformity, p. 204. 18 Perhaps the most impressive tour de force in this paratactic genre is Nathan Leites's A Study of Bolshevism (New York, 1953). 19 K. Burke, The Philosophy of Literary Form, Studies in Symbolic Action (Baton Rouge, 1941). In the following discussion, I use 'symbol" broadly in the sense of any physical, social, or cultural act or object that serves as the vehicle for a conception. For an explication of this view, under which "five" and "the Cross" are equally symbols, see S. Langer, Philosophy in a New Key, 4th ed. (Cambridge, Mass., 1960), pp. 60-66. 20 Useful general summaries of the tradition of literary criticism can be found in S. E. Hyman, The Armed Vision (New York, 1948) and in R. Welleck and A. Warren, Theory of Literature, 2nd ed. (New York, 1958). A similar summary of the somewhat more diverse philosophical development is apparently not available, but the seminal works are C. S. Peirce, Collected Papers, ed. C. Hartshorne and P. Weiss, 8 vols. (Cambridge, Mass., 1931-1958); E. Cassirer, Die Philosophie der symholischen Formen, 3 vols. (Berlin, 1923-1929); C. W. Morris, Signs, Language and Behavior (Englewood Cliffs, N.J., 1944); and L. Wittgenstein, Philosophical Investigations (Oxford, 1953). 21 W. Percy, "The Symbolic Structure of Interpersonal Process," Psychiatry 24 (1961):39-52. Italics in original. The reference is to Sapir's "The Status of Linguistics as a Science," originally published in 1929 and reprinted in D. Mandlezaum, ed., Selected Writings of Edward Sapir (Berkeley and Los Angeles, 1949), pp. 160-166. 22 A partial exception to this stricture, although marred by his obsession with power as the sum and substance of politics, is Lasswell's "Style in the Language of Politics," in Lasswell et al., Language of Politics, pD. 20-39. It also should be remarked that the emphasis on verbal symbolism in the following discussion is merely for the sake of simplicity and is not intended to deny the importance of plastic, theatrical, or other nonlinguistic devices-- the rhetoric of uniforms, floodlit stages, and marching bands--in ideological thought. 23 Sutton, et al., American Business Creed, pp. 4-5. 24 An excellent recent review is to be found in P. Henle, ed., Language Thought and Culture (Ann Arbor, 1958), pp. 173-195. The quotation is frorn Langer, Philosophy, P. 117. 25 W. Percy, "Metaphor as Mistake," The Sewanee Review 66 (1958): 79-99. 26 Quoted in J Crowiey, "Japanese Army Factionalism in the Early 1930's," The Journal of Asian Studies 21 (1958): 309-326. 27 Henle, Language, Thought and Culture, pp 4-5. 28 K. Burke, Counterstatement (Chicago, 1957), p. 149. 29 Sapir, "Status of Linguistics," p. 568. 30 Metaphor is, of course, not the only stylistic resource upon which ideology draws. Metonymy ("All I have to offer is blood, sweat and tears ), hyperbole ("The thousand-year Reich"), meiosis (I shall return" ), synechdoche ("Wall Street" ), oxymoron ("Iron curtain" ), personification ("The hand that held the dagger has plunged it into the back of its neighbor"), and all the other figures the classical rhetoricians so painstakingly collected and so carefully classified are utilized over and over again, as are such syntactical devices as antithesis, inversion, and repetition, such prosodic ones as rhyme, rhythm, and alliteration; such literary ones as irony, eulogy, and sarcasm. Nor is all ideological expression figurative. The bulk of it consists of quite literal, not to say flat--footed, assertions, which, a certain tendency toward prima facie implausibility aside, are difficult to distinguish from properly scientific statements: "The history of all hitherto existing society is the history of class struggles"; "The whole of the morality of Europe is based upon the values which are useful to the herd"; and so forth. As a cultural system, an ideology that has developed beyond the stage of mere sloganeering consists of an intricate structure of interrelated meanings-- interrelated in terms of the semantic mechanisms that formulate them--of which the two-level organization of an isolated metaphor is but a feeble representation. 31 Percy, "Symbolic Structure." 32 G. Ryle, The Concept of Mind (New York, 1949). 33 E. Galanter and M. Gerstenhaber, "On Thought: The Extrinsic Theory," Psychol. Rev. 63 (1956):218-227. 34 Ibid. I have quoted this incisive passage above (pp. 77-78), in attempting to set the extrinsic theory of thought in the context of recent evolutionary, neurological, and cultural anthropological findings. 35 W. Percy, "Symbol, Consciousness and Intersubjectivity," Journal of Philosophy 55 (1958) 631-641. Italics in original. Quoted by permission. 36 Ibid. Quoted by permission. 37 S. Langer, Feeling and Form (New York, 1953). 38 The quotations are from Ryle, Concept of Mind, p. 51. 39 T. Parsons, "An Approach to Psychological Theory in Terms of the Theory of Action," in Psychology: A Study of a Science, ed. S. Koch (New York, 1959), vol. 3. Italics in original. Compare: "In order to account for this selectivity, it is necessary to assume that the structure of the enzyme is related in some way to the structure of the gene. By a logical extension of this idea we arrive at the concept that the gene is a representation --blueprint so to speak --of the enzyme molecule, and that the function of the gene is to serve as a source of information regarding the structure of the enzyme. It seems evident that the synthesis of an enzyme--a giant protein molecule consisting of hundreds of ammo acid units arranged endtoend in a specific and unique order--requires a model or set of instructions of some kind. These instructions must be characteristic of the species; they must be automatically transmitted from generation to generation, and they must be constant yet capable of evolutionary change. The only known entity that could perform such a function is the gene. There are many reasons for believing that it transmits information, by acting as a model or template." N. H. Horowitz, "The Gene," Scientific American, February 1956, p. 85. 40 This point is perhaps somewhat too baldly put in light of recent analyses of animal learning; but the essential thesis--that there is a general trend toward a more diffuse, less determinate control of behavior by intrinsic (innate) parameters as one moves from lower to higher animals--seems well established. See above, Chapter 3, pp. 70-76. 41 Of course, there are moral, economic, and even aesthetic ideologies, as well as specifically political ones, but as very few ideologies of any social prominence lack political implications, it is perhaps permissible to view the problem here in this somewhat narrowed focus. In any case, the arguments developed for political ideologies apply with equal force to nonpolitical ones. For an analysis of a moral ideology cast in terms very similar to those developed in this paper, see A. L. Green, "The Ideology of Anti-Fluoridation Leaders," The Journal of Social Issues 17 (1961): 13-25. 42 That such ideologies may call, as did Burke's or De Maistre's, for the reinvigoration of custom or the reimposition of religious hegemony is, of course, no contradiction. One constructs arguments for tradition only when its credentials have been questioned. To the degree that such appeals are successful they bring, not a return to naive traditionalism, but ideological retraditionalization--an altogether different matter. See Mannheim, "Conservative Thought," in his Essays on Sociology and Social Psychology (New York, 1953), especially pp. 94-98. 43 It is important to remember, too, that the principle was destroyed long before the king; It was to the successor principle that he was, in fact, a ritual sacrifice: "When [Saint-Just] exclaims: "To determine the principle in virtue of which the accused [Louis XVI] is perhaps to die, is to determine the principle by which the society that judges him lives, he demonstrates that it is the philosophers who are going to kill the King: the King must die in the name of the social contract." A. Camus, The Rebel (New York. 1958). p. 114. 44 Alphonse de Lamartine, "Declaration of Principles," in Introduction to Contemporary Civilization in the West, A Source Book (New York, 1946), 2: 328-333. 45 The following very schematic and necessarily ex cathedra discussion is based mainly on my own research and represents only my own views, but I have a!so drawn heavily on the work of Herbert Feith for factual material. See especially, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (New York, 1962) and "Dynamics of Guided Democracy," in Indonesia, ed. R. McVey (New Haven, 1963), pp. 309-409. For the general cultural analysis within which my interpretations are set, see C. Geertz, The Religion of Java (New York, 1960). 46 R. Heme-Geldern, "Conceptions of State and Kinship in Southeast Asia," Far Eastern Quarterly 2 (1942): 15--30. 47 Ibid. 48 The whole expanse of Yawa-land [Java] is to be compared with one town in the Prince's reign. / By thousands are [counted] the people's dwelling places, to be compared with the manors of Royal servants, surrounding the body of the Royal compound. / All kinds of foreign islands--to be compared with them are the cultivated land's areas, made happy and quiet. / Of the aspect of parks, then, are the forests and mountains, all of them set foot on by Him, without feeling anxiety. Canto 17, stanza 3 of the "Nagara-Kertagama," a fourteenth century royal epic. Translated in Th. Piegeaud, Java in the 14th Century (The Hague, 1960) 3:21. The term nagara still means, indifferently, "palace," "capital city," "state,' "country," or "government" sometimes even "civilization"-- in Java. 49 For a description of the Pantjasila speech, see G. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca, 1952), pp.122--127. 50 The quotations are from the Pantjasila speech, as quoted in ibid., p. 126. 51 The proceedings of the convention, unfortunately still untranslated, form one of the fullest and most instructive records of ideological combat in the new states available. See Tentang Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante, 3 vols. (n.p. [Diakarta?].n.d. [1958?]]. 52 Feith, "Dynamics of Guided Democracy," p. 367. A vivid, if somewhat shrill, description of "Manipol-USDEKism" in action can be found in W. Hanna, Bung Karno's Indonesia (New York, 1961). 53 Feith, "Dynamics of Guided Democracy," 367-368. Pegang literally means "to grasp" thus peganean "something graspable." 54 Ibid. 55 For an analysis of the role of ideology in an emerging African nation, conducted along lines similar to our own, see L. A. Fallers, "Ideology and Culture In Uganda Nationalism," American Anthropologist 63 (1961): 677-686. For a superb case study of an "adoiescent" nation in which the process of thorough-going ideologlical reconstruction seems to have been conducted with reasonable success, see B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London, 1961), especially Chap. 10. 56 This point is, however, not quite the same as saying that the two sorts of activity may not in practice be carried on together, any more than a man cannot, for example, paint a portrait of a bird that is both ornithologically accurate and aesthetically effective. Marx is, of course, the outstanding case, but for a more recent successful synchronization of scientific analysis, and ideological argument, see E. Shils, The Torment of Secrecy (New York, 1956). Most such attempts to mix genres are however, distinctly less happy. 57 Fallers, "Ideology and Culture." The patterns of belief and value defended may be, of course, those of a socially subordinate group, as well as those of a socially dominant one, and the "apology" therefore for reform or revolution. |
注 1 F. X. Sutton, S. E. Harris, C. Kaysen, and J. Tobin, The American Business Creed (Cambridge, Mass., 1956), pp. 3-6. 2 K. マニフェスト、 『イデオロギーとユートピア』、ハーベスト社(ニューヨーク、発行年不明)、59-83ページ。また、R. マートン著『社会理論と社会構造』(ニューヨーク)も参照のこと。 3 W. ホワイト著『コンフォーミティを超えて』(ニューヨーク、1961年)、211ページ。 4 W. スターク著『知識の社会学』(ロンドン、1958年)、48ページ。 5 同書、90-91ページ。イタリック体は原文のまま。マンハイムにおける同様の議論の近似値については、「全体的」イデオロギーと「特殊」イデオロギーの 区別として定式化されている。『イデオロギーとユートピア』を参照のこと。 6 E. Shils, 「Ideology and Civility: On the Politics of te Intellectual,」 The Sewanee Review 66 (1958): 450-480. 7 T. パーソンズ、「知識社会学へのアプローチ」、第4回世界社会学会議議事録(ミラノおよびストレーザ、1959年)、25-49ページ。イタリック体は原文 のまま。 8 R. アロン、『インテレクチュアルの阿片』(ニューヨーク、1962年)。 9 ここで誤解される危険性は深刻であるため、私の批判は技術的なものであり、政治的なものではないと認めていただきたい。率直に言って、私の一般的なイデオ ロギー上の立場(私がそう呼ぶもの)は、アロン、シルズ、パーソンズなどとほぼ同じである。私は彼らの、穏健で英雄的でない政治を求める主張に同意してい る。また、イデオロギーの非評価的概念の要求は、イデオロギーの非評価の要求ではないということも指摘しておくべきだろう。宗教の非評価的概念が宗教的相 対主義を意味しないのと同様である。 10 Sutton, et al., American Business Creed; White, Beyond Conformity; H. Eckstem, Pressure Croup Politics: The Case of the British Medical Association (Stanford, 1960); C. Wright Mills, The New Men of Power (New York, 1948); J. Schumpeter, 「Science and Ideology」, American Economic Review 39 (1949). 11 実際、イデオロギーが「プラトンの高貴な嘘」からソレルの「神話」、パレートの「演繹」に至るまで、広範な現象を「示す」ものとして、文献では数多くの他 の用語が使用されてきた。しかし、そのいずれも「イデオロギー」ほど技術的に中立的な高いレベルに達したものはなかった。H. D. ラッセル著『権力の言語』、ラッセル、N. レイテス、および共同執筆者著『政治の言語』(ニューヨーク、1949 年)、3~19ページを参照。 12 Sutton, et al., American Business Creed pp. I l-12, 303--310. 13 引用は、最も著名な最近の利害理論家であるA. Wright Millsによる『第三次世界大戦の原因』(ニューヨーク、1958年)の54ページと65ページから引用した。 14 一般的な図式については、パーソンズ著『社会システム』(ニューヨーク、1951年)の第1章と第7章を参照のこと。 ストレーン理論の最も詳細な展開は、サットン他著『アメリカン・ビジネス・クリード』の第15章に記載されている。 15 サットン他著『アメリカン・ビジネス・クリード』307-308ページ。 16 パーソンズ著「アプローチ」。 17 ホワイト『規範を超えて』204ページ。 18 このパラタクティクのジャンルにおける最も印象的な力作は、おそらくネイサン・レイテスの『ボルシェビズム研究』(ニューヨーク、1953年)であろう。 19 K. バーク『文学形式の哲学』『象徴的行為の研究』(バトンルージュ、1941年)。以下の議論では、「象徴」という語を、概念の媒介となる物理的、社会的、 あるいは文化的行為や対象を意味する広義の語として使用する。「5」と「十字架」が等しく象徴であるというこの見解の説明については、S. Langer著『哲学の新しい鍵』第4版(マサチューセッツ州ケンブリッジ、1960年)60~66ページを参照のこと。 文学批評の伝統に関する20の有用な一般的な要約は、S. E. Hyman著『The Armed Vision』(ニューヨーク、1948年)およびR. WelleckとA. Warren著『Theory of Literature』(第2版、ニューヨーク、1958年)に記載されている。より多様化した哲学の発展に関する同様の要約は、おそらく存在しないと思 われるが、その分野における重要な著作としては、C. S. Peirce著『Collected Papers』編者:C. HartshorneとP. Weiss、全8巻(ケンブリッジ、マサチューセッツ、1931年~1958年)、E. Cassirer著『Die Philosophie der symholischen Formen』全3巻(1923年~1929年)がある。C. HartshorneとP. Weiss編、8巻(マサチューセッツ州ケンブリッジ、1931年~1958年)、E. Cassirer著『象徴的形態の哲学』全3巻 (ベルリン、1923-1929年)、C. W. モリス著『Signs, Language and Behavior』(ニュージャージー州イングルウッドクリフ、1944年)、L. ウィトゲンシュタイン著『Philosophical Investigations』(オックスフォード、1953年)。 21 W. パーシー著「The Symbolic Structure of Interpersonal Process(対人関係の過程における象徴構造)」『Psychiatry 24』(1961年):39-52ページ。 原文のイタリック体。この文献は、1929年に初版が出版され、D. Mandlezaum編『エドワード・サピアの論文集』(バークレーおよびロサンゼルス、1949年)の160~166ページにも再版された、サピアの 「科学としての言語学の地位」を参照している。 22 この厳格な規定に対する部分的な例外は、政治の総体と本質としての権力への執着によって損なわれているものの、ラッセルの「政治の言語様式」である。ラッ セル他著『政治の言語』pD. 20-39。また、以下の議論における言語的象徴の強調は、単純化のためであり、イデオロギー思想における、画一的な制服、照明に照らされたステージ、 マーチングバンドといった、造形的な、演劇的な、あるいはその他の非言語的装置(修辞)の重要性を否定する意図はないことを指摘しておくべきであろう。 23 Sutton, et al., American Business Creed, pp. 4-5. 24 最近の優れた概説は、P. Henle編『言語、思想、文化』(ミシガン州アンアーバー、1958年)の173~195ページを参照のこと。引用はLanger著『哲学』117ペー ジより。 25 W. パーシー、「比喩としての誤り」、The Sewanee Review 66 (1958): 79-99. 26 J. クロウリー、「1930年代初期における日本陸軍の派閥主義」、The Journal of Asian Studies 21 (1958): 309-326. 27 ヘンレ著『言語・思想・文化』4-5ページ。 28 K. バーク著『反論』(シカゴ、1957年)149ページ。 29 サピア著『言語学の地位』568ページ。 30 もちろん、イデオロギーが利用する文体の手法は隠喩だけではない。換喩(「私が提供できるのは血と汗と涙だけだ」)、誇張(「千年帝国」)、縮約(「必ず 戻ってくる」)、換喩(「ウォール街」)、オクシモロン(「鉄のカーテン」)、擬人法(「短剣を握っていた手が隣人の背中に短剣を突き刺した」 )、そして古典修辞学者たちが丹念に収集し、慎重に分類したその他の修辞技法が繰り返し用いられている。反語、倒置、反復などの統語的技法、韻、リズム、 頭韻などの韻律的技法、皮肉、賛辞、皮肉などの文学的技法も同様である。また、すべての観念的な表現が比喩的であるわけではない。その大半は、かなり文字 通りの、平面的な、あるいは安直な主張から成り立っており、一見して信憑性に欠けるという傾向はさておき、正統な科学的声明と区別することが難しい。「こ れまでに存在した社会の歴史は、階級闘争の歴史である」、「ヨーロッパの道徳のすべては、群れにとって有益な価値観に基づいている」など。文化システムと して、単なるスローガン以上の段階にまで発展したイデオロギーは、それらを形作る意味のメカニズムの観点から相互に関連する意味の複雑な構造から成り立っ ている。孤立した隠喩の2段階の組織化は、そのごく一部の表現にすぎない。 31 パーシー、「象徴構造」 32 G. ライル、『心の概念』(ニューヨーク、1949年)。 33 E. Galanter and M. Gerstenhaber, 「On Thought: The Extrinsic Theory,」 Psychol. Rev. 63 (1956):218-227. 34 同上。私は、思考の外的理論を最近の進化論、神経科学、文化人類学の知見の文脈に位置づけようとして、この鋭い一節を引用した(77-78ページ)。 35 W. パーシー、「シンボル、意識、相互主観性」、Journal of Philosophy 55 (1958) 631-641。 イタリック体は原文のまま。 引用許可取得済み。 36 同上。 引用許可取得済み。 37 S. ランガー、『Feeling and Form』(ニューヨーク、1953年)。 38 引用はRyle, Concept of Mind, p. 51より。 39 T. Parsons, 「An Approach to Psychological Theory in Terms of the Theory of Action,」 in Psychology: A Study of a Science, ed. S. Koch (New York, 1959), vol. 3. イタリック体は原文のまま。比較:「この選択性を説明するためには、酵素の構造が遺伝子の構造と何らかの形で関連していると仮定する必要がある。この考え を論理的に推し進めると、遺伝子は酵素分子のいわば設計図であり、遺伝子の機能は酵素の構造に関する情報の源となることであるという概念に行き着く。 酵素の合成には、数百のアミノ酸単位が特定のユニークな順序で端から端まで配列された巨大なタンパク質分子であるが、何らかのモデルまたは一連の指示が必 要であることは明らかである。これらの指示は、その種に特有のものでなければならず、世代から世代へと自動的に伝達され、かつ一定でありながら進化の変化 にも対応できるものでなければならない。このような機能を持つことが知られている唯一の存在は遺伝子である。遺伝子がモデルまたはテンプレートとして作用 することで情報を伝達していると考える理由は数多くある。」N. H. Horowitz, 「The Gene,」 Scientific American, February 1956, p. 85. 40 この指摘は、動物の学習に関する最近の分析に照らすと、やや極端に過ぎるかもしれない。しかし、本質的な命題、すなわち、下等動物から高等動物へと進むに つれて、本質的(生得)パラメータによる行動の制御がより拡散的で決定性が低い傾向にあるという命題は、十分に確立されていると思われる。上記、第3章、 70~76ページを参照。 41 もちろん、政治的なイデオロギーだけでなく、道徳的、経済的、さらには美的なイデオロギーもあるが、社会的に目立ったイデオロギーのほとんどすべてに政治 的な含意が欠けているわけではないため、この問題をある程度狭い範囲に絞って考えることは許されるだろう。いずれにしても、政治的イデオロギーのために展 開された議論は、非政治的なものにも同様に当てはまる。本論文で展開された議論と非常に類似した観点から展開された道徳的イデオロギーの分析については、 A. L. Green著『反フッ素化推進派のイデオロギー』『The Journal of Social Issues』17(1961年):13-25を参照のこと。 42 このようなイデオロギーが、バークやド・マエストルのように、慣習の再活性化や宗教的ヘゲモニーの再確立を求める可能性があることは、もちろん矛盾しな い。伝統の正当性が疑われたときにのみ、伝統を擁護する論拠が構築されるのである。このような訴えが成功する程度は、素朴な伝統主義への回帰ではなく、イ デオロギー的な再伝統化をもたらす。これはまったく異なる問題である。マンハイム著『社会学・社会心理学論集』(ニューヨーク、1953年)の「保守思 想」、特に94~98ページを参照。 43 また、王よりもずっと前にその原則が破壊されていたことも忘れてはならない。王は、後継の原則に対して、事実上、儀式的な生け贄となったのだ。「サン= ジュストが叫ぶ。「被告(ルイ16世)が死ぬべき理由となった原則を決定することは、彼を裁く社会が生きる原則を決定することである。彼は、王を殺すのは 哲学者たちであることを示している。王は社会契約の名において死なねばならないのだ」と叫んだ。A. カミュ著『反逆者』(ニューヨーク、1958年)114ページ。 44 アルフォンス・ド・ラマルティーヌ、「原則宣言」、『西洋における現代文明入門:ソースブック』(ニューヨーク、1946年)、2: 328-333。 45 以下の極めて概略的で、必然的に権威主義的な議論は、主に私の独自の研究に基づくものであり、私の個人的な見解を表している。しかし、事実関係については ハーバート・ファイスの著作を大いに参考にしている。特に、『インドネシアにおける立憲民主主義の衰退』(ニューヨーク、1962年)と、R. マクヴィ編『インドネシア』(ニューヘイブン、1963年)の「誘導民主主義の力学」309~409ページを参照されたい。私の解釈が置かれている一般的 な文化分析については、C. ゲルツ著『ジャワの宗教』(ニューヨーク、1960年)を参照されたい。 46 R. Heme-Geldern, 「Conceptions of State and Kinship in Southeast Asia,」 Far Eastern Quarterly 2 (1942): 15--30. 47 同上。 48 ヤワランド(ジャワ)の全域は、王子の統治下にある一つの町に例えることができる。王の領地を取り囲むように、王の家臣たちの屋敷に匹敵する人々の住居が 数千と数えられている。/ あらゆる種類の外国の島々――それらに匹敵する耕作地は、幸せで静かな場所である。/ 公園のような様相を呈する森林や山々、それらすべては、彼が足を踏み入れる場所であり、不安を感じることはない。14世紀の王族叙事詩『ナラガ・カルタガ マ』第17章第3節。Th. Piegeaud, Java in the 14th Century (The Hague, 1960) 3:21による翻訳。ナラガという用語は、ジャワでは今でも「宮殿」、「首都」、「国家」、「国」、「政府」、時には「文明」という意味で、無差別に使わ れている。 49 パンチャシラの演説については、G. カヒン著『インドネシアのナショナリズムと革命』(1952年、イサカ)122~127ページを参照のこと。 50 引用は、同書126ページに引用されているパンチャシラの演説からのものである。 51 その会議の議事録は、残念ながら未だに翻訳されていないが、新生国家におけるイデオロギー闘争の最も詳細で、最も参考になる記録のひとつである。 Tentang Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante, 3 vols. (n.p. [Diakarta?].n.d. [1958?]].を参照のこと。 52 フェイス、「誘導型民主主義の力学」、367ページ。 「マニポル・USDEK主義」の活き活きとした、しかしやや耳障りな描写は、W. ハンナ著『ブン・カルノのインドネシア』(ニューヨーク、1961年)にみられる。 53 フェイス著『誘導型民主主義の力学』367-368ページ。ペガンは文字通り「把握する」という意味であり、したがってペガネアンは「把握可能なもの」を 意味する。 54 同上 55 私たちの研究と類似した観点から、アフリカの新生国家におけるイデオロギーの役割を分析したものとして、L. A. Fallers著「ウガンダ民族主義におけるイデオロギーと文化」『アメリカン・アントロポロジスト』63号(1961年)677-686ページを参照。 徹底的なイデオロギーの再構築がそれなりの成功を収めたと思われる「アドイセンシャル(adoiestant)」な国民の優れた事例研究としては、B. ルイス著『近代トルコの誕生』(ロンドン、1961年)の第10章を参照のこと。 56 しかし、この点は、2つの活動が実際には同時に遂行されることはないというのとは少し異なる。人間が、例えば、鳥類学的に正確で美的にも効果的な鳥の肖像 画を描くことができないのと同じことだ。もちろん、マルクスは際立った事例であるが、科学分析とイデオロギー論争のより最近の成功した同時進行について は、E. Shils著『The Torment of Secrecy』(ニューヨーク、1956年)を参照のこと。しかし、このようなジャンルを混ぜ合わせる試みのほとんどは、明らかに成功していない。 57 Fallers, 「Ideology and Culture.」 擁護される信念や価値観のパターンは、もちろん、社会的に従属的なグループのものである場合も、社会的に支配的なグループのものである場合もあり、した がって改革や革命に対する「弁明」となる。 |
| Ideology as a cultural system,
in: Apter, David Ernest (ed.): Ideology and discontent.
New-York/N.Y./USA 1964: The Free Press of Glencoe, pp. 47-76. |
|
| http://hypergeertz.jku.at/GeertzTexts/Ideology_Cultural.htm |
リンク
文献
その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆