
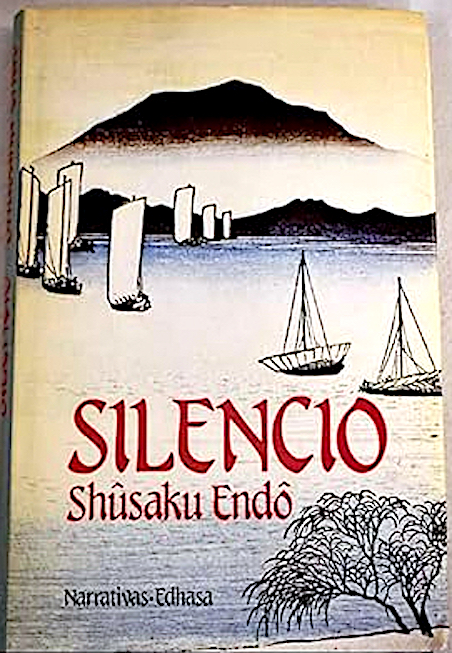
ふたつの『沈黙』(1966-2016)
Comparative study of reading/watching between two works of Shusaku Endo's "Silence," 1966-2006.

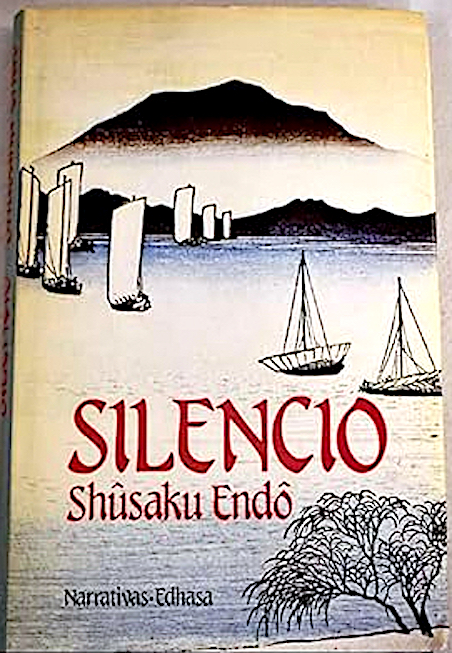
☆ 沈黙』(ちんもく)は、日本の作家、遠藤周作による1966年の神学・歴史小説である。17世紀の日本に派遣されたイエズス会の宣教師が、島原の乱の敗北 に続く隠れキリシタンの時代の迫害に耐える物語である。1966年に谷崎賞を受賞したこの作品は、「遠藤の最高傑作」、「20世紀で最も優れた小説 のひとつ」と称されている。一部、主人公の手紙の形式で書かれており、逆境にある信者に寄り添う沈黙の神というテーマは、カトリック信者であった遠 藤の、日本での宗教差別、フランスでのカルチャーギャップ、結核による衰弱の経験に大きな影響を受けている。
| Silence Silence (Japanese: 沈黙, Hepburn: Chinmoku) is a 1966 novel of theological and historical fiction by Japanese author Shūsaku Endō. It tells the story of a Jesuit missionary sent to 17th-century Japan, who endures persecution in the time of Kakure Kirishitan ("Hidden Christians") that followed the defeat of the Shimabara Rebellion. The recipient of the 1966 Tanizaki Prize, it has been called "Endō's supreme achievement"[1] and "one of the twentieth century's finest novels".[2] Written partly in the form of a letter by its central character, the theme of a silent God who accompanies a believer in adversity was greatly influenced by the Catholic Endō's experience of religious discrimination in Japan, culture gap in France, and a debilitating bout with tuberculosis.[3] Silence was published in English in 1969 by Peter Owen Publishers. The novel has been adapted to film three times, a 1971 Japanese film directed by Masahiro Shinoda (for which Endō co-wrote the screenplay), a 1996 Portuguese film directed by João Mário Grilo, and a 2016 American film directed by Martin Scorsese. |
『沈
黙』 『沈 黙』(ちんもく)は、日本の作家、遠藤周作による1966年の神学・歴史小説である。17世紀の日本に派遣されたイエズス会の宣教師が、島原の乱の敗北に 続く隠れキリシタンの時代の迫害に耐える物語である。1966年に谷崎賞を受賞したこの作品は、「遠藤の最高傑作」[1]、「20世紀で最も優れた小説の ひとつ」[2]と称されている。一部、主人公の手紙の形式で書かれており、逆境にある信者に寄り添う沈黙の神というテーマは、カトリック信者であった遠藤 の、日本での宗教差別、フランスでのカルチャーギャップ、結核による衰弱の経験に大きな影響を受けている[3]。この小説は3度映画化されており、 1971年の篠田正浩監督による日本映画(遠藤は共同脚本を担当)、1996年のジョアン・マリオ・グリロ監督によるポルトガル映画、そして2016年の マーティン・スコセッシ監督によるアメリカ映画である。 |
| Plot summary The young Portuguese Jesuit priest Sebastião Rodrigues (based on the historical Italian figure Giuseppe Chiara) travels to Japan to assist the local Church and investigate reports that his mentor, a Jesuit priest in Japan named Ferreira, based on Cristóvão Ferreira, has committed apostasy. Less than half of the book is the written journal of Rodrigues, while the other half of the book is written either in the third person, or in the letters of others associated with the narrative. The novel relates the trials of Christians and the increasing hardship suffered by Rodrigues. Rodrigues and his companion Francisco Garrpe (also a Jesuit priest) arrive in Japan in 1639. There they find the local Christian population driven underground. To ferret out hidden Christians, security officials force suspected Christians to trample on a fumi-e, a carved image of Christ. Those who refuse are imprisoned and killed by ana-tsurushi, which is by being hung upside down over a pit and slowly bled. Rodrigues and Garrpe are eventually captured and forced to swim as Japanese Christians lay down their lives for the faith. There is no glory in these martyrdoms, as Rodrigues had always imagined – only brutality and cruelty. Prior to the arrival of Rodrigues, the authorities had been attempting to force priests to renounce their faith by torturing them. Beginning with Ferreira, they torture other Christians as the priests look on, telling the priests that all they must do is renounce their faith in order to end the suffering of their flock. Rodrigues' journal depicts his struggles: he understands suffering for the sake of one's own faith; but he struggles over whether it is self-centered and unmerciful to refuse to recant when doing so will end another's suffering. At the climactic moment, Rodrigues hears the moans of those who have recanted but are to remain in the pit until he tramples the image of Christ. As Rodrigues looks upon a fumi-e, Christ breaks his silence: "You may trample. You may trample. I more than anyone know of the pain in your foot. You may trample. It was to be trampled on by men that I was born into this world. It was to share men's pain that I carried my cross." Rodrigues puts his foot on the fumi-e. An official tells Rodrigues, "Father, it was not by us that you were defeated, but by this mudswamp, Japan."[4] |
あらすじ ポルトガルの若きイエズス会司祭セバスティアン・ロドリゲス(イタリアの歴史上の人物ジュゼッペ・キアラがモデル)は、現地の教会を支援し、彼の師である 日本のイエズス会司祭フェレイラ(クリストヴァン・フェレイラがモデル)が背教を犯したという報告を調査するために日本を訪れる。本書の半分以下はロドリ ゲスの手記であり、残りの半分は三人称か、物語に関係する人々の手紙によって書かれている。この小説は、キリシタンの試練とロドリゲスが被る苦難の増大を 描いている。 ロドリゲスと同行のフランシスコ・ガルペ(同じくイエズス会司祭)は1639年に日本に到着する。そこで彼らは、現地のキリスト教徒が地下に追いやられて いるのを発見する。隠れキリシタンを探し出すため、治安当局は疑わしいキリシタンにふみ絵を踏ませる。拒否した者は投獄され、穴吊り(穴の上に逆さ吊りに され、ゆっくりと血を流される)によって殺される。 ロドリゲスとガープは最終的に捕らえられ、日本人キリスト教徒が信仰のために命を捨てるように泳がされる。これらの殉教には、ロドリゲスがいつも想像して いたような栄光はなく、残忍さと残酷さだけである。ロドリゲスが到着する以前から、当局は司祭を拷問することで信仰を捨てさせようとしていた。フェレイラ に始まり、彼らは神父たちが見守る中、他のキリスト教徒を拷問し、神父たちに、自分たちの群れの苦しみを終わらせるためには信仰を捨てればいいのだと言い 聞かせる。 ロドリゲスの手記には、彼の葛藤が描かれている。彼は自分の信仰のために苦しむことは理解できるが、そうすることで他の人の苦しみが終わるのに、信仰を捨 てることを拒むのは自己中心的で無慈悲なことなのか、と葛藤する。クライマックスの瞬間、ロドリゲスは、キリストの像を踏みにじるまで穴の中にとどまるこ とになった棄権者たちのうめき声を聞く。ロドリゲスがふみ絵を見ていると、キリストが沈黙を破る: 「踏みつけてもよい。踏みにじるがいい。私は誰よりもお前の足の痛みを知っている。踏みつけてもいい。私がこの世に生まれたのは、人に踏みつけられるため だった。私が自分の十字架を背負ったのは、人の痛みを分かち合うためだった」。ロドリゲスはふみ絵に足をかける。 役人がロドリゲスに言う。「パドレ、あなたが敗れたのは私たちによってではなく、この泥沼、日本によってです」[4]。 |
| Reception Silence received the 1966 Tanizaki Prize for the year's best full-length literature. It has also been the subject of extensive analysis.[5] In a review published by The New Yorker, John Updike called Silence "a remarkable work, a sombre, delicate, and startlingly empathetic study of a young Portuguese missionary during the relentless persecution of the Japanese Christians in the early seventeenth century."[6] William Cavanaugh highlights the novel's "deep moral ambiguity" due to the depiction of a God who "has chosen not to eliminate suffering, but to suffer with humanity."[7] Silence was not immediately successful among Japanese Catholics, who were among some of the novel's harshest critics. Instead, the novel's popularity was boosted by "left-wing college students" who saw a connection to the plight of Japanese Marxists in the circumstances of Rodrigues. The novel was notably compared to Graham Greene's The Power and the Glory, leading Endo to be referred to as "the Graham Greene of Japan."[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Silence_(End%C5%8D_novel) |
レセプション(受容) 『沈黙』は、その年の最優秀長編文学に贈られる谷崎賞を1966年に受賞した。ジョン・アップダイクは『ニューヨーカー』誌の批評で、『沈黙』を「驚くべ き作品であり、17世紀初頭の日本のキリシタンに対する容赦ない迫害の中で、若いポルトガル人宣教師を描いた、陰鬱で、繊細で、驚くほど共感的な研究であ る」と評した[6]。ウィリアム・キャヴァノーは、「苦しみをなくすことを選ばず、人間とともに苦しむことを選んだ」神の描写による、この小説の「深い道 徳的曖昧さ」を強調している[7]。 『沈黙』は日本のカトリック信者の間ではすぐには成功せず、彼らはこの小説を最も厳しく批判した人たちの一人であった。その代わりに、ロドリゲスの境遇に日本のマルクス主義者の苦境とのつながりを見出した「左翼の大学生」たちによって、この小説の人気は高まった。この小説はグレアム・グリーンの『権力と栄光』と比較され、遠藤は「日本のグレアム・グリーン」と呼ばれるようになった[8]。 |
| The Power and the Glory The Power and the Glory is a 1940 novel by British author Graham Greene. The title is an allusion to the doxology often recited at the end of the Lord's Prayer: "For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever, amen." It was initially published in the United States under the title The Labyrinthine Ways. Greene's novel tells the story of a renegade Catholic 'whisky priest' (a term coined by Greene) living in the Mexican state of Tabasco in the 1930s, a time when the Mexican government was attempting to suppress the Catholic Church. That suppression had resulted in the Cristero War (1926–1929), so named for its Catholic combatants' slogan "Viva Cristo Rey" ("Long live Christ the King"). In 1941, the novel received the Hawthornden Prize British literary award. In 2005, it was chosen by TIME magazine as one of the hundred best English-language novels since 1923.[1] Plot During the period when Catholicism was outlawed in Mexico, the state of Tabasco enforces the ban rigorously, while many other states follow a don't-ask-don't-tell policy. But in Radical Socialist Tabasco, priests have been settled by the state with wives (breaking celibacy) and pensions in exchange for their renouncing the faith and being strictly banned from fulfilling pastoral functions. Those who refuse are on the run and liable to be shot. A scene-setting introduction to some of the characters, who are enduring a barely satisfactory existence in the provincial capital, now gives way to the story of the novel's protagonist: a fugitive priest returned after years to the small country town that was formerly his parish. The narrative then follows him on his journey through the state, where he tries to minister to the marginalised people as best he can. In doing so, he is faced by many problems, not least of which is that Tabasco is also prohibitionist, with the unspoken prime objective to hinder celebration of the Sacrifice of the Mass, for which actual wine is an essential. Otherwise it is fairly easy to obtain beer or hard liquor, despite their being forbidden. The unnamed "traitor to the state" is a 'whisky priest' who, among his other personal failings, had fathered a child in his parish some years before. Now he meets his daughter during a brief stay, but is unable to feel repentance. Rather, he feels a deep love for the evil-looking and awkward little girl and decides to do everything in his power to save her from damnation. His chief antagonist is the police lieutenant, who is morally irreproachable but unbending in outlook. While he is supposedly "living for the people", he puts into practice a plan of taking hostages from villages and shooting them if he discovers the priest has sojourned there without being denounced. On account of bad experiences with the church in his youth, there is a personal element in his pursuit. For his part, the priest has remained on the run in order to serve the religious needs of the poverty-stricken agriculturists he meets, despite his deep sense of unworthiness. In order to save them from harm at the hands of the vengeful lieutenant, he now feels compelled to cross the mountainous border to the less stringent, neighbouring state. During this time, he twice encounters the lieutenant - once during a round-up in his village and then after he is imprisoned as a drunk – but is not recognised and allowed to go on his way. Near death after a perilous journey, he is rescued by the workers of the Lehrs, Protestant land-owners from the US, who nurse the priest back to health and help him make plans to reach the local capital. As he sets out, the priest meets again a mestizo whom he has earlier learned to mistrust and who eventually reveals himself to be a Judas figure. The mestizo persuades the priest to return to hear the confession of a dying man just over the border, an American gunman who is the lieutenant's second target. Though suspecting that it is a trap, the priest feels compelled to fulfil his sacramental duty. Urged by the dying man to escape and save himself, the priest falls into the hands of the waiting lieutenant nevertheless. Though the lieutenant admits that he has nothing against the priest as a man, and rather admires him, the lieutenant persists that he must be shot "as a danger". On the eve of the execution, the lieutenant shows mercy and attempts to enlist the renegade Padre José to hear the condemned man's confession (which in extremis the Church would allow), but the effort is thwarted by Padre José's domineering wife. The lieutenant is now convinced that he has "cleared the province of priests", but in the final chapter another covert priest arrives in the capital. A faithful Catholic woman, who has previously figured as reading pious tracts about the lives of native saints to her children, has added the protagonist to her repertoire of Christian martyrs and now agrees to harbour this new arrival. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Power_and_the_Glory |
『力と栄光』 『力と栄光』はイギリスの作家グレアム・グリーンによる1940年の小説。タイトルは、主の祈りの最後によく唱えられる頌栄(しょうえい)を暗示している: 「王権と力と栄光は汝のものである。アメリカでは当初、『迷宮の道』というタイトルで出版された。 グリーンの小説は、メキシコ政府がカトリック教会を弾圧しようとしていた1930年代、メキシコのタバスコ州に住む反逆のカトリック「ウイスキー司祭」 (グリーンの造語)の物語である。この弾圧はクリステロ戦争(1926年〜1929年)を引き起こしたが、クリステロ戦争はカトリック教徒のスローガン "Viva Cristo Rey"(「王であるキリスト万歳」)から名づけられた。 1941年、この小説はイギリスの文学賞ホーソンデン賞を受賞。2005年、TIME誌が選ぶ1923年以降の英語小説ベスト100に選ばれた[1]。 プロット(あらすじ) メキシコでカトリックが非合法化された時代、タバスコ州は厳格に禁教を執行し、他の多くの州は "聞かない""言わない "政策をとっていた。しかし、急進的社会主義タバスコ州では、神父たちは信仰を捨て、司牧の職務を果たすことを厳しく禁じられる代わりに、妻(独身を破る)と年金を国から支給されることになった。拒否した者は逃亡し、銃殺刑に処される。 地方都市でかろうじて満足のいく生活に耐えている登場人物たちの紹介から、この小説の主人公である逃亡神父の物語が始まる。そして物語は、彼が州を旅し、疎外された人々に精一杯の奉仕をしようとする姿を追う。その際、彼は多くの問題に直面する。特に、タバスコ州は禁酒主義であり、実際のワインが不可欠であるミサの聖祭(the Sacrifice of the Mass)を妨げるという暗黙の目的がある。そうでなければ、禁止されているにもかかわらず、ビールやハードリカーを入手するのはかなり簡単だ。 無名の "国家の裏切り者 "は "ウイスキー司祭 "であり、個人的な欠点もあるが、数年前に自分の教区で子供を作ってしまった。今、彼は束の間の滞在中に娘に会うが、懺悔の念を抱くことはできない。むし ろ、邪悪そうで不器用な少女に深い愛情を感じ、彼女を天罰から救うために全力を尽くすことを決意する。彼の最大の敵は警部補であり、彼は道徳的には非の打 ち所がないが、考え方は曲がっていない。彼は「人々のために生きている」はずなのに、村から人質を取り、神父が糾弾されずにそこに滞在していることがわかれば、彼らを射殺するという計画を実行に移す。若い頃に教会で嫌な思いをしたこともあり、彼の追跡には個人的な要素もある。 神父のほうは、自分の不甲斐なさを痛感しながらも、出会った貧しい農民たちの宗教的ニーズに応えるために逃亡を続けてきた。復讐に燃える警部補の手から彼 らを救うため、彼は山間の国境を越えて、より厳格でない隣国へ行かざるを得なくなる。この間、彼は二度、警部補に出会う。一度目は村での一斉検挙のとき、 そして二度目は酒飲みとして投獄されたあとだった。危険な旅の末に死にかけた彼は、アメリカから来たプロテスタントの地主であるレール家の労働者に助けら れる。 旅立ちの時、司祭は以前から不信感を抱いていたメスティーソに再会す る。そのメスティーソは、国境を越えたところにいる瀕死の男の懺悔を聞くために司祭を説得する。罠だと思いつつも、司祭は聖餐の務めを果たさなければと思 う。瀕死の男に救出を促された司祭は、それでも待ち受ける警部補の手に落ちる。警部補は神父を一人の人間として恨んでいるわけではなく、むしろ賞賛してい ることを認めるが、警部補は「危険人物として」神父を射殺しなければならないと主張する。死刑執行の前夜、警部補は情けをかけ、逆賊であるホセ神父に死刑 囚の告白を聞いてもらおうとするが(極端な話、教会はそれを許可している)、ホセ神父の威圧的な妻によって阻止される。 警部補はこれで「司祭を一掃した」と確信するが、最終章で別の秘密司祭 が首都に到着する。信仰心の厚いカトリックの女性は、以前は子供たちに土着の聖人の生涯についての敬虔な小冊子を読み聞かせていたが、主人公をキリスト教 の殉教者たちのレパートリーに加え、今度はこの新しい到着者をかくまうことに同意する。 |
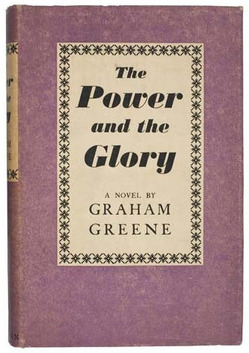 遠
藤周作『沈黙』は、発表時(あるいは翻訳を通して)グレアム・グリーンの「権力と栄光」とならび称されたんだそうです。この小説は、メキシコでカトリック
禁制の時期(クリステロ戦争
1926-1929)に、カトリック信仰の棄教のかわりに、妻と年金(社会主義なので)を受け取っている、他方、住民のニーズに応えるために、棄教したは
ずのカトリックの秘跡を授ける、元司祭の信仰と葛藤(自分はユダだと表現する)を描いたものだというのです。なかなか、興味深いです。 遠
藤周作『沈黙』は、発表時(あるいは翻訳を通して)グレアム・グリーンの「権力と栄光」とならび称されたんだそうです。この小説は、メキシコでカトリック
禁制の時期(クリステロ戦争
1926-1929)に、カトリック信仰の棄教のかわりに、妻と年金(社会主義なので)を受け取っている、他方、住民のニーズに応えるために、棄教したは
ずのカトリックの秘跡を授ける、元司祭の信仰と葛藤(自分はユダだと表現する)を描いたものだというのです。なかなか、興味深いです。1936年にメヒコに訪問し、小説の取材をした、グレアム・グリーンがメキシコ人を「嫌いになる」。他方、人類学者は、現地の生活に辟易しながらも、自ら の信仰告白「文化相対主義」により、現地人や現地文化を「呪ってはいけない」と禁止する。そのストレスが、やがて民族誌における「研究対象」となった人た ちに対するアンビバレントな気持ちに変わっていくのだろうか?かつて小説の人類学というサブジャンルを構成した人たちはおり、その解釈学的伝統に照らして 「表象対象」と「自己」について考察したのかもしれないが、まったく僕にはその記憶が残っていない。憎悪が創作ための肥やし(あるいはガソリン)だとした ら、人類学者はどうしてそのガソリンを無駄に浪費するのだろうか?これを、マリノフスキーの日記症候群と呼んでもいいだろう。 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ Greene visited Mexico from January to May 1938 to research and write a nonfiction account of the persecution of the Catholic Church in Mexico, that he had been planning since 1936.[2][a] The persecution of the Catholic Church was especially severe in the province of Tabasco, under anti-clerical governor Tomás Garrido Canabal.[4][5][6] His campaign succeeded in closing all the churches in the state. It forced the priests to marry and give up their soutanes.[7][8][9] Greene called it the "fiercest persecution of religion anywhere since the reign of Elizabeth."[10] He chronicled his travels in Tabasco in The Lawless Roads, published in 1939. In that generally hostile account of his visit he wrote "That, I think, was the day I began to hate the Mexicans"[11] and at another point described his "growing depression, almost pathological hatred ... for Mexico."[12] Pico Iyer has marveled at how Greene's responses to what he saw could be "so dyspeptic, so loveless, so savagely self-enclosed and blind" in his nonfiction treatment of his journey,[13] though, as another critic has noted, "nowhere in The Power and the Glory is there any indication of the testiness and revulsion" in Greene's nonfiction report.[14] Many details reported in Greene's nonfiction treatment of his Tabasco trip appeared in the novel, from the sound of a revolver in the police chief's holster to the vultures in the sky. The principal characters of The Power and the Glory all have antecedents in The Lawless Roads, mostly as people Greene encountered directly or, in the most important instance, a legendary character that people told him about, a certain "whisky priest", a fugitive who, as Greene writes in The Lawless Roads, "existed for ten years in the forest and swamps, venturing out only at night".[12] Another of Greene's inspirations for his main character was the Jesuit priest Miguel Pro, who performed his priestly functions as an underground priest in Tabasco and was executed without trial in 1927 on false charges.[12][14] In 1983, Greene said that he first started to become a Christian in Tabasco, where the fidelity of the peasants "assumed such proportions that I couldn't help being profoundly moved."[15] Despite having visited Mexico and published an account of his travels, in the novel Greene was not meticulous about Tabasco's geography. In The Power and the Glory, he identified the region's northern border as another Mexican state and its southern border as the sea, when Tabasco's northern border is actually the Bay of Campeche and its southern border is Chiapas. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Power_and_the_Glory |
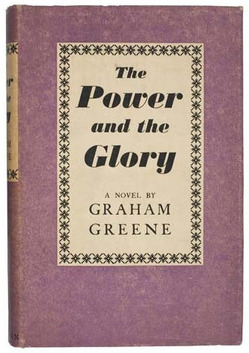 遠
藤周作『沈黙』は、発表時(あるいは翻訳を通して)グレアム・グリーンの「権力と栄光」とならび称されたんだそうです。この小説は、メキシコでカトリック
禁制の時期(クリステロ戦争
1926-1929)に、カトリック信仰の棄教のかわりに、妻と年金(社会主義なので)を受け取っている、他方、住民のニーズに応えるために、棄教したは
ずのカトリックの秘跡を授ける、元司祭の信仰と葛藤(自分はユダだと表現する)を描いたものだというのです。なかなか、興味深いです。 遠
藤周作『沈黙』は、発表時(あるいは翻訳を通して)グレアム・グリーンの「権力と栄光」とならび称されたんだそうです。この小説は、メキシコでカトリック
禁制の時期(クリステロ戦争
1926-1929)に、カトリック信仰の棄教のかわりに、妻と年金(社会主義なので)を受け取っている、他方、住民のニーズに応えるために、棄教したは
ずのカトリックの秘跡を授ける、元司祭の信仰と葛藤(自分はユダだと表現する)を描いたものだというのです。なかなか、興味深いです。1936年にメヒコに訪問し、小説の取材をした、グレアム・グリーンがメキシコ人を「嫌いになる」。他方、人類学者は、現地の生活に辟易しながらも、自ら の信仰告白「文化相対主義」により、現地人や現地文化を「呪ってはいけない」と禁止する。そのストレスが、やがて民族誌における「研究対象」となった人た ちに対するアンビバレントな気持ちに変わっていくのだろうか?かつて小説の人類学というサブジャンルを構成した人たちはおり、その解釈学的伝統に照らして 「表象対象」と「自己」について考察したのかもしれないが、まったく僕にはその記憶が残っていない。憎悪が創作ための肥やし(あるいはガソリン)だとした ら、人類学者はどうしてそのガソリンを無駄に浪費するのだろうか?これを、マリノフスキーの日記症候群と呼んでもいいだろう。 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ グリーンは1938年1月から5月までメキシコを訪れ、1936年から計画していたメキシコにおけるカトリック教会の迫害についてのノンフィクションを調 査・執筆した[2][a] 。カトリック教会に対する迫害は、反教権的なトマス・ガリド・カナバル知事の下、タバスコ州で特に深刻なものであった[4][5][6]。グリーンはそれ を「エリザベスの治世以来、宗教に対する最も激しい迫害」と呼んだ[10]。その一般的に敵対的な訪問記の中で、彼は「その日が、私がメキシコ人を憎み始 めた日だと思う」と書き[11]、また別の箇所では「メキシコに対する憂鬱な、ほとんど病的な憎しみが......増えていった」と述べている。 12] ピコ・アイヤーは、彼が見たものに対するグリーンの反応が、彼の旅についてのノンフィクションの扱いにおいて、なぜ「これほどまでに厭世的で、これほどま でに愛がなく、これほどまでに野蛮に自己閉鎖的で、盲目的」であり得たのかに驚嘆している[13]が、別の批評家が指摘しているように、グリーンのノン フィクションの報告には「『力と栄光』のどこにも、苛立ちや反発を示すものはない」。 [警察署長のホルスターに収められたリボルバーの音から空に舞うハゲワシに至るまで、タバスコ旅行に関するグリーンのノンフィクションで報告された多くの 詳細が小説に登場する。権力と栄光』の主要な登場人物はすべて『無法街道』にその前身があり、そのほとんどはグリーンが直接出会った人物か、あるいは最も 重要な例としては、『無法街道』の中でグリーンが書いているように、「10年間、森と沼地に存在し、夜だけ外に出た」逃亡者である「ウィスキー司祭」とい う、人々が彼に語った伝説的な人物である[12]。 グリーンが主人公の着想を得たもう一人はイエズス会のミゲル・プロ司祭で、彼はタバスコの地下司祭として司祭職を果たし、1927年に冤罪で裁判にかけられずに処刑された[12][14]。 1983年、グリーンはタバスコで初めてクリスチャンになり、そこで農民たちの忠実さに「深い感動を禁じ得なかったほどだ」と語っている[15]。 メキシコを訪れ、その旅行記を出版しているにもかかわらず、グリーンは小説の中でタバスコの地理について詳しく述べていない。『力と栄光』では、タバスコ の北部国境はカンペチェ湾であり、南部国境はチアパス州であるにもかかわらず、タバスコの北部国境はメキシコの別の州であり、南部国境は海であるとしてい る。 |
| ★日本語ウィキペディア「沈黙 (遠藤周作)」のあらすじ | ☆日本語ウィキペディア「沈黙 -サイレンス-」のストーリー(シノプシス)https://x.gd/0jAXV |
| 島
原の乱が収束して間もないころ、イエズス会の司祭で高名な神学者であるクリストヴァン・フェレイラが、布教に赴いた日本での苛酷な弾圧に屈して、棄教した
という報せがローマにもたらされた。フェレイラの弟子セバスチャン・ロドリゴとフランシス・ガルペは日本に潜入すべくマカオに立寄り、そこで軟弱な日本人
キチジローと出会う。キチジローの案内で五島列島に潜入したロドリゴは潜伏キリシタンたちに歓迎されるが、やがて長崎奉行所に追われる身となる。幕府に処
刑され、殉教する信者たちを前に、ガルペは思わず彼らの元に駆け寄って命を落とす。ロドリゴはひたすら神の奇跡と勝利を祈るが、神は「沈黙」を通すのみで
あった。逃亡するロドリゴはやがてキチジローの裏切りで密告され、捕らえられる。連行されるロドリゴの行列を、泣きながら必死で追いかけるキチジローの姿
がそこにあった。 長崎奉行所でロドリゴは棄教した師のフェレイラと出会い、さらにかつて は自身も信者であった長崎奉行の井上筑後守との対話を通じて、日本人にとって果たしてキリスト教は意味を持つのかという命題を突きつけられる。奉行所の門 前ではキチジローが何度も何度も、ロドリゴに会わせて欲しいと泣き叫んでは追い返されている。ロドリゴはその彼に軽蔑しか感じない。 神の栄光に満ちた殉教を期待して牢につながれたロドリゴに夜半、フェレ イラが語りかける。その説得を拒絶するロドリゴは、彼を悩ませていた遠くから響く鼾(いびき)のような音を止めてくれと叫ぶ。その言葉に驚いたフェレイラ は、その声が鼾などではなく、拷問されている信者の声であること、その信者たちはすでに棄教を誓っているのに、ロドリゴが棄教しない限り許されないことを 告げる。自分の信仰を守るのか、自らの棄教という犠牲によって、イエスの教えに従い苦しむ人々を救うべきなのか、究極のジレンマを突きつけられたロドリゴ は、フェレイラが棄教したのも同じ理由であったことを知るに及んで、ついに踏絵を踏むことを受け入れる。 夜明けに、ロドリゴは奉行所の中庭で踏絵を踏むことになる。すり減った 銅板に刻まれた「神」の顔に近づけた彼の足を襲う激しい痛み。そのとき、踏絵のなかのイエスが「踏むがいい。お前の足の痛さをこの私が一番よく知ってい る。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生まれ、お前たちの痛さを分つため十字架を背負ったのだ。」と語りかける。 こうして踏絵を踏み、敗北に打ちひしがれたロドリゴを、裏切ったキチジ ローが許しを求めて訪ねる。イエスは再び、今度はキチジローの顔を通してロドリゴに語りかける。「私は沈黙していたのではない。お前たちと共に苦しんでい たのだ」「弱いものが強いものよりも苦しまなかったと、誰が言えるのか?」 踏絵を踏むことで初めて自分の信じる神の教えの意味を理解したロドリゴは、自分が今でもこの国で最後に残ったキリシタン司祭であることを自覚する。 https://x.gd/ipqQu |
17
世紀、江戸時代初期―
ポルトガルで、イエズス会の宣教師であるセバスチャン・ロドリゴ神父[5](アンドリュー・ガーフィールド)とフランシス・ガルペ神父(アダム・ドライ
ヴァー)のもとに、日本でのキリスト教の布教を使命としていたクリストヴァン・フェレイラ神父(リーアム・ニーソン)が日本で棄教したという噂が届いた。
尊敬していた師が棄教したことを信じられず、2人は日本へ渡ることを決意する。 2人は中国・マカオで日本人の漁師にしてキリシタン(キリスト教徒)であるキチジロー(窪塚洋介)の手引きにより、日本のトモギ村に密入国する。そこでは 隠れキリシタンが奉行の弾圧に苦しみながらも信仰を捨てずに祈り続けていた。司祭はなく、「じいさま」と呼ばれる村長のイチゾウ(笈田ヨシ)だけが洗礼の みを行えるという環境だった。2人は村人達と交流を交わし、布教活動を行っていく。キチジローはかつて弾圧を受け、踏み絵により棄教を示したが、自分以外 の家族は踏み絵を行えず、眼前で処刑されたのだという。罪の意識を背負い苦しむキチジローは自分の村である五島列島にも2人の宣教師を招き、布教を広め る。そこでフェレイラの手掛かりも掴み、任務は順調かと思えた。 しかし、キリシタンがトモギ村に潜んでいることを嗅ぎ付けた長崎奉行・井上筑後守(イッセー尾形)が村に訪れ、2人の宣教師の身柄を要求した。村人達は必 死に匿ったが、代償としてイチゾウ、キチジロー、そして敬虔な信者であったモキチ(塚本晋也)を含む4人の村人が人質となった。奉行は踏み絵だけではキリ シタンをあぶり出すことは困難と考え、「イエス・キリストの像に唾を吐け」と強要した。4人の内キチジローを除く3人は棄教しきれず、処刑されることと なった。 自分達を守るために苦しむ信者達を見てロドリゴは苦悩する。「なぜ神は我々にこんなにも苦しい試練を与えながら、沈黙したままなのか―?」 ロドリゴ神父はキチジローに銀300枚で売られる。奉行所では、井上筑後守と通辞(浅野忠信)が穏当に棄教を勧めるがロドリゴは拒絶。ある日ロドリゴは海 辺に連れていかれる。そこでは、キリシタンの百姓たちが簀巻きで海に沈められ、既に捕縛されていたガルペ神父も後を追って溺死する。奉行たちはキリストの 教えで多くの民が死んでいくことを責め立てる。ロドリゴは、棄教して沢野忠庵を名乗るフェレイラ元神父と対面。フェレイラも棄教を勧める。ロドリゴの牢の そばで穴吊りの刑がはじまる。殉教者たちの苦しみの声に耐えかねたロドリゴは、踏み絵の前に立つ。ここでロドリゴは踏絵の中のイエスの声を聞く。「私を踏 みなさい」"Step on me"と聞いたロドリゴは踏み絵を踏み、棄教する。 1641 年、来日したオランダ人ディーター・アルブレヒトはロドリゴの消息を伝える。ロドリゴは井上奉行から岡田三右衛門の名を与えられ、妻を娶り、輸入品からキ リスト関係の物品を除く任務にあたった。キチジローはロドリゴの前でこっそり告解するが、守り袋に小さなキリスト像を彫った板を隠していたとして連行され た。ロドリゴは棄教を守り、日本で亡くなる。棺桶に守り刀が入れられ、仏教式の葬儀で火葬される。だが遺体が炎に包まれる直前、ロドリゴの掌にかつてモキ チから託された小さなキリスト像があった。 https://x.gd/0jAXV |
| ●セバスチャン・ロドリゴ(岡田三右衛門) ポルトガル人の若きイエズス会司祭。恩師であるフェレイラ棄教の謎を追うため、同時に、日本にキリスト教の灯を絶やさないようにするため、日本へ向か う。しかし、その後キチジローの裏切りで長崎奉行所に捕らえられ、そこで信仰を続けるか棄教するかの重い選択を迫られることになる。モデルとなったのはイ タリア出身の実在の神父ジュゼッペ・キアラ。キアラは棄教後、斬首刑に処された下級武士、岡本三右衛門の名を与えられ、江戸小石川の切支丹屋敷で生涯を終えている。 ●フランシス・ガルペ ロドリゴとともに日本に渡った同僚のポルトガル人司祭。のち別行動をとるがやはり奉行所に捕らえられ、ロドリゴの見る前で殉教する信徒たちとともに命を落とす。 ●クリストヴァン・フェレイラ ポルトガル人の高名な神学者にしてイエズス会の司祭。日本で布教中に捕縛され、「穴吊り」の拷問に屈して棄教したと伝えられる。歴史上実在した人物。 「この国は(すべてのものを腐らせていく)沼だ」とする台詞は当時の流行語にもなったが、日本の精神的土壌とキリスト教との背反問題へ向き合った者たちを 描いた武田清子『背教者の系譜 -日本人とキリスト教-』(岩波新書、ISBN 9784004121626)[1]も引用している。 ●ヴァリニャーノ マカオに駐在するイエズス会の司祭。日本での布教経験があり、ロドリゴとガルペに日本における苛烈なキリスト教弾圧を伝える。史実で著名なイエズス会員に天正遣欧少年使節を率いたアレッサンドロ・ヴァリニャーノがいるが、島原の乱よりも前の1606年に没している。 ●キチジロー ロドリゴがマカオで出会った日本人の男。ロドリゴを日本へ連れて行くが、やがて彼を裏切り、長崎奉行所にロドリゴの居場所を密告する。しかしその後もロドリゴの後を追い続け、彼の許しと告解の秘蹟による神の赦しを乞う。遠藤周作は後に、この人物は彼に幼児洗礼を受けさせた母親を裏切った自分自身をモデルにしたと述べている。 ●井上筑後守 幕府大目付・宗門改役。「穴吊り」というもっとも有効に棄教に結びつける拷問方法を編み出した人物として恐れられているが、本人は温厚な初老の政治家。自らもかつては熱心なキリスト教徒であった[2]。ロドリゴにキリスト教はこの国では根付かないと説く。 ●通辞 井上の部下で奉行所の通訳を務める男。ロドリゴに対しては説得という形で棄教を勧め、時に議論を戦わせるが彼もまた神学校で学び洗礼を受けた過去を持つ。彼が棄教したのは宣教師の傲慢で日本人への侮蔑意識に満ちた態度に失望したためであることが作中で示唆されている。 https://x.gd/ipqQu |
セバスチャン・ロドリゴ神父 - アンドリュー・ガーフィールド フランシス・ガルペ神父 - アダム・ドライヴァー 通辞 - 浅野忠信 キチジロー - 窪塚洋介 井上筑後守 - イッセー尾形 モキチ - 塚本晋也 モニカ - 小松菜奈 ジュアン - 加瀬亮 イチゾウ - 笈田ヨシ クリストヴァン・フェレイラ神父 - リーアム・ニーソン[6] ヴァリニャーノ院長/イエス・キリスト(声) - キアラン・ハインズ[7] ヨヘイ(トモギ村の村民) - パンタ ツネ( 〃 ) - 片桐はいり ヒロ( 〃 ) - 伊佐山ひろ子 クロ(五島の男) - 三島ゆたか ハク( 〃 ) - 竹嶋康成 ナカ(キチジローの母) - 洞口依子 タエ(キチジローの妹) - 石坂友里 ハル( 〃 ) - 佐藤玲 キチタ(キチジローの弟) - 藤原季節 モスケ(五島の老人) - 江藤漢斉 奉行所の侍 - 菅田俊 奉行所の侍補佐 - 真柴幸平 井上筑後守随行人 - 藤田尚弘 牢番1 - 青木崇高 牢番2 - 渡辺哲 牢番3 - 斎藤歩 大男 - 高山善廣 牢役人 - EXILE AKIRA 牢番人- 上西雄大 武士 - SABU 岡田三右衛門の妻 - 黒沢あすか 老僧 - 中村嘉葎雄 https://x.gd/0jAXV |
| ジュゼッペ・キアラ(Giuseppe
Chiara、慶長7年(1602年) -
貞享2年7月25日(1685年8月24日))は、イタリア出身のカトリックイエズス会宣教師。キリシタン禁教令下の日本に潜入したが捕らえられ、迫害と
拷問の責め苦に耐えかねて強制改宗により棄教し、岡本三右衛門(おかもと さんえもん)という日本名を名乗って生きた。 1602年、シチリア王国のキウーザ・スクラーファニで生まれる[1]。 江戸幕府はいわゆる「鎖国令」(ポルトガル商船の追放およびオランダ人の出島移住)を布告した直後であり、キリシタン禁教令によりキリスト教は厳しい弾圧 下にあった。寛永10年(1633年)、ポルトガル人イエズス会司祭クリストヴァン・フェレイラが長崎で捕らえられ、穴吊りの拷問を受けて3日後に棄教、 最初の転びバテレンとなっていた[2]。 この知らせを聞いてキアラを含む10名のイエズス会士が日本へ向かった。一行はマニラを経由し、寛永20年(1643年)1643年6月27日に筑前国に上陸したが、すぐ捕らえられて長崎へ送られ、同年8月27日には江戸へ移送された[2]。 宗門改奉行・井上政重の邸に預けられ詮議が行われ、この詮議にはフェレイラ(沢野忠庵)自身も協力した[2]。また大老酒井忠勝・老中堀田正盛らの邸でも 取り調べが行われ、その際は将軍徳川家光も自ら検分したという。キアラはフェレイラと同じく穴吊りの拷問を受け3日後に棄教、その後信仰に戻ると言っても 許されることはなかった[2]。 正保3年(1646年)、小石川の切支丹屋敷(現在の東京都文京区小日向1-24-8[3])に移され[2]、同じく入国を企てた仲間とともに収容され た。幕命により岡本三右衛門という殉教した下級武士の後家を妻として娶り、そのまま岡本三右衛門の名を受け継いだ。幕府からは十人扶持を与えられたが、切 支丹屋敷から出ることは許されなかった。その後もたびたびキリシタンおよび宣教師についての情報を幕府に提出し、宗門改方の業務も行った。 晩年の延宝2年(1674年)、役人からキリスト教の教義について書くことを要求され『天主教大意』3巻を執筆した[2]。後にジョヴァンニ・シドッティ を尋問するにあたり新井白石がこれを研究し、白石はシドッティへの尋問に基づき『西洋紀聞』を著した[2]。またキアラは寺の檀家になることも求められた が拒否している[2]。 幽閉43年の後、貞享2年(1685年)7月25日に病死。遺体は荼毘に付され(当時のキリスト教では火葬は禁忌とされていた)[4]、切支丹屋敷に近い 小石川無量院に葬られた[2]。墓碑には「入専浄真信士霊位、貞享二乙丑年七月廿五日」とある。墓石の笠が司祭帽に似た特徴的な形で、戒名の「入専」は 「ジュセン」と読み「ジュゼッペ」から取られたものとされている[2][4]。 https://x.gd/IGlgu |
|
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆ ☆
☆