健康の概念と医療人類学の再想像
Re-imagining the Concept of Health and Medical Anthropology
健康の概念と医療人類学の再想像
Re-imagining the Concept of Health and Medical Anthropology
私は1980年代中頃に中米ホンジュラスにおいて青年海外協力隊に参加し、村落に おける保健衛生教育に従事した。私は具体的な実践を通して人びとが「健康」についてどのように考え行動しているか調査し、帰国してそれに関する論文を執筆 した(「ヘルスプロモーションとヘルスイデオロギー」『日本保健医療行動科学会年報』5巻、1990)。
そこでわかったことは、現地の人たちは「健康」をたんに病気のない状態と して意味づけるだけで、我々が教育されてきたような積極的な意味をそのことばには持たせなかった。「健康」の概念が外部から導入されるときに、そこではさ まざまなレベルでの抗争がおこるというのが、その論文の主旨であった。しかし、なにか重要なことを忘れていたのではないか。
村落の人びとにとって、保健計画を通して、健康は積極的に求めるものだと いうイデオロギッシュな教化は、人びとが健康を消極的な価値としてしかみないという認知的なバリアーによって阻止された。また保健省の職員から「無知」と 呼ばれる人びとが当局の考えるようには行動を変容させなかったことによって、その計画が無力化されていた。しかし当の本人たちは、それを抵抗とは自覚して おらず、たんに不便なだけ、馴染まないだけと表明していた。
ただし外部から持ち込まれる薬の配分や簡易便所設置のための無償や低金利 の補償金は、そのような「無知」から逃れ「学習」した啓蒙的な住民に与えられるために、その教化の軍門に下るという御しがたい魅力も当然のことながら生じ る。古い考えは終わり、新しい考え方に馴染むことが開明的だとみる人も登場する。
しかし、大多数の人たちがおこなう「無知」というサボタージュは、健康の 言説を普及させようとする外部の人たちにとって、露骨な彼らへの挑戦と映る。ようやく設置したモダンな簡易便所を人びとは受け入れようとしないし、作って も使わない。このことは、保健省当局にとってはゆゆしき問題である。なぜなら、そのプロジェクトは外国政府の借款によって運営されているからであり、プロ ジェクトの成否は、今後の援助のインセンティブにも影響する。
啓蒙を通しての合意という形態をとりながら、その背後には、強制的に他者 の主体を形成することが試みられること。このような言説の構図を外部からのマイルドな強制として理解したい。人びとのサボタージュが抵抗の実践として見え てくるゆえんである。
だが、外部から導入される健康の言説に対抗する住民という図式の描き方に は限界がある。この対抗図式というのは、実は土着的な概念を尊重しながらプロジェクトを遂行していかねばならない保健省職員としての私の臆見の産物ではな かったのか。ある対立した概念を立て、一方の概念を他方の概念に優越化させながらも、最終的にプロジェクトをより洗練した場として止揚できる概念装置とし て医療人類学の効用を説こうとすることではなかったのか。だからこそ、この図式は「啓蒙」にもとづく住民の合意形成をうながす有益な理論的根拠となりえた のである。では、この場合の医療人類学の使い方は、はたして強制ではなく同意によって人びとを導く道具になりうるだろうか。
私には、そうは思われない。「土着」と「近代」の調停者として振る舞い、 一方的に近代医療の浸透と展開を許してしまう医療人類学の言説は住民を教化し良導する植民者のそれとかわらない。この批判は、医療人類学それ自体が、どの ような社会状況のもとで生まれてきたのかということを思い起こさなければ、論点をより明確にすることはできない。
医療人類学は二つの反省的動機から1960年代後半に生まれてきたと言われ る。一つは西洋近代医学を批判し改良することである。そこで、土着医療から学ぼうとした。このモーメントは、新しい医療を想像する自己の主体の確立のため に、そのモデルを土着医療に求めることであった。もう一つは、土着社会に対してより適切に西洋近代医療を広めることができるのかという現実の要請に応える ことであった。これは国際公衆衛生運動の中で生まれてきた動きである。新しい西洋医療を受容する他者の主体をどのように外部から形成できるかということを 試みたのである。一方で自己の主体形成に他者をモデルにすることを求めておきながら、他方で他者の主体の改造を夢見る。これらの主体形成をめぐるモーメン トは最初から分裂していたのである。
近代的な主体の担い手として私は、ホンジュラスの村落民の保健活動を通し て、彼らのきわめていい加減な主体のあり方——ひとときの餌にはありつくが、それを持続的なものとして受容しない態度、場当たり的でその場かぎりの反応な ど——を改造しようと試みていた。このような私の自画像が最近になるまで見えなかったのは、変わるのは彼らで、人類学者としての自分自身ではないという信 念を私が保持していたからである。しかし、外部からのアンビバレントな脅迫にも屈しない——サボタージュに似た——柔軟な彼らの西洋近代医療の「健康」の 言説に対する身のこなし方こそが、医療人類学がその誕生の時期に抱えていた反省的動機のひとつ、すなわち西洋医療を批判的に乗りこえる主体形成のモデルに ふさわしい。
内部と外部という対抗図式を導入し、そこに立つことで調停者としての位置
を確保してきたこれまでの医療人類学者の自画像を私は拒否し、医療人類学運動がもっていた批判的な反省作用を救出することのきっかけとしたい。
私が仲間とともに志向した医療人類学の目的はそこにあり、それをここに再確認したのである。
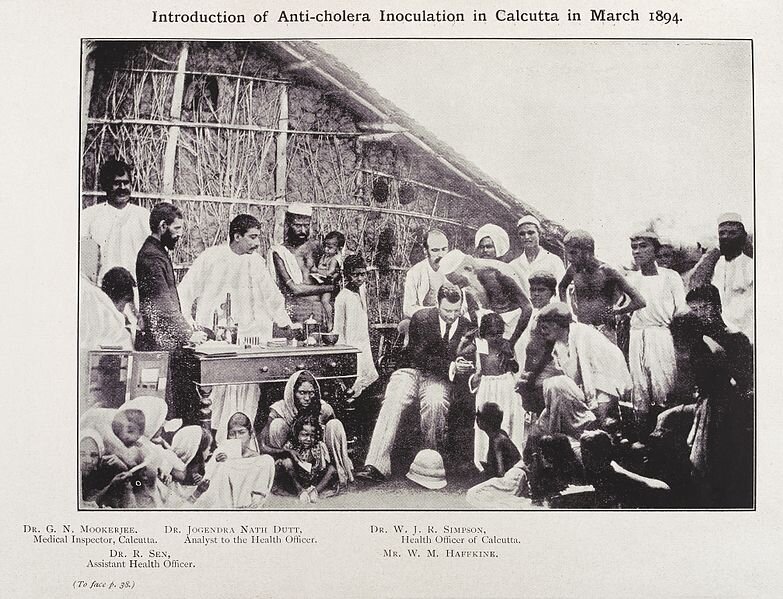
【初出】『医療人類学』第21号、 p.1、1996年
リンク
文献
その他の情報