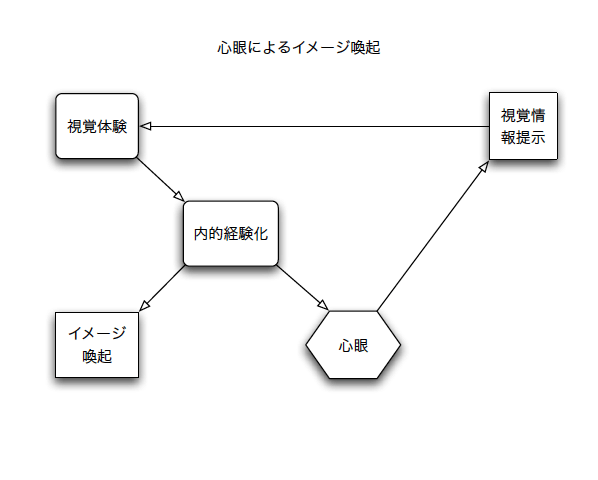臨床コミュニケーション研究における〈聴覚優位〉の問題
Does listening take more dominant than acting in studies for human communication in practice?

臨床コミュニケーション研究における〈聴覚優位〉の問題
Does listening take more dominant than acting in studies for human communication in practice?

「はじめにことばあり、ことばはかみとと
もにあり、ことばはかみなりき」(ヨハネ
1:1)の言葉は、インスクリプションとしての言葉ではない、聴覚表象としての言葉なのだ。その意味で、真理を聴覚上の現象としたベンヤミン(「独逸悲劇
の起源」序文)は正しく、世界の事物に(発語を通して)名前を与えたアダムが、哲学の文字通りの《父》なのだ……(父の声)
現場力(げんばりょく)とは、実践の現場 で人が協働する時に育まれ、伝達することが可能な技能であり、またそれと不可分な対人関係的能力などの 総称のことをさす(→出典「現場力」)。これに関する対概念は「文字という視覚優位のコミュニケーション」である。
伝統的哲学は、長い間、視覚優位の伝統を 取り続けてきた。例えばホワイト ヘッド(Alfred North Whitehead, 1861-1947)は次のようにいう。
"Philosophers have disdained the information about the universe
obtained through their visceral feelings, and have concentrated on
visual feelings." -
(伝統的)哲学者たちは、内臓の感受を通して得られた宇宙についての情報について蔑み、視覚感受に(のみ)専心してきたのです。Whitehead,
Process and Reality, p.121, The Free Press, 1929.
従って、伝統的哲学の呪縛から解放される
ためには、視覚以外の〈思考〉のメタファーを、取り上げる必要があった。臨床哲学者たちが好んで主張す
る「聴く力」はその典型例である。
臨床コミュニケーション研究における、現場のコミュニケーション能力のうち、聴覚の意義を強調するものがいる。彼らの主張に耳 を傾けてみよう。
「……語ること以上に、聴くことに神経を向ける必要があるということ。わたしは、哲学を〈臨床〉という社会のベッドサイドに置いてみて、そ のことで哲学の、この時代、この社会における〈試み〉としての可能性を探ってみたいとおもうのだが、そのときに、哲学がこれまで必死になって試みてきたよ うな「語る」——世界のことわりを探る、言を分け/る、分析する——ではなく、むしろ「聴く」ことをこととするような哲学のありかたというものが、ほのか に見えてくるのではないかとおもっている」(鷲田 1999: 46-7)。
聴覚のメタファーが、戦略的に優位になる のは次の2つの理由があるように思われる。
まず、従来のコミュニケーション研究にお ける視覚のメタファーの優位である(ミッシェル・フーコーのいう「臨床のまなざし」を想起したまえ)。 視覚→識字能力→ロゴセントリズムという論理に対する批判を含意した、臨床コミュニケーション研究の特異性や優位性を強調することができることである。し かし、臨床のまなざしを、近代理性の論理パターンとして特権化したフーコーの議論は、同じ時期のパリ病院学派を素朴なまでに実証的に検討したA・アッカー クネヒトからみれば、臨床的まなざし(視覚優位の思考)はいつも同じパターンの理性的論理を引き出すというよりも、ある特定の歴史的社会的文脈のなかで、 我々とは異質な思考を生み出す可能性について、十分思慮深い議論をしているとは思えない[→拙稿「臨床 概念の誕生」]。
次に、聴覚はアンプでも使わない限り、あ るいは自然の音でも鳴り響かないかぎり、限りなく肉声を聴くことが重要にされているように思われるから だ。肉声を聞き取るためには、(数メータ以内が妥当な範囲だが)近づかなければならない。聴覚のメタファーに訴えることは、身体的親密性を喚起する。
もちろん「聴く力」「傾聴することの重要 性」が聖典化してしまったり、そこで思考が止まってしまえば、それは聴くことを通して、さまざまな人間 のコミュニケーションの知恵について考えようとするこのユニークな試みを逆に台無しにしてしまうことは、論をまたない。
リンク
文献
《創世記とヴァルター・ベンヤミン》
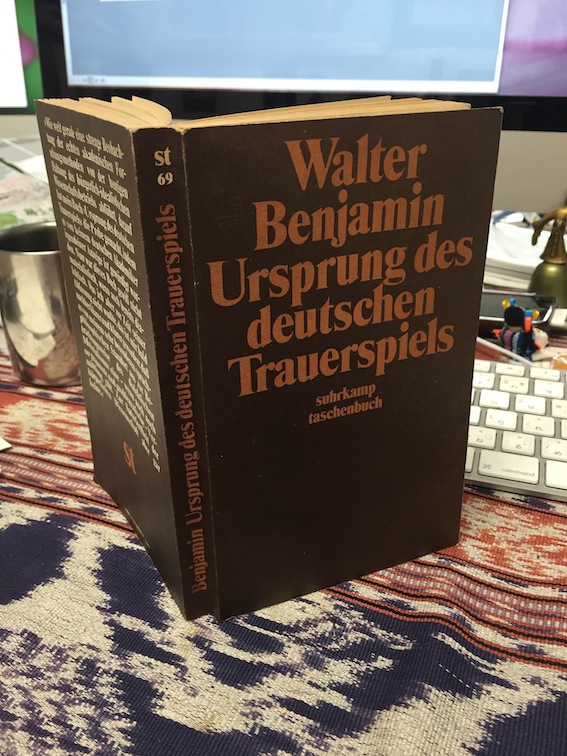
「はじめにことばあり、ことばはかみとと もにあり、ことばはかみなりき」(ヨハネ 1:1)


【補論】視覚メタファーと着想力