
強い文化概念としての部族
Tribe as strong cultural concept

部族(ぶぞく, トライブ: tribe)という用語とその概念は、長く、植民地主義の遺産 として宗主国から植民地の人びと(people)の集団の種別概念として扱われてきた。またその歴史的事実もそれに対応している(Gregory 2003)。それゆえ、部族の概念は、外部から押し付けられたカテゴリーであり、ある意味で19世紀のフィクションにちかい概念であるという批判も当然指 摘されてきた(Freid 1975)。
"Nation-states seized positions of political power a long time ago, and like corporations more recently with their economic power, label and disparage those who are left out from participation and involvement. The word “tribe” is one such label, and the term fits a wide diversity of people, most of whom never regarded themselves as being a member of a “tribe.” Still, those people have conceptualised, designed, and experienced strategic and tactical relationships with the proverbial powers that be and managed to survive, and frequently, thrive. We can learn much from tribes, the origin, use, and futures of tribes, and their rich experiences in living" (Gregory 2003:5).
「国民国家は、はるか昔に政治権力を掌握し、最近で
は経済力を持つ企業と同様に、参加や関与から排除された人々をレッテル貼りし、軽蔑している。「部族」という言葉は、そのようなレッテルのひとつであり、
この用語は、そのほとんどが自分自身を「部族」の一員とは決して考えていなかった、多種多様な人々に当てはまる。それでも、こうした人々は、ことわざにあ
るような権力者たちとの戦略的かつ戦術的な関係を概念化し、設計し、経験し、生き残るだけでなく、多くの場合、繁栄を遂げてきた。部族の起源、用途、未
来、そして豊かな生活経験から、私たちは多くのことを学ぶことができる」
このため、ポストコロニアルな現今においては、その ような用語を差し控えるべきであるという主張が当然のことながら出てくる。それに代わる政治的に脱色され用語がエスニシティである。部族(トライブ)がも つレッテルの劣等性や侮蔑性を嫌うという統治者側の「配慮」もある。しかし、この概念は国民国家体制なかで少数民族や先住民を管理する便利な用語になりか ねないという批判がある。現に、劣等性や侮蔑性とは無関係に、(元)部族の人びとが、自分たちのカテゴリーを堂々と名乗っている事実もある。例えば、下記 に事例で示してあるMashpee Wampanoag Tribeの人びとがそうである。
ジェームズ・クリフォードは、部族の概念には、アン ビバレントだが力強い意味が当事者側からの申し立てと自己カテゴリーの命名としてあり、このことは無視できない歴史的事実であると同時に、文化人類学が学 ぶべき「観点」だと主張する。
「文化と部族という民族誌カテゴリーが弱体化された ものであるとはいえ、最近のより流動性が高いエスニシティの言説に組み込まれるべきだなどと私は主張しているわけではない。エスニシティは通常考えられているように、多元主義的な国家内部で多様性を 組織するのに都合のよい脆弱な文化概念である。部族という制度は、いまだに先住民的匂いをぷんぷんと発し、18(ママ: 19?)世紀には、部族と同義語であったネイションを連想させるのであり、そう易々と現代の多民族的、多人種的国家に統合され るものではない。インディアン諸部族が主張している復権的な文化=政治的アイデンティティは、アイルランド系アメリカ人やイタリア系アメリ カ人のアイデンティティよりも、はるかに顛覆的なものだ。 北米先住民は、アメリカ合州国の完全市民であることと完全にその外側に位置づけられることのどちらとも要求してい るのである」(クリフォード 2003:467:原注(5)——太字は原文の強調;下線は引用者による強調)
文献
アメリカ先住民に対する行政訴訟権の付与 (1946)
アメリカの先住民の土地は「通商交易法 (Nonintercourse Act(1790, 1793, 1796, 1799, 1802, and 1834)」により連邦議会の承認がないかぎりは転売が禁止され ていた。もちろん法が有名無実化していたのは歴史が示す通りである。アメリカ議会はアメリカ 先住民への差別的な法的地位の撤廃の一環として、過去に先住民に損害を与えた行為に対しても行政訴訟を認めた。ただし、それを訴える権利があるのは「部 族、バンド、もしくは他の帰属集団」にのみインディアン請求委員会への提訴を認めるものだった。この、「部族、バンド、もしくは他の帰属集団」の定義は、 ジュリアン・スチュアードの後の著作 "Theory of Culture Change," (1955)に結実するような理論的研究の成果の反映だと、考えられている(ローゼン 2011:102-103)。
Joint Tribal Council of the Passamaquoddy Tribe v. Morton, 528 F.2d 370 (1st Cir. 1975)
土地の権利請求運動でもっとも有名な訴訟は「パ サマ クォディとペノブスコットの両部族の訴訟」であり、この訴訟は、1981年にカーター大統領の直接介入もあり1981年に和解した(クリフォード 2003:350)。
先住民が土地の権利要求をおこなった時に根拠にした のは、「通商交易法 (Nonintercourse Act(1790, 1793, 1796, 1799, 1802, and 1834)」であった。
See: https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Tribal_Council_of_the_Passamaquoddy_Tribe_v._Morton
マシュピーの土地返還請求訴訟(1976年)
マサチューセッツ州ケープゴッドの一地区に対して、 連邦裁判所に提訴された土地訴訟。ここで問題になったのは、訴訟を提訴した人たちが、はたして「マシュピー先住民」であるかどうかをめぐるものであった (クリフォード 2003:12章)。この訴訟は、「マシュピー・トライブ〈対〉ニューシバリー社訴訟(Mashpee Tribe v. New Seabury Corp., 592 F.2d 575 (1st Cir. 1979))」といわれる(クリフォード 2003:351)。原告は「マシュピー・ワンパノアグ部族 (Mashpee Wampanoag Tribe)評 議会」、被告にあるニューシバリー社とは、この土地の大規模開発会社であるが、その被告総体は、会社のほかに、土地を所有するマシュピー住民と保険会社、 事業家、資産家なども含まれた集合的なものである。
この裁判には、ローレンス・ローゼン("Law
as Culture," 2006
の作者)も関わっている。クリフォード(2003)による、ローゼンの評価には傾聴すべきものがあるので、ここで記載しておこう。:「彼[ローゼン]は、
当事者対抗主義が規制するものや倫理的ジレンマを論じ、部族、バンド、国家、そして、チーフ[ダム?—引用者]のような語句を定義することの根深い問題を
議論した。ローゼンは訴訟行為に関する人類学者の役割はおそらく増大することになると示唆し、それゆえ学者たちは危険ではあるが避けられない領域に自らを
参入させる準備が必要であると助言している」(クリフォード 2003:467:原注(3))。
しかし、マシュピーの場合は、その先住民性が問われ のであった。数々の失敗を重ねて、2007年に内務省はようやくマシュピーの連邦承認を得た。
"Mashpee Tribe v. New Seabury Corp., 592 F.2d 575 (1st Cir. 1979), was the first litigation of the Nonintercourse Act to go to a jury.[1] After a 40 day trial, the jury decided that the Mashpee Tribe was not a "tribe" at several of the relevant dates for the litigation, and the United States Court of Appeals for the First Circuit upheld that determination (the panel included two judges from the landmark Joint Tribal Council of the Passamaquoddy Tribe v. Morton (1975) panel). / The Mashpee, as a tribe and individually, attempted to re-litigate the issue several times without success.[2] In 2007, the Department of the Interior granted federal recognition to the Mashpee,[3] and the tribe and the town of Mashpee, Massachusetts entered into a settlement agreement.[4]" source: http://bit.ly/1jF7YN6
| 62■部族=ト
ライブ概念について 部族(ぶぞく、トライブ、トリブ等)は、異民族を表現する方法として定着した「人の集合呼称」である。しかし部族という用語には、多義的な意味と話者の価 値判断が付与され変遷を遂げてきたために、現在では統一した術語としては使えないものになってしまった、というのが我々の共通認識のようにも思える。もち ろん、それゆえ、可能性のある用語ということもできる(池田 Online)。 当初、トライブを人類史における政治権力の誕生を複 数のクランの競合で説明(用例:部族国家、部族法典)し、やがてオーストラリア先住民などの内婚制を説明するために婚姻クラスの説明として、この用語が使 われた。また19世紀の社会進化論では、社会組織の進化をバンド・部族・首長制・国家という発展段階で説明したりしたが、今日では言語や文化を共有する民 族集団(エスニック・グループ)の同義語としても使うことがある。部族概念が(歴史を除いた)非西欧の社会に使われたために、西欧列強が植民地を分割統治 するために部族概念を「発明」し、既存のものを再編成・再加工したという主張もある。それゆえ部族という言葉は、現在でも利用可能だがが、その際に概念規 定を明確にしないと――まさに酋長(しゅうちょう)と用語と同様に――聞く人に大変混乱を招く概念となります。 このため、ポストコロニアルな現今においては、そのような用語を差し控えるべきであるという主張が当然のことながら出てくる。それに代わる政治的に脱色さ れ用語がエスニシティである。 法律学者のL・R・ウェザーヘッドは、人類学者の 「ありふれた定義」ではなく、エスノヒストリーの定義と法律学のそれ――北米の先住民との政治的取り決めのなかで鍛えられてきた「部族」概念――を調停 し、フレキシブルな基準を作ろうともくろみる。この発想は、実証主義に鍛えられているにも関わらず経験から抽象的概念を紡ぎ出そうとする人類学者よりも、 より現実に即した法律のプラグマティックな使い方に「部族」の用語を馴染ませようとする方向性を示唆している。 "Because the socio-political situations in which indigenous Americans were found were varied and numerous, references in this paper to "'tribe' in the ethnohistorical sense" refers not to a stock anthropological definition of "tribe" but rather than to the peculiar history of each Indian group. Thus, in speaking of reconciling the legal and ethnohistorical meanings of "tribe," we are talking about deriving a legal standard flexible enough to include the different social, political and cultural arrangements of each American Indian group."(Weatherhead 1980:5の脚注27)。 「先住アメリカ人についてこれまで明らかになった社会政治的状況は多様でおびただしいものであるので、この論文で取り上げた参照文献における〈エスノヒス トリーの意味でいう「部族」〉とは、「部族」のありふれた人類学的定義ではなく、むしろ、それぞれのインディアン集団の固有の歴史をさすものである。した がって「部族」に関する法律とエスノヒストリーの意味を調和することについて語るのであれば、個々のインディアン集団の社会的、政治的、文化的の多様な布 置を包含するのに十分に柔軟な法律上の基準を引き出すことを、私たちは語ることになる」 部族(トライブ)がもつレッテルの劣等性や侮蔑性を 嫌うという統治者側の「配慮」もある。しかし、この概念は国民国家体制なかで少数民族や先住民を管理する便利な用語になりかねないという批判がある。現 に、劣等性や侮蔑性とは無関係に、(元)部族の人びとが、自分たちのカテゴリーを堂々と名乗っている事実もある。例えば、マサチューセッツ州ケープゴッド のMashpee Wampanoag Tribeの人びとがそうである。 ジェームズ・クリフォードは、部族の概念には、アンビバレントだが力強い意味が当事者側からの申し立てと自己カテゴリーの命名としてあり、このことは無視 できない歴史的事実であると同時に、文化人類学が学ぶべき「観点」だと主張する。 Gregory, Robert J., 2003. Tribes and Tribal: Origin, Use, and Future of the Concept. Stud. Tribes Tribals, 1 (1): 1-5. Fried, Morton. 1975. The Notion of Tribe. Menlo Park, CA: Cummings Publishing Company. 文化の窮状 : 二十世紀の民族誌、文学、芸術 / ジェイムズ・クリフォード著 ; 太田好信 [ほか] 訳、京都 : 人文書院 , 2003(The predicament of culture : twentieth-century ethnography, literature, and art / James Clifford, Cambridge, Mass. : Harvard University Press , 1988) Weatherhead, L.R., 1980. What Is an "Indian Tribe"? The Question of Tribal Existence. American Indian Law Review Vol. 8, No. 1 (1980), pp. 1-47. 池田光穂(Online)「強い文化概念としての部族」http://www.cscd.osaka- u.ac.jp/user/rosaldo/151003tribe&culture.html |
リンク
文献
Do not paste, but [re]think this message for all undergraduate students!!!
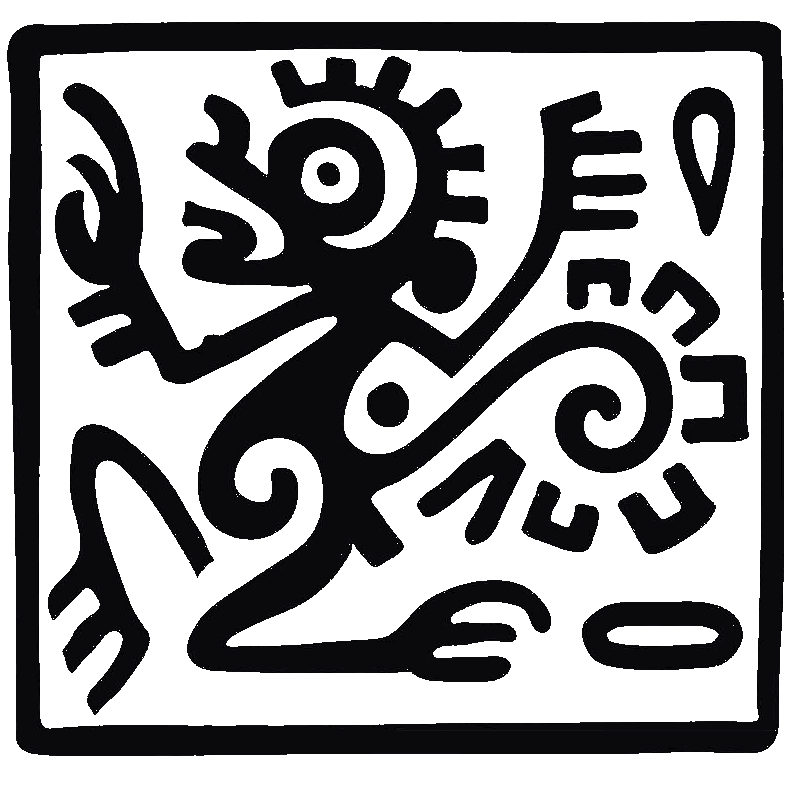

++
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099