——文化人類学の研究倫理上のレッスンとして考える——
Siichi
IZUMI, 1915-1970, is positioned in left end. Source: http://peruvianart2014.blogspot.jp/2014_08_01_archive.html
泉靖一とアイヌ民族
——文化人類学の研究倫理上のレッスンとして考える——
Siichi
IZUMI, 1915-1970, is positioned in left end. Source: http://peruvianart2014.blogspot.jp/2014_08_01_archive.html
このエッセーの目的は、文化人類学の研究倫理上の レッスンとして、泉靖一(1915-1970)と彼が十勝で出会ったサハリン・アイヌの女性がおこなった調査者に対する異議申し立て(minority group objection against cultural anthropologist)について考える。そのため、このエッセーは泉のフィールドワークにおける「挫折」の理由探究ではない。また、アイヌ側の抗 議に屈しなかった泉の研究倫理上の背徳についての歴史的検証でもない。泉の研究者としての倫理性云々を事後的に「検証」すること「擁護」することでも、ま してや「非難」することでもない。むしろ、泉がフィールドワークにおいて出会った「調査される側の声」になぜ耳を傾けることができなかったのか?について 私はこだわりたい。そして、現在の我々からある種の妥当な解釈を与えることの不当性や恣意性の付与にまつわる我々が持ち得る「偽善感」を克服し、泉になり 代わり我々は、この抗議にどのように応答することができるのか?——時間を遡行して、あるは現在になりつつある過去(池田 Online)として、泉が1950年代に直面したアイヌの女性からの異議に対する、現在の文化人類学者からの応答の問題として考えてみたい。
***
泉靖一が1950年代にアイヌ調査をする過程のなか で、サハリン・アイヌ(樺太アイヌ)のインフォーマントに叱られる話はよく知られている。誰がどのような文脈の中で語られたのかという言及はないが、(日 本の)文化人類学者が、アイヌ研究に対して、当事者への差別と貧困を抜きには〈中立で客観的な〉調査がなりたたないことを示した政治的糾弾とも言える重い 批判であり、比較的よく引用されるエピソードである。以下は、木名瀬高嗣(1997:11)からの引用である。
「おめたちは,カラフト・アイヌがどんな苦労をして いるか,どんな貧乏をしているかしるめえ,それにのこのこ,こんなところまで出掛けてきて,おれたちの恥をさらすきか?それとも,おれたちをだしにして金 をもうけるきか,博士さまになるきか!!」(泉 1971:39)
これは上掲の木名瀬の論文では、このインフォーマン トの語り口を転写したものとして泉靖一の「アイヌと人 種的偏見」(河野本道編)(旭川人権擁護委員連合会)(編)『コタン痕跡:アイヌ人権史の一断片』Pp.37- 43, 旭川人権擁護委員連合会、1971年という出典をあげている。清水(2009:45, n78)によると、泉は1949年の出来事としているが、アイヌ綜合調査が行われた(1951年〜)と齟齬をおこしているが、そもそも「泉の発言は 1960年代末の状況における発言と解釈すべき」としている(清水 2009:45, n78)。
日本の文化人類学(=民族学)の歴史では、このアイ ヌ当事者からの糾弾に、アイヌの当時の社会状況の調査は継続不可能と判断して、「その後ブラジル移民調査などを経て南米先史学に『転向』した泉は、アイヌ の『現在』から一切手を引く。そして『アイヌ研究者』としての彼は、明治以前のアイヌの『本質』的な姿を少しでもうかがうことのできる(と彼が考えた) 『アイヌ絵』の集大成という方向へ進んでいった(泉編 1968)」(木名瀬 1997:11)というのが、定番の泉のストーリーとして語られる。泉編(1968)とは彼の編んだ『アイヌの世界』鹿島出版社のことである。
泉は1950年に日本民族学協会が計画した「アイヌ 民族綜合調査」に参加し、1951年8月に杉浦健一(1905-1954)との沙流アイヌ集落でフィールド ワークをおこない、調査上の困難にであっていた。それは「半世紀以前の彼らの社会生活はあとかたなきまでに変貌」していたと記している(泉 1952:45)。
さて、木名瀬(1997)の論文から15年後に書か れた山 崎幸治(2012:368)でも、その出典箇所の指示はないものの、このアイヌからの「非難」された状況を描いている。
「後年、泉は総合調査について「私は後半で挫折し た」と述べ、その原因として、親族組織とiworに関する調査で十勝に住んでいた樺太アイヌのもとを訪ねた際に、対応のために畑から戻った女性から、「お めたちは、カラフト・アイヌがどんな苦労をしているか、どんな貧乏をしているかしるめえ、それにのこのこ、こんなところまで出掛けてきて、おれたちの恥を さらす気か?それとも、おれたちをだしにして金をもうける気か、博士さまになる気か!」と非難されて雷に打たれたよりも激しい衝撃をうけ、その時以来アイ ヌの人々に会うのがつらくなり、アイヌの実態調査を断念してしまったと回想している[泉一九七二]」(山崎 2012:368)。
山崎は引用文に引いたように泉靖一著作集から、この 非難の状況を引いている。つまりその出典は、泉靖一(1972)「遥かな山々」寺田和夫編『泉靖一著作集:文化人類学の眼』7,読売新聞社、Pp.159 -383、とある。
木名瀬(1997)と山崎(2012:367)の指 摘を総合すると、1950(泉は1951年と記載——泉 1972:306-307)年度からはじまる「アイヌ民族総合調査」——漢字では「綜合」と使われているが同じ意味である——によるものであり、先のカラ フト・アイヌからの「非難」を受けるまえの情景が泉によって描かれている。
「翌(1952)年、十勝川の川口の十勝太(とかち ぶと)にカラフトから引き揚げてきたカラフト・アイヌをたずねたときのことである。私は、彼らから直接、カラフト・アイヌの親族組織とイオルのことについ て聞きたかった。それは夏の暑い昼さがりで、来意を告げると、畑にでていた主婦を子供がよびにいった。汗だらけで帰ってきた彼女に、私は突然たずねた無礼 を詫び、要件を語った。一瞬、彼女の顔色が変わると、つぎのように叫びはじめた」(泉1972:308)。この後に、先の「おめたちは、カラフト・アイヌ がどんな苦労をしているか……」が続く。
その後は、山崎の先の要約のとおりだが、実際には つぎのような文章がつづく。
「私は雷にうたれたよりも激しい衝撃をうけ、ただあ やまって調査をせずに帰ってきた。その時以来、アイヌの人々に会うのがつらくなり、学問の上では興味はもっていても、アイヌの実態調査を断念してしまっ た。こんなとき、これまで歩いてきたフィールドワーカーとしての自分に大きな疑いを抱かざるをえなくなるのである」(泉1972:308)
じつは、この「遥かな山々」というエッセーは『アル プ』誌に1967年8月から1970年6月まで掲載されたもので、泉の証言は15年以上を経て記録されたということになる。木名瀬(1997)によると、 このアイヌ調査を継続することの断念から、南米研究への向かわしめるというストーリーになるだろうが、実際の『アルプ』の連載のこの次の号は「南アメリカ の日本人研究」ということになっている。日本国内の調査者である先住民からの「非難」を海外の調査対象への転換というのはわかりやすい説明だが、事情はさ らに複雑である。そのことを木名瀬(2016)が最近かかれた論文のなかで再度検証しているからである。
20年後の木名瀬は、国立民族学博物館に所蔵されて いる泉靖一のノートなども検証している。他方、件の「非難」については、1969年に出版された『フィールドワークの記録:文化人類学の実践』講談社現 代新書から引いている。同じ「非難」を何度も引用するのは気が引けるが、これが印刷されたもののなかでは一番古く、かつ重要なので、そのことを厭わず引用 する。
「北海道の十勝太にあるカラフト・アイヌ系の老女を
訪ねて、カラフト・アイヌについて私のもっている学問上の疑問をただそうとした。そのとき彼女は大声で私をどなりつけた。
——おめたちは、カラフト・アイヌがどんな苦労をしているか、どんな貧乏をしているかしるめえ、それにのこのこ、こんなところまで出掛けてきて、おれたち
の恥をさらすきか? それとも、おれたちをだしにして金をもうけるきか、博士さまになるきか!!
私は雷光に打たれたよりも激しい衝撃をうけ、ただあやまって調査をせずに帰ってきた。それいらい、アイヌ系の人びとにあうことが苦痛だし、フィールド・
ワークを試みようともしない。こんな考え方は、フィールド・ワーカーとしては不適当で、もっと説得し、もっと執念をもって、苦しくてもあきらめてはいけな
いのかもしれない。ところが、私にはそれができないのである。(泉 一九六九:四——五頁)」(木名瀬 2016:178-179)
それ以降が発話者を除いてカラフト・アイヌのままに
なっているが、この初出(?)は、カラフト・アイヌ系という呼称でよばれている。
木名瀬のこの新しい記述にあるように、彼の1997年のカラフトアイヌからの批判が泉の眼を海外にむけさせるという説明は、生前の祖父江孝男(1926-
2012)から論文の公刊後に「事実に反している点」を指摘されている(木名瀬
2016:179)。そして、祖父江から木名瀬への1997年10月22日付け私信を引用する。
「泉さんは一九五三年に帰国したのですが、アイヌに どなられたのはこの年の夏の事で、泉さんと私の二人で、ある樺太アイヌのおじいさんから話を聞いていたところ、たまたま訪れていた隣家の四〇代の威勢のよ いおばさんからどなられ、おじいさんもひるんで奥へひっこんでしまったという次第だったのですが、その当時、泉さんはこの出来事に大きなショックを受けた という風もありませんでした」(木名瀬 2016:180)。
そして、先の民博のアーカイブの中のフィールドノー ト(1953年8月29日)につぎのような記述を認める。貴重なもので、通常の人にはなかなかアクセスできないので、木名瀬のこの記述はきわめて重要な指 摘である——その後、民博でもアクセス可能になったと聞く(木名瀬氏私信 2016年11月5日)。
「朝食をすませると、火事がおきた。祖父江君とかけ つけて消火につとめる。男が全部浜に行っていたために、かけつけた人は女と老人のみ。樺太の人の話を聞ふと[中略]おばあさんのところにゆく。話を聞いて いよいよ要点の母系の問題にふれていると一人のアイヌ女性が大声でどなりこみ「戦争に負けたのに、何故戦争に負けた自分たちをアイヌとして調査するか」 「自分らはよいが子供たちが差別を、つけることをどうしてくれる」「何故スピーカーで土人と云った。歌なんど放送して、アイヌの祖先のごうをさらすのだ」 「何故アイヌが胴が長いなどと、つまらぬことを云って、シャモと差別するか」「何故つまらぬことしらべて金もうけするや」……「どうして調査するならば、 もっと有益な生活の為になるような調査をしないか」立つづけにまくし立てられる。お婆さんはこそこそと引きこんで、針をつかいはじめ、白々しい空気が流れ る。XXさんと二人で色々説明したがどうにもならず、調査を打ち切ってOOさんの家に帰り昼食をすまして、祖父江君が迎えに行くと不在、あきらめていると ××氏来り、仕方ないと……なげく。ところがひょっこり婆さんがやって来 る。余りアネチヤの剣幕がひどいので畑に出て、来たと云ふ。それから話はすらすらとはこぶ。しかし話は親族の問題に限定されて、Iworなどの経済生活と は結びつかない。※[XX、OO の人名は引用者による伏せ字]」(木名瀬 2016:180-181)。
山崎からの引用にもあるように、iwor, Iwor(イオル)とは、狩り場などを中心としたアイヌの伝統的な生活空間(=生業形態を内包したエコシステムを想起されたい)のことであり、政府の「ア イヌ文化振興等対策推進会議」等においてもイオルの再生は、重要な政策課題になっているものである。
木名瀬は、この泉のフィールドノートから、(1)祖 父江の記憶していたインフォーマントはおじいさんではなく、おばあさんであったこと、そして(2)泉は、このアイヌの女性からショックをいきなり得ること がなかったが、自分の記憶を回顧するうちに「複数の記憶を(意識的にせよ無意識的にせよ)混同して語っている可能性がある」(木名瀬 2016:181)と記述する。そして、藤本英夫の『泉靖一伝:アンデスから済州島へ』平凡社(1994)を脚注で援用しながら、泉がしばしば出来事の年 代を記載には「大雑把なところがある」と伝記の著者藤本は記している。
さて、泉靖一による後年の潤色があろうがなかろう が、アイヌからの人類学者への抵抗や批判はここまでである。1959年を皮切りに泉らは岡田宏明をともなってオンコロマナイを含む各地の考古学調査に従事 する。
木名瀬によると、1959年8月17日から同年9月 7日にかけて毎日新聞で18回連載された 「アイヌの国を訪ねて」は毎日新聞の藤野好太郎記者の署名記事であるが、そこに記載されたアイヌとは、貧困にあえぐ「痛ましい姿」がみられるのみである (木名瀬 2016:183-184)。


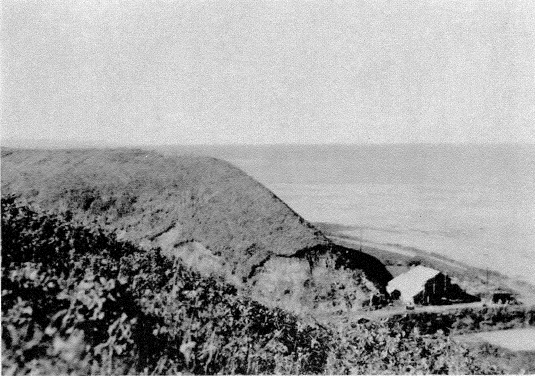
The Onkoromanai
Archeological Site #2, near the Cape of Soya(出典:(左)北海道縄文のまち連絡会)右(2葉:泉靖一・曽野寿彦(編)(1967)より)
1967年に公刊されたオンコロマナイ遺跡の調査報 告書のなかにみられる泉のアイヌの「人種的集団」の未来は決して明るいものではない。また、泉が当時痛みを感じないまでも記憶には鮮烈に 残ったはずであろう、抗議するアイヌの女性の姿の片鱗もみられない。それを木名瀬から孫引きする。
「アイヌの民族誌学的研究つまり伝統的文化の復元を めざすような研究に寄与しうる、アイヌの集団または報告者は、残念ながらほとんど存在していない。ただ、言語だけに限るならば、わずかに数名の報告者はい るけれども、彼らも遠からず人間の運命にしたがうことになるであ ろう。しかし、人種的集団としてのアイヌ社会は、地方によっては和人社会と複合して存在 し、両者のあいだに、差別意識や対立意識が存在していることはいなめない事実であった。このようなアイヌの人種的集団にたいする社会人類学的研究は、ごく わずかしかなされていないので、今後私たちにあたえられた、大きな課題であることを、痛感せざるをえなかった。(泉・曽野編一九六七:一頁)」(木名瀬 2016:186-187)[下線は池田による]。
泉の『フィールドワークの記録』が出版される前年の 1968年の春、清水昭俊は、河野本道(当時、東大文化人類学院生)の紹介で、静内で短い調査をおこなった。その後で、同年9月に東京と京都で開催される 第8回「国際人類学・民族学会議」による白老でのエクスカーション案内で英文で記載されたパンフレットの内容に抗議文※を送ったという——残念ながらその 典 拠は書かれているが、なにをどのように批判したのかは木名瀬論文からは不詳である(渡辺 1969;荻中ら 1972)。ただし、清水昭俊が翌年、東大の大林太良研究室で発行されていた『東南アジアの民族と文化』(2号、Pp.49-64)に「人 類学的調査についてのノート」を寄稿していることを、木名瀬は次のように引用する。
「私はここがアイヌ系住人の部落だからというより
は、北海道の農村の生業や、人種的出自を異にする人々の構成する集団の性格等を知りたくて行ったのだが、アイヌ系の人々はどうしても私がアイヌ研究にやっ
て来たとしか受け取ってくれなかった。彼等にとっては、やってくる和人の学者は全てアイヌ研究者なのだ。そして彼等はアイヌ研究者を、アイヌと和人という
歴史的対立の中に位置づけているようだった。即ち彼等の説明によれば、アイヌが和人に敗けたのは、アイヌが文字を知らなかったからである。和人は文字を
知っているから、アイヌから財産を盗み取ることができた。こうしてアイヌの文化は敗れ、滅びる運命にある。それを、滅ぼした当の和人が、文字の形にして記
録し、後世に伝えている。云々。アイヌ者は彼等の意識の中でもアイヌ差別の一環として受け取られている。更に調査を困難にするのは次のような事情である。
差別に苦しめられて来たアイヌ系住民のとりえた殆んど唯一の対処策は和人への形質的文化的同化であった。外見からも、一所に暮してもアイヌ系の人だと分ら
なくなること、これが彼等の念願である。ということは、彼等はアイヌ系住民ではありたくない、何故ならば、差別が行なわれるのは全て自分等がアイヌ系だか
ら、ということである。彼等には、彼等がアイヌ系であると指摘されることすら苦痛になっている。これに対して、アイヌ研究は相手がアイヌ系住民だから行な
われる。彼等にとってはアイヌ研究者がやって来ることすら差別の現れなのであり、苦痛なのである。人種その他の差別のある所では、そして人類学者が差別す
る側にidentifyされる限りは、同じ困難が待ち受けていよう。このような所では、差別をしないで調査することは至難の業であろうし、調査には余程慎
重にとり組まねばならぬであろう(清水 1968:60-61)——木名瀬の脚注によると(清水 2006:24-25)にも再掲されている」(木名瀬
2016:188-189)
ここに書かれているのは、アイヌからの和人に対する わずかばかりの非難と告発——「アイヌから財産を盗み取ること」——であるが、そのほとんどは、引用文からみるかぎり、そのような差別や苦悩へのアイヌ側 の和人への従属とそれを中長期的に回避するための同化という戦略のようなものである。差別と搾取の構造の中での和人=調査者、アイヌ=インフォーマントの 関 係は、現実の和人/アイヌの政治経済的搾取と並行関係にあるために、差別しない調査は「至難」であり「慎重」を要するものだと指摘されているにすぎない。
木名瀬によると、泉が「挫折」譚を語るようになるの は、さまざまな抗議活動を通した1968年のアイヌとの関係との悪化と不可分ではないようだ。
「泉が例のアイヌ研究における「挫折」のエピソード
を語り出すのは、彼が「最悪の」と振り返った1968 年におけるそのような背景と無縁ではなかったと思われる——『遥かな山々』p.
370-383。そしておそらくは、1959年の「いまわしい」調査がほとんど人々の口の端に上らなくなってしまったことも、泉自身が錯誤して語った「挫
折」譚が流布されたことと関連しているに違いない」(木名瀬 2015:129/2016:189)[『遥かな山々』の註は引用者=池田が補った]。——泉靖一は1970年11月15日に55歳で急逝する。
もちろん1972年8月での第26回日本人類学会・ 日本民族学会連合大会シンポジウム(会場:札幌医科大学)における太田竜らによる演壇占拠事件、同年 10月23日の風雪の群像・北方文化研究施設爆破事件という政治状況もあった当時、対話や(謝罪や赦しにもとづく)和解という今日では当たり前になった 「紛争解決手法」——そもそもアイヌ研究というものが始まって以来「研究者と被調査者の関係」を紛争状態とみなした者などいまい——について思いを馳せる ことなど不可能だったにちかいだろう。
※なお今日においてもなお旅行代理店が”hairy Ainu”と人種主義的に表現することがあることに関しても、しばしば抗議の声があがるのは周知の事実である。
***
このことを考えることは、文化人類学がインフォーマ ントとの関係において「固有の文化」なるものを強迫的に析出する、これまでの文化人類学のパラダイム維持が果たして健全な営為であったのかどうかというこ と の再検討にもつながる。和人の文化人類学者とカラフト・アイヌの女性のディスコミュニケーションの問題は解決しているとは言い難いが、このすれ違い には、文化人類学者とフィールドで日々生活をする調査対象の人々の関係性をつねに更新し、対話を継続してゆくためのヒントが豊富に伏在しているように思え る。
***
言うまでもないが、アイヌによる調査や「文化の剥 奪」について、アイヌの当事者が反発していることは以下の山川力[やまかわ・つとむ](1980)からも容易に推測できる。いわゆる「抵抗の日常的実践」 と言っても過言ではない。
北海道新聞社の山川が1968年2月に、観光アイヌ
のコラムについての記事において「浅薄な観光演出に反発してほしい」と書いたところ、日高のアイヌのFさんという人から投書がきて、「趣味でアイヌを語る
郷土史家にも、ユーカラをあつめにくるテープレコーダーをかついた学者先生にも、また墓掘りやトレンチ掘りの考古学者にも、アイヌ系住民はつよく反発して
いる。…… 現実に、コタンという未解放部落で、前近代的な身分差別と偏見のために、貧困においやられ、娘やむすこたちが都会に逃避(やがて敗残のすがた
でかえることになるが)、家や部落が崩壊しつつある、という時点で、つよく反発している」(山川
1980:9)。
このFさんは、『北方群』という同人誌を発行してい る人だと山川は指摘している。
『北方群』については、「アイヌ民族と文化人類学研 究の現在」で引用した、「日本キリスト教団北海教区 アイヌ民族情報センター」のブログに下記のような記録がある。
「1970年7月発行のアイヌ民族の同人誌『北方
群』創刊号の巻頭文(向井喜美恵)の内容は胸を打ちます。『北方群』第2号(1972年)の巻頭言「ウタリに対する不当差別の告発を」には、HBCテレビ
ドラマ『お荷物小荷物』によるアイヌ差別に対し、北海道ウタリ協会石狩(札幌)支部が抗議して放映中止と謝罪をさせた。このような不当な差別に対し直接行
動を取りはじめたのは画期的なことだ、と記述していることを紹介しています」http://bit.ly/21HcZ8u
つまり、アイヌからの抗議というのものは、泉靖一が 受けたものも、以前からどうも存在してきたようである。また、差別糾弾が恒常化していた1970年前後も引き続き続いていたということだ。そして、このよ うな事態の最大の問題 は、泉が受けた抗議を、文化人類学(当時は民族学や考古学)は、およそ20年以上あるいは現在までを含めると半世紀以上なにも真摯にうけとめてこなかった ことになる。さらに悪いことに、それに対する、学会そのものの公的な「応答」すらないということなのである。このような無反省な学者の姿を、山川は次のよ うに批判的に述べる:
「コタンからコタンへの足を棒にした学者の中にも、
第二、第三の松浦武四郎をついにみずじまい。いわゆる〈アイヌ研究〉なるもののナゾというべきだ。/〈アイヌ研究〉は、ひとつには、植民地原住者をおいま
わすクセのあるヨーロッパ・アメリカ型民族学の限界を、そっくりうけついでいる、ということなのか。あるいは、明治・大正・昭和を貫流しているあの陰湿さ
が、学者たちを臆病にさせ、実感を文字にすることをためらわせたのか。/しかも、それが、ひとびとの認識をゆがめ、おくらせることに奉仕することになる。
のみならず、それは、アイヌをいつまでも偏見・差別の世界にほおりこんでおく、という結果をまねいている。/政治にはなんのかかわりもなさそうにみえた
〈研究〉が、じつは、きわめて政治的だったのである」」(山川 1980:71)。
学問に特定の政治的偏向を持ち込んではならぬという が、それは学問を政治と無縁にすることではあるまい。むしろ、どのような学問でも政治的であることは避けられない問題であり、そのことを理解するからこそ 「研究倫理」という課題が浮上するのである。とりわけ、文化人類学は、人を対象に する学問であり、調査対象となる人と、調査者の間には、さまざまな恩恵や利害関係が絡まる。ましてや、文化人類学という学問は、営利を目的とする学問では ない。人々の生活と文化を、その人たちが理解するように再学習すること、そこからわかったことを、より多くの人と共有すること。それが、学問を通しての、 他者に対する共感と理解というものである。
泉靖一とアイヌ民族の具体的な邂逅がどのようなもの
であり、また、その出会いがどのようなものであったのかを、正確に甦らせることは不可能かもしれない。しかし、この出会いは日本の文化人類学(ないしは民
族学)の「歴史」(ベンヤミン)にとって非常に重要な出来事である。日本で文化人類学研究をする者にとって、長い間、重要な研究対象であると同時に重要な
同胞・隣人・先生でありつづけてきたアイヌ民族との関係を問い直そうとする時に、泉靖一が我々にもたらす経験は、歴史上のひとつのエピソードを超えた、さ
まざまな意義を我々にもたらすであろう。
補足説明
文献中にある泉(1971)「アイヌと人種的偏見」 は、泉が生前、旭川人権擁護委員連合会に寄稿を約束していたが、1970年11月15日に急逝したために、河野本道が、それまでの泉のアイヌに関する既存 の発表媒体のなかからアイヌに関する記述を編んだアンソロジーである。引用記録は(1)『アイヌの世界』鹿島研究所出版会、189ページ、1968年。 (2)『フィールドワークの記録』講談社、4-5ページ、1969年。(3)『岡本太郎・泉靖一対話・日本列島文化論』大光社、179-183ページ、 1970年。
泉 靖一略譜(→こちらで今後改訂作業します「泉靖一」)
■前史:初めてのアイヌ志願兵(帝国海軍)1925年——東京朝日新聞大正14(1925)年10月30日夕刊2面
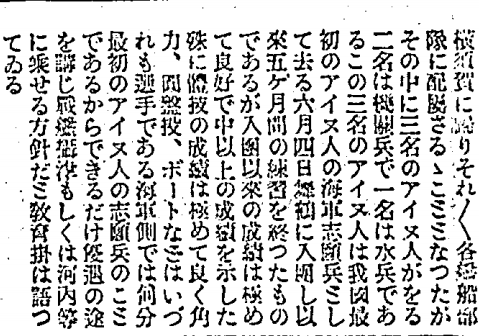
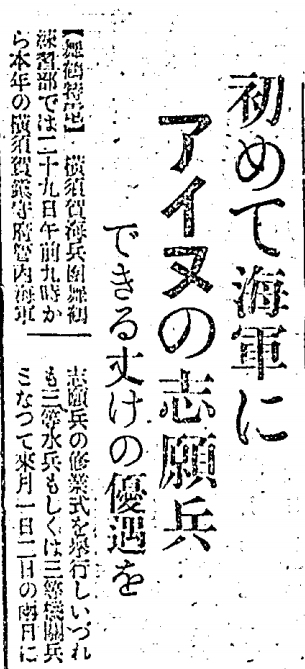
++
リンク
文献
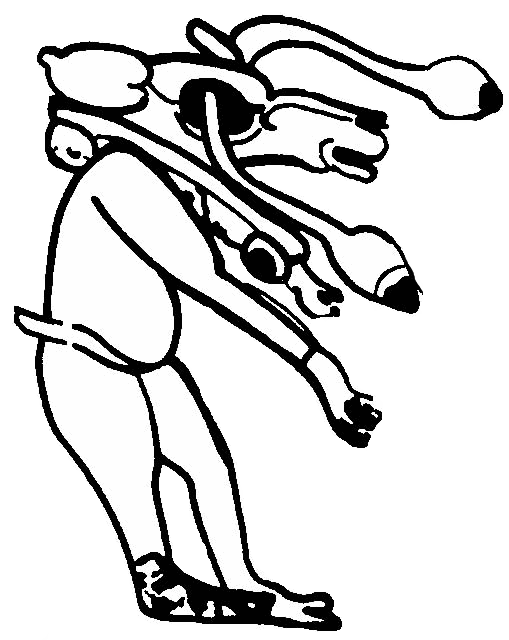
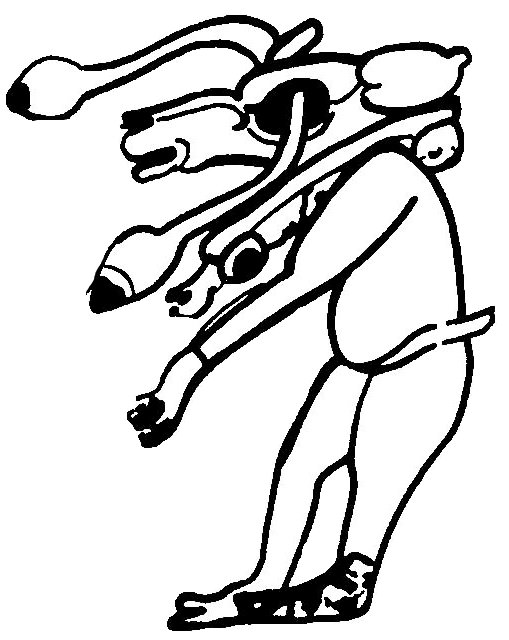
(c)Mitzub'ixi Quq Chi'j. Copy&wright[not rights] 2016
Do not paste, but [re]think this message for all undergraduate students!!!