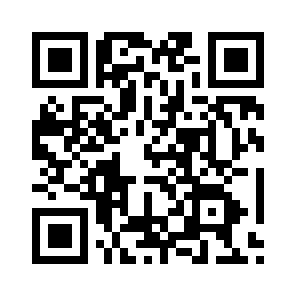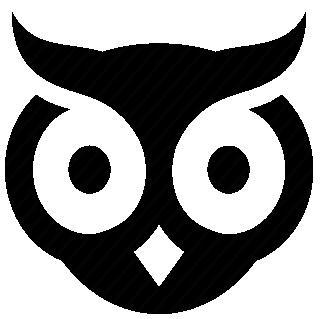はじめによんでください
研究倫理入門
The syllabus of
Introduction to Research Ethics
for Young
Students

池田光穂
■ま
ず自分自身を欺[=あざむ]いてはいけません。自分自身こそが
最も欺きやすい人間だからです。このことに気をつけましょう。自分を欺かなくなった
ら、ほかの科学者を欺かないようにすることは容易です——リ
チャード・ファインマン(1974)
■研究倫理・研究公正は1人では学ぶことが困難かもしれません。その理由は、
倫理というものは人と人の間になりたつ規約だからです。でも、3人以上のグループなら、研究倫理は、研究というものを経験した人であれば、必ず学び、そし
て身に付けることができます。授業は終わりましたが(日付が00月00日とあるのは皆さん自身が作るものです)、自習者は同僚とチームを組んで以下で提供されているテーマで30分議論、30分討論で一通りの
「研究倫理(Research Ethics)」を学ぶことができま
す[英語版はこちら]。
■以
下の資料は、The National Academy of Science, Engineering, Meicine, 2009. On Being a Scientist: A Guide to
Responsible Conduct in Research, Third Edition, The National
Academies Press. に収載されている事例集からの引用と改変したものです。もともとは、大学の学部ならびに大学院(修士)向けのアクティブラーニングの授業用のシラバスから、発展し、みなさんが各個
人あるいは自発的組織したグループで学べるようにしたものです。
00 授業のすすめ
方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[対話・討議によるワークショップ技法]
01 科学者になるというこ
と・・・・・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[研究倫理の3つの公理]
02 科学の社会的基
礎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[計画の変更(原著:5)]
03 実験テクニックとデータの扱
い方・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[データの[恣意的]選別(原著:10)]
04 科学における価値
観・・・・・・・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[エラーの発見(原著:14)]
05 利害の衝
突・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[研究資金申請書における捏造(原著:17)][利
益相反]
06 出版と公
開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[それは剽窃だろうか?(原著:18)]
07 業績評価とその表
記・・・・・・・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[十字路にたつキャリア(原著:22)]
08 オーサーシップとはなにか
1・・・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[学生を被験者にしたテスト(原著:25)]
09 科学上の間違いと手抜き行
為・・・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[実験プロトコルの変更(原著:26)]
10 不正行
為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[論文公表のやりかた(原著:32)]
10 オーサーシップとはなにか
2・・・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[だれが論文著者として掲載されるか(原著:36)]
11 倫理違反とその対
処・・・・・・・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[商業的営利チャンス(原著:42)]
12 フィールドワーク研
究・・・・・・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[フィールドワークの倫理]
13 動物実
験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[動物実験(解説)/動物実験倫
理講義録]
14 社会に埋め込まれた科学者
(および有機的知識人論)・・・00月00日 00時00分〜[関与することの対立(原著:45)]
15 まとめの議論:科学者になる
ということ・・・・・・・・・00月00日 00時00分〜[科学者の定言命法、あるいは主観的実践原則]
16 【番外】先住民の遺骨等の返
還に関する文化的主権と研究倫理・・・・00時00分〜[アイヌ遺骨等返還の研究倫理について]
17 【番外】研究上起こり得る人
権侵害について・・・・・・・00
月00日 00時00分〜 Violation
ageist Human Rights in Academic Research Process
18 【番外】科学研究におけるレントシーキング・・・・・・・00月00日 00時00分〜
19 英語で学ぶ研究倫
理・・・・・・・・・・・・・・・・・・[︎Ethics for Academic Research (in
English)]
★討論(研究倫理事例検討集より)上のリンクと重複してい
る場合が
あるので御了承ください。
︎▶︎研究倫理の3つの公理▶︎︎計画の変更(原著:5)▶データの[恣意的]選別(原著:10)︎▶︎︎エラーの発見(原著:14)▶︎研究資金申請書における捏造(原著:17)▶︎︎それは剽窃だろうか?(原著:18)▶十字路にたつキャリア(原著:22)︎▶学生を被験者にしたテスト(原著:25)︎︎▶︎実験プロトコルの変更(原著:26)▶︎︎論文公表のやりかた(原著:32)▶だれが論文著者(クレジット)として掲載されるか(原著:36)︎▶︎︎商業的営利チャンス(原著:42)▶︎関与することの対立(原著:45)▶科学者の定言命法、あるいは主観的実践原則︎︎▶︎研究倫理授業の討議用の資料集▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎
関連リンク(サイト内リンク)
︎▶︎︎▶︎▶研究倫理ABC:2012年琉球大学大学院医学研究科でのFD講演のス
ライドです▶フィールドワーク研究の倫理︎▶︎︎教
員・研究者はこちらに飛んでください!▶︎組織管理者のための研究倫理教育実施チェックリスト▶︎︎公的研究費の管理・監査のガイドラインと、その考え方について▶︎ある組織での研究費の不正使用事例に対する組織の対応▶公的資金の取り扱い方に関する「常識」について知ろう!︎︎▶︎倫理委員会:Institutional Revew Board▶︎︎日本物理学会第33回臨時総会(1967)の決議三の
ゆくえ▶有
機的知識人論︎▶著作権譲渡についての覚書︎︎▶︎政府系の研究倫理情報・ニュース・資源▶︎︎研究倫理教育教材2015(出典:大阪大学
2015.06.10)▶︎研究倫理データベース:研究倫理や生命倫理を考え
るためサイト内リン
ク集です▶︎︎不正論理入門(introduction to
logical fallacies)▶あれっ?おかしいぞ?!」から
出発する研究倫理(pdf
ファイルです:パスワードなし、約900KB)▶︎︎学術論文投稿者の倫理規定▶︎チャレンジャー号事故とファインマンさん▶倫理的・法的・社会的連累(ELSI)︎︎▶︎▶︎
︎Ethics for Academic Research
(in English)▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎
関連リンク(サイト外)
「日
本学術会議」声明:科学者の行動規範について(2006年10月3日)
日本文化人類学会倫理綱領
日本民俗学会倫理綱領
日本社
会学会倫理要綱
教科書
[資料集:ResearchEthics2011.pdf]
パスワードは授業でお知らせします。ネット利用の方はリンク先の情報に従い御照
会ください。
米国科学アカデミー編『科学者をめざす君たちへ』池内了訳、化学同人、2010年(原著はインターネットで講読できます:下記のリン
ク参
照)On
Being a
Scientist: A Guide to Responsible Conduct in Research: Third Edition
参考書 授業時に適宜紹介します。
ステネック、ニコラス著『ORI 研究倫理入門:責任ある研究者になるために』山崎茂明訳、丸善、2005年:研究倫理授業の討議用の資料集
Nicholas H. Steneck (2007), ORI Introduction to the Responsible
Conduct of Research, Revised Edition, Washington, D.C.: Office of
Research Integrity (ORI). https://ori.hhs.gov/sites/default/files/rcrintro.pdf
成績評価
研究倫理の説明と定義(→出典)
研究倫理(Research
Ethics)とは、研究活動がなんらかの社会性をもち、かつその成果が社会に影響を与える時に、社会がその成員とりわけ科学者集団に対して、なんらかの
規範を与えて、それを適切に制御(コントロール)することを意味します。通常、人が考えたり、研究したりすることは、研究する人の独自で自
由な活動であ
り、それが何らかのかたちでコントロールされることは、一見理
不尽なような印象を与えます。しかし、社会性をおびた人間の属性から、研究が他の人々になんらかに危害を及ぼすことは、その量や数の多寡にかか
わらず常に起こりうる危険性をもっています。さらに、研究が「人類を幸せにする」という社会的使命を標榜し、社会から承認され研究費や声援(モラルサポー
ト)を受けている場合において
は、研究倫理上の規範をを、研究者自身あるいは研究集団そのもののが作り、それを遵守することは避けられません。他方で、研究の正しさ、客観性の担保、そ
して「人類の福利」などの基準などは、時代や社会によって相対的に決まるという特性があるために、研究倫理上の正しさや正当性の基準もまた変化します。そ
れゆえに、研究倫理は、研究者集団およびそれを見守る社会によって、定期的に管理、点検
され、必要に応じて改訂してゆく作業が不可欠です。[池田光穂「研究倫理」医療人類学辞典]
研究倫理を考える
近代科学やそれを実用化した革新的技術は飛躍的に発展し、人間や社会に対して多大な恩恵をもたらしてきた一方で、環境・生態系の破壊や大量
殺戮などの問題を引き起こしてきたことも歴史的事実です。科学や技術はまた、政治権力や巨大ビジネスと結びつくとき、様々なマイノリティの人権の侵害につ
ながるということもあったし、その成果が万人に享受されないことも珍しくありません。自由かつ独創的で、質の高い科学研究は、そうした人間生活や社会との
関係を視野に収めた研究倫理に裏づけられたものでなければならなりません。言い換えれば、科学研究は、それが人間や社会に対してどのような影響を及ぼすの
かを意識し、絶えず自らの営みを反省することが必要となるのです。従って、科学研究における責任ある行動が、誠実さ、正確さ、効率性、客観性といった基本
的な価値を尊重するものでなければならないことを踏まえ、科学研究の健全な発展を図ることが研究に従事する者一人一人に求められます。
今、なぜ、研究倫理か
近年、成果至上主義や利潤追求などの圧力によると思われる科学研究の不正行為が頻発する傾向が見られます。科学研究において不正行為が行わ
れると、健全かつ正しい科学研究の発展が阻害されるだけでなく、研究に対する社会の信頼が損なわれ、多くの人々に対して重大な悪影響がもたらされる可能性
があります。それゆえ、多くの国では、不正行為を予防し、かつ起こった場合にこれを適切に処理して再発防止に務めるために、国家レベルあるいは各大学・研
究施設がそれぞれ指針を定め、研究不正行為に対処するための研究倫理委員会を設置しています。これに対して日本では、研究の不正行為が頻発している中で、
十分な対応ができているとは言えない状況にあり、政府や学術会議あるいは各大学・研究施設がようやく取り組みを開始しているところです。
研究倫理観の向上のために
本講義では、医学・工学のみならずすべての大阪大学大学院で研究者を目指す大学院生(3年次以上の学部学生を含む)を対象として、研究開発
(R&D)の社会的意味、研究実践上における公正、研究者集団と社会における公正、研究室内の人間関係における公正などについて多角的に考察しま
す。そこでは、科学研究を取り巻く社会的な課題が具体的に取り上げられ、受講者自身が自分自身の問題として考える姿勢を身につけること、そして受講者各自
の研究倫理観を向上させることが目指されます。
この授業科目は、本年度(2011[平成23]年度)をもってこのタイトルと内容での最終年度となる可能性があります。次年度以降の開講タイト
ルと内容は未定です。
【資料】
【クレジット】研究倫理入門(けんきゅうりんりにゅうもん, 科学者になるということ)Introduction to Research
Ethics for Young Students
- 授業科目名: 研究倫理 単位数2 単位(2010年度コミュニケーションデザイン科目)
- 英語標記: Research Ethics
- 授業コード:XXXXXX
- 受講人数: 15 人
- 担当教員: 池田 光穂
- 対象 3年次以上の学部学生、全研究科大学院生、社会人(3名程度)
- 開講時間等:【第1学期】水曜5限(16時20分〜17時50分)
- 開講場所:オレンジショップ(豊中キャンパス:基礎工学部
i (アイ)棟1階)
- キーワード:学問、科学研究、倫理、研究上の不正行為、倫理的・法的・社会的連累
(ELSI)、科学の社会的信頼性、応用倫理学[語彙集]
- 授業の目的 医歯薬学系、工学系などの研究に関わる倫理的諸問題の全体像を把握し、具体的なトピック
に即して、研究に従事する者として踏まえておくべき倫理原則と規範を習得する。
- 講義内容:教科書に準拠した話題による参加者どうしの討論と発表およびコメントによるフィードバックという対話型授業で以下のような観点
に関
す
る議論をおこなう。
- リンク先のPdfファイルの開錠にはパスワードが必要です。授業でお知らせします。ネッ
ト利用の方はリンク先の情報に従い御照会ください。
【関連授業】人文社会系のための研究倫理入門(リ
テラシーG)2018
授業ポータル(池田)に戻る
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099
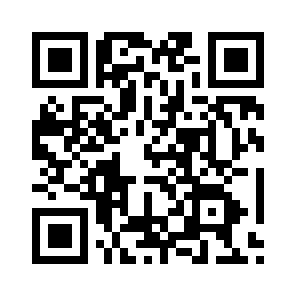
このページのQRコード
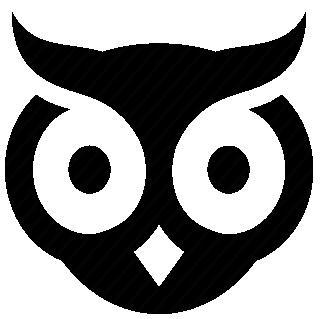
[ひな形のhtmlファイル:この授業
の利
用者には直接関係ありません]