 |
『小島の春』断章
On "Spring
in a small island," 1938, by Dr. Masako Ogawa
 |
《菊》
医官小川正子先生病む
「この島の医官が君の少女なす語りごとこそ親しかりしを」
「かりそめに病み給ふにも秋のはやさ庭の菊は香には寂びつつ」——二首とも、明石海人『白描(第一部)』(1939)より
《御快癒を待ちつつ(長歌)》
い とけなき少女[をとめ]の子らの ある日わが家に来て云ふ にこにこと笑みて 物云はすは園長先生 おいしき薬下さるは小川先生と 幼子は心の直ぐ いみ じくも云へるものかな 良薬は口に苦しと 古の人は云へども たはや女の心やさしく 良き薬味ひ甘く ととのへてたまわる君を 幼子も少女[をとめ]の 子らもむくつけき不自由者我らも 母ごとまた姉のごと 敬ひつつなきつつ経にけるものを 明暮のみどりのわざの 劇しきあまりにか 医局にもおん姿無きは 此の頃をおもりたまふとか 秋たてど未だは暑き朝夕をいかにますらむ いたつきの疾く癒えまして ほがらかなる御声を聞かむと 人も云ひ我も願[ね]ぐ なり 島里の秋をさやかに 風渡る頃ともならば すこやけき君をこそ見む 島の子ら心をこめて かくもこそ祈れ やがてまたゆたけき笑顔に 園を守[も] りませ 良き薬も甘く盛りませ うつくしき御歌を詠みませ 待たるるは其の日ぞ 待たるるは実[げ]にもその日ぞ
(反歌)
こもりますわが師の君のおもかげも現に見えておもひの傷む
ひたごころひたぶるに願[ね]ぐわが恃[たの]む医師[くすし]の君のまさきくとこそ
——長歌と反歌、『明石海人歌集』村井編、Pp.202-204, 岩波文庫。
++
1.去来する記憶
陸軍皇道派青年将校によるクーデター事件である2・26事件が起こった昭和11(1936)年の春、長島愛生園の医師・小川正子(1902- 1943; Masako Ogawa) は、ハンセン病患者を収容するために瀬戸内の小島を、園長であった光田健輔の「御命令で検診」巡回していた。彼女が島の山道を歩いていた時のこ とである(→"Lepers, Nation-State, and Empress Dowager")。
「山の裾まで下りてくるといきなりぶよが眼に飛び込 んで、どうしても取れなかった。弱り切った心に私は母の乳が恋しくなった。幼くて野遊びにぶよを眼に入れて泣き泣き帰ってくると未だ赤坊の弟を持っていた 母は、その乳首から乳を私の眼の中に流し込んでくれたのだった。そうして、乳と一緒に真黒な小さい虫が流れ出してしまうと、あとはもう何でも無かった。大 きな態(なり)をして癩伝染宣伝隊で他所を歩き廻る様になっていて、私はこんな遠い島の山みちにこんな幼い事をおもいなつかしむのだった」(小川 2003:220)
そこで「からたちの花」を季題とする二首の歌を詠むが、その一首を挙げてみよう。
からたちの花をこぼしてかえりみちま た同じ道廻り来る も
ある時代の何の変哲もない情景。私と同年配かそれ以上の人なら、忘れていた習慣的行為——眼に入った小虫を母乳で流すこと——を思い起こすだ ろう。民俗学を勉強する若い学生なら、いわゆる『俗信事典』の類や古い市町村史の〈俗信〉の項目のなかに、類似のことを発見するかも知れない。
古い習慣の発見を通して出来事の一端を理解することは可能だ。だが私がここで問題にしたいのは、保健に関わる習俗を図式的な理解のパターン ——眼に入った小虫の除去の民俗的療法——の枠に当てはめることではない。そうではなく問題にしたいのは、母乳で眼を洗った人の経験と、それを頭で理解す る、言い換えれば文化研究というレンズを通して理解するという〈経験〉の間にある、根本的な差異とそれらの架橋についてである。私が、ここに拘(こだわ) るのは大学の授業で前者の経験を後者の〈経験〉で語り、学生に伝えることの難しさに常に直面しているからである。後者の〈経験〉の理解は、参照文献で武装 し幾重にも文字を重ねた論文を書くことで、それなりの自己満足が得られるものだ。だが本物の経験はそうではないはずだという欲求不満は常に残る。
フィールドワークに基づく文化人類学は、その確立期以来、この両者の間の経験の根本的差異と闘ってきたと言っても 過言ではない。人類学の書記 法にまつわる観察者の優位性批判や、フィールドにおける人類学者の政治的位置という古くて新しい問題系がたとえ参入してきても、文化人類学者は、この落差 の問題を、人類学の学問内部に抱えるものとして、あるいは対外的に人類学のあり方を自己提示する際にも最重要視しているし、おそらくこのことは絶えること がないだろう。仮に絶えることになるならば、今度は私が文化人類学という学問に忠誠心をもはや抱かなくなるだろう。
別の言葉で言おう。人間の健康にまつわるさまざな社会現象を取り扱う文化人類学(医療人類学)を勉強する学生に私は次のように忠告するだろ う。「ありきたりの現象に学術用語を貼り付けて満足するのではなく、保健や医療にまつわるあらゆる些細な事象に拘り続けなさい」。そして「なぜ自分がその 事象に拘るのか、事象の文化的解釈と同じくらい、その事実の理由説明を探究することも忘れずに」と。もちろんこれは言うは易し行うは難しで、学生に対する 助言ばかりではなく私自身の自戒の銘でもある。
したがって私は次のように弁明しよう。つまり、「ハンセン病[にまつわ る]文学」として小川正子を議論するのではなく、どうして私はこの事象 に拘るのか、そしてそれは私の思考に何をもたらすのか、ということを。また、そのことが、文化的説明をもって医療や福祉に関わる現象を理解するこれまでの やり方とは、異なった文化人類学のアプローチへのヒントになることを。
2.記録が公刊されるまで
瀬戸内での経験の二年後の秋、小川正子の『小島の春』(1938)は出版される。この年に、日本の保健行政は内務省から新しく設置された厚生 省に移管される。時は蘆溝橋事件の翌年で日中戦争は本格化していた。
明治35(1902)年の生まれの小川の人生は当時の医師としては極めて特異的だった。しかし、別の意味では、当時の人たちが抱く典型的な人 間主義的理想像を生きた人でもあった(もちろん小説から垣間見える彼女は聖人君子よりもむしろ仕事に真摯に打ち込む「誠実な人」である)。小川は山梨の甲 府高等女学校を卒業した後、結婚をしたが三年後に離婚し、東京女子医学専門学校に入学し昭和4(1929)年卒業している。「癩救済事業」には在学中から 関心をもっていた。岡山にある長島愛生園は彼女の卒業の翌年に設立され、1931年には光田健輔が園長に就任した。この年は、満州における日中の交戦状態 に入る柳条湖事件がおこっていた。国内では「癩予防に関する件」に代わる「癩予防法」が成立した。この法律は、それまでの放浪ハンセン病患者の収容隔離か ら、すべてのハンセン病の隔離収容政策への変更を意味する(藤野 2003)。もちろん総力戦態勢の当時、医療行政は内務省[と陸軍省]に管轄され、ハン セン病者の隔離収容政策は着々と整備が続いていた。植民地朝鮮では1935年に「癩予防令」が公布施行される(滝尾 2001)。その数年後の小川の姿に みられるように、地元の役場関係者と巡査らとともに、医師たちは地方の村々の患者のもとを訪れ検診をおこない、診断にもとづいて収容を決定し、法律に従っ て人々の移送が行なっていた。
医専卒業後も小川の救癩の情熱は冷めやらずハンセン病療養施設であった東京の全生病院への赴任を希望するが、光田の面接を受け、実地医学の一 般研修を先に受けるように諭された。彼女は3年間、細菌学、内科、小児科の臨床経験を積んだ。 しかしながら全体主義的傾向が強かった内務省管轄の施設では、救癩の施設であるにもかかわらず女性医師の任官のチャンスは少なかった。小川は、全生病院 (のちの全生園)で働いていた女医の西原蕾や五十嵐正のアドバイスに従い、岡山県の長島愛生園に「直接談判」に赴き、ようやく光田によって受け入れられ た。昭和7(1932)年6月のことである。
現在も変わらぬ近代医療の最先端の現場、とくに国立の機関は男性中心主義に独占されており、未だ女性が活躍できる場はすくなかった。他方民間 の救癩事業の現場では女性が多くが活躍してきた。癩病というスティグマを貼られた病者に対する慈愛の精神を体現するのは、洋の東西を問わず聖女たる女性で あり、その中で治療と慈愛が女性の性役割に関連づけられていたと考えられる。ハンセン病対策が、民間による慈善事業から国家による統治手段として位置づけ られるようになった時、女性の領域と位置づけられてきた慈愛の精神と実践もまた、国家制度に組み込まれてゆくことになる。赴任した彼女の仕事は、長島愛生 園での収容者の診療の他に、その3年前に改定された癩予防法のプロトコルに従い、「祖国浄化」——収容政策は関係者の間ではこのように表現されていた—— の理想に燃えて、中国四国地方の村々を定期的に巡回検診——より多く病者を発見——することであった。
小川の作品中にみられる巡回の様子やそこで出会うさまざまなハンセン病者との邂逅のエピソードは、後に述べるように、今日の我々にとって共感 と違和感が相半ばするものである。このような手記が残されるに到ったのは光田による「検診行の記録は全部くわしく書いて置きなさい。時がたつとその時の気 分がうすらいで千遍一律の物になってしまうから、その度々直ぐに書き残しておくんですな」という助言によるものである。しかしながら小川はそれを瞬時に理 解できなかったようで、すぐに光田の語調が強くなり「出張してその報告書を提出するのは官吏としての義務ですよ」と改めて諭される(小川 2001: 281)。
小川に対する光田の助言は、調査実習のレポート提出を学生に督促する大学の教師のようだ——このことは私と同業の多くが同意してくれるだろ う。「記録は全部くわしく書いて置きなさい」という指示は学問的助言であり、「報告書を提出するのは……義務ですよ」とは権限にもとづく命令である。
『小島の春』は、昭和9年から11年までの巡回検診記録であり、当初、長島愛生園慰安会による『愛生』という所内の雑誌(戦前のシリーズは昭 和5年創刊)に掲載された。小川の結核発病により、今度は本にまとめる時間的余裕がうまれ、昭和13年の発刊になった。この書物は刊行と同時にベストセ ラーになる。また女優の夏川静江の主演で、豊田四郎監督作品として映画公開され、昭和15年度の『キネマ旬報』のベストテン第1位になった。小川の意識は 同時に国民に共感されるようになる。
3.善意による舗装は地獄への道か?
40年後に日本社会事業大学教授(当時)吉田久一(1915年生)は『小島の春』の往事の流行を回顧して言う。「現在の学生諸君がちょっと想 像できないほど、われわれ社会事業を志す学生に影響を与えた」と(吉田 1980:75)。
私たちは現在、日本政府のハンセン病対策が法的な社会制度としても、医療制度としても、患者の隔離を通して社会を守るという社会防衛に主力が おかれ、病者の人権が軽視されてきたことを知っている。そしてこの過失に対する国家賠償責任履行の不十分さや管理当事者たちの責任回避、さらにはハンセン 病者の文字通りの社会復帰の現状が未だ不十分であることも知っている。この認識は、無医村の状況を改善するために厚生省の末端機関で勉励努力していた官僚 や医師やその他の保健普及員たちのみならず、無産者診療運動や医療利用組合運動に参画していったかつての左翼運動家や共鳴者たちにも抜け落ちていたもの だった。彼らは同じ罠に捕らえられていた。
これらの私の判断は、現時点での価値観にもとづく過去の出来事の無慈悲な断罪である。この判断が許されるのは、罪の有限性を確認し、処罰と赦 しを含めた認識と実践を未来の生活に反映することを約束する者のみである。すなわち、これらのすべての医療・福祉の実践者たちが陥っていた罠は「ヒューマ ニズムという衣を纏ったパターナリズム」という一言に尽きる。
先ほど、小川の巡回の様子やそこで出会うさまざまなハンセン病者との邂逅のエピソードは、今日の我々にとって共感と違和感が相半ばするだろう と書いた。それは『小島の春』が「正しい」啓蒙的知識の普及を通して癩の国家的撲滅という理念の成就に賭ける情熱という〈純粋〉さと、悲惨な人々への慈悲 の深さという〈純粋さ〉と、それらが放つ偽善的な〈妖しさ〉の不気味な混成物だからである。完全に純粋で真面目なものの真の恐ろしさがそこにはある。はた してマルクスが言ったように地獄への道は善意の石で敷き詰められているのだろうか。
『小島の春』の情景は、ほとんど地理的にも歴史的にも共通点をもたないそれから半世紀後の私がみた田舎の情景と二重写しになる。1980年代 の中頃、中央アメリカのホンジュラス共和国西部の村落地帯で、私は予防接種の普及や伝統的出産介助者(産婆)への教育活動をおこなっていた。それらの違い は、社会改良の情熱に燃えた女医が、ここでは青年海外協力隊のボランティアになり、ハンセン病は〈開発途上国で普通にみられる病気〉に変わっている点にあ る。
誰でもこの「ヒューマニズムという衣を纏ったパターナリズム」の熱病に冒されている時には冷静にはなれないものだ。それを〈相対化してくれる レンズ〉を病者もまた周囲の人たちも提供してくれないからだ。ただ断片的に、医療者に対する敵意や不同意が慎ましく語られ、冷や水を浴びせられることぐら いである。癩の療養所への収容に対する人々の恐怖は「病院へやると直ぐに注射して殺してしまう」(小川 2003:207)という〈風評〉に現れる。実際 数年後の中国大陸(七三一部隊)ではそれが現実のものになっていた。それに対して、医療者もボランティアも、唯々笑うか——精神的不安を解消する表出手段 だ——逆に硬直して言葉を返す精神的余裕をもてなくなる。この情景もまた二重写しである。
そんな中で、中米の田舎道を私と歩いていた調査助手のリンドルフォ君は、顔 見知りの妊婦と出会った後、彼女と一言二言話した後、とたんに道ばたの芝の上に横になって、その女性から足の捻挫のマッサージを受け始めた。どうしてかと いう私の質問に調査助手は、妊婦は〈つよい視線 ojo fuerte〉をもっておりマッサージをしてもらうのは、病気を治してもらうだけでなく予防にもよいのだと、教えてくれた。これは偶然に手に入った私の調 査資料の一つである。神話や伝承の収集とは少し趣向が異なり、身体経験に支配されている医療人類学の調査データは、調査者自身や助手の病気の経験など身近 な経験の長期にわたる積み重ねによるものが多い。だが依然として経験と〈経験〉の差異は存在する。したがって「保健や医療にまつわる文化現象の些細な事 象」に拘ることが、どのようにしてそれらの2つの経験を架橋するかについて説明しなければならない。
小川は出版当時には結核の発病がわかっており、5年後の昭和18(1943)年に41歳でこの世を去った。夭折と言っても過言ではない。『小 島の春』刊行の1938年には結核予防法が改正され、結核患者の国家管理もまた強化される。つまり社会防衛の立場から患者が登録され隔離等の管理が強化さ れ、彼女自身が診療に携わることができなくなったからだ。
からたちの花をこぼしてかえりみちま た同じ道廻り来る も
「からたち」の花言葉は「私は胸を痛めています」である。しかし、女学生言葉では、それは恋心ならぬ本当に胸を痛めること、つまり肺病の病むと いう隠語的意味もあった。小川が幼い頃に母乳でぶよをとってもらった時のことを、瀬戸内の小島で回想した時、彼女は将来に迫り来る自分自身の病気の危機に ついて知り得なかった。自分の身体よりも他人の身体が気になって仕方がない。(また田舎の子供らに対する心地よい慈愛に溢れることも小川の叙述の特徴で あった)。
小川正子の生きた時代。それは〈健康〉の社会化が最も叫ばれた時代だ。それは自分へのケアのみならず、他人へのケアも見事に社会防衛との関連 性を意識させた時代である。社会の大義を実践し、自分が救うべき存在であると錯認し、自己が救われるべき存在であったことを忘却し、そしてそれを追想の中 でしか経験できなくなった時、小川の自己の病気からの救済の道は閉ざされてしまった。小川だけでなく我々もまた、同じ道を廻り巡っているような気がする。
(いけだ・みつほ/文化人類学)
注記:本論文は、学術研究とその社会的実践の関係について論じる目的をもって 執筆されました。癩 (らい)という用語は、その言葉が使われた当時の社会の価値観を反映し、現在では差別語として意味をもつことも多くあり、次第に使われなくなってきた語彙 の一つです。筆者は差別的用法の廃絶を念頭におきつつ、歴史的用語として「癩」を使っていることをご了承ください。
この文章をpdf
で読みたい方はこちらです【On_Masako_Ogawa.pdf】
このページの作者:池田光穂(左
端):この映像は本文とは関係ありません
小川正子(Masako Ogawa, 1902-1943)年譜(ウィキペディアによる)
1902 3月26日山梨県東山梨郡春日居村(現在の笛吹市)に生まれる
1918 甲府高等女学校(現・山梨県立甲府西高校)卒業
1920 樋貝詮三(ひがい・せんぞう, 1890-1953)と結婚。樋貝は、政治家法学者、第37代衆議院議長で、横濱専門学校(神奈川大学)初代理事でもある。
1923 樋貝と離婚
1924 東京女子医学専門学校に入学
1929 卒業時、多磨全生病院(現・国立療養所多磨全生園:Tama Zenshoen Sanatorium)院長光田健輔を訪問。就職を希望するが、採用されなかった。東京市立大久保病院に勤務。内科、細菌学を 研究
1930 賛育会砂町診療所勤務。賛育会は、キリスト教系(YMCA)の社会福祉法人。当時の理事長は、吉野作造
1931 泉橋慈恵病院勤務。同年、開業。
1932 6月12日長島愛生園にいき、医務嘱託として採用(この同時期に、入所した明石海人[1901-1939]と出会う——冒頭の短歌二 首参照)
1934
1934 医官に就任。『小島の春』の「土佐の秋(検診昭和9年9月)」の時期。しばしば検診にいく。光田より検診の記録を残すように勧められ る
1934 8月末、小川正子は光田健輔園長(任期1931-1957)から高知県に患者収容に行くことを命じられた。一行は山田書記、青山看護長と小川正子であ る。難所をこえ、人が集まる所では講演や映写もおこなう旅で、また相当な僻地において、未収容のらい患者を診察する経験を記した手記である。
「この山中に十年、二十年と病み住めば男といえどもどうして山を下れよう。ましてや家には純朴な一徹な無智善良な肉親と周囲があって伝染と
いうことさえ知らずに同じ炉を囲んで朝夕。そして悲劇は何時の日までも果てしなく続けられていく。(中略)母に寄り添って立っていた十一歳という女の子、
まととない愛くるしい顔、背中の二銭銅貨大の痛みのない赤い部分、白い跡はおできのあとと母親はいうのだが、水泡を疑うのは非か。七つの子をあやしつつ、
いぶかしいと思うところをつついてみると痛くない。(中略)病人のほかに二人とも異常があることになった。私は言い出す術をしらなかった。強いて微笑んで
はきたけれど、すべてが「手遅れ(ツーレート)」であった」——『小島の春』からの引用
1936 『小島の春』より→再び土佐へ(昭和11年1月);小島の春(その1、昭和11年4月):(その2、昭和11年7月):国境の雲(昭 和11年7月):阿波講演旅行の歌(昭和11年11月):無名遍路の墓、淋しき父母(昭和12年6月)
1937 初夏。結核を発病。島で療養生活に入る。田河水泡『のらくろ総攻撃』 発刊。
1938 肺疾患のために郷里にて静養する。11月『小島の春 ある女医の手記』を長崎書店より出版(昭和13年11月20日)[→検 証記録]
同書収載のものより:「これやこの夫と妻子の一生の別れかと想へば我も泣かるる」「夫と妻が親とその子が生き別る悲しき病世になからしめ」
「記録を書くように命じたのは光田健輔であるが、彼の努力は最初はうまくいかなかったので医師内田守に任せた。内田守は内田守人というペン ネームを持つ「水甕」の歌人でのちに明石海人の『白描』を出版させた人であったから、小川への勧めも強引だったろう。自費出版には300円必要であった が、内田は小川を説得して100円出させ、内田は医局などで200円を工面した。光田は出さなかった。長崎次郎書店に頼んだが、書店も勝負とみて、各方面 に送ったのが当たったという。」
”あれだけ感動させる力のあるのは事実の描写というものの他に作者のシンセリティ(誠実さ)と文学的素養があるからで、特殊性という付加物 なしにも本当の文学だと思う。もうひとつは叙景がすばらしい。"——木下杢太郎
「1926(大正
15)年、東京帝国大学医科を卒業し、慶應義塾大学医科教授を務めた内務省衛生局予防課長高野六郎は、将来のハンセン病予防策として、公立療養所の拡大、
国立療養所の開設、患者が自由意思で療養する「癩村」の設置をあげ、絶対隔離を「癩予防上の根本」とする意見を発表した。これは、保健衛生調査会の決議と
軌を一にするものであるが、高野はハンセン病予防の課題を「民族の血を浄化する」ことに求めていることに注目したい(高野六郎[1884-1960]「民族浄化のために—癩予防
策の将来—」、『社会事業』10 巻 3 号、1926 年 6
月)。「民族の血を浄化する」という発想には優生思想に通じるものを認めるからである」(厚労省HP「ハ
ンセン病に関する情報ページ」より)。
1939 明石海人『白描』同年6月9日海人は腸結
核にて死亡(39歳)。
1940 「小島の春」が映画化。監督:豊田四郎、出演:夏川静江、菅井一郎、杉村春子
「在宅らい病(ハンセン病)患者を国立療養所に収容する旅を記録した小川正子の同名手記を、八木保太郎が脚色し豊田四郎(1906 -1977)が監督した。高峰秀子に強い影響を与えたという杉村春子の熱演や、戦前の瀬戸内海の美しい風景を切り取った映像など、高い評価を受けた。しか しその反面、らい病の誤った知識を描いていることから、批判も多い。 国立らい病療養所である長島愛生園に勤める女医の小山正子は、戦前の瀬戸内の小さな島で在宅患者を探し隔離し、病気に関する正しい知識を広めようとして いた。島ではらい病に関する知識が乏しく、患者は座敷牢に閉じ込められたりしていた。正子は同僚たちと患者の家を訪ね回り、患者やその家族と直接面会する のだった」https://www.allcinema.net/cinema/134176
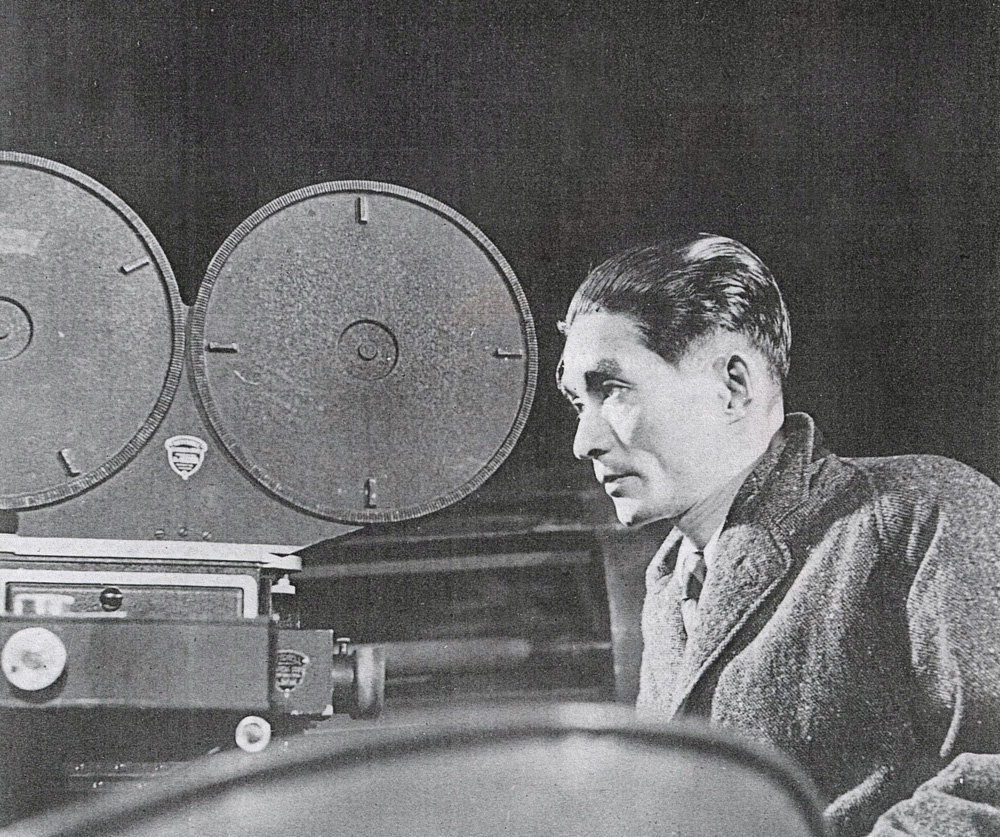
豊田四郎(1906-1977)キネマ旬報 - 『キネマ旬報』1938年2月21日号
1941 自主退職
1943 4月29日、41歳で死去
1947 池尻 愼一(1908-1945:ペンネーム邑楽 愼一:おおら・しんいち)『傷める葦』 山雅房、発行
(章立て)国立国会図書 館デジタルコレクション
1948 長島愛生園に歌碑建立
1984 東山梨郡春日居町(現・笛吹市春日居町)名誉町民
1991 小川正子記念館開館——「生きてゆく日に 愛と正義の十字路に立たば必ず愛の道に就け」
国立療養所長島愛生園の歴史
1909 (国立療養所邑久光明園):4月1日、大阪府西成郡川北村大字外島(現在の大阪市西淀川区中島2丁目北西部)に、「外島保養院」 として開院。施設長は今田虎次郎
1926 1926年12月、村田正太が二代目園長に任命された。
1930 国立らい療養所として発足
1938 4月:国立療養所邑久光明園が大阪市から当園の隣に移設された——岡山県の長島に、長島愛生園に隣接して、外島保養院を復興、名 称は「邑久光明園」とした。外島保養院の患者を引き受けた。施設長は神宮良一。
1941 7月1日(邑久光明園)第3区連合府県立療養所は国に移管され、厚生省の所管となり名称も「国立癩療養所邑久光明園」と改称
1946 国立癩療養所邑久光明園」は「国立療養所邑久光明園」に改称。同時に、「国立らい療養所長島愛生園」から「国立療養所長島愛生 園」へ改称
1952 長島愛生園附属准看護婦養成所開設
1996 4月1日らい予防法廃止
●Jacoby先生の、Spring on Leper’s Island(Director Shiro Toyoda, 1940)での英語での解説がとても、よい
"Constrained by the draconian Film Law, which imposed restrictions on content and expression, Japanese cinema faced profound ideological challenges in the early 1940s. Three cheers, then, for this delicate and compassionate story of a woman doctor (Shizue Natsukawa) working in a leper colony, which, as Joseph Anderson and Donald Richie comment, “ignored national policy” in order to pronounce “a cry for humanism in an age marching toward militarism”. Director Shiro Toyoda remains unjustly neglected in the west; he was to go on to craft a string of postwar masterpieces, among them Wild Geese (1953), the atmospheric account of an unhappily married woman’s love for a student, and Marital Relations (1955), a wonderfully delicate account of the affair between the son of a wealthy family and a geisha." - Dr. Alexander Jacoby.
●リンク(サイト外)
文献
■ウェブリンク:ハンセン病と癩(らい)を考えるページ


Michelangelo Merisi (1571-1610), Sto. Hieronymus