★カルメンとはどんな作品か?
「『カルメン』(Carmen)は、ジョルジュ・ビゼーが作曲したフランス語によるオペラで ある。世界でもっとも人気のあるオペラの一つとされる[1]。声楽抜きでオーケストラのみによる組曲もコンサートや録音で頻繁に演奏されている。 本項ではオペラの他に、バレエやミュージカルといった舞台作品についても記載する。 概説 ジョルジュ・ビゼー オペラ『カルメン』は、プロスペル・メリメの小説『カルメン』を元に、アンリ・メイヤック(英語版)とリュドヴィク・アレヴィ(英語版)がリブレット(台 本)を作り、ビゼーが作曲した4幕もののオペラである[1]。音楽(歌)の間を台詞でつないでいくオペラ・コミック様式で書かれていた。 1875年3月3日、パリのオペラ=コミック座で初演される[1]。初演は不評であった[2]が、その後の客入りと評判は決して悪くなく、ビゼーのもとに は『カルメン』のウィーン公演と、そのために台詞をレチタティーヴォに改めたグランド・オペラ版への改作が依頼された。この契約を受けたビゼーだったが、 持病の慢性扁桃炎による体調不良から静養中の6月4日、心臓発作を起こして急死してしまう。そこで友人である作曲家エルネスト・ギローが改作を担当して ウィーン上演にこぎつけ、それ以降フランス・オペラの代表作として世界的な人気作品となった。リブレットはフランス語で書かれているが、物語の舞台はスペ インである。そのため日本では役名の「José」をスペイン語読みで「ホセ」と書きあらわすが、実際はフランス語読みで「ジョゼ」と発音して歌われる。音 楽もハバネラやセギディーリャ(英語版)などスペインの民族音楽を取り入れて作曲されている。 近年では、音楽学者フリッツ・エーザー(ドイツ語版)がビゼーのオリジナルであるオペラ・コミック様式に復元するとして、1964年に出版された「アルコ ア版」による上演も行われる。現行の主要な版は原典版のほか、オペラ・コミック版、グランド・オペラ版、メトロポリタン歌劇場版がある。ギロー版はフラン ス語ネイティブ以外のキャストでも台詞に訛りがつくのを避けられることもあり、現在でも使用されている。 2000年代初めには決定版ともいうべきミヒャエル・ロート(de:Michael Rot)による校訂版が作られており、一応の完成(A:自筆譜)から初演時点、初版などの各時点とその周辺の成立時点ごとに全てが併記されており、指揮者 や演出家などのプランナーが自由に取捨選択することが可能な版となっている」https://x.gd/AYZzU)
ビ
ゼーの遺作だけど、結局改作されて、人気が出るようになる。作品のポテンシャルって、作者の手から外れたときに、その真価がためされるようになるかもね
☆登場人物
カ
ルメン(メゾソプラノまたはソプラノ)- タバコ工場で働くジプシーの女
ドン・ホセ(テノール)- 竜騎兵長
ミカエラ(ソプラノ)- ドン・ホセの婚約者
エスカミーリョ(バリトン)- 闘牛士
スニガ(バス)- 衛兵隊長、ドン・ホセの上官
モラレス(バリトンまたはテノール)- 士官
ダンカイロ(バリトンまたはテノール) - 密輸商人
フラスキータ(ソプラノ)- カルメンの友人
メルセデス(メゾソプラノ、ただしソプラノとする楽譜もある)- カルメンの友人
レメンダード(テノール)- ダンカイロの仲間
| 第1幕 1820年ごろのセビリヤ。昼休みに広場に現れたタバコ工場の女工たちに、男たちが言い寄るが、カルメンは全く相手にしない。カルメンは、女工たちに興味 を示さない衛兵の伍長ドン・ホセに花を投げつけ、気を引こうとする。ホセの婚約者であるミカエラが現れ、ホセに故郷の彼の母親からの便りを届ける。セビリ アの煙草工場でジプシーの女工カルメンはけんか騒ぎを起こし、牢に送られることになった。しかし護送を命じられた竜騎兵伍長のドン・ホセは、カルメンに誘 惑されて彼女を逃がす。パスティアの酒場で落ち合おうと言い残してカルメンは去る。 |
| 第2幕 1ヶ月後、カルメンを逃がした罪で牢に入れられていたホセが、釈放される。カルメンが、友人二人(メルセデスとフラスキータ)、衛兵隊長スニガと酒場で歌 い踊っていると、花形闘牛士エスカミーリョが現れ、カルメンの気を引く。釈放されたホセが酒場に着くと、カルメンはホセのために歌って踊り、密輸団の仲間 になるよう誘う。カルメンの色香に迷ったドン・ホセは、婚約者ミカエラを振り切ってカルメンの元に行き、上司とのいさかいのため密輸をするジプシーの群れ に身を投じる。しかし、そのときすでにカルメンの心は闘牛士エスカミーリョに移っていた。 |
| 第3幕 冒頭で、ジプシーの女たちがカードで占いをする。カルメンが占いをすると、不吉な占いが出て結末を暗示する。密輸の見張りをするドン・ホセを、婚約者ミカ エラが説得しに来る。闘牛士エスカミーリョもやってきて、ドン・ホセと決闘になる。騒ぎが収まったあと、思い直すように勧めるミカエラを無視するドン・ホ セに、ミカエラは切ない気持ちを一人独白する。カルメンの心をつなぎとめようとするドン・ホセだが、カルメンの心は完全に離れていた。ミカエラから母の危 篤を聞き、ドン・ホセはカルメンに心を残しつつ、盗賊団を去る。 |
| 第4幕 ホセが盗賊団を去って1ヶ月後、エスカミーリョとその恋人になっているカルメンが闘牛場の前に現れる。エスカミーリョが闘牛場に入ったあと、一人でいるカ ルメンの前にドン・ホセが現れ、復縁を迫る。復縁しなければ殺すと脅すドン・ホセに対して、カルメンはそれならば殺すがいいと言い放つ。そんなホセの執拗 な言動にカルメンは業を煮やし、以前彼からもらった指輪を外して投げつける。逆上したドン・ホセがカルメンを刺し殺し、その場で呆然と立ちつくす。 出典:https://x.gd/AYZzU |
☆カルメンのエチカ(倫理学)とは?
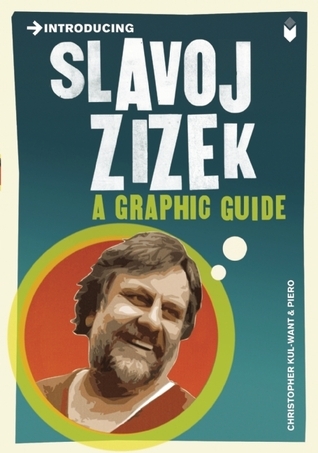
スラヴォイ・ジジェクは面白いことをいう。カルメンは
恋人の人生を破壊し、かつ、自分の死をまねく(=嫉妬によりドンホセにより殺される)にもかかわらず、彼女の行動は「倫理的」だと……ね!!
ジジェクは、ラカン派の現代思想家である。それゆえ、ジジェクが言う「倫理的」とは、決して人畜無害の正しい人のお約束などではなく、倫理的とは、ナチの
強制収容所は生命倫理の極限形態だという、アラン・バディウ(バディウ『倫理』)
の議論をうけており、倫理の本質のなかに、欲望の他者への暴力的な押し付けという性質を避けることができないという。ここで重要なことは、(一見矛盾する
ような——なぜなら普通、倫理的道徳を守るためには、自分の「欲望」を辛抱するつまり抑圧するものだと見なされているので)倫理と欲望の奇妙な共存をどの
ように「理解」するのかということだ。ジジェク派なら、自分の欲望を何であるかについて無自覚なまま「大文字の他者」の欲望を忖度して、自分の生きる倫理
基準にして生きているのが、資本主義下における人間の姿だ、というだろう。したがって、そこから解放されるためには、「大文字の他者」の廃棄、なぜなら(ジジェク派なら)「大文字の他者」などは虚構であり存在しないからだ、「大文字の他者」など存在しない、忘れてしまうことだ。もちろん、社会(=大文字の他者のひとつの事例)の欲望と、われわれ一人一人の欲望はつねに衝突をおこす。その典型的な事例が、ヘーゲルが好んでとりあげた、ソポクレスの悲劇『アンティゴネー』に出てくる、国王クレオーンの命令に不服従の姿勢を貫いて、兄のポリュネイケースの埋葬を「挙行(=劇中ではその点は不明瞭)」し死を覚悟するアンティゴネーの生き方である。アンティゴネーは、ヘーゲルやコージェヴを経由して、ラカンも好んでとりあげた。そして、ラカン派のジジェクもそうである。結論に入ろう。カルメンとアンティゴネーは、
自分の欲望に忠実であるという意味で、きわめて「倫理的」なのである。言い方を帰ると、自分の欲望の成就と、自分の行動の合致というのが、倫理的なるもの
の姿であり、倫理とは、我慢して従ったり、あるいは「研究倫理」研修をあくびを噛み殺して出席者の名簿にサインをすることではないのである。
| ジジェク( Less than nothing : Hegel and the shadow of dialectical materialism / Slavoj Žižek, Verso , 2013)より "If hedonism is to be rejected, is Lacanian ethics then a version of the heroic immoralist ethics, enjoining us to remain faithful to ourselves and persist on our chosen way beyond good and evil? Think of don Giovanni in the last act of Mozart's opera, when the Stone Guest confronts him with a choice: he is near death, but if he repents of his sins, he can still be redeemed; if, however, he does not renounce his sinful life, he will burn in hell forever. Don Giovanni heroically refuses to repent, although well aware that he has nothing to gain, except eternal suffering, for his persistence. Why does he do it? Obviously not for any profit or promise of pleasure to come. The only explanation is his utmost fidelity to the dissolute life he has chosen. This is a dear case of immoral ethics: don Giovanni's life was undoubtedly immoral; however, as his fidelity to himself proves, he was immoral not for pleasure or profit, but out of principle, acting the way he did in accordance with a fundamental choice. pp.123-124. Or, to take a feminine example also from opera: George Bizet's Carmen. Carmen is, of course, immoral (ruthlessly promiscuous, ruining men's lives, destroying families), but nonetheless thoroughly ethical (faithful to her chosen path to the end, even when this means certain death) Along these lines, Lee Edelman has developed the notion of homosexuality as involving an ethics of "now;' of unconditional fidelity to jouissance, of following the death drive by totally ignoring any reference to the future or engagement with the practical complex of worldly affairs. Homosexuality thus stands for the thorough assumption of the negativity of the death drive, of withdrawing from reality into the real of the "night of the world:' Along these lines, Edelman opposes the radical ethics of homosexuality to the predominant obsession with posterity (i.e., children): children are the "pathological" moment which binds us to pragmatic considerations and thus compels us to betray the radical ethics of jouissance.6t (Incidentally, does this line of thought-the idea that homosexuality at its most fundamental involves the rejection of children-not justify those who argue that gay couples should not be allowed to adopt children 1) The figure of an innocent and helpless child is the ultimate ethical trap, the emblem-fetish of betraying the ethics of jouissance. Friedrich Nietzsche (a great admirer of Carmen) was the great philosopher of immoral ethics, and we should always remember that the title of Nietzsche's masterpiece is "genealogy of morals;' not "of ethics": the two are not the same. Morality is concerned with the symmetry of my relations to other humans; its zero-level rule is "do not do to me what you do not want me to do to you.” Ethics, in contrast, deals with my consistency in relation to myself, my fidelity to my own desire. On the back flyleaf of the 1939 edition of Lenin's Materialism and Empirio-Criticism, Stalin made the following note in red pencil: 1) Weakness
2) Idleness 3) Stupidity These are the only things that can be called vices. Everything else, in the absence of the aforementioned, is undoubtedly virtue. If a man is 1) strong (spiritually), 2) active, 3) clever (or capable), then he is good, regardless of any other "vices" 1) plus 3) make 2)." pp.124-125 This is as concise as ever a formulation of immoral ethics; in contrast, a weakling who obeys moral rules and worries about his guilt stands for unethical morality, the target of Nietzsche's critique of resentment. It is a supreme irony (and one of the greatest cases of poetic justice) that, among American writers, the one who provided the most precise formulation of the same immoral ethics was none other than the rabidly anti-Communist Russian emigrant Ayn Rand, in her first (still moderate) US success, the play Night of January 16th. Although written in a traditional realist mode, this courtroom (melo )drama engages its spectators in a very contemporary, almost Brechtian, manner: at the beginning, the twelve jury members are randomly selected from among the theater audience; they are seated on the stage and, at the play's end, they briefly withdraw before returning to deliver the verdict of guilty or not guilty-Rand proVided different final lines depending on which it was. The decision they have to make is not only about the murder of Bjorn Faulkner, a ruthless Swedish tycoon: did Karen Andre, his devoted mistress and secretary, do it or not? It is also about two opposed ethics-to quote the play itself: if you value a strength that is
its own motor, an audacity that is its own law, a spirit that is its
own vindication-if you are able to admire a man who, no matter what
mistakes he may have made in form, had never betrayed his essence: his
selfesteem-if, deep in your hearts, you've felt a longing for greatness
and for a sense of life beyond the lives around you, if you have known
a hunger which gray timidity can't satisfy ...
In short, if you advocate immoral ethics, you will find Karen not guilty; if, however, you believe in social respectability, in a life of service, duty, and unselfishness, etc., then you will flnd Karen guilty. There is, however, a limit to tbis Stalinist immoral ethics: not that it is too immoral, but that it is secretly too moral, still relying on a figure of the big Other. In what is arguably the most intelligent legitimization of Stalinist terror, Maurice Merleau-Ponty's Humanism and Terror Ii'om 1946, the terror is justified as a kind of wager on the h,ture, almost in the mode of Pascal: if the final result of to day's horror turns out to be a bright communist future, then this outcome will retroactively redeem the terrible things a revolutionary has to do today. Along similar lines, even some Stalinists themselves-when forced to admit (mostly in private) that many of the victims of the purges were innocent, that they were accused and killed because "the Party needed their blood to fortify its unity"¬ imagined a future moment of final victory when all the victims would be given their due, and their innocence and sacrifice for the Cause would be recognized. This is what Lacan, in his seminar on Ethics, refers to as the "perspective of the Last Judgment;' a perspective even more clearly discernible in two key terms of the Stalinist discourse, "objective guilt" and "objective meaning": while you can be an honest individual who acts with the most sincere intentions, you are nonetheless "objectively guilty" if your acts serve reactionary forces-and it is, of course, the Party that decides what your acts "objectively mean." p.126 Here, again, we get not only the perspective of the Last Judgment (from which the "objective meaning" of your acts is formulated), but also the agent in the present who already has the unique ability to jndge today's events and acts from this perspective.The name of Raskolnikov (the hero of Dostoyevsky's Crime and Punishment) evokes a split (raskol); Raskolnikov is "the split one"¬ bnt split between what and what? The standard answer is that he is "torn between the 'Napoleonic idea; the notion that all is permitted to a strong person, and the 'Russian idea' of selfless devotion to humanity"- however, this version misses the properly "totalitarian" coincidence of the two ideas: it is my very selfless devotion to humanity, my awareness that I am an instrument of Humanity, which justifies my claim that all is permitted to me. The paradox is thus that what Raskolnikov lacks is the split itself, the distance between the two ideas, the "Napoleonic" and the "Russian:' We can see now why Lacan's motto "il n'y a pas de grand Autre" (there is no big Other) takes us to the very core of the ethical problematic: what it excludes is precisely this "perspective of the Last Judgment:' the idea that somewhere even if as a thoroughly virtual reference point, even if we concede that we can never occupy its place and pass the actual judgment-there must be a standard which would allow us to take the measure of our acts and pronounce on their "true meaning:' their true ethical status. Even Derrida' s notion of "deconstruction as justice" seems to rely on a utopian hope which sustains the specter of "infinite justice:' forever postponed, always to come, but nonetheless here as the ultimate horizon of our activity.The harshness of Lacanian ethics lies in its demand that we thoroughly relinquish this reference to the big Other-and its further wager is that not only does this renunciation not plunge us into ethical insecurity or relativism (or even sap the very fundamentals of ethical activity), but that renouncing the guarantee of some big Other is the very condition of a truly autonomous ethics. Recall that the exemplary dream Freud used to illustrate his procedure of dream analysis was a dream about responsibility (Freud's own responsibility for the failure of his treatment of Irma)-this fact alone indicates that responsibility is a crucial Freudian notion. But how are we to conceive of this responsibility? How are we to avoid the common misperception that the basic ethical message of psychoanalysis is, precisely, that we should relieve ourselves of responsibility and instead place the blame on the Other ("since the Unconscious is the discourse of the Other, I am not responsible for its formations, it is the big Other who speaks through me, I am merely its instrument")? Lacan himself pointed the way out of this deadlock by referring to Kant's philosophy as the crucial antecedent of psychoanalytic ethics." - Less Than Nothing, Zizek. |
ジジェク( Less than nothing : Hegel and the shadow of dialectical materialism / Slavoj Žižek, Verso , 2013)より 快楽主義が否定されるのであれば、ラカンの倫理学は、自分自身に忠実であり続けること、善悪を超えて自分の選んだ道を貫くことを私たちに勧める、英雄的非 道徳主義者の倫理学のバージョンなのだろうか?モーツァルトのオペラの終幕で、石の客に選択を迫られるドン・ジョヴァンニを思い浮かべてほしい。彼は死を 目前にしているが、罪を悔い改めればまだ救済される。ドン・ジョヴァンニは、永遠の苦しみ以外に得るものがないことを十分承知しながらも、勇気をもって悔 い改めることを拒否する。なぜ彼はそれをするのか?明らかに、利益を得るためでも、来るべき喜びを約束するためでもない。唯一の説明は、自分が選んだ放蕩 生活への最大限の忠誠である。ドン・ジョヴァンニの人生は間違いなく不道徳であった。しかし、彼の自分自身への忠実さが証明しているように、彼は快楽や利 益のためではなく、原理から不道徳になったのであり、根本的な選択に従ってそのように行動したのである。 あるいは、同じくオペラの女性的な例を挙げよう: ジョージ・ビゼーの『カルメン』だ。カルメンはもちろん不道徳だが(冷酷に乱交し、男性の人生を破滅させ、家庭を破壊する)、それにもかかわらず、徹底的 に倫理的である(たとえそれが確実な死を意味するものであっても、最後まで自分の選んだ道に忠実である)。この線に沿って、リー・エデルマンは、同性愛を 「今」の倫理に関わるものとしてとらえ、ジュイサンスへの無条件の忠実さ、未来への言及や現実的な複雑な世俗問題との関わりを完全に無視することによって 死の衝動に従うという概念を展開した。したがって、同性愛は、死の衝動の否定性を徹底的に引き受けること、現実から「世界の夜」の現実へと引きこもること の象徴なのである。この線に沿って、エーデルマンは、同性愛の急進的倫理を、後世(すなわち子ども)への支配的な執着と対立させる。子どもは、われわれを 現実的な配慮に縛りつけ、その結果、われわれにジュイサンスの急進的倫理を裏切らせる「病的な」瞬間なのである6。 無垢で無力な子どもの姿は、究極の倫理的罠であり、ユイサンスの倫理を裏切ることの象徴である。 フリードリヒ・ニーチェ(カルメンの偉大な崇拝者)は、不道徳な倫理の偉大な哲学者である。道徳とは、私と他の人間との関係の対称性に関わるものであり、 そのゼロ・レベルのルールは「自分がしてほしくないことを自分にしてはならない」である。これに対して倫理は、私自身との関係における一貫性、つまり私自 身の欲望に対する忠実さを扱う。レーニンの『唯物論と経験批判』(1939年版)の裏のチラシに、スターリンは赤鉛筆で次のように記している: 1)弱さ
2)怠惰 3)愚かさ それ以外のものは、前述のものがなければ、間違いなく美徳である。もし人が1)強く(精神的に)、2)活動的で、3)利口(あるいは有能)であれば、1)+3)で2)となる他の「悪徳」があろうとも、その人は善である。" これとは対照的に、道徳的な規則を守り、自分の罪を心配する弱者は、非道徳的な道徳の象徴であり、ニーチェの怨恨批判の対象である。アメリカの作家の中 で、同じ非道徳的倫理を最も正確に定式化したのが、熱狂的な反共産主義者であるロシア移民のアイン・ランドであり、彼女のアメリカでの最初の(まだ穏健 な)成功作である戯曲『1月16日の夜』であったことは、この上ない皮肉である(そして詩的正義の最も偉大なケースの一つである)。伝統的なリアリズムの 様式で書かれたこの法廷劇は、観客を非常に現代的な、ほとんどブレヒト的な方法で惹きつける。冒頭、12人の陪審員が劇場の観客の中から無作為に選ばれ、 舞台に着席し、劇の最後に、有罪か無罪かの評決を下すために戻ってくる前に、いったん退席する。彼らが下さなければならない決断は、冷酷なスウェーデンの 大物ビョルン・フォークナーの殺人についてだけではない。また、劇中の言葉を引用すれば、2つの相反する倫理観についても描かれている: もしあなたが、自らの原動力となる強さ、自らの掟となる大胆さ、自らの正当性を証明する精神に価値を見出すなら、もしあなたが、形の上ではどんな過ちを犯 そうとも、その本質、すなわち自尊心を決して裏切らなかった男を賞賛できるなら、もしあなたが、心の奥底で、偉大さへの憧れや、周囲の人生を超えた人生へ の感覚を感じたことがあるなら、もしあなたが、灰色の臆病さでは満たすことのできない飢えを知っているなら......。 要するに、もしあなたが不道徳な倫理を唱えるなら、カレンは無罪となる。しかし、もしあなたが社会的な尊敬、奉仕、義務、無私の生き方などを信じるなら、カレンは有罪となる。
しかし、このスターリン主義的不道徳倫理学には限界がある。それは、不道徳すぎるということではなく、密かに道徳的すぎるということであり、依然として大 きな他者の姿に依存している。1946年に発表されたモーリス・メルロ=ポンティの『ヒューマニズムとテロル』(邦題『スターリン主義的テロル』)は、間 違いなくスターリン主義的テロルを最も理性的に正当化したものであるが、このテロルは、ほとんどパスカルのようなやり方で、一種の賭けとして正当化されて いる。同じような路線で、スターリニスト自身も、粛清の犠牲者の多くが無実であったこと、「党の団結を強固にするために彼らの血が必要であった」ために告 発され殺されたことを(主に内輪で)認めざるを得なくなったとき、すべての犠牲者に相応の報いが与えられ、彼らの無実と大義のための犠牲が認められる将来 の最終的な勝利の瞬間を想像した。これは、ラカンが倫理学のセミナーで「最後の審判の視点」と呼んでいるものである。この視点は、スターリン主義者の言説 の2つの重要な用語、「客観的な有罪」と「客観的な意味」において、さらにはっきりと見分けることができる。 ドストエフスキーの『罪と罰』の主人公であるラスコーリニコフの名前は、分裂(raskol)を連想させる。標準的な答えは、彼が「『ナポレオン的発 想』、つまり強い人間にはすべてが許されるという考え方と、『ロシア的発想』、つまり人類への無私の献身との間で葛藤している」というものだが、このバー ジョンでは、この2つの発想の適切な「全体主義的」一致を見逃している。つまり、ラスコーリニコフに欠けているのは、分裂そのものであり、「ナポレオン 的」と「ロシア的」という二つの思想の間の距離なのである。 ここでもまた、私たちは最後の審判の視点(そこからあなたの行為の「客観的意味」が定式化される)だけでなく、そこから今日の出来事や行為を判断する独特 の能力をすでに持っている現在の主体者についても知ることができます。 視点。ラスコーリニコフ(ドストエフスキーの『罪と罰』の主人公)の名前は分裂(ラスコル)を呼び起こします。 ラスコーリニコフは「分裂した者」であり、何と何の間で分裂しているのでしょうか? 標準的な答えは、彼が「強い者にはすべてが許されるという『ナポレオンの考え』と、人類への無私の献身という『ロシアの考え』の間で引き裂かれている」と いうものだ。しかし、このバージョンでは適切な「全体主義的」な偶然が欠けている。 それは人類に対する私の非常に無私な献身であり、私は人類の道具であるという認識であり、それは私にすべてが許されているという私の主張を正当化します。 したがって、ラスコーリニコフに欠けているのは、「ナポレオン的」と「ロシア的」という二つの思想の間の距離である分裂そのものであるという矛盾である。 ラカンのモットー "il n'y a pas de grand Autre"(大きな他者は存在しない)がなぜ倫理的問題の核心に迫 るのか、その理由がわかるだろう。ラカンが排除しているのは、まさにこの「最後の審判の視点」であり、たとえ徹底的 にヴァーチャルな基準点であったとしても、私たちがその場所を占拠し、実際の審判を下すこと ができないことを認めたとしても、どこかに、私たちの行為を測定し、その「真の意味」、 すなわち真の倫理的地位を宣告することを可能にする基準があるはずだという考えである。デリダの「正義としての脱構築」という概念でさえも、「無限の正 義」(永遠に先延ばし され、常に来るべきものであるが、それでもなお、われわれの活動の究極的な地平とし てここにある)の亡霊を支えるユートピア的な希望に依拠しているように思われる。 ラカンの倫理学の厳しさは、この「大きな他者」への言及を徹底的に放棄することを要求するところにあり、そのさらなる賭けは、この放棄によって倫理的不安 や相対主義に陥らない(あるいは、倫理的活動の根幹が損なわれない)だけでなく、「大きな他者」の保証を放棄することが、真に自律的な倫理の条件そのもの であるということである。フロイトが夢分析の手順を説明するために用いた模範的な夢が、責任(イルマに対する治療の失敗に対するフロイト自身の責任)に関 する夢であったことを思い出してほしい--この事実だけでも、責任がフロイトの重要な概念であることを示している。しかし、この責任をどのように考えれば よいのだろうか。精神分析の基本的な倫理的メッセージが、正確には、私たち自身の責任を免除し、その代わりに他者に責任を負わせることである(「無意識は 他者の言説であるため、その形成について私は責任を負わない。) ラカン自身は、精神分析倫理の決定的な先例としてカント哲学に言及することで、この行き詰まりを打開する道を指し示している。 |
| https://www.reddit.com/r/zizek/comments/7hwkg6/the_good/ | https://www.deepl.com/ja/translator |
★他方、ラカンさんは?
Lacan's
work is vast: twenty years of seminars, the long and difficult volume
Écrits, several other articles and the Television interview we have
discussed here. That means weeks, months, years of work and effort for
the reader who wants to understand something about it. One could say
the same thing about psychoanalytic treatment itself: so many years, so
much time, so much money. Is it worth it?
If it is worth dedicating so much libido to psychoanalysis, it's
because psychoanalysis is not psychotherapy.
If
it were only to cure the neurotic symptom, if it were only to put an
end to the neurotic complaint, it would be out of all proportion to do
so. Psychoanalysis has therapeutic effects, but psychoanalysis is much
more than psychotherapy.
Let's turn to
the interpreting of the
analyst. In a certain
sense we can say that
this is what the
analyst owes to the
analysand. To interpret
seems to be something
active, not something
passive, but it is
nevertheless important
to see the extent of
what is excluded by
this duty of
interpretation, the
area of what we can
call the abstention of
the psychoanalyst. To
interpret means not to
evaluate, not to judge,
not to act and even to
leave aside any
feelings. No doubt
there is something else
that the analyst
requires here: he has
to make the rule of
free association apply.
So there is a demand
for speech, but he has
nothing to discuss; he
has nothing to say
about what is said; he
isn't there to agree,
to condemn or to blame;
he neither censors nor
endorses.
So he does not say
anything, only
interprets. This is a
choice, sometimes a
difficult one which
needs to be repeated
every day with each
patient.
To interpret is only to designate what was said in what the subject articulated, and in that sense the desire of the psychoanalyst — you know that Lacan gave a key function to this desire — is first of all a desire for interpretation. We could say that the desire of the analyst emerges in the interpretation. [...] * The Lacan Conference, April 15, 1990, at Barnard College, Columbia University, New York.
ラ カンの仕事は膨大である。20年にわたるセミナー、長くて難解な『Écrits』、その他いくつかの論文、そしてここで取り上げたテレビのインタビュー。 つまり、何かを理解しようとする読者にとっては、数週間、数カ月、数年にわたる仕事と努力が必要なのだ。精神分析の治療そのものについても同じことが言え る。それだけの価値があるのだろうか?精神分析に多くのリビドーを捧げる価値があるとすれば、それは精神分析が心理療法ではないからである。
神経症的な症状を治すだけなら、神経症的な訴えに終止符を打つだけなら、そんなことをするのは筋違いである。精神分析には治療効果があるが、精神分析は精神療法以上のものである。
ラ カン自身の言葉「分析者の解釈に目を向けよう。ある意味では、これは分析者が分析者に負っているものだと言える。解釈するということは、受動的なことでは なく、能動的なことであるように思われるが、それにもかかわらず、この解釈の義務によって排除されるものの範囲、精神分析家の禁欲と呼ぶことのできる領域 を見ることは重要である。解釈するということは、評価しないこと、判断しないこと、行動しないこと、さらにはいかなる感情も脇に置いておくことを意味す る。分析家がここで要求するのは、自由連想のルールを適用させることである。つまり、言論の要求はあるが、彼は何も議論することはなく、言われたことにつ いて何も言うことはない。だから彼は何も言わず、ただ解釈する。これは時に困難な選択であり、患者一人ひとりに対して毎日繰り返す必要がある。」
その意味で、精神分析家の欲望——ラカンがこの欲望に重要な機能を与えたことはご存じかと思う——は、まず第一に解釈への欲望なのである。分析者の欲望は解釈の中に現れると言える。
https://www.lacan.com/frameII2.htm
リンク
★カルメンとはどんな作品か?
「『カルメン』(Carmen)は、ジョルジュ・ビゼーが作曲したフランス語によるオペラで ある。世界でもっとも人気のあるオペラの一つとされる[1]。声楽抜きでオーケストラのみによる組曲もコンサートや録音で頻繁に演奏されている。 本項ではオペラの他に、バレエやミュージカルといった舞台作品についても記載する。 概説 ジョルジュ・ビゼー オペラ『カルメン』は、プロスペル・メリメの小説『カルメン』を元に、アンリ・メイヤック(英語版)とリュドヴィク・アレヴィ(英語版)がリブレット(台 本)を作り、ビゼーが作曲した4幕もののオペラである[1]。音楽(歌)の間を台詞でつないでいくオペラ・コミック様式で書かれていた。 1875年3月3日、パリのオペラ=コミック座で初演される[1]。初演は不評であった[2]が、その後の客入りと評判は決して悪くなく、ビゼーのもとに は『カルメン』のウィーン公演と、そのために台詞をレチタティーヴォに改めたグランド・オペラ版への改作が依頼された。この契約を受けたビゼーだったが、 持病の慢性扁桃炎による体調不良から静養中の6月4日、心臓発作を起こして急死してしまう。そこで友人である作曲家エルネスト・ギローが改作を担当して ウィーン上演にこぎつけ、それ以降フランス・オペラの代表作として世界的な人気作品となった。リブレットはフランス語で書かれているが、物語の舞台はスペ インである。そのため日本では役名の「José」をスペイン語読みで「ホセ」と書きあらわすが、実際はフランス語読みで「ジョゼ」と発音して歌われる。音 楽もハバネラやセギディーリャ(英語版)などスペインの民族音楽を取り入れて作曲されている。 近年では、音楽学者フリッツ・エーザー(ドイツ語版)がビゼーのオリジナルであるオペラ・コミック様式に復元するとして、1964年に出版された「アルコ ア版」による上演も行われる。現行の主要な版は原典版のほか、オペラ・コミック版、グランド・オペラ版、メトロポリタン歌劇場版がある。ギロー版はフラン ス語ネイティブ以外のキャストでも台詞に訛りがつくのを避けられることもあり、現在でも使用されている。 2000年代初めには決定版ともいうべきミヒャエル・ロート(de:Michael Rot)による校訂版が作られており、一応の完成(A:自筆譜)から初演時点、初版などの各時点とその周辺の成立時点ごとに全てが併記されており、指揮者 や演出家などのプランナーが自由に取捨選択することが可能な版となっている」https://x.gd/AYZzU)
ビ
ゼーの遺作だけど、結局改作されて、人気が出るようになる。作品のポテンシャルって、作者の手から外れたときに、その真価がためされるようになるかもね
☆登場人物
カ
ルメン(メゾソプラノまたはソプラノ)- タバコ工場で働くジプシーの女
ドン・ホセ(テノール)- 竜騎兵長
ミカエラ(ソプラノ)- ドン・ホセの婚約者
エスカミーリョ(バリトン)- 闘牛士
スニガ(バス)- 衛兵隊長、ドン・ホセの上官
モラレス(バリトンまたはテノール)- 士官
ダンカイロ(バリトンまたはテノール) - 密輸商人
フラスキータ(ソプラノ)- カルメンの友人
メルセデス(メゾソプラノ、ただしソプラノとする楽譜もある)- カルメンの友人
レメンダード(テノール)- ダンカイロの仲間
| 第1幕 1820年ごろのセビリヤ。昼休みに広場に現れたタバコ工場の女工たちに、男たちが言い寄るが、カルメンは全く相手にしない。カルメンは、女工たちに興味 を示さない衛兵の伍長ドン・ホセに花を投げつけ、気を引こうとする。ホセの婚約者であるミカエラが現れ、ホセに故郷の彼の母親からの便りを届ける。セビリ アの煙草工場でジプシーの女工カルメンはけんか騒ぎを起こし、牢に送られることになった。しかし護送を命じられた竜騎兵伍長のドン・ホセは、カルメンに誘 惑されて彼女を逃がす。パスティアの酒場で落ち合おうと言い残してカルメンは去る。 |
| 第2幕 1ヶ月後、カルメンを逃がした罪で牢に入れられていたホセが、釈放される。カルメンが、友人二人(メルセデスとフラスキータ)、衛兵隊長スニガと酒場で歌 い踊っていると、花形闘牛士エスカミーリョが現れ、カルメンの気を引く。釈放されたホセが酒場に着くと、カルメンはホセのために歌って踊り、密輸団の仲間 になるよう誘う。カルメンの色香に迷ったドン・ホセは、婚約者ミカエラを振り切ってカルメンの元に行き、上司とのいさかいのため密輸をするジプシーの群れ に身を投じる。しかし、そのときすでにカルメンの心は闘牛士エスカミーリョに移っていた。 |
| 第3幕 冒頭で、ジプシーの女たちがカードで占いをする。カルメンが占いをすると、不吉な占いが出て結末を暗示する。密輸の見張りをするドン・ホセを、婚約者ミカ エラが説得しに来る。闘牛士エスカミーリョもやってきて、ドン・ホセと決闘になる。騒ぎが収まったあと、思い直すように勧めるミカエラを無視するドン・ホ セに、ミカエラは切ない気持ちを一人独白する。カルメンの心をつなぎとめようとするドン・ホセだが、カルメンの心は完全に離れていた。ミカエラから母の危 篤を聞き、ドン・ホセはカルメンに心を残しつつ、盗賊団を去る。 |
| 第4幕 ホセが盗賊団を去って1ヶ月後、エスカミーリョとその恋人になっているカルメンが闘牛場の前に現れる。エスカミーリョが闘牛場に入ったあと、一人でいるカ ルメンの前にドン・ホセが現れ、復縁を迫る。復縁しなければ殺すと脅すドン・ホセに対して、カルメンはそれならば殺すがいいと言い放つ。そんなホセの執拗 な言動にカルメンは業を煮やし、以前彼からもらった指輪を外して投げつける。逆上したドン・ホセがカルメンを刺し殺し、その場で呆然と立ちつくす。 出典:https://x.gd/AYZzU |
☆カルメンのエチカ(倫理学)とは?
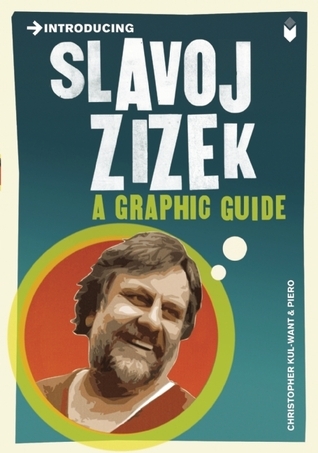
スラヴォイ・ジジェクは面白いことをいう。カルメンは
恋人の人生を破壊し、かつ、自分の死をまねく(=嫉妬によりドンホセにより殺される)にもかかわらず、彼女の行動は「倫理的」だと……ね!!
ジジェクは、ラカン派の現代思想家である。それゆえ、ジジェクが言う「倫理的」とは、決して人畜無害の正しい人のお約束などではなく、倫理的とは、ナチの
強制収容所は生命倫理の極限形態だという、アラン・バディウ(バディウ『倫理』)
の議論をうけており、倫理の本質のなかに、欲望の他者への暴力的な押し付けという性質を避けることができないという。ここで重要なことは、(一見矛盾する
ような——なぜなら普通、倫理的道徳を守るためには、自分の「欲望」を辛抱するつまり抑圧するものだと見なされているので)倫理と欲望の奇妙な共存をどの
ように「理解」するのかということだ。ジジェク派なら、自分の欲望を何であるかについて無自覚なまま「大文字の他者」の欲望を忖度して、自分の生きる倫理
基準にして生きているのが、資本主義下における人間の姿だ、というだろう。したがって、そこから解放されるためには、「大文字の他者」の廃棄、なぜなら(ジジェク派なら)「大文字の他者」などは虚構
であり存在しないからだ、「大文字の他者」など存在しない、忘れてしまうこ
とだ。もちろん、社会(=大文字の他者のひとつの事例)の欲望と、われわれ一人一人の欲望はつねに衝突をおこす。その典型的な事例が、ヘーゲルが好んでとりあげた、ソポクレスの悲劇『アンティゴネー』に出てくる、国王クレオーンの命令に不服従の姿勢を貫いて、兄のポ
リュネイケースの埋葬を「挙行(=劇中ではその点は不明瞭)」し死を覚悟するアンティゴネーの生き方である。アンティゴネーは、ヘーゲルやコージェヴを経由して、ラカンも好んでとりあげた。そして、ラカン派のジジェクも
そうである。結論に入ろう。カルメンとアンティゴネーは、
自分の欲望に忠実であるという意味で、きわめて「倫理的」なのである。言い方を帰ると、自分の欲望の成就と、自分の行動の合致というのが、倫理的なるもの
の姿であり、倫理とは、我慢して従ったり、あるいは「研究倫理」研修
をあくびを噛み殺して出席者の名簿にサインをすることではないのである。
| ジジェク( Less than
nothing : Hegel and the shadow of dialectical materialism /
Slavoj Žižek, Verso , 2013)より "If hedonism is to be rejected, is Lacanian ethics then a version of the heroic immoralist ethics, enjoining us to remain faithful to ourselves and persist on our chosen way beyond good and evil? Think of don Giovanni in the last act of Mozart's opera, when the Stone Guest confronts him with a choice: he is near death, but if he repents of his sins, he can still be redeemed; if, however, he does not renounce his sinful life, he will burn in hell forever. Don Giovanni heroically refuses to repent, although well aware that he has nothing to gain, except eternal suffering, for his persistence. Why does he do it? Obviously not for any profit or promise of pleasure to come. The only explanation is his utmost fidelity to the dissolute life he has chosen. This is a dear case of immoral ethics: don Giovanni's life was undoubtedly immoral; however, as his fidelity to himself proves, he was immoral not for pleasure or profit, but out of principle, acting the way he did in accordance with a fundamental choice. pp.123-124. Or, to take a feminine example also from opera: George Bizet's Carmen. Carmen is, of course, immoral (ruthlessly promiscuous, ruining men's lives, destroying families), but nonetheless thoroughly ethical (faithful to her chosen path to the end, even when this means certain death) Along these lines, Lee Edelman has developed the notion of homosexuality as involving an ethics of "now;' of unconditional fidelity to jouissance, of following the death drive by totally ignoring any reference to the future or engagement with the practical complex of worldly affairs. Homosexuality thus stands for the thorough assumption of the negativity of the death drive, of withdrawing from reality into the real of the "night of the world:' Along these lines, Edelman opposes the radical ethics of homosexuality to the predominant obsession with posterity (i.e., children): children are the "pathological" moment which binds us to pragmatic considerations and thus compels us to betray the radical ethics of jouissance.6t (Incidentally, does this line of thought-the idea that homosexuality at its most fundamental involves the rejection of children-not justify those who argue that gay couples should not be allowed to adopt children 1) The figure of an innocent and helpless child is the ultimate ethical trap, the emblem-fetish of betraying the ethics of jouissance. Friedrich Nietzsche (a great admirer of Carmen) was the great philosopher of immoral ethics, and we should always remember that the title of Nietzsche's masterpiece is "genealogy of morals;' not "of ethics": the two are not the same. Morality is concerned with the symmetry of my relations to other humans; its zero-level rule is "do not do to me what you do not want me to do to you.” Ethics, in contrast, deals with my consistency in relation to myself, my fidelity to my own desire. On the back flyleaf of the 1939 edition of Lenin's Materialism and Empirio-Criticism, Stalin made the following note in red pencil: 1) Weakness
2) Idleness 3) Stupidity These are the only things that can be called vices. Everything else, in the absence of the aforementioned, is undoubtedly virtue. If a man is 1) strong (spiritually), 2) active, 3) clever (or capable), then he is good, regardless of any other "vices" 1) plus 3) make 2)." pp.124-125 This is as concise as ever a formulation of immoral ethics; in contrast, a weakling who obeys moral rules and worries about his guilt stands for unethical morality, the target of Nietzsche's critique of resentment. It is a supreme irony (and one of the greatest cases of poetic justice) that, among American writers, the one who provided the most precise formulation of the same immoral ethics was none other than the rabidly anti-Communist Russian emigrant Ayn Rand, in her first (still moderate) US success, the play Night of January 16th. Although written in a traditional realist mode, this courtroom (melo )drama engages its spectators in a very contemporary, almost Brechtian, manner: at the beginning, the twelve jury members are randomly selected from among the theater audience; they are seated on the stage and, at the play's end, they briefly withdraw before returning to deliver the verdict of guilty or not guilty-Rand proVided different final lines depending on which it was. The decision they have to make is not only about the murder of Bjorn Faulkner, a ruthless Swedish tycoon: did Karen Andre, his devoted mistress and secretary, do it or not? It is also about two opposed ethics-to quote the play itself: if you value a strength that is
its own motor, an audacity that is its own law, a spirit that is its
own vindication-if you are able to admire a man who, no matter what
mistakes he may have made in form, had never betrayed his essence: his
selfesteem-if, deep in your hearts, you've felt a longing for greatness
and for a sense of life beyond the lives around you, if you have known
a hunger which gray timidity can't satisfy ...
In short, if you advocate immoral ethics, you will find Karen not guilty; if, however, you believe in social respectability, in a life of service, duty, and unselfishness, etc., then you will flnd Karen guilty. There is, however, a limit to tbis Stalinist immoral ethics: not that it is too immoral, but that it is secretly too moral, still relying on a figure of the big Other. In what is arguably the most intelligent legitimization of Stalinist terror, Maurice Merleau-Ponty's Humanism and Terror Ii'om 1946, the terror is justified as a kind of wager on the h,ture, almost in the mode of Pascal: if the final result of to day's horror turns out to be a bright communist future, then this outcome will retroactively redeem the terrible things a revolutionary has to do today. Along similar lines, even some Stalinists themselves-when forced to admit (mostly in private) that many of the victims of the purges were innocent, that they were accused and killed because "the Party needed their blood to fortify its unity"¬ imagined a future moment of final victory when all the victims would be given their due, and their innocence and sacrifice for the Cause would be recognized. This is what Lacan, in his seminar on Ethics, refers to as the "perspective of the Last Judgment;' a perspective even more clearly discernible in two key terms of the Stalinist discourse, "objective guilt" and "objective meaning": while you can be an honest individual who acts with the most sincere intentions, you are nonetheless "objectively guilty" if your acts serve reactionary forces-and it is, of course, the Party that decides what your acts "objectively mean." p.126 Here, again, we get not only the perspective of the Last Judgment (from which the "objective meaning" of your acts is formulated), but also the agent in the present who already has the unique ability to jndge today's events and acts from this perspective.The name of Raskolnikov (the hero of Dostoyevsky's Crime and Punishment) evokes a split (raskol); Raskolnikov is "the split one"¬ bnt split between what and what? The standard answer is that he is "torn between the 'Napoleonic idea; the notion that all is permitted to a strong person, and the 'Russian idea' of selfless devotion to humanity"- however, this version misses the properly "totalitarian" coincidence of the two ideas: it is my very selfless devotion to humanity, my awareness that I am an instrument of Humanity, which justifies my claim that all is permitted to me. The paradox is thus that what Raskolnikov lacks is the split itself, the distance between the two ideas, the "Napoleonic" and the "Russian:' We can see now why Lacan's motto "il n'y a pas de grand Autre" (there is no big Other) takes us to the very core of the ethical problematic: what it excludes is precisely this "perspective of the Last Judgment:' the idea that somewhere even if as a thoroughly virtual reference point, even if we concede that we can never occupy its place and pass the actual judgment-there must be a standard which would allow us to take the measure of our acts and pronounce on their "true meaning:' their true ethical status. Even Derrida' s notion of "deconstruction as justice" seems to rely on a utopian hope which sustains the specter of "infinite justice:' forever postponed, always to come, but nonetheless here as the ultimate horizon of our activity.The harshness of Lacanian ethics lies in its demand that we thoroughly relinquish this reference to the big Other-and its further wager is that not only does this renunciation not plunge us into ethical insecurity or relativism (or even sap the very fundamentals of ethical activity), but that renouncing the guarantee of some big Other is the very condition of a truly autonomous ethics. Recall that the exemplary dream Freud used to illustrate his procedure of dream analysis was a dream about responsibility (Freud's own responsibility for the failure of his treatment of Irma)-this fact alone indicates that responsibility is a crucial Freudian notion. But how are we to conceive of this responsibility? How are we to avoid the common misperception that the basic ethical message of psychoanalysis is, precisely, that we should relieve ourselves of responsibility and instead place the blame on the Other ("since the Unconscious is the discourse of the Other, I am not responsible for its formations, it is the big Other who speaks through me, I am merely its instrument")? Lacan himself pointed the way out of this deadlock by referring to Kant's philosophy as the crucial antecedent of psychoanalytic ethics." - Less Than Nothing, Zizek. |
ジジェク( Less than nothing : Hegel
and the shadow of dialectical materialism / Slavoj Žižek, Verso ,
2013)より 快楽主義が否定されるのであれば、ラカンの倫理学は、自分自身に忠実であり続けること、善悪を超えて自分の選んだ道を貫くことを私たちに勧める、英雄的非 道徳主義者の倫理学のバージョンなのだろうか?モーツァルトのオペラの終幕で、石の客に選択を迫られるドン・ジョヴァンニを思い浮かべてほしい。彼は死を 目前にしているが、罪を悔い改めればまだ救済される。ドン・ジョヴァンニは、永遠の苦しみ以外に得るものがないことを十分承知しながらも、勇気をもって悔 い改めることを拒否する。なぜ彼はそれをするのか?明らかに、利益を得るためでも、来るべき喜びを約束するためでもない。唯一の説明は、自分が選んだ放蕩 生活への最大限の忠誠である。ドン・ジョヴァンニの人生は間違いなく不道徳であった。しかし、彼の自分自身への忠実さが証明しているように、彼は快楽や利 益のためではなく、原理から不道徳になったのであり、根本的な選択に従ってそのように行動したのである。 あるいは、同じくオペラの女性的な例を挙げよう: ジョージ・ビゼーの『カルメン』だ。カルメンはもちろん不道徳だが(冷酷に乱交し、男性の人生を破滅させ、家庭を破壊する)、それにもかかわらず、徹底的 に倫理的である(たとえそれが確実な死を意味するものであっても、最後まで自分の選んだ道に忠実である)。この線に沿って、リー・エデルマンは、同性愛を 「今」の倫理に関わるものとしてとらえ、ジュイサンスへの無条件の忠実さ、未来への言及や現実的な複雑な世俗問題との関わりを完全に無視することによって 死の衝動に従うという概念を展開した。したがって、同性愛は、死の衝動の否定性を徹底的に引き受けること、現実から「世界の夜」の現実へと引きこもること の象徴なのである。この線に沿って、エーデルマンは、同性愛の急進的倫理を、後世(すなわち子ども)への支配的な執着と対立させる。子どもは、われわれを 現実的な配慮に縛りつけ、その結果、われわれにジュイサンスの急進的倫理を裏切らせる「病的な」瞬間なのである6。 無垢で無力な子どもの姿は、究極の倫理的罠であり、ユイサンスの倫理を裏切ることの象徴である。 フリードリヒ・ニーチェ(カルメンの偉大な崇拝者)は、不道徳な倫理の偉大な哲学者である。道徳とは、私と他の人間との関係の対称性に関わるものであり、 そのゼロ・レベルのルールは「自分がしてほしくないことを自分にしてはならない」である。これに対して倫理は、私自身との関係における一貫性、つまり私自 身の欲望に対する忠実さを扱う。レーニンの『唯物論と経験批判』(1939年版)の裏のチラシに、スターリンは赤鉛筆で次のように記している: 1)弱さ
2)怠惰 3)愚かさ それ以外のものは、前述のものがなければ、間違いなく美徳である。もし人が1)強く(精神的に)、2)活動的で、3)利口(あるいは有能)であれば、1) +3)で2)となる他の「悪徳」があろうとも、その人は善である。" これとは対照的に、道徳的な規則を守り、自分の罪を心配する弱者は、非道徳的な道徳の象徴であり、ニーチェの怨恨批判の対象である。アメリカの作家の中 で、同じ非道徳的倫理を最も正確に定式化したのが、熱狂的な反共産主義者であるロシア移民のアイン・ランドであり、彼女のアメリカでの最初の(まだ穏健 な)成功作である戯曲『1月16日の夜』であったことは、この上ない皮肉である(そして詩的正義の最も偉大なケースの一つである)。伝統的なリアリズムの 様式で書かれたこの法廷劇は、観客を非常に現代的な、ほとんどブレヒト的な方法で惹きつける。冒頭、12人の陪審員が劇場の観客の中から無作為に選ばれ、 舞台に着席し、劇の最後に、有罪か無罪かの評決を下すために戻ってくる前に、いったん退席する。彼らが下さなければならない決断は、冷酷なスウェーデンの 大物ビョルン・フォークナーの殺人についてだけではない。また、劇中の言葉を引用すれば、2つの相反する倫理観についても描かれている: もしあなたが、自らの原動力となる強さ、自らの掟となる大胆さ、自らの正当性を証明する精神に価値を見出すなら、もしあなたが、形の上ではどんな過ちを犯 そうとも、その本質、すなわち自尊心を決して裏切らなかった男を賞賛できるなら、もしあなたが、心の奥底で、偉大さへの憧れや、周囲の人生を超えた人生へ の感覚を感じたことがあるなら、もしあなたが、灰色の臆病さでは満たすことのできない飢えを知っているなら......。 要するに、もしあなたが不道徳な倫理を唱えるなら、カレンは無罪となる。
しかし、もしあなたが社会的な尊敬、奉仕、義務、無私の生き方などを信じるなら、カレンは有罪となる。
しかし、このスターリン主義的不道徳倫理学には限界がある。それは、不道徳すぎるということではなく、密かに道徳的すぎるということであり、依然として大 きな他者の姿に依存している。1946年に発表されたモーリス・メルロ=ポンティの『ヒューマニズムとテロル』(邦題『スターリン主義的テロル』)は、間 違いなくスターリン主義的テロルを最も理性的に正当化したものであるが、このテロルは、ほとんどパスカルのようなやり方で、一種の賭けとして正当化されて いる。同じような路線で、スターリニスト自身も、粛清の犠牲者の多くが無実であったこと、「党の団結を強固にするために彼らの血が必要であった」ために告 発され殺されたことを(主に内輪で)認めざるを得なくなったとき、すべての犠牲者に相応の報いが与えられ、彼らの無実と大義のための犠牲が認められる将来 の最終的な勝利の瞬間を想像した。これは、ラカンが倫理学のセミナーで「最後の審判の視点」と呼んでいるものである。この視点は、スターリン主義者の言説 の2つの重要な用語、「客観的な有罪」と「客観的な意味」において、さらにはっきりと見分けることができる。 ドストエフスキーの『罪と罰』の主人公であるラスコーリニコフの名前は、分裂(raskol)を連想させる。標準的な答えは、彼が「『ナポレオン的発 想』、つまり強い人間にはすべてが許されるという考え方と、『ロシア的発想』、つまり人類への無私の献身との間で葛藤している」というものだが、このバー ジョンでは、この2つの発想の適切な「全体主義的」一致を見逃している。つまり、ラスコーリニコフに欠けているのは、分裂そのものであり、「ナポレオン 的」と「ロシア的」という二つの思想の間の距離なのである。 ここでもまた、私たちは最後の審判の視点(そこからあなたの行為の「客観的意味」が定式化される)だけでなく、そこから今日の出来事や行為を判断する独特 の能力をすでに持っている現在の主体者についても知ることができます。 視点。ラスコーリニコフ(ドストエフスキーの『罪と罰』の主人公)の名前は分裂(ラスコル)を呼び起こします。 ラスコーリニコフは「分裂した者」であり、何と何の間で分裂しているのでしょうか? 標準的な答えは、彼が「強い者にはすべてが許されるという『ナポレオンの考え』と、人類への無私の献身という『ロシアの考え』の間で引き裂かれている」と いうものだ。しかし、このバージョンでは適切な「全体主義的」な偶然が欠けている。 それは人類に対する私の非常に無私な献身であり、私は人類の道具であるという認識であり、それは私にすべてが許されているという私の主張を正当化します。 したがって、ラスコーリニコフに欠けているのは、「ナポレオン的」と「ロシア的」という二つの思想の間の距離である分裂そのものであるという矛盾である。 ラカンのモットー "il n'y a pas de grand Autre"(大きな他者は存在しない)がなぜ倫理的問題の核心に迫 るのか、その理由がわかるだろう。ラカンが排除しているのは、まさにこの「最後の審判の視点」であり、たとえ徹底的 にヴァーチャルな基準点であったとしても、私たちがその場所を占拠し、実際の審判を下すこと ができないことを認めたとしても、どこかに、私たちの行為を測定し、その「真の意味」、 すなわち真の倫理的地位を宣告することを可能にする基準があるはずだという考えである。デリダの「正義としての脱構築」という概念でさえも、「無限の正 義」(永遠に先延ばし され、常に来るべきものであるが、それでもなお、われわれの活動の究極的な地平とし てここにある)の亡霊を支えるユートピア的な希望に依拠しているように思われる。 ラカンの倫理学の厳しさは、この「大きな他者」への言及を徹底的に放棄することを要求するところにあり、そのさらなる賭けは、この放棄によって倫理的不安 や相対主義に陥らない(あるいは、倫理的活動の根幹が損なわれない)だけでなく、「大きな他者」の保証を放棄することが、真に自律的な倫理の条件そのもの であるということである。フロイトが夢分析の手順を説明するために用いた模範的な夢が、責任(イルマに対する治療の失敗に対するフロイト自身の責任)に関 する夢であったことを思い出してほしい--この事実だけでも、責任がフロイトの重要な概念であることを示している。しかし、この責任をどのように考えれば よいのだろうか。精神分析の基本的な倫理的メッセージが、正確には、私たち自身の責任を免除し、その代わりに他者に責任を負わせることである(「無意識は 他者の言説であるため、その形成について私は責任を負わない。) ラカン自身は、精神分析倫理の決定的な先例としてカント哲学に言及することで、この行き詰まりを打開する道を指し示している。 |
| https://www.reddit.com/r/zizek/comments/7hwkg6/the_good/ | https://www.deepl.com/ja/translator |
★他方、ラカンさんは?
Lacan's
work is vast: twenty years of seminars, the long and difficult volume
Écrits, several other articles and the Television interview we have
discussed here. That means weeks, months, years of work and effort for
the reader who wants to understand something about it. One could say
the same thing about psychoanalytic treatment itself: so many years, so
much time, so much money. Is it worth it?
If it is worth dedicating so much libido to psychoanalysis, it's
because psychoanalysis is not psychotherapy.
If
it were only to cure the neurotic symptom, if it were only to put an
end to the neurotic complaint, it would be out of all proportion to do
so. Psychoanalysis has therapeutic effects, but psychoanalysis is much
more than psychotherapy.
Let's turn to
the interpreting of the
analyst. In a certain
sense we can say that
this is what the
analyst owes to the
analysand. To interpret
seems to be something
active, not something
passive, but it is
nevertheless important
to see the extent of
what is excluded by
this duty of
interpretation, the
area of what we can
call the abstention of
the psychoanalyst. To
interpret means not to
evaluate, not to judge,
not to act and even to
leave aside any
feelings. No doubt
there is something else
that the analyst
requires here: he has
to make the rule of
free association apply.
So there is a demand
for speech, but he has
nothing to discuss; he
has nothing to say
about what is said; he
isn't there to agree,
to condemn or to blame;
he neither censors nor
endorses.
So he does not say
anything, only
interprets. This is a
choice, sometimes a
difficult one which
needs to be repeated
every day with each
patient.
To interpret is only to designate what was said in what the subject articulated, and in that sense the desire of the psychoanalyst — you know that Lacan gave a key function to this desire — is first of all a desire for interpretation. We could say that the desire of the analyst emerges in the interpretation. [...] * The Lacan Conference, April 15, 1990, at Barnard College, Columbia University, New York.
ラ カンの仕事は膨大である。20年にわたるセミナー、長くて難解な『Écrits』、その他いくつかの論文、そしてここで取り上げたテレビのインタビュー。 つまり、何かを理解しようとする読者にとっては、数週間、数カ月、数年にわたる仕事と努力が必要なのだ。精神分析の治療そのものについても同じことが言え る。それだけの価値があるのだろうか?精神分析に多くのリビドーを捧げる価値があるとすれば、それは精神分析が心理療法ではないからである。
神 経症的な症状を治すだけなら、神経症的な訴えに終止符を打つだけなら、そんなことをするのは筋違いである。精神分析には治療効果があるが、精神分析は精神 療法以上のものである。
ラ カン自身の言葉「分析者の解釈に目を向けよう。ある意味では、これは分析者が分析者に負っているものだと言える。解釈するということは、受動的なことでは なく、能動的なことであるように思われるが、それにもかかわらず、この解釈の義務によって排除されるものの範囲、精神分析家の禁欲と呼ぶことのできる領域 を見ることは重要である。解釈するということは、評価しないこと、判断しないこと、行動しないこと、さらにはいかなる感情も脇に置いておくことを意味す る。分析家がここで要求するのは、自由連想のルールを適用させることである。つまり、言論の要求はあるが、彼は何も議論することはなく、言われたことにつ いて何も言うことはない。だから彼は何も言わず、ただ解釈する。これは時に困難な選択であり、患者一人ひとりに対して毎日繰り返す必要がある。」
そ
の意味で、精神分析家の欲望——ラカンがこの欲望に重要な機能を与えたことはご存じかと思う——は、まず第一に解釈への欲望なのである。分析者の欲望は解
釈の中に現れると言える。
https://www.lacan.com/frameII2.htm
リンク
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099
++
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆