
ヘーゲルとアンティゴネー
Antigone and G.W.F. Hegel
「政治的対立を法的訴えにつくりかえて、国家にフェ ミズムの主張を支持するような合法化を求めようとする現在のフェミニズムの試みのなかでは、アンティゴネーの反抗の遺産は失われているように思えた」—— ジュディス・バトラー『アンティゴネーの主張』竹村和子訳、p.14, 青土社, 2002年
「ヘーゲルにおけるアンティゴネー読解でラカンが気に入らないのは、ヘーゲルがアンティゴネーとクレオンに、対立する原理や諸力、親族〈対〉国家、個人〈対〉普遍を代表させようとしている点です」(バトラー2019:19)
「共同体意識が、自分と対立する掟と権力の存在をあらかじめ承知し、それを暴力的で不当な権
力、たまたま共同体を代表しているにすぎない権力と見なし、犯罪と知りつつ犯罪を犯すアンティゴネーのような場合には、共同体意識としていっそう完全な意
識であり、その責任も純粋である」——ヘーゲル『精神現象学』(長谷川訳 1998:318)
『アンティゴネ』 (アンティゴネー、古代ギリシア語: Ἀντιγόνη、ラテン語: Antigone)は「古代ギリシア三大悲劇詩人の一人であるソポクレスが紀元前442年ごろに書いたギリシア悲劇。オイディプスの娘でテーバイの王女で あるアンティゴネを題材とする。……先王オイディプスが自己の呪われた運命を知って盲目となり(『オイディプス王』)、放浪の末にこの世を去った(『コロ ノスのオイディプス』)後、アンティゴネとイスメネはテーバイへ戻った。しかしテーバイでもアンティゴネの兄たちが王位を巡って争いを始めて、アルゴス人 の援助を受けてテーバイに攻め寄せたポリュネイケスとテーバイの王位にあったエテオクレスが刺し違えて死に、クレオンがテーバイの統治者となった。/クレオンは国家に対する反逆者であるポリュネイケスの埋葬や一切の葬礼を禁止し、見張りを立て てポリュネイケスの遺骸を監視させる。アンティゴネはこの禁令を犯し、見張りに捕らえられてクレオンの前に引き立てられる。人間の自然に基づく法を主張するアンティゴネと国家の法の厳正さを主張するクレオンは互いに譲らず、イスメネやハイモンの取り 成しの甲斐もなくて、クレオンは実質の死刑宣告として、一日分の食料を持たせてアンティゴネを地下に幽閉することを決定する。/その後、クレオンはテイレシアースの占いと長老たちの進言を受けてアンティゴネへの処分を撤回し、ポ リュネイケスの遺体の埋葬を決める。しかし時既に遅く、アンティゴネは首を吊り、父(クレオン)を恨んだアンティゴネの夫ハイモンも剣に伏 して自殺した。、クレオンが自らの運命を嘆く場面で劇は終わる」 #Wiki.
| Kreon: Now tell me, not at length, but in brief space, Knew you the order not to do it? Antigone: Yes I knew it; what should hinder? It was plain. Kreon: And you made free to overstep my law? Antigone: Because it was not Zeus who ordered it, Nor Justice, dweller with the Nether Gods, Gave such a law to men; nor did I deem Your ordinance of so much binding force, As that a mortal man could overbear The unchangeable unwritten code of Heaven; This is not of today and yesterday, But lives forever, having origin Whence no man knows: whose sanctions I were loath In Heaven’s sight to provoke, fearing the will Of any man. I knew that I should die – How otherwise? Even although your voice Had never so prescribed. And that I die Before my hour is due, that I count gain. For one who lives in many ills, as I – How should he fail to gain by dying? Thus To me the pain is light, to meet this fate: But had I borne to leave the body of him My mother bare unburied, then, indeed, I might feel pain; but as it is, I cannot: And if my present actions seems to you Foolish – ‘tis like I am found guilty of folly At a fool’s mouth! (ll 446-470, Young translation) |
クレオン: さて、長々とではなく、簡潔に教えてくれ、 それをするなという命令を知っていたのか? アンティゴネー:はい: 知っていた。 知っていた。明白なことだ。 クレオン: 私の掟を自由に踏み越えたのか? アンティゴネー: それを命じたのはゼウスではないからだ、 ネザー神々の住まいである正義でもない、 そのような掟を人に与えたのでもない。 あなたの掟がそれほど拘束力があるとは思わなかった、 死すべき人間が、この不変の不文律に打ち勝つことができるほど 天の不変の不文律を、死すべき人間が覆すほどの拘束力があるとは思わなかった; これは今日や昨日のものではない、 永遠に生き続ける。 その制裁を,わたしは憎む。 天の御目には,人の意志を恐れて,挑発することを嫌う。 その制裁を私は天の目には恐れた。私は死ぬことを知っていた。 そうでなければどうする?たとえあなたの声が 私は死ぬのだ。そして私は死ぬ 私は得をしたと思っている。 わたしと同じように、多くの悪の中に生きている者が 死んで得をしないはずがない。このように 私にとっては、この運命を迎える苦痛は軽い: だが、もし私が、彼の遺体を、母が埋葬されないままにしておくのを忍んでいたなら 母が埋葬されずに彼の遺体を残していたなら、確かにそうであっただろう、 苦痛を感じるかもしれない: そして、もし私の今の行動が、あなたがたに愚かに見えるなら 愚かなことだ。 愚か者の口で!(446-470, ヤング訳) |
| https://creatureandcreator.ca/?p=1830/ |
ポイントを整理しよう;テーバイで、アンティゴネの 兄たちが王位を巡って争いを始めて、最終的に彼らの叔父にあたるクレオンが新しい統治者になる。クレオンは、謀反者のポ リュネイケス(アンティゴネの兄)らを埋葬を禁じる。しかし、アンティゴネは、その国禁を侵し、兄を埋葬することを主張する。アンティゴネは捕まり、クレ オンの前で、自然なキョウダイへの愛を実践する兄の埋葬の正当性を主張する。クレオンは法の厳密な実行こそが重要だと譲らない。クレオンは、アンティゴネ を幽閉することを決めるが、託宣により、アンティゴネへの処分を取り消すが、アンティゴネもその夫のハイモンも自死して、クレオンはその運命を呪いつつ劇 はおわる。
Antigone, by Frederic
Leighton
アンティゴネーの 悲劇は、兄への弔意という肉親の情および人間を埋葬するという人倫的習俗と神への宗 教的義務と、国家による法の適用の対立から来るもので ある。哲学者ヘーゲルは『精神現象学』の「BB 精神 VI 精神 A真の精神——共同体精神(つまり道徳)」の章にて、アンティゴネーを人間意識の客観的段階のひとつである道徳=人倫の象徴とし て分析している(長谷川訳「精神現象学」Pp.313-324.)。
| Phänomenologie des Geistes |
精神現象学 |
| VI Der Geist |
VI 精神 |
| A Der wahre Geist , die Sittlichkeit |
A 真の精神、道徳 |
| b Die sittliche Handlung, das menschliche und göttliche Wissen, die Schuld und das Schicksal |
b 道徳的行為、人間的および神的な知識、罪、そして運命 |
| Wie aber in diesem Reiche der
Gegensatz beschaffen ist, so ist das Selbstbewußtsein noch nicht in
seinem Rechte als einzelne Individualität aufgetreten; sie gilt in ihm
auf der einen Seite nur als allgemeiner Willen, auf der andern als Blut
der Familie; dieser Einzelne gilt nur als der unwirkliche Schatten. --
Es ist noch keine Tat begangen; die Tat aber ist das wirkliche Selbst.
-- Sie stört die ruhige Organisation und Bewegung der sittlichen Welt.
Was in dieser als Ordnung und Übereinstimmung ihrer beiden Wesen
erscheint, deren eins das andere bewährt und vervollständigt, wird
durch die Tat zu einem Übergange entgegengesetzter, worin jedes sich
vielmehr als die Nichtigkeit seiner selbst und des andern beweist, denn
als die Bewährung; -- es wird zu der negativen Bewegung oder der ewigen
Notwendigkeit des furchtbaren Schicksals, welche das göttliche wie das
menschliche Gesetz, sowie die beiden Selbstbewußtsein, in denen diese
Mächte ihr Dasein haben, in den Abgrund seiner Einfachheit verschlingt
-- und für uns in das absolute Für-sich-sein des rein einzelnen
Selbstbewußtseins übergeht. |
しかし、この領域における対立の性質上、自己意識はまだ個々の個性とし
てその権利を発揮していない。この領域では、自己意識は、一方では一般的な意志として、他方では家族の血としてのみ機能しており、この個人は、非現実的な
影にすぎない。まだ行為は実行されていない。しかし、行為こそが真の自己である。--
それは、道徳の世界の穏やかな組織と動きを乱す。この世界において、その二つの存在の秩序と調和として現れ、一方が他方を証明し、完成しているものは、行
為によって、反対のものへと移行し、そこでは、それぞれが、むしろ、自分自身と他方の無意味さを証明するものであり、証明ではない。--
それは、神聖な法則と人間の法則、そしてこれらの力が現存在(Dasein)を持つ2つの自己意識を、その単純さの深淵に飲み込む、恐ろしい運命の否定的
な動き、あるいは永遠の必然性となり、そして私たちにとっては、純粋に個別の自己意識の絶対的な「それ自体」へと移行する。 |
| 1. 個性と本質の矛盾 |
1. Contradiction of Individuality with its Essence |
| Der Grund, von dem diese
Bewegung aus- und auf dem sie vorgeht, ist das Reich der Sittlichkeit;
aber die Tätigkeit dieser Bewegung ist das Selbstbewußtsein. Als
sittliches Bewußtsein ist es die einfache reine Richtung auf die
sittliche Wesenheit, oder die Pflicht. Keine Willkür, und ebenso kein
Kampf, keine Unentschiedenheit ist in ihm, indem das Geben und das
Prüfen der Gesetze aufgegeben worden, sondern die sittliche Wesenheit
ist ihm das Unmittelbare, Unwankende, Widerspruchslose. Es gibt daher
nicht das schlechte Schauspiel, sich in einer Kollision von
Leidenschaft und Pflicht, noch das Komische, in einer Kollision von
Pflicht und Pflicht zu befinden -- einer Kollision, die dem Inhalte
nach dasselbe ist als die zwischen Leidenschaft und Pflicht; denn die
Leidenschaft ist ebenso fähig, als Pflicht vorgestellt zu werden, weil
die Pflicht, wie sich das Bewußtsein aus ihrer unmittelbaren
substantiellen Wesenheit in sich zurückzieht, zum Formell-Allgemeinen
wird, in das jeder Inhalt gleich gut paßt, wie sich oben ergab. Komisch
aber ist die Kollision der Pflichten, weil sie den Widerspruch, nämlich
eines entgegengesetzten Absoluten, also Absolutes und unmittelbar die
Nichtigkeit dieses sogenannten Absoluten oder Pflicht, ausdrückt. --
Das sittliche Bewußtsein aber weiß, was es zu tun hat; und ist
entschieden, es sei dem göttlichen oder dem menschlichen Gesetze
anzugehören. Diese Unmittelbarkeit seiner Entschiedenheit ist ein
An-sich-sein, und hat daher zugleich die Bedeutung eines natürlichen
Seins, wie wir gesehen; die Natur, nicht das Zufällige der Umstände
oder der Wahl, teilt das eine Geschlecht dem einen, das andere dem
andern Gesetze zu -- oder umgekehrt, die beiden sittlichen Mächte
selbst geben sich an den beiden Geschlechtern ihr individuelles Dasein
und Verwirklichung. |
この運動の出発点であり、その基盤となっているのは道徳の領域である
が、この運動の活動は自己意識だ。道徳的意識として、それは道徳の本質、すなわち義務への単純で純粋な指向なのである。そこには、恣意も、闘争も、優柔不
断さも存在しない。なぜなら、法律の制定と検証が放棄されているからだ。道徳の本質は、彼にとって直接的で、揺るぎない、矛盾のないものである。したがっ
て、情熱と義務の衝突という悪い光景も、義務と義務の衝突という滑稽な光景も存在しない。この衝突は、その内容としては情熱と義務の衝突と同じである。な
ぜなら、情熱は義務として表現することも可能だからだ。義務は、その直接的な実体的な本質から意識が後退すると、形式的な一般性となり、上述のように、あ
らゆる内容が等しく適合するからだ。しかし、義務の衝突は、矛盾、すなわち相反する絶対、つまり絶対と、このいわゆる絶対、あるいは義務の無意味さを直接
的に表現しているから、滑稽なんだ。しかし、道徳的意識は、自分がすべきことを知っていて、それが神の法則に属するか、人間の法則に属するかについて決定
している。この決意の直接性は、それ自体であるということであり、したがって、これまで見てきたように、自然の存在という意味も持つ。偶然の事情や選択で
はなく、自然が、ある性別には一方の法則を、別の性別にはもう一方の法則を割り当てている。あるいは逆に、2つの道徳的力自体が、2つの性別にそれぞれの
個別の現存在(Dasein)と実現を与えている。 |
| Hiedurch nun, daß einesteils die
Sittlichkeit wesentlich in dieser unmittelbaren Entschiedenheit
besteht, und darum für das Bewußtsein nur das eine Gesetz das Wesen
ist, andernteils, daß die sittlichen Mächte in dem Selbst des
Bewußtseins wirklich sind, erhalten sie die Bedeutung, sich
auszuschließen und sich entgegengesetzt zu sein; -- sie sind in dem
Selbstbewußtsein für sich, wie sie im Reiche der Sittlichkeit nur an
sich sind. Das sittliche Bewußtsein, weil es für eins derselben
entschieden ist, ist wesentlich Charakter; es ist für es nicht die
gleiche Wesenheit beider; der Gegensatz erscheint darum als eine
unglückliche Kollision der Pflicht nur mit der rechtlosen Wirklichkeit.
Das sittliche Bewußtsein ist als Selbstbewußtsein in diesem Gegensatze,
und als solches geht es zugleich darauf, dem Gesetze, dem es angehört,
diese entgegengesetzte Wirklichkeit durch Gewalt zu unterwerfen, oder
sie zu täuschen. Indem es das Recht nur auf seiner Seite, das Unrecht
aber auf der andern sieht, so erblickt von beiden dasjenige, welches
dem göttlichen Gesetze angehört, auf der andern Seite menschliche
zufällige Gewalttätigkeit; das aber dem menschlichen Gesetze zugeteilt
ist, auf der andern den Eigensinn und den Ungehorsam des innerlichen
Für-sich-seins; denn die Befehle der Regierung sind der allgemeine, am
Tage liegende öffentliche Sinn; der Willen des andern Gesetzes aber ist
der unterirdische, ins Innre verschlossne Sinn, der in seinem Dasein
als Willen der Einzelnheit erscheint, und im Widerspruche mit dem
ersten der Frevel ist. |
このように、一方では道徳は本質的にこの直接的な決定性に存在し、それ
ゆえ意識にとって唯一の法則がその本質である一方、他方では道徳的力は意識の自己の中に実在しているため、それらは互いに排除し合い、対立する意味を持
つ。--
それらは、道徳の領域ではそれ自体としてのみ存在するのに対し、自己意識の中ではそれ自体として存在する。道徳的意識は、そのうちの1つとして決定されて
いるため、本質的に性格である。それは、その両方と同じ本質ではない。したがって、その対立は、義務と無権利の現実との不幸な衝突として現れる。道徳的意
識は、この対立において自己意識として存在し、そのようにして、同時に、それが属する法則に対して、この対立する現実を暴力によって服従させるか、あるい
は欺くか、という行動に走ります。正義は自分の側にあり、不正は相手側にあると見ることで、神聖な法則に属するものを一方に見、他方では人間の偶発的な暴
力を見出す。一方、人間の法則に属するものとして、内面の自己存在の頑固さと不服従を見ます。なぜなら、政府の命令は、表面的で公的な一般的な意味である
のに対し、
しかし、もう一方の法則の意志は、地下に隠され、内面に閉じ込められた意味であり、その現存在(Dasein)において、個々の意志として現れ、最初の法
則と矛盾する不敬(=共同体に対する反抗)である。 |
| Es entsteht hiedurch am
Bewußtsein der Gegensatz des Gewußten und des Nichtgewußten, wie in der
Substanz, des Bewußten und Bewußtlosen; und das absolute Recht des
sittlichen Selbstbewußtseins kommt mit dem göttlichen Rechte des Wesens
in Streit. Für das Selbstbewußtsein als Bewußtsein hat die
gegenständliche Wirklichkeit als solche Wesen; nach seiner Substanz
aber ist es die Einheit seiner und dieses Entgegengesetzten; und das
sittliche Selbstbewußtsein ist das Bewußtsein der Substanz; der
Gegenstand als dem Selbstbewußtsein entgegengesetzt, hat darum gänzlich
die Bedeutung verloren, für sich Wesen zu haben. Wie die Sphären, worin
er nur ein Ding ist, längst verschwunden, so auch diese Sphären, worin
das Bewußtsein etwas aus sich befestiget und ein einzelnes Moment zum
Wesen macht.. |
これにより、意識において、知られているものと知られていないもの、つ
まり実体における意識と無意識との対立が生じ、道徳的自己意識の絶対的権利は、存在の神聖な権利と対立する。意識としての自己意識にとって、対象的な現実
はそれ自体として実体を有している。しかし、その実体としては、自己意識は、自己とこの対立物との統一である。そして、道徳的自己意識は、実体の意識であ
る。自己意識と対立する対象は、それゆえ、それ自体として実体を持つという意味を完全に失っている。彼がただ一つの物である領域は、とっくに消滅している
ように、意識がそれ自体から何かを固定し、単一の瞬間を本質とする領域も消滅している。 |
| Gegen solche Einseitigkeit hat
die Wirklichkeit eine eigene Kraft; sie steht mit der Wahrheit im Bunde
gegen das Bewußtsein, und stellt diesem erst dar, was die Wahrheit ist.
Das sittliche Bewußtsein aber hat aus der Schale der absoluten Substanz
die Vergessenheit aller Einseitigkeit des Für-sich-seins, seiner Zwecke
und eigentümlichen Begriffe getrunken, und darum in diesem stygischen
Wasser zugleich alle eigne Wesenheit und selbstständige Bedeutung der
gegenständlichen Wirklichkeit ertränkt. Sein absolutes Recht ist daher,
daß es, indem es nach dem sittlichen Gesetze handelt, in dieser
Verwirklichung nicht irgend etwas anderes finde, als nur die
Vollbringung dieses Gesetzes selbst, und die Tat nichts anders zeige,
als das sittliche Tun ist. -- |
そのような偏見に対して、現実は独自の力を持っている。それは真実と結
託して意識に対抗し、意識に真実とは何であるかを初めて示すのだ。しかし、道徳的意識は、絶対的な実体の殻から、自己存在の一方的な側面、その目的、そし
て固有の概念のすべてを忘却し、そのスティクス川の水の中で、対象的な現実の固有の本質と自立した意味を同時に溺死させてしまった。したがって、道徳的意
識の絶対的な権利とは、道徳的法則に従って行動する際に、その実現において、その法則自体の成就以外の何物も発見せず、行為が道徳的行為以外の何物も示さ
ないことである。-- |
| Das Sittliche, als das absolute
Wesen und die absolute Macht zugleich kann keine Verkehrung seines
Inhalts erleiden. Wäre es nur das absolute Wesen ohne die Macht, so
könnte es eine Verkehrung durch die Individualität erfahren; aber diese
als sittliches Bewußtsein hat mit dem Aufgeben des einseitigen
Für-sich-seins dem Verkehren entsagt; so wie die bloße Macht umgekehrt
vom Wesen verkehrt werden würde, wenn sie noch ein solches
Für-sich-sein wäre. Um dieser Einheit willen ist die Individualität
reine Form der Substanz, die der Inhalt ist, und das Tun ist das
Übergehen aus dem Gedanken in die Wirklichkeit, nur als die Bewegung
eines wesenlosen Gegensatzes, dessen Momente keinen besondern von
einander verschiedenen Inhalt und Wesenheit haben. Das absolute Recht
des sittlichen Bewußtseins ist daher, daß die Tat, die Gestalt seiner
Wirklichkeit, nichts anders sei, als es weiß |
道徳は、絶対的な存在であり、同時に絶対的な力でもあるため、その内容
に逆転は起こらない。もしそれが権力のない絶対的な存在だけなら、個性の影響を受けてその内容が逆転する可能性はある。しかし、道徳的意識としての個性
は、一方的な自己存在を放棄することで、その逆転を拒否している。逆に、単なる権力が、もしそれがまだそのような自己存在であったならば、存在によって逆
転されるだろう。この統一のために、個性は、内容である実体の純粋な形態であり、行為は、思考から現実への移行であり、その瞬間は、互いに異なる内容や実
体を持たない、実体のない対立の運動としてのみ存在する。したがって、道徳的意識の絶対的な権利は、その現実の形である行為が、それが知っているもの以外
の何物でもないことにある。 |
| Aber das sittliche Wesen hat
sich selbst in zwei Gesetze gespalten, und das Bewußtsein, als
unentzweites Verhalten zum Gesetze, ist nur einem zugeteilt. Wie dies
einfache Bewußtsein auf dem absoluten Rechte besteht, daß ihm als
sittlichem das Wesen erschienen sei, wie es an sich ist, so besteht
dieses Wesen auf dem Rechte seiner Realität, oder darauf, gedoppeltes
zu sein. Dies Recht des Wesens steht aber zugleich dem Selbstbewußtsein
nicht gegenüber, daß es irgendwoanders wäre, sondern es ist das eigne
Wesen des Selbstbewußtseins; es hat darin allein sein Dasein und seine
Macht, und sein Gegensatz ist die Tat des Letztern. Denn dieses, eben
indem es sich als Selbst ist und zur Tat schreitet, erhebt sich aus der
einfachen Unmittelbarkeit und setzt selbst die Entzweiung. Es gibt
durch die Tat die Bestimmtheit der Sittlichkeit auf, die einfache
Gewißheit der unmittelbaren Wahrheit zu sein, und setzt die Trennung
seiner selbst in sich als das Tätige und in die gegenüberstehende für
es negative Wirklichkeit. Es wird also durch die Tat zur Schuld. Denn
sie ist sein Tun, und das Tun sein eigenstes Wesen; und die Schuld
erhält auch die Bedeutung des Verbrechens: denn als einfaches
sittliches Bewußtsein hat es sich dem einen Gesetze zugewandt, dem
andern aber abgesagt, und verletzt dieses durch seine Tat. -- |
しかし、道徳的存在はそれ自体を二つの法則に分割し、法則に対する分割
されていない行動としての意識は、そのうちの1つだけに割り当てられている。この単純な意識が、道徳的存在としてその本質がそのまま現れているという絶対
的な権利に基づいて存在しているように、この本質は、その現実性、すなわち二重性という権利に基づいて存在している。しかし、この実体の権利は、自己意識
に対して、それがどこか別の場所にあるという対立関係にあるのではなく、自己意識の固有の実体であり、自己意識は、その中にのみその現存在
(Dasein)と力を持ち、その対立は、後者の行為である。なぜなら、後者は、まさに自己として存在し、行為へと進むことによって、単純な直接性から立
ち上がり、自ら二分するからだ。行為によって、道徳は、直接的な真実であるという単純な確実性を放棄し、行為としての自己と、それに対して否定的な現実と
の分裂を、自己の中に設定する。したがって、行為によってそれは罪となる。なぜなら、行為はそれ自身の行動であり、行動はそれ自身の最も本質的な性質であ
るから。そして、罪は犯罪の意味も持つ。なぜなら、単純な道徳的意識として、ある法則に従うことを選び、別の法則を拒否し、その行為によってその法則に違
反するからである。-- |
| Die Schuld ist nicht das
gleichgültige doppelsinnige Wesen, daß die Tat, wie sie wirklich am
Tage liegt, Tun ihres Selbsts sein könne oder auch nicht, als ob mit
dem Tun sich etwas Äußerliches und Zufälliges verknüpfen könnte, das
dem Tun nicht angehörte, von welcher Seite das Tun also unschuldig
wäre. Sondern das Tun ist selbst diese Entzweiung, sich für sich, und
diesem gegenüber eine fremde äußerliche Wirklichkeit zu setzen; daß
eine solche ist, gehört dem Tun selbst an und ist durch dasselbe.
Unschuldig ist daher nur das Nichttun wie das Sein eines Steines, nicht
einmal eines Kindes. -- |
罪は、その行為が実際にその日に起こったものとして、その行為自体がそ
れ自体であるかもしれないし、そうでないかもしれないという、無関心で曖昧な性質ではない。それは、その行為に、その行為に属さない、外的な、偶然的なも
のが結びついているかのように、その行為がどちらの側面から見て無罪であるかを決定するものではない。むしろ、行為そのものが、自分自身に対して、そして
それに対して、外部の現実を対立させるという分裂である。そのような現実が存在することは、行為そのものに属し、行為によって生じる。したがって、無罪な
のは、石の存在のように、あるいは子供でさえもない、行為をしないことだけだ。-- |
| Dem Inhalte nach aber hat die
sittliche Handlung das Moment des Verbrechens an ihr, weil sie die
natürliche Verteilung der beiden Gesetze an die beiden Geschlechter
nicht aufhebt, sondern vielmehr als unentzweite Richtung auf das Gesetz
innerhalb der natürlichen Unmittelbarkeit bleibt, und als Tun diese
Einseitigkeit zur Schuld macht, nur die eine der Seiten des Wesens zu
ergreifen, und gegen die andre sich negativ zu verhalten, d.h. sie zu
verletzen. Wohin in dem allgemeinen sittlichen Leben Schuld und
Verbrechen, Tun und Handeln fällt, wird nachher bestimmter ausgedrückt
werden; es erhellt unmittelbar soviel, daß es nicht dieser Einzelne
ist, der handelt und schuldig ist; denn er als dieses Selbst ist nur
der unwirkliche Schatten, oder er ist nur als allgemeines Selbst, und
die Individualität rein das formale Moment des Tuns überhaupt, und der
Inhalt die Gesetze und Sitten, und bestimmt für den Einzelnen, die
seines Standes; er ist die Substanz als Gattung, die durch ihre
Bestimmtheit zwar zur Art wird, aber die Art bleibt zugleich das
Allgemeine der Gattung. Das Selbstbewußtsein steigt innerhalb des
Volkes vom Allgemeinen nur bis zur Besonderheit, nicht bis zur
einzelnen Individualität herab, welche ein ausschließendes Selbst, eine
sich negative Wirklichkeit in seinem Tun setzt; sondern seinem Handeln
liegt das sichre Vertrauen zum Ganzen zugrunde, worin sich nichts
Fremdes, keine Furcht noch Feindschaft einmischt. |
しかし、その内容から言えば、道徳的行為には犯罪の要素がある。なぜな
ら、それは、2つの法律を2つの性別に自然に分配することを止揚するのではなく、むしろ、自然の直接性の中で法律に対する分割不可能な方向性として残って
おり、行為として、この一方的な側面だけを取り上げ、もう一方の側面に対して否定的な態度、すなわちそれを侵害する行為を行うという罪悪感をもたらすから
だ。一般的な道徳的生活において、罪と犯罪、行為と行動がどこに該当するかは、後でより明確に表現される。このことは、行為を行い、罪を犯すのはこの個人
ではないことはすぐに明らかだ。なぜなら、この個人は、この自己として、ただ非現実的な影にすぎず、あるいは、一般的な自己としてのみ存在し、個体性は、
行為そのものの形式的な要素にすぎず、その内容は、法則や道徳であり、個人にとっては、その地位に固有のものであるからだ。彼は、その決定性によって種と
なる物質であるが、同時に種は種の一般性であり続ける。国民の中で、自己意識は、一般性から特殊性までしか下降せず、その行為において排他的な自己、否定
的な現実を設定する個々の個性まで下降することはない。その行為の根底には、何ものにも邪魔されない、恐怖や敵意が混ざらない、全体に対する確固たる信頼
がある。 |
| 2. 倫理的行動の反対の特徴 |
2. Opposite Characteristics of Ethical Action |
| Die entwickelte Natur des
wirklichen Handelns erfährt nun das sittliche Selbstbewußtsein an
seiner Tat, ebensowohl wenn es dem göttlichen, als wenn es dem
menschlichen Gesetze sich ergab. Das ihm offenbare Gesetz ist im Wesen
mit dem entgegengesetzten verknüpft; das Wesen ist die Einheit beider;
die Tat aber hat nur das eine gegen das andere ausgeführt. Aber im
Wesen mit diesem verknüpft, ruft die Erfüllung des einen das andere
hervor, und, wozu die Tat es machte, als ein verletztes, und nun
feindliches, Rache forderndes Wesen. Dem Handeln liegt nur die eine
Seite des Entschlusses überhaupt an dem Tage; er ist aber an sich das
Negative, das ein ihm Anderes, ein ihm, der das Wissen ist, Fremdes
gegenüberstellt. Die Wirklichkeit hält daher die andere dem Wissen
fremde Seite in sich verborgen, und zeigt sich dem Bewußtsein nicht,
wie sie an und für sich ist -- dem Sohne nicht den Vater in seinem
Beleidiger, den er erschlägt; nicht die Mutter in der Königin, die er
zum Weibe nimmt. Dem sittlichen Selbstbewußtsein stellt auf diese Weise
eine lichtscheue Macht nach, welche erst, wenn die Tat geschehen,
hervorbricht und es bei ihr ergreift; denn die vollbrachte Tat ist der
aufgehobne Gegensatz des wissenden Selbst und der ihm
gegenüberstehenden Wirklichkeit. Das Handelnde kann das Verbrechen und
seine Schuld nicht verleugnen; -- die Tat ist dieses, das Unbewegte zu
bewegen und das nur erst in der Möglichkeit Verschlossene
hervorzubringen, und hiemit das Unbewußte dem Bewußten, das
Nichtseiende dem Sein zu verknüpfen. In dieser Wahrheit tritt also die
Tat an die Sonne; -- als ein solches, worin ein Bewußtes einem
Unbewußten, das Eigne einem Fremden verbunden ist, als das entzweite
Wesen, dessen andere Seite das Bewußtsein, und auch als die seinige
erfährt, aber als die von ihm verletzte und feindlich erregte Macht. |
現実の行動の展開した性質は、それが神の法則に従った場合でも、人間の
法則に従った場合でも、その行為において道徳的自己意識を経験する。彼に明らかにされた法則は、その本質において反対の法則と結びついている。その本質は
両者の統一であるが、行為は一方を他方に対して実行したにすぎない。しかし、その本質と結びついているため、一方の実現は他方を呼び起こし、行為がそれに
したこと、すなわち、傷つけられた、そして今や敵対的で復讐を求める存在として。行為には、その日その日に下された決定の一面しか存在しない。しかし、行
為はそれ自体、否定的なものであり、それとは別の、知識であるそれとは異質なものを対峙させる。したがって、現実は、知識にとって異質なもう一方の側面を
その中に隠しており、それ自体が本来ある姿で意識に現れない。息子には、彼が殺した父親の侮辱者としての側面は現れない。また、彼が妻とする女王の母親と
しての側面も現れない。このように、道徳的な自己意識には、光を嫌う力が追いかけてきて、行為が行われたときに初めて現れて、それを捕らえる。なぜなら、
実行された行為は、知的な自己と、その対極にある現実との矛盾が解消されたものだからだ。行為者は、犯罪とその罪を否定することはできない。行為とは、動
かないものを動かし、可能性の中にのみ閉じ込められていたものを引き出すことであり、それによって、無意識を意識と結びつけ、存在しないものを存在と結び
つけることだ。この真実において、行為は太陽の下に現れる。それは、意識が、無意識、つまり自己と他者との結びつき、つまり分裂した存在であり、そのもう
一方の側面は意識であり、また、その側面も、自分によって傷つけられ、敵対的に刺激された力として認識する。 |
| Es kann sein, daß das Recht,
welches sich im Hinterhalte hielt, nicht in seiner eigentümlichen
Gestalt für das handelnde Bewußtsein, sondern nur an sich, in der
innern Schuld des Entschlusses und des Handelns vorhanden ist. Aber das
sittliche Bewußtsein ist vollständiger, seine Schuld reiner, wenn es
das Gesetz und die Macht vorher kennt, der es gegenübertritt, sie für
Gewalt und Unrecht, für eine sittliche Zufälligkeit nimmt, und
wissentlich, wie Antigone, das Verbrechen begeht. Die vollbrachte Tat
verkehrt seine Ansicht; die Vollbringung spricht es selbst aus, daß was
sittlich ist, wirklich sein müsse; denn die Wirklichkeit des Zwecks ist
der Zweck des Handelns. Das Handeln spricht gerade die Einheit der
Wirklichkeit und der Substanz aus, es spricht aus, daß die Wirklichkeit
dem Wesen nicht zufällig ist, sondern mit ihm im Bunde keinem gegeben
wird, das nicht wahres Recht ist. Das sittliche Bewußtsein muß sein
Entgegengesetztes um dieser Wirklichkeit willen, und um seines Tuns
willen, als die seinige, es muß seine Schuld anerkennen; |
隠れていた権利は、行動する意識にとってその固有の形態では存在せず、
ただそれ自体として、決定と行動の内的な罪悪感の中に存在しているだけかもしれない。しかし、道徳的意識は、それに対峙する法律と権力をあらかじめ知って
おり、それらを暴力と不正、道徳的な偶然性であると認識し、アンティゴネのように故意に犯罪を犯す場合、より完全であり、その罪はより純粋である。実行さ
れた行為は、その見解を覆す。実行自体が、道徳的なものは現実でなければならないことを表明している。なぜなら、目的の実在性が、行動の目的であるから
だ。行動はまさに現実と実体の統一を表明し、現実は本質に偶然に与えられたものではなく、本質と結びついて、真の権利ではないものには与えられないことを
表明する。道徳的意識は、この現実のために、そして自らの行為のために、その反対を自らのものとして認め、その罪を認めなければならない。 |
| weil wir leiden, anerkennen wir, daß wir gefehlt. | 私たちは苦しむということは、自分が間違っていたことを認めることなのでしょう(アンティゴネーの言葉) |
| Dies Anerkennen drückt den
aufgehobenen Zwiespalt des sittlichen Zweckes und der Wirklichkeit, es
drückt die Rückkehr zur sittlichen Gesinnung aus, die weiß, daß nichts
gilt als das Rechte. Damit aber gibt das Handelnde seinen Charakter und
die Wirklichkeit seines Selbsts auf, und ist zugrunde gegangen. Sein
Sein ist dieses, seinem sittlichen Gesetze als seiner Substanz
anzugehören; in dem Anerkennen des Entgegengesetzten hat dies aber
aufgehört, ihm Substanz zu sein; und statt seiner Wirklichkeit hat es
die Unwirklichkeit, die Gesinnung, erreicht. -- |
この認識は、道徳的目的と現実との矛盾の解消を表しており、正しいこと
だけが価値あるものであることを認識した道徳的態度への回帰を表している。しかし、それにより、行為者はその性格と自己の現実性を放棄し、滅びてしまう。
その存在は、道徳的法則をその本質として属することにある。しかし、その反対を認めることで、それはその本質ではなくなり、その現実性の代わりに、非現実
性、すなわち態度に達した。-- |
| Die Substanz erscheint zwar an
der Individualität als das Pathos derselben, und die Individualität als
das, was sie belebt, und daher über ihr steht; aber sie ist ein Pathos,
das zugleich sein Charakter ist; die sittliche Individualität ist
unmittelbar und an sich eins mit diesem seinem Allgemeinen, sie hat
ihre Existenz nur in ihm, und vermag den Untergang, den diese sittliche
Macht durch die entgegengesetzte leidet, nicht zu überleben. |
その物質は、個性のパトスとして、そして個性を活気づけるもの、した
がって個性よりも上位にあるものとして現れるが、それは同時にその特徴でもあるパトスである。道徳的個性は、この普遍的なものと直接かつ本質的に一体であ
り、その中にのみ存在し、この道徳的力が反対の力によって被る滅亡を生き残ることはできない。 |
| Sie hat aber dabei die
Gewißheit, daß diejenige Individualität, deren Pathos diese
entgegengesetzte Macht ist, nicht mehr Übel erleidet, als sie zugefügt.
Die Bewegung der sittlichen Mächte gegeneinander und der sie in Leben
und Handlung setzenden Individualitäten hat nur darin ihr wahres Ende
erreicht, daß beide Seiten denselben Untergang erfahren. Denn keine der
Mächte hat etwas vor der andern voraus, um wesentlicheres Moment der
Substanz zu sein. Die gleiche Wesentlichkeit und das gleichgültige
Bestehen beider nebeneinander ist ihr selbstloses Sein; in der Tat sind
sie als Selbstwesen, aber ein verschiedenes, was der Einheit des
Selbsts widerspricht, und ihre Rechtlosigkeit und notwendigen Untergang
ausmacht. Der Charakter gehört ebenso teils nach seinem Pathos oder
Substanz nur der einen an, teils ist nach der Seite des Wissens der
eine wie der andere in ein Bewußtes und Unbewußtes entzweit; und indem
jeder selbst diesen Gegensatz hervorruft, und durch die Tat auch das
Nichtwissen sein Werk ist, setzt er sich in die Schuld, die ihn
verzehrt. Der Sieg der einen Macht und ihres Charakters und das
Unterliegen der andern Seite wäre also nur der Teil und das
unvollendete Werk, das unaufhaltsam zum Gleichgewichte beider
fortschreitet. Erst in der gleichen Unterwerfung beider Seiten ist das
absolute Recht vollbracht, und die sittliche Substanz als die negative
Macht, welche beide Seiten verschlingt, oder das allmächtige und
gerechte Schicksal aufgetreten. |
しかし、その一方で、その反対の力である個性が、与えた悪以上の悪を受
けることはないと確信している。道徳的な力同士の対立と、それを生命と行動に具現化する個性の動きは、双方が同じ破滅を経験することによってのみ、その真
の意味での終焉を迎える。なぜなら、どちらの力も、本質的な要素として他よりも優れているところはないからだ。両者が並存する同じ本質と無差別な存在が、
その無私の存在だ。実際、それらは自己存在であるが、自己の統一性に反する異なる存在であり、その無権利性と必然的な滅亡を構成している。性格も、その感
情や本質によっては一方にのみ属し、知識の面では、一方も他方も意識と無意識に二分されている。そして、それぞれがこの対立を引き起こし、その行為によっ
て無知も自分の仕業となることで、自分を滅ぼす罪を犯している。一方の力とその性格の勝利、そしてもう一方の側の敗北は、したがって、両者の均衡に向かっ
て止まることなく進む、部分的で不完全な成果にすぎない。両者が等しく服従して初めて、絶対的な正義が達成され、両者を飲み込む否定的な力、すなわち全能
で公正な運命としての道徳的本質が現れる。 |
| Werden beide Mächte nach ihrem
bestimmten Inhalte und dessen Individualisation genommen, so bietet
sich das Bild ihres gestalteten Widerstreits, nach seiner formellen
Seite, als der Widerstreit der Sittlichkeit und des Selbstbewußtseins
mit der bewußtlosen Natur und einer durch sie vorhandenen Zufälligkeit
-- diese hat ein Recht gegen jenes, weil es nur der wahre Geist, nur in
unmittelbarer Einheit mit seiner Substanz ist -- und seinem Inhalte
nach als der Zwiespalt des göttlichen und menschlichen Gesetzes dar. --
Der Jüngling tritt aus dem bewußtlosen Wesen, aus dem Familiengeiste,
und wird die Individualität des Gemeinwesens; daß er aber der Natur,
der er sich entriß, noch angehöre, erweist sich so, daß er in der
Zufälligkeit zweier Brüder heraustritt, welche mit gleichem Rechte sich
desselben bemächtigen; die Ungleichheit der frühern und spätern Geburt
hat für sie, die in das sittliche Wesen eintreten, als Unterschied der
Natur, keine Bedeutung. Aber die Regierung, als die einfache Seele oder
das Selbst des Volksgeistes, verträgt nicht eine Zweiheit der
Individualität; und der sittlichen Notwendigkeit dieser Einheit tritt
die Natur als der Zufall der Mehrheit gegenüber auf. Diese beiden
werden darum uneins, und ihr gleiches Recht an die Staatsgewalt
zertrümmert beide, die gleiches Unrecht haben. Menschlicherweise
angesehen, hat derjenige das Verbrechen begangen, welcher, nicht im
Besitze, das Gemeinwesen, an dessen Spitze der andere stand, angreift;
derjenige dagegen hat das Recht auf seiner Seite, welcher den andern
nur als Einzelnen, abgelöst von dem Gemeinwesen, zu fassen wußte und in
dieser Machtlosigkeit vertrieb; er hat nur das Individuum als solches,
nicht jenes, nicht das Wesen des menschlichen Rechts, angetastet. Das
von der leeren Einzelnheit angegriffene und verteidigte Gemeinwesen
erhält sich, und die Brüder finden beide ihren wechselseitigen
Untergang durcheinander; denn die Individualität, welche an ihr
Für-sich-sein die Gefahr des Ganzen knüpft, hat sich selbst vom
Gemeinwesen ausgestoßen, und löst sich in sich auf. Den einen aber, der
auf seiner Seite sich fand, wird es ehren; den andern hingegen, der
schon auf den Mauern seine Verwüstung aussprach, wird die Regierung,
die wiederhergestellte Einfachheit des Selbsts des Gemeinwesens, um die
letzte Ehre bestrafen; wer an dem höchsten Geiste des Bewußtseins, der
Gemeine, sich zu vergreifen kam, muß der Ehre seines ganzen vollendeten
Wesens, der Ehre des abgeschiedenen Geistes, beraubt werden. |
両者の力が、その特定のコンテンツとその個別性に基づいて捉えられる
と、その形式的な側面から、道徳と自己意識が、無意識の自然と、それによって生じる偶然性との対立という構図が浮かび上がる。--
これは、真の精神は、その本質と直接的に一体である場合にのみ存在するため、それに対して権利を有している --
内容的には、神法と人間法の対立として現れる。--
青年は、無意識の存在、家族精神から抜け出し、共同体の個性となる。しかし、彼が、自ら脱した自然にもまだ属していることは、同じ権利をもってそれを奪い
合う2人の兄弟の偶然性から抜け出すことで明らかになる。道徳的な存在となった彼らにとって、生まれの早さの違いは、自然の違いとして何の意味も持たな
い。しかし、単純な魂、あるいは国民精神の自己である政府は、個性の二元性を容認できない。そして、この統一の道徳的必然性に対して、自然は多数決の偶然
性として対峙する。このため、この二者は対立し、国家権力に対する同等の権利によって、同等の不正を犯した両者が打ち砕かれる。人間的に見れば、所有権を
持たない者が、他者がトップに立つ共同体を攻撃したのは犯罪だ。一方、他者を共同体から切り離した個人としてのみ認識し、その無力な状態を利用して追放し
た者は、権利を自分の側に持っている。彼は、人間としての本質ではなく、個人としてのみその者を攻撃しただけだからだ。空虚な個別性によって攻撃され、防
衛された共同体は存続し、兄弟たちは互いに滅び合う。なぜなら、その存在そのものに全体としての危険を結びつける個別性は、共同体から自らを排除し、その
内部で崩壊するからだ。一方、自分の立場を見出した者は、名誉を授けられる。しかし、城壁の上で破壊を叫んだ者は、共同体の自己の単純さが回復した政府に
よって、最後の名誉を罰される。最高意識、すなわち共同体そのものを冒涜した者は、その完成された存在の栄誉、すなわち分離した精神の栄誉を奪われる。 |
| Aber wenn so das Allgemeine die
reine Spitze seiner Pyramide leicht abstößt, und über das sich
empörende Prinzip der Einzelnheit, die Familie, zwar den Sieg
davonträgt, so hat es sich dadurch mit dem göttlichen Gesetze, der
seiner selbstbewußte Geist sich mit dem Bewußtlosen nur in Kampf
eingelassen; denn dieser ist die andre wesentliche und darum von jener
unzerstörte und nur beleidigte Macht. Er hat aber gegen das
gewalthabende, am Tage liegende Gesetz seine Hülfe zur wirklichen
Ausführung nur an dem blutlosen Schatten. Als das Gesetz der Schwäche
und der Dunkelheit unterliegt er daher zunächst dem Gesetze des Tages
und der Kraft, denn jene Gewalt gilt unten, nicht auf Erden. Allein das
Wirkliche, das dem Innerlichen seine Ehre und Macht genommen, hat damit
sein Wesen aufgezehrt. Der offenbare Geist hat die Wurzel seiner Kraft
in der Unterwelt; die ihrer selbst sichere und sich versichernde
Gewißheit des Volkes hat die Wahrheit ihres Alle in Eins bindenden
Eides nur in der bewußtlosen und stummen Substanz Aller, in den Wässern
der Vergessenheit. Hiedurch verwandelt sich die Vollbringung des
offenbaren Geistes in das Gegenteil, und er erfährt, daß sein höchstes
Recht das höchste Unrecht, sein Sieg vielmehr sein eigener Untergang
ist. Der Tote, dessen Recht gekränkt ist, weiß darum für seine Rache
Werkzeuge zu finden, welche von gleicher Wirklichkeit und Gewalt sind
mit der Macht, die ihn verletzt. Diese Mächte sind andere Gemeinwesen,
deren Altäre die Hunde oder Vögel mit der Leiche besudelten, welche
nicht durch die ihr gebührende Zurückgabe an das elementarische
Individuum in die bewußtlose Allgemeinheit erhoben, sondern über der
Erde im Reiche der Wirklichkeit geblieben, und als die Kraft des
göttlichen Gesetzes, nun eine selbstbewußte wirkliche Allgemeinheit
erhält. Sie machen sich feindlich auf, und zerstören das Gemeinwesen,
das seine Kraft, die Pietät der Familie, entehrt und zerbrochen hat. |
しかし、そうして一般性がそのピラミッドの純粋な頂点をわずかに押し下
げ、個性の反逆的な原理、すなわち家族に対して勝利を収めたとしても、それによって、その自己意識のある精神は、無意識と闘争にのみ巻き込まれただけであ
り、それは神聖な法則に反するものではない。なぜなら、無意識は、そのもう一つの本質的な力であり、それゆえ、前者に破壊されることはなく、ただ侮辱され
るだけだからだ。しかし、暴力的な、昼間の法則に対して、その実際の執行のための助けは、血なき影にしか見出せない。弱さと闇の法則は、したがって、まず
昼間の法則と力、すなわち、その暴力は地下で、地上では効力を有しない。しかし、内面にその名誉と力を奪った現実だけが、その本質を消耗してしまう。顕在
的な精神は、その力の根源を冥界に持ってる。民衆の、それ自体で確固とした、そして確信に満ちた確信は、すべてを一つに結ぶ誓いの真実を、意識のない、無
言のすべての物質、忘却の海の中にのみ持ってる。これにより、顕在的な精神の達成は正反対のものへと変化し、その精神は、自らの最高の権利が最高の不正で
あり、その勝利はむしろ自らの滅亡であることを知る。その権利を侵害された死者は、その復讐のために、自分を傷つけた力と同じ現実と暴力を持つ道具を見つ
けることを知っている。これらの力は、他の共同体であり、その祭壇は、死体を汚した犬や鳥たちによって汚されている。死体は、本来あるべき姿である、元素
の個体へと返されることなく、無意識の普遍性へと昇華されることなく、現実の領域である地上に残り、神の法の力として、今や、自己意識のある現実の普遍性
として存在している。それらは敵対し、その力を、家族の敬虔さを汚し、破壊した共同体を破壊する。 |
| In dieser Vorstellung hat die
Bewegung des menschlichen und göttlichen Gesetzes den Ausdruck ihrer
Notwendigkeit an Individuen, an denen das Allgemeine als ein Pathos und
die Tätigkeit der Bewegung als individuelles Tun erscheint, welches der
Notwendigkeit derselben den Schein der Zufälligkeit gibt. Aber die
Individualität und das Tun macht das Prinzip der Einzelnheit überhaupt
aus, das in seiner reinen Allgemeinheit das innere göttliche Gesetz
genannt wurde. Als Moment des offenbaren Gemeinwesens hat es nicht nur
jene unterirdische oder in seinem Dasein äußerliche Wirksamkeit,
sondern ein ebenso offenbares an dem wirklichen Volke wirkliches Dasein
und Bewegung. In dieser Form genommen, erhält das, was als einfache
Bewegung des individualisierten Pathos vorgestellt wurde, ein anderes
Aussehen, und das Verbrechen und die dadurch begründete Zerstörung des
Gemeinwesens die eigentliche Form ihres Daseins. -- |
この観念において、人間的および神聖な法則の動きは、その必然性を、一
般性がパトスとして、動きの活動が個々の行為として現れる個人に表現している。この個々の行為は、その必然性に偶然性の外観を与える。しかし、個性と行為
は、その純粋な一般性において、内なる神の法則と呼ばれた、個性の原理そのものを構成している。明白な共同体としての瞬間として、それは、その現存在の外
にある地下的な効力だけでなく、現実の民衆における現実の現存在と運動という、同様に明白な効力も持っている。この形で捉えると、個別化された情念の単純
な運動として考えられていたものは、別の姿となり、犯罪とそれによって生じた共同体の破壊は、その現存在の真の姿となる。-- |
| Das menschliche Gesetz also in
seinem allgemeinen Dasein, das Gemeinwesen, in seiner Betätigung
überhaupt die Männlichkeit, in seiner wirklichen Betätigung die
Regierung, ist, bewegt und erhält sich dadurch, daß es die Absonderung
der Penaten oder die selbstständige Vereinzelung in Familien, welchen
die Weiblichkeit vorsteht, in sich aufzehrt, und sie in der Kontinuität
seiner Flüssigkeit aufgelöst erhält. Die Familie ist aber zugleich
überhaupt sein Element, das einzelne Bewußtsein allgemeiner
betätigender Grund. Indem das Gemeinwesen sich nur durch die Störung
der Familienglückseligkeit und die Auflösung des Selbstbewußtseins in
das allgemeine sein Bestehen gibt, erzeugt es sich an dem, was es
unterdrückt und was ihm zugleich wesentlich ist, an der Weiblichkeit
überhaupt seinen innern Feind. Diese -- die ewige Ironie des
Gemeinwesens -- verändert durch die Intrige den allgemeinen Zweck der
Regierung in einen Privatzweck, verwandelt ihre allgemeine Tätigkeit in
ein Werk dieses bestimmten Individuums, und verkehrt das allgemeine
Eigentum des Staats zu einem Besitz und Putz der Familie. Sie macht
hiedurch die ernsthafte Weisheit des reifen Alters, das, der
Einzelnheit -- der Lust und dem Genusse, sowie der wirklichen Tätigkeit
-- abgestorben, nur das Allgemeine denkt und besorgt, zum Spotte für
den Mutwillen der unreifen Jugend, und zur Verachtung für ihren
Enthusiasmus; erhebt überhaupt die Kraft der Jugend zum Geltenden --
des Sohnes, an dem die Mutter ihren Herrn geboren, des Bruders, an dem
die Schwester den Mann als ihresgleichen hat, des Jünglings, durch den
die Tochter ihrer Unselbstständigkeit entnommen, den Genuß und die
Würde der Frauenschaft erlangt. -- |
つまり、人間の法律は、その一般的な現存在として、共同体として、その
活動として、男性性として、その実際の活動として、政府として、ペナテスの分離、すなわち、女性が主導する家族への自立的な分離を、その流動性の連続性の
中で解消し、維持することによって、動き、維持されている。しかし、家族は同時に、その要素であり、個々の意識が一般的に活動する根拠でもある。共同体
は、家族の幸福の混乱と、自己意識の一般的な存在への解消によってのみその存在を確立するため、抑圧し、同時にその本質である女性性、すなわちその内なる
敵を生み出している。この、共同体の永遠の皮肉は、陰謀によって、政府の一般的な目的を私的な目的へと変え、その一般的な活動を、この特定の個人の仕事へ
と変え、国家の一般的な所有物を、家族の所有物および装飾品へと変える。これにより、成熟した年齢の真剣な知恵、つまり、個々の人間性、つまり快楽と享
楽、そして現実の活動から死滅し、普遍的なものだけを考え、それを追求する知恵は、未熟な若者の気まぐれに対する嘲笑の対象となり、彼らの熱狂に対する軽
蔑の対象となる。そして、若者の力、すなわち、母親が主として産んだ息子、姉妹が同等の夫として迎える兄弟、娘が自立から解放され、女性の喜びと尊厳を得
る青年、を一般に有効なものとして高めている。 |
| 3. 倫理的存在の解消 |
3. Dissolution of the Ethical Being |
| Das Gemeinwesen kann sich aber
nur durch Unterdrückung dieses Geistes der Einzelnheit erhalten, und,
weil er wesentliches Moment ist, erzeugt es ihn zwar ebenso, und zwar
durch die unterdrückende Haltung gegen denselben als ein feindseliges
Prinzip. Dieses würde jedoch, da es vom allgemeinen Zwecke sich
trennend, nur böse und in sich nichtig ist, nichts vermögen, wenn nicht
das Gemeinwesen selbst die Kraft der Jugend, die Männlichkeit, welche
nicht reif noch innerhalb der Einzelnheit steht, als die Kraft des
Ganzen anerkannte. Denn es ist ein Volk, es ist selbst Individualität
und wesentlich nur so für sich, daß andere Individualitäten für es
sind, daß es sie von sich ausschließt und sich unabhängig von ihnen
weiß. Die negative Seite des Gemeinwesens, nach innen die Vereinzelung
der Individuen unterdrückend, nach außen aber selbsttätig, hat an der
Individualität seine Waffen. Der Krieg ist der Geist und die Form,
worin das wesentliche Moment der sittlichen Substanz, die absolute
Freiheit des sittlichen Selbstwesens von allem Dasein, in ihrer
Wirklichkeit und Bewährung vorhanden ist. Indem er einerseits den
einzelnen Systemen des Eigentums und der persönlichen Selbstständigkeit
wie auch der einzelnen Persönlichkeit selbst die Kraft des Negativen zu
fühlen gibt, erhebt andererseits in ihm eben dies negative Wesen sich
als das Erhaltende des Ganzen; der tapfre Jüngling, an welchem die
Weiblichkeit ihre Lust hat, das unterdrückte Prinzip des Verderbens
tritt an den Tag und ist das Geltende. Nun ist es die natürliche Kraft
und das, was als Zufall des Glücks erscheint, welche über das Dasein
des sittlichen Wesens und die geistige Notwendigkeit entscheiden; weil
auf Stärke und Glück das Dasein des sittlichen Wesens beruht, so ist
schon entschieden, daß es zugrunde gegangen. -- Wie vorhin nur Penaten
im Volksgeiste, so gehen die lebendigen Volksgeister durch ihre
Individualität itzt in einem allgemeinen Gemeinwesen zugrunde, dessen
einfache Allgemeinheit geistlos und tot, und dessen Lebendigkeit das
einzelne Individuum, als einzelnes ist. Die sittliche Gestalt des
Geistes ist verschwunden, und es tritt eine andere an ihre Stelle. |
しかし、共同体は、この個人主義の精神を抑圧することによってのみ存続
することができる。そして、この精神は本質的な要素であるため、共同体は、それを敵対的な原理として抑圧する姿勢を通じて、この精神を同様に生み出してい
る。しかし、これは、一般的な目的から分離しているため、悪であり、それ自体では無意味であり、共同体自体が、まだ成熟しておらず、個人の中に留まってい
る若さの力、男らしさを、全体としての力として認めなければ、何の効果も持たない。なぜなら、共同体とは、それ自体が個性であり、他の個性がそのために存
在し、それらを排除し、それらから独立していると認識している、そのようにしてのみ本質的に存在するものだからだ。共同体の否定的な側面は、内部では個人
の孤立を抑圧し、外部に対しては自発的に作用し、その武器は個性にある。戦争は、道徳的実体の本質的な要素、すなわち、あらゆる現存在から解放された道徳
的自己の存在の絶対的自由が、その現実性と実証において存在する精神と形態である。一方では、個々の財産制度や個人の自立、そして個々の人格そのものに否
定的な力を感じさせる一方で、他方では、まさにこの否定的な本質が、全体を維持する力として立ち上がる。女性たちが欲望の対象とする勇敢な青年は、抑圧さ
れた腐敗の原理を露わにし、支配的な存在となる。さて、道徳的存在の現存在と精神的な必然性を決定するのは、自然の力と、偶然の幸運のように見えるものな
のだ。道徳的存在の現存在は力と幸運に依存しているため、その滅亡はすでに決定している。--
以前、民衆の精神の中にペナテスだけが存在していたように、今や、民衆の生き生きとした精神は、その個性によって、単純で無精神で死んだ一般的な共同体の
中で滅びていく。その共同体の活気は、個々の個人、つまり個々にあるものにある。精神の道徳的な形は消滅し、別の形がそれに取って代わる。 |
| Dieser Untergang der sittlichen
Substanz und ihr Übergang in eine andere Gestalt ist also dadurch
bestimmt, daß das sittliche Bewußtsein auf das Gesetz wesentlich
unmittelbar gerichtet ist; in dieser Bestimmung der Unmittelbarkeit
liegt, daß in die Handlung der Sittlichkeit die Natur überhaupt
hereinkommt. Ihre Wirklichkeit offenbart nur den Widerspruch und den
Keim des Verderbens, den die schöne Einmütigkeit und das ruhige
Gleichgewicht des sittlichen Geistes eben an dieser Ruhe und Schönheit
selbst hat; denn die Unmittelbarkeit hat die widersprechende Bedeutung,
die bewußtlose Ruhe der Natur, und die selbstbewußte unruhige Ruhe des
Geistes zu sein. -- Um dieser Natürlichkeit willen ist überhaupt dieses
sittliche Volk eine durch die Natur bestimmte und daher beschränkte
Individualität, und findet also ihre Aufhebung an einer andern. Indem
aber diese Bestimmtheit, die im Dasein gesetzt, Beschränkung, aber
ebenso das Negative überhaupt und das Selbst der Individualität ist,
verschwindet, ist das Leben des Geistes und diese in Allen ihrer
selbstbewußte Substanz verloren. Sie tritt als eine formelle
Allgemeinheit an ihnen heraus, ist ihnen nicht mehr als lebendiger
Geist inwohnend, sondern die einfache Gediegenheit ihrer Individualität
ist in viele Punkte zersprungen. |
道徳的実体の崩壊と、それが別の形へと移行することは、道徳的意識が本
質的に法律に直接向けられていることによって決定される。この直接性の決定には、道徳的行為に自然がまったく介入するという事実がある。その現実性は、道
徳的精神の美しい一致と穏やかな均衡が、まさにその静けさと美しさそのものに持つ矛盾と腐敗の芽を明らかにするだけだ。なぜなら、直接性は、自然の無意識
の静けさと、精神の自己意識的な不安定な静けさという、相反する意味を持っているからだ。この自然性のために、この道徳的な民族は、自然によって決定さ
れ、したがって制限された個別性であり、したがって、他の個別性においてその止揚を見出す。しかし、現存在に置かれたこの決定性は、制限であると同時に、
否定そのものであり、個別性の自己でもあるため、それが消滅すると、精神の生命と、その自己意識的な実体はすべて失われる。それは、彼らの中に形式的な普
遍性として現れ、もはや彼らの中に生きた精神として内在するものではなく、彼らの個性の単純な純粋さは多くの点に分裂してしまう。 |
| https://www.waste.org/~roadrunner/Hegel/PhenSpirit/464_BIL.html |
ヘーゲルによるアンティゴネーの議論は、『精神現象 学』の他に、『美学』詩、『法哲学』家族、においてみられるという。ヘーゲルの時代に、その盟友ヘルダーリンは、『アンティゴネ』の新訳を完成させる。
●クレオンの呪詛
「私が彼女(アンティゴネ)を生かしておけば、私は もはや男ではなく、彼女のほうが男だ」
クレオンの本音は、女性的なものが、侵食していき、
社会が危険なものになる。
●アンティゴネーに対するさまざまな解釈
・女(アンティゴネ)が、クレオンの原理(=私情を 交えず法に厳密にしたがうべし)に従わねば、女は死や暴力にさらされる。
・クレオンのアンティゴネに対する立場が、微妙にぶ れるので、人間の自然な情念を「否定」して、社会秩序は構築されることを示唆している。
・国法の原理は、私情のあり方を理解できないが、同 時に、自然や自然法に対して「つねに負債を担う」ことをこのシステムは示唆している。
・法の執行による正義の実現と、私情や慣習による服
喪がもつ倫理的情感とは、まったく別の原理である。
●まとめ
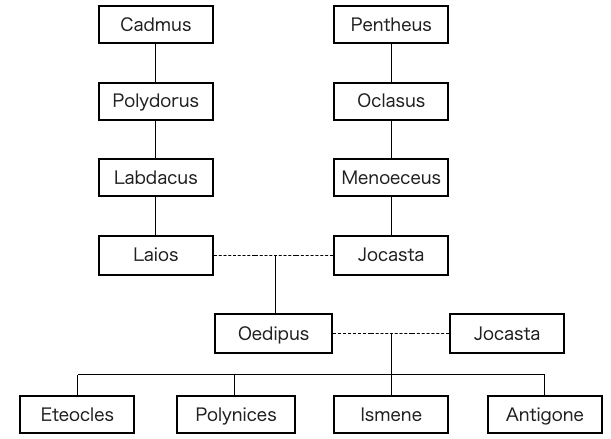
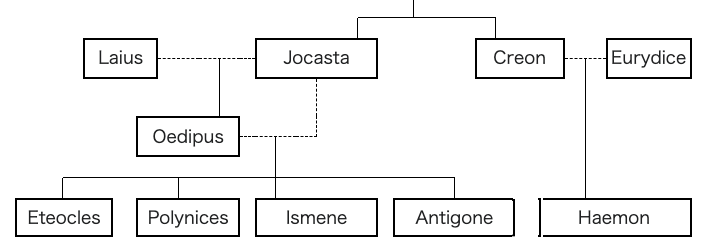
・エテオクレス、ポリュネイケス、アンティゴネは、 イオカステを母に、オイディプスを父にもつ兄弟たちである。
・イオカステの兄弟、すなわちアンティゴネたちの叔 父で、現在のテバイの王であるクレオンは、刺し違えた兄弟の兄のエテオクレスの死を賞賛するが、(叛逆の科を認定された)ポリュネイケスの埋葬は禁止し た。クレオンは「人間による命令」で埋葬を禁止する。
・アンティゴネは人間の「決められた正義」=慣行 の・普遍的で神的な理由(=ノモス)を尊重すべきだと主張した。
・クレオンは怒り、アンティゴネを岩窟に閉じ込めて 生き埋めにせよと命令がくだった時に、クレオンは自分で縊死する。
・スタシスとは、ポリスを内側から崩壊させる反乱の 原理である。ポレモスはポリスの栄光を高める外部戦争である。彼女の縊死は、ポリスからスタシスの毒を吸い出したとも言われる。
★アンティゴネー入門——演劇の構造
| Antigone
(/ænˈtɪɡəni/ ann-TIG-ə-nee; Ancient Greek: Ἀντιγόνη) is an Athenian
tragedy written by Sophocles in (or before) 441 BC and first performed
at the Festival of Dionysus of the same year. It is thought to be the
second oldest surviving play of Sophocles, preceded by Ajax, which was
written around the same period. The play is one of a triad of tragedies
known as the three Theban plays, following Oedipus Rex and Oedipus at
Colonus. Even though the events in Antigone occur last in the order of
events depicted in the plays, Sophocles wrote Antigone first.[1] The
story expands on the Theban legend that predates it, and it picks up
where Aeschylus' Seven Against Thebes ends. The play is named after the
main protagonist Antigone. |
アンティゴネー』(/ænˈtəni/
ann-TIGA-ə-nee; Ancient Greek:
Ἀντιγόνη)は、紀元前441年(またはそれ以前)にソフォクレスによって書かれたアテナイの悲劇で、同年のディオニュソス祭で初演された。現存す
るソフォクレスの戯曲としては、同時期に書かれた『エイジャックス』に次いで2番目に古いものと考えられている。オイディプス王』と『コロノスのオイディ
プス』に続く、テーバン三部作と呼ばれる悲劇のひとつである。アンティゴネー』で描かれる出来事は、戯曲の中で描かれる出来事の順序としては最後に起こる
にもかかわらず、ソフォクレスは『アンティゴネー』を最初に書いた[1]。この物語は、それ以前のテーバンの伝説を発展させたもので、アイスキュロスの
『テーベに対する七人』が終わったところから始まる。戯曲名は主人公アンティゴネーにちなむ。 |
| After Oedipus' self-exile, his
sons Eteocles and Polynices engaged in a civil war for the Theban
throne, which resulted in both brothers dying fighting each other.
Oedipus' brother-in-law and new Theban ruler Creon ordered the public
honoring of Eteocles and the public shaming of Thebes' traitor
Polynices. The story follows the attempts of Antigone, the sister of
Eteocles and Polynices, to bury Polynices, going against the decision
of her uncle Creon and placing her relationship with her brother above
human laws. |
オイディプスが自害した後、息子のエテオクレスとポリュニケスはテーベ
王位をめぐって内戦を繰り広げ、その結果、兄弟は互いに争って死んでしまう。オイ
ディプスの義兄でテーベンの新支配者クレオンは、エテオクレスを讃え、テーベの裏切り者ポリニスを辱めるよう命じた。物語は、エテオクレスとポリュニクス
の妹であるアンティゴネが、叔父クレオンの決定に反し、兄との関係を人間の掟よりも優先してポリュニクスを葬ろうとする姿を描く。 |
| Prior to the beginning of the
play, the brothers Eteocles and Polynices, leading opposite sides in
Thebes' civil war, died fighting each other for the throne. Creon, the
new ruler of Thebes and brother of the former Queen Jocasta, has
decided that Eteocles will be honored and Polynices will be in public
shame. The rebel brother's body will not be sanctified by holy rites
and will lie unburied on the battlefield, prey for carrion animals,[a]
the harshest punishment at the time. Antigone and Ismene are the
sisters of the dead Polynices and Eteocles. |
戯曲が始まる前、テーベの内戦で敵味方を率いたエテオクレスとポリニス
の兄弟は、王位をめぐって互いに争って死んだ。テーベの新しい統治者であり、前王妃ジョカスタの弟であるクレオンは、エテオクレスは讃えられ、ポリュニケ
スは公の恥となることを決定した。反乱を起こした弟の遺体は聖なる儀式によって聖別されることなく、戦場に埋葬されないまま横たわり、当時最も過酷な罰で
あった[a]腐肉動物の餌食となる。アンティゴネとイスメネは死んだポリニスとエテオクレスの姉妹である。 |
| In the opening of the play,
Antigone brings Ismene outside the palace gates late at night for a
secret meeting: Antigone wants to bury Polynices' body, in defiance of
Creon's edict. Ismene refuses to help her, not believing that it will
actually be possible to bury their brother, who is under guard, but she
is unable to stop Antigone from going to bury her brother herself. |
戯曲の冒頭で、アンティゴネはイスメネを夜遅くに宮殿の門の外に連れ出
し、密会をする:
アンティゴネは、クレオンの勅令に背いてポリニスの遺体を埋葬しようとしていた。クレオンの勅令を無視してポリニスの遺体を埋葬しようとするアンティゴネ
を止めることはできなかった。 |
| The Chorus, consisting of Theban
elders, enter and cast the background story of the Seven against Thebes
into a mythic and heroic context. Creon enters, and seeks the support of the Chorus in the days to come and in particular, wants them to back his edict regarding the disposal of Polynices' body. The leader of the Chorus pledges his support out of deference to Creon. A sentry enters, fearfully reporting that the body has been given funeral rites and a symbolic burial with a thin covering of earth, though no one saw who actually committed the crime. Creon, furious, orders the sentry to find the culprit or face death himself. The sentry leaves. |
テーベの長老たちで構成される合唱団が登場し、テーベに対抗する七人という背景の物語を神話的で英雄的な文脈に落とし込む。 クレオンは合唱団の支持を求め、特にポリュニセスの遺体処理に関する勅令を支持するよう求める。合唱団のリーダーはクレオンに敬意を表し、支持を約束す る。歩哨が入ってきて、遺体は葬儀の儀式を受け、薄い土で覆われた象徴的な埋葬をされたが、実際に誰が罪を犯したのかは誰も見ていないと恐る恐る報告す る。クレオンは激怒し、衛兵に犯人を見つけなければ自分が死ぬと命じる。歩哨は立ち去る。 |
| The Chorus sing of the ingenuity of human beings; but add that they do not wish to live in the same city as law-breakers. The sentry returns, bringing Antigone with him. The sentry explains that the watchmen uncovered Polynices' body and then caught Antigone as she did the funeral rituals. Creon questions her after sending the sentry away, and she does not deny what she has done. She argues unflinchingly with Creon about the immorality of the edict and the morality of her actions. Creon becomes furious, and seeing Ismene upset, thinks she must have known of Antigone's plan. He summons her. Ismene tries to confess falsely to the crime, wishing to die alongside her sister, but Antigone will not have it. Creon orders that the two women be imprisoned. |
合唱団は人間の巧妙さを歌うが、法を犯す者と同じ街には住みたくないと付け加える。 見張りがアンティゴネを連れて戻ってくる。見張りがポリニスの遺体を発見し、葬儀を執り行うアンティゴネを捕らえたと説明する。クレオンは見張りを追い 払った後、アンティゴネを問い詰めるが、アンティゴネは自分のしたことを否定しない。彼女はクレオンに、勅令の不道徳さと自分の行為の道徳性について堂々 と反論する。クレオンは激怒し、動揺するイスメネを見て、彼女がアンティゴネの計画を知っていたに違いないと考える。彼女を呼び出す。イスメネは姉と一緒 に死にたいと罪を偽り告白しようとするが、アンティゴネはそれを許さなかった。クレオンは二人を投獄するよう命じる。 |
| The Chorus sing of the troubles of the house of Oedipus. Haemon, Creon's son, enters to pledge allegiance to his father, even though he is engaged to Antigone. He initially seems willing to forsake Antigone, but when he gently tries to persuade his father to spare Antigone, claiming that "under cover of darkness the city mourns for the girl", the discussion deteriorates, and the two men are soon bitterly insulting each other. When Creon threatens to execute Antigone in front of his son, Haemon leaves, vowing never to see Creon again. |
合唱団はオイディプス家の災難を歌う。 クレオンの息子ヘーモンが、アンティゴネと婚約しているにもかかわらず、父に忠誠を誓うために入ってくる。当初はアンティゴネを見捨てる気でいるようだっ たが、「闇に紛れて都は少女を悼む」と主張してアンティゴネを助けるよう父を優しく説得しようとすると、話し合いは悪化し、二人はすぐに激しく侮辱し合 う。クレオンが息子の前でアンティゴネを処刑すると脅すと、ヘーモンはクレオンに二度と会わないと誓って立ち去る。 |
| The Chorus sing of the power of love. Antigone is brought in under guard on her way to execution. She sings a lament. The Chorus compares her to the goddess Niobe, who was turned into a rock, and say it is a wonderful thing to be compared to a goddess. Antigone accuses them of mocking her. |
コーラスが愛の力を歌う。 アンティゴネーは処刑される途中、警護のもとに連行される。彼女は嘆きを歌う。合唱団は彼女を岩に変えられた女神ニオベにたとえ、女神にたとえられるのは素晴らしいことだと言う。アンティゴネーは自分を馬鹿にしていると非難する。 |
| Creon decides to spare Ismene
and to bury Antigone alive in a cave. By not killing her directly, he
hopes to pay minimal respects to the gods. She is brought out of the
house, and this time, she is sorrowful instead of defiant. She
expresses her regrets at not having married and dying for following the
laws of the gods. She is taken away to her living tomb. |
クレオンはイスメネを惜しみ、アンティゴネーを洞窟に生き埋めにするこ
とを決める。彼女を直接殺さないことで、神々に最低限の敬意を払おうと考えたのだ。家から連れ出されたアンティゴネは、今度は反抗的ではなく悲しげな表情
を浮かべる。彼女は、神々の掟に従ったために結婚せず死んでしまったことへの後悔を口にする。彼女は生きている墓に連れて行かれる。 |
| The Chorus encourage Antigone by singing of the great women of myth who suffered. Tiresias, the blind prophet, enters. Tiresias warns Creon that Polynices should now be urgently buried because the gods are displeased, refusing to accept any sacrifices or prayers from Thebes. However, Creon accuses Tiresias of being corrupt. Tiresias responds that Creon will lose "a son of [his] own loins"[3] for the crimes of leaving Polynices unburied and putting Antigone into the earth (he does not say that Antigone should not be condemned to death, only that it is improper to keep a living body underneath the earth). Tiresias also prophesies that all of Greece will despise Creon and that the sacrificial offerings of Thebes will not be accepted by the gods. The leader of the Chorus, terrified, asks Creon to take Tiresias' advice to free Antigone and bury Polynices. Creon assents, leaving with a retinue of men. |
合唱団は苦悩した神話の偉大な女性たちを歌い、アンティゴネーを励ます。 盲目の預言者ティレシアスが入ってくる。ティレシアスはクレオンに、ポリュネイケスを早急に葬るべきだと警告する。神々は不興を買い、テーベからの生贄や 祈りを拒んだからだ。しかしクレオンは、ティレシアスが堕落していると非難する。ティレシアスは、ポリュネイケスを埋葬せずに放置し、アンティゴネーを土 に埋めた罪で、クレオンは「自分の子」[3]を失うだろうと答える(彼はアンティゴネーを死刑にするべきではないと言っているのではなく、生きている遺体 を土の下に埋めておくのは不適切だと言っているだけである)。ティレジアスはまた、ギリシア全土がクレオンを軽蔑し、テーベの生贄は神々に受け入れられな いだろうと予言する。恐怖におののいた合唱団の団長は、アンティゴネーを解放しポリュケネイスを葬るよう、ティレシアスの忠告を聞くようクレオンに頼む。 クレオンはそれを承諾し、従者を連れてその場を去る。 |
| The Chorus deliver an oral ode to the god Dionysus. A messenger enters to tell the leader of the Chorus that Haemon has killed himself. Eurydice, Creon's wife and Haemon's mother, enters and asks the messenger to tell her everything. The messenger reports that Creon saw to the burial of Polynices. When Creon arrived at Antigone's cave, he found Haemon lamenting over Antigone, who had hanged herself. Haemon unsuccessfully attempted to stab Creon, then stabbed himself. Having listened to the messenger's account, Eurydice silently disappears into the palace. |
合唱団がディオニュソス神への頌歌を口上する。 合唱団の団長に、ヘーモンが自殺したことを伝える使者が入ってくる。クレオンの妻でハエモンの母であるエウリュディケが入ってきて、使者にすべてを話すよ うに頼む。使者は、クレオンがポリュネイケスの埋葬を見届けたことを報告する。クレオンがアンティゴネーの洞窟に着くと、首を吊ったアンティゴネーを嘆く ハエモンがいた。ヘーモンはクレオンを刺そうとしたが失敗し、自らも刺した。使者の話を聞いたエウリュディケは、静かに宮殿へと消えていく。 |
| Creon enters, carrying Haemon's
body. He understands that his own actions have caused these events and
blames himself. A second messenger arrives to tell Creon and the Chorus
that Eurydice has also killed herself. With her last breath, she cursed
her husband for the deaths of her sons, Haemon and Megareus. Creon
blames himself for everything that has happened, and, a broken man, he
asks his servants to help him inside. The order he valued so much has
been protected, and he is still the king, but he has acted against the
gods and lost his children and his wife as a result. After Creon
condemns himself, the leader of the Chorus closes by saying that
although the gods punish the proud, punishment brings wisdom. |
クレオンがヘーモンの遺体を抱えて入ってくる。彼は自分の行いがこのよ
うな事態を引き起こしたことを理解し、自分を責める。二人目の使者がクレオンと合唱団に、エウリディーチェも自殺したことを告げにやってくる。彼女は息を
引き取る際、息子であるハエモンとメガレウスの死について夫を呪った。クレオンは、起こったことのすべてを自分のせいだと責め、打ちひしがれた彼は、使用
人たちに自分の家の手伝いを頼む。彼が大切にしていた秩序は守られ、王であることに変わりはないが、神々に背く行為をした結果、子供たちと妻を失ったの
だ。クレオンが自責の念に駆られた後、合唱団のリーダーは、神々は高慢な者を罰するが、罰は知恵をもたらす、と締めくくる。 |
| Characters Antigone, compared with her beautiful and docile sister, is portrayed as a heroine who recognizes her familial duty. Her dialogues with Ismene reveal her to be as stubborn as her uncle.[4] In her, the ideal of the female character is boldly outlined.[5] She defies Creon's decree despite the consequences she may face, in order to honor her deceased brother. Ismene serves as a foil for Antigone, presenting the contrast in their respective responses to the royal decree.[4] Considered the beautiful one, she is more lawful and obedient to authority. She hesitates to bury Polynices because she fears Creon. Creon is the current King of Thebes, who views law as the guarantor of personal happiness. He can also be seen as a tragic hero, losing everything for upholding what he believes is right. Even when he is forced to amend his decree to please the gods, he first tends to the dead Polynices before releasing Antigone.[4] Eurydice of Thebes is the Queen of Thebes and Creon's wife. She appears towards the end and only to hear confirmation of her son Haemon's death. In her grief, she dies by suicide, cursing Creon, whom she blames for her son's death. Haemon is the son of Creon and Eurydice, betrothed to Antigone. Proved to be more reasonable than Creon, he attempts to reason with his father for the sake of Antigone. However, when Creon refuses to listen to him, Haemon leaves angrily and shouts he will never see him again. He dies by suicide after finding Antigone dead. Koryphaios is the assistant to the King (Creon) and the leader of the Chorus. He is often interpreted as a close advisor to the King, and therefore a close family friend. This role is highlighted in the end when Creon chooses to listen to Koryphaios' advice. Tiresias is the blind prophet whose prediction brings about the eventual proper burial of Polynices. Portrayed as wise and full of reason, Tiresias attempts to warn Creon of his foolishness and tells him the gods are angry. He manages to convince Creon, but is too late to save the impetuous Antigone. The Chorus, a group of elderly Theban men, is at first deferential to the king.[5] Their purpose is to comment on the action in the play and add to the suspense and emotions, as well as connecting the story to myths. As the play progresses they counsel Creon to be more moderate. Their pleading persuades Creon to spare Ismene. They also advise Creon to take Tiresias's advice. |
登場人物 アンティゴネーは、美しく従順な姉に比べ、家族の義務を自覚するヒロインとして描かれている。イスメネとの対話は、彼女が叔父のように頑固であることを明 らかにしている[4]。彼女の中には、女性の理想像が大胆に描かれている[5]。彼女は、亡くなった兄を敬うために、自分が直面するかもしれない結果にも かかわらず、クレオンの命令に逆らう。 イスメネはアンティゴネーの箔の役割を果たし、勅令に対するそれぞれの反応の対照を示す[4]。彼女がポリュネイケスを葬るのをためらうのは、クレオンを恐れているからである。 クレオンはテーベの現王であり、法を人格の幸福を保証するものと考えている。彼はまた、自分が正しいと信じることを守るためにすべてを失う、悲劇のヒー ローともいえる。神々を喜ばせるために命令を修正せざるを得なくなったときでさえ、彼はアンティゴネーを解放する前に、まず死んだポリュネイケスの看病を する[4]。 テーベのエウリュディケはテーベの女王であり、クレオンの妻である。テーベの王妃でクレオンの妻である。悲しみのあまり、息子の死を責めたクレオンを呪いながら自殺する。 ヘーモンはクレオンとエウリュディケの息子で、アンティゴネーと婚約していた。クレオンよりも理性的であることが証明され、アンティゴネーのために父親を 説得しようとする。しかしクレオンに拒絶されると、ヘーモンは怒って立ち去り、二度と会わないと叫ぶ。彼はアンティゴネーの死体を見つけて自殺する。 コリファイオスは王(クレオン)の補佐役であり、コーラスのリーダーでもある。彼はしばしば王の側近であり、従って家族の親友であると解釈される。この役割は、クレオンがコリファイオスの助言に耳を傾けることを選択するラストで強調される。 ティレシアスは盲目の予言者で、その予言によって最終的にポリュネイケスがきちんと埋葬されることになる。賢くて理性に満ちた人物として描かれるティレシ アスは、クレオンに自分の愚かさを警告し、神々が怒っていることを告げる。彼はなんとかクレオンを説得するが、気の早いアンティゴネーを救うには遅すぎ た。 テーバンの老人たちからなる合唱団は、最初は王に従順である[5]。彼らの目的は、劇中の行動にコメントし、サスペンスと感情を盛り上げ、物語を神話に結 びつけることである。劇が進むにつれて、彼らはクレオンにもっと節度を持つよう助言する。彼らの懇願により、クレオンはイスメネを助けるよう説得される。 彼らはまた、ティレシアスの忠告を聞くようクレオンに助言する。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Antigone_(Sophocles_play) |
★アンティゴネーの解析、これまでの識者の講釈、原作の翻訳や翻案など
| Historical context Antigone was written at a time of national fervor. In 441 BCE, shortly after the play was performed, Sophocles was appointed as one of the ten generals to lead a military expedition against Samos. It is striking that a prominent play in a time of such imperialism contains little political propaganda, no impassioned apostrophe, and—with the exception of the epiklerate (the right of the daughter to continue her dead father's lineage)[6] and arguments against anarchy—makes no contemporary allusion or passing reference to Athens.[7] Rather than become sidetracked with the issues of the time, Antigone remains focused on the characters and themes within the play. It does, however, expose the dangers of the absolute ruler, or tyrant, in the person of Creon, a king to whom few will speak freely and openly their true opinions, and who therefore makes the grievous error of condemning Antigone, an act that he pitifully regrets in the play's final lines. Athenians, proud of their democratic tradition, would have identified his error in the many lines of dialogue which emphasize that the people of Thebes believe he is wrong, but have no voice to tell him so. Athenians would identify the folly of tyranny. |
歴史的背景 アンティゴネーは、国民が熱狂していた時代に書かれた。この戯曲が上演された直後の前441年、ソフォクレスはサモスに対する軍事遠征を指揮する10人の 将軍のひとりに任命された。このような帝国主義の時代の著名な戯曲が、政治的プロパガンダをほとんど含まず、熱烈なアポストロフィーもなく、エピクラーテ (死んだ父の血統を継ぐ娘の権利)[6]と無政府主義に反対する主張を除いては、アテネに関する現代的な言及や通り一遍の言及もないのは驚くべきことであ る[7]。しかし、絶対的な支配者、すなわち暴君の危険性を、クレオンという人格の中で暴いている。クレオンは、自分の本当の意見を自由かつ率直に語ろう としない王であり、それゆえにアンティゴネーを断罪するという重大な過ちを犯す。民主主義の伝統を誇るアテネ人なら、テーベの人々は彼が間違っていると信 じているが、それを彼に伝える声がないことを強調する台詞の数々から、彼の誤りを見抜いただろう。アテネ人なら、専制政治の愚かさを見抜くだろう。 |
| Notable features The Chorus in Antigone departs significantly from the chorus in Aeschylus' Seven Against Thebes, the play of which Antigone is a continuation. The chorus in Seven Against Thebes is largely supportive of Antigone's decision to bury her brother. Here, the chorus is composed of old men who are largely unwilling to see civil disobedience in a positive light. The chorus also represents a typical difference in Sophocles' plays from those of both Aeschylus and Euripides. A chorus of Aeschylus' almost always continues or intensifies the moral nature of the play, while one of Euripides' frequently strays far from the main moral theme. The chorus in Antigone lies somewhere in between; it remains within the general moral in the immediate scene, but allows itself to be carried away from the occasion or the initial reason for speaking.[8] |
注目すべき特徴 『アンティゴネー』の合唱は、『アンティゴネー』の続編であるアイスキュロスの『テーベに対する七人』の合唱とは大きく異なっている。アンティゴネー』の 合唱は、兄を埋葬するというアンティゴネーの決断を支持している。ここで合唱団は、市民的不服従を肯定的にとらえようとしない老人たちで構成されている。 合唱はまた、ソフォクレスの戯曲における、アイスキュロスやエウリピデスの戯曲との典型的な相違を表している。エスキロスの合唱は、ほとんど常に劇の道徳 的性格を継続させるか強めるが、エウリピデスの合唱は、しばしば主要な道徳的テーマから大きく逸脱する。アンティゴネー』の合唱はその中間に位置し、直前 の場面では一般的な道徳の範囲内にとどまるが、その場あるいは最初に話した理由からは外れてしまうのである[8]。 |
| Significance and interpretation Once Creon has discovered that Antigone buried her brother against his orders, the ensuing discussion of her fate is devoid of arguments for mercy because of youth or sisterly love from the Chorus, Haemon or Antigone herself. Most of the arguments to save her center on a debate over which course adheres best to strict justice.[9][10] |
意義と解釈 アンティゴネーが自分の命令に反して兄を埋葬したことをクレオンが発見した後、彼女の運命について続く議論には、コーラス、ヘーモン、アンティゴネー自身から、若さや姉妹愛ゆえの慈悲を求める議論は出てこない。彼女を救おうとする議論のほとんどは、厳格な正義に最も忠実なのはどの道かという議論が中心となっている[9][10]。 |
| Both
Antigone and Creon claim divine sanction for their actions; but
Tiresias the prophet supports Antigone's claim that the gods demand
Polynices' burial. It is not until the interview with Tiresias that
Creon transgresses and is guilty of sin. He had no divine intimation
that his edict would be displeasing to the Gods and against their will.
He is here warned that it is, but he defends it and insults the prophet
of the Gods. This is his sin, and it is this that leads to his
punishment. The terrible calamities that overtake Creon are not the
result of his exalting the law of the state over the unwritten and
divine law that Antigone vindicates, but are his intemperance that led
him to disregard the warnings of Tiresias until it was too late. This
is emphasized by the Chorus in the lines that conclude the play.[11] |
アンティゴネーもクレオンも、自分たちの行動に神の許しが
あると主張するが、預言者ティレシアスは、神がポリュネイケスの埋葬を要求しているというアンティゴネーの主張を支持する。クレオンが罪を犯すのは、ティ
レジアスとの面談のときである。彼は、自分の勅令が神々の不興を買い、神々の意思に反するものであるという神のお告げを受けていなかった。しかし、彼はそ
れを擁護し、神々の預言者を侮辱した。これが彼の罪であり、これが彼の罰につながるのである。クレオンを襲う恐ろしい災難は、アンティゴネーが擁護する不
文律や神の掟よりも国家の掟を尊んだ結果ではなく、手遅れになるまでティレシアスの警告を無視した彼の不摂生が招いたものである。このことは、劇を締めく
くる台詞でコーラスによって強調されている[11]。 |
| The
German poet Friedrich Hölderlin, whose translation had a strong impact
on the philosopher Martin Heidegger, brings out a more subtle reading
of the play: he focuses on Antigone's legal and political status within
the palace, her privilege to be the heiress (according to the legal
instrument of the epiklerate) and thus protected by Zeus. According to
the legal practice of classical Athens, Creon is obliged to marry his
closest relative (Haemon) to the late king's daughter in an inverted
marriage rite, which would oblige Haemon to produce a son and heir for
his dead father in law. Creon would be deprived of grandchildren and
heirs to his lineage – a fact that provides a strong realistic motive
for his hatred against Antigone. This modern perspective has remained
submerged for a long time.[12] |
ド
イツの詩人フリードリヒ・ヘルダーリンは、その翻訳が哲学者マルティン・ハイデガーに強い影響を与えたが、この戯曲をより微妙に読み解く。彼は、アンティ
ゴネーの王宮内での法的・政治的地位、(エピクラーテという法的手段による)相続人としての特権、したがってゼウスによって保護されていることに焦点を当
てる。古典アテネの法律慣習によれば、クレオンは最も近親の者(ヘーモン)と亡き王の娘との逆結婚の儀式を義務づけられ、ヘーモンは死んだ義父のために息
子と跡継ぎを生むことを義務づけられる。クレオンは孫や世継ぎを奪われることになる。この事実は、アンティゴネーに対する憎しみの強い現実的な動機とな
る。この現代的な視点は、長い間没却されたままであった[12]。 |
| Heidegger, in his essay, The Ode on Man in Sophocles' Antigone, focuses on the chorus' sequence of strophe and antistrophe that begins on line 278. His interpretation is in three phases: first to consider the essential meaning of the verse, and then to move through the sequence with that understanding, and finally to discern what was nature of humankind that Sophocles was expressing in this poem. In the first two lines of the first strophe, in the translation Heidegger used, the chorus says that there are many strange things on earth, but there is nothing stranger than man. Beginnings are important to Heidegger, and he considered those two lines to describe the primary trait of the essence of humanity within which all other aspects must find their essence. Those two lines are so fundamental that the rest of the verse is spent catching up with them. The authentic Greek definition of humankind is the one who is strangest of all. Heidegger's interpretation of the text describes humankind in one word that captures the extremes — deinotaton. Man is deinon in the sense that he is the terrible, violent one, and also in the sense that he uses violence against the overpowering. Man is twice deinon. In a series of lectures in 1942, Hölderlin's Hymn, The Ister, Heidegger goes further in interpreting this play, and considers that Antigone takes on the destiny she has been given, but does not follow a path that is opposed to that of the humankind described in the choral ode. When Antigone opposes Creon, her suffering the uncanny is her supreme action.[13][14] | ハ
イデガーは小論『ソフォクレスのアンティゴネーにおける人間頌歌』の中で、278行目から始まる合唱のストロープとアンチスロープの連続に注目している。
彼の解釈は三段階に分かれている。まず、この詩の本質的な意味を考察し、次にその理解に基づいて一連の流れを進め、最後にソフォクレスがこの詩で表現した
人間の本質とは何かを見極める。ハイデガーが用いた訳では、最初のストロープの最初の2行で、合唱は「地上には奇妙なものがたくさんあるが、人間ほど奇妙
なものはない」と言っている。ハイデガーにとって始まりは重要であり、彼はこの2行が人間の本質の主要な特徴を表していると考えた。この2行は非常に基本
的なものであるため、詩の残りの部分はこの2行に追いつくことに費やされている。本場ギリシアにおける人間の定義は、「最も奇妙な者」である。ハイデガー
の解釈では、その両極端を捉える一つの言葉、デイノタトンで人類を表現している。人間は、恐ろしい、暴力的な者であるという意味でデイノタトンであり、ま
た、圧倒的なものに対して暴力を行使するという意味でもデイノタトンである。人間は二度、デイノタトンなのである。ハイデガーは1942年の連続講義『ヘ
ルダーリンの讃歌』において、この戯曲の解釈をさらに進め、アンティゴネーは与えられた運命を引き受けるが、合唱の頌歌に描かれた人類の運命と対立する道
を歩むことはないと考察している。アンティゴネーがクレオンに対抗するとき、不気味な苦悩は彼女の至高の行動である[13][14]。 |
| The problem of the second burial An important issue still debated regarding Sophocles' Antigone is the problem of the second burial. When she poured dust over her brother's body, Antigone completed the burial rituals and thus fulfilled her duty to him. Having been properly buried, Polynices' soul could proceed to the underworld whether or not the dust was removed from his body. However, Antigone went back after his body was uncovered and performed the ritual again, an act that seems to be completely unmotivated by anything other than a plot necessity so that she could be caught in the act of disobedience, leaving no doubt of her guilt. More than one commentator has suggested that it was the gods, not Antigone, who performed the first burial, citing both the guard's description of the scene and the chorus's observation.[15] It's possible, however, that Antigone not only wants her brother to have burial rites, but that she wants his body to stay buried. The guard states that after they found that someone covered Polynices' body with dirt, the birds and animals left the body alone (lines 257–258). But when the guards removed the dirt, then the birds and animals returned, and Tiresias emphasizes that birds and dogs have defiled the city's altars and hearths with the rotting flesh from Polynices' body; as a result of which the gods will no longer accept the peoples' sacrifices and prayers (lines 1015–1020). It's possible, therefore, that after the guards remove the dirt protecting the body, Antigone buries him again to prevent the offense to the gods.[16] Even though Antigone has already performed the burial rite for Polynices, Creon, on the advice of Tiresias (lines 1023–1030), makes a complete and permanent burial for his body. |
二度目の埋葬の問題 ソフォクレスの『アンティゴネー』に関していまだに議論されている重要 な問題は、二度目の埋葬の問題である。兄の遺体に塵をかけたとき、アンティゴネーは埋葬の儀礼を完了し、兄に対する義務を果たした。適切に埋葬されたポ リュネイケスの魂は、遺体から塵が取り除かれようが取り除かれまいが、冥界へと進むことができた。しかしアンティゴネーは、彼の死体が暴かれた後に戻って 再び儀礼を行った。この行為は、彼女が自分の罪を疑うことなく、不従順の行為で捕らえられるという筋書きの必要性以外には、まったく動機がないように思わ れる。しかし、アンティゴネーは弟に埋葬の儀式を受けさせたいだけでなく、弟の遺体を埋葬したままにしておきたいのかもしれない。衛兵は、誰かがポリュネ イケスの遺体を土で覆ったのを発見した後、鳥や動物は遺体を放っておいたと述べている(257-258行)。ティレシアスは、鳥や犬がポリュネイセスの遺 体の腐った肉で街の祭壇や囲炉裏を汚し、その結果、神々はもはや人々の犠牲や祈りを受け入れないと強調する(1015-1020行)。アンティゴネーがポ リュネイケスの埋葬の儀式を済ませたにもかかわらず、クレオンはティレシアスの助言によって(1023-1030行)、ポリュネイケスの遺体を完全かつ永 続的に埋葬する。 |
| Richard C. Jebb suggests that
the only reason for Antigone's return to the burial site is that the
first time she forgot the Choaí (libations), and "perhaps the rite was
considered completed only if the Choaí were poured while the dust still
covered the corpse."[17] |
リチャード・C・ジェブは、アンティゴネーが埋葬地に戻ってきた唯一の理由は、一度目にチョアイ(献杯)を忘れたことであり、「おそらく、まだ埃が死体を覆っている間にチョアイを注いで初めて儀式が完了したと見なされたのだろう」と示唆している[17]。 |
| Gilbert Norwood explains
Antigone's performance of the second burial in terms of her
stubbornness. His argument says that had Antigone not been so obsessed
with the idea of keeping her brother covered, none of the deaths of the
play would have happened. This argument states that if nothing had
happened, nothing would have happened, and does not take much of a
stand in explaining why Antigone returned for the second burial when
the first would have fulfilled her religious obligation, regardless of
how stubborn she was. This leaves that she acted only in passionate
defiance of Creon and respect to her brother's earthly vessel.[18] |
ギルバート・ノーウッドは、アンティゴネーが2度目の埋葬を行ったこと
を、彼女の頑固さという観点から説明している。彼の主張によれば、アンティゴネーが兄を隠しておくという考えに固執していなければ、劇中の死は何も起こら
なかったというのだ。この主張は、何も起こらなかったら何も起こらなかったとするもので、アンティゴネーがどれほど頑固であったとしても、最初の埋葬で宗
教的義務は果たせたはずなのに、なぜ2度目の埋葬のために戻ってきたのかを説明する立場にはあまり立っていない。このことは、彼女がクレオンへの熱烈な反
抗と、兄の地上での器への敬意から行動したに過ぎないということを残している[18]。 |
| Tycho von
Wilamowitz-Moellendorff justifies the need for the second burial by
comparing Sophocles' Antigone to a theoretical version where Antigone
is apprehended during the first burial. In this situation, news of the
illegal burial and Antigone's arrest would arrive at the same time and
there would be no period of time in which Antigone's defiance and
victory could be appreciated. |
ティコ・フォン・ウィラモヴィッツ=メレンドルフは、ソフォクレスの
『アンティゴネー』を、アンティゴネーが最初の埋葬中に逮捕されるという理論的なバージョンと比較することで、二度目の埋葬の必要性を正当化している。こ
の状況では、不法埋葬とアンティゴネー逮捕の知らせが同時に届き、アンティゴネーの反抗と勝利が評価される期間はないだろう。 |
| J. L. Rose maintains that the
problem of the second burial is solved by close examination of Antigone
as a tragic character. Being a tragic character, she is completely
obsessed by one idea, and for her this is giving her brother his due
respect in death and demonstrating her love for him and for what is
right. When she sees her brother's body uncovered, therefore, she is
overcome by emotion and acts impulsively to cover him again, with no
regards to the necessity of the action or its consequences for her
safety.[18] |
J.
L.ローズは、二度目の埋葬の問題は、悲劇的人物としてのアンティゴネーを詳細に検討することによって解決されると主張している。悲劇的な性格である彼女
は、ある一つの考えに完全にとらわれており、それは彼女にとって、兄に死後相応の敬意を払い、兄への愛と正しいことを示すことである。それゆえ、兄の死体
が覆い隠されていないのを見たとき、彼女は感情に打ちひしがれ、その行為の必要性や自分の安全に対するその結果を顧みることなく、兄を再び覆い隠そうと衝
動的に行動する[18]。 |
| Bonnie Honig uses the problem of
the second burial as the basis for her claim that Ismene performs the
first burial, and that her pseudo-confession before Creon is actually
an honest admission of guilt.[19] |
ボニー・ホーニグは、2回目の埋葬の問題を根拠に、イスメネが1回目の埋葬を行い、クレオンの前での彼女の偽りの告白は、実は罪を素直に認めたものだと主張している[19]。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Antigone_(Sophocles_play) |
|
| Modern adaptations Drama Felix Mendelssohn composed a suite of incidental music for Ludwig Tieck's staging of the play in 1841. It includes an overture and seven choruses. Walter Hasenclever wrote an adaptation in 1917, inspired by the events of World War I. Jean Cocteau created an adaptation of Sophocles' Antigone at Théâtre de l'Atelier in Paris on December 22, 1922. French playwright Jean Anouilh's tragedy Antigone was inspired by both Sophocles' play and the myth itself. Anouilh's play premièred in Paris at the Théâtre de l'Atelier in February 1944, during the Nazi occupation of France. Right after World War II, Bertolt Brecht composed an adaptation, Antigone, which was based on a translation by Friedrich Hölderlin and was published under the title Antigonemodell 1948. The Haitian writer and playwright Félix Morisseau-Leroy translated and adapted Antigone into Haitian Creole under the title, Antigòn (1953). Antigòn is noteworthy in its attempts to insert the lived religious experience of many Haitians into the content of the play through the introduction of several Loa from the pantheon of Haitian Vodou as voiced entities throughout the performance. Antigone inspired the 1967 Spanish-language novel La tumba de Antígona (English title: Antigone's Tomb) by María Zambrano. Puerto Rican playwright Luis Rafael Sánchez's 1968 play La Pasión según Antígona Pérez sets Sophocles' play in a contemporary world where Creon is the dictator of a fictional Latin American nation, and Antígona and her 'brothers' are dissident freedom fighters. The Island, a 1973 apartheid-era play by the South African playwrights Athol Fugard, John Kani, and Winston Nthsona, features two cellmates who rehearse and ultimately perform Antigone for the other prisoners, drawing parallels between Antigone herself and black political prisoners held in Robben Island prison. In 1977, Antigone was translated into Papiamento for an Aruban production by director Burny Every together with Pedro Velásquez and Ramon Todd Dandaré. This translation retains the original iambic verse by Sophocles. Antigona Furiosa, written in the period of 1985-86 by Griselda Gambaro, is an Argentinian drama heavily influenced by Antigone by Sophocles, and comments on an era of government terrorism that later transformed into the Dirty War of Argentina. In 2004, theatre companies Crossing Jamaica Avenue and The Women's Project in New York City co-produced the Antigone Project written by Tanya Barfield, Karen Hartman, Chiori Miyagawa, Pulitzer Prize winner Lynn Nottage and Caridad Svich, a five-part response to Sophocles' text and to the US Patriot Act. The text was published by NoPassport Press as a single edition in 2009 with introductions by classics scholar Marianne McDonald and playwright Lisa Schlesinger. Bangladeshi director Tanvir Mokammel in his 2008 film Rabeya (The Sister) also draws inspiration from Antigone to parallel the story to the martyrs of the 1971 Bangladeshi Liberation War who were denied a proper burial.[26] In 2000, Peruvian theatre group Yuyachkani and poet José Watanabe adapted the play into a one-actor piece that remains as part of the group's repertoire.[27] An Iranian absurdist adaptation of Antigone was written and directed by Homayoun Ghanizadeh and staged at the City Theatre in Tehran in 2011.[28] In 2012, the Royal National Theatre adapted Antigone to modern times. Directed by Polly Findlay,[29] the production transformed the dead Polynices into a terrorist threat and Antigone into a "dangerous subversive."[30] Roy Williams's 2014 adaptation of Antigone for the Pilot Theatre relocates the setting to contemporary street culture.[31] Syrian playwright Mohammad Al-Attar adapted Antigone for a 2014 production at Beirut, performed by Syrian refugee women.[32] Antigone in Ferguson is an adaptation conceived in the wake of the shooting of Michael Brown by police in 2014, through a collaboration between Theater of War Productions and community members from Ferguson, Missouri. Translated and directed by Theater of War Productions Artistic Director Bryan Doerries and composed by Phil Woodmore.[33] Elena Carapetis' rewritten version, described as a response to the original, portrays a feminist theme. It was produced by the State Theatre Company of South Australia in Adelaide in June 2022, directed by Anthony Nicola.[34] Antigone in the Amazon (premiered March 2023), a performance that combines storytelling, music, and film to create a political performance, by Belgian theatre-maker Milo Rau.[35][36][37][38] Antigone - Marie Senf. 25.01.2025. Schauspiel Dortmund. Federative Republic of Germany. Marie Senf, a playwright from the Federal Republic of Germany, wrote the anti-totalitarian, anti-fascist and also acrobatic "Antigone". This "Antigone" was premiered at the Schauspiel Dortmund - Dortmund Drama Theatre on January 25th, 2025. This production contains an intertemporal dramatic allusion to Charlie Chaplin's "The Great Dictator" and Istvan Szabo's "Mephisto". And the political, cultural and historical spirit of Marie Senff's dramatic creation continues the Thespian civil tradition of Bertolt Brecht's "Antigone". |
現代の映画化 ドラマ フェリックス・メンデルスゾーンは、1841年にルートヴィヒ・ティークの演出のために付随音楽一式を作曲した。序曲と7つの合唱が含まれている。 ウォルター・ハーサンクルバーは、第一次世界大戦の出来事に触発され、1917年に脚色を手がけた。 ジャン・コクトーは1922年12月22日、パリのアトリエ劇場でソフォクレスの『アンティゴネー』を上演した。 フランスの劇作家ジャン・アヌイユの悲劇『アンティゴネー』は、ソフォクレスの戯曲と神話そのものから着想を得ている。アヌイユの戯曲は、ナチス占領下の1944年2月にパリのアトリエ劇場で初演された。 第二次世界大戦直後、ベルトルト・ブレヒトが、フリードリヒ・ヘルダーリンの翻訳をもとに脚色した『アンティゴネー』を創作し、『アンティゴネーモデル1948』というタイトルで出版された。 ハイチの作家で劇作家のフェリックス・モリソー=ルロワは、『アンティゴネー』をハイチ・クレオール語に翻訳し、『アンティゴネー』(1953年)という タイトルで出版した。Antigòn』は、ハイチ・ヴォドゥーのパンテオンから数人のロアを登場させ、パフォーマティビティを通して、多くのハイチ人の生 きた宗教的経験を劇の内容に挿入しようとした点で注目に値する。 アンティゴネー』は、マリア・ザンブラノによる1967年のスペイン語小説『La tumba de Antígona(英語タイトル:アンティゴネーの墓)』に影響を与えた。 プエルトリコの劇作家ルイス・ラファエル・サンチェスの1968年の戯曲『La Pasión según Antígona Pérez』は、ソフォクレスの戯曲を、クレオンが架空のラテンアメリカ国民の独裁者であり、アンティゴナと彼女の 「兄弟 」たちが反体制の自由戦士である現代世界に設定した。 南アフリカの劇作家アソル・フガード、ジョン・カニ、ウィンストン・ントソナによる1973年のアパルトヘイト時代の戯曲『島』は、アンティゴネーを他の 囚人のためにリハーサルし、最終的に上演する2人の同房者を主人公とし、アンティゴネー自身とロベン島刑務所に収容された黒人政治犯との類似性を描いてい る。 1977年、『アンティゴネー』は、ペドロ・ヴェラスケス、ラモン・トッド・ダンダレとともに、演出家バーニー・エヴリーがアルバニアで上演するためにパピアメント語に翻訳した。この翻訳では、ソフォクレスによるオリジナルのイアンビック詩が維持されている。 グリセルダ・ガンバロによって1985年から86年にかけて書かれた『アンティゴナ・フュリオサ』は、ソフォクレスの『アンティゴネー』の影響を強く受け たアルゼンチンのドラマで、後にアルゼンチンのダーティ・ウォーへと変貌を遂げる政府によるテロリズムの時代を描いている。 2004年、ニューヨークの劇団クロッシング・ジャマイカ・アヴェニューとウィメンズ・プロジェクトは、ターニャ・バーフィールド、カレン・ハートマン、 宮川千織、ピューリッツァー賞受賞者リン・ノッテージ、カリダッド・スヴィッチの5人によるアンティゴネー・プロジェクトを共同制作した。このテキスト は、古典学者マリアンヌ・マクドナルドと劇作家リサ・シュレシンジャーによる序文付きで、2009年にNoPassport Pressから単行本として出版された。 バングラデシュの監督タンヴィール・モカンメルは、2008年の映画『Rabeya(The Sister)』において、アンティゴネーからインスピレーションを得て、適切な埋葬を拒否された1971年のバングラデシュ解放戦争の殉教者と物語を並列させている[26]。 2000年には、ペルーの演劇グループ、ユヤチカニと詩人のホセ・ワタナベが、この戯曲を一人芝居に翻案し、現在も同グループのレパートリーの一部となっている[27]。 イランの不条理劇『アンティゴネー』は、ホマユン・ガニザーデによって脚本・演出され、2011年にテヘランのシティ・シアターで上演された[28]。 2012年、ロイヤル・ナショナル・シアターが『アンティゴネー』を現代に翻案した。ポリー・フィンドレイが演出し[29]、死んだポリュネイケスをテロリストの脅威に、アンティゴネーを「危険な破壊者」に変貌させた[30]。 ロイ・ウィリアムズが2014年にパイロット・シアターで脚色した『アンティゴネー』は、舞台を現代のストリート・カルチャーに移した[31]。 シリアの劇作家モハマド・アル=アッタルは、2014年にベイルートでアンティゴネーを翻案し、シリア難民の女性たちによって上演された[32]。 ファーガソンのアンティゴネー』は、2014年にマイケル・ブラウンが警察に射殺された事件をきっかけに、シアター・オブ・ウォー・プロダクションズとミ ズーリ州ファーガソンのコミュニティ・メンバーとのコラボレーションによって構想された翻案である。翻訳・演出はシアター・オブ・ウォー・プロダクション ズの芸術監督ブライアン・ドアリーズ、作曲はフィル・ウッドモアが担当した[33]。 エレナ・カラペティスの書き直したバージョンは、原作への応答と説明され、フェミニズムをテーマに描いている。2022年6月、南オーストラリア州立劇団によって、アンソニー・ニコラ演出でアデレードで上演された[34]。 アマゾンのアンティゴネー』(2023年3月初演)は、ベルギーの演劇人ミロ・ラウによる、ストーリーテリング、音楽、映画を組み合わせた政治的パフォーマンスである[35][36][37][38]。 アンティゴネー - マリー・ゼンフ。Schauspielドルトムント。ドイツ連邦共和国。 ドイツ連邦共和国の劇作家マリー・ゼンフは、反全体主義、反ファシスト、そしてアクロバティックな『アンティゴネー』を書いた。この『アンティゴネー』 は、2025年1月25日にドルトムントのドラマ劇場で初演された。この作品には、チャーリー・チャップリンの『偉大なる独裁者』やイシュトヴァン・サー ボの『メフィスト』への同時代的なドラマの引用が含まれている。そして、マリー・センフが創作する政治的、文化的、歴史的精神は、ベルトルト・ブレヒトの 『アンティゴネー』のテスピア市民の伝統を受け継いでいる。 |
| Opera Antigone, opera by Arthur Honegger, premiered on December 28, 1927, at Théâtre de la Monnaie in Bruxelles. Antigonae, opera by Carl Orff, a Literaturoper, which uses Friedrich Hölderlin's translation of Sophokles' drama (1805), premiered on August 8, 1949, at the Felsenreitschule in the context of Salzburg Festival. Antigone (1977) by Dinos Constantinides, on an English libretto by Fitts and Fitzgerald Antigone (1986) by Marjorie S. Merryman Antigone oder die Stadt (1988) by Georg Katzer with a libretto by Gerhard Müller, premiered at the Komische Oper Berlin in 1991, staged by Harry Kupfer and conducted by Jörg-Peter Weigle The Burial at Thebes (2007–2008) by Dominique Le Gendre and libretto by Seamus Heaney, based on his translation for spoken theatre. The production features conductor William Lumpkin, stage director Jim Petosa, and six singers and ten instrumentalists.[39] Antigone (2020) oratory composed by Samy Moussa with stage direction and choreography by Nanine Linning, premiered on March 9, 2024 at the Dutch National Opera & Ballet in conjunction with Stravinsky’s Oedipus Rex (1927) Literature Sara Uribe's Antígona González, a book of prose set in Tamaulipas, Mexico exploring violent and fatal effects of the drug war, draws heavily on Antigone to reflect everyone in Latin America searching for the missing loved one. In 2017 Kamila Shamsie published Home Fire, which transposes some of the moral and political questions in Antigone into the context of Islam, ISIS and modern-day Britain. 2023 saw bestselling author Veronica Roth publish a speculative fiction version of Antigone, Arch-Conspirator, which explores concepts of gender equity, reproductive rights, and the loss of freedoms under self-righteous tyranny. Cinema George Tzavellas adapted the play into a 1961 film, which he also directed. It featured Irene Papas as Antigone. Liliana Cavani's 1969 The Year of the Cannibals is a contemporary political fantasy based upon the Sophocles play, with Britt Ekland as Antigone and Pierre Clémenti as Tiresias. The 1978 omnibus film Germany in Autumn features a segment by Heinrich Böll entitled "The Deferred Antigone"[40] where a fictional production of Antigone is presented to television executives who reject it as "too topical".[41] In 1992, Jean-Marie Straub and Danièle Huillet made a film adaptation based on Brecht’s stage version of Hölderlin’s translation — Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Brecht (1948). A 2019 Canadian film adaption transposed the story into one of a modern-day immigrant family in Montreal. It was adapted and directed by Sophie Deraspe, with additional inspiration from the Death of Fredy Villanueva. Antigone was played by Nahéma Ricci. Television Vittorio Cottafavi directed two television productions of the play, in 1958 for RAI Radiotelevisione Italiana and in 1971 for Rai 1. Valentina Fortunato and Adriana Asti, respectively, performed the title role. It was filmed for Australian TV in 1966. In 1986, Juliet Stevenson starred as Antigone, with John Shrapnel as Creon and John Gielgud as Tiresias in the BBC's The Theban Plays. Antigone at the Barbican was a 2015 filmed-for-TV version of a production at the Barbican directed by Ivo van Hove; the translation was by Anne Carson and the film starred Juliette Binoche as Antigone and Patrick O'Kane as Kreon. Other TV adaptations of Antigone have starred Irene Worth (1949) and Dorothy Tutin (1959), both broadcast by the BBC. |
オペラ アンティゴネー』(アルトゥール・オネゲル作)は、1927年12月28日にブリュッセルのモネ劇場で初演された。 ソフォクレスの戯曲(1805年)のフリードリヒ・ヘルダーリンの翻訳を用いた文学者カール・オルフのオペラ『アンティゴネー』は、1949年8月8日、ザルツブルク音楽祭の一環としてフェルゼンライツシューレで初演された。 アンティゴネー』(1977年)ディノス・コンスタンティニデス作、フィッツとフィッツジェラルドの英語台本による。 アンティゴネー』(1986)マージョリー・S・メリーマン作 アンティゴネー」(1988)ゲオルク・カッツァー作、ゲルハルト・ミュラー台本、1991年ベルリン・コミッシェ・オーパー初演、ハリー・クプファー演出、イェルク=ペーター・ヴァイグル指揮。 テーベの埋葬』(2007-2008)はドミニク・ル・ジャンドル作、シェイマス・ヒーニー台本、口語訳。指揮者ウィリアム・ランプキン、舞台監督ジム・ペトサ、6人の歌手と10人の器楽奏者が出演している[39]。 アンティゴネー』(2020年)サミー・ムーサ作曲、ナニーヌ・リニング演出・振付によるオラトリオで、ストラヴィンスキーの『オイディプス王』(1927年)と連動し、2024年3月9日にオランダ国民歌劇場&バレエ団で初演された。 文学 サラ・ウリベの『アンティゴネー』は、メキシコのタマウリパス州を舞台に、麻薬戦争の暴力的で致命的な影響を探る散文集で、アンティゴネーを多用し、行方不明の愛する人を探すラテンアメリカの人々を映し出している。 2017年、カミラ・シャムジーは『Home Fire』を出版し、『アンティゴネー』の道徳的・政治的問題のいくつかをイスラム教、ISIS、現代のイギリスの文脈に置き換えた。 2023年には、ベストセラー作家のヴェロニカ・ロスが、ジェンダー平等、生殖の権利、独善的な専制政治のもとでの自由の喪失という概念を探求した、スペキュレイティブ・フィクション版アンティゴネー『Arch-Conspirator』を発表した。 映画 ジョージ・ツァヴェラスはこの戯曲を1961年に映画化し、監督も務めた。アンティゴネー役にはイレーネ・パパスが起用された。 リリアナ・カヴァーニの1969年の『食人族の年』は、ソフォクレスの戯曲を基にした現代の政治ファンタジーで、アンティゴネー役にブリット・エクランド、ティレジアス役にピエール・クレメンティが扮している。 1978年のオムニバス映画『秋のドイツ』には、ハインリヒ・ベールによる「延期されたアンティゴネー」と題されたセグメントがあり[40]、アンティゴネーの架空の演出がテレビ局の重役たちに提示されるが、「時事的すぎる」として却下される[41]。 1992年、ジャン=マリー・ストローブとダニエーレ・ユイレは、ブレヒトによるヘルダーリン訳の舞台版『ソフォクレスのアンティゴネー』(Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Brecht、1948年)を基に映画化した。 2019年にカナダで映画化された作品は、この物語をモントリオールの現代の移民家族の物語に置き換えている。フレディ・ヴィラヌエヴァの死からインスピレーションを得て、ソフィー・デラスペが脚色・監督した。アンティゴネーはナヘマ・リッチが演じた。 テレビ ヴィットリオ・コッタファヴィは、1958年にRAIイタリア放送で、1971年にRai 1で、この戯曲を2度テレビ放映した。ヴァレンティーナ・フォルトゥナートとアドリアーナ・アスティがそれぞれタイトルロールを演じた。 1966年にはオーストラリアのテレビでも放映された。 1986年にはジュリエット・スティーヴンソンがアンティゴネー役を演じ、ジョン・シュラプネルがクレオン役、ジョン・ギールグッドがティレシアス役でBBCの『Theban Plays』に出演した。 バービカンのアンティゴネー』は、イヴォ・ヴァン・ホーヴェが演出したバービカンでの上演を2015年にテレビ用に映像化したもので、翻訳はアン・カーソン、アンティゴネー役はジュリエット・ビノシュ、クレオン役はパトリック・オケインが演じた。 アンティゴネー』の他のテレビ映画化作品には、アイリーン・ワース主演の『アンティゴネー』(1949年)とドロシー・チューティン主演の『アンティゴネー』(1959年)があり、いずれもBBCで放送された。 |
| Translations and adaptations 1550 – Georgio Rotallero: text in Latin 1729 – George Adams, prose: full text 1782 – Vittorio Alfieri, in hendecasyllables: text in Italian 1839 – Johann Jakob Christian Donner, German verse 1865 – Edward H. Plumptre, verse (full text on Wikisource, with audio) 1883 – Lewis Campbell, verse (full text on Wikisource) 1888 – Sir George Young, verse (Dover, 2006; ISBN 978-0486450490) 1899 – G. H. Palmer, verse (Boston: Houghton and Mifflin, 1899) 1904 – Richard C. Jebb, prose: (full text on Wikisource) 1911 – Joseph Edward Harry, verse (Cincinnati: Robert Clarke, 1911) (full text on Wikisource) 1912 – F. Storr, verse: full text 1926 – Ettore Romagnoli, in hendecasyllables, text in Italian 1931 – Shaemas O'Sheel, prose 1938 – Dudley Fitts and Robert Fitzgerald, verse: full text 1946 – Jean Anouilh, (modern French translation) 1947 – E. F. Watling, verse (Penguin classics) 1949 – Robert Whitelaw, verse (Rinehart Editions) 1950 – Theodore Howard Banks, verse 1950 – W. J. Gruffydd (translation into Welsh) 1953 – Félix Morisseau-Leroy (translated and adapted into Haitian Creole) 1954 – Elizabeth Wyckoff, verse 1954 – F. L. Lucas, verse translation 1956 – Shahrokh Meskoob (into Persian) 1958 – Paul Roche, verse 1962 – H. D. F. Kitto, verse 1962 – Michael Townsend, (Longman, 1997; ISBN 978-0810202146) 1973 – Richard Emil Braun, verse 1982 – Robert Fagles, verse with introduction and notes by Bernard Knox 1986 – Don Taylor, prose (The Theban Plays, Methuen Drama; ISBN 978-0413424600) 1991 – David Grene, verse 1994 – Hugh Lloyd-Jones, verse (Sophocles, Volume II: Antigone, The Women of Trachis, Philoctetes, Oedipus at Colonus, Loeb Classical Library No. 21, 1994; ISBN 978-0674995581) 1997 – George Judy, adaptation for children (Pioneer Drama, 1997) 1998 – Ruby Blondell, prose with introduction and interpretive essay (Focus Classical Library, Focus Publishing/R Pullins Company; ISBN 0941051250) 1999 – Declan Donnellan, with introduction by Nicholas Dromgoole (Oberon Books, 1999; ISBN 978-1840021363) 2000 – Marianne MacDonald, (Nick Hern Books, 2000; ISBN 978-1854592002) 2001 – Paul Woodruff, verse (Hackett, 2001; ISBN 978-0-87220-571-0) 2003 – Reginald Gibbons and Charles Segal, verse (Oxford UP, 2007; ISBN 978-0195143102) 2004 – Seamus Heaney, The Burial at Thebes – verse adaptation (Farrar, Straus and Giroux, 2005; ISBN 978-0374530075), also adapted as an opera in 2008 2005 – Ian C. Johnston, verse (modern English): full text 2006 – George Theodoridis, prose: full text 2006 – A. F. Th. van der Heijden, 'Drijfzand koloniseren' ("Colonizing quicksand"), prose, adapting Antigone's story using characters from the author's 'Homo Duplex' saga. 2009 – Tanya Barfield, Karen Hartman, Lynn Nottage, Chiori Miyagawa, Caridad Svich, play adaptation (NoPassport Press, 2009; ISBN 978-0578031507) 2011 – Diane Rayor, Sophocles' Antigone: A New Translation. Cambridge University Press. 2012 – Anne Carson, play adaptation (Antigonick, New Directions Press; ISBN 978-0811219570) 2013 – George Porter, verse ("Black Antigone: Sophocles' tragedy meets the heartbeat of Africa", ISBN 978-1909183230) 2014 – Marie Slaight and Terrence Tasker, verse and art ('"The Antigone Poems, Altaire Productions; ISBN 978-0980644708) 2016 – Frank Nisetich 2016 – Slavoj Žižek, with introduction by Hanif Kureishi, Bloomsbury, New York 2017 – Kamila Shamsie, Home Fire, novel. An adaptation in a contemporary context, London: Bloomsbury Circus. ISBN 978-1408886779 2017 – Brad Poer, Antigone: Closure, play adaptation (contemporary American prose adaptation set post-fall of United States government) 2017 – Griff Bludworth, ANTIGONE (born against). A contemporary play adaptation that addresses the theme of racial discrimination. 2017 – Seonjae Kim, Riot Antigone. A punk rock musical adaptation inspired by the Riot grrrl movement that focuses on Antigone's coming of age. 2019 – Niloy Roy, Antigone: Antibody, play adaptation (contemporary Indian adaptation set in post-anarchic context of conflict between state and individual) 2019 – Sophie Deraspe, Antigone 2019 – Beth Piatote, Antíkoni, a modern Indigenous (specifically Nez Perce) play adaptation, published in The Beadworkers (CounterPoint Press, ISBN 978-1640092686) 2023 – Edward Alexander, Antigone,, verse, Invictus Publishing, ISBN 979-8393254292 |
翻訳と翻案 1550年 - Georgio Rotallero:ラテン語テキスト 1729 - ジョージ・アダムス散文:全文 1782年 - ヴィットリオ・アルフィエーリ(Vittorio Alfieri):イタリア語テキスト 1839 - ヨハン・ヤコブ・クリスチャン・ドナー(ドイツ詩 1865 - Edward H. Plumptre、詩(ウィキソースに全文、音声あり) 1883 - ルイス・キャンベル、詩(ウィキソースに全文あり) 1888 - Sir George Young, 詩 (Dover, 2006; ISBN 978-0486450490) 1899 - G. H. パーマー、詩 (Boston: Houghton and Mifflin, 1899) 1904 - リチャード・C・ジェブ、散文:(ウィキソースに全文あり) 1911 - ジョセフ・エドワード・ハリー、詩(シンシナティ:ロバート・クラーク、1911年)(Wikisourceに全文あり) 1912 - F. Storr(詩): 全文 1926 - エットーレ・ロマニョーリ(Ettore Romagnoli)、ヘンテコリン、テキスト:イタリア語 1931 - シェーマス・オシール、散文 1938 - ダドリー・フィッツとロバート・フィッツジェラルド、詩:全文 1946 - ジャン・アヌイユ(現代フランス語訳) 1947 - E・F・ワトリング、詩(ペンギン・クラシックス) 1949 - ロバート・ホワイトロー 詩(ラインハート・エディションズ) 1950 - セオドア・ハワード・バンクス 詩 1950 - W. J. グルフィド(ウェールズ語訳) 1953 - フェリックス・モリソー=ルロワ(ハイチ・クレオール語に翻訳・翻案) 1954 - エリザベス・ワイコフ(詩 1954 - F. L. ルカーチ(詩の翻訳 1956 - シャーロック・メスコブ(ペルシア語訳) 1958 - ポール・ロッシュ(詩 1962年 - H. D. F. キトー、詩 1962年 - マイケル・タウンゼント(Longman, 1997; ISBN 978-0810202146) 1973年 - リチャード・エミール・ブラウン、詩 1982年 ロバート・ファッグルズ 詩(バーナード・ノックスによる序文と注釈付き 1986年 - ドン・テイラー、散文(『The Theban Plays』Methuen Drama; ISBN 978-0413424600) 1991 - デイヴィッド・グレーン(詩 1994 - ヒュー・ロイド=ジョーンズ、詩(『ソフォクレス』第2巻:アンティゴネー、トラキスの女たち、フィロクテテテス、コロノスのオイディプス、ローブ・クラシカル・ライブラリー21号、1994年、ISBN 978-0674995581) 1997 - ジョージ・ジュディ、子供向け脚色(パイオニア・ドラマ、1997年) 1998 - ルビー・ブロンデル、散文、序文・解説エッセイ付き(フォーカス・クラシカル・ライブラリー、フォーカス出版/Rプリンズ社、ISBN 0941051250) 1999 - デクラン・ドネラン、ニコラス・ドロムグールによる序文付き(オベロンブックス、1999;ISBN 978-1840021363) 2000 - マリアンヌ・マクドナルド(ニック・ヘルン・ブックス、2000年;ISBN 978-1854592002) 2001 - ポール・ウッドラフ、詩(ハケット、2001年; ISBN 978-0-87220-571-0) 2003 - レジナルド・ギボンズ、チャールズ・シーガル詩集(オックスフォード大学、2007年、ISBN 978-0195143102) 2004 - Seamus Heaney, The Burial at Thebes - 詩の翻案(Farrar, Straus and Giroux, 2005; ISBN 978-0374530075)2008年にオペラ化もされた。 2005 - イアン・C・ジョンストン(Ian C. Johnston):詩(現代英語):全文 2006 - ジョージ・テオドリディス散文:全文 2006 - A. F. Th. van der Heijden, 『Drijfzand koloniseren』 (「流砂の植民地化」), 散文, 作者の「ホモ・デュプレックス」サーガの登場人物を使ってアンティゴネーの物語を脚色。 2009 - Tanya Barfield, Karen Hartman, Lynn Nottage, Chiori Miyagawa, Caridad Svich, 戯曲化(NoPassport Press, 2009; ISBN 978-0578031507) 2011 - ダイアン・レイヨー『ソフォクレスのアンティゴネー』: A New Translation. ケンブリッジ大学出版局。 2012 - アン・カーソン、戯曲化(『アンティゴニック』、ニュー・ディレクションズ・プレス、ISBN 978-0811219570) 2013 - ジョージ・ポーター、詩(「黒いアンティゴネー」: ソフォクレスの悲劇とアフリカの鼓動」、ISBN 978-1909183230) 2014 - マリー・スライトとテレンス・タスカー、詩と美術(『アンティゴネーの詩』、アルテール・プロダクションズ、ISBN 978-0980644708) 2016 - フランク・ニセティッチ 2016 - スラヴォイ・ジジェク、ハニフ・クレイシによる紹介付き、ブルームズベリー、ニューヨーク 2017年 - カミラ・シャムジー『ホーム・ファイヤー』小説。現代の文脈における翻案、ロンドン:ブルームズベリー・サーカス。ISBN 978-1408886779 2017年 - ブラッド・ポアー『アンティゴネー』: Closure』(戯曲化)(合衆国政府崩壊後を舞台とした現代アメリカの散文翻案 2017年 - グリフ・ブラッドワース『アンティゴネー』(born against)。人種差別をテーマにした現代劇の翻案。 2017年 - キム・ソンジェ『暴動アンティゴネー』。ライオット・グリル・ムーブメントにインスパイアされ、アンティゴネーの青春に焦点を当てたパンク・ロック・ミュージカルの翻案。 2019 - ニロイ・ロイ『アンティゴネー』: アンティゴネー:抗体」、戯曲化(国家と個人の対立というアナーキー以降の文脈を舞台にした現代インディアンへの翻案)。 2019 - ソフィー・デラスペ『アンティゴネー 2019年 - ベス・ピアトート『アンティコニ』、現代先住民(特にネズパース族)の戯曲翻案、『ビーズワーカーズ』(カウンターポイント・プレス、ISBN 978-1640092686)に掲載される。 2023 - エドワード・アレクサンダー、『アンティゴネー』、詩、インヴィクタス・パブリッシング、ISBN 979-8393254292 |
| Further reading Butler, Judith (2000). Antigone's Claim: Kinship Between Life and Death. New York: Columbia University Press. ISBN 0231118953. Heaney, Seamus (December 2004). "The Jayne Lecture: Title Deeds: Translating a Classic" (PDF). Proceedings of the American Philosophical Society. 148 (4): 411–426. Archived from the original (PDF) on 2011-10-18. Heidegger, Martin; Gregory Fried; Richard Polt (2000). An Introduction to Metaphysics. New Haven: Yale University Press. pp. 156–176. ISBN 978-0300083286. Heidegger, Martin; McNeill, William; Davis, Julia (1996). Hölderlin's Hymn "The Ister". Bloomington: Indiana University Press. Lacan, Jacques (1992). The Seminar of Jacques Lacan, Book VII: The Ethics of Psychoanalysis. Translated by Dennis Porter. New York: W.W. Norton. pp. 240–286. ISBN 0393316130. Miller, Peter (2014). "Helios, vol. 41 no. 2, 2014 © Texas Tech University Press 163 Destabilizing Haemon: Radically Reading Gender and Authority in Sophocles' Antigone". Helios. 41 (2): 163–185. doi:10.1353/hel.2014.0007. hdl:10680/1273. S2CID 54829520. Segal, Charles (1999). Tragedy and Civilization: An Interpretation of Sophocles. Norman: University of Oklahoma Press. p. 266. ISBN 978-0806131368. Steiner, George (1996). Antigones: How the Antigone Legend Has Endured in Western Literature, Art, and Thought. New Haven: Yale University Press. ISBN 0300069154. |
さらに読む Butler, Judith (2000). アンティゴネーの主張:生と死の間の親族関係」。ニューヨーク: コロンビア大学出版局. ISBN 0231118953. Heaney, Seamus (December 2004). 「The Jayne Lecture: タイトル証書: 古典の翻訳" (PDF). Proceedings of the American Philosophical Society. 148 (4): 411-426. 2011-10-18にオリジナル(PDF)からアーカイブされた。 ハイデガー、マーティン; グレゴリー・フリード; リチャード・ポルト (2000). 形而上学入門. New Haven: Yale University Press. ISBN 978-0300083286. ハイデガー, マーティン; マクニール, ウィリアム; デイヴィス, ジュリア (1996). ヘルダーリン讃歌「イスター」. Bloomington: Indiana University Press. Lacan, Jacques (1992). ジャック・ラカンのセミナー』第Ⅶ巻:精神分析の倫理。デニス・ポーター訳。ニューヨーク: 240-286ページ。ISBN 0393316130. Miller, Peter (2014). "Helios, vol. 41 no. 2, 2014 © Texas Tech University Press 163 Destabilizing Haemon: Destabilizing Haemon: Radically Reading Gender and Authority in Sophocles' Antigone". Helios. 41 (2): 163-185. doi:10.1353/hel.2014.0007. hdl:10680/1273. s2cid 54829520. Segal, Charles (1999). Tragedy and Civilization: An Interpretation of Sophocles. Norman: University of Oklahoma Press. ISBN 978-0806131368. Steiner, George (1996). アンティゴネー: Antigones: How the Antigone Legend Has Endured in Western Literature, Art, and Thought. New Haven: Yale University Press. ISBN 0300069154. |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Antigone_(Sophocles_play) |
★議論すべきテーマ
| Themes Civil disobedience A well established theme in Antigone is the right of the individual to reject society's infringement on one's freedom to perform a personal obligation.[20] Antigone comments to Ismene, regarding Creon's edict, that "He has no right to keep me from my own."[21] Related to this theme is the question of whether Antigone's will to bury her brother is based on rational thought or instinct, a debate whose contributors include Goethe.[20] The contrasting views of Creon and Antigone with regard to laws higher than those of state inform their different conclusions about civil disobedience. Creon demands obedience to the law above all else, right or wrong. He says that "there is nothing worse than disobedience to authority" (An. 671). Antigone responds with the idea that state law is not absolute, and that it can be broken in civil disobedience in extreme cases, such as honoring the gods, whose rule and authority outweigh Creon's. |
テーマ 市民的不服従 『アンティゴネー』のテーマとしてよく知られているのは、個人的な義務を果たす自由に対する社会の侵害を拒否する個人の権利である[20]。アンティゴ ネーはクレオンの勅令について、イスメネーに「彼は私を私自身のものから遠ざける権利はない」とコメントしている[21]。このテーマに関連して、弟を葬 るというアンティゴネーの意志が合理的な思考に基づいているのか、それとも本能に基づいているのかという問題があり、この議論にはゲーテも参加している [20]。 クレオンとアンティゴネーの、国家より上位の法に関する対照的な見解は、市民的不服従に関する二人の異なる結論に影響を与えている。クレオンは、善悪を問 わず、何よりも法律への服従を要求する。彼は「権威に背くことほど悪いことはない」(An. 671)と言う。アンティゴネーは、国家法は絶対的なものではなく、クレオンを凌駕する支配と権威を持つ神々を敬うような極端な場合には、市民的不服従と してそれを破ることができるという考えで反論する。 |
| Natural law and contemporary legal institutions Creon's decree to leave Polynices unburied in itself makes a bold statement about what it means to be a citizen, and what constitutes abdication of citizenship. It was the firmly kept custom of the Greeks that each city was responsible for the burial of its citizens. Herodotus discussed how members of each city would collect their own dead after a large battle to bury them.[22] In Antigone, it is therefore natural that the people of Thebes did not bury the Argives, but very striking that Creon prohibited the burial of Polynices. Since he is a citizen of Thebes, it would have been natural for the Thebans to bury him. Creon is telling his people that Polynices has distanced himself from them, and that they are prohibited from treating him as a fellow-citizen and burying him as is the custom for citizens. In prohibiting the people of Thebes from burying Polynices, Creon is essentially placing him on the level of the other attackers—the foreign Argives. For Creon, the fact that Polynices has attacked the city effectively revokes his citizenship and makes him a foreigner. As defined by this decree, citizenship is based on loyalty. It is revoked when Polynices commits what in Creon's eyes amounts to treason. When pitted against Antigone's view, this understanding of citizenship creates a new axis of conflict. Antigone does not deny that Polynices has betrayed the state, she simply acts as if this betrayal does not rob him of the connection that he would have otherwise had with the city. Creon, on the other hand, believes that citizenship is a contract; it is not absolute or inalienable, and can be lost in certain circumstances. These two opposing views – that citizenship is absolute and undeniable and alternatively that citizenship is based on certain behavior – are known respectively as citizenship 'by nature' and citizenship 'by law.'[22] |
自然法と現代の法制度 ポリュネイケスを埋葬せずに放置するというクレオンの命令は、それ自体、市民であることの意味と、市民権の放棄を構成するものについて大胆な声明を出して いる。ギリシアでは、各都市が市民の埋葬に責任を持つという習慣が固く守られていた。アンティゴネー』では、テーベの人々がアルギヴ人を埋葬しなかったの は当然だが、クレオンがポリュネイケスの埋葬を禁止したのは非常に印象的だった。ポリニスはテーベの市民であるから、テーベの人々がポリニスを埋葬するの は当然である。クレオンは、ポリュネイケスが人民と距離を置いたので、人民がポリュネイケスを同胞として扱い、人民の習慣に従って埋葬することを禁じたの である。 テーベの人々がポリュネイケスを埋葬することを禁止することで、クレオンはポリュネイケスを他の襲撃者たち(外国のアルギヴ人)と同列に扱うことになる。 クレオンにとって、ポリュネイケスが都市を攻撃したという事実は、ポリュネイケスの市民権を事実上剥奪し、彼を外国人にしてしまう。この勅令で定義されて いるように、市民権は忠誠心に基づいている。ポリュネイケスがクレオンの目に反逆と映る罪を犯したとき、市民権は剥奪される。アンティゴネーの見解と対立 させると、市民権に対するこの理解は新たな対立軸を生み出す。アンティゴネーはポリュネイケスが国家を裏切ったことを否定しないが、単にこの裏切りによっ てポリュネイケスが持っていたはずの都市とのつながりが奪われないかのように振る舞っている。一方クレオンは、市民権は契約であり、絶対的なものでも不可 分のものでもなく、状況によっては失うこともあり得ると考えている。市民権は絶対的で否定できないものであり、また、市民権は一定の行動に基づくものであ るという、この対立する二つの見解は、それぞれ「自然による」市民権、「法による」市民権として知られている[22]。 |
| Fidelity Antigone's determination to bury Polynices arises from a desire to bring honor to her family, and to honor the higher law of the gods. She repeatedly declares that she must act to please "those that are dead" (An. 77), because they hold more weight than any ruler, that is the weight of divine law. In the opening scene, she makes an emotional appeal to her sister Ismene saying that they must protect their brother out of sisterly love, even if he did betray their state. Antigone believes that there are rights that are inalienable because they come from the highest authority, or authority itself, that is the divine law. While he rejects Antigone's actions based on family honor, Creon appears to value family himself. When talking to Haemon, Creon demands of him not only obedience as a citizen, but also as a son. Creon says "everything else shall be second to your father's decision" ("An." 640–641). His emphasis on being Haemon's father rather than his king may seem odd, especially in light of the fact that Creon elsewhere advocates obedience to the state above all else. It is not clear how he would personally handle these two values in conflict, but it is a moot point in the play, for, as absolute ruler of Thebes, Creon is the state, and the state is Creon. It is clear how he feels about these two values in conflict when encountered in another person, Antigone: loyalty to the state comes before family fealty, and he sentences her to death. |
忠誠 アンティゴネーがポリュネイケスを埋葬しようと決意するのは、家族に名誉をもたらし、神々の崇高な掟を尊重したいという願望からである。彼女は「死んだ者 たち」(An. 77)を喜ばせるために行動しなければならないと繰り返し宣言するが、それは彼らがどんな支配者よりも重みを持つからであり、それは神の掟の重みである。 冒頭のシーンでは、妹のイスメネに、たとえ兄が国を裏切ったとしても、姉妹愛から兄を守らなければならないと感情的に訴える。アンティゴネーは、神の法と いう最高の権威、つまり権威そのものに由来するものだからこそ、譲れない権利があると信じている。 家族の名誉に基づくアンティゴネーの行動を否定する一方で、クレオンは家族を大切にしているように見える。ヘーモンと話すとき、クレオンは彼に市民として の服従だけでなく、息子としての服従も要求する。クレオンは「他のことはすべて、父上の決定に従わなければならない」(「An.」 640-641)と言う。クレオンは他の場面で、何よりも国家への服従を唱えている。テーベの絶対的支配者として、クレオンは国家であり、国家はクレオン なのである。アンティゴネーという別の人格の中でこの2つの価値観が対立したとき、クレオンがどのように感じるかは明らかだ。 |
| Portrayal of the gods In Antigone as well as the other Theban Plays, there are very few references to the gods. Hades is the god who is most commonly referred to, but he is referred to more as a personification of Death. Zeus is referenced a total of 13 times by name in the entire play, and Apollo is referenced only as a personification of prophecy. This lack of mention portrays the tragic events that occur as the result of human error, and not divine intervention. The gods are portrayed as chthonic, as near the beginning there is a reference to "Justice who dwells with the gods beneath the earth." Sophocles references Olympus twice in Antigone. This contrasts with the other Athenian tragedians, who reference Olympus often. |
神々の描写 『アンティゴネー』や他のテーバン劇では、神々についての言及はほとんどない。ハデスは最もよく言及される神だが、死の擬人化として言及されることが多 い。ゼウスは戯曲全体で合計13回しか名前が言及されず、アポロは予言の擬人化として言及されるだけである。この言及の少なさは、神の介入ではなく、人間 の過ちの結果として起こる悲劇的な出来事を描いている。冒頭近くで 「地底の神々と共にある正義 」について言及されているように、神々は神話的な存在として描かれている。ソフォクレスは『アンティゴネー』の中でオリンポスに二度言及している。これ は、オリンポスに頻繁に言及する他のアテナイの悲劇家たちとは対照的である。 |
| Love for family Antigone's love for family is shown when she buries her brother, Polynices. Haemon was deeply in love with his cousin and fiancée Antigone, and he killed himself in grief when he found out that his beloved Antigone had hanged herself. |
家族への愛 アンティゴネの家族への愛は、兄ポリュネイケスを埋葬したときに示される。ヘーモンは従兄弟で婚約者のアンティゴネーを深く愛していたが、最愛のアンティゴネーが首を吊ったことを知り、悲しみのあまり自殺した。 |
| Equity Following in the Aristotelian tradition, Antigone is also seen as a case-study for equity. Catharine Titi has likened Antigone's 'divine' law to modern peremptory norms of customary international law (ius cogens) and she has discussed Antigone's dilemma as a situation that invites the application of equity contra legem in order to correct the law.[23] |
公平性 アリストテレスの伝統に倣い、アンティゴネーもまた衡平性のケーススタディと見なされている。キャサリン・ティティはアンティゴネーの「神的な」法を現代 の国際慣習法の厳格な規範(ius cogens)になぞらえ、アンティゴネーのジレンマを、法を正すために衡平法(equity contra legem)の適用を招く状況として論じている[23]。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Antigone_(Sophocles_play) |
★ Collection « Digraphe », dirigée par Jean Ristat
| D'abord : deux colonnes.
Tronquées, par le haut et par le bas;
taillées aussi dans leur flanc : incises, tatouages, incrustations. Une
première lecture peùt faire comme si deux textes dressés, l'un contre
l'autre ou l'un sans_ l'autre, entre eux ne communiquaient pas. Et
d'une
certaine façon délibérée, cela reste vrai, quant au prétexte, à
l'objet, à
la langue, au i,tyle, au rythme, à la loi. Une dialectique d'un côté,
une
galactique de l'autre, hétérogènes et cependant indiscernables dans
leurs
effets, parfois jusqu'à l'hallucination. Entre les deux, le battant
d'un
autre texte, on dirait d'une autre « logique » : aux surnoms d'
obséquence,
de penêtre, de stricture, de serrure, d'anthérection, de mors,
etc. |
まず、2本の柱がある。上と下で切り取られ、側面にも切り込み、刺青、
埋め込みが施されている。最初の読みでは、2つのテキストが互いに対峙しているか、あるいは互いに無関係に立っているように見える。そして、ある意味で意
図的に、その前提、対象、言語、スタイル、リズム、法則に関しては、それは事実だ。一方には弁証法、もう一方には銀河系、異質でありながらその効果は区別
がつかず、時には幻覚の域に達する。その間には、別のテキストの拍子、別の「論理」のようなものが存在する。従順、隙、厳格、鍵、アンテレクション、噛み
つきなどといった形容詞が、その特徴を表現している。 |
| Pour qui tient à la signature, au corpus et au propre, déclarons que, mettant en· jeu, en pièces plutôt, mon nom, mon corps et mon seing, j'élabore d'un même coup, en toutes lettres, ceux du dénommé Hegel dans une çolonne, ceux du dénommé Genet dans l'autre. On verra pourquoi, chance et nécessité, ces deux-là. La chose, donc, s'élève, se détaille - et détache selon deux tours, et l'accélération incessante d'un tour-àtour. Dans leur double solitude, les colosses échangent une infinité de clins, par exemple d'oeil, se doublent à l'envi, se pénètr.ent, collent et décollent, passant l'un dans l'autre, entre l'un et dans l'autre. Chaque colonne figureici un colosse (colossos), nom donné au double du mort, au substitut de son érection. Plus qu'un, avant tout. | 署名、本文、そして文字の正確さを重視する方のために、私は、私の名
前、私の身体、そして私の署名というものを賭け、むしろ切り刻んで、ヘーゲルという名の者のものを一列に、ジェネという名の者のものを別の列に、一筆で書
き記す。なぜこの二人なのか、その理由はおのずとわかるだろう。そのものは、 thus,
立ち上がり、詳細を現し、二つの回転に従って分離し、絶え間ない回転の加速によって加速していく。二重の孤独の中で、巨人は無限の合図、例えば目配せを交
わし、互いに競うように二重になり、互いに浸透し、くっつき、離れ、互いに通り抜け、互いの間を通り抜ける。各柱は、死者の分身、その勃起の代用として名
付けられた「コロッソス」(colossos)を表している。何よりもまず、一つ以上の存在だ。 |
| L'écriture colossale déjoue tout autrement les calculs . du deuil. Elle surprend et dérésonne l'économie àe la mort dans tous ses ret(;!..ntisse. ments. Glas en décomposition, (son ou sa) double bande, bande contre bande, c'est d'abord l'analyse du niot glas dans les virtualités retorses et retranchées de son « sens » (portées, volées de toutes les cloches, la sépulture, la pompe funèbre, le legs; le testament, le contrat, la signature, te nom propre, le prénom, le surnom, la classification et la lutte des classes, le travail du deuil dans les rapports de production, le fétichisme, le travestissement, la toilette du mort, l'incorporation, l'introjection du cadavre, l'idéalisation, la sublimation, la relève, le rejet, le reste, etc.) et de son « signifiant » (vol et déportation de toutes les formes sonores et graphiques, musicales et rythmiques, chorégraphie de Glas dans ses lettres et fécondations polyglottiques. Mais cette opposition (Sé/Sa), comme toutes les oppositions du reste, la sexuelle en particulier, par chance régulière se compromet, chaque terme en deux divisé s'agglutinant à l'autre. Un effet de gl (colle, glu, crachat, sperme, chrême, onguent, etc.} forme le conglomérat sans identité de ce cérémonial. Il rejoue la mimesis et l'arbitraire de la signature dans un accouplement déchaîné (toc/seing/lait), ivre comme un sonneur à sa corde pendu. | 巨大な文字は、悲嘆の計算をまったく異なる方法で覆す。それは、死の経
済をそのすべての反復において驚かせ、理屈を覆す。腐敗するガラス、その二重の帯、帯対帯——これはまず、その「意味」の複雑で隠れた可能性の中で、ニ
オット・グラス(niot glas)の分析だ(鐘の鳴り響き、盗まれた鐘、埋葬、葬送、遺言;
遺言、契約、署名、固有名詞、名前、あだ名、分類と階級闘争、生産関係における悲嘆の作業、フェティシズム、変装、死者の装束、死体の取り込み、内面化、
理想化、昇華、交代、拒絶、残骸、
など)とその「意味内容」(音や文字、音楽やリズムのあらゆる形態の盗用と転用、グラスが手紙で示した舞踏、多言語の交配など)。しかし、この対立
(Sé/Sa)は、他のすべての対立、特に性的な対立と同様に、幸運なことに規則的に妥協し、それぞれの用語は二つに分かれて互いに結合する。「gl」
(接着剤、粘液、唾液、精液、聖油、軟膏など)の効果は、この儀式的な行為の無個性な集合体を形成する。それは、署名における模倣と恣意性を、暴走した結
合(toc/seing/lait)の中で再現し、吊るされた鐘を鳴らす者처럼酔っ払ったように鳴り響く。 |
| Que reste-t-il du savoir absolu ? de l'histoire, de la philosophie, de
l'économie politique, de la psychanalyse, de la sémiotique, de la
linguistique,
de la poétique ? du travail, de la langue, de la sexualité, de la
famille, de la religion, de l'Etat, etc. ? Que reste-t-il, à détailler,
du
reste ? Pourquoi ces questions en forme de colosses et de fleurs
phalliques
? Pourquoi exulter. dans la thanatopraxie ? De quoi jouir à célébrer,
moi, ici, maintenant, à telle heure, le baptême ou la circoncision,
le mariage ou la mort, du père et de la mère, celui de Hegel, celle de
Genet ? Reste à savoir .....:.c.e.. . qu'on n'a pu penser : le détaillé
d'un
coup. |
絶対的な知識とは何なのか?歴史、哲学、政治経済学、精神分析学、記号
論、言語学、詩学、労働、言語、性、家族、宗教、国家など、これらの分野において何が残っているのか?残りの部分について、具体的に何が残っているのか?
なぜこれらの質問は、巨像や男性器を模した花の形をしているのか?なぜ死体解剖で歓喜するのか?なぜ、私たちが、今、ここで、この時間に、ヘーゲルの父や
ジェネットの父の洗礼や割礼、結婚や死を祝うことに喜びを見出すのか?残された疑問は……:.c.e.. .
考えられなかったこと:一挙に詳細を明らかにすること。 |
| Collection « Digraphe », dirigée par Jean Ristat 1 vol. 25 X 25, 296 pages, 62 F ÉDITIONS GALILÉE 9, rue Linné, 75005 Paris J.D. |
●ジュディス・バトラー『アンティゴネーの主張』竹村和子訳、 青土社, 2002年
1)アンティゴネーの主張 Antigone's
Claim
2)書かれない法、逸脱する伝達
Unwritten Laws, Aberrant Transmissions
3)乱行的服従 Promiscuous Obedience
●バトラーにとってのアンティゴネー Butler on Antigone
「……アンティゴネーとは誰なのか、……。彼女は人
間でないが、人間の言葉で語る。行動を禁じられていながらも行動し、彼女の行動は既存の規範の単純な同化ではない。しかも行動する権利をもたないものとし
て行動することによって、人間の前提条件である親族関係の語彙を混乱させ、このような前提条件が本当はどんなものであるべきかという問題を、私たちにそれ
となく提示している。……。彼女にけっして属することはない語彙に彼女が従事するかぎり、彼女は政治的規範を語る言葉のなかで、ある種の交差対句として機
能する」(バトラー 2002:158-159)。
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆