エドワード・サイード『オリエンタリズム』ノート
On Edward Said's Orientalism
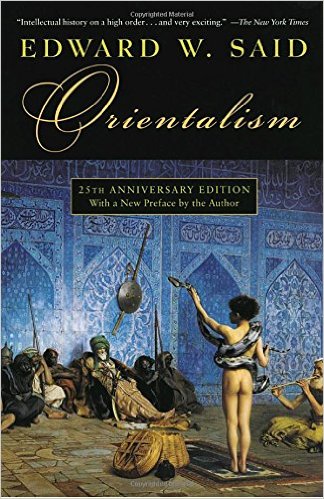

The Eastern world depicted in The Snake Charmer (1880), by Jean-Léon
Gérôme, illustrates the sensuous beauty and cultural mystery of the
fiction that is "the exotic Orient"
エドワード・サイード『オリエンタリズム』ノート
On Edward Said's Orientalism
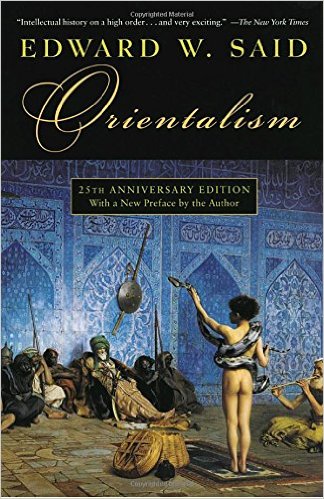

The Eastern world depicted in The Snake Charmer (1880), by Jean-Léon
Gérôme, illustrates the sensuous beauty and cultural mystery of the
fiction that is "the exotic Orient"
解説:池田光穂
オ リエンタリズムには、2つの意味があります。ひとつは、一般名詞あるいは芸術形式としての「オリエンタリズム」あるいは東洋趣味と呼ばれるもの。もうひと つは、エドワード・サイードの著作『オリエンタリズム』(1978)[=このページの課題]であり、その著作では、知識と権力アンサンブルとしての「東洋を見る眼」あるいはイデ オロギー的レンズとして、西洋が東洋を見る「知の形式」としてのそれ(=「オリエンタリズム」)があります。
もちろん、これまでの「オリエンタリズム」という言葉には、芸術の様式や(西洋世界にとっての) エキゾチックな文化表象を指し示す一般的な用語法があるが、人文社会学者が頻繁に言う批判的概念としてのオリエンタリズムは、次のような特徴があることに 注意しなければならない。
1.オリエンタリズムの反対は、オクシデンタリ ズムではないこと(つまり過度の認識論的相対化をしないこと)
オリエント(東方)の反対は、西洋(オクシデント)なので、これはお互いに、東西の文化から みた、政治的中立な立場をとった他者表象であると思ってはならない。オリエンタリズムの独自性とは、その逆がなりたたないこと。言い換えれば、他者を表象 する側と、表象される側の権力的な不均衡関係に由来する言葉である(→2.を参照)(→「「寛容であること」と相対主義の関係」)。
2.オリエントを表象する認識的作用は、権力と 無関係ではないこと.を忘れないように
この著書におけるサイードの批判的視点の源泉に、フーコー的な意味での、権力と知識の不可分 な実態あるいは相互補完関係というものがある。何かを見る(=分析する)、表象する、それらの表象について考えるという一連の知的作業は、権力の真空状態 の中で生まれるものではなく、我々の社会関係と同様、権力的なプロセスと深い関係にある、ということがポイントである。何かを表象する〈主体〉がもつ力 は、表象される〈主体〉の構築にも関連してくることが、これで理解されるだろう。
2.1 知と権力(M・フーコー)で表現される、言説と権力の結びつきについてどのように批判するのか?(西洋の学問自体が「知と権力」が結びついたものであれば、いかに、西洋学問の枠組みのなかで、その批判的「知」が権力から自由になることができるのか?)
2.2 この方法論/認識論は、西洋の学問伝統全体に直結することを再認識させるものである(→「知識の脱植民地化」「脱植民地化の方法論」)。
このページは長くorientalism.html のファイル名でしたが、今回
Saids_orientalism.html に改名しました。
E・サイード(1935-2003)『オリエンタリズム』(1978)ノート 【書誌】
| 第1章 オリエンタリズムの領域 第2章 オリエンタリズムの構成と再構成 第3章 今日のオリエンタリズム オリエンタリズム再考 |
|
| 第1章 オリエンタリズムの領域 東洋人を知る 心象地理とその諸表象—オリエントのオリエント化 プロジェクト 危機 |
|
| 第2章 オリエンタリズムの構成と再構成 再設定された境界線・再定義された問題・世俗化された宗教 シルヴェストル・ド・サシとエルネスト・ルナン—合 理主義的人類学と文献学実験室 オリエント在住とオリエントに関する学識—語彙記述と想像力とが必要とするもの 巡礼者と巡礼行—イギリス人とフランス 人 |
|
|
第3章 今日のオリエンタリズム 潜在的オリエンタリズムと顕在的オリエンタリズム 様式、専門知識、ヴィジョン—オリエンタリズムの世俗性 現代英仏オリエンタリズムの最盛期 最新の局面 |
|
| オリエンタリズム再考 |
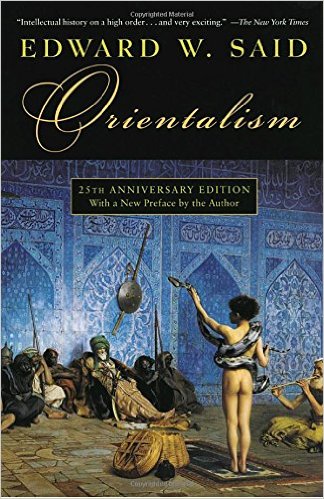 Orientalism
is a
1978 book by Edward W. Said, in which the author establishes the
eponymous term "Orientalism" as a critical concept to describe the
West's commonly contemptuous depiction and portrayal of The East, i.e.
the Orient. Societies and peoples of the Orient are those who inhabit
the places of Asia, North Africa, and the Middle East. Said argues that
Orientalism, in the sense of the Western scholarship about the Eastern
World, is inextricably tied to the imperialist societies who produced
it, which makes much Orientalist work inherently political and servile
to power.[1] Orientalism
is a
1978 book by Edward W. Said, in which the author establishes the
eponymous term "Orientalism" as a critical concept to describe the
West's commonly contemptuous depiction and portrayal of The East, i.e.
the Orient. Societies and peoples of the Orient are those who inhabit
the places of Asia, North Africa, and the Middle East. Said argues that
Orientalism, in the sense of the Western scholarship about the Eastern
World, is inextricably tied to the imperialist societies who produced
it, which makes much Orientalist work inherently political and servile
to power.[1]According to Said, in the Middle East, the social, economic, and cultural practices of the ruling Arab elites indicate they are imperial satraps who have internalized a romanticized version of Arab Culture created by French, British and later, American, Orientalists. Examples used in the book include critical analyses of the colonial literature of Joseph Conrad,[verification needed] which conflates a people, a time, and a place into one narrative of an incident and adventure in an exotic land.[2] Through the critical application of post-structuralism in its scholarship, Orientalism influenced the development of literary theory, cultural criticism, and the field of Middle Eastern studies, especially with regard to how academics practice their intellectual inquiries when examining, describing, and explaining the Middle East.[3] Moreover, the scope of Said's scholarship established Orientalism as a foundational text in the field of postcolonial studies, by denoting and examining the connotations of Orientalism, and the history of a given country's post-colonial period.[4] As a public intellectual, Edward Said debated historians and scholars of area studies, notably, historian Bernard Lewis, who described the thesis of Orientalism as "anti-Western."[5] For subsequent editions of Orientalism, Said wrote an Afterword (1995)[6]: 329–52 and a Preface (2003)[6]: xi–xxiii addressing discussions of the book as cultural criticism. |
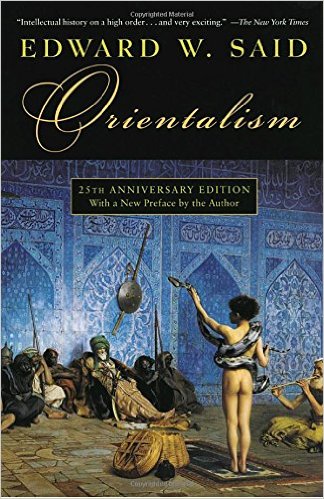 オリエンタリズムとは、エドワー
ド・W・サイードが1978年に著した本で、著者は西洋が一般的に蔑視している東洋、すなわちオリエントに対する描写や描写を表す批判的概念として「オリ
エンタリズム」という言葉を確立した。オリエントとは、アジア、北アフリカ、中東に住む人々のことである。サイードは、東洋世界に関する西洋の学問という
意味でのオリエンタリズムは、それを生み出した帝国主義社会と表裏一体であり、そのため多くのオリエンタリズム作品は本質的に政治的であり、権力に隷属し
ていると主張する[1]。 オリエンタリズムとは、エドワー
ド・W・サイードが1978年に著した本で、著者は西洋が一般的に蔑視している東洋、すなわちオリエントに対する描写や描写を表す批判的概念として「オリ
エンタリズム」という言葉を確立した。オリエントとは、アジア、北アフリカ、中東に住む人々のことである。サイードは、東洋世界に関する西洋の学問という
意味でのオリエンタリズムは、それを生み出した帝国主義社会と表裏一体であり、そのため多くのオリエンタリズム作品は本質的に政治的であり、権力に隷属し
ていると主張する[1]。サイードによれば、中東では、支配的なアラブ人エリートの社会的、経済的、文化的実践は、彼らがフランス、イギリス、そして後にはアメリカのオリエンタリ ストによって作られたアラブ文化のロマンチックなバージョンを内包する帝国飽食主義者(サトラップ)であることを示すという。本書で使用されている例とし ては、ジョセフ・コンラッドの植民地文学の批判的分析があり[要検証]、コンラッドは民族、時間、場所を異国での事件と冒険の物語に混同している[2]。 また、サイードの研究の範囲は、オリエンタリズムの意味合いと特定の国のポストコロニアル時代の歴史を指摘し、検討することによって、ポストコロニアル研 究の分野で基礎となるテキストとしてオリエンタリズムを確立した[4]。 公共知識人として、エドワード・サイードは歴史家や地域研究の学者と議論し、特に歴史家のバーナード・ルイスは、オリエンタリズムの論文を「反西洋」と表 現した[5]。 329-52と序文(2003)[6]: xi-xiiiを書き、文化批評としての本書の議論に言及している。 |
| "Orientalism" The term orientalism denotes the exaggeration of difference, the presumption of Western superiority, and the application of clichéd analytical models for perceiving the "Oriental world". This intellectual tradition is the background for Said's presentation of Orientalism as a European viewpoint reflecting a contrived Manichean duality. As such, Orientalism is the pivotal source of the inaccurate cultural representations that form the foundations of Western thought and perception of the Eastern world, specifically in relation to the Middle East region. Said distinguishes between at least three separate but interrelated meanings of the term:[6]: 2–3 1. an academic tradition or field; 2. a worldview, representation, and "style of thought based upon an ontological and epistemological distinction made between 'the Orient' and (most of the time) 'the Occident';" and 3. as a powerful political instrument of domination. In other words, Said had in mind the "Occidental" (or Western) views of eastern cultures that mirrored the prejudices and ideologies that the colonial experience of Western individuals was shaded by Said's work drew attention to the obsession of Western writers with women and their role in the preservation (or destruction) or so-called cultural mores, viewing them as either "pristine" (redeemed) or "contaminated" (fallen).[7] According to an article published by The New Criterion, the principal characteristic of Orientalism is a "subtle and persistent Eurocentric prejudice against Arab-Islamic peoples and their culture,"[8] which derives from Western images of what is Oriental (i.e., cultural representations) that reduce the Orient to the fictional essences of "Oriental peoples" and "the places of the Orient;" such representations dominate the discourse of Western peoples with and about non-Western peoples.[citation needed] These cultural representations usually depict the ‘Orient’ as primitive, irrational, violent, despotic, fanatic, and essentially inferior to the westerner or native informant, and hence, ‘enlightenment’ can only occur when “traditional” and “reactionary” values are replaced by “contemporary” and “progressive” ideas that are either western or western-influenced.[9] In practice, the imperial and colonial enterprises of the West are facilitated by collaborating régimes of Europeanized Arab élites who have internalized the fictional, and romanticized representations of Arabic culture. The idea of the "Orient" was conceptualized by French and English Orientalists during the 18th century, and was eventually adopted in the 20th century by American Orientalists.[10][11] As such, Orientalist stereotypes of the cultures of the Eastern world have served, and continue to serve, as implicit justifications for the colonial ambitions and the imperial endeavors of the U.S. and the European powers. In that vein, about contemporary Orientalist stereotypes of Arabs and Muslims, Said states: So far as the United States seems to be concerned, it is only a slight overstatement to say that Moslems and Arabs are essentially seen as either oil suppliers or potential terrorists. Very little of the detail, the human density, the passion of Arab–Moslem life has entered the awareness of even those people whose profession it is to report the Arab world. What we have, instead, is a series of crude, essentialized caricatures of the Islamic world, presented in such a way as to make that world vulnerable to military aggression.[12] Moving from the assertion that ‘pure knowledge’ is simply not possible (as all forms of knowledge are inevitably influenced by ideological standpoints), Said sought to explain the connection between ideology and literature. He argued that “Orientalism is not a mere political subject or field that is reflected passively by culture, scholarship, or institutions,” but rather “a distribution of geopolitical awareness into aesthetic, scholarly, economic, sociological, historical, and philological texts.”[13] European literature for Said carried, actualised, and propelled Orientalist notions forward and constantly reinforced them. Put differently, literature produced by Europeans made possible the domination of the people of the ‘East’ because of the Orientalist discourse embedded within these texts. Literature here is understood as a kind of carrier and distributor of ideology. He underscored again and again the importance of understanding the intimate relationship between knowledge and power, declaring: "If the knowledge of Orientalism has any meaning, it is in being a reminder of the seductive degradation of knowledge, of any knowledge, anywhere, at any time.”[14] |
"オリエンタリズム" オリエンタリズムという言葉は、差異の誇張、西洋の優位性の推定、そして「東洋の世界」を認識するための陳腐な分析モデルの適用を意味する。この知的伝統 は、サイードがオリエンタリズムを、仕組まれたマニキアの二元性を反映するヨーロッパの視点として提示する背景となっている。 このように、オリエンタリズムは、東洋世界、特に中東地域に関する西洋の思考と認識の基礎を形成する不正確な文化的表象の極めて重要な源泉である。 サイードは、この用語の少なくとも3つの別々の、しかし相互に関連する意味を区別している[6]:2-3 1. 学術的な伝統や分野 2. 世界観、表現、および「『東洋』と(ほとんどの場合)『西洋』との間の存在論的および認識論的な区別に基づく思考のスタイル」、および 3. 支配の強力な政治的道具として。 言い換えれば、サイードは東洋文化に対する「西洋的」(あるいは西洋人)な見方を念頭に置いており、それは西洋人の植民地経験が影を落としていた偏見やイ デオロギーを反映していた。サイードの作品は、西洋の作家が女性やいわゆる文化道徳の保存(あるいは破壊)における女性の役割に執着し、女性を「純粋」 (救済)あるいは「汚染」(転落)として見ていることに注意を促したのである[7]。 ニュー・クリテリオンに掲載された記事によれば、オリエンタリズムの主要な特徴は「アラブ・イスラムの人々とその文化に対する微妙で根強いヨーロッパ中心 主義の偏見」[8]であり、これは東洋を「東洋人」と「東洋の場所」の架空の本質に還元する西洋の「何が東洋的であるか」のイメージ(すなわち文化的表 象)から派生しており、そうした表象が西洋人の非西洋人に対する、あるいは西洋人についての言説を支配する[引用符][要訳]...。 これらの文化的表象は通常「オリエント」を原始的、非理性的、暴力的、専制的、狂信的であり、西洋人や先住民の情報提供者に対して本質的に劣るものとして 描いており、それゆえ「啓発」は「伝統的」で「反動的」な価値が西洋または西洋の影響を受けている「現代的」で「進歩的」な考えによって置き換えられると きにだけ起こることが可能であるとしている[9]。 実際には、西洋の帝国と植民地の事業は、アラブ文化の虚構とロマンチックな表現を内面化したヨーロッパ化したアラブのエリートの協力体制によって促進され ている。東洋」という概念は18世紀にフランスとイギリスのオリエンタリストによって概念化され、20世紀にはアメリカのオリエンタリストによって採用さ れた[10][11]。このように、東洋世界の文化に対するオリエンタリストのステレオタイプは、アメリカとヨーロッパ列強の植民地的野心と帝国的努力に 対する暗黙の正当化として機能しており、今もなお機能しつづけている。その流れで、現代のアラブ人やイスラム教徒に対するオリエンタリズムのステレオタイ プについて、サイードは次のように述べている。 アメリカに関する限り、イスラム教徒とアラブ人は本質的に石油供給者か潜在的なテロリストのどちらかと見られていると言っても、それは少し言い過ぎに過ぎ ない。アラブ・モスリムの生活の細部、人間的な密度、情熱は、アラブ世界を報道することを職業とする人々でさえ、ほとんど意識に入っていない。その代わり に私たちが手にしているのは、イスラム世界の粗雑で本質化された一連の戯画であり、その世界を軍事的侵略に対して脆弱にするような方法で提示されている [12]。 純粋な知識」は単純に不可能であるという主張から(あらゆる形式の知識は必然的にイデオロギー的立場から影響を受けるため)、サイードはイデオロギーと文 学の間の関係を説明しようとした。彼は「オリエンタリズムは文化、学問、制度によって受動的に反映される単なる政治的主題や分野ではなく」、むしろ「美 学、学問、経済、社会学、歴史、言語学のテキストへの地政学的意識の分配」だと主張した[13] サイードにとってヨーロッパ文学はオリエンタリズムの概念を運び、実現し、推進し、絶えずそれらを強化したものであった。別の言い方をすれば、ヨーロッパ 人によって生み出された文学は、これらのテクストの中に埋め込まれたオリエンタリズムの言説のために、「東洋」の人々の支配を可能にしたのである。ここで いう文学とは、一種のイデオロギーの運搬人、流通人であると理解される。 彼は、知識と権力の密接な関係を理解することの重要性を何度も強調し、こう宣言している。「もしオリエンタリズムの知識が何らかの意味を持つとすれば、そ れは知識の、どんな知識であれ、いつでもどこでも、魅惑的な劣化を思い起こさせることである」[14]。 |
| Thesis of representation Orientalism (1978) proposes that much of the Western study of Islamic civilization was an exercise in political intellectualism; a psychological exercise in the self-affirmation of "European identity"; not an objective exercise of intellectual enquiry and the academic study of Eastern cultures. Therefore, Orientalism was a method of practical and cultural discrimination that was applied to non-European societies and peoples in order to establish European imperial domination. In justification of empire, the Orientalist claims to know more—essential and definitive knowledge—about the Orient than do the Orientals.[6]: 2–3 One of the main themes of Said's critique is that the representations of the Orient as "different" from the West are based entirely on accounts taken from textual sources, many of them produced by Westerners. Modern on-the-ground reality is heavily discounted such that the Orient is implicitly disregarded as incapable or not credible to describe itself.[15] Western writings about the Orient, the perceptions of the East presented in Orientalism, cannot be taken at face value, because they are cultural representations based upon fictional, Western images of the Orient. The history of European colonial rule and political domination of Eastern civilizations, distorts the intellectual objectivity of even the most knowledgeable, well-meaning, and culturally sympathetic Western Orientalist; thus did the term "Orientalism" become a pejorative word regarding non–Western peoples and cultures:[16] I doubt if it is controversial, for example, to say that an Englishman in India, or Egypt, in the later nineteenth century, took an interest in those countries, which was never far from their status, in his mind, as British colonies. To say this may seem quite different from saying that all academic knowledge about India and Egypt is somehow tinged and impressed with, violated by, the gross political fact—and yet that is what I am saying in this study of Orientalism.[6]: 11 The notion of cultural representations as a means for domination and control would remain a central feature of Said's critical approach proposed in Orientalism. Towards the end of his life for instance, Said argued that while representations are essential for the function of human life and societies—as essential as language itself—what must cease are representations that are authoritatively repressive, because they do not provide any real possibilities for those being represented to intervene in this process.[13] The alternative to an exclusionary representational system for Said would be one that is “participatory and collaborative, non-coercive, rather than imposed,” yet he recognised the extreme difficulty involved in bringing about such an alternative.[13] Difficult because advances in the “electronic transfer of images” is increasing media concentration in the hands of powerful, transnational conglomerates.[13] This concentration is of such great magnitude that ‘dependent societies’ situated outside of the “central metropolitan zones” are greatly reliant upon these systems of representation for information about themselves - otherwise known as self-knowledge.[13] For Said, this process of gaining self-knowledge by peripheral societies is insidious, because the system upon which they rely is presented as natural and real, such that it becomes practically unassailable.[13 |
表象のテーゼ オリエンタリズム』(1978年)は、西洋のイスラム文明研究の多くは、政治的知性の行使であり、「ヨーロッパ人のアイデンティティ」を自己確認するため の心理的運動であって、知的探求や東洋文化の学術的研究という客観的運動ではなかったと提唱している。したがって、オリエンタリズムとは、ヨーロッパ帝国 による支配を確立するために、非ヨーロッパの社会と民族に適用された実践的・文化的差別の方法であったのである。帝国を正当化するために、オリエンタリス トは東洋人よりも東洋について本質的かつ決定的な知識を知っていると主張する[6]: 2-3。 サイードの批判の主要なテーマの一つは、西洋とは「異なる」東洋の表現が、その多くが西洋人によって作られたテキスト資料から取られた説明に完全に基づい ていることである。現代の現場の現実は大きく割り引かれており、そのため東洋は暗黙のうちに自分自身を説明することができない、あるいは信用できないもの として無視されている[15]。 東洋についての西洋の著作、オリエンタリズムで提示された東洋の認識は額面通りには受け取れない、なぜならそれらは東洋の架空の西洋のイメージに基づいた 文化表現であるからである。ヨーロッパによる東洋文明の植民地支配と政治的支配の歴史は、最も知識があり、善意で、文化的に同情的な西洋のオリエンタリス トでさえ、知的客観性を歪める。こうして「オリエンタリズム」という言葉は、西洋以外の民族と文化に関する蔑称となった[16]。 例えば、19世紀後半にインドやエジプトにいたイギリス人が、それらの 国々に興味を持ったと言うことは、彼の中ではイギリスの植民地としての地位から決し て離れてはいなかったと言うことは、議論の余地があるのかどうか疑問である。このように言うことは、インドやエジプトに関するすべての学問的知識が、何ら かの形でこの重大な政治的事実を帯びており、その影響を受けていると言うこととは全く異なるように思われるかもしれない。[6]: 11 支配と管理のための手段としての文化的表象の概念は、『オリエンタリズム』で提案されたサイードの批判的アプローチの中心的な特徴であり続けることにな る。例えば、サイードは晩年になって、表象は人間の生活や社会の機能にとって不可欠であるが、それは言語そのものと同様に不可欠であり、権威的に抑圧する 表象は、表象される人々がこのプロセスに介入するための現実の可能性を提供しないので、やめなければならないと主張した[13]。 サイードにとっての排他的な表象システムの代替案は、「参加と協力、非強制的、むしろ課されたもの」であるが、彼はそのような代替案をもたらすことに関わ る極めて困難さを認識していた[13]。 難しいのは「画像の電子転送」の進歩によって、強力で国境を越えた複合企業の手中にメディアの集中が進んでいるためである[13]。 [サイードにとって、周辺社会が自己認識を獲得するこのプロセスは陰湿なものであり、それは彼らが依存しているシステムが自然でリアルなものとして提示さ れ、それが事実上難攻不落になるためである[13]。 |
| Geopolitics and cultural
hierarchy Said said that the Western world sought to dominate the Eastern world for more than 2,000 years, since Classical antiquity (8th c. BC – AD 6th c.), the time of the play The Persians (472 BC), by Aeschylus, which celebrates a Greek victory (Battle of Salamis, 480 BC) against the Persians in the course of the Persian Wars (499–449 BC)—imperial conflict between the Greek West and the Persian East.[6]: 1–2 [17] Europe's long, military domination of Asia (empire and hegemony) made unreliable most Western texts about the Eastern world, because of the implicit cultural bias that permeates most Orientalism, which was not recognized by most Western scholars. In the course of empire, after the physical-and-political conquest, there followed the intellectual conquest of a people, whereby Western scholars appropriated for themselves (as European intellectual property) the interpretation and translation of Oriental languages, and the critical study of the cultures and histories of the Oriental world.[18] In that way, by using Orientalism as the intellectual norm for cultural judgement, Europeans wrote the history of Asia, and invented the "exotic East" and the "inscrutable Orient", which are cultural representations of peoples and things considered inferior to the peoples and things of the West.[6]: 38–41 The contemporary, historical impact of Orientalism was in explaining the how? and the why? of imperial impotence; in the 1970s, to journalists, academics, and Orientalists, the Yom Kippur war (6–25 October 1973) and the OPEC petroleum embargo (October 1973 – March 1974) were recent modern history. The Western world had been surprised, by the pro-active and decisive actions of non-Western peoples, whom the ideology of Orientalism had defined as essentially weak societies and impotent countries. The geopolitical reality of their actions, of military and economic warfare, voided the fictional nature of Orientalist representations, attitudes, and opinions about the non-Western Other self.[6]: 329–54 |
地政学と文化的ヒエラルキー サイードによれば、西洋世界は古典古代(紀元前8世紀〜紀元6世紀)以来2000年以上にわたって東洋世界を支配しようとした。それはペルシャ戦争(紀元 前499〜449年)-ギリシャ西方とペルシャ東方の帝国紛争の過程で、ペルシャに対するギリシャの勝利(サラミスの戦い、紀元前480)を謳ったアイス キュロスの『ペルシャ人』劇の時代である[6](前 472)。 1-2[17]ヨーロッパのアジアに対する長期にわたる軍事的支配(帝国と覇権)は、ほとんどのオリエンタリズムに浸透している暗黙の文化的 偏向のために、東洋世界に関する西洋のテキストのほとんどが信頼できないものであり、ほとんどの西洋学者によって認識されることはなかった。 帝国の過程において、物理的・政治的な征服の後に、ある民族の知的征服が行われ、 それによって西洋の学者たちは東洋の言語の解釈と翻訳、そして東洋世界の文化と歴史に 関する批判的研究を自らのために(ヨーロッパの知的財産として)占有するようになった [18] 。 [18] そのようにして、オリエンタリズムを文化判断の知的規範とすることによって、ヨーロッパ人はアジアの歴史を書き、西洋の民族や物事よりも劣ると考えられる 民族や物事の文化表現である「異国の東」「不可解な東洋」を発明した[6]: 38-41 1970年代、ジャーナリスト、学者、オリエンタリストにとって、ヨム・キプール戦争(1973年10月6日〜25日)とOPEC石油禁輸措置(1973 年10月〜1974年3月)は最近の現代史であった。オリエンタリズムのイデオロギーが、本質的に弱い社会、無力な国と定義していた非西洋人たちの積極的 で果断な行動に、西洋世界は驚いたのであった。彼らの行動、軍事的・経済的戦争という地政学的現実は、非西洋の他者である自己についてのオリエンタリズム の表象、態度、意見の虚構性を無効にしたのである[6]。 329-54 |
| Influence The greatest intellectual impact of Orientalism (1978) was upon the fields of literary theory, cultural studies, and human geography, by way of which originated the field of Post-colonial studies. Edward Said's method of post-structuralist analysis derived from the analytic techniques of Jacques Derrida and Michel Foucault; and the perspectives to Orientalism presented by Abdul Latif Tibawi,[19] Anouar Abdel-Malek,[20] Maxime Rodinson,[21] and Richard William Southern.[22] |
影響力 オリエンタリズム』(1978年)の知的影響は、文学、文化研究、人文地理学の分野に及び、そこからポストコロニアル研究という分野が生まれた。エドワー ド・サイードのポスト構造主義的な分析方法は、ジャック・デリダとミシェル・フーコーの分析技術に由来し、アブドゥル・ラティフ・ティバウィ、アヌアー ル・アブデル・マレク[19]、マキシム・ロディンソン[21]、リチャード・ウィリアム・サザンによって示されたオリエンタリズムへの視点は、このよう なものであった[22]。 |
| Post-colonial culture studies As a work of cultural criticism, Orientalism (1978) is a foundational document in the field of postcolonialism, providing a framework and method of analysis to answer the how? and the why? of the cultural representations of "Orientals," "The Orient," and "The Eastern world," as presented in the mass-media of the Western world.[23] Postcolonial theory studies the power and continued dominance of Western ways of intellectual enquiry, as well as the production of knowledge in the academic, intellectual, and cultural spheres of decolonised countries. Said's survey concentrated upon the British and the French varieties of Orientalism that supported the British Empire and the French Empire as commercial enterprises constructed from colonialism, and gave perfunctory coverage, discussion, and analyses of German Orientalist scholarship.[24] Such disproportional investigation provoked criticism from opponents and embarrassment for supporters of Said, who, in "Orientalism Reconsidered" (1985), said that no single opponent provided a rationale, by which limited coverage of German Orientalism limits either the scholarly value or the practical application of Orientalism as a cultural study.[25] In the Afterword to the 1995 edition of Orientalism, Said presented follow-up refutations of the criticisms that the Orientalist and historian Bernard Lewis made against the book's first edition (1978).[6]: 329–54 |
ポストコロニアル文化研究 文化批評の作品として、『オリエンタリズム』(1978年)はポストコロニアリズムの分野における基礎的な文書であり、西洋世界のマスメディアで提示され る「東洋人」、「東洋」、「東洋世界」の文化表象の方法と理由に答える分析の枠組み及び方法を提供している[23]。 ポストコロニアル理論は、脱植民地化された国々の学術的、知的、文化的領域における知識の生産と同様に、西洋の知的探求の方法の力と継続的な支配を研究し ている。サイードの調査は、植民地主義から構築された商業企業としての大英帝国とフランス帝国を支えたイギリスとフランスのオリエンタリズムの多様性に集 中し、ドイツのオリエンタリズムの学問についてはおざなりに報道、議論、分析をしていた[24]。 このような不均衡な調査は反対派からの批判を招き、サイードの支持者は困惑した。サイードは『Orientalism Reconsidered』(1985年)の中で、ドイツのオリエンタリズムを限定的に取り上げることが文化研究としてのオリエンタリズムの学術的価値や 実用的応用を限定する根拠を提示した反対派は一人もいないと述べている[25]。 [25] サイードは1995年版の『オリエンタリズム』のあとがきで、東洋学者で歴史家のバーナード・ルイスが本書の初版(1978年)に対して行った批判に対す るフォローアップの反論を紹介している[6]。 329-54 |
| Literary criticism In the fields of literary criticism and of cultural studies, the notable Indian scholars of postcolonialism were Gayatri Chakravorty Spivak (In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, 1987), whose essay "Can the Subaltern Speak?" (1988) also became a foundational text of postcolonial culture studies;[26] Homi K. Bhabha (Nation and Narration, 1990);[27] Ronald Inden (Imagining India, 1990);[28] Gyan Prakash ("Writing Post–Orientalist Histories of the Third World: Perspectives from Indian Historiography", 1990);[29] Nicholas Dirks (Castes of Mind, 2001);[30] and Hamid Dabashi (Iran: A People Interrupted, 2007). In White Mythologies: Writing History and the West (1990), Robert J. C. Young reports post-colonial explanations of the "How?" and the "Why?" of the nature of the post-colonial world, the peoples, and their discontents;[31][32] which verify the efficacy of the critical method applied in Orientalism (1978), especially in the field of Middle Eastern studies.[3] In the late 1970s, the survey range of Orientalism (1978) did not include the genre of Orientalist painting or any other visual arts, despite the book-cover featuring a detail-image of The Snake Charmer (1880), a popular, 19th-century Orientalist painting—to which the writer Linda Nochlin applied Said's method of critical analysis "with uneven results."[33] In the field of epistemological studies, Orientalism is an extended application of methods of critical analysis developed by the philosopher Michel Foucault.[34] Anthropologist Talal Asad said that the book Orientalism is: not only a catalogue of Western prejudices about and misrepresentations of Arabs and Muslims" ... [but an investigation and analysis of the] authoritative structure of Orientalist discourse—the closed, self-evident, self-confirming character of that distinctive discourse, which is reproduced, again and again, through scholarly texts, travelogues, literary works of imagination, and the obiter dicta of public men-of-affairs.[35] Historian Gyan Prakash said that Orientalism describes how "the hallowed image of the Orientalist, as an austere figure, unconcerned with the world and immersed in the mystery of foreign scripts and languages, has acquired a dark hue as the murky business of ruling other peoples, now forms the essential and enabling background of his or her scholarship" about the Orient; without colonial imperialism, there would be no Orientalism.[36] |
文芸批評 文芸批評や文化研究の分野では、ポストコロニアリズムの著名なインドの学者として、ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク(In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, 1987)、その論文「サブアルタンは語ることができるか」(Can the Subaltern Speak? (1988) はポストコロニアル文化研究の基礎となるテキストとなった[26]; Homi K. Bhabha (Nation and Narration, 1990); [27] Ronald Inden (Imagining India, 1990); [28] Gyan Prakash ("Writing Post-Orientalist Histories of the Third World."): Perspectives from Indian Historiography", 1990);[29] Nicholas Dirks(Castes of Mind, 2001);[30] and Hamid Dabashi(Iran: A People Interrupted, 2007)。 白人の神話』(White Mythologies: Robert J. C. YoungはWriting History and the West (1990)において、ポストコロニアルな世界、民族、そして彼らの不満の本質の「どのように」と「なぜ」についてのポストコロニアルな説明を報告してお り、特に中東研究の分野においてOrientalism (1978) において適用した批判手法の有効性を検証している[31][32]。 1970年代後半、『オリエンタリズム』(1978年)の調査対象にはオリエンタリズム絵画やその他の視覚芸術のジャンルは含まれていなかったが、本の表 紙には19世紀に描かれた人気のあるオリエンタリズム絵画『蛇使い』(1880年)の詳細画像が掲載されており、作家リンダ・ノクリンがサイードの批判的 分析方法を「不均一な結果で適用している」[33]。 33] 認識論的研究の分野では、オリエンタリズムは哲学者ミシェル・フーコーによって開発された批判的分析の手法の拡張適用である[34] 人類学者タラル・アサドは、この書籍『オリエンタリズム』は…… アラブ人やイスラム教徒に対する西洋の偏見や誤った表現についてのカタログであるだけでなく」。しかし、オリエンタリズムの言説の権威的な構造、つまり閉 じた、自明な、自己確証的な特徴であり、それは学術的なテキスト、旅行記、想像力の文学作品、そして公人たちの傍論を通じて何度も何度も再生される [35]」と述べている[36]。 歴史家のギャン・プラカシュは、オリエンタリズムは「世界に無関心で外国文字と言語の謎に没頭している厳格な人物としてのオリエンタリストの神聖なイメー ジが、他の民族を支配するという泥臭いビジネスが、今や彼または彼女の東洋についての研究の本質的かつ可能な背景となって、暗い色を獲得した」ことを描写 していると述べており、植民地帝国主義なしでは、オリエンタリズムも存在しないであろうという[36]。 |
| Oriental Europe In Eastern Europe, Milica Bakić-Hayden developed the concept of Nesting Orientalisms (1992), based upon and derived from the work of the historian Larry Wolff (Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, 1994), and the ideas Said presents in Orientalism (1978).[37] Bulgarian historian Maria Todorova (Imagining the Balkans, 1997) presented her ethnologic concept of Nesting Balkanisms (Ethnologia Balkanica,1997), which is thematically extended and theoretically derived from Bakić-Hayden's Nesting Orientalisms.[38] Moreover, in "A Stereotype, Wrapped in a Cliché, Inside a Caricature: Russian Foreign Policy and Orientalism" (2010), James D. J. Brown says that Western stereotypes of Russia, Russianness, and things Russian are cultural representations derived from the literature of "Russian studies," which is a field of enquiry little afflicted with the misconceptions of Russia-as-the-Other, but does display the characteristics of Orientalism—the exaggeration of difference, the presumption of Western cultural superiority, and the application of cliché in analytical models. That overcoming such intellectual malaise requires that area scholars choose to break their "mind-forg'd manacles" and deeply reflect upon the basic cultural assumptions of their area-studies scholarship.[39] |
東欧 東 ヨーロッパにおいては、ミリカ・バキッチ=ヘイデンが、歴史家ラリー・ウォルフの仕事(Inventing Eastern Europe, 1994)に基づき、そこから派生した「入れ子型オリエンタリズム」(1992)という概念を構築した。またサイードが『オリエンタリズム』(1978 年)で提示している思想にも基づいている[37]。 ブルガリアの歴史家マリア・トドロヴァは(Imagining the Balkans, 1997)、バキッチ=ヘイデンの入れ子式オリエンタリズムから主題的に拡張され理論的に導かれた入れ子式バルカニズム(Ethnologia Balkanica,1997) という民族学の概念を提示した[38]。 さらに、「ステレオタイプ、クリシェに包まれ、カリカチュアの中にあるもの。James D. J. Brownは "Russian Foreign Policy and Orientalism" (2010)において、ロシア、ロシア人、ロシア的なものに対する西洋のステレオタイプは「ロシア研究」の文献から派生した文化表現であるとし、この分野 はロシアを他者とする誤解にはあまり悩まされていないが、差異の誇張、西洋文化の優位性の仮定、分析モデルへのクリシェの適用といったオリエンタリズムの 特徴を示しているとしている[38]。このような知的倦怠感を克服するためには、地域研究者が「心の枷」を外し、地域研究の学問の基本的な文化的前提を深 く省察することを選択する必要がある[39]。 |
| Criticism Despite the book's wide-ranging influence, some have taken issue with the arguments and assumptions of Orientalism. Critics include Albert Hourani (A History of the Arab Peoples, 1991), Robert Graham Irwin (For Lust of Knowing: The Orientalists and their Enemies, 2006), Nikki Keddie (An Islamic Response to Imperialism, 1968), and Bernard Lewis ("The Question of Orientalism", Islam and the West, 1993).[40][41][42] In a review of a book by Ibn Warraq, American classicist Bruce Thornton dismissed Orientalism as an "incoherent amalgam of dubious postmodern theory, sentimental Third Worldism, glaring historical errors, and Western guilt".[43] Likewise, in the preface paragraphs of a book-review article "Enough Said" (2007), about Dangerous Knowledge (2007), which is the American title for British-published For Lust of Knowing: The Orientalists and Their Enemies by Robert Irwin, Martin Kramer criticized what he said was the way Said turned the term "Orientalism" into a pejorative, saying "In a semantic sleight of hand, Said appropriated the term "Orientalism", as a label for the ideological prejudice he described, thereby, neatly implicating the scholars who called themselves Orientalists."[44] Nonetheless, the literary critic Paul De Man said that, as a literary critic, "Said took a step further than any other modern scholar of his time, something I dare not do. I remain in the safety of rhetorical analysis, where criticism is the second-best thing I do."[45] |
批判 本書が広範な影響を与えたにもかかわらず、オリエンタリズムの主張と前提を問題視する声もある。批評家としては、アルバート・ホーラーニー(A History of the Arab Peoples, 1991)、ロバート・グラハム・アーウィン(For Lust of Knowing: The Orientalists and their Enemies, 2006)、ニッキー・ケディー(An Islamic Response to Imperialism, 1968)、バーナード・ルイス(The Question of Orientalism, Islam and the West, 1993)などがいる[40][41][42]。 イブン・ワラクの本のレビューにおいて、アメリカの古典学者ブルース・ソーントンはオリエンタリズムを「怪しげなポストモダン理論、感傷的な第三世界主 義、明白な歴史的誤り、西洋の罪悪感の首尾一貫しないアマルガム」として退けている[43] 同様に書評記事「Enough Said」(2007)の前段でDangerous Knowledge(イギリス出版のFor Lust of Knotingに対するアメリカのタイトル、2007)について、その内容を述べている[45] 。マーティン・クレイマーはサイードが「オリエンタリズム」という言葉を蔑称に変えたと言うことを批判し、「意味論的な手品の中で、サイードは「オリエン タリズム」という言葉を彼が説明した思想的偏見のラベルとして流用し、それによって、オリエンタリストと自称する学者をきちんと暗示している」と述べてい る[44]。 それにもかかわらず、文芸批評家のポール・デマンは文芸批評家として「サイードは当時の他のどの近代学者よりも一歩を踏み出したが、それは私が敢えてやら ないことです」と述べている。私は批評が二番煎じである修辞学的分析の安全性にとどまっている」[45]。 |
| History Ernest Gellner, in his book review titled "The Mightier Pen? Edward Said and the Double Standards of Inside-out Colonialism: a review of Culture and Imperialism, by Edward Said" (1993), says that Said's contention of Western domination of the Eastern world for more than 2,000 years was unsupportable, because, until the late 17th century, the Ottoman Empire (1299–1923) was a realistic military, cultural, and religious threat to (Western) Europe.[46] In "Disraeli as an Orientalist: The Polemical Errors of Edward Said" (2005), Mark Proudman noted incorrect 19th-century history in Orientalism, that the geographic extent of the British Empire was not from Egypt to India in the 1880s, because the Ottoman Empire and the Persian Empire in that time intervened between those poles of empire.[47] Moreover, at the zenith of the imperial era, European colonial power in the Eastern world never was absolute, it was relative and much dependent upon local collaborators—princes, rajahs, and warlords—who nonetheless often subverted the imperial and hegemonic aims of the colonialist power.[48] In For Lust of Knowing: The Orientalists and Their Enemies (2006), Robert Irwin says that Said's concentrating the scope of Orientalism to the Middle East, especially Palestine and Egypt, was a mistake, because the Mandate of Palestine (1920–1948) and British Egypt (1882–1956) were only under direct European control for a short time, in the late 19th and early 20th centuries; thus they are poor examples for Said's theory of Western cultural imperialism. That Orientalism should have concentrated upon noteworthy examples of imperialism and cultural hegemony, such as the British colony of India (1858–1947) and Russian colonies in Asia (1721–1917), but he did not, because, as a public intellectual, Edward Said was more interested in making political points about the politics of the Middle East, in general, and of Palestine, in particular.[49] Moreover, that by unduly concentrating on British and French Orientalism, Said ignored the domination of 19th century Oriental studies by German and Hungarian academics and intellectuals, whose countries did not possess colonies in the East.[50] He frankly states that the “book seems to me to be a work of malignant charlatanry in which it is hard to distinguish honest mistakes from wilful misrepresentations.”[51] Irwin's book was later reviewed by Amir Taheri, writing in Asharq Al-Awsat. He listed certain factual and editing errors, and noted a number of prominent Orientalists were left unmentioned, but says that he believes it to be "the most complete account of Orientalism from the emergence of its modern version in the 19th century to the present day." He also describes it as "a highly enjoyable read both for the specialist and the broadly interested reader."[52] American scholar of religion Jason Ānanda Josephson has argued that data from Japan complicates Said's thesis about Orientalism as a field linked to imperial power. Not only did Europeans study Japan without any hope of colonizing it, but Japanese academics played a prominent role as informants and interlocutors in this academic discipline, providing information both on their own practices and history and on the history of China.[53] Moreover, Josephson has documented that European conferences on East Asia predate European conferences on the Middle East described by Said, necessitating an alternative chronology of Western academic interest in the Orient.[54] |
歴史 アーネスト・ゲルナーは、"The Mightier Pen? Edward Said and the Double Standards of Inside-out Colonialism: a review of Culture and Imperialism, by Edward Said" (1993)は、17世紀後半までオスマン帝国(1299-1923)は(西)ヨーロッパにとって現実的な軍事的、文化的、宗教的脅威だったため、 2000年以上にわたる東洋世界の西洋支配のサイードの主張は支持されないと述べている[46][47]。 オリエンタリストとしてのディズレーリ」(Disraeli as an Orientalist: マーク・プラウドマンは "The Polemical Errors of Edward Said"(2005)において、1880年代に大英帝国の地理的範囲がエジプトからインドまでではなかったこと、それは当時のオスマン帝国とペルシャ帝 国が帝国のこれらの極の間に介在していたためである、とオリエンタリズムにおける誤った19世紀の歴史を指摘している[47]。 [さらに、帝国時代の頂点において、東洋世界におけるヨーロッパの植民地権力は決して絶対的なものではなく、相対的であり、それにもかかわらずしばしば植 民地主義権力の帝国的・覇権的目的を破壊する地元の協力者である王子、ラジャ、軍閥に大きく依存していた[48]。 For Lust of Knowing: なぜなら、パレスチナ委任統治領(1920-1948)とイギリス領エジプト(1882-1956)は、19世紀末から20世紀初頭の短い期間しかヨー ロッパの直接統治下になかったため、サイードの西洋文化帝国主義論の例としては不十分であったからだ。オリエンタリズムは、イギリスのインド植民地 (1858-1947)やロシアのアジア植民地(1721-1917)のような帝国主義や文化覇権の顕著な例に集中すべきだったが、そうしなかった。なぜ なら、エドワード・サイードは公的知識人として、中東全般、特にパレスチナの政治について、より政治的主張をすることに関心があったのである[49]。 [49]さらに、イギリスとフランスのオリエンタリズムに不当に集中することによって、サイードは東洋に植民地を保有していなかったドイツとハンガリーの 学者や知識人による19世紀の東洋学の支配を無視したという。 50] 彼は率直に「この本は私には、正直な間違いを故意の誤報と区別することが困難な悪意の戯言の作品と思われる」[51]と述べている。 アーウィンの本は後にAsharq Al-Awsatに書いているアミール・タヘリによってレビューされている。彼は事実誤認や編集上の誤りを挙げ、多くの著名なオリエンタリストが言及され ていないことを指摘したが、「19世紀の近代版の出現から今日までのオリエンタリズムに関する最も完全な説明」であると信じていると述べている。また、 「専門家にとっても、広く関心を持つ読者にとっても、非常に楽しく読める」と評している[52]。 アメリカの宗教学者であるJason Ānanda Josephsonは、日本からのデータが帝国権力と結びついた分野としてのオリエンタリズムに関するサイードのテーゼを複雑にしていると論じている。 ヨーロッパ人は日本を植民地化するという希望を持たずに日本を研究していただけでなく、日本の学者がこの学問分野の情報提供者や対話者として重要な役割を 果たし、彼ら自身の実践や歴史と中国の歴史の両方について情報を提供していた[53] さらにジョセフソンは、東アジアに関するヨーロッパの会議がサイードが説明した中東に関するヨーロッパの会議より古いことを記録し、西洋学者がオリエント に興味を持った別の年代を必要とさせている[54]。 |
| Professional In the article "Said's Splash" (2001), Martin Kramer says that, fifteen years after the publication of Orientalism (1978), UCLA historian Nikki Keddie (whom Said praised in Covering Islam, 1981) who originally had praised Orientalism as an "important, and, in many ways, positive" book, had changed her mind. In Approaches to the History of the Middle East (1994), Keddie criticises Said's work on Orientalism, for the unfortunate consequences upon her profession as an historian: I think that there has been a tendency in the Middle East field to adopt the word "orientalism" as a generalized swear-word, essentially referring to people who take the "wrong" position on the Arab–Israeli dispute, or to people who are judged too "conservative". It has nothing to do with whether they are good or not good in their disciplines. So, "orientalism", for many people, is a word that substitutes for thought and enables people to dismiss certain scholars and their works. I think that is too bad. It may not have been what Edward Said meant at all, but the term has become a kind of slogan.[55] |
プロフェッショナル マーティン・クレイマーは、『オリエンタリズム』(1978年)の出版から15年後、UCLAの歴史家ニッキー・ケディー(サイードが『イスラムを覆う』 (1981年)で賞賛)が、当初『オリエンタリズム』を「重要で、多くの点で肯定的な」本だと評価していたが、考えを改めたと述べている(「サイードの飛 沫」(2001年))。中東史へのアプローチ』(1994年)の中で、ケディーはサイードのオリエンタリズムに関する著作が、歴史家としての自分の職業に 不幸な結果をもたらしたと批判している。 中東の分野では、「オリエンタリズム」という言葉を、アラブ・イスラエル紛争について「間違った」立場をとる人々や、「保守的」すぎると判断される人々を 指す、一般的な悪口として採用する傾向があるように思うのです。その人が専門分野で優秀かそうでないかとは関係ない。だから、多くの人にとって「オリエン タリズム」は、思想に代わる言葉であり、特定の学者やその著作を否定することを可能にするものなのです。それはあまりにもひどいと思います。エドワード・ サイードが言いたかったことは全く違うかもしれませんが、この言葉は一種のスローガンになってしまっています[55]。 |
| Literature In the article, "Edward Said's Shadowy Legacy" (2008), Robert Irwin says that Said ineffectively distinguished among writers of different centuries and genres of Orientalist literature. That the disparate examples, such as the German poet Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) who never travelled to the Orient; the French novelist Gustave Flaubert (1821–1880) who briefly toured Egypt; the French Orientalist Ernest Renan (1823–1892), whose anti-Semitism voided his work; and the British Arabist Edward William Lane (1801–1876), who compiled the Arabic–English Lexicon (1863–93)—did not constitute a comprehensive scope of investigation or critical comparison.[56] In that vein, in Defending the West: A Critique of Edward Said's Orientalism (2007), Ibn Warraq earlier had said that in Orientalism (1978) Said had constructed a binary-opposite representation, a fictional European stereotype that would counter-weigh the Oriental stereotype. Being European is the only common trait among such a temporally and stylistically disparate group of literary Orientalists.[57] |
文学 ロバート・アーウィンは、「エドワード・サイードの影の遺産」(2008年)という論文で、サイードが異なる世紀やジャンルのオリエンタリズム文学の作家 を非効率的に区別していると述べている。東洋を旅したことのないドイツの詩人ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749-1832)、エジプトを 短期間旅行したフランスの小説家ギュスターヴ・フローベール(1821-1880)、反ユダヤ主義によってその仕事を無効にしたフランスの東洋学者エルネ スト・レナン(1823-1892)、アラビア語-英語語彙集(1863-93)を編纂したイギリスのアラビア学者エドワード・ウィリアム・レーン (1801-1876)など異種の例では調査や批判の包括範囲を構成しなかったと述べている。 [56] そのような流れの中で、『西洋を擁護する。イブン・ワラクは先に、『オリエンタリズム』(1978年)において、サイードが二律背反の表現、つまり東洋の ステレオタイプに対抗する架空のヨーロッパのステレオタイプを構築したと述べていた。ヨーロッパ人であることは、このように時間的にも文体的にもばらばら な文学的オリエンタリストのグループの中で唯一の共通の特徴である[57]。 |
| Philosophy In The Asiatic Society of Bengal and the Discovery of India's Past (1988), O. P. Kejariwal says that with the creation of a monolithic Occidentalism to oppose the Orientalism of Western discourse with the Eastern world, Said had failed to distinguish between the paradigms of Romanticism and the Enlightenment, and ignored the differences among Orientalists; and that he failed to acknowledge the positive contributions of Orientalists who sought kinship, between the worlds of the East and the West, rather than to create an artificial "difference" of cultural inferiority and superiority; such a man was William Jones (1746–1794), the British philologist–lexicographer who proposed that Indo–European languages are interrelated.[58] In the essay "The Debate About 'Orientalism'", Harry Oldmeadow says that "Said’s treatment of Orientalism, particularly the assertion of the necessary nexus with imperialism, is over-stated and unbalanced." He objected to Said's view that Western Orientalists were projecting upon the "artificial screen" called 'the East' or 'the Orient', but that such projection was only a small part of the relationship. That Said failed to adequately distinguish between the genuine experiences of the Orient and the cultural projections of Westerners. He further criticized Said for using reductionist models of religion and spirituality, that are based on "Marxist/Foucauldian/psychoanalytic thought."[59] George Landlow argued that Said assumed that such projection and its harmful consequences are a purely Western phenomenon, when in reality all societies do this to each other. This was a particular issue given Said treated Western colonialism as unique, which Landlow regarded as unsatisfactory for a work of serious scholarship.[60] |
哲学 『ベンガル・アジア協会とインドの過去の発見』(1988年)のなかで、O. Kejariwalは、西洋の言説が東洋的であることに対抗して、一枚岩の西洋主義を作り上げたサイードは、ロマン主義と啓蒙主義のパラダイムを区別せ ず、東洋学者間の相違を無視したと述べている。そして、文化的な劣等感と優越感という人工的な「差異」を作り出すのではなく、東洋と西洋の世界の間に、親 族関係を求めたオリエンタリストたちの積極的な貢献を認めなかった。そのような人物として、インドヨーロッパ語族が相互に関連していると提案したイギリス の文献学者・文献学者ウィリアム・ジョーンズ(1746-1794年)がいるのだ。 [58] ハリー・オールドメドウは「『オリエンタリズム』についての議論」というエッセイの中で、「サイードのオリエンタリズムの扱い、特に帝国主義との必要な結 びつきの主張は、過度に強調されバランスが取れていない」と述べている]。彼は、西洋のオリエンタリストは「東洋」あるいは「東洋」と呼ばれる「人工的な スクリーン」に投影しているが、そうした投影は関係のごく一部に過ぎないというサイードの見解に異論を唱えた。サイードは、東洋の真の経験と西洋人の文化 的投影とを適切に区別することができなかったと。さらに彼はサイードが「マルクス主義/フーコーディアン/精神分析的思想」に基づく宗教と霊性の還元主義 的モデルを用いていると批判していた[59]。 ジョージ・ランドローは、サイードがそのような投影とその有害な結果が純粋に西洋の現象であると仮定しているが、実際にはすべての社会がお互いにそうして いるのであると論じていた。これはサイードが西洋の植民地主義を独特なものとして扱っていることから特に問題となり、ランドローは真面目な学問の作品とし ては不満足であるとみなしていた[60]。 |
| Cultural turn Several scholars have critiqued Orientalism and Said's embrace of the cultural turn as a means of explaining colonialism. Vivek Chibber has highlighted how Orientalism argues that orientalist discourse was both a cause and an effect of colonialism - that on the one hand, orientalist scholarship (described by Said as "manifest orientalism") developed from the eighteenth century as a means of justifying the process of imperialist expansion, whilst on the other, a deeply ingrained tradition of broader orientalist depictions of the East stretching back to the classical era (which Said labelled "latent orientalism") played a role in creating the conditions for the launching of colonial projects. Whilst the first claim had previously been made by anti-colonial thinkers, the latter was novel.[61] In the years after Orientalism was published, Said's arguments were critiqued by Sadiq Jalal al-Azm and Aijaz Ahmad. In 1981 Al-Azm suggested that conceiving of orientalism as "the natural product of an ancient and almost irresistible European bent of mind to misrepresent the realities of other cultures, peoples, and their languages, in favour of Occidental self-affirmation" served to reinforce the essentialism that was at the heart of orientalism, rather than challenging it, i.e. that the West is inherently incapable of understanding the East. Just over ten years later Ahmad raised two criticisms of Said's assertions: firstly, that according to Said orientalist views were so pervasive that he did not differentiate critics of colonialism such as Karl Marx from supporters of imperialism, despite the role of Marxists in anti-colonial struggles across the world, and secondly that Said's suggestion of cultural causes for imperialism displaced older Marxist, nationalist and liberal analyses based on the interests of economic classes, nations and individuals in favour of a "Clash of Civilizations" thesis.[61] More recently, Chibber has pointed out that essentialist and ethnocentric portrayals of foreign cultures can be found in pre-colonial Eastern civilisations as well: whilst Said acknowledged that "all cultures impose corrections upon raw reality", Chibber has argued that this fact weakens the contention that such essentialism was itself a cause of colonialism, since the latter was practiced by a relatively small number of mostly Western European countries. Regarding a weaker interpretation of Said's thesis - that latent orientalism was a necessary but not sufficient prerequisite for colonialism - Chibber contends that economic and political factors are universally accepted as contributory causes of colonialism, that these in themselves would generate pressure for arguments to legitimise imperial projects, and therefore a case cannot be made that pre-existing latent orientalism was indispensable for the rise of colonialism.[61] |
文化的転回 何人かの学者は、オリエンタリズムとサイードが植民地主義を説明する手段として文化的転回を採用したことを批判している。Vivek Chibberは、オリエンタリズムの言説が植民地主義の原因であると同時に結果であるとして、オリエンタリズムを論じていることを強調している。つま り、一方では、帝国主義の拡大過程を正当化する手段として、18世紀からオリエンタリズム研究(Saidは「顕在オリエンタリズム」と表現)が発展した。 一方、古典時代にまで遡る東洋に関する広範なオリエンタリズム的描写の深く根付いた伝統(サイードはこれを「潜在的オリエンタリズム」と呼んだ)は、植民 地プロジェクトを開始するための条件整備に一役買っているのです。前者の主張は反植民地主義者たちによって以前からなされていたのに対して、後者の主張は 斬新であった[61]。 オリエンタリズムが出版された後、サイードの議論はSadiq Jalal al-AzmとAijaz Ahmadによって批評された。1981年、アル=アズムはオリエンタリズムを「西洋の自己肯定感を支持するために、他の文化、民族、言語の現実を誤魔化 そうとする、古代からほとんど抵抗できないヨーロッパの心の傾向から生まれた自然物」と考えることは、オリエンタリズムの中核にある本質主義、つまり西洋 は本質的に東洋を理解できないということに挑戦するというより、強化する役割を果たしたと指摘する。それからちょうど10年後、アフマドはサイードの主張 に対して2つの批判を行った。第一に、サイードによれば、東洋的な見方があまりにも浸透しているため、マルクスが世界各地の反植民地闘争において役割を果 たしたにもかかわらず、カール・マルクスのような植民地主義の批判者を帝国主義の支持者と区別しないこと、第二に、サイードの帝国主義の文化的原因に関す る提案は、経済階級、国家、個人の利益に基づいた古いマルクス主義、民族主義、リベラルの分析を置き換え、「文明の衝突」論文を支持することである [61]。 [61] より最近では、チバーは外国文化に対する本質主義的で民族中心的な描写が植民地以前の東洋文明にも見られると指摘している。サイードは「すべての文化は生 の現実に修正を加える」ことを認めていたが、チバーは、植民地主義が比較的少数の主に西ヨーロッパ諸国によって実践されていたため、この事実によってその ような本質主義がそれ自体の原因であるという主張が弱められると主張している。潜在的なオリエンタリズムは植民地主義の必要条件ではあるが十分条件ではな いというサイードのテーゼのより弱い解釈について、チバーは経済的・政治的要因は植民地主義の寄与する原因として普遍的に受け入れられており、それ自体が 帝国プロジェクトを正当化するための議論の圧力を生み出すと主張しており、したがって、既存の潜在的オリエンタリズムが植民地主義の台頭に不可欠であると いうケースは成立し得ない[61]と論じている。 |
| Personality In the sociological article, "Review: Who is Afraid of Edward Said?" (1999) Biswamoy Pati said that in making ethnicity and cultural background the tests of moral authority and intellectual objectivity in studying the Oriental world, Said drew attention to his personal identity as a Palestinian and as a subaltern of the British Empire, in the Near East.[62] Therefore, from the perspective of the Orientalist academic, Said's personal background might, arguably, exclude him from writing about the Oriental world, hindered by an upper-class birth, an Anglophone upbringing, a British-school education in Cairo, residency in the U.S., a university-professor job; and categorical statements, such as: "any and all representations...are embedded, first, in the language, and then, in the culture, institutions, and political ambience of the representer...[the cultural representations are] interwoven with a great many other things, besides 'the Truth', which is, itself, a representation."[6]: 272 Hence, in the article "Orients and Occidents: Colonial Discourse Theory and the Historiography of the British Empire", D.A. Washbrook said that Said and his academic cohort indulge in excessive cultural relativism, which intellectual excess traps them in a "web of solipsism," which limits conversation exclusively to "cultural representations" and to denying the existence of any objective truth.[63] That Said and his followers fail to distinguish between the types and degrees of Orientalism represented by the news media and popular culture (e.g., the Orientalism of the film Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), and heavy academic Orientalism about the language and literature, history and culture of the peoples of the Eastern world.[6]: 347 [64] In the article "Orientalism Now" (1995), historian Gyan Prakash says that Edward Said had explored fields of Orientalism already surveyed by his predecessors and contemporaries, such as V. G. Kiernan, Bernard S. Cohn, and Anwar Abdel Malek, who also had studied, reported, and interpreted the social relationship that makes the practice of imperialism intellectually, psychologically, and ethically feasible; that is, the relationship between European imperial rule and European representations of the non-European Other self, the colonised people.[65] That, as an academic investigator, Said already had been preceded in the critical analysis of the production of Orientalist knowledge and about Western methods of Orientalist scholarship, because, in the 18th century, "Abd al-Rahman al-Jabarti [1753–1825], the Egyptian chronicler, and a witness to Napoleon's invasion of Egypt in 1798, for example, had no doubt that the expedition was as much an epistemological as military conquest". Nonetheless, George Landow, of Brown University, who criticized Said's scholarship and contested his conclusions, acknowledged that Orientalism is a major work of cultural criticism.[66] |
パーソナリティ 社会学論文「レビュー。誰がエドワード・サイードを恐れているのか"。(1999) ビスワモイ・パティは、エスニシティと文化的背景を東洋世界の研究における道徳的権威と知的客観性のテストとすることで、サイードはパレスチナ人として、 また近東の大英帝国のサバルタンとして、彼の個人的アイデンティティに注目したのだと述べている[62]。 [したがって、オリエンタリズムの学問的観点からすれば、サイードの個人的背景は、上流階級の生まれ、英国人の育ち、カイロでの英国学校での教育、米国で の居住、大学教授の仕事などに妨げられ、間違いなく、東洋世界について書くことから除外されるかもしれない。大学教授という仕事、そして次のような断定的 な記述。あらゆる表象は...まず言語に、次に表象者の文化、制度、政治的雰囲気に埋め込まれている...(文化的表象は)、それ自体が表象である『真 理』以外にも、非常に多くのものと織り込まれている」[6]:272。 それゆえ、論文「Orients and Occidents: 植民地言説論と大英帝国の歴史学」において、D.A.ウォッシュブルックは、サイードと彼の学究的仲間は過度の文化相対主義に耽っており、その知的過剰 が、会話を「文化表象」だけに限定し、いかなる客観的真実の存在を否定する「独我論の網」に彼らを閉じ込めていると述べた [63] サイードと彼の支持者たちがニュースメディアや大衆文化によって表されるオリエンタリズム(例えば...)の種類と程度を区別していないことを。映画『イ ンディ・ジョーンズと運命の寺』(1984年)のオリエンタリズム)と、東洋世界の人々の言語や文学、歴史や文化に関する重厚な学術的オリエンタリズムと を区別していない[6]。 347 [64] 歴史家のギャン・プラカシュは「オリエンタリズムの現在」(1995年)という論文で、エドワード・サイードが、彼の先達や同時代の研究者、例えばV. G. キールナン、バーナード S. コーン、アンワル・アブソーバーなどがすでに調査したオリエンタリズムの分野を探求していたと述べている。また、サイードは、帝国主義の実践を知的に、心 理的に、そして倫理的に可能にする社会的関係、すなわち、ヨーロッパ帝国支配と非ヨーロッパ的な他者である植民地の人々に対するヨーロッパの表象との関係 について研究し、報告し、解釈していた[65]と述べている。 [というのも、18世紀において、「エジプトの年代記作家であり、例えば1798年のナポレオンのエジプト侵攻の目撃者であるアブド・アル・ラフマン・ア ル・ジャバルティ(1753-1825)は、この遠征が軍事的征服と同様に認識論的征服であることに疑いの余地はなかった」と述べているからである [65] 学術調査官としてサイードはすでに東洋学知識の生産に関する批判分析、西洋における東洋学研究方法に関して先行してきたのだ。それにもかかわらず、サイー ドの学問を批判し、彼の結論に異議を唱えたブラウン大学のジョージ・ランドウは、オリエンタリズムが文化批判の主要な作品であることを認めている [66]。 |
| Posthumous In October 2003, one month after the death of Edward Said, the Lebanese newspaper Daily Star recognized the intellectual import of the book, saying "Everyone agrees that Said's work was a work of fiction designed to derail Western civilisation" and that "U.S. Middle Eastern Studies were taken over, by Edward Said's postcolonial studies paradigm."[67] |
死後 エドワード・サイードの死から1ヶ月後の2003年10月、レバノンの新聞デイリー・スターは「サイードの作品が西洋文明を脱線させるために作られたフィ クションであることは誰もが認めている」、「米国の中東研究はエドワード・サイードのポストコロニアル研究のパラダイムによって、乗っ取られた」と、この 本の知的重要性を認識している[67]。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Orientalism_(book) |
https://www.deepl.com/ja/translator |
| Postcolonialism Subaltern Lila Abu-Lughod Occidentalism Ornamentalism Imagined geographies |
ポストコロニアリズム サバルタン ライラ・アブ=ルゴッド オクシデンタリズム 装飾主義 想像の地理学 |
| 【序 説】思考様式・言説としてのオリエンタリズム | |
|
「オリエンタリズムの出発点を18世紀末とするならば、オリエンタリズムとは、オリエントを扱うための——オリエントについて何かを述
べた
り、オリエントに関する見解を権利づけたり、オリエントを描写したり、教授したり、またそこに植民したり、統治したりするための——同業組合的制度とみな
すことができる。簡単に言えば、オリエンタリズムとは、オリエン
トを支配し再構成し威圧するための西洋のスタイルなのである」【p.21】 「オリエンタリズムは「東洋」と(しばしば)「西洋」とされるものとのあいだに設けられ た存 在論的・認識論的区別にもとづく思考様式なのである」(p.3) 「オリエンタリズムとは、地政学的 知識を、美学的、学術的、経済学的、社会学的、歴史的、文 献学的テクストに配分することである。またオリエンタリズムとは、(世界を東洋と西洋という不均等な二つから成るものに仕立てあげる)地理的な基本的区分 であるだけでなく、一連の「関心」、すなわち学問的発見、文献学的再構成、心理学的分析、地誌や社会誌の記述などを媒介としてつくり出され、また維持され ているような「関心」を精緻なものにすることでもある。さらにまた、オリエンタリズムとは、我々の世界と異なっていることが一目瞭然であるような(あるい は我々の世界にかわりうる新しい)世界を理解し、場合によっては支配し、操縦し、統合しようとさえする一定の意志または目的意識——を表現するよりはむし ろ——そのものである。なによりも、オリエンタリズムとは言説である」(pp.12-3) ・オリエンタリズムとは、「オリエントを支配し再構成し威圧するため の西洋の様式なのである」(p.4)【p.21】 ・「オリエンタリズムとは、結局、著作と著者を引用するシステムなの である」(p.21) ・「哲学的にみた場合、私がこれまで非常に広義にオリエンタリズムと 呼んできた言語、思考、ヴィジョンの類は、ラディカルなリアリズムの 一形態であるということができる。オリエンタリズムとはオリエンタル と見なされる問題、対象、特質、地域を扱うさいのひとつの習慣にほか ならず、これを行うものは誰であれ、自分が語り、考える対象を、ある 言葉や言い回しによって指示し、命名し、固定する。すると今度は、そ の言葉や言い回しが現実性を獲得し、あるいはもっと単純に、それが現 実そのものであるとみなされるようになるのである」(英語版,1978:7 2) |
|
| 思想的源泉 | |
|
・思想的源泉としての『知の考古学』および『監獄の誕生——監視と処罰』 「言説としてのオリエンタリズムを検討しない限り、啓蒙主義時代以降のヨーロッパ文 化が、政 治的・社会学的・軍事的・イデオロギー的・科学的に、また想像力によって、オリエントを管理したり、むしろオリエントを生産することさえした場合の、その 巨大な組織的規律=訓練というものを理解することは不可能である。」(p.4) |
|
| 使用の際の限定条件 | |
|
・オリエンタリズムを考える際の限定条件 1「オリエントが本質的に符合する現実をもたない観念、あるいはつくられた想念で あった、な どと断定してはならない。」(pp.5ー6) 2「観念や文化や歴史をまともに理解したり研究したりしようとするならば、必ずそれ
らの強制
力——より正確に言えばそれらの力の編成形態(コンフィギュレーション)——をもあわせて研究しなければならない。」(p.6)
3「オリエンタリズムは虚偽と神話とからできあがったものにすぎず、もしこの真実が
語られる
ならば、虚偽と神話は一挙に吹き飛んでしまうなどと、絶対に考えてはならない」。(p.7)
|
|
|
・権威をとり扱う視座(p.20) 戦略的位置(strategic location):「著作家が題材として取りあげたオリエント的素材に対して彼自身がテクストのなかでいかなる位置を占めているかを記述する手法」 戦略的配置(strategic formation):「テキストのグループ、テキストのタイプ、さらにテキストのジャンルが初めはテクスト群全体のなかで、後には文化全体のなかで、量 と密度と参照能力(referential power)をましてゆく過程と、テクストの本文との関係を分析する手法である。」 |
|
| 【今日のオリエンタリズ ム】・記述することの政治性 | |
| 「オリエンタリストとは 書く人間であり、オリエンタル(東洋人)とは書かれる人間である。こ れこそ、オリエンタリストがオリエントに対して課した、いっそう暗黙裏の、いっそう強力な区別である」(p.312) | |
| ・実体としてのオリエン タルなものへの批判(p.326):「これまで私が議論してきたのは「オリエント」それ自体 が一箇の構成された実体であるという こと、そして、ある地理的空間に固有の宗教・文化・民族的本質にもとづいて定義しうるような、土着の、根本的に他と「異なった」住民が住む地理的空間とい うものが存在するという考え方、やはりきわめて議論の余地のある観念であるということであった」(要ページ確認)。 | |
| ・疑問を抱き続けること
(p.329)の重要性: 「我々は異文化をいかにして表象することができるのか。異文化とは何なのか。ひとつのはっき りした文化(人種、宗教、文明)という概念は有益なものであるのかどうか。あるいは、それは常に(自己の文化を論ずるさいには)自己賛美か、(「異」文化 を論ずるさいには)敵意と攻撃とにまきこまれるものではないだろうか。文化的・宗教的・人種的差異は、社会=経済的・政治=歴史的カテゴリーより重要なも のといえるだろうか。観念とはいかにして権威、「正常性」、あるいは「自明の」真理という地位を獲得するものだろうか。知識人の役割とは何であるのか。知 識人とは、彼が属している文化や国家を正当化するために存在するものなのだろうか。知識人は、独立した批判意識、つまり対立的批判意識にどれだけの重要性 を付与すべきなのだろうか。」(p.329) |
|
| ラディカル・リアリズム | |
| 「哲学的にみた場合、私 がこれまで非常に広義にオリエンタリズムと呼んできた言語、思考、 ヴィジョンの類は、ラディカルなリアリズムの一形態であるということができる。オリエンタリズムとはオリエンタルと見なされる問題、対象、特質、地域を扱 うさいのひとつの習慣にほかならず、これを行うものは誰であれ、自分が語り、考える対象を、ある言葉や言い回しによって指示し、命名し、固定する。すると 今度は、その言葉や言い回しが現実性を獲得し、あるいはもっと単純に、それが現実そのものであるとみなされるようになるのである」(英語版,1978: 72) | |
| 【オリエンタリズム再 考】 | |
| ・ある地域を理解するこ と | |
|
「世界のなかのある地域を理解しようとすることがいかに難しいかということである。 そうした 地域の主たる特徴は、まず第一に絶え間なく流動してやまないということであり、第二にその地域を理解しようとする誰にしても、純然たる意志にもとづく行為 や統治者の立場からの理解という行為によっては、この流動の外の何らかのアルキメデス的立場に立つことはできないということであるように思われる。」 (p.339) 「アラブもイスラムも「解釈の共同体」としてしか存在せず、それによってはじめて存 在を与え られるのだということであり、また、オリエントそれ自体と同様に、それぞれの呼称もまた、激しい軋轢や公然たる戦争状態に置かれたさまざまの利害関心や要 求、プロジェクト、野望、レトリックを表象するものであるということであった。」(p.340)「いかなるものも、たとえ単純な記述的レッテルであろうと も、解釈の領域を超越した局外者の位置に立つことはできない。」(p.341) |
|
| ・中間カテゴリー (median category)について(サイード) | |
| 「明らかに異質で遠く隔 たったものは、どうしたわけか、かえってよりなじみ深い地位を獲得す るものなのだ。人は事物を、まったく新奇なものとまったく既知なものとの二種類に分かつ場合には、判断を停止する傾向がある。新しい中間カテゴリーが浮か び上がってきて、そのために我々ははじめて見る新しい事物を、既知の事物の変形にすぎないと考えることができるようになるからである。こうしたカテゴリー は、本質的に、新しい情報を受け取る手段であるというより、むしろ、すでに確立された事物の見方に対して脅威と見えるものを制御する手段である。」(原 典、1978:58-9:訳本p.58) サイード『オリエンタリズム』今沢訳、1986平凡社 | |
| 【イスラム報道】 ・「『オリエンタリズム』の基本的テーマは知識と権力の癒着である」(「イスラム報 道」 1986:1) ・他者表象の問題 (1)真実の形態——知識の制度と再生産 (2)文化の中の不平等 ・制度と構造がオリエンタリズムなのだ (「オリエンタリズムとは、オリエントを題材とするヨーロッパ製の空想物語など ではなく、一 体のものとしてつくりだされてきた理論および実践なのである」p.7) ・外在化と心象地理と《西洋が内在化してゆくこと》 ・言説(discourse)VS.対抗言説(counter- discourse)という図式 ではない ・『諸民族の動物園』の現実と、クレオール化/メスティーソ化 ・我々にとってのオリエンタリズム(メラネシアの原住民、パパラギ、‥‥) |
|
| 《本人の20年後の所 感》 | |
| "At
this point
I should say something about one of the frequent criticisms addressed
to me, and to which I have always wanted to respond, that in the
process of characterizing the production of Europe’s inferior Others,
my work is only negative polemic which does not advance a new
epistemological approach or method, and expresses only desperation at
the possibility of ever dealing seriously with other cultures. These
criticisms are related to the matters I’ve been discussing so far, and
while I have no desire to unleash a point-by-point refutation of my
critics, I do want to respond in a way that is intellectually pertinent
to the topic at hand.What I took myself to be undertaking in
Orientalism was an adversarial critique not only of the field’s
perspective and political economy, but also of the sociocultural
situation that makes its discourse both so possible and so sustainable.
Epistemologies, discourses, and methods like Orientalism are scarcely
worth the name if they are reductively characterized as objects like
shoes, patched when worn out, discarded and replaced with new objects
when old and unfixable. The archival dignity, institutional authority,
and patriarchal longevity of Orientalism should be taken seriously
because in the aggregate these traits function as a worldview with
considerable political force not easily brushed away as so much
epistemology. Thus Orientalism in my view is a structure erected in the
thick of an imperial contest whose dominant wing it represented and
elaborated not only as scholarship but as a partisan ideology. Yet
Orientalism hid the contest beneath its scholarly and aesthetic idioms.
These things are what I was trying to show, in addition to arguing that
there is no discipline, no structure of knowledge, no institution or
epistemology that can or has ever stood free of the various
sociocultural, historical, and political formations that give epochs
their peculiar individuality." - - Edward W.
Said is Parr Professor of English and Comparative Literature at
Columbia University. His most recent contribution to Critical Inquiry
is “An Ideology of Difference"- Edward W. Said, Representing the
Colonized: Anthropology's Interlocutors. Critical Inquiry 15
(2):205-225 (1989) ++ 「この時点で、私に向けられた頻繁な批判の一つ、そして私が常に応えた いと考えてきた、ヨーロッパの劣った他者の生産を特徴づける過程で、私の仕事は新しい認識論的アプローチや方法を前進させない否定的極論でしかなく、他文 化と真剣に向き合う可能性への絶望を表現しているだけだということについて一言述べておかなければならない。これらの批判は、これまで私が論じてきた事柄 と関連しており、批判者に対する一点一点の反論を繰り広げたいとは思わないが、目の前の話題に知的に適切な形で応えたい。私が『オリエンタリズム』で取り 組んだのは、この分野の視点や政治経済だけでなく、その言説を可能かつ持続可能にしている社会文化状況に対する逆張り批判であった。オリエンタリズムのよ うな認識論、言説、方法は、靴のように取り替えれるものとして特徴づけられ、擦り切れたら補修し、古くて直せなくなったら捨て、新しいものと取り替えるの であれば、その名に値しないものである。オリエンタリズムのアーカイブとしての威厳、制度的権威、家父長制の長命性は真剣に受け止めるべきで、これらの特 質は総体として、単なる認識論として簡単に片付けられない、かなりの政治力を持った世界観として機能しているからである。したがって、私の考えでは、オリ エンタリズムは、帝国的な争いの渦中に築かれた構造物であり、その支配的な翼は、学問としてだけでなく党派的イデオロギーとして表現され、練り上げられた ものである。しかし、オリエンタリズムは、その学問的・美学的イディオムの下に、この争いを隠蔽していたのである。こうしたことを私は示したかった。さら に、エポック=時代に独特の個性を与える様々な社会文化的、歴史的、政治的な形成から自由である学問、知識の構造、制度、認識論は存在しないし、これまで 存在しなかったと主張したのである」。 |
|
| 【マーカスとフィッ シャーの反応】(→表象あるいは修辞の問題へ矮小化しているのでは?という批判の 観点から検討する必要がある) | |
|
「エドワード・サイードによる『オリエンタリズム』(1979)は、非西洋社会を表象す るために 西洋において作りあげられた書式のジャンルにたいする攻撃である。‥‥対象を受動的に位置に置き去りにしたままで、西洋人である作者を能動的位置へと駆り 立てる修辞学上の手法をことに彼は攻撃している。このような対象となった人々とは代弁されてしまわざるをえない人々であり、一般的に言って彼等は西洋の植 民地主義もしくは新植民地主義によって支配された世界の住人たちなのである。」(マーカスとフィッシャー:22) 「だからこそこの修辞法は、西洋の支配を増大させるとともに強化しているわけだ。さらに この修辞 法はそれが権力の行使であり、そのために事実上反対意見を述べる権利を対象から奪ってしまっている。研究される人々は書き手とはいかに違ったものであろう とも、書き手と同じ妥当性において物事を見ているのだという認識が読者から抜け落ちてしまうのである」(マーカスとフィッシャー:22) 「このような修辞学上の手法のなかでもとりわけ際だっているのが現代アラブ人、ギリシャ 人、エジ プト人、マヤ人の価値剥奪であり、それは彼等の祖先たちに関係づけてなされている。‥‥今日でさえなおも、調査が行なわれるのは往々にして、後世につたえ られていくうちに衰微し、崩れ去ったあの栄光の遺産を再生させるためであり、現代の彼等の文化固有の価値はいかなるものであれ否定されている。」(マーカ スとフィッシャー:22-23) |
|
| モダニスト人類学/ポスト モダン人類学(池田光穂) | |
オ
リエンタリズムのサ
イードへの批判
|
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

Odalisque,
1840 Natale
Schiavoni (1777 - 1858)
++
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆