
利己的な遺伝子
The Selfish Gene which thinks
itself as a benevolent

「利己的(Selfish)という用語を遺伝子の性質に表現するのは妄想である」が、そのような妄想の言語で、人びとを 「真理」に導こうとする方便としては、功利的に考えれば、それは正当化される、 ことを明らかにしておこう。ドーキンスのレトリックは、アダム・スミス以来の、神の見えざる手の表現とおなじで、種の進化において、遺伝子とそれがもたら す「形態」は、生物や生物集団になにか功利的に役立とうとして機能しているのではなく、むしろ、中立的にランダムに動き変異して、「結果的に」生物と生物 集団の環境や他のライバルとの競争にさまざまな影響を与える「結果」にすぎないと主張しているのである。そのため、遺伝子の役割を徹底的に功利主義的な理 解から離そうと格闘しているのであり、その意味では、ダーウィンの『種の起源』とならぶ、神の恩寵からはもっとも遠いところにいる無神論的著作ではある。 ドーキンスはその後『神は妄想である』という著作をあらわしているが、それはこの著作の当然の帰結である。
| The Selfish Gene
is a 1976 book on evolution by the ethologist Richard Dawkins,
in which
the author builds upon the principal theory of George C. Williams's
Adaptation and Natural Selection (1966). Dawkins uses the term "selfish
gene" as a way of expressing the gene-centred view of evolution (as
opposed to the views focused on the organism and the group),
popularising ideas developed during the 1960s by W. D. Hamilton and
others. From the gene-centred view, it follows that the more two
individuals are genetically related, the more sense (at the level of
the genes) it makes for them to behave cooperatively with each other. A lineage is expected to evolve to maximise its inclusive fitness—the number of copies of its genes passed on globally (rather than by a particular individual). As a result, populations will tend towards an evolutionarily stable strategy. The book also introduces the term meme for a unit of human cultural evolution analogous to the gene, suggesting that such "selfish" replication may also model human culture, in a different sense. Memetics has become the subject of many studies since the publication of the book. In raising awareness of Hamilton's ideas, as well as making its own valuable contributions to the field, the book has also stimulated research on human inclusive fitness.[1] In the foreword to the book's 30th-anniversary edition, Dawkins said he "can readily see that [the book's title] might give an inadequate impression of its contents" and in retrospect thinks he should have taken Tom Maschler's advice and called the book The Immortal Gene.[2] In July 2017, a poll to celebrate the 30th anniversary of the Royal Society science book prize listed The Selfish Gene as the most influential science book of all time.[3] Background Dawkins builds upon George C. Williams's book Adaptation and Natural Selection (1966), which argued that altruism is not based upon group benefit per se,[4] but results from selection that occurs "at the level of the gene mediated by the phenotype"[5] and that any selection at the group level occurred only under rare circumstances.[6] W. D. Hamilton and others developed this approach further during the 1960s; they opposed the concepts of group selection and of selection aimed directly at benefit to the individual organism.[7] Despite the principle of 'survival of the fittest' the ultimate criterion which determines whether [a gene] G will spread is not whether the behavior is to the benefit of the behaver, but whether it is to the benefit of the gene G ...With altruism this will happen only if the affected individual is a relative of the altruist, therefore having an increased chance of carrying the gene. — W. D. Hamilton, The Evolution of Altruistic Behavior (1963), pp. 354–355. Wilkins and Hull (2014) provide an extended discussion of Dawkins's views and of his book The Selfish Gene.[8] |
『利己的な遺伝子』(原題:The Selfish
Gene)は、動物行動学者リチャード・ドーキンスが1976年に
出版した進化論に関する著書で、著者はジョージ・C・ウィリアムズの『適応と自然淘汰』(原
題:Adaptation and Natural
Selection、1966年)の主要理論をベースにしている。ドーキンスは「利己的な遺伝子」という言葉を、(生物や集団に焦点を当てた見方とは対照
的な)遺伝子を中心とした進化の見方を表現する方法として用いており、W・D・ハミルトンらによって1960年代に開発された考え方を一般化したも
のであ
る。遺伝子中心の考え方からすると、2つの個体が遺伝的に近縁であればあるほど、(遺伝子のレベルでは)互いに協力的に行動することがより理にかなってい
るということになる。 ある系統は、(特定の個体によってではなく)全体として受け継がれる遺伝子のコピー数である包括的フィットネスを最大化するように進化すると予想される。 その結果、集団は進化的に安定した戦略をとるようになる。本書はまた、遺伝子に類似した人間の文化的進化の単位を表すミームという言葉も紹介しており、こ のような「利己的な」複製が、別の意味で人間の文化をもモデル化する可能性を示唆している。この本の出版以来、ミームは多くの研究の対象となった。ハミル トンのアイデアの認知度を高めるとともに、この分野に独自の価値ある貢献をしたことで、この本は人間の包括的適合性に関する研究も刺激した[1]。 この本の30周年記念版の序文でドーキンスは、「(本のタイトルが)その内容に対して不十分な印象を与えるかもしれないことは容易に理解できる」と述べ、 振り返ってみると、トム・マシュラーの助言を受けて、この本を『不滅の遺伝子』と呼ぶべきだったと考えている[2]。 2017年7月、英国王立協会の科学書賞30周年を記念した投票では、『利己的な遺伝子』が史上最も影響力のある科学書として挙げられた[3]。 背景 ドーキンスはジョージ・C・ウィリアムズの著書『適応と自然淘汰』 (1966年)を基に、利他主義はそれ自体が集団の利益に基づいているのではなく、「表現型を媒介として遺伝子のレベルで」起こる淘汰の結果であり [5]、集団レベルでの淘汰はまれな状況下でしか起こらないと主張した[6]。W・D・ハミルトンらは1960年代にこのアプローチをさらに発展させ、集 団淘汰や生物個体の利益を直接目的とした淘汰という概念に反対した[7]。 適者生存」の原則にもかかわらず、[遺伝子]Gが広がるかどうかを決定する究極の基準は、その行動が行動者の利益になるかどうかではなく、遺伝子Gの利益 になるかどうかである。 - W. D. Hamilton, The Evolution of Altruistic Behavior (1963), pp.354-355. ウィルキンスとハル(2014)は、ドーキンスの見解と彼の著書『利己的な遺伝子』についての拡張された議論を提供している[8]。 |
| Book Contents Dawkins begins by discussing the altruism that people display, indicating that he will argue it is explained by gene selfishness, and attacking group selection as an explanation. He considers the origin of life with the arrival of molecules able to replicate themselves. From there, he looks at DNA's role in evolution, and its organisation into chromosomes and genes, which in his view behave selfishly. He describes organisms as apparently purposive but fundamentally simple survival machines, which use negative feedback to achieve control. This extends, he argues, to the brain's ability to simulate the world with subjective consciousness, and signalling between species. He then introduces the idea of the evolutionarily stable strategy, and uses it to explain why alternative competitive strategies like bullying and retaliating exist. This allows him to consider what selfishness in a gene might actually mean, describing W. D. Hamilton's argument for kin selection, that genes for behaviour that improves the survival chances of close relatives can spread in a population, because those relatives carry the same genes. Dawkins examines childbearing and raising children as evolutionary strategies. He attacks the idea of group selection for the good of the species as proposed by V. C. Wynne-Edwards, arguing instead that each parent necessarily behaves selfishly. A question is whether parents should invest in their offspring equally or should favour some of them, and explains that what is best for the survival of the parents' genes is not always best for individual children. Similarly, Dawkins argues, there are conflicts of interest between males and females, but he notes that R. A. Fisher showed that the optimal sex ratio is 50:50. He explains that this is true even in an extreme case like the harem-keeping elephant seal, where 4% of the males get 88% of copulations. In that case, the strategy of having a female offspring is safe, as she'll have a pup, but the strategy of having a male can bring a large return (dozens of pups), even though many males live out their lives as bachelors. Amotz Zahavi's theory of honest signalling explains stotting as a selfish act, he argues, improving the springbok's chances of escaping from a predator by indicating how difficult the chase would be. Dawkins discusses why many species live in groups, achieving mutual benefits through mechanisms such as Hamilton's selfish herd model: each individual behaves selfishly but the result is herd behaviour. Altruism too can evolve, as in the social insects such as ants and bees, where workers give up the right to reproduce in favour of a sister, the queen; in their case, the unusual (haplodiploid) system of sex determination may have helped to bring this about, as females in a nest are exceptionally closely related. The final chapter of the first edition introduced the idea of the meme, a culturally-transmitted entity such as a hummable tune, by analogy to genetic transmission. Dawkins describes God as an old idea which probably arose many times, and which has sufficient psychological appeal to survive effectively in the meme pool. The second edition (1989) added two more chapters. |
書籍 目次 ドーキンスはまず、人々が示す利他主義について論じ、それが遺伝子の利己主義によって説明されると主張し、説明として集団選択を攻撃することを示す。そし て、自己複製が可能な分子の登場による生命の起源について考察する。そこから、進化におけるDNAの役割、染色体や遺伝子への組織化について考察する。彼 は、生物は一見合目的的であるが、基本的には単純な生存機械であり、負のフィードバックによって制御されていると述べている。このことは、主観的な意識で 世界をシミュレートする脳の能力や、種間のシグナル伝達にも及ぶと彼は主張する。次に、進化的に安定した戦略という考え方を紹介し、それを使って、いじめ や報復のような代替的な競争戦略が存在する理由を説明する。ドーキンスは、遺伝子の利己主義が実際にどのような意味を持つのか、W.D.ハミルトンによる 近親淘汰の議論、つまり、近親者の生存確率を向上させる行動の遺伝子は、近親者が同じ遺伝子を持っているため、集団の中で広まる可能性があることを説明す る。 ドーキンスは出産と子育てを進化戦略として検証している。ドーキンスは、V.C.ウィン・エドワーズが提唱した種の利益のための集団淘汰という考え方を攻 撃し、代わりにそれぞれの親は必然的に利己的に行動すると主張する。問題は、親は平等に子孫に投資すべきか、それとも一部の子孫を優遇すべきかということ であり、親の遺伝子の存続にとって最善であることが、必ずしも個々の子供にとって最善であるとは限らないと説明する。同様に、ドーキンスはオスとメスの間 には利害の対立があると主張するが、R.A.フィッシャーが最適な男女比は50:50であることを示したと指摘する。これは、ハーレムを作るゾウアザラシ のように、4%のオスが88%の交尾をするような極端な場合にも当てはまると説明する。この場合、メスに子供を産ませるという戦略は、メスが仔を産むので 安全であるが、オスに子供を産ませるという戦略は、多くのオスが独身で一生を終えるにもかかわらず、大きなリターン(何十頭もの仔)をもたらすことがあ る。アモッツ・ザハヴィ(Amotz Zahavi)の正直なシグナリング理論によれば、ストーティングは利己的な行為であり、追跡がいかに困難であるかを示すことで、スプリングボックが捕食 者から逃れる可能性を高めている、と彼は主張する。 ドーキンスは、なぜ多くの種が集団で生活し、ハミルトンの利己的群れモデルのようなメカニズムによって相互利益を得ているのかについて論じている。アリや ミツバチなどの社会性昆虫では、働き蜂が姉妹である女王蜂のために生殖権を放棄するように、利他主義も進化する可能性がある。彼らの場合、巣の中のメスは 例外的に密接な関係にあるため、珍しい(ハプロ倍数体の)性決定システムがこれをもたらすのに役立ったのかもしれない。 初版の最終章では、ミームという考え方が紹介された。ミームとは、鼻歌のような文化的に伝達されるもので、遺伝子の伝達と類似している。ドーキンスは神に ついて、おそらく何度も生まれた古い考えであり、ミームのプールで効果的に生き残るのに十分な心理的魅力を持っていると述べている。第2版(1989年) では、さらに2章が追加された。 |
| Themes "Selfish" genes In describing genes as being "selfish", Dawkins states unequivocally that he does not intend to imply that they are driven by any motives or will, but merely that their effects can be metaphorically and pedagogically described as if they were. His contention is that the genes that are passed on are the ones whose evolutionary consequences serve their own implicit interest (to continue the anthropomorphism) in being replicated, not necessarily those of the organism. In later work, Dawkins brings evolutionary "selfishness" down to creation of a widely proliferated extended phenotype.[9] For some, the metaphor of "selfishness" is entirely clear, while to others it is confusing, misleading, or simply silly to ascribe mental attributes to something that is mindless. For example, Andrew Brown has written:[10] ""Selfish", when applied to genes, doesn't mean "selfish" at all. It means, instead, an extremely important quality for which there is no good word in the English language: "the quality of being copied by a Darwinian selection process." This is a complicated mouthful. There ought to be a better, shorter word—but "selfish" isn't it." Donald Symons also finds it inappropriate to use anthropomorphism in conveying scientific meaning in general, and particularly in this instance. He writes in The Evolution of Human Sexuality (1979):[11] "In summary, the rhetoric of The Selfish Gene exactly reverses the real situation: through [the use of] metaphor genes are endowed with properties only sentient beings can possess, such as selfishness, while sentient beings are stripped of these properties and called machines...The anthropomorphism of genes...obscures the deepest mystery in the life sciences: the origin and nature of mind." "Replicators" Dawkins proposes the idea of the "replicator":[12] "It is finally time to return to the problem with which we started, to the tension between individual organism and gene as rival candidates for the central role in natural selection...One way of sorting this whole matter out is to use the terms ‘replicator’ and ‘vehicle’. The fundamental units of natural selection, the basic things that survive or fail to survive, that form lineages of identical copies with occasional random mutations, are called replicators. DNA molecules are replicators. They generally, for reasons that we shall come to, gang together into large communal survival machines or 'vehicles'." — Richard Dawkins, The Selfish Gene, p. 253 (Anniversary Edition) The original replicator (Dawkins Replicator) was the initial molecule which first managed to reproduce itself and thus gained an advantage over other molecules within the primordial soup.[13] As replicating molecules became more complex, Dawkins postulates, the replicators became the genes within organisms, with each organism's body serving the purpose of a 'survival machine' for its genes. Dawkins writes that gene combinations which help an organism to survive and reproduce tend to also improve the gene's own chances of being replicated, and, as a result, "successful" genes frequently provide a benefit to the organism. An example of this might be a gene that protects the organism against a disease. This helps the gene spread, and also helps the organism. Genes vs organisms There are other times when the implicit interests of the vehicle and replicator are in conflict, such as the genes behind certain male spiders' instinctive mating behaviour, which increase the organism's inclusive fitness by allowing it to reproduce, but shorten its life by exposing it to the risk of being eaten by the cannibalistic female. Another example is the existence of segregation distorter genes that are detrimental to their host, but nonetheless propagate themselves at its expense.[14] Likewise, the persistence of junk DNA that [Dawkins believed at that time] provides no benefit to its host can be explained on the basis that it is not subject to selection. These unselected for but transmitted DNA variations connect the individual genetically to its parents, but confer no survival benefit.[15] These examples might suggest that there is a power struggle between genes and their interactor. In fact, the claim is that there isn't much of a struggle because the genes usually win without a fight. However, the claim is made that if the organism becomes intelligent enough to understand its own interests, as distinct from those of its genes, there can be true conflict. An example of such a conflict might be a person using birth control to prevent fertilisation, thereby inhibiting the replication of his or her genes. But this action might not be a conflict of the 'self-interest' of the organism with his or her genes, since a person using birth control might also be enhancing the survival chances of their genes by limiting family size to conform with available resources, thus avoiding extinction as predicted under the Malthusian model of population growth. Altruism Dawkins says that his "purpose" in writing The Selfish Gene is "to examine the biology of selfishness and altruism." He does this by supporting the claim that "gene selfishness will usually give rise to selfishness in individual behaviour. However, as we shall see, there are special circumstances in which a gene can achieve its own selfish goals best by fostering a limited form of altruism at the level of individual animals." Gene selection provides one explanation for kin selection and eusociality, where organisms act altruistically, against their individual interests (in the sense of health, safety or personal reproduction), namely the argument that by helping related organisms reproduce, a gene succeeds in "helping" copies of themselves (or sequences with the same phenotypic effect) in other bodies to replicate. The claim is made that these "selfish" actions of genes lead to unselfish actions by organisms. A requirement upon this claim, supported by Dawkins in Chapter 10: "You scratch my back, I'll ride on yours" by examples from nature, is the need to explain how genes achieve kin recognition, or manage to orchestrate mutualism and coevolution. Although Dawkins (and biologists in general) recognize these phenomena result in more copies of a gene, evidence is inconclusive whether this success is selected for at a group or individual level. In fact, Dawkins has proposed that it is at the level of the extended phenotype:[9][16] "We agree [referring to Wilson and Sober's book Unto others: The evolution and psychology of unselfish behavior] that genes are replicators, organisms and groups are not. We agree that the group selection controversy ought to be a controversy about groups as vehicles, and we could easily agree to differ on the answer...I coined the [term] vehicle not to praise it but to bury it....Darwinism can work on replicators whose phenotypic effects (interactors) are too diffuse, too multi-levelled, too incoherent to deserve the accolade of vehicle...Extended phenotypes can include inanimate artifacts like beaver dams...But the vehicle is not something fundamental...Ask rather 'Is there a vehicle in this situation and, if so, why?'" —Richard Dawkins, Burying the Vehicle Although Dawkins agrees that groups can assist survival, they rank as a "vehicle" for survival only if the group activity is replicated in descendants, recorded in the gene, the gene being the only true replicator. An improvement in the survival lottery for the group must improve that for the gene for sufficient replication to occur. Dawkins argues qualitatively that the lottery for the gene is based upon a very long and broad record of events, and group advantages are usually too specific, too brief, and too fortuitous to change the gene lottery. "We can now see that the organism and the group of organisms are true rivals for the vehicle role in the story, but neither of them is even a candidate for the replicator role. The controversy between ‘individual selection’ and ‘group selection’ is a real controversy between alternative vehicles...As it happens the outcome, in my view, is a decisive victory for the individual organism. The group is too wishy-washy an entity." —Richard Dawkins, The Selfish Gene, pp. 254-255 Prior to the 1960s, it was common for altruism to be explained in terms of group selection, where the benefits to the organism or even population were supposed to account for the popularity of the genes responsible for the tendency towards that behaviour. Modern versions of "multilevel selection" claim to have overcome the original objections,[17] namely, that at that time no known form of group selection led to an evolutionarily stable strategy. The claim still is made by some that it would take only a single individual with a tendency towards more selfish behaviour to undermine a population otherwise filled only with the gene for altruism towards non-kin.[18] |
テーマ 「利己的な」遺伝子 遺伝子を「利己的」であると表現する際、ドーキンスは、遺伝子が何らかの動機や意志によって動かされることを意味するのではなく、遺伝子の作用があたかも そうであるかのように比喩的かつ教育的に表現されるだけである、と明確に述べている。ドーキンスの主張は、遺伝子が受け継がれるのは、その遺伝子が複製さ れるという暗黙の利益(擬人化を続けるならば)に資する進化的結果をもたらすものであり、必ずしも生物のものではないということである。後の研究では、 ドーキンスは進化の「利己主義」を、広く増殖した表現型の創造にまで引き下げている[9]。 ある人にとっては「利己主義」の比喩は全く明快であるが、別の人にとっては、無心なものに精神的属性を付与することは混乱させ、誤解を招き、あるいは単に 愚かなことである。例えば、アンドリュー・ブラウンは次のように書いている[10]。 "利己的 "を遺伝子に当てはめた場合、"利己的 "という意味は全くない。その代わりに、英語には良い言葉がない極めて重要な性質を意味する: 「ダーウィンの淘汰プロセスによってコピーされる性質 "である。これは複雑な表現である。もっと簡潔な言葉があるはずだが、"selfish "はそうではない。 ドナルド・シモンズもまた、科学的な意味を伝えるのに擬人法を用いるのは一般的に不適切であり、特にこの例では不適切であると考える。彼は『人間の性の進 化』(1979年)の中で次のように書いている[11]。 要約すると、『利己的な遺伝子』のレトリックは、現実の状況を正確に逆転させている。隠喩(メタファー)を使うことによって、遺伝子は利己的であるという ような、感覚を持つ生物だけが持ちうる特性を付与され、一方、感覚を持つ生物はそのような特性を剥奪され、機械と呼ばれる......遺伝子の擬人化 は......生命科学における最も深い謎、すなわち心の起源と本質を曖昧にしている。" "複製者" ドーキンスは「複製者」という考えを提唱している[12]。 この問題全体を整理する一つの方法は、「複製者」と「乗り物」という用語を使うことである。自然淘汰の基本的な単位、生き残るか生き残れないかの基本的な もの、時折ランダムな突然変異を起こしながら同一コピーの系統を形成するものは、複製体と呼ばれる。DNA分子は複製体である。DNA分子は一般に、これ から述べるような理由から、集団で大きな生存機械、あるいは "乗り物 "になる。 - リチャード・ドーキンス『利己的な遺伝子』253頁(記念版) 複製を行う分子がより複雑になるにつれて、複製を行う分子は生物内の遺伝子となり、各生物の体はその遺伝子のための「生存機械」としての役割を果たすよう になるとドーキンスは仮定している[13]。 ドーキンスは、生物の生存と繁殖を助ける遺伝子の組み合わせは、遺伝子自身の複製される確率も向上させる傾向があり、その結果、「成功した」遺伝子はしば しば生物に利益をもたらすと書いている。その結果、"成功した "遺伝子はしばしば生物に利益をもたらす。この例として、生物を病気から守る遺伝子が挙げられる。その結果、「成功した」遺伝子は生物に利益をもたらすこ とが多い。 遺伝子対生物 例えば、ある種のオスのクモの本能的な交尾行動の背後にある遺伝子のように、乗り物と複製者の暗黙の利害が対立する場合もある。この遺伝子は、繁殖を可能 にすることで生物の包括的なフィットネスを高めるが、共食いするメスに食べられる危険にさらすことで生物の寿命を縮める。別の例としては、宿主にとって有 害であるにもかかわらず、宿主の犠牲の上に増殖する分離歪曲遺伝子の存在がある[14]。同様に、宿主に何の利益ももたらさないジャンクDNAの存続は、 それが選択の対象にならないという根拠で説明できる。淘汰されないが伝達されるこれらのDNA変異は、個体とその両親を遺伝的に結びつけるが、生存の利益 は与えない。 これらの例は、遺伝子とその相互作用者の間に権力闘争があることを示唆しているかもしれない。実際には、遺伝子は戦わずに勝利するのが普通であるため、そ れほど大きな争いはないというのが主張である。しかし、もし生物が、遺伝子の利益とは異なる自分自身の利益を理解するのに十分な知性を持つようになれば、 真の対立が起こりうるという主張がなされている。 そのような対立の例としては、受精を防ぐために避妊を行い、それによって自分の遺伝子の複製を阻害するようなことが考えられる。なぜなら、避妊をする人 は、利用可能な資源に合わせて家族のサイズを制限することで、遺伝子の生存の可能性を高め、マルサスの人口増加モデルで予測されるような絶滅を回避してい るかもしれないからである。 利他主義 z ドーキンスは『利己的な遺伝子』を書いた「目的」を「利己主義と利他主義の生物学を調べること」と語っている。彼は、「遺伝子の利己主義は、通常、個人の 行動に利己主義をもたらす」という主張を支持することによって、これを実現したのである。しかし、これから見るように、動物個体のレベルで限定的な利他主 義を育むことによって、遺伝子が利己的な目標を達成することができる特別な状況もある。つまり、関連する生物の繁殖を助けることで、遺伝子は他の体内の自 分自身のコピー(あるいは同じ表現型効果を持つ配列)の複製を「助ける」ことに成功するという主張である。遺伝子のこのような「利己的な」行動は、生物に よる利己的でない行動につながるという主張である。ドーキンスが第10章「あなたは私の背中を掻く、私はあなたの背中に乗る」で自然界の例を挙げて支持し ているこの主張の前提条件は、遺伝子がどのようにして血縁認識を達成するのか、あるいは相互主義や共進化を組織的に管理するのかを説明する必要性である。 ドーキンス(そして一般的な生物学者)は、これらの現象が遺伝子のコピー数を増やす結果であると認識しているが、この成功が集団レベル、個体レベルのどち らで選択されたものなのか、決定的な証拠はない。実際、ドーキンスはそれが拡大表現型のレベルであると提唱している[9][16]。 ウィルソンとソバーの著書『Unto others: 遺伝子が複製者であり、生物と集団はそうではないことに我々は同意する。私たちは、集団選択の論争は乗り物としての集団についての論争であるべきだという ことに同意する。 ダーウィニズムは、表現型効果(相互作用因子)が拡散しすぎ、多段階化しすぎ、支離滅裂で、乗り物という栄誉に値しない複製体に対しても働くことができ る......拡張された表現型には、ビーバーダムのような無生物の人工物も含まれる......しかし、乗り物は何か根本的なものではない...... むしろ『この状況に乗り物はあるか、あるとすればなぜか』を問うのだ」。 -リチャード・ドーキンス『乗り物を葬る ドーキンスは集団が生存を助けることに同意するが、集団が生存のための "乗り物 "として位置づけられるのは、集団の活動が子孫に複製され、遺伝子に記録された場合だけである。遺伝子が唯一の真の複製者である。集団の生存抽選が改善さ れれば、遺伝子の生存抽選も改善され、十分な複製が行われることになる。ドーキンスは定性的には、遺伝子の抽選は非常に長く広範な出来事の記録に基づいて おり、集団の利点は遺伝子の抽選を変えるには、通常あまりに特殊で、あまりに短く、あまりに偶然的であると主張している。 「生物と生物集団は、この物語における乗り物の役割については真のライバルであるが、複製者の役割についてはどちらも候補にすらならないことがわかった。 個体淘汰』と『集団淘汰』の論争は、まさに代替的な乗り物の論争である。集団はあまりにも気まぐれな存在なのだ」。 -リチャード・ドーキンス『利己的な遺伝子』254-255頁 1960年代以前は、利他主義は集団選択の観点から説明されるのが一般的であった。そこでは、生物あるいは集団にとっての利益は、その行動をとる傾向の原 因となる遺伝子の人気のために説明されると考えられていた。すなわち、当時は進化的に安定した戦略を導く集団選択の形態は知られていなかったということで ある。より利己的な行動をとる傾向を持つ個体がたった一匹いるだけで、そうでなければ非親族に対する利他主義の遺伝子だけで満たされた集団を弱体化させる ことができるという主張は、今でも一部の人々によってなされている[18]。 |
| Reception The Selfish Gene was extremely popular when first published, causing "a silent and almost immediate revolution in biology",[19] and it continues to be widely read. It has sold over a million copies, and has been translated into more than 25 languages.[20] Proponents argue that the central point, that replicating the gene is the object of selection, usefully completes and extends the explanation of evolution given by Charles Darwin before the basic mechanisms of genetics were understood. According to the ethologist Alan Grafen, acceptance of adaptionist theories is hampered by a lack of a mathematical unifying theory and a belief that anything in words alone must be suspect.[21] According to Grafen, these difficulties along with an initial conflict with population genetics models at the time of its introduction "explains why within biology the considerable scientific contributions it [The Selfish Gene] makes are seriously underestimated, and why it is viewed mainly as a work of exposition."[21] According to comparative psychologist Nicky Hayes, "Dawkins presented a version of sociobiology that rested heavily on metaphors drawn from animal behavior, and extrapolated these...One of the weaknesses of the sociological approach is that it tends only to seek confirmatory examples from among the huge diversity of animal behavior. Dawkins did not deviate from this tradition."[22] More generally, critics argue that The Selfish Gene oversimplifies the relationship between genes and the organism. (As an example, see Thompson.[23]) The Selfish Gene further popularised sociobiology in Japan after its translation in 1980.[24] With the addition of Dawkins's book to the country's consciousness, the term "meme" entered popular culture. Yuzuru Tanaka of Hokkaido University wrote a book, Meme Media and Meme Market Architectures, while the psychologist Susan Blackmore wrote The Meme Machine (2000), with a foreword by Dawkins.[25] The information scientist Osamu Sakura has published a book in Japanese and several papers in English on the topic.[24][26][27] Nippon Animation produced an educational television program titled The Many Journeys of Meme. In 1976, the ecologist Arthur Cain, one of Dawkins's tutors at Oxford in the 1960s, called it a "young man's book" (which Dawkins points out was a deliberate quote of a commentator on the New College, Oxford[a] philosopher A. J. Ayer's Language, Truth, and Logic (1936)). Dawkins noted that he had been "flattered by the comparison, [but] knew that Ayer had recanted much of his first book and [he] could hardly miss Cain's pointed implication that [he] should, in the fullness of time, do the same."[2] This point also was made by the philosopher Mary Midgley: "The same thing happened to AJ Ayer, she says, but he spent the rest of his career taking back what he'd written in Language, Truth and Logic. "This hasn't occurred to Dawkins", she says. "He goes on saying the same thing.""[28] However, according to Wilkins and Hull,[29] Dawkins's thinking has developed, although perhaps not defusing this criticism: "In Dawkins's early writings, replicators and vehicles played different but complementary and equally important roles in selection, but as Dawkins honed his view of the evolutionary process, vehicles became less and less fundamental... In later writings Dawkins goes even further and argues that phenotypic traits are what really matter in selection and that they can be treated independently of their being organized into vehicles....Thus, it comes as no surprise when Dawkins proclaims that he "coined the term ‘vehicle’ not to praise it but to bury it."[16] As prevalent as organisms might be, as determinate as the causal roles that they play in selection are, reference to them can and must be omitted from any perspicuous characterization of selection in the evolutionary process. Dawkins is far from a genetic determinist, but he is certainly a genetic reductionist." — John S Wilkins, David Hull, Dawkins on Replicators and Vehicles, The Stanford Encyclopedia of Philosophy Units of selection As to the unit of selection: "One internally consistent logical picture is that the unit of replication is the gene,...and the organism is one kind of ...entity on which selection acts directly."[30] Dawkins proposed the matter without a distinction between 'unit of replication' and 'unit of selection' that he made elsewhere: "the fundamental unit of selection, and therefore of self-interest, is not the species, nor the group, nor even strictly the individual. It is the gene, the unit of heredity."[31] However, he continues in a later chapter: "On any sensible view of the matter Darwinian selection does not work on genes directly. ...The important differences between genes emerge only in their effects. The technical word phenotype is used for the bodily manifestation of a gene, the effect that a gene has on the body...Natural selection favours some genes rather than others not because of the nature of the genes themselves, but because of their consequences—their phenotypic effects...But we shall now see that the phenotypic effects of a gene need to be thought of as all the effects that it has on the world. ...The phenotypic effects of a gene are the tools by which it levers itself into the next generation. All I am going to add is that the tools may reach outside the individual body wall...Examples that spring to mind are artefacts like beaver dams, bird nests, and caddis houses." — Richard Dawkins, The Selfish Gene, Chapter 13, pp. 234, 235, 238 Dawkins's later formulation is in his book The Extended Phenotype (1982), where the process of selection is taken to involve every possible phenotypical effect of a gene. Stephen Jay Gould finds Dawkins's position tries to have it both ways:[32] "Dawkins claims to prefer genes and to find greater insight in this formulation. But he allows that you or I might prefer organisms—and it really doesn't matter." — Stephen Jay Gould, The Structure of Evolutionary Theory, pp. 640-641 The view of The Selfish Gene is that selection based upon groups and populations is rare compared to selection on individuals. Although supported by Dawkins and by many others, this claim continues to be disputed.[33][34] While naïve versions of group selectionism have been disproved, more sophisticated formulations make accurate predictions in some cases while positing selection at higher levels.[35] Both sides agree that very favourable genes are likely to prosper and replicate if they arise and both sides agree that living in groups can be an advantage to the group members. The conflict arises in part over defining concepts: "Cultural evolutionary theory, however, has suffered from an overemphasis on the experiences and behaviors of individuals at the expense of acknowledging complex group organization...Many important behaviors related to the success and function of human societies are only properly defined at the level of groups".[34] In The Social Conquest of Earth (2012), the entomologist E. O. Wilson contends that although the selfish-gene approach was accepted "until 2010 [when] Martin Nowak, Corina Tarnita, and I demonstrated that inclusive fitness theory, often called kin selection theory, is both mathematically and biologically incorrect."[36] Chapter 18 of The Social Conquest of Earth describes the deficiencies of kin selection and outlines group selection, which Wilson argues is a more realistic model of social evolution. He criticises earlier approaches to social evolution, saying: "...unwarranted faith in the central role of kinship in social evolution has led to the reversal of the usual order in which biological research is conducted. The proven best way in evolutionary biology, as in most of science, is to define a problem arising during empirical research, then select or devise the theory that is needed to solve it. Almost all research in inclusive-fitness theory has been the opposite: hypothesize the key roles of kinship and kin selection, then look for evidence to test that hypothesis." According to Wilson: "People must have a tribe...Experiments conducted over many years by social psychologists have revealed how swiftly and decisively people divide into groups, and then discriminate in favor of the one to which they belong." (pp. 57, 59) According to Wilson: "Different parts of the brain have evolved by group selection to create groupishness." (p. 61) Some authors consider facets of this debate between Dawkins and his critics about the level of selection to be blather:[37] "The particularly frustrating aspects of these constantly renewed debates is that, even though they seemed to be sparked by rival theories about how evolution works, in fact they often involve only rival metaphors for the very same evolutionary logic and [the debates over these aspects] are thus empirically empty." — Laurent Keller, Levels of Selection in Evolution, p.4 Other authors say Dawkins has failed to make some critical distinctions, in particular, the difference between group selection for group advantage and group selection conveying individual advantage.[38] Choice of words A good deal of objection to The Selfish Gene stemmed from its failure to be always clear about "selection" and "replication". Dawkins says the gene is the fundamental unit of selection, and then points out that selection does not act directly upon the gene, but upon "vehicles" or '"extended phenotypes". Stephen Jay Gould took exception to calling the gene a 'unit of selection' because selection acted only upon phenotypes.[39] Summarizing the Dawkins-Gould difference of view, Sterelny says:[40] "Gould thinks gene differences do not cause evolutionary changes in populations, they register those changes." —Kim Sterelny: Dawkins vs. Gould, p. 83 The word "cause" here is somewhat tricky: does a change in lottery rules (for example, inheriting a defective gene "responsible" for a disorder) "cause" differences in outcome that might or might not occur? It certainly alters the likelihood of events, but a concatenation of contingencies decides what actually occurs. Dawkins thinks the use of "cause" as a statistical weighting is acceptable in common usage.[41] Like Gould, Gabriel Dover in criticizing The Selfish Gene says:[42] "It is illegitimate to give 'powers' to genes, as Dawkins would have it, to control the outcome of selection...There are no genes for interactions, as such: rather, each unique set of inherited genes contributes interactively to one unique phenotype...the true determinants of selection". — Gabriel Dover: Dear Mr. Darwin, p. 56 However, from a comparison with Dawkins's discussion of this very same point, it would seem both Gould's and Dover's comments are more a critique of his sloppy usage than a difference of views.[37] Hull suggested a resolution based upon a distinction between replicators and interactors.[43] The term "replicator" includes genes as the most fundamental replicators but possibly other agents, and interactor includes organisms but maybe other agents, much as do Dawkins's 'vehicles'. The distinction is as follows:[43][44] replicator: an entity that passes on its structure largely intact in successive replications. interactor: an entity that interacts as a cohesive whole with its environment in such a way that this interaction causes replication to be differential. selection: a process in which the differential extinction or proliferation of interactors causes the differential perpetuation of the replicators that produced them. Hull suggests that, despite some similarities, Dawkins takes too narrow a view of these terms, engendering some of the objections to his views. According to Godfrey-Smith, this more careful vocabulary has cleared up "misunderstandings in the "units of selection" debates."[44] Enactive arguments Behavioural genetics entertains the view: "that genes are dynamic contributors to behavioral organization and are sensitive to feedback systems from the internal and external environments." "Technically behavior is not inherited; only DNA molecules are inherited. From that point on behavioral formation is a problem of constant interplay between genetic potential and environmental shaping"[45] —D.D. Thiessen, Mechanism specific approaches in behavior genetics, p. 91 This view from 1970 is still espoused today,[46][47] and conflicts with Dawkins's view of "the gene as a form of "information [that] passes through bodies and affects them, but is not affected by them on its way through"".[48] The philosophical/biological field of enactivism stresses the interaction of the living agent with its environment and the relation of probing the environment to cognition and adaptation. Gene activation depends upon the cellular milieu. An extended discussion of the contrasts between enactivism and Dawkins's views, and with their support by Dennett, is provided by Thompson.[49] In Mind in Life, the philosopher Evan Thompson has assembled a multi-sourced objection to the "selfish gene" idea.[49] Thompson takes issue with Dawkin's reduction of "life" to "genes" and "information": "Life is just bytes and bytes and bytes of digital information"[50] — Richard Dawkins: River out of Eden: A Darwinian View of Life, p. 19 "On the bank of the Oxford canal...is a large willow tree, and it is pumping downy seeds into the air...It is raining instructions out there; it's raining programs; it's raining tree-growing, fluff-spreading algorithms. That is not a metaphor, it is the plain truth"[51] — Richard Dawkins: The Blind Watchmaker, p. 111 Thompson objects that the gene cannot operate by itself, since it requires an environment such as a cell, and life is "the creative outcome of highly structured contingencies". Thompson quotes Sarkar:[47] "there is no clear technical notion of "information" in molecular biology. It is little more than a metaphor that masquerades as a theoretical concept and ...leads to a misleading picture of the nature of possible explanations in molecular biology." — Sahotra Sarkar Biological information: a skeptical look at some central dogmas of molecular biology, p. 187 Thompson follows with a detailed examination of the concept of DNA as a look-up-table and the role of the cell in orchestrating the DNA-to-RNA transcription, indicating that by anyone's account the DNA is hardly the whole story. Thompson goes on to suggest that the cell-environment interrelationship has much to do with reproduction and inheritance, and a focus on the gene as a form of "information [that] passes through bodies and affects them, but is not affected by them on its way through"[52] is tantamount to adoption of a form of material-informational dualism that has no explanatory value and no scientific basis. (Thomson, p. 187) The enactivist view, however, is that information results from the probing and experimentation of the agent with the agent's environment subject to the limitations of the agent's abilities to probe and process the result of probing, and DNA is simply one mechanism the agent brings to bear upon its activity. Moral arguments Another criticism of the book is its treatment of morality, and more particularly altruism, as existing only as a form of selfishness: "It is important to realize that the above definitions of altruism and selfishness are behavioural, not subjective. I am not concerned here with the psychology of motives...My definition is concerned only with whether the effect of an act is to lower or raise the survival prospects of the presumed altruist and the survival prospects of the presumed beneficiary." — Richard Dawkins, The Selfish Gene, p. 12 "We can even discuss ways of cultivating and nurturing pure, disinterested altruism, something that has no place in nature, something that has never existed before in the whole history of the world." — Richard Dawkins, The Selfish Gene, p. 179 The philosopher Mary Midgley has suggested this position is a variant of Hobbes's explanation of altruism as enlightened self-interest, and that Dawkins goes a step further to suggest that our genetic programming can be overcome by what amounts to an extreme version of free will.[53] Part of Mary Midgley's concern is that Richard Dawkins's account of The Selfish Gene serves as a moral and ideological justification for selfishness to be adopted by modern human societies as simply following "nature", providing an excuse for behavior with bad consequences for future human society. Dawkins's major concluding theme, that humanity is finally gaining power over the "selfish replicators" by virtue of their intelligence, is criticized also by primatologist Frans de Waal, who refers to it as an example of a "veneer theory" (the idea that morality is not fundamental, but is laid over a brutal foundation).[54] Dawkins claims he merely describes how things are under evolution, and makes no moral arguments.[55][56] On BBC-2 TV, Dawkins pointed to evidence for a "Tit-for-Tat" strategy (shown to be successful in game theory[57]) as the most common, simple, and profitable choice.[58] More generally, the objection has been made that The Selfish Gene discusses philosophical and moral questions that go beyond biological arguments, relying upon anthropomorphisms and careless analogies.[59] The Selfish Gene was first published by Oxford University Press in 1976 in eleven chapters with a preface by the author and a foreword by Robert Trivers.[60] A second edition was published in 1989. This edition added two extra chapters, and substantial endnotes to the preceding chapters, reflecting new findings and thoughts. It also added a second preface by the author, but the original foreword by Trivers was dropped. The book contains no illustrations. The book has been translated into at least 23 languages including Arabic, Thai and Turkish.[61] In 2006, a 30th-anniversary edition[20] was published with the Trivers foreword and a new introduction by the author in which he states, "This edition does, however---and it is a source of particular joy to me---restore the original Foreword by Robert Trivers." This edition was accompanied by a festschrift entitled Richard Dawkins: How a Scientist Changed the Way We Think (2006). In March 2006, a special event entitled The Selfish Gene: Thirty Years On was held at the London School of Economics.[62] In March 2011, Audible Inc published an audiobook edition narrated by Richard Dawkins and Lalla Ward. In 2016, Oxford University Press published a 40th anniversary edition with a new epilogue, in which Dawkins describes the continued relevance of the gene's eye view of evolution and states that it, along with coalescence analysis "illuminates the deep past in ways of which I had no inkling when I first wrote The Selfish Gene...."[63] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Selfish_Gene |
レセプション 利己的な遺伝子』は出版当時、「生物学に静かな、そしてほとんど即座の革命」を引き起こし[19]、絶大な人気を博した。支持者たちは、遺伝子の複製が淘 汰の対象であるという中心的な論点は、遺伝学の基本的なメカニズムが理解される前にチャールズ・ダーウィンが行った進化の説明を有益に補完し、拡張するも のだと主張する。 民族学者のアラン・グラフェンによれば、数学的な統一理論がないことと、言葉だけでは何でも疑わしいと思われることが、適応主義理論の受容を妨げている。 「比較心理学者のニッキー・ヘイズによれば、「ドーキンスは、動物行動から引き出されたメタファーに大きく依存し、それらを外挿した社会生物学のバージョ ンを提示した。ドーキンスはこの伝統から逸脱していない」[22]。より一般的には、『利己的な遺伝子』は遺伝子と生物の関係を単純化しすぎていると批判 する。(その例として、トンプソンを参照。 1980年に『利己的な遺伝子』が翻訳されると、日本では社会生物学がさらに一般化した[24]。北海道大学の田中譲は『ミーム・メディアとミーム・マー ケット・アーキテクチャ』という本を書き、心理学者のスーザン・ブラックモアはドーキンスの序文とともに『ミーム・マシーン』(2000年)を書いた [25]。 情報科学者の佐倉統は、このトピックに関する日本語の本と英語の論文を出版した[24][26][27]。 日本アニメーションは『ミームの旅』という教育テレビ番組を制作した。 1976年、1960年代にオックスフォード大学でドーキンスの家庭教師の一人であった生態学者のアーサー・ケインは、この本を「若者の本」と呼んだ(こ れはオックスフォード大学ニューカレッジ[a]の哲学者A.J.エアの『言語、真理、論理』(1936年)の解説者の言葉を意図的に引用したものであると ドーキンスは指摘している)。ドーキンスは、「比較されたことに光栄に思ったが、エイヤーが最初の著書の多くを撤回したことを知っていた: 同じことがAJ Ayerにも起こったが、彼は『言語、真理、論理』で書いたことを撤回することに残りのキャリアを費やしたと彼女は言う。「ドーキンスはこのことに気づか なかった。「しかし、ウィルキンスとハルによれば[29]、ドーキンスの思考は、おそらくこの批判を打ち消すまでには至らないものの、発展している: 「ドーキンスの初期の著作では、複製体と輸送体は淘汰において異なるが相補的で等しく重要な役割を果たしたが、ドーキンスが進化の過程についての見解を磨 くにつれて、輸送体は基本的なものではなくなっていった...。後の著作では、ドーキンスはさらに踏み込んで、表現型形質こそが選択において本当に重要な ものであり、それらはビークルに組織化されることとは無関係に扱うことができると主張している......したがって、ドーキンスが「『ビークル』という 言葉を作ったのは、それを賞賛するためではなく、それを葬り去るためである」と宣言しても驚くにはあたらない。 「生物が淘汰において果たす因果的役割が決定的に重要であるのと同様に、進化過程における淘汰の明確な特徴付けからは、生物への言及は省くことができる し、省かなければならない。ドーキンスは遺伝的決定論者からは程遠いが、遺伝的還元論者であることは確かである」。 - ジョン・S・ウィルキンス、デビッド・ハル、ドーキンス、複製者と乗り物、スタンフォード哲学百科事典 淘汰の単位 淘汰の単位について 複製単位は遺伝子であり、...生物は淘汰が直接作用する一種の...実体である」[30] ドーキンスは、他の場所で行った「複製単位」と「淘汰単位」の区別なしに、この問題を提案した: 「選択の基本的な単位、したがって利己的な単位は、種でも、集団でも、厳密には個人でもない。それは遺伝子であり、遺伝の単位である」[31] : 「ダーウィンの淘汰は遺伝子には直接作用しない。遺伝子間の重要な違いは、その影響においてのみ現れる。自然淘汰が他の遺伝子よりある遺伝子を好むのは、 遺伝子そのものの性質によるのではなく、その結果、つまり表現型効果によるのである。...遺伝子の表現型効果とは、その遺伝子が次の世代に自分自身を残 すための道具なのである。ビーバーのダム、鳥の巣、カダヤシの家などの人工物がその例である。 - リチャード・ドーキンス『利己的な遺伝子』第13章、234、235、238頁 ドーキンスが後に定式化したのは著書『拡張された表現型』(1982年)であり、そこでは淘汰の過程は遺伝子のあらゆる表現型的影響に関与するとされてい る。 スティーヴン・ジェイ・グールドは、ドーキンスの立場は両論併記を試みていると考えている[32]。 「ドーキンスは遺伝子を好み、この定式化により大きな洞察を見出すと主張している。しかし彼は、あなたや私が生物を好むかもしれないことを認めている。 - スティーヴン・ジェイ・グールド『進化論の構造』640-641頁 利己的な遺伝子』の見解は、集団や個体群に基づく淘汰は、個体に対する淘汰に比べて稀であるというものである。ドーキンスや他の多くの人々によって支持さ れているが、この主張には論争が続いている[33][34]。集団選択論のナイーブなバージョンは反証されているが、より洗練された定式化は、より高いレ ベルでの選択を仮定しながら、場合によっては正確な予測を行う[35]。対立は概念の定義をめぐって生じている: 「しかし、文化進化論は、複雑な集団組織を認めることを犠牲にして、個人の経験や行動を過度に強調することに苦しんできた......人間社会の成功と機 能に関連する多くの重要な行動は、集団のレベルにおいてのみ適切に定義される」[34]。 昆虫学者のE.O.ウィルソンは『The Social Conquest of Earth』(2012年)の中で、利己的遺伝子のアプローチは「2010年までは受け入れられていたが、マーティン・ノワック、コリーナ・タルニタ、そ して私は、しばしば親族選択理論と呼ばれる包括的適合性理論が数学的にも生物学的にも間違っていることを証明した」と主張している。彼は社会進化に対する 以前のアプローチを批判し、次のように述べている: 「社会進化における親族関係の中心的役割に対する不当な信頼が、生物学的研究の通常の順序を逆転させた。ほとんどの科学がそうであるように、進化生物学に おいても、実証的研究の中で生じた問題を定義し、それを解決するために必要な理論を選択・考案することが、最善の方法であることが証明されている。親族関 係や親族選択の重要な役割について仮説を立て、その仮説を検証する証拠を探すのである。ウィルソンによれば、「人は部族を持たなければならな い......社会心理学者が長年にわたって行ってきた実験によって、人がいかに迅速かつ決定的に集団に分かれ、そして自分が属する集団に有利な差別を行 うかが明らかになった」(57、59ページ)。(57、59頁) ウィルソンによれば、「脳のさまざまな部分が、集団淘汰によって進化し、集団性を生み出してきた」のである。(p. 61) 淘汰のレベルに関するドーキンスと彼の批評家たちとの間のこの論争の一面を、くだらないものだと考える著者もいる[37]。 "このような絶え間なく更新される論争の特にいらだたしい点は、進化がどのように機能するかについての対立理論に端を発しているように見えても、実際に は、まったく同じ進化の論理に対する対立的な比喩にすぎないことが多く、[このような側面をめぐる論争は]経験的に空虚であるということである。" - ローラン・ケラー『進化における淘汰のレベル』p.4 他の著者によれば、ドーキンスはいくつかの重要な区別、特に集団の優位性のための集団淘汰と個人の優位性を伝える集団淘汰の違いを区別できていない [38]。 言葉の選択 利己的な遺伝子』に対する多くの反論は、「選択」と「複製」について常に明確にしていないことに起因している。ドーキンスは遺伝子が淘汰の基本的な単位で あるとした上で、淘汰は遺伝子に直接作用するのではなく、「乗り物」や「拡張された表現型」に作用すると指摘している。スティーヴン・ジェイ・グールド は、選択が表現型にのみ作用するので、遺伝子を「選択の単位」と呼ぶことに異論を唱えた[39]。ドーキンスとグールドの見解の違いを要約して、ステレル ニーは次のように述べている[40]。 「グールドは遺伝子の違いが集団の進化的変化を引き起こすのではなく、その変化を登録すると考えている。 -キム・ステレニー ドーキンス対グールド、p. 83 抽選ルールの変化(例えば、障害の「原因」である欠陥遺伝子を受け継ぐこと)は、起こるかもしれない、あるいは起こらないかもしれない結果の違いを「引き 起こす」のだろうか?確かに起こりうる可能性は変わるが、実際に何が起こるかは偶発的な出来事の積み重ねが決めるのである。ドーキンスは統計的な重み付け としての「原因」の使用は一般的な用法として受け入れられると考えている[41]。グールドと同様に、ガブリエル・ドーバーも『利己的な遺伝子』を批判し て次のように述べている[42]。 ドーキンスが言うように、淘汰の結果をコントロールするために遺伝子に "力 "を与えることは非合法である。相互作用のための遺伝子など存在しない。むしろ、遺伝した遺伝子のそれぞれのユニークなセットが、一つのユニークな表現型 に相互作用的に寄与するのである。 - ガブリエル・ドーバー 親愛なるダーウィン、p. 56 しかし、この全く同じ点に関するドーキンスの議論と比較すると、グールドのコメントもドーバーのコメントも、見解の相違というよりは、彼のずさんな用法に 対する批判であるように思われる[37]。ハルは複製者と相互作用者の区別に基づく解決策を提案している[43]。その区別は以下の通りである[43] [44]。 複製者:連続的な複製においてその構造をほぼそのまま受け継ぐ実体。 相互作用体:環境と凝集体として相互作用し、その相互作用によって複製に差異が生じるような実体。 淘汰:相互作用体の差次的な消滅や増殖が、それを生み出した複製体の差次的な存続を引き起こす過程。 ハルは、いくつかの類似点があるにもかかわらず、ドーキンスはこれらの用語をあまりにも狭くとらえすぎており、それが彼の見解に対する反論のいくつかを生 んでいると指摘している。Godfrey-Smithによれば、このようにより注意深い語彙は、「『淘汰の単位』論争における誤解」を解いている [44]。 能動的な議論 行動遺伝学では、次のような見解がある: 「遺伝子は行動構成にダイナミックに寄与し、内的・外的環境からのフィードバックシステムに敏感である。「厳密には行動は遺伝しない。遺伝するのはDNA 分子だけである。その点から、行動形成は遺伝的可能性と環境形成との間の絶え間ない相互作用の問題である」[45]。 -D.D.ティッセン『行動遺伝学におけるメカニズム特異的アプローチ』p.91 1970年からのこの見解は今日でも支持されており[46][47]、ドーキンスの「遺伝子は "情報 "の一形態であり、身体を通過し、身体に影響を与えるが、通過する途中で身体から影響を受けることはない」という見解と対立している[48]。遺伝子の活 性化は細胞環境に依存している。トンプソン(Thompson)[49]は、アクエンティヴィズムとドーキンス(Dawkins)の見解の対比について、 またデネット(Dennett)によるその支持について、幅広く論じている。 生命の中の心』の中で、哲学者のエヴァン・トンプソンは「利己的な遺伝子」という考えに対する複数のソースによる反論を組み立てている: 「生命はデジタル情報のバイト、バイト、バイトにすぎない」[50]。 - リチャード・ドーキンス エデンの河 ダーウィンの生命観, p. 19 「オックスフォード運河の土手には...大きな柳の木があり、綿毛のような種を空中に送り出している。それは比喩ではなく、明白な真実だ」[51]。 - リチャード・ドーキンス 盲目の時計職人』111ページ トンプソンは、遺伝子は細胞のような環境が必要であり、生命は「高度に構造化された偶発性の創造的な結果」であるため、遺伝子単体では活動できないと反論 している。トンプソンはサルカーの言葉を引用している[47]。 「分子生物学には「情報」という明確な技術的概念はない。それは理論的概念の仮面をかぶった比喩にすぎず、分子生物学において可能な説明の性質について誤 解を招くような図式を導くものである」。 - サホトラ・サルカー 生物学的情報:分子生物学のいくつかの中心的教義に対する懐疑的な見方 187頁 続いてトンプソンは、ルックアップテーブルとしてのDNAの概念と、DNAからRNAへの転写を指揮する細胞の役割について詳細に検討し、誰が考えても DNAがすべてではないことを示している。トンプソンはさらに、細胞と環境の相互関係は生殖と遺伝に大きく関係しており、遺伝子を「身体を通過し、身体に 影響を与えるが、通過する途中で身体から影響を受けることはない情報」[52]の一形態として注目することは、説明的価値も科学的根拠もない物質-情報二 元論の採用にも等しいと指摘する。(Thomson、187頁) しかし、enactivistの見解は、情報は、エージェントの環境に対するエージェントの探索と実験から生じるものであり、探索の結果を処理するエー ジェントの能力の限界に従うというものであり、DNAは、エージェントがその活動にもたらすメカニズムの一つに過ぎないというものである。 道徳的議論 この本に対するもう一つの批判は、道徳、特に利他主義を利己主義の一形態としてのみ存在するものとして扱っていることである: 「上記の利他主義と利己主義の定義は、主観的なものではなく、行動学的なものであることを理解することが重要である。私の定義は、ある行為の効果が、利他 主義者と受益者と思われる人物の生存の見込みを下げるか上げるかということだけに関係している。 - リチャード・ドーキンス『利己的な遺伝子』12ページ 「自然界には存在しないものであり、世界の全歴史においてかつて存在したことのないものである。 - リチャード・ドーキンス『利己的な遺伝子』179頁 哲学者のメアリー・ミッドグリーは、この立場はホッブズの利他主義を啓蒙された利己主義として説明することの変形であり、ドーキンスはさらに一歩進んで、 私たちの遺伝的プログラミングは極端な自由意志のバージョンに相当するものによって克服することができると示唆している[53]。メアリー・ミッドグリー の懸念の一部は、リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』の説明が、利己主義が単に「自然」に従うものとして現代の人間社会で採用されることを道徳 的・イデオロギー的に正当化し、将来の人間社会に悪い結果をもたらす行動の言い訳を提供することである。 ドーキンスの主要な結論テーマである、人類はその知性によって「利己的な複製者」に対して最終的に力を得ているという説は、霊長類学者であるフランズ・ デ・ワールからも批判されており、彼はこれを「ベニヤ理論」(道徳は基本的なものではなく、残忍な土台の上に築かれたものであるという考え方)の一例と呼 んでいる。 [54]ドーキンスは、進化のもとで物事がどのようにあるのかを説明しているだけであり、道徳的な議論はしていないと主張している[55][56]。 BBC-2 TVで、ドーキンスは「Tit-for-Tat」戦略(ゲーム理論で成功することが示されている[57])が最も一般的で単純で有益な選択であるという証 拠を指摘している[58]。 より一般的には、『利己的な遺伝子』は生物学的な議論を超えた哲学的・道徳的な問題を論じており、擬人化や不注意な類推に頼っているという反論がなされて いる[59]。 利己的な遺伝子』は1976年にオックスフォード大学出版局から11章構成で初版が発行され、著者による序文とロバート・トリヴァースによる序文が添えら れた[60]。この版では、2つの章が追加され、新しい知見や考えを反映して、前の章にかなりの注釈が加えられた。また、著者による第二の序文が追加され たが、当初のトリヴァースによる序文は削除された。図版はない。 この本はアラビア語、タイ語、トルコ語を含む少なくとも23の言語に翻訳されている[61]。 2006年、30周年記念版[20]が出版され、トリヴァースの序文と著者による新しい序文が加えられた。この版には、『リチャード・ドーキンス:科学者 はいかにわれわれの考え方を変えたか』(2006年)と題された祝辞が添えられている。2006年3月、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで『利己 的な遺伝子:30年後』と題した特別イベントが開催された[62]。2011年3月、オーディブル社がリチャード・ドーキンスとララ・ワードのナレーショ ンによるオーディオブック版を出版。 2016年、オックスフォード大学出版局は新たなエピローグを加えた40周年記念版を出版し、その中でドーキンスは遺伝子の目による進化観の継続的な妥当 性について述べ、合体分析とともに「『利己的な遺伝子』を最初に書いたときにはまったく想像もつかなかったような方法で、深い過去を照らし出している」と 述べている[63]。 |
| Endless Forms Most Beautiful Non-cooperative game Selfish DNA Evolutionarily stable strategy Green-beard effect |
|
| 日本語ウィキペディアからの情報→ |
利己的遺伝子論(りこてきいでんしろん)と は、進化学における比喩表現および理論の一つで、自然選択や生物進化を遺伝子中心の視点で理解すること 。遺伝子選択説もほぼ同じものを指す。1970年代の血縁選択説、社会生物学の発展を受けてジョージ・ウィリアムズ、E・O・ウィルソンらによって提唱さ れた。イギリスの動物行動学者リチャード・ドーキンスが1976年に、『The Selfish Gene』(邦題『利己的な遺伝子』)で一般向けに解説したことが広く受け入れられるきっかけとなったため、ドーキンスは代表的な論者と見なされるように なった。 |
| 個体の行動は、その個体の中にある遺伝子によって支配されている。ある
利他的行動が集団の中で増えるということはその行動を支配する遺伝子が増えたことを意味する。ここでいう遺伝子とは、個々のDNA片のすべてのコピーのこ
とである。遺伝子の目的は、自分のコピーを遺伝子プール内に増やすことであり、遺伝子は他の個体を助けることによって、その個体の中にある自分のコピーを
助けることが出来る。これは、個体のレベルで見れば利他的行動だろうが、実質的には遺伝子による利己的行動である。[4] |
個体としての利他主義、遺伝子としての利己主義 ここでは「利己的」とは「自己の成功率(生存と繁殖率)を他者よりも高 めること」と定義される。「利他的」とは「自己の成功率を損なってでも他者の成功率を高めること」と定義される。これらの用語は日常語の「利己」のように 行為者の意図やもくろみを表す言葉ではなく、行動自体をその結果のみに基づいて分類するための用語である。行為者がどのような意図を持っていようとも、行 為の結果が自己の成功率を高めるのであれば、それは「姿を変えた利己主義」と考えることができる。[1] |
| 遺伝子中心で考えると理解がたやすいのは、ミツバチの働きバチなど、社
会性昆虫における不妊階層がみせる利他的な行動である。自らは子孫を残さずひたすら女王バチに献身する働きバチの行動に、どのような進化的利益があるの
か?遺伝子中心の立場からはこう説明できる。働きバチの持つ遺伝子(母親の手助け行動をとらせる遺伝子も含む)にとって、働きバチ自身が繁殖をし50%だ
け自分の遺伝子を持った子を作るよりも、女王バチの繁殖を助けて75%の共通遺伝子を持つ妹を育てることが、遺伝子のコピーを効率的に増やすことになるの
である(血縁選択説#社会性昆虫への適用を参照)。つまり働きバチの行動は個体としては利他的だが、遺伝子にとっては利己的なのである。 |
個体レベルでの自然選択に注目すると、きびしい生存競争の中でわずかで も利他的な行動をとる個体は、そうでない個体よりも平均して「うまくやっていけない」と予測できる。全ての個体が利他的であれば、その群に属するもの達は 非常に上手くやっていけるであろうが、中に一個体でも利己的な個体が混入すれば、利他的個体を食い物にして繁栄するであろう。利己的個体は多くの子を残 し、次第に利己的な個体は数を増していくであろう。他集団からの移住や、突然変異など利己的な個体の混入をふせぎ続けることは不可能である(進化的に安定 な戦略も参照)。 |
| 動物がとる明らかに利己的な行動の例としては、南極のペンギンがあげら
れる。彼らは氷棚の上で海面を見つめて長時間じっとしていることがある。これは天敵のアザラシが海中にいないか覗っているのである。そのうち待ちきれなく
なると、押し合いをして他の個体を海に突き落とそうとまでする。もし率先して飛び込む「利他的」な個体がいれば、彼の中の「利他的遺伝子」と共に真っ先に
食べられてしまう可能性が高いだろう。この場合利益を受けるのは他の個体である。真っ先に飛び込まない性質、真っ先に飛び込まない遺伝子が利益を享受す
る。よりよく知られている例としては、カマキリの共食いがある。カマキリは動くものは何でも食べる習性あり、メスのカマキリは交尾の前や最中、後に交尾の
相手のカマキリを食べようとする。カマキリオスは頭部がなくなると生殖能力が上昇するので、メスのカマキリは、オスを食べることによる食物の獲得ととも
に、生殖の成功率を上げることができる。この場合のカマキリのメスは自分の利益を上昇させると同時に相手の利益を減少させるという点で利己的である。さら
に他の例として、ユリカモメの例がある。ユリカモメの雛は小さく、他の鳥がひとのみにできてしまうほどである。ユリカモメは大きなコロニーを作り、一つの
巣と他の巣はわずか数十センチしか離れていない。ある親鳥は他の巣の親鳥が巣を離れた際にその巣のひな鳥を食べてしまうことがある。[5] |
しかし、現実の自然界では、子育て行為や群れの中での役割分担など多く
の利他的行動と考えられる例も見られる。この事実は、一見すると自然選択説の予想と矛盾するように感じられる。 ドーキンスをはじめとする遺伝子選択論者は、選択や淘汰は実質的には遺伝子に対して働くものと考え[2]、利他的行動が自然界に存在しうる理由を以下のよ うに説明した。 ある遺伝子Aに促された行動は、自ら損害を被っても同じ遺伝子Aを持つ他の個体を助ける性質があると仮定する。これは個体レベルで見れば利他的行動であ る。 その行動による個体の損失より遺伝子Aを持つ個体全体が受ける利益が大きいなら、遺伝子Aは淘汰を勝ち抜き、遺伝子プール中での頻度を増していくと考えら れる。 結果として、遺伝子Aに促された利他的行動も広く見られるようになる。 遺伝子Aは繁殖率が高いので利己的と言える。すなわち、個体の利他的行 動も遺伝子の利己性に基づいた行動として説明される。他の個体がある遺伝子を持っているかを直接見極めることは野生動物には不可能である。ドーキンスは、 実際の動物の行動は同一遺伝子を持つ確率に関係する事柄に基づいていると考えており、同一遺伝子を持つ確率が高い例として、外見の特徴の類似、血縁関係の 強い群れのメンバー同士であること、そもそも出会う相手が血縁者である確率が高い種(個体があまり移動しない種や小群で行動する種)の場合は相手が同種で あること自体などを挙げている。[3] |
| 利他主義による利益:遺伝子が他の体に宿る自分自身のコピーへの援助
を、個体レベルの利他的行動で行うことは前述の通りだが、実際にはどのようにして自身のコピーが宿る個体を見分けるのだろうか。また、どの程度の利他的行
動が遺伝子にとって利益を最大にするのだろうか。人間のアルビノ(先天性色素欠乏症)について考えると、アルビノの遺伝子は劣性であり、この遺伝子は他の
アルビノの個体を助けるように、自分の宿っている体をプログラミングすることによって自身のコピーを助けることが出来る。この場合、肌が白いというアルビ
ノの形質は、遺伝子がその個体にアルビノに関する遺伝子を持っているかを見分けるのに役に立つ。このようにしてアルビノの遺伝子は助け合うのだが、実際に
アルビノの個体同士は助け合って生きているわけではない。アルビノの遺伝子は、他のアルビノ遺伝子を助けたいという意志はもっていない。遺伝子に意志はな
いのである。だが、アルビノの遺伝子が、他のアルビノの個体を助けるように、自分のいる体を促すという性質を持っているなら、この遺伝子は遺伝子プール内
で増えていくはずである。そのためには、アルビノが体に白い肌を与えるという効果と、他の肌の白い個体を助けるといった二つの独立した効果を持っていなけ
ればならない。アルビノの個体が、ある他の個体に自分のコピーである遺伝子があるかどうかを見極めるには二つの方法がある。一つは、前述のアルビノ、また
えんどう豆のひげの色やショウジョウバエの目の色とった外見に表れる形質である。そしてもう一つは、血縁である。[6] |
個体としての利他主義によって遺伝子の受ける利益 |
| 遺伝子の近縁度:遺伝子の利他的行動の利益の計算に必要な近縁度とは、
二人の親類がひとつの遺伝子を共有している確率である。ここでは、話を簡潔にするために遺伝子Xについての近縁度を見ていく。ある個体が遺伝子Xを持って
いたとしてその個体の姉がXを持っている確率は50%である。ある個体がXのコピーを一つ持っていたとして、それはその個体の父親か母親のどちらかから受
け取っているはずである。このXを父親から受け取ったとすると、父親の体細胞のすべてはXを一つ持っており、精子を作るときには父親の全遺伝子の半分が精
子に入るので、姉がXを受け取っている確率は50%である。母親のときも同じように50%の確率で姉はXを受け取っている。これは、ある個体に100人の
兄弟がいればそのうちの約50人はXを持っており、また、ある個体が100個の珍しい遺伝子を持っていればそのうちの約50個を兄弟が持っているというこ
とでもある。先ほどの例の兄弟の場合は1/2である。近縁度の計算には、まず世代間隔を数える必要がある。世代間隔を求めるためにはまずAとBの共通の祖
先を見つけ出す。そして、Aから共通の祖先まで世代を遡り、再びBまで世代を下ることで得られる。AがBの叔父であるなら世代間隔は3である。AとBの近
縁度を求めるには世代ごとに1/2を掛けていけばいい。AとBが叔父と甥の関係ならば近縁度は(1/2)3である。なお、これはAB間の血縁度の一部であ
る。二人に共通の祖先が複数人いる場合には先ほどの近縁度に共通の祖先の人数をかける。いとこ同士には共通の祖先が二人いる(祖父と祖母)。いとこの世代
間隔は4なので近縁度は2×(1/2)4=1/8である。 |
|
| 近縁度の計算が出来たら、利他的行動の利益についてより正確に理解でき
るようになる。5人のいとこ(近縁度=1/8)を救うために命を捨てる遺伝子は増えていかないだろうが、5人の兄弟(近縁度=1/2)か10人のいとこを
救うために命を投げ出す遺伝子は増えていくだろう。この遺伝子は平均として利益の受益者の中で行き続けることができるからである。ここでは個体間の近縁度
を計算によって求めたが、自然の中で動物がそのように近縁度を計算することはない。しかし、人間が放り投げた玉の放物線の軌道を、複雑な微分方程式なしに
予測して玉をキャッチできるように、動物は複雑な計算をしているがごとく血縁者の利益のために行動する。そのように遺伝子はプログラミングされているので
ある。[7] |
|
| 生物個体が実際に遺伝子の利益になるように利他的行動をとるのは、前述
のような対数による計算を行っているのではなく、遺伝子によってあたかも対数による計算の結果に従っているかのようにふるまうようにプログラムされている
からである。生物が行動の基準とする賞味の利益の方法は例えば次のようなものである。 行動パターンの正味の利益=自分の利益-自分の危険+兄弟の利益の1/2-兄弟の危険の1/2+ いとこの利益の1/8-いとこの危険の1/8+他のいとこの利益の1/8-他のいとこの危険の1/8・・・・ 生物は、遺伝子の利益が最大になるように、この合計結果が最大になるように行動するものと考えられる。ここで、食料に関する利他主義の利益の例を見てみよ う。例えば、ある個体Cがキノコを3個見つけたとする。近くには弟といとこがいる。キノコ1個を食べたときの利益を5とすると、キノコ3個を独り占めした ときの利益は5×3=15である。では、弟といとこを呼ぶとどうなるだろうか。Cの中にある遺伝子が受け取る利益は、自分で食べた分が5×1=5、弟の食 べた分の利益が5×1×1/2=5/2、いとこの食べた分の利益が5×1×1/8=5/8である。よって、行動パターンの正味の利益は65/8で、ひとり で食べた場合の15に劣る。この場合は弟といとこを呼ばないほうが良いことになる。これは、かなり単純化した例であって、実際には個体本体の空腹状態など 様々な要因が絡んでくる。[8] |
|
| 進化は自然淘汰によって進み、淘汰は最適者に利益をもたらす。では、こ
の場合の最適者とは何を指すのだろうか。最適個体のことか、最適品種のことか、あるいは最適種のことだろうか。淘汰が種や集団に働くのだとすれば、各個体
が種や集団の他の個体の利益のために自分を犠牲にしている種や集団は、繁栄する確率が高いだろう。したがって、このような種や集団によって地球は占められ
ていくことになる。これが群淘汰説である。もう一つの一般的な説が、個体淘汰あるいは遺伝子淘汰と呼ばれるものである。この本の中では、著者は個体淘汰あ
るいは遺伝子淘汰の支持者であり、遺伝子淘汰説という呼び方の方を好んでいる。[9]実際に長い進化の時間の中で生きたり死んだりするのは個体である。し
かし個体は一時的な存在である。たとえばガゼルの群れの中に警戒心が強い個体と、足の速い個体が生まれたとする。この二個体は生き延びるのに有利で、多く
の子孫を残し、繁栄すると考えられる。何世代も経った後、そのガゼルの群れは強い警戒心と足の速さを持つ個体ばかりになっているだろう。このとき、数を増
やしたと言えるのは、警戒心が強い個体でも足の速い個体でもない。警戒心の強さと足の速さという形質、そしてそれに影響を与える一連の遺伝子である。有性
生殖する生物では個体は一世代のみのユニークな存在である。彼らが子孫を残す時、彼らの体を作っていた遺伝子はばらばらにされ、混ぜ合わされて子に伝えら
れる。また、個体の表現型は遺伝要因と環境要因の相互作用によって作られるため、そのまま子に伝わるわけではない。いっぽう遺伝子一つ一つはより長い時間
存在することができる。つまり、進化の営みの中で、数を増やしたり、減らしたりする実質的な単位は遺伝子と言える。このことは、生物の起源をさかのぼるこ
とで理解することが出来る。生命の誕生以前の地球には水、二酸化炭素、メタン、アンモニアなどの単純な化合物があった可能性が高い。これらの物質を、フラ
スコに入れ紫外線や電気花火などのエネルギー源を2週間ほど与え続けることでアミノ酸を作ることが出来る。さらに、実験室での原始の地球を模した実験では
プリンやピリミジンといった有機物を作ることにも成功している。これらはDNAの構成物質である。[10]原始の地球において長い時間をかけて発生したア
ミノ酸やタンパク質は海や水溜りの中で凝集していきより大きな分子となっていった。ある時点で自分の複製を作れる特異的な分子が発生した。それが自己複製
子であり、DNAである。この自己複製子が漂っている周りには複製子の構成分子も漂っていた。構成分子は自分と同じものと親和性があったので、元のDNA
に同じ順序で結合していきDNAは複製されることとなった。その後、自己複製子のある水溜りは生産性、寿命、複製の正確性が優れている自己複製子によって
占められていくようになった。ある自己複製子は自分の回りをタンパク質で囲むようになり、この自己複製子はそのおかげで他の自己複製子よりも安定になり、
プールの中でより大きな割合を占めるようになっていった。現在の生物の個体とは、このDNAの周りを囲むタンパク質が長い時間の進化を経て複雑に、高度に
なったものである。したがって、進化の単位は個体ではなく、個体の中にある遺伝子に働くものと考えられる。[11] |
選択の単位としての遺伝子 |
| 群選択説や古典的自然選択説である個体選択説では、種のための個体、個
体のための遺伝子という考え方をするが、一連の利己的遺伝子論ではこれを逆転して考える。遺伝子は自らのコピーを残し、その過程で生物体ができあがるとい
う考え方である。つまり、我々人間を含めた生物個体は遺伝子が自らのコピーを残すために一時的に作り出した「乗り物」に過ぎないということになる。コピー
を残す効率に優れた「乗り物」を作り出せる遺伝子が、結果として今日まで存続してきたと言えることになるのである。 重要なのは、進化で中心的な役割を果たすのは種や個体の存続ではなく、遺伝子そのものの残りやすさとした点にある。個体の系統や種の存続はその結果にすぎ ない。生存・自己複製の究極的な単位は個体ではなく個別の遺伝子であるとし、個体内でも遺伝子同士の相克があると考える。 |
生存機械論 |
| 1960年から70年代の進化生物学における重要な論争の一つは、自然
選択が働く単位は何か?であった。自然選択の定義に照らせば、自然選択を受ける実体は常に利己的である。なぜなら、自己の成功率を低めるような存在は、そ
れが個体、群れ、種、そのほかの何であれ自然選択によって取り除かれるからである。自然選択が働く単位は何か?は、利己的な存在は何か?と言い直すことが
できる[12]。 1970年代までは「種の保存」論やナイーブな群選択説、すなわち生物の利他的行動は種のためであり、生物の性質は種や群などグループの繁栄のために最適 化されているという考えが一般的であった。しかし群選択説は理論的にも実証的にも確認されたものではなく、無批判に肯定されていた。それに対する別の見解 が「利己的遺伝子論」に代表される遺伝子中心視点である。 はじめて遺伝子の視点から生物進化を解釈できることを示したのは、20世紀前半の集団遺伝学の創設者ロナルド・フィッシャーとJ・B・S・ホールデンらで あった。1950年代にはテオドシウス・ドブジャンスキーが「進化」を「遺伝子プール内の遺伝子頻度の変化」と定義した。1964年にウィリアム・ハミル トンが社会性昆虫の研究から血縁選択説を提唱したが、これは遺伝子中心視点主義を論理的に支持する重要な概念であった。ハミルトンの血縁淘汰説はそれまで のダーウィンの唱えた進化説の矛盾を解消するものであった。ダーウィンは進化を自然淘汰と言う考えを用いて上手く説明したが、その考えは淘汰は個体に対し て働くと言うものだったため例外的に説明できない例が自然界に存在した。ミツバチが他の固体の子供を育てる理由などを説明できなかった。それに対し、ハミ ルトンの唱えた血縁淘汰説は自分の血縁者の利益は自分の利益にもなると言う考えでミツバチの子育てなどの一見利他的な行動を上手く説明することが出来た [13]。 1966年にジョージ・ウィリアムスが『適応と自然選択』で群選択説の論理的な誤りを指摘し、初めて進化における遺伝子中心視点主義を明確に提唱した。 1975年にはやはり社会性昆虫の研究者であったエドワード・オズボーン・ウィルソンが論争的な大著『社会生物学』をあらわした。1976年のリチャー ド・ドーキンスの『利己的な遺伝子』は、当時広く信じられていた(現在でも信じられている)種の保存論が誤りであることと、血縁選択説、ジョン・メイナー ド=スミスのESS(進化的に安定な戦略)理論、ロバート・トリヴァーズの親の投資と互恵的利他主義などの当時の最新の研究成果を、難解な数式を使わずに 一般向けに説明したものである。『利己的な遺伝子』の遺伝子淘汰説以前は、ダーウィンの進化説のジレンマである利他的行動を説明するために血縁淘汰説が用 いられていたが、血縁淘汰説は利他的行動を説明するために突然出てきたためになぜ血縁淘汰説が成立するのかの説明が不十分であった。しかし、ドーキンスの 遺伝子淘汰説は「遺伝子は個体に優先する」という原理をとるだけで利他的行動を上手く説明することが出来た[13]。1980年代の社会生物学論争を経 て、遺伝子を自然選択の単位と見なすこの立場は広く受け入れられていった。 この説の拡張に貢献している現代の主要な理論家には、メイナード=スミス、G.ウィリアムス、トリヴァーズらの他ヘレナ・クローニン、デイビッド・ヘイ グ、デイビット・ハル、フィリップ・キッチャー、ティム・クラットンブロック、ダニエル・デネットなどがいる。 |
背景と学説史 |
| この語はあくまでも「遺伝子から生物の進化を解釈する」ことを言い換え
ただけであるが、遺伝子という機械的なシステムに対して「利己的」のような擬人的な形容を使ったことが目新しく、生物学よりむしろ、それ以外の一般メディ
アで広がってしまった。スティーヴン・ジェイ・グールドやリチャード・レウォンティンは優生学の復活を懸念し、1975年から85年にかけてウィルソンを
公に非難した[14]。76年にタイム誌がこの問題を取り上げると批判は拡大し、ウィルソンの講義は妨害を受け、『利己的な遺伝子』の出版後にはドーキン
スも同様の批判に晒された[15]。 |
影響 |
| 利己的遺伝子という言葉はあくまで一種の比喩表現だが、しばしば次のよ
うな誤解を招いている。 利己的遺伝子論は遺伝決定論や還元主義だという誤解。 利己的遺伝子論は遺伝子が意志を持って振る舞うと主張しているという誤解。 利己的遺伝子論は生物個体の振る舞いが常に利己的だと主張しているという誤解。 利己的遺伝子論は遺伝子だけが価値ある物で、生物個体は無価値だと主張しているという誤解。 誤解の原因の一つに、一般に用いる「利己的」は道徳的判断を含むが、この場合の「利己的」とは純粋に行動上の評価であり道徳的な意味はない事が挙げられる [16]。例えば、あるオス鳥が仲間のために餌を運び続けたとする。その様子を見たメスが、その行動を気に入り、多くのメスがそのオスと交尾をした場合、 人間の道徳心から見れば、結果はどうであれ餌を運び続けたのは利他的な行為だったと言うだろう。しかし遺伝子中心視点では、結果的に自己の繁殖率を高めて いるのだから、鳥の意図はどうであれ利己的な行動であったとみなす。 あたかも遺伝子自体が意志をもって利己的に振る舞うかのごとくイメージされることがあるが、誤読である。ドーキンスも誤読されることを予測して本書の中で 「利己的な遺伝子」という表現は説明を簡単にするための比喩、あるいは群淘汰の対比に過ぎないと繰り返し強調している。 人間は赤の他人に手を貸すような真の利他性を見せることがある。だから利己的遺伝子と言う説明では不十分だと指摘もある[17]。ウィルソンは人間行動に 遺伝子中心視点を遠慮無く当てはめたが、そのうえで人間は社会や文化の拘束も受けると認めている。ドーキンスも、人間を遺伝子視点だけで説明しようとする のは誤りであると述べる。一方人間の真の利他行為は社会的評価に結びついている適応的な行為であると見なす社会選択説もある。 用いられる比喩が単純なものであったため、ある性質は一対一である遺伝子に結びついているのだ、のような遺伝子決定論・還元論的な用いられ方をすることも ある。例えば「浮気は浮気遺伝子のせいだ」などである。この誤解は遺伝子の利己性を否定するものだけでなく[18]、肯定するものにも見られる[19]。 一つの遺伝子が一つの形質と一対一で対応している事はまれであるから、「○○のための遺伝子」など存在しないといってよく、机上の空論であるという批判も ある[20]。しかしここで問題になっているのは、ある性質が単一の遺伝子によって決まるかどうかではなく、ある性質が選択されるかどうかである。「○○ のための遺伝子」は話を単純化するための便宜的な表現でしかない。そしてたとえばイヌは人為選択の末、人になつきやすい性質を発達させてきた。おそらくな つきやすさを決める単一の遺伝子など存在しないが、それでも「なつきやすさ」は選択の対象となりうる。 「生物が生存機械であるならば、人間が生きる目的や意義はないのか?」という指摘に対してドーキンスは次のように答えている。 確かにこの宇宙には究極的な意志や目的など何もないのだろう。しかし、一方、個人の人生における希望を宇宙の究極的な運命に託している人間など私たちのう ちに一人も存在していないこともまた事実である。それが普通の感じ方というものだ。我々の人生を左右するのは、もっと身近で、より具体的な思いや認識であ る[21]。 また、生物の究極的な運命や、生物がどうであると言う言明と、人間がどうであるべきと言う主張は全く別であるとも述べている(「である-べきである議論」 も参照)。 |
さまざまな誤解 |
| 霊長類学者フランス・ドゥ・ヴァールは利己的という語の用い方につい
て、ある単語に全く異なる意味を与えて用いる際には決して誤解が起きないような単語を選ぶべきであった、と述べた。哲学者エリオット・ソーバー(Elliott Sober,
1948-
)はこの点について、一般的に我々が用いる道徳的判断である利己主義を「俗称的利己主義」、比喩表現としての利己主義を「進化的利己主義」と使い分けるよ
う提案した。 |
批判 |
| ●ミーム:
文化を伝達する単位。人の心から心へと伝達や複製される自己複製子(replicator)のこと(つまり脳内の情報の単位)。遺伝子と同様、
ミームは「進化する」と主張されている。動物行動学者のリチャード・ドーキンス(Clinton Richard Dawkins, 1941-
)が1976年に『利己的な遺伝子』のなかでこのような概念を提唱し、彼は、それを歌詞やメロディ、さまざ
まな衣服の流行、理論や、工芸品や建築物などの例をあげている。ミームを提唱したドーキンスは「ミームの生息するコンピュータが人間の脳」だと主張してい
る。 |
ミーム |
| The neutral
theory of molecular evolution
holds that most evolutionary changes occur at the molecular level, and
most of the variation within and between species are due to random
genetic drift of mutant alleles that are selectively neutral. The
theory applies only for evolution at the molecular level, and is
compatible with phenotypic evolution being shaped by natural selection
as postulated by Charles Darwin. The neutral theory allows for the
possibility that most mutations are deleterious, but holds that because
these are rapidly removed by natural selection, they do not make
significant contributions to variation within and between species at
the molecular level. A neutral mutation is one that does not affect an
organism's ability to survive and reproduce. The neutral theory assumes
that most mutations that are not deleterious are neutral rather than
beneficial. Because only a fraction of gametes are sampled in each
generation of a species, the neutral theory suggests that a mutant
allele can arise within a population and reach fixation by chance,
rather than by selective advantage.[1] The theory was introduced by the Japanese biologist Motoo Kimura in 1968, and independently by two American biologists Jack Lester King and Thomas Hughes Jukes in 1969, and described in detail by Kimura in his 1983 monograph The Neutral Theory of Molecular Evolution. The proposal of the neutral theory was followed by an extensive "neutralist–selectionist" controversy over the interpretation of patterns of molecular divergence and gene polymorphism, peaking in the 1970s and 1980s. Neutral theory is frequently used as the null hypothesis, as opposed to adaptive explanations, for describing the emergence of morphological or genetic features in organisms and populations. This has been suggested in a number of areas, including in explaining genetic variation between populations of one nominal species,[2] the emergence of complex subcellular machinery,[3] and the convergent emergence of several typical microbial morphologies.[4] |
分子進化の中立説は、進化の変化の
ほとんどは分子レベルで起こり、種内および種間の変異のほとんどは、選択的に中立である突然変異対立遺伝子のランダムな遺伝的ドリフトによるものであると
いうものである。この理論は分子レベルの進化にのみ適用され、チャールズ・ダーウィンが提唱した自然淘汰によって形成される表現型の進化と両立する。中立
説は、ほとんどの突然変異が有害である可能性を許容するが、それらは自然淘汰によって速やかに除去されるため、分子レベルでは種内・種間の変異に大きく寄
与することはないとしている。中立的突然変異とは、生物の生存・繁殖能力に影響を与えない突然変異のことである。中立説は、致死的でない突然変異のほとん
どは有益ではなく中立であると仮定している。ある種の各世代において、配偶子はほんの一部しか採取されないため、中立説は、突然変異対立遺伝子が集団内で
発生し、選択的優位性によってではなく、偶然に固定に達する可能性があることを示唆している[1]。 この理論は1968年に日本の生物学者である木村資生によって、1969年にはアメリカの生物学者であるジャック・レスター・キングとトーマス・ヒュー ズ・ジュークスによって発表された。中立説の提唱後、分子分岐や遺伝子多型のパターンの解釈をめぐって、1970年代から1980年代にかけて「中立主義 者-選択主義者」の論争が繰り広げられた。 中立説は、生物や個体群における形態学的特徴や遺伝的特徴の出現を説明する際に、適応的説明とは対照的に帰無仮説として用いられることが多い。この仮説は 多くの分野で示唆されており、その例として、1つの公称種の個体群間の遺伝的変異、[2]複雑な細胞内機構の出現、[3]いくつかの典型的な微生物形態の 収斂的出現などが挙げられる[4]。 |
| Origins While some scientists, such as Freese (1962)[5] and Freese and Yoshida (1965),[6] had suggested that neutral mutations were probably widespread, the original mathematical derivation of the theory had been published by R.A. Fisher in 1930.[7] Fisher, however, gave a reasoned argument for believing that, in practice, neutral gene substitutions would be very rare.[8] A coherent theory of neutral evolution was first proposed by Motoo Kimura in 1968[9] and by King and Jukes independently in 1969.[10] Kimura initially focused on differences among species; King and Jukes focused on differences within species. Many molecular biologists and population geneticists also contributed to the development of the neutral theory.[1][11][12] The principles of population genetics, established by J.B.S. Haldane, R.A. Fisher, and Sewall Wright, created a mathematical approach to analyzing gene frequencies that contributed to the development of Kimura's theory. Haldane's dilemma regarding the cost of selection was used as motivation by Kimura. Haldane estimated that it takes about 300 generations for a beneficial mutation to become fixed in a mammalian lineage, meaning that the number of substitutions (1.5 per year) in the evolution between humans and chimpanzees was too high to be explained by beneficial mutations. Functional constraint The neutral theory holds that as functional constraint diminishes, the probability that a mutation is neutral rises, and so should the rate of sequence divergence. When comparing various proteins, extremely high evolutionary rates were observed in proteins such as fibrinopeptides and the C chain of the proinsulin molecule, which both have little to no functionality compared to their active molecules. Kimura and Ohta also estimated that the alpha and beta chains on the surface of a hemoglobin protein evolve at a rate almost ten times faster than the inside pockets, which would imply that the overall molecular structure of hemoglobin is less significant than the inside where the iron-containing heme groups reside.[13] There is evidence that rates of nucleotide substitution are particularly high in the third position of a codon, where there is little functional constraint.[14] This view is based in part on the degenerate genetic code, in which sequences of three nucleotides (codons) may differ and yet encode the same amino acid (GCC and GCA both encode alanine, for example). Consequently, many potential single-nucleotide changes are in effect "silent" or "unexpressed" (see synonymous or silent substitution). Such changes are presumed to have little or no biological effect.[15] Quantitative theory 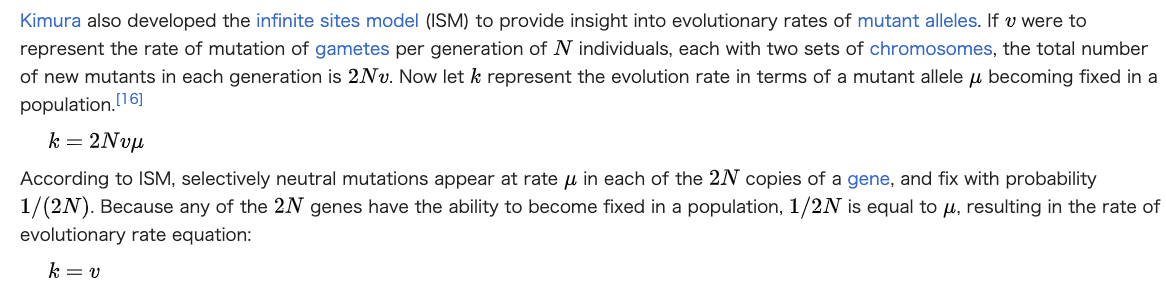 This means that if all mutations were neutral, the rate at which fixed differences accumulate between divergent populations is predicted to be equal to the per-individual mutation rate, independent of population size. When the proportion of mutations that are neutral is constant, so is the divergence rate between populations. This provides a rationale for the molecular clock, which predated neutral theory.[17] The ISM also demonstrates a constancy that is observed in molecular lineages. This stochastic process is assumed to obey equations describing random genetic drift by means of accidents of sampling, rather than for example genetic hitchhiking of a neutral allele due to genetic linkage with non-neutral alleles. After appearing by mutation, a neutral allele may become more common within the population via genetic drift. Usually, it will be lost, or in rare cases it may become fixed, meaning that the new allele becomes standard in the population. According to the neutral theory of molecular evolution, the amount of genetic variation within a species should be proportional to the effective population size. The "neutralist–selectionist" debate See also: History of evolutionary thought and History of molecular evolution A heated debate arose when Kimura's theory was published, largely revolving around the relative percentages of polymorphic and fixed alleles that are "neutral" versus "non-neutral". A genetic polymorphism means that different forms of particular genes, and hence of the proteins that they produce, are co-existing within a species. Selectionists claimed that such polymorphisms are maintained by balancing selection, while neutralists view the variation of a protein as a transient phase of molecular evolution.[1] Studies by Richard K. Koehn and W. F. Eanes demonstrated a correlation between polymorphism and molecular weight of their molecular subunits.[18] This is consistent with the neutral theory assumption that larger subunits should have higher rates of neutral mutation. Selectionists, on the other hand, contribute environmental conditions to be the major determinants of polymorphisms rather than structural and functional factors.[16] According to the neutral theory of molecular evolution, the amount of genetic variation within a species should be proportional to the effective population size. Levels of genetic diversity vary much less than census population sizes, giving rise to the "paradox of variation" .[19] While high levels of genetic diversity were one of the original arguments in favor of neutral theory, the paradox of variation has been one of the strongest arguments against neutral theory. There are a large number of statistical methods for testing whether neutral theory is a good description of evolution (e.g., McDonald-Kreitman test[20]), and many authors claimed detection of selection.[21][22][23][24][25][26] Some researchers have nevertheless argued that the neutral theory still stands, while expanding the definition of neutral theory to include background selection at linked sites.[27] Nearly neutral theory Tomoko Ohta also emphasized the importance of nearly neutral mutations, in particularly slightly deleterious mutations.[28] The population dynamics of nearly neutral mutations are only slightly different from those of neutral mutations unless the absolute magnitude of the selection coefficient is greater than 1/N, where N is the effective population size in respect of selection.[1][11][12] The value of N may therefore affect how many mutations can be treated as neutral and how many as deleterious.[citation needed] Constructive neutral evolution Further information: Constructive neutral evolution The groundworks for the theory of constructive neutral evolution (CNE) was laid by two papers in the 1990s.[29][30][31] Constructive neutral evolution is a theory which suggests that complex structures and processes can emerge through neutral transitions. Although a separate theory altogether, the emphasis on neutrality as a process whereby neutral alleles are randomly fixed by genetic drift finds some inspiration from the earlier attempt by the neutral theory to invoke its importance in evolution.[31] Conceptually, there are two components A and B (which may represent two proteins) which interact with each other. A, which performs a function for the system, does not depend on its interaction with B for its functionality, and the interaction itself may have randomly arisen in an individual with the ability to disappear without an effect on the fitness of A. This present yet currently unnecessary interaction is therefore called an "excess capacity" of the system. However, a mutation may occur which compromises the ability of A to perform its function independently. However, the A:B interaction that has already emerged sustains the capacity of A to perform its initial function. Therefore, the emergence of the A:B interaction "presuppresses" the deleterious nature of the mutation, making it a neutral change in the genome that is capable of spreading through the population via random genetic drift. Hence, A has gained a dependency on its interaction with B.[32] In this case, the loss of B or the A:B interaction would have a negative effect on fitness and so purifying selection would eliminate individuals where this occurs. While each of these steps are individually reversible (for example, A may regain the capacity to function independently or the A:B interaction may be lost), a random sequence of mutations tends to further reduce the capacity of A to function independently and a random walk through the dependency space may very well result in a configuration in which a return to functional independence of A is far too unlikely to occur, which makes CNE a one-directional or "ratchet-like" process.[33] CNE, which does not invoke adaptationist mechanisms for the origins of more complex systems (which involve more parts and interactions contributing to the whole), has seen application in the understanding of the evolutionary origins of the spliceosomal eukaryotic complex, RNA editing, additional ribosomal proteins beyond the core, the emergence of long-noncoding RNA from junk DNA, and so forth.[34][35][36][37] In some cases, ancestral sequence reconstruction techniques have afforded the ability for experimental demonstration of some proposed examples of CNE, as in heterooligomeric ring protein complexes in some fungal lineages.[38] CNE has also been put forwards as the null hypothesis for explaining complex structures, and thus adaptationist explanations for the emergence of complexity must be rigorously tested on a case-by-case basis against this null hypothesis prior to acceptance. Grounds for invoking CNE as a null include that it does not presume that changes offered an adaptive benefit to the host or that they were directionally selected for, while maintaining the importance of more rigorous demonstrations of adaptation when invoked so as to avoid the excessive flaws of adaptationism criticized by Gould and Lewontin.[39][3][40] Empirical evidence for the neutral theory One of corollaries of the neutral theory is that the efficiency of positive selection is higher in population or species with higher effective population size.[41] This relationship between the effective population size and selection efficiency was evidenced by genomic studies of species including chimpanzee and human[41] and domesticated species.[42] https://en.wikipedia.org/wiki/Neutral_theory_of_molecular_evolution |
起源 Freese(1962年)[5]やFreese and Yoshida(1965年)[6]のような一部の科学者は中立的突然変異がおそらく広まっていると示唆していたが、理論の数学的導出の原型は1930年 にR.A.Fisherによって発表されていた[7]。 [8]中立進化に関する首尾一貫した理論は、1968年に木村元男によって初めて提案され[9]、1969年にはキングとジュークスによって独立に提案さ れた[10]。 J.B.S.ハルデン、R.A.フィッシャー、セウォール・ライトによって確立された集団遺伝学の原理は、遺伝子頻度を分析する数学的アプローチを生み出 し、木村の理論の発展に貢献した。 淘汰のコストに関するハルデンのジレンマは、木村の動機として利用された。つまり、ヒトとチンパンジーの進化における置換の数(年間1.5個)は、有益な 突然変異で説明するには多すぎるということである。 機能的制約 中立理論では、機能的制約が減少するにつれて、突然変異が中立である確率が上昇し、配列の分岐率も上昇すると考える。 様々なタンパク質を比較したところ、フィブリノペプチドやプロインスリンのC鎖のような、活性分子に比べてほとんど機能を持たないタンパク質において、極 めて高い進化速度が観察された。木村と太田はまた、ヘモグロビンタンパク質の表面にあるα鎖とβ鎖は、内部のポケットよりもほぼ10倍速い速度で進化する と推定しており、ヘモグロビンの全体的な分子構造は、鉄を含むヘム基が存在する内部よりも重要性が低いことを示唆している[13]。 この見解は、3つのヌクレオチド(コドン)の配列が異なっていても、同じアミノ酸をコードしている(例えば、GCCとGCAは両方ともアラニンをコードし ている)という縮退遺伝暗号に基づいている。その結果、潜在的な一塩基の変化の多くは、事実上「サイレント」または「非表現」である(同義置換またはサイ レント置換を参照)。このような変化は生物学的にほとんど、あるいは全く影響を与えないと推定される[15]。 定量的理論 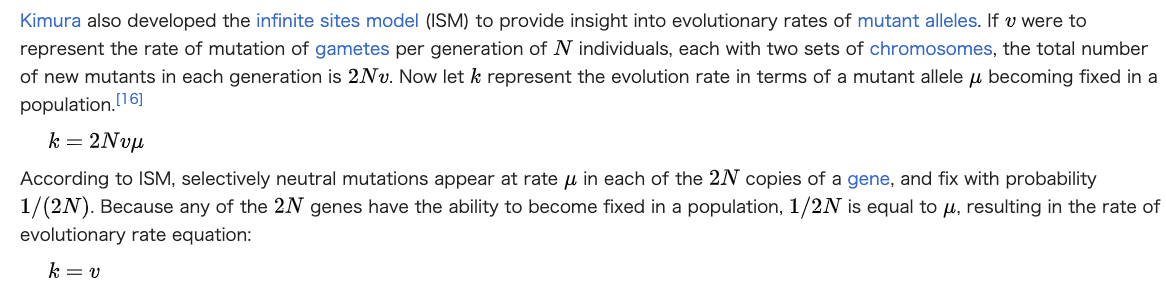 つまり、すべての突然変異が中立であった場合、分岐した集団間で固定的な差異が蓄積する速度は、集団の大きさに関係なく、個体当たりの突然変異率に等しい と予測される。中立的な突然変異の割合が一定であれば、集団間の分岐率も一定である。ISMはまた、分子系統で観察される恒常性を示している。 この確率過程は、例えば非中立対立遺伝子との遺伝的連鎖による中立対立遺伝子の遺伝的ヒッチハイクではなく、サンプリングの偶然によるランダムな遺伝的ド リフトを記述する方程式に従うと仮定される。突然変異によって中立対立遺伝子が出現した後、遺伝的ドリフトによって集団内で中立対立遺伝子がより一般的に なることがある。通常は失われるが、まれに固定化され、新しい対立遺伝子が集団の標準となることもある。 分子進化の中立理論によれば、種内の遺伝的変異の量は有効な個体群サイズに比例するはずである。 中立主義者と淘汰主義者」の論争 こちらも参照: 進化思想史、分子進化史 木村の理論が発表されたとき、主に「中立」と「非中立」の多型対立遺伝子と固定対立遺伝子の相対的な割合をめぐって激しい論争が起こった。 遺伝子多型とは、ある種の中で特定の遺伝子、ひいてはその遺伝子が作り出すタンパク質の異なる形が共存していることを意味する。淘汰派は、このような多型 は淘汰の均衡によって維持されていると主張し、中立派はタンパク質の変異を分子進化の一過性の段階とみなす。 リチャード・K・ケーン(Richard K. Koehn)とW・F・イーンズ(W. F. Eanes)による研究では、多型と分子サブユニットの分子量との間に相関関係があることが示された。一方、淘汰論者は、多型の主要な決定要因は、構造 的・機能的要因よりもむしろ環境条件であるとする[16]。 分子進化の中立理論によれば、種内の遺伝的変異の量は有効な個体群サイズに比例するはずである。遺伝的多様性のレベルは国勢調査の個体群サイズよりもはる かに小さく、「変異のパラドックス」を生み出している。 中立説が進化を正しく記述しているかどうかを検証するための統計的手法は数多く存在し(例えば、マクドナルド-クライトマン検定[20])、多くの著者が 選択の検出を主張している[21][22][23][24][25][26]。それにもかかわらず、中立説の定義を拡大し、連鎖部位における背景選択を含 める一方で、中立説が依然として有効であると主張する研究者もいる[27]。 ほぼ中立説 太田朋子はまた、ほぼ中立的な突然変異、特にわずかに劇薬的な突然変異の重要性を強調している[28]。ほぼ中立的な突然変異の集団動態は、選択係数の絶 対的な大きさが1/Nより大きくない限り、中立的な突然変異の集団動態とわずかに異なるだけである。 建設的中立進化 さらなる情報 構成的中立進化 構成的中立進化(CNE)理論の下地は、1990年代に2つの論文によって築かれた[29][30][31]。全く別の理論ではあるが、中立的な対立遺伝 子が遺伝的ドリフトによってランダムに固定されるプロセスとしての中立性を強調することは、進化におけるその重要性を呼び起こすという中立理論による以前 の試みからいくらかのインスピレーションを得ている。システムの機能を果たすAは、その機能のためにBとの相互作用に依存しておらず、相互作用自体は、A のフィットネスに影響を与えることなく消滅する能力を持つ個体においてランダムに生じた可能性がある。しかし、突然変異が起こり、Aが独立してその機能を 果たす能力が損なわれることがある。しかし、すでに出現しているA:Bの相互作用は、Aが最初の機能を果たす能力を維持する。したがって、A:B相互作用 の出現は突然変異の有害な性質を「抑制」し、ランダムな遺伝的ドリフトによって集団に広がる可能性のあるゲノム上の中立的な変化となる。したがって、Aは Bとの相互作用に依存するようになった[32]。この場合、BまたはA:B相互作用が失われると、フィットネスにマイナスの影響を与えるので、純化選択に よってこのようなことが起こる個体が排除されることになる。これらのステップはそれぞれ可逆的であるが(例えば、Aが独立して機能する能力を回復したり、 A:B相互作用が失われたりする)、突然変異のランダムな連続はAが独立して機能する能力をさらに低下させる傾向があり、依存性空間をランダムに歩くと、 Aの機能的独立性の回復が起こる可能性があまりにも低い構成になる可能性が非常に高い。 [CNEは、より複雑なシステム(より多くの部分と相互作用が全体に寄与する)の起源のための適応論的メカニズムを呼び起こさないが、スプライセオソーム 真核複合体の進化の起源、RNA編集、コア以外の追加リボソームタンパク質、ジャンクDNAからのロングノンコーディングRNAの出現などの理解に応用さ れている。 [34][35][36][37]。場合によっては、祖先の配列を再構築する技術によって、いくつかの菌類系統におけるヘテロオリゴマー環状タンパク質複 合体のように、CNEの提案されたいくつかの例を実験的に証明することができるようになった。 CNEはまた、複雑な構造を説明するための帰無仮説として提唱されており、したがって複雑性の出現に関する適応主義的説明は、受け入れられる前に、この帰 無仮説に対してケースバイケースで厳密に検証されなければならない。CNEを帰無仮説とする根拠としては、変化が宿主に適応的な利益をもたらすことや、そ れが方向性をもって選択されたことを前提としないことが挙げられるが、一方で、グールドやルーウォンティンが批判した適応主義の過剰な欠陥を避けるため に、帰無仮説を唱える際には適応をより厳密に実証することの重要性を維持している[39][3][40]。 中立説の経験的証拠 中立説の帰結の1つは、正の淘汰の効率は有効母集団のサイズが大きい集団や種で高くなるということである[41]。有効母集団のサイズと淘汰効率の間のこ の関係は、チンパンジーやヒト[41]、家畜化された種を含む種のゲノム研究によって証明された[42]。 Jayce Lewis - Shields  Musician Jayce Lewis at Dawkins' home while working on Million (Part 2) リチャード・ドーキンス(Richard Dawkins FRS FRSL、1941年3月26日生まれ) |
 Richard Dawkins FRS FRSL (born 26 March 1941)[3] is a British evolutionary biologist and author. He is an emeritus fellow of New College, Oxford, and was Professor for Public Understanding of Science in the University of Oxford from 1995 to 2008. His 1976 book The Selfish Gene popularised the gene-centred view of evolution, as well as coining the term meme. Dawkins has won several academic and writing awards.[4] Dawkins is well known for his criticism of creationism and intelligent design as well as for being a vocal atheist.[5] Dawkins wrote The Blind Watchmaker in 1986, arguing against the watchmaker analogy, an argument for the existence of a supernatural creator based upon the complexity of living organisms. Instead, he describes evolutionary processes as analogous to a blind watchmaker, in that reproduction, mutation, and selection are unguided by any sentient designer. In 2006, Dawkins published The God Delusion, contending that a supernatural creator almost certainly does not exist and that religious faith is a delusion. He founded the Richard Dawkins Foundation for Reason and Science in 2006.[6][7] Dawkins has published two volumes of memoirs, An Appetite for Wonder (2013) and Brief Candle in the Dark (2015). |
 リチャード・ドーキンス(Richard Dawkins FRS FRSL、1941年3月26日生まれ)[3]は、イギリスの進化生物学者、作家。オックスフォード大学ニュー・カレッジの名誉フェローであり、1995 年から2008年までオックスフォード大学の公共科学理解教授を務めた。1976年に出版した『利己的な遺伝子』(原題:The Selfish Gene)は、遺伝子を中心とした進化論を広めるとともに、ミームという言葉を生み出した。ドーキンスはいくつかの学術賞や著作賞を受賞している[4]。 ドーキンスは創造論やインテリジェント・デザインを批判し、また声高な無神論者であることでも知られている[5]。ドーキンスは1986年に『盲目の時計 職人』を執筆し、生物の複雑性に基づいて超自然的な創造主の存在を主張する時計職人の類推に反論した。その代わりに、ドーキンスは、生殖、突然変異、淘汰 がいかなる知覚的な設計者によっても導かれないという点で、進化の過程を盲目の時計職人に類似していると述べている。2006年、ドーキンスは『神の妄 想』を出版し、超自然的な創造主はほぼ確実に存在せず、宗教的信仰は妄想であると主張した。2006年、理性と科学のためのリチャード・ドーキンス財団を 設立。[6][7] ドーキンスは2冊の回顧録『An Appetite for Wonder』(2013年)と『Brief Candle in the Dark』(2015年)を出版。 |
| Background Early life Dawkins was born Clinton Richard Dawkins on 26 March 1941 in Nairobi, the capital of Kenya during British colonial rule.[8] He later dropped Clinton from his name by deed poll.[3] He is the son of Jean Mary Vyvyan (née Ladner; 1916–2019)[9][10] and Clinton John Dawkins (1915–2010), an agricultural civil servant in the British Colonial Service in Nyasaland (present-day Malawi), of an Oxfordshire landed gentry family.[8][11][12] His father was called up into the King's African Rifles during the Second World War[13][14] and returned to England in 1949, when Dawkins was eight. His father had inherited a country estate, Over Norton Park in Oxfordshire, which he farmed commercially.[12] Dawkins lives in Oxford, England.[15] He has a younger sister, Sarah.[16] His parents were interested in natural sciences, and they answered Dawkins's questions in scientific terms.[17] Dawkins describes his childhood as "a normal Anglican upbringing".[18] He embraced Christianity until halfway through his teenage years, at which point he concluded that the theory of evolution alone was a better explanation for life's complexity, and ceased believing in a god.[16] He states: "The main residual reason why I was religious was from being so impressed with the complexity of life and feeling that it had to have a designer, and I think it was when I realised that Darwinism was a far superior explanation that pulled the rug out from under the argument of design. And that left me with nothing."[16] This understanding of atheism combined with his western cultural background, informs Dawkins as he describes himself in several interviews as a "cultural Christian" and a "cultural Anglican".[19][20][21] Education The Great Hall, Oundle School On his return to England from Nyasaland in 1949, at the age of eight, Dawkins joined Chafyn Grove School, in Wiltshire,[22] and after that from 1954 to 1959 attended Oundle School in Northamptonshire, an English public school with a Church of England ethos,[16] where he was in Laundimer House.[23] While at Oundle, Dawkins read Bertrand Russell's Why I Am Not a Christian for the first time.[24] He studied zoology at Balliol College, Oxford, graduating in 1962; while there, he was tutored by Nobel Prize-winning ethologist Nikolaas Tinbergen. He graduated with upper-second class honours.[25] Dawkins continued as a research student under Tinbergen's supervision, receiving his Doctor of Philosophy[26] degree by 1966, and remained a research assistant for another year.[27][28] Tinbergen was a pioneer in the study of animal behaviour, particularly in the areas of instinct, learning, and choice;[29] Dawkins's research in this period concerned models of animal decision-making.[30] Teaching From 1967 to 1969, Dawkins was an assistant professor of zoology at the University of California, Berkeley. During this period, the students and faculty at UC Berkeley were largely opposed to the ongoing Vietnam War, and Dawkins became involved in the anti-war demonstrations and activities.[31] He returned to the University of Oxford in 1970 as a lecturer. In 1990, he became a reader in zoology. In 1995, he was appointed Simonyi Professor for the Public Understanding of Science at Oxford, a position that had been endowed by Charles Simonyi with the express intention that the holder "be expected to make important contributions to the public understanding of some scientific field",[32] and that its first holder should be Richard Dawkins.[33] He held that professorship from 1995 until 2008.[34] Since 1970, he has been a fellow of New College, Oxford, and he is now an emeritus fellow.[35][36] He has delivered many lectures, including the Henry Sidgwick Memorial Lecture (1989), the first Erasmus Darwin Memorial Lecture (1990), the Michael Faraday Lecture (1991), the T. H. Huxley Memorial Lecture (1992), the Irvine Memorial Lecture (1997), the Tinbergen Lecture (2004), and the Tanner Lectures (2003).[27] In 1991, he gave the Royal Institution Christmas Lectures for Children on Growing Up in the Universe. He also has edited several journals and has acted as an editorial advisor to the Encarta Encyclopedia and the Encyclopedia of Evolution. He is listed as a senior editor and a columnist of the Council for Secular Humanism's Free Inquiry magazine and has been a member of the editorial board of Skeptic magazine since its foundation.[37] Dawkins has sat on judging panels for awards as diverse as the Royal Society's Faraday Award and the British Academy Television Awards,[27] and has been president of the Biological Sciences section of the British Association for the Advancement of Science. In 2004, Balliol College, Oxford, instituted the Dawkins Prize, awarded for "outstanding research into the ecology and behaviour of animals whose welfare and survival may be endangered by human activities".[38] In September 2008, he retired from his professorship, announcing plans to "write a book aimed at youngsters in which he will warn them against believing in 'anti-scientific' fairytales."[39] In 2011, Dawkins joined the professoriate of the New College of the Humanities, a private university in London established by A. C. Grayling, which opened in September 2012.[40] |
生い立ち 生い立ち ドーキンスは1941年3月26日、イギリスの植民地支配下にあったケニアの首都ナイロビでクリントン・リチャード・ドーキンスとして生まれた[8]。 [3]オックスフォードシャーの地主の家系で、ニャサランド(現在のマラウイ)の英国植民地局の農業公務員であったジャン・メアリー・ヴィヴィアン(旧姓 ラドナー、1916-2019)[9][10]とクリントン・ジョン・ドーキンス(1915-2010)の息子である[8][11][12]。父親は第二 次世界大戦中にキングズ・アフリカン・ライフルズに召集され[13][14]、ドーキンスが8歳だった1949年にイギリスに戻った。父親はオックス フォードシャーのオーバー・ノートン・パークという土地を相続し、商業農業を営んでいた[12]。 両親は自然科学に関心があり、ドーキンスの質問にも科学的な言葉で答えていた[17]。ドーキンスは幼少期を「普通の英国国教会の教育」だったと述べてい る[18]: 「私が信心深かった主な理由は、生命の複雑さに感銘を受け、それには設計者がいるはずだと感じたからです。ダーウィニズムがはるかに優れた説明であること に気づいたとき、設計の議論から引きずり降ろされたのだと思います。そして私には何も残らなかった」[16]。無神論に対するこのような理解と西洋文化的 背景が相まって、ドーキンスはいくつかのインタビューで自らを「文化的キリスト教徒」「文化的英国国教会」と表現している[19][20][21]。 教育 オンドル・スクールのグレート・ホール 1949年、8歳でニャサランドからイングランドに戻ったドーキンスは、ウィルトシャー州のチャフィン・グローブ・スクールに入学し[22]、その後 1954年から1959年までノーザンプトンシャー州のオンドル・スクールに通った。 [23]オンドル在学中、ドーキンスはバートランド・ラッセルの『なぜ私はクリスチャンではないのか』を初めて読んだ[24]。オックスフォード大学のバ リオール・カレッジで動物学を学び、1962年に卒業。彼は2級上の優等で卒業した[25]。 ドーキンスはティンバーゲンの指導のもとで研究生を続け、1966年までに哲学博士号[26]を取得し、さらに1年間研究助手を務めた[27][28]。 ティンバーゲンは動物行動学、特に本能、学習、選択の分野における研究の先駆者であった[29]。 教育 1967年から1969年まで、ドーキンスはカリフォルニア大学バークレー校の動物学の助教授であった。この時期、カリフォルニア大学バークレー校の学生 や教員はベトナム戦争に反対しており、ドーキンスは反戦デモや活動に参加した[31]。1990年には動物学の読者となる。この地位は、チャールズ・シモ ニイによって「ある科学分野の一般大衆の理解に重要な貢献をすることが期待される」[32]という明確な意図のもとに寄贈されたもので、その最初の保持者 はリチャード・ドーキンスであるべきである[33]。 1970年以来、オックスフォード大学ニュー・カレッジのフェローであり、現在は名誉フェローである[35][36]。 ヘンリー・シドウィック記念講演(1989年)、第1回エラスマス・ダーウィン記念講演(1990年)、マイケル・ファラデー記念講演(1991年)、 T. H.ハクスリー記念講演(1992年)、アーヴァイン記念講演(1997年)、ティンバーゲン講演(2004年)、タナー講演(2003年)[27]。 1991年には、王立研究所の子供向けクリスマス講演会で「Growing Up in the Universe(宇宙で育つ)」を行った。また、複数の学術誌の編集に携わり、Encarta EncyclopediaとEncyclopedia of Evolutionの編集顧問を務める。世俗的ヒューマニズム評議会の『Free Inquiry』誌の上級編集者およびコラムニストとして名を連ねており、『Skeptic』誌の創刊以来編集委員を務めている[37]。 ドーキンスは、英国王立協会のファラデー賞や英国アカデミーテレビ賞[27]など様々な賞の審査委員を務め、英国科学振興協会の生物科学部門の会長を務め ている。2004年、オックスフォード大学バリオール・カレッジはドーキンス賞を創設し、「人間の活動によって福祉と生存が脅かされる可能性のある動物の 生態と行動に関する卓越した研究」に授与した[38]。2008年9月、教授職を退き、「若者を対象にした本を執筆し、『反科学的』なおとぎ話を信じない ように警告する」計画を発表した[39]。 2011年、ドーキンスはA.C.グレイリングが設立し、2012年9月に開校したロンドンの私立大学、ニュー・カレッジ・オブ・ザ・ヒューマニティーズ の教授に就任した[40]。 |
| Work Evolutionary biology Further information: Gene-centred view of evolution At the University of Texas at Austin, March 2008 Dawkins is best known for his popularisation of the gene as the principal unit of selection in evolution; this view is most clearly set out in two of his books:[41][42] The Selfish Gene (1976), in which he notes that "all life evolves by the differential survival of replicating entities." The Extended Phenotype (1982), in which he describes natural selection as "the process whereby replicators out-propagate each other". He introduces to a wider audience the influential concept he presented in 1977,[43] that the phenotypic effects of a gene are not necessarily limited to an organism's body, but can stretch far into the environment, including the bodies of other organisms. Dawkins regarded the extended phenotype as his single most important contribution to evolutionary biology and he considered niche construction to be a special case of extended phenotype. The concept of extended phenotype helps explain evolution, but it does not help predict specific outcomes.[44] Dawkins has consistently been sceptical about non-adaptive processes in evolution (such as spandrels, described by Gould and Lewontin)[45] and about selection at levels "above" that of the gene.[46] He is particularly sceptical about the practical possibility or importance of group selection as a basis for understanding altruism.[47] Altruism appears at first to be an evolutionary paradox, since helping others costs precious resources and decreases one's own chances for survival, or "fitness". Previously, many had interpreted altruism as an aspect of group selection, suggesting that individuals are doing what is best for the survival of the population or species as a whole. British evolutionary biologist W. D. Hamilton used gene-frequency analysis in his inclusive fitness theory to show how hereditary altruistic traits can evolve if there is sufficient genetic similarity between actors and recipients of such altruism, including close relatives.[48][a] Hamilton's inclusive fitness has since been successfully applied to a wide range of organisms, including humans. Similarly, Robert Trivers, thinking in terms of the gene-centred model, developed the theory of reciprocal altruism, whereby one organism provides a benefit to another in the expectation of future reciprocation.[49] Dawkins popularised these ideas in The Selfish Gene, and developed them in his own work.[50] In June 2012, Dawkins was highly critical of fellow biologist E. O. Wilson's 2012 book The Social Conquest of Earth as misunderstanding Hamilton's theory of kin selection.[51][52] Dawkins has also been strongly critical of the Gaia hypothesis of the independent scientist James Lovelock.[53][54][55] Critics of Dawkins's biological approach suggest that taking the gene as the unit of selection (a single event in which an individual either succeeds or fails to reproduce) is misleading. The gene could be better described, they say, as a unit of evolution (the long-term changes in allele frequencies in a population).[56] In The Selfish Gene, Dawkins explains that he is using George C. Williams's definition of the gene as "that which segregates and recombines with appreciable frequency".[57] Another common objection is that a gene cannot survive alone, but must cooperate with other genes to build an individual, and therefore a gene cannot be an independent "unit".[58] In The Extended Phenotype, Dawkins suggests that from an individual gene's viewpoint, all other genes are part of the environment to which it is adapted. Advocates for higher levels of selection (such as Richard Lewontin, David Sloan Wilson, and Elliott Sober) suggest that there are many phenomena (including altruism) that gene-based selection cannot satisfactorily explain. The philosopher Mary Midgley, with whom Dawkins clashed in print concerning The Selfish Gene,[59][60] has criticised gene selection, memetics, and sociobiology as being excessively reductionist;[61] she has suggested that the popularity of Dawkins's work is due to factors in the Zeitgeist such as the increased individualism of the Thatcher/Reagan decades.[62] Besides, other, more recent views and analysis on his popular science works also exist.[63] In a set of controversies over the mechanisms and interpretation of evolution (what has been called 'The Darwin Wars'),[64][65] one faction is often named after Dawkins, while the other faction is named after the American palaeontologist Stephen Jay Gould, reflecting the pre-eminence of each as a populariser of the pertinent ideas.[66][67] In particular, Dawkins and Gould have been prominent commentators in the controversy over sociobiology and evolutionary psychology, with Dawkins generally approving and Gould generally being critical.[68] A typical example of Dawkins's position is his scathing review of Not in Our Genes by Steven Rose, Leon J. Kamin, and Richard C. Lewontin.[69] Two other thinkers who are often considered to be allied with Dawkins on the subject are Steven Pinker and Daniel Dennett; Dennett has promoted a gene-centred view of evolution and defended reductionism in biology.[70] Despite their academic disagreements, Dawkins and Gould did not have a hostile personal relationship, and Dawkins dedicated a large portion of his 2003 book A Devil's Chaplain posthumously to Gould, who had died the previous year. When asked if Darwinism informs his everyday apprehension of life, Dawkins says, "In one way it does. My eyes are constantly wide open to the extraordinary fact of existence. Not just human existence but the existence of life and how this breathtakingly powerful process, which is natural selection, has managed to take the very simple facts of physics and chemistry and build them up to redwood trees and humans. That's never far from my thoughts, that sense of amazement. On the other hand, I certainly don't allow Darwinism to influence my feelings about human social life", implying that he feels that individual human beings can opt out of the survival machine of Darwinism since they are freed by the consciousness of self.[15] "Meme" as behavioural concept Main article: Meme Dawkins at Cooper Union in New York City to discuss his book The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution in 2010 In his book The Selfish Gene, Dawkins coined the word meme (the behavioural equivalent of a gene) as a way to encourage readers to think about how Darwinian principles might be extended beyond the realm of genes.[71] It was intended as an extension of his "replicators" argument, but it took on a life of its own in the hands of other authors, such as Daniel Dennett and Susan Blackmore. These popularisations then led to the emergence of memetics, a field from which Dawkins has distanced himself.[72] Dawkins's meme refers to any cultural entity that an observer might consider a replicator of a certain idea or set of ideas. He hypothesised that people could view many cultural entities as capable of such replication, generally through communication and contact with humans, who have evolved as efficient (although not perfect) copiers of information and behaviour. Because memes are not always copied perfectly, they might become refined, combined, or otherwise modified with other ideas; this results in new memes, which may themselves prove more or less efficient replicators than their predecessors, thus providing a framework for a hypothesis of cultural evolution based on memes, a notion that is analogous to the theory of biological evolution based on genes.[73] Although Dawkins invented the term meme, he has not claimed that the idea was entirely novel,[74] and there have been other expressions for similar ideas in the past. For instance, John Laurent has suggested that the term may have derived from the work of the little-known German biologist Richard Semon.[75] Semon regarded "mneme" as the collective set of neural memory traces (conscious or subconscious) that were inherited, although such view would be considered as Lamarckian by modern biologists.[76] Laurent also found the use of the term mneme in Maurice Maeterlinck's The Life of the White Ant (1926), and Maeterlinck himself stated that he obtained the phrase from Semon's work.[75] In his own work, Maeterlinck tried to explain memory in termites and ants by claiming that neural memory traces were added "upon the individual mneme".[76] Nonetheless, James Gleick describes Dawkins's concept of the meme as "his most famous memorable invention, far more influential than his selfish genes or his later proselytising against religiosity".[77] Foundation Main article: Richard Dawkins Foundation for Reason and Science In 2006, Dawkins founded the Richard Dawkins Foundation for Reason and Science (RDFRS), a non-profit organisation. RDFRS financed research on the psychology of belief and religion, financed scientific education programs and materials, and publicised and supported charitable organisations that are secular in nature.[78] In January 2016, it was announced that the foundation was merging with the Center for Inquiry, with Dawkins becoming a member of the new organization's board of directors.[79] Criticism of religion Lecturing on his book The God Delusion, 24 June 2006 Dawkins was confirmed into the Church of England at the age of 13, but began to grow sceptical of the beliefs. He said that his understanding of science and evolutionary processes led him to question how adults in positions of leadership in a civilised world could still be so uneducated in biology,[80] and is puzzled by how belief in God could remain among individuals who are sophisticated in science. Dawkins says that some physicists use 'God' as a metaphor for the general awe-inspiring mysteries of the universe, which he claims causes confusion and misunderstanding among people who incorrectly think they are talking about a mystical being who forgives sins, transubstantiates wine, or makes people live after they die.[81] He disagrees with Stephen Jay Gould's principle of nonoverlapping magisteria (NOMA)[82] and suggests that the existence of God should be treated as a scientific hypothesis like any other.[83] Dawkins became a prominent critic of religion and has stated his opposition to religion as twofold: religion is both a source of conflict and a justification for belief without evidence.[84] He considers faith—belief that is not based on evidence—as "one of the world's great evils".[85] On his spectrum of theistic probability, which has seven levels between 1 (100% certainty that a God or gods exist) and 7 (100% certainty that a God or gods do not exist), Dawkins has said he is a 6.9, which represents a "de facto atheist" who thinks "I cannot know for certain but I think God is very improbable, and I live my life on the assumption that he is not there." When asked about his slight uncertainty, Dawkins quips, "I am agnostic to the extent that I am agnostic about fairies at the bottom of the garden."[86][87] In May 2014, at the Hay Festival in Wales, Dawkins explained that while he does not believe in the supernatural elements of the Christian faith, he still has nostalgia for the ceremonial side of religion.[88] In addition to beliefs in deities, Dawkins has criticized religious beliefs as irrational, such as that Jesus turned water into wine, that an embryo starts as a blob, that magic underwear will protect you, that Jesus was resurrected, that semen comes from the spine, that Jesus walked on water, that the sun sets in a marsh, that the Garden of Eden existed in Adam-ondi-Ahman, Missouri, that Jesus' mother was a virgin, that Muhammad split the moon, and that Lazarus was raised from the dead.[96] Dawkins has risen to prominence in public debates concerning science and religion since the publication of his most popular book, The God Delusion, in 2006, which became an international bestseller.[97] As of 2015, more than three million copies have been sold and the book has been translated into over 30 languages.[98] Its success has been seen by many as indicative of a change in the contemporary cultural zeitgeist and has also been identified with the rise of New Atheism.[99] In the book, Dawkins contends that a supernatural creator almost certainly does not exist and that religious faith is a delusion—"a fixed false belief".[100] In his February 2002 TED talk entitled "Militant atheism", Dawkins urged all atheists to openly state their position and to fight the incursion of the church into politics and science.[101] On 30 September 2007, Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, and Daniel Dennett met at Hitchens's residence for a private, unmoderated discussion that lasted two hours. The event was videotaped and entitled "The Four Horsemen".[102] Dawkins sees education and consciousness-raising as the primary tools in opposing what he considers to be religious dogma and indoctrination.[31][103][104] These tools include the fight against certain stereotypes, and he has adopted the term bright as a way of associating positive public connotations with those who possess a naturalistic worldview.[104] He has given support to the idea of a free-thinking school,[105] which would not "indoctrinate children" but would instead teach children to ask for evidence and be skeptical, critical, and open-minded. Such a school, says Dawkins, should "teach comparative religion, and teach it properly without any bias towards particular religions, and including historically important but dead religions, such as those of ancient Greece and the Norse gods, if only because these, like the Abrahamic scriptures, are important for understanding English literature and European history."[106][107] Inspired by the consciousness-raising successes of feminists in arousing widespread embarrassment at the routine use of "he" instead of "she", Dawkins similarly suggests that phrases such as "Catholic child" and "Muslim child" should be considered as socially absurd as, for instance, "Marxist child", as he believes that children should not be classified based on the ideological or religious beliefs of their parents.[104] While some critics, such as writer Christopher Hitchens, psychologist Steven Pinker and Nobel laureates Sir Harold Kroto, James D. Watson, and Steven Weinberg have defended Dawkins's stance on religion and praised his work,[108] others, including Nobel Prize-winning theoretical physicist Peter Higgs, astrophysicist Martin Rees, philosopher of science Michael Ruse, literary critic Terry Eagleton, philosopher Roger Scruton, academic and social critic Camille Paglia, atheist philosopher Daniel Came and theologian Alister McGrath,[115] have criticised Dawkins on various grounds, including the assertion that his work simply serves as an atheist counterpart to religious fundamentalism rather than a productive critique of it, and that he has fundamentally misapprehended the foundations of the theological positions he claims to refute. Rees and Higgs, in particular, have both rejected Dawkins's confrontational stance toward religion as narrow and "embarrassing", with Higgs going as far as to equate Dawkins with the religious fundamentalists he criticises.[116][117][118][119] Atheist philosopher John Gray has denounced Dawkins as an "anti-religious missionary", whose assertions are "in no sense novel or original", suggesting that "transfixed in wonderment at the workings of his own mind, Dawkins misses much that is of importance in human beings." Gray has also criticised Dawkins's perceived allegiance to Darwin, stating that if "science, for Darwin, was a method of inquiry that enabled him to edge tentatively and humbly toward the truth, for Dawkins, science is an unquestioned view of the world."[120] A 2016 study found that many British scientists held an unfavourable view of Dawkins and his attitude towards religion.[121] In response to his critics, Dawkins maintains that theologians are no better than scientists in addressing deep cosmological questions and that he is not a fundamentalist, as he is willing to change his mind in the face of new evidence.[122][123][124] Dawkins has faced backlash over some of his public comments about Islam. In 2013, Dawkins tweeted that "All the world's Muslims have fewer Nobel Prizes than Trinity College, Cambridge. They did great things in the Middle Ages, though."[125] In 2016, Dawkins' invitation to speak at the Northeast Conference on Science and Skepticism was withdrawn over his sharing of what was characterized as a "highly offensive video" satirically showing cartoon feminist and Islamist characters singing about the things they hold in common. In issuing the tweet, Dawkins stated that it "Obviously doesn't apply to vast majority of feminists, among whom I count myself. But the minority are pernicious."[126] Criticism of creationism Dawkins is a prominent critic of creationism, a religious belief that humanity, life, and the universe were created by a deity[127] without recourse to evolution.[128] He has described the young Earth creationist view that the Earth is only a few thousand years old as "a preposterous, mind-shrinking falsehood".[129] His 1986 book, The Blind Watchmaker, contains a sustained critique of the argument from design, an important creationist argument. In the book, Dawkins argues against the watchmaker analogy made famous by the eighteenth-century English theologian William Paley via his book Natural Theology, in which Paley argues that just as a watch is too complicated and too functional to have sprung into existence merely by accident, so too must all living things—with their far greater complexity—be purposefully designed. Dawkins shares the view generally held by scientists that natural selection is sufficient to explain the apparent functionality and non-random complexity of the biological world, and can be said to play the role of watchmaker in nature, albeit as an automatic, unguided by any designer, nonintelligent, blind watchmaker.[130] Wearing a scarlet 'A' lapel pin, at the 34th annual conference of American Atheists (2008) In 1986, Dawkins and biologist John Maynard Smith participated in an Oxford Union debate against A. E. Wilder-Smith (a Young Earth creationist) and Edgar Andrews (president of the Biblical Creation Society).[b] In general, however, Dawkins has followed the advice of his late colleague Stephen Jay Gould and refused to participate in formal debates with creationists because "what they seek is the oxygen of respectability", and doing so would "give them this oxygen by the mere act of engaging with them at all". He suggests that creationists "don't mind being beaten in an argument. What matters is that we give them recognition by bothering to argue with them in public."[131] In a December 2004 interview with American journalist Bill Moyers, Dawkins said that "among the things that science does know, evolution is about as certain as anything we know." When Moyers questioned him on the use of the word theory, Dawkins stated that "evolution has been observed. It's just that it hasn't been observed while it's happening." He added that "it is rather like a detective coming on a murder after the scene... the detective hasn't actually seen the murder take place, of course. But what you do see is a massive clue... Huge quantities of circumstantial evidence. It might as well be spelled out in words of English."[132] Dawkins has opposed the inclusion of intelligent design in science education, describing it as "not a scientific argument at all, but a religious one".[133] He has been referred to in the media as "Darwin's Rottweiler",[134][135] a reference to English biologist T. H. Huxley, who was known as "Darwin's Bulldog" for his advocacy of Charles Darwin's evolutionary ideas. He has been a strong critic of the British organisation Truth in Science, which promotes the teaching of creationism in state schools, and whose work Dawkins has described as an "educational scandal". He plans to subsidise schools through the Richard Dawkins Foundation for Reason and Science with the delivery of books, DVDs, and pamphlets that counteract their work.[136] |
仕事 進化生物学 さらに詳しい情報 遺伝子中心の進化観 2008年3月、テキサス大学オースティン校にて ドーキンスは、進化における淘汰の主要な単位として遺伝子を一般に広めたことで最もよく知られている。この見解は、彼の2冊の著書[41][42]の中で 最も明確に示されている。 利己的な遺伝子』(1976年)では、「すべての生命は、複製された実体の生存の差異によって進化する」と述べている。 The Extended Phenotype』(1982年)では、自然淘汰を「複製体が互いに増殖し合うプロセス」と説明している。彼は1977年に発表した、遺伝子の表現型の 効果は必ずしも生物の体内だけに限定されるものではなく、他の生物の体内を含む環境にまで及ぶ可能性があるという影響力のある概念[43]を、より多くの 読者に紹介した。ドーキンスは拡張表現型を進化生物学への唯一で最も重要な貢献とみなし、ニッチ構築は拡張表現型の特別なケースであると考えた。拡張表現 型の概念は進化を説明するのに役立つが、特定の結果を予測するのには役立たない。 ドーキンスは一貫して進化における非適応的プロセス(グールドやルウォンティンが説明したスパンドレルなど)[45]や遺伝子の「上の」レベルでの選択に ついて懐疑的である[46]。特に利他主義を理解するための基礎としての集団選択の実際的な可能性や重要性については懐疑的である[47]。 利他主義は、他者を助けることで貴重な資源が犠牲になり、自分自身の生存機会、すなわち「適性」が低下するため、最初は進化論的パラドックスのように見え る。以前は、多くの人が利他主義を集団淘汰の一側面として解釈し、個人が集団や種全体の生存のために最善のことをしていることを示唆していた。イギリスの 進化生物学者W.D.ハミルトンは、その包括的フィットネス理論において遺伝子頻度分析を用い、利他主義の行為者と受益者(近親者を含む)の間に十分な遺 伝的類似性があれば、遺伝性の利他的形質がどのように進化しうるかを示した[48][a]。ドーキンスは『利己的な遺伝子』の中でこれらの考え方を普及さ せ、自身の研究でも発展させた。 2012年6月、ドーキンスは同じ生物学者であるE.O.ウィルソンの2012年の著書『The Social Conquest of Earth(地球の社会的征服)』について、ハミルトンの血縁淘汰理論を誤解しているとして強く批判した[51][52]。 ドーキンスはまた独立科学者ジェームズ・ラブロックのガイア仮説についても強く批判している[53][54][55]。 ドーキンスの生物学的アプローチに対する批判者たちは、遺伝子を淘汰の単位(個体が繁殖に成功するか失敗するかのどちらかである単一の事象)とすることは 誤解を招くと指摘している。ドーキンスは『利己的な遺伝子』の中で、ジョージ・C・ウィリアムズによる遺伝子の定義を「評価できる頻度で分離・再結合する もの」と説明している。 [57]もう一つの一般的な反論は、遺伝子は単独では生存できないが、個体を構築するためには他の遺伝子と協力しなければならず、したがって遺伝子は独立 した「単位」ではありえないというものである。 リチャード・レウォンティン、デビッド・スローン・ウィルソン、エリオット・ソーバーなど)より高次の淘汰を支持する人々は、遺伝子に基づく淘汰では満足 に説明できない多くの現象(利他主義を含む)が存在することを示唆している。ドーキンスが『利己的な遺伝子』に関して紙上で衝突した哲学者のメアリー・ ミッドグリーは[59][60]、遺伝子選択、ミメティックス、社会生物学を過度に還元主義的であると批判しており[61]、ドーキンスの著作の人気は、 サッチャー/レーガンの数十年間における個人主義の高まりといった時代精神の要因によるものであると示唆している[62]。 進化のメカニズムや解釈をめぐる一連の論争(「ダーウィン戦争」と呼ばれている)において、一方の派閥はしばしばドーキンスの名を冠し[64][65]、 他方の派閥はアメリカの古生物学者であるスティーヴン・ジェイ・グールドの名を冠しており、適切な考え方の普及者としてのそれぞれの優位性を反映している [66][67]。 特に、ドーキンスとグールドは社会生物学と進化心理学をめぐる論争において著名な論客であり、ドーキンスは一般的に肯定的であり、グールドは一般的に批判 的である。 [ドーキンスの立場の典型的な例として、スティーヴン・ローズ、レオン・J・カミン、リチャード・C・ルウォンチンによる『Not in Our Genes』の酷評がある[69]。この問題に関してドーキンスと同盟関係にあると見なされることが多い他の2人の思想家は、スティーヴン・ピンカーとダ ニエル・デネットであり、デネットは遺伝子を中心とした進化観を推進し、生物学における還元主義を擁護している。 [ドーキンスとグールドは学問的には意見の相違があったものの、個人的には敵対的な関係にはなく、ドーキンスは2003年に出版した『悪魔のチャプレン』 の大部分を、前年に亡くなったグールドに捧げている。 ダーウィニズムが彼の日常的な人生観に影響を与えているかという質問に、ドーキンスは次のように答えている。私の目は常に、存在という驚異的な事実に対し て大きく開かれています。人間の存在だけでなく、生命の存在や、自然淘汰という息をのむほど強力なプロセスが、物理学や化学の非常に単純な事実を、アカマ ツの木や人間にまで発展させたことに。その驚きを忘れることはない。その一方で、私はダーウィニズムが人間の社会生活に対する私の感情に影響を与えること を許さない。 「行動概念としての「ミーム 主な記事 ミーム 著書『The Greatest Show on Earth』について語るため、ニューヨークのクーパー・ユニオンで講演するドーキンス: 2010年、進化論の証拠 ドーキンスは著書『利己的な遺伝子』の中で、ダーウィンの原理が遺伝子の領域を超えてどのように拡張されるかを読者に考えさせる方法として、ミーム(遺伝 子に相当する行動)という言葉を生み出した[71]。これは彼の「複製者」論の拡張として意図されたものであったが、ダニエル・デネットやスーザン・ブ ラックモアといった他の著者の手によって独自の生命を持つようになった。これらの一般化は、ドーキンスが距離を置いている分野であるミーム学の出現につな がった[72]。 ドーキンスの言うミームとは、観察者があるアイデアやアイデアの集合の複製者とみなすような文化的実体のことである。ドーキンスは、多くの文化的実体がそ のような複製が可能であると人々がみなすことができるという仮説を立てた。一般的には、情報や行動の効率的な(完全ではないが)コピー者として進化してき た人間とのコミュニケーションや接触を通じてである。ミームは常に完璧にコピーされるわけではないため、洗練されたり、結合されたり、あるいは他のアイデ アと修正されたりする可能性がある。その結果、新たなミームが生まれ、そのミーム自体が前任者よりも効率的な複製者であったり、そうでなかったりする。 ドーキンスはミームという用語を発明したが、その考え方が全く斬新であったとは主張しておらず[74]、過去にも似たような考え方の表現はあった。例え ば、ジョン・ローランは、この用語があまり知られていないドイツの生物学者リチャード・セモンの研究に由来している可能性を示唆している[75]。セモン は「ミーム」を遺伝する神経記憶の痕跡(意識的または潜在意識的)の集合体とみなしていたが、このような見方は現代の生物学者にとってはラマルク的である と考えられている。 ローランはまた、モーリス・メーテルリンクの『白蟻の一生』(1926年)にも「ムネーメ」という言葉が使われていることを発見し、メーテルリンク自身も この言葉をセモンの仕事から得たと述べている[75]。 [メーテルリンクは自身の著作において、神経記憶の痕跡が「個々のミームの上に」付け加えられたと主張することで、シロアリやアリにおける記憶を説明しよ うとした[76]。それにもかかわらず、ジェームズ・グリークはドーキンスのミームの概念を「彼の最も有名な記憶に残る発明であり、利己的な遺伝子や後に 宗教性に対して布教するよりもはるかに影響力がある」と評している[77]。 財団 主な記事 リチャード・ドーキンス理性と科学財団 2006年、ドーキンスは非営利団体リチャード・ドーキンス理性科学財団(RDFRS)を設立した。RDFRSは信念と宗教の心理学に関する研究に資金を 提供し、科学教育プログラムや教材に資金を提供し、世俗的な慈善団体を広報・支援している[78]。2016年1月、同財団がCenter for Inquiryと合併することが発表され、ドーキンスは新組織の理事会のメンバーとなった[79]。 宗教批判 著書『神の妄想』についての講演(2006年6月24日 ドーキンスは13歳で英国国教会に入信したが、その信仰に懐疑的になり始めた。科学と進化の過程を理解したことで、文明世界で指導的立場にある大人が、生 物学の教養がないことに疑問を抱くようになり[80]、科学に精通した人々の中に神への信仰が残っていることに困惑しているという。ドーキンスによれば、 物理学者の中には「神」を宇宙の一般的な畏敬の念を抱かせる神秘の比喩として使っている者もおり、それが人々の間に混乱と誤解を引き起こし、彼らは誤っ て、罪を赦し、ワインを変質させ、死後も人々を生かす神秘的な存在について語っているのだと考えていると主張している[81]。 彼はスティーヴン・ジェイ・グールドのNOMA(non-overlapping magisteria)の原則に同意しておらず[82]、神の存在は他の仮説と同様に科学的仮説として扱われるべきであると提案している[83]。 ドーキンスは著名な宗教批判者となり、宗教に対する彼の反対は2つあると述べている。 1(神や神々が存在するという100%の確信)から7(神や神々が存在しないという100%の確信)までの7段階からなる神論的確率のスペクトルにおい て、ドーキンスは自分が6.9であると述べており、これは「事実上の無神論者」であることを表している。2014年5月、ウェールズで開催されたヘイ・ フェスティバルでドーキンスは、キリスト教信仰の超自然的な要素は信じていないものの、宗教の儀式的な側面には懐かしさを感じていると説明した[86] [87]。 [88]神々への信仰に加え、ドーキンスは、イエスが水をワインに変えた、胚は塊から始まる、魔法の下着はあなたを守る、イエスは復活した、などの宗教的 信仰を非合理的であると批判してきた、 精液が背骨から出ること、イエスが水の上を歩いたこと、太陽が沼地に沈むこと、エデンの園がミズーリ州のアダム・オンディ・アフマンに存在したこと、イエ スの母親が処女だったこと、ムハンマドが月を割ったこと、ラザロが死からよみがえったことなどである。 [96] ドーキンスは、2006年に最も人気のある著書『神の妄想』を出版して以来、科学と宗教に関する公的な議論において脚光を浴びるようになり、世界的なベス トセラーとなった[97]。 2015年現在、300万部以上が販売され、同書は30以上の言語に翻訳されている[98]。その成功は、現代の文化的な時代の流れの変化を示していると 多くの人々に見られており、また新無神論の台頭とも同一視されている。 [この本の中でドーキンスは、超自然的な創造主はほぼ確実に存在せず、宗教的な信仰は妄想であり、「固定した誤った信念」であると主張している [100]。2002年2月の「Militant atheism(過激な無神論)」と題するTED講演で、ドーキンスはすべての無神論者に自らの立場を公然と表明し、政治や科学への教会の侵入と戦うよう 促した。 [101]2007年9月30日、ドーキンス、クリストファー・ヒッチェンス、サム・ハリス、ダニエル・デネットはヒッチェンスの邸宅で、司会者なしで2 時間にわたる非公開の討論を行った。このイベントはビデオ撮影され、「フォー・ホースメン」と題された[102]。 ドーキンスは教育と意識改革を、彼が宗教的教義や洗脳と考えるものに対抗するための主要な手段であると考えている[31][103][104]。これらの 手段には特定の固定観念との戦いも含まれ、彼は自然主義的世界観を持つ人々に肯定的な世間的意味合いを連想させる方法として、明るいという言葉を採用して いる。 [104]ドーキンスは、「子供たちを教え込む」のではなく、子供たちに証拠を求め、懐疑的で、批判的で、オープンマインドであることを教える、自由な考 え方の学校[105]のアイデアを支持している。そのような学校は「比較宗教を教えるべきであり、特定の宗教に偏ることなく、古代ギリシャや北欧の神々な ど、歴史的に重要だが死滅した宗教も含めてきちんと教えるべきである。 "she "の代わりに "he "を日常的に使用することに対して広く困惑を呼び起こすというフェミニストたちの意識改革の成功に触発され、ドーキンスは同様に、「カトリックの子供」や 「イスラム教徒の子供」といった表現は、例えば「マルクス主義の子供」と同様に社会的に不合理なものとみなされるべきであると示唆している。 作家のクリストファー・ヒッチェンズ、心理学者のスティーヴン・ピンカー、ノーベル賞受賞者のハロルド・クルート卿、ジェームス・D・ワトソン、スティー ヴン・ウィーヴンといった批評家もいるが、彼は「マルクス主義者の子ども」と同じように、社会的に不合理なものだと考えている。また、ノーベル賞を受賞し た理論物理学者のピーター・ヒッグス、宇宙物理学者のマーティン・リース、科学哲学者のマイケル・ルース、文芸批評家のテリー・イーグルトン、哲学者のロ ジャー・スクルトン、学者で社会批評家のカミーユ・パグリア、無神論哲学者のダニエル・クルーリアなど、ドーキンスの宗教に対するスタンスを擁護し、彼の 仕事を賞賛している[108]、 無神論哲学者のダニエル・ケイム、神学者のアリスター・マクグラス[115]らは、ドーキンスの仕事は宗教原理主義に対する生産的な批判というよりは、単 に無神論者のカウンターパートとしての役割を果たすものであり、ドーキンスが反論すると主張する神学的立場の基礎を根本的に誤って理解しているという主張 など、様々な理由でドーキンスを批判している。特にリーズとヒッグスは、ドーキンスの宗教に対する対決姿勢を狭量で「恥ずべきもの」として否定しており、 ヒッグスはドーキンスを彼が批判する宗教原理主義者と同一視するほどである。 [116][117][118][119]無神論者の哲学者ジョン・グレイはドーキンスを「反宗教的宣教師」として非難しており、その主張は「ある意味斬 新でも独創的でもない」。グレイはまた、ドーキンスのダーウィンに対する忠誠心を批判し、「ダーウィンにとっての科学が、彼が暫定的かつ謙虚に真理に向か うことを可能にする探求の方法であったとすれば、ドーキンスにとっての科学は、疑いようのない世界観である」と述べている[120]。2016年の調査で は、多くのイギリスの科学者がドーキンスと彼の宗教に対する態度に対して好意的でない見方をしていることがわかった。 [121]批評家に対してドーキンスは、神学者は宇宙論的な深い問いに取り組むことにおいて科学者よりも優れておらず、新たな証拠に直面して考えを変える ことも厭わないので、自分は原理主義者ではないと主張している[122][123][124]。 ドーキンスはイスラム教に関するいくつかの公のコメントで反発に直面している。2013年、ドーキンスは「世界中のイスラム教徒はケンブリッジのトリニ ティ・カレッジよりもノーベル賞の数が少ない」とツイートした。しかし、彼らは中世に偉大なことをした」[125] 2016年、ドーキンスは「科学と懐疑主義に関する北東部会議」での講演への招待を取り下げられたが、その理由は、漫画のフェミニストとイスラム主義者の キャラクターが彼らの共通点について歌っている風刺的な「非常に不快なビデオ」を共有したことにあった。ドーキンスはこのツイートの中で、「大多数のフェ ミニストには当てはまらないのは明らかだ。しかし、少数派は悪質だ」と述べている[126]。 創造論批判 ドーキンスは創造論の著名な批判者であり、人類、生命、宇宙は進化論に頼ることなく神によって創造されたとする宗教的信念[127]を持つ[128]。 彼は、地球が数千年しか経っていないという若い地球創造論者の見解を「とんでもない、心が縮むような虚偽」[129]と評している。1986年に出版され た彼の著書『The Blind Watchmaker』には、創造論者の重要な主張である設計からの議論に対する持続的な批判が含まれている。この本の中でドーキンスは、18世紀のイギ リスの神学者ウィリアム・ペイリーの著書『自然神学』によって有名になった時計職人のアナロジーに反論している。ペイリーは、時計があまりにも複雑で、あ まりにも機能的であるため、単に偶然存在するようになったのではないと主張している。ドーキンスは、自然淘汰は生物界の見かけの機能性と非ランダムな複雑 性を説明するのに十分であり、自然界における時計職人の役割を果たしていると言えるが、それは自動的で、設計者に導かれておらず、非知的で、盲目の時計職 人である[130]。 第34回アメリカ無神論者年次大会にて、緋色の「A」ラペルピンを着用(2008年) 1986年、ドーキンスと生物学者ジョン・メイナード・スミスはオックスフォード大学連合会の討論会に参加し、A・E・ワイルダー=スミス(若い地球の創 造論者)とエドガー・アンドリュース(聖書創造協会会長)と対戦した[b]。しかし、一般的にドーキンスは故スティーブン・ジェイ・グールドの助言に従 い、創造論者との正式な討論会に参加することを拒否している。彼は、創造論者は「議論で負けることは気にしない。重要なのは、公の場でわざわざ彼らと議論 することで、彼らに評価を与えることだ」[131]。2004年12月、アメリカのジャーナリスト、ビル・モイヤーズとのインタビューで、ドーキンスは 「科学が知っていることの中で、進化論は我々が知っていることと同じくらい確かなことだ」と述べた。モイヤーズが理論という言葉を使うことについて質問す ると、ドーキンスは「進化は観察されている。ただ、進化が起こっている間は観察されていないだけです」。彼はさらに、「それはむしろ、刑事が殺人事件の現 場を後から見に来るようなものだ......もちろん、刑事は実際に殺人が起こっているところは見ていない。しかし、あなたが目にするのは膨大な手がかり だ......。大量の状況証拠。それは英語の単語で綴られているのと同じかもしれない」[132]。 ドーキンスはインテリジェント・デザインを科学教育に取り入れることに反対しており、それを「科学的な議論ではなく、宗教的な議論」であると述べている [133]。ドーキンスは、英国の団体「トゥルース・イン・サイエンス」を強く批判している。トゥルース・イン・サイエンスは、州立学校で創造論を教える ことを推進しており、ドーキンスはその活動を「教育スキャンダル」と表現している。ドーキンスは「理性と科学のためのリチャード・ドーキンス財団 (Richard Dawkins Foundation for Reason and Science)」を通じて、彼らの活動に対抗する書籍、DVD、パンフレットを学校に提供し、助成金を提供することを計画している[136]。 |
| Political views Further information: Political views of Richard Dawkins With Ariane Sherine at the Atheist Bus Campaign launch in London, January 2009 Dawkins is an outspoken atheist[137] and a supporter of various atheist, secular,[138][139] and humanist organisations,[140][141][142][143] including Humanists UK and the Brights movement.[101] Dawkins suggests that atheists should be proud, not apologetic, stressing that atheism is evidence of a healthy, independent mind.[144] He hopes that the more atheists identify themselves, the more the public will become aware of just how many people are nonbelievers, thereby reducing the negative opinion of atheism among the religious majority.[145] Inspired by the gay rights movement, he endorsed the Out Campaign to encourage atheists worldwide to declare their stance publicly.[146] He supported a UK atheist advertising initiative, the Atheist Bus Campaign in 2008 and 2009, which aimed to raise funds to place atheist advertisements on buses in the London area.[147] Speaking at Kepler's Books, Menlo Park, California, 29 October 2006 Dawkins has expressed concern about the growth of the human population and about the matter of overpopulation.[148] In The Selfish Gene, he briefly mentions population growth, giving the example of Latin America, whose population, at the time the book was written, was doubling every 40 years. He is critical of Roman Catholic attitudes to family planning and population control, stating that leaders who forbid contraception and "express a preference for 'natural' methods of population limitation" will get just such a method in the form of starvation.[149] As a supporter of the Great Ape Project—a movement to extend certain moral and legal rights to all great apes—Dawkins contributed the article 'Gaps in the Mind' to the Great Ape Project book edited by Paola Cavalieri and Peter Singer. In this essay, he criticises contemporary society's moral attitudes as being based on a "discontinuous, speciesist imperative".[150] Dawkins also regularly comments in newspapers and blogs on contemporary political questions and is a frequent contributor to the online science and culture digest 3 Quarks Daily.[151] His opinions include opposition to the 2003 invasion of Iraq,[152] the British nuclear deterrent, the actions of then-US President George W. Bush,[153] and the ethics of designer babies.[154] Several such articles were included in A Devil's Chaplain, an anthology of writings about science, religion, and politics. He is also a supporter of Republic's campaign to replace the British monarchy with a democratically elected president.[155] Dawkins has described himself as a Labour voter in the 1970s[156] and voter for the Liberal Democrats since the party's creation. In 2009, he spoke at the party's conference in opposition to blasphemy laws, alternative medicine, and faith schools. In the UK general election of 2010, Dawkins officially endorsed the Liberal Democrats, in support of their campaign for electoral reform and for their "refusal to pander to 'faith'".[157] In the run up to the 2017 general election, Dawkins once again endorsed the Liberal Democrats and urged voters to join the party. Dawkins discusses free speech and Islam(ism) at the 2017 Conference on Free Expression and Conscience. In April 2021, Dawkins said on Twitter that "In 2015, Rachel Dolezal, a white chapter president of NAACP, was vilified for identifying as Black. Some men choose to identify as women, and some women choose to identify as men. You will be vilified if you deny that they literally are what they identify as. Discuss." After receiving criticism for this tweet, Dawkins responded by saying that "I do not intend to disparage trans people. I see that my academic "Discuss" question has been misconstrued as such and I deplore this. It was also not my intent to ally in any way with Republican bigots in US now exploiting this issue."[158] The American Humanist Association retracted Dawkins' 1996 Humanist of the Year Award in response to these comments.[159] Robby Soave of Reason magazine criticized the retraction, saying that "The drive to punish dissenters from various orthodoxies is itself illiberal."[160] Dawkins has voiced his support for the Campaign for the Establishment of a United Nations Parliamentary Assembly, an organisation that campaigns for democratic reform in the United Nations, and the creation of a more accountable international political system.[161] Dawkins identifies as a feminist.[162] He has said that feminism is "enormously important".[163] Dawkins has been accused by writers such as Amanda Marcotte, Caitlin Dickson, and Adam Lee of misogyny, criticizing those who speak about sexual harassment and abuse while ignoring sexism within the New Atheist movement.[164][165][166] Views on postmodernism In 1998, in a book review published in Nature, Dawkins expressed his appreciation for two books connected with the Sokal affair, Higher Superstition: The Academic Left and Its Quarrels with Science by Paul R. Gross and Norman Levitt and Intellectual Impostures by Sokal and Jean Bricmont. These books are famous for their criticism of postmodernism in U.S. universities (namely in the departments of literary studies, anthropology, and other cultural studies).[167] Echoing many critics, Dawkins holds that postmodernism uses obscurantist language to hide its lack of meaningful content. As an example he quotes the psychoanalyst Félix Guattari: "We can clearly see that there is no bi-univocal correspondence between linear signifying links or archi-writing, depending on the author, and this multireferential, multi-dimensional machinic catalysis." This is explained, Dawkins maintains, by certain intellectuals' academic ambitions. Figures like Guattari or Lacan, according to Dawkins, have nothing to say but want to reap the benefits of reputation and fame that derive from a successful academic career: "Suppose you are an intellectual impostor with nothing to say, but with strong ambitions to succeed in academic life, collect a coterie of reverent disciples and have students around the world anoint your pages with respectful yellow highlighter. What kind of literary style would you cultivate? Not a lucid one, surely, for clarity would expose your lack of content."[167] Other fields Musician Jayce Lewis at Dawkins' home while working on Million (Part 2) In his role as professor for public understanding of science, Dawkins has been a critic of pseudoscience and alternative medicine. His 1998 book Unweaving the Rainbow considers John Keats's accusation that by explaining the rainbow, Isaac Newton diminished its beauty; Dawkins argues for the opposite conclusion. He suggests that deep space, the billions of years of life's evolution, and the microscopic workings of biology and heredity contain more beauty and wonder than do "myths" and "pseudoscience".[168] For John Diamond's posthumously published Snake Oil, a book devoted to debunking alternative medicine, Dawkins wrote a foreword in which he asserts that alternative medicine is harmful, if only because it distracts patients from more successful conventional treatments and gives people false hopes.[169] Dawkins states that "There is no alternative medicine. There is only medicine that works and medicine that doesn't work."[170] In his 2007 Channel 4 TV film The Enemies of Reason, Dawkins concluded that Britain is gripped by "an epidemic of superstitious thinking".[171] Continuing a long-standing partnership with Channel 4, Dawkins participated in a five-part television series, Genius of Britain, along with fellow scientists Stephen Hawking, James Dyson, Paul Nurse, and Jim Al-Khalili. The series was first broadcast in June 2010, and focuses on major, British, scientific achievements throughout history.[172] In 2014, he joined the global awareness movement Asteroid Day as a "100x Signatory".[173] |
政治的見解 さらに詳しい情報 リチャード・ドーキンスの政治的見解 2009年1月、ロンドンでの無神論者バスキャンペーン立ち上げにて、アリアーヌ・シェリーヌと。 ドーキンスは率直な無神論者であり[137]、ヒューマニストUKやブライツ運動を含む様々な無神論者、世俗主義者、[138][139]、ヒューマニス ト組織[140][141][142][143]の支持者である[101]。 [144]ドーキンスは、より多くの無神論者が自らを明らかにすることで、一般の人々がいかに多くの人々が無神論者であるかを認識するようになり、それに よって宗教的多数派の無神論に対する否定的な意見が減少することを望んでいる。 [145]同性愛者の権利運動に触発され、彼は世界中の無神論者が自分たちの立場を公に宣言することを奨励するOut Campaignを支持した[146]。彼は2008年と2009年にイギリスの無神論者の広告イニシアチブであるAtheist Bus Campaignを支援し、ロンドン地域のバスに無神論者の広告を掲載するための資金調達を目指した[147]。 2006年10月29日、カリフォルニア州メンローパークのケプラーズ・ブックスにて講演。 ドーキンスは人類の人口増加や人口過剰の問題について懸念を表明している[148]。『利己的な遺伝子』の中で、彼は人口増加について簡単に触れており、 この本が書かれた当時、40年ごとに人口が倍増していたラテンアメリカの例を挙げている。彼は家族計画や人口抑制に対するローマ・カトリックの姿勢に批判 的で、避妊を禁じ、「人口制限の『自然な』方法を好むと表明する」指導者は、飢餓という形でまさにそのような方法を得ることになるだろうと述べている [149]。 パオラ・カヴァリエリとピーター・シンガーが編集したGreat Ape Projectの本に、ドーキンスは「Gaps in the Mind」という論文を寄稿している。このエッセイの中で彼は、現代社会の道徳的態度は「非連続的で種族主義的な命令」に基づいていると批判している [150]。 2003年のイラク侵攻、[152]イギリスの核抑止力、ジョージ・W・ブッシュ米大統領(当時)の行動、[153]デザイナーズベビーの倫理などに反対 している[154] 。ドーキンスは、1970年代には労働党の有権者であり[156]、自由民主党が創設されてからは自由民主党の有権者であると自称している[155]。 2009年には、同党の党大会で冒涜法、代替医療、信仰学校への反対を表明した。2010年のイギリス総選挙では、ドーキンスは選挙制度改革のキャンペー ンを支持し、「『信仰』に迎合することを拒否する」自由民主党を公式に支持した[157]。2017年の総選挙に向けて、ドーキンスは再び自由民主党を支 持し、有権者に同党への入党を促した。 2017年の「表現の自由と良心に関する会議」で言論の自由とイスラム教について語るドーキンス。 2021年4月、ドーキンスはツイッターで「2015年、NAACPの白人支部長レイチェル・ドレザルは、黒人であることを名乗ったことで中傷された。女 性であることを選ぶ男性もいれば、男性であることを選ぶ女性もいる。彼らが文字通りそうであることを否定すれば、あなたは中傷されるでしょう。議論してく ださい" このツイートに対する批判を受けたドーキンスは、「トランスの人々を中傷するつもりはありません。私の学術的な "Discuss "の質問がそのように誤解されているようで、遺憾に思います。また、この問題を悪用する米国の共和党の偏屈者と手を組むつもりもなかった」[158]。米 国ヒューマニスト協会は、このコメントを受けて、ドーキンスが1996年に受賞したヒューマニスト・オブ・ザ・イヤーを撤回した[159]。『リーズン』 誌のロビー・ソーブは、「さまざまな正統性からの異論者を罰する動きは、それ自体が非自由主義的だ」と述べ、撤回を批判した[160]。 ドーキンスは、国連の民主的改革と、より説明責任のある国際政治システムの構築を求めるキャンペーン組織である「国連議会設立キャンペーン」への支持を表 明している[161]。 ドーキンスはフェミニストであると自認している[162]。彼はフェミニズムは「非常に重要」であると述べている[163]。ドーキンスはアマンダ・マー コット、ケイトリン・ディクソン、アダム・リーなどの作家から女性差別で非難されており、新無神論運動内の性差別を無視してセクハラや虐待について語る人 々を批判している[164][165][166]。 ポストモダニズムに対する見解 1998年、ドーキンスは『ネイチャー』誌に掲載された書評の中で、ソーカル事件に関連した2冊の本『Higher Superstition: ポール・R・グロスとノーマン・レヴィット著『The Academic Left and Its Quarrels with Science』とソーカルとジャン・ブリクモン著『Intellectual Impostures』である。これらの本は、アメリカの大学(すなわち文学研究、人類学、その他の文化研究の学部)におけるポストモダニズムを批判して いることで有名である[167]。 多くの批評家と同じように、ドーキンスもポストモダニズムは意味のない内容を隠すために曖昧主義的な言葉を使っていると考えている。その例として、彼は精 神分析学者フェリックス・ガタリの言葉を引用している: 「作者によって異なるが、直線的な意味づけのリンクやアーキ・ライティングと、この多参照的で多次元的な機械的触媒作用との間には、二元的な対応関係がな いことがよくわかる」。このことは、ある種の知識人の学問的野心によって説明されるとドーキンスは主張する。ドーキンスによれば、ガタリやラカンのような 人物は、何も言うことはないが、学問的なキャリアを成功させることで得られる評判や名声という利益を得たいのだという: 「仮にあなたが、何も語ることのない知的詐欺師でありながら、学問の世界で成功し、尊敬する弟子たちを集め、世界中の学生たちに尊敬の黄色い蛍光ペンであ なたのページを塗りたくってもらいたいという強い野望を抱いているとしよう。あなたならどんな文体を育てるだろうか?明晰なものではないことは確かだ。明 晰でなければ、内容のなさが露呈してしまうからだ」[167]。 その他の分野 ミリオンの制作中にドーキンスの自宅で撮影されたミュージシャン、ジェイス・ルイス(その2) ドーキンスは、一般市民の科学理解のための教授として、疑似科学や代替医療を批判してきた。1998年の著書『Unweaving the Rainbow』では、虹を説明することによってアイザック・ニュートンがその美しさを減じたというジョン・キーツの非難について考察している。ドーキン スは、深宇宙、数十億年にわたる生命の進化、生物学と遺伝の微細な営みには、「神話」や「疑似科学」よりも多くの美と驚きが含まれていることを示唆してい る[168]。ジョン・ダイアモンドが死後に出版した『スネーク・オイル』(Snake Oil)は、代替医療を論破することに特化した本であるが、ドーキンスはその序文を執筆し、代替医療は、より成功率の高い従来の治療法から患者の目をそら し、人々に誤った希望を与えるという理由だけでも、有害であると主張している[169]。あるのは効く医学と効かない医学だけだ」と述べている [170]。2007年のチャンネル4のテレビ映画『The Enemies of Reason』で、ドーキンスはイギリスが「迷信的思考の流行」に陥っていると結論づけた[171]。 チャンネル4との長年にわたるパートナーシップを継続し、ドーキンスは同僚の科学者スティーヴン・ホーキング、ジェームズ・ダイソン、ポール・ナース、ジ ム・アル=カリリとともに、5部構成のテレビシリーズ『Genius of Britain』に参加した。このシリーズは2010年6月に初めて放送され、歴史上のイギリスの主要な科学的業績に焦点を当てた[172]。 2014年には、世界的な意識向上運動「アステロイド・デー」に「100倍署名者」として参加した[173]。 |
| Awards and recognition Receiving the Deschner Prize in Frankfurt, 12 October 2007, from Karlheinz Deschner He holds honorary doctorates in science from the University of Huddersfield, University of Westminster, Durham University,[174] the University of Hull, the University of Antwerp, the University of Oslo, the University of Aberdeen,[175] Open University, the Vrije Universiteit Brussel,[27] and the University of Valencia.[176] He also holds honorary doctorates of letters from the University of St Andrews and the Australian National University (HonLittD, 1996), and was elected Fellow of the Royal Society of Literature in 1997 and a Fellow of the Royal Society (FRS) in 2001.[1][27] He is one of the patrons of the Oxford University Scientific Society. In 1987, Dawkins received a Royal Society of Literature award and a Los Angeles Times Literary Prize for his book The Blind Watchmaker. In the same year, he received a Sci. Tech Prize for Best Television Documentary Science Programme of the Year for his work on the BBC's Horizon episode The Blind Watchmaker.[27] In 1996, the American Humanist Association gave him their Humanist of the Year Award, but the award was withdrawn in 2021, with the statement that he "demean[ed] marginalized groups", including transgender people, using "the guise of scientific discourse".[177][158] Other awards include the Zoological Society of London's Silver Medal (1989), the Finlay Innovation Award (1990), the Michael Faraday Award (1990), the Nakayama Prize (1994), the fifth International Cosmos Prize (1997), the Kistler Prize (2001), the Medal of the Presidency of the Italian Republic (2001), the 2001 and 2012 Emperor Has No Clothes Award from the Freedom From Religion Foundation, the Bicentennial Kelvin Medal of The Royal Philosophical Society of Glasgow (2002),[27] the Golden Plate Award of the American Academy of Achievement (2006),[178] and the Nierenberg Prize for Science in the Public Interest (2009).[179] He was awarded the Deschner Award, named after German anti-clerical author Karlheinz Deschner.[180] The Committee for Skeptical Inquiry (CSICOP) has awarded Dawkins their highest award In Praise of Reason (1992).[181] Dawkins accepting the Services to Humanism award at the British Humanist Association Annual Conference in 2012 Dawkins topped Prospect magazine's 2004 list of the top 100 public British intellectuals, as decided by the readers, receiving twice as many votes as the runner-up.[182][183] He was shortlisted as a candidate in their 2008 follow-up poll.[184] In a poll held by Prospect in 2013, Dawkins was voted the world's top thinker based on 65 names chosen by a largely US and UK-based expert panel.[185] In 2005, the Hamburg-based Alfred Toepfer Foundation awarded him its Shakespeare Prize in recognition of his "concise and accessible presentation of scientific knowledge". He won the Lewis Thomas Prize for Writing about Science for 2006, as well as the Galaxy British Book Awards's Author of the Year Award for 2007.[186] In the same year, he was listed by Time magazine as one of the 100 most influential people in the world in 2007,[187] and was ranked 20th in The Daily Telegraph's 2007 list of 100 greatest living geniuses.[188] Since 2003, the Atheist Alliance International has awarded a prize during its annual conference, honouring an outstanding atheist whose work has done the most to raise public awareness of atheism during that year; it is known as the Richard Dawkins Award, in honour of Dawkins's own efforts.[189] In February 2010, Dawkins was named to the Freedom From Religion Foundation's Honorary Board of distinguished achievers.[190] In 2012, a Sri Lankan team of ichthyologists headed by Rohan Pethiyagoda named a new genus of freshwater fish Dawkinsia in Dawkins's honor. (Members of this genus were formerly members of the genus Puntius).[191] |
受賞と評価 2007年10月12日、フランクフルトにてカールハインツ・デシュナーよりデシュナー賞を授与される。 ハダースフィールド大学、ウェストミンスター大学、ダラム大学[174]、ハル大学、アントワープ大学、オスロ大学、アバディーン大学[175]、オープ ン大学、ブリュッセル自由大学[27]、バレンシア大学から名誉科学博士号を授与。 [176] また、セント・アンドリュース大学とオーストラリア国立大学から名誉文学博士号(HonLittD、1996年)を授与されており、1997年には英国王 立文学協会のフェローに、2001年には英国王立協会のフェロー(FRS)に選出されている[1][27]。 1987年、『The Blind Watchmaker』で英国王立文学協会賞とロサンゼルス・タイムズ文学賞を受賞。同年、BBCの『Horizon』のエピソード『The Blind Watchmaker』でSci.Tech Prizeの年間最優秀テレビドキュメンタリー科学番組賞を受賞[27]。 1996年、アメリカ・ヒューマニスト協会は彼にヒューマニスト・オブ・ザ・イヤーを授与したが、2021年に「科学的言説を装って」トランスジェンダー を含む「社会から疎外されたグループを貶める」という声明を発表し、受賞は取り消された[177][158]。 その他の受賞歴には、ロンドン動物学会のシルバーメダル(1989年)、フィンレイ・イノベーション賞(1990年)、マイケル・ファラデー賞(1990 年)、中山賞(1994年)、第5回コスモス国際賞(1997年)、キスラー賞(2001年)、イタリア共和国大統領メダル(2001年)などがある、 宗教からの自由財団から2001年および2012年のEmperor Has No Clothes賞、グラスゴー王立哲学協会から200周年記念ケルヴィン・メダル(2002年)[27]、アメリカ業績アカデミーからゴールデンプレート 賞(2006年)[178]、公益科学ニーレンバーグ賞(2009年)[179]。 [179]ドイツの反教派作家カールハインツ・デシュナーにちなんで名付けられたデシュナー賞を受賞[180]。 懐疑的探究委員会(CSICOP)はドーキンスに最高賞『In Praise of Reason』(1992年)を授与[181]。 2012年、英国ヒューマニスト協会年次大会でヒューマニズムへの貢献賞を受賞するドーキンス。 ドーキンスはプロスペクト誌が2004年に発表した、読者が選ぶイギリスの知識人トップ100の中でトップとなり、次点の2倍の票を獲得した[182] [183]。 2013年にプロスペクト誌が行った投票では、ドーキンスは主にアメリカとイギリスを拠点とする専門家パネルによって選ばれた65人の名前に基づいて、世 界のトップ思想家に選ばれた[185]。 2005年、ハンブルクを拠点とするアルフレッド・トープファー財団は、「科学的知識を簡潔かつ分かりやすく提示した」ことが評価され、彼にシェイクスピ ア賞を授与。2006年にはルイス・トーマス賞(Lewis Thomas Prize for Writing about Science)を、2007年にはギャラクシー・ブリティッシュ・ブック・アワード(Galaxy British Book Awards)のオーサー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞している[186]。 2003年以来、国際無神論同盟は年次大会の際に賞を授与し、その年に無神論に対する一般の認識を高めるために最も貢献した傑出した無神論者を称えてい る。2010年2月、ドーキンスは宗教からの自由財団の名誉理事会の功労者に選ばれた[190]。 2012年、ローハン・ペティヤゴダが率いるスリランカの魚類学者チームが、ドーキンスに敬意を表して淡水魚の新属をドーキニアと命名。(この属のメン バーは、以前はプンティウス属に属していた)[191]。 |
| Personal life Dawkins has been married three times and has a daughter. On 19 August 1967, Dawkins married ethologist Marian Stamp in the Protestant church in Annestown, County Waterford, Ireland;[192] they divorced in 1984. On 1 June 1984, he married Eve Barham (1951–1999) in Oxford. They had a daughter. Dawkins and Barham divorced.[193] In 1992, he married actress Lalla Ward[193] in Kensington and Chelsea, London. Dawkins met her through their mutual friend Douglas Adams,[194] who had worked with her on the BBC's Doctor Who. Dawkins and Ward separated in 2016 and they later described the separation as "entirely amicable".[195] He identifies as an atheist who is a "cultural Anglican", associated with the Church of England, and a "secular Christian".[196][197][198][199] On 6 February 2016, Dawkins suffered a minor haemorrhagic stroke while at home.[200][201] Dawkins reported later that same year that he had almost completely recovered.[202][203] |
私生活 ドーキンスは3度の結婚歴があり、娘がいる。1967年8月19日、ドーキンスはアイルランドのウォーターフォード州アネスタウンのプロテスタント教会 で、倫理学者のマリアン・スタンプと結婚した[192]。1984年6月1日、オックスフォードでイヴ・バーハム(1951-1999)と結婚。二人の間 には娘がいた。1992年、ロンドンのケンジントン&チェルシーで女優のララ・ワードと結婚[193]。ドーキンスは共通の友人であるダグラス・アダムス [194]を通じて彼女と知り合い、彼はBBCの『ドクター・フー』で彼女と仕事をしたことがあった。ドーキンスとウォードは2016年に別居し、後に二 人はその別居を「まったく友好的なもの」であったと述べている[195]。 彼はイングランド国教会に関連する「文化的英国国教会」であり、「世俗的キリスト教徒」である無神論者であると自認している[196][197] [198][199]。 2016年2月6日、ドーキンスは自宅で軽い出血性脳卒中を起こした[200][201]。 ドーキンスは同年末、ほぼ完全に回復したことを報告した[202][203]。 |
| Selected publications Main article: Richard Dawkins bibliography. The Selfish Gene. 1976. The Extended Phenotype. 1982. The Blind Watchmaker. 1986. River Out of Eden. 1995. Climbing Mount Improbable. 1996. Unweaving the Rainbow. 1998. A Devil's Chaplain. 2003. The Ancestor's Tale. 2004. The God Delusion. 2006. The Oxford Book of Modern Science Writing. 2008. The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution. 2009. The Magic of Reality: How We Know What's Really True. 2011. An Appetite for Wonder. 2013.. First volume of his memoirs. Brief Candle in the Dark. 2015.. Second volume of his memoirs. Science in the Soul. 2017. Outgrowing God. 2019. Books Do Furnish a Life. 2021. Flights of Fancy: Defying Gravity by Design and Evolution. 2021. |
|
リンク
リンク
リンク(医療人類学関連)
文献
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆