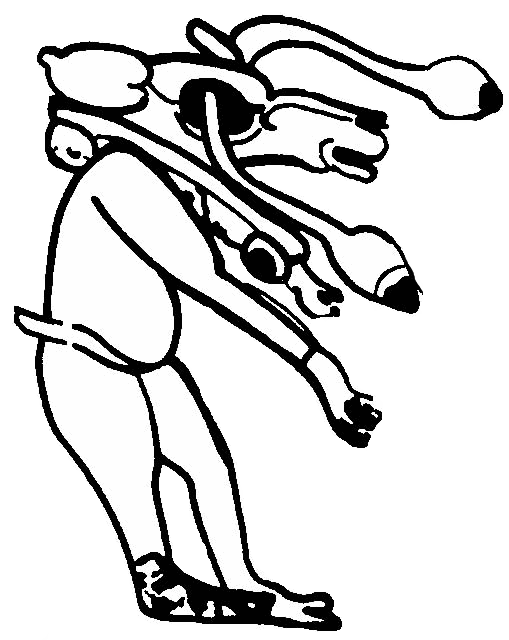

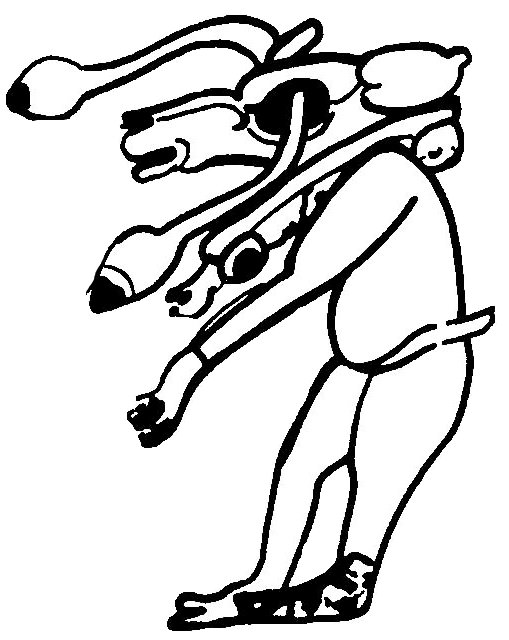
新しい器
New vessel
or fresh
wineskins
池田光穂
── はじめに、神はみんなに器を与えた。粘土でできた器だ。この器で彼らは自分たちのいのちを飲んだ。‥‥彼らはみんなそれで水をすくったが、彼らの器はそれ ぞれ別々だ。我々の器は今では壊れてしまった。もう終わってしまったのだ(Benedict 1959:21-22)。
これはルース・ベネディクトが書きとめたディガー・インディアンの首長 ラモンの語りである。ラモンの言う器は、彼らの伝統的な儀礼体系に みられる独特の概念であるのか、それとも彼自身の思いつきであったのかは、彼女自身も分からないという。彼女は白人によって滅ぼされてゆく彼らの文化体系 ──彼女は価値基準と信条の構造(fabric)と表現する──の崩壊の象徴として「我々の器は壊れてしまった」という表現をとりあげた。ベネディクト は、ラモンたちが水を掬っていた器が失われて、もはや取り返しがつかないと述べるが、かと言って彼らが完全に絶望的な状況の中に生きているというわけでは ないとも言う。白人との交渉の中で生きるという、別の生き方の器は残されているからである。つまり、苦悩の宿命を担ってはいるが、彼らは2つの文化の中で 生きているからだ。他方、ベネディクトによると北アメリカの「単一のコスモポリタンな文化」における社会科学、心理学、そして神学でさえも、ラモンの表現 する「真理」を拒絶してきたし、そのような語りに耳を傾けてこなかった。
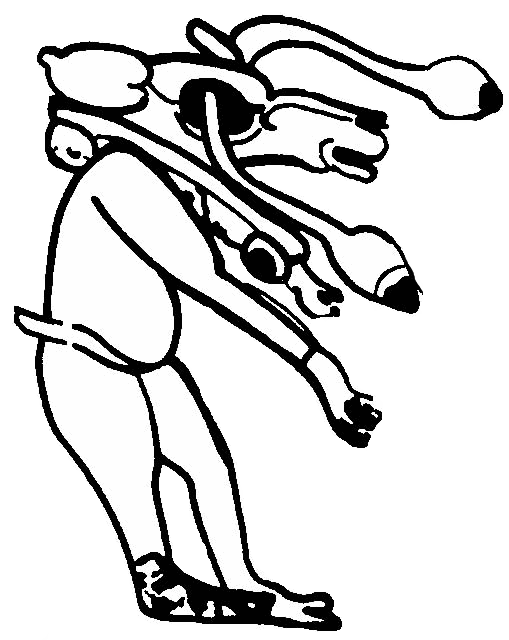

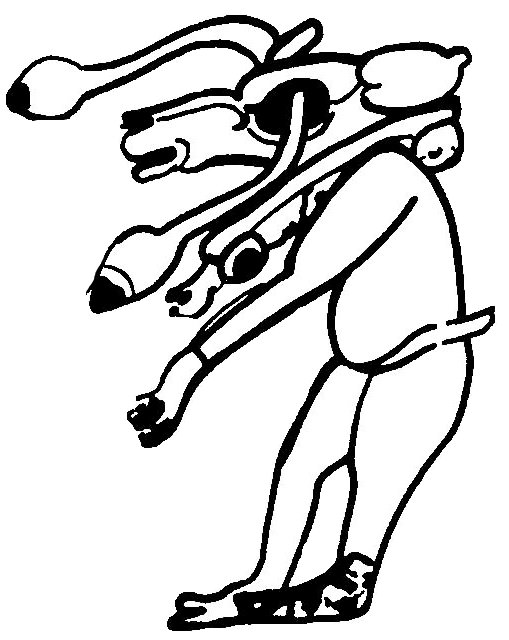
はたして自分たちの器を失い、別の器しか 残されていないラモンにとって、新たな器をもちうることが可能だろうか。また彼らの器についての み議論すれば、我々はそれで事足りるだろうか。ラモンの器は、ラモン個人が生み出したメタファーであるのと同時に、ディガーの人びとが共有できるメタ ファーであり、また人類学者ベネディクトとの対話の中で生まれた共感のメタファーでもある。ラモンの器は、一種の象徴表現のひとつであるが、器それ自体 は、我々の用語法に従うならば媒体(メディア)のことに他ならない。
ベネディクトの例を引くまでもなく、従来 の人類学が他の人文社会科学の諸分野に対して独自性を強調するとき、駆使される修辞はおもに、 (1)伝統社会と近代社会の二分法を立てて、近代社会の内容を特段に吟味することなく伝統社会の「独自性」を強調すること、(2)そのように強調される伝 統社会が、多種多様性をもち、社会の全体性からの解釈をもってはじめて理解しうるものであること、である。これらの2つの修辞のうち、前者は人類学外部の 研究領域に、後者は類似の研究をおこなう隣接研究領域ならびに人類学の領域の内部にむけて利用されてきた。ここでは、それらのうち前者の修辞は、社会意識 の産出にかんする議論にはもはや効力をもたないことを説明し、伝統と近代という二分法的な思考に代わる代替的方法について考察する。
そもそも伝統と近代、あるいは未開と文明 の二分法が生まれてくる前提条件とは何だったのか。
それを一言でいうと、近代社会の省察のた めの参照点として、伝統社会が対比的関係の中で持ち込まれることになったということである。19 世紀における伝統社会に関する研究は、当時の宣教師や商人からの通信を通して断片的に集積がはじまった「未開社会」や西欧の周辺社会の習俗の記述をもと に、慣習法、親族組織、宗教等の比較研究からはじまった。このような研究に拍車をかけたのは、フーコーの言う古典主義時代に分類表(タブロー)に配列され ていた事物が、19世紀以降には時系列のなかでの変化として捉えられるようになったという人文学の知的枠組みにおける変更にも関係しているように思われ る。時系列的な発想のもっとも強力なものは、発展というモデルであり、進化主義はその時代を代表する思潮である。ところが、この進化主義が提示する、時系 列における先行する古代と、周辺の空間にある「未開社会」の配置を、進化や発展という因果法則に関連づける方法には、それに先行する分類表的発想により親 和性が見られるように思える。より大胆に言えば、進化主義には伝統と近代の二分法というものは、存在しない。この断絶を象徴するものが伝統と近代を理念的 な二分法として考えるM・ウェーバーの見解であり、彼は歴史における因果法則に関しては大いなる疑問を抱き、特に進化論的な進歩の概念を退けている。
伝統と近代の二分法は、19世紀も終わり になってデュルケーム『社 会分業論』(1893)によって明確な形を与えられた。この社会学にお ける社会観の単純化と、その傍証に関する議論の洗練化は、それまでの進化主義とは完全に発想や理解を画するものである。ただし彼の議論は、伝統(未開)社 会は近代社会にくらべて個人の自由度が少ない──つまり新しい器を持ち得ない──というものではない。デュルケームの社会観には個人の自由度などというも のは存在しない、あるいはあっても微々たるものにすぎない。個人が自由や閉塞を感じることすらも、彼らの属する社会によって規定されていることを、彼の方 法論とそれに基づく一連の著作は示している。初期の機能主義人類学の古典は、このデュルケーム的な思考を、具体的な「未開社会」に徹底化して集積に血道を あげた結果であると言っても過言ではない。
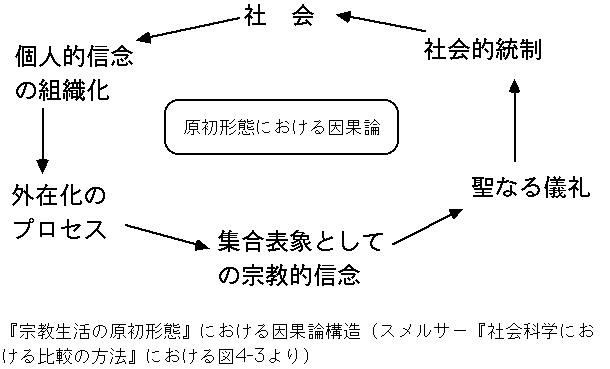


G・ジンメルを含めて近代社会学の創設に 多大なる影響を与えた上のような人たちは、近代人が主体性をもち、合理的に行動するための自由が 与えているということなどは、ゆめ考えてはいなかった。フィールドワークの方法論も確立し、近代社会科学として認知されつつあった機能主義人類学は、デュ ルケーム的命題を守り、個々の具体的な「未開社会」の固有の実体を明らかにすることに邁進した。しかしながら、この努力の結果は、「未開人」の意識に関す る社会拘束性に関する過度の期待を煽ったことになる。しばしば人類学が文化を本質主義化したという批判の論拠はここに求められる。あたかも新しい器をもつ ことができる主体という西洋近代のアイデンティティの神話のネガ像を、未開社会の機能主義人類学は提供したのである。そこでは、近代社会においても人々の 主体的選択もまた社会的に構成されたものであるという視点と、伝統社会における人々の主体的選択の様態そのものに関する視点は、共に捨象されたのである。 したがって未開社会の文化の本質主義化は、人類学の政治性──例えば、人類学は植民地科学の一つであるという批判──だけに還元される問題ではなく、西洋 近代社会の自己と他者の認識におけるある種の帰結であった。
文化を本質主義的に捉えてきたという批判 が本格化する以前は、伝統社会に住む人々が、その社会組織の構成原理に則って経験を形成するとい う理解が──新植民地主義批判という稀な例を除けば──比較的長い間受け入れられてきた。それは、西洋近代に対するアンチテーゼであり、また認識論的な反 省材料にもなったからである。
この時代における人類学の役回りは、その 文化の本質主義的な「理論」を、より高度に洗練させてゆくことにほかならなかった。ラモンの器の 例で言うならば、「古い器」に関するさまざまな情報が蓄積され、それについての議論が雪だるま式に増殖していった過程である。何事も文化に収斂させる人類 学理論が発展してゆくわけであるが、その営為は近代批判という弁明のもとで正当化された。その極限形態の例としてレヴィ=ストロースの構造主義があげられ る。レヴィ=ストロースは音韻論の構造からの構造主義アイディアを発展させたことはよく知られているが、社会理論に関しては、彼はデュルケームとモースの 知的遺産をたっぷりと受け継いだ。だから構造主義において主体性をもった個人というものは存在しないのは、当然の帰結なのである。五月革命 (May 68; Mai 68)の頃、構造主義 の外側からはアンチ・ヒューマニズムのラベルを貼られ、自己弁明としてはヒューマニズムを主張したことは、構造主義の社会観のアンビバレントな面をよく表 している。システムに支配された社会観をとる点では構造主義はアンチ・ヒューマニスティックであるが、ここの社会の固有性にあくまでもこだわる点では極め てヒューマニスティックなのである。構造主義には、新しい器について建設的な意見を表明するための認識論的な枠組みがそもそも欠けているし、そのような関 心は無益なのである。
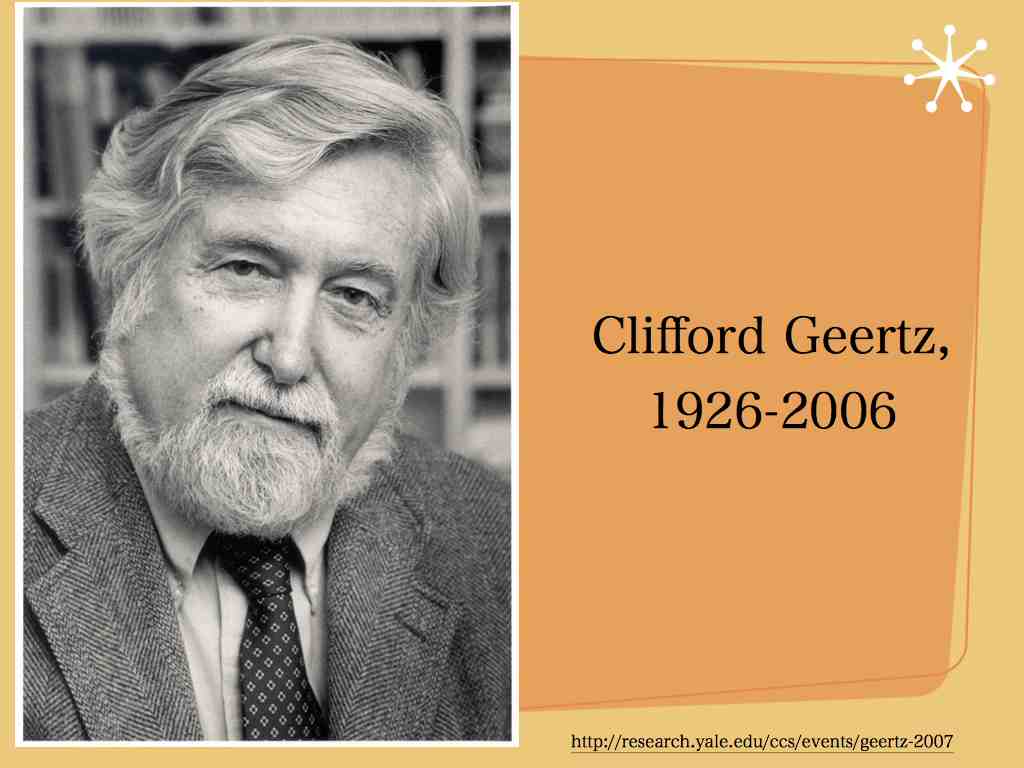
ポスト構造主義における、文化の本質主義 による隘路の乗り越えのひとつと考えられるのが、クリフォード・ギアーツによる人類学における解釈学的な転回で あり、またさらに、ある意味で文化の本質主義をさらに推進させたことにある。しかし、文化の本質を決定するのは解釈の妥当性や「厚い記述」であるので、文 化の本質的な解釈自体もまた反省の材料になりうる。解釈人類学が、自己に向けられる文化の本質主義批判から逃れる潜在的な可能性をもつのも、実はこの営為 にある。だが解釈人類学は、ラモンの言う器の形態、材質、文様などについて、より洗練された議論を重ねることに成功はしたかもしれないが、壊れた器を、は たして取り戻すことが可能なのか、あるいは新しい器を自ら作り出すことができるのかについては、解答を留保したままなのである。もちろん、その可能性はな いとは言えない(Geertz 1988:146-149)。
もちろん、重要なことは解釈人類学のみな らず、メディアを社会意識の審級とする議論にとって重要なことは、新しい器を人類がどのような形 で持ち得るのか、そして、そうであるならその器はどのようなものなのかを明らかにすることである。
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆