倫理学者は安楽椅子の人類学者たりえるか?
Can the ethists be an armchair anthropologist?
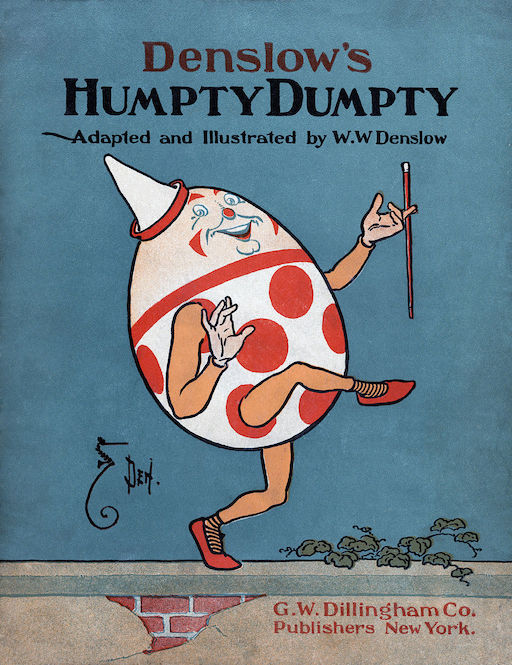
倫理学者は安楽椅子の人類学者たりえるか?
Can the ethists be an armchair anthropologist?
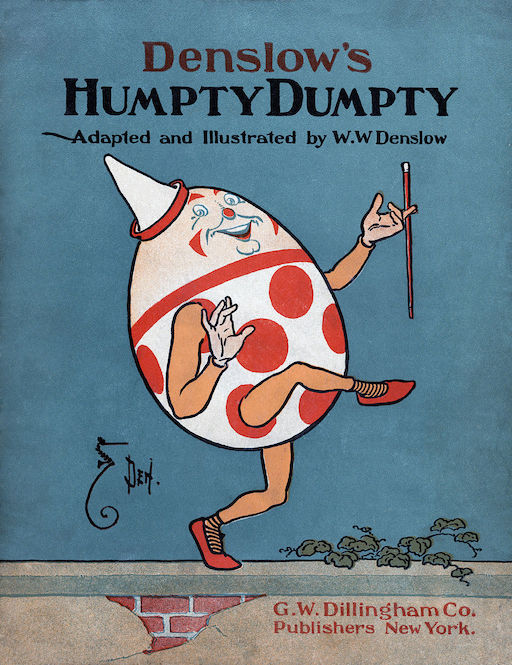
今日において倫理学者の名前で呼ばれる人たちは、かつて安楽椅 子の人類学者と呼ばれた人たちのことをさすのか?あるいは今日において応用人類学者と呼ばれる人たちのことをさすのか?
「安楽椅子(アームチェア)の人類学者はフィールドワークをおこなわない者としてマリノフスキーにおおいに軽蔑されているが当のマルセル・モースなんかはフィールド系のデータを使い縦横無尽に理論構築したので堂々とあるいは博物館の人類学者だと自称している.偉いわ」
問題提起:池田光穂
倫理学者(ethist)とは、倫理学(ethics)あるいは道徳哲学(moral philosophy)を研究(考究)している人のことをさす。したがって、倫理学者とは道 徳哲学者(moral philosopher)とも呼ばれる。
応用倫理学、生命[医療]倫理 学、ビジネス倫理学、科学倫理(→「研究倫理」)、技術者の倫理学(→「技術者倫理」)、あげくのはては、政治家の倫理学にいたるまで、今日では「倫 理」という思想=アイテムは、人間が 身につけなければならない、必要かつ不可欠なものであるらしい。
それに伴い、倫理学者の社会進出が著しい。かつて思弁的、現実をから遊離している、理想論あるい は常識の追認など、酷いことを言われ続けてきた倫理学は、「倫理が荒廃した」と言われる現代社会において、いまや人間の理性を保証する最後の砦のごとく取 り扱われている。
しかしながら、そのような倫理学の科学的ないしは理論的厳密性を保証するものは何かということを 反省的に[=倫理的に?]考えた際には、倫理学の内容証明のレベルというものはいささか心もとない。
カント[別に聖書を代替してもかまわない]の書物を暗記したり、それに精通することが倫理的では あるまい。英語の倫理学つまりエシックス[ethics]の語源となるギリシャ語のエトス(ethos)に遡れば、倫理とは、反復される慣習行為の中に見 いだせるものであり、その行為実践や価値観の精髄(エッセンス)を倫理とよぶものではなく[なぜなら、そのような実践や価値観は多様であり、ひとつのもと にまとめようとした瞬間に矛盾だらけで精髄=理論的統一性の夢は脆くも打ち砕かれるからであろう]、徹頭徹尾、個別の経験の中に回帰するものであるから だ。倫理は、経験とその経験を想起するたびに再検討される、人々の気持ちや価値観(エトス)である。
もし、そうだとしたら、今日の倫理学者が、社会の現実の実践のなかに、自らの存在意義を確認して いる今日的状況[少なくとも1990年代以降2007年までは]は、極めて健全、倫理学的実践の原点に「復帰」したと言っても過言ではない。
しかしながら、一部の臨床哲学者と呼ばれる人たちを除いて、倫理学者たちは、いまだ思弁という惰 眠の中にいるのではないだろうか? そして、それは、かつてフィールドワーク派の文化人類学たちが後に批判して止まなかった「安楽椅子(アームチェア)の 人類学者」と今日の倫理学者像は重なる。
倫理学者たちが、もしフィールドワークを している倫理学者を臨床哲学者と呼ぶのであれば、それは かつての、安楽椅子の人類学者たちが、フィールドワークをするニューウェーブの人類学者たちと観ていたのと同じような光景に出会う。
先に、安楽椅子の人類学者は、フィールド派人類学者により批判されるのであるが、フィールド派の 人類学が正統になるまでは、両者の人類学者の間の関係は比較的良好で、安楽椅子の人類学者は、現地からの宣教師たちなどの歴史的報告よりも、より洗練され たフィールドデータを提供する「現今の」正確な資料を敬意を払って取り扱っていたふしすらある。
フィールド派の人類学者が、自らのアームチェアを暖めることを嫌悪するようになった時に、はじめ て安楽椅子の人類学者のあり方(生き方)を否定的な眼で観ることができたのである。別の見方をすれば、フィールド派の人類学者は、アームチェア派の思弁的 立場を「同時に」取ることができるようになったため、アームチェア[オンリー]派を、人類学の王座から放逐する——ないしはフレイザー流の王殺し——をす るようになったのではなかろうか。
同じことが、フィールド派の人類学が陥った理論中心主義ないしはフィールドデータの思弁的解釈主 義への反動として、「真に人類にとって役立つものにするため」に生成した応用人類学にも言える。これらは、相互依存関係をもちながら、最終的に異質な面を 過度に強調することで、異質な部分を本質化し、最終的に敵として葬り去る、典型的な「中心へ回帰することを目的とした分派遠心活動」ではなかろうかという ことだ。
このようにみると、倫理学の中でおこりつつあることと、かつて文化人類学が経験してきたことに は、驚くべき一致がある。文化人類学者[である私]には、倫理学の ことを見下し、「倫理学者はもっと文化人類学のことを勉強するべきだ」などという傲慢な アドバイスは口が裂けても面と向かって言えない——陰口を叩くのは、その物語の寓意を当人がよく理解しているからである。
リンク
文献
その他の情報
