アルチュール・ド・ゴビノーの人種論
Arthur de Gobineau and history of
Racism

解説:池田光穂
アルチュール・ド・ゴビノーの人種論
Arthur de Gobineau and history of
Racism

解説:池田光穂
人種主義(レイシズム)とは、ルース・ベネディクト (1997: 116)によると「ある民族集団が先天的に劣っ ており、別の集団が先天的に優等であるように運命づけられている、と語るドグマ」のことである (Benedict 1945:98)。今 日では、人間集団の社会的違いを、生物学を基調とする本質主義的な種的な違いをあら ゆるタイプの差別や 権力にもとづく選別に利用する考え、をそう呼ぶことができる(→「人種主義」)。
さて、19世紀半ばのヨーロッパで最も重要な人種イデオロギーの推進者は、アルチュール・ド・ゴビノー伯爵(Joseph Arthur de Gobineau, 1816-1882)で、彼は19世紀後半の社会理論にほとんど計り知れない影響を及ぼした。1853年から55年にかけて出版された『人種間の不平等に 関 する論考』は、さまざまな作家によって広く読まれ、脚色され、宣伝された。彼は、その議論の一部を、多元論者、特にアメリカのサミュエル・モートンか ら輸 入した。ゴビノーは、世界の三大民族(白人、黒人、黄色人種)が築いた文明は、すべて白人種の産物であり、彼らの協力なしには文明は生まれないと主張し た。白人種の中で最も純粋なのはアーリア人である。アーリア人が下層人種との婚姻によってその血を薄めれば、文明の衰退を招くことになる。
★ゴビノーはいつも『Essai sur l'inégalité des races humaines』を自分の最高傑作とみなしており、その著者として記憶されることを望んでいた。平民に対する貴族の生来の優越性を信じていた強固な反動 主義者-彼はそれを完全に軽蔑していた-ゴビノーは、人種的に劣る平民に対する貴族の支配を正当化 するために、今では信頼されていない科学的人種主義の教義を受け入れていた。 ゴビノーは人種が文化を創造すると考えるよう になった。彼は、「黒人」、「白人」、「黄色人種」という3つの人種の間の区別は自然の障壁であり、「人種混 合」はそれらの障壁を破壊し、混乱をもたらすと主張した。また、「黄色人種」(アジア人)については、肉体的にも知性的にも平凡であるが、極めて強い物質 主義を持っており、それによって一定の成果を上げることができるとした。最後にゴビノーは、白人だけが知的な思考ができ、美を創造し、最も美しかったの で、白人が3つの人種の中で最高で偉大であると書いている 。「白人はもともと美と知性と強さを独占していた」と彼は書き、アジア人と黒人が持っている肯定的な性質はその後の混血のためであった。 ゴビノーはアーリア人(「光の者」または「高貴な者」)という言葉をヒンドゥー教の伝説と神話から取 り、遠い過去のある時期にインド亜大陸がアーリア人に よって征服されたことを記述している。19世紀には、ウィリアム・ジョーンズのような東洋学者によるインド・ヨーロッパ諸語の発見に大きな関心が寄せら れ、英語、アイルランド語、アルバニア語、イタリア語、ギリシャ語、ロシア語、サンスクリット語、ヒンディー語、ベンガル語、クルド語、ペルシア語など、 一見無関係な言語も、アイルランドからインドまでの広い範囲で話される同じ語族に属していると考えられていた[citation needed]...。 アーリア人の英雄の物語が書かれた古代ヒンドゥー教の聖典は、インド・ヨーロッパ人の起源を探ろうとする学者にとって大きな関心事であった [citation needed] 。ゴビノーは、白人はシベリアのどこかで、アジア人はアメリカ大陸で、黒人はアフリカで発生したと考えていた[58]。彼はアジア人の数の優位性から、白 人はヨーロッパ、中東、インド亜大陸に至る大移動を強いられたと考えており、征服したアーリア人の英雄に関する聖書とヒンズーの伝説はどちらもこの移動に 関する民間の記憶を反映していた[60]。 そして白人はハム人、セム人、ヤペ人という三つの下位人種に分裂したと考えている。後者はヒンドゥー教の伝説のアーリア人であり、すべての白人の中で最も 優秀で偉大な存在であった(→「アルチュール・ド・ゴビノー」)。
| Essai sur l'inégalité des races humaines (Essay on the Inequality of the Human Races, 1853–1855)
is a racist and pseudoscientific work of French writer Arthur de
Gobineau,[1] which argues that there are intellectual differences
between human races, that civilizations decline and fall when the races
are mixed and that the white race is superior. It is today considered
to be one of the earliest examples of scientific racism.[1] Expanding upon Boulainvilliers' use of ethnography to defend the Ancien Régime against the claims of the Third Estate, Gobineau aimed for an explanatory system universal in scope: namely, that race is the primary force determining world events. Using scientific disciplines as varied as linguistics and anthropology, Gobineau divides the human species into three major groupings, white, yellow and black, claiming to demonstrate that "history springs only from contact with the white races." Among the white races, he distinguishes the Aryan race, specifically the Nordic race and Germanic peoples, as the pinnacle of human development, comprising the basis of all European aristocracies. However, inevitable miscegenation led to the "downfall of civilizations". |
Essai sur l'inégalité des races
humaines、1853年-1855年)は、フランスの作家アルチュール・ド・ゴビノーの人種差別的で疑似科学的な著作であり[1]、人類の人種間に
は知的差異があり、人種が混血すると文明は衰退し没落し、白人種が優れていると主張している。これは今日、科学的人種差別の最も初期の例のひとつと考えら
れている[1]。 ブーランヴィリエが第三身分の主張からアンシャン・レジームを擁護するために民族誌を用いたことを発展させ、ゴビノーは普遍的な説明体系を目指した。ゴビ ノーは、言語学や人類学などさまざまな科学分野を駆使して、人類を白人、黄色人種、黒色人種の3つに大別し、「歴史は白色人種との接触によってのみ生まれ る」と主張する。白人種の中でもアーリア人種、特に北欧人種とゲルマン民族を人類発展の頂点と位置づけ、ヨーロッパ貴族の基礎を築いたとする。しかし、必 然的な混血が「文明の没落」につながった。 |
| Background Gobineau was a Legitimist who despaired at France's decline into republicanism and centralization. The book was written after the 1848 revolution when Gobineau began studying the works of physiologists Xavier Bichat and Johann Blumenbach. The book was dedicated to King George V of Hanover (1851–66), the last king of Hanover. In the dedication, Gobineau writes that he presents to His Majesty the fruits of his speculations and studies into the hidden causes of the "revolutions, bloody wars, and lawlessness" ("révolutions, guerres sanglantes, renversements de lois") of the age. In a letter to Count Anton von Prokesch-Osten in 1856 he describes the book as based upon "a hatred for democracy and its weapon, the Revolution, which I satisfied by showing, in a variety of ways, where revolution and democracy come from and where they are going."[2] |
背景 ゴビノーは、フランスが共和制と中央集権主義に堕落していくことに絶望した正統主義者であった。本書は、ゴビノーが生理学者グザヴィエ・ビシャとヨハン・ブルメンバッハの研究を始めた1848年の革命後に書かれた。 本書は、ハノーファー最後の国王ジョージ5世(1851-66)に献呈された。献辞の中でゴビノーは、この時代の「革命、血なまぐさい戦争、無法」 (「révolutions, guerres sanglantes, renversments de lois」)の隠された原因についての思索と研究の成果を陛下に献呈すると書いている。 1856年にアントン・フォン・プロケシュ=オステン伯爵に宛てた手紙の中で、彼はこの本を「民主主義とその武器である革命に対する憎悪に基づいており、 革命と民主主義がどこから来てどこへ行こうとしているのかを様々な方法で示すことによって、それを満足させた」と述べている[2]。 |
| Gobineau and the Bible In Vol I, chapter 11, "Les différences ethniques sont permanentes" ("The ethnic differences are permanent"), Gobineau writes that "Adam is the originator of our white species" ("Adam soit l'auteur de notre espèce blanche"), and creatures not part of the white race are not part of that species. By this Gobineau refers to his division of humans into three main races: white, black, and yellow. The biblical division into Hamites, Semites, and Japhetites is for Gobineau a division within the white race. In general, Gobineau considers the Bible to be a reliable source of actual history, and he was not a supporter of the idea of polygenesis. |
ゴビノーと聖書 第1巻第11章「民族の相違は永続的である」(「Les différences ethniques sont permanentes」)で、ゴビノーは「アダムはわれわれの白色人種の始祖である」(「Adam soit l'auteur de notre espèce blanche」)と書いており、白色人種に属さない生き物はその種族に属さないとしている。これはゴビノーが人間を白、黒、黄の三大種族に分けたことを 指している。聖書のハム人、セム人、ヤフェット人という区分は、ゴビノーにとっては白人種の中の区分である。一般的に、ゴビノーは聖書が実際の歴史につい て信頼できる情報源であると考えており、彼は多系統発生説=人種多元論者(polygenist)の支持者ではなかった。 |
| Translation Josiah Clark Nott hired Henry Hotze to translate the work into English. Hotze's translation was published in 1856 as The Moral and Intellectual Diversity of Races, with an added essay from Hotze and appendix from Nott. However, it "omitted the laws of repulsion and attraction, which were at the heart of Gobineau's account of the role of race-mixing in the rise and fall of civilizations".[3] Gobineau was not pleased with the version; Gobineau was "particularly concerned that Hotze had ignored his comments on 'American decay generally and upon slaveholding in particular'."[4] The German translation Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen first appeared in 1897 and was translated by Ludwig Schemann, a member of the Bayreuth Circle and "one of the most important racial theorists of imperial and Weimar Germany".[5] A new English-language version The Inequality of Human Races, translated by Adrian Collins, was published in Britain and the US in 1915 and remains the standard English-language version. It continues to be republished in the US. |
翻訳 ジョサイア・クラーク・ノットはヘンリー・ホッツェに英訳を依頼した。ホッツェの翻訳は、ホッツェのエッセイとノットの付録を加え、『The Moral and Intellectual Diversity of Races』として1856年に出版された。しかし、「文明の興亡における人種混血の役割に関するゴビノーの説明の核心であった斥力と引力の法則が省かれ ていた」[3]。ゴビノーはこの翻訳に満足していなかった。ゴビノーは「特に、ホッツェが『一般的にはアメリカの衰退、特に奴隷飼育』に関する彼のコメン トを無視したことを懸念していた」[4]。 ドイツ語訳のVersuch über die Ungleichheit der Menschenrassenは1897年に初めて出版され、バイロイト・サークルのメンバーであり「帝政ドイツとヴァイマル・ドイツの最も重要な人種論 者の一人」であったルートヴィヒ・シェーマンによって翻訳された[5]。 エイドリアン・コリンズによって翻訳された新しい英語版『The Inequality of Human Races』は、1915年にイギリスとアメリカで出版され、現在でも標準的な英語版となっている。アメリカでは現在も再版されている。 |
| Influence Steven Kale argues that Gobineau's "influence on the development of racial theory has been exaggerated and his ideas have been routinely misconstrued".[6] Gobineau's ideas found an audience in the United States and in German-speaking areas more so than in France, becoming the inspiration for a host of racial theories, for example those of Houston Stewart Chamberlain. "Gobineau was the first to theorize that race was the deciding factor in history and the precursors of Nazism repeated some of his ideas, but his principle arguments were either ignored, deformed, or taken out of context in German racial thought".[7] German historian Joachim C. Fest, who wrote a biography of Hitler, describes Gobineau, in particular his negative views on race-mixing as expressed in his essay, as an eminent influence on Adolf Hitler and Nazism. Fest writes that the influence of Gobineau on Hitler can be easily seen and that Gobineau's ideas were used by Hitler in simplified form for demagogic purposes: "Significantly, Hitler simplified Gobineau's elaborate doctrine until it became demagogically usable and offered a set of plausible explanations for all the discontents, anxieties, and crises of the contemporary scene."[8] However, Professor Steven Kale has cautioned that "Gobineau's influence on German racism has been repeatedly overstated".[7] Although cited by groups such as the Nazi Party, the text implicitly criticizes antisemitism and describes Jews in positive terms, the Jews being seen as a superbly forged race of "ancient Greek-like strength" of cohesion. Implicitly, the folk of Judah merely represented a wandering, semi-austral variation of Ur-Aryan blood-stock. Gobineau stated, "Jews... became a people that succeeded in everything it undertook, a free, strong, and intelligent people, and one which, before it lost, sword in hand, the name of an independent nation, had given as many learned men to the world as it had merchants." Philo-Judaic sentiment was intermixed with ethnological theories concerning the primally Indo-Iranian/Indo-Aryan archeogenetic matrix whence sprang the Jews. In these lines of speculative anthropology, the Jews were anciently (supposedly) primordially interpreted as of atypical Indo-European ethnicity: Judaic racial typology emerged from Iranid–Nordid founders, the details considered inessential, possessors of compatibly "white" "Aryan" blood being the main point. The latter-day "Hamiticized" Jewish folk came into existence from non-Afro-Asiatic Hurrian (or Horite), Jebusite, Amorite or early-Hittite, Mittani-affiliated racial nuclei, the "consensus science" of the time asserted. The blatantly, ironically almost aggressive pro-Jewish attitude of Gobineau, akin to Nietzsche in sheer admiration and lionization of the Jews as one of the "highest races", proved ideologically vertiginous to the Nazi propagandists and Procrustean thinkers—here Gobineau unmistakably contradicted perhaps the main pillar of Nazi political ideology, which has been described as the schizoid, neo-Gnostic dualism of "Jewish demonology". Incompatible with Nazi ideology, the Count's fervent Judaic positivity and total dearth of antisemitism the Nazis could only attempt to ignore or minimize away in the silence of hypocrisy.[9][10] The book continued to influence the white supremacist movement in the United States in the early 21st century.[11] |
影響力 スティーヴン・ケールは、ゴビノーの「人種論の発展への影響は誇張されており、彼の思想は日常的に誤って解釈されてきた」と論じている[6]。 ゴビノーの思想はフランスよりもアメリカやドイツ語圏の人々に受け入れられ、例えばヒューストン・スチュワート・チェンバレンのような多くの人種理論のイ ンスピレーションとなった。「ゴビノーは人種が歴史を決定する要因であると理論化した最初の人物であり、ナチズムの先駆者たちは彼の考えのいくつかを繰り 返したが、ドイツの人種思想では彼の原則的な主張は無視されるか、変形されるか、文脈から外れるかのいずれかであった」[7]。 ドイツの歴史家ヨアヒム・C. ヒトラーの伝記を著したドイツの歴史家ヨアヒム・C・フェストは、ゴビノー、特に彼のエッセイで述べられているような人種混合に対する彼の否定的な見解 は、アドルフ・ヒトラーとナチズムに多大な影響を与えたと述べている。フェストは、ゴビノーがヒトラーに与えた影響は容易に見て取れ、ゴビノーの思想はヒ トラーによってデマゴーグのために単純化された形で利用されたと書いている: 「重要なのは、ヒトラーがゴビノーの精緻な教義を単純化し、それがデマゴギー的に使えるようになり、現代のあらゆる不満、不安、危機に対してもっともらし い一連の説明を提供するようになったことである」[8]。しかし、スティーヴン・ケール教授は「ゴビノーのドイツ人種主義への影響は繰り返し誇張されてき た」と警告している[7]。 ナチ党のような集団によって引用されたとはいえ、このテキストは暗黙のうちに反ユダヤ主義を批判し、ユダヤ人を肯定的な言葉で描写している。暗黙のうち に、ユダの民はウル=アーリア人の血統を半オーストリア的に変化させた流浪の民に過ぎないとされているのだ。ゴビノーは、「ユダヤ人は......引き受 けたことすべてにおいて成功した民族となり、自由で、強く、知的な民族となり、剣を手にして独立国民の名を失う前に、商人と同じくらい多くの学識者を世に 送り出した民族となった」と述べている。フィロ・ユダヤ主義的な感情は、ユダヤ人がどこから生まれたのか、原初的にはインド・イラン/インド・アーリア人 の原型に関する民族学的な理論と混ざり合っていた。このような思索的人類学において、ユダヤ人は古来(と思われる)原初的には非典型的なインド・ヨーロッ パ系民族であると解釈された: ユダヤ人の人種類型論はイラン系と北欧系の祖先から生まれたもので、その詳細は重要ではなく、適合する「白人」「アーリア人」の血を持つことが重要だと考 えられていた。後世の 「ハミタイ化した 」ユダヤ人は、アフロ・アジア系ではないヒュリア人(またはホライト人)、エブス人、アモリ人、あるいはヒッタイト人初期、ミッタニ系の人種核から生まれ たと、当時の 「コンセンサス・サイエンス 」は主張していた。ゴビノーの露骨な、皮肉にもほとんど攻撃的な親ユダヤ的態度は、ニーチェのようにユダヤ人を「最高の人種」の一つとして賞賛し、獅子奮 迅の活躍を見せたが、ナチスの宣伝担当者やプロクラステス派の思想家にとっては、イデオロギー上、癇に障るものであった-ここでゴビノーは、「ユダヤ人の 悪魔論」の分裂主義的、新グノーシス主義的二元論と形容されるナチスの政治イデオロギーの主要な柱と、紛れもなく矛盾していた。ナチスのイデオロギーとは 相容れず、伯爵の熱烈なユダヤ教肯定論と反ユダヤ主義の完全な欠落は、ナチスは偽善の沈黙の中で無視を試みるか、最小限に食い止めることしかできなかった [9][10]。 この本は21世紀初頭のアメリカにおける白人至上主義運動に影響を与え続けた[11]。 |
| IQ and Global Inequality Scientific racism |
IQと世界の不平等 科学的人種差別 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/An_Essay_on_the_Inequality_of_the_Human_Races |
|
| Essai sur l'inégalité des races humaines
est un essai d'Arthur de Gobineau paru en 1853 pour la première
édition, partielle, visant à établir les différences séparant les
différentes « races humaines », blanche, jaune et noire. Il est édité
en entier pour la première fois en 1855. La valeur de l'ouvrage est très contestée étant considéré comme un ouvrage raciste mais, pour certains spécialistes de Gobineau, ce n'est pas le cas, le titre portant ombrage à l’œuvre littéraire1. Jean Boissel parle de « livre-musée qui est aussi un livre-pamphlet »2. |
Essai sur l'inégalité des races humaines(人種間の不平等に関するエッセイ)はアルチュール・ド・ゴビノーのエッセイで、初版は1853年に出版された。1855年に初めて全文が出版された。 この作品は人種差別的であると考えられているため、その価値については多くの議論があるが、一部のゴビノーの専門家にとっては、タイトルが文学作品に影を 落としているため、そうではないようだ1。ジャン・ボワセルはこの作品を「本のパンフレットでもある博物館」と呼んでいる2。 |
| Méthode L'Essai sur l'inégalité des races humaines est un long ouvrage mêlant assertions scientifiques et préjugés populaires. Bien que son but soit de « faire entrer l’histoire dans la famille des sciences naturelles », le caractère scientifique de l'ouvrage est à nuancer fortement en ce que le point de départ de la réflexion de Gobineau, clairement revendiqué, est l'histoire du monde telle qu'elle est décrite dans l'Ancien Testament : il passe en revue l'histoire ancienne et sa succession de peuples et de civilisations à l'aune du critère unique des trois races noire, jaune et blanche, qu'il définit succinctement au début de l'ouvrage par quelques considérations essentiellement physiologiques et psychologiques. Le mélange des races est pour Gobineau le moteur de l'histoire. Tout est réductible à cette cause comme il le souligne lui-même : « je ne me dissimule pas non plus que la libre action des lois organiques, auxquelles je borne mes recherches, est souvent retardée par l'immixtion d'autres mécanismes qui lui sont étrangers. Il faut passer sans étonnement par-dessus ces perturbations momentanées, qui ne sauraient changer le fond des choses. À travers tous les détours où les causes secondes peuvent entraîner les conséquences ethniques, ces dernières finissent toujours par retrouver leurs voies. Elles y tendent imperturbablement et ne manquent jamais d'y arriver » Gobineau analyse chaque peuple un à un, en expliquant ses réussites ou ses échecs selon la prédominance de tel ou tel élément ethnique en son sein ; en réalité, sa vision ethnologique est marquée par une hiérarchie des races rarement dissimulée. Guidé par ce principe raciste qu'il justifie finalement peu, le contenu de l'œuvre apparaît donc essentiellement historique, avec l'aide de l'archéologie, de la linguistique, de la littérature. Parlant de l'ethnologie, Gobineau souligne que « C’est la frapper de stérilité que de l’appuyer avec prédilection sur une science isolée, et principalement sur la physiologie. Ce domaine lui est ouvert, sans nul doute ; mais, pour que les matériaux qu’elle lui emprunte acquièrent le degré d’authenticité nécessaire et revêtent son caractère spécial, il est presque toujours indispensable qu’elle leur fasse subir le contrôle de témoignages venus d’ailleurs, et que l’étude comparée des langues, l’archéologie, la numismatique, la tradition ou l’histoire écrite, aient garanti leur valeur, soit directement, soit par induction, a priori ou a posteriori. » Les analyses physiologiques des races sont en effet minoritaires chez Gobineau par rapport aux discours sur le caractère des peuples tels qu'il se révèle dans les annales ou dans l'archéologie. Finalement, en plus de cette tendance à l'érudition, l'ouvrage frappe par sa forte charge littéraire, soulignée par exemple par Hubert Juin dans sa préface3. |
方法 『人種不平等論』は、科学的主張と民衆の偏見を組み合わせた長大な著作である。その目的は「歴史を自然科学の範疇に入れる」ことであるが、ゴビノーの思考 の出発点が旧約聖書に記述されている世界の歴史であることを明確に主張しているため、この作品の科学的性格は強く制限されている。 ゴビノーにとって、人種の混合は歴史の原動力である。彼自身が指摘しているように、すべてはこの原因に還元できる: 「私が研究対象としている有機的法則の自由な作用が、しばしば、それとは異質な他のメカニズムの干渉によって遅延されることを、私は自分自身から隠すつも りはない。物事の本質を変えることのできないこれらの瞬間的な妨害は、驚くことなく乗り越えなければならない。二次的な原因が民族的な結果を導くあらゆる 回り道を経て、後者は常に戻る道を見つけることになる。それは、決して失敗することなく、平然と行われるのである。 ゴビノーは各民族をひとつひとつ分析し、その中の民族的要素の優劣によってその成功や失敗を説明する。現実には、彼の民族学的ビジョンは、めったに隠されることのない民族のヒエラルキーによって特徴づけられる。 この人種主義的原則に導かれ、それを正当化することはほとんどなく、著作の内容は、考古学、言語学、文学の助けを借りて、基本的に歴史的なものである。民族学について、ゴビノーは次のように指摘する。 「孤立した科学、主として生理学を基礎とするのは不毛のしるしである。しかし、そこから借用する資料が必要な程度の信憑性を獲得し、その特別な性格を帯び るためには、ほとんどの場合、他所からの証言の統制を受けることが不可欠であり、言語、考古学、貨幣学、伝承、文字史の比較研究は、直接的に、あるいは先 験的、後験的に、帰納的に、その価値を保証するものでなければならない」と述べている。 ゴビノーの人種に関する生理学的分析は、年代記や考古学で明らかにされた民族の性格に関する言説と比較すると、実際には少数派である。最後に、このような 博学的な傾向に加えて、この著作は、例えばユベール・ジュアンが序文で強調しているように、強い文学性を持っていることが印象的である3。 |
| Résumé de l'ouvrage Livre 1 : Considérations préliminaires Gobineau y explique la cause de la chute des civilisations: Les civilisations sont « Un état de stabilité relative, où des multitudes s'efforcent de chercher pacifiquement la satisfaction de leurs besoins, et raffinent leur intelligence et leurs mœurs » Leurs décadences ne s'expliquent ni par des causes climatiques, ni par des considérations morales, ni par l'action du politique, mais par des causes raciales. Contre l'idée d'une émergence de plusieurs races humaines dans le monde, Gobineau pose une origine commune à une époque adamique. Une période de climats très intenses (époque des géants) a modifié par la suite en profondeur la physiologie des hommes, et donné naissance à trois races bien distinctes, chaque race possédant son caractère propre. L'auteur affirme que ces caractères peuvent être hiérarchisés, avec au sommet les Blancs : ainsi les Noirs auraient le front fuyant, les traits affirmés, une intelligence inférieure, un sens de l'odorat et du goût développé, et un penchant pour l'extrême et le grotesque ; les Jaunes un front large d'où les traits peinent à se dégager, et un sens pratique visant à une jouissance tranquille de petit bourgeois ; le Blanc enfin est caractérisé par son sens de l'action et une largeur de vue très développée, associée à un manque de sensualité et de goût artistique. Livre 2 : Civilisation antique rayonnant de l'Asie centrale au Sud-Ouest Gobineau dresse alors la carte des mouvements des races qu'il a définies : les Noirs se répandent d'Afrique jusqu'en Asie, les Jaunes depuis l'Amérique soit vers l'Europe, soit le long des côtes asiatiques (où ils fusionnent avec les Noirs dans le type du Malais), quant aux Blancs, le berceau de leur race serait situé autour de la Mongolie-Mandchourie. Entre l'Asie et l'Afrique, plusieurs races, notamment les Chamites, que Gobineau n'assimile pas aux Noirs, et les Sémites, développent des civilisations, toutes marquées à un degré plus ou moins fort, par un métissage avec la race noire : c'est le temps de l'Assyrie, de la Phénicie, ou de l'Egypte. Les monuments de ces civilisations s'expliquent selon lui par le goût de la démesure de ces peuples orientaux et le sens artistique des Noirs : « le nègre est la créature humaine la plus énergiquement saisie par l'émotion artistique, mais cette émotion est toujours guettée par le grotesque. » Gobineau reconsidère ainsi les civilisations : la civilisation égyptienne aurait par exemple été stationnaire, tandis que l'Assyrie, berceau de l'art grec selon Winckelmann, lui serait supérieure. Livre 3 : Civilisation rayonnant de l’Asie centrale vers le Sud et le Sud-Est L'Inde, pour laquelle Gobineau ne cache pas son admiration, voit la perpétuation d'une race aryenne malgré de multiples invasions, grâce à une ségrégation par les castes : l'ordre de la société n'y est qu'un paravent d'un ordre racial. Alors que les Aryens s'entredéchirent dans des divisions incessantes, la Chine se développe de manière presque autonome autour d'un Empire unifié, où règnent l'administration et l'utilitarisme. Autour de ces deux civilisations, des peuples marqués par le sang noir se développent sans pouvoir atteindre à la perfection de l'Inde et de la Chine. Les Blancs naissent en Mongolie, où ils sont surpris par la vitalité des Jaunes et se déplacent vers l'ouest, conquérant alors des territoires de peuples plus faibles. Livre 4 : Civilisations sémitisées du Sud-Ouest Le miracle grec naît de la conjonction des sangs blanc et jaune, et la décadence hellénistique s'explique par l'influence des peuples sémites environnants, sensible dans l'art monumental ou dans le despotisme politique. Livre 5 : Civilisation européenne sémitisée Rome se développe également grâce au sang blanc des différents peuples installés alors en Europe. Les Sabins, héritiers des Cimbres ou Gaulois, donnent une dimension aristocratique et guerrière à la Rome naissante. L'empire qui se crée par la suite ne fait qu'amalgamer les peuples et favoriser le métissage en ménageant les particularités de chacun par un droit de plus en plus développé. Rome, comme la Grèce, tombera à cause de ses tendances sémitiques visibles clairement dans le byzantinisme. Livre 6 : La civilisation occidentale Tandis que les marches de l'Europe sont tenues par le Slave, marqué par son sang blanc, jaune et finnois, et sa personnalité « trop faible et trop douce pour exciter de bien longues colères chez les hommes qui l'envahissent, sa facilité à accepter le rôle secondaire dans les nouveaux États fondés par la conquête, son naturel laborieux », les Aryens développent leur culture égalitaire de propriétaires terriens et de guerriers. Les Aryens germains revivifient l'Empire romain et font entrer l'Europe dans le Moyen Âge, tandis que les Aryens scandinaves poussent leurs expéditions en Mer Noire et en Amérique. Cette vitalité, visible dans les villes italiennes, la France de l'Oïl ou la région du Rhin au Moyen Âge, se perpétuera dans l'entreprise d'expansion coloniale, avec le massacre, justifié dans la perspective naturaliste du développement des races, des peuples indiens, essentiellement jaunes, qui peuplaient l'Amérique. Conclusion générale Gobineau conclut sur un tableau pessimiste : la race blanche est pour lui le principe vivifiant qui met en contact les races et permet la civilisation ; avec les empires coloniaux, elle a achevé sa tâche. « Les deux variétés inférieures de notre espèce, la race noire, la race jaune, sont le fond grossier, le coton et la laine, que les familles secondaires de la race blanche assouplissent en y mêlant leur soie tandis que le groupe arian, faisant circuler ses filets plus minces à travers les générations ennoblies, applique à leur surface, en éblouissant chef-d'œuvre, ses arabesques d'argent et d'or. » Dans le même temps, la race blanche s'annihile, puisqu'elle se dissout dans un métissage généralisé qu'elle a contribué à créer. L'histoire voit donc la disparition progressive de l'homme blanc, remplacé par des peuples métis uniformes et sans vitalité. Une fois que ce principe de vitalité aura disparu, l'humanité tout entière se laissera mourir. En prévoyant la fin de toute communauté humaine, Gobineau utilise une formule qui a profondément impressionné ses contemporains, y inclus Richard Wagner: « Les nations, non, les troupeaux humains, accablés sous une morne somnolence, vivront dès lors engourdis dans leur nullité, comme les buffles ruminants dans les flaques stagnantes des marais Pontins. » |
作品概要 第1巻:予備的考察 ゴビノーは文明が滅びる原因を次のように説明する。 「相対的に安定した状態であり、その中で大群衆は平和的に欲求を満たそうと努力し、知性と道徳を磨いている」。 その衰退は、気候的な原因でも、道徳的な考慮でも、政治的な行動でもなく、人種的な原因によって説明することができる。 ゴビノーは、世界に複数の人種が生まれたという考えに対して、アダムの時代に共通の起源があるとする。その後、非常に激しい気候の時代(巨人の時代)が人 間の生理を大きく変化させ、それぞれが独自の性格を持つ3つの非常に異なる人種を生み出した。黒人は後退した眉、自己主張の強い顔立ち、劣った知性、発達 した嗅覚と味覚、極端でグロテスクなものを好む、黄色人種は広い額から顔を出そうともがく顔立ち、プチ・ブルジョワの静かな楽しみを目指した実用的な感覚 を持つ、白人は行動的な感覚と高度に発達した視野の広さ、官能性と芸術的センスの欠如が特徴である。 第2巻:中央アジアから南西部へ放射状に広がる古代文明 黒人はアフリカからアジアへ、黄色人種はアメリカからヨーロッパへ、あるいはアジアの海岸沿い(そこで黒人と融合してマレー系を形成した)、そして白人はその発祥の地であるモンゴル・満州周辺に位置する。 アジアとアフリカの間には、いくつかの民族、特にゴビノーが黒人と同一視していないシャム人とセム人が文明を発展させたが、いずれも多かれ少なかれ黒人と 交雑していた。アッシリア、フェニキア、エジプトの時代である。これらの文明のモニュメントは、これらの東方民族の過剰な趣味と黒人の芸術的センスによっ て説明することができる: 黒人は芸術的感情に最もエネルギッシュに捕らわれる人間であるが、この感情は常にグロテスクなものに脅かされている」。 ゴビノーはこうして文明を再考する。例えば、エジプト文明は停滞していたと言われ、一方、ウィンケルマンによればギリシャ芸術の発祥地であるアッシリアは優れていたと言われる。 第3巻:中央アジアから南・南東へ放射状に広がる文明 ゴビノーが賞賛を隠さなかったインドでは、カーストによる隔離のおかげで、何度もの侵略にもかかわらずアーリア人種が永続した。 アーリア人が絶え間ない分裂の中で互いに争っていた一方で、中国は統一された帝国を中心にほぼ自律的に発展し、そこでは行政と功利主義が最高位に君臨していた。 この2つの文明の周辺では、黒人の血を引く民族が、インドや中国のような完璧な発展を遂げることなく発展していった。 白人はモンゴルで生まれ、黄人の生命力に驚き、西へ西へと移動し、より弱い民族の領土を征服した。 第4巻:南西部のセム文明 ギリシャの奇跡は、白人と黄色人種の血のつながりから生まれた。ヘレニズムの退廃は、記念碑的な芸術や政治的専制主義に見られる、周辺のセム系民族の影響によって説明できる。 第5巻:セム系ヨーロッパ文明 ローマもまた、当時ヨーロッパに定住していたさまざまな民族の白人の血のおかげで発展した。チンブル人やガリア人の血を引くサビネス人は、新興ローマに貴 族的で戦争好きな側面を与えた。その後誕生した帝国は、それぞれの民族を単純に統合し、相互融合を促した。ローマはギリシアと同様、ビザンティン主義に はっきりと見られるセム人的傾向のために滅亡した。 第6巻 西洋文明 白、黄、フィンランドの血を引くスラヴ人と、「弱く、優しすぎるため、侵略してきた人々に長い間怒りを抱かせることができず、征服によって建国された新し い国家では二次的な役割を容易に受け入れ、勤勉な性格」であることが特徴的なスラヴ人がヨーロッパの進軍路を確保する一方で、アーリア人は地主と戦士とい う平等主義的な文化を発展させた。 ゲルマン系アーリア人はローマ帝国を復活させ、ヨーロッパを中世へと導き、スカンジナビア系アーリア人は黒海やアメリカへの遠征を推し進めた。この活力 は、中世のイタリアの都市、オイール・フランス、ライン地方に見られ、植民地拡大という事業の中で永続し、アメリカ大陸に移住したインディアン(本来は黄 色人種)の虐殺は、種族の発展という自然主義の観点から正当化された。 結論 ゴビノーは悲観的な見解で締めくくっている。彼にとって、白人種とは、人種を接触させ、文明を可能にする生命を与える原理であり、植民地帝国によって、その役目を終えたのである。 「黒人種と黄色人種という2つの下等種族は、綿と羊毛という粗い背景であり、白人種の中等種族は絹を混ぜて柔らかくし、アリウス種族はより細い糸を高貴な世代に渡して、銀と金の唐草模様をその表面に施し、まばゆいばかりの傑作とする。 同時に、白人種は、その創造に貢献した一般化された異種交配の中で溶解し、消滅しつつある。それゆえ歴史は、白人が徐々に消滅し、生命力のない画一的な混血民族に取って代わられるのを目撃している。この生命力の原理が消滅すれば、人類は全体として滅亡する。 ゴビノーは、すべての人間共同体の終焉を予言する際に、リヒャルト・ワーグナーを含む同時代の人々に深い感銘を与えた言葉を用いた: 「国家は、いや、人間の群れは、どんよりとした気だるさに打ちひしがれ、ポンティーヌ沼の淀んだ池で反芻する水牛のように、それからは無感覚のうちに生きていくだろう」。 |
| Postérité et critiques En 1885, trois ans après la mort d'Arthur de Gobineau, l'écrivain haïtien Joseph Anténor Firmin publia un essai d'un volume comparable (650 pages) où il réfute les thèses sur l'inégalité des races. Le titre de son livre, De l'égalité des races humaines4, fait allusion au livre d'Arthur de Gobineau. Alors qu'il accepte a priori la notion de race, il explique le flou sur leurs définitions et l'absence de fondement des théories de hiérarchisation de ces races. Il souligne les réalisations noires à travers l'histoire, depuis l’Égypte antique et l’Éthiopie jusqu'à la République noire d'Haïti. Le titre du livre I indique Considérations préliminaires ; définitions, recherche et exposition des lois naturelles qui régissent le monde social. Gobineau part « du fait établi » que les civilisations meurent, et il cherche les causes de ce déclin supposé des civilisations. Il proclame que l'athéisme ou l'immoralisme n'ont jamais fait mourir une société, pas plus que les mauvaises institutions ou les mauvais gouvernements5. Pour Gobineau, les civilisations déclinent de façon naturelle par dégénération, terme qu'il emprunte à la zoologie de son époque, représentée alors par Georges Cuvier (1769-1832). La dégénération est pour Cuvier ce qu'il advient des espèces domestiquées par l'homme par croisements successifs. Selon Cuvier, il y a dans les animaux une permanence qui résiste à toutes les influences, naturelles et humaines, ce qui lui permet d'affirmer le concept d'espèce fixe, toute variation qui s'en écarte étant dégénération5. Ce que Cuvier applique à l'espèce, Gobineau va l'appliquer à la race, en disant que les différences ethniques sont permanentes (titre chap. XI du livre I), en prenant l'exemple des Juifs. Gobineau associe et identifie race et peuple, race et nation, en prétendant s'appuyer sur les leçons de l'histoire. Il affirme que la race blanche est la plus noble de toutes. Pour cela, il ramène l'histoire à 6 grandes civilisations qu'il identifie à la race, en proclamant qu'une civilisation n'est grande qu'en gardant son groupe fondateur, et d'autant plus grande qu'elle découle de la race blanche, et de son rameau le plus illustre, la famille « ariane »5. Gobineau, comme tous les historiens de son temps, commence par poser l'importance fondamentale de la race franque dans la naissance de la civilisation occidentale puis s’interroge sur ce qu'il reste de cette race et répond : « rien ». Contrairement à Richard Wagner, il ne croit pas à un destin cyclique de la race allemande. Il précise d'ailleurs qu'il ne reste de l'ancienne race aryenne que de ridicules poches en Angleterre et en Belgique6. Pour Gobineau, l'homme contemporain est un homme de la décadence, un dégénéré, un produit différent de ses fondateurs, « parce qu'il n'a plus dans ses veines le même sang, dont des alliages successifs ont graduellement modifié la valeur ; autrement dit, qu'avec le même nom, il n'a pas conservé la même race »5. Marie-Françoise Audouard conclut au sujet de l'ouvrage : « L’Essai, dont on a voulu faire une des sources du nazisme, est très précisément le contraire puisque l'auteur y dénonce tout ce que le nazisme systématisera : le nationalisme, le fonctionnarisme, la démagogie, la misère intellectuelle des parvenus et des petits chefs, la haine des supériorités morales et, bien entendu, l'uniformisation sociale. Il faut n'avoir jamais lu une ligne de Gobineau pour le rendre complice d'un Hitler déclarant en 1933 : « Je n'ai que faire de chevaliers. Ce qu'il me faut, ce sont des révolutionnaires ! » Gobineau a simplement chanté la fin d'un monde idéal, qui était le sien, et annoncé un monde toujours possible où l'on ira s'agenouillant devant le sacro-saint inspecteur et le divin délégué »6. Viktor Klemperer dans LTI (1947) aborde justement la question du legs de Gobineau au nazisme. Pour lui, Gobineau a établi une rupture dans les conceptions prévalentes en basant les nationalismes sur des questions raciales et en minorant l'idée jusqu'alors dominante d'une race humaine commune tout en radicalisant les différences entre races, et en étant « le premier à enseigner que la race aryenne est supérieure, que la pure germanité est l'aboutissement de la race humaine et même la seule digne de ce nom, et qu'elle est menacée par le sang sémite » (chap. 20, La racine allemande). Et cela a un aspect ironique, puisque les historiens nazis (Herman Blome) chercheront en vain un précurseur allemand au français Gobineau chez les Romantiques. Selon Esther Benbassa, l'Essai.... est certes dénué de tout projet de restauration d'une « race supérieure », « mais les élucubrations pessimistes de Gobineau sur la déchéance irréversible des « Arians » condamnés au métissage, n'en dresse pas moins la première histoire raciste de l'humanité construite autour du mythe aryen. »7. Pour Pierre-André Taguieff, les théories de Gobineau sur le métissage et sur les inégalités entre races, ont contribué à alimenter des théories racistes, et ont été ensuite utilisées à ce titre par d'autres8. Une autre façon de résumer l'évolution des analyses successives concernant cet essai, est de lire les différentes mentions et notices que lui consacre le dictionnaire Larousse. En 1922, dans le Larousse universel publié cette année-là, il est noté à son propos : « Fondé sur l’idée de la race comme facteur fondamental de l’histoire, il présente l’aryen dolichocéphale blond comme le type de l’humanité supérieure. » En 1999, le Petit Larousse est plus nuancé et avance que l'ouvrage « prétend retracer et expliquer par le processus historique du métissage la marche de l’humanité vers un déclin inéluctable ». Il précise aussi que les « théoriciens du racisme germanique se réclament » des théories du comte de Gobineau, mais ont en partie travesti ses thèses9. |
後世と批判 アルチュール・ド・ゴビノーの死から3年後の1885年、ハイチの作家ジョゼフ・アンテノール・フィルマンが、650ページに及ぶ長大なエッセイを発表 し、人種の不平等に関するテーゼに反論した。彼の著書のタイトル『De l'égalité des races humanaines』4は、アルチュール・ド・ゴビノーの著書を暗示している。彼は、人種という概念をアプリオリに受け入れる一方で、その定義の曖昧さ と、これらの人種の階層化に関する理論の基礎の欠如を説明している。彼は、古代エジプトやエチオピアからハイチの黒人共和国に至るまで、歴史を通じて黒人 が成し遂げた功績を強調している。 第1巻のタイトルは「予備的考察:社会世界を支配する自然法則の定義、研究、説明」となっている。ゴビノーは、文明は滅びるという 「既成事実 」から出発し、文明衰退の原因を探っている。彼は、無神論や不道徳主義は、悪い制度や悪い政府以上に、社会を滅亡させたことはないと主張する5。 ジョルジュ・キュヴィエ(1769-1832)に代表される当時の動物学から借用した言葉である。キュヴィエにとって退化とは、人間によって家畜化された 種が次々に交配されることによって起こることである。キュヴィエによれば、動物には自然的、人為的なあらゆる影響に抵抗する永続性があり、それが固定種と いう概念を主張することを可能にし、そこから逸脱した変異は退化であるとした5。 キュヴィエが種に適用したものを、ゴビノーは人種に適用し、ユダヤ人を例にとって、民族の違いは永続的であると述べた(表題、第1巻第11章)。ゴビノー は民族と国民、人種と国家を関連付け、識別し、歴史の教訓に基づくと主張する。ゴビノーは、白色人種が最も高貴であると主張する。そのために、彼は歴史を 6つの偉大な文明に還元し、それを人種と同一視し、文明はその創始集団を保持している場合にのみ偉大であり、白色人種とその最も輝かしい枝である「アリア ン」一族に由来するものであればあるほど偉大であると宣言する5。 ゴビノーは、同時代の他の歴史家と同様、西洋文明の誕生におけるフランク民族の基本的重要性を述べることから始め、この民族に何が残っているのかと問い、 「何も残っていない」と答える。リヒャルト・ワーグナーとは異なり、彼はドイツ民族の周期的な運命を信じなかった。さらに彼は、古代のアーリア人種が残っ ているのは、イギリスとベルギーにあるばかげたポケットだけだと指摘した6。 ゴビノーにとって、現代人は退廃の人であり、退化の人であり、祖先とは異なる産物である。「その静脈にはもはや同じ血が流れておらず、その血の価値は連続する合金によって徐々に変化している。 マリー=フランソワーズ・オードゥアールは、この作品について次のように締めくくっている。「人々がナチズムの源流のひとつにしようとしているこのエッセ イは、まさに正反対である。なぜなら、この中で著者は、ナチズムが体系化しようとするあらゆるもの、すなわちナショナリズム、官能主義、デマゴギー、庶民 や小ボスの知的不幸、道徳的優越性への憎悪、そしてもちろん社会的標準化を非難しているからである。1933年に「私に必要なのは騎士ではない。私に必要 なのは革命家だ」!ゴビノーは、彼自身であった理想世界の終わりを歌い、まだ可能な世界、すなわち、神聖な監察官と神聖な代議士の前にひざまずいて行く世 界を告げただけである6。 ヴィクトル・クレンペラーは『LTI』(1947年)の中で、ゴビノーのナチズムへの遺産という問題を取り上げている。彼にとってゴビノーは、ナショナリ ズムを人種問題に立脚させ、それまで支配的であった人類共通の種族という考えを軽視する一方で、人種間の差異を急進化させ、「アーリア人種が優れており、 純粋なドイツ人こそが人類の頂点であり、まさにその名にふさわしい唯一のものであり、セム人の血によって脅かされていることを最初に説いた」(『ドイツの 根』第20章)ことで、一般的な概念との決別を確立したのである。ナチスの歴史家たち(ヘルマン・ブローム)は、ロマン派の中にフランスのゴビノーの前身 となるドイツ人を無駄に探していたのだから。 エステル・ベンバッサによれば、この『エッセイ』には確かに「優秀な人種」を復活させようという計画はない。「しかし、混血を余儀なくされた「アリアン 人」の不可逆的な衰退に関するゴビノーの悲観的な解明は、それにもかかわらず、アーリア神話を中心に構築された最初の人種主義的人類史を構成している」 7。 ピエール=アンドレ・タギエフにとって、混血と人種間の不平等に関するゴビノーの理論は、人種主義理論を煽るのに役立ち、その後、他の人々によってそのように利用された8。 このエッセイの連続的な分析の変遷を要約するもうひとつの方法は、ラルース辞典のさまざまな参考文献や項目を読むことである。1922年、その年に出版さ れた『Larousse universel』には、次のように記されている。「歴史における基本的な要因としての人種という考え方に基づき、金髪で頭頂部を持つアーリア人を優れ た人類のタイプとして提示する」。1999年の『Petit Larousse』誌はより微妙なニュアンスで、この作品は「混血の歴史的過程を通じて、人類が必然的な衰退に向かう過程をたどり、説明すると主張してい る」と述べている。また、「ゲルマン人種主義の理論家たちは、ゴビノー伯爵の理論に倣うと主張している」が、彼のテーゼを部分的に偽装していると指摘して いる9。 |
| Éditions Première édition : Tomes I et II, livres 1 à 4, dédicace à Georges V, roi de Hanovre, Didot, Paris, 1853. Tomes III et IV, livres 5 et 6, conclusion générale, Didot, Paris, 1855. Deuxième édition en deux volumes, avec un avant-propos de l'auteur, Didot, Paris, 1884. Cette édition, préparée par l'auteur, est parue après sa mort. Le texte n'a pas été retouché. Essai sur l'inégalité des Races humaines, 1854. Édition de 1933. Réédition aux éditions Pierre Belfond, Paris, 1967, avec une introduction d'Hubert Juin. [lire en ligne [archive]] sur Les Classiques des sciences sociales. |
出版社 初版: 第1巻と第2巻、第1巻から第4巻、ハノーブル王ジョルジュ5世への手紙、ディドー、パリ、1853年。 第3巻と第4巻、第5巻と第6巻、総論、Didot、パリ、1855年。 1884年、著者による序文付きの第2版、全2巻。この版は著者の死後に出版された。本文は変更されていない。 人種不平等論』1854年。1933年版。 1967年、パリ、ピエール・ベルフォンにより、ユベール・ジュアンによる序文付きで再版された。[オンライン [アーカイブ] で読む。 |
| https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_sur_l%27in%C3%A9galit%C3%A9_des_races_humaines |
|
+++
| Gobineau’s
Essay on the Inequality of Human Races The most important promoter of racial ideology in Europe during the mid-19th century was Joseph-Arthur, comte de Gobineau, who had an almost incalculable effect on late 19th-century social theory. Published in 1853–55, his Essay on the Inequality of Human Races was widely read, embellished, and publicized by many different kinds of writers. He imported some of his arguments from the polygenists, especially the American Samuel Morton. Gobineau claimed that the civilizations established by the three major races of the world (white, Black, and yellow) were all products of the white races and that no civilization could emerge without their cooperation. The purest of the white races were the Aryans. When Aryans diluted their blood by intermarriage with lower races, they helped to bring about the decline of their civilization. Following Boulainvilliers, Gobineau advanced the notion that France was composed of three separate races—the Nordics, the Alpines, and the Mediterraneans—that corresponded to France’s class structure. Each race had distinct mental and physical characteristics; they differed in character and natural abilities, such as leadership, economic resourcefulness, creativity, and inventiveness, and in morality and aesthetic sensibilities. The tall, blond Nordics, who were descendants of the ancient Germanic tribes, were the intellectuals and leaders. Alpines, who were brunet and intermediate in size between Nordics and Mediterraneans, were the peasants and workers; they required the leadership of Nordics. The shorter, darker Mediterraneans he considered a decadent and degenerate product of the mixture of unlike races; to Gobineau they were “nigridized” and “semitized.” https://www.britannica.com/topic/race-human/Gobineaus-Essay-on-the-Inequality-of-Human-Races |
ジョ
ゼフ・アルチュール・ド・ゴビノーの人種不平等論 19世紀半ばのヨーロッパで最も重要な人種イデオロギーの推進者は、ゴビノー伯爵(Joseph-Arthur de Gobineau)で、彼は19世紀後半の社会理論にほとんど計り知れない影響を及ぼした。1853年から55年にかけて出版された『人種間の不平等に関 する論考』は、さまざまな作家によって広く読まれ、脚色され、宣伝された。彼は、その議論の一部を、多元論者、特にアメリカのサミュエル・モートンから輸 入した。ゴビノーは、世界の三大民族(白人、黒人、黄色人種)が築いた文明は、すべて白人種の産物であり、彼らの協力なしには文明は生まれないと主張し た。白人種の中で最も純粋なのはアーリア人である。アーリア人が下層人種との婚姻によってその血を薄めれば、文明の衰退を招くことになる。 ブーランヴィリエに続いてゴビノーは、フランスは北欧、アルプス、地中海の3つの人種からなり、それはフランスの階級構造に対応しているという考えを示し た。それぞれの民族は、精神的、肉体的な特徴を持ち、指導力、経済力、創造力、発明力などの性格や天賦の才能、道徳心や美的感覚も異なっている。古代ゲル マン民族の子孫である長身で金髪のノルディック人は、知識人であり指導者であった。アルプス人は褐色でノルディックと地中海の中間的な体格で、農民や労働 者であり、ノルディックのリーダーシップを必要とした。背が低く、色黒の地中海沿岸の人々は、ゴビノーにとって、異民族の混血が生み出した退廃的で堕落し た産物であり、「ニグリド化」「セミタイズド化」していると考えていた。 |
| Americans of this period were
among Gobineau’s greatest admirers. So were many Germans. The latter
saw in his works a formula for unifying the German peoples and
ultimately proclaiming their superiority. Many proponents of German
nationalism became activists and organized political societies to
advance their goals. They developed a new dogma of “Aryanism” that was
to expand and become the foundation for Nazi race theories in the 20th
century. Gobineau was befriended by the great composer Richard Wagner, who was a major advocate of racial ideology during the late 19th century. It was Wagner’s future son-in-law Houston Stewart Chamberlain, writing at the end of the 19th century, who glorified the virtues of the Germans as the superrace. In a long book titled The Foundations of the Nineteenth Century, Chamberlain explained the history of the entire 19th century—with its European conquests, dominance, colonialism, and exploitation—as a product of the great accomplishments of the German people. Though English-born, Chamberlain had a fanatical attraction to all things German and an equally fanatic hatred of Jews. He believed Jesus was a Teuton, not a Jew, and argued that all Jews had as part of their racial character a moral defect. Fueled by rising anti-Semitism in Europe, race ideology facilitated the manufacture of an image of Jews as a distinct and inferior population. Chamberlain’s publications were widely disseminated in Germany during the turn of the 20th century. His speculations about the greatness of the Germans and their destiny were avidly consumed by many, especially young men such as Adolf Hitler and his companions in the National Socialist Party. As this history shows, European intellectual leaders took the constituent components of the ideology of race and molded them to the exigencies of their particular political and economic circumstances, applying them to their own ethnic and class conflicts. Race thus emerged as a powerful denoter of unbridgeable differences that could be applied to any circumstances, particularly of ethnic conflict. The German interpretation of race eventually took the ideology to its logical extreme, the belief that a “superior race” has the right to eliminate “inferior races.” |
この時代のアメリカ人は、ゴビノーの最大の崇拝者の一人であった。多く
のドイツ人もそうであった。ドイツ人は、彼の著作に、ドイツ民族を統一し、最終的に自分たちの優位性を宣言するための方式を見出したのである。ドイツ・ナ
ショナリズムの支持者の多くは、活動家となり、その目標を達成するために政治結社を組織した。彼らは「アーリアニズム」という新しいドグマを打ち立てた
が、これは20世紀におけるナチスの人種理論の基礎となるものであった。 ゴビノーは、19世紀後半に人種思想を提唱した大作曲家リヒャルト・ワーグナーと親交を結んだ。ワーグナーの娘婿となるヒューストン・スチュワート・チェ ンバレンが、19世紀末に書いた「ドイツ人を超人種として美化する」という本がある。チェンバレンは『19世紀の基礎』という長い本の中で、ヨーロッパの 征服、支配、植民地支配、搾取といった19世紀全体の歴史が、ドイツ人の偉大な業績の産物であると説明した。イギリス生まれでありながら、チェンバレンは ドイツ的なものに狂信的な魅力を感じ、ユダヤ人を同様に狂信的に憎んでいた。彼は、イエスはユダヤ人ではなくチュートン人であると信じ、すべてのユダヤ人 はその人種的性格の一部として道徳的欠陥を持っていると主張した。ヨーロッパにおける反ユダヤ主義の高まりは、人種的イデオロギーによって、ユダヤ人を特 殊で劣った集団であるというイメージを作り上げることにつながった。チェンバレンの出版物は、20世紀初頭のドイツで広く普及した。特にアドルフ・ヒト ラーとその仲間である国家社会党の若者たちは、ドイツ人の偉大さとその運命についての彼の思索を熱心に読みふけった。 この歴史が示すように、ヨーロッパの知識人たちは、人種というイデオロギーの構成要素を、それぞれの政治的、経済的状況の必要性に応じて成形し、自分たち の民族や階級間の対立に適用したのである。こうして、人種は、あらゆる状況、特に民族紛争に適用できる、埋めがたい差異を示す強力なデノターとして登場し た。ドイツにおける人種の解釈は、やがて論理的な極限に達し、「優秀な人種」は「劣った人種」を排除する権利を有するという信念を持つに至った。 |
| Galton and Spencer: The rise of
social Darwinism Hereditarian ideology also flourished in late 19th-century England. Two major writers and proselytizers of the idea of the innate racial superiority of the upper classes were Francis Galton and Herbert Spencer. Galton wrote books with titles such as Hereditary Genius (1869), in which he showed that a disproportionate number of the great men of England—the military leaders, philosophers, scientists, and artists—came from the small upper-class stratum. Spencer incorporated the themes of biological evolution and social progress into a grand universal scheme. Antedating Darwin, he introduced the ideas of competition, the struggle for existence, and the survival of the fittest. His “fittest” were the socially and economically most successful not only among groups but within societies. The “savage” or inferior races of men were clearly the unfit and would soon die out. For this reason, Spencer advocated that governments eschew policies that helped the poor; he was against all charities, child labour laws, women’s rights, and education for the poor and uncivilized. Such actions, he claimed, interfered with the laws of natural evolution; these beliefs became known as social Darwinism. The hereditarian ideologies of European writers in general found a ready market for such ideas among all those nations involved in empire building. In the United States these ideas paralleled and strengthened the racial ideology then deeply embedded in American values and thought. They had a synergistic effect on ideas of hereditary determinism in many aspects of American life and furthered the acceptance and implementation of IQ tests as an accurate measure of innate human ability. |
ガルトンとスペンサー 社会ダーウィニズムの台頭 19世紀末のイギリスでも、世襲制の思想が盛んであった。上流階級は生まれながらにして人種的に優れているという説を唱えたのは、ゴルトンとハーバート・ スペンサーという二大著作家である。ガルトンは『天才の遺伝』(1869年)という本を書き、イギリスの偉人たち(軍事指導者、哲学者、科学者、芸術家) の多くが、少数の上流階級の出身であることを明らかにした。スペンサーは、生物学的進化と社会的進歩というテーマを、壮大な普遍的スキームに組み込んだ。 ダーウィンに先駆けて、彼は競争、生存競争、適者生存の考えを導入した。適者」とは、社会的、経済的に最も成功した者であり、集団の中だけでなく、社会の 中においても成功した者である。野蛮人」あるいは劣等人種は明らかに不適格者であり、すぐに絶滅してしまう。このため、スペンサーは、政府が貧しい人々を 助ける政策を避けるよう主張した。彼は、あらゆる慈善事業、児童労働法、女性の権利、貧しい人々や未開の人々への教育などに反対したのである。このような 行為は、自然進化の法則を阻害するものであると主張し、社会ダーウィニズムと呼ばれるようになった。 ヨーロッパの作家たちの遺伝主義的なイデオロギーは、帝国建設に携わるすべての国々にそのような思想の市場を提供することを可能にした。アメリカでは、こ れらの思想は、当時アメリカの価値観や思想に深く浸透していた人種的イデオロギーと並行し、強化された。これらの思想は、アメリカ人の生活の多くの側面 で、遺伝的決定論の思想と相乗効果をもたらし、人間の生来の能力を正確に測定するものとして、IQテストの受け入れと実施を促進させた。 |
| “Race” ideologies in Asia,
Australia, Africa, and Latin America European conquest and the classification of the conquered As they were constructing their own racial identities internally, western European nations were also colonizing most of what has been called, in recent times, the Third World, in Asia and Africa. Since all the colonized and subordinated peoples differed physically from Europeans, the colonizers automatically applied racial categories to them and initiated a long history of discussions about how such populations should be classified. There is a very wide range of physical characteristics among Third World peoples, and subjective impressions generated much scientific debate, particularly about which features were most useful for racial classification. Experts never reached agreement on such classifications, and some questions, such as how to classify indigenous Australians, were subjects of endless debate and were never resolved. Race and race ideology had become so deeply entrenched in American and European thought by the end of the 19th century that scholars and other learned people came to believe that the idea of race was universal. They searched for examples of race ideology among indigenous populations and reinterpreted the histories of these peoples in terms of Western conceptions of racial causation for all human achievements or lack thereof. Thus, the so-called Aryan invasions of the Indian subcontinent that began about 2000 BCE were seen, and lauded by some, as an example of a racial conquest by a light-skinned race over darker peoples. The Aryans of ancient India (not to be confused with the Aryans of 20th-century Nazi and white supremacist ideology) were pastoralists who spread south into the Indian subcontinent and intermingled with sedentary peoples, such as the Dravidians, many of whom happened to be very dark-skinned as a result of their long adaptation to a hot, sunny tropical environment. Out of this fusion of cultures and peoples, modern Indian culture arose. Such conquests and syntheses of new cultural forms have taken place numerous times in human history, even in areas where there was little or no difference in skin colour (as, for example, with the westward movements of Mongols and Turkish peoples). |
アジア、オーストラリア、アフリカ、ラテンアメリカにおける「人種」イ
デオロギー ヨーロッパの征服と被征服者の分類 西欧諸国は、自分たちの人種的アイデンティティを内部で構築する一方で、アジアやアフリカの、近年では第三世界と呼ばれている地域の大部分を植民地化して いた。植民地化され、従属する人々は、身体的にヨーロッパ人と異なるため、植民地化した人々は自動的に人種的カテゴリーを適用し、そうした人々をどのよう に分類すべきかについて長い歴史を持つ議論を開始したのである。第三世界の人々の身体的特徴は実に多様であり、主観的な印象が多くの科学的議論を生み、特 にどの特徴が人種分類に最も有用であるかについて議論された。専門家の間でこのような分類について合意が成立することはなく、オーストラリア先住民をどの ように分類するかなど、いくつかの問題は果てしない議論の対象となり、解決されることはなかった。 19世紀末になると、人種と人種イデオロギーはアメリカやヨーロッパの思想に深く浸透し、学者や学識経験者は人種という概念が普遍的なものであると考える ようになった。彼らは先住民の中に人種イデオロギーの例を探し出し、これらの人々の歴史を、人類のあらゆる功績や不足に人種的な因果関係があるという西洋 的な概念で再解釈したのである。こうして、紀元前2000年頃に始まったいわゆるアーリア人のインド亜大陸への侵入は、肌の白い人種が黒い人種を征服した 例と見なされ、一部の人々はこれを賞賛した。古代インドのアーリア人(20世紀のナチスや白人至上主義思想のアーリア人と混同してはいけない)は牧畜民 で、インド亜大陸に南下し、ドラヴィダ人などの定住民族と混血した。このような文化や民族の融合から、現代のインド文化が生まれたのである。このような征 服と新しい文化形態の融合は、肌の色の違いがほとんどない地域でも(例えばモンゴル人やトルコ人の西への移動のように)、人類の歴史上何度も行われてき た。 |
| India’s caste system India has a huge population encompassing many obvious physical variations, from light skins to some of the darkest in the world and a wide variety of hair textures and facial features. Such variations there, as elsewhere, are a product of natural selection in tropical and semitropical environments, of genetic drift among small populations, and of historical migrations and contact between peoples. The Hindu sociocultural system was traditionally divided into castes that were exclusive, hereditary, and endogamous. They were also ranked and unequal and thus appeared to have many of the characteristics of “race.” But the complex caste system was not based primarily on skin colour, as castes included people of all physical variations. Nor was it based on a “scientific” ideology of superiority or inferiority, although late 19th-century pseudoscientific analyses attempted to explain the system’s longevity (see below). Although some early 20th-century European scholars tried to divide the Indian and other Asian peoples into races, their efforts were hindered not only by the complexity of physical variations in India, parts of Southeast Asia, and Melanesia but by the developing fields of science. Castes were, and are still, occupational groups as well as elements in a religious system that accords different values and different degrees of purity to different occupations. They also are the main regulators of marriage and inheritance rights. Some castes were originally small-scale tribal groups who were incorporated into the Hindu kingdoms. It has been noted that there are thousands of castes in India and many different ways of ranking them, including through such cultural features as food taboos and sharing obligations, but none derive from skin colour or “race.” Caste discrimination has been outlawed in India, although it remains deeply rooted in the cultures of ordinary people. Moreover, democratic values, the human rights movement, and the processes of industrialization have affected the rigid social caste system of India and led in some areas to a blurring of caste boundaries and a decline in the importance of caste identity. |
インドのカースト制度 インドには膨大な人口があり、明るい肌から世界で最も暗い肌まで、また髪質や顔立ちもさまざまなバリエーションがある。これは、熱帯・亜熱帯の自然淘汰、 少数民族の遺伝的偏り、歴史的な民族の移動と接触がもたらしたものである。 ヒンズー教の社会文化システムは、伝統的に排他的、遺伝的、内縁的なカーストに分かれていた。また、カーストには階級があり、不平等であったため、「人 種」の特徴の多くを備えているように思われた。しかし、複雑なカースト制度は、主に肌の色に基づくものではなく、カーストにはあらゆる身体的変異を持つ人 々が含まれていたからだ。また、19世紀末の疑似科学的分析によって、この制度の長寿を説明しようとしたが、優劣の「科学的」イデオロギーに基づくもので もなかった(後述)。20世紀初頭のヨーロッパの学者の中には、インドや他のアジアの人々を人種に分けようとした者もいたが、インド、東南アジアの一部、 メラネシアにおける身体的変異の複雑さだけでなく、科学の発展分野にも阻まれ、そのような努力はできなかった。 カーストは職業集団であると同時に、職業によって異なる価値観や純度を与える宗教システムの要素である。また、結婚や相続の権利もカーストが中心となって 決定している。カーストの中には、もともと小規模な部族集団であったものが、ヒンドゥー教の王国に組み入れられたものもある。インドには何千ものカースト が存在し、食べ物のタブーや共有の義務などの文化的特徴によって、さまざまなランク付けが行われているが、肌の色や "人種 "に由来するものはないと指摘されている。 インドではカースト差別は違法とされているが、一般の人々の文化に深く根ざしている。また、民主主義、人権運動、工業化の進展は、硬直したカースト制度に 影響を与え、カーストの境界を曖昧にし、カーストアイデンティティの重要性を低下させた地域もある。 |
| Audrey Smedley Japan’s minority peoples A few ethnographic studies have suggested that a form of racial ideology has developed independently of the West in some traditional societies such as that of Japan, where various minority peoples, notably the burakumin and the Ainu, have been victimized and exploited by the dominant society. The burakumin, the former outcastes, have suffered from various forms of discrimination because of folk myths about their “polluted blood,” a discourse that has historical origin but no biological reality. Discrimination against them has been made possible by identifying group membership on the basis of descent—in modern times this discrimination is most pronounced in marriage, but historically it also affected housing and employment—and “traditional” occupations—such as butchering animals or disposing of corpses—which had been considered undesirable for the centuries during which Buddhism was a dominant religion. Medieval documents reveal that long before Japan imported Western racial ideology in the modern age, they were portrayed as being of a different shu (“race”), and discrimination against them was institutionalized and legalized. Although the burakumin were declared by law in 1871 to be of equal status, prejudice against them persisted into the 21st century. The Ainu are an indigenous people who once occupied the northern part of Japan. Today they inhabit Hokkaido and various other parts of Japan as well, including the greater Tokyo region. Contemporary scholars agree that both the Ainu and the more dominant Japanese share the ancestral Jōmon culture. The old theory that claimed that the Ainu bore greater resemblance to Europeans than to Asians, as seen in their abundance of body hair and rounder eyes, is no longer accepted. It should be noted that when the indigenous racial worldview that developed independently in premodern Japan merged with Western scientific racism after the 1868 Meiji Restoration, the “biological differences” from the dominant Japanese of such groups as the Ainu, the Okinawans, and the burakumin, which physical anthropologists “found” or redefined through various body measures, were used to justify both the government’s assimilation policies and discriminatory practices. In the post-World War II era, discrimination against Koreans, one of the largest minorities in contemporary Japan, has been a major issue of racism. Ethnic Koreans are forced to choose between giving up various resources available only to Japanese citizens so that they can maintain their Korean identities and giving up recognition of their Korean identity in order to receive Japanese citizenship. |
オードリー・スメドレー 日本の少数民族 日本のような伝統的な社会では、西洋とは無関係に人種的イデオロギーが発達し、特に被差別部落やアイヌといった少数民族が支配社会の犠牲になり、搾取され てきたとする民俗学的研究がいくつかなされている。被差別部落の人々は、「汚れた血」という、歴史的由来はあるが生物学的実態のない言説のために、さまざ まな差別を受けてきた。この差別は、現代では結婚に顕著に見られるが、歴史的には住宅や雇用にも影響し、また、仏教が支配的であった数世紀の間、好ましく ないとされてきた動物の屠殺や死体処理などの「伝統的」職業にも影響を及ぼしてきた。中世の文献は、日本が近代に西洋の人種思想を輸入する以前から、被差 別部落民が別の修羅(人種)として描かれ、差別が制度化・合法化されていたことを明らかにしている。1871年、法律で部落民の地位は平等とされたが、部 落民に対する偏見は21世紀に入っても続いている。 アイヌは、かつて日本の北部を占めていた先住民族である。アイヌはかつて日本の北部に住んでいた先住民族で、現在は北海道をはじめ、首都圏などさまざまな 地域に住んでいる。アイヌ民族と日本人は、祖先である縄文文化を共有しているというのが、現代の学者の共通認識である。アイヌは体毛が濃く、目が丸いこと から、アジア人よりもヨーロッパ人に似ているとする古い説は、もはや通用しない。 前近代日本で独自に発展した土着的人種世界観が、1868年の明治維新後に西洋の科学的人種主義と融合すると、アイヌ、沖縄、被差別部落などの集団が、身 体人類学者の「発見」あるいは身体測定による再定義によって、支配的日本人との「生物学的差異」が政府の同化政策や差別的行為の正当化に使われたことは注 目すべき点であろう。 第二次世界大戦後、現代日本における最大の少数民族の一つである朝鮮人に対する差別は、人種差別の大きな問題であった。朝鮮民族は、朝鮮人としてのアイデ ンティティを維持するために、日本国民だけが利用できるさまざまな資源を放棄するか、日本国籍を取得するために朝鮮人としてのアイデンティティを認める か、その選択を迫られているのである。 |
| Race in Asia A crucial element in understanding the various ideas of race in Asia is that morphological (phenotypic) differences do not always play the major role in determining racial differences, although exposure to Western definitions of race and forms of racism since the mid-19th century have made morphological differences more important than they once were. As elsewhere, Asian ideologies of status arose with the development of agriculture and the accompanying territorial expansions of imperial states. Traditionally, Asian notions of difference tended to be shaped by criteria such as descent, religion, and language rather than by physical characteristics. The historical discrimination against the burakumin in Japan and the demarcation between ethnic Chinese and “barbarians” in the Qing dynasty (1644–1911/12), for example, were already as rigidly institutionalized in the premodern period as the anti-Semitism found throughout European history. Thus, perceptions of skin colour did not have the same significance or connotation as in Europe and the Americas. In India many of the supreme deities, including Shiva, Rama, and Krishna, were depicted as dark blue or black—colours that are said to symbolize the dark clouds that bring rain to the fields and, by implication, the prosperity that accompanies a plentiful harvest. Japanese paintings depicting encounters with European missionaries in the 17th century emphasize differences in the shapes of noses and hair and eye colour but depict the skin tone of visiting Europeans as the same as that of Japanese. Yet, in various Asian regions, Europeans are sometimes referred to as “red faces” or “red people,” while in other cases Chinese and Japanese are labeled as “white people.” The introduction of European theories of race in the 19th century had enormous impact almost everywhere in Asia—as it did in the rest of the world. Recognized as part of Western knowledge, and thus symbolizing modernity, racial classification theories became a new tool of authority for European colonizers and Asian leaders alike. These ideas were invoked to justify the hierarchical relationship between “white” colonizers and “yellow” or “brown” Asians in general, as well as that between high- and low-status Asians. Colonizers were preoccupied with race (a term they rarely defined, and then inconsistently) and began to use it as a gloss for the aforementioned forms of traditional Asian social differentiation. By the mid-1800s colonial Europeans were employing techniques such as ethnographic research, mapping, and census taking to describe Asia’s various “races.” In Japan, Western racial classification theories, along with Western sciences, started to become known by the late Tokugawa period (1603–1867) through missionaries and Dutch writings. They spread widely throughout the country after the Meiji Restoration in 1868, and Johann Friedrich Blumenbach’s five classifications (Caucasian, Mongolian, Malayan, Ethiopian, and American), for instance, appeared in elementary school textbooks as early as the 1870s. Blumenbach’s classifications were introduced to China by missionaries and by Chinese intellectuals who had studied Japan in the late 19th century. About the same time, the Han Chinese started to celebrate their descent from Huangdi (c. 2700 BCE) and to reclaim their mythical Yellow Emperor as the founder of Chinese civilization—a narrative that bolstered the Chinese arguments according to which they were the prime race within the “yellow” race. There was a relatively short time span in Asia between the acceptance of a Westernized racial classificatory system and the adoption of social Darwinism, a philosophy positing that “weak” groups or races will eventually be driven to extinction by those that are more “fit.” Chinese and Japanese intellectuals—the former in the social chaos partly rooted in the aftermath of the Opium Wars, and the latter on the brink of modernization—did not critically question the Eurocentric and bigoted nature of the Western conception of race or of social Darwinism. In fact, “racial improvement” through amalgamation with the white race was proposed by some influential thinkers in both countries. Various anthropometric methods were employed or invented in China and Japan under the influence of Western scientific racism and were soon used to “verify” the “low” racial status of domestic marginalized groups and of the “barbarian” races outside national boundaries. Such findings were soon used to justify the state-led subjugation of these groups. Western racial characterizations spread to other parts of Asia in the latter half of the 19th century. These classifications not only justified the superior social position of European colonizers in regard to Asian subordinates but also evolved into detailed subdivisions between colonial subjects themselves, wherein the elite characterized “tribes” and other marginalized groups as “barbarian” and “primitive.” In colonial India the British anthropologists who conducted ethnographic research built reciprocal relationships with Indian elites and went so far as to construct a defense of the country’s caste system. This defense was based on the “scientific” analysis of cranial differences between members of different castes. The findings were taken seriously at the time, however, and indicated that Bengali upper castes were Aryan in origin and that the lower castes such as foragers and pastoralists were, under the precepts of social Darwinism, destined to die out. Thus, in the closing decades of the 19th century, the idea of race gained a particular meaning in colonial Southeast Asia and India—a meaning that supported public policies that were beneficial to colonizers and the ruling classes and very injurious to nonelites, who were presumed to be on the path to extinction. European racial ideology was put to a different use in independent Southeast Asian countries such as Siam (now Thailand). There, in the late 19th century, elites seeking to create a modern state employed European ideas of race to position within a global racial and civilizational hierarchy not only their own peoples but also those of neighbouring states. They located each group in a hierarchy according to perceived degrees of “civilization.” Western studies tracing the common linguistic origins of various cultures led to the conceptualization of a Thai “nation” or Thai “race” that consisted of all Thai-speaking peoples living within or beyond Siam’s national borders. As elsewhere, public policy was affected by concepts of race: Siam initiated assimilation and integration policies in the early 20th century as part of a pan-Thai movement, intending to build a Thai empire that would politically and geographically unite all peoples of the Thai race into one nation-state. |
アジアにおける人種 アジアにおける人種に関する様々な考え方を理解する上で重要なことは、形態的(表現型)な差異が必ずしも人種差を決定する上で主要な役割を担っていないと いうことである。 他の地域と同様、アジアの身分制度は農業の発達とそれに伴う帝国国家の領土拡張に伴って生まれた。伝統的にアジアでは、身体的特徴よりもむしろ家系、宗 教、言語などの基準によって差異が形成される傾向があった。例えば、日本における部落差別や清朝(1644-1911/12)における中国人と「蛮族」の 区分は、ヨーロッパの歴史に見られる反ユダヤ主義のように、前近代においてすでに厳格に制度化されていた。 したがって、肌の色に対する認識は、ヨーロッパやアメリカ大陸のような意義や意味合いを持つことはなかった。インドでは、シヴァ神、ラーマ神、クリシュナ 神などの最高神が紺色や黒色で描かれ、これは田畑に雨をもたらす暗雲、すなわち豊かな収穫に伴う繁栄を象徴する色と言われている。17世紀に描かれたヨー ロッパ人宣教師との出会いを描いた日本画では、鼻の形や髪や目の色の違いは強調されているが、肌の色は日本人と同じように描かれている。しかし、アジア各 地では、ヨーロッパ人を "red face "や "red people "と呼ぶこともあれば、中国人や日本人を "white people "と表記する場合もある。 19世紀にヨーロッパから導入された人種論は、世界の他の地域と同様、アジアのほぼ全域で大きな影響を与えた。西欧の知識の一部として認識され、近代化の 象徴となった人種分類理論は、ヨーロッパの植民地支配者にとっても、アジアの指導者にとっても、新しい権威の道具となったのである。これらの考え方は、 「白人」植民者と「黄色」または「褐色」アジア人との間の階層的関係や、地位の高いアジア人と低いアジア人との間の階層的関係を正当化するために持ち出さ れたのである。 植民地化した人々は、人種(彼らはこの言葉をほとんど定義せず、しかも一貫性がない)に気をとられ、それを前述のようなアジアの伝統的な社会的差別化のた めの用語として使い始めたのである。1800年代半ばまでに、植民地時代のヨーロッパ人は、民俗学的調査、地図作成、国勢調査などの手法を用いて、アジア のさまざまな「人種」を表現するようになった。日本では、徳川時代(1603-1867)末期に宣教師やオランダ人の著作を通じて、西洋の人種分類理論が 西洋科学とともに知られるようになった。1868年の明治維新後、広く全国に普及し、例えばヨハン・フリードリヒ・ブルーメンバッハの5分類(コーカサ ス、モンゴル、マレー、エチオピア、アメリカ)は、1870年代には早くも小学校の教科書に掲載されている。ブルーメンバッハの分類は、19世紀後半に宣 教師や日本を研究していた中国の知識人によって中国に伝えられた。同じ頃、漢民族は黄帝(紀元前2700年頃)の子孫であることを称え、神話上の黄帝を中 国文明の始祖とし、自分たちは「黄色人種」の中の優良人種であるという主張を強化するような説を唱え始めたのである。 アジアでは、西洋式の人種分類が受け入れられるようになってから、社会ダーウィニズム(弱い集団や人種は、より「適合」したものによって最終的に絶滅に追 い込まれるという哲学)が採用されるまで、比較的短い期間しかなかったのである。アヘン戦争後の社会的混乱の中にあった中国と日本の知識人たちは、西洋の 人種観や社会ダーウィニズムのヨーロッパ中心的で偏狭な性格を批判的に問うことはしなかった。実際、白人種との融合による「人種改良」は、両国の有力な思 想家によって提案されていた。中国や日本では、西洋の科学的人種主義の影響を受けて、さまざまな人体測定法が採用されたり発明されたりし、国内の疎外され た集団や国境外の「野蛮な」人種の「低い」状態を「検証」するためにすぐに使われた。このような発見は、すぐにこれらの集団の国家主導の服従を正当化する ために使われた。 西欧の人種区分は、19世紀後半にはアジアの他の地域にも広がっていった。こうした分類は、ヨーロッパの植民地支配者がアジアの従属者に対して優位な社会 的地位を占めることを正当化するだけでなく、エリートが「部族」やその他の周辺集団を「野蛮人」「原始人」として位置づけるなど、植民地支配の対象者自身 による細かい区分へと発展していったのである。植民地インドでは、民俗学的調査を行ったイギリスの人類学者がインドのエリートと相互関係を築き、この国の カースト制度の擁護を構築するに至った。この防衛策は、異なるカースト間の頭蓋の違いを「科学的」に分析することに基づいていた。しかし、この研究結果 は、ベンガルの上流階級はアーリア人であり、下層階級は社会ダーウィニズムの教えのもと、滅びる運命にあることを示すもので、当時は真剣に受け止められて いた。それは、植民地支配者や支配階級にとっては有益であるが、絶滅への道を歩むとされた非エリートにとっては非常に有害な公共政策を支えるものであっ た。 ヨーロッパの人種イデオロギーは、シャム(現タイ)のような東南アジアの独立国では別の使われ方をされた。19世紀後半、近代国家の建設を目指すエリート たちは、ヨーロッパの人種思想を用いて、自国民だけでなく近隣諸国の人々をもグローバルな人種的・文明的ヒエラルキーの中に位置づけたのである。彼らは、 それぞれの集団を、認識された「文明」の程度に応じたヒエラルキーの中に位置づけたのである。様々な文化の共通の言語的起源をたどる西洋の研究は、シャム の国境内または国境外に住むすべてのタイ語を話す人々からなるタイの「国民」またはタイの「人種」という概念につながった。他の地域と同様、公共政策も人 種の概念に影響された。シャムは20世紀初頭、汎タイ運動の一環として同化・統合政策を開始し、タイ民族のすべての人々を政治的・地理的に統合して一つの 国民国家とするタイ帝国を建設することを意図していた。 |
| Two contrasting censuses taken
in Malaysia in 1911 reflect sharp differences in race consciousness:
while the Straits Settlements census used alphabetic ordering starting
with “Aboriginees of the Peninsula,” the Federated Malay States (Negeri
Sembilan, Pahang, Perak, and Selangor) census listed categories by
racial classification, with Europeans appearing at the top, followed by
Eurasians, Malays, Chinese, Indians, and “other.” After 1911 ethnic
classification generally followed the latter pattern. The “Yellow Race” began to be perceived as a threat to “White civilized countries,” particularly after Japan’s victory in the Russo-Japanese War of 1904–05, which was sensationally cast in the West as the first loss of the white race to a nonwhite race in centuries. Resistance to the mounting European invasion of China and other parts of Asia and Euro-American racism toward the burgeoning Asian population grew and intensified. A commonly shared and mutually reinforcing conviction developed between the Chinese and the Japanese: they saw themselves as different branches of a single “yellow” race that was involved in a pan-Asiatic struggle against Western imperialism. Simultaneously, they projected their own prejudices against the “brown” races of other Asian countries, whom they regarded as barbarian and backward. Yet each country also interpreted the situation to its own benefit. China believed its central position within the “yellow” race was to counteract the hegemony of the “white” race while at the same time advocating that the “red,” “brown,” and “black” races be allowed (under the auspice of social Darwinism) to pass into extinction. Japan, on the other hand, claimed its destiny was to be the leading race in Asia. Japan used this concept to justify its invasion of Manchuria in 1931–32 and later to expand its reach across different Asian countries in the name of the Greater East Asia Co-Prosperity Sphere in an attempt to control these regions and obtain much-needed natural resources. |
海峡植民地の国勢調査が「半島の先住民」から始まるアルファベット順で
あるのに対し、マレー連邦(ネゲリ・センビラン、パハン、ペラック、セランゴール)の国勢調査では、ヨーロッパ人を筆頭に、ユーラシア、マレー、中国、イ
ンド、「その他」と人種区分別に分類されている点が、人種意識の相違を顕著に示している。1911年以降の民族分類は、概ね後者のパターンを踏襲してい
る。 特に1904年から2005年にかけての日露戦争で日本が勝利した後、「黄色人種」は「白人文明国」に対する脅威として認識され始めた。この戦争は、西洋 では数世紀ぶりに白人種が非白人種に敗れたというセンセーショナルな出来事として語られた。ヨーロッパ人の中国やアジアへの侵略、そして急増するアジア人 に対するアメリカ人の人種差別に対する抵抗は、ますます強まっていった。中国人と日本人は、自分たちを西洋帝国主義に対抗する汎アジア的な闘争に参加して いる単一の「黄色人種」の異なる分派とみなしていたのである。同時に、他のアジア諸国の「褐色」人種を野蛮で後進的と見なし、それに対する偏見を投影して いた。 しかし、このような状況を、各国は自国の利益のために解釈した。中国は、黄色人種の中心的な立場として、白色人種の覇権に対抗すると同時に、赤色、茶色、 黒色人種の絶滅を(社会ダーウィニズムのもとで)容認すると主張した。一方、日本は、アジアを代表する民族になることを宿命づけられたと主張した。 1931年から32年にかけての満州侵攻を正当化し、その後、大東亜共栄圏の名のもとにアジア諸国を支配し、必要な天然資源を獲得するために、この概念を 用いて手を広げていったのである。 |
| In the period following World
War II, as Asian countries embarked on nation building, perceptions of
race have played essential roles in defining their national identities
and shaping their external relations, particularly with Europe and
America. The advancement of Westernization and the wide presence of
U.S. military bases in Asia have significantly affected aesthetic
ideals among Asian peoples. In different regions of contemporary Asia,
lighter skin and other phenotypes that are traditionally considered
traits of Europeans are now regarded as more desirable. Asian countries
are not exempt from trends in global migration since the late 20th
century. Even a society such as that of Korea, which is considered to
be one of the most “homogeneous” in the world, is facing increasing
immigration and issues of multiculturalism. Nongovernmental organizations (NGOs) and government-sponsored multicultural policies have helped spread the notions of civil rights and antiracism in Asia. However, the influence of neoliberal economic policies has also affected immigrants and minorities, further marginalizing them economically and socially. Racism today sometimes appears not just within a nation-state framework but also in complex transnational and global frameworks, thus making it more difficult to combat. Since the turn of the 21st century, transnational alliances to combat racism have been formed, such as that between the burakumin in Japan and the Dalits (or “untouchables”) in India, as exemplified in the UN World Conference Against Racism and Anti-Discrimination (2001), held in Durban, S.Af. On the other hand, the global hegemony of neoliberalism after the end of the Cold War has made it more difficult to combat racism because of the emergence of new divisions within the same racialized group. While those with corresponding cultural resources may become power brokers and represent their communities vis-à-vis the multicultural state apparatus, the poor are increasingly exploited and are pushed into informal and insecure forms of employment. Meanwhile, a new nonwhite economic elite has risen to global power while maintaining diasporic connections across the world. Whether all these developments together will result in a change in the global racial hierachies remains to be seen. https://www.britannica.com/topic/race-human/Gobineaus-Essay-on-the-Inequality-of-Human-Races |
第二次世界大戦後、アジア諸国が国家建設を進める中で、人種に関する認
識は、ナショナル・アイデンティティを定義し、対外関係、特に欧米との関係を形成する上で重要な役割を担ってきた。欧米化が進み、米軍基地がアジアに広く
存在するようになったことは、アジア人の美意識に大きな影響を与えるようになった。現代アジアのさまざまな地域で、従来ヨーロッパ人の特徴とされてきた肌
の色やその他の表現型が、より望ましいものとみなされるようになった。20世紀後半からの世界的な移住の流れは、アジア諸国も例外ではない。世界で最も
「均質」な社会の一つとされる韓国のような国でも、移民が増加し、多文化主義が問題になっている。 非政府組織(NGO)や政府主導の多文化共生政策は、アジアにおける市民権や反人種主義といった概念の普及に貢献しました。しかし、新自由主義的な経済政 策の影響もあり、移民やマイノリティは経済的、社会的にさらに疎外されるようになった。今日のレイシズムは、時に国民国家の枠組みだけでなく、国境を越え た複雑なグローバルな枠組みの中に現れるため、その対策はより困難なものとなっている。21世紀に入ってから、日本の被差別部落やインドのダリット(不可 触民)など、国境を越えた人種差別撤廃のための同盟が形成され、2001年の国連反人種主義・反差別世界会議(ダーバン、アフガニスタン)に代表されるよ うな動きも出てきた。 他方、冷戦終結後の新自由主義の世界的覇権により、同じ人種集団の中に新たな分断が生まれ、人種差別との戦いはより困難になっている。対応する文化的資源 をもつ人々が権力者となり、多文化国家機構に対してコミュニティを代表することができる一方で、貧しい人々はますます搾取され、インフォーマルで不安定な 雇用形態に追いやられているのである。一方、新たな非白人経済エリートは、世界中にディアスポラ的なつながりを維持しながら、グローバルな権力に上り詰め ている。このような一連の動きが、グローバルな人種階層に変化をもたらすかどうかは、まだわからない。 |
| アーリア人種の提唱者としてのゴビノー 1850年代にフランスの作家アルチュール・ド・ゴビノーによって 「アーリア人」という言葉が人種カテゴリーとして採用され、後のヒューストン・スチュワート・チェンバレンの著作を通じ て、ナチスの人種思想に影響を与え たナチス支配下(1933-1945)では、ユダヤ人を除くドイツのほとんどの住人にこの言葉が当てはまる。1935年にニュルンベルク法が 制定されてからドイツ人や血縁関係(アーリアン)者で帝国市民となるためにはアーリアン証明が第一要件であった。ス ウェーデン人やイギリス人、フランス人やチェコ人、ポーランド人やイタリア人」は血縁者、つまり「アーリア人」であるとされた。非アーリア人」に分類され た者、特にユダヤ人は、ホロコーストとして知られる組織的大量殺戮に遭う前に差別された(ロマ ニの大量殺戮についてはポライモスを参 照のこと)。アーリア人至上主義思想の名の下に行われた残虐行為により、学者たちは一般的に「アーリア人」という言葉を避けるようになり、ほとんどの場合 「インド・イラン人」に置き換えられているが、南アジアの支部は今でも「インド・アーリア人」と呼ばれる。 |
|
| https://www.britannica.com/topic/race-human/Gobineaus-Essay-on-the-Inequality-of-Human-Races |
●ゴビノーの人種理論
| Gobineau's racial
theories |
ゴビノーの人種理論 |
| In his own lifetime, Gobineau
was known as a novelist, a poet and for his travel writing recounting
his adventures in Iran and Brazil rather than for the racial theories
for which he is now mostly remembered.[56] However, he always regarded
his book Essai sur l'inégalité des races humaines (An Essay on the
Inequality of the Human Races) as his masterpiece and wanted to be
remembered as its author.[56] A firm reactionary who believed in the
innate superiority of aristocrats over commoners—whom he held in utter
contempt—Gobineau embraced the now-discredited doctrine of scientific
racism to justify aristocratic rule over racially inferior
commoners.[43] Gobineau came to believe race created culture. He argued that distinctions among the three races—"black", "white", and "yellow"—were natural barriers; "race-mixing" breaks those barriers and leads to chaos. Of the three races, he argued blacks were physically very strong but incapable of intelligent thought.[57] Regarding the "yellows" (Asians) he said they were physically and intellectually mediocre but had an extremely strong materialism that allowed them to achieve certain results.[57] Finally, Gobineau wrote whites were the best and greatest of the three races as they alone were capable of intelligent thought, creating beauty and were the most beautiful.[57] "The white race originally possessed the monopoly of beauty, intelligence and strength" he wrote, and any positive qualities the Asians and blacks possessed was due to subsequent miscegenation.[58] Within the white race, there was a further subdivision between the Aryans, who were the epitome of all that was great about the white race and non-Aryans.[59] Gobineau took the term Aryan ("light one" or "noble one") from Hindu legend and mythology, which describes how the Indian subcontinent was conquered at some time in the distant past by the Aryans. This is generally believed to have reflected folk memories of the arrival of the Indo-European peoples into the Indian subcontinent.[citation needed] In the 19th century, there had been much public interest in the discovery by Orientalists like William Jones of the Indo-European languages, and that apparently unrelated languages such as English, Irish, Albanian, Italian, Greek, Russian, Sanskrit, Hindi, Bengali, Kurdish, Persian and so forth were all part of the same family of languages spoken across a wide swath of Eurasia from Ireland to India.[citation needed] The ancient Hindu scriptures with their tales of Aryan heroes were of major interest to scholars attempting to trace the origins of the Indo-European peoples. Gobineau believed the white race had originated somewhere in Siberia, the Asians in the Americas and the blacks in Africa.[58] He thought the numerical superiority of the Asians had forced the whites to make a vast migration that led them into Europe, the Middle East and the Indian subcontinent; both the Bible and Hindu legends about the conquering Aryan heroes reflected folk memories of this migration.[60] In turn, the whites had broken into three sub-races, namely the Hamitic, Semitic and Japhetic peoples. The latter were the Aryans of Hindu legends and were the best and greatest of all the whites.[61] |
ゴビノーはいつも『Essai sur l'inégalité
des races humaines』を自分の最高傑作とみなしており、その著者として記憶されることを望んでいた[56][56]。 [56]
平民に対する貴族の生来の優越性を信じていた強固な反動主義者-彼はそれを完全に軽蔑していた-ゴビノーは、人種的に劣る平民に対する貴族の支配を正当化
するために、今では信頼されていない科学的人種主義の教義を受け入れていた[43]。 ゴビノーは人種が文化を創造すると考えるよう になった。彼は、「黒人」、「白人」、「黄色人種」という3つの人種の間の区別は自然の障壁であり、「人種混 合」はそれらの障壁を破壊し、混乱をもたらすと主張した。また、「黄色人種」(アジア人)については、肉体的にも知性的にも平凡であるが、極めて強い物質 主義を持っており、それによって一定の成果を上げることができるとした[57]。 [57]最後にゴビノーは、白人だけが知的な思考ができ、美を創造し、最も美しかったので、白人が3つの人種の中で最高で偉大であると書いている [57]。「白人はもともと美と知性と強さを独占していた」と彼は書き、アジア人と黒人が持っている肯定的な性質はその後の混血のためであった[58]。 ゴビノーはアーリア人(「光の者」または「高貴な者」)という言葉をヒンドゥー教の伝説と神話から取 り、遠い過去のある時期にインド亜大陸がアーリア人に よって征服されたことを記述している。19世紀には、ウィリアム・ジョーンズのような東洋学者によるインド・ヨーロッパ諸語の発見に大きな関心が寄せら れ、英語、アイルランド語、アルバニア語、イタリア語、ギリシャ語、ロシア語、サンスクリット語、ヒンディー語、ベンガル語、クルド語、ペルシア語など、 一見無関係な言語も、アイルランドからインドまでの広い範囲で話される同じ語族に属していると考えられていた[citation needed]...。 アーリア人の英雄の物語が書かれた古代ヒンドゥー教の聖典は、インド・ヨーロッパ人の起源を探ろうとする学者にとって大きな関心事であった [citation needed] 。ゴビノーは、白人はシベリアのどこかで、アジア人はアメリカ大陸で、黒人はアフリカで発生したと考えていた[58]。彼はアジア人の数の優位性から、白 人はヨーロッパ、中東、インド亜大陸に至る大移動を強いられたと考えており、征服したアーリア人の英雄に関する聖書とヒンズーの伝説はどちらもこの移動に 関する民間の記憶を反映していた[60]。 そして白人はハム人、セム人、ヤペ人という三つの下位人種に分裂したと考えている。後者はヒンドゥー教の伝説のアーリア人であり、すべての白人の中で最も 優秀で偉大な存在であった[61]。 |
| Racial magnum opus: An Essay on
the Inequality of the Human Races |
人種学の大作。人類の不平等に関するエッセイ |
| In his An Essay on the
Inequality of the Human Races, published in 1855, Gobineau ultimately
accepts the prevailing Christian doctrine that all human beings shared
the common ancestors Adam and Eve (monogenism as opposed to
polygenism). He suggests, however, that "nothing proves that at the
first redaction of the Adamite genealogies the colored races were
considered as forming part of the species"; and, "We may conclude that
the power of producing fertile offspring is among the marks of a
distinct species. As nothing leads us to believe that the human race is
outside this rule, there is no answer to this argument."[62] He
originally wrote that, given the past trajectory of civilization in
Europe, white race miscegenation was inevitable and would result in
growing chaos. Despite his opinion that whites were the most beautiful
of the races, he believed Asian and black women had immense powers of
sexual attraction over white men. Whenever whites were in close
proximity to blacks and Asians, the result was always miscegenation as
white men were seduced by the beauty of Asian and black women, to the
detriment of whites.[61] Though not expressly obsessed with
antisemitism, Gobineau saw the Jews as praiseworthy for their ability
to avoid miscegenation while at the same time depicting them as another
alien force for the decay of Aryan Europe.[63] Gobineau thought the development of civilization in other periods was different from that of his own, and speculated that other races might have superior qualities in those civilizations. But, he believed European civilization represented the best of what remained of ancient civilizations and held the most superior attributes capable for continued survival. Gobineau stated he was writing about races, not individuals: examples of talented black or Asian individuals did not disprove his thesis of the supposed inferiority of the black and Asian races.[citation needed] He wrote: "I will not wait for the friends of equality to show me such and such passages in books written by missionaries or sea captains, who declare some Wolof is a fine carpenter, some Hottentot a good servant, that a Kaffir dances and plays the violin, that some Bambara knows arithmetic … Let us leave aside these puerilities and compare together not men, but groups."[64] Gobineau argued that race was destiny, declaring rhetorically: So the brain of a Huron Indian contains in undeveloped form an intellect which is absolutely that same as an Englishman or a Frenchman! Why then, in the course of the ages has he not then invented printing or steam power? |
1855年に出版された『人類の不平等に関する試論』でゴビノーは、す
べての人類は共通の祖先アダムとイブを共有しているというキリスト教の教義を最終的に受け入れている(多元論に対して単元論)。しかし、「アダムの系図が
最初に編集されたとき、有色人種が種の一部であると考えられていたことを証明するものはない」、「繁殖力のある子孫を残す力は、別種の印の一つであると結
論づけることができる」と示唆している。彼はもともと、ヨーロッパにおける過去の文明の軌跡を考えると、白人の混血は不可避であり、混沌を拡大させる結果
になると書いていた[62]。彼は白人が人種の中で最も美しいという意見にもかかわらず、アジアや黒人の女性は白人の男性に対して絶大な性的魅力を有して
いると考えていた。白人が黒人やアジア人と接近すると、白人男性がアジア人や黒人女性の美しさに誘惑され、白人の不利益になるため、結果は常に混血であっ
た[61]。
反ユダヤ主義に明確にこだわってはいないが、ゴビノーはユダヤ人を混血を避ける能力において賞賛に値すると見ていたが、同時に彼らをアーリアン・ヨーロッ
パを衰退させる別の異能者として描いている[63]。 ゴビノーは他の時代の文明の発展が自分の時代とは異なると考えており、それらの文明において他の人種が優れた資質を有しているかもしれないと推測してい た。しかし、彼はヨーロッパ文明が古代文明の残されたものの中で最良のものを代表し、継続的な生存のために可能な最も優れた属性を持っていると信じてい た。ゴビノーは、自分は個人ではなく人種について書いているのだと述べ、才能ある黒人やアジア人の例は、黒人やアジア人が劣っているとする彼のテーゼを否 定するものではないとした[citation needed]。 「私は平等の友人たちが、宣教師や船長によって書かれた本の中の、あるウォルフは立派な大工であり、あるホッテントットは良い召使いであり、カフィールは 踊り、バイオリンを弾き、あるバンバラは算数を知っていると宣言するような箇所を私に示すのを待つつもりはない...これらの愚かさを捨て、人間ではな く、集団を一緒に比較しようじゃないか」[64]と述べた。 ゴビノーは人種は運命であると主張し、修辞的に宣言していた。 ヒューロン系インディアンの脳には、未発達な形で、イギリス人やフランス人とまったく同じ知性が備わっているのだ。では、なぜ、時代の流れの中で、印刷や 蒸気を発明しなかったのだろうか。 |
| Focus on Aryans as a superior
race Gobineau asserted that the Aryans had founded the ten great civilizations of the world, writing: "In the ten civilizations no Negro race is seen an initiator. Only when it is mixed with some other, can it even be initiated into a civilization. Similarly, no spontaneous civilization is to be found among the yellow races; and when the Aryan blood is exhausted stagnation supervenes".[65] Gobineau, mindful of his own supposed noble and Frankish descent classified the Germanic peoples as being the Aryans in Europe.[citation needed] He believed Aryans had also moved into India and Persia. Gobineau used medieval Persian epic poetry, which he treated as completely historically accurate accounts, together with the beauty of Persian women (whom he saw as the most beautiful in the world) to argue that Persians were once great Aryans, but unfortunately the Persians had interbred too often with the Semitic Arabs for their own good.[66] At the same time, Gobineau argued that in Southeast Asia the blacks and Asians had intermixed to create the sub-race of the Malays.[61] He classified Southern Europe, South-Eastern Europe, the Middle East, Central Asia, and North Africa as racially mixed.[62] Gobineau's primary thesis was that European civilization flowed from Greece to Rome, and then to Germanic and contemporary civilization. He thought this corresponded to the ancient Indo-European culture, which earlier anthropologists had misconceived as "Aryan"—a term that only Indo-Iranians are known to have used in ancient times.[67] This included groups classified by language like the Celts, Slavs and the Germans.[68][69] Gobineau later came to use and reserve the term Aryan only for the "Germanic race", and described the Aryans as la race germanique.[70] By doing so, he presented a racist theory in which Aryans—that is Germanic people—were all that was positive.[71] Gobineau described the Aryans as physically extremely beautiful and very tall; of immense intelligence and strength, and endowed with incredible energy, great creativity in the arts and a love of war.[72] Like many other racists, he believed one's looks determined what one did, or in other words, that beautiful people created beautiful art while ugly people created ugly art.[72] He attributed much of the economic turmoil in France to pollution of the races. Despite his pride in being French, Gobineau often attacked many aspects of French life under the Third Republic as reflecting "democratic degeneration"—namely the chaos that he believed resulted when the mindless masses were allowed political power—which meant that critical reception of Gobineau in France was very mixed.[73] His contempt for ordinary people emerges from his letters, where his preferred term for common folk was la boue ("the mud").[74] Gobineau questioned the belief that the black and yellow races belong to the same human family as the white race and share a common ancestor. Trained neither as a theologian nor a naturalist, and writing before the popular spread of evolutionary theory, Gobineau took the Bible to be a true telling of human history. |
優れた民族としてのアーリア人への注目(→「アーリア人」) ゴビノーは、アーリア人が世界の十大文明を築いたと主張し、こう書いている。「10の文明の中に、黒人が創始者である姿は見られない。10の文明の中で、 黒人が文明を興したとは思えない。他の人種と混血して初めて、文明を興すことができる。同様に、黄色人種には自然発生的な文明は見られず、アーリア人の血 が尽きると停滞が生じる」[65]。 ゴビノーは、彼自身が高貴でフランクな子孫であることを意識して、ゲルマン民族をヨーロッパのアーリア人であると分類した[引用者註:1]。 彼はアーリア人がインドやペルシャにも移動していると考えていた。ゴビノーは中世ペルシャの叙事詩を完全に歴史的に正確な記録として扱い、ペルシャ女性の 美しさ(彼は世界で最も美しいと見ていた)と共に、ペルシャ人はかつて偉大なアーリア人だったが、残念ながらペルシャ人はセム系アラブ人とあまりにも頻繁 に交配し、彼ら自身のためにならなかったと主張している[66]。 [同時にゴビノーは東南アジアにおいて黒人とアジア人が混血してマレー人の亜人種を生み出したと主張していた[61]。 彼は南ヨーロッパ、南東ヨーロッパ、中東、中央アジア、北アフリカを人種的に混血していると分類していた[62]。 ゴビノーの主要なテーゼは、ヨーロッパ文明がギリシャからローマへ、そしてゲルマン文明と現代文明へと流れていったというものであった。彼はこれが古代の インド・ヨーロッパ文化に対応すると考えたが、それ以前の人類学者は「アーリア人」-インド・イラン人だけが古代に使用したことが知られている用語-とし て誤解していた[67]。これにはケルト人、スラブ人、ドイツ人などの言語によって分類される集団が含まれていた[68][69]。 [68][69] ゴビノーは後にアーリア人という用語を「ゲルマン民族」に対してのみ使用し留保するようになり、アーリア人をla race germaniqueと表現した[70]。 そうすることによって彼はアーリア人-すなわちゲルマン人-がすべて肯定的であるという人種主義理論を提示したのである[71]。 ゴビノーはアーリア人を身体的に非常に美しく、非常に背が高く、巨大な知性と力を持ち、信じられないほどのエネルギー、芸術における偉大な創造性、戦争へ の愛に恵まれていると説明していた[72]。 他の多くの人種主義者と同様に、彼は人の容姿が人の行動を決める、言い換えれば、美しい人は美しい芸術を、醜い人は醜い芸術を生み出すと信じていた [72] 彼はフランスにおける経済の混乱の多くを人種の汚染によるものと考えていた。 フランス人であることに誇りを持っていたにもかかわらず、ゴビノーはしばしば第三共和制下のフランス生活の多くの側面を「民主主義の退廃」、すなわち心な い大衆が政治権力を持つようになったときに生じる混乱であると信じて攻撃しており、フランスにおけるゴビノーの批評的受容は非常に複雑であったことを意味 している[73]。 [ゴビノーは、黒人と黄色人種が白人と同じ人類に属し、共通の祖先を持つという信念に疑問を呈していた[74]。神学者でも自然科学者でもなく、進化論が 一般に広まる前に執筆したゴビノーは、聖書が人類の歴史を正しく伝えていると考えていた。 |
| Reaction to Gobineau's essay The Essai attracted mostly negative reviews from French critics, which Gobineau used as a proof of the supposed truth of his racial theories, writing "the French, who are always ready to set anything afire—materially speaking—and who respect nothing, either in religion or politics, have always been the world's greatest cowards in matters of science".[75] However, events such as the expansion of European and American influence overseas and the unification of Germany led Gobineau to alter his opinion to believe the "white race" could be saved. The German-born American historian George Mosse argued that Gobineau projected his fear and hatred of the French middle and working classes onto Asian and Black people.[76] Summarizing Mosse's argument, Davies argued that: "The self-serving, materialistic oriental of the Essai was really an anti-capitalist's portrait of the money-grubbing French middle class" while "the sensual, unintelligent and violent negro" that Gobineau portrayed in the Essai was an aristocratic caricature of the French poor.[77] In his writings on the French peasantry, Gobineau characteristically insisted in numerous anecdotes, which he said were based on personal experience, that French farmers were coarse, crude people incapable of learning, indeed of any sort of thinking beyond the most rudimentary level of thought. As the American critic Michelle Wright wrote, "the peasant may inhabit the land, but they are certainly not part of it".[78] Wright further noted the very marked similarity between Gobineau's picture of the French peasantry and his view of blacks.[79] |
ゴビノーのエッセイに対する反応 エセーはフランスの批評家からほとんど否定的な評価を受け、ゴビノーはそれを自分の人種論が真実であると思われることの証明として、「物質的に言えば常に 何でも燃やそうとし、宗教でも政治でも何も尊重しないフランス人は、科学の問題では常に世界一の臆病者だ」と書いている[75]。 しかし、ヨーロッパとアメリカの影響力の海外進出やドイツの統一などの出来事が、ゴビノーの「白人」は救われると考えるようになり、その意見は変化してい る。ドイツ生まれのアメリカの歴史家であるジョージ・モッセは、ゴビノーはフランスの中流階級や労働者階級に対する恐怖や憎悪をアジア人や黒人に投影して いたと論じていた[76]。 モッセの議論を要約して、デイヴィスは次のように論じていた。「エッセーの利己的で物質主義的な東洋人は実際には反資本主義者による金食い虫のフランス中 産階級の肖像」であり、ゴビノーがエッセーで描いた「官能的で知性がなく暴力的な黒人」はフランス貧困層の貴族の戯画であった[77]。 ゴビノーは、フランスの農民についての著作の中で、フランスの農民は学習することができず、実際、最も初歩的な思考レベルを超えたいかなる種類の思考もで きない粗野な人々であると、個人の経験に基づくという数々の逸話を特徴的に主張している[77]。アメリカの批評家ミシェル・ライトが書いたように、「農 民は土地に住んでいるかもしれないが、確かにその一部ではない」[78]。ライトはさらにゴビノーのフランスの農民像と彼の黒人観の間に非常に著しい類似 性があることを指摘した[79]。 |
| Time in Persia In 1855, Gobineau left Paris to become the first secretary at the French legation in Tehran, Persia (modern Iran). He was promoted to chargé d'affaires the following year.[80] The histories of Persia and Greece had played prominent roles in the Essai and Gobineau wanted to see both places for himself.[81] His mission was to keep Persia out of the Russian sphere of influence, but he cynically wrote: "If the Persians ... unite with the western powers, they will march against the Russians in the morning, be defeated by them at noon and become their allies by evening".[81] Gobineau's time was not taxed by his diplomatic duties, and he spent time studying ancient cuneiform texts and learning Persian. He came to speak a "kitchen Persian" that allowed him to talk to Persians somewhat. (He was never fluent in Persian as he said he was.)[80] Despite having some love for the Persians, Gobineau was shocked they lacked his racial prejudices and were willing to accept blacks as equals. He criticized Persian society for being too "democratic". Gobineau saw Persia as a land without a future destined to be conquered by the West sooner or later. For him this was a tragedy for the West. He believed Western men would all too easily be seduced by the beautiful Persian women causing more miscegenation to further "corrupt" the West.[80] However, he was obsessed with ancient Persia, seeing in Achaemenid Persia a great and glorious Aryan civilization, now sadly gone. This was to preoccupy him for the rest of his life.[82] Gobineau loved to visit the ruins of the Achaemenid period as his mind was fundamentally backward looking, preferring to contemplate past glories rather than what he saw as a dismal present and even bleaker future.[82] His time in Persia inspired two books: Mémoire sur l'état social de la Perse actuelle (1858) ("Memoire on the Social State of Today's Persia") and Trois ans en Asie (1859) ("Three Years in Asia").[82] Gobineau was less than complimentary about modern Persia. He wrote to Prokesch-Osten that there was no "Persian race" as modern Persians were "a breed mixed from God knows what!". He loved ancient Persia as the great Aryan civilization par excellence, however, noting that Iran means "the land of the Aryans" in Persian.[83] Gobineau was less Eurocentric than one might expect in his writings on Persia, believing the origins of European civilization could be traced to Persia. He criticized western scholars for their "collective vanity" in being unable to admit to the West's "huge" debt to Persia.[83] |
ペルシャでの時間 1855年、ゴビノーはパリを離れ、ペルシャのテヘラン(現在のイラン)にあるフランス公使館で一等書記官となる。ペルシャとギリシアの歴史はエッサイに おいて重要な役割を果たしており、ゴビノーは自分の目で両地域を見てみたいと考えていた[81]。彼の使命はペルシャをロシアの勢力圏から外すことだった が、彼は「もしペルシャ人が西側勢力と団結すれば、彼らはペルシャに対して進軍するだろう」とシニカルな文章を書いている[82]。 ゴビノーの時間は外交任務のために割かれることはなく、彼は古代の楔形文字を研究し、ペルシア語を学ぶために時間を費やした。彼はペルシャ人と多少話すこ とができる「台所ペルシャ語」を話すようになった。(ペルシャ人に対する愛情はあったものの、ゴビノーは彼らが自分のような人種的偏見を持たず、黒人を対 等に受け入れようとすることに衝撃を受けた[80]。彼はペルシャの社会があまりにも「民主的」であると批判していた。 ゴビノーはペルシャを、遅かれ早かれ西洋に征服される運命にある未来なき土地と見ていた。彼にとっては、これは西洋の悲劇であった。しかし、彼は古代ペル シャに執着し、アケメネス朝ペルシャに偉大で輝かしいアーリア文明を見たが、今は悲しいことに失われてしまった。ゴビノーはアケメネス朝時代の遺跡を好ん で訪れ、彼の心は基本的に後ろ向きであり、悲惨な現在やさらに暗い未来と見るよりも過去の栄光を熟考することを好んでいた[82]。 ペルシャでの生活は2冊の本に影響を与えた。Mémoire sur l'état social de la Perse actuelle (1858) ("Memoire on the Social State of Today's Persia") and Trois ans en Asie (1859) ("Three Years in Asia").[82]. ゴビノーは現代ペルシャをあまり褒めていなかった。彼はプロケッシュ・オステンに、現代のペルシャ人は「神のみぞ知る混血種」であり、「ペルシャ民族」は 存在しないと書いている[82]。しかし、彼は古代ペルシャを偉大なアーリア文明の最高峰として愛し、イランがペルシャ語で「アーリア人の土地」を意味す ることを指摘した[83]。ゴビノーはペルシャに関する著作で予想されるほどヨーロッパ中心主義ではなく、ヨーロッパ文明の起源はペルシャに辿ることがで きると考えていた。彼は西洋の学者たちがペルシャに対する西洋の「巨大な」負債を認めることができないという「集団的虚栄心」を批判していた[83]。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_de_Gobineau |
https://www.deepl.com/ja/translator |
●ゴビノー年譜(→「アルチュール・ド・ゴビノー」に移転しています)
リンク
文献
その他の情報
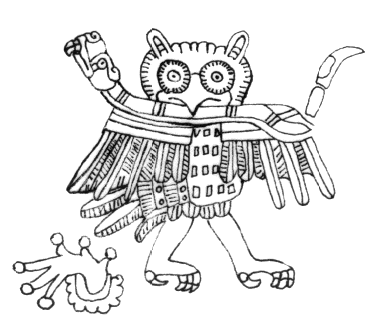
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099