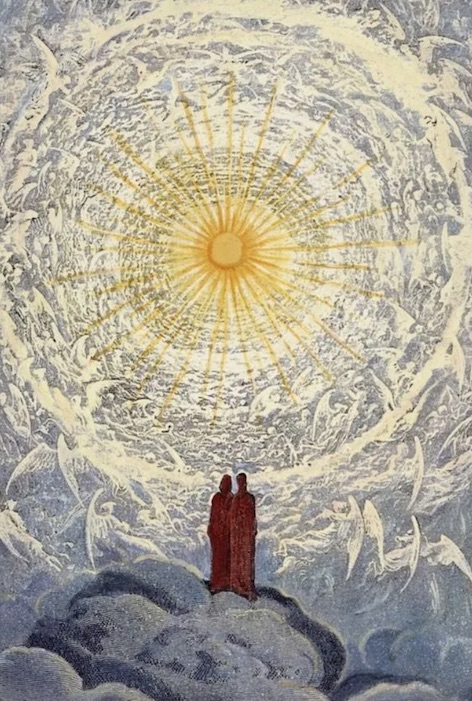
肉体なき人
discarnate person
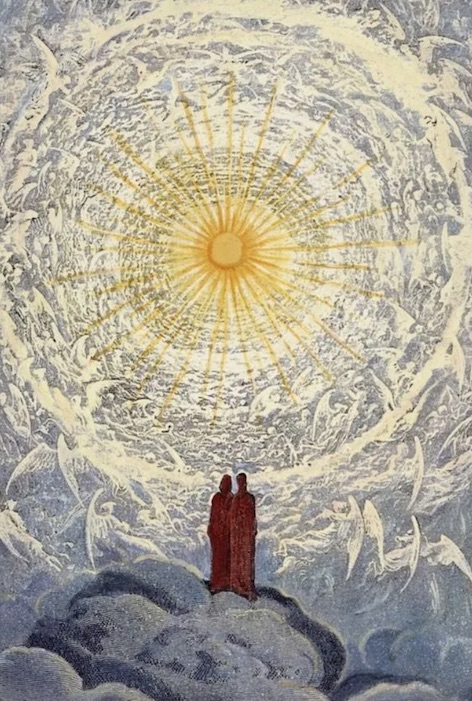
☆グローバル・ヴィレッジ(地球村)の住民は、身体を もたない「肉 体 なき人」たちである。肉体のない人には、実践上の倫理というものは存在するのか? 身体刑にも精神的拷問にも耐え得るこの「肉体なき人」たちを、 倫理規範を通してなんらかの秩序を保ち、人間の間の基本的信頼をどのように担保することができるのか? それがわれわれの当面の問題である(→「グローバ ル・ヴィレッジの地政学」)。
| "Global
village" refers to the concept that advancements in media and
communication technologies have interconnected the world, making it
feel like a single, unified community. The term was popularized by
Marshall McLuhan in the 1960s to describe how the world is shrinking
due to global interconnectedness. This interconnectedness is driven by
factors like international trade, migration, and the spread of culture.
|
「グローバル・ヴィレッジ」とは、メディアと通信技術の進歩によって世界が相互につながり、単一の統一されたコミュニティのように感じられるようになったという概念を指します。この用語は、1960年代にマーシャル・マクルーハンによって、グローバルな相互接続性によって世界が縮小している状況を表現するために広められました。この相互接続性は、国際貿易、移民、文化の拡散などの要因によって推進されています。 |
| Here's a more detailed look: Origin and Meaning: Marshall McLuhan's Idea: McLuhan, a media theorist, introduced the concept in his books, "The Gutenberg Galaxy" (1962) and "Understanding Media" (1964). Interconnectedness: The core idea is that electronic media, particularly television, have created a sense of immediacy and closeness, making the world feel smaller and more connected. Globalized Marketplace: The term also relates to the idea of a single, globalized marketplace and community fostered by trade and cultural exchange. Cultural Integration: The "Global Village" concept can also refer to spaces or programs designed to promote interaction and cultural exchange between people from different parts of the world, like Osaka University's Global Village. |
より詳しく見てみよう。 起源と意味: マーシャル・マクルーハンの考え: メディア理論家のマクルーハンは、著書『グーテンベルク・ギャラクシー』(1962年)および『メディアを理解する』(1964年)でこの概念を紹介した。 相互関連性: この概念の核心は、電子メディア、特にテレビが、即時性と親近感を生み出し、世界をより小さく、よりつながりのあるものにしたという考え方だ。 グローバル化された市場: この用語は、貿易や文化交流によって育まれた、単一のグローバル化された市場やコミュニティの概念にも関連している。 文化の統合: 「グローバル・ヴィレッジ」という概念は、大阪大学のグローバル・ヴィレッジのように、世界のさまざまな地域の人々の交流や文化の交流を促進するために設計された空間やプログラムも指す。 |
| Examples: Global Village Dubai: A popular entertainment and shopping destination in Dubai, featuring pavilions representing different countries and cultures. Global Village Program (Habitat for Humanity): An international volunteer program where people from around the world work together to build and repair homes in various locations. Global Village (International Preschool): An international preschool in Osaka that focuses on providing a total English immersion environment for young children. |
例: グローバルビレッジドバイ: ドバイの人気エンターテイメント&ショッピングスポット。さまざまな国や文化を紹介するパビリオンがある。 グローバルビレッジプログラム(ハビタット・フォー・ヒューマニティ): 世界中から人々が集まり、さまざまな場所で住宅の建設や修繕を行う国際的なボランティアプログラム。 グローバルビレッジ(国際幼稚園): 幼児に完全な英語環境を提供する、大阪にある国際幼稚園。 |
| Global village In the early 1960s, McLuhan wrote that the visual, individualistic print culture would soon be brought to an end by what he called "electronic interdependence" wherein electronic media replaces visual culture with aural/oral culture. In this new age, humankind would move from individualism and fragmentation to a collective identity, with a "tribal base." McLuhan's coinage for this new social organization is the global village.[h] |
グローバル・ヴィレッジ 1960年代初頭、マクルーハンは、視覚的で個人主義的な活字文化は、電子メディアが視覚文化を聴覚・口承文化に置き換える「電子相互依存」によって、間 もなく終焉を迎えるだろうと書いた。この新しい時代において、人類は個人主義と断片化から「部族的基盤」を持つ集団的アイデンティティへと移行するだろ う。マクルーハンがこの新しい社会組織に与えた造語は「グローバル・ヴィレッジ」である。 |
| The
term is sometimes described as having negative connotations in The
Gutenberg Galaxy, but McLuhan was interested in exploring effects, not
making value judgments:[48] |
この用語は『グーテンベルク・ギャラクシー』では否定的な意味合いで説明されているが、マクルーハンは価値判断を下すのではなく、その影響を探求すること に関心を持っていた。[48] |
| Instead
of tending towards a vast Alexandrian library the world has become a
computer, an electronic brain, exactly as an infantile piece of science
fiction. And as our senses have gone outside us, Big Brother goes
inside. So, unless aware of this dynamic, we shall at once move into a
phase of panic terrors, exactly befitting a small world of tribal
drums, total interdependence, and superimposed co-existence.… Terror is
the normal state of any oral society, for in it everything affects
everything all the time.… |
世
界は膨大なアレクサンドリア図書館に向かうのではなく、コンピュータ、電子頭脳となった。まさに幼児向けのSF小説の通りだ。そして、私たちの感覚が外
に向かうにつれ、ビッグブラザーは内に向かう。したがって、この力学を認識しない限り、私たちはたちまちパニックに陥るだろう。それはまさに、部族の太鼓
の音が鳴り響き、完全に相互依存し、重なり合う共存が繰り広げられる小さな世界にふさわしい恐怖である。恐怖は、口承社会における通常の状態である。なぜ
なら、そこではすべてが常にすべてに影響を及ぼすからだ。 |
| In
our long striving to recover for the Western world a unity of
sensibility and of thought and feeling we have no more been prepared to
accept the tribal consequences of such unity than we were ready for the
fragmentation of the human psyche by print culture. |
西洋世界が感覚、思考、感情の統一性を回復しようと長い間努力してきた中で、私たちは、活字文化による人間の精神の断片化に備える以上に、そのような統一 性から生じる部族的帰結を受け入れる準備ができていなかった。 |
| Key
to McLuhan's argument is the idea that technology has no per se moral
bent—it is a tool that profoundly shapes an individual's and, by
extension, a society's self-conception and realization:[62] |
マクルーハンの主張の要点は、テクノロジーそれ自体には道徳的な傾向はないという考え方である。テクノロジーは、個人、ひいては社会の自己概念と自己実現 を形作るツールである。 |
| Is it not obvious that there are always enough moral problems without also taking a moral stand on technological grounds?… |
テクノロジーの観点から道徳的な立場を取らないとしても、常に十分な道徳的な問題があることは明らかではないだろうか? |
| Print is the extreme phase of
alphabet culture that detribalizes or decollectivizes man in the first
instance. Print raises the visual features of alphabet to highest
intensity of definition. Thus, print carries the individuating power of
the phonetic alphabet much further than manuscript culture could ever
do. Print is the technology of individualism. If men decided to modify
this visual technology by an electric technology, individualism would
also be modified. To raise a moral complaint about this is like cussing
a buzz-saw for lopping off fingers. "But", someone says, "we didn't
know it would happen." Yet even witlessness is not a moral issue. It is
a problem, but not a moral problem; and it would be nice to clear away
some of the moral fogs that surround our technologies. It would be good
for morality. |
印刷は、まず第一に、人間を部族化または集団化から解放するアルファ
ベット文化の極限的な段階である。印刷は、アルファベットの視覚的特徴を最大限に明確
にする。したがって、印刷は、音声アルファベットの個別化能力を、手書き文化がこれまでなし得たことよりもはるかに遠くまで運ぶ。印刷は個人主義の技術で
ある。人間がこの視覚的技術を電気技術によって修正することを決めた場合、個人主義も修正されるだろう。これについて道徳的な不満を述べるのは、指を切り
落とすための電動のこぎりをののしるようなものだ。しかし、誰かが言うように、「私たちはそれが起こるとは知らなかった」のだ。しかし、無知でさえも道徳
的な問題ではない。それは問題ではあるが、道徳的な問題ではない。そして、私たちの技術を取り巻く道徳的な霧を晴らすことは素晴らしいことだ。それは道徳
にとって良いことだろう。 |
| The
moral valence of technology's effects on cognition is, for McLuhan, a
matter of perspective. For instance, McLuhan contrasts the considerable
alarm and revulsion that the growing quantity of books aroused in the
latter 17th century with the modern concern for the "end of the book."
If there can be no universal moral sentence passed on technology,
McLuhan believes that "there can only be disaster arising from
unawareness of the causalities and effects inherent in our
technologies".[63] |
マ
クルーハンにとって、テクノロジーが認知に及ぼす影響の道徳的価値は、視点の問題である。例えば、マクルーハンは、17世紀後半に書籍の量が増加したこ
とによって引き起こされた大きな不安や嫌悪感と、現代における「本の終焉」への懸念とを対比させている。テクノロジーに対する普遍的な道徳的判断を下すこ
とはできないが、マクルーハンは「テクノロジーに内在する因果関係や影響に対する認識の欠如から生じる災厄だけは避けられない」と考えている。[63] |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099