Foreign
Labor Problem accoding the reference of "ancient slave
system of the Roman Empire"
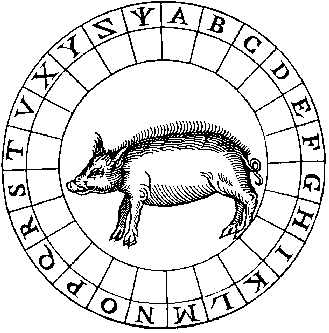
古代ローマの奴隷制から考える外国人労働問題
Foreign
Labor Problem accoding the reference of "ancient slave
system of the Roman Empire"
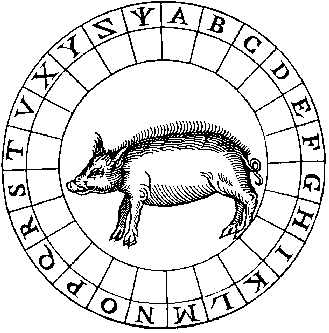
池田光穂
古代ローマの奴隷制から考える外国人労働問題,
Foreign Labor
Problem accoding the reference of "ancient slave
system of the Roman Empire"
奴隷制から外国人が抱える労働問題を考える、というのは、良識ある皆さんにとってある種の道徳的混乱を引き起こすでしょう。
まず、奴隷制は現代社会においては容認されていませ ん。「奴隷制が激しい攻撃の的である時代」[アンリ・レヴィ=ブリュール 1974:230]では、人身売買や奴隷労働は国際法において禁止され、またそれぞれの独立国家において容認されていません。他方、外国人の国境を越えた 流動化は現在は当たり前になった以上、(すでに廃絶された制度である)奴隷制の視点などは、現在の外国人の国際移動と、その異動先で引き起こされるさまざ まな問題と「全く関係のないものである」とすることができます。そのとおりです。しかしながら、過酷な外国人労働者への処遇の酷さと賃金の低さ、さらに (移民先の)社会保障制度の恩恵から排除される傾向から、我々はしばしば、過酷な労働の現場を「奴隷労働」と呼ぶことに吝かではありません。
奴隷が生まれる要因はさまざまなものがあります。ま ず(1)同一社会における身分制の存在、とりわけその社会の中に制度としての奴隷制を組み込んだも の。次に(2)戦争や植民という行為により、敗戦したり、侵略された人々が、勝利者たちにより奴隷にされることがあります。この2つは「社会制度としての 奴隷」です。そして、最後に(3)奴隷制をモデルにして、犯罪や虐待を通してそれと類似の使役を特定の個人に行うこと、です。この最後のものは、冒頭で述 べたように、奴隷制を禁止した社会にとっては、異常で犯罪に相当するものです。そのため、これを「機会主義的な奴隷」あるいは「非制度としての奴隷」と呼 ぶことができます。私がここで検討したいのは、社会制度としての奴隷で、(3)の奴隷についてはこれ以上考察しないことにします。
さて、奴隷制と外国人問題を考えるきっかけになった
は、アンリ・レヴィ=ブリュル——哲学者でかつ興味深いアームチェア人類学者であったリュシアンの息
子——の古代ローマに関する奴隷制に関する次のような主張でした。
「古代ローマ法における奴隷制に関する知識を提供するすべての記録から、最も確実に引き出せそうな見解は、奴隷制とは、奴隷と外国人との2つの概念が混在
しているという意味で、当時における本質的に国際的レベルの身分制度だということである。いいかえれば、この時代の奴隷とは権利の欠如した外国人以外の何
ものでもない」[レヴィ=ブリュール 1974:215]。
古代ローマは、御存知のように帝国の周辺への軍事的侵攻と征服(平定)とその属国を帝国に編入することにおいて巨大な領土拡張に成功しました。この帝国
の拡大は、都市国家レベルにとどまっていた古代ギリシャと性格を異にして、広大な帝国内の管理についての未曾有の統治制度についての技術を洗練させていき
ました。その帝国の統治術において大きな意味をもつものが、法制度と徴税制度です。したがって、ここでの問題は、法制度と奴隷制度をどのように考えるかで
す。しかしながら、征服の帰結としての被征服民の奴隷化がいかに一般的であっても、帝国の拡大をさらにその外延に保証するためには、帝国内の人間の身分を
統一化することが不可欠になります。同一の帝国内で、征服/被征服の人間の区分が続くかぎり、被征服民の離反や反乱は避けがたく、また同時に帝国の理念に
も反しますし、そして、さらなる征服という帝国がもつ拡張の原理——千数百年後に大英帝国のケープ植民地首相だったセシル・ローズは「拡張こそはすべてで
ある」と主張します——にも矛盾します。
現実のローマ帝国(Senatus
Populusque
Romanus)は千年近い歴史をもつので、このテーマは極端に単純化したものにすぎません。現実のローマがどのようなものであろうとも、ローマの統治原
則における奴隷制と外国人の扱いがどのようなものであったのかという法解釈から、現代における外国人「労働」の性格を考察するヒントがここにあるように思
われます。
奴隷制をめぐる2つのテーゼがあります。
(1)「あらゆる奴隷は外国人である」
(2)「いかなるローマ人もローマにおいて奴隷になることはない」
また、奴隷制をめぐる法的解釈を、ローマ人は奴隷制 は万物法(jus gentium)、つまり奴隷制は普遍だと言います。しかし、これはレヴィ=ブリュルによると、普遍的な存在意義があるというよりも「彼らが言いたいの は、奴隷制が彼らの知るあらゆる民族に見出されるということ」だといいます[レヴィ=ブリュール 1974:216]。この場合のローマ人の奴隷制普遍説は、法的な推論から帰結されるのではなく、周辺民族との観察から経験的事実として受け入れられ、ま たローマ人においてもそれは可能だと考えていることになります。
かれらの法的見解は、
(3)奴隷は権利を剥奪された存在である、そして
(4)奴隷は、モノあるいは動物として捉えられる。
『ガイウス、法学提要』(船田亨二訳)有斐閣 1967:123、には「有体物とは接触できる物をいう。例えば……奴隷である」。
(5)市民法に関しては、奴隷は無[人格]と見なさ
れる
(6)奴隷は……いかなる人格も持たない
Ulpianus apud Dig., 50,17,32.
したがって、奴隷には(現実や慣習的取り扱いはとも かくも、法的には)保護される権利どころか、権利というものがないものとされています。そしてアリスト テレスは、
(7)奴隷は財産である、(ただし)生命ある財産で ある。
と述べています。つまり、生命(zoe)はあるが、 主体性をある生命(bios)とは見なされていないのです。
これは、債務を負い、労働を通して対価を支払わねば ならない隷属状態に置かれている人とは根本的に異なることをさします。
権利がないことは、移動の自由がないことも意味しま す。もちろん、財産をもつ権利もありません。
ただし、ストア派の考え方がローマ社会に流布した時 に、奴隷に人格を認める自然法(jus naturale)にもとづく見解も同時に存在しました。
さて、家父長は、家子の生殺与奪の権利をもち、その 家長が債務者になった時に、家子を売却することは可能だと言いますが、しかし、家子を奴隷にすること はできないと言います[レヴィ=ブリュール 1974:218]。このことからレヴィ=ブリュルは「奴隷身分には刑罰以外のもの、つまり対人法規の実質的な変更を見るべきであって、その変更は、いか に強力であっても特定の意志が作り出しうるものはなかった」と[ibid, pp.218-219]。
また、ローマ法には、
(8)刑罰として奴隷身分に処することができる、
とも言います。しかしこの処罰は、(2)の原則に反 すると思われます。また、レヴィ=ブリュルも、古代ではなく後の時代になり、このような法規が登場する と言います[レヴィ=ブリュール 1974:219-220]。債務者ですら、奴隷にできないのは、十二表法に、それを行いたかったら「ティベル川の彼岸に」国境の外のエトルリアに売らな ければならないことを規定しています。
刑罰を通して市民を奴隷の身分に落とすという考え方 は、レヴィ=ブリュルの歴史的解釈[1974:230-231]によると、ストア派の流布と、奴隷の 社会的かつ経済的貢献から、奴隷が人種的に異なる外国人という見解を維持することがもはやできなくなったことと関係しています。つまり奴隷と自由民との間 に質的な差異を見ることができなくなったときに、(市民権が剥奪された差別と排除の対象として)〈自由民を奴隷する〉ことができる法的手続きが始まったと 考える余地が生まれます。
いずれにせよ、レヴィ=ブリュルの主張である、奴隷
は外国人という命題を確認して、その根拠をローマ人は奴隷制を、絶対的な差異——奴隷の世襲に象徴
されます——すなわち「人種的」なものであると考えていたと次のように言います。
「……奴隷が外国人であると主張することは、奴隷状態がいわばその人格に賦与された奴隷の極印であって、どのような人間にも影響を及ぼしうる単純な法的関
係ではないということである。もし言葉の意味を少し強めることを恐れないならば、奴隷制は人種的な、したがって消し去ることのできない特質を持つといえよ
う」[レヴィ=ブリュール 1974:221]。
また、ラテン語では Semel servus, semper servus (一旦奴隷になれば、永久に奴隷)という表現があります。
このような奴隷の絶対的な他者性に対して、古代ローマは3つの解消——奴隷解放——を同時に併せ持っていました。それが以下のような解放の方式です。ま
ず(i)「棍棒による解放」:政務官が判決により奴隷の主人の意志を承認する手続き、(ii)戸口調査による解放:戸口按察官(ケンソル)が戸籍調査の際
に外国人を市民に帰化されたものとみなす方法、および(iii)遺言による解放:主人が遺言により申し出て市民団が民会で承認する手続きがとられる解放、
です。いずれにしても、奴隷は、主人の意志によってその状態が維持されているわけではなく、奴隷の地位は、主人の「解放」のための手続きと社会による承認
がなされない限り、奴隷状態は不変——永遠に続く——です。主人に捨てられた奴隷は「『主人のない奴隷(servus sine
domino)』であり、誰が捕まえてもよい。したがって奴隷を奴隷たらしめるのは『主人の権力(dominica
potestas)』ではない。奴隷状態が[権利を]欠落した状態であることをこれ以上によく証明できるものはないだろう」[レヴィ=ブリュール
1974:222]。
つまり、ローマでは、奴隷は外国人、それも——解放という手続きにより市民化しないかぎりは——法的権利がない外国人なのです。古代ギリシャでは、自由
人は奴隷になれませんし、ユダヤの法では奴隷制は外国人にのみ適用されます[レヴィ=ブリュール
1974:223]。もちろん、解放後の奴隷がすべてに、ローマの「市民権と自由」のもとに生活できるようになったのかどうかについては疑問の余地があり
ます[ibid 1974:227]。
ここからレヴィ=ブリュルは、次のように結論します。そのような制度をもつ人たちは、同国人を奴隷にすることに嫌悪するだろう、と。すくなくとも(国民
を統一した基準で諸権利を与える/持つ)市民権にもとづいた社会には、このような感情を共有するだろうと言います。
このように奴隷制を同国民=同胞に対して導入することを嫌悪す
る市民社会は、外国人に対して、あるいは外国人とみなして、奴隷制を維持することが考えら
れます。他方で、冒頭で述べたように、帝国の領土を拡大し、それを市民による構成体として維持拡張するためには、包摂した外国人を常に奴隷
化することに
は、大きなリスクが伴います。このような排他原理は、奴隷が多数化することで、維持管理することが破綻することは目に見えています。それは、帝国に包摂さ
れる側の人間にとっても同じで、もしローマが外国人を常に奴隷にする原理をもって外国人に対処していたら、そこまで帝国を拡大することはできなかったよう
に思われます。
事実、ローマには平和条約を結んでいない外国人たちにも、被護民(クリエンス)として包摂する制度がありました。
「……ローマ人でもラテン人でもない者で、ローマと平和条約を結んだ国家(civitates)に属さない者がローマに入る時は、奴隷状態に陥る危険を冒
したといえるだろうか。危険を免れる方法はあった。それは氏族(gens)の長の保護下に入ること、つまり彼の被護民(クリエンス)になることであった。
この場合、彼らの間には両者の負担すべき義務を生み出す契約が結ばれた。義務とはクリエンスの側の服従、氏族長の側の保護である。庇護制度(クリエンテ
ラ)に関するわれわれの知識がまだ曖昧だとしても、クリエンスが奴隷でなかったことに疑問の余地はないと思われる」[レヴィ=ブリュール
1974:224]。
外国人すなわちローマ人でないことの最大の特徴は、「市民権と
自由」を保持していないことにつきます。だからレヴィ=ブリュルは、ローマにおける外国人
は奴隷と同だと結論づけます。つまり、人間としての権利を確保していないのです。庇護民——氏族の代わりに国際機関の保護下に入ることを、
現在の制度では
「難民」がそれに相当するでしょう——このような制限の可能性のある回路を通して、ローマにおいて奴隷(=外国人)にならない方法はあったということが重
要なのです。ただし、古代ローマ人に、今日の外国人労働者問題にみられるように、奴隷としての外国人を労働力として「有効活用」しようという発想はありま
せんでした。
「もし、こう言う方が良ければ、外国人とは、誰もが好きなように取得したり、使用できる存在、つまり殺しても罰せられない、法益剥奪を受けた者(アウト
ロー)なのである。動物を殺すかわりに、飼育しよう考えるのとちょうど同様に、経済事情を考慮してその労働力を利用するという考えに至る以前は、外国人の
運命はこのようなものであることが多かった」[レヴィ=ブリュール 1974:228]。
以上のレヴィ=ブリュルによる奴隷を外国人としてみる見方は、あらゆる時代における外国人を構造的に差別し、権利をもった市民のために流用しようとする発
想にとっては、とても有用なものに思われます。しかしながら、奴隷(外国人)が社会的あるいは経済的力をもって、むしろ市民として処遇する必要性が生じて
きたり、逆に市民から処罰として市民権を剥奪する、つまり奴隷の地位に陥れるという法的な措置が可能になった時点で、奴隷と外国人を、市民とは根本的に異
なるものとして区分し、差別待遇するための論理的な正当性が失われたために、奴隷=外国人という論理は、運用上は完全に破綻してしまいました。
カント的な道徳の適用の基準は原則から演繹されるべ きもので、経験的な事実から、その原則をアド・ホックに曲げるべきではないと言われます。しかしなが ら、倫理の起源にまつわるアリストテレス的な説明(=道徳 morale は慣習 ēthos から生まれる)からみると、カントによる基準や原則は、無から有を産み出せないという理由でかなり窮屈なやり方のようです。
さすれば、外国人労働を、奴隷労働として認めること はできません。また、労働者がかりに不法入国者であったとしても、その過酷な労働を通して、日本の経 済界に対して貢献をしている/いたと認められるのであれば、奴隷労働の経営者を何らかの罪に問わずして、入国管理法にもとづいてすぐに労働者を国外退去す る措置は、受け入れ国家としては倫理性あるいは正義にもとること——より厳しく言えば社会的悪に匹敵すること——をおこなっていると言えるでしょう。もっ ともベストな方法は、奴隷労働という非人道的な業務に従事していたことに鑑み、一定の市民権を与えてから、(不法入国等の)処罰手続きに入るべきでしょ う。
■文献
■関連リンク集
Do not paste, but [re]think this message for all undergraduate students!!!