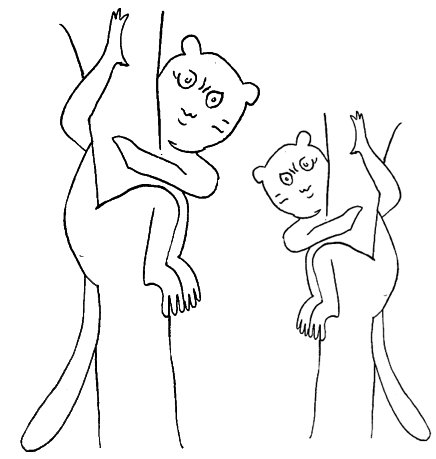ミルマン・パリーとホメロス
Milman Parry and Homer
☆ ミルマン・パリー(Milman Parry、1902年6月23日 - 1935年12月3日)はアメリカの古典学者で、そのホメロス作品の起源に関する理論は、「ホメロス研究のダーウィン」と評されるほど、ホメロス研究に根 本的な革命をもたらした。1928年にフランス語で出版された学位論文の中で、パ リーはホメーロ スの文体が、同じ計量的条件のもとで与えられたアイデアを表現するために適応された 固定表現、すなわち「定型」の多用によって特徴づけられることを実証した。たとえば、「神々しいオデュッセウス」、「多弁なオデュッセウス」、「大いに耐 え忍ぶ神々しいオデュッセウス」などは、物語を前進させることよりも、ヘキサメーター(六歩格)の詩の残りの部分に収めるべき素材の量に応じたものであっ た。この詩の口語的な性質は、記憶の補助として、また即興を容易にするために、このような仕掛けに依存していることからも明らかである。それらは、ホメロ ス叙事詩が一人の詩人の発明ではなく、長年の伝統の中で徐々に進化してきたことを示唆する手がかりであった(口承定型仮説, 口承定型文)。
| ★Milman Parry (June
23, 1902 – December 3, 1935) was an American Classicist whose theories
on the origin of Homer's works have revolutionized Homeric studies to
such a fundamental degree that he has been described as the "Darwin of
Homeric studies".[1] In addition, he was a pioneer in the discipline of
oral tradition. |
ミルマン・パリー(Milman Parry、1902年6月23日
-
1935年12月3日)はアメリカの古典学者で、そのホメロス作品の起源に関する理論は、「ホメロス研究のダーウィン」と評されるほど、ホメロス研究に根
本的な革命をもたらした。 |
| Early life and education Parry was born in 1902 in Oakland, California. He grew up in a house full of books, with a father who was self-taught and widely read. He and his siblings often recited poems from memory as a game.[2] He graduated from Oakland Technical High School in 1919,[3] and studied at the University of California, Berkeley (B.A. and M.A.) where he became proficient in ancient Greek and the Classics.[2] He then studied for a PhD at the Sorbonne in Paris and was a student of the linguist Antoine Meillet. In his dissertations, which were published in French in 1928, Parry demonstrated that the Homeric style is characterized by the extensive use of fixed expressions, or "formulas", adapted for expressing a given idea under the same metrical conditions. For example, "divine Odysseus", "many-counseled Odysseus", or "much-enduring divine Odysseus" had less to do with moving the story forward than with being in accordance with the amount of material to be fitted into the remainder of the hexameter verse. The oral nature of the poem was evident in the dependence on these devices, both as memory aids and to allow for easier improvisation. They were clues suggesting that the two Homeric epics were not the inventions of a single poet but had been gradually evolved in a long-standing tradition.[2][4] As one scholar put it, "Parry never solved the Homeric Question [who was Homer]; he demonstrated that it was irrelevant".[2] Meillet introduced Parry to Matija Murko, who had worked on oral epic traditions in Yugoslavia[5] and had made phonograph recordings of some performances. |
生い立ちと教育 パリーは1902年、カリフォルニア州オークランドに生まれた。独学で幅広い読書をした父のもと、本が溢れる家で育った。兄妹はよくゲーム感覚で詩を暗唱 していた[2]。 1919年にオークランド工業高校を卒業し[3]、カリフォルニア大学バークレー校で学び(学士号と修士号)、古代ギリシャ語と古典に精通した[2]。 1928年にフランス語で出版された学位論文の中で、パリーはホメーロ スの文体が、同じ計量的条件のもとで与えられたアイデアを表現するために適応された 固定表現、すなわち「定型」の多用によって特徴づけられることを実証した。たとえば、「神々しいオデュッセウス」、「多弁なオデュッセウス」、「大いに耐 え忍ぶ神々しいオデュッセウス」などは、物語を前進させることよりも、ヘキサメーター(六歩格)の詩の残りの部分に収めるべき素材の量に応じたものであっ た。この詩の口語的な性質は、記憶の補助として、また即興を容易にするために、このような仕掛けに依存していることからも明らかである。それらは、ホメロ ス叙事詩が一人の詩人の発明ではなく、長年の伝統の中で徐々に進化してきたことを示唆する手がかりであった[2][4]。 ある学者が言うように、「パリーはホメロス問題(誰がホメロスなのか)を解決することはなかった。 メイエはユーゴスラビアで口承叙事詩の伝統に取り組み[5]、いくつかの演奏を蓄音機で録音していたマティヤ・ムルコにパリーを紹介した。 |
Academic career In 1928-1929,
Parry began his academic career as a Professor of Latin
and Greek at Drake University. Between 1933 and 1935 Parry, at the time
an assistant professor at Harvard University, made two visits to
Yugoslavia, where he studied and recorded oral traditional poetry in
Serbo-Croat with the help on his second visit of his assistant Albert
Lord, and a native singer and fixer named Nikola Vujnović, who became
essential to finding and communicating with other singers, known as the
guslar. They worked in Bosnia, where literacy was lowest and the oral
tradition was, in the term used by Parry and Lord, "purest". They made
thousands[6] of hours of recordings in remote mountain villages of
illiterate farmers who sang epic songs of prodigious length from
memory. Parry and Lord recorded on newly invented equipment, flat
aluminum records instead of vinyl, custom made for the expedition, with
only a five minute recording time. Discs were continually swapped with
a special two-disc machine to create a single long recording, later
transcribed. They also recorded conversations between guslari after it
became apparent this was also part of the creative process that
fertilized improvisation.[2] In 1928-1929,
Parry began his academic career as a Professor of Latin
and Greek at Drake University. Between 1933 and 1935 Parry, at the time
an assistant professor at Harvard University, made two visits to
Yugoslavia, where he studied and recorded oral traditional poetry in
Serbo-Croat with the help on his second visit of his assistant Albert
Lord, and a native singer and fixer named Nikola Vujnović, who became
essential to finding and communicating with other singers, known as the
guslar. They worked in Bosnia, where literacy was lowest and the oral
tradition was, in the term used by Parry and Lord, "purest". They made
thousands[6] of hours of recordings in remote mountain villages of
illiterate farmers who sang epic songs of prodigious length from
memory. Parry and Lord recorded on newly invented equipment, flat
aluminum records instead of vinyl, custom made for the expedition, with
only a five minute recording time. Discs were continually swapped with
a special two-disc machine to create a single long recording, later
transcribed. They also recorded conversations between guslari after it
became apparent this was also part of the creative process that
fertilized improvisation.[2]The "jewel of the collection" is The Wedding Song of Smailagić Meho, by a poet named Avdo Međedović, "by far the most skillful and versatile performer whom Milman encountered".[6] One of the songs, running to some 13,000 lines and performed over five days, was the closest analogue to Homer in quality and quantity; Parry said one "has the overwhelming sense that, in some way, he is hearing Homer". Međedović boasted he knew longer songs.[6] In his American publications of the 1930s, Parry introduced the hypothesis that the formulaic structure of Homeric epic is to be explained as a characteristic feature of oral composition, the so-called Oral Formulaic Hypothesis. After Parry's death, the idea was championed by Albert Lord, most notably in The Singer of Tales (1960).[7] |
学者としてのキャリア 1928年から1929年にかけて、
パリーはドレイク大学でラテン語とギリシア語の教授としてアカデミックなキャリアをスタートさせた。1933年から
1935年にかけて、当時ハーバード大学の助教授であったパリーはユーゴスラビアを2度訪れ、セルボ・クロアチア語の口承伝統詩を研究・録音した。2度目
の訪問では、助手のアルバート・ロードと、グスラーとして知られる他の歌手を見つけ、コミュニケーションをとるために不可欠となったニコラ・ヴイノヴィッ
チというネイティブの歌手兼フィクサーの助けを借りた。彼らは、識字率が最も低く、パリーとロードの言葉を借りれば「最も純粋な」口承伝統があったボスニ
アで活動した。彼らは人里離れた山村で、膨大な長さの叙事詩を記憶に基づいて歌う文盲の農民たちの録音を何千時間にもわたって行った[6]。パリーとロー
ドは、新しく発明された機材で録音を行った。ビニールの代わりに平らなアルミのレコードで、この探検のために特注されたもので、録音時間はわずか5分だっ
た。ディスクは特殊な2枚組の機械で絶えず交換され、後に書き起こされる1枚の長い録音が作られた。また、グスラーリ同士の会話も録音されたが、これも即
興を生み出す創造的なプロセスの一部であることが明らかになってからである[2]。 1928年から1929年にかけて、
パリーはドレイク大学でラテン語とギリシア語の教授としてアカデミックなキャリアをスタートさせた。1933年から
1935年にかけて、当時ハーバード大学の助教授であったパリーはユーゴスラビアを2度訪れ、セルボ・クロアチア語の口承伝統詩を研究・録音した。2度目
の訪問では、助手のアルバート・ロードと、グスラーとして知られる他の歌手を見つけ、コミュニケーションをとるために不可欠となったニコラ・ヴイノヴィッ
チというネイティブの歌手兼フィクサーの助けを借りた。彼らは、識字率が最も低く、パリーとロードの言葉を借りれば「最も純粋な」口承伝統があったボスニ
アで活動した。彼らは人里離れた山村で、膨大な長さの叙事詩を記憶に基づいて歌う文盲の農民たちの録音を何千時間にもわたって行った[6]。パリーとロー
ドは、新しく発明された機材で録音を行った。ビニールの代わりに平らなアルミのレコードで、この探検のために特注されたもので、録音時間はわずか5分だっ
た。ディスクは特殊な2枚組の機械で絶えず交換され、後に書き起こされる1枚の長い録音が作られた。また、グスラーリ同士の会話も録音されたが、これも即
興を生み出す創造的なプロセスの一部であることが明らかになってからである[2]。「コレクションの宝石」は、アヴド・メジェドヴィッチという詩人による『スマイラ ギッチ・メホの結婚式の歌』であり、「ミルマンが出会った中で最も巧みで多 才な演奏家」[6]であった。5日間にわたって演奏された約13,000行に及ぶ歌のひとつは、質・量ともにホメロスに最も近いものであり、パリーは「あ る意味で、ホメロスを聞いているような圧倒的な感覚を覚える」と述べている。メジェドヴィッチはもっと長い曲を知っていると自慢していた[6]。 1930年代にアメリカで出版された本の中で、パリーはホメロス叙事詩の定型構造を口承文の特徴として説明するという仮説、いわゆる口承定型仮説を紹介し た。パリーの死後、この考えはアルバート・ロードによって支持され、特に『The Singer of Tales』(1960年)において顕著である[7]。 |
| Death and commemoration When Parry returned to the United States in 1935, he learned that his wealthy mother-in-law had fallen in with some people who were stealing from her without her knowledge. During his field excursions in the Balkans, Parry had developed the habit of carrying a gun, and he packed one in his luggage for a visit to California with his wife for the purpose of aiding his mother-in-law. In the late afternoon of December 3, at the Palms Hotel in Los Angeles, Parry was dressing for a dinner with friends, while his wife was in another room. Accounts differ, but she either heard a muffled shot or Parry groaning, and found him shot in the heart. He died soon afterwards. Police detectives determined that the gun was fired accidentally as he was removing clothing from his luggage. The safety had not been set and the trigger had become entangled in a shirt, which bore gunpowder burns.[2] Various rumors circulated, including the ideas that Parry committed suicide because he was despondent over Harvard's failure to give him a permanent appointment, or that his wife killed him.[2] Parry's daughter, Marian, believed for the rest of her life that her mother killed him, and pointed to her mother's insane fits and accusations of infidelity.[2] Detailed examination of the evidence by classicist Steve Reece concurs with the contemporary official conclusion that Parry's death was accidental.[8] Parry's collected papers were published posthumously in The Making of Homeric Verse: The Collected Papers of Milman Parry, edited by his son Adam Parry (Oxford University Press, 1971). The Milman Parry collection of records and transcriptions of South Slavic heroic poetry is now in the Widener Library of Harvard University. The journal Oral Tradition is devoted to advancing Parry's work. |
死と記念 1935年に米国に戻ったパリーは、裕福な義母が、義母の知らないところで盗みを働く輩に引っかかっていたことを知った。バルカン半島での遠征で銃を携帯 する習慣を身につけたパリーは、義母を助けるために妻とともにカリフォルニアを訪れる際、荷物に銃を忍ばせた。12月3日の午後遅く、ロサンゼルスのパー ムス・ホテルで、パリーは友人たちとの夕食のために着替えていたが、妻は別の部屋にいた。証言はさまざまだが、妻はかすかな銃声かパリーのうめき声を聞 き、心臓を撃たれているのを発見した。彼はまもなく死亡した。警察の刑事は、彼が荷物から衣服を取り出そうとしたときに誤って発砲したと断定した。安全装 置がセットされておらず、引き金がシャツに絡まって火薬の焼け跡が残っていた[2]。 パリーが自殺したのは、ハーバード大学が彼に永久的な任命を与えなかったことに落胆したからだとか、妻が彼を殺したのだとか、様々な噂が流れた[2]。パ リーの娘マリアンは、母親が彼を殺したのだと生涯信じ続け、母親の狂気の発作と不倫の告発を指摘した[2]。古典学者スティーブ・リースによる証拠の詳細 な検証は、パリーの死は事故死であったという現代の公式結論と一致している[8]。 パリーの論文集は死後に『The Making of Homeric Verse:The Collected Papers of Milman Parry, edited by his son Adam Parry』として出版された: (Oxford University Press, 1971). 南スラブ英雄詩の記録と書き写しのミルマン・パリー・コレクションは現在、ハーバード大学のワイドナー図書館に所蔵されている。オーラル・トラディショ ン』誌は、パリーの研究を発展させることに専念している。 |
| Influence According to Steve Reece, there is "an enormous body of literature on Parry’s intellectual legacy".[8] His influence is evident in the work of later scholars who have argued that there was a fundamental break in institutional structure between Homeric Greece and Platonic Greece, a break characterized by the transition from an oral culture to a written culture. This line of thought holds that in Homeric society, oral poetry served as a record of institutional and cultural practices. This thesis is associated with Eric Havelock, who cites Parry. Havelock argues that the fixed expressions that Parry identified can be understood as mnemonic aids, which were vital to the well-being of society, given the importance of the information carried by the poetry. Personal life Parry was married to Marian Thanhouser, who came from a German Jewish family, and endured anti-Semitic comments from some of her husband's colleagues.[2][8] They had two children, Marian and Adam (1928–1971). The latter was the chairman of Yale University's Classics Department, until his untimely death, together with his wife Anne Amory, in a motorbike accident.[9][10] |
影響力 スティーヴ・リース(Steve Reece)によれば、「パリーの知的遺産に関する膨大な文献」[8]が存在する。彼 の影響は、ホメロス朝ギリシアとプラトン朝ギリシアの間に制度構造の 根本的な断絶があり、口承文化から文字文化への移行を特徴とする断絶があったと主張する後世の学者たちの研究に顕著である。ホメロス社会では、口承詩が制 度的・文化的慣習の記録として機能していたとする考え方である。このテーゼは、パリーを引用したエリック・ハヴェロックと関連している。Havelock は、Parryが特定した固定表現は、詩が伝える情報の重要性を考えれば、社会の幸福に不可欠なニーモニック補助として理解できると主張している。 私生活 パリーは、ドイツ系ユダヤ人の家庭に生まれたマリアン・タンハウザーと結婚し、夫の同僚たちからの反ユダヤ主義的な発言に耐えていた[2][8]。アダム はイェール大学古典学部の学長を務めたが、妻のアン・エイモリーとともにバイク事故で早世した[9][10]。 |
| Kanigel, Robert. Hearing Homer's
Song: The Brief Life and Big Idea of Milman Parry. 2021. Penguin. ISBN
978-0525520948 (soft cover). Young Albert and Mr. Parry When she asked where they were going and why, Milman Parry’s daughter, Marian, would recall, my father explained that Jugoslavia was an uncivilized country at the edge of the world, on the border of the Slavic wilderness which stretched from the Adriatic to Alaska. Since hardly anyone could read or write Jugoslavians still had retained their oral poetry and their ancient native national civilization. There were still heroes, and heroic acts and the ancient heroes were celebrated in ballads by guslars, or bards, who knew by heart so much poetry that if it were written down it would fill libraries. But the whole thing depended, my father explained, on the fact that they couldn’t write it down; as soon as literacy becomes common in a country, everyone gets lazy; they don’t bother to learn things by heart anymore and poetry is no longer a part of their daily life. ln 1934 and 1935, Parry spent fifteen months in Yugoslavia, driving his black Ford sedan from town to town with his young assistant, Albert Lord. They stopped at village coffeehouses, spread word they were looking for local singers, recorded the songs they sang while strumming their rude, raspy one-stringed gusles. For a few days, or a week or two, Parry would stay, then head off for the next town, for Gacko or Kolašin, Bihać or Novi Pazar. In that hardscrabble, mostly mountainous backcountry, of roads rutted and electricity scarce, of dialects, religions, ancient wars, and tribal resentments all butting up against one another, they struggled with equipment and supplies and bedbug-infested village inns. They powered their recording instrument with a battery charged by the engine of the Ford, shipped over from the States. Along with their native translator, Nikola, they’d periodically return to Dubrovnik, in a Croatian corner of the Kingdom of Yugoslavia, where Parry’s wife, daughter, and son awaited them. Then, the Parry house, halfway up the hill above the city, with its fine views of the harbor and the sea, became headquarters of almost military stamp, as transcribers set to work, typewriters clattering, taking down the words of the old songs. In the end, Parry would gather half a ton of twelve-inch aluminum discs—phonograph records, the size of old vinyl LPs but in white metal—filled with a young nation’s, and an old world’s, cultural tradition. But Parry was interested in them not primarily for what they said of Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, and elsewhere in the Balkans, but for what they might reveal, by analogy, of the older world of ancient Greece that had produced Homer’s Iliad and Odyssey. Finally, in a town nineteen hundred feet up into the mountains of northern Montenegro, an old man named Avdo Međedović, singer of tales of weddings and war that took days and days to tell, led Parry to conclude that in him they had found their own living Homer. In September 1935, the Parrys and young Albert Lord returned to America. On November 16, Parry, back at Harvard, where he was assistant professor of Greek and Lord was a recent graduate, wrote his sister that his wife was just then in Los Angeles. He gave her mailing address, which was that of his financially distraught mother-in-law. On November 17, Parry was to give a talk on Yugoslav folk songs at Harvard. On the eighteenth, he met with a student and reported on his progress. A day or two later, he left for the West Coast. On December 3, in a Los Angeles hotel room with his wife, a bullet fired from a handgun, said to have become entangled in his luggage as Parry rummaged through it, struck him in the chest and nicked his heart. He died later that day. He was thirty-three. When hotel employees responded to Mrs. Parry’s call, they assumed she had killed her husband; she was the only other person in their suite. The police, however, concluded otherwise, that it was an accident. No autopsy was performed. No charges were brought. Some would suspect that Parry had committed suicide. Later, among Parry’s own children, that their mother had killed him was regarded as a real possibility: Maybe in one of her fits of fierce, irrational rage. Or maybe as cool-headed revenge for real or imagined infidelities, or other hurts he’d inflicted on her over the years. Mrs. Parry and her daughter, twisted by a lifetime’s mutual antagonism, were both named Marian. Marian the younger was all but certain her mother had killed her father and held to this view all her life. On December 5, 1935, Parry’s body was cremated in Los Angeles. Two weeks later, back at Harvard, a memorial service was held in Appleton Chapel. In the eulogy it was said that Parry had returned from Yugoslavia “with copious material which no future investigators in his field can afford to neglect. His work will endure long after him.” In early 1936, Mrs. Parry donated most of her husband’s books, recordings, and papers to Harvard and, with remarkable efficiency, decamped from Cambridge with her children, moved across the continent to Berkeley, California, returned to school at the university, and in little more than a year had earned the BA degree that pregnancy, marriage to Milman, and life with him in France and Cambridge had interrupted. Meanwhile, Parry’s young assistant, Albert Lord, was left with the Yugoslav materials. After working with the man he would call his “master and friend” for fifteen months, he was now almost alone responsible for making something of them. Parry himself had had no chance to do so. Back in Yugoslavia, the winter before coming home, he’d dictated a few pages of notes and ideas; Lord typed them up. And he had a title for the book he hoped to write, Singer of Tales. Now it was all in the hands of Lord, who, at age twenty-three, was scarcely equipped to tackle the job. Approaching graduation from Harvard in June 1934, Lord “had not the slightest idea of what to do with himself,” reports David Bynum, a student and admiring younger colleague of Lord’s from a later period. Yugoslavia had come at an opportune time—immediately after graduation, in the middle of the Depression, a time of few other job prospects. Lord served Parry as typist, gofer, and “recording engineer,” freeing Parry for more substantive and intellectually challenging work. He had “no opportunity whatever, as well as no personal inclination, to inquire or know anything meaningful concerning what Parry was about or why in Yugoslavia.” The shiny white aluminum discs were, in their thousands, logistical monster and intellectual mystery. What transformed this untenable situation was this: However much or little his time in Yugoslavia might make him responsible in the eyes of the world for making something of Parry’s work, Lord seemed to feel it did. And he felt it all the more with the passage of time, as a deep, pressing, personal need, one impossible to shirk. He had worked beside Parry for fifteen months; he would help advance and enrich Parry’s ideas for more than fifty years. “In spite of moments when it seemed otherwise,” Lord would write, “my life has been devoted to Parry’s collection and to the work which he had only begun to do.” |
若きアルバートとパリー氏 どこに行くのか、なぜ行くのかと尋ねると、ミルマン・パリーの娘マリアンはこう答えた、 父は、ユーゴスラビアは世界の果てにある未開の国で、アドリア海からアラスカまで続くスラブ原野の境界にあると説明した。ユーゴスラビアの人々は、ほとん ど誰も文字を読むことも書くこともできなかったので、口承詩や古代の民族文明が残っていた。英雄はまだいたし、英雄的行為や古代の英雄は、グスラー(吟遊 詩人)によってバラッドで讃えられた。識字率が一般的な国になると、誰もが怠け者になり、わざわざ物事を暗記することもなくなり、詩は日常生活の一部では なくなったのだ。 1934年から1935年にかけて、パリーはユーゴスラビアで15ヵ月を過ごし、若い助手のアルバート・ロードとともに、黒のフォード・セダンで町から町 へと車を走らせた。村の喫茶店に立ち寄り、地元の歌手を探しているという情報を流し、無骨で荒々しい一弦のガズルをかき鳴らしながら歌う歌を録音した。数 日間、あるいは1週間、2週間、パリーは滞在し、ガッコやコラシン、ビハッチやノヴィ・パザールといった次の町へと向かった。道路はわだちだらけ、電気は 乏しく、方言、宗教、古代の戦争、部族の恨みなどが互いにぶつかり合い、機材や物資の調達、南京虫の湧く村の宿など、苦労の多い、ほとんどが山岳地帯の奥 地で、彼らは奮闘した。彼らはアメリカから輸送したフォードのエンジンで充電したバッテリーで録音機を動かした。ネイティブの通訳ニコラとともに、彼らは 定期的にユーゴスラビア王国のクロアチアの片隅にあるドブロヴニクに戻り、そこでパリーの妻、娘、息子が待っていた。そして、港と海が見渡せる丘の中腹に あるパリーの家は、ほとんど軍隊のような本部となり、タイプライターをガチャガチャと鳴らしながら、古い歌の歌詞を書き写す作業に取りかかった。 結局、パリーは半トンもの12インチのアルミ盤を集めることになった。これは昔のレコード盤の大きさだが、白い金属製のレコード盤で、若い国の、そして古 い世界の文化的伝統が詰まっていた。しかし、パリーが興味を持ったのは、ボスニア、ヘルツェゴビナ、セルビア、モンテネグロなどバルカン半島の国々につい てではなく、ホメロスの『イリアス』や『オデュッセイア』を生み出した古代ギリシャの古い世界についてであった。そしてついに、モンテネグロ北部の山岳地 帯にある標高1,900フィートの町で、アヴド・メジェドヴィッチという老人が、何日もかけて語る結婚式と戦争の物語を歌い、パリーは彼の中に自分たち自 身の生きたホメロスを見つけたと確信した。 1935年9月、パリー夫妻と若きアルバート・ロードはアメリカに戻った。 11月16日、ギリシャ語の助教授としてハーバード大学に戻っていたパリーと、卒業したばかりのロードは、妻がちょうどロサンゼルスにいると妹に手紙を書 いた。そして、経済的に困窮している義母の住所を伝えた。 11月17日、パリーはハーバード大学でユーゴスラビアの民謡について講演することになっていた。 18日、彼は学生と会い、進捗状況を報告した。 その1日か2日後、彼は西海岸に向けて出発した。 12月3日、ロサンゼルスのホテルの一室で、妻と一緒にいたパリーの胸に拳銃の弾丸が命中した。彼はその日のうちに死んだ。彼は33歳だった。 パリー夫人の通報を受けたホテルの従業員は、パリー夫人が夫を殺したと考えた。しかし、警察はそうではなく、事故であると結論づけた。検死は行われなかっ た。告訴もされなかった。パリーの自殺を疑う者もいた。後に、パリーの実の子供たちの間では、母親がパリーを殺したという可能性が現実味を帯びてきた: 母親がパリーを殺したというのは、現実的な可能性として考えられていた。あるいは、現実の、あるいは想像上の不貞行為や、長年にわたって母に与えてきた傷 に対する冷静な復讐だったのかもしれない。パリー夫人とその娘は、一生の間に互いに敵対しあってねじれ、二人ともマリアンという名前だった。若い方のマリ アンは、母親が父親を殺したと確信し、生涯その考えを持ち続けた。 1935年12月5日、パリーの遺体はロサンゼルスで火葬された。その2週間後、ハーバード大学に戻り、アップルトン・チャペルで追悼式が行われた。弔辞 の中で、パリーはユーゴスラビアから帰国し、「この分野の将来の研究者が無視することのできない膨大な資料を携えて帰国した。彼の仕事は、彼の後も長く続 くだろう」。 1936年初め、パリー夫人は夫の著書、録音、論文のほとんどをハーバード大学に寄贈し、驚くべき効率で子供たちを連れてケンブリッジを離れ、大陸を横断 してカリフォルニア州バークレーに移り住み、大学に復学して、妊娠、ミルマンとの結婚、フランスとケンブリッジでの夫との生活が中断していた学士号を1年 あまりで取得した。 一方、パリーの若い助手アルバート・ロードはユーゴスラビアの資料を預かることになった。彼が「師であり友人」と呼ぶことになる人物と15ヵ月間一緒に仕 事をした後、彼は今、ほとんど一人でユーゴスラビアの資料を作る責任を負っていた。パリー自身にはそのチャンスはなかった。ユーゴスラビアに戻り、帰国す る前の冬、彼は数ページのメモとアイデアを口述筆記した。そして、彼が書きたいと思っていた本のタイトル、『物語の歌い手』を手に入れた。ロードは23歳 で、この仕事に取り組むにはまだ力不足だった。 1934年6月にハーバード大学を卒業しようとしていたロードは、「自分が何をすべきなのか、少しも考えていなかった」と、後年のロードの学生であり尊敬 する後輩でもあったデイヴィッド・バイナムは報告している。ユーゴスラビアは、卒業直後、大恐慌の真っただ中、他の仕事の見込みがほとんどない時期という 絶好のタイミングで訪れた。ロードはパリーにタイピスト、雑用係、そして "録音技師 "として仕え、パリーをより本質的で知的な仕事に解放した。彼は「ユーゴスラビアでパリーが何をしていたのか、なぜそうなったのかについて、個人的な興味 だけでなく、尋ねる機会もなく、有意義なことを知る気もなかった」。白く輝くアルミの円盤は、何千枚という単位で、物流の怪物であり、知的な謎であった。 このどうしようもない状況を一変させたのは、これだった: ユーゴスラビアで過ごした時間が、パリーの作品を世に知らしめたという点で、彼の責任がどれほどであろうとなかろうと、ロードはそう感じていたようだ。そ してロードは、時が経つにつれて、それをより強く、深く、差し迫った、個人的な必要性として感じていた。彼は15ヵ月間パリーのそばで働いていたが、50 年以上にわたってパリーの考えを発展させ、豊かにする手助けをすることになる。「そうでないと思われる瞬間があったにもかかわらず、私の人生はパリーのコ レクションと、彼がまだ始めたばかりの仕事に捧げられてきた。 |
| Milman Parry was arguably the
most important American classical scholar of the twentieth century, by
one reckoning “the Darwin of Homeric Studies.” At age twenty-six, this
young man from California stepped into the world of Continental
philologists and overturned some of their most deeply cherished notions
of ancient literature. Homer, Parry showed, was no “writer” at all. The
Iliad and the Odyssey were not “written,” but had been composed orally,
drawing on traditional ways that went back centuries. Generations of high school and college students can recall descriptive flourishes of Odysseus, as “much-enduring,” or “the man of many schemes”; or of the goddess Athena as “bright-eyed”; or of “swift-footed Achilles.” Parry showed that these “ornamental epithets” were not odd little explosions of creativity. Nor, in their repetition, were they failures of the imagination. Nor were they random. They were the oral poet’s way to fill out lines of verse and thus keep the great river of words flowing. They were the product of long tradition, and many voices. Parry wrote of the fifth-century BCE Greek sculptor Phidias that his work was not his alone but shot through with “the spirit of a whole race”; much the same, he said, applied to the Homeric epics. Homer, of course, was no trifling asterisk of classical studies but stood at the very roots of Western civilization, his epic poems filled with stories of the warrior Achilles and the goddess Athena and the other gods and heroes enshrined on every ancient Greek potsherd, represented in paintings, sculpture, and literature for three thousand years, inspiring Shelley and Keats, Shakespeare and James Joyce. After Parry, just how Homer had come into the world and become embedded in the memory of humankind came to be seen in a new way. As Walter Ong summed up the case in his groundbreaking 1982 book, Orality and Literacy, The Iliad and the Odyssey have been commonly regarded from antiquity to the present as the most exemplary, the truest and the most inspired secular poems in the western heritage. To account for their received excellence, each age has been inclined to interpret them as doing better what it conceived its [own] poets to be doing or aiming at. That is, they tended to be seen like the poems of one’s own age, whatever it was, only better. But no, said Parry, Homer was different, and not just from the literature of our own time, or from Victorian literature, or from that of the Middle Ages, but even from almost all other ancient Greek literature. A rough, ill-formed thought might place the Odyssey and, say, Aeschylus’s three-part tragedy, the Oresteia, under the same broad heading—ancient “classics,” revered literary products of Greece, stalwarts of the Western literary tradition. But Parry showed they were different animals altogether, because Aeschylus wrote, as you and I write, while the Odyssey was something else entirely, percolating up from oral performance over the centuries, shaped by its own, maddeningly “unliterary” rules: The literary critic sees repetition, stereotype, and cliché as unwelcome or worse. But for on-the-fly oral composition they were virtually essential, characteristic of it, understood and expected by audience and performer alike. For Parry they were the clue to how the epic poems had been made. In time, Parry’s ideas came to constitute their own orthodoxy, with scholars questioning them as they would anything else, placing them under relentless scrutiny. And yet in all the years since—it is now nearly a century since Parry first asserted them—they have become one of the cornerstones on which Homeric studies stand. And extended into new realms, they have altered understanding of other early cultures as well—not just in the West but in Asia, Africa, and around the world; and not just in past centuries but our own. Parry’s ideas have forced us to rethink the role of books and print generally. The Yugoslav singers, like those of ancient Greece, could not read or write. Milman Parry helped us to imagine, understand, and respect another species of human creativity. “The effects of oral states of consciousness,” Walter Ong has written, “are bizarre to the literate mind.” * I come to Milman Parry from outside the world of classical studies. While for a dozen years in the early 2000s I held a faculty position at a university, MIT, most of my working life has been spent outside academia altogether, as an independent writer. In the early years, I wrote articles, essays, and reviews for magazines and newspapers. Then, beginning in the 1980s, books—about mentor relationships among elite scientists, about tourism in Nice, about an Indian mathematical genius. A servant to my enthusiasms, I never much restricted myself by subject. In 2007, the object of my fascination became a tiny island community off the far west coast of Ireland, known as the Great Blasket, inhabited by a few hundred Irish-speaking fishermen, visited by scholars, writers, and linguists from all over Europe. One of these scholars was an Englishman, George Thomson, who first arrived on the island in 1923 and took a lively interest in it for the rest of his life. Professionally, he was a classicist, a student of Greek lyric poetry, of Aeschylus, of Homer. For most of his life he was professor of Greek at the University of Birmingham. Through his books, correspondence, and personal story I found him a warming and inspiring figure. Such were his sensibilities, and such were mine, that I could not confine my interest to his place in the Irish story; I became intrigued by whatever intrigued him. Soon I was reading his translation of the Oresteia, from which I came away thrilled by the astonishing transformation wrought by Athena in the third play, where vengeance metamorphoses into something like justice. From Aeschylus, then, it was on to the Odyssey and the Iliad through the lustrous and lucid Robert Fagles translations; these were my first forays into Homer since junior high school. Ultimately, I was caught up in Thomson’s ideas about the Homeric Question, the fertile, endlessly fascinating, centuries-old debate about who Homer was, when and where he’d lived, and what it meant, if anything, to attribute to him the authorship of the ancient epics. And the Homeric Question, in turn, led me to Milman Parry. As one over-neat formulation of his achievement put it, Parry “never solved the Homeric Question; he demonstrated that it was irrelevant.” Jettisoning contradictions in Homer that to his mind weren’t contradictions at all, he opened the world of classical scholarship to new notions of literary creation. And he did so in a peculiarly single-minded way that made for its own, charmingly geekish story: In the decade after first asserting his ideas, Parry enriched his original insights with such deep analysis of the hexametric line in which the epics were written, such abundance of detail, such obsessive regard for closing off alternative explanations, that, in a scholarly world riven by fractious debate, few could doubt their truth, leaving others to pick at the periphery of his big idea. Classicists today refer to “before Parry” and “after Parry.” They speak not of Parry’s “theory,” or “argument,” but of his “discovery.” This isn’t quite true, but it is true enough, many of his demonstrations and proofs seemingly airtight. Over the years much attention has been paid to Parry’s ideas; less to the progression of his thought set against the times and places in which he lived, or the sensibilities and personal history of Parry himself. This book is a story of intellectual discovery rooted in a field, classical studies, often relegated in the popular imagination to the outlands of the irrelevant and the obscure. But success in any field, however recondite, is always a story of humans at work, in all their hope and glory, and in the face of all their foibles and excesses. Homer and ancient Greece stand near the center of this book; but nearer still is Mr. Parry himself. Our story plays out in the times and places in which he lived—across just a dozen years in the 1920s and 1930s, in California, in Paris, at Harvard, and on the Balkan peninsula, where Parry went to test his ideas on a living tradition. |
ミルマン・パリーは間違いなく20世紀で最も重要なアメリカ人古典学者
であり、「ホメロス研究のダーウィン」と呼ばれた。カリフォルニア出身のこの青年は、26歳にして大陸の言語学者たちの世界に足を踏み入れ、彼らが古代文
学に対して最も深く抱いていた概念を覆した。ホメロスは "作家
"ではなかったのだ。イリアス』や『オデュッセイア』は「書かれた」ものではなく、何世紀も前の伝統的な方法を用いて口頭で書かれたものだったのだ。 高校生や大学生の世代は、オデュッセウスを "不朽の男 "や "策略に長けた男 "と表現したり、女神アテナを "明るい目をした男 "と表現したり、"足の速いアキレス "と表現したりする。パリーは、これらの "装飾的な蔑称 "が、創造性の奇妙で小さな爆発ではなかったことを示した。また、その繰り返しは想像力の失敗でもない。無作為でもない。それらは口承詩人が詩の行を埋 め、言葉の大河の流れを維持するための方法であった。それらは長い伝統と多くの声の産物だった。パリーは紀元前5世紀のギリシアの彫刻家フィディアスにつ いて、彼の作品は彼一人のものではなく、「民族全体の精神」で貫かれていると書いている。 彼の叙事詩には、戦士アキレスや女神アテナをはじめ、古代ギリシアのあらゆる土器に祀られていた神々や英雄たちの物語が詰まっており、絵画や彫刻、そして 3000年にわたる文学の中で表現され、シェリーやキーツ、シェイクスピアやジェームズ・ジョイスにインスピレーションを与えてきた。パリー以降、ホメー ロスがどのようにしてこの世に生まれ、人類の記憶に刻まれるようになったのかが、新たな形でとらえられるようになった。 ウォルター・オングが1982年に発表した画期的な著書『オラリティとリテラシー』(原題:Orality and Literacy)の中で、このケースを要約している、 イリアス』と『オデュッセイア』は、古代から現在に至るまで、西洋の遺産の中で最も模範的で、最も真実的で、最も霊感に満ちた世俗詩であると一般にみなさ れてきた。その卓越性を説明するために、各時代は、自国の詩人たちがやっている、あるいは目指していると考えていることを、よりよくやっていると解釈する 傾向があった。 つまり、自分の時代の詩と同じように、それが何であれ、より優れているとみなす傾向があった。 私たちの時代の文学、ヴィクトリア朝の文学、中世の文学だけでなく、他のほとんどすべての古代ギリシア文学でさえも。大雑把で、形骸化した考えであれば、 『オデュッセイア』と、たとえばアイスキュロスの三部悲劇『オレステイア』を同じ大枠の下に置くかもしれない。エスキルスは、あなたや私が書くように書い たが、オデュッセイアはまったく別のものであり、何世紀にもわたって口承で上演され、気の遠くなるような「文学的でない」独自のルールによって形作られた ものだからである: 文芸批評家は、繰り返し、ステレオタイプ、決まり文句は歓迎されない、あるいはもっと悪いものだと考える。文芸批評家は、繰り返し、ステレオタイプ、決ま り文句を好ましくないものとしてとらえる。しかし、その場限りの口承文芸にとって、それらは事実上不可欠であり、その特徴であり、聴衆にも演奏者にも理解 され、期待されていた。パリーにとって、それらは叙事詩がどのように作られたかを知る手がかりであった。 やがて、パリーの考えは正統派を構成するようになり、学者たちは他のものと同じように疑問を呈し、執拗な監視下に置くようになった。しかし、パリーが最初 にこの考えを主張して以来100年近くが経ち、この考えはホメロス研究を支える礎石のひとつとなった。そして新たな領域へと拡張され、西洋だけでなくアジ ア、アフリカ、そして世界中の他の初期文化に対する理解にも変化をもたらした。パリーの考え方は、一般的に本や印刷物の役割を再考させるものだ。ユーゴス ラビアの歌い手たちは、古代ギリシャの歌い手たちと同様、読み書きができなかった。ミルマン・パリーは、人間の創造性の別の種を想像し、理解し、尊重する 手助けをしてくれた。 「ウォルター・オングは、「口承による意識状態の効果は、文字が読める人にとっては奇妙なものである」と書いている。 * 私は古典研究の外からミルマン・パリーを知った。2000年代初頭の十数年間、私はMITという大学で教鞭をとっていたが、私の社会人生活の大半は、アカ デミズムの外で独立したライターとして過ごしてきた。初期の頃は、雑誌や新聞に記事やエッセイ、評論を書いていた。そして1980年代からは、エリート科 学者たちの師弟関係、ニース観光、インドの天才数学者についての本も書いた。私は自分の情熱に奉仕する人間であり、テーマを限定することはあまりなかっ た。数百人のアイルランド語を話す漁師が住み、ヨーロッパ中から学者、作家、言語学者が訪れる。 そのうちの一人、イギリス人のジョージ・トムソンは、1923年に初めてこの島に到着し、生涯にわたってこの島に強い関心を抱いた。職業的には古典学者 で、ギリシャの抒情詩、アイスキュロス、ホメロスの研究者だった。生涯の大半をバーミンガム大学のギリシア語教授として過ごした。彼の著書、書簡、個人的 な話を通して、私は彼が温かく、刺激的な人物であることを知った。彼の感性がそうであったし、私の感性もそうであったから、私はアイルランドの物語におけ る彼の位置づけだけに興味をとどめることができなかった。やがて私は、彼の訳した『オレステイア』を読むようになり、第3幕でアテナが復讐を正義のような ものに変容させるという驚くべき変容に感動した。エスキューロスから、艶やかで明晰なロバート・ファグルス訳のオデュッセイアとイーリアスへと進んだ。最 終的に私は、ホメロスは誰なのか、いつ、どこに住んでいたのか、古代の叙事詩の作者をホメロスとすることに何か意味があるとすれば、それは何なのか、とい う豊饒で果てしなく魅力的な、何世紀も続く議論である「ホメロス問題」についてのトムソンの考えに巻き込まれた。そしてホメロス問題は、私をミルマン・パ リーに導いた。 パリーの功績を端的に表現すれば、「パリーはホメロス問題を解決したのではなく、ホメロス問題が無関係であることを証明した」のである。ホメロスにおける 矛盾を捨て去り、文学的創造に関する新たな概念へと古典研究の世界を切り開いたのである。そして彼は、独特の一途なやり方でそれを実現し、魅力的でオタク 的な物語を作り上げた: 自分の考えを最初に主張してからの10年間、パリーは、叙事詩が書かれたヘキサメトリック・ラインの深い分析、豊富なディテール、代替的な説明を排除する ことへの執着によって、その独創的な洞察に磨きをかけた。古典学者たちは今日、"パリー以前 "と "パリー以後 "と呼んでいる。彼らはパリーの "理論 "や "議論 "ではなく、彼の "発見 "について語る。これは正確ではないが、彼の実証や証明の多くは、一見、確固としたものである。 長年にわたり、パリーの思想に多くの関心が向けられてきたが、彼が生きた時代や場所、あるいはパリー自身の感性や個人的な歴史と照らし合わせた彼の思想の 進展にはあまり関心が向けられてこなかった。本書は、古典学という、一般的な想像力ではしばしば無関係で無名の外野に追いやられがちな分野に根ざした知的 発見の物語である。しかし、どのような分野であれ、成功とは常に、人間の希望と栄光、そして欠点と行き過ぎに直面した人間の営みの物語なのである。ホメロ スや古代ギリシャは本書の中心近くにあるが、パリー氏自身はもっと近くにいる。1920年代から30年代にかけて、カリフォルニア、パリ、ハーバード、バ ルカン半島など、パリー氏が生きた時代と場所で、私たちの物語は展開する。 |
| Oral-formulaic composition Oral-formulaic composition is a theory that originated in the scholarly study of epic poetry and developed in the second quarter of the twentieth century. It seeks to explain two related issues: the process by which oral poets improvise poetry the reasons for orally improvised poetry (or written poetry deriving from traditions of oral improvisation) having the characteristics that it does The key idea of the theory is that poets have a store of formulae (a formula being 'an expression that is regularly used, under the same metrical conditions, to express a particular essential idea')[1] and that by linking the formulae in conventionalised ways, poets can rapidly compose verse. Antoine Meillet expressed the idea in 1923, thus: Homeric epic is entirely composed of formulae handed down from poet to poet. An examination of any passage will quickly reveal that it is made up of lines and fragments of lines which are reproduced word for word in one or several other passages. Even those lines of which the parts happen not to recur in any other passage have the same formulaic character, and it is doubtless pure chance that they are not attested elsewhere.[2] In the hands of Meillet's student Milman Parry (1902-1935), and subsequently the latter's student Albert Lord (1912-1991), the approach transformed the study of ancient and medieval poetry and of oral poetry generally. The main exponent and developer of their approaches was John Miles Foley (1947-2012). https://en.wikipedia.org/wiki/Oral-formulaic_composition |
口
承定型文 口承定型文は、叙事詩の研究に端を発し、20世紀第2四半期に発展した 理論である。この理論は、二つの関連する問題を説明しようとするものである(→「君もラッパーにな れる!!」): 口承詩人が即興で詩を作るプロセス 口承即興詩(あるいは口承即興詩の伝統に由来する書かれた詩)が、そのような特徴を持つ理由。 この理論の重要な考え方は、詩人は定型(定型とは「特定の本質的なアイデアを表現するために、同じ計量的条件の下で定期的に使用される表現」のことであ る)[1]を蓄えており、定型を慣例化された方法で結びつけることによって、詩人は迅速に詩を詠むことができるというものである。アントワーヌ・メイエは 1923年にこの考えをこう表現している: ホメロス叙事詩はすべて、詩人から詩人へと受け継がれてきた定型で構成されている。ホメロス叙事詩はすべて、詩人から詩人へと受け継がれた定型によって構 成されている。他のどのパッセージにも繰り返し出てこない部分でさえ、同じ定型的な性格を持っており、それが他の箇所で証明されていないのは間違いなく偶 然である[2]。 Meilletの弟子であるMilman Parry (1902-1935)、そしてその後Meilletの弟子であるAlbert Lord (1912-1991)の手にかかると、このアプローチは古代と中世の詩の研究、そして一般的な口承詩の研究を一変させた。彼らのアプローチの主唱者であ り開発者であったのが、ジョン・マイルズ・フォーリー(1947-2012)である。 |
| Homeric verse In Homeric verse, a phrase like rhododaktylos eos ("rosy fingered dawn") or oinopa ponton ("winedark sea") occupies a certain metrical pattern that fits, in modular fashion, into the six-foot Greek hexameter, which aids the aoidos or bard in extemporaneous composition. (The Iliad and The Odyssey both use dactylic hexameter verse form, where every line contains six groups of syllables.) Moreover, such phrases would be subject to internal substitutions and adaptations, permitting flexibility in response to narrative and grammatical needs: podas okus Akhilleus ("swift footed Achilles") is metrically equivalent to koruthaiolos Ektor ("glancing-helmed Hector"). Formulas can also be combined into type-scenes, longer, conventionalised depictions of generic actions in epic like the steps taken to arm oneself or to prepare a ship for sea. https://en.wikipedia.org/wiki/Oral-formulaic_composition |
ホメロス詩 ホメロス詩では、rhododaktylos eos(「バラ色の指の夜明け」)やoinopa ponton(「ワイン色の海」)のようなフレーズは、アオイドスや吟遊詩人の即興的な作曲を助ける6フィートギリシャ語のヘキサメーテルに、モジュール 方式で適合する一定の計量パターンを占める。(イリアス』も『オデュッセイア』も、各行に6つの音節が含まれるダクティリック・ヘキサメーターを用いてい る)。さらに、このような句は、物語や文法的な必要性に柔軟に対応できるよう、内部的な置換や適応が可能である。例えば、podas okus Akhilleus(「足の速いアキレウス」)は、koruthaiolos Ektor(「まぶしいヘクトル」)と計量的に等価である。定型はまた、タイプ・シーンに組み入れることもできる。タイプ・シーンとは、叙事詩における一 般的な動作を、より長く、定型化した描写のことで、例えば、武装するための手順や、出航する船の準備をする手順などがこれにあたる。 |
https://www.youtube.com/watch?v=UdyXlUmD3v4 Homer, Odyssey rhapsody 01 (audiobook spoken in reconstructed Ancient Greek) |
|
| Work of Parry and successors Oral-formulaic theory was originally developed, principally by Parry in the 1920s, to explain how the Homeric epics could have been passed down through many generations purely through word of mouth and why its formulas appeared as they did. His work was influential in the field of Homeric scholarship and changed the discourse on the oral theory and the Homeric Question. The locus classicus for oral-formulaic poetry, however, was established by the work of Parry and his student Lord, not on oral recitation of Homer (which no longer was practiced), but on the (similar) Serbian oral epic poetry of what was then of Yugoslavia, where oral-formulaic composition could be observed and recorded ethnographically.[3] Formulaic variation is apparent, for example, in the following lines: a besjedi od Orasca Tale ("But spoke of Orashatz Tale") a besjedi Mujagin Halile ("But spoke Mujo's Halil"). Lord, and more prominently Francis Peabody Magoun, also applied the theory to Old English poetry (principally Beowulf) in which formulaic variation such as the following is prominent: Hrothgar mathelode helm Scildinga ("Hrothgar spoke, protector of the Scildings") Beowulf mathelode bearn Ecgtheowes ("Beowulf spoke, son of Ecgtheow") Magoun thought that formulaic poetry was necessarily oral in origin. That sparked a major and ongoing debate over the extent to which Old English poetry, which survives only in written form, should be seen as, in some sense, oral poetry. The oral-formulaic theory of composition has now been applied to a wide variety of languages and works. A provocative new application of oral-formulaic theory is its use in attempting to explain the origin of at least some parts of the Quran.[4] Oral-Formulaic theory has also been applied to early Japanese works.[5] The oral-formulaic theory has also been applied to the Olonko epic of the Sakha people of Siberia.[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Oral-formulaic_composition |
パリーと後継者たちの研究 口承形式論は、ホメロス叙事詩が純粋に口承によって何世代にもわたって受け継がれ、なぜそのような形式が現れたのかを説明するために、主に1920年代に パリーによって提唱された。彼の研究はホメロス研究の分野に大きな影響を与え、口承説とホメロス問題についての言説を一変させた。しかし、口承定型詩の古 典的位置づけは、パリーとその弟子ロードの研究によって確立された。それはホメロスの口承朗読(もはや行われていなかった)ではなく、口承定型詩の構成が 民俗学的に観察され記録されていた、当時ユーゴスラビアにあったセルビアの(類似した)口承叙事詩に関するものであった[3]: a besjedi od Orasca Tale(「しかし、オラシャッツの話をした。) a besjedi Mujagin Halile ("But spoke Mujo's Halil"). ロード、そしてより顕著なフランシス・ピーボディ・マグーンもまた、次のような定型変化が顕著な古英語詩(主にベオウルフ)にこの理論を適用した: Hrothgar mathelode helm Scildinga(「Hrothgarは語った、Scildingsの保護者」)。 Beowulf mathelode bearn Ecgtheowes(「ベオウルフは語った、Ecgtheowの息子である) マグーンは、定型詩は必然的に口承に由来すると考えた。このことは、書き言葉の形でしか残っていない古英語の詩を、ある意味で口承詩とみなすべきかどうか をめぐる大きな、そして現在も続いている論争に火をつけた。 口承形式による作文理論は、現在ではさまざまな言語や作品に適用されている。口承形式説の新たな応用として、コーランの少なくとも一部の起源を説明しよう とする試みがある[4]。 口承形式説はまた、日本の初期の作品にも適用されている[5]。 口承形式説はまた、シベリアのサハ民族のオロンコ叙事詩にも適用されている[6]。 |
| Precursors of Parry Before Parry, at least two other folklorists also noted the use of formulas among the epic tale singers of Yugoslavian (known as guslars),[7] (something acknowledged by Parry):[8][9] Friedrich Salomon Krauss (1859-1938), a specialist in Yugoslavian folklore, who had done fieldwork with guslars, believed these storytellers depended on "the fixed formulas from which he neither can nor wishes to vary".[10] Arnold van Gennep (1873-1957), who suggested that "the poems of the guslars consist of a juxtaposition of cliches relatively few in number and with which it suffices merely to be conversant … A fine guslar is one who handles these cliches as we play with cards, who orders them differently according to the use he wishes to make of them".[11][12] https://en.wikipedia.org/wiki/Oral-formulaic_composition |
パリーの前身 パリー以前にも、少なくとも二人の民俗学者がユーゴスラヴィア(グスラーとして知られる)の叙事詩を歌う人々の間で定型文が用いられていることに注目して いた[7]。 ユーゴスラビアの民俗学の専門家であり、グスラールのフィールドワークを行ったフリードリッヒ・サロモン・クラウス(1859-1938)は、これらの語 り手は「固定された定型に依存しており、そこから変化することはできないし、変化することも望まない」と考えていた[10]。 アーノルド・ヴァン・ジェネップ(1873-1957)は、「グスラーの詩は比較的数の少ない決まり文句の並置から成り、単にそれに精通しているだけで十 分である......優れたグスラーとは、トランプで遊ぶようにこれらの決まり文句を扱い、それらを使いたい用途に応じて異なる順序に並べる人である」と 示唆した[11][12]。 |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099