正戦論
Just War Theory
Gerard Seghers (attr) - The Four
Doctors of the Western Church, Saint Augustine of Hippo (354–430)
正戦論
Just War Theory
Gerard Seghers (attr) - The Four
Doctors of the Western Church, Saint Augustine of Hippo (354–430)
正戦論(Just War Theory)、つまり、戦争の前の準備状態あるいは、実際に戦争を遂行する際の倫理原則 は主に「戦争のための法(Jus ad Bellum)」と「戦争における法(Jus in Bello)」というもののなかにまとめられている(バジーニ 2015:219-221)。
正義の戦争理論(正戦論)は、どのように、そしてな
ぜ戦争が行われるの
かを正当化することを扱っている。正当化には、理論的なものと歴史的なものがある。理論的側面は、戦争を倫理的に正当化すること、および、戦争が取るべき
形態と取るべきでない形態に関わるものである。歴史的側面、すなわち「正しい戦争の伝統」は、時代を超えてさまざまな戦争に適用されてきた規則や協定の歴
史的体系を扱うものである。例えば、ジュネーブ条約やハーグ条約のような国際協定は、ある種の戦争を制限することを目的とした歴史的ルールであり、弁護士
が違反者を訴追する際に参照することができる。しかし、こうした制度的協定の哲学的一貫性を検証するとともに、協定の側面を変更すべきかどうかを検討する
のは倫理の役割である。正義の戦争の伝統は、時代を超えて様々な哲学者や法律家の考えを検討し、戦争の倫理的限界(または不在)についての彼らの哲学的ビ
ジョンと、彼らの考えが戦争と戦争を導くために発展してきた一連の慣習に貢献したかどうかの両方を検証することも可能である。
| 戦争のための法
(Jus ad Bellum) |
戦争に
おける法(Jus in Bello) |
| ・大義があること ・正しい意図をもつ ・正当な権利をもつ ・成功の可能性をもつ ・最後の手段(ultima ratio)であること ・軍事力に釣り合いがとれている |
・非戦闘員を尊重し
危害を加えない ・捕虜の権利をみとめ、虐待しないこと ・必要最小の武力行使であること |
| 出典:両サイドとも に(バジーニ 2015:221)より | 出典:両サイドとも に(バジーニ 2015:221)より |
◎宗教と正戦論
「正
戦論はアウグスティヌスが一定の戦争の正当化をキリスト教神学で基礎づけたことに始まる。トマス・アクイナスは同じくキリスト教的立場
から正戦の体系化を進めた。神学的正戦論ではキリスト教的正義を守る側の行為だけが正当化された。要するに正当なキリスト教だけが正義で、それ以外はすべ
て悪だとするものだった。これは後の十字軍や非ヨーロッパ地域への侵略と植民地支配の理論的根拠ともなった。グロティウスは『戦争と平和の法』などを著
し、戦争自体の正当性(ユス・アド・ベルム)だけではなく戦争中の行為の正当性(ユス・イン・ベロ)について論じた。正当性に関するこの二段構えの議論
が、後に形成されていく戦時国際法の構造の土台をなすことになる。一八世紀以降、植民地でのヨーロッパ諸国間の争いが始まるに至って、当事国を平等なもの
とみなす無差別戦争観が主張されるようになった。これは正戦か否かを区別せずに、戦争を主権国家の正当な権利として認めるというものであり、正戦論は衰退
していった。二O世紀に入ってからは、二度の世界大戦があまりに甚大な被害をもたらしたため、無差別戦争観は戦争違法観に取ってかわられ、ジュネーヴ議定
書や国際連合憲章などでは戦争を含む武力行使が国際法に違反すると明言された。だが、国違憲章には軍事的制裁や自衛権について定めた部分があり、これは一
定の条件下での武力行使を正当化すると解釈することも可能なために、正 戦論の復活だと考える意見もある」(訳者、脚注)(モレノ 2008:314-315)。
☆正戦論
| The just war
theory
(Latin: bellum iustum)[1][2] is a doctrine, also referred to as a
tradition, of military ethics that aims to ensure that a war is morally
justifiable through a series of criteria, all of which must be met for
a war to be considered just. It has been studied by military leaders,
theologians, ethicists and policymakers. The criteria are split into
two groups: jus ad bellum ("right to go to war") and jus in bello
("right conduct in war").[3] There have been calls for the inclusion of
a third category of just war theory (jus post bellum) dealing with the
morality of post-war settlement and reconstruction. The just war theory
postulates the belief that war, while it is terrible but less so with
the right conduct, is not always the worst option. The just war theory
presents a justifiable means of war with justice being an objective of
armed conflict.[4] Important responsibilities, undesirable outcomes, or
preventable atrocities may justify war.[3] Opponents of the just war theory may either be inclined to a stricter pacifist standard (proposing that there has never been nor can there ever be a justifiable basis for war) or they may be inclined toward a more permissive nationalist standard (proposing that a war need only to serve a nation's interests to be justifiable). In many cases, philosophers state that individuals do not need to be plagued by a guilty conscience if they are required to fight. A few philosophers ennoble the virtues of the soldier while they also declare their apprehensions for war itself.[5] A few, such as Rousseau, argue for insurrection against oppressive rule. The historical aspect, or the "just war tradition", deals with the historical body of rules or agreements that have applied in various wars across the ages. The just war tradition also considers the writings of various philosophers and lawyers through history, and examines both their philosophical visions of war's ethical limits and whether their thoughts have contributed to the body of conventions that have evolved to guide war and warfare.[6] In the twenty-first century there has been significant debate between traditional just war theorists, who largely support the existing law of war and develop arguments to support it, and revisionists who reject many traditional assumptions, although not necessarily advocating a change in the law.[7][8] |
正義の戦争論(ラテン語:bellum iustum)[1][2]
は、戦争が道徳的に正当化されるための基準を定めた軍事倫理の教義であり、伝統とも呼ばれる。これらの基準をすべて満たす場合のみ、戦争は正義とみなされ
る。この理論は、軍事指導者、神学者、倫理学者、政策立案者によって研究されてきた。基準は、jus ad
bellum(「戦争を行う権利」)とjus in
bello(「戦争における適切な行動」)の2つのグループに分けられる[3]。戦争後の和平と再建の道徳性を扱う第三のカテゴリー(jus post
bellum)を正当戦争論に含めるべきだという主張もある。正義の戦争理論は、戦争は恐ろしいものだが、適切な行動を伴えばその恐ろしさは軽減され、必
ずしも最悪の選択肢ではないという信念を前提としている。正義の戦争理論は、正義を武力衝突の目的とする戦争の正当な手段を提示している。[4]
重要な責任、望ましくない結果、または防止可能な残虐行為は、戦争を正当化する可能性がある。[3] 正義の戦争理論の反対者は、より厳格な平和主義の基準(戦争を正当化できる根拠はこれまでにも、そして今後も決して存在しない、と主張する)に傾倒する か、あるいはより寛容なナショナリストの基準(戦争は国民の利益に資する限り、正当化できる、と主張する)に傾倒するかのいずれかだ。多くの場合、哲学者 たちは、戦闘を命じられた個人が罪悪感に悩まされる必要はないと述べる。一部の哲学者たちは、兵士の美徳を称賛しつつも、戦争そのものに対する懸念を表明 している。[5] ルーソーのような少数派は、抑圧的な支配に対する反乱を主張している。 歴史的側面、または「正義の戦争の伝統」は、時代を超えて様々な戦争に適用されてきた規則や合意の歴史的体系を扱う。正義の戦争の伝統は、歴史上の様々な 哲学者や法学者の著作も検討し、彼らの戦争の倫理的限界に関する哲学的ビジョンと、その思想が戦争と戦争の指導原則として発展した慣習体系の形成に貢献し たかどうかを検証する。[6] 21世紀には、既存の戦争法を主に支持し、それを支持する議論を展開する伝統的な正義戦争理論家と、多くの伝統的な前提を拒否するものの、必ずしも法の変 更を主張するわけではない修正主義者との間で、重要な議論が繰り広げられている。[7][8] |
| Origins Ancient Egypt A 2017 study found that the just war tradition can be traced as far back as to Ancient Egypt.[9] Egyptian ethics of war usually centered on three main ideas, these including the cosmological role of Egypt, the pharaoh as a divine office and executor of the will of the gods, and the superiority of the Egyptian state and population over all other states and peoples. Egyptian political theology held that the pharaoh had the exclusive legitimacy in justly initiating a war, usually claimed to carry out the will of the gods. Senusret I, in the Twelfth Dynasty, claimed, "I was nursed to be a conqueror...his [Atum's] son and his protector, he gave me to conquer what he conquered." Later pharaohs also considered their sonship of the god Amun-Re as granting them absolute ability to declare war on the deity's behalf. Pharaohs often visited temples prior to initiating campaigns, where the pharaoh was believed to receive their commands of war from the deities. For example, Kamose claimed that "I went north because I was strong (enough) to attack the Asiatics through the command of Amon, the just of counsels." A stele erected by Thutmose III at the Temple of Amun at Karnak "provides an unequivocal statement of the pharaoh's divine mandate to wage war on his enemies." As the period of the New Kingdom progressed and Egypt heightened its territorial ambition, so did the invocation of just war aid the justification of these efforts. The universal principle of Maat, signifying order and justice, was central to the Egyptian notion of just war and its ability to guarantee Egypt virtually no limits on what it could take, do, or use to guarantee the ambitions of the state.[9] |
起源 古代エジプト 2017年の研究によると、正義の戦争の伝統は古代エジプトにまでさかのぼることができることが明らかになっている[9]。エジプトの戦争倫理は、通常、 3つの主要な考え方に中心していた。それらは、エジプトの宇宙論的役割、ファラオの神聖な職位と神々の意志の執行者としての役割、そして他のすべての国家 や人民に対するエジプト国家と国民の上位性である。エジプトの政治神学では、ファラオが正義の戦争を正当に開始する唯一の正当性を有するとされ、通常は神 の意志を実行するものと主張された。第12王朝のセヌセリト1世は、「私は征服者として育てられた…アトゥムの息子であり守護者である彼は、彼が征服した ものを征服するために私を与えた」と主張した。後のファラオたちも、神アメン・レの息子であることが、神の名において戦争を宣言する絶対的な権限を付与す るものと考えていた。ファラオは戦争を開始する前に神殿を訪問し、そこで神々から戦争の命令を受けると信じられていた。例えば、カモセは「私はアモン、正 義の助言者の命令により、アジア人を攻撃するに十分な力があったため、北へ進軍した」と主張した。トゥトメス3世がカルナックのアメン神殿に建立した石碑 は、「ファラオが敵に対して戦争を仕掛ける神聖な使命を明確に表明した」とされている。新王国時代が進むにつれ、エジプトの領土拡大の野心が強まるにつ れ、正義の戦争の呼びかけはこれらの努力の正当化を助けるようになった。秩序と正義を意味する普遍的な原則「マアト」は、エジプトの正義の戦争の概念の中 心であり、国家の野心を保証するために、エジプトが奪うこと、行うこと、使用することにほぼ制限を課さない能力を保証していた。[9] |
| India The Indian Hindu epic, the Mahabharata, offers the first written discussions of a "just war" (dharma-yuddha or "righteous war"). In it, one of five ruling brothers (Pandavas) asks if the suffering caused by war can ever be justified. A long discussion then ensues between the siblings, establishing criteria like proportionality (chariots cannot attack cavalry, only other chariots; no attacking people in distress), just means (no poisoned or barbed arrows), just cause (no attacking out of rage), and fair treatment of captives and the wounded.[10] In Sikhism, the term dharamyudh describes a war that is fought for just, righteous or religious reasons, especially in defence of one's own beliefs. Though some core tenets in the Sikh religion are understood to emphasise peace and nonviolence, especially before the 1606 execution of Guru Arjan by Mughal Emperor Jahangir,[11] military force may be justified if all peaceful means to settle a conflict have been exhausted, thus resulting in a dharamyudh.[12] |
インド インドのヒンドゥー教の叙事詩『マハーバーラタ』は、「正義の戦争」(ダルマ・ユッダまたは「正義の戦争」)に関する最初の書面による議論を提示して いる。その中で、5人の統治者兄弟(パンダヴァ)の一人が、戦争によって引き起こされる苦悩が正当化されることがあるかどうかを問う。その後、兄弟たち之 间で長い議論が交わされ、比例性(戦車は騎兵を攻撃できず、他の戦車のみを攻撃できる;苦境にある人々を攻撃してはならない)、正当な手段(毒矢や鋲付き の矢を使用してはならない)、正当な理由(怒りから攻撃してはならない)、捕虜や負傷者への公正な待遇といった基準が確立される。[10] シク教では、ダルマユダという用語は、特に自分の信念を守るために、正義、正義、または宗教的な理由のために行われる戦争を表す。シク教の核心的な教義の 一部は、特に1606年にムガル帝国のジャハーンギール皇帝によってグル・アルジャンが処刑されるまで、平和と非暴力に重点を置いていると理解されている が、[11] 紛争を解決するための平和的な手段がすべて尽きた場合、軍事力の行使が正当化され、その結果としてダルマユッドが発生する可能性がある。[12] |
| East Asian Chinese philosophy produced a massive body of work on warfare, much of it during the Zhou dynasty, especially the Warring States era. War was justified only as a last resort and only by the rightful sovereign; however, questioning the decision of the emperor concerning the necessity of a military action was not permissible. The success of a military campaign was sufficient proof that the campaign had been righteous.[13] Japan did not develop its own doctrine of just war but between the 5th and the 7th centuries drew heavily from Chinese philosophy, and especially Confucian views. As part of the Japanese campaign to take the northeastern island Honshu, Japanese military action was portrayed as an effort to "pacify" the Emishi people, who were likened to "bandits" and "wild-hearted wolf cubs" and accused of invading Japan's frontier lands.[14] |
東アジア 中国の哲学は、戦争に関する膨大な著作を生み出しました。その多くは周王朝時代、特に戦国時代に執筆されました。戦争は、最後の手段として、そして正当な 君主によってのみ正当化されました。しかし、軍事行動の必要性に関する皇帝の決定に疑問を呈することは許されませんでした。軍事作戦の成功は、その作戦が 正当であったことを示す十分な証拠とされました。[13] 日本は独自の正義の戦争の教義を発展させなかったが、5 世紀から 7 世紀にかけて、中国の哲学、特に儒教の考え方に大きく影響を受けた。日本が東北地方の本州を征服する軍事行動の一環として、日本の軍事行動は「エミシの人 民」を「盗賊」や「野生の狼の仔」に例え、日本の辺境地域を侵略したとして非難し、「平定」する努力として描かれた。[14] |
| Ancient Greece and Rome The notion of just war in Europe originates and is developed first in ancient Greece and then in the Roman Empire.[15][16][17] It was Aristotle who first introduced the concept and terminology to the Hellenic world that called war a last resort requiring conduct that would allow the restoration of peace. Aristotle argues that the cultivation of a military is necessary and good for the purpose of self-defense, not for conquering: "The proper object of practising military training is not in order that men may enslave those who do not deserve slavery, but in order that first they may themselves avoid becoming enslaved to others" (Politics, Book 7).[18] Stoic philosopher Panaetius considered war inhuman, but he contemplated just war when it was impossible to bring peace and justice by peaceful means. Just war could be waged solely for retribution or defense, in both cases having to be declared officially. He also established the importance of treating the defeated in a civilized way, especially those who surrendered, even after a prolonged conflict.[19] In ancient Rome, a "just cause" for war might include the necessity of repelling an invasion, or retaliation for pillaging or a breach of treaty.[20] War was always potentially nefas ("wrong, forbidden"), and risked religious pollution and divine disfavor.[21] A "just war" (bellum iustum) thus required a ritualized declaration by the fetial priests.[22] More broadly, conventions of war and treaty-making were part of the ius gentium, the "law of nations", the customary moral obligations regarded as innate and universal to human beings.[23] |
古代ギリシャとローマ ヨーロッパにおける「正義の戦争」の概念は、古代ギリシャで生まれ、その後ローマ帝国で発展した。[15][16][17] 戦争を平和の回復を可能にする行動を必要とする最後の手段とする概念と用語を、ギリシャ世界に初めて導入したのはアリストテレスだった。アリストテレス は、軍事力の育成は征服のためではなく、自己防衛のために必要で良いものだと主張している:「軍事訓練を行う適切な目的は、奴隷に値しない者を奴隷にする ためではなく、まず自分たちが他者に奴隷にされないためである」(『政治学』第7巻)。[18] ストア派の哲学者パナエティウスは、戦争を非人間的であると見なしましたが、平和的な手段で平和と正義をもたらすことが不可能な場合には、正義の戦争を容 認しました。正義の戦争は、報復または防衛のためだけに遂行することができ、いずれの場合も公式に宣言されなければなりません。また、彼は、特に降伏した 者については、長引く紛争の後でも、文明的な方法で扱うことの重要性を確立しました。[19] 古代ローマでは、戦争の「正当な理由」には、侵略を撃退する必要性、略奪や条約違反への報復などが含まれていた。[20] 戦争は常に潜在的に「ネファス」(「間違った、禁じられた」)であり、宗教的な汚染や神の怒りを招くリスクがあった。[21] 「正義の戦争」(bellum iustum)には、フェティア神官による儀礼的な宣言が必要だった。[22] より広くは、戦争の慣習や条約締結は、ius gentium(国際法)の一部であり、人間に先天的に普遍的な道徳的義務とみなされていた。[23] |
| Christian views Christian theory of the Just War begins around the time of Augustine of Hippo (Saint Augustine).[24] The Just War theory, with some amendments, is still used by Christians today as a guide to whether or not a war can be justified. Christians may argue "Sometimes war may be necessary and right, even though it may not be good." In the case of a country that has been invaded by an occupying force, war may be the only way to restore justice. [25] Saint Augustine Saint Augustine held that individuals should not resort immediately to violence, but God has given the sword to government for a good reason (based upon Romans 13:4). In Contra Faustum Manichaeum book 22 sections 69–76, Augustine argues that Christians, as part of a government, need not be ashamed of protecting peace and punishing wickedness when they are forced to do so by a government. Augustine asserted that was a personal and philosophical stance: "What is here required is not a bodily action, but an inward disposition. The sacred seat of virtue is the heart."[26] Nonetheless, he asserted, peacefulness in the face of a grave wrong that could be stopped by only violence would be a sin. Defense of oneself or others could be a necessity, especially when it is authorized by a legitimate authority: They who have waged war in obedience to the divine command, or in conformity with His laws, have represented in their persons the public justice or the wisdom of government, and in this capacity have put to death wicked men; such persons have by no means violated the commandment, "Thou shalt not kill."[27] While not breaking down the conditions necessary for war to be just, Augustine nonetheless originated the very phrase itself in his work The City of God: But, say they, the wise man will wage Just Wars. As if he would not all the rather lament the necessity of just wars, if he remembers that he is a man; for if they were not just he would not wage them, and would therefore be delivered from all wars.[27] Augustine further taught: No war is undertaken by a good state except on behalf of good faith or for safety.[28] J. Mark Mattox writes, In terms of the traditional notion of jus ad bellum (justice of war, that is, the circumstances in which wars can be justly fought), war is a coping mechanism for righteous sovereigns who would ensure that their violent international encounters are minimal, a reflection of the Divine Will to the greatest extent possible, and always justified. In terms of the traditional notion of jus in bello (justice in war, or the moral considerations which ought to constrain the use of violence in war), war is a coping mechanism for righteous combatants who, by divine edict, have no choice but to subject themselves to their political masters and seek to ensure that they execute their war-fighting duty as justly as possible.[29] |
キリスト教の立場 キリスト教の「正義の戦争」の理論は、ヒッポのアウグスティヌス(聖アウグスティヌス)の時代に始まったとされている。[24] いくつかの修正は加えられたものの、この「正義の戦争」の理論は、今日でもキリスト教徒が戦争を正当化できるかどうかを判断するための指針として用いられ ている。キリスト教徒は、「戦争は、たとえ良いことではないとしても、時には必要かつ正しい場合もある」と主張する。占領軍に侵略された国の場合、戦争は 正義を回復するための唯一の手段であるかもしれない。[25] 聖アウグスティヌス 聖アウグスティヌスは、個人はすぐに暴力に訴えるべきではないと主張したが、神は正当な理由(ローマ人への手紙 13:4 に基づく)から、政府に剣を与えたと述べた。『マニ教徒ファウストへの反論』第22章69~76節で、アウグスティヌスは、キリスト教徒は政府の一員とし て、政府によって強制された場合、平和を保護し悪を罰することに恥じる必要はないと主張した。アウグスティヌスは、これは人格で哲学的な立場であると主張 した:「ここでの要求は、身体的な行動ではなく、内面の態度である。徳の聖なる座は心にある。」[26] しかし、彼は、暴力によってのみ阻止できる重大な不正に対して平和を保つことは罪であると主張した。自己や他者を守ることは、特に正当な権威によって承認 されている場合、必要となることがある: 神の命令に従って、または神の法に従って戦争を行った者は、その人格において公共の正義または政府の知恵を体現し、その立場において悪人を処刑した。その ような者は、「殺してはならない」という戒めを違反したわけではない。[27] アウグスティヌスは、戦争が正義であるための条件を崩すことなく、その表現自体を『神の国』で初めて用いた。 しかし、彼らは言う。「賢者は正義の戦争を戦うだろう」。まるで、彼が人間であることを思い出せば、正義の戦争の必要性をむしろ嘆くはずだとでもいうよう に。なぜなら、もしそれが正義でなければ、彼はそれを戦わないだろうから、したがってすべての戦争から解放されるだろう。[27] アウグスティヌスはさらに次のように教えた。 善良な国家は、誠実さや安全のため以外には戦争を行わない。[28] J. マーク・マトックスは次のように書いている。 伝統的な「jus ad bellum」(戦争の正義、すなわち戦争が正当に遂行される状況)の概念によれば、戦争は、暴力的な国際紛争を最小限に抑え、可能な限り神の意志を反映 し、常に正当化されるよう努める正義の君主のための対処メカニズムである。伝統的な「jus in bello」(戦争の正義、すなわち戦争における暴力の使用を制約すべき道徳的考慮事項)の概念において、戦争は、神の命令により、政治的支配者に服従す るほかなく、戦争遂行の義務を可能な限り正義に基づいて実行するよう努める正義の戦闘者にとっての対応メカニズムである。[29] |
| Isidore of Seville Isidore of Seville writes: Those wars are unjust which are undertaken without cause. For aside from vengeance or to fight off enemies no just war can be waged. [30] Peace and Truce of God Main article: Peace and Truce of God The medieval Peace of God (Latin: pax dei) was a 10th century mass movement in Western Europe instigated by the clergy that granted immunity from violence for non-combatants. Starting in the 11th Century, the Truce of God (Latin: treuga dei) involved Church rules that successfully limited when and where fighting could occur: Catholic forces (e.g. of warring barons) could not fight each other on Sundays, Thursdays, holidays, the entirety of Lent and Advent and other times, severely disrupting the conduct of wars. The 1179 Third Council of the Lateran adopted a version of it for the whole church. |
セビリアのイシドール セビリアのイシドールは次のように書いている。 理由のない戦争は不当である。復讐や敵と戦う場合を除き、正当な戦争は存在しない。[30] 神の平和と休戦 主な記事:神の平和と休戦 中世の「神の平和」(ラテン語:pax dei)は、10 世紀に西ヨーロッパで聖職者たちによって引き起こされた大衆運動で、非戦闘員に暴力からの免責を認めた。 11世紀から始まった神の休戦(ラテン語:treuga dei)は、戦闘の時期と場所を制限する教会の規則で、カトリック勢力(例えば、対立する貴族の軍隊)は日曜日、木曜日、祝日、四旬節と待降節の期間中、 およびその他の特定の時期に互いに戦闘を行うことが禁止され、戦争の進行に重大な支障をきたした。1179年の第3ラテラノ公会議では、この制度の教会全 体への適用が採択された。 |
| Saint Thomas Aquinas Further information: Thomas Aquinas § Just war 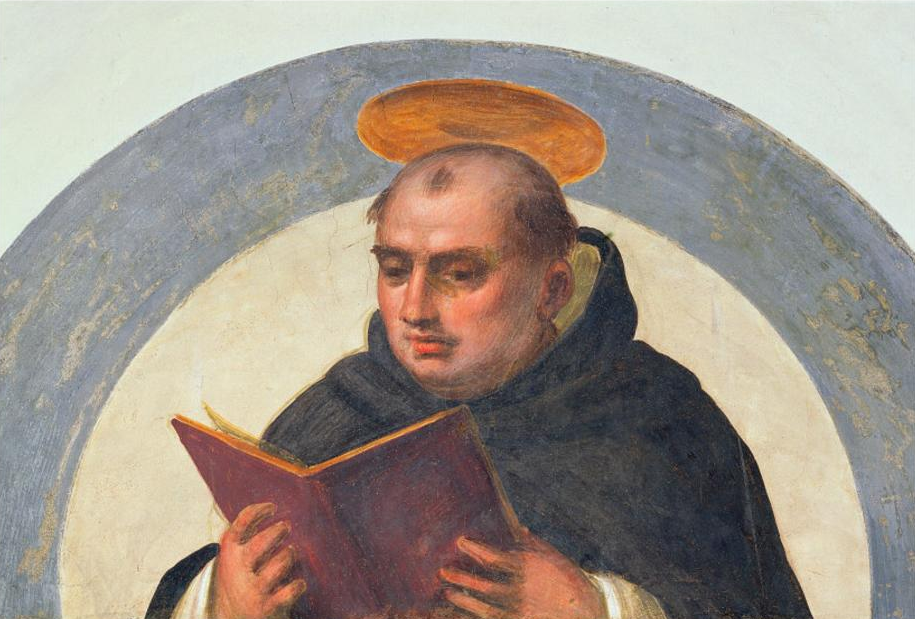 Saint Thomas Aquinas contributed to the development of the just war theory in medieval Europe. The just war theory by Thomas Aquinas has had a lasting impact on later generations of thinkers and was part of an emerging consensus in medieval Europe on just war.[31] In the 13th century Aquinas reflected in detail on peace and war. Aquinas was a Dominican friar and contemplated the teachings of the Bible on peace and war in combination with ideas from Aristotle, Plato, Socrates, Saint Augustine and other philosophers whose writings are part of the Western canon. Aquinas' views on war drew heavily on the Decretum Gratiani, a book the Italian monk Gratian had compiled with passages from the Bible. After its publication in the 12th century, the Decretum Gratiani had been republished with commentary from Pope Innocent IV and the Dominican friar Raymond of Penafort. Other significant influences on Aquinas just war theory were Alexander of Hales and Henry of Segusio.[32] In Summa Theologica Aquinas asserted that it is not always a sin to wage war, and he set out criteria for a just war. According to Aquinas, three requirements must be met. Firstly, the war must be waged upon the command of a rightful sovereign. Secondly, the war needs to be waged for just cause, on account of some wrong the attacked have committed. Thirdly, warriors must have the right intent, namely to promote good and to avoid evil.[33][34] Aquinas came to the conclusion that a just war could be offensive and that injustice should not be tolerated so as to avoid war. Nevertheless, Aquinas argued that violence must only be used as a last resort. On the battlefield, violence was only justified to the extent it was necessary. Soldiers needed to avoid cruelty and a just war was limited by the conduct of just combatants. Aquinas argued that it was only in the pursuit of justice, that the good intention of a moral act could justify negative consequences, including the killing of the innocent during a war.[35] |
聖トマス・アクィナス 詳細情報:トマス・アクィナス § 正当戦争 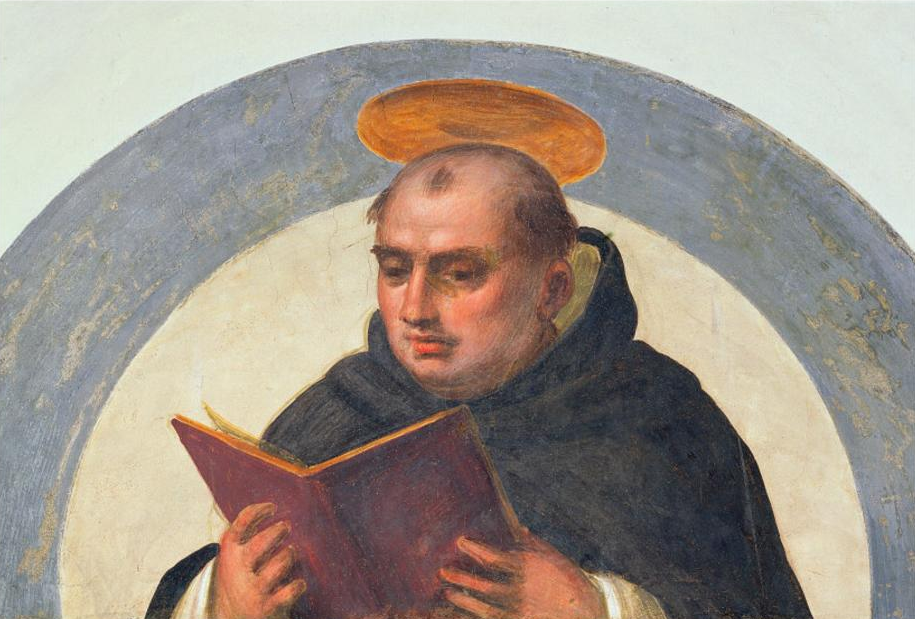 聖トマス・アクィナスは、中世ヨーロッパにおける正当戦争論の発展に貢献した。 トマス・アクィナスの正当戦争論は、後世の思想家に多大な影響を与え、中世ヨーロッパにおける正当戦争に関する新たなコンセンサスの一部となった。 [31] 13 世紀、アクィナスは平和と戦争について詳細に考察した。アクィナスはドミニコ会修道士であり、聖書の平和と戦争に関する教えを、アリストテレス、プラト ン、ソクラテス、聖アウグスティヌス、および西洋の古典文学の一部である著作を残したその他の哲学者の考えと組み合わせて考察した。アクィナスの戦争に関 する見解は、イタリアの修道士グラティアヌスが聖書の文章を編集した『グラティアヌス法典』に大きく影響を受けている。12 世紀に出版された後、『グラティアヌス法典』は、教皇イノセント 4 世とドミニコ会修道士レイモンド・デ・ペナフォルトによる解説付きで再出版された。アクィナスによる正戦論に重要な影響を与えた人物としては、アレクサン ダー・オブ・ヘイルズとヘンリー・オブ・セギウソも挙げられる。[32] 『神学大全』の中で、アクィナスは、戦争を行うことが必ずしも罪ではないと主張し、正義の戦争の基準を定めました。アクィナスによると、3つの要件が満た されなければなりません。第一に、戦争は、正当な主権者の命令に基づいて行われなければなりません。第二に、戦争は、攻撃を受けた側が犯した何らかの不正 行為を理由として、正当な理由に基づいて行われなければなりません。第三に、戦士は、善を促進し、悪を回避するという正しい意図を持っていなければならな い[33][34]。アクィナスは、正義の戦争は攻撃的であってもよく、戦争を回避するために不正を容認してはならないという結論に達した。それにもかか わらず、アクィナスは、暴力は最後の手段としてのみ使用すべきであると主張した。戦場では、暴力は必要な範囲でのみ正当化される。兵士は残虐行為を避け、 正義の戦争は正義の戦闘員の行動によって制限される。ア奎ナスは、正義の追求においてのみ、道徳的行為の善意が、戦争中の無辜の者の殺害を含む負の結果を 正当化できると主張した。[35] |
| Renaissance and Christian
Humanists Various Renaissance humanists promoted Pacificist views. John Colet famously preached a Lenten sermon before Henry VIII, who was preparing for a war, quoting Cicero "Better an unjust peace rather than the justest war."[36] Erasmus of Rotterdam wrote numerous works on peace which criticized Just War theory as a smokescreen and added extra limitations, notably The Complaint of Peace and the Treatise on War (Dulce bellum inexpertis). A leading humanist writer after the Reformation was legal theorist Hugo Grotius, whose De jura belli ac pacis re-considered Just War and fighting wars justly. First World War At the beginning of the First World War, a group of theologians in Germany published a manifesto that sought to justify the actions of the German government. At the British government's request, Randall Davidson, Archbishop of Canterbury, took the lead in collaborating with a large number of other religious leaders, including some with whom he had differed in the past, to write a rebuttal of the Germans' contentions. Both German and British theologians based themselves on the just war theory, each group seeking to prove that it applied to the war waged by its own side.[37] |
ルネサンスとキリスト教ヒューマニスト さまざまなルネサンスのヒューマニストたちが平和主義的な見解を唱えた。 ジョン・コレットは、戦争の準備を進めていたヘンリー 8 世の前で四旬節の説教を行い、キケロの「最も公正な戦争よりも、不公正な平和の方がましだ」という言葉を引用して有名になった[36]。 ロッテルダムのエラスムスは、正義の戦争論を煙幕だと批判し、さらに制限を加えた数多くの平和に関する著作を残した。特に『平和の嘆き』と『戦争論 (Dulce bellum inexpertis)』が有名だ。 宗教改革後の主要なヒューマニスト作家は、法理論家のウーゴ・グロティウスで、彼の『戦争と平和の法』は、正義の戦争と正義の戦争の戦い方を再考した。 第一次世界大戦 第一次世界大戦の開始時、ドイツの神学者グループが、ドイツ政府の行動を正当化しようとする宣言を発表した。イギリス政府の要請により、カンタベリー大主 教ランダル・デイヴィソンは、過去に対立した人物を含む多くの宗教指導者と協力し、ドイツの主張を反論する文書を執筆する主導的役割を果たした。ドイツと イギリスの神学者たちはともに正義の戦争理論を基盤とし、それぞれが自国が展開する戦争にその理論が適用されることを証明しようとした。[37] |
| Contemporary Catholic doctrine The just war doctrine of the Catholic Church found in the 1992 Catechism of the Catholic Church, in paragraph 2309, lists four strict conditions for "legitimate defense by military force:"[38][39] 1. The damage inflicted by the aggressor on the nation or community of nations must be lasting, grave and certain. 2. All other means of putting an end to it must have been shown to be impractical or ineffective. 3. There must be serious prospects of success. 4. The use of arms must not produce evils and disorders graver than the evil to be eliminated. The Compendium of the Social Doctrine of the Church elaborates on the just war doctrine in paragraphs 500 to 501, while citing the Charter of the United Nations:[40] If this responsibility justifies the possession of sufficient means to exercise this right to defense, States still have the obligation to do everything possible "to ensure that the conditions of peace exist, not only within their own territory but throughout the world". It is important to remember that "it is one thing to wage a war of self-defense; it is quite another to seek to impose domination on another nation. The possession of war potential does not justify the use of force for political or military objectives. Nor does the mere fact that war has unfortunately broken out mean that all is fair between the warring parties". The Charter of the United Nations ... is based on a generalized prohibition of a recourse to force to resolve disputes between States, with the exception of two cases: legitimate defence and measures taken by the Security Council within the area of its responsibilities for maintaining peace. In every case, exercising the right to self-defence must respect "the traditional limits of necessity and proportionality". Therefore, engaging in a preventive war without clear proof that an attack is imminent cannot fail to raise serious moral and juridical questions. International legitimacy for the use of armed force, on the basis of rigorous assessment and with well-founded motivations, can only be given by the decision of a competent body that identifies specific situations as threats to peace and authorizes an intrusion into the sphere of autonomy usually reserved to a State. — Compendium of the Social Doctrine of the Church[40] Pope John Paul II in an address to a group of soldiers noted the following:[41] Peace, as taught by Sacred Scripture and the experience of men itself, is more than just the absence of war. And the Christian is aware that on earth a human society that is completely and always peaceful is, unfortunately, an utopia and that the ideologies which present it as easily attainable only nourish vain hopes. The cause of peace will not go forward by denying the possibility and the obligation to defend it. |
現代のカトリック教義 1992年の『カトリック教理要綱』第2309項に記されているカトリック教会の「正義の戦争」の教義は、「軍事力による正当防衛」の4つの厳格な条件を 挙げている[38][39]。 1. 侵略者が国民または国家共同体にもたらす損害は、永続的、重大かつ確実でなければならない。 2. それを終結させるための他のすべての手段が、実践不可能または効果がないことが示されなければならない。 3. 成功の見込みが真剣でなければならない。 4. 武力の行使は、排除すべき悪よりも重大な悪や混乱を引き起こしてはならない。 『カトリック教会の社会教義要綱』は、第500項から第501項で正義の戦争教義を詳細に説明し、国連憲章を引用している:[40] この責任が、この防衛権を行使するための十分な手段を保有することを正当化するとしても、国家は「自国の領土内だけでなく、全世界において平和の条件を確 保するためにあらゆる努力を尽くす」義務がある。 「自衛戦争を行うことと、他国民に支配を課そうとすることはまったく別のことである」ことを覚えておくことが重要だ。戦争の潜在的能力を有することは、政 治的または軍事的目的のための武力行使を正当化するものではない。また、戦争が不幸にも勃発したからといって、交戦当事者間のすべてが許されるわけではな い」。 国連憲章 ... は、国家間の紛争を解決するための武力行使の一般的な禁止を基盤としている。ただし、正当防衛と、安全保障理事会が平和維持の責任範囲内で講じる措置の2 つの例外がある。いずれの場合も、自衛権を行使する際には、「必要性と比例性の伝統的な限界」を尊重しなければならない。 したがって、攻撃が差し迫っているという明確な証拠がないまま予防戦争を行うことは、深刻な道徳的および法的問題を引き起こさざるを得ない。武力行使の国 際的な正当性は、厳格な評価と十分な根拠に基づく動機に基づいて、平和に対する脅威と特定された状況を認定し、通常国家に留保されている自治の領域への介 入を承認する権限を有する機関の決定によってのみ付与される。 — 教会の社会教説要覧[40] 教皇ヨハネ・パウロ二世は、兵士たちに向けた演説の中で、次のように述べている。[41] 聖書と人間の経験が教える平和は、単に戦争の不在を超えたものです。そして、キリスト教徒は、地上に完全に、そして常に平和な人間社会が存在することは、 残念ながらユートピアであり、それを容易に達成可能だと主張するイデオロギーは、空しい希望を養うだけであることを認識しています。平和の実現は、それを 守る可能性と義務を否定することによって前進するものではありません。 |
| Russian Orthodox Church The War and Peace section in the Basis of the Social Concept of the Russian Orthodox Church is crucial for understanding the Russian Orthodox Church's attitude towards war. The document offers criteria of distinguishing between an aggressive war, which is unacceptable, and a justified war, attributing the highest moral and sacred value of military acts of bravery to a true believer who participates in a justified war. Additionally, the document considers the just war criteria as developed in Western Christianity to be eligible for Russian Orthodoxy; therefore, the justified war theory in Western theology is also applicable to the Russian Orthodox Church.[42] In the same document, it is stated that wars have accompanied human history since the fall of man, and according to the gospel, they will continue to accompany it. While recognizing war as evil, the Russian Orthodox Church does not prohibit its members from participating in hostilities if there is the security of their neighbours and the restoration of trampled justice at stake. War is considered to be necessary but undesirable. It is also stated that the Russian Orthodox Church has had profound respect for soldiers who gave their lives to protect the life and security of their neighbours.[43] |
ロシア正教会 ロシア正教会の社会概念の基礎における「戦争と平和」の章は、ロシア正教会の戦争に対する姿勢を理解する上で極めて重要だ。この文書は、容認できない侵略 戦争と正当な戦争を区別する基準を示し、正当な戦争に参加する真の信者に、軍事的勇気の行為に最も高い道徳的・神聖な価値を付与している。さらに、この文 書は、西洋キリスト教で発展した正当な戦争の基準をロシア正教会にも適用可能だと考えており、したがって、西洋神学における正当な戦争の理論は、ロシア正 教会にも適用可能だとしている。[42] 同じ文書では、戦争は人間の堕落以来、人類の歴史に付き添ってきたものであり、福音によれば、今後も付き添い続けるだろうと述べられている。戦争を悪と認 識しつつも、ロシア正教会は、隣人の安全と踏みにじられた正義の回復が懸かっている場合、その信徒が戦闘に参加することを禁止していない。戦争は、必要で はあるが望ましくないものとされている。また、ロシア正教会は、隣人の生命と安全を守るために命を捧げた兵士たちに対して、深い尊敬の念を抱いてきたと述 べられている。[43] |
| Just war tradition The just war theory, propounded by the medieval Christian philosopher Thomas Aquinas, was developed further by legal scholars in the context of international law. Cardinal Cajetan, the jurist Francisco de Vitoria, the two Jesuit priests Luis de Molina and Francisco Suárez, as well as the humanist Hugo Grotius and the lawyer Luigi Taparelli were most influential in the formation of a just war tradition. The just war tradition, which was well established by the 19th century, found its practical application in the Hague Peace Conferences (1899 and 1907) and in the founding of the League of Nations in 1920. After the United States Congress declared war on Germany in 1917, Cardinal James Gibbons issued a letter that all Catholics were to support the war[44] because "Our Lord Jesus Christ does not stand for peace at any price... If by Pacifism is meant the teaching that the use of force is never justifiable, then, however well meant, it is mistaken, and it is hurtful to the life of our country."[45] Armed conflicts such as the Spanish Civil War, World War II and the Cold War were, as a matter of course, judged according to the norms (as established in Aquinas' just war theory) by philosophers such as Jacques Maritain, Elizabeth Anscombe and John Finnis.[31] The first work dedicated specifically to just war was the 15th-century sermon De bellis justis of Stanisław of Skarbimierz (1360–1431), who justified war by the Kingdom of Poland against the Teutonic Knights.[46] Francisco de Vitoria criticized the conquest of America by the Spanish conquistadors on the basis of just-war theory.[47] With Alberico Gentili and Hugo Grotius, just war theory was replaced by international law theory, codified as a set of rules, which today still encompass the points commonly debated, with some modifications.[48] Just-war theorists combine a moral abhorrence towards war with a readiness to accept that war may sometimes be necessary. The criteria of the just-war tradition act as an aid in determining whether resorting to arms is morally permissible. Just-war theories aim "to distinguish between justifiable and unjustifiable uses of organized armed forces"; they attempt "to conceive of how the use of arms might be restrained, made more humane, and ultimately directed towards the aim of establishing lasting peace and justice".[49] The just war tradition addresses the morality of the use of force in two parts: when it is right to resort to armed force (the concern of jus ad bellum) and what is acceptable in using such force (the concern of jus in bello).[50] In 1869 the Russian military theorist Genrikh Antonovich Leer [ru] theorized on the advantages and potential benefits of war.[51] The Soviet leader Vladimir Lenin defined only three types of just war.[52] But picture to yourselves a slave-owner who owned 100 slaves warring against a slave-owner who owned 200 slaves for a more "just" distribution of slaves. Clearly, the application of the term "defensive" war, or war "for the defense of the fatherland" in such a case would be historically false, and in practice would be sheer deception of the common people, of philistines, of ignorant people, by the astute slaveowners. Precisely in this way are the present-day imperialist bourgeoisie deceiving the peoples by means of "national ideology" and the term "defense of the fatherland" in the present war between slave-owners for fortifying and strengthening slavery.[53] The anarcho-capitalist scholar Murray Rothbard (1926–1995) stated that "a just war exists when a people tries to ward off the threat of coercive domination by another people, or to overthrow an already-existing domination. A war is unjust, on the other hand, when a people try to impose domination on another people or try to retain an already-existing coercive rule over them."[54] Jonathan Riley-Smith writes: The consensus among Christians on the use of violence has changed radically since the crusades were fought. The just war theory prevailing for most of the last two centuries—that violence is an evil that can, in certain situations, be condoned as the lesser of evils—is relatively young. Although it has inherited some elements (the criteria of legitimate authority, just cause, right intention) from the older war theory that first evolved around AD 400, it has rejected two premises that underpinned all medieval just wars, including crusades: first, that violence could be employed on behalf of Christ's intentions for mankind and could even be directly authorized by him; and second, that it was a morally neutral force that drew whatever ethical coloring it had from the intentions of the perpetrators.[55] |
正義の戦争の伝統 中世キリスト教の哲学者トマス・アクィナスによって提唱された正義の戦争理論は、国際法の文脈において法学者たちによってさらに発展した。カジェタン枢機 卿、法学者フランシスコ・デ・ヴィトリア、イエズス会の神父ルイス・デ・モリーナとフランシスコ・スアレス、人文主義者ウーゴ・グロティウス、弁護士ルイ ジ・タパレリは、正義の戦争の伝統の形成に最も影響を与えた人物たちだ。19世紀までに確立された正義の戦争の伝統は、1899年と1907年のハーグ平 和会議および1920年の国際連盟の設立において実践的な応用を見出した。1917年にアメリカ合衆国議会がドイツに対して宣戦布告した際、ジェームズ・ ギボンズ大司教は、すべてのカトリック教徒が戦争を支持すべきだとする書簡を発表した[44]。その理由として、「私たちの主イエス・キリストは、いかな る代償を払っても平和を支持するものではない…もし平和主義が『武力の行使は決して正当化されない』という教義を指すのであれば、その意図がどれだけ善意 であっても、それは誤りであり、私たちの国の生命に害を及ぼすものだ」と述べた[45]。 スペイン内戦、第二次世界大戦、冷戦などの武力紛争は、当然のことながら、ジャック・マリタン、エリザベス・アンスカム、ジョン・フィニスなどの哲学者に よって、トマス・アクィナスが確立した正義の戦争理論の規範に基づいて判断された。[31] 正義の戦争に特に焦点を当てた最初の著作は、15 世紀のスタニスワフ・スカルビミェシュ(1360–1431)の説教『De bellis justis』で、ポーランド王国によるドイツ騎士団に対する戦争を正当化した。[46] フランシスコ・デ・ヴィトリアは、正義の戦争理論に基づいて、スペインの征服者によるアメリカ大陸の征服を批判した。[47] アルベリコ・ジェンティリとウーゴ・グロティウスにより、正戦論は国際法理論に取って代わられ、一連の規則として成文化された。この規則は、いくつかの修 正は加えられているものの、今日でも一般的に議論されている点を網羅している。[48] 正戦論者は、戦争に対する道徳的な嫌悪感と、戦争が時には必要であるとの認識とを両立させている。正戦論の伝統の基準は、武力行使が道徳的に容認できるか どうかを判断するための手助けとなる。正義の戦争理論は、「組織化された武力行使の正当な使用と不正な使用を区別すること」を目的とし、「武力行使を制限 し、より人道的にし、最終的に持続可能な平和と正義の確立という目的 towards に向ける方法を考案すること」を試みる。[49] 正戦論の伝統は、武力行使の道徳性を 2 つの部分に分けて考察している。武力行使が正当である場合(jus ad bellum)と、そのような武力行使において何が容認されるか(jus in bello)だ。[50] 1869 年、ロシアの軍事理論家ゲンリフ・アントノヴィッチ・レール [ru] は、戦争の利点と潜在的なメリットについて理論化した。[51] ソ連の指導者ウラジーミル・レーニンは、正義の戦争を 3 種類にのみ定義した。[52] しかし、100 人の奴隷を所有する奴隷所有者が、より「公正な」奴隷の分配を求めて 200 人の奴隷を所有する奴隷所有者と戦争をしている状況を想像してみてください。明らかに、このような場合、「防御的」戦争、または「祖国防衛のための戦争」 という用語の適用は歴史的に誤りであり、実践的には、巧妙な奴隷所有者によって、一般の人民、俗物、無知な人々を欺く行為に他ならない。まさにこの方法 で、現在の帝国主義的ブルジョアジーは、奴隷所有者同士の戦争において「国家イデオロギー」と「祖国防衛」という用語を用いて、国民を欺いている。 [53] アナキスト資本主義の学者マーレイ・ロスバード(1926–1995)は、「正当な戦争とは、ある人民が別の人民による強制的な支配の脅威を排除しようと したり、既に存在する支配を打倒しようとしたりする戦争である。一方、戦争が不正義であるのは、ある人民が別の人民に支配を強要しようとしたり、既に存在 する強制的な支配を維持しようとしたりする時だ」と述べている。[54] ジョナサン・ライリー・スミスは次のように書いている: 十字軍が戦われた以来、キリスト教徒の間で暴力の使用に関するコンセンサスは根本的に変化した。過去2世紀の大部分で支配的だった「正義の戦争」理論—— 暴力は悪であるが、特定の状況下ではより小さな悪として容認できる——は比較的新しいものだ。この理論は、AD 400年ごろに初めて発展した古い戦争理論からいくつかの要素(正当な権威の基準、正当な原因、正しい意図)を継承しているが、中世の正義の戦争(十字軍 を含む)の基盤を成していた二つの前提を拒否している:第一に、暴力はキリストの人類に対する意図のために用いられ、甚至いは彼によって直接承認される可 能性があるという前提; 第二に、それは道徳的に中立な力であり、その倫理的な色合いは加害者の意図主義から導かれるという前提だ。[55] |
| Criteria The just war theory has two sets of criteria, the first establishing jus ad bellum (the right to go to war), and the second establishing jus in bello (right conduct within war).[56] Jus ad bellum Main article: Jus ad bellum The just war theory directs jus ad bellum to norms that aim to require certain circumstances to enable the right to go to war.[57] Competent authority Only duly constituted public authorities may wage war. "A just war must be initiated by a political authority within a political system that allows distinctions of justice. Dictatorships (e.g. Hitler's regime) or deceptive military actions (e.g. the 1968 US bombing of Cambodia) are typically considered as violations of this criterion. The importance of this condition is key. Plainly, we cannot have a genuine process of judging a just war within a system that represses the process of genuine justice. A just war must be initiated by a political authority within a political system that allows distinctions of justice".[58] Probability of success According to this principle, there must be good grounds for concluding that aims of the just war are achievable.[59] This principle emphasizes that mass violence must not be undertaken if it is unlikely to secure the just cause.[60] This criterion is to avoid invasion for invasion's sake and links to the proportionality criteria. One cannot invade if there is no chance of actually winning. However, wars are fought with imperfect knowledge, so one must simply be able to make a logical case that one can win; there is no way to know this in advance. These criteria move the conversation from moral and theoretical grounds to practical grounds.[61] Essentially, this is meant to gather coalition building and win approval of other state actors. Last resort - ultima ratio The principle of last resort stipulates that all non-violent options must first be exhausted before the use of force can be justified. Diplomatic options, sanctions, and other non-military methods must be attempted or validly ruled out before the engagement of hostilities. Further, in regard to the amount of harm—proportionally—the principle of last resort would support using small intervention forces first and then escalating rather than starting a war with massive force such as carpet bombing or nuclear warfare.[62] Just cause The reason for going to war needs to be just and cannot, therefore, be solely for recapturing things taken or punishing people who have done wrong; innocent life must be in imminent danger and intervention must be to protect life. A contemporary view of just cause was expressed in 1993 when the US Catholic Conference said: "Force may be used only to correct a grave, public evil, i.e., aggression or massive violation of the basic human rights of whole populations." Jus in bello Once war has begun, just war theory (jus in bello) also directs how combatants are to act or should act: Distinction Just war conduct is governed by the principle of distinction. The acts of war should be directed towards enemy combatants, and not towards non-combatants caught in circumstances that they did not create. The prohibited acts include bombing civilian residential areas that include no legitimate military targets, committing acts of terrorism or reprisal against civilians or prisoners of war (POWs), and attacking neutral targets. Moreover, combatants are not permitted to attack enemy combatants who have surrendered, or who have been captured, or who are injured and not presenting an immediate lethal threat, or who are parachuting from disabled aircraft and are not airborne forces, or who are shipwrecked. Proportionality Just war conduct is governed by the principle of proportionality. Combatants must make sure that the harm caused to civilians or civilian property is not excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated by an attack on a legitimate military objective. This principle is meant to discern the correct balance between the restriction imposed by a corrective measure and the severity of the nature of the prohibited act. Military necessity Just war conduct is governed by the principle of military necessity. An attack or action must be intended to help in the defeat of the enemy; it must be an attack on a legitimate military objective, and the harm caused to civilians or civilian property must be proportional and not excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated. Jus in bello allows for military necessity and does not favor a specific justification in allowing for counter-attack recourse.[63] This principle is meant to limit excessive and unnecessary death and destruction. Fair treatment of prisoners of war Enemy combatants who surrendered or who are captured no longer pose a threat. It is therefore wrong to torture them or otherwise mistreat them. No means malum in se - "wrong" or "evil in itself". Combatants may not use weapons or other methods of warfare that are considered evil, such as mass rape, forcing enemy combatants to fight against their own side or using weapons whose effects cannot be controlled (e.g., nuclear/biological weapons). |
基準 正戦論には 2 つの基準があり、1 つ目は「戦争を行う権利(jus ad bellum)」を、2 つ目は「戦争における正しい行動(jus in bello)」を規定している。[56] jus ad bellum - 戦争を行う権利 主な記事:jus ad bellum 正戦論は、戦争を行う権利を認める特定の状況を要求する規範に jus ad bellum を適用している。[57] 管轄権 正当に設立された公的機関のみが戦争を行うことができる。「正義の戦争は、正義の区別を認める政治体制内の政治当局によって開始されなければならない。独 裁政権(ヒトラー政権など)や欺瞞的な軍事行動(1968年の米国によるカンボジア爆撃など)は、通常、この基準の違反とみなされる。この条件の重要性は 極めて高い。明らかに、真の正義の過程を抑制するシステムの中で、正当な戦争を判断するための真のプロセスは存在し得ない。正当な戦争は、正義の区別を認 める政治体制内の政治権力によって開始されなければならない」。[58] 成功の可能性 この原則によれば、正当な戦争の目的が達成可能であると結論付けるための十分な根拠がなければならない。[59] この原則は、正当な目的を達成する可能性が低い場合、大規模な暴力を行ってはならないことを強調している。[60] この基準は、侵略のための侵略を回避し、比例性の基準と関連している。勝利の可能性がない場合、侵略はできない。しかし、戦争は不完全な知識の下で行われ るため、勝利できるという論理的な根拠を示すことができれば十分であり、事前にこれを知ることは不可能だ。これらの基準は、議論を道徳的・理論的な領域か ら実践的な領域に移すものだ。[61] 本質的には、これは連合の構築と他の国家主体の承認を得ることを目的としている。 最後の手段 最後の手段原則は、武力行使を正当化するには、まず非暴力的な選択肢をすべて尽くさなければならないと規定している。外交的手段、制裁、その他の非軍事的 な手段を試み、または有効に排除してから、敵対行為に踏み切らなければならない。さらに、被害の程度(比例性)に関して、最終手段原則は、大規模な爆撃や 核戦争のような大規模な武力行使で戦争を開始するのではなく、まず小規模な介入部隊を派遣し、その後段階的に武力行使を強化する方針を支持する。[62] 正当な理由 戦争を行う理由は正当でなければならず、したがって、奪われたものを取り戻すため、または悪を行った人々を罰するためだけのもであってはなりません。無実 の生命が差し迫った危険にさらされており、その生命を守るために介入しなければならない場合でなければなりません。正当な理由に関する現代的な見解は、 1993年に米国カトリック会議が次のように述べた際に表明された:「武力行使は、重大な公の悪、すなわち侵略や全体の人口の基礎的人権の重大な侵害を是 正するためだけに使用されるべきだ。」 戦争中の正義 戦争が始まると、正義の戦争理論(jus in bello)は、戦闘員がどのように行動すべきか、または行動すべきかを指示する: 区別 正義の戦争の行動は、区別の原則によって規律される。戦争行為は敵の戦闘員に向けられるべきであり、自ら招いた状況に陥った非戦闘員に向けられるべきでは ない。禁止される行為には、正当な軍事目標を含まない民間人居住地域の爆撃、民間人または戦争捕虜(POW)に対するテロ行為または報復行為、中立目標へ の攻撃が含まれる。さらに、戦闘員は、降伏した敵戦闘員、捕虜となった敵戦闘員、負傷して直ちに致命的な脅威を呈していない敵戦闘員、故障した航空機から パラシュートで降下中で空中の部隊ではない敵戦闘員、または難破した船の乗組員を攻撃してはならない。 比例性 正義の戦争の行動は、比例性の原則によって規律される。戦闘員は、正当な軍事目標に対する攻撃によって予想される具体的かつ直接的な軍事上の利益に比し て、民間人または民間財産に与える損害が過剰でないことを確保しなければならない。この原則は、是正措置によって課される制限と、禁止された行為の性質の 深刻さとの間の適切な均衡を判断するためのものだ。 軍事上の必要性 正義の戦争の行動は、軍事上の必要性の原則によって規律される。攻撃または行動は、敵の敗北に役立つことを目的とし、正当な軍事目標に対する攻撃でなけれ ばならない。また、民間人または民間財産に与える損害は、具体的な直接的な軍事的利益と比例し、過剰であってはならない。jus in belloは軍事的必要性を認めており、反撃の手段を認める際に特定の正当化を優先しない。[63] この原則は、過剰で不要な死と破壊を制限することを目的としている。 捕虜の公正な待遇 降伏した敵戦闘員または捕虜となった敵戦闘員は、もはや脅威を構成しない。したがって、彼らを拷問したり、その他の方法で虐待することは間違っている。 悪事が自己目的になってはならない( No means malum in se) 戦闘員は、集団強姦、敵戦闘員を自軍に対して戦わせる行為、またはその効果を制御できない武器(例:核兵器/生物兵器)の使用など、悪とみなされる武器や 戦争手段を使用してはならない。 |
| Ending a war: Jus post bellum In recent years, some theorists, such as Gary Bass, Louis Iasiello and Brian Orend, have proposed a third category within the just war theory. "Jus post bellum is described by some scholars as a new "discipline," or as "a new category of international law currently under construction".[64] Jus post bellum[65] concerns justice after a war, including peace treaties, reconstruction, environmental remediation, war crimes trials, and war reparations. Jus post bellum has been added to deal with the fact that some hostile actions may take place outside a traditional battlefield. Jus post bellum governs the justice of war termination and peace agreements, as well as the prosecution of war criminals, and publicly labelled terrorists.The idea has largely been used to help decide what to do with prisoners taken during battle. It is through government labeling and public opinion that people use jus post bellum to justify the pursuit of individuals labeled as terrorists for the safety of the government's state in a modern context. The actual fault lies with the aggressor, and by being the aggressor, they forfeit their rights to honorable treatment by their actions. That theory is used to justify the actions taken by anyone fighting in a war to treat prisoners outside the bounds of war.[66][67] |
戦争の終結:Jus post bellum 近年、ゲイリー・バス、ルイ・イアセロ、ブライアン・オレンなどの理論家は、正義の戦争論の中に第三のカテゴリーを提唱している。「戦後法(Jus post bellum)」は、一部の学者によって「新たな『学問分野』」または「現在構築中の国際法の新たなカテゴリー」と説明されている。[64] 戦後法(Jus post bellum)[65] は、戦争後の正義に関するもので、平和条約、再建、環境回復、戦争犯罪の裁判、戦争賠償などを含む。戦後法は、伝統的な戦場外で敵対行為が発生する可能性 に対応するため追加された。Jus post bellumは、戦争の終結と平和協定の正義、戦争犯罪者の起訴、および公にテロリストと指定された者の処罰を規律する。この概念は、主に戦闘中に捕虜と なった者に対する処遇を決定するために用いられてきた。現代の文脈では、政府の国家安全保障のため、政府の指定と世論を通じて、テロリストと指定された個 人を追跡する行為を正当化するためにJus post bellumが用いられる。実際の責任は加害者にあり、加害者であることで、彼らは自らの行動により名誉ある待遇を受ける権利を放棄する。この理論は、戦 争に参加する者が戦争の枠組み外で捕虜を扱う行為を正当化する根拠として用いられている。[66][67] |
| Traditionalists and Revisionists There are two altering views related to the just war theory that scholars align with, which are traditionalists and revisionists. The debates between these different viewpoints rest on the moral responsiblites of actors in jus in bello.[68] Traditionalists In the just war theory as it pertains to jus in bello, traditionalist scholars view that the two principles, jus ad bellum and jus in bello, are distinct in which actors in war are morally responsible. The traditional view places accountability on leaders who start the war, while soldiers are accountable for actions breaking jus in bello.[69] Revisionists Revisionist scholars view that moral responsibility in conduct of war is placed on individual soldiers who participate in war, even if they follow the rules associated with jus in bello. Soldiers that participate in unjust wars are morally responsible. The revisionist view is based on an individual level, rather than on a collective whole.[70][68][69] |
伝統主義者と修正主義者 学者たちが支持する、正義の戦争理論に関する2つの異なる見解がある。それは、伝統主義者と修正主義者だ。これらの異なる見解間の議論は、jus in bello における行為者の道徳的責任に基づいている。[68] 伝統主義者 jus in bello に関連する正戦論において、伝統主義者の学者は、jus ad bellum と jus in bello の 2 つの原則は、戦争における行為者の道徳的責任において別個のものであるとみなしている。伝統的な見解では、戦争を開始した指導者に責任があり、兵士は jus in bello に違反する行為について責任があるとしている。[69] 修正主義者 修正主義の学者は、戦争の遂行における道徳的責任は、jus in belloに関連する規則に従っている場合でも、戦争に参加する個々の兵士にあるとみなしている。不公正な戦争に参加する兵士は、道徳的責任がある。修正 主義の見解は、集団全体ではなく、個人レベルに基づいている。[70][68][69] |
| Appeasement Christian pacifism Cost–benefit analysis Democratic peace theory Deterrence theory Peace and conflict studies Right of conquest Moral equality of combatants Supreme emergency Peace discourse in the Israeli–Palestinian conflict |
宥和 キリスト教の平和主義 費用便益分析 民主的平和論 抑止論 平和と紛争の言説 征服権 戦闘者の道徳的平等 最高緊急事態 イスラエル・パレスチナ紛争における平和言説 |
| Benson, Richard. "The Just War
Theory: A Traditional Catholic Moral View", The Tidings (2006). Showing
the Catholic view in three points, including John Paul II's position
concerning war. Blattberg, Charles. Taking War Seriously. A critique of just war theory. Brough, Michael W., John W. Lango, Harry van der Linden, eds., Rethinking the Just War Tradition (Albany, NY: SUNY Press, 2007). Discusses the contemporary relevance of just war theory. Offers an annotated bibliography of current writings on just war theory. Brunsletter, D., & D. O'Driscoll, Just war thinkers from Cicero to the 21st century (Routledge, 2017). Butler, Paul (2002–2003). "By Any Means Necessary: Using Violence and Subversion to Change Unjust Law". UCLA Law Review. 50: 721 – via HeinOnline. Churchman, David. Why we fight: the origins, nature, and management of human conflict (University Press of America, 2013) online. Crawford, Neta. "Just War Theory and the US Countertenor War", Perspectives on Politics 1(1), 2003. online Elshtain, Jean Bethke, ed. Just war theory (NYU Press, 1992) online. Evans, Mark (editor) Just War Theory: A Reappraisal (Edinburgh University Press, 2005) Fotion, Nicholas. War and Ethics (London, New York: Continuum, 2007). ISBN 0-8264-9260-6. A defence of an updated form of just war theory. Heindel, Max. The Rosicrucian Philosophy in Questions and Answers – Volume II (The Philosophy of War, World War I reference, ed. 1918), ISBN 0-911274-90-1 (Describing a philosophy of war and just war concepts from the point of view of his Rosicrucian Fellowship) Gutbrod, Hans. Russia's Recent Invasion of Ukraine and Just War Theory ("Global Policy Journal", March 2022); applies the concept to Russia's February 2022 invasion of Ukraine. Holmes, Robert L. On War and Morality (Princeton University Press, 1989.[1] Khawaja, Irfan. Review of Larry May, War Crimes and Just War, in Democratiya 10, ([1]), an extended critique of just war theory. Kwon, David. Justice after War: Jus Post Bellum in the 21st Century (Washington, D.C., Catholic University of America Press, 2023). ISBN 978-0-813236-51-3 MacDonald, David Roberts. Padre E. C. Crosse and 'the Devonshire Epitaph': The Astonishing Story of One Man at the Battle of the Somme (with Antecedents to Today's 'Just War' Dialogue), 2007 Cloverdale Books, South Bend. ISBN 978-1-929569-45-8 McMahan, Jeff. "Just Cause for War," Ethics and International Affairs, 2005. Nájera, Luna. "Myth and Prophecy in Juan Ginés de Sepúlveda's Crusading "Exhortación" Archived 11 March 2011 at the Wayback Machine, in Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies, 35:1 (2011). Discusses Sepúlveda's theories of war in relation to the war against the Ottoman Turks. Nardin, Terry, ed. The ethics of war and peace: Religious and secular perspectives (Princeton University Press, 1998) online O'Donovan, Oliver. The Just War Revisited (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). Steinhoff, Uwe. On the Ethics of War and Terrorism (Oxford, Oxford University Press, 2007). Covers the basics and some of the most controversial current debates. Walzer, Michael. Arguing about War, (Yale University Press, 2004). ISBN 978-0-300-10978-8 |
ベンソン、リチャード。「正義の戦争論:伝統的なカトリックの道徳
観」、『The Tidings』(2006年)。戦争に関するヨハネ・パウロ2世の立場を含む、カトリックの見解を3つのポイントで紹介している。 ブラットバーグ、チャールズ。『戦争を真剣に考える。正義の戦争理論の批判』。 ブラフ、マイケル・W.、ジョン・W・ランゴ、ハリー・ファン・デル・リンデン編。『正義の戦争の伝統を再考する』(ニューヨーク州アルバニー:SUNY Press、2007年)。正義の戦争理論の現代的意義について論じている。正義の戦争理論に関する最近の著作の注釈付き書誌目録を掲載している。 ブルンスレター、D.、D. O'Driscoll、『シセロから21世紀までの正義の戦争思想家たち』(Routledge、2017年)。 バトラー、ポール(2002年~2003年)。「必要なあらゆる手段:不公正な法律を変えるための暴力と破壊活動」。UCLA Law Review. 50: 721 – via HeinOnline. チャーチマン、デビッド。なぜ私たちは戦うのか:人間紛争の起源、本質、および管理(University Press of America、2013)オンライン。 クロフォード、ネタ。「正義の戦争論と米国の対位法戦争」、Perspectives on Politics 1(1)、2003。オンライン エルシュタイン、ジャン・ベスケ、編。正義の戦争論(NYU Press、1992)オンライン。 エヴァンス、マーク(編集)正義の戦争論:再評価(エジンバラ大学出版、2005) フォティオン、ニコラス。戦争と倫理(ロンドン、ニューヨーク:Continuum、2007)。ISBN 0-8264-9260-6。公正戦争論の最新の形態の擁護。 ヘインデル、マックス。The Rosicrucian Philosophy in Questions and Answers – Volume II (The Philosophy of War, World War I reference, ed. 1918), ISBN 0-911274-90-1 (彼の薔薇十字団の見解から、戦争の哲学と公正戦争の概念について記述したもの) ハンス・グトブロッド。ロシアの最近のウクライナ侵攻と正義の戦争論(「グローバル・ポリシー・ジャーナル」、2022年3月)。この概念を、2022年 2月のロシアのウクライナ侵攻に適用している。 ロバート・L・ホームズ。戦争と道徳について(プリンストン大学出版局、1989年。[1] イフラン・カワジャ。ラリー・メイ著『戦争犯罪と正義の戦争』の書評、Democratiya 10、([1])、正義の戦争論に対する広範な批判。 クォン、デビッド。戦争後の正義:21 世紀の Jus Post Bellum(ワシントン D.C.、カトリック大学出版、2023 年)。ISBN 978-0-813236-51-3 マクドナルド、デビッド・ロバーツ。パドレ・E・クロスと「デボンシャーの墓碑銘」:ソンムの戦いで1人の男が繰り広げた驚くべき物語(今日の「正義の戦 争」の対話への先例を含む)、2007年、クローバーデール・ブックス、サウスベンド。ISBN 978-1-929569-45-8 マクマハン、ジェフ。「戦争の正当な理由」『倫理と国際問題』2005年。 ナヘラ、ルナ。「フアン・ヒネス・デ・セプルベダの十字軍『Exhortación』における神話と予言」 2011年3月11日ウェイバックマシンにアーカイブ、Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies、35:1 (2011)。セプルベダの戦争論をオスマン・トルコ戦争との関係で論じている。 ナーディン、テリー編『戦争と平和の倫理:宗教的・世俗的視点』(プリンストン大学出版局、1998年)オンライン オドノバン、オリバー『正義の戦争再考』(ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、2003年)。 シュタインホフ、ウーヴェ。『戦争とテロリズムの倫理』(オックスフォード:オックスフォード大学出版局、2007年)。基礎的な内容と、現在最も議論の 分かれている論点について解説している。 ウォルツアー、マイケル。『戦争について論じる』(エール大学出版局、2004年)。ISBN 978-0-300-10978-8 |
| "Just war theory". Internet
Encyclopedia of Philosophy. Catholic Teaching Concerning Just War at Catholicism.org "Just War" In Our Time, BBC Radio 4 discussion with John Keane and Niall Ferguson (3 June 1999)(現在リンク切れ) |
「正義の戦争論」。インターネット哲学事典。 Catholicism.org の「正義の戦争に関するカトリックの教え 「私たちの時代における正義の戦争」、BBC ラジオ 4 のジョン・キーンとニール・ファーガソンによる討論(1999年6月3日)(現在リンク切れ) |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Just_war_theory |
リンク集
文献
その他の情報

++
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099