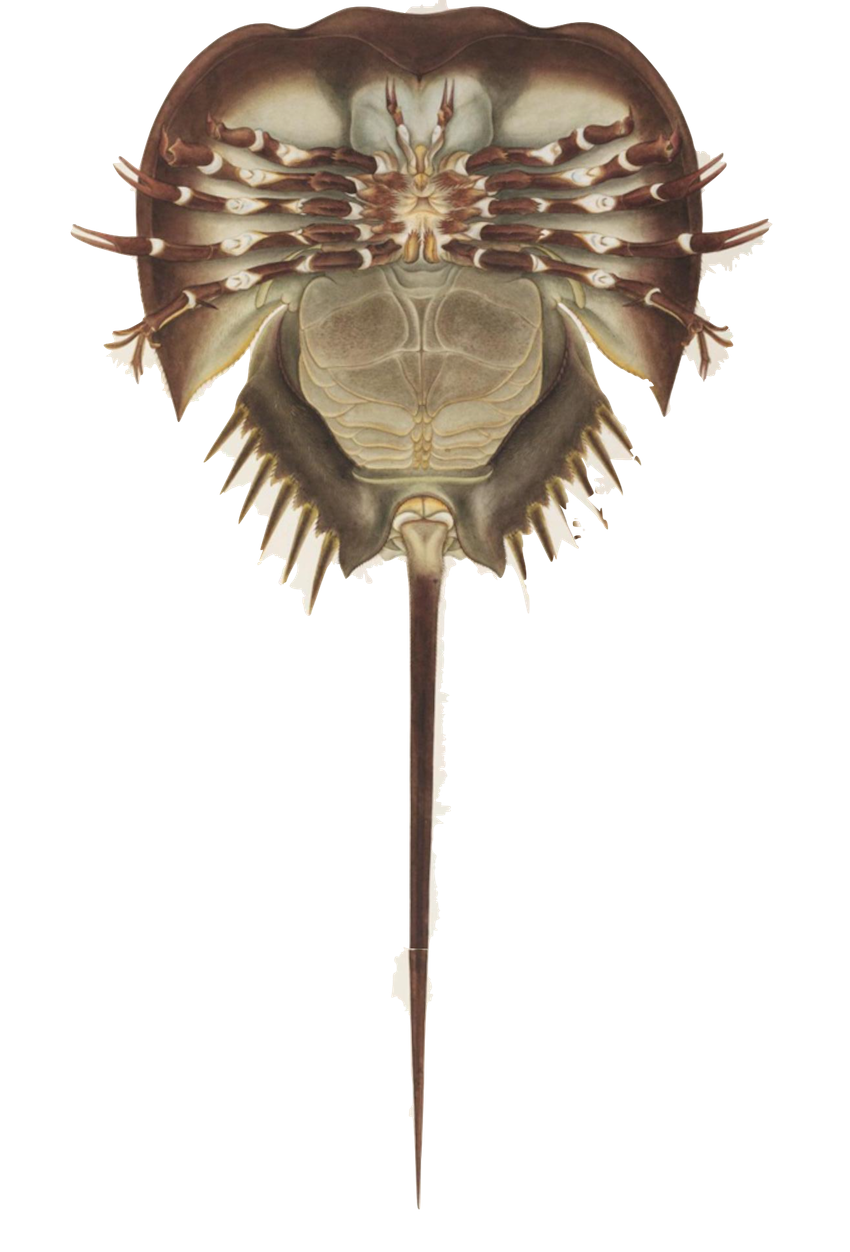


ジジェクの「サイバースペース、あるいはリアルの仮想性」ノート
Uncychropedia of Slavoj Zizek
☆ジジェク師範については、「ス ラヴォイ・ジジェク」をご参照くださいませ。
CYBERSPACE, OR THE VIRTUALITY OF THE REAL(https://x.gd/RqRxB)
☆サイバースペースに関する2つの支配的な神話はどちらも、モダニズムの時代(一元論的主観
性、機械論的理性など)からポストモダンの普及の時代(究極的な真理への言及にもはや根拠を持たない外観の戯れ、構築された自己の複数の形態など)への転
換の真っ只中にある、という通説に基づいている。
| The two predominant
myths about cyberspace are both based on the commonplace
according to which we are today in the middle of the shift from the
epoch of
modernism (monological subjectivity, mechanistic Reason, etc.) to the
post-modern
epoch of dissemination (the play of appearances no longer grounded in
the reference
to some ultimate Truth, the multiple forms of constructed Selves, etc.). |
サイバースペースに関する2つの支配的な神話はどちらも、モダニズムの
時代(一元論的主観性、機械論的理性など)からポストモダンの普及の時代(究極的な真理への言及にもはや根拠を持たない外観の戯れ、構築された自己の複数
の形態など)への転換の真っ只中にある、という通説に基づいている。 |
| In cyberspace, we witness a
return to pensée sauvage, to “concrete”, “sensual”
thought: an “essay” in cyberspace confronts fragments of music and
other sounds,
text, images, video clips, etc., and it is this confrontation of
“concrete” elements which
produces “abstract” meaning... Are we not here again back at
Eisenstein’s dream of
“intellectual montage” - of filming Capital, of producing the Marxist
theory out of the
clash of concrete images? Is not hypertext a new practice of montage? |
サイバースペースにおける「エッセイ」は、音楽やその他の音、テキス
ト、画像、ビデオクリップなどの断片と対峙し、この「具体的な」要素の対峙が「抽象的な」意味を生み出すのである...。資本論』を撮影し、具体的なイ
メージの衝突からマルクス主義理論を生み出すという、エイゼンシュテインの「知的モンタージュ」の夢に、ここで再び立ち戻ることにならないだろうか。ハイ
パーテキストは、モンタージュの新しい実践ではないのか? |
| We are witnessing today the move
from the modernist culture of calculation to the
postmodernist culture of simulation.2 The clearest index of this move
is the shift in the
use of the term “transparency”: modernist technology is “transparent”
in the sense of
retaining the illusion of the insight into “how the machine works”,
i.e. the screen of the
interface was supposed to enable the user to have direct access to the
machine
behind the screen; the user was supposed to “grasp” its working, in
ideal conditions
even to reconstruct it rationally. The postmodernist “transparency”
designates almost
the exact opposite of this attitude of analytical global planning: the
interface screen is
supposed to conceal the working of the machine behind it and to
simulate as faithfully
as possible our everyday experience (the Macintosh style of interface
in which written
orders are replaced by simple mouse-clicking in iconic signs...);
however, the price
for this illusion of the continuity with our everyday environs is that
the user becomes
“accustomed to opaque technology” - the digital machinery “behind the
screen”
retreats into total impenetrability, even invisibility. In other words,
the user renounces
the endeavour to grasp the functioning of the computer, resigning
himself to the fact
that, in his interaction with cyberspace, he is thrown into a
non-transparent situation
homologous to that of his everyday Lebenswelt, a situation in which he
has to “find
his bearings”, to act in the mode of tinkering (bricolage), by means of
trial and error,
not simply to follow some pre-established general rules - or, to repeat
Sherry Turkle’s
pun, in the postmodernist attitude, we “take things at their interface
value”. If the
modernist universe is the universe, hidden behind the screen, of bytes,
wires and
chips, of electric current running, the postmodernist universe is the
universe of the
naive trust in the screen which makes irrelevant the very quest for
“what lies behind
it”. “To take things at their interface value” involves a
phenomenological attitude, an
attitude of “trusting the phenomena”: the modernist programmer takes
refuge in
cyberspace as a transparent, clearly structured universe which allows
him to elude
(momentarily, at least) the opacity of his everyday environs in which
he is part of an a
priori unfathomable background, full of institutions whose functioning
follows
unknown rules which exert domination over his life; for the
postmodernis programmer, on the contrary, the fundamental features of
cyberspace coincide with
those described by Heidegger as the constitutive features of our
everyday life-world
(the finite individual is thrown into a situation whose co-ordinates
are not regulated by
clear universal rules, so that the individual has to find his way in it
gradually)... |
この動きの最も明確な指標は、「透明性」という用語の使い方の変化であ
る。モダニズムのテクノロジーは、「機械がどのように動作しているか」を洞察する幻想を保持するという意味で「透明」である。ポストモダニズムの「透明
性」は、このような分析的なグローバル・プランニングの態度のほとんど正反対を意味している。インターフェイスの画面は、その背後にあるマシンの動作を隠
し、私たちの日常的な経験をできるだけ忠実にシミュレートすることになっている(マッキントッシュ・スタイルのインターフェイスでは、文字による命令がア
イコンの単純なマウス・クリックに置き換えられている。
しかし、この日常的な環境との連続性の錯覚の代償として、ユーザーは「不透明なテクノロジーに慣れる」ことになる。言い換えれば、ユーザーはコンピュー
ターの機能を把握しようとする努力を放棄し、サイバースペースとの相互作用の中で、日常生活と同じような非透明な状況に身を置くことになる、 つまり、シェリー・タークルのダジャレを繰り返せば、ポストモダニズムの態度では、「物事をそのイン
ターフェイスの価値で受け取る」のである。モダニズムの宇宙が、画面の背後に隠された、バイト、ワイヤー、チップ、電流の流れる宇宙だとす
れば、ポストモダニズムの宇宙は、「画面の背後にあるもの」を探求すること自体を無意味にしてしまう、画面に対する素朴な信頼の宇宙である。「インター
フェイスの価値で物事をとらえる」ことは、現象学的な態度、つまり「現象を信頼する」態度を伴う:
モダニズムのプログラマーは、サイバースペースという透明で明確に構造化された宇宙に避難する。それによって彼は、自分が先験的に理解できない背景の一部
であり、その機能は未知の規則に従っており、彼の生活を支配する制度で満ちている日常の環境の不透明さから(少なくとも一瞬は)逃れることができる;
ポストモダニスのプログラマーにとっては、逆に、サイバースペースの基本的特徴は、ハイデガーが日常生活世界の構成的特徴として述べたものと一致する(有
限の個人は、その座標が明確な普遍的規則によって規制されていない状況に投げ込まれるため、個人はその中で徐々に自分の道を見つけなければならない)。
.. |
| In both these myths, the error
is the same: yes, in cyberspace, we are dealing with a
return to premodern “concrete thought” or to the non-transparent
life-world, but this
new life-world already presupposes the background of the scientific
digital universe:
bytes, or, rather, the digital series is the real behind the screen,
i.e. we are never
submerged in the play of appearances without an “indivisible
remainder”. Postmodernism focuses on
the
mystery of what Turkle calls the
“emergence” and
what Deleuze elaborated as the “sense-event”: the emergence of the pure
appearance which cannot be reduced to the simple effect of its bodily
causes;
nonetheless, this emergence is the effect of the digitalized Real. |
どちらの神話においても、誤りは同じである。そう、サイバースペースに
おいて、私たちは前近代的な「具体的思考」への回帰、あるいは非透明な生命世界への回帰を扱っているのだが、この新しい生命世界はすでに科学的なデジタル
宇宙の背景を前提としている。ポストモダニズムは、タークルが「出現」と呼び、ドゥ
ルーズが「感覚事象」と呼んだものの謎に焦点を当てる。にもかかわらず、身体的原因の単純な効果に還元できない純粋な外観の出現、つまりこの出現はデジタ
ル化されたリアルの影響である。 |
| A propos of the notion of
interface, the temptation here is, of course, to bring it to the
point of its self-reference: what if one conceives of the
“consciousness” itself, the
frame through which we perceive the universe, as a kind of “interface”?
However, the
moment we yield to this temptation, we accomplish a kind of foreclosure
of the real.
When the user playing with the multiplicity of Internet Relay Chat
(IRC) channels
says to himself “What if real life (RL) itself is just one more IRC
channel?”, or, with
respect to multiple windows in a hypertext, “What if RL is just one
more window?”,
the illusion to which he succumbs is strictly correlative to the
opposite one, i.e. to the
common-sense attitude of maintaining our belief in the full reality
outside the virtual
universe. That is to say, one should avoid both traps, the simple
direct reference to
external reality outside cyberspace as well as the opposite attitude of
“there is no
external reality, RL is just another window." |
もし、私たちが宇宙を認識するフレームである「意識」そのものを、一種
の「インターフェイス」と考えたらどうなるだろうか。しかし、この誘惑に負けた瞬間、私たちは現実のある種の閉鎖を達成してしまう。インターネット・リ
レー・チャット(IRC)の多重チャンネルで遊んでいるユーザーが、「もし現実の生活(RL)そのものが、もうひとつのIRCチャンネルに過ぎないとした
ら」、あるいはハイパーテキストの多重ウィンドウに関して、「もしRLが、もうひとつのウィンドウに過ぎないとしたら」と自分に言い聞かせるとき、彼が屈
する錯覚は、厳密には逆のもの、つまり仮想宇宙の外にある完全な現実を信じ続けるという常識的な態度と相関している。つまり、サイバースペースの外にある
外的な現実を単純に直接参照することと、"外的な現実など存在しない、RLは単なる窓の一つに過ぎない
"という正反対の態度の両方の罠を避けるべきなのだ。 |
| In the domain of sexuality, this
foreclosure of the Real gives rise to the New Age
vision of the new computerised sexuality in which bodies mix in the
ethereal virtual
space, delivered of their material weight. This vision is stricto sensu
an ideological
fantasy, since it unites the impossible: sexuality (linked to the real
of the body) with
the “mind” decoupled from the body, as if - in today’s universe where
our bodily
existence is (perceived as) more and more threatened by environmental
dangers,
AIDS, etc., to the extreme vulnerability of today’s narcissistic
subject to the actual
psychic contact with another person - we can reinvent a space where one
can fully
indulge in bodily pleasures by getting rid of our actual bodies. In
short, this vision is
that of a state without lack and obstacles, a state of free floating in
virtual space in
which nonetheless desire somehow survives... |
セクシュアリティの領域では、このような現実の差し押さえが、ニューエ
イジの、コンピュータ化された新しいセクシュアリティのビジョンを生み出している。このヴィジョンは、感覚的にはイデオロギー的なファンタジーである。な
ぜなら、不可能なこと、つまり(身体のリアルと結びついた)セクシュアリティを、身体から切り離された「心」と結びつけるからである。あたかも、環境的な
危険やエイズなどによって、私たちの身体的存在がますます脅かされている(と認識されている)今日の宇宙では、今日のナルシシズム的な主体が他者との実際
の精神的接触に対して極度に脆弱であるように、私たちは、実際の身体を取り除くことによって、身体的快楽に完全に溺れることができる空間を再発明すること
ができる。要するに、このヴィジョンは、欠乏も障害もない状態、仮想空間での自由な浮遊状態であり、その中で欲望はどうにか生き延びる......。 |
| So, instead of indulging in
these ideologies, it is far more productive to begin with
how computerisation affects the horizon of our everyday bodily
experience: the
progressive immobilisation of the body overlaps with bodily
hyperactivity. On the one
hand, I rely less and less on my proper body, my bodily activity is
more and more
reduced to giving signals to machines which do the work for me
(clicking on a
computer-mouse, etc.); on the other hand, my body is strengthened,
“hyperactivated”, through body-building and jogging, pharmaceutical
means, as well as direct implants, so that, paradoxically, the
hyperactive superman coincides with
the cripple who can only move around by means of prostheses regulated
by a
computer-chip (like the Robocop). The prospect is thus that the human
being will
gradually lose his grounding in the concrete life-world, i.e. the basic
set of coordinates which determine its (self)experience (the surface
separating inside from
outside, the direct relationship to one’s own body, etc.).
Tendentially, total
subjectivization (reduction of reality to electro-mechanically
generated cyberspace
“windows”) coincides with total objectivization (the subordination of
our “inner” bodily
rhythm to a set of stimulations regulated by external apparatuses). |
だから、このようなイデオロギーに耽溺するのではなく、コンピュータ化
が私たちの日常的な身体経験の地平にどのような影響を及ぼすかから始める方がはるかに生産的である。一方では、自分の身体に頼ることが少なくなり、自分の
身体活動は、自分の代わりに仕事をしてくれる機械に信号を与えること(コンピュータのマウスをクリックするなど)にどんどん還元されていく。他方では、身
体作りやジョギング、薬学的手段、直接的なインプラントなどによって、自分の身体は強化され、「過活性化」される。そのため、逆説的ではあるが、過活性な
スーパーマンは、コンピュータ・チップによって制御された義肢によってしか動き回れない廃人と重なる(ロボコップのように)。こうして、人間は次第に具体
的な生活世界、すなわち(自己)経験を決定する基本的な座標軸(内と外を隔てる表面、自分の身体との直接的な関係等)への根拠を失っていくことになる。傾
向的には、完全な主観化(現実を電気機械的に生成されたサイバースペースの「窓」に還元すること)は、完全な客観化(私たちの「内なる」身体のリズムを、
外部の装置によって調節された一連の刺激に従属させること)と一致する。 |
| Progressive “subjectivisation”
is thus strictly correlative to its opposite, to the
progressive “externalisation” of the hard kernel of subjectivity. This
paradoxical
coincidence of the two opposed processes has its roots in the fact
that, today, with
VR and technobiology, we are dealing with the loss of the surface which
separates
inside from outside. This loss jeopardises our most elementary
perception of “our
own body” as it is related to its environs; it cripples our standard
phenomenological
attitude towards the body of another person, in which we suspend our
knowledge of
what actually exists beneath the skin surface (glands, flesh...) and
conceive the
surface (of a face, for example) as directly expressing the “soul”. On
the one hand,
inside is always outside: with the progressive implantation and
replacement of our
internal organs, techno-computerized prostheses (bypasses,
pacemakers...) function
as an internal part of our “living” organism; the colonisation of the
outer space thus
reverts inside, into “endo-colonization”
4
, the technological colonisation of our body
itself. On the other hand, outside is always inside: when we are
directly immersed
into VR, we lose contact with reality, i.e. electro-waves bypass the
interaction of
external bodies and directly attack our senses, “it is the eyeball that
now englobes
man’s entire body.” |
従って、「主観化」の進行は、その反対、つまり主観性の硬い核の「外在
化」の進行と厳密に相関している。この2つの相反するプロセスの逆説的な一致は、今日、VRとテクノバイオロジーによって、内部と外部を隔てる表面の喪失
に対処しているという事実にその根源がある。この喪失は、「自分の身体」がその周囲に関連しているという最も初歩的な認識を危うくし、他人の身体に対する
私たちの標準的な現象学的態度を麻痺させる。この態度では、皮膚の表面の下に実際に存在するもの(腺、肉...)についての知識は保留され、(たとえば顔
の)表面は「魂」を直接表現していると考えられる。一方では、内部は常に外部である。内臓の移植と交換が進むにつれて、テクノ・コンピュータ化された人工
器官(バイパス、ペースメーカー...)は、私たちの「生きている」有機体の内部部分として機能する。こうして、外部空間の植民地化は、内部へと回帰し、
「内部植民地化」4、つまり、私たちの身体そのものの技術的植民地化となる。一方、外は常に内である。VRに直接没入するとき、私たちは現実との接触を失
う。つまり、電界波が外部との相互作用を迂回し、私たちの感覚を直接攻撃するのだ。 |
| At a more fundamental level,
however, this “derailment” - this lack of support, of a
fixed instinctual standard, in the co-ordination between the natural
rhythm of our body
and its surrounding - characterises man as such: man as such is
“derailed”, it eats
more than “natural”, it is obsessed with sexuality more than “natural”,
i.e. it follows its
drives with an excess far beyond “natural” (instinctual) satisfaction,
and this excess of
drive has to be “gentrified” through “second nature” (man-created
institutions and
patterns). The old Marxist formula about “second nature” is thus to be
taken more
literally than usual: the point is not only that we are never dealing
with pure natural
needs, that our needs are always already mediated by the cultural
process;
moreover, the labour of culture has to re-instate the lost support in
natural needs, to
re-create a “second nature” as the recompense for the loss of support
in the “first
nature” - the human animal has to re-accustom itself to the most
elementary bodily
rhythm of sleep, feeding, movement. |
しかし、より根本的なレベルでは、この「脱線」、つまり、私たちの肉体
の自然なリズムとその周囲との間の調整における、固定した本能的基準の支えの欠如が、人間というものを特徴づける。
つまり、「自然な」(本能的な)満足をはるかに超えた過剰さで欲望に従い、この過剰な欲望は「第二の自然」(人間が作り出した制度やパターン)によって
「高級化」されなければならない。第二の自然」についての古いマルクス主義の公式は、こうして通常よりも文字通りに解釈される。重要なのは、私たちが純粋
な自然的欲求を扱っていることは決してなく、私たちの欲求は常に文化的プロセスによってすでに媒介されているということだけでなく、文化の労働は、自然的
欲求における失われた支えを再び植え付け、「第一の自然」における支えの喪失の代償として「第二の自然」を再創造しなければならないということである。 |
| What we encounter here is the
loop of (symbolic) castration in which one endeavours
to reinstate the lost “natural” co-ordination on the ladder of desire:
on the one hand,
one reduces the bodily gestures to the necessary minimum (of the clicks
on the
computer-mouse...), on the other hand, one attempts to recover the lost
bodily fitness
by means of jogging, body-building, etc.; on the one hand, one reduces
the body
odours to a minimum (by regularly taking showers, etc.), on the other
hand, one attempts to recover these same odours through toilet-waters
and perfumes; etc.etc. |
ここで私たちが遭遇するのは、(象徴的な)去勢のループであり、人は欲
望の梯子の上で、失われた「自然な」協調性を取り戻そうとする。
一方では、ジョギングやボディービルなどによって、失われた体力回復を試みる。一方では、(定期的にシャワーを浴びるなどして)体臭を最小限に抑え、他方
では、トイレットウォーターや香水によって、同じ臭いを回復しようと試みる。 |
| This paradox is condensed in the
phallus as the signifier of desire, i.e. as the point of
inversion at which the very moment of “spontaneous” natural power turns
into an
artificial prosthetic element. That is to say, against the standard
notion of phallus as
the siege of male “natural” penetrative-aggressive potency-power (to
which one then
opposes the “artificial” playful prosthetic phallus), the point of
Lacan’s concept of the
phallus as a signifier is that the phallus “as such” is a kind of
“prosthetic”, “artificial”
supplement: it designates the point at which the big Other, a
decentered agency,
supplements the subject’s failure. When, in her criticism of Lacan,
Judith Butler
emphasises the parallel between mirror-image (ideal-ego) and phallic
signifier6
, one
should shift the focus onto the feature they effectively share: both
mirror-image and
phallus qua signifier are “prosthetic” supplements for the subject’s
foregoing
dispersal/failure, for the lack of co-ordination and unity; in both
cases, the status of
this prosthesis is “illusory”, with the difference that, in the first
case, we are dealing
with imaginary illusion (identification with a decentered immobile
image), while in the
second case, the illusion is symbolic, it stands for phallus as pure
semblance. |
この逆説は、欲望の記号としてのファルス、すなわち「自然発生的な」自
然の力が人工的な補綴的要素に変わるまさにその瞬間の反転点として凝縮されている。つまり、男性の「自然な」貫通力-攻撃力-力の包囲としてのファルスと
いう標準的な概念(それに対して、「人工的な」遊び心のある補綴的なファルスを対抗させる)に対して、ラカンのシニフィアンとしてのファルスの概念のポイ
ントは、「そのような」ファルスが一種の「補綴的な」、「人工的な」補足であるということである。ラカン批判の中で、ジュディス・バトラーが鏡像(理想自
我)と男根のシニフィアン6 の並列を強調するとき、両者が事実上共有している特徴に焦点を移すべきである:
どちらの場合も、このプロテーゼの地位は「幻想的」であるが、第一の場合、われわれは想像上の幻想(中心を失った不動のイメージとの同一化)を扱っている
のに対して、第二の場合、幻想は象徴的であり、それは純粋な意味としてのファルスを表しているという違いがある。 |
| Cyberspace thus poses a threat
to the fundamental limit between “inside” and
“outside”, surface and bodily depth, which accounts for our everyday
experience; the
threat to this limit determines today’s form of the hysterical
question, i.e. today,
hysteria stands predominantly under the sign of vulnerability, of a
threat to our bodily
and/or psychic identity - suffice it to recall the all-pervasiveness of
the logic of
victimisation, from sexual harassment to the dangers of food and
tobacco, so that the
subject itself is more and more reduced to “that which can be hurt”.
Today’s form of
the obsessional question “Am I alive or dead?” is “Am I a machine (does
my brain
really function as a computer) or a living human being (with a spark of
spirit or
something else irreducible to the computer-circuit)?”; it is not
difficult to discern in this
alternative the split between A (Autre) and J (Jouissance), between the
“big Other”,
the dead symbolic order, and the Thing, the living substance of
enjoyment. According
to Sherry Turkle, our reaction to this question goes through three
phases: first, the
emphatic assertion of an irreducible difference: man is not a machine,
there is
something unique about it...; then, fear and panic when we become aware
of all the
potentials of a machine: it can think, reason, answer our questions...;
finally,
disavowal, i.e. recognition through denial: the guarantee that there is
some feature of
man inaccessible to the computer (sublime enthusiasm, anxiety...)
allows us to treat
the computer as a “living and thinking partner”, since “we know this is
only a game, a
computer is not really like that”. Suffice it to recall the way John
Searle’s polemics
against AI (his Chinese Room thought experiment) was “gentrified” and
integrated
into the user’s everyday attitude: Searle has proven that a computer
cannot really
think and understand language - so, since there is the
ontological-philosophical
guarantee that the machine does not pose a threat to human uniqueness,
I can
calmly accept the machine and play with it... Is this split attitude in
which “disavowal
and appropriation are each tied up with the other”
7
, not a new variation on the old
philosophical game of “transcendental illusion” practised already by
Kant apropos of
the notion of teleology - since I know a computer cannot think, I can
act, in my
everyday life, as if it really does think? - At a different level, this
same ambiguity
determines the way we relate to our screen personae: |
この限界への脅威が、今日のヒステリックな問いの形を決定している。こ
の限界への脅威が、今日のヒステリックな問いの形式を決定する。今日、ヒステリー
は、脆弱性、私たちの身体的/精神的アイデンティティへの脅威という徴候の下に主に立っている。セクシャル・ハラスメントから食べ物やタバコの危険性に至
るまで、被害者化の論理が蔓延していることを思い起こせば十分である。私は生きているのか、死んでいるのか」という強迫観念的な問いの今日
の形は、「私は機械なのか(私の脳は本当にコンピューターとして機能しているのか)、それとも生きている人間なのか(コンピューター回路には還元できない
精神の輝きや何か他のものをもっているのか)」である。この選択肢の中に、A(オートレ)とJ(ジュイサンス)の分裂、「大きな他者」、つまり死んだ象徴
秩序と、「もの」、つまり享受の生きた実体との分裂を見出すことは難しくない。シェリー・タークルによれば、この問いに対するわれわれの反応は3つの段階
を経る。まず、還元しがたい差異を強調的に主張する。
最後に、否認、つまり否定による認識:コンピュータにはアクセスできない人間の特徴(崇高な熱狂、不安...)があるという保証があるからこそ、私たちは
コンピュータを「生きて考えるパートナー」として扱うことができる。ジョン・サールのAIに対する極論(彼の「中国の部屋」での思考実験)が「高級化」さ
れ、ユーザーの日常的な態度に組み込まれた方法を思い起こせば十分だろう:
サールは、コンピューターが本当に考えたり言語を理解したりすることはできないと証明した。だから、機械が人間の独自性を脅かすものではないという存在論
的・哲学的保証があるから、私は冷静に機械を受け入れ、機械と遊ぶことができる...」。この「否認と充当がそれぞれ他と結びついている」7
という分裂した態度は、カントがすでにテ レオロジーの概念で実践していた「超越論的幻想」という古い哲学的ゲームの新しいバリエー
ションではないのだろうか。- 別の次元では、この同じ曖昧さが、スクリーン上のペルソナとの関わり方を決定する: |
| - on the one hand, we maintain
the attitude of external distance, of playing with false
images: “I know I’m not like that (brave, seductive...), but it’s nice,
from time to time,
to forget one’s true self and to put on a more satisfying mask - this
way, you can
relax, you are delivered of the burden to be what you are, to live with
yourself and to
be fully responsible for it...” |
- 一方では、外的な距離を保ち、虚像と戯れる:
「自分はそんな人間ではない(勇敢で、魅惑的で......)とわかっているが、時々は本当の自分を忘れて、より満足のいく仮面をかぶるのもいいものだ。
こうすればリラックスできるし、ありのままの自分でいる重荷から解放され、自分自身とともに生き、それに全責任を負うことができる......」。 |
| - on the other hand, the screen
persona I create for myself can be “more myself than
my “real-life” person (my “official” self-image), insofar as it renders
visible aspects of
myself I would never dare to admit in RL. Say, when I play anonymously
in MUD, I
can present myself as a promiscuous woman and engage in activities
which, were I
to indulge in them in RL, would bring about the disintegration of my
sense of personal
identity... This is one of the ways to read Lacan’s dictum “truth has
the structure of a
fiction”: I can articulate the hidden truth about my drives precisely
insofar as I am
aware that I’m just playing a game on the screen. In cyberspace sex,
there is no
“face to face”, just the external impersonal space in which everything,
inclusive of my
most intimate internal fantasies, can be articulated with no
inhibitions... What one
encounters here, in this pure “flux of desire”, is, of course, the bad
surprise of
“repressive desublimation” (if we are to borrow this term from Herbert
Marcuse): the
universe freed of everyday inhibitions turns out to be the universe of
unbridled
sadomasochistic violence and will to domination... |
-
その一方で、スクリーンに映し出される自分のペルソナは、RLでは決して認めることのできない自分の側面を可視化する限りにおいて、「現実の自分(「公式
な」自己イメージ)よりも自分らしい」ものになりうる。例えば、MUDで匿名でプレイしているとき、私は乱れた女性であることを示すことができ、RLでそ
れに耽溺していたら、私の個人的なアイデンティティの感覚を崩壊させるような行為に従事することができる...。これは、ラカンの「真実は虚構の構造を持
つ」という言葉を読み解く一つの方法である:
私は、自分がスクリーン上でゲームをしているだけだと自覚している限りにおいてこそ、自分の衝動に関する隠された真実を明確に語ることができるのだ。サイ
バースペースでのセックスでは、"face to face
"は存在せず、ただ外的な非人間的空間において、私の最も親密な内的ファンタジーを含むすべてを、何の抑制もなく表現することができる...。この純粋な
"欲望の流転 "の中で遭遇するのは、もちろん
"抑圧的脱昇華"(この言葉をヘルベルト・マルクーゼから借りるなら)という悪い驚きである。日常的な抑制から解放された宇宙は、奔放なサドマゾ的暴力と
支配への意志の宇宙であることが判明する...。 |
| In order to conceptualise the
two poles of this undecidability, Turkle resorts to the
opposition between “acting out” and “working through” the difficulties
of RL9
: I can
follow the escapist logic and simply act out my RL difficulties in VR,
or I can use VR
to become aware of the inconsistency and multiplicity of the components
of my
subjective identifications and work them through. In this second case,
the interface
screen functions in a way homologous to the psychoanalyst: the
suspension of the
symbolic rules which regulate my RL activity enables me to
stage-externalise my
repressed content which I am otherwise unable to confront. The same
ambiguity is
reproduced in the impact of cyberspace on community life. On the one
hand, there is
the dream of the new populism, where decentralised networks will allow
individuals to
band together and build a participatory grass-roots political system, a
transparent
world in which the mystery of the impenetrable bureaucratic state
agencies is
dispelled. On the other hand, the use of computers and VR as a tool to
rebuild
community results in the building of a community inside the machine,
reducing
individuals to isolated monads, each of them alone, facing a computer,
ultimately
unsure if the person s/he communicates with on the screen is a “real”
person, a false
persona, an agent which combines several “real” persons or a
computerised
program... Again, the ambiguity is irreducible. |
この決定不可能性の両極を概念化するために、タークルはRLの困難を
「演じる」ことと「やり抜く」ことの対立に頼っている9:私は逃避主義の論理に従って、単純にVRの中でRLの困難を演じることもできるし、VRを使って
自分の主観的同一性の構成要素の矛盾と多重性に気づき、それをやり抜くこともできる。この2つ目のケースでは、インターフェイスのスクリーンは精神分析医
と同じような働きをする。私のRL活動を規制する象徴的なルールが一時停止されることで、他の方法では直面することのできない抑圧された内容を段階的に外
在化することができるのだ。同じ曖昧さは、サイバースペースがコミュニティ生活に与える影響にも再現される。一方では、新しいポピュリズムの夢があり、そ
こでは分散型ネットワークによって個人が団結し、参加型の草の根政治システムを構築することができる。その一方で、コミュニティを再構築するためのツール
としてコンピューターやVRを使うことは、結果的に機械の中にコミュニティを構築することになり、個人を孤立したモナド(単細胞生物)へと落とし込むこと
になる。ここでも曖昧さは解消できない。 |
| However, this ambiguity,
although irreducible, is not symmetrical. What one should introduce
here is the elementary Lacanian distinction between imaginary
projectionidentification and symbolic identification. The most concise
definition of symbolic
identification is perhaps that it consists in a mask which is more real
and binding than
the true face beneath it (in accordance with Lacan’s notion that the
human feigning is
the feigning of feigning itself: in imaginary deception, I simply
present a wrong image
of myself, while in symbolic deception, I present a true image and
count on it being
taken for a lie...10). A husband, for example, can maintain his
marriage as just
another social role and engage in adultery as “the real thing”;
however, the moment
he is confronted with the choice of actually leaving his wife or not,
he suddenly
discovers that the social mask of marriage means more to him than the
intense
private passion... The VR persona thus offers a case of imaginary
deception insofar
as it externalises-displays a wrong image of myself (a fearful man
playing a hero in
MUD...), and a symbolic deception insofar as it renders the truth about
myself in the
guise of a playful game (by way of playfully adopting an aggressive
persona, I
disclose my true aggressivity). |
しかし、この両義性は還元可能ではあるが、対称的なものではない。ここ
で紹介すべきは、想像的投影同一化と象徴的同一化というラカン流の初歩的な区別である。象徴的同一化の最も簡潔な定義は、おそらくそれは、その下にある本
当の顔よりも現実的で拘束力のある仮面から成るということである(人間の仮装は仮装そのものの仮装であるというラカンの概念に従っている:想像的欺瞞で
は、私は単に自分自身の間違ったイメージを提示するだけであるが、象徴的欺瞞では、私は本当のイメージを提示し、それが嘘と受け取られることを当てにす
る...10)。しかし、実際に妻と別れるかどうかの選択を迫られた瞬間、彼は突然、結婚という社会的仮面が、私的な激しい情熱よりも自分にとって重要で
あることに気づく...。このように、VRのペルソナは、自分自身の間違ったイメージ(MUDでヒーローを演じる怖がりな男...)を外在化させて見せる
という点で、想像的欺瞞のケースを提供し、遊びのゲームを装って自分自身の真実を明らかにするという点で、象徴的欺瞞のケースを提供する(遊び心を持って
攻撃的なペルソナを採用することで、自分の本当の攻撃性を明らかにする)。 |
| In other words, VR confronts us,
in the most radical way imaginable, with the old
enigma of transposed/displaced emotions at work from the so-called
“weepers”
(women hired to cry at funerals) in “primitive” societies to the
“canned laughter” on
TV: when I adopt a screen persona on MUD, the emotions I feel and
“feign” as part of
my screen persona are not simply false: although (what I experience as)
my “true
self” does not feel them, they are nonetheless in a sense “true” -the
same as with
watching a TV mini-series with canned laughter where, even if I do not
laugh, but just
stare at the screen, tired after a hard day’s work, I nonetheless feel
relieved after the
show... This is what the Lacanian notion of decentered subject aims at:
my most
intimate feelings can be radically externalised, I can literally “laugh
and cry through
an other”. More generally, this mystery is the mystery of the symbolic
order as such
as exemplified by the enigmatic status of what we call “politeness”:
when, upon
meeting an acquaintance, I say “Glad to see you! How are you today?”,
it is clear to
me and to him that, in a way, I “do not mean it seriously” (if my
partner suspects that I
am really interested in how he is, he may even be unpleasantly
surprised, as if I am
aiming at something too intimate and of no concern to me). It would
nonetheless be
wrong to designate my act as simply “hypocritical”, since, in another
way, I do mean
it: the polite exchange does establish a kind of pact between the two
of us - in the
same sense as I do “sincerely” laugh through the canned laughter (the
proof being
the fact that I effectively do “feel relieved” afterwards). |
言い換えれば、VRは、「原始的な」社会におけるいわゆる「泣き女」
(葬式で泣くために雇われた女性)からテレビの「笑いの定型文」に至るまで、転置/置換された感情という古くからの謎に、想像しうる最も根本的な方法で私
たちを直面させる:
本当の自分」が感じているわけではないが、ある意味で「本当の自分」なのである。テレビのミニシリーズを笑いの定型文つきで見ているとき、たとえ自分が笑
わず、ただ画面を見つめていたとしても、一日の仕事を終えて疲れていたとしても、番組が終わるとほっとするのと同じである。 ..
私の最も親密な感情を根本的に外在化し、文字通り「他者を通して笑い、泣く」ことができるのだ。もっと一般的に言えば、この謎は、私たちが「礼儀正しさ」
と呼ぶものの謎めいた地位に代表されるように、象徴秩序の謎である!知人に会ったとき、「お会いできてうれしいです!」「ご機嫌いかがですか!」と言うと
き、ある意味で私が「本気で言っているわけではない」ことは、私にも彼にも明らかである(もし相手が、私が彼の様子に本当に興味を持っているのではないか
と疑っているとしたら、彼は不愉快に驚くかもしれない。)
それにもかかわらず、私の行為を単に「偽善的」だと決めつけるのは間違いだろう。別の意味で、私は本気なのだから。丁寧なやりとりは、私たち二人の間に一
種の協定を確立している--私が定型文の笑いによって「心から」笑っているのと同じ意味で(その証拠に、そのあと私は事実上「ほっとした」気分になる)。 |
| At a somewhat different level,
we encounter the same paradox apropos of TinySex:
what TinySex compels us to accept is the blurred line of separation
between “things”
and “mere words”. Their separation is not simply suspended, it is still
here, but
displaced - a third realm emerges which is neither “real things” nor
“merely words”,
but demands its own specific (ethical) rules of conduct. Let us
consider virtual sex:
when I play sex games with a partner on the screen, exchanging “mere”
written
messages, it is not only that the games can effectively arouse me or my
partner and
provide us with a “real” orgasmic experience (with the further paradox
that, when -
and if – I later encounter my partner in RL, I can be deeply
disappointed, turned off: |
タイニーセックスが私たちに受け入れさせるのは、「モノ」と「単なる言
葉」の間の曖昧な境界線である。その分離は単に中断されているのではなく、まだここにあるのだが、ずらされているのだ。「現実のもの」でも「単なる言葉」
でもない第三の領域が出現し、独自の(倫理的な)行動規範を要求する。バーチャル・セックスについて考えてみよう。私がスクリーン上でパートナーとセック
ス・ゲームをし、「単なる」文字メッセージを交換するとき、ゲームが私やパートナーを効果的に興奮させ、私たちに「本物の」オーガズム体験を提供すること
ができるだけではない: |
| my on-screen experience can be
in a sense “more real” than the encounter in reality);
it is not only that, beyond mere sexual arousal, me and my partner can
“really” fall in
love with each other without meeting in RL. What if, on the net, I rape
my partner? On
the one hand, there is a gap which separates it from RL - what I did
remains in a
sense closer to impoliteness, to rude, offensive talk. On the other
hand, it can cause
a deep offence, even an emotional catastrophe, which is not reducible
to “mere
words”.... And, back to Lacan: what is this middle-mediating level,
this third domain
interposing itself between “real life” and “mere imagination”, this
domain in which we
are not directly dealing with reality, but also not with “mere words”
(since our words
do have real effects), if not the symbolic order itself? |
単
なる性的興奮にとどまらず、私とパートナーは現実に会わなくても「本当に」恋に落ちることができるのだ。ネット上でパートナーをレイプしてしまったら?一
方では、RLとは隔たりがある。私がしたことは、ある意味、無作法で攻撃的な話し方に近いままだ。その一方で、「単なる言葉」では済まされないような、深
い不快感や感情的な大惨事を引き起こすこともある......。そして、ラカンの話に戻ろう。この中間の媒介的なレベル、「現実生活」と「単なる想像」の
間に介在する第三の領域、私たちが現実を直接扱っているのでもなく、「単なる言葉」を扱っているのでもないこの領域(私たちの言葉は現実的な効果をもたら
すのだから)とは、象徴秩序そのものでないとすれば、何なのだろうか? |
| When deconstructionist
cyberspace-ideologists (as opposed to the predominant New
Age cyberspace-ideologists) try to present cyberspace as providing a
“real life”,
“empirical”, realisation or confirmation of the deconstructionist
theories, they usually
focus on how cyberspace “decenters” the subject. However, it is crucial
to introduce
here the distinction between “Self” (“person”) and subject: the
Lacanian “decentered
subject” is not simply a multiplicity of good old “Selves”, i.e.
partial centres; the
“divided” subject does not mean there are simply more Egos/Selves in
the same
individual, as in the so-called “Multiple Personality Disorders”. The
“decentering” is
the decentering of the $ (the void of the subject) with respect to its
content (“Self”, the
bundle of imaginary and/or symbolic identifications); the “splitting”
is the splitting
between $ and the fantasmatic “persona” as the “stuff of the I”. The
subject is thus
split even if it possesses only one “unified” Self, since this split is
the very split
between $ and Self... In more topological terms: the subject’s division
is not the
division between one and another Self, between two contents, but the
division
between something and nothing, between the feature of identification
and the void. |
脱構築主義のサイバースペース理想主義者(ニューエイジのサイバース
ペース理想主義者が
主流であるのとは対照的である)が、サイバースペースを、脱構築主義の理論の「現実的な」、「経験的な」、実現や確証を提供するものとして提示しようとす
るとき、彼らは通常、サイバースペースがいかに主体を「脱中心化」するかに焦点を当てる。ラカン的な「脱中心化された主体」とは、単に古き良き「自我」の
多重性、すなわち部分的な中心を意味するものではない。脱中心化」とは、その内容(「自己」、想像的および/または象徴的同一性の束)に対する$(主体の
空虚)の脱中心化であり、「分裂」とは、$と「私のもの」としての空想的「ペルソナ」との分裂である。この分裂はまさに「私」と「私」の分裂なのだから。
より位相幾何学的な言い方をすれば、主体の分裂は、一つの自己ともう一つの自己、二つの内容の分裂ではなく、何かと無、同一性の特徴と空虚の分裂なのであ
る。 |
| This pure substanceless subject
beyond imaginary and/or symbolic identifications is
correlative to the dimension of the Real - it is, as Jacques-Alain
Miller put it, an
“answer of the real”. One can approach this Real through the difference
between
imitation and simulation11: VR doesn’t imitate reality, it simulates it
by way of
generating its semblance. Imitation imitates a pre-existing real-life
model, whereas
simulation generates the semblance of a non-existing reality - it
simulates something
that doesn’t exist. Let us take the most elementary case of virtuality
in a computer,
the so-called “virtual memory”: a computer can simulate far greater
memory than it
actually has, i.e. it can function as if its memory is larger than it
effectively is. And
does the same not hold for every symbolic arrangement, up to the
financial system
which simulates a far larger extent of coverage than it is effectively
able to provide?
The entire system of deposits etc. works on the presupposition that
anyone can, at
any moment, withdraw his or her money from the bank; - a presupposition
which,
although it can never be realised, nonetheless renders possible the
very “real”,
“material” functioning of the financial system... |
こ
の、想像や象徴の同一性を超えた純粋な実体なき主体は、リアルの次元と相関している。ジャック=アラン・ミレールが言うように、それは「リアルの答え」な
のだ。VRは現実を模倣するのではなく、その類似性を生み出すことで現実をシミュレートする。模倣は現実に存在するモデルを模倣するのに対し、シミュレー
ションは存在しない現実の似姿を生成する--つまり、存在しないものをシミュレーションするのだ。コンピュータにおける仮想性の最も初歩的なケース、いわ
ゆる「仮想メモリ」を例にとってみよう。コンピュータは、実際に持っているよりもはるかに大きなメモリをシミュレートすることができる。同じことが、あら
ゆる象徴的な取り決めにも当てはまるのではないだろうか。金融システムに至っては、実際に提供できる範囲よりもはるかに広い範囲をシミュレートしている。
預金などのシステム全体は、誰でも、いつでも、自分のお金を銀行から引き出すことができるという前提のもとに機能している。この前提は、決して実現するこ
とはできないが、それにもかかわらず、金融システムのまさに「現実的」で「物質的」な機能を可能にしている...。 |
| The consequences of this
difference between imitation and simulation are more
radical than may appear. In contrast to imitation, which sustains
belief in pre-existing
“organic” reality, simulation retroactively “denaturalises” reality
itself by way of
disclosing the mechanism responsible for its generation. In other
words, the
“ontological wager” of simulation is that there is no ultimate
difference between nature and its artificial reproduction - there is a
more elementary level of the Real
with reference to which both simulated screen-reality and “real”
reality are generated
effects, the Real of pure computation: behind the event viewed through
the interface
(the simulated effect of reality), there is pure subjectless
(“acephalic”) computation, a
series of 1 and 0, of + and -. In his Seminar II12, where Lacan
develops for the first
time this notion of the series of + and -, he reduces it precipitously
to the order of the
signifier, for that reason, one should reread these passages from the
perspective of
the opposition between signifier and letter (or writing) established in
Seminar XX13:
subjectless digital computation is neither the differential symbolic
order (the symbolic
realm of meaning is part of the pseudo-reality manipulated on the
screen) nor reality
outside the screen of the interface (in bodily reality behind the
screen, there are only
chips, electric current, etc.). The wager of VR is that the universe of
meaning, of
narrativization, is not the ultimate reference, the unsurpassable
horizon, since it relies
on pure computation. Therein resides the gap that separates forever
Lacan from
postmodernist deconstructionism: the latter conceives science as one of
the possible
local narrativizations, whereas for Lacan, contemporary science enables
us to gain
access to the Real of pure computation which underlies the play of
multiple
narrarivizations. This is the Lacanian Real: the purely virtual, “not
really existing”,
order of subjectless computation which nonetheless regulates every
“reality”, material
and/or imaginary. CYBERSPACE, OR THE VIRTUALITY OF THE REAL(https://x.gd/RqRxB) |
模
倣とシミュレーションのこの違いがもたらす結果は、見た目以上に根本的である。既存の "有機的
"な現実を信じる模倣とは対照的に、シミュレーションは、その生成の原因となるメカニズムを開示することによって、現実そのものを遡及的に "非自然化
"する。言い換えれば、シミュレーションの「存在論的賭け」とは、自然とその人工的複製との間に究極的な違いはないということである。シミュレートされた
画面上の現実と「現実」の現実の両方が生成された効果であり、純粋な計算の現実である、より初等的な現実のレベルが存在する。ラカンは『セミナー
II12』において、この「+」と「-」の系列という概念を初めて展開するが、彼はそれをシニフィエの秩序へと峻厳に還元する:
主語のないデジタル計算は、差延的な記号秩序(意味の記号的領域は、スクリーン上で操作される擬似現実の一部である)でもなければ、インターフェイスのス
クリーンの外側の現実(スクリーンの裏側の身体的現実には、チップや電流などがあるだけである)でもない。 ).
VRの賭けは、純粋な計算に依存しているため、意味の宇宙、物語化の宇宙は、究極の参照、超えられない地平ではないということだ。後者は科学を可能な局所
的な物語化の一つとして考えているのに対し、ラカンにとって現代科学は、複数の物語化の戯れの根底にある純粋な計算の実在にアクセスすることを可能にして
いる。これがラカン的リアルである。純粋にヴァーチャルな、「実際には存在しない」、主体なき計算の秩序は、それにもかかわらず、物質的であれ想像的であ
れ、あらゆる「現実」を支配している。 |
| TinySex, also known as TS or
tiny.sex and other variations, is a specific subset of Cybersex.
Cybersex refers to a virtual sex encounter in which two or more persons
connected remotely via a computer network send one another sexually
explicit messages describing a sexual experience. It is a form of
role-playing in which the participants pretend they are having actual
sexual relations. In one iteration, this fantasy sex is accomplished by
the participants describing their actions and responding to their chat
partners in a mostly written form designed to stimulate their own
sexual feelings and fantasies. - https://en.wikifur.com/wiki/TinySex |
TinySex
は、TSまたはtiny.sexやその他のバリエーションとしても知られ、Cybersexの特定のサブセットである。サイバーセックスとは、コンピュー
タネットワークを介して遠隔接続された2人以上の人物が、性的な体験を描写した露骨なメッセージを送り合う、バーチャルなセックスのことを指す。これは、
参加者が実際の性的関係を持っているふりをするロールプレイングの一形態である。ある反復では、このファンタジー・セックスは、参加者が自分自身の性的感
情や妄想を刺激するようにデザインされた、主に書かれた形式で、自分の行動を記述し、チャット相手に応答することによって達成される。 |
| A
MUD (acronym for Multi-User Dungeon) is an online role-playing game
that is usually text-based and accessable through telnet, as well as a
variety of MUD clients.
Each MUD has its own sets of rules and policies. Some MUDs allow
players to be out of character (OOC) as much as they like, while others
require them to be in character (IC) more often, or always. Rules can
vary in different areas of the MUD.
Unlike MOOs, MUDs are static environments that may contain objects that
have descriptions and limited actions. While more advanced text-based
environments allow for complicated object-heirarchy models to create a
feature-rich world, MUD's are more akin to chatrooms that have
describable objects.
While more chatty mediums such as IRC are more prone to idle users and
periods of non-activity, MUD's typically disconnect idle users, so the
ability to find partners for role-play are greater on a MUD or MUCK. https://en.wikifur.com/wiki/MUD |
MUD
(マルチユーザーダンジョンの頭文字)とは、オンラインのロールプレイングゲームのことで、通常はテキストベースで、telnetやさまざまなMUDクラ
イアントからアクセスできる。それぞれのMUDは独自のルールとポリシーを持っている。あるMUDでは、プレイヤーは好きなだけキャラクターから外れて
(OOC)遊ぶことができますが、あるMUDでは、より頻繁に、または常にキャラクター内にいる(IC)必要がある。ルールはMUDのエリアによって異な
ります。MOOとは異なり、MUDは静的な環境であり、説明と制限された行動を持つオブジェクトを含むかもしれない。より高度なテキストベースの環境で
は、機能豊富な世界を作るために複雑なオブジェクト階層モデルを使うことができるが、MUDは記述可能なオブジェクトを持つチャットルームに似ている。
IRCのようなチャットの多いメディアは、アイドルユーザーや活動しない期間が発生しやすいが、MUDは通常アイドルユーザーを切断する。 |
リンク
文献
その他の情報


Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆