Références
1. Daniel Mouchard, « Intellectuel spécifique », Dictionnaire des
mouvements sociaux, Presses de Sciences Po, 2009, p. 307.
2. Michelle Perrot, « La leçon des ténèbres. Michel Foucault et la
prison », in Les Ombres de l'histoire. Crime et châtiment au XIXè
siècle. Flammarion, Paris, 2001, p. 31
3. Perrot (2001), p. 34.
4. Cité par Perrot (2001), p. 28.
5. Perrot (2001), p. 27.
6. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,
lire en ligne [archive]), p. 27
7. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,
lire en ligne [archive])
8. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,
lire en ligne [archive]), p. 14
9. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,
lire en ligne [archive]), p. 15
10. Michel Foucault, Surveiller et punir, naissance de la prison,
Paris, Gallimard, 1975, p. 18.
11. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,
lire en ligne [archive]), p. 17
12. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,
lire en ligne [archive]), p. 18
13. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,
lire en ligne [archive]), p. 21
14. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,
lire en ligne [archive]), p. 31
15. Illustration par gravure figurant dans l'ouvrage [archive]
16. Jacques Léonard, « L'historien et le philosophe : À propos de
«Surveiller et punir. Naissance de la prison », Annales historiques de
la Révolution française, no 228, 1977, pp. 163-181 (lire en ligne
[archive])
17. Michelle Perrot (dir.), L'Impossible prison. Recherches sur le
système pénitentiaire au XIXe siècle, Paris, Seuil, L'univers
historique, pp. 40-55
18. Jacques Léonard, « L'historien et le philosophe : À propos de
«Surveiller et punir. Naissance de la prison» », Annales historiques de
la Révolution française, vol. 228, no 1, 1977, p. 163–181 (DOI
10.3406/ahrf.1977.4050, lire en ligne [archive], consulté le 21 juillet
2024)
|
参考文献
1. Daniel Mouchard, 「Intellectuel spécifique」, Dictionnaire des
movements sociiaux, Presses de Sciences Po, 2009, p. 307.
2. Michelle Perrot, "La leçon des ténèbres. Michel Foucault et la
prison", in Les Ombres de l'histoire. Michel Foucault et la prison", in
Les Ombres de l'histoire. Flammarion, Paris, 2001, p. 31.
3. Perrot (2001), p. 34.
4. Perrot (2001), p. 28より引用。
5. Perrot (2001), p. 27.
6. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,
read online [archive]), p. 27.
7. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 and 978-2-07-029179-3, OCLC
1504053, read online [archive]).
8. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 and 978-2-07-029179-3, OCLC
1504053, read online [archive]), p. 14.
9. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 and 978-2-07-029179-3, OCLC
1504053, online reading [archive]), p. 15.
10. Michel Foucault, Surveiller et punir, naissance de la prison,
Paris, Gallimard, 1975, p. 18.
11. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 et 978-2-07-029179-3, OCLC 1504053,
available online [archive]), p. 17.
12. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 and 978-2-07-029179-3, OCLC
1504053, available online [archive]), p. 18.
13. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 and 978-2-07-029179-3, OCLC
1504053, online reading [archive]), p. 21.
14. Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,
Gallimard, 1975 (ISBN 2-07-029179-0 and 978-2-07-029179-3, OCLC
1504053, online reading [archive]), p. 31.
15. 本書に掲載されているエングレーヴィングによるイラスト [archive].
16. Jacques Léonard, 「L'historien et le philosophe: À propos de
」Surveiller et punir. Naissance de la prison", Annales historiques de
la Révolution française, no 228, 1977, pp.
17. Michelle Perrot (ed.), L'Impossible prison. Recherches sur le
système pénitentiaire au XIXe siècle, Paris, Seuil, L'univers
historique, pp.
18. Jacques Léonard, 「L'historien et le philosophe: À propos de
」Surveiller et punir. Naissance de la prison", Annales historiques de
la Révolution française, vol. 228, no 1, 1977, pp. 228, no 1, 1977, pp.
163-181 (DOI 10.3406/ahrf.1977.4050, read online [archive], accessed 21
July 2024). |
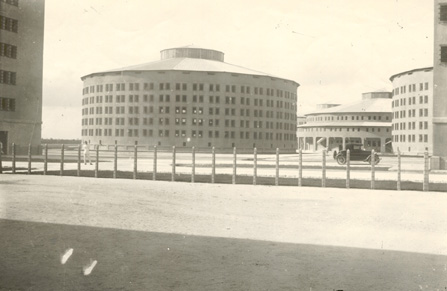
![]()




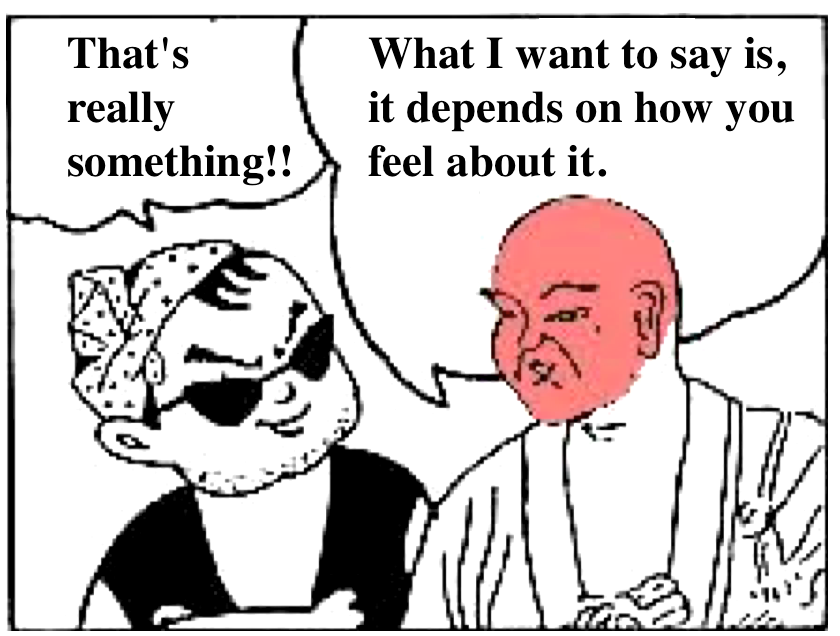

 ☆
☆