いくたびもミッシェル
Memento Michel, 1926-1984
いくたびもミッシェル
Memento Michel, 1926-1984


■ 年譜:ウィキペディア(日本語・英語)「ミッシェル・フーコー」「Michel Foucault」 などにより作成。これと類似のサイト内ファイルに「ミッシェル・フーコー」があ ります。
1926年10月15日 ポワティエにて生まれる
1938 フッサール『ヨーロッパ諸学の危機と超越
論的現象学』死後公刊(1936〜1938年までハンガリーのベオグラードの哲学雑誌『フィロソフィア』で発表)
1943年6月 バカロレア(大学入学資格試験)に 合格
1945年 高等師範学校(Ecole Normale Supérieure)の試験を受けるも不合格
1946 高等師範学校合格(エコール・ノルマル〜 1951)
1948 自殺未遂事件
1950 大学教員資格試験に失敗
1950 6月17日再度、自殺未遂事件
1951 大学教員資格試験に合格。リール大学の助 手
1954 『精神疾患とパーソナリティ』(中山元・ 訳、筑摩書房[文庫])Maladie mentale et Personnalit・ Paris: PUF, 1954.
1955-1958
スウェーデン・ウプサラでフラ ンス会館館長就任。ウプサラ大学でフランス語を教え るかたわら、ウプサラ大学図書館(「ヴァレール文庫」と呼ばれる近代医学史関係の重要書を網羅したコレクションがある)に通いつめ、博士論文である『狂気 の歴史』を著す。
1958 10月〜1959年 ポーランド滞在。
「監視されていることを知っているポーランド人は、 親しくない人の受託には、いたるところに隠しマイクがとりつけられていることを知っているので、そうし た人に何かを話そうとするときは、街路で待っているものです。そのときの沈黙と、ごくありふれた身振り(みぶり)のうちに、レストランで声を小さくして語 る話しかたのうちに、手紙を燃やす身振りのうちに、息詰まるようなあらゆる種類の身振りのうちに、そして大学のキャンパスを襲うチュニジアの警察のむき出 しで野蛮な暴力のうちに、わたしは権力がもたらすある種の身体的な経験を、そして身体と権力との関係の経験を味わったのです」(フーコー2008 [June, 1975]:37)。出典:フーコー,ミッシェル『私は花火師です』中山元訳、筑摩書房、2008年
1961
『狂気の歴史』(Histoire
de la folie à l'âge
classique)とは、西欧の歴史において狂気を扱った文化と法律、政治、哲学、思想、制度、芸術そして医学などにおける、狂気の意味の展開の考察で
あり―そして歴史の理念及び歴史学研究法の理念の批判である、ミシェル・フーコーの1961年の著作である。フランス語の教師をしていたスウェーデンのウ
プサラで第一稿が書かれたが(ウプサラ大学図書館の医学文庫が重要な役割を果たした)、スウェーデンにおける博士論文提出を拒否され、その後ワルシャワ、
パリで完成された。『狂
気の歴史』はソルボンヌ大学に博士論文として提出され(審査員はジョルジュ・カンギレム、ダニエル・ラガーシュ(英語版、フランス語版))、同時に『狂気
と非理性、古典主義時代における狂気の歴史』というタイトルで1961年にプロン社(英語版、フランス語版)から出版された。出版された本書に対して、
フェルナン・ブローデル、モーリス・ブランショは熱烈な賛辞を送っている。その後、1972年、初版の序文を削除した現在の版『古典主義時代における狂気
の歴史』が、ガリマール社「歴史学叢書」から再刊された。
1962 『精神疾患と心理学』(神谷美恵子・訳、 みすず書房)Maladie mentale et Psychologie (Paris: PUF, 1962). = second and extensively revised edition of Maladie mentale et Personnalte
1963 『臨床医学の誕生』(神谷美恵子・訳、み すず書房)Naissance de la clinique: une archaologie du regard m仕ical (Paris: PUF, 1963).
1963 『レーモン・ルーセル』(豊崎光一・訳、 法政大学出版局)Raymond Roussel. (Paris: Gallimard, 1963), date of issue May 1963.
1966 『言葉と物』(渡辺一民ほか訳、新潮社) Les Mots et les Choses. Une archaologie des sciences humaines. Paris 1966.
1966-1968 チュニジアに滞在
1968 5月10日パリで「68年5月」は じまる(5月2日〜6月23日:Mai 68)。 その2ヶ月前にチュニジアで流血の学生でもをフーコーは体験する。チュニジアでも学生ストライキ。
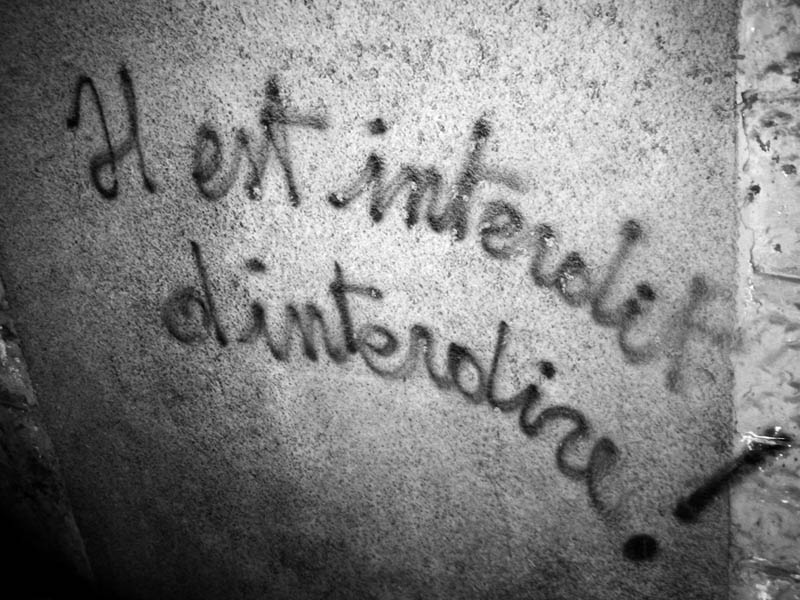

Il est interdit d'interdire !- "it is forbidden to forbid"
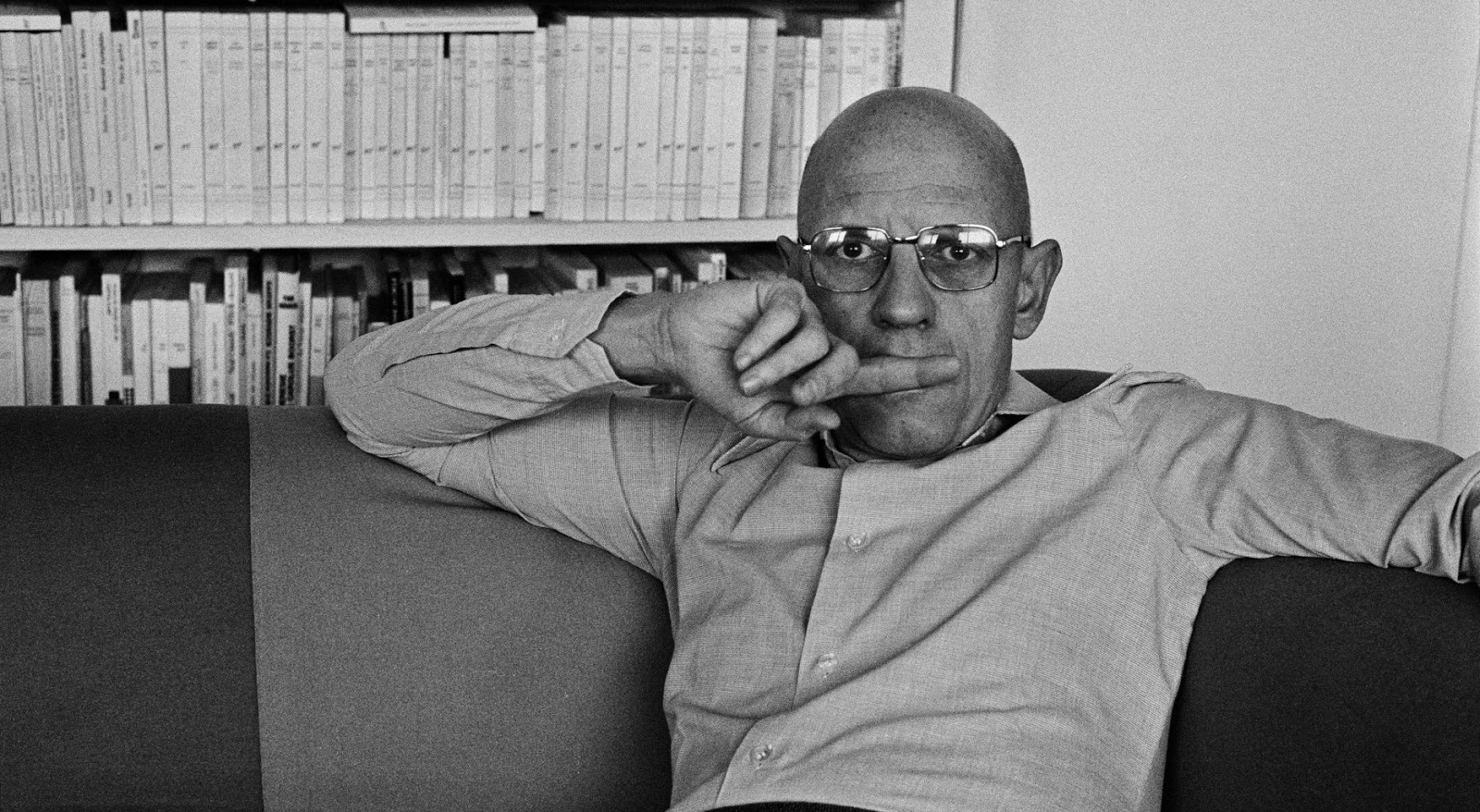
1968
モーリス・パンゲ(Maurice Pinguet, 1929-1991)が東京大学での教職を辞 した際に、フーコーはその後任を務めたいと申し出たが実現には至らなかった。この逸話の典拠は、『フーコー・コレクション1 狂気・理性』405頁 ちくま学芸文庫、2006年。
1968-1969
(冬)パリ・ヴァンセンヌ(パ リ第8大学)で教える。「誰にも聞こえるように『わたしはマルクス主義者ではない』と広言したことは、現実にはきわめてこんなことでした」(フーコー 2008 [June, 1975]:39)上掲書。
1969 『知の考古学』(中村雄一郎訳、河出書房 新社)L'Archaologie du savoir (Paris: Gallimard, March 1969).
1970 コレージュ・ド・フランス教授:講義『知 への意志』(コレージュ・ド・フランス講義 1970-71)
1971
『言説表現の秩序』(中村雄一郎訳、河出 書房新社)L'ordre du discours (Paris, Gallimard, 1971)
刑罰の理論と制度 (コレージュ・ド・フランス講義 1971-72)
Chomsky-Foucault Debate
on Power vs Justice (1971)
1972
処罰社会 (コレージュ・ド・フランス講義
1972-73)
『狂気の歴史:古典主義時代における』 (田村俶訳、新潮社)Histoire de la folie a l'age classique. Gallimard, 1972
1973
精神医学の権力 (コレージュ・ド・フランス講義
1973-74)
1974
異常者たち (コレージュ・ド・フランス講義
1974-75)
1975
『監獄の誕生』Surveiller et punir, naissance de la prison (Paris: Gallimard, February 1975).
コレージュドフランス講義『異常者たち』でカトリッ ク神秘主義に言及
社会は防衛しなければならない (コレージュ・ド・フランス講義
1975-76)
1976
『性の歴史 1権力への意志』 Histoire de la sexualit・1. La volonte de savoir (Paris: Gallimard, 1976).——この時の予告:2『肉と身体』、3『少年十字軍』、4『女性、母、ヒステリー患者』、5『倒錯者たち』、6『人口と人種』
1977
安全・領土・人口
(コレージュ・ド・フランス講義 1977-78)
1978
年頭(1月)よりイラン革命はじまる(→「アーヤトッラー・ルーホッラー・ホメイニーとイラン革命」)。
1-4月。コレージュドフランス講義『安全・領土・ 人口』にて、生権力の問題から授業をはじめる。権力はいくつもの手続きを経るプロ セスであり、(その中で)原因と結果が循環する構成体になる。それが授業内容の「安全」装置の説明(装置概念は1970年代後半のフーコーがよく使った用 語)。そこから「統治性」概念の検討に入る。司牧制、内政、外交と軍事。しかし2月8 日の5回目からは司牧制に絞られてゆく。8回目(3月1日)魂の統治技術に傾注される。ギリシア教父に対して「魂のオイコノミア」という用語を使う。
【フーコーとイラン革命, 1978-1979】秋 に2度イランを訪問する。フーコーとイラン革命については、ヘーゲルとフランス革命(あるいはハイチ革命)のような関係かどうかということである。フー コーにとって、ホメイニのイラン革命は、ある種の、思想的起爆剤ないしは「躓きの石」になり、後の彼の思考経験にどのように反映したか/反映されなかった のか?という問題である。
+++
| "In 1976, Gallimard published Foucault's Histoire de la sexualité: la volonté de savoir (The History of Sexuality: The Will to Knowledge), a short book exploring what Foucault called the "repressive hypothesis". It revolved largely around the concept of power, rejecting both Marxist and Freudian theory. Foucault intended it as the first in a seven-volume exploration of the subject.[132] Histoire de la sexualité was a best-seller in France and gained positive press, but lukewarm intellectual interest, something that upset Foucault, who felt that many misunderstood his hypothesis.[133] He soon became dissatisfied with Gallimard after being offended by senior staff member Pierre Nora.[134] Along with Paul Veyne and François Wahl, Foucault launched a new series of academic books, known as Des travaux (Some Works), through the company Seuil, which he hoped would improve the state of academic research in France.[135] He also produced introductions for the memoirs of Herculine Barbin and My Secret Life.[136]/ Foucault remained a political activist, focusing on protesting government abuses of human rights around the world. He was a key player in the 1975 protests against the Spanish government to execute 11 militants sentenced to death without fair trial. It was his idea to travel to Madrid with 6 others to give their press conference there; they were subsequently arrested and deported back to Paris.[138] In 1977, he protested the extradition of Klaus Croissant to West Germany, and his rib was fractured during clashes with riot police.[139] In July that year, he organised an assembly of Eastern Bloc dissidents to mark the visit of Soviet Premier Leonid Brezhnev to Paris.[140] In 1979, he campaigned for Vietnamese political dissidents to be granted asylum in France.[141]/ In 1977, Italian newspaper Corriere della sera asked Foucault to write a column for them. In doing so, in 1978 he travelled to Tehran in Iran, days after the Black Friday massacre. Documenting the developing Iranian Revolution, he met with opposition leaders such as Mohammad Kazem Shariatmadari and Mehdi Bazargan, and discovered the popular support for Islamism.[142] Returning to France, he was one of the journalists who visited the Ayatollah Khomeini, before visiting Tehran. His articles expressed awe of Khomeini's Islamist movement, for which he was widely criticised in the French press, including by Iranian expatriates. Foucault's response was that Islamism was to become a major political force in the region, and that the West must treat it with respect rather than hostility.[143] In April 1978, Foucault traveled to Japan, where he studied Zen Buddhism under Omori Sogen at the Seionji temple in Uenohara.[120]"︎ | 1976年、ガリマール社はフーコーの『性の歴史:知識への意志』
(Histoire de la sexualité: la volonté de
savoir)を出版した。これはフーコーが「抑圧仮説」と呼ぶものを探求した短編集であった。マルクス主義やフロイトの理論を否定し、権力の概念に大き
く関わるものであった。フーコーはこの本を、7巻からなるこのテーマの探求の最初の一冊とするつもりだった。フランスではベストセラーとなり、好意的な報
道がなされたが、知的関心は低く、フーコーは自分の仮説を多くの人が誤解していると感じ、憤慨した。ガリマール社では、先輩のピエール・ノラに怒られ、す
ぐに不満を募らせた。フーコーは、ポール・ヴェイヌ、フランソワ・ワールらとともに、フランスの学術研究の状況を改善するために、スイル社から新しい学術
書シリーズ「Des
travaux(いくつかの作品)」を創刊した。また、エルキュリーヌ・バルバンの回顧録『私の秘密の生活』の序文も執筆した。フーコーは政治活動家とし
て、世界各地で政府による人権侵害に抗議することに力を注いでいた。1975年、スペイン政府が死刑判決を受けた11人の過激派を公正な裁判を経ずに処刑
したことに対する抗議デモでは、中心的な役割を担った。その際、6人の仲間とともにマドリードで記者会見を行ったが、逮捕され、パリに送還された。
1977年、クラウス・クロワッサンの西ドイツへの引き渡しに抗議し、機動隊と衝突して肋骨を骨折した。同年7月、ソ連のブレジネフ首相のパリ訪問を記念
して、東欧諸国の反体制者たちの集会を組織した。1977年、イタリアの新聞社コリエール・デラ・セラはフーコーにコラムの執筆を依頼する。その際、
1978年にイランのテヘランを訪れ、「黒い金曜日」の大虐殺の数日後にイラン革命を記録した。発展途上のイラン革命を記録し、モハマド・カゼム・シャリ
アトマダーリやメフディ・バザルガンといった野党指導者と会い、イスラム主義への民衆の支持を発見したのである。フランスに戻り、テヘランを訪れる前にホ
メイニ師を訪ねたジャーナリストの一人である。彼の記事は、ホメイニのイスラム主義運動に対する畏敬の念を表現しており、イラン人駐在員を含むフランスの
新聞で広く批判された。フーコーの回答は、イスラム主義がこの地域の主要な政治勢力になること、そして西洋はそれを敵対視するのではなく、敬意をもって扱
うべきであるというものであった。1978年4月、フーコーは日本を訪れ、上野原市の西園寺で大森曹玄に禅を学んだ︎。 |
+++
▶︎Foucault and the Iranian Revolution : gender and the seductions of Islamism / Janet Afary and Kevin B. Anderson, University of Chicago Press , 2005.▶︎︎Tetz Hakoda, Bodies and Pleasures in the Happy Limbo of a Non-identity: Foucault against Butler on Herculine Barbin, ZINBUN No. 45 2014▶Thinking the Unthinkable: Foucault and the Islamic Revolution, Talk by Professor Behrooz Ghamari-Tabrizi at Stanford University on May 3, 2018︎▶︎︎ジジェク、スラヴォイ「ミッシェル・フーコーとイランの出来事」(Pp.166-181)「3章ラディカルな知識人たち、あるいは……」 『大義を忘れるな』中山徹・鈴木英明訳、青土社、2010年▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎
生政治の誕生 (コレージュ・ド・フランス講義
1978-79)[→「研究ノート:バイオポリティクス」「バイオポリティクス」]
1979
2月アーヤトッラー・ルーホッラー・ホメイニー帰国。

11月アメリカ大使館人質事件
生者たちの統治 (コレージュ・ド・フランス講義
1979-80)
1980
4月にアメリカ合衆国はイランに対して国交断絶。
主体性と真理 (コレージュ・ド・フランス講義
1980-81)
1981
「主体の解釈学 (コレージュ・ド・フランス講義 1981-82)
1982
Le Désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille. Présenté par Arlette Farge et Michel Foucault, («Collection Archives », 91) 1982
自己と他者の統治
(コレージュ・ド・フランス講義 1982-83)
1983
真理の勇気
(コレージュ・ド・フランス講義 1983-84)
1984
『性の歴史 2快楽の活用』 Histoire de la sexualite II, L'usage des plaisirs (Paris: Gallimard, 1984)
『性の歴史 3自己への配慮』 Histoire de la sexualite III, Le souci de soi (Paris: Gallimard, 1984)
CFでの「生政治装置」という講義アイディアは捨て られる(グロ 2020:7-8)
『肉の告白』の予告「キリスト教の最初の数世紀にお ける肉の経験と、欲望の解釈学および清めのための欲望の解読がそこではたす役割とを扱う」(グロ 2020:8-9)
エイズで死去
1989
2月ホメイニは、サルマン・ラシュディに対して死刑
のファトゥア(勅諭)を示す。6月にはこの判断は覆らせないと宣言される。
1991
7月11日ラシュディ『悪魔の詩』翻訳者であった筑
波大学助教授・五十嵐一(いがらし・ひとし, Hitoshi IGARASHI,
1947-1991)が大学構内にて首を切られて殺害(→「悪魔の詩訳者殺人事件」)
1994
Dits et écrits, 1954-1988 / Michel Foucault ; édition établie sous la direction de Daniel Defert et François Ewald ; avec la collaboration de Jacques Lagrange, 1 - 4. - [Paris] : Gallimard , c1994. - (Bibliothèque des sciences humaines)
1997
"Il faut défendre la société" : cours au Collège de France (1975-1976) / Michel Foucault ; édition établie, dans le cadre de l'Association pour le Centre Michel Foucault, sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana par Mauro Bertani et Alessandro Fontana: pbk. - [Paris] : Gallimard : Seuil , c1997. - (Hautes études)
1999 Les anormaux : cours au Collège de France (1974-1975) / Michel Foucault ; édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Valerio Marchetti et Antonella Salomoni: pbk. - [Paris] : Gallimard : Seuil , c1999. - (Hautes études)
2001 L'herméneutique du sujet : cours au Collège de France (1981-1982) / Michel Foucault ; édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Frédéric Gros: pbk. - [Paris] : Gallimard : Seuil , c2001. - (Hautes études)
2003 Le pouvoir psychiatrique : cours au Collège de France (1973-1974) / Michel Foucault ; édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Jacques Lagrange: pbk. - [Paris] : Gallimard : Seuil , c2003. - (Hautes études)
2004 Sécurité, territoire, population : cours au Collège de France (1977-1978) / Michel Foucault ; édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Michel Senellart : pbk. - [Paris] : Gallimard : Seuil , c2004. - (Hautes études)
2004 Naissance de la
biopolitique : cours au collège de France (1978-1979) / Michel Foucault
; édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro
Fontana, par Michel Senellart : pbk. - [Paris] : Gallimard : Seuil ,
c2004. - (Hautes études)
2008 Le gouvernement de soi et des autres : cours au Collège de France (1982-1983) / Michel Foucault ; édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Frédéric Gros [Paris] : Gallimard : Seuil , c2008. - (Hautes études)
2009
Le courage de la vérité : cours au Collège de France (1983-1984) / Michel Foucault [Paris] : Seuil : Gallimard , c2009. - (Hautes études ; . { Le gouvernement de soi et des autres / Michel Foucault ; édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana par Frédéric Gros } ; v. 2)
2011 Leçons sur la
volonté de savoir : cours au collège de France, 1970-1971 suivi de Le
savoir d'Œdipe / Michel Foucault ; édition établie sous la direction de
François Ewald et Alessandro Fontana, par Daniel Defert : pbk. -
[Paris] : Gallimard : Seuil , c2011. - (Hautes études)
2018 Les Aveux de la Chair (肉の告白) Histoire de la sexualite IV, (solo se puede observar su Advertencia en PDF con clave, Frederic Gros: MFoucault_avertisse_Aveux_Chair_2018.pdf)
2020 肉の告白 / ミシェル・フーコー
[著] ; フレデリック・グロ編 : 槙改康之訳、新潮社 , 2020 . - (性の歴史 / ミシェル・フーコー著 ; 4)
****
+++
★英語版ウィキペディア"Paul-Michel
Foucault"からの翻訳:
| Paul-Michel
Foucault
(UK: /ˈfuːkoʊ/, US: /fuːˈkoʊ/;[9] French: [pɔl miʃɛl fuko]; 15 October
1926 – 25 June 1984) was a French philosopher, historian of ideas,
writer, political activist, and literary critic. Foucault's theories
primarily address the relationships between power and knowledge, and
how they are used as a form of social control through societal
institutions. Though often cited as a structuralist and postmodernist,
Foucault rejected these labels.[10] His thought has influenced
academics, especially those working in communication studies,
anthropology, psychology, sociology, criminology, cultural studies,
literary theory, feminism, Marxism and critical theory. Born in Poitiers, France, into an upper-middle-class family, Foucault was educated at the Lycée Henri-IV, at the École Normale Supérieure, where he developed an interest in philosophy and came under the influence of his tutors Jean Hyppolite and Louis Althusser, and at the University of Paris (Sorbonne), where he earned degrees in philosophy and psychology. After several years as a cultural diplomat abroad, he returned to France and published his first major book, The History of Madness (1961). After obtaining work between 1960 and 1966 at the University of Clermont-Ferrand, he produced The Birth of the Clinic (1963) and The Order of Things (1966), publications that displayed his increasing involvement with structuralism, from which he later distanced himself. These first three histories exemplified a historiographical technique Foucault was developing called "archaeology". From 1966 to 1968, Foucault lectured at the University of Tunis before returning to France, where he became head of the philosophy department at the new experimental university of Paris VIII. Foucault subsequently published The Archaeology of Knowledge (1969). In 1970, Foucault was admitted to the Collège de France, a membership he retained until his death. He also became active in several left-wing groups involved in campaigns against racism and human rights abuses and for penal reform. Foucault later published Discipline and Punish (1975) and The History of Sexuality (1976), in which he developed archaeological and genealogical methods that emphasized the role that power plays in society. Foucault died in Paris from complications of HIV/AIDS; he became the first public figure in France to die from complications of the disease. His partner Daniel Defert founded the AIDES charity in his memory. |
ポール=ミシェル・フーコー(イギリス: (イギリス:
/ˈfu(, アメリカ: /fuːko(; [9] French: [pɔl mi((]) /1926年10月15日 -
1984年6月25日)は、フランスの哲学者、思想史家、作家、政治活動家、文芸評論家。フーコーの理論は主に、権力と知識の関係、そしてそれらが社会制
度を通じて社会統制の一形態としてどのように利用されているかを扱っている。フーコーの思想は、特にコミュニケーション研究、人類学、心理学、社会学、犯
罪学、カルチュラル・スタディーズ、文学理論、フェミニズム、マルクス主義、批評理論などの研究者に影響を与えている。 フランスのポワチエで上流中産階級の家庭に生まれたフーコーは、アンリ4世リセ、高等師範学校(École Normale Supérieure)、パリ大学(ソルボンヌ大学)で教育を受け、哲学と心理学の学位を取得。海外で文化外交官を数年務めた後、フランスに戻り、最初の 主著『狂気の歴史』(1961年)を出版。1960年から1966年にかけてクレルモンフェラン大学で仕事を得た後、『診療所の誕生』(1963年)と 『物事の秩序』(1966年)を出版した。これらの最初の3つの歴史は、フーコーが開発しつつあった「考古学」と呼ばれる歴史学的技法を例証するもので あった。 1966年から1968年まで、フーコーはチュニス大学で教鞭をとった後、フランスに戻り、パリ第8大学の新しい実験大学の哲学部長となった。その後、 『知の考古学』(1969年)を出版。1970年、フーコーはコレージュ・ド・フランスの教員となり、この会員資格は亡くなるまで保持された。フーコーは また、人種差別や人権侵害に反対し、刑罰改革を求めるキャンペーンを展開するいくつかの左翼グループで活動するようになる。その後、『規律と罰』 (1975年)と『セクシュアリティの歴史』(1976年)を出版し、社会で権力が果たす役割を強調する考古学的・系図学的手法を開発した。 フーコーはHIV/AIDSの合併症によりパリで死去。HIV/AIDSの合併症で死亡したフランス初の公人となった。フーコーのパートナーであったダニ エル・デフェールは、フーコーを偲んで慈善団体AIDESを設立した。 |
| Early life Early years: 1926–1938 Paul-Michel Foucault was born on 15 October 1926 in the city of Poitiers, west-central France, as the second of three children in a prosperous, socially conservative, upper-middle-class family.[11] Family tradition prescribed naming him after his father, Paul Foucault (1893–1959), but his mother insisted on the addition of Michel; referred to as Paul at school, he expressed a preference for "Michel" throughout his life.[12] His father, a successful local surgeon born in Fontainebleau, moved to Poitiers, where he set up his own practice.[13] He married Anne Malapert, the daughter of prosperous surgeon Dr. Prosper Malapert, who owned a private practice and taught anatomy at the University of Poitiers' School of Medicine.[14] Paul Foucault eventually took over his father-in-law's medical practice, while Anne took charge of their large mid-19th-century house, Le Piroir, in the village of Vendeuvre-du-Poitou.[15] Together the couple had three children—a girl named Francine and two boys, Paul-Michel and Denys—who all shared the same fair hair and bright blue eyes.[16] The children were raised to be nominal Catholics, attending mass at the Church of Saint-Porchair, and while Michel briefly became an altar boy, none of the family was devout.[17] Michel is not related to the physicist Léon Foucault. In later life, Foucault revealed very little about his childhood.[18] Describing himself as a "juvenile delinquent", he said his father was a "bully" who sternly punished him.[19] In 1930, two years early, Foucault began his schooling at the local Lycée Henry-IV. There he undertook two years of elementary education before entering the main lycée, where he stayed until 1936. Afterwards, he took his first four years of secondary education at the same establishment, excelling in French, Greek, Latin, and history, though doing poorly at mathematics, including arithmetic.[20] Teens to young adulthood: 1939–1945 In 1939, the Second World War began, followed by Nazi Germany's occupation of France in 1940. Foucault's parents opposed the occupation and the Vichy regime, but did not join the Resistance.[21] That year, Foucault's mother enrolled him in the Collège Saint-Stanislas, a strict Catholic institution run by the Jesuits. Although he later described his years there as an "ordeal", Foucault excelled academically, particularly in philosophy, history, and literature.[22] In 1942 he entered his final year, the terminale, where he focused on the study of philosophy, earning his baccalauréat in 1943.[23] Returning to the local Lycée Henry-IV, he studied history and philosophy for a year,[24] aided by a personal tutor, the philosopher Louis Girard [fr].[25] Rejecting his father's wishes that he become a surgeon, in 1945 Foucault went to Paris, where he enrolled in one of the country's most prestigious secondary schools, which was also known as the Lycée Henri-IV. Here he studied under the philosopher Jean Hyppolite, an existentialist and expert on the work of 19th-century German philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hyppolite had devoted himself to uniting existentialist theories with the dialectical theories of Hegel and Karl Marx. These ideas influenced Foucault, who adopted Hyppolite's conviction that philosophy must develop through a study of history.[26] University studies: 1946–1951 I wasn't always smart, I was actually very stupid in school ... [T]here was a boy who was very attractive who was even stupider than I was. And to ingratiate myself with this boy who was very beautiful, I began to do his homework for him—and that's how I became smart, I had to do all this work to just keep ahead of him a little bit, to help him. In a sense, all the rest of my life I've been trying to do intellectual things that would attract beautiful boys. — Michel Foucault, 1983[27] In autumn 1946, attaining excellent results, Foucault was admitted to the élite École Normale Supérieure (ENS), for which he undertook exams and an oral interrogation by Georges Canguilhem and Pierre-Maxime Schuhl to gain entry. Of the hundred students entering the ENS, Foucault ranked fourth based on his entry results, and encountered the highly competitive nature of the institution. Like most of his classmates, he lived in the school's communal dormitories on the Parisian Rue d'Ulm.[28] He remained largely unpopular, spending much time alone, reading voraciously. His fellow students noted his love of violence and the macabre; he decorated his bedroom with images of torture and war drawn during the Napoleonic Wars by Spanish artist Francisco Goya, and on one occasion chased a classmate with a dagger.[29] Prone to self-harm, in 1948 Foucault allegedly attempted suicide; his father sent him to see the psychiatrist Jean Delay at the Sainte-Anne Hospital Center. Obsessed with the idea of self-mutilation and suicide, Foucault attempted the latter several times in ensuing years, praising suicide in later writings.[30] The ENS's doctor examined Foucault's state of mind, suggesting that his suicidal tendencies emerged from the distress surrounding his homosexuality, because same-sex sexual activity was socially taboo in France.[31] At the time, Foucault engaged in homosexual activity with men whom he encountered in the underground Parisian gay scene, also indulging in drug use; according to biographer James Miller, he enjoyed the thrill and sense of danger that these activities offered him.[32] Although studying various subjects, Foucault soon gravitated towards philosophy, reading not only Hegel and Marx but also Immanuel Kant, Edmund Husserl and most significantly, Martin Heidegger.[33] He began reading the publications of philosopher Gaston Bachelard, taking a particular interest in his work exploring the history of science.[34] He graduated from the ENS with a B.A. (licence) in Philosophy in 1948[2] and a DES (diplôme d'études supérieures [fr], roughly equivalent to an M.A.) in Philosophy in 1949.[2] His DES thesis under the direction of Hyppolite was titled La Constitution d'un transcendental dans La Phénoménologie de l'esprit de Hegel (The Constitution of a Historical Transcendental in Hegel's Phenomenology of Spirit).[2] In 1948, the philosopher Louis Althusser became a tutor at the ENS. A Marxist, he influenced both Foucault and a number of other students, encouraging them to join the French Communist Party. Foucault did so in 1950, but never became particularly active in its activities, and never adopted an orthodox Marxist viewpoint, rejecting core Marxist tenets such as class struggle.[35] He soon became dissatisfied with the bigotry that he experienced within the party's ranks; he personally faced homophobia and was appalled by the anti-semitism exhibited during the 1952–53 "Doctors' plot" in the Soviet Union. He left the Communist Party in 1953, but remained Althusser's friend and defender for the rest of his life.[36] Although failing at the first attempt in 1950, he passed his agrégation in philosophy on the second try, in 1951.[37] Excused from national service on medical grounds, he decided to start a doctorate at the Fondation Thiers in 1951, focusing on the philosophy of psychology,[38] but he relinquished it after only one year in 1952.[39] Foucault was also interested in psychology and he attended Daniel Lagache's lectures at the University of Paris, where he obtained a B.A. (licence) in psychology in 1949 and a Diploma in Psychopathology (Diplôme de psychopathologie) from the university's institute of psychology (now Institut de psychologie de l'université Paris Descartes [fr]) in June 1952.[2] |
幼少期 若い頃 1926-1938 ポール=ミッシェル・フーコーは1926年10月15日、フランス中西部のポワチエ市で、裕福で社会的に保守的な上流中産階級の家庭に3人兄弟の2番目と して生まれた[11]。家訓では父ポール・フーコー(1893-1959)にちなんでフーコーと名付けることになっていたが、母はミシェルをつけることを 主張した。 父はフォンテーヌブロー生まれの外科医で、ポワチエに移り住み、開業医となった[13]。 [14] ポール・フーコーは義父の診療所を引き継ぎ、アンヌはヴァンドゥーブル・デュ・ポワトゥー村にある19世紀半ばに建てられた大きな家、ル・ピロワールを管 理した。 [15]夫妻の間には、フランシーヌという名の女の子と、ポール=ミッシェルとドゥニーという2人の男の子という3人の子供が生まれた。 1930年、フーコーは2年早く地元のリセ・アンリ4世で学び始める。そこで2年間の初等教育を受けた後、本科のリセに入学し、1936年まで在籍した。 その後、同校で最初の4年間の中等教育を受け、フランス語、ギリシャ語、ラテン語、歴史に秀でたが、算数を含む数学は苦手だった[20]。 10代から青年期:1939-1945年 1939年、第二次世界大戦が始まり、1940年にはナチス・ドイツがフランスを占領。フーコーの両親は占領とヴィシー政権に反対していたが、レジスタン スには参加しなかった[21]。後にフーコーはそこでの学生時代を「試練」であったと語るが、フーコーは学業、特に哲学、歴史、文学に秀でていた [22]。1942年、彼は最終学年であるターミナールに入り、そこで哲学の研究に専念し、1943年にバカロレアを取得した[23]。 地元のリセ・アンリ=Ⅳに戻り、哲学者ルイ・ジラールの個人指導を受けながら、歴史と哲学を1年間学んだ[24][25]。外科医になることを望んだ父の 反対を押し切り、1945年、フーコーはパリに渡り、リセ・アンリ=Ⅳとして知られるパリで最も権威のある中等学校に入学。ここで彼は、実存主義者であ り、19世紀ドイツの哲学者ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの研究の専門家であった哲学者ジャン・ヒュポリットに師事した。ヒュポリット は、実存主義の理論をヘーゲルやカール・マルクスの弁証法的理論と結びつけることに力を注いでいた。これらの思想はフーコーに影響を与え、哲学は歴史の研 究を通じて発展していかなければならないというハイポライトの信念を採用した[26]。 大学での研究 1946-1951 私はいつも頭が良かったわけではなく、実は学校ではとても頭が悪かった.[とても魅力的な男の子がいて、その子は私よりもっとバカだった。そうやって私は 賢くなったんだ。ある意味、私は残りの人生ずっと、美少年を惹きつけるような知的なことをしようとしてきた。 - ミシェル・フーコー、1983年[27]。 1946年秋、優秀な成績を収めたフーコーは、エリート校である高等師範学校(ENS)に入学を許可され、ジョルジュ・カンギレムとピエール=マクシム・ シュールによる試験と口頭試問を受け、入学を果たした。ENSに入学した100人の学生のうち、フーコーは成績で4位にランクされ、ENSの競争の激しさ に直面した。ほとんどの同級生と同様、彼はパリのウルム通りにある学校の共同寮に住んでいた[28]。 彼はほとんど人気がなく、多くの時間を一人で過ごし、熱心に読書をしていた。寝室にはスペインの画家フランシスコ・ゴヤがナポレオン戦争中に描いた拷問や 戦争の絵が飾られ、短剣を持って同級生を追いかけたこともあった[29]。自傷癖のあったフーコーは、1948年に自殺未遂を図ったとされ、父親は彼をサ ント・アンヌ病院センターの精神科医ジャン・ドレイに診せた。自傷行為と自殺のアイデアに取りつかれたフーコーは、その後何度も自殺を試み、後の著作では 自殺を賞賛している[30] 。 [31] 当時、フーコーはパリのアンダーグラウンドなゲイ・シーンで出会った男たちと同性愛の営みを行い、薬物使用にも耽っていた。伝記作家のジェームズ・ミラー によれば、彼はこれらの営みが彼に与えるスリルと危機感を楽しんでいた[32]。 様々な学問を学んだが、フーコーはすぐに哲学に傾倒し、ヘーゲルやマルクスだけでなく、イマヌエル・カント、エドムント・フッサール、そして最も重要なマ ルティン・ハイデガーも読んだ[33]。 1948年に哲学のA(免許)を取得し[2]、1949年に哲学のDES(diplôme d'études supérieures [fr]、修士にほぼ相当)を取得した[2]。ハイポライトの指導の下でのDESの論文のタイトルは『La Constitution d'un transcendental dans La Phénoménologie de l'esprit de Hegel(ヘーゲルの精神現象学における歴史的超越論者の構成)』であった[2]。 1948年、哲学者ルイ・アルチュセールがENSの講師となる。マルクス主義者であったアルチュセールは、フーコーや他の学生たちに影響を与え、フランス 共産党への入党を勧めた。フーコーは1950年に共産党に入党したが、共産党の活動に特に積極的に参加することはなく、階級闘争のようなマルクス主義の中 核的な考え方を否定し、正統的なマルクス主義の視点を採用することはなかった[35]。彼はすぐに党内で経験した偏見に不満を抱くようになり、個人的に同 性愛嫌悪に直面し、1952年から53年にかけてソビエト連邦で起こった「医師たちの陰謀」の際に示された反ユダヤ主義に愕然とした。彼は1953年に共 産党を離党したが、アルチュセールの友人であり擁護者であり続けた[36]。1950年の最初の受験では失敗したものの、1951年の2回目の受験で哲学 のアグレガシオン試験に合格した[37]。 フーコーは心理学にも興味を持っており、パリ大学でダニエル・ラガシュの講義を受け、1949年に心理学の学士号(免許)を取得し、1952年6月に同大 学の心理学研究所(現在のパリ・デカルト大学心理学研究所[fr])で精神病理学のディプロマ(Diplôme de psychopathologie)を取得した[2]。 |
| Early career (1951–1960) In the early 1950s, Foucault came under the influence of German philosopher Friedrich Nietzsche, who remained a core influence on his work throughout his life. France: 1951–1955 Over the following few years, Foucault embarked on a variety of research and teaching jobs.[40] From 1951 to 1955, he worked as a psychology instructor at the ENS at Althusser's invitation.[41] In Paris, he shared a flat with his brother, who was training to become a surgeon, but for three days in the week commuted to the northern town of Lille, teaching psychology at the Université de Lille from 1953 to 1954.[42] Many of his students liked his lecturing style.[43] Meanwhile, he continued working on his thesis, visiting the Bibliothèque Nationale every day to read the work of psychologists like Ivan Pavlov, Jean Piaget and Karl Jaspers.[44] Undertaking research at the psychiatric institute of the Sainte-Anne Hospital, he became an unofficial intern, studying the relationship between doctor and patient and aiding experiments in the electroencephalographic laboratory.[45] Foucault adopted many of the theories of the psychoanalyst Sigmund Freud, undertaking psychoanalytical interpretation of his dreams and making friends undergo Rorschach tests.[46] Embracing the Parisian avant-garde, Foucault entered into a romantic relationship with the serialist composer Jean Barraqué. Together, they tried to produce their greatest work, heavily used recreational drugs and engaged in sado-masochistic sexual activity.[47] In August 1953, Foucault and Barraqué holidayed in Italy, where the philosopher immersed himself in Untimely Meditations (1873–1876), a set of four essays by the philosopher Friedrich Nietzsche. Later describing Nietzsche's work as "a revelation", he felt that reading the book deeply affected him, being a watershed moment in his life.[48] Foucault subsequently experienced another groundbreaking self-revelation when watching a Parisian performance of Samuel Beckett's new play, Waiting for Godot, in 1953.[49] Interested in literature, Foucault was an avid reader of the philosopher Maurice Blanchot's book reviews published in Nouvelle Revue Française. Enamoured of Blanchot's literary style and critical theories, in later works he adopted Blanchot's technique of "interviewing" himself.[50] Foucault also came across Hermann Broch's 1945 novel The Death of Virgil, a work that obsessed both him and Barraqué. While the latter attempted to convert the work into an epic opera, Foucault admired Broch's text for its portrayal of death as an affirmation of life.[51] The couple took a mutual interest in the work of such authors as the Marquis de Sade, Fyodor Dostoyevsky, Franz Kafka and Jean Genet, all of whose works explored the themes of sex and violence.[52] I belong to that generation who, as students, had before their eyes, and were limited by, a horizon consisting of Marxism, phenomenology and existentialism. For me the break was first Beckett's Waiting for Godot, a breathtaking performance. — Michel Foucault, 1983[53] Interested in the work of Swiss psychologist Ludwig Binswanger, Foucault aided family friend Jacqueline Verdeaux in translating his works into French. Foucault was particularly interested in Binswanger's studies of Ellen West who, like himself, had a deep obsession with suicide, eventually killing herself.[54] In 1954, Foucault authored an introduction to Binswanger's paper "Dream and Existence", in which he argued that dreams constituted "the birth of the world" or "the heart laid bare", expressing the mind's deepest desires.[55] That same year, Foucault published his first book, Maladie mentale et personalité (Mental Illness and Personality), in which he exhibited his influence from both Marxist and Heideggerian thought, covering a wide range of subject matter from the reflex psychology of Pavlov to the classic psychoanalysis of Freud. Referencing the work of sociologists and anthropologists such as Émile Durkheim and Margaret Mead, he presented his theory that illness was culturally relative.[56] Biographer James Miller noted that while the book exhibited "erudition and evident intelligence", it lacked the "kind of fire and flair" which Foucault exhibited in subsequent works.[57] It was largely critically ignored, receiving only one review at the time.[58] Foucault grew to despise it, unsuccessfully attempting to prevent its republication and translation into English.[59] Sweden, Poland, and West Germany: 1955–1960 Foucault spent the next five years abroad, first in Sweden, working as cultural diplomat at the University of Uppsala, a job obtained through his acquaintance with historian of religion Georges Dumézil.[60] At Uppsala he was appointed a Reader in French language and literature, while simultaneously working as director of the Maison de France, thus opening the possibility of a cultural-diplomatic career.[61] Although finding it difficult to adjust to the "Nordic gloom" and long winters, he developed close friendships with two Frenchmen, biochemist Jean-François Miquel and physicist Jacques Papet-Lépine, and entered into romantic and sexual relationships with various men. In Uppsala he became known for his heavy alcohol consumption and reckless driving in his new Jaguar car.[62] In spring 1956 Barraqué broke from his relationship with Foucault, announcing that he wanted to leave the "vertigo of madness".[63] In Uppsala, Foucault spent much of his spare time in the university's Carolina Rediviva library, making use of their Bibliotheca Walleriana collection of texts on the history of medicine for his ongoing research.[64] Finishing his doctoral thesis, Foucault hoped that Uppsala University would accept it, but Sten Lindroth, a positivistic historian of science there, remained unimpressed, asserting that it was full of speculative generalisations and was a poor work of history; he refused to allow Foucault to be awarded a doctorate at Uppsala. In part because of this rejection, Foucault left Sweden.[65] Later, Foucault admitted that the work was a first draft with certain lack of quality.[66] Again at Dumézil's behest, in October 1958 Foucault arrived in the capital of the Polish People's Republic, Warsaw and took charge of the University of Warsaw's Centre Français.[67] Foucault found life in Poland difficult due to the lack of material goods and services following the destruction of the Second World War. Witnessing the aftermath of the Polish October of 1956, when students had protested against the governing communist Polish United Workers' Party, he felt that most Poles despised their government as a puppet regime of the Soviet Union, and thought that the system ran "badly".[68] Considering the university a liberal enclave, he traveled the country giving lectures; proving popular, he adopted the position of de facto cultural attaché.[69] Like France and Sweden, Poland legally tolerated but socially frowned on homosexual activity, and Foucault undertook relationships with a number of men; one was with a Polish security agent who hoped to trap Foucault in an embarrassing situation, which therefore would reflect badly on the French embassy. Wracked in diplomatic scandal, he was ordered to leave Poland for a new destination.[70] Various positions were available in West Germany, and so Foucault relocated to the Institut français Hamburg [de] (where he served as director in 1958–1960), teaching the same courses he had given in Uppsala and Warsaw.[71][72] Spending much time in the Reeperbahn red light district, he entered into a relationship with a transvestite.[73] |
初期のキャリア(1951-1960) 1950年代初頭、フーコーはドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェの影響を受ける。 フランス:1951年~1955年 1951年から1955年まで、彼はアルチュセールの招きでENSで心理学の講師として働いていた。 [サント=アンヌ病院の精神医学研究所で研究を行うため、彼は非公式なインターンとなり、医師と患者の関係を研究したり、脳波実験室で実験を手伝ったりし た[44]。 [フーコーは精神分析家ジークムント・フロイトの理論の多くを取り入れ、夢の精神分析的解釈を引き受け、友人たちにロールシャッハ・テストを受けさせた [46]。 パリのアヴァンギャルドを受け入れたフーコーは、シリアル派の作曲家ジャン・バラケと恋愛関係に入る。1953年8月、フーコーとバラケはイタリアで休暇 を過ごし、哲学者は哲学者フリードリヒ・ニーチェの4つのエッセイから成る『時ならぬ瞑想』(1873-1876)に没頭した。後にニーチェの著作を「啓 示」と表現したフーコーは、この本を読んだことが自分の人生に深い影響を与え、分岐点となったと感じていた[48]。フーコーはその後、1953年にサ ミュエル・ベケットの新作戯曲『ゴドーを待ちながら』のパリ公演を観劇した際にも、画期的な自己啓示を経験している[49]。 文学に興味を持ったフーコーは、哲学者モーリス・ブランショの『ヌーヴェル・ルヴュ・フランセーズ』誌に掲載された書評の熱心な読者であった。ブランショ の文学的スタイルと批評理論に魅了されたフーコーは、後年、ブランショの「自分自身にインタビューする」という手法を取り入れた[50]。後者がこの作品 を叙事詩的なオペラに改作しようとしたのに対し、フーコーは生を肯定するものとして死を描いたブロッホのテキストを賞賛した[51]。夫婦はサド侯爵、 フョードル・ドストエフスキー、フランツ・カフカ、ジャン・ジュネといった作家の作品に相互に関心を持ち、その作品はすべて性と暴力のテーマを探求してい た[52]。 私は、学生時代にマルクス主義、現象学、実存主義からなる地平を目の前にし、それによって制限されていた世代に属する。私にとっての区切りは、まずベケッ トの『ゴドーを待ちながら』であり、息をのむようなパフォーマンスだった。 - ミシェル・フーコー、1983年[53]。 スイスの心理学者ルートヴィヒ・ビンスワンガーの著作に興味を持ったフーコーは、家族の友人であるジャクリーヌ・ヴェルドーに彼の著作のフランス語への翻 訳を手伝わせた。1954年、フーコーはビンスワンガーの論文「夢と実存」の序論を執筆し、その中で夢は「世界の誕生」あるいは「むき出しにされた心」で あり、心の最も深い欲望を表現していると主張した[55]。 [55]同年、フーコーは最初の著書『精神病と人格』(Maladie mentale et personalité)を出版し、パブロフの反射心理学からフロイトの古典的な精神分析まで幅広い題材を扱いながら、マルクス主義思想とハイデガー思想 の両方から影響を受けていることを示した。エミール・デュルケームやマーガレット・ミードといった社会学者や人類学者の研究を参照しながら、病気は文化的 に相対的なものであるという持論を展開した[56]。伝記作家のジェームズ・ミラーは、本書は「博識と明らかな知性」を示しているものの、フーコーがその 後の著作で示したような「火とセンス」に欠けていると指摘した[57]。 [フーコーはこの本を軽蔑するようになり、再出版や英語への翻訳を阻止しようとして失敗した[59]。 スウェーデン、ポーランド、西ドイツ:1955年-1960年 フーコーはその後5年間を海外で過ごし、最初はスウェーデンで、宗教史家ジョルジュ・デュメジルと知り合ったことで得たウプサラ大学の文化外交官として働 く。 [61] 「北欧の憂鬱」と長い冬に慣れることは難しかったが、2人のフランス人、生化学者のジャン=フランソワ・ミケルと物理学者のジャック・パペ=レピーヌと親 交を深め、さまざまな男性と恋愛や性的関係を結んだ。1956年春、バラケはフーコーとの関係を断ち切り、「狂気の眩暈」から抜け出したいと発表した [63]。ウプサラでは、フーコーは余暇の多くを大学のカロリナ・レディヴィヴァ図書館で過ごし、医学史に関する蔵書を利用して研究を続けた。 [博士論文を書き上げたフーコーは、ウプサラ大学がその論文を受理してくれることを期待したが、同大学の実証主義的な科学史家であるステン・リンドロス は、その論文が推測に基づく一般論に満ちており、歴史学としては稚拙であると主張し、フーコーにウプサラ大学で博士号を授与することを認めなかった。この 拒絶のせいもあり、フーコーはスウェーデンを去った[65]。後にフーコーは、この著作が初稿であり、一定の質を欠いていたことを認めている[66]。 1958年10月、フーコーは再びデュメジルの要請を受け、ポーランド人民共和国の首都ワルシャワに到着し、ワルシャワ大学のセンター・フランセの責任者 となった。1956年の「ポーランドの十月」の余波を目の当たりにしたフーコーは、学生たちが共産主義政権であるポーランド労働者党に抗議したことから、 ほとんどのポーランド人が自分たちの政権をソビエト連邦の傀儡政権として軽蔑しており、体制が「ひどく」機能していると感じていた。 [69]フランスやスウェーデンと同様、ポーランドは法的には同性愛を容認していたが、社会的には顰蹙を買っており、フーコーは多くの男性と関係を持っ た。外交上のスキャンダルに悩まされたフーコーは、ポーランドを去り、新たな目的地へと向かうことを命じられる[70]。西ドイツで様々な職を得ることが できたため、フーコーはアンスティチュ・フランセ・ハンブルク(1958年から1960年にかけて院長を務めた)に移り、ウプサラやワルシャワで行ってい たのと同じ講義を担当する[71][72]。レーパーバーンの歓楽街で多くの時間を過ごし、女装子と関係を持つ[73]。 |
| Growing career (1960–1970) Madness and Civilization: 1960 Histoire de la folie is not an easy text to read, and it defies attempts to summarise its contents. Foucault refers to a bewildering variety of sources, ranging from well-known authors such as Erasmus and Molière to archival documents and forgotten figures in the history of medicine and psychiatry. His erudition derives from years pondering, to cite Poe, 'over many a quaint and curious volume of forgotten lore', and his learning is not always worn lightly. — Foucault biographer David Macey, 1993[74] In West Germany, Foucault completed in 1960 his primary thesis (thèse principale) for his State doctorate, titled Folie et déraison: Histoire de la folie à l'âge classique (trans. "Madness and Insanity: History of Madness in the Classical Age"), a philosophical work based upon his studies into the history of medicine. The book discussed how West European society had dealt with madness, arguing that it was a social construct distinct from mental illness. Foucault traces the evolution of the concept of madness through three phases: the Renaissance, the later 17th and 18th centuries, and the modern experience. The work alludes to the work of French poet and playwright Antonin Artaud, who exerted a strong influence over Foucault's thought at the time.[75] Histoire de la folie was an expansive work, consisting of 943 pages of text, followed by appendices and a bibliography.[76] Foucault submitted it at the University of Paris, although the university's regulations for awarding a State doctorate required the submission of both his main thesis and a shorter complementary thesis.[77] Obtaining a doctorate in France at the period was a multi-step process. The first step was to obtain a rapporteur, or "sponsor" for the work: Foucault chose Georges Canguilhem.[78] The second was to find a publisher, and as a result Folie et déraison was published in French in May 1961 by the company Plon, whom Foucault chose over Presses Universitaires de France after being rejected by Gallimard.[79] In 1964, a heavily abridged version was published as a mass market paperback, then translated into English for publication the following year as Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason.[80] Folie et déraison received a mixed reception in France and in foreign journals focusing on French affairs. Although it was critically acclaimed by Maurice Blanchot, Michel Serres, Roland Barthes, Gaston Bachelard, and Fernand Braudel, it was largely ignored by the leftist press, much to Foucault's disappointment.[81] It was notably criticised for advocating metaphysics by young philosopher Jacques Derrida in a March 1963 lecture at the University of Paris. Responding with a vicious retort, Foucault criticised Derrida's interpretation of René Descartes. The two remained bitter rivals until reconciling in 1981.[82] In the English-speaking world, the work became a significant influence on the anti-psychiatry movement during the 1960s; Foucault took a mixed approach to this, associating with a number of anti-psychiatrists but arguing that most of them misunderstood his work.[83] Foucault's secondary thesis (thèse complémentaire), written in Hamburg between 1959 and 1960, was a translation and commentary on German philosopher Immanuel Kant's Anthropology from a Pragmatic Point of View (1798);[72] the thesis was titled Introduction à l'Anthropologie.[84] Largely consisting of Foucault's discussion of textual dating—an "archaeology of the Kantian text"—he rounded off the thesis with an evocation of Nietzsche, his biggest philosophical influence.[85] This work's rapporteur was Foucault's old tutor and then-director of the ENS, Hyppolite, who was well acquainted with German philosophy.[76] After both theses were championed and reviewed, he underwent his public defense of his doctoral thesis (soutenance de thèse) on 20 May 1961.[86] The academics responsible for reviewing his work were concerned about the unconventional nature of his major thesis; reviewer Henri Gouhier noted that it was not a conventional work of history, making sweeping generalisations without sufficient particular argument, and that Foucault clearly "thinks in allegories".[87] They all agreed however that the overall project was of merit, awarding Foucault his doctorate "despite reservations".[88] University of Clermont-Ferrand, The Birth of the Clinic, and The Order of Things: 1960–1966 In October 1960, Foucault took a tenured post in philosophy at the University of Clermont-Ferrand, commuting to the city every week from Paris,[89] where he lived in a high-rise block on the rue du Dr Finlay.[90] Responsible for teaching psychology, which was subsumed within the philosophy department, he was considered a "fascinating" but "rather traditional" teacher at Clermont.[91] The department was run by Jules Vuillemin, who soon developed a friendship with Foucault.[92] Foucault then took Vuillemin's job when the latter was elected to the Collège de France in 1962.[93] In this position, Foucault took a dislike to another staff member whom he considered stupid: Roger Garaudy, a senior figure in the Communist Party. Foucault made life at the university difficult for Garaudy, leading the latter to transfer to Poitiers.[94] Foucault also caused controversy by securing a university job for his lover, the philosopher Daniel Defert, with whom he retained a non-monogamous relationship for the rest of his life.[95] Foucault adored the work of Raymond Roussel and wrote a literary study of it. Foucault maintained a keen interest in literature, publishing reviews in literary journals, including Tel Quel and Nouvelle Revue Française, and sitting on the editorial board of Critique.[96] In May 1963, he published a book devoted to poet, novelist, and playwright Raymond Roussel. It was written in under two months, published by Gallimard, and was described by biographer David Macey as "a very personal book" that resulted from a "love affair" with Roussel's work. It was published in English in 1983 as Death and the Labyrinth: The World of Raymond Roussel.[97] Receiving few reviews, it was largely ignored.[98] That same year he published a sequel to Folie et déraison, titled Naissance de la Clinique, subsequently translated as The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception. Shorter than its predecessor, it focused on the changes that the medical establishment underwent in the late 18th and early 19th centuries.[99] Like his preceding work, Naissance de la Clinique was largely critically ignored, but later gained a cult following.[98] It was of interest within the field of medical ethics, as it considered the ways in which the history of medicine and hospitals, and the training that those working within them receive, bring about a particular way of looking at the body: the 'medical gaze'.[100] Foucault was also selected to be among the "Eighteen Man Commission" that assembled between November 1963 and March 1964 to discuss university reforms that were to be implemented by Christian Fouchet, the Gaullist Minister of National Education. Implemented in 1967, they brought staff strikes and student protests.[101] In April 1966, Gallimard published Foucault's Les Mots et les choses ('Words and Things'), later translated as The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences.[102] Exploring how man came to be an object of knowledge, it argued that all periods of history have possessed certain underlying conditions of truth that constituted what was acceptable as scientific discourse. Foucault argues that these conditions of discourse have changed over time, from one period's épistémè to another.[103] Although designed for a specialist audience, the work gained media attention, becoming a surprise bestseller in France.[104] Appearing at the height of interest in structuralism, Foucault was quickly grouped with scholars such as Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, and Roland Barthes, as the latest wave of thinkers set to topple the existentialism popularized by Jean-Paul Sartre. Although initially accepting this description, Foucault soon vehemently rejected it.[105] Foucault and Sartre regularly criticised one another in the press. Both Sartre and Simone de Beauvoir attacked Foucault's ideas as "bourgeois", while Foucault retaliated against their Marxist beliefs by proclaiming that "Marxism exists in nineteenth-century thought as a fish exists in water; that is, it ceases to breathe anywhere else."[106] University of Tunis and Vincennes: 1966–1970 I lived [in Tunisia] for two and a half years. It made a real impression. I was present for large, violent student riots that preceded by several weeks what happened in May in France. This was March 1968. The unrest lasted a whole year: strikes, courses suspended, arrests. And in March, a general strike by the students. The police came into the university, beat up the students, wounded several of them seriously, and started making arrests ... I have to say that I was tremendously impressed by those young men and women who took terrible risks by writing or distributing tracts or calling for strikes, the ones who really risked losing their freedom! It was a political experience for me. — Michel Foucault, 1983[107] In September 1966, Foucault took a position teaching psychology at the University of Tunis in Tunisia. His decision to do so was largely because his lover, Defert, had been posted to the country as part of his national service. Foucault moved a few kilometres from Tunis, to the village of Sidi Bou Saïd, where fellow academic Gérard Deledalle lived with his wife. Soon after his arrival, Foucault announced that Tunisia was "blessed by history", a nation which "deserves to live forever because it was where Hannibal and St. Augustine lived".[108] His lectures at the university proved very popular, and were well attended. Although many young students were enthusiastic about his teaching, they were critical of what they believed to be his right-wing political views, viewing him as a "representative of Gaullist technocracy", even though he considered himself a leftist.[109] Foucault was in Tunis during the anti-government and pro-Palestinian riots that rocked the city in June 1967, and which continued for a year. Although highly critical of the violent, ultra-nationalistic and anti-semitic nature of many protesters, he used his status to try to prevent some of his militant leftist students from being arrested and tortured for their role in the agitation. He hid their printing press in his garden, and tried to testify on their behalf at their trials, but was prevented when the trials became closed-door events.[110] While in Tunis, Foucault continued to write. Inspired by a correspondence with the surrealist artist René Magritte, Foucault started to write a book about the impressionist artist Édouard Manet, but never completed it.[111] In 1968, Foucault returned to Paris, moving into an apartment on the Rue de Vaugirard.[112] After the May 1968 student protests, Minister of Education Edgar Faure responded by founding new universities with greater autonomy. Most prominent of these was the Centre Expérimental de Vincennes in Vincennes on the outskirts of Paris. A group of prominent academics were asked to select teachers to run the centre's departments, and Canguilheim recommended Foucault as head of the Philosophy Department.[113] Becoming a tenured professor of Vincennes, Foucault's desire was to obtain "the best in French philosophy today" for his department, employing Michel Serres, Judith Miller, Alain Badiou, Jacques Rancière, François Regnault, Henri Weber, Étienne Balibar, and François Châtelet; most of them were Marxists or ultra-left activists.[114] Lectures began at the university in January 1969, and straight away its students and staff, including Foucault, were involved in occupations and clashes with police, resulting in arrests.[115] In February, Foucault gave a speech denouncing police provocation to protesters at the Maison de la Mutualité.[116] Such actions marked Foucault's embrace of the ultra-left,[117] undoubtedly influenced by Defert, who had gained a job at Vincennes' sociology department and who had become a Maoist.[118] Most of the courses at Foucault's philosophy department were Marxist–Leninist oriented, although Foucault himself gave courses on Nietzsche, "The end of Metaphysics", and "The Discourse of Sexuality", which were highly popular and over-subscribed.[119] While the right-wing press was heavily critical of this new institution, new Minister of Education Olivier Guichard was angered by its ideological bent and the lack of exams, with students being awarded degrees in a haphazard manner. He refused national accreditation of the department's degrees, resulting in a public rebuttal from Foucault.[120] |
成長期のキャリア(1960-1970) 狂気と文明 1960 Histoire de la folie』は読みやすいテキストではない。フーコーは、エラスムスやモリエールといった有名な作家から、古文書や医学・精神医学史の忘れられた人物に至 るまで、困惑するほど多様な資料に言及している。彼の博識は、ポーの言葉を借りれば「忘れ去られた言い伝えの多くの古風で好奇心をそそる書物の上で」何年 も思索にふけったことに由来するものであり、その学識は必ずしも軽々しく身につけられているわけではない。 - フーコーの伝記作家デイヴィッド・メイシー、1993年[74]。 西ドイツにおいて、フーコーは1960年に『Folie et déraison』というタイトルの博士論文を完成させた: 同書は医学史の研究に基づいた哲学的著作である。この本は、西ヨーロッパ社会が狂気をどのように扱ってきたかを論じ、狂気は精神病とは異なる社会的構成物 であると主張した。フーコーは、ルネサンス、17世紀後半と18世紀、そして近代の経験という3つの段階を通して、狂気の概念の変遷をたどっている。この 作品は、当時のフーコーの思想に強い影響を与えたフランスの詩人であり劇作家であったアントナン・アルトーの作品を暗示している[75]。 フーコーはこの論文をパリ大学に提出したが、パリ大学の博士号授与の規定では、主論文とそれを補完する短い論文の両方を提出する必要があった[77]。最 初のステップは、ラポルトゥール、つまり研究の「スポンサー」を得ることであった: フーコーが選んだのはジョルジュ・カンギレムであった[78]。第二のステップは出版社を見つけることであり、その結果『Folie et déraison』は1961年5月にガリマールに断られた後、フーコーがPresses Universitaires de Franceよりも選んだプロン社からフランス語で出版された[79]: A History of Insanity in the Age of Reason』として出版された[80]。 この『Folie et déraison』はフランス国内でも、またフランス問題に焦点を当てた海外の雑誌でも、さまざまな評価を受けた。モーリス・ブランショ、ミシェル・セレ ス、ロラン・バルト、ガストン・バシュラール、フェルナン・ブローデルらによって批評的に絶賛されたものの、左派のマスコミからはほとんど無視され、フー コーを失望させた。1963年3月にパリ大学で行われた講義で、若手の哲学者ジャック・デリダによって形而上学を提唱していると批判されたことは記憶に新 しい。それに対してフーコーは、ルネ・デカルトに対するデリダの解釈を批判した。英語圏では、この著作は1960年代の反精神医学運動に大きな影響を与え た。フーコーはこれに対して複雑なアプローチをとり、多くの反精神医学者と付き合ったが、彼らのほとんどは自分の著作を誤解していると主張した[83]。 1959年から1960年にかけてハンブルクで書かれたフーコーの副論文(thèse complémentaire)は、ドイツの哲学者であるイマニュエル・カントの『プラグマティックな視点からの人間学』(1798年)の翻訳と解説で あった[72]。 [この論文の報告者はフーコーの古くからの家庭教師であり、当時ENSの所長であったヒポライトであり、彼はドイツ哲学に精通していた。 [76] 両論文が支持され、審査された後、彼は1961年5月20日に博士論文の公開弁論(soutenance de thèse)を行った。 [86]査読を担当した学者たちは、彼の主要な論文の型破りな性質に懸念を抱いていた。査読者のアンリ・グヒエは、それが従来の歴史学の著作ではなく、十 分な特定の議論なしに大雑把な一般化をしており、フーコーは明らかに「寓話で考えている」と指摘した[87]。しかし、彼らは全員、全体的なプロジェクト が有益であることに同意し、「留保はあったが」フーコーに博士号を授与した[88]。 クレルモンフェラン大学、『診療所の誕生』、『物事の秩序』: 1960-1966 1960年10月、フーコーはクレルモンフェラン大学で哲学の終身ポストを得て、毎週パリからクレルモンフェランに通い[89]、フィンレー通りにある高 層ビルに住んでいた[90]。哲学科の中に含まれていた心理学を教える責任を負っていた彼は、クレルモンでは「魅力的」だが「どちらかといえば伝統的」な 教師だと考えられていた[91]。 [1962年にヴュイユマンがコレージュ・ド・フランスに選出されると、フーコーはヴュイユマンの職を引き継ぐ: 共産党幹部のロジェ・ガロディである。フーコーは、ガロディに大学での生活を困難にさせ、ガロディをポワチエに移籍させた[94]。フーコーはまた、恋人 である哲学者ダニエル・ドフェールのために大学の職を確保し、論争を引き起こした。 フーコーはレイモン・ルーセルの作品を崇拝し、その文学的研究を書いた。 1963年5月、詩人、小説家、劇作家であるレイモン・ルーセルに捧げた本を出版。この本はガリマール社から出版され、伝記作家のデイヴィッド・メイシー によれば、ルーセルの作品への「恋情」から生まれた「非常に個人的な本」であった。この本は1983年に『死と迷宮』として英語で出版された: 同年、『Folie et déraison』の続編『Naissance de la Clinique』(後に『クリニックの誕生』と訳される)を出版: An Archaeology of Medical Perception』と訳された。前作よりも短い本書は、18世紀後半から19世紀初頭にかけての医学界の変化に焦点を当てたものであった[99]。 [フーコーはまた、1963年11月から1964年3月にかけて、ガウリスト派の国民教育大臣であったクリスチャン・フーシェによって実施される予定で あった大学改革を議論するために集められた「18人委員会」の一員にも選ばれていた。1967年に実施されたこの改革は、職員のストライキと学生の抗議行 動を引き起こした[101]。 1966年4月、ガリマール社からフーコーの『言葉と物』(Les Mots et les choses)が出版される: 人間がいかにして知の対象となったかを探求するこの本は、歴史のあらゆる時代において、科学的な言説として受け入れられるものを構成する、ある種の真理の 基礎的な条件を持っていたと論じている[102]。フーコーは、こうした言説の条件は時代とともに変化し、ある時代のエピステーメーから別の時代のエピス テーメーへと変化してきたと論じている[103]。専門家向けに作られたものの、この著作はメディアの注目を集め、フランスでは驚きのベストセラーとなっ た。フーコーとサルトルは定期的に新聞でお互いを批判していた。サルトルとシモーヌ・ド・ボーヴォワールはともにフーコーの思想を「ブルジョワ」として攻 撃し、フーコーは「マルクス主義は魚が水の中に存在するように、19世紀の思想の中に存在する。 チュニス大学とヴァンセンヌ大学:1966-1970年 チュニジアに)2年半住んだ。それは実に印象的だった。私は、フランスで5月に起こったことに数週間先行して起こった、大規模で暴力的な学生暴動に立ち 会った。これは1968年3月のことだった。暴動は1年間続いた。ストライキ、授業停止、逮捕。そして3月、学生によるゼネストが起こった。警察が大学に 入ってきて、学生を殴り、何人かに重傷を負わせ、逮捕を始めた......。小冊子を書いたり、配布したり、ストライキを呼びかけたりして、本当に自由を 失う危険を冒した若者たちに、私はとてつもない感銘を受けた!それは私にとって政治的な経験だった - ミシェル・フーコー、1983年[107]。 1966年9月、フーコーはチュニジアのチュニス大学で心理学を教える職に就く。そうすることにしたのは、恋人のデフェールが国家公務の一環としてチュニ ジアに赴任することになったからである。フーコーはチュニスから数キロ離れたシディ・ブ・サイード村に移り住み、そこには学者仲間のジェラール・デレダル が妻と住んでいた。到着後すぐにフーコーは、チュニジアは「歴史に祝福された」国であり、「ハンニバルと聖アウグスティヌスが住んでいた場所であるため、 永遠に生きるに値する」国であると発表した[108]。大学での彼の講義は非常に人気があり、多くの聴講者があった。多くの若い学生たちはフーコーの講義 に熱狂的であったが、彼の右翼的な政治的見解には批判的で、彼自身は左翼主義者であったにもかかわらず、彼を「ガウリスト・テクノクラシーの代表」とみな していた[109]。 フーコーは、1967年6月にチュニスを揺るがした反政府・親パレスチナ暴動の間、チュニスにいた。多くのデモ参加者の暴力的、超国家主義的、反ユダヤ主 義的な性質を強く批判しながらも、彼は自分の地位を利用して、過激な左翼の学生たちが、この扇動に参加したために逮捕され、拷問されるのを防ごうとした。 チュニスにいる間、フーコーは執筆活動を続けた。シュルレアリスムの芸術家ルネ・マグリットとの往復書簡に触発され、フーコーは印象派の芸術家エドゥアー ル・マネについての本を書き始めたが、完成することはなかった[111]。 1968年、フーコーはパリに戻り、ヴォジラール通りのアパートに引っ越した[112]。1968年5月の学生運動の後、エドガー・フォール教育大臣は、 より大きな自治権を持つ新しい大学を設立することで対応した。その中で最も顕著だったのは、パリ郊外のヴァンセンヌにあるヴァンセンヌ・エクスペリメンタ ル・センターであった。著名な学者のグループが、センターの学科を運営する教師を選ぶよう依頼され、カンギルハイムはフーコーを哲学科の学科長に推薦した [113]。 [113]ヴァンセンヌの終身教授となったフーコーの望みは、「今日のフランス哲学の最高峰」を自分の学部で獲得することであり、ミシェル・セレス、ジュ ディス・ミラー、アラン・バディウ、ジャック・ランシエール、フランソワ・ルノー、アンリ・ウェーバー、エティエンヌ・バリバール、フランソワ・シャトレ を採用し、彼らのほとんどはマルクス主義者や極左活動家であった[114]。 講義は1969年1月に同大学で開始され、フーコーを含む学生や職員はすぐに占拠や警察との衝突に巻き込まれ、逮捕者を出した。 [2月には、フーコーはメゾン・ド・ラ・ミュチュアリテで抗議者たちに対して警察の挑発行為を糾弾する演説を行った[116]。こうした行動は、フーコー が極左を受け入れたことを示すものであり[117]、ヴァンセンヌの社会学部で職を得、毛沢東主義者となったデフェールの影響を受けたことは間違いない。 [118] フーコーの哲学科のコースのほとんどはマルクス・レーニン主義を志向するものであったが、フーコー自身はニーチェ、「形而上学の終焉」、「セクシュアリ ティの言説」に関するコースを開講し、非常に人気が高く、定員を超える申し込みがあった[119]。右派の報道機関がこの新しい教育機関を激しく批判する 一方で、新しい教育大臣オリヴィエ・ギシャールは、そのイデオロギー的な傾向と、学生が行き当たりばったりで学位を授与される試験の欠如に怒りを覚えた。 彼は同学科の学位の国家認定を拒否し、フーコーは公の場で反論する結果となった[120]。 |
| Later life (1970–1984) Collège de France and Discipline and Punish: 1970–1975 Foucault desired to leave Vincennes and become a fellow of the prestigious Collège de France. He requested to join, taking up a chair in what he called the "history of systems of thought", and his request was championed by members Dumézil, Hyppolite, and Vuillemin. In November 1969, when an opening became available, Foucault was elected to the Collège, though with opposition by a large minority.[121] He gave his inaugural lecture in December 1970, which was subsequently published as L'Ordre du discours (The Discourse of Language).[122] He was obliged to give 12 weekly lectures a year—and did so for the rest of his life—covering the topics that he was researching at the time; these became "one of the events of Parisian intellectual life" and were repeatedly packed out events.[123] On Mondays, he also gave seminars to a group of students; many of them became a "Foulcauldian tribe" who worked with him on his research. He enjoyed this teamwork and collective research, and together they published a number of short books.[124] Working at the Collège allowed him to travel widely, giving lectures in Brazil, Japan, Canada, and the United States over the next 14 years.[125] In 1970 and 1972, Foucault served as a professor in the French Department of the University at Buffalo in Buffalo, New York.[126] In May 1971, Foucault co-founded the Groupe d'Information sur les Prisons (GIP) along with historian Pierre Vidal-Naquet and journalist Jean-Marie Domenach. The GIP aimed to investigate and expose poor conditions in prisons and give prisoners and ex-prisoners a voice in French society. It was highly critical of the penal system, believing that it converted petty criminals into hardened delinquents.[127] The GIP gave press conferences and staged protests surrounding the events of the Toul prison riot in December 1971, alongside other prison riots that it sparked off; in doing so it faced a police crackdown and repeated arrests.[128] The group became active across France, with 2,000 to 3,000, members, but disbanded before 1974.[129] Also campaigning against the death penalty, Foucault co-authored a short book on the case of the convicted murderer Pierre Rivière.[130] After his research into the penal system, Foucault published Surveiller et punir: Naissance de la prison (Discipline and Punish: The Birth of the Prison) in 1975, offering a history of the system in western Europe. In it, Foucault examines the penal evolution away from corporal and capital punishment to the penitentiary system that began in Europe and the United States around the end of the 18th century.[131] Biographer Didier Eribon described it as "perhaps the finest" of Foucault's works, and it was well received.[132] Foucault was also active in anti-racist campaigns; in November 1971, he was a leading figure in protests following the perceived racist killing of Arab migrant Djellali Ben Ali.[citation needed] In this he worked alongside his old rival Sartre, the journalist Claude Mauriac, and one of his literary heroes, Jean Genet. This campaign was formalised as the Committee for the Defence of the Rights of Immigrants, but there was tension at their meetings as Foucault opposed the anti-Israeli sentiment of many Arab workers and Maoist activists.[133] At a December 1972 protest against the police killing of Algerian worker Mohammad Diab, both Foucault and Genet were arrested, resulting in widespread publicity.[134] Foucault was also involved in founding the Agence de Press-Libération (APL), a group of leftist journalists who intended to cover news stories neglected by the mainstream press. In 1973, they established the daily newspaper Libération, and Foucault suggested that they establish committees across France to collect news and distribute the paper, and advocated a column known as the "Chronicle of the Workers' Memory" to allow workers to express their opinions. Foucault wanted an active journalistic role in the paper, but this proved untenable, and he soon became disillusioned with Libération, believing that it distorted the facts; he did not publish in it until 1980.[135] In 1975 he had an LSD experience with Simeon Wade and Michael Stoneman in Death Valley, California and later wrote "it was the greatest experience of his life, and that it profoundly changed his life and his work". In front of Zabriskie Point they took LSD while listening to a well-prepared music program: Richard Strauss's Four Last Songs, followed by Charles Ives's Three Places in New England, ending with a few avant-garde pieces by Stockhausen.[136][137] According to Wade, as soon as he came back to Paris, Foucault scrapped the second History of Sexuality's manuscript, and totally rethought the whole project.[138] The History of Sexuality and Iranian Revolution: 1976–1979 In 1976, Gallimard published Foucault's Histoire de la sexualité: la volonté de savoir (The History of Sexuality: The Will to Knowledge), a short book exploring what Foucault called the "repressive hypothesis". It revolved largely around the concept of power, rejecting both Marxist and Freudian theory. Foucault intended it as the first in a seven-volume exploration of the subject.[139] Histoire de la sexualité was a best-seller in France and gained positive press, but lukewarm intellectual interest, something that upset Foucault, who felt that many misunderstood his hypothesis.[140] He soon became dissatisfied with Gallimard after being offended by senior staff member Pierre Nora.[141] Along with Paul Veyne and François Wahl, Foucault launched a new series of academic books, known as Des travaux (Some Works), through the company Seuil, which he hoped would improve the state of academic research in France.[142] He also produced introductions for the memoirs of Herculine Barbin and My Secret Life.[143] Foucault's Histoire de la sexualité concentrates on the relation between truth and sex.[144] He defines truth as a system of ordered procedures for the production, distribution, regulation, circulation, and operation of statements.[145] Through this system of truth, power structures are created and enforced. Though Foucault's definition of truth may differ from other sociologists before and after him, his work with truth in relation to power structures, such as sexuality, has left a profound mark on social science theory. In his work, he examines the heightened curiosity regarding sexuality that induced a "world of perversion" during the elite, capitalist 18th and 19th century in the western world. According to Foucault in History of Sexuality, society of the modern age is symbolized by the conception of sexual discourses and their union with the system of truth.[144] In the "world of perversion", including extramarital affairs, homosexual behavior, and other such sexual promiscuities, Foucault concludes that sexual relations of the kind are constructed around producing the truth.[146] Sex became not only a means of pleasure, but an issue of truth.[146] Sex is what confines one to darkness, but also what brings one to light.[147] Similarly, in The History of Sexuality, society validates and approves people based on how closely they fit the discursive mold of sexual truth.[148] As Foucault reminds us, in the 18th and 19th centuries, the Church was the epitome of power structure within society. Thus, many aligned their personal virtues with those of the Church, further internalizing their beliefs on the meaning of sex.[148] However, those who unify their sexual relation to the truth become decreasingly obliged to share their internal views with those of the Church. They will no longer see the arrangement of societal norms as an effect of the Church's deep-seated power structure. There exists an international citizenry that has its rights, and has its duties, and that is committed to rise up against every abuse of power, no matter who the author, no matter who the victims. After all, we are all ruled, and as such, we are in solidarity. — Michel Foucault, 1981[149] Foucault remained a political activist, focusing on protesting government abuses of human rights around the world. He was a key player in the 1975 protests against the Spanish government who were set to execute 11 militants sentenced to death without fair trial. It was his idea to travel to Madrid with six others to give a press conference there; they were subsequently arrested and deported back to Paris.[150] In 1977, he protested the extradition of Klaus Croissant to West Germany, and his rib was fractured during clashes with riot police.[151] In July that year, he organised an assembly of Eastern Bloc dissidents to mark the visit of Soviet general secretary Leonid Brezhnev to Paris.[152] In 1979, he campaigned for Vietnamese political dissidents to be granted asylum in France.[153] In 1977, Italian newspaper Corriere della sera asked Foucault to write a column for them. In doing so, in 1978 he travelled to Tehran in Iran, days after the Black Friday massacre. Documenting the developing Iranian Revolution, he met with opposition leaders such as Mohammad Kazem Shariatmadari and Mehdi Bazargan, and discovered the popular support for Islamism.[154] Returning to France, he was one of the journalists who visited the Ayatollah Khomeini, before visiting Tehran. His articles expressed awe of Khomeini's Islamist movement, for which he was widely criticised in the French press, including by Iranian expatriates. Foucault's response was that Islamism was to become a major political force in the region, and that the West must treat it with respect rather than hostility.[155] In April 1978, Foucault traveled to Japan, where he studied Zen Buddhism under Omori Sogen at the Seionji temple in Uenohara.[125] |
その後の人生(1970-1984) コレージュ・ド・フランスと『規律と罰』:1970-1975年 フーコーはヴァンセンヌを離れ、名門コレージュ・ド・フランスのフェローになることを望んだ。彼は「思想システム史」と呼ばれる講座に参加することを希望 し、デュメジル、ヒュポリット、ヴュイユマンの3人の会員が彼の希望を支持した。1969年11月、空席ができたため、フーコーは少数派の反対を押し切っ てコレージュに選出された[121]。1970年12月、彼は就任講演を行い、その講演は後に『言語の言説』(L'Ordre du discours)として出版された。 [この講義は「パリの知的生活のイベントのひとつ」となり、何度も満員御礼となった[123]。月曜日には、彼はまた学生のグループに対してセミナーを 行った。フーコーはこのチームワークと集団的な研究を楽しんでおり、彼らは一緒に数多くの短い本を出版した[124]。コレージュで働くことで、彼は広く 旅することができ、その後14年間にわたってブラジル、日本、カナダ、アメリカで講義を行った[125]。 1971年5月、フーコーは歴史家のピエール・ヴィダル=ナケ、ジャーナリストのジャン=マリー・ドメナックとともにGIP(Groupe d'Information sur les Prisons)を共同設立。GIPは、刑務所の劣悪な状況を調査・暴露し、囚人や元囚人にフランス社会での発言権を与えることを目的としていた。GIP は1971年12月にトゥール刑務所で起こった暴動をめぐって記者会見を開き、抗議活動を行った。 [128]このグループはフランス全土で活動するようになり、2,000人から3,000人のメンバーを擁したが、1974年以前に解散した[129]。 また、死刑反対運動を展開し、フーコーは有罪判決を受けた殺人者ピエール・リヴィエールの事件に関する短い本を共著した[130]: 1975年に『規律と罰:刑務所の誕生』を出版し、西ヨーロッパにおける刑罰制度の歴史を提示した。その中でフーコーは、18世紀末頃にヨーロッパとアメ リカで始まった、体罰と死刑から刑務所制度への刑罰の進化を検証している[131]。伝記作家のディディエ・エリボンは、この著作をフーコーの著作の中で 「おそらく最高傑作」と評し、好評を博した[132]。 1971年11月、アラブからの移民であるジェラリ・ベン・アリが人種差別によって殺害されたと認識されたことを受けて、フーコーは抗議活動の中心人物と なった。このキャンペーンは「移民の権利擁護委員会」として正式に発足したが、フーコーは多くのアラブ人労働者や毛沢東主義活動家の反イスラエル感情に反 対していたため、彼らの会合には緊張感があった。 [1972年12月、警察によるアルジェリア人労働者モハマド・ディアブの殺害に対する抗議活動で、フーコーとジュネは逮捕され、広く世間に知られること になった[134]。フーコーはまた、主流紙によって無視されたニュースを報道することを目的とした左派ジャーナリストのグループ、Agence de Press-Libération(APL)の設立にも関わった。1973年、彼らは日刊紙『リベラシオン』を創刊し、フーコーはフランス全土に委員会を 設置してニュースを収集し、紙面を配布することを提案し、労働者が意見を表明できるように「労働者の記憶のクロニクル」と呼ばれるコラムを提唱した。 1975年、カリフォルニア州デスバレーでシメオン・ウェイドとマイケル・ストーンマンとLSD体験をし、後に「人生最大の体験であり、彼の人生と仕事を 大きく変えた」と記している[135]。ザブリスキー・ポイントの前で、彼らは用意周到な音楽プログラムを聴きながらLSDを摂取した: リヒャルト・シュトラウスの『4つの最後の歌』、チャールズ・アイヴズの『ニューイングランドの3つの場所』と続き、シュトックハウゼンの前衛的な小品で 終わる[136][137]。ウェイドによれば、パリに戻るとすぐにフーコーは『セクシュアリティの歴史』第2版の原稿を破棄し、プロジェクト全体を全面 的に考え直したという。 セクシュアリティの歴史』とイラン革命: 1976-1979 1976年、ガリマールはフーコーの『性の歴史:知識への意志』(Histoire de la sexualité: la volonté de savoir)を出版した。この本は、マルクス主義とフロイトの理論を否定し、権力の概念を中心に展開された。フーコーはこの本を7巻からなる主題の探求 の最初の一冊とするつもりであった[139]。Histoire de la sexualitéはフランスでベストセラーとなり、好意的な報道を得たが、知的関心は薄く、多くの人が自分の仮説を誤解していると感じていたフーコーを 動揺させた[140]。 フーコーは上級スタッフのピエール・ノラに腹を立て、すぐにガリマールに不満を抱くようになる。 [141]ポール・ヴェイヌとフランソワ・ヴァールとともに、フーコーはフランスの学術研究の状況を改善することを期待し、セイユ社を通じて『Des travaux(いくつかの作品)』として知られる学術書の新シリーズを立ち上げた[142]。 フーコーのHistoire de la sexualitéは真理と性の関係に集中している[144]。彼は真理を陳述の生産、分配、規制、流通、運用のための秩序だった手続きのシステムとして 定義している[145]。フーコーの真理の定義は彼の前後の社会学者とは異なるかもしれないが、セクシュアリティのような権力構造との関係における真理に 関する彼の仕事は、社会科学理論に深い足跡を残している。フーコーの著作では、18世紀から19世紀にかけての西欧世界におけるエリート、資本主義の時代 に、「倒錯の世界」を誘発したセクシュアリティに対する好奇心の高まりを検証している。セクシュアリティの歴史』におけるフーコーによれば、近代の社会 は、性的言説の観念と真理の体系との結合によって象徴されている。 [144]婚外交渉、同性愛行動、その他のそのような性的乱交を含む「倒錯の世界」において、フーコーは、その種の性的関係は真実を生み出すことを中心に 構築されていると結論付けている[146]。 セックスは快楽の手段であるだけでなく、真実の問題となった[146]。 同様に、『セクシュアリティの歴史』においては、社会は、彼らがどれだけ性的真実の言説的型に忠実であるかに基づいて人々を正当化し、承認する [148]。フーコーが思い起こさせるように、18世紀から19世紀にかけて、教会は社会における権力構造の典型であった。148]しかし、自分の性的関 係を真理に統一する者は、自分の内的見解を教会の見解と共有する義務が減少していく。彼らはもはや、社会規範の取り決めを、教会の根深い権力構造の影響と みなすことはないだろう。 国際的な市民が存在し、その市民には権利があり、義務があり、誰が作者であろうと、誰が被害者であろうと、あらゆる権力の乱用に対して立ち上がることを約 束する。結局のところ、私たちはみな支配されているのであり、連帯しているのである。 - ミシェル・フーコー、1981年[149]。 フーコーは政治活動家であり続け、世界各地で政府による人権侵害に抗議することに力を注いだ。彼は、公正な裁判を経ずに死刑判決を受けた11人の過激派を 処刑しようとしていたスペイン政府に対する1975年の抗議活動の中心人物であった。1977年には、クラウス・クロワッサンの西ドイツへの引き渡しに抗 議し、機動隊と衝突して肋骨を骨折した[151]。同年7月には、ソ連のレオニード・ブレジネフ書記長のパリ訪問を記念して、東欧圏の反体制派の集会を組 織した[152]。1979年には、ベトナムの政治的反体制派にフランスへの亡命を認めるよう運動した[153]。 1977年、イタリアのコリエレ・デラ・セラ紙がフーコーにコラムの執筆を依頼。その際、1978年にイランのテヘランを訪れた。発展途上のイラン革命を 記録し、モハマド・カゼム・シャリアートマダーリやメフディ・バザルガンといった反対派の指導者たちと会い、イスラム主義に対する民衆の支持を知った [154]。フランスに戻り、テヘランを訪れる前にホメイニ師を訪問したジャーナリストの一人となる。彼の記事は、ホメイニのイスラム主義運動に対する畏 敬の念を表現したもので、イラン人駐在員を含め、フランスの新聞で広く批判された。1978年4月、フーコーは日本を訪れ、上野原にある清音寺で大森曹玄 に禅宗を学んだ[125]。 |
| Final years: 1980–1984 Although remaining critical of power relations, Foucault expressed cautious support for the Socialist Party government of François Mitterrand following its electoral victory in 1981.[156] But his support soon deteriorated when that party refused to condemn the Polish government's crackdown on the 1982 demonstrations in Poland orchestrated by the Solidarity trade union. He and sociologist Pierre Bourdieu authored a document condemning Mitterrand's inaction that was published in Libération, and they also took part in large public protests on the issue.[157] Foucault continued to support Solidarity, and with his friend Simone Signoret traveled to Poland as part of a Médecins du Monde expedition, taking time out to visit the Auschwitz concentration camp.[158] He continued his academic research, and in June 1984 Gallimard published the second and third volumes of Histoire de la sexualité. Volume two, L'Usage des plaisirs, dealt with the "techniques of self" prescribed by ancient Greek pagan morality in relation to sexual ethics, while volume three, Le Souci de soi, explored the same theme in the Greek and Latin texts of the first two centuries CE. A fourth volume, Les Aveux de la chair, was to examine sexuality in early Christianity, but it was not finished.[159] In October 1980, Foucault became a visiting professor at the University of California, Berkeley, giving the Howison Lectures on "Truth and Subjectivity", while in November he lectured at the Humanities Institute at New York University. His growing popularity in American intellectual circles was noted by Time magazine, while Foucault went on to lecture at UCLA in 1981, the University of Vermont in 1982, and Berkeley again in 1983, where his lectures drew huge crowds.[160] Foucault spent many evenings in the San Francisco gay scene, frequenting sado-masochistic bathhouses, engaging in unprotected sex. He praised sado-masochistic activity in interviews with the gay press, describing it as "the real creation of new possibilities of pleasure, which people had no idea about previously".[161] Foucault contracted HIV and eventually developed AIDS. Little was known of the virus at the time; the first cases had only been identified in 1980.[162] Foucault initially referred to AIDS as a "dreamed-up disease".[163] In summer 1983, he developed a persistent dry cough, which concerned friends in Paris, but Foucault insisted it was just a pulmonary infection.[164] Only when hospitalized was Foucault correctly diagnosed as being HIV-positive; treated with antibiotics, he delivered a final set of lectures at the Collège de France.[165] Foucault entered Paris' Hôpital de la Salpêtrière—the same institution that he had studied in Madness and Civilisation—on 10 June 1984, with neurological symptoms complicated by sepsis. He died in the hospital on 25 June.[166] Death On 26 June 1984, Libération announced Foucault's death, mentioning the rumour that it had been brought on by AIDS. The following day, Le Monde issued a medical bulletin cleared by his family that made no reference to HIV/AIDS.[167] On 29 June, Foucault's la levée du corps ceremony was held, in which the coffin was carried from the hospital morgue. Hundreds attended, including activists and academic friends, while Gilles Deleuze gave a speech using excerpts from The History of Sexuality.[168] His body was then buried at Vendeuvre-du-Poitou in a small ceremony.[169] Soon after his death, Foucault's partner Daniel Defert founded the first national HIV/AIDS organisation in France, AIDES; a play on the French word for "help" (aide) and the English- language acronym for the disease.[170] On the second anniversary of Foucault's death, Defert publicly revealed in The Advocate that Foucault's death was AIDS-related.[171] |
晩年 1980-1984 フーコーは権力関係に批判的であり続けたが、1981年の選挙での勝利後、フランソワ・ミッテラン社会党政権への慎重な支持を表明した[156]。しか し、同党が1982年にポーランドで連帯労働組合が組織したデモに対するポーランド政府の弾圧を非難することを拒否したため、彼の支持はすぐに悪化した。 社会学者ピエール・ブルデューとともにミッテランの無策を非難する文書を執筆し、『リベラシオン』誌に掲載され、この問題に関する大規模な抗議行動にも参 加した[157]。第2巻『L'Usage des plaisirs』では、古代ギリシャの異教道徳が性的倫理に関連して規定した「自己の技法」を扱い、第3巻『Le Souci de soi』では、紀元後2世紀のギリシャ語とラテン語のテキストにおける同じテーマを探求した。第4巻『Les Aveux de la chair』は初期キリスト教におけるセクシュアリティを考察する予定だったが、未完に終わった[159]。 1980年10月、フーコーはカリフォルニア大学バークレー校の客員教授となり、「真理と主観性」に関するハウソン講義を行い、11月にはニューヨーク大 学の人文科学研究所で講義を行った。フーコーは1981年にはUCLA、1982年にはバーモント大学、1983年にはバークレーで講義を行い、彼の講義 は多くの聴衆を集めた[160]。フーコーはサンフランシスコのゲイ・シーンで多くの夜を過ごし、サド・マゾ的な浴場に足繁く通い、無防備なセックスに興 じた。彼はゲイプレスとのインタビューでサド・マゾヒスティックな行為を賞賛し、それを「人々が以前は考えもしなかった新しい快楽の可能性の真の創造」と 表現した[161]。フーコーは当初、エイズを「夢物語のような病気」と呼んでいた[163]。1983年夏、乾いた咳が続くようになり、パリの友人たち は心配したが、フーコーはただの肺感染症だと主張した[164]。 [164] 入院して初めてフーコーはHIV陽性であると正しく診断され、抗生物質による治療を受け、コレージュ・ド・フランスで最後の講義を行った[165] 。6月25日に病院で死去した[166]。 死 1984年6月26日、リベラシオンはフーコーの死を発表し、エイズによるものだという噂に触れた。翌日、ル・モンド紙は遺族が確認した医学的速報を発表 し、HIV/AIDSについては言及しなかった[167]。6月29日、フーコーの死体安置所から棺を運ぶ儀式が行われた。ジル・ドゥルーズが『セクシュ アリティの歴史』からの抜粋を用いたスピーチを行い、彼の遺体はヴァンドゥヴル=デュ=ポワトゥーに埋葬された。 [169]フーコーのパートナーであったダニエル・ドフェールは、彼の死後すぐにフランス初のHIV/AIDSの全国組織であるAIDESを設立した。 フーコーの2回目の命日に、ドフェールは『アドヴォケイト』誌でフーコーの死がAIDSに関連したものであったことを公にした[171]。 |
| Personal life Foucault's first biographer, Didier Eribon, described the philosopher as "a complex, many-sided character", and that "under one mask there is always another".[172] He also noted that he exhibited an "enormous capacity for work".[173] At the ENS, Foucault's classmates unanimously summed him up as a figure who was both "disconcerting and strange" and "a passionate worker".[174] As he aged, his personality changed: Eribon noted that while he was a "tortured adolescent", post-1960, he had become "a radiant man, relaxed and cheerful", even being described by those who worked with him as a dandy.[175] He noted that in 1969, Foucault embodied the idea of "the militant intellectual".[176] Foucault was an atheist.[177][178] He loved classical music, particularly enjoying the work of Johann Sebastian Bach and Wolfgang Amadeus Mozart,[179] and became known for wearing turtleneck sweaters.[180] After his death, Foucault's friend Georges Dumézil described him as having possessed "a profound kindness and goodness", also exhibiting an "intelligence [that] literally knew no bounds".[181] His life-partner Daniel Defert inherited his estate,[182] whose archive was sold in 2012 to the National Library of France for €3.8 million ($4.5 million in April 2021).[183] Politics Politically, Foucault was a leftist throughout much of his life, though his particular stance within the left often changed. In the early 1950s, while never adopting an orthodox Marxist viewpoint, Foucault had been a member of the French Communist Party, leaving the party after three years as he expressed disgust in the prejudice within its ranks against Jews and homosexuals. After spending some time working in Poland, which was a Communist state ostensibly governed by the Polish United Workers' Party but actually was an abject police-state satellite of the Soviet Union, he became further disillusioned with communist ideology. As a result, in the early 1960s, Foucault was considered to be "violently anticommunist" by some of his detractors,[184] even though he was involved in leftist campaigns along with most of his students and colleagues.[185] Views on underage sex Foucault argued that children could give sexual consent.[186] In 1977, along with Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, and other intellectuals, Foucault signed a petition to the French parliament calling for the decriminalization of all "consensual" sexual relations between adults and minors below the age of fifteen, the age of consent in France.[187][188] In a 1978 broadcast, Foucault said that "to assume that a child is incapable of explaining what happened and was incapable of giving his consent are two abuses that are intolerable, quite unacceptable."[189] Philosophical work See also: Michel Foucault bibliography Foucault's colleague Pierre Bourdieu summarized the philosopher's thought as "a long exploration of transgression, of going beyond social limits, always inseparably linked to knowledge and power".[190] The theme that underlies all Foucault's work is the relationship between power and knowledge, and how the former is used to control and define the latter. What authorities claim as 'scientific knowledge' are really just means of social control. Foucault shows how, for instance, in the eighteenth century 'madness' was used to categorize and stigmatize not just the mentally ill but the poor, the sick, the homeless and, indeed, anyone whose expressions of individuality were unwelcome. — Philip Stokes, Philosophy: 100 Essential Thinkers (2004)[191] Philosopher Philip Stokes of the University of Reading noted that overall, Foucault's work was "dark and pessimistic". Though it does, however, leave some room for optimism, in that it illustrates how the discipline of philosophy can be used to highlight areas of domination. In doing so, as Stokes claimed, the ways in which we are being dominated become better understood, so that we may strive to build social structures that minimise this risk of domination.[191] In all of this development there had to be close attention to detail; it is the detail which eventually individualizes people.[192] Later in his life, Foucault explained that his work was less about analyzing power as a phenomenon than about trying to characterize the different ways in which contemporary society has expressed the use of power to "objectivise subjects". These have taken three broad forms: one involving scientific authority to classify and 'order' knowledge about human populations; the second has been to categorize and 'normalise' human subjects (by identifying madness, illness, physical features, and so on); and the third relates to the manner in which the impulse to fashion sexual identities and train one's own body to engage in routines and practices ends up reproducing certain patterns within a given society.[193] Literature In addition to his philosophical work, Foucault also wrote on literature. Death and the Labyrinth: The World of Raymond Roussel, published in 1963 and translated in English in 1986, is Foucault's only book-length work on literature. He described it as "by far the book I wrote most easily, with the greatest pleasure, and most rapidly".[194] Foucault explores theory, criticism, and psychology with reference to the texts of Raymond Roussel, one of the first notable experimental writers. Foucault also gave a lecture responding to Roland Barthes' famous essay "The Death of the Author" titled "What Is an Author?" in 1969, later published in full.[195] According to literary theoretician Kornelije Kvas, for Foucault, "denying the existence of a historical author on account of his/her irrelevance for interpretation is absurd, for the author is a function of the text that organizes its sense".[196] Power Foucault's analysis of power comes in two forms: empirical and theoretical. The empirical analyses concern themselves with historical (and modern) forms of power and how these emerged from previous forms of power. Foucault describes three types of power in his empirical analyses: sovereign power, disciplinary power, and biopower.[197] Foucault is generally critical of "theories" that try to give absolute answers to "everything". Therefore, he considered his own "theory" of power to be closer to a method than a typical "theory". According to Foucault, most people misunderstand power. For this reason, he makes clear that power cannot be completely described as:[197] A group of institutions and/or mechanisms whose aim it is for a citizen to obey and yield to the state (a typical liberal definition of power);[197] Yielding to rules (a typical psychoanalytical definition of power);[197] or A general and oppressing system where one societal class or group oppresses another (a typical feminist or Orthodox Marxist definition of power).[197] Foucault is not critical of considering these phenomena as "power", but claims that these theories of power cannot completely describe all forms of power. Foucault also claims that a liberal definition of power has effectively hidden other forms of power to the extent that people have uncritically accepted them.[197] Foucault's power analysis begins on micro-level, with singular "force relations". Richard A. Lynch defines Foucault's concept of "force relation" as "whatever in one's social interactions that pushes, urges or compels one to do something".[198] According to Foucault, force relations are an effect of difference, inequality or unbalance that exists in other forms of relationships (such as sexual or economic). Force, and power, is however not something that a person or group "holds" (such as in the sovereign definition of power), instead power is a complex group of forces that comes from "everything" and therefore exists everywhere. That relations of power always result from inequality, difference or unbalance also means that power always has a goal or purpose. Power comes in two forms: tactics and strategies. Tactics is power on the micro-level, which can for example be how a person chooses to express themselves through their clothes. Strategies on the other hand, is power on macro-level, which can be the state of fashion at any moment. Strategies consist of a combination of tactics. At the same time, power is non-subjective according to Foucault. This posits a paradox, according to Lynch, since "someone" has to exert power, while at the same time there can be no "someone" exerting this power.[197] According to Lynch this paradox can be solved with two observations: By looking at power as something which reaches further than the influence of single people or groups. Even if individuals and groups try to influence fashion, for example, their actions will often get unexpected consequences.[197] Even if individuals and groups have a free choice, they are also affected and limited by their context/situation.[197] According to Foucault, force relations are constantly changing, constantly interacting with other force relations which may weaken, strengthen or change one another. Foucault writes that power always includes resistance, which means there is always a possibility that power and force relations will change in some way. According to Richard A. Lynch, the purpose of Foucault's work on power is to increase peoples' awareness of how power has shaped their way of being, thinking and acting, and by increasing this awareness making it possible for them to change their way of being, thinking and acting.[197] Sovereign power With "sovereign power" Foucault alludes to a power structure that is similar to a pyramid, where one person or a group of people (at the top of the pyramid) holds the power, while the "normal" (and oppressed) people are at the bottom of the pyramid. In the middle parts of the pyramid are the people who enforce the sovereign's orders. A typical example of sovereign power is absolute monarchy.[197] In historical absolute monarchies, crimes had been considered a personal offense against the sovereign and his/her power. The punishment was often public and spectacular, partly to deter others from committing crimes, but also to reinstate the sovereign's power. This was however both expensive and ineffective—it led far too often to people sympathizing with the criminal. In modern times, when disciplinary power is dominant, criminals are instead subjected to various disciplinary techniques to "remold" the criminal into a "law abiding citizen".[199] According to Chloë Taylor, a characteristic for sovereign power is that the sovereign has the right to take life, wealth, services, labor and products. The sovereign has a right to subtract—to take life, to enslave life, etc.—but not the right to control life in the way that later happens in disciplinary systems of power. According to Taylor, the form of power that the philosopher Thomas Hobbes is concerned about, is sovereign power. According to Hobbes, people are "free" so long they are not literally placed in chains.[200] Disciplinary power What Foucault calls "disciplinary power" aims to use bodies' skills as effectively as possible.[201] The more useful the body becomes, the more obedient it also has to become. The purpose of this is not only to use the bodies' skills, but also prevent these skills from being used to revolt against the power.[201] Disciplinary power has "individuals" as its object, target and instrument. According to Foucault, "individual" is however a construct created by disciplinary power.[201] The disciplinary power's techniques create a "rational self-control",[202] which in practice means that the disciplinary power is internalized and therefore doesn't continuously need external force. Foucault says that disciplinary power is primarily not an oppressing form of power, but rather so a productive form of power. Disciplinary power doesn't oppress interests or desires, but instead subjects bodies to reconstructed patterns of behavior to reconstruct their thoughts, desires and interests. According to Foucault this happens in factories, schools, hospitals and prisons.[203] Disciplinary power creates a certain type of individual by producing new movements, habits and skills. It focuses on details, single movements, their timing and speed. It organizes bodies in time and space, and controls every movement for maximal effect. It uses rules, surveillance, exams and controls.[203] The activities follow certain plans, whose purpose it is to lead the bodies to certain pre-determined goals. The bodies are also combined with each other, to reach a productivity that is greater than the sum of all bodies activities.[201] Disciplinary power has according to Foucault been especially successful due to its usage of three technologies: hierarchical observation, normalizing judgement and exams.[201] By hierarchical observation, the bodies become constantly visible to the power. The observation is hierarchical since there is not a single observer, but rather so a "hierarchy" of observers. An example of this is mental asylums during the 19th century, when the psychiatrist was not the only observer, but also nurses and auxiliary staff. From these observations and scientific discourses, a norm is established and used to judge the observed bodies. For the disciplinary power to continue to exist, this judgement has to be normalized. Foucault mentions several characteristics of this judgement: (1) all deviations, even small ones, from correct behavior are punished, (2) repeated rule violations are punished extra, (3) exercises are used as a behavior correcting technique and punishment, (4) rewards are used together with punishment to establish a hierarchy of good and bad behavior/people, (5) rank/grades/etc. are used as punishment and reward. Examinations combine the hierarchical observation with judgement. Exams objectify and individualize the observed bodies by creating extensive documentation about every observed body. The purpose of the exams is therefore to gather further information about each individual, track their development and compare their results to the norm.[201] According to Foucault, the "formula" for disciplinary power can be seen in philosopher Jeremy Bentham's plan for the "optimal prison": the panopticon. Such a prison consists of a circle-formed building where every cell is inhabited by only one prisoner. In every cell there are two windows—one to let in light from outside and one pointing to the middle of the circle-formed building. In this middle there is a tower where a guard can be placed to observe the prisoners. Since the prisoners will never be able to know whether they are being watched or not at a given moment, they will internalize the disciplinary power and regulate their own behavior (as if they were constantly being watched). Foucault says this construction (1) creates an individuality by separating prisoners from each other in the physical room, (2) since the prisoners cannot know if they are being watched at any given moment, they internalize the disciplinary power and regulate their own behavior as if they were always watched, (3) the surveillance makes it possible to create extensive documentation about each prisoner and their behavior. According to Foucault the panopticon has been used as a model also for other disciplinary institutions, such as mental asylums in the 19th century.[201] Biopower Further information: Biopower With "biopower" Foucault refers to power over bios (life)—power over populations. Biopower primarily rests on norms which are internalized by people, rather than external force. It encourages, strengthens, controls, observes, optimizes and organize the forces below it. Foucault has sometimes described biopower as separate from disciplinary power, but at other times he has described disciplinary power as an expression of biopower. Biopower can use disciplinary techniques, but in contrast to disciplinary power its target is populations rather than individuals.[200] Biopower studies populations regarding (for example) number of births, life expectancy, public health, housing, migration, crime, which social groups are over-represented in deviations from the norm (regarding health, crime, etc.) and tries to adjust, control or eliminate these norm deviations. One example is the age distribution in a population. Biopower is interested in age distribution to compensate for future (or current) lacks of labor power, retirement homes, etc. Yet another example is sex: because sex is connected to population growth, sex and sexuality have been of great interest to biopower. On a disciplinary level, people who engaged in non-reproductive sexual acts have been treated for psychiatric diagnoses such as "perversion", "frigidity" and "sexual dysfunction". On a biopower-level, the usage of contraceptives has been studied, some social groups have (by various means) been encouraged to have children, while others (such as poor, sick, unmarried women, criminals or people with disabilities) have been discouraged or prevented from having children.[200] In the era of biopower, death has become a scandal and a catastrophe, but despite this biopower has according to Foucault killed more people than any other form of power has ever done before it. Under sovereign power, the sovereign king could kill people to exert his power or start wars simply to extend his kingdom, but during the era of biopower wars have instead been motivated by an ambition to "protect life itself". Similar motivations has also been used for genocide. For example, Nazi Germany motivated its attempt to eradicate Jews, the mentally ill and disabled with the motivation that Jews were "a threat to the German health", and that the money spent on healthcare for mentally ill and disabled people would be better spent on "viable Germans". Chloë Taylor also mentions the Iraq War was motivated by similar tenets. The motivation was at first that Iraq was thought to have weapons of mass destruction and connections to Al-Qaeda. However, when the Bush and Blair administrations didn't find any evidence to support either of these theories, the motivation for the war was changed. In the new motivation, the cause of the war was said to be that Saddam Hussein had committed crimes against his own population. Taylor means that in modern times, war has to be "concealed" under a rhetoric of humanitarian aid, despite the fact that these wars often cause humanitarian crises.[200] During the 19th century, slums were increasing in number and size across the western world. Criminality, illness, alcoholism and prostitution was common in these areas, and the middle class considered the people who lived in these slums as "unmoral" and "lazy". The middle class also feared that this underclass sooner or later would "take over" because the population growth was greater in these slums than it was in the middle class. This fear gave rise to the scientific study of eugenics, whose founder Francis Galton had been inspired by Charles Darwin and his theory of natural selection. According to Galton, society was preventing natural selection by helping "the weak", thus causing a spread of the "negative qualities" into the rest of the population.[200] The body and sexuality According to Foucault, the body is not something objective that stands outside history and culture. Instead, Foucault argues, the body has been and is continuously shaped by society and history—by work, diet, body ideals, exercise, medical interventions, etc. Foucault presents no "theory" of the body, but does write about it in Discipline and Punish as well as in The History of Sexuality. Foucault was critical of all purely biological explanations of phenomena such as sexuality, madness and criminality. Further, Foucault argues, that the body is not sufficient as a basis for self-understanding and understanding of others.[203] In Discipline and Punish, Foucault shows how power and the body are tied together, for example by the disciplinary power primarily focusing on individual bodies and their behavior. Foucault argues that power, by manipulating bodies/behavior, also manipulates people's minds. Foucault turns the common saying "the body is the prison of the soul" and instead posits that "the soul is the prison of the body".[203] According to Foucault, sexology has tried to exert itself as a "science" by referring to the material (the body). In contrast to this, Foucault argues that sexology is a pseudoscience, and that "sex" is a pseudo-scientific idea. For Foucault the idea of a natural, biologically grounded and fundamental sexuality is a normative historical construct that has also been used as an instrument of power. By describing sex as the biological and fundamental cause to peoples' gender identity, sexual identity and sexual behavior, power has effectively been able to normalize sexual and gendered behavior. This has made it possible to evaluate, pathologize and "correct" peoples' sexual and gendered behavior, by comparing bodies behaviors to the constructed "normal" behavior. For Foucault, a "normal sexuality" is as much of a construct as a "natural sexuality". Therefore, Foucault was also critical of the popular discourse that dominated the debate over sexuality during the 1960s and 1970s. During this time, the popular discourse argued for a "liberation" of sexuality from a cultural, moral and capitalistic oppression. Foucault, however, argues that peoples' opinions about and experiences of sexuality are always a result of cultural and power mechanisms. To "liberate" sexuality from one group of norms only means that another group of norms takes its place. This, however, does not mean that Foucault considers resistance to be futile. What Foucault argues for is rather that it is impossible to become completely free from power, and that there is simply no "natural" sexuality. Power always involves a dimension of resistance, and therefore also a possibility for change. Although Foucault considers it impossible to step outside of power-networks, it is always possible to change these networks or navigate them differently.[203] According to Foucault, the body is not only an "obedient and passive object" that is dominated by discourses and power. The body is also the "seed" to resistance against dominant discourses and power techniques. The body is never fully compliant, and experiences can never fully be reduced to linguistic descriptions. There is always a possibility to experience something that is not possible to describe with words, and in this discrepancy there is also a possibility for resistance against dominant discourses.[203] Foucault's view of the historical construction of the body has influenced many feminist and queer-theorists. According to Johanna Oksala, Foucault's influence on queer theory has been so great than he can be considered one of the founders of queer theory. The fundamental idea behind queer theory is that there is no natural fundament that lies behind identities such as gay, lesbian, heterosexual, etc. Instead these identities are considered cultural constructions that have been constructed through normative discourses and relations of power. Feminists have with the help of Foucault's ideas studied different ways that women form their bodies: through plastic surgery, diet, eating disorders, etc. Foucault's historization of sex has also affected feminist theorists such as Judith Butler, who used Foucault's theories about the relation between subject, power and sex to question gendered subjects. Butler follows Foucault by saying that there is no "true" gender behind gender identity that constitutes its biological and objective fundament. However, Butler is critical of Foucault. She argues Foucault "naively" presents bodies and pleasures as a ground for resistance against power, without extending his historization of sexuality to gendered subjects/bodies. Foucault has received criticism from other feminists, such as Susan Bordo and Kate Soper.[203] Johanna Oksala argues that Foucault, by saying that sex/sexuality are constructed, doesn't deny the existence of sexuality. Oksala also argues that the goal of critical theories such as Foucault is not to liberate the body and sexuality from oppression, but rather to question and deny the identities that are posited as "natural" and "essential" by showing how these identities are historical and cultural constructions.[203] Subjectivity Foucault considered his primary project to be the investigation of how people through history have been made into "subjects".[204] Subjectivity, for Foucault, is not a state of being, but a practice—an active "being".[205] According to Foucault, "the subject" has, by western philosophers, usually been considered as something given; natural and objective. On the contrary, Foucault considers subjectivity to be a construction created by power.[204] Foucault talks of "assujettissement", which is a French term that for Foucault refers to a process where power creates subjects while also oppressing them using social norms. For Foucault "social norms" are standards that people are encouraged to follow, that are also used to compare and define people. As an example of "assujettissement", Foucault mentions "homosexual", a historically contingent type of subjectivity that was created by sexology. Foucault writes that sodomy was previously considered a serious sexual deviation, but a temporary one. Homosexuality, however, became a "species", a past, a childhood and a type of life. "Homosexuals" has by the same power that created this subjectivity been discriminated against, due to homosexuality being considered as a deviation from the "normal" sexuality. However, Foucault argues, the creation of a subjectivity such as "homosexuality" does not only have negative consequences for the people who are subjectivised—subjectivity of homosexuality has also led to the creation of gay bars and the pride parade.[206] According to Foucault, scientific discourses have played an important role in the disciplinary power system, by classifying and categorizing people, observing their behavior and "treating" them when their behavior has been considered "abnormal". He defines discourse as a form of oppression that does not require physical force. He identifies its production as "controlled, selected, organized and redistributed by a certain number of procedures", which are driven by individuals' aspiration of knowledge to create "rules" and "systems" that translate into social codes.[207] Moreover, discourse creates a force that extends beyond societal institutions and could be found in social and formal fields such as health care systems, educational and law enforcement. The formation of these fields may seem to contribute to social development; however, Foucault warns against discourses' harmful aspects on society. Sciences such as psychiatry, biology, medicine, economy, psychoanalysis, psychology, sociology, ethnology, pedagogy and criminology have all categorized behaviors as rational, irrational, normal, abnormal, human, inhuman, etc. By doing so, they have all created various types of subjectivity and norms,[202] which are then internalized by people as "truths". People have then adapted their behavior to get closer to what these sciences has labeled as "normal".[203] For example, Foucault claims that psychological observation/surveillance and psychological discourses has created a type of psychology-centered subjectivity, which has led to people considering unhappiness a fault in their psychology rather than in society. This has also, according to Foucault, been a way for society to resist criticism—criticism against society has been turned against the individual and their psychological health.[199] Self-constituting subjectivity According to Foucault, subjectivity is not necessarily something that is forced upon people externally—it is also something that is established in a person's relation to themselves.[205] This can, for example, happen when a person is trying to "find themselves" or "be themselves", something Edward McGushin describes as a typical modern activity. In this quest for the "true self", the self is established in two levels: as a passive object (the "true self" that is searched for) and as an active "searcher". The ancient Cynics and the 19th-century philosopher Friedrich Nietzsche posited that the "true self" can only be found by going through great hardship and/or danger. The ancient Stoics and 17th-century philosopher René Descartes, however, argued that the "self" can be found by quiet and solitary introspection. Yet another example is Socrates, who argued that self-awareness can only be found by having debates with others, where the debaters question each other's foundational views and opinions. Foucault, however, argued that "subjectivity" is a process, rather than a state of being. As such, Foucault argued that there is no "true self" to be found. Rather so, the "self" is constituted/created in activities such as the ones employed to "find" the "self". In other words, exposing oneself to hardships and danger does not "reveal" the "true self", according to Foucault, but rather creates a particular type of self and subjectivity. However, according to Foucault the "form" for the subject is in great part already constituted by power, before these self-constituting practices are employed. Schools, workplaces, households, government institutions, entertainment media and the healthcare sector all, through disciplinary power, contribute to forming people into being particular types of subjects.[208] Freedom Todd May defines Foucault's concept of freedom as: that which we can do of ourselves within our specific historical context. A condition for this, according to Foucault, is that we are aware of our situation and how it has been created/affected (and is still being affected) by power. According to May, two of the aspects of how power has shaped peoples′ way of being, thinking and acting is described in the books where Foucault describes disciplinary power and the history of sexuality. However, May argues, there will always be aspects of peoples′ formation that will be unknown to them, hence the constant necessity for the type of analyses that Foucault did.[199] Foucault argues that the forces that have affected people can be changed; people always have the capacity to change the factors that limit their freedom.[199] Freedom is thus not a state of being, but a practice—a way of being in relation to oneself, to others and to the world.[209] According to Todd May Foucault's concept of freedom also includes constructing histories like the ones Foucault did about the history of disciplinary power and sexuality—histories that investigate and describe the forces that have influenced people into becoming who they are. From the knowledge that is reached from such investigations, people can thereafter decide which forces they believe are acceptable and which they consider to be intolerable and has to be changed. Freedom is for Foucault a type of "experimentation" with different "transformations". Since these experiments cannot be controlled completely, May argues they may lead to the reconstruction of intolerable power relations or the creation of new ones. Thus, May argues, it is always necessary to continue with such experimentation and Foucauldian analyses.[199] Practice of critique Foucault's "alternative" to the modern subjectivity is described by Cressida Heyes as "critique". For Foucault there are no "good" and "bad" forms of subjectivity, since they are all a result of power relations.[206] In the same way, Foucault argues there are no "good" and "bad" norms. All norms and institutions are at the same time enabling as they are oppressing. Therefore, Foucault argues, it is always crucial to continue with the practice of "critique".[205] Critique is for Foucault a practice that searches for the processes and events that led to our way of being—a questioning of who we "are" and how this "we" came to be. Such a "critical ontology of the present" shows that peoples′ current "being" is in fact a historically contingent, unstable and changeable construction. Foucault emphasizes that since the current way of being is not a necessity, it is also possible to change it.[209] Critique also includes investigating how and when people are being enabled and when they are being oppressed by the current norms and institutions, finding ways to reduce limitations on freedom, resist normalization and develop new and different way of relating to oneself and others. Foucault argues that it is impossible to go beyond power relations, but that it is always possible to navigate power relations in a different way.[205] Epimeleia heautou, "care for the self" As an alternative to the modern "search" for the "true self",[208] and as a part of "the work of freedom",[209] Foucault discusses the antique Greek term epimeleia heautou, "care for the self" (ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ). According to Foucault, among the ancient Greek philosophers, self-awareness was not a goal in itself, but rather something that was sought after in order to "care for oneself". Care for the self consists of what Foucault calls "the art of living" or "technologies of the self".[208] The goal of these techniques was, according to Foucault, to transform oneself into a more ethical person. As an example of this, Foucault mentions meditation,[202] the stoic activity of contemplating past and future actions and evaluating if these actions are in line with one's values and goals, and "contemplation of nature". Contemplation of nature is another stoic activity, that consists of reflecting on how "small" one's existence is when compared to the greater cosmos.[208] Knowledge Main article: Power-knowledge Foucault is described by Mary Beth Mader as an epistemological constructivist and historicist.[210] Foucault is critical of the idea that humans can reach "absolute" knowledge about the world. A fundamental goal in many of Foucault's works is to show how that which has traditionally been considered as absolute, universal and true in fact are historically contingent. To Foucault, even the idea of absolute knowledge is a historically contingent idea. This does however not lead to epistemological nihilism; rather, Foucault argues that we "always begin anew" when it comes to knowledge.[204] At the same time Foucault is critical of modern western philosophy for lacking "spirituality". With "spirituality" Foucault refers to a certain type of ethical being, and the processes that lead to this state of being. Foucault argues that such a spirituality was a natural part of the ancient Greek philosophy, where knowledge was considered as something that was only accessible to those that had an ethical character. According to Foucault this changed in the "cartesian moment", the moment when René Descartes reached the "insight" that self-awareness was something given (Cogito ergo sum, "I think, therefore I am"), and from this "insight" Descartes drew conclusions about God, the world, and knowledge. According to Foucault, since Descartes knowledge has been something separate from ethics. In modern times, Foucault argues, anyone can reach "knowledge", as long as they are rational beings, educated, willing to participate in the scientific community and use a scientific method. Foucault is critical of this "modern" view of knowledge.[211] Foucault describes two types of "knowledge": "savoir" and "connaissance", two French terms that both can be translated as "knowledge" but with separate meanings for Foucault. By "savoir" Foucault is referring to a process where subjects are created, while at the same time these subjects also become objects for knowledge. An example of this can be seen in criminology and psychiatry. In these sciences, subjects such as "the rational person", "the mentally ill person", "the law abiding person", "the criminal", etc. are created, and these sciences center their attention and knowledge on these subjects. The knowledge about these subjects is "connaissance", while the process in which subjects and knowledge is created is "savoir".[210] A similar term in Foucaults corpus is "pouvoir/savoir" (power/knowledge). With this term Foucault is referring to a type of knowledge that is considered "common sense", but that is created and withheld in that position (as "common sense") by power. The term power/knowledge comes from Jeremy Bentham's idea that panopticons wouldn't only be prisons, but would be used for experiments where the criminals′ behaviour would be studied. Power/knowledge thus refers to forms of power where the power compares individuals, measures differences, establishes a norm and then forces this norm unto the subjects. This is especially successful when the established norm is internalized and institutionalized (by "institutionalized" Foucault refers to when the norm is omnipresent). Because then, when the norm is internalized and institutionalized, it has effectively become a part of peoples' "common sense"—the "obvious", the "given", the "natural". When this has happened, this "common sense" also affects the explicit knowledge (scientific knowledge), Foucault argues. Ellen K. Feder states that the premise "the world consists of women and men" is an example of this. This premise, Feder argues, has been considered "common sense", and has led to the creation of the psychiatric diagnosis gender identity disorder (GID). For example, during the 1970s, children with behavior that was not considered appropriate for their gender was diagnosed with GID. The treatment then consisted of trying to make the child adapt to the prevailing gender norms. Feder argues that this is an example of power/knowledge since psychiatry, from the "common sense" premise "the world consists of women and men" (a premise which is upheld in this status by power), created a new diagnosis, a new type of subject and a whole body of knowledge surrounding this new subject.[212] |
私生活 フーコーの最初の伝記作者であるディディエ・エリボンは、この哲学者を「複雑で多面的な性格」であり、「仮面の下には常に別の仮面がある」と評している [172]。 また、彼は「仕事に対する膨大な能力」を発揮したとも述べている[173]。ENSでは、フーコーの同級生たちは異口同音に、彼を「不穏で奇妙」であり、 「情熱的な仕事人」であると評している[174]。 [エリボンは、フーコーが「苦悩に満ちた思春期」であったのに対し、1960年以降は「晴れやかな男、リラックスした陽気な男」になり、一緒に働いていた 人々からはダンディとさえ評されるようになったと述べている[175]。 彼は、1969年、フーコーは「戦闘的知識人」の思想を体現していたと述べている[176]。 フーコーは無神論者であった[177][178]。クラシック音楽を愛し、特にヨハン・セバスティアン・バッハとヴォルフガング・アマデウス・モーツァル トの作品を楽しんでいた[179]。 [180]死後、フーコーの友人であるジョルジュ・デュメジルは彼を「深遠な優しさと善良さ」を持ち、また「文字通り際限のない知性」を示していたと評し ている[181]。 生涯のパートナーであったダニエル・デフェールが彼の遺産を相続し[182]、そのアーカイブは2012年にフランス国立図書館に380万ユーロ (2021年4月には450万ドル)で売却された[183]。 政治 政治的には、フーコーは生涯を通じて左翼主義者であったが、左翼の中での特定のスタンスはしばしば変化した。1950年代初頭、フーコーはフランス共産党 員であったが、ユダヤ人や同性愛者に対する党内の偏見に嫌気がさし、3年で党を去った。表向きはポーランド統一労働者党が統治する共産主義国家だが、実際 はソビエト連邦の警察国家の衛星だったポーランドでしばらく働いた後、彼は共産主義イデオロギーにさらに幻滅した。その結果、1960年代初頭、フーコー は、彼の学生や同僚の多くとともに左翼運動に参加していたにもかかわらず、彼を非難する一部の人々からは「激しく反共主義的」であるとみなされていた [184]。 未成年のセックスに対する見解 1977年、フーコーはジャン=ポール・サルトル、ジャック・デリダ、その他の知識人たちとともに、フランスの同意年齢である15歳未満の未成年者と成人 との間のすべての「同意に基づく」性的関係の非犯罪化を求めるフランス議会への請願書に署名した[186]。 [187][188]1978年の放送でフーコーは、「子どもは何が起こったかを説明する能力がなく、同意を与える能力もないと仮定することは、耐えがた く、まったく容認できない2つの虐待である」と述べた[189]。 哲学的著作 こちらも参照: ミシェル・フーコー文献目録 フーコーの同僚であるピエール・ブルデューは、この哲学者の思想を「常に知識と権力と不可分に結びついた、社会的限界を超えることについての長い探求」と 要約している[190]。 フーコーのすべての著作の根底にあるテーマは、権力と知識の関係であり、前者が後者を支配し定義するためにどのように用いられるかである。権威が「科学的 知識」と主張するものは、実際には社会的統制の手段にすぎない。フーコーは、例えば18世紀において「狂気」が、精神病者だけでなく、貧困者、病人、ホー ムレス、さらには個性の表現が歓迎されないすべての人を分類し、汚名を着せるためにどのように使われたかを示している。 - フィリップ・ストークス『哲学:100人の重要な思想家たち』(2004年)[191] レディング大学の哲学者フィリップ・ストークスは、フーコーの仕事は全体的に「暗く悲観的」であると指摘する。しかし、哲学という学問が支配の領域を浮き 彫りにするためにどのように利用されうるかを示しているという点で、楽観主義の余地も残されている。そうすることで、ストークスが主張したように、我々が 支配されている方法がよりよく理解されるようになり、支配のリスクを最小限に抑える社会構造を構築するよう努めることができるようになるのである [191]。このような発展のすべてにおいて、細部に細心の注意を払う必要があった。 後年、フーコーは自分の仕事は現象としての権力を分析することよりも、現代社会が「主体を客観化」するために権力の行使を表現してきた様々な方法を特徴付 けようとすることであったと説明している。ひとつは、人間の集団に関する知識を分類し「秩序化」するための科学的権威に関わるものであり、もうひとつは (狂気、病気、身体的特徴などを特定することによって)人間の主体を分類し「正常化」することであり、そして三つ目は、性的アイデンティティをファッショ ン化し、ルーティンや実践に従事するために自らの身体を訓練する衝動が、結局は与えられた社会の中で特定のパターンを再生産してしまうという方法に関する ものである[193]。 文学 哲学に加え、フーコーは文学についても執筆している。死と迷宮 1963年に出版され、1986年に英訳された『レイモン・ルーセルの世界』は、フーコーの文学に関する唯一の著作である。フーコーは、最初の著名な実験 的作家の一人であるレイモン・ルーセルのテキストを参照しながら、理論、批評、心理学を探求している。また、フーコーは1969年にロラン・バルトの有名 なエッセイ『著者の死』に対して『著者とは何か』と題した講演を行っており、後に全文が出版されている[195]。文学理論家のコルネリイェ・クヴァスに よれば、フーコーにとって「解釈にとって無関係であるという理由で歴史的著者の存在を否定することは馬鹿げている。 権力 フーコーの権力分析には、経験的なものと理論的なものの2つの形態がある。経験的な分析では、権力の歴史的な(そして近代的な)形態と、それらが以前の権 力の形態からどのように出現したかに関心を持つ。フーコーは彼の経験的分析において、主権的権力、規律的権力、バイオパワーという3つのタイプの権力を説 明している[197]。 フーコーは一般的に、「すべて」に対して絶対的な答えを与えようとする「理論」に対して批判的である。それゆえ、彼自身の権力に関する「理論」は典型的な 「理論」よりも方法に近いと考えていた。フーコーによれば、ほとんどの人は権力を誤解している。このため、彼は権力を以下のように完全に説明することはで きないと明言している[197]。 市民が国家に服従し屈服することを目的とする制度やメカニズムのグループ(権力の典型的な自由主義的定義)、[197]。 規則に屈服すること(権力の典型的な精神分析的定義)、[197]あるいは ある社会階級や集団が別の社会階級や集団を抑圧する一般的で抑圧的なシステム(典型的なフェミニストや正統的なマルクス主義者による権力の定義) [197]。 フーコーはこれらの現象を「権力」とみなすことに批判的ではないが、権力のこれらの理論は権力のすべての形態を完全に記述することはできないと主張してい る。フーコーはまた、権力のリベラルな定義が、人々が無批判的にそれらを受け入れてきた程度に、他の形態の権力を効果的に隠してきたと主張している [197]。 フーコーの権力分析はミクロ・レベルで、特異な「力関係」から始まる。リチャード・A・リンチはフーコーの「力関係」の概念を「人の社会的相互作用の中 で、人に何かをさせたり、促したり、強制したりするあらゆるもの」と定義している[198]。フーコーによれば、力関係は他の形態の関係(性的関係や経済 的関係など)に存在する差異、不平等、不均衡の影響である。しかしながら、力、そして権力は、(権力の主権的な定義におけるような)個人や集団が「保持」 するものではなく、その代わりに権力は「すべて」から生じる力の複雑なグループであり、それゆえどこにでも存在するものである。権力関係が常に不平等、差 異、不均衡から生じるということは、権力には常に目標や目的があるということでもある。権力には戦術と戦略の2つの形態がある。戦術とは、ミクロレベルで の権力であり、例えば、人が服装を通してどのように自分を表現するかを選択することである。一方、戦略とはマクロレベルでのパワーのことで、その時々の ファッションの状態などがこれにあたる。戦略は戦術の組み合わせで構成される。同時に、フーコーによれば、権力は非主体的である。リンチによれば、「誰 か」は権力を行使しなければならないが、同時にこの権力を行使する「誰か」は存在しえないので、これはパラドックスを提起する[197]: 権力を、一個人や集団の影響力よりももっと先まで届くものとして見ることである。例えば、個人や集団がファッションに影響を与えようとしても、その行動は しばしば予期せぬ結果をもたらすことになる[197]。 たとえ個人や集団が自由な選択を持っていたとしても、彼らはまたその文脈/状況によって影響され、制限されるのである[197]。 フーコーによれば、力関係は常に変化しており、他の力関係と常に相互作用しており、それらは互いに弱めたり、強めたり、変化したりする可能性がある。フー コーは、権力は常に抵抗を含み、それは権力と力関係が何らかの形で変化する可能性が常にあることを意味していると書いている。リチャード・A・リンチによ れば、権力に関するフーコーの研究の目的は、権力がどのように彼らのあり方、考え方、行動を形作ってきたかについて人々の認識を高めることであり、この認 識を高めることによって、彼らのあり方、考え方、行動を変えることを可能にすることである[197]。 主権的権力 フーコーは「主権的権力」によって、ピラミッドに似た権力構造を暗示している。そこでは、(ピラミッドの頂点にいる)一人の人間や集団が権力を握ってお り、「普通の」(そして抑圧された)人々はピラミッドの底辺にいる。ピラミッドの中央部には、主権者の命令を執行する人々がいる。君主権力の典型的な例は 絶対君主制である[197]。 歴史的な絶対君主制では、犯罪は君主とその権力に対する個人的な犯罪とみなされてきた。処罰は、他の者が犯罪を犯すのを抑止するためでもあったが、君主の 権力を復活させるためでもあり、しばしば公的で派手なものであった。しかし、これは費用がかかる上に効果もなく、人々が犯罪者に同調してしまうことがあま りにも多かった。規律権力が支配的である現代では、犯罪者を「法を守る市民」に「作り変える」ために、犯罪者は代わりにさまざまな規律的手法にさらされる [199]。 クロエ・テイラーによれば、主権者の権力の特徴は、主権者が生命、富、サービス、労働力、生産物を奪う権利を持っていることである。主権者は、生命を奪 う、生命を奴隷にするなどの引き算をする権利を持っているが、後に権力の規律システムで起こるような方法で生命を支配する権利は持っていない。テイラーに よれば、哲学者トマス・ホッブズが懸念する権力の形態とは、主権的権力である。ホッブズによれば、文字通り鎖につながれていない限り、人々は「自由」であ る[200]。 規律権力 フーコーが「規律権力」と呼ぶものは、身体の技能を可能な限り効果的に利用することを目的としている[201]。この目的は、身体の技能を利用するだけで なく、これらの技能が権力に反旗を翻すために利用されるのを防ぐことでもある[201]。 規律権力は「個人」をその対象、標的、道具としている。フーコーによれば、「個人」はしかし規律権力によって作り出された構成概念である[201]。規律 権力の技法は「理性的な自己統制」[202]を生み出すが、これは実際には規律権力が内面化され、したがって継続的に外力を必要としないことを意味する。 フーコーは、規律権力は主に抑圧的な権力形態ではなく、むしろ生産的な権力形態であると言う。規律権力は利益や欲望を抑圧するのではなく、彼らの思考、欲 望、利益を再構築するために、身体を再構築された行動パターンに従わせる。フーコーによれば、これは工場、学校、病院、刑務所で起こることである [203] 。規律権力は、細部、単一の動き、そのタイミングとスピードに焦点を当てる。時間と空間の中で身体を組織化し、最大限の効果を得るためにあらゆる動きを統 制する。規則、監視、試験、統制を用いる。[203] 活動は一定の計画に従って行われ、その目的は身体をあらかじめ決められた特定の目標に導くことである。身体はまた、すべての身体の活動の総和よりも大きな 生産性に到達するために、互いに組み合わされる[201]。 フーコーによれば、規律権力は、階層的観察、正常化する判断、試験という3つの技術を用いることによって、特に成功を収めてきた[201]。観察者は一人 ではなく、むしろ観察者の「階層」であるため、観察は階層的である。19世紀の精神病院では、精神科医だけが観察者ではなく、看護師や補助スタッフも観察 者であった。こうした観察と科学的言説から、規範が確立され、観察された身体を判断するために用いられる。規律権力が存在し続けるためには、この判断が規 範化されなければならない。フーコーはこの判断の特徴をいくつか挙げている:(1)正しい行動からの逸脱はすべて、たとえ小さなものであっても罰せられ る、(2)規則違反が繰り返されると余計に罰せられる、(3)行動を正す技術や罰として演習が用いられる、(4)罰とともに報酬が用いられ、良い行動・悪 い人間のヒエラルキーが確立される、(5)罰や報酬として階級・等級などが用いられる。試験は、階層的観察と判断を結びつける。検査は、観察されるすべて の身体について広範な文書を作成することによって、観察される身体を客観化し、個別化する。したがって試験の目的は、各個人についてのさらなる情報を収集 し、その成長を追跡し、その結果を規範と比較することにある[201]。 フーコーによれば、規律権力の「公式」は、哲学者ジェレミー・ベンサムの「最適な監獄」の計画、すなわちパノプティコンに見ることができる。このような牢 獄は円形の建物で構成され、すべての独房には囚人が一人しか住んでいない。どの独房にも2つの窓があり、1つは外からの光を取り込み、もう1つは円形の建 物の中央を指している。この真ん中には塔があり、看守が囚人を監視できるようになっている。囚人たちは、ある瞬間から監視されているかどうかを知ることが できないため、規律権力を内面化し、(常に監視されているかのように)自らの行動を規制するようになる。フーコーはこの構造について、(1)物理的な部屋 の中で囚人同士を分離することで個性を生み出す、(2)囚人たちはある瞬間に監視されているかどうかを知ることができないため、規律権力を内面化し、常に 監視されているかのように自らの行動を規制する、(3)監視によって囚人一人ひとりとその行動に関する広範な記録を作成することが可能になる、と述べてい る。フーコーによれば、パノプティコンは、19世紀の精神病院など、他の規律制度にもモデルとして用いられている[201]。 バイオパワー(生権力) さらなる情報 バイオパワー フーコーは「バイオパワー」によって、ビオス(生命)に対する権力、すなわち集団に対する権力を指している。バイオパワーは主に、外的な力ではなく、人々 によって内面化された規範に基づいている。それは、それ以下の力を奨励し、強化し、統制し、観察し、最適化し、組織化する。フーコーは、バイオパワーを規 律権力とは別のものとして説明することもあるが、規律権力をバイオパワーの表現として説明することもある。バイオパワーは規律的手法を用いることができる が、規律的権力とは対照的に、その対象は個人ではなく集団である[200]。 バイオパワーは、(例えば)出生数、平均寿命、公衆衛生、住宅、移民、犯罪、どの社会集団が(健康、犯罪などに関して)規範からの逸脱において過剰に代表 されているかについて集団を研究し、これらの規範の逸脱を調整、制御、排除しようとする。その一例が、人口の年齢分布である。バイオパワーは、将来(ある いは現在)の労働力不足や老人ホームなどの不足を補うため、年齢分布に関心を持つ。セックスは人口増加につながるため、セックスとセクシュアリティはバイ オパワーにとって大きな関心事である。規律レベルでは、非繁殖的な性行為に従事する人々は、「倒錯」、「姦淫」、「性機能障害」といった精神医学的診断を 受けてきた。生物権力のレベルでは、避妊具の使用法が研究され、ある社会集団は(様々な手段によって)子どもを持つことを奨励され、一方で他の集団(貧困 層、病人、未婚女性、犯罪者、障害者など)は子どもを持つことを奨励されなかったり、妨げられたりしてきた[200]。 バイオパワーの時代において、死はスキャンダルであり大惨事となったが、それにもかかわらず、フーコーによれば、バイオパワーはそれ以前のどのような権力 の形態よりも多くの人々を殺してきた。君主権力のもとでは、君主である王が権力を行使するために人を殺したり、単に王国を拡大するために戦争を始めたりす ることができたが、バイオパワーの時代には、戦争はその代わりに「生命そのものを守る」という野心によって動機づけられている。同様の動機は大量虐殺にも 使われてきた。例えば、ナチス・ドイツはユダヤ人、精神障害者、身体障害者を根絶やしにしようとした動機として、ユダヤ人は「ドイツの健康を脅かす存在」 であり、精神障害者や身体障害者の医療に使うお金を「生存可能なドイツ人」に使った方がよいということを挙げている。クロエ・テイラーもまた、イラク戦争 が同様の信条によって動機づけられたことに触れている。動機は当初、イラクが大量破壊兵器を持ち、アルカイダとつながりがあると考えられていたからだ。し かし、ブッシュとブレアの両政権がどちらの説も裏付ける証拠を見つけられなかったため、戦争の動機は変更された。新しい動機では、戦争の原因はサダム・フ セインが自国民に対して犯罪を犯したことだとされた。テイラーは、こうした戦争がしばしば人道的危機を引き起こしているにもかかわらず、現代においては、 戦争は人道支援というレトリックの下に「隠蔽」されなければならないことを意味している[200]。 19世紀、スラムは西側世界全域でその数と規模を拡大していた。これらの地域では犯罪、病気、アルコール中毒、売春が一般的であり、中産階級はこれらのス ラムに住む人々を「非道徳的」で「怠惰」であるとみなしていた。中産階級はまた、これらのスラム街では中産階級よりも人口増加が大きかったため、遅かれ早 かれこの下層階級が「乗っ取られる」ことを恐れていた。この恐れは、優生学という科学的研究を生み出した。その創始者フランシス・ガルトンは、チャール ズ・ダーウィンと彼の自然淘汰理論に影響を受けていた。ガルトンによれば、社会は「弱者」を助けることで自然淘汰を妨げており、その結果、「負の資質」が 他の集団に広がる原因となっていた[200]。 身体とセクシュアリティ フーコーによれば、身体は歴史や文化の外に立つ客観的なものではない。それどころか、身体は社会と歴史によって、仕事、食事、身体の理想像、運動、医療介 入などによって絶えず形成されてきたし、形成されているのだとフーコーは主張する。フーコーは身体についての「理論」は提示していないが、『規律と罰』や 『セクシュアリティの歴史』では身体について書いている。フーコーは、セクシュアリティ、狂気、犯罪性といった現象について、純粋に生物学的に説明するこ とに批判的であった。さらにフーコーは、身体は自己理解や他者理解の基礎として十分ではないと主張している[203]。 規律と罰』の中でフーコーは、例えば規律権力が主に個人の身体とその行動に焦点を当てることによって、権力と身体がいかに結びついているかを示している。 フーコーは、権力は身体/行動を操作することによって、人々の心も操作すると論じている。フーコーは、「身体は魂の牢獄である」という一般的な諺を翻し、 代わりに「魂は身体の牢獄である」と仮定する[203]。 フーコーによれば、性科学は物質(身体)に言及することで「科学」として自らを発揮しようとしてきた。これに対してフーコーは、性科学は疑似科学であり、 「性」は疑似科学的な思想であると主張する。フーコーにとって、自然で、生物学的に根拠があり、根源的なセクシュアリティという考え方は、規範的な歴史的 構築物であり、権力の道具としても使われてきた。人々のジェンダー・アイデンティティ、性的アイデンティティ、性的行動の生物学的かつ根本的な原因として 性を記述することで、権力は効果的に性的でジェンダー化された行動を正規化することができた。これによって、構築された「正常な」行動と身体的行動を比較 することで、人々の性的・ジェンダー的行動を評価し、病理化し、「矯正」することが可能になった。フーコーにとって「正常なセクシュアリティ」とは、「自 然なセクシュアリティ」と同様に構築物である。したがって、フーコーは1960年代から1970年代にかけてセクシュアリティをめぐる議論を支配した大衆 的言説にも批判的であった。この時期、大衆の言説は、文化的、道徳的、資本主義的抑圧からのセクシュアリティの「解放」を主張していた。しかしフーコー は、人々のセクシュアリティに対する意見や経験は、常に文化的・権力的メカニズムの結果であると主張する。ある規範のグループからセクシュアリティを「解 放」することは、別の規範のグループがそれに取って代わることを意味するだけである。しかしこれは、フーコーが抵抗を無益なものとみなすことを意味するわ けではない。フーコーが主張するのはむしろ、権力から完全に自由になることは不可能であり、「自然な」セクシュアリティなど存在しないということである。 権力には常に抵抗の側面があり、それゆえに変化の可能性もある。フーコーは、権力ネットワークの外に出ることは不可能であると考えているが、これらのネッ トワークを変えたり、異なる方法で運行したりすることは常に可能である[203]。 フーコーによれば、身体は言説と権力に支配される「従順で受動的な対象」であるだけではない。身体はまた、支配的な言説や権力技法に対する抵抗の「種」で もある。身体は決して完全には従順ではないし、経験は決して言語的な記述に完全に還元されることはない。言葉で記述することができない何かを経験する可能 性は常にあり、この矛盾の中に支配的な言説に対する抵抗の可能性もある[203]。 身体の歴史的構築に関するフーコーの見解は、多くのフェミニストやクィア理論家に影響を与えてきた。ヨハンナ・オクサラによれば、クィア理論に対するフー コーの影響は、彼がクィア理論の創始者の一人と考えられるほど大きい。クィア理論の背後にある基本的な考え方は、ゲイ、レズビアン、ヘテロセクシュアルな どのアイデンティティの背後にある自然な基盤は存在しないというものだ。その代わりに、これらのアイデンティティは、規範的な言説や権力関係を通じて構築 された文化的な構築物であると考えられている。フェミニストたちは、フーコーの思想の助けを借りて、整形手術、ダイエット、摂食障害など、女性が自分の身 体を形成するさまざまな方法を研究してきた。フーコーの性の歴史化は、ジュディス・バトラーのようなフェミニスト理論家にも影響を与えた。彼女は、主体、 権力、性の関係についてのフーコーの理論を、ジェンダー化された主体への問いかけに用いた。バトラーはフーコーに倣い、ジェンダー・アイデンティティの背 後には、生物学的かつ客観的な根底を構成する「真の」ジェンダーは存在しないと述べている。しかし、バトラーはフーコーに批判的である。彼女は、フーコー がセクシュアリティの歴史化をジェンダー化された主体/身体に拡張することなく、権力に対する抵抗の根拠として身体と快楽を「素朴に」提示していると主張 する。フーコーは、スーザン・ボルドやケイト・ソーパーといった他のフェミニストからも批判を受けている[203]。 ヨハンナ・オクサラは、フーコーはセックス/セクシュアリティが構築されたものであると言うことによって、セクシュアリティの存在を否定しているわけでは ないと論じている。オクサラはまた、フーコーのような批判的理論のゴールは、抑圧から身体やセクシュアリティを解放することではなく、むしろ「自然」であ り「本質的」であると仮定されるアイデンティティがいかに歴史的・文化的な構築物であるかを示すことによって、そのアイデンティティに疑問を投げかけ、否 定することであると論じている[203]。 主観性 フーコーにとっての主体性とは、存在の状態ではなく、実践、つまり能動的な「存在」である[205]。フーコーによれば、西洋の哲学者たちによって「主 体」とは通常、与えられたもの、自然で客観的なものとみなされてきた。フーコーは「assujettissement」について語っているが、これはフラ ンス語の用語であり、フーコーにとっては、権力が主体を生み出す一方で、社会規範を用いて主体を抑圧するプロセスを指している[204]。フーコーにとっ ての「社会規範」とは、人々が従うことを奨励される基準であり、人々を比較し定義するためにも用いられる。assujettissement」の一例とし て、フーコーは「同性愛」に言及している。これは、性科学によって生み出された、歴史的に偶発的な主観性のタイプである。フーコーは、以前はソドミーは深 刻な性的逸脱とみなされていたが、一時的なものだったと書いている。しかし、同性愛は「種」であり、過去であり、幼年期であり、人生のタイプとなった。 「ホモセクシュアルは「正常な」セクシュアリティからの逸脱とみなされるため、この主観を生み出した同じ権力によって差別されてきた。しかしフーコーは、 「同性愛」のような主体性の創出は、主体化された人々にとって否定的な結果をもたらすだけではないと論じている-同性愛の主体性は、ゲイ・バーやプライ ド・パレードの創出にもつながっている[206]。 フーコーによれば、科学的言説は、人々を分類し、カテゴライズし、彼らの行動を観察し、彼らの行動が「異常」とみなされたときに「治療」することによっ て、規律権力システムにおいて重要な役割を果たしてきた。彼は言説を、物理的な力を必要としない抑圧の一形態と定義している。彼はその生産を「一定の手続 きによって制御され、選択され、組織化され、再分配される」ものとしており、それは社会規範に変換される「規則」や「システム」を作り出すための個人の知 識欲によって推進される[207]。さらに、言説は社会制度を超えて拡大する力を生み出し、医療制度、教育、法執行といった社会的・形式的な分野に見出す ことができる。これらの分野の形成は社会の発展に寄与しているように見えるかもしれないが、フーコーは言説が社会に及ぼす有害な側面に対して警告を発して いる。 精神医学、生物学、医学、経済学、精神分析学、心理学、社会学、民族学、教育学、犯罪学などの科学はすべて、行動を合理的、非合理的、正常、異常、人間 的、非人間的などに分類してきた。そうすることで、それらはすべて様々なタイプの主観性と規範を生み出し、[202]それらは「真理」として人々に内面化 される。例えば、フーコーは、心理学的観察/監視と心理学的言説が、一種の心理学中心の主観性を生み出し、それによって人々は不幸を社会のせいではなく自 分の心理のせいだと考えるようになったと主張している。これはまた、フーコーによれば、社会が批判に抵抗するための方法であり、社会に対する批判が個人と その心理的健康に向けられることになったのである[199]。 自己構成する主観性 フーコーによれば、主観性とは必ずしも外的に人に強制されるものではなく、人が自分自身との関係の中で確立されるものでもある[205]。これは例えば、 エドワード・マクグシンが典型的な近代の活動として述べているように、人が「自分自身を見つけよう」あるいは「自分自身であろう」としているときに起こり うる。この「真の自己」の探求において、自己は受動的な対象(探求される「真の自己」)と能動的な「探求者」としての2つのレベルで確立される。古代のシ ニックス派や19世紀の哲学者フリードリヒ・ニーチェは、「真の自己」は大きな苦難や危険を乗り越えることでしか見いだせないとした。しかし、古代のスト ア学派や17世紀の哲学者ルネ・デカルトは、「自己」は静かで孤独な内省によって見つけることができると主張した。さらにもう一人の例はソクラテスで、彼 は自己認識は他者との討論によってのみ見出されると主張した。しかしフーコーは、「主観性」とはある状態ではなく、むしろプロセスであると主張した。その ため、フーコーは「真の自己」は存在しないと主張した。そうではなく、「自己」は「自己」を「発見」するための活動の中で構成/創造される。言い換えれ ば、フーコーによれば、苦難や危険に身をさらすことが「真の自己」を「明らかにする」のではなく、むしろ特定のタイプの自己と主観を作り出すのである。し かし、フーコーによれば、主体の「形」は、こうした自己を構成する実践が採用される前に、権力によってすでに構成されている部分が大きい。学校、職場、家 庭、政府機関、娯楽メディア、医療部門はすべて、規律権力を通じて、人々を特定のタイプの主体として形成することに寄与している[208]。 自由 トッド・メイは、フーコーの自由の概念を「特定の歴史的文脈の中で私たちが自分自身のためにできること」と定義している。フーコーによれば、そのための条 件は、われわれが自分の置かれている状況や、それが権力によってどのようにつくられ/影響を受けてきたか(そして現在も影響を受けているか)を認識してい ることである。メイによれば、権力が人々のあり方、考え方、行動をどのように形作ってきたかについては、フーコーが規律権力とセクシュアリティの歴史につ いて述べた本の中で2つの側面が述べられている。しかしながら、人々の形成には常に彼らにとって未知の側面があり、それゆえにフーコーが行ったような分析 が常に必要なのだとメイは主張している[199]。 フーコーは、人々に影響を及ぼしてきた力は変えることが可能であると主張している。そのような調査から得られた知識から、人々はその後、どの力を受け入 れ、どの力を耐え難く、変えなければならないと考えるかを決めることができる。フーコーにとって自由とは、さまざまな「変容」を伴う「実験」の一種であ る。こうした実験は完全にコントロールすることができないため、耐え難い権力関係の再構築や新たな権力関係の創造につながる可能性があるとメイは主張す る。したがって、このような実験とフーコー的分析を継続することが常に必要であるとメイは主張している[199]。 批評の実践 近代的主観性に対するフーコーの「オルタナティブ」をクレシダ・ヘイズは「批評」と表現している。フーコーにとって主観性の「良い」形態と「悪い」形態は 存在せず、それらはすべて権力関係の結果であるからである[206]。すべての規範と制度は、抑圧していると同時に可能にしている。したがって、フーコー は「批評」の実践を継続することが常にきわめて重要であると主張している[205]。フーコーにとって批評とは、われわれのあり方に至った過程や出来事を 探求する実践であり、われわれが「何者」であるのか、そしてこの「われわれ」がどのようにして存在するようになったのかを問うものである。このような「現 在の批判的存在論」は、人々の現在の「存在」が実際には歴史的に偶発的で、不安定で、変化しやすい構築物であることを示す。フーコーは、現在のあり方が必 然的なものでない以上、それを変えることも可能であることを強調している[209]。批評にはまた、人々が現在の規範や制度によってどのように、またどの ようなときに可能にされ、またどのようなときに抑圧されるのかを調査し、自由に対する制限を減らし、正常化に抵抗し、自分自身や他者との新しい、また異な る関わり方を開発する方法を見つけることも含まれる。フーコーは、権力関係を超えることは不可能であるが、権力関係を別の方法でナビゲートすることは常に 可能であると主張している[205]。 エピメリア・ヘウトウ、"自己への配慮" 真の自己」のための近代的な「探求」に代わるものとして[208]、また「自由の作業」の一部として[209]、フーコーは古代ギリシア語のエピメレイ ア・ヘウトゥ(epimeleia heautou)、「自己への配慮」(ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ)について論じている。フーコーによれば、古代ギリシャの哲学者たちの間では、自己認識はそれ自体が目的ではなく、むしろ「自己をケアする」 ために求められるものであった。自己のケアは、フーコーが「生きる技術」あるいは「自己の技術」と呼ぶものから構成されている[208]。フーコーによれ ば、これらの技術の目的は、自分自身をより倫理的な人間に変容させることであった。その例として、フーコーは瞑想、[202]過去と未来の行動を熟考し、 それらの行動が自分の価値観や目標に沿ったものであるかどうかを評価するストイックな活動、そして「自然の観照」に言及している。自然観照はもうひとつの ストイックな活動であり、大いなる宇宙と比較したときに、自分の存在がいかに「小さい」かを振り返ることからなる[208]。 知識 主な記事 権力-知識 フーコーはメアリー・ベス・メーダーによって認識論的構成主義者であり歴史主義者であると説明されている[210]。フーコーの作品の多くにおける基本的 な目標は、伝統的に絶対的で普遍的で真実であると考えられてきたものが、実際には歴史的に偶発的であることを示すことである。フーコーに言わせれば、絶対 的な知識という概念でさえ、歴史的に偶発的なものなのである。しかし、このことは認識論的ニヒリズムにはつながらない。むしろフーコーは、知識に関しては 「常に新しく始める」のだと主張している[204]。同時にフーコーは、近代西洋哲学には「精神性」が欠けていると批判している。フーコーは「霊性」に よって、ある種の倫理的存在と、このような状態に至るプロセスを指している。フーコーは、このような精神性は古代ギリシャ哲学の自然な一部であり、知識は 倫理的な性格を持つものだけがアクセスできるものと考えられていたと主張する。フーコーによれば、これが変化したのは「デカルトの瞬間」であり、ルネ・デ カルトが自己認識は与えられたものであるという「洞察」(Cogito ergo sum、「我思う、ゆえに我あり」)に達した瞬間であり、この「洞察」からデカルトは神、世界、知識についての結論を導き出したのである。フーコーによれ ば、デカルト以来、知識は倫理から切り離されたものであった。現代では、理性的な存在であり、教育を受け、科学コミュニティに参加し、科学的方法を用いる 意志さえあれば、誰でも「知識」に到達することができるとフーコーは主張する。フーコーはこの「近代的な」知識観に批判的である[211]。 フーコーは2種類の「知識」について述べている: 「savoir "と "connaissance "という2つのフランス語の用語は、どちらも「知識」と訳すことができるが、フーコーにとっては別々の意味を持つ。フーコーは「サヴォワール」によって、 主体が創造されるプロセスを指しているが、同時にこれらの主体はまた、知の対象となる。この例は、犯罪学や精神医学に見ることができる。これらの科学で は、「理性的な人」、「精神病の人」、「法を守る人」、「犯罪者」などの主体が作り出され、これらの科学はこれらの主体に注目し、知識を集中させる。これ らの主体に関する知識は「connaissance」であり、主体や知識が生み出される過程は「savoir」である[210]。フーコーの著作における 同様の用語は「pouvoir/savoir」(権力/知識)である。この用語でフーコーは、「常識」とされているが、権力によって(「常識」としての) その位置づけが創出され、また保留されているタイプの知識について言及している。権力/知識という用語は、ジェレミー・ベンサムの「パノプティコンは刑務 所であるだけでなく、犯罪者の行動を研究する実験に使われる」という考えに由来している。このように、権力/知識とは、権力が個人を比較し、差異を測定 し、規範を確立し、その規範を被験者に強制するような権力の形態を指す。これは特に、確立された規範が内面化され、制度化されたときに成功する(「制度化 された」とは、フーコーは規範が遍在する場合を指している)。なぜなら、規範が内面化され制度化されたとき、それは事実上、人々の「常識」--「自明」で あり、「所与」であり、「自然」である--の一部となっているからである。そうなると、この「常識」は明示的知識(科学的知識)にも影響を及ぼす、とフー コーは主張する。エレン・K・フェダーは、「世界は女性と男性からなる」という前提がその一例だと述べる。この前提は「常識」とされ、性同一性障害 (GID)という精神医学的診断を生み出すことにつながったとフェダーは主張する。例えば、1970年代には、自分の性別にふさわしくないと考えられる行 動をとる子どもはGIDと診断された。その時の治療は、子どもを一般的なジェンダー規範に適応させようとするものだった。フェダーは、精神医学が「世界は 女性と男性で構成されている」という「常識的」な前提(この前提は権力によってその地位を維持されている)から、新たな診断、新たなタイプの対象、そして この新たな対象を取り巻く知識全体を生み出したので、これは権力/知識の一例であると論じている[212]。 |
| Influence and reception Foucault's works have exercised a powerful influence over numerous humanistic and social scientific disciplines as one of the most influential and controversial scholars of the post-World War II period.[213][214] According to a London School of Economics' analysis in 2016, his works Discipline and Punish and The History of Sexuality were among the 25 most cited books in the social sciences of all time, at just over 100,000 citations.[215] In 2007, Foucault was listed as the single most cited scholar in the humanities by the ISI Web of Science among a large quantity of French philosophers, the compilation's author commenting that "What this says of modern scholarship is for the reader to decide—and it is imagined that judgments will vary from admiration to despair, depending on one's view".[216] According to Gary Gutting, Foucault's "detailed historical remarks on the emergence of disciplinary and regulatory biopower have been widely influential".[217] Leo Bersani wrote that: "[Foucault] is our most brilliant philosopher of power. More originally than any other contemporary thinker, he has attempted to define the historical constraints under which we live, at the same time that he has been anxious to account for—if possible, even to locate—the points at which we might resist those constraints and counter some of the moves of power. In the present climate of cynical disgust with the exercise of political power, Foucault's importance can hardly be exaggerated."[218] Foucault's work on "biopower" has been widely influential within the disciplines of philosophy and political theory, particularly for such authors as Giorgio Agamben, Roberto Esposito, Antonio Negri, and Michael Hardt.[219] His discussions on power and discourse have inspired many critical theorists, who believe that Foucault's analysis of power structures could aid the struggle against inequality. They claim that through discourse analysis, hierarchies may be uncovered and questioned by way of analyzing the corresponding fields of knowledge through which they are legitimated. This is one of the ways that Foucault's work is linked to critical theory.[220] His work Discipline and Punish influenced his friend and contemporary Gilles Deleuze, who published the paper "Postscript on the Societies of Control", praising Foucault's work but arguing that contemporary western society has in fact developed from a 'disciplinary society' into a 'society of control'.[221] Deleuze went on to publish a book dedicated to Foucault's thought in 1988 under the title Foucault. Foucault's discussions of the relationship between power and knowledge has influenced postcolonial critiques in explaining the discursive formation of colonialism, particularly in Edward Said's work Orientalism.[222] Foucault's work has been compared to that of Erving Goffman by the sociologist Michael Hviid Jacobsen and Soren Kristiansen, who list Goffman as an influence on Foucault.[223] Foucault's writings, particularly The History of Sexuality, have also been very influential in feminist philosophy and queer theory, particularly the work of the major Feminist scholar Judith Butler due to his theories regarding the genealogy of maleness and femaleness, power, sexuality, and bodies.[213] Critiques and engagements Douglas Murray, writing in his book The War on The West, argued that "Foucault's obsessive analysis of everything through a quasi-Marxist lens of power relations diminished almost everything in society into a transactional, punitive and meaningless dystopia".[224] Crypto-normativity, self-refutation, defeatism Main article: Foucault–Habermas debate A prominent critique of Foucault's thought concerns his refusal to propose positive solutions to the social and political issues that he critiques. Since no human relation is devoid of power, freedom becomes elusive—even as an ideal. This stance which critiques normativity as socially constructed and contingent, but which relies on an implicit norm to mount the critique led philosopher Jürgen Habermas to describe Foucault's thinking as "crypto-normativist", covertly reliant on the very Enlightenment principles he attempts to argue against.[225] A similar critique has been advanced by Diana Taylor, and by Nancy Fraser who argues that "Foucault's critique encompasses traditional moral systems, he denies himself recourse to concepts such as 'freedom' and 'justice', and therefore lacks the ability to generate positive alternatives."[226] Genealogy as historical method and defeatism The philosopher Richard Rorty has argued that Foucault's "archaeology of knowledge" is fundamentally negative, and thus fails to adequately establish any "new" theory of knowledge per se. Rather, Foucault simply provides a few valuable maxims regarding the reading of history. Rorty writes: As far as I can see, all he has to offer are brilliant redescriptions of the past, supplemented by helpful hints on how to avoid being trapped by old historiographical assumptions. These hints consist largely of saying: "do not look for progress or meaning in history; do not see the history of a given activity, of any segment of culture, as the development of rationality or of freedom; do not use any philosophical vocabulary to characterize the essence of such activity or the goal it serves; do not assume that the way this activity is presently conducted gives any clue to the goals it served in the past".[227] Foucault has frequently been criticized by historians for what they consider to be a lack of rigor in his analyses.[228] For example, Hans-Ulrich Wehler harshly criticized Foucault in 1998.[229] Wehler regards Foucault as a bad philosopher who wrongfully received a good response by the humanities and by social sciences. According to Wehler, Foucault's works are not only insufficient in their empiric historical aspects, but also often contradictory and lacking in clarity. For example, Foucault's concept of power is "desperatingly undifferentiated", and Foucault's thesis of a "disciplinary society" is, according to Wehler, only possible because Foucault does not properly differentiate between authority, force, power, violence and legitimacy.[230] In addition, his thesis is based on a one-sided choice of sources (prisons and psychiatric institutions) and neglects other types of organizations as e.g. factories. Also, Wehler criticizes Foucault's "francocentrism" because he did not take into consideration major German-speaking theorists of social sciences like Max Weber and Norbert Elias. In all, Wehler concludes that Foucault is "because of the endless series of flaws in his so-called empirical studies ... an intellectually dishonest, empirically absolutely unreliable, crypto-normativist seducer of Postmodernism".[231] Feminist critiques Though American feminists have built on Foucault's critiques of the historical construction of gender roles and sexuality, some feminists note the limitations of the masculinist subjectivity and ethical orientation that he describes.[232] A related issue raised by scholars Elizabeth Povinelli and Kathryn Yusoff is the almost complete absence of any discussion of race in his writings. Yusoff (2018, p. 211) says "Povinelli draws our attention to the provinciality of Foucault’s project in its conceptualization of a Western European genealogy".[233] Sexuality The philosopher Roger Scruton argues in Sexual Desire (1986) that Foucault was incorrect to claim, in The History of Sexuality, that sexual morality is culturally relative. He criticizes Foucault for assuming that there could be societies in which a "problematisation" of the sexual did not occur, concluding that, "No history of thought could show the 'problematisation' of sexual experience to be peculiar to certain specific social formations: it is characteristic of personal experience generally, and therefore of every genuine social order."[234] Foucault's approach to sexuality, which he sees as socially constructed, has become influential in queer theory. Foucault's resistance to identity politics, and his rejection of the psychoanalytic concept of "object choice", stands at odds with some theories of queer identity.[232] Social constructionism and human nature See also: social constructivism Foucault is sometimes criticized for his purported social constructionism, which some see as an affront to the concept of truth. In Foucault's 1971 televised debate with Noam Chomsky, Foucault argued against the possibility of any fixed human nature, as posited by Chomsky's concept of innate human faculties. Chomsky argued that concepts of justice were rooted in human reason, whereas Foucault rejected the universal basis for a concept of justice.[235] Following the debate, Chomsky was stricken with Foucault's total rejection of the possibility of a universal morality, stating "He struck me as completely amoral, I'd never met anyone who was so totally amoral [...] I mean, I liked him personally, it's just that I couldn't make sense of him. It's as if he was from a different species, or something."[236] Defeatism in education and authority Peruvian writer Mario Vargas Llosa, while acknowledging that Foucault contributed to give a right of citizenship in cultural life to certain marginal and eccentric experiences (of sexuality, of cultural repression, of madness), asserts that his radical critique of authority was detrimental to education.[237] Psychology of the self One of Foucault's claims regarding the subjectivity of the self has been disputed. Opposing Foucault's view of subjectivity, Terje Sparby, Friedrich Edelhäuser, and Ulrich W. Weger argue that other factors, such as biological, environmental, and cultural are explanations for the self.[238] Forget Foucault [icon] This section needs expansion. You can help by adding to it. (October 2022) Jean Baudrillard, in his 1977 tract Oublier Foucault (trans. Forget Foucault), asserted that "Foucault's discourse is a mirror of the powers it describes."[239]: 30 Since "it is possible at last to talk with such definitive understanding about power, sexuality, the body, and discipline [...] it is because at some point all this is here and now over with." Therefore, with "the coincidence between this new version of power and the new version of desire proposed by Deleuze and Lyotard [...] [which was] not accidental: it's simply that in Foucault power takes the place of desire [...] That is why there is no desire in Foucault: its place is already taken [...] When power blends into desire and desire blends into power, let's forget them both."[239] |
影響と受容 フーコーの著作は、第二次世界大戦後において最も影響力があり、論争を巻き起こした学者の一人として、数多くの人文・社会科学分野に強い影響力を行使して きた[213][214]。 2016年のロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの分析によれば、彼の著作である『規律と処罰』と『セクシュアリティの歴史』は、10万件強の被引用 数で、歴代の社会科学分野で最も引用された25冊のうちの一冊に数えられていた[215]。 [215]2007年、フーコーはISI Web of Scienceによって、フランスの哲学者の中で人文科学分野で最も引用された唯一の学者としてリストアップされ、同編集の著者は「このことが現代の学問 について何を語るかは読者が決めることであり、その判断は賞賛から絶望まで、見方によって様々であろうと想像される」とコメントしている[216]。 ゲーリー・ガッティングによれば、フーコーの「規律と規制のバイオパワーの出現に関する詳細な歴史的考察は、広く影響を及ぼしている」[217]: 「フーコーはわれわれにとって最も優れた権力の哲学者である。フーコーは他のどの現代思想家よりも本質的に、われわれが生きている歴史的制約を定義しよう と試みてきたが、同時に彼は、われわれがその制約に抵抗し、権力の動きに対抗することができるかもしれないポイントを説明することに、可能であれば、その 位置を特定することにさえ、心を砕いてきた。政治権力の行使に冷笑的な嫌悪感を抱く現在の風潮において、フーコーの重要性を誇張することはできない」 [218]。 フーコーの「生権力」に関する研究は、哲学や政治理論の分野において、特にジョルジョ・アガンベン、ロベルト・エスポジート、アントニオ・ネグリ、ミヒャ エル・ハルトといった著者に広く影響を及ぼしている[219]。権力と言説に関する彼の議論は多くの批判的理論家を刺激し、彼らはフーコーの権力構造の分 析が不平等との闘いを助けることができると信じている。彼らは、言説分析を通じて、ヒエラルキーが正統化されている対応する知識分野を分析することによっ て、ヒエラルキーを明らかにし、疑問を投げかけることができると主張している。フーコーの著作『規律と処罰』は彼の友人であり同時代のジル・ドゥルーズに 影響を与え、彼は論文「支配の社会についての追記」を発表し、フーコーの著作を賞賛しながらも、現代の西洋社会は事実上「規律社会」から「支配の社会」へ と発展していると主張している[221]。 フーコーの権力と知識の関係についての議論は、特にエドワード・サイードの著作『オリエンタリズム』において、植民地主義の言説的形成を説明する上でポス トコロニアル批評に影響を与えている[222]。 [223]フーコーの著作、特に『セクシュアリティの歴史』は、フェミニズム哲学やクィア理論、特に主要なフェミニスト学者であるジュディス・バトラーの 研究においても、男性性と女性性、権力、セクシュアリティ、身体の系譜に関する彼の理論により、非常に大きな影響を及ぼしている[213]。 批評と関与 ダグラス・マレーは、著書『The War on The West』の中で、「フーコーは、権力関係という準マルクス主義的なレンズを通してあらゆるものを執拗に分析し、社会のほとんどすべてを取引的で、懲罰的 で、無意味なディストピアへと矮小化した」と論じている[224]。 偽規範性、自己反駁、敗北主義 主な記事 フーコー=ハーバーマス論争 フーコーの思想に対する著名な批評は、彼が批評する社会的・政治的問題に対する肯定的な解決策を提案することを拒否していることに関するものである。どの ような人間関係も権力と無縁ではないため、自由は捉えどころのないものとなる。規範性を社会的に構築された偶発的なものとして批判しながらも、その批判を 行うために暗黙の規範に依拠するこの姿勢は、哲学者のユルゲン・ハーバーマスにフーコーの思考を「隠微規範主義者」と表現させ、彼が反論しようとする啓蒙 主義そのものに密かに依拠している。 [225]同様の批評はダイアナ・テイラーや、「フーコーの批評は伝統的な道徳体系を包含しており、彼は『自由』や『正義』といった概念に頼ることを自ら 否定しており、それゆえ肯定的な代替案を生み出す能力を欠いている」と主張するナンシー・フレイザーによってもなされている[226]。 歴史的方法としての系譜学と敗北主義 哲学者リチャード・ローティは、フーコーの「知の考古学」は基本的に否定的であり、それゆえ知の「新しい」理論それ自体を適切に確立することができないと 主張している。むしろ、フーコーは歴史の読み方に関するいくつかの貴重な格言を提供しているに過ぎない。ローティはこう書いている: 私が見る限り、フーコーが提供するのは、過去の見事な再記述と、古い歴史学的前提に囚われないための有用なヒントだけである。これらのヒントは、主にこう 言っている: 「歴史に進歩や意味を求めてはならない。与えられた活動や文化のいかなる区分の歴史も、合理性や自由の発展として見てはならない。そのような活動の本質や それが奉仕する目標を特徴づけるために、いかなる哲学的な語彙も用いてはならない。この活動が現在行われている方法が、過去にそれが奉仕した目標について 何らかの手がかりを与えてくれると仮定してはならない」[227]。 例えば、ハンス=ウルリッヒ・ヴェーラー(Hans-Ulrich Wehler)は1998年にフーコーを厳しく批判している。ヴェーラーによれば、フーコーの著作はその経験史的側面において不十分であるだけでなく、し ばしば矛盾しており、明瞭さを欠いている。例えば、フーコーの権力概念は「絶望的なまでに未分化」であり、「規律社会」というフーコーのテーゼは、ウェー ラーによれば、フーコーが権威、力、権力、暴力、正当性を適切に区別していないからこそ可能なのである[230]。さらに、彼のテーゼは一方的な情報源の 選択(刑務所と精神科施設)に基づいており、工場など他のタイプの組織を軽視している。また、ヴェーラーは、フーコーがマックス・ヴェーバーやノルベル ト・エリアスのようなドイツ語圏の主要な社会科学の理論家を考慮していないことから、フーコーの「フランス中心主義」を批判している。結局のところ、 ヴェーラーはフーコーは「彼のいわゆる経験的研究の果てしない一連の欠陥のために......知的に不誠実で、経験的に絶対的に信頼できず、ポストモダニ ズムを誘惑する暗号規範主義者である」と結論づけている[231]。 フェミニスト批判 アメリカのフェミニストたちは、ジェンダーの役割とセクシュアリティの歴史的構築に関するフーコーの批評を土台としているが、一部のフェミニストたちは、 彼が記述する男性主体主義的主観性と倫理的志向性の限界を指摘している[232]。学者であるエリザベス・ポヴィネリとキャサリン・ユーソフによって提起 された関連する問題は、彼の著作において人種に関する議論がほとんど完全に欠如していることである。ユソフ(2018年、211頁)は「ポヴィネリは西欧 の系譜の概念化におけるフーコーのプロジェクトの地方性に注意を喚起している」と述べている[233]。 セクシュアリティ 哲学者のロジャー・スクルトンは『性の欲望』(1986年)の中で、フーコーが『セクシュアリティの歴史』の中で性的道徳は文化的に相対的であると主張し たのは誤りであったと論じている。彼はフーコーが性的なものの「問題化」が起こらない社会が存在しうると仮定したことを批判し、「いかなる思想史も性的経 験の『問題化』が特定の社会形成に特有であることを示すことはできない。 社会的に構築されたものとみなすフーコーのセクシュアリティへのアプローチは、クィア理論において影響力を持つようになった。アイデンティティ・ポリティ クスに対するフーコーの抵抗、そして「対象選択」という精神分析的概念の拒絶は、クィア・アイデンティティに関するいくつかの理論と対立している [232]。 社会構築主義と人間性 社会構築主義 フーコーはその社会構築主義と称されるものに対して批判されることがあり、それは真理の概念に対する冒涜であるとみなす者もいる。1971年、フーコーは ノーム・チョムスキーとテレビ討論を行い、チョムスキーが提唱する生得的な人間の能力という概念にあるような、固定的な人間性の可能性に反論した。チョム スキーは正義の概念は人間の理性に根ざしていると主張したが、フーコーは正義の概念の普遍的な根拠を否定した[235]。討論の後、チョムスキーはフー コーの普遍的な道徳の可能性の完全な拒絶に打ちのめされ、「彼は完全に非道徳的だと感じた。まるで違う種族か何かから来たかのように」[236]。 教育と権威における敗北主義 ペルーの作家マリオ・バルガス・リョサは、フーコーがある種の周縁的で風変わりな経験(セクシュアリティ、文化的抑圧、狂気)に文化生活における市民権を 与えることに貢献したことを認めつつも、彼の権威に対する急進的な批判は教育にとって有害であったと主張している[237]。 自己の心理学 自己の主体性に関するフーコーの主張のひとつに論争がある。フーコーの主観性についての見解に反対して、テリエ・スパービー、フリードリッヒ・エーデルホ イザー、ウルリッヒ・W・ヴェーガーは、生物学的、環境的、文化的といった他の要因が自己の説明であると主張している[238]。 フーコーを忘れる [アイコン] このセクションは拡張が必要です。追加することで貢献できます。(2022年10月) ジャン・ボードリヤールは1977年の小冊子『オーブリエ・フーコー』(訳注:『フーコーを忘れよ』)の中で、「フーコーの言説は、それが記述する権力の 鏡である」と主張している[239]: 30 「権力、セクシュアリティ、身体、規律についてこのように決定的な理解をもって語ることがようやく可能になった[...]のは、ある時点でこのすべてが今 ここで終わったからである」。したがって、「この権力の新しいヴァージョンとドゥルーズとリオタールによって提案された欲望の新しいヴァージョンとの間の 一致は[...][...]偶然のものではなかった。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault |
|
●リンク
︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶コレージュ・ド・フランス講義︎︎▶思考集成(日本語 版)・ 目次︎▶︎教育を通した人類学的デモクラシーの実践/文化人類学人物群像/ミッシェル・フーコーの権力論/フーコー思考集成・目次/フー コーの 生権力論/臨床医学 の誕生・読解/監獄 の誕生/言葉と物/知 への意志/狂気の歴史/統治術・統治性/フーコー「社会医学 の誕生」:ノート/バイオポリティクス/統治性に関するノート/統治ユニットとしての家族/生・ 権力(せい・けんりょく)/権力について考える/フーコー『性の歴史』読解入門/近代主体概念を問いなおす
●文献

+++
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099