フーコー『言葉と物』ノート
Les mots et les choses
池田光穂(ポー タルに戻る)
フーコー『言葉と物』ノート
Les mots et les choses
池田光穂(ポー タルに戻る)
[書誌]言葉と物 : 人文科学の考古学 / ミシェル・フーコー [著] ; 渡辺一民, 佐々 木明訳<コトバ ト モノ : ジンブン カガク ノ コウコガク>. -- (BN01839320 ) 東京 : 新潮社, 1974.6 413, 61p, 図版1枚 ; 20cm 注記: 索引: 巻末 ISBN: 410506701X 別タイトル: Les mots et les choses 著者標目: Foucault, Michel, 1926-1984 ; 渡辺, 一民(1932-)<ワタナベ, カズタミ> ; 佐々木, 明(1934-)<ササキ, アキラ> 分類: NDC8 : 204 ; NDLC : G14 件名:
「おそらくこのベラスケスの絵のなかに は、古典主義時代における表象関係の表象のようなもの、そしてそうした表象のひらく空間の定義があるといえるだろう」——邦訳(2020:39)
●『知の考古学』ノートはこちらに移転しています。
| The Order of Things:
An Archaeology of the Human Sciences (Les Mots et les Choses: Une
archéologie des sciences humaines) is a book by French philosopher
Michel Foucault. It proposes that every historical period has
underlying epistemic assumptions, ways of thinking, which determine
what is truth and what is acceptable discourse about a subject, by
delineating the origins of biology, economics, and linguistics. The
introduction to the origins of the human sciences begins with detailed,
forensic analyses and discussion of the complex networks of sightlines,
hidden-ness, and representation that exist in the group painting Las
Meninas (The Ladies-in-waiting, 1656) by Diego Velázquez. Foucault's
application of the analyses shows the structural parallels in the
similar developments in perception that occurred in researchers' ways
of seeing the subject in the human sciences. |
『物とことば:人文科学の考古学』(Les Mots et les
Choses: Une archéologie des sciences humaines)は、フランスの哲学者ミシェル・フーコーの著書である。この本は、生物学、経済学、言語学の起源を明らか
にすることで、あらゆる歴史的時代には、真理とは何か、ある主題について許容される議論とは何かを決定する認識論的前提、思考の方法が存在していると主張
している。人間科学の起源についての序論は、ディエゴ・ベラスケスによる『侍女たち』(1656年)という絵画に存在する視線、隠蔽、表現の複雑なネット
ワークの詳細な法医学的分析と考察から始まる。フーコーの分析の応用は、人間科学の対象を研究者が見る方法における類似した知覚の発展における構造的な類
似性を示している。 |
| The concept of episteme In The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences Foucault wrote that a historical period is characterized by epistemes — ways of thinking about truth and about discourse — which are common to the fields of knowledge, and determine what ideas it is possible to conceptualize and what ideas it is acceptable to affirm as true. That the acceptable ideas change and develop in the course of time, manifested as paradigm shifts of intellectualism, for instance between the "Classical Age"[1] and "Modernity" (from Kant onwards) — which is the period considered by Foucault in the book — is support for the thesis that every historical period has underlying epistemic assumptions, ways of thinking that determined what is truth and what is rationally acceptable. 1. Concerning language: from general grammar to linguistics 2. Concerning living organisms: from natural history to biology 3. Concerning money: from the science of wealth to economics[2] Foucault analyzes three epistemes: 1. The episteme of the Renaissance, characterized by resemblance and similitude 2. The episteme of the Classical era, characterized by representation and ordering, identity and difference, as categorization and taxonomy 3. The episteme of the Modern era, the character of which is the subject of the book In the Classical-era episteme, the concept of "man" was not yet defined. Man was not subject to a distinct epistemological awareness.[3] Classical thought, and previous ones, were able to talk about the mind and the body, about the human being, and about his very limited place in the universe, about all the limits of knowledge and his freedom, but none of them have ever known man as modern thought has done. The humanism of the Renaissance, the rationalism of the "classics" assigned human beings a privileged place in the order of the world, but they did not think of man.[4] This happened only with Kant's Critique of Pure Reason, when the entire Western episteme was overturned. The connection between "positivity and finitude", the duplication of the empirical and the transcendental, the "perpetual reference of the cogito to the unthought", the "retreat and the return of the origin", define, for Foucault, man's way of being, because now reflection tries to philosophically found the possibility of knowledge on the analysis of this way of being and no longer on that of representation.[5] |
エピステーメーの概念 『物事の秩序:人間科学の考古学』の中で、フーコーは、ある歴史的時代はエピステーメー(episteme)によって特徴づけられると述べている。エピス テーメーとは、真理や言説についての思考様式であり、知識の分野に共通するものであり、どのような考え方を概念化することが可能であり、どのような考え方 を真実として肯定することが妥当であるかを決定するものである。受け入れられる考え方は時代とともに変化し、発展していくが、例えば「古典時代」[1]と 「近代」(カント以降)の間における知的パラダイムのシフトとして現れる。フーコーが著書で考察している時代である。これは、あらゆる歴史的時代には、真 理とは何か、何が合理的であると受け入れられるかを決定する思考方法である、根底にある認識論的前提があるという主張を裏付けるものである。 1. 言語について:一般文法から言語学へ 2. 生物について:博物学から生物学へ 3. 貨幣について:富の科学から経済学へ[2] フーコーは3つのエピステーメーを分析している。 1. ルネサンスのエピステーメー(認識論)は、類似性と相似性によって特徴づけられる 2. 古典時代のエピステーメー(認識論)は、表現と秩序、同一性と差異、分類と分類学によって特徴づけられる 3. 近代のエピステーメー(認識論)は、本書の主題である 古典時代のエピステーメーでは、「人間」という概念はまだ定義されていなかった。人間は明確な認識論的意識の対象ではなかった。[3] 古典思想やそれ以前の思想は、心や身体、人間、宇宙における人間の非常に限られた位置、知識の限界や人間の自由について語ることはできたが、近代思想のよ うに人間について知ることは決してなかった。ルネサンスのヒューマニズムや「古典」の合理主義は、人間を世界の秩序における特権的な存在と位置づけたが、 人間について考えることはなかった。[4] こうした状況は、カントの『純粋理性批判』によって西洋のエピステーメー全体が覆されるまで続いた。「実在性と有限性」のつながり、経験と超越論の重複、 思考の対象が思考されていないものへと絶えず回帰すること、起源への退却と回帰は、フーコーによれば、人間の存在のあり方を定義する。なぜなら、今や思考 は、もはや表象ではなく、この存在のあり方の分析に基づいて、知識の可能性を哲学的に確立しようとしているからだ。[5] |
Epistemic interpretation Las Meninas (The Ladies-in-waiting, 1656), by Diego Velázquez. (Museo del Prado, Madrid) The Order of Things (1966) is about the "cognitive status of the modern human sciences" in the production of knowledge — the ways of seeing that researchers apply to a subject under examination. Foucault's introduction to the epistemic origins of the human sciences is a forensic analysis of the painting Las Meninas (The Ladies-in-waiting, 1656), by Diego Velázquez, as an objet d'art.[6] For the detailed descriptions, Foucault uses language that is "neither prescribed by, nor filtered through the various texts of art-historical investigation."[7] Ignoring the 17th-century social context of the painting — the subject (a royal family); the artist's biography, technical acumen, artistic sources and stylistic influences; and the relationship with his patrons (King Philip IV of Spain and Queen Mariana of Austria) — Foucault analyzes the conscious, artistic artifice of Las Meninas as a work of art, to show the network of complex, visual relationships that exist among the painter, the subjects, and the spectator who is viewing the painting: We are looking at a picture in which the painter is, in turn, looking out at us. A mere confrontation, eyes catching one another's glance, direct looks superimposing themselves upon one another as they cross. And yet, this slender line of reciprocal visibility embraces a whole complex network of uncertainties, exchanges, and feints. The painter is turning his eyes towards us only in so far as we happen to occupy the same position as his subject.[7][8] As a representational painting Las Meninas is a new episteme (way of thinking) that is at the midpoint between two "great discontinuities" in European intellectualism, the Classical and the modern: "Perhaps there exists, in this painting by Velázquez, the representation, as it were, of Classical representation, and the definition of the space it opens up to us . . . representation freed, finally, from the relation that was impeding it, can offer itself as representation, in its pure form."[7][9] Now he [Velázquez the painter] can be seen, caught in a moment of stillness, at the neutral centre of his oscillation. His dark torso and bright face are half-way between the visible and the invisible: emerging from the canvas, beyond our view, he moves into our gaze; but when, in a moment, he makes a step to the right, removing himself from our gaze, he will be standing exactly in front of the canvas he is painting; he will enter that region where his painting, neglected for an instant, will, for him, become visible once more, free of shadow and free of reticence. As though the painter could not, at the same time, be seen on the picture where he is represented, and also see that upon which he is representing something.[10] The Order of Things concludes with Foucault's explanation of why he did the forensic analysis: Let us, if we may, look for [representation] the previously existing law of that interplay in the painting of Las Meninas. . . . In Classical thought, the personage for whom the representation exists, and who represents himself within it, recognizing himself, therein, as an image or reflection, he who ties together all the interlacing threads of the "representation in the form of a picture or table" — he is never to be found in that table himself. Before the end of the eighteenth century, Man did not exist — any more than the potency of life, the fecundity of labour, or the historical density of language. He is a quite recent creature, which the demiurge of knowledge fabricated with its own hands, less than two hundred years ago: but he has grown old so quickly that it has been only too easy to imagine that he had been waiting for thousands of years in the darkness for that moment of illumination in which he would finally be known.[11] |
認識論的解釈 ディエゴ・ベラスケス作『侍女たち』(1656年) 『物事の秩序』(1966年)は、知識の生産における「現代の人文科学の認識状態」についてのものである。すなわち、研究者が調査対象に適用する見方であ る。フーコーによる人文科学の認識論的起源の紹介は、芸術作品としてのディエゴ・ベラスケス作『侍女たち』(1656年)の法医学的分析である。[6] 詳細な説明を行うために、フーコーは「美術史研究のさまざまなテキストによって規定されたものでも、それらを通して濾過されたものでもない」言語を使用し ている。[7] 17世紀の社会的 絵画の社会的背景(主題(王族)、芸術家の伝記、技術的洞察力、芸術的源泉、様式的影響、パトロン(スペイン王フェリペ4世とオーストリア王妃マリアナ) との関係)を無視し、フーコーは『ラス・メニーナス』を芸術作品として意識的に作り出された技巧として分析し、画家、主題、そして絵画を鑑賞する観客の間 にある複雑な視覚的関係のネットワークを示している。 私たちは絵画を見ているが、その絵画の画家もまた、私たちを見ている。 画家と鑑賞者の視線が交差する。 しかし、この細い視線の交差は、不確実性、交換、フェイントの複雑なネットワーク全体を包含している。 画家が私たちの方を向くのは、私たちと画家の主題が同じ位置を占めている場合だけである。[7][8] 『ラス・メニーナス』は、ヨーロッパの知性主義における2つの「大きな不連続」の中間点に位置する、新しいエピステーメー(思考様式)である。すなわち、 古典主義と近代である。「おそらくベラスケスのこの絵画には、 古典的表現の、いわば表現があり、それが私たちに開く空間の定義がある。... 表現は、ついにそれを妨げていた関係から解放され、純粋な形での表現として、それ自身を表現することができる。」[7][9] 今、画家ベラスケスは、静止した一瞬の動きを捉えられ、その揺れ動く中間点に立っている。彼の暗い胴体と明るい顔は、見えるものと見えないもののちょうど 中間にある。キャンバスから現れ、私たちの視界を超えて、彼は私たちの視線の中へと移動する。しかし、一瞬、彼が右に一歩踏み出し、私たちの視線から離れ ると、 私たちの視線から外れ、彼はまさに自分が描いているキャンバスの前に立つことになる。彼は、一瞬忘れ去られた自分の絵画が再び見えるようになるその領域へ と入っていく。影もなく、遠慮もなく、再び見えるようになるのだ。画家は、同時に、自分が描かれている絵画の中で見られると同時に、自分が何かを描いてい る対象物を見ることはできないかのように。 『物の秩序』は、フーコーが法医学的分析を行った理由についての説明で締めくくられている。 もし可能であれば、ラス・メニーナスに描かれた絵画における相互作用の以前から存在する法則として、[表現]を探してみよう。古典的な思考では、表現が存 在し、その中で自らを表現する人物は、そこにイメージや反射として自身を認識する。「絵画や表形式の表現」の交差する糸をすべて結び合わせる人物は、その 表の中に自身を見出すことは決してない。18世紀末以前には、人間は存在していなかった。生命の潜在能力、労働の繁殖力、言語の歴史的密度も同様である。 人間は、200年足らず前に、知識の創造主が自らの手で作り出した、ごく最近に誕生した生き物である。しかし、人間は急速に成長したため、人間が何千年も の間、ついに知られることになるその瞬間を闇の中で待ち続けていたと想像するのは、あまりにも容易である。[11] |
| Influence The critique of epistemic practices presented in The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences expanded and deepened the research methodology of cultural history.[12] Foucault's presentation and explanation of cultural shifts in awareness about ways of thinking, prompted the historian of science Theodore Porter to investigate and examine the contemporary bases for the production of knowledge, which yielded a critique of the scientific researcher's psychological projection of modern categories of knowledge upon past people and things that remain intrinsically unintelligible, despite contemporary historical knowledge of the past under examination.[13] In France, The Order of Things established Foucault's intellectual pre-eminence among the national intelligentsia; in a review of which, the philosopher Jean-Paul Sartre said that Foucault was "the last barricade of the bourgeoisie." Responding to Sartre, Foucault said, "poor bourgeoisie; if they needed me as a 'barricade', then they had already lost power!"[14] In the book Structuralism (Le Structuralisme, 1968) Jean Piaget compared Foucault's episteme to the concept of paradigm shift, which the philosopher of science Thomas Kuhn presented in The Structure of Scientific Revolutions (1962).[15] |
影響 『物事の秩序:人間科学の考古学』で提示された認識論的実践の批判は、文化史の研究方法を拡大し、深化させた。[12] 思考方法に関する意識の文化的な変化について、フーコーが提示し、説明したことは、科学史家セオドア・ポーターに、 。その結果、科学的研究者が、現代の歴史的知識にもかかわらず、本質的に理解不能な過去の人物や事物に、現代の知識のカテゴリーを心理的に投影していると いう批判が生まれた。 フランスでは、『物たちの秩序』によって、フーコーは国内の知識人たちの間で知的な卓越性を確立した。この書評で、哲学者のジャン=ポール・サルトルは、 フーコーを「ブルジョワジーの最後のバリケード」と評した。サルトルに答えて、フーコーは「哀れなブルジョワたちよ。もし彼らが私を『バリケード』として 必要としているのであれば、彼らはすでに権力を失っているのだ!」と述べた。[14] ジャン・ピアジェは著書『構造主義』(Le Structuralisme、1968年)の中で、フーコーのエピステーメーを科学哲学者トーマス・クーンが著書『科学革命の構造』(1962年)で提 示したパラダイムシフトの概念と比較している。[15] |
| The
Archaeology of Knowledge |
フーコー『知の考古学』ノート |
| https://en.wikipedia.org/wiki/The_Order_of_Things |
★以下は、イマイチで支離滅裂なフランス
語ウィキペディアからの引用です!!
| Les Mots
et les Choses (sous-titré Une archéologie des sciences humaines)
est un essai de Michel Foucault, publié aux éditions Gallimard en 1966.
Avec L'Archéologie du savoir, c'est dans cet ouvrage que Foucault
développe la notion d'« épistémè ». Foucault semble avoir tout d'abord privilégié le titre de L'Ordre des choses, avant de le changer pour satisfaire son éditeur, Pierre Nora1. Contenu du livre Notion d’épistémè2 Le livre s'ouvre sur une description et un commentaire détaillés du tableau Les Ménines de Diego Velázquez et de l'arrangement complexe de ses lignes de plan et de ses effets cachés. « Peut-être y a-t-il, dans ce tableau de Velásquez, comme la représentation de la représentation classique », écrit Foucault. Y est ensuite développée l'idée maîtresse de l'ouvrage : dans toutes les périodes de l'histoire, il existe un certain nombre de conditions de vérité qui conditionnent ce qu'il est possible et acceptable de dire ; par exemple dans un discours de connaissance puis scientifique. Foucault défend la thèse que les « conditions » du discours changent au cours du temps de façon plus ou moins progressive. Il désigne ces « conditions du discours » par le terme d'« épistémè » (de la racine grecque qui donne épistémologie). Foucault analyse diverses transformations des sciences : Celles du langage : la grammaire générale se transforme en linguistique. Celles de la vie : l'histoire naturelle se transforme en biologie. La science des richesses correspond à une mutation de l'« épistémè » qui donne naissance à l'économie moderne. La notion d'épistémè ne doit pas être confondue avec celle de Weltanschauung (vision ou conception du monde), prônée par Dilthey et à laquelle Foucault s'oppose explicitement3. « Ce sont tous ces phénomènes de rapport entre les sciences ou entre les différents discours dans les divers secteurs scientifiques qui constituent ce que j’appelle épistémè d’une époque » — Foucault, Dits et Écrits I, in Sur la justice populaire, op. cit.[réf. non conforme], p. 1239 Trois épistémès Michel Foucault mentionne trois épistémès : L’épistémè de la Renaissance et du xvie siècle, qui sera l’âge de la ressemblance et de la similitude. L’épistémè classique, qui sera l’âge de la représentation, de l'ordre, de l'identité et de la différence qui donnent les catégories. L’épistémè moderne à laquelle nous appartenons, qui est l’enjeu même du livre, et dont il s’agit pour Foucault de rendre compte en cherchant ses limites, ses seuils. L’épistémè du xvie siècle est l’objet du deuxième chapitre, c’est aussi l’analyse la plus courte ; l’épistémè classique est analysée dans tout le reste de la première partie et l’épistémè moderne dans la seconde. Pour le passage de l'âge classique (xviie siècle) au xxe siècle, Foucault identifie quelques penseurs qui ont été déterminants dans la mise en place de l'épistémè moderne, parmi lesquels, par ordre chronologique : La Logique de Port-Royal (1662), travaux sur la logique, la grammaire, la syntaxe, auxquels ont participé Descartes et Pascal. Adam Smith et sa Richesse des nations. Antoine Destutt de Tracy (vers 1800). Dans l’épistémè classique, Foucault dit que l’homme n’existe pas : « Il n’a ni puissance de vie, ni fécondité du travail, ni épaisseur historique du langage. C’est une toute récente créature que la démiurgie du savoir a fabriquée de ses mains, depuis deux cents ans. » — Foucault, Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 319 On parlait certes de l’homme à l’âge classique, mais « il n’y a pas de conscience épistémologique de l’homme »P 1. |
Les Mots et les
Choses』(副題『人間科学の考古学』)は、1966年にガリマール社から出版されたミシェル・フーコーのエッセイである。
L'Archéologie du savoir』とともに、フーコーが「エピステーメー」という概念を発展させたのはこの著作である。 フーコーは当初、L'Ordre des chosesというタイトルを好んでいたようだが、出版社のピエール・ノラを満足させるために変更した1。 本の内容 エピステーメーの概念2 本書の冒頭は、ディエゴ・ベラスケスの絵画『メニーヌ』についての詳細な説明と解説で始まる。フーコーは、「おそらくベラスケスのこの絵には、古典的表象 の表象のようなものがあるのだろう」と書いている。 歴史のどの時代においても、真実には一定の条件があり、それは例えば、知識の言説、そして科学の言説において、何を語ることが可能であり、受け入れられる かを規定する。フーコーは、言説の「条件」は時代とともに多かれ少なかれ緩やかに変化するというテーゼを擁護している。 彼はこれらの「言説の条件」を「エピステーメー」(ギリシャ語の「認識論」の語源)と呼んでいる。フーコーは科学における様々な変容を分析する: 言語:一般的な文法は言語学へと変化する。 生命の科学:博物学は生物学へと変貌する。 富の科学は、近代経済学を生み出した「エピステーメー」の突然変異に相当する。 エピステーメーという概念は、ディルタイが提唱し、フーコーが明確に反対した世界観(Weltanschauung)と混同してはならない3。 「科学間の関係、あるいはさまざまな科学部門におけるさまざまな言説間の関係におけるこうした現象すべてが、私がエポックのエピステーメーと呼ぶものを構 成している」。 - Foucault, Dits et Écrits I, in Sur la justice populaire, op. cit [non-conforming ref], p. 1239 三つのエピステーム ミシェル・フーコーは3つのエピステームに言及している: ルネサンスと16世紀のエピステーメーは、類似と相似の時代であった。 表象、秩序、同一性、差異の時代であり、カテゴリーを生み出した古典的エピステーメー。 私たちが属する近代のエピステーメーとは、まさにこの本で争点となっている問題であり、フーコーがその限界と閾値を探すことによって説明しようとするもの である。 16世紀のエピステーメーが第2章の主題であり、最も短い分析でもある。古典的エピステーメーは第1部の残りの部分を通して分析され、近代的エピステー メーは第2部で分析される。 古典期(17世紀)から20世紀への移行期において、フーコーは近代エピステーメーの確立に貢献した思想家を年代順に挙げている: La Logique de Port-Royal』(1662年)は、デカルトやパスカルがその一翼を担った論理学、文法、構文に関する著作である。 アダム・スミスと『国富論』。 アントワーヌ・デストゥット・ド・トレーシー(1800年頃)。 古典的エピステーメーにおいて、フーコーは人間は存在しないと言う: 「彼は生命の力も、労働の豊饒さも、言語の歴史的厚みも持っていない。彼は、知識のデミウルギーが200年もの間、自らの手で製造してきたごく最近の生き 物なのである。 - Foucault, Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 319 古典的な時代には確かに人間について語ったが、「人間についての認識論的な認識はない」 P 1. |
| Pour apercevoir l’épistémè, il a
fallu, comme nous le dit Georges Canguilhem à propos de Foucault : «
sortir d’une science et de l’histoire des sciences : il a fallu défier
la spécialisation des spécialistes et tenter de devenir un spécialiste
non pas de la généralité, mais un spécialiste de l’inter-régionalité »4. Il ne s’agit absolument pas pour Foucault de simplement catégoriser des périodes historiques, l’épistémè n’est pas pour une époque donnée une sorte de grande théorie sous-jacente. Ce n’est pas « la somme de ses connaissances, ou le style général des recherches » mais c’est bien plutôt « l’écart, les distances, les oppositions, les différences [...] c’est un espace de la dispersion, c’est un champ ouvert et sans doute indéfiniment descriptible de relations »P 2. Pour comprendre l’épistémè foucaldienne il faut sortir d’une pensée de l’histoire qui « emporterait toutes les sciences dans une grande envolée »4. L’épistémè n’est paradoxalement pas un objet pour l’épistémologie, c’est avant tout, et dans son développement même, ce pour quoi un statut du discours est recherché tout au long de Les Mots et les Choses. L’objet est ce qu’en dit celui qui en parle. L’épistémè se heurte donc à l’histoire des idées, à l’histoire des sciences, elle est l’objet et le résultat d’une élaboration conceptuelle où « l’archéologie » remplace « l’Histoire »5. C’est à partir de ce concept d’épistémè, et de son rapport à l’archéologie, qu’on a fait de Foucault le penseur de la discontinuité historique, penseur de la rupture. Certes Foucault récuse bien toute histoire continue, progressive, mais son travail n’est pas de s’opposer à l’histoire des sciences ou des idées (même si ces dernières doivent être relativisées et critiquées), il s’agit plutôt chez Foucault d’essayer de faire un pas de côté, de risquer sa pensée en introduisant de la signification à l’intérieur même de l’écart que l’on peut apercevoir avec notre propre pensée. Foucault définissait d’ailleurs le “travail” comme « ce qui est susceptible d’introduire une différence significative dans le champ du savoir, au prix d’une certaine peine pour l’auteur et le lecteur, et avec l’éventuelle récompense d’un certain plaisir, c’est-à-dire d’un accès à une autre figure de la vérité »P 3. Le sous-titre de Les Mots et les Choses est « archéologie des sciences humaines ». Foucault conçoit que l’originalité de ses analyses heurte « ceux qui préfèreront nier que le discours soit une pratique complexe et différenciée, obéissant à des règles et à des transformations analysables, plutôt que d’être privé de cette tendre certitude, de pouvoir changer sinon le monde, sinon la vie, du moins leur « sens » par la fraîcheur d’une parole qui ne viendrait que d’eux-mêmes »P 4. On peut noter par exemple pour la biologie, « que l’évolutionnisme constitue une théorie biologique dont les conditions de possibilité fut une biologie sans évolution – celle de Cuvier »P 5. De même que Foucault fait de Ricardo la condition de possibilité de l’œuvre de Marx, il fait de l’œuvre de Cuvier la condition de possibilité de l’œuvre de Darwin (encore que Foucault ressentant un certain malaise devant cette catégorisation exemplaire d' « auteurs », il préférera en 1970, parler de « transformation Cuvier » ou de « transformation Ricardo », car ce n’est pas « l’œuvre » de ces auteurs qu’il cherchait à mettre en valeur, mais les transformations qui ont eu lieu à une époque donnéeP 6). Le rapprochement de ce concept avec le concept de structure tel que le développe le structuralisme n’est pas totalement pertinent. Les structures supposent une transformation et un invariant. Or les différentes épistémès que Foucault identifie se juxtaposent selon des « discontinuités énigmatiques »P 7. Jean Piaget considère que leur « émergence contingente »6 est contradictoire avec l'idée de structure. Réception Les Mots et les Choses donnèrent presque immédiatement à Michel Foucault un statut d'intellectuel prééminent, provoquant des réactions passionnées, qu'elles soient positives ou négatives. L'ouvrage, publié la même année que les Écrits de Jacques Lacan et Critique et vérité de Roland Barthes, semble, aux yeux des lecteurs contemporains, participer du mouvement structuraliste, bien que Foucault se défende d'y appartenir7. Vingt mille exemplaires sont vendus la première année, et plus de 110 000 le seront en vingt ans7. Publié dans la collection « Tel » depuis 1990, l'ouvrage continue à se vendre à 5 000 exemplaires par an, selon l'éditeur7. Dans le numéro 30 de L'Arc (en octobre 1966), Jean-Paul Sartre attaque Foucault en le désignant comme « le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx », voyant dans son œuvre « le refus de l'Histoire. [...] Que trouvons-nous dans Les Mots et les Choses ? Non pas une "archéologie" des sciences humaines. [...] Ce que Foucault nous présente c'est, comme l'a très bien vu Kanters, une géologie : la série des couches successives qui forment notre "sol". [...] Mais Foucault ne nous dit pas ce qui serait le plus intéressant : à savoir comment chaque pensée est construite à partir de ces conditions, ni comment les Hommes passent d'une pensée à une autre. [...] il remplace le cinéma par la lanterne magique, le mouvement par une succession d'immobilités »8. Un an après la publication par Althusser de Pour Marx, les derniers mots de Foucault dans ce livre, qui affirme qu'une nouvelle épistémè pourrait bien faire disparaître la figure de l'homme en tant qu'objet des sciences humaines, « comme à la limite de la mer un visage de sable », suscite une controverse à propos de l'« anti-humanisme théorique »9 supposé de Foucault. Ainsi Jean Lacroix commente le livre dans un article intitulé « Fin de l'humanisme » dans Le Monde7. Gilles Deleuze intitule, quant à lui, son article dans Le Nouvel Observateur, « L'homme, une existence douteuse », tandis que Georges Canguilhem choisit comme titre pour le sien, un an plus tard, dans la revue Critique : « Mort de l'homme ou épuisement du cogito »7. Pourtant, chez Foucault, la « critique » des sciences humaines semble en fait n'avoir que peu en commun avec une critique de l'humanisme en tant que tel, comme l'indique par exemple le texte sur l'opuscule de Kant, Qu'est-ce que les Lumières ?10. En 1967, dans La Chinoise (de Jean-Luc Godard), le livre de Foucault est attaqué à coup de tomates par l'actrice principale7. La notion d’épistémè a posé des problèmes et produit des malentendus. Foucault dans une interview en 1972, explique : « ce que j’ai appelé dans Les Mots et les Choses « épistémè » n’a rien à voir avec les catégories historiques. J’entends tous les rapports qui ont existé à une certaine époque entre les différents domaines de la science [...] Ce sont tous ces phénomènes de rapport entre les sciences ou entre les différents discours dans les divers secteurs scientifiques qui constituent ce que j’appelle épistémè d’une époque »P 8. L’identification de l’épistémè d’une époque, ce n’est pas une catégorisation historique et progressive des objets d’un savoir d’une période donnée, mais la mise en perspective archéologique (et critique) de l’écart même que l’on pourrait assigner entre nos propres cadres de pensée, pris eux-mêmes dans un réseau imperceptible de contraintes lié à l’épistémè à laquelle nous appartenons, avec une épistémè antérieure (en l’occurrence ici l’épistémè classique) où il est impossible de nous reconnaître tant la disposition générale des savoirs a subi de « discontinuités énigmatiques »P 7 que Foucault n’a pas la prétention d’expliquer, mais qu’il qualifie comme « mutation », « évènement radical », « décalage infime mais essentiel »P 9. Dans la préface de Les Mots et les Choses, Foucault définit le travail archéologique et le projet qu’il poursuit de cette manière : « ce qui s’offre à l’analyse archéologique, c’est tout le savoir classique, ou plutôt ce seuil qui nous sépare de la pensée classique et constitue notre modernité. C’est sur ce seuil qu’est apparue pour la première fois cette étrange figure du savoir qu’on appelle l’homme, et qui a ouvert un espace propre aux sciences humaines »P 10. Canguilhem, un an seulement après sa sortie, commente ainsi le livre : « En désignant sous le nom général d’anthropologie l’ensemble de ces sciences qui se sont constituées au xixe siècle, non comme un héritage du xviiie, mais comme un « événement dans l’ordre du savoir »P 11, Foucault nomme alors « sommeil anthropologique » la tranquille assurance avec laquelle les promoteurs actuels des sciences humaines prennent pour accordé comme objet, donné là d’avance à leurs études progressives, ce qui n’était au départ que leur projet de constitution [...] Les Mots et les Choses est pour les sciences de l’homme ce que la Critique de la raison pure était pour les sciences de la nature »4. C'est à partir des « contre-sciences » humaines, c'est-à-dire la psychanalyse, l'ethnologie et la linguistiqueP 12, mais aussi à partir de la littérature11, que Foucault élabore sa pensée. |
エピステーメーを垣間見るためには、ジョルジュ・カンギレムがフーコー
について言うように、「科学と科学の歴史から脱却しなければならなかった。専門家の専門化に逆らい、一般性ではなく、地域間の専門家になろうとしなければ
ならなかった」4。 フーコーにとって、エピステーメーとは、ある時代にとって、根本的な大理論のようなものではない。エピステーメーとは、ある時代にとって、根本的な大理論 のようなものではないのである。エピステーメーとは「知識の総体、あるいは研究の一般的なスタイル」ではなく、むしろ「ギャップ、距離、対立、差異 [......]のことであり、それは分散の空間であり、開かれた、間違いなく無限に記述可能な関係の場である」P 2. フーコー的エピステーメーを理解するためには、「すべての科学を大飛翔のうちに運び去る」ような歴史についての考え方から離れる必要がある4。 逆説的だが、エピステーメーは認識論の対象ではなく、何よりもまず、その発展そのものが、『言葉と物』全体を通して言説の地位を求める理由なのである。対 象とは、話し手がそれについて語ることである。エピステーメーとは、このように思想史や科学史と衝突するものであり、「考古学」が「歴史」に取って代わる 概念的精緻化の対象であり結果なのである5。 このエピステーメーの概念と考古学との関係から、フーコーは歴史的不連続の思想家、断絶の思想家とされたのである。確かに、フーコーは連続的で漸進的な歴 史を否定しているが、彼の仕事は科学や思想の歴史に反対することではなく(たとえ後者が相対化され批判されなければならないとしても)、むしろ、フーコー は一歩横に踏み出そうとすることであり、私たち自身の思考と他者の思考の間に見られるまさにそのギャップに意味を導入することによって、自分の思考を危険 にさらすことなのである。フーコーは 「作品 」を、「作者と読者に一定の苦痛を与え、一定の快楽、つまり別の真実の姿へのアクセスという報酬を得る可能性をもって、知識の分野に重要な差異を導入する ことができるもの」と定義したP 3。 Les Mots et les Choses』の副題は「人間科学の考古学」である。フーコーは、自分の分析の独創性が「言説が複雑で分化した実践であり、分析可能な規則と変容に従うこ とを否定するよりも、自分自身からしか生まれない言葉の新鮮さによって、世界や人生とまではいかなくても、少なくとも自分の『意味』を変えることができる という優しい確信を奪われることを望む人々」を怒らせることを自覚しているP 4. 例えば生物学では、「進化論は、進化のない生物学、つまりキュヴィエの生物学が可能性の条件であった生物学理論を構成している」P 5. フーコーがリカルドをマルクスの仕事の可能性の条件にしているのと同じように、彼はキュヴィエの仕事をダーウィンの仕事の可能性の条件にしている(ただ し、フーコーはこのような「作者」の例示的な分類にある種の不安を感じており、1970年には「キュヴィエの変容」や「リカルドの変容」について語ること を好んだ。) この概念と構造主義が発展させた構造の概念との比較は、まったく関係がないわけではない。構造は変容と不変を前提とする。しかし、フーコーが特定したさま ざまなエピステムは、「謎めいた不連続性」P 7に従って並置されている。ジャン・ピアジェは、それらの「偶発的な出現」6 は構造の概念と矛盾すると考えている。 受容 Les Mots et les Choses』は、ミシェル・フーコーに傑出した知識人としての地位をほぼ即座に与え、肯定的にも否定的にも情熱的な反応を引き起こした。ジャック・ラカ ンの『Écrits』やロラン・バルトの『Critique et vérité』と同じ年に出版された本書は、フーコーが構造主義運動への参加を否定していたにもかかわらず、現代の読者には構造主義運動の一部であるかの ように思われた7。 初年度に2万部が売れ、20年間で11万部以上が売れた7。出版社によれば、この本は1990年以来「テル」コレクションとして出版され、年間5,000 部売れ続けている7。 『ラルク』30号(1966年10月)で、ジャン=ポール・サルトルはフーコーを攻撃し、「ブルジョワジーがマルクスに対抗できる最後の障壁」と評し、彼の 作品に「歴史の拒絶」を見た。[私たちは『言葉と言葉』に何を見出すのだろうか。人間科学の「考古学」ではない。[フーコーがわれわれに提示するのは、カ ンタースが正しく見抜いたように、地質学である。[しかしフーコーは、何が最も興味深いか、すなわち、それぞれの思考がこれらの条件に基づいてどのように 構築されるのか、あるいは、人間がある思考から別の思考へとどのように移行するのか、については語らない。[彼は映画を魔法の提灯に、運動を不動の連続に 置き換えている」8。 アルチュセールが『マルクスを注ぐ』を出版した1年後、フーコーが本書で最後に述べた言葉は、新しい認識論が人間科学の対象として人間の姿を「海辺の砂の 顔のように」消滅させる可能性があると主張し、フーコーの「理論的反人間主義」とされる論争を巻き起こした9。ジャン・ラクロワは『ル・モンド』誌の 「ヒューマニズムの終焉」と題する記事でこの本についてコメントしている7。ジル・ドゥルーズは『Le Nouvel Observateur』誌の論文に「L'homme, une existence douteuse」というタイトルをつけ、ジョルジュ・カンギレムは一年後、『Critique』誌の書評に「Mort de l'homme ou épuisement du cogito」というタイトルをつけた7。しかし、フーコーの人間科学に対する「批評」は、たとえばカントの著作『ルミエール』に関する文章10に見られ るように、人文主義に対する批評とはほとんど共通点がないように思われる。 ジャン=リュック・ゴダールの1967年の映画『ラ・シノワーズ』では、フーコーの本が主演女優によってトマトで攻撃されている7。 エピステーメーという概念は問題を引き起こし、誤解を生んだ。1972年のインタビューで、フーコーは次のように説明している。「私が『言葉と言葉』の中 で『エピステーメー』と呼んだものは、歴史的カテゴリーとは何の関係もない。私が『エピステーメー』と呼んだものは、歴史的なカテゴリーとは何の関係もな い。私が意味するのは、ある時代に科学の異なる分野の間に存在したすべての関係である[......]私がある時代のエピステーメーと呼ぶものを構成する のは、科学間の、あるいはさまざまな科学部門におけるさまざまな言説間の、こうした関係性のすべての現象である」P 8. ある時代のエピステーメーを特定することは、ある時代の知の対象を歴史的かつ漸進的に分類することではなく、私たちが属するエピステーメーに結びついた知 覚できない束縛のネットワークに巻き込まれた私たち自身の思考の枠組みの間にある、まさにそのギャップを考古学的(かつ批判的)にとらえることなのであ る、 フーコーはそれを説明しようとはしないが、「突然変異」、「急進的な出来事」、「微小だが本質的な変化」P 9と呼んでいる。考古学的分析のために提供されるのは、古典的知識全体であり、むしろ、われわれを古典的思想から引き離し、われわれの近代性を構成してい るこの閾値である。人間という奇妙な知の形象が最初に登場し、人間科学に独自の空間を切り開いたのは、この敷居の上であった」P 10. 18世紀の遺産としてではなく、『知の秩序における出来事』P 11として、19世紀に構成されたこれらの科学全体を人類学という一般的な名称のもとに指定することによって、フーコーは次に、現在の人間科学の推進者た ちが、彼らの進歩的な研究にあらかじめ与えられている対象として、当初は彼らの構成プロジェクトにすぎなかったものを当然視する静かな保証を『人類学の眠 り』と呼んだ[......]。 純粋理性批判』が自然科学にとってそうであったように、『言葉と物』は人間科学にとってそうである」4。 フーコーがその思考を発展させたのは、人間の「反科学」、すなわち精神分析、民族学、言語学P12に基づくものであったが、文学11にも基づくものであっ た。 |
| https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mots_et_les_Choses |
|
[章立て]
第1部
第2部
| 考古学的方法 |
共時的な認識論的事象に関連づけていくア
プローチ。考古学の発掘のように、「非連続的に」地層を掘り進めていくと思いもよらないものが発見されるが、それらは発掘された後に、考古学者により関連
づけ、解釈され
てゆく必要がある。直感によって新しいものが生まれることはなく、あくまでも目の前に現れる客観的なものを中心に分析していく手法である。 |
| 系譜学的方法 |
ニーチェ『道徳の系譜』に倣ったアプロー チ。とりあげる事物を「現在に繋がる系譜として」遡及的連続的に扱う方法である。目の前にある素材は、抽象的に洗練され体系的に完成しているかのように提 示されるが、それらの起源が どのような闇から生じるのか、つねにさまざまな認識論的警戒をおこたらない手法である。 |
[章立て]
第1部
第2部
|
ルネサンス(14?・15?・16世紀) _____________________ 類似 |
古典主義時代(17・18世紀) _____________________ タブロー |
近代(19世紀〜) _____________________ 体系 1795〜1825年以降 |
| . | Mathesis 計量と秩序の普遍学/代数学 Taxinomia 分類の原理/学名分類 表象(表象を見る主体はLas Meninasを見る主体のように不在である)
|
. |
| . | 博物学、一般文法、交換の分析、富の分析、 | 生物学、文献学、生産の分析、経済学 |
※これらの対応は、置き換えの関係ではな く、項目内の相互の関係性から構成されるエピステーメーである。
リンク
︎
★フーコー思考集成・目次▶︎ミッシェル・フーコー『古典時代における狂人の歴史』▶フーコー『知への意志』ノート︎︎▶︎フー コー「社会医学の誕生」ノート▶︎︎フーコー『知の考古学』ノー ト▶︎フーコー『性の歴史』読解入門▶︎ミッシェル・フーコー事典プロジェクト▶監視と処罰:監獄の誕生▶︎︎M・フーコー『臨床医学の誕生』の読解▶社会は防衛しなければならない︎▶︎︎性的欲望の装置▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎
★︎︎ミッシェル・フーコー▶︎フーコー派による言説分析▶ミッシェル・フーコーの権力論︎︎▶︎統治術・統治能力▶︎︎生権力▶︎フーコー派の社会医学入門▶︎︎統治性▶︎知と権
力▶︎︎アナトモポリティーク(解剖政治学)とバイオポリティーク(生政
治学)▶︎統治性に関するノート▶︎︎研究ノート:バイオポリティクス▶権
力概念の考察︎▶言説・ディスコース︎︎▶︎バイオポリティクス▶︎︎権
力性の英訳について▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎
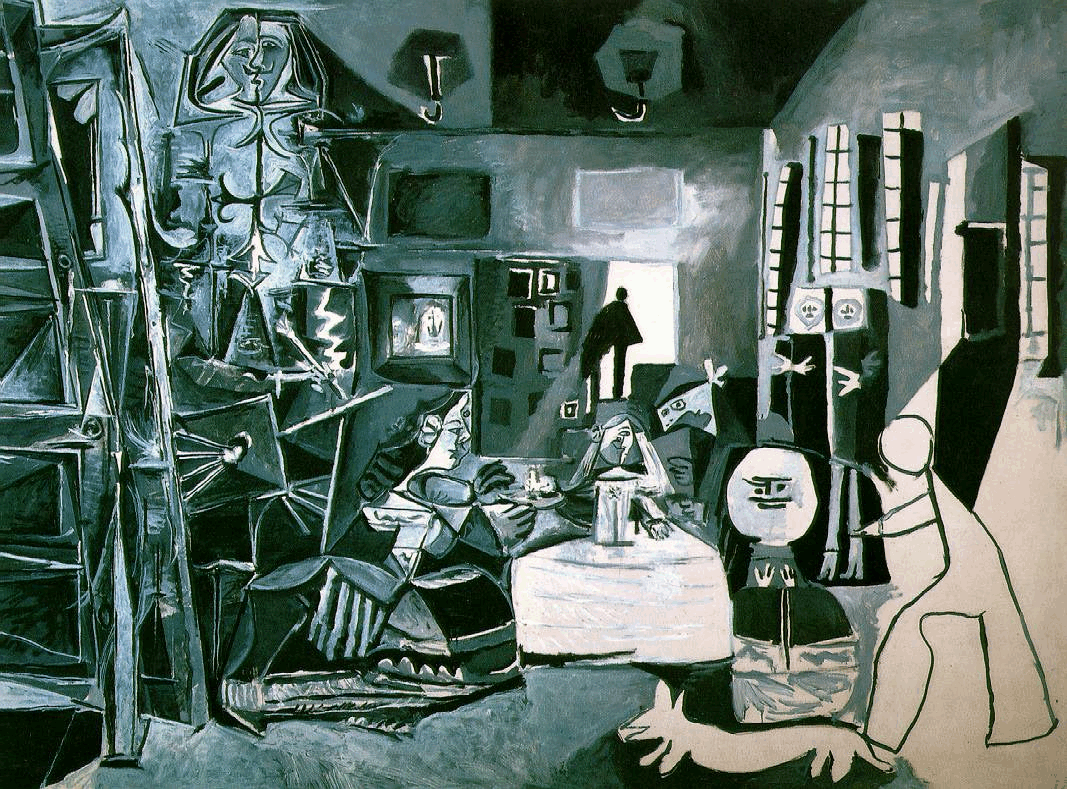
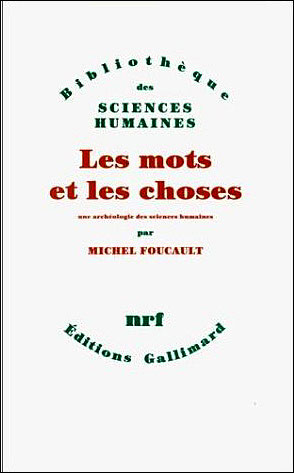
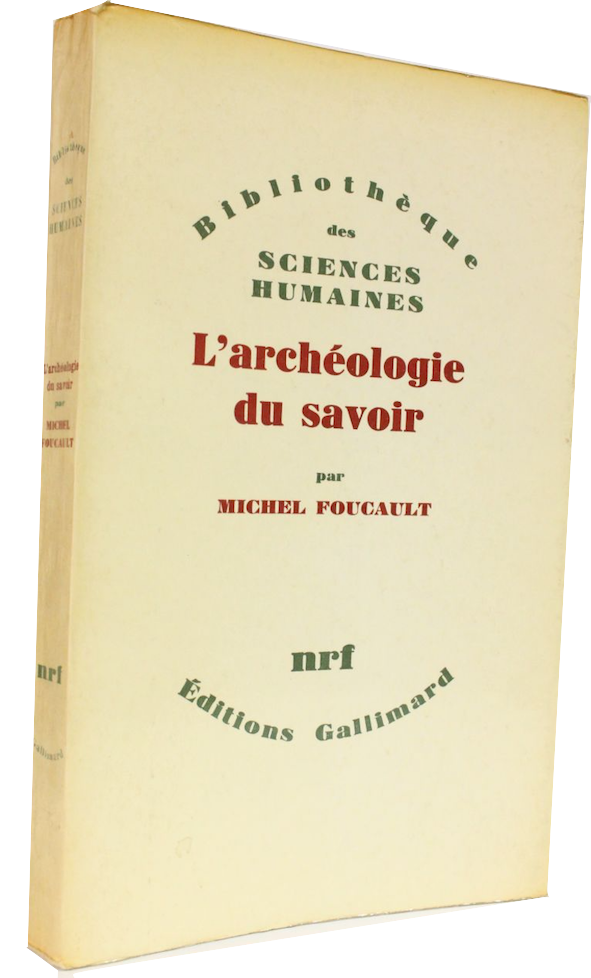
■フーコーの肉声を聞く:Michel Foucault présente son livre Les mots et les choses
Michel Foucault présente son livre Les mots et les choses
Michel Foucault sur
Les mots et le choses
■ 簡単な著作目録
- 『精神疾患とパーソナリティ』(中山元・訳、筑摩書房[文庫])Maladie mentale et Personnalit・ Paris: PUF, 1954.
- 『精神疾患と心理学』(神谷美恵子・訳、みすず書房) Maladie mentale et Psychologie (Paris: PUF, 1962). = second and extensively revised edition of Maladie mentale et Personnalte
- 『臨床医学の誕生』(神谷美恵子・訳、みすず書房) Naissance de la clinique: une archaologie du regard m仕ical (Paris: PUF, 1963).
- 『レーモン・ルーセル』(豊崎光一・訳、法政大学出版局)Raymond Roussel. (Paris: Gallimard, 1963), date of issue May 1963.
- 『言 葉と物』 (渡辺一民ほか訳、新潮社)Les Mots et les Choses. Une archaologie des sciences humaines. Paris 1966.
- 『知の考古学』(中村雄一郎訳、河出書房新社) L'Archaologie du savoir (Paris: Gallimard, March 1969).
- 『言説表現の秩序』(中村雄一郎訳、河出書房新社) L'ordre du discours (Paris, Gallimard, 1971)
- 『狂気の歴史:古典主義時代における』(田村俶訳、新潮社)Histoire de la folie a l'age classique. Gallimard, 1972
- 『監獄の誕生』Surveiller et punir, naissance de la prison (Paris: Gallimard, February 1975).
- 『性の歴史 1権力への意志』Histoire de la sexualit・1. La volonte de savoir (Paris: Gallimard, 1976).
- [未訳]Le désordre des familles : lettres de cachet des Archives de la Bastille au XVIIIe siècle / présenté par Arlette Farge et Michel Foucault, [Paris] : Gallimard, Julliard , c1982. - (Collection Archives ; 91)
- 『性の歴史 2快楽の活用』Histoire de la sexualite II, L'usage des plaisirs (Paris: Gallimard, 1984)
- 『性の歴史 3自己への配慮』Histoire de la sexualite III, Le souci de soi (Paris: Gallimard, 1984)
●『知の考古学』ノートはこちらに移転しています。The Archaeology of Knowledge
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

The order of things, by Michael DeFecault. Pupulon Publisher.
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆