Sociology of scientific knowledge
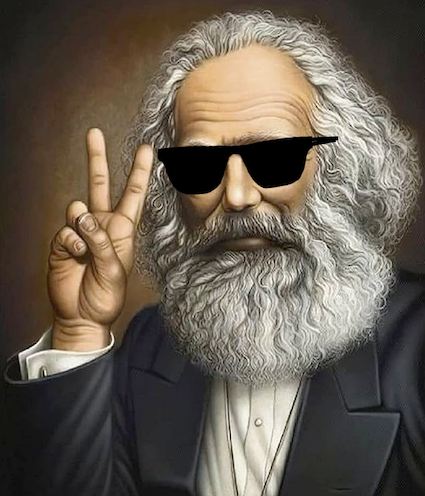

池田光穂
科学的知識の社会学
Sociology of scientific knowledge
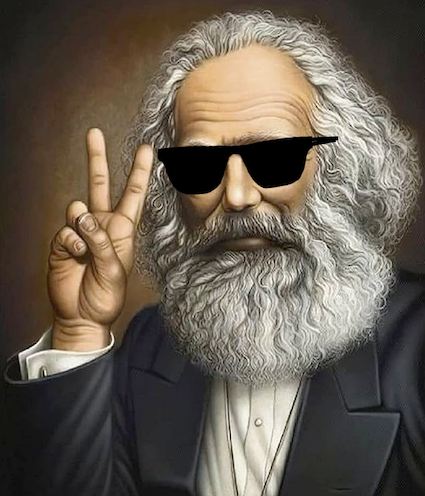

池田光穂
☆科学社会学(Sociology of Science)は、科学の社会的側面を理解することを目的としている。科学社会学は、科学的知識への影響や科学的知識の構築だけでなく、科学制度の社会的構造や他の制度との関係についての研究を含んでいる(出典:PhilPapers)。
★科学的知識の社会学(SSK)とは、科学を社会的活動として研究する学問であり、特に「科学の社会的条件と影響、および科学的活動の社会的構造と過程」を 扱う。[1] 科学的無知の社会学(SSI)は科学的知識の社会学を補完する。[2][3] 比較のため、知識社会学は人間の知識や支配的観念が社会に与える影響、および知識とそれが生じる社会的文脈との関係を研究する。/科学知識社会学の研究者は、科学分野の発展を研究し、曖昧性が存在する不確実性や解釈の柔軟性のポイントを特定しようとする。[4] このような差異は、様々な政治的、歴史的、文化的、経済的要因と関連している可能性がある。重要なのは、この分野が相対主義を推進したり科学プロジェクト を攻撃したりすることを目的としていない点だ。研究者の目的は、外部的な社会的・歴史的状況によって、なぜある解釈が別の解釈よりも成功するのかを説明す ることにある。
| The sociology of
scientific knowledge (SSK) is the study of science as a social
activity, especially dealing with "the social conditions and effects of
science, and with the social structures and processes of scientific
activity."[1] The sociology of scientific ignorance (SSI) is
complementary to the sociology of scientific knowledge.[2][3] For
comparison, the sociology of knowledge studies the impact of human
knowledge and the prevailing ideas on societies and relations between
knowledge and the social context within which it arises. Sociologists of scientific knowledge study the development of a scientific field and attempt to identify points of contingency or interpretative flexibility where ambiguities are present.[4] Such variations may be linked to a variety of political, historical, cultural or economic factors. Crucially, the field does not set out to promote relativism or to attack the scientific project; the objective of the researcher is to explain why one interpretation rather than another succeeds due to external social and historical circumstances. The field emerged in the late 1960s and early 1970s and at first was an almost exclusively British practice. Other early centers for the development of the field were in France, Germany, and the United States (notably at Cornell University).[5] Major theorists include Barry Barnes, David Bloor, Sal Restivo, Randall Collins, Gaston Bachelard, Harry Collins, Karin Knorr Cetina, Paul Feyerabend, Steve Fuller, Martin Kusch, Bruno Latour, Mike Mulkay, Derek J. de Solla Price, Lucy Suchman and Anselm Strauss. |
科学的知識の社会学(SSK)とは、科学を社会的活動として研究する学
問であり、特に「科学の社会的条件と影響、および科学的活動の社会的構造と過程」を扱う。[1]
科学的無知の社会学(SSI)は科学的知識の社会学を補完する。[2][3]
比較のため、知識社会学は人間の知識や支配的観念が社会に与える影響、および知識とそれが生じる社会的文脈との関係を研究する。 科学知識社会学の研究者は、科学分野の発展を研究し、曖昧性が存在する不確実性や解釈の柔軟性のポイントを特定しようとする。[4] このような差異は、様々な政治的、歴史的、文化的、経済的要因と関連している可能性がある。重要なのは、この分野が相対主義を推進したり科学プロジェクト を攻撃したりすることを目的としていない点だ。研究者の目的は、外部的な社会的・歴史的状況によって、なぜある解釈が別の解釈よりも成功するのかを説明す ることにある。 この分野は 1960 年代後半から 1970 年代初頭にかけて出現し、当初はほぼ英国でのみ実践されていた。この分野の発展におけるその他の初期の中心地は、フランス、ドイツ、そして米国(特にコー ネル大学)であった。[5] 主な理論家としては、バリー・バーンズ、デヴィッド・ブルア、サル・レスティヴォ、ランドール・コリンズ、ガストン・バシュラール、ハリー・コリンズ、カ リン・クノール・セティナ、ポール・フェイヤーアバント、スティーブ・フラー、マーティン・クッシュ、ブルーノ・ラトゥール、マイク・マルカイ、デレク・ J・デ・ソラ・プライス、ルーシー・サックマン、アンセルム・ストラウスなどが挙げられる。 |
| Programmes and schools The sociology of scientific knowledge in its Anglophone versions emerged in the 1970s in self-conscious opposition to the sociology of science associated with the American Robert K. Merton, generally considered one of the seminal authors in the sociology of science. Merton's was a kind of "sociology of scientists," which left the cognitive content of science out of sociological account; SSK by contrast aimed at providing sociological explanations of scientific ideas themselves, taking its lead from aspects of the work of Ludwik Fleck,[6][7] Thomas S. Kuhn,[8] but especially from established traditions in cultural anthropology (Durkheim, Mauss) as well as the late Wittgenstein. David Bloor, one of SSK's early champions, has contrasted the so-called 'weak programme' (or 'program'—either spelling is used) which merely gives social explanations for erroneous beliefs, with what he called the 'strong programme', which considers sociological factors as influencing all beliefs.[9] The weak programme is more of a description of an approach than an organised movement. The term is applied to historians, sociologists and philosophers of science who merely cite sociological factors as being responsible for those beliefs that went wrong. Imre Lakatos and (in some moods) Thomas S. Kuhn might be said to adhere to it. The strong programme is particularly associated with the work of two groups: the 'Edinburgh School' (David Bloor, Barry Barnes, and their colleagues at the Science Studies Unit at the University of Edinburgh) in the 1970s and '80s, and the 'Bath School' (Harry Collins and others at the University of Bath) in the same period. "Edinburgh sociologists" and "Bath sociologists" promoted, respectively, the Strong Programme and Empirical Programme of Relativism (EPOR).[10] Also associated with SSK in the 1980s was discourse analysis as applied to science (associated with Michael Mulkay at the University of York), as well as a concern with issues of reflexivity arising from paradoxes relating to SSK's relativist stance towards science and the status of its own knowledge-claims (Steve Woolgar, Malcolm Ashmore).[11] The sociology of scientific knowledge has major international networks through its principal associations, 4S and EASST, with recently established groups in Japan, South Korea, Taiwan, and Latin America. It has made major contributions in recent years to a critical analysis of the biosciences and informatics. |
プログラムと学派 科学知識社会学の英語圏における形態は、1970年代に、アメリカのロバート・K・マートンに関連する科学社会学への自覚的な対抗として現れた。マートン は一般に科学社会学の創始的な著者の一人と見なされている。マートンのアプローチは一種の「科学者社会学」であり、科学の認知的内容を社会学的考察の対象 外とした。これに対しSSK(科学知識社会学)は、科学思想そのものの社会学的説明を目指した。その基盤は、ルドヴィク・フレック[6][7]やトマス・ S・クーン[8]の研究の一面、特に文化人類学の確立された伝統(デュルケーム、モース)および後期ウィトゲンシュタインに由来する。SSKの初期の支持 者の一人であるデイヴィッド・ブルアは、誤った信念に対して単に社会的説明を与えるだけのいわゆる「弱プログラム」(または「プログラム」―どちらの綴り も使用される)と、全ての信念に影響を与える社会学的要因を考慮する「強プログラム」とを対比させた。[9] 弱プログラムは、組織化された運動というより、あるアプローチの記述に近い。この用語は、誤った信念の原因として社会学的要因を単に挙げる歴史学者、社会 学者、科学哲学者に適用される。イムレ・ラカトシュや(時として)トーマス・S・クーンもこれに属すると見なせる。強いプログラムは、1970年代から 80年代にかけての「エジンバラ学派」(デビッド・ブルア、バリー・バーンズ、およびエジンバラ大学科学研究ユニットの同僚たち)と、同時期の「バース学 派」(ハリー・コリンズおよびバース大学の仲間たち)という2つのグループの研究と特に関連している。「エジンバラの社会学者」と「バースの社会学者」 は、それぞれ、ストロング・プログラムと経験的相対主義プログラム(EPOR)を推進した。[10] 1980年代のSSKには、科学に適用される談話分析(ヨーク大学のマイケル・マルケイに関連)や、SSKの科学に対する相対主義的立場と、その知識主張 の地位に関するパラドックスから生じる再帰性の問題への関心(スティーブ・ウールガー、マルコム・アッシュモア)も関連していた。[11] 科学知識社会学は主要な学会組織である4SとEASSTを通じて国際的なネットワークを有し、近年では日本、韓国、台湾、ラテンアメリカに新たなグループが設立されている。近年では生物科学と情報科学の批判的分析に重要な貢献を果たしている。 |
| The sociology of mathematical knowledge Studies of mathematical practice and quasi-empiricism in mathematics are also rightly part of the sociology of knowledge since they focus on the community of those who practice mathematics. Since Eugene Wigner raised the issue in 1960 and Hilary Putnam made it more rigorous in 1975, the question of why fields such as physics and mathematics should agree so well has been debated. Proposed solutions point out that the fundamental constituents of mathematical thought, space, form-structure, and number-proportion are also the fundamental constituents of physics. It is also worthwhile to note that physics is more than merely modeling of reality and the objective basis is upon observational demonstration. Another approach is to suggest that there is no deep problem, that the division of human scientific thinking through using words such as 'mathematics' and 'physics' is only useful in their practical everyday function to categorize and distinguish. Fundamental contributions to the sociology of mathematical knowledge have been made by Sal Restivo and David Bloor. Restivo draws upon the work of scholars such as Oswald Spengler (The Decline of the West, 1918), Raymond Louis Wilder[12] and Leslie Alvin White, as well as contemporary sociologists of knowledge and science studies scholars. David Bloor draws upon Ludwig Wittgenstein and other contemporary thinkers. They both claim that mathematical knowledge is socially constructed and has irreducible contingent and historical factors woven into it. More recently Paul Ernest has proposed a social constructivist account of mathematical knowledge, drawing on the works of both of these sociologists. |
数学的知識の社会学 数学の実践研究や数学における準経験主義も、数学を実践する共同体に焦点を当てる点で、知識社会学の一部として正当に位置づけられる。ユージン・ウィグ ナーが1960年に問題を提起し、ヒラリー・パトナムが1975年により厳密化したように、物理学と数学といった分野がなぜこれほどよく一致するのかとい う疑問は議論されてきた。提案された解決策は、数学的思考の根本的構成要素である空間、形式構造、数・比例が物理学の根本的構成要素でもあると指摘する。 また物理学が単なる現実のモデル化を超え、客観的基盤が観察的実証にある点も留意に値する。別のアプローチでは、根本的な問題など存在せず、「数学」や 「物理学」といった言葉による人間の科学的思考の区分は、日常的な分類や区別という実用的な機能においてのみ有用であると示唆している。 数学的知識の社会学への根本的な貢献は、サル・レスティヴォとデイヴィッド・ブルールによってなされた。レスティヴォはオズワルド・シュペングラー(『西 洋の没落』1918年)、レイモンド・ルイス・ワイルダー[12]、レスリー・アルヴィン・ホワイトといった学者たちの研究に加え、現代の知識社会学者や 科学研究学者たちの成果も参照している。デイヴィッド・ブルールはルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインや他の現代思想家を参照している。両者とも数学的知 識は社会的に構築され、不可逆的な偶発的・歴史的要因が織り込まれていると主張する。近年ではポール・アーネストが、これら二人の社会学者の研究を参照し つつ、数学的知識に関する社会構成主義的解釈を提案している。 |
| Criticism SSK has received criticism from theorists of the actor-network theory (ANT) school of science and technology studies. These theorists criticise SSK for sociological reductionism and a human centered universe. SSK, they say, relies too heavily on human actors and social rules and conventions settling scientific controversies. The debate is discussed in an article titled Epistemological Chicken.[13] |
批判 SSKは、科学技術研究におけるアクター・ネットワーク理論(ANT)学派の理論家たちから批判を受けている。これらの理論家たちは、SSKが社会学的還 元主義と人間中心の宇宙観に陥っていると非難する。SSKは科学的論争を解決する際に、人間主体や社会的規則・慣習に過度に依存していると彼らは主張す る。この論争は『認識論的チキン』と題された論文で論じられている。[13] |
| Academic careerism – Tendency of academics to put career over truth Cliodynamics – Mathematical modeling of historical processes Economics of scientific knowledge Historiography of science – History of the history of science Paradigm shift – Fundamental change in ideas and practices within a scientific discipline Philosophy of social science – Study of the logic, methods, and foundations of social sciences Public awareness of science – Aspect of education and communication Science studies – Research area analyzing scientific expertise Science and technology studies – Academic field Scientific community metaphor Social constructionism – Sociological theory regarding shared understandings Social construction of technology – Theory in science and technology studies Sociology of knowledge – Field of study Sociology of quantification Sociology of scientific ignorance – Study of ignorance in science Sociology of the history of science Technology and society Disputes: Bogdanov affair – 2002 French academic dispute Sokal affair – 1996 scholarly publishing sting accepted by an academic journal |
学問的キャリア主義 – 学者が真実よりもキャリアを優先する傾向 クリオダイナミクス – 歴史的過程の数学的モデル化 科学的知識の経済学 科学史学 – 科学の歴史に関する歴史 パラダイム転換 – 科学分野における思想と実践の根本的変化 社会科学哲学 – 社会科学の論理、方法、基礎の研究 科学の公共認識 – 教育とコミュニケーションの側面 科学研究 – 科学的専門性を分析する研究領域 科学技術研究 – 学術分野 科学共同体メタファー 社会構築主義 – 共有された理解に関する社会学的理論 技術の社会的構築 – 科学技術研究における理論 知識社会学 – 研究分野 定量化社会学 科学的無知の社会学 – 科学における無知の研究 科学史の社会学 技術と社会 論争: ボグダノフ事件 – 2002年のフランス学術論争 ソカル事件 – 1996年に学術誌が受理した学術出版物への潜入調査 |
| 1. Ben-David, Joseph; Teresa A.
Sullivan (1975). "Sociology of Science". Annual Review of Sociology. 1
(1): 203–222. doi:10.1146/annurev.so.01.080175.001223. Retrieved
2006-11-29. 2. Stocking, Holly (1998). "On Drawing Attention to Ignorance". Science Communication. 20 (1): 165–178. doi:10.1177/1075547098020001019. S2CID 145791904. 3. Wehling, Peter (2001). "Beyond knowledge? Scientific ignorance from a sociological point of view". Zeitschrift für Soziologie [de]. 30 (6): 465–484. Retrieved 2013-01-19. 4. Baber, Zaheer (1992). Ashmore, Malcolm; Bhaskar, Roy; Mukerji, Chandra; Woolgar, Steve; Yearley, Steven (eds.). "Sociology of Scientific Knowledge: Lost in the Reflexive Funhouse?". Theory and Society. 21 (1): 105–119. doi:10.1007/BF00993464. ISSN 0304-2421. JSTOR 657625. S2CID 145211615. 5. "Department of Sociology | Department of Sociology Cornell Arts & Sciences". sociology.cornell.edu. Retrieved 2021-09-05. 6. Fleck 1935. 7. Fleck 1979. 8. KUHN, THOMAS (2021-06-08), "The Structure of Scientific Revolutions", Philosophy after Darwin, Princeton University Press, pp. 176–177, doi:10.2307/j.ctv1jk0jrs.26, S2CID 236228428, retrieved 2021-09-05 9. Eriksson, Lena (2007). "Scientific Knowledge, Sociology of". The Blackwell Encyclopedia of Sociology. pp. 1–3. doi:10.1002/9781405165518.wbeoss048. ISBN 9781405165518. 10. Collins, H. M. (1981). "Introduction: Stages in the Empirical Programme of Relativism". Social Studies of Science. 11 (1). Sage Publications, Ltd.: 3–10. doi:10.1177/030631278101100101. ISSN 0306-3127. 11. Mulkay, Michael; Gilbert, G. Nigel (1982). "What is the Ultimate Question? Some Remarks in Defence of the Analysis of Scientific Discourse". Social Studies of Science. 12 (2): 309–319. doi:10.1177/030631282012002006. ISSN 0306-3127. S2CID 144024114. 12. Raymond Wilder (1981) Mathematics as a Cultural System. ISBN 0-08-025796-8 13. Collins, H. M. and S. Yearley (1992). "Epistemological Chicken". In A. Pickering (Ed.) Science as Practice and Culture. Chicago, Chicago University Press: 301-326. Referenced at ANT resource list University of Lancaster, with the summary "Argues against the generalised symmetry of actor-network, preferring in the interpretive sociology tradition to treat humans as ontologically distinct language carriers". Website accessed 8 February 2011. |
1. ベン=デイヴィッド, ジョセフ; テレサ・A・サリヴァン
(1975). 「科学社会学」. 『社会学年次レビュー』. 1 (1): 203–222.
doi:10.1146/annurev.so.01.080175.001223. 2006年11月29日取得. 2. ストッキング, ホリー (1998). 「無知への注意喚起について」. 『科学コミュニケーション』. 20 (1): 165–178. doi:10.1177/1075547098020001019. S2CID 145791904. 3. ヴェーリング、ピーター(2001)。「知識を超えて?社会学的視点から見た科学的無知」。『社会学雑誌』[ドイツ語]。30巻6号:465–484頁。2013年1月19日閲覧。 4. ババー、ザヒール(1992)。アシュモア、マルコム;バスクァル、ロイ;ムケルジ、チャンドラ;ウールガー、スティーブ;イヤーリー、スティーブン (編)。「科学的知識の社会学:反射的な迷宮で迷子か?」『理論と社会』21巻1号:105–119頁。doi:10.1007/BF00993464. ISSN 0304-2421. JSTOR 657625. S2CID 145211615. 5. 「社会学部 | コーンネル大学文理学部社会学部」. sociology.cornell.edu. 2021-09-05 取得. 6. フレック 1935. 7. フレック 1979. 8. クーン, トーマス (2021-06-08), 「科学革命の構造」, 『ダーウィン以降の哲学』, プリンストン大学出版局, pp. 176–177, doi:10.2307/j.ctv1jk0jrs.26, S2CID 236228428, 2021-09-05 参照 9. エリクソン、レナ (2007). 「科学的知識、社会学」. ブラックウェル社会学百科事典. pp. 1–3. doi:10.1002/9781405165518.wbeoss048. ISBN 9781405165518. 10. コリンズ、H. M. (1981). 「序論:相対主義の実証的プログラムにおける段階」. 科学の社会学. 11 (1). Sage Publications, Ltd.: 3–10. doi:10.1177/030631278101100101. ISSN 0306-3127. 11. マルケイ、マイケル、ギルバート、G. ナイジェル (1982)。「究極の疑問とは何か?科学的言説の分析を擁護するいくつかの所見」。Social Studies of Science. 12 (2): 309–319. doi:10.1177/030631282012002006. ISSN 0306-3127。S2CID 144024114。 12. Raymond Wilder (1981) Mathematics as a Cultural System. ISBN 0-08-025796-8 13. コリンズ、H. M.、S. イヤーリー (1992). 「認識論的チキン」。A. ピッカリング (編)『実践と文化としての科学』シカゴ、シカゴ大学出版局: 301-326。ANT リソースリスト、ランカスター大学で参照され、「行為者ネットワークの一般化された対称性に反論し、解釈社会学の伝統において、人間を存在論的に異なる言 語の担い手として扱うことを好む」と要約されている。2011年2月8日アクセス。 |
| References Kusch, Martin (1998). "Sociology of scientific knowledge – research guide". Retrieved February 23, 2012. Further reading Baez, John (2010). "The Bogdanoff Affair". Bloor, David (1976) Knowledge and social imagery. London: Routledge. Bloor, David (1999) "Anti-Latour". Studies in History and Philosophy of Science Part A Volume 30, Issue 1, March 1999, Pages 81–112. Chu, Dominique (2013), The Science Myth---God, society, the self and what we will never know, ISBN 1782790470 Collins, H.M. (1975) The seven sexes: A study in the sociology of a phenomenon, or the replication of experiments in physics, Sociology, 9, 205-24. Collins, H.M. (1985). Changing order: Replication and induction in scientific practice. London: Sage. Collins, Harry and Steven Yearley. (1992). "Epistemological Chicken" in Science as Practice and Culture, A. Pickering (ed.). Chicago: The University of Chicago Press, 301-326. Edwards, D., Ashmore, M. & Potter, J. (1995). Death and furniture: The rhetoric, politics, and theology of bottom line arguments against relativism. History of the Human Sciences, 8, 25-49. Fleck, Ludwik (1935). Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv [Emergence and development of a scientific fact: Introduction to the study of thinking style and thinking collectives] (in German). Verlagsbuchhandlung, Basel: Schwabe. Fleck, Ludwik (1979). Genesis and development of a scientific fact. Chicago, Illinois: University of Chicago Press. Gilbert, G. N. & Mulkay, M. (1984). Opening Pandora's box: A sociological analysis of scientists' discourse. Cambridge: Cambridge University Press. Latour, B. & Woolgar, S. (1986). Laboratory life: The construction of scientific facts. 2nd Edition. Princeton: Princeton University Press. (not an SSK-book, but has a similar approach to science studies) Latour, B. (1987). Science in action : how to follow scientists and engineers through society. Cambridge, MA: Harvard University Press. (not an SSK-book, but has a similar approach to science studies) Pickering, A. (1984). Constructing Quarks: A sociological history of particle physics. Chicago; University of Chicago Press. Schantz, Richard and Markus Seidel (2011). The Problem of Relativism in the Sociology of (Scientific) Knowledge. Frankfurt: ontos. Shapin, S. & Schaffer, S. (1985). Leviathan and the Air-Pump. Princeton, NJ: Princeton University Press. Williams, R. & Edge, D. (1996). The Social Shaping of Technology. Research Policy, vol. 25, pp. 856–899 [1] Willard, Charles Arthur. (1996). Liberalism and the Problem of Knowledge: A New Rhetoric for Modern Democracy, University of Chicago Press. Zuckerman, Harriet. (1988). "The sociology of science." In NJ Smelser (Ed.), Handbook of sociology (p. 511–574). London: Sage. Jasanoff, S. Markle, G. Pinch T. & Petersen, J. (Eds)(2002), Handbook of science, technology and society, Rev Ed.. London: Sage. Other relevant materials Becker, Ernest (1968). The structure of evil; an essay on the unification of the science of man. New York: G. Braziller. Shapin, Steven (1995). "Here and Everywhere: Sociology of Scientific Knowledge" (PDF). Annual Review of Sociology. 21. Annual Reviews: 289–321. doi:10.1146/annurev.so.21.080195.001445. S2CID 3395517. Historical sociologist Simon Schaffer and Steven Shapin are interviewed on SSK The Sociology of Ignorance website featuring the sociology of scientific ignorance Strong Programme in Sociology of Knowledge and Actor-Network Theory: The Debate within Science Studies (includes questions posed to David Bloor and Bruno Latour related to their dispute, in Appendix) |
参考文献 Kusch, マーティン (1998). 「科学的知識の社会学 - 研究ガイド」. 2012年2月23日取得。 関連文献 Baez, ジョン (2010). 「ボグダノフ事件」. Bloor, デイヴィッド (1976) 『知識と社会的イメージ』. ロンドン: Routledge. Bloor, David (1999) 「反ラトゥール」. 科学の歴史と哲学の研究 Part A 第 30 巻、第 1 号、1999年3月、81-112 ページ。 Chu, Dominique (2013), 科学の神話---神、社会、自己、そして私たちが決して知ることのないもの、ISBN 1782790470 コリンズ、H.M. (1975) 『7つの性別:現象の社会学的研究、あるいは物理学の実験の再現』、『Sociology』 9、205-24。 コリンズ、H.M. (1985). 『変化する秩序:科学実践における再現と帰納』 ロンドン:Sage。 コリンズ、ハリー、スティーブン・ヤーリー。(1992). 「認識論的チキン」『実践と文化としての科学』A. ピッカリング (編). シカゴ: シカゴ大学出版局, 301-326. エドワーズ, D., アッシュモア, M. & ポッター, J. (1995). 死と家具: 相対主義に対する最終的な議論のレトリック、政治学、神学. 人間科学の歴史、8、25-49。 フレック、ルドウィック(1935)。Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv [科学的事実の創生と発展:思考様式と思考集団の研究入門](ドイツ語)。Verlagsbuchhandlung、バーゼル:シュワーベ。 フレック、ルドヴィク(1979)。『科学的事実の生成と発展』。シカゴ、イリノイ州:シカゴ大学出版局。 ギルバート、G. N. & マルケイ、M.(1984)。『パンドラの箱を開ける:科学者の言説の社会学的分析』。ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。 ラトゥール、B. & ウールガー、S. (1986). 『実験室生活:科学的事実の構築』第2版. プリンストン:プリンストン大学出版局. (SSK書籍ではないが、科学研究への類似したアプローチを持つ) ラトゥール、B. (1987). 『科学の営み:科学者と技術者を社会の中で追う方法』. マサチューセッツ州ケンブリッジ:ハーバード大学出版局. (SSK書籍ではないが、科学研究への類似したアプローチを持つ) ピッカリング、A.(1984)。『クォークの構築:素粒子物理学の社会学的歴史』。シカゴ:シカゴ大学出版局。 シャンツ、リチャードとマルクス・ザイデル(2011)。『(科学的)知識社会学における相対主義の問題』。フランクフルト:オントス。 シャピン、S. & シェイファー、S. (1985). 『リヴァイアサンと空気ポンプ』. ニュージャージー州プリンストン: プリンストン大学出版局. ウィリアムズ、R. & エッジ、D. (1996). 「技術の社会的形成」. Research Policy, vol. 25, pp. 856–899 [1] ウィラード、チャールズ・アーサー(1996)。『自由主義と知識の問題:現代民主主義のための新たな修辞学』シカゴ大学出版局。 ザッカーマン、ハリエット(1988)。「科学社会学」NJ スメルサー編『社会学ハンドブック』(511–574頁)所収。ロンドン:セージ。 ジャサノフ、S. マークル、G. ピンチ T. & ピーターセン、J.(編)(2002)『科学・技術・社会ハンドブック』改訂版。ロンドン:セージ。 その他の関連資料 ベッカー、アーネスト(1968)『悪の構造:人間科学の統一に関する試論』。ニューヨーク:G. ブラジラー。 シャピン、スティーブン(1995)。「ここであり、あらゆる場所:科学的知識の社会学」(PDF)。『社会学年次レビュー』21巻。Annual Reviews: 289–321頁。doi:10.1146/annurev.so.21.080195.001445. S2CID 3395517. 歴史社会学者サイモン・シェイファーとスティーブン・シャピンがSSKでインタビューを受ける 科学的無知の社会学を特集したウェブサイト「無知の社会学」 知識社会学におけるストロング・プログラムとアクター・ネットワーク理論:科学研究学における論争(付録にデイヴィッド・ブルアとブルーノ・ラトゥールへの論争関連質問を含む) |
| Sociology of Science at PhilPapers |
科学社会学(か がく・しゃかいがく、 Sociology of Science)とは、科学者と彼らが実践する科学的営為を、社会的営為としてみな し、それを社会学の理論や方法を使って分析する学問である。
サイエンス・スタディーズの短い歴史は、1996年 にSocial Text 誌において、ニューヨーク大学物理学教授だったアラン・ソーカル(Alan Sokal, 1955- )が、その2年に投稿し、前年に公刊された同誌の論文"Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity"をめぐって編集者にでっち上げを暴露した、ソーカル事件あるいはサイエンス・ウォーズの前後に大きな分水嶺をもつ。科学社会学も同じよう な流れのなかに位置づけられる。つまり、1996年以前の科学社会学は、ロバート・キング・マートンらに代表される、牧歌的な科学者集団の社会的エートス の形式主義的分析であり、それ以降は、研究費と社会的名誉をめぐる熾烈なドッグレースをくりひろげる一流研究者と、(科学史家トーマス・クーンのいう)パ ラダイム内で、大学や高等研究機関という制度的枠組みのなかで、ルーティン・ワークをつづける、ノーマルサイエンスを再生産する研究者たちである。
前者の牧歌的時代は、形式主義的アプローチと呼んで もよく、科学者の思弁的な議論と、研究の現場を混同する貧弱なアプローチである。池田は、その細かい細部な事情の以下のように表現している。
「このような科学的進歩概念の相対化とそれと
関連する科学者集団もつ「意識」に着目する流れは、研究者の関心を、科学研究者の著作や論文のみな
らず、実験ノートや私信などへと移し、さらには科学者自身がどのように実験データから知識を構成していったのかという——「あまりにもカント的」な名称の
——知識社会学の細部への関心を生むにいたった[ギアーツ
1999:267]。その結果、科学者自身が生きた社会との関係、すなわち科学の社会史という研究下位領域の再活性化の契機にもなった[マルケイ
1985; 松本 1998]。もっとも有力なものがエジンバラ大学の科学研究グループ(ブルア[David Bloor, 1942-
]、バーンズ[S. Barry Barnes, ]、シェイピン[Steven Shapin, 1942-
]ら)のストロング・プログラムである。「科学的知識の社会学[Sociology of Scientific Knowledge,
SSK]」のひとつであるストロング・プ ログラム[the strong
programme]では、科学知識の信念や知識に関する社会的条件(因果性)、その時代におこった真偽、正否、合理/非合理の説明を価値判断ぬ
きに行う(不偏性)、
それらの対立する要素の説明が同じ論理のなかで対称的に説明できる(対称性)、および説明がみずからの正しさを証明できる(自己反射性)という原則におい
て科学の説明を試みようとした[ブルア 1986; バーンズ
1989]。ストロング・プログラムに代表される——科学論ではこれにバース学派が加わる——科学知識の社会学(Sociology of
Scientific Knowledge,
SSK)は、科学の社会現象を認識論的相対化によって理解しようとした立場である。さらにその認識論的な相対化ゆえに、あらゆる知識表象がその現
場の知識 生産のプロセスと無媒介的に認識論的に自由に操作されるという危険性を孕んでいた。
しかし、サイエンス・ウォーズの勃発と、アラン・ ソーカルとジャン・ブリクモンという火付け人たちの、内省性のない中途半端な問題提起だけに終わり、サイエンス・スタディーズは死ぬことはなかった。なぜ なら、その研究対象であるメイン・ストリームのサイエンスのほうが、現在もなお隆盛を保っているからである。形式主義的アプローチにも数多くの新しい課題 が生まれている。
| The term physics envy is
used to criticize modern writing and research of academics working in
areas such as "softer sciences", philosophy, liberal arts, business
administration education, humanities, and social sciences.[1][2][3] The
term argues that writing and working practices in these disciplines
have overused confusing jargon and complicated mathematics to seem more
'rigorous' as in heavily mathematics-based natural science subjects
like physics.[4][5] |
物理学の嫉妬(physics envy)という用
語は、「ソフトサイエンス」、哲学、リベラルアーツ、経営学教育、人文科学、社会科学などの分野で働く学者の現代的な文章や研究を批判するために使用され
る[1][2][3]。この用語は、これらの分野での文章や仕事のやり方が、物理学のような数学を多用する自然科学科目のように、より「厳格」に見えるよ
うに、紛らわしい専門用語や複雑な数学を多用していると主張している[4][5]。 |
| Background The success of physics in "mathematicizing" itself, particularly since Isaac Newton's Principia Mathematica, is generally considered remarkable and often disproportionate compared to other areas of inquiry.[6] "Physics envy" refers to the envy (perceived or real) of scholars in other disciplines for the mathematical precision of fundamental concepts obtained by physicists. It is an accusation raised against disciplines (typically against social sciences such as economics and psychology) when these academic areas try to express their fundamental concepts in terms of mathematics, which is seen as an unwarranted push for reductionism. .[6] For example, Eugene Wigner remarked "The miracle of the appropriateness of the language of mathematics for the formulation of the laws of physics is a wonderful gift which we neither understand nor deserve."[citation needed], while Richard Feynman said "To those who do not know mathematics it is difficult to get across a real feeling as to the beauty, the deepest beauty, of nature ... If you want to learn about nature, to appreciate nature, it is necessary to understand the language that she speaks in."[citation needed] Evolutionary biologist Ernst Mayr discusses the issue of the inability to reduce biology to its mathematical basis in his book What Makes Biology Unique?.[7] Noam Chomsky discusses the ability and desirability of reduction to its mathematical basis in his article "Mysteries of Nature: How Deeply Hidden."[8] Chomsky contributed extensively to the development of the field of theoretical linguistics, a formal science. |
背景 物理学の 「数学化 」の成功は、特にアイザック・ニュートンの「プリンキピア・マテマティカ」以来顕著であり、他の学問分野と比較して不釣り合いであると考えられている。こ のような学問領域が、その基本概念を数学的に表現しようとするとき、(典型的には経済学や心理学などの社会科学に対して)学問に対する非難であり、還元主 義を不当に推し進めるものとみなされる。 .[6] 例えば、ユージン・ウィグナーは「物理法則の定式化に数学の言語が適しているという奇跡は、私たちには理解も値しない素晴らしい贈り物である」[要出典] と述べ、リチャード・ファインマンは「数学を知らない人に、自然の美しさ、最も深い美しさについて実感を伝えるのは難しい...。自然について学びたい、 自然を評価したいと思うなら、自然が話す言語を理解することが必要だ」[要出典]と述べている。 進化生物学者のエルンスト・マイヤーは、その著書『生物学をユニークにするものは何か』の中で、生物学を数学的基礎に還元することができないという問題に ついて論じている[7]。ノーム・チョムスキーは、その論文『自然の神秘』の中で、数学的基礎に還元することの能力と望ましいことについて論じている: チョムスキーは、形式科学である理論言語学の発展に大きく貢献した。 |
| Examples The social sciences have been accused of possessing an inferiority complex, which has been associated with physics envy. For instance, positivist scientists accept a mistaken image of natural science so it can be applied to the social sciences.[9] The phenomenon also exists in business strategy research as demonstrated by historian Alfred Chandler Jr.'s strategy structure model. This framework holds that a firm must evaluate the environment in order to set up its structure that will implement strategies.[10] Chandler also maintained that there is close connection "between mathematics, physics, and engineering graduates and the systemizing of the business strategy paradigm".[10] In the field of artificial intelligence (AI), physics envy arises in cases of projects that lack interaction with each other, using only one idea due to the manner by which new hypotheses are tested and discarded in the pursuit of one true intelligence.[11] |
例 社会科学は劣等感を抱いていると非難されてきたが、それは物理学への嫉妬と関連している。例えば、実証主義の科学者たちは、自然科学が社会科学に適用でき るように、自然科学に対する誤ったイメージを受け入れている。このフレームワークは、企業が戦略を実行する構造を設定するためには環境を評価しなければな らないとしている[10]。チャンドラーはまた、「数学、物理学、工学の卒業生とビジネス戦略のパラダイムの体系化の間には密接な関係がある」と主張して いる[10]。 人工知能(AI)の分野では、1つの真の知性を追求するために新たな仮説が検証され、捨てられるというやり方が原因で、1つのアイデアしか使わず、互いの 相互作用が欠如しているプロジェクトの場合に物理学的羨望が生じる[11]。 |
| Scientism Academese Newtonianism Philosophy of biology Philosophy of physics Philosophy of science Reductionism Unreasonable ineffectiveness of mathematics |
科学主義 アカデミズム ニュートン主義 生物学の哲学 物理学の哲学 科学哲学 還元主義 数学の不合理な非効率性 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Physics_envy |
しかし、さらに重要なのは、科学社会学の方法論的核 心である。それは、エスノグラフィー的方法である。もちろん、20世紀の初等からはじ まったこの方法の科学の営為の現場での応用はサイエンス・ウォーズの 勃発以前からあった。しかし重要なことは、この第二世代の科学社会学は、エスノグラフィー的方法を身にまとうことで、科学人類学とおよびサイエンス・スタディーズとシームレスになり、科学の新 しい研究ジャンルを生み出したことにあるからである。それを池田は次のように描写する
科学研究への関心は歴史的発見から科学者自身が実験 室で行う日常的実践へと移動した。それは科学の発見のような歴史的事実の再構成では得られ ないような、より詳細で正確な情報が手に入るからであった。その背景には、会話分析やエスノメソドロジー、エスノサイエンスなど隣接経験科学(社会学や人 類学)の研究分析手法の発達があったこともその流行に拍車をかけた[ブラニガン 1984; ギルバートとマルケイ 1990]。科学の民族誌学研究の代表にあげられるのは、ラトゥールとウールガー『実験室の生活』[LATOUR and WOOLGAR 1986]、クノール=セティナ『知識の製作』[KNORR-CETINA 1981]、先にも触れたリンチ『実験室における技と人工物』[LYNCH 1985]、ラビノウ『PCRの誕生』(1998[1996])などである。今日では科学の人類学研究は、知識の権力性[e.g. NADER 1996; GOODMAN et al. 2003]に焦点があてられたものが多いが、この実験室から社会性への関心の移行は、後述するようにアクターネットワーク理論進展による(よい、そして悪 い)影響であることは明らかである。」(出典:池田光穂「科学的事実の産出と研究者の実践について」)
科学社会学は、このようにして、2つの重要な遺産を
受け継いで、研究領域としては、十分に成熟した領域を形成するに至った。
有益なリンク
文献
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099