Memoir on Professor Yonezo Nakagawa, 1926-1997

中川米造先生の思い出
Memoir on Professor Yonezo Nakagawa, 1926-1997

解説:池田光穂
中川米造先生の思い出を書いてほしいと編集子(西岡明彦氏——元メ ディカ出版編集者)から言わ れたある日、はじめて出会った頃の師匠の年齢と現在の私の馬齢との差がそれほど違わないと改めて気づいた。師匠への思い出が、不遜にも師匠を乗り越えたく も結局は乗り越えられなかった自らの器の狭さへの自己嫌悪とない交ぜになって「自分の墓碑銘をわざわざ書くような気分ですね」と思わず口走ってしまったの だった。想起(メモリアル)には相応しくない文章だが、出来の悪い門前の小僧の愚痴として後の世代の皆さんに反面教師としてお役に立てれば幸いである。
送られてきた〈メモリアル〉の在りし日の師匠の写真は、滑舌痛快な当時の中川さんそのもの——カッと開いた眼の先がちょっと行方不明でカリスマ 宗教者の不気味さを漂わせているが——で先生へのビジュアルな私の記憶とも寸分違わないことに妙な安堵もした。しかし中川さんのもうひとつの私の心象は、 はにかみ笑いをする一秒前のような非常にニュートラルで穏やかな顔と、院生たちを前に「そーーーかぁ?」と身を乗り出して話に頷くその声やアクションその ものである。
生前の中川さんには、学問に非常に厳しく学友に時には攻撃的になる厳しい「前期」中川さんと、オーストラリアでの医学教育の研修を終えて帰国後 あたりから、人間的に丸くなり笑顔を絶やさない「後期」中川さんがいるとのもっぱらの噂があった。私が知っている中川さんは後期のそれだったので、嫌な顔 をせず何でも聴いてくれる「仏さま」のような師匠の思い出しかない。
後年、中川さんご自身が、がん罹患でカミングアウトされてから後の古稀講演会の時に、この前期と後期の時代区分を私が講釈して話したら、師は ちょっとムスっとしてから、これまでの中川は中期で、これから後期が始まるとおっしゃったのが印象的であった。この軽率な私の発言は実際のところ、まった く赤面どころか青面もので、今でも思い起こす後味の悪い経験である。たしかにその通り。すでに師の学問的使命はおわりとご本人に宣告したようなものだから だ。私じしんは後期フーコー、後期ヴィトゲンシュタインなどと、我が師を知的英雄に仕立てたつもりだったのだが、引導を 渡したのも確かも知れぬ。
さて私が知る「中期」の中川さんの研究室は、かつての中之島キャンパスにあった旧蛋白質研究所の二階にあったと記憶している。そして発足したば かりの医学研究科修士課程の教室は鳥居記念館という一階が生協と食堂になっていた二階の部分を使っていたようだった。
修士課程の教室は、中之島にある医学部の「格調」と「権威ある」——私たちの心証を表現する別の言い換え語は「いけ好かない」だが——階段教室 や川向こうの附属病院にあったさまざまな臨床講義用の講堂やセミナールームでもあったが、中川先生は、内装をやり直し明るくてこざっぱりした鳥居記念館の 教室での授業を愛された。もっともこの頃の私は落ちこぼれの劣等生だったので、教育熱心な恩師の諸先生方には大変失礼ながら、今思い起こしてみると何を学 んだのかさっぱり憶えていない。
私は修士の一年目の自主的な研究を吹田にあった本物正真正銘の蛋白質研究所で生物実験をおこなっていたが、こちらのほうは実験に馴染めず落ちこ ぼれ、中川先生に拾ってもらうために旧蛋白研の研究室をお邪魔したのだった(人権を尊重するようになった昨今「落ちこぼれ」や「(人に)拾ってもらう」と いう表現は穏当さを欠くが、当時の時代状況はそのようなものだった)。
中川さんは、日本における医療の人文社会学的研究の第一人者であったので、欧米からの研究者などの知り合いも多く、私の希望などをひと通り聴い てくださり、その後「医療人類学」という新興学問があり、それに挑戦するのはどうかという旨を おっしゃった。もちろん私は藁をもすがる思いでこの新興学問 に齧りついて、なんとかその分野で仕事をおこなってきた。今の私はこの時の紹介のお陰である。
中川さんは、日本における医療・医学の人文社会学的伝統のパイオニアたるさまざまな仕事をおこなってきた。その興味の数は夥しい。しかし他方 で、蛸壺に住む知識人(これは丸山真男の表現によるものと聞く)からは、詰めが甘いとずいぶん酷い陰口を叩かれたようだ。私はその批判はもっともだと思 う。なぜなら我が師はまさに文芸復興期の知識人(私はそのイメージを当時熱読していた花田清輝や林達夫から随分仕込んだものだ)そのものだったからだ。細 かい論証ではなく大きな見取り図を書く人。知識と権力の癒着以前の時代を生きた幸せな人。あるい は彼こそは近代が生んだ専門知識人誕生以前に数多く棲息し ていたと思われる「智慧ある人」だったかもしれない。中川さんの最大の人徳は、その知識習得を可能にする寛容性にあった。
そういう智慧ある人が、ほとんど絶滅危惧種となった現在、中川さんの記憶を自分の都合のよいように思い起こすことはよく言えばノスタルジー、悪 く言えばアナクロニズムである。彼の死後、弟子を僭称する数多くの知人友人あるいは面識のない人と出会ってきたが、そのたびに同門のよしみとして先方がど うやら私のことを値踏みするような眼差しを向けたように感じまったく辟易してきた。それがどうした(so what?)と言い返したい気分である。ある高名な学者を死後批判的に評したエッセーの標題を捩って、この文章を閉じるとすれば、それは「中川米造に弟子 なし」という一言に尽きるだろう。
リンク
文献
その他の情報

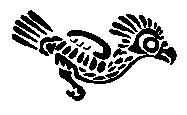
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099