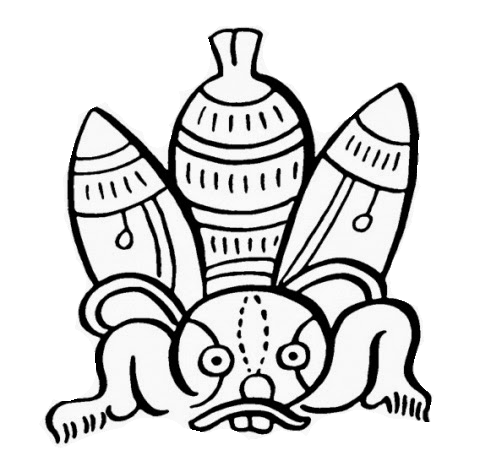
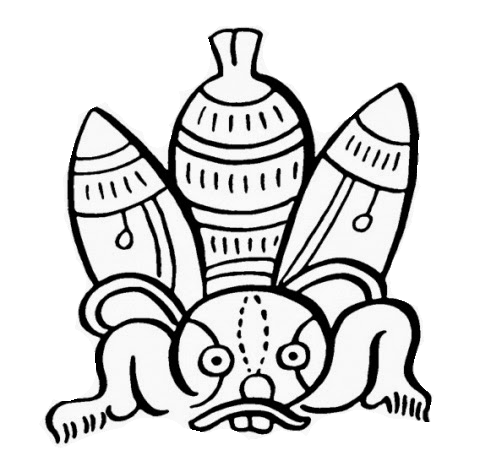
解説 池田光穂
01 文化進化論
人類学的研究は長年にわたって積み重ねら れてきた。しかし、それと同時にその理論の「通俗化」もまた起こっている。「異なる人びとは、異なる 社会に住む」という文化相対主義の認識論もまたその例外ではない。文化が異なれば、人びとの「世界観」もまた異なる、と私たちは簡単に口にしてしまうが、 ことはそのように単純なものではない(1)。文化が異なることが世界観を変えてしまうのか、あるいは世界観が異なるゆえに文化が違うのだろうか。言うまで もなく、この議論に決着をつけることはナンセンスである。しかしながら、このような一種の同語反復はしばしば見受けられる。
はたして「世界観」というのものは、どの ように理解されているであろうか。世界観は、人びとが身の回りに起こった現象を解釈し、また人生に意 味を与える、と言われる。だが、この表現には注意が必要だ。つまり、この論法は、私たちの生活に先だって、すでに「世界観が存在する」ことを前提としてい るのである。では、「世界観」なるものは、人類が存在する以前からあるのだろうか。そんな愚かなことを言う人はいまい。世界観は私たちの生活とともにある のだ。今を去ることおよそ90年前に、『未開社会の分類体系』についてのフレーザー (J.Frazer)の意見に対して、デュルケーム (E.Durkheim)とその甥であるモース(M.Mauss)が与 えた反論(2)は、現在の私たちに対しても示唆的である。[デュルケームとモース 『未開の分類形態』小関藤一郎訳、1980]
フレーザーは、「未開社会」(la société primitive)の人間はヨーロッパの人たちが共有していた「科学的な論理」を持ち合わせておらず、ものごとを解釈するにあたって は、科学とは異なった「彼らなりの論理」すなわち呪術の論理があると考えた。この論理は「科学」と「呪術」を対立させるのではなく、『金枝篇』などにみら れるように、呪術を支持していた社会の内部からそれを否定する論理が生まれ、やがて「宗教」に発展したと彼は考えた(3)。そして西洋においては、宗教の 論理はさらに「科学」の論理へと発展してゆくのである。このような思考様式の進化のようすを、当時において入手できた民族誌資料から再構成を試みたのがフ レーザーであった。そして、この発展図式は当然のことながら呪術の解釈にもあてはめられ。そこにおいてフレーザーは、「思考形態」が社会を構成するという 見解をとった。
後述するが、18世紀後半から20世紀初 頭のヨーロッパの研究者たちがトーテミズムという信仰および社会制度を「発見」したときに、彼らは次 のようなことに注目し理解しようとした。それはトーテムとされている動植物を殺したり食べたりすることの禁止と共に、同じトーテムをもつ集団の内部での結 婚が禁止されていることである。このことからトーテムへの信仰と結婚相手を外部に求めること(外婚制)が相互に関連するものとみなされていた。
しかしながら、フレーザーによると、この 思考と制度の一致は最初から与えられたものではなく、何らかの社会的発展の結果としてできあがったも のである。彼は、その先行形態をオーストラリア・アボリジニのアルンタの人たちのトーテム信仰にみた。アルンタ(あるいはアランダ)においては、トーテム を食べないことは絶対的な禁止ではなく、またアルンタの内部での族内婚がおこなわていた。フレーザーは、彼らの伝承に注目し、その祖先たちがトーテムの動 植物を自由に食べたり殺したりしていたことに注目し、現在のあり方はそれの痕跡だと推理したのである。通常のトーテム信仰において禁止されている土植物の 禁止は後になって——すなわち発展の結果——始まったと主張した。「未開人」はトーテムの動植物と自己ないしは自己のグループを同じものと考えていたの で、動物間で殺し合うことのないことに気づけば、やがてトーテムを殺したり食したりすることは矛盾であるとなるように感じるようになり、実際に禁止するよ うに「発展」したのだ、という主張である。「未開人」はその考え方の論理的発展にしたがって、社会を整備し新しい制度を構築してゆく、と考えたのであっ た。この見解によると、事物を理解する世界観こそが、社会を作っていく原因となる。
だが、オーストラリアのトーテム分類、北 アメリカのズニ・インディアン、さらには中国の易の体系とそれぞれの社会について比較検討し たデュルケームとモースは、社会の組織のされ方が、その社会に属する人たちが事物を分類する見方——世界観——に反映されていることを突き止めた。すなわ ちフレーザーの見解とは逆に、社会の存在様式そのものが彼らの世界観を構成しているという。彼らの説明は説得的である。なぜなら、異なる文化を理解するた めに、私たちとは異なる「別の論理体系」を操作的に想定しなくても、人びとが無意識のうちに従っている社会の存在様式——それは外部から観察可能である ——が、人びとの世界観に反映されていることを検証すればよいからである。
デュルケームとモースの理論がフレイザー に比べて正しいというのではない。前者は後者よりも説得的である。その理由は、デュルケームらの議論 の展開のほうが、個々の社会を具体的に調査してゆくのに都合がよく、またその成否を検証するためにその対応関係について議論すればよいので、より「開かれ た議論」が可能になっている点にある。
■文化進化論(このページ)
| Cultural
evolution
is an evolutionary theory of social change. It follows from the
definition of culture as "information capable of affecting individuals'
behavior that they acquire from other members of their species through
teaching, imitation and other forms of social transmission".[1]
Cultural evolution is the change of this information over time.[2] Cultural evolution, historically also known as sociocultural evolution, was originally developed in the 19th century by anthropologists stemming from Charles Darwin's research on evolution. Today, cultural evolution has become the basis for a growing field of scientific research in the social sciences, including anthropology, economics, psychology, and organizational studies. Previously, it was believed that social change resulted from biological adaptations; anthropologists now commonly accept that social changes arise in consequence of a combination of social, environmental, and biological influences (viewed from a nature vs nurture framework).[3][4] There have been a number of different approaches to the study of cultural evolution, including dual inheritance theory, sociocultural evolution, memetics, cultural evolutionism, and other variants on cultural selection theory. The approaches differ not just in the history of their development and discipline of origin but in how they conceptualize the process of cultural evolution and the assumptions, theories, and methods that they apply to its study. In recent years, there has been a convergence of the cluster of related theories towards seeing cultural evolution as a unified discipline in its own right.[5][6] |
文化進化とは、社会変化の進化論である。文化とは「個人の行動に影響を
与えることができる情報であり、教えや模倣、その他の社会的伝達を通じて他の種族から獲得されるもの」[1]であると定義されている。 文化進化は、歴史的には社会文化進化とも呼ばれ、もともとはチャールズ・ダーウィンの進化に関する研究に端を発し、人類学者によって19世紀に開発され た。今日、文化進化は、人類学、経済学、心理学、組織学など、社会科学における科学的研究の成長分野の基礎となっている。以前は、社会的変化は生物学的適 応から生じると信じられていたが、人類学者は現在、社会的変化は社会的、環境的、生物学的影響(自然対養育の枠組みから見た)の組み合わせの結果として生 じることを一般的に受け入れている[3][4]。 文化進化の研究に対しては、二重継承理論、社会文化進化論、ミーム論、文化進化論、その他文化選択理論の変種など、様々なアプローチがある。これらのアプ ローチは、その発展の歴史や起源となる学問分野だけでなく、文化進化のプロセスをどのように概念化し、その研究にどのような前提、理論、方法を適用するか においても異なっている。近年では、文化進化をそれ自体で統一された学問分野と見なすべく、関連する理論群が収束しつつある[5][6]。 |
| History Main article: Sociocultural evolution Aristotle thought that development of cultural form (such as poetry) stops when it reaches its maturity.[7] In 1873, in Harper's New Monthly Magazine, it was written: "By the principle which Darwin describes as natural selection short words are gaining the advantage over long words, direct forms of expression are gaining the advantage over indirect, words of precise meaning the advantage of the ambiguous, and local idioms are everywhere in disadvantage".[8] Cultural evolution, in the Darwinian sense of variation and selective inheritance, could be said to trace back to Darwin himself.[9] He argued for both customs (1874 p. 239) and "inherited habits" as contributing to human evolution, grounding both in the innate capacity for acquiring language.[10][9][11] Darwin's ideas, along with those of such as Comte and Quetelet, influenced a number of what would now be called social scientists in the late nineteenth and early twentieth centuries. Hodgson and Knudsen[12] single out David George Ritchie and Thorstein Veblen, crediting the former with anticipating both dual inheritance theory and universal Darwinism. Despite the stereotypical image of social Darwinism that developed later in the century, neither Ritchie nor Veblen were on the political right. The early years of the 20th century and particularly World War I saw biological concepts and metaphors shunned by most social sciences. Even uttering the word evolution carried "serious risk to one's intellectual reputation."[citation needed] Darwinian ideas were also in decline following the rediscovery of Mendelian genetics but were revived, especially by Fisher, Haldane, and Wright, who developed the first population genetic models and as it became known the modern synthesis. Cultural evolutionary concepts, or even metaphors, revived more slowly. If there were one influential individual in the revival it was probably Donald T. Campbell. In 1960[13] he drew on Wright to draw a parallel between genetic evolution and the "blind variation and selective retention" of creative ideas; work that was developed into a full theory of "socio-cultural evolution" in 1965[14] (a work that includes references to other works in the then current revival of interest in the field). Campbell (1965 26) was clear that he perceived cultural evolution not as an analogy "from organic evolution per se, but rather from a general model for quasiteleological processes for which organic evolution is but one instance". Others pursued more specific analogies notably the anthropologist F. T. (Ted) Cloak who argued in 1975[15] for the existence of learnt cultural instructions (cultural corpuscles or i-culture) resulting in material artefacts (m-culture) such as wheels.[16] The argument thereby introduced as to whether cultural evolution requires neurological instructions continues to the present day [citation needed]. Unilinear theory In the 19th century cultural evolution was thought to follow a unilineal pattern whereby all cultures progressively develop over time. The underlying assumption was that Cultural Evolution itself led to the growth and development of civilization.[3][17][18] Thomas Hobbes in the 17th century declared indigenous culture to have "no arts, no letters, no society" and he described facing life as "solitary, poor, nasty, brutish, and short." He, like other scholars of his time, reasoned that everything positive and esteemed resulted from the slow development away from this poor lowly state of being.[3] Under the theory of unilinear Cultural Evolution, all societies and cultures develop on the same path. The first to present a general unilineal theory was Herbert Spencer. Spencer suggested that humans develop into more complex beings as culture progresses, where people originally lived in "undifferentiated hordes" culture progresses and develops to the point where civilization develops hierarchies. The concept behind unilinear theory is that the steady accumulation of knowledge and culture leads to the separation of the various modern day sciences and the build-up of cultural norms present in modern-day society.[3][17] In Lewis H. Morgan's book Ancient Society (1877), Morgan labels seven differing stages of human culture: lower, middle, and upper savagery; lower, middle, and upper barbarism; and civilization. He justifies this staging classification by referencing societies whose cultural traits resembled those of each of his stage classifications of the cultural progression. Morgan gave no example of lower savagery, as even at the time of writing few examples remained of this cultural type. At the time of expounding his theory, Morgan's work was highly respected and became a foundation for much of anthropological study that was to follow.[3][17][18] Cultural particularism There began a widespread condemnation of unilinear theory in the late 19th century. Unilinear cultural evolution implicitly assumes that culture was borne out of the United States and Western Europe. That was seen by many to be racist, as it assumed that some individuals and cultures were more evolved than others.[3] Franz Boas, a German-born anthropologist, was the instigator of the movement known as 'cultural particularism' in which the emphasis shifted to a multilinear approach to cultural evolution. That differed to the unilinear approach that used to be favoured in the sense that cultures were no longer compared, but they were assessed uniquely. Boas, along with several of his pupils, notably A.L. Kroeber, Ruth Benedict and Margaret Mead, changed the focus of anthropological research to the effect that instead of generalizing cultures, the attention was now on collecting empirical evidence of how individual cultures change and develop.[3] Multilinear theory Cultural particularism dominated popular thought for the first half of the 20th century before American anthropologists, including Leslie A. White, Julian H. Steward, Marshall D. Sahlins, and Elman R. Service, revived the debate on cultural evolution. These theorists were the first to introduce the idea of multilinear cultural evolution.[3] Under multilinear theory, there are no fixed stages (as in unilinear theory) towards cultural development. Instead, there are several stages of differing lengths and forms. Although, individual cultures develop differently and cultural evolution occurs differently, multilinear theory acknowledges that cultures and societies do tend to develop and move forward.[3][19] Leslie A. White focused on the idea that different cultures had differing amounts of 'energy', White argued that with greater energy societies could possess greater levels of social differentiation. He rejected separation of modern societies from primitive societies. In contrast, Steward argued, much like Darwin's theory of evolution, that culture adapts to its surroundings. 'Evolution and Culture' by Sahlins and Service is an attempt to condense the views of White and Steward into a universal theory of multilinear evolution.[3] Robert Wright recognized the inevitable development of cultures. He proposed that population growth was a crucial component of cultural evolution. Population has a symbiotic relationship with technological, economic, and political development. [20] Memetics Main article: Memetics Richard Dawkins' 1976 book The Selfish Gene proposed the concept of the "meme", which is analogous to that of the gene. A meme is an idea-replicator that can reproduce itself, by jumping from mind to mind via the process of one human learning from another via imitation. Along with the "virus of the mind" image, the meme might be thought of as a "unit of culture" (an idea, belief, pattern of behaviour, etc.), which spreads among the individuals of a population. The variation and selection in the copying process enables Darwinian evolution among memeplexes and therefore is a candidate for a mechanism of cultural evolution. As memes are "selfish" in that they are "interested" only in their own success, they could well be in conflict with their biological host's genetic interests. Consequently, a "meme's eye" view might account for certain evolved cultural traits, such as suicide terrorism, that are successful at spreading the meme of martyrdom, but fatal to their hosts and often other people. Evolutionary epistemology Main article: Evolutionary epistemology "Evolutionary epistemology" can also refer to a theory that applies the concepts of biological evolution to the growth of human knowledge and argues that units of knowledge themselves, particularly scientific theories, evolve according to selection. In that case, a theory, like the germ theory of disease, becomes more or less credible according to changes in the body of knowledge surrounding it. One of the hallmarks of evolutionary epistemology is the notion that empirical testing alone does not justify the pragmatic value of scientific theories but rather that social and methodological processes select those theories with the closest "fit" to a given problem. The mere fact that a theory has survived the most rigorous empirical tests available does not, in the calculus of probability, predict its ability to survive future testing. Karl Popper used Newtonian physics as an example of a body of theories so thoroughly confirmed by testing as to be considered unassailable, but they were nevertheless improved on by Albert Einstein's bold insights into the nature of space-time. For the evolutionary epistemologist, all theories are true only provisionally, regardless of the degree of empirical testing they have survived. Popper is considered by many to have given evolutionary epistemology its first comprehensive treatment, but Donald T. Campbell had coined the phrase in 1974.[21] Dual inheritance theory This section is an excerpt from Dual inheritance theory.[edit] Dual inheritance theory (DIT), also known as gene–culture coevolution or biocultural evolution,[22] was developed in the 1960s through early 1980s to explain how human behavior is a product of two different and interacting evolutionary processes: genetic evolution and cultural evolution. Genes and culture continually interact in a feedback loop:[23] changes in genes can lead to changes in culture which can then influence genetic selection, and vice versa. One of the theory's central claims is that culture evolves partly through a Darwinian selection process, which dual inheritance theorists often describe by analogy to genetic evolution.[24] |
歴史 主な記事 社会文化の進化 アリストテレスは、(詩のような)文化的形式の発展は、それが成熟に達した時点で止まると考えた[7]。 1873年、ハーパーズニューマンスリーマガジンにこう書かれている: 「ダーウィンが自然淘汰と表現する原理によって、短い言葉が長い言葉よりも優位に立ち、直接的な表現形式が間接的な表現よりも優位に立ち、正確な意味の言 葉が曖昧な言葉よりも優位に立ち、ローカルな慣用句はいたるところで不利になっている」[8]。 ダーウィンは習慣(1874年、239ページ)と「受け継がれた習慣」の両方が人類の進化に寄与していると主張し、その両方の根拠を言語習得の生得的能力 に置いている[10][9][11]。 ダーウィンの考えは、コントやケテレなどの考えとともに、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、現在社会科学者と呼ばれている多くの人々に影響を与え た。ホジソンとクヌッセン[12]は、デイヴィッド・ジョージ・リッチーとソーシュタイン・ヴェブレンを挙げ、前者が二重継承説と普遍的ダーウィニズムの 両方を先取りしていたと評価している。リッチーもヴェブレンも政治的右派ではなかった。 20世紀初頭、特に第一次世界大戦では、生物学的な概念や比喩はほとんどの社会科学から敬遠された。進化という言葉を口にすることさえ、「知的評判に対す る深刻なリスク」[要出典]を伴っていた。メンデル遺伝学の再発見後、ダーウィンの考え方も衰退したが、特にフィッシャー、ハルデイン、ライトによって復 活し、彼らは最初の集団遺伝学的モデルを開発し、それが現代総合学として知られるようになった。 文化的進化の概念、あるいはメタファーの復活はもっと遅かった。この復活に影響力を持った人物がいるとすれば、それはドナルド・T・キャンベルであろう。 1960年[13]、彼はライトに依拠して、遺伝的進化と創造的なアイデアの「盲目的な変異と選択的保持」の間の並列を描いた。この仕事は1965年 [14]に「社会文化進化」の完全な理論へと発展した(この仕事には、当時この分野への関心が再燃していた他の仕事への言及も含まれている)。キャンベル (1965 26)は、文化的進化を「有機的進化それ自体からのアナロジーではなく、むしろ有機的進化が一つの事例に過ぎない準地質学的プロセスの一般的モデルからの アナロジー」として認識していることを明言していた。 他の人々はより具体的なアナロジーを追求しており、特に人類学者F. T. (Ted) Cloakは1975年に車輪のような物質的な人工物(m-culture)をもたらす学習された文化的指示(cultural corpusclesまたはi-culture)の存在を主張していた[15]。 単線説 19世紀には、文化進化は一次的なパターンに従うと考えられていた。その根底にある仮定は、文化進化そのものが文明の成長と発展をもたらすというもので あった[3][17][18]。 17世紀のトマス・ホッブズは、土着の文化には「芸術も文字も社会もない」と宣言し、彼は直面する生活を「孤独で、貧しく、厄介で、残忍で、短い」と表現 した。彼は当時の他の学者と同様に、肯定的で尊敬されるものはすべて、このような貧しく卑しい状態からゆっくりと発展していった結果であると推論した [3]。 単線的文化進化論の下では、すべての社会と文化は同じ道筋をたどって発展する。最初に一般的な単線的理論を提示したのはハーバート・スペンサーである。ス ペンサーは、人間は文化が進歩するにつれて、より複雑な存在へと発展することを示唆した。人間はもともと「未分化な大群」で生活していたが、文化は進歩 し、文明が階層を発達させるところまで発展する。ユニリニア理論の背後にある概念は、知識と文化の着実な蓄積が、現代の様々な科学の分離と現代社会に存在 する文化的規範の構築につながるというものである[3][17]。 ルイス・H・モーガンの著書『古代社会』(1877年)の中で、モーガンは人類文化の7つの異なる段階、すなわち下層、中層、上層の未開、下層、中層、上 層の野蛮、そして文明を分類している。この段階分類を正当化するために、モーガンは文化的特質がそれぞれの段階分類に類似している社会を参照している。 モーガンは下層野蛮の例を挙げていないが、それは執筆当時でさえ、この文化タイプの例はほとんど残っていなかったからである。彼の理論を説明した当時、 モーガンの研究は高く評価され、その後の人類学研究の多くの基礎となった[3][17][18]。 文化的特殊主義 19世紀後半になると、単線的理論に対する非難が広まった。単線的文化進化論は、文化はアメリカと西ヨーロッパから生まれたと暗に仮定している。それは、 ある個人や文化が他よりも進化していると仮定するものであり、人種差別的であると多くの人々に見なされた[3]。 ドイツ生まれの人類学者であるフランツ・ボースは、「文化特殊主義」として知られる運動の扇動者であり、文化進化に対する多直線的アプローチに重点を移し た。それは、文化はもはや比較されるものではなく、独自に評価されるという意味で、かつて好まれていた単線的アプローチとは異なっていた。ボースは、特に A.L.クルーバー、ルース・ベネディクト、マーガレット・ミードといった何人かの弟子たちとともに、人類学研究の焦点を、文化を一般化するのではなく、 個々の文化がどのように変化し、発展していくのかについての経験的証拠を収集することに向けるように変えた[3]。 マルチリニア理論 レスリーA.ホワイト、ジュリアンH.スチュワード、マーシャルD.サーリンズ、エルマンR.サービスなどのアメリカの人類学者が文化進化に関する議論を 復活させるまで、20世紀前半は文化特殊主義が一般的な思想を支配していた。これらの理論家たちは、マルチリニア文化進化論という考え方を初めて導入した [3]。 マルチリニア理論では、文化的発展に向けた(ユニリニア理論のような)固定された段階は存在しない。その代わりに、長さや形態が異なる複数の段階が存在す る。個々の文化の発展や文化の進化は異なるが、マルチリニア理論は文化や社会が発展し前進する傾向があることを認めている[3][19]。 レスリーA.ホワイトは、異なる文化は異なる量の「エネルギー」を持っているという考えに注目し、ホワイトは、より大きなエネルギーを持つ社会はより大き なレベルの社会分化を持つことができると主張した。彼は近代社会と原始社会の分離を否定した。これに対してスチュワードは、ダーウィンの進化論と同様に、 文化は周囲の環境に適応すると主張した。サーリンズとサービスによる'Evolution and Culture'は、ホワイトとスチュワードの見解をマルチリニア進化論という普遍的な理論に凝縮しようとする試みである[3]。 ロバート・ライトは文化の必然的な発展を認識していた。彼は人口増加が文化進化の重要な要素であると提唱した。人口は技術的、経済的、政治的発展と共生的 な関係にある。[20] 記憶論 主な記事 記憶論 リチャード・ドーキンスの1976年の著書『利己的な遺伝子』は、遺伝子に類似した「ミーム」という概念を提唱した。ミームとは、ある人間が模倣によって 別の人間から学ぶ過程で、心から心へと飛び移ることによって、それ自体を再生産することができるアイデア・リプリケーターである。心のウイルス」というイ メージとともに、ミームは「文化の単位」(アイデア、信念、行動パターンなど)と考えることもできる。コピー過程における変異と淘汰は、ミームプレックス 間のダーウィン進化を可能にし、したがって文化進化のメカニズムの候補となる。ミームは自分の成功にしか「関心がない」という意味で「利己的」であるた め、生物学的宿主の遺伝的利益と対立する可能性がある。その結果、殉教のミームを広めることには成功するが、宿主や多くの場合他の人々にとっては致命的 な、自殺テロのような進化したある種の文化的特徴を、「ミームの目」という見方で説明できるかもしれない。 進化論的認識論 主な記事 進化論的認識論 「進化論的認識論」とは、生物学的進化の概念を人間の知識の成長に適用し、知識の単位自体、特に科学的理論は淘汰に従って進化すると主張する理論を指すこ ともある。この場合、ある理論、例えば病気の細菌説は、それを取り巻く知識体系の変化に応じて、より信憑性が高くなったり低くなったりする。 進化論的認識論の特徴のひとつは、経験的検証だけでは科学理論の実用的価値は正当化されず、むしろ社会的・方法論的プロセスによって、与えられた問題に最 も「適合」する理論が選択されるという考え方である。ある理論が最も厳密な経験的テストに耐えたという事実だけで、その理論が将来のテストに耐えられるか どうかを確率論的に予測することはできない。カール・ポパーは、ニュートン物理学を例として、テストによって完全に確認され、難攻不落とされた理論が、ア ルベルト・アインシュタインの時空の本質に関する大胆な洞察によって改良されたことを挙げている。進化論的認識論者にとっては、経験的検証の程度にかかわ らず、すべての理論は暫定的にしか真実ではないのである。 ポパーは進化論的認識論に最初の包括的な治療を与えたと多くの人に考えられているが、ドナルド・T・キャンベルは1974年にこのフレーズを作った [21]。 二重継承理論 このセクションは二重継承説からの抜粋である[編集]。 二重継承理論(Dual inheritance theory: DIT)は、遺伝子-文化共進化または生物文化進化としても知られており[22]、人間の行動が遺伝的進化と文化的進化という2つの異なる相互作用する進 化の過程の産物であることを説明するために1960年代から1980年代初頭にかけて開発された。遺伝子の変化は文化の変化につながり、それが遺伝子の選 択に影響を与え、またその逆もしかりである。この理論の中心的な主張のひとつは、文化は部分的にはダーウィン的な淘汰過程を通じて進化するというものであ り、二重継承論者はしばしば遺伝子の進化との類似性によってそれを説明する[24]。 |
| Criticism and controversy [icon] This section needs expansion. You can help by adding to it. (September 2023) As a relatively new and growing scientific field, cultural evolution is undergoing much formative debate. Some of the prominent conversations are revolving around Universal Darwinism,[14][25] dual inheritance theory,[26] and memetics.[27][28][29][30] More recently, cultural evolution has drawn conversations from multi-disciplinary sources with movement towards a unified view between the natural and social sciences. There remains some accusation of biological reductionism, as opposed to cultural naturalism, and scientific efforts are often mistakenly associated with Social Darwinism. However, some useful parallels between biological and social evolution still appear to be found.[31] Researchers Alberto Acerbi and Alex Mesoudi's criticism of Cultural Evolution lies in the ambiguity surrounding the analogy between cultural and genetic evolution. They clarify the distinction between cultural selection (high-fidelity replication of traits) and cultural attraction (reconstruction of traits with lower fidelity). They argue that both mechanisms coexist in cultural evolution, making it essential to empirically determine their prevalence in different contexts, addressing confusion in the field.[32] Criticism of historic approaches to cultural evolution Cultural evolution has been criticized over the past two centuries that it has advanced its development into the form it holds today. Morgan's theory of evolution implies that all cultures follow the same basic pattern. Human culture is not linear, different cultures develop in different directions and at differing paces, and it is not satisfactory or productive to assume cultures develop in the same way.[33] A further key critique of cultural evolutionism is what is known as "armchair anthropology". The name results from the fact that many of the anthropologists advancing theories had not seen first hand the cultures they were studying. The research and data collected was carried out by explorers and missionaries as opposed to the anthropologists themselves. Edward Tylor was the epitome of that and did very little of his own research.[29][33] Cultural evolution is also criticized for being ethnocentric; cultures are still seen as attempting to emulate western civilization. Under ethnocentricity, primitive societies are said to not yet be at the cultural levels of other Western societies.[33][34] Much of the criticism aimed at cultural evolution is focused on the unilinear approach to social change. Broadly speaking in the second half of the 20th century the criticisms of cultural evolution have been answered by the multilinear theory. Ethnocentricity, for example, is more prevalent under the unilinear theory.[33][29][34] Some recent approaches, such as dual inheritance theory, make use of empirical methods including psychological and animal studies, field site research, and computational models.[35] |
批判と論争 [アイコン] このセクションは拡張が必要です。追加することで貢献できます。(2023年9月) 比較的新しく成長中の科学分野として、文化進化論は多くの形成的な議論を経ている。著名な議論のいくつかは、普遍的ダーウィニズム[14][25]、二重 継承理論[26]、ミメティックス[27][28][29][30]を中心に展開されている。 より最近では、文化進化論は、自然科学と社会科学の間の統一的な見解に向けた動きとともに、学際的な情報源から会話を引き寄せている。文化的自然主義とは 対照的に、生物学的還元主義に対する非難も残っており、科学的な取り組みはしばしば社会ダーウィニズムと誤って結び付けられる。しかし、生物学的進化と社 会的進化との間には、有益な類似点がまだいくつか見出されているようである[31]。 研究者であるアルベルト・アセルビとアレックス・メソウディの文化進化論に対する批判は、文化進化と遺伝進化の類似性をめぐる曖昧さにある。彼らは文化的 選択(形質の忠実度の高い複製)と文化的魅力(忠実度の低い形質の再構成)の区別を明確にしている。彼らは、文化的進化には両方のメカニズムが共存してお り、異なる文脈におけるそれらの有病率を実証的に決定することが不可欠であると主張し、この分野における混乱に対処している[32]。 文化進化に対する歴史的アプローチへの批判 文化進化論は過去2世紀にわたり、今日のような形に発展してきたという批判を受けてきた。モーガンの進化論は、すべての文化が同じ基本パターンに従うこと を暗示している。人間の文化は直線的ではなく、異なる文化は異なる方向や異なるペースで発展しており、文化が同じように発展すると仮定することは満足でき るものでも生産的なものでもない[33]。 文化進化論に対するさらに重要な批判は、「アームチェア人類学」として知られているものである。この名称は、理論を提唱している人類学者の多くが、彼らが 研究している文化を直接見たことがないという事実に起因している。調査やデータの収集は、人類学者自身とは対照的に、探検家や宣教師によって行われた。エ ドワード・タイラーはその典型であり、彼自身はほとんど調査を行っていない。民族中心主義のもとでは、原始社会はまだ他の西洋社会の文化レベルに達してい ないと言われている[33][34]。 文化進化に向けられた批判の多くは、社会変化に対する単線的なアプローチに焦点が当てられている。大まかに言えば、20世紀後半において、文化的進化に対 する批判は、マルチリニア理論によって回答されてきた。例えば、エスノセントリック(民族中心主義)は単線説のもとでより広まっている[33][29] [34]。 二重継承説のような最近のアプローチでは、心理学的研究や動物実験、現地調査、計算モデルなどの経験的手法が用いられている[35]。 |
| Behavioral ecology – Study of
the evolutionary basis for animal behavior due to ecological pressures Cliodynamics – Mathematical modeling of historical processes Cognitive ecology – Branch of ecology studying cognition in social and natural contexts Cultural group selection – Model of cultural evolution Cultural selection theory – Study of cultural change modelled on theories of evolutionary biology Dual inheritance theory – Theory of human behavior Environmental determinism – Theory that a society's development is predetermined by its physical environment Spatial ecology – Study of the distribution or space occupied by species |
|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_evolution |
|
| 社会文化的進化 |
アニミズム(animism)とは,19 世紀の文化進化主義者タイラー(E.B.Tylor)の用語であるが、彼は、宗教は自然崇拝から死者 崇拝や呪物崇拝(フェティシズム)を経て多神教になり、そして最後に一神教へ進化したと考えた。したがって、もっとも原始的な宗教の萌芽的状態における、 霊的存在への信仰をアニミズム——ラテン語の霊魂(anima)に由来——と命名した。ただし、タイラーによると、アニミズムの形態は高度の信仰の段階に なってもすぐに消失するのではなく、形を変えて生き残るといっている。今日、文化進化主義を支持する人類学者はほとんどいないので、日常世界のさまざまな 諸物に霊魂が宿っており、それを敬う信仰の形態を指して、緩やかな意味あいにおいてアニミズムと呼んでいる。
| 新しくアニミズムのページを作り直しました。こちらご覧ください。 |
|
ある社会がいくつかの集団に分かれ、各々 の集団とひとつないしは複数の動物や植物、ときには人工的なものや動物の一部などと特別な関連がある とする宗教形態がトーテミズム(totemism)とよばれる。
トーテミズムはスコットランドの法学者マ クレナン(J.F.Maclenan)が19世紀の中ごろに、進化主義の立場から結婚の原理を人類学 的に説明するための概念として、はじめて定式化した。彼は内婚・外婚の用語をつくった人としても知られるが、トーテミズムは外婚制(エクソガミー, exogamy)——結婚対象を特定集団以外から求める規則——に深く関係すると主張する。マクレナンによると、自分が崇拝している同じトーテムを崇拝す る人間は、同じ集団の人間であり、そこから結婚の相手を選ぶことができない。このような特定の事物であるトーテム崇拝——事物にこだわるから、それはフェ ティシズム(呪物崇拝)とよばれる——が、社会のなかに登場したことで、それまで人びとが、結婚相手を特定の集団から選ぶ規則すなわち内婚(エンドガ ミー,endogamy)からとき放たれて、より進んだ制度である外婚制へと発達したと考えたのである。トーテミズムは、婚姻を媒介としてより開かれた社 会を形成するルールであると同時に、もっとも原始的な宗教なのであった。社会のあり方を規定する「婚姻制度」と彼らの観念を規定する「宗教形態」の関係を 統一的に理解できる、このマクレナンの説は、19世紀後半の臨床心理学(S・フロイト)、社会学(E・デュルケーム)、民族学(J・フレーザー)に多大な 影響を与えた。
マクレナンの主張はなるほど理路整然とし ているが、その最初の前提となっている社会がそのように「進化」したという確固とした証拠はないため に、現代の文化人類学では、もうそれを支持する者はいない。
| Totemism
is a belief about the relationship between people and nature. The term
totem comes from an Ojibwe word meaning “a relative of mine”. It was
first written about in 1791 by a trader, James Long. It has been
recorded across native tribes of America, Africa and Australia. It has
been the subject of much research into ethnic groups. Usually, totems
of a kinship group will be animals or plants. They will be represented
in sacred objects and will belong exclusively to them. |
トーテミズムとは、人と自然の関係についての信仰である。
トーテムという言葉は、オジブエ語で「私の親戚」を意味する言葉に由来する。1791年、貿易商のジェームス・ロングによって初めて書かれた。トーテム
は、アメリカ、アフリカ、オーストラリアの先住民族全体で記録されている。民族グループに関する多くの研究の対象となっている。通常、親族グループのトー
テムは動物や植物である。それらは神聖なものに表され、彼らだけのものとなる。 |
| Early records Totemism was considered a primitive religion by many European thinkers in the 1800s. It was thought to be related to beliefs about food and incest taboos. In 1869, John Ferguson McLennan said that "there is no race of men that has not come through this primitive stage of speculative belief". Early thinkers had the idea that beliefs in totemism came from indiginous clans being uneducated about the difference between humans and animals. This is not still talked about as true in modern discussions on totemism. |
初期の記録 トーテミズムは、1800年代のヨーロッパの多くの思想家から原始宗教とみなされていた。それは食べ物や近親相姦のタブーに関する信仰と関係があると考え られていた。1869年、ジョン・ファーガソン・マクレナンは「思弁的な信仰のこの原始的な段階を経ていない人種はいない」と述べた。初期の思想家たち は、トーテミズムの信仰は、原住民の氏族が人間と動物の違いについて教育を受けていないことに由来するという考えを持っていた。これはトーテミズムに関す る現代の議論では、今でも真実として語られることはない。 |
| Totem poles Totem poles are carved with symbols on large trees, mostly cedar or spruce, by native northwest North American clans. Totem poles are also found in Alaska. They are not for worship, but early missionaries had them burned down. This was a mistake because the poles just tell stories about the clan they belong to. Eagles or ravens are carved at the highest level. Lower down the pole are carved beavers, foxes, bears and frogs. A carving of a person is located on top. He is the watchman, who warns about approaching danger in the village.[1] |
トーテムポール トーテムポールは、北米北西部の先住民族が、主にスギやトウヒなどの大木にシンボルを刻んだもの。トーテムポールはアラスカにもある。トーテムポールは崇 拝するためのものではないが、初期の宣教師たちはこれを焼き払った。トーテムポールは、その一族の物語を伝えるものだからだ。最も高い位置にはワシやカラ スが彫られている。ポールの下の方には、ビーバー、キツネ、クマ、カエルが彫られている。一番上には人の彫刻がある。彼は村に危険が近づいていることを警 告する番人である[1]。 |
| History of totemic theory Émile Durkheim said in 1915 that totemism was just a way of thinking about groups in society. Durkheim decided this because he spent time working with Aboriginal Australian clans. Each clan had its own totem, which could be any natural feature such as animals, plants or rivers. These totems and symbols of them were worshiped and protected. This was because only as long as the totem was healthy would the clan stay healthy. Durkheim decided that the worship of the totems was a type of self-worship for the clan. Claude Lévi-Strauss published Totemism in 1962. In this book he says that totemism is a way that humans tend to classify people into similar groups. Once a population has made rules like exogamy (marrying outside the group) it becomes important to keep the clan different from others. But humans themselves do not have different features like wolves or birds do, so giving the identity of an animal to the clan makes its member distinctly different. This makes social boundaries. |
トーテミズム理論の歴史 エミール・デュルケームは1915年、トーテミズムは社会における集団についての考え方に過ぎないと述べた。デュルケムがこのように考えたのは、オースト ラリアのアボリジニの氏族との共同作業に時間を費やしたからである。それぞれの氏族にはトーテムがあり、それは動物、植物、川など自然のものであれば何で もよかった。これらのトーテムやそのシンボルは崇拝され、保護されていた。トーテムが健康である限り、氏族は健康でいられるからである。デュルケムは、 トーテムの崇拝は一族の自己崇拝の一種であると考えた。 クロード・レヴィ=ストロースは1962年に『トーテミズム』を出版した。この本の中で彼は、トーテミズムとは人間が人々を同じようなグループに分類する 傾向のある方法だと述べている。集団が一度、外婚(集団の外で結婚すること)のようなルールを作ると、一族を他と異なるものに保つことが重要になる。しか し人間自身はオオカミや鳥のように異なる特徴を持っているわけではないので、動物のアイデンティティを氏族に与えることで、そのメンバーは明らかに異なる 存在となる。これが社会的な境界を作る。 |
| https://simple.wikipedia.org/wiki/Totemism |
アニミズム、トーテミズムの議論につづい て注目されたのはマナ(mana) である(11)。マナは、もともと1891年にコドリントン (R.H.Codrington)により紹介されたメラネシアの宗教概念を理解するための用語であったが、その後「原始的な宗教」を説明するために頻繁に 使われるようになり、広く普及した。マナは、ひとことで言えば、一種の超自然的力であり、何に対しても伝播することができ、その効力をあらわすものであ る。モースによれば、マナは、事物が有するある種の資質であり、人間や事物に宿ることのできる実体であり、またそれがもつ力(=作用)としてさまざまな形 であらわれるという。一般化されたイメージとしての「マナ」は、現代日本のマスメディアなどでよく使われる「パワー」と似たものだと考えればよい。その 「パワー」が人間のみならず、事物(もの自体)にも宿り、また事物から人間にその「パワー」が伝わる。マナはそのようなものである。
では、なぜメラネシア起源の特殊なある概 念が、広く議論されるようになったのだろうか。それはトーテミズムと同様、19世紀から20世紀の初 頭にかけては、宗教というものがどのような呪術から生まれてきたのかという議論が盛んだったからである。トーテミズム、アニミズムと同様、マナも宗教の原 初形態の一種とみなされ、どの信仰のタイプがいちばん古いかという論争があった。例えば、アニミズムを宗教の起源とするタイラーに対して、人類学者マレッ トはマナをアニミズムに先行する形態、すなわちプレアニミズムのなかに、このマナへの信仰があると主張した。だが、先にも述べたように、歴史的により古い 形態の証明は決着がつかず、同時代を生きていた「未開社会」の信仰を歴史的に古いものだとする科学的証拠は存在しないので、この議論は文化人類学内部にお いてはやがて下火になった。
| In Melanesian and
Polynesian cultures, mana
is
a supernatural force that permeates the universe.[1] Anyone or anything
can have mana. They believed it to be a cultivation or possession of
energy and power, rather than being a source of power.[1] It is an
intentional force.[1] Mana has been discussed mostly in relation to cultures of Polynesia, but also of Melanesia, notably the Solomon Islands[2][3] and Vanuatu.[4][5][6][7][8] In the 19th century, scholars compared mana to similar concepts such as the orenda of the Iroquois Indians and theorized that mana was a universal phenomenon that explained the origin of religions.[1] Etymology The reconstructed Proto-Oceanic word *mana is thought to have referred to "powerful forces of nature such as thunder and storm winds" rather than supernatural power.[9] As the Oceanic-speaking peoples spread eastward, the word started to refer instead to unseen supernatural powers.[9] |
メラネシアやポリネシアの文化では、マナは宇宙に浸透している超自然的
な力である[1]。彼らはマナを力の源というよりも、エネルギーや力の育成や所有であると信じていた[1]。 マナは主にポリネシアの文化に関連して論じられてきたが、メラネシア、特にソロモン諸島[2][3]やバヌアツでも論じられている[4][5][6] [7][8]。 19世紀、学者たちはマナをイロコイ・インディアンのオレンダなどの類似した概念と比較し、マナは宗教の起源を説明する普遍的な現象であると理論化した [1]。 語源 復元された原オセアニア語の*manaは、超自然的な力ではなく、「雷や暴風などの強力な自然の力」を指していたと考えられている[9]。オセアニア語を 話す民族が東に広がるにつれて、この単語は代わりに目に見えない超自然的な力を指すようになった[9]。 |
| Polynesian culture Mana is a foundation of Polynesian theology, a spiritual quality with a supernatural origin and a sacred, impersonal force. To have mana implies influence, authority, and efficacy: the ability to perform in a given situation. The quality of mana is not limited to individuals; peoples, governments, places and inanimate objects may also possess mana, and its possessors are accorded respect. Mana protects its protector and they depend on each other for growth both positive and negative. It depends on the person where he takes his mana.[citation needed] In Polynesia, mana was traditionally seen as a "transcendent power that blesses" that can "express itself directly" through various ways, but most often shows itself through the speech, movement, or traditional ritual of a "prophet, priest, or king."[10] Hawaiian and Tahitian culture In Hawaiian and Tahitian culture, mana is a spiritual energy and healing power which can exist in places, objects and persons. Hawaiians believe that mana may be gained or lost by actions, and Hawaiians and Tahitians believe that mana is both external and internal. Sites on the Hawaiian Islands and in French Polynesia are believed to possess mana—for example, the top rim of the Haleakalā volcano on the island of Maui and the Taputapuatea marae on the island of Raiatea in the Society Islands.[citation needed] Ancient Hawaiians also believed that the island of Molokaʻi possessed mana, compared with its neighboring islands. Before the unification of the Kingdom of Hawaii by King Kamehameha I, battles were fought for possession of the island and its south-shore fish ponds which existed until the late 19th century.[citation needed] A person may gain mana by pono (right actions). In ancient Hawaii, there were two paths to mana: sexual means or violence. In at least this tradition, nature is seen as dualistic, and everything has a counterpart. A balance between the gods Kū and Lono formed, through whom are the two paths to mana (ʻimihaku, or the search for mana). Kū, the god of war and politics, offers mana through violence; this was how Kamehameha gained his mana. Lono, the god of peace and fertility, offers mana through sexuality.[citation needed] Prayers were believed to have mana, which was sent to the akua at the end when the priest usually said "amama ua noa," meaning "the prayer is now free or flown."[11] Māori (New Zealand) culture Māori use In Māori culture, there are two essential aspects of a person's mana: mana tangata, authority derived from whakapapa (genealogy) and mana huaanga, defined as "authority derived from having a wealth of resources to gift to others to bind them into reciprocal obligations".[12] Hemopereki Simon, from Ngāti Tūwharetoa, asserts that there are many forms of mana in Maori beliefs.[13] The indigenous word reflects a non-Western view of reality, complicating translation.[14] This is confirmed by the definition of mana provided by Māori Marsden who states that mana is: Spiritual power and authority as opposed to the purely psychic and natural force — ihi.[15] According to Margaret Mutu, mana in its traditional sense means: Power, authority, ownership, status, influence, dignity, respect derived from the atua.[16][13] In terms of leadership, Ngāti Kahungunu legal scholar Carwyn Jones comments: "Mana is the central concept that underlies Māori leadership and accountability." He also considers mana as a fundamental aspect of the constitutional traditions of Māori society.[17] According to the New Zealand Ministry of Justice: Mana and tapu are concepts which have both been attributed single-worded definitions by contemporary writers. As concepts, especially Maori concepts they can not easily be translated into a single English definition. Both mana and tapu take on a whole range of related meanings depending on their association and the context in which they are being used.[18] A tribe with mana whenua must have demonstrated their authority over a territory. General English usage In contemporary New Zealand English, the word "mana" refers to a person or organisation of people of great personal prestige and character.[19] The increased use of the term mana in New Zealand society is the result of the politicisation of Māori issues stemming from the Māori Renaissance.[citation needed] |
ポリネシア文化 マナはポリネシア神学の根幹をなすもので、超自然的な起源を持つ霊的な性質であり、神聖で非人間的な力である。マナを持つということは、影響力、権威、効 力、つまり与えられた状況において実行する能力を意味する。マナの性質は個人に限定されるものではなく、民族、政府、場所、無生物もマナを持つことがあ り、マナを持つ者は尊敬される。マナはその保護者を守り、プラスとマイナスの両方の成長のために互いに依存し合う。マナをどこに持っていくかはその人次第 である[要出典]。 ポリネシアでは、マナは伝統的に「祝福する超越的な力」と見なされており、それは様々な方法を通じて「それ自身を直接表現する」ことができるが、最も多く の場合、「預言者、司祭、王」の話し方、動き、または伝統的な儀式を通じてそれ自身を示す[10]。 ハワイとタヒチの文化 ハワイとタヒチの文化では、マナは霊的なエネルギーであり、場所や物、人の中に存在する癒しの力である。ハワイ人は、マナは行動によって得たり失ったりす ると信じており、ハワイ人とタヒチ人は、マナは外的なものと内的なものの両方があると信じている。例えば、マウイ島のハレアカラ火山の頂上や、ソサエティ 諸島のライアテア島のタプタプアテア・マラエなどである[要出典]。 古代ハワイアンはまた、モロカイ島は近隣の島々に比べてマナがあると信じていました。カメハメハ大王がハワイ王国を統一する前は、島と南岸の養魚池の所有 権をめぐって戦いが繰り広げられ、19世紀後半まで存在した[要出典]。 人はポノ(正しい行い)によってマナを得ることができる。古代ハワイでは、マナを得るには性的手段と暴力の2つの道があった。少なくともこの伝統では、自 然は二元論的なものと見なされ、すべてのものには対応するものがある。クーとロノという神々の間で均衡が生まれ、彼らを通してマナへの2つの道(イミハ ク、またはマナの探求)が存在する。戦争と政治の神であるクーは、暴力によってマナを提供し、カメハメハはこうしてマナを得た。平和と豊穣の神であるロノ は、性愛を通してマナを提供する。[要出典]祈りにはマナがあると信じられており、そのマナは、司祭が通常「アママ・ウア・ノア」、つまり「祈りは今、自 由である、あるいは飛翔している」と言うときに、最後にアクアに送られる[11]。 マオリ(ニュージーランド)の文化 マオリの使用 マオリ文化では、人のマナには2つの本質的な側面がある。マナ・タンガタとは、ワカパパ(系譜)に由来する権威であり、マナ・フアンガとは、「互恵的な義 務を負わせるために他者に贈る豊かな資源を持つことに由来する権威」と定義される。 [12]トゥワレトア先住民のヘモペレキ・サイモンは、マオリの信仰には様々な形のマナが存在すると主張している[13]。この先住民の言葉は非西洋的な 現実観を反映しており、翻訳を複雑にしている[14]: 純粋に精神的で自然な力であるイヒとは対照的に、霊的な力と権威である[15]。 マーガレット・ムトゥによれば、伝統的な意味でのマナとは次のようなものである: 権力、権威、所有権、地位、影響力、威厳、アトゥアに由来する尊敬[16][13]。 リーダーシップに関して、ンガティ・カフングヌの法学者であるカーウィン・ジョーンズは次のようにコメントしている: 「マナはマオリのリーダーシップと説明責任を支える中心的な概念である。また、マナはマオリ社会の憲法上の伝統の基本的な側面であるとも考えている [17]。 ニュージーランド法務省によると マナ(Mana)とタプ(Tapu)は、現代の作家によって一言で定義されている概念である。概念として、特にマオリ族の概念として、単一の英語の定義に 簡単に翻訳することはできません。マナもタプも、その関連性や使用される文脈によって、様々な意味を持つのである[18]。 マナウィヌアを持つ部族は、領土に対する権威を示さなければならない。 一般的な英語の用法 現代のニュージーランド英語では、"mana "という単語は、個人的な威信と人格を持つ人または組織を指す[19]。 |
| Academic study Photo of a three-masted schooner  The 1891 Southern Cross, one of the ships at Norfolk Island's Melanesian Mission where Codrington taught and worked  Missionary Robert Henry Codrington traveled widely in Melanesia, publishing several studies of its language and culture. His 1891 book The Melanesians: Studies in their Anthropology and Folk-Lore contains the first detailed description of mana in English.[9] Codrington defines it as "a force altogether distinct from physical power, which acts in all kinds of ways for good and evil, and which it is of the greatest advantage to possess or control".[4] Pre-animism Describing pre-animism, Robert Ranulph Marett cited the Melanesian mana (primarily with Codrington's work): "When the science of Comparative Religion employs a native expression such as mana, it is obliged to disregard to some extent its original or local meaning. Science, then, may adopt mana as a general category ... ".[20]: 99 In Melanesia the animae are the souls of living men, the ghosts of deceased men, and spirits "of ghost-like appearance" or imitating living people. Spirits can inhabit other objects, such as animals or stones.[20]: 115–120 The most significant property of mana is that it is distinct from, and exists independently of, its source. Animae act only through mana. It is impersonal, undistinguished, and (like energy) transmissible between objects, which can have more or less of it. Mana is perceptible, appearing as a "Power of awfulness" (in the sense of awe or wonder).[20]: 12–13 Objects possessing it impress an observer with "respect, veneration, propitiation, service" emanating from the mana's power. Marett lists a number of objects habitually possessing mana: "startling manifestations of nature", "curious stones", animals, "human remains", blood,[20]: 2 thunderstorms, eclipses, eruptions, glaciers, and the sound of a bullroarer.[20]: 14–17 If mana is a distinct power, it may be treated distinctly. Marett distinguishes spells, which treat mana quasi-objectively, and prayers (which address the anima). An anima may have departed, leaving mana in the form of a spell which can be addressed by magic. Although Marett postulates an earlier pre-animistic phase, a "rudimentary religion" or "magico-religious" phase in which the mana figures without animae, "no island of pure 'pre-animism' is to be found."[20]: xxvi Like Tylor, he theorizes a thread of commonality between animism and pre-animism identified with the supernatural—the "mysterious", as opposed to the reasonable.[20]: 22 Durkheim's totemism In 1912, French sociologist Émile Durkheim examined totemism, the religion of the Aboriginal Australians, from a sociological and theological point of view, describing collective effervescence as originating in the idea of the totemic principle or Mana.[citation needed] Criticism In 1936, Ian Hogbin criticised the universality of Marett's pre-animism: "Mana is by no means universal and, consequently, to adopt it as a basis on which to build up a general theory of primitive religion is not only erroneous but indeed fallacious".[21] However, Marett intended the concept as an abstraction.[20]: 99 Spells, for example, may be found "from Central Australia to Scotland."[20]: 55 Early 20th-century scholars also saw mana as a universal concept, found in all human cultures and expressing fundamental human awareness of a sacred life energy. In his 1904 essay, "Outline of a General Theory of Magic", Marcel Mauss drew on the writings of Codrington and others to paint a picture of mana as "power par excellence, the genuine effectiveness of things which corroborates their practical actions without annihilating them".[22]: 111 Mauss pointed out the similarity of mana to the Iroquois orenda and the Algonquian manitou, convinced of the "universality of the institution";[22]: 116 "a concept, encompassing the idea of magical power, was once found everywhere".[22]: 117 Mauss and his collaborator, Henri Hubert, were criticised for this position when their 1904 Outline of a General Theory of Magic was published. "No one questioned the existence of the notion of mana", wrote Mauss's biographer Marcel Fournier, "but Hubert and Mauss were criticized for giving it a universal dimension".[23] Criticism of mana as an archetype of life energy increased. According to Mircea Eliade, the idea of mana is not universal; in places where it is believed, not everyone has it, and "even among the varying formulae (mana, wakan, orenda, etc.) there are, if not glaring differences, certainly nuances not sufficiently observed in the early studies".[24] "With regard to these theories founded upon the primordial and universal character of mana, we must say without delay that they have been invalidated by later research".[25] Holbraad[26] argued in a paper included in the volume "Thinking Through Things: Theorising Artefacts Ethnographically" that the concept of mana highlights a significant theoretical assumption in anthropology: that matter and meaning are separate. A hotly debated issue, Holbraad suggests that mana provides motive to re-evaluate the division assumed between matter and meaning in social research. His work is part of the ontological turn in anthropology, a paradigm shift that aims to take seriously the ontology of other cultures.[27] |
学術研究 3本マストのスクーナー船  コドリントンが教鞭を執ったノーフォーク島メラネシア伝道所の船のひとつ、1891年サザンクロス号  宣教師ロバート・ヘンリー・コドリントンは、メラネシアを広く旅し、その言語と文化についていくつかの研究を発表した。彼の1891年の著書『The Melanesians: Studies in their Anthropology and Folk-Lore (メラネシア人の人類学と民間伝承の研究)』には、英語によるマナに関する最初の詳細な記述が含まれている[9]。コドリントンはマナを「物理的な力とは まったく異なる力であり、善と悪のためにあらゆる方法で作用し、それを所有または制御することが最大の利点である」と定義している[4]。 プレアニミズム ロバート・ラヌルフ・マレットはアニミズム以前について、メラネシアのマナを引き合いに出した(主にコドリントンの研究による): 「比較宗教学がマナのような土着の表現を用いる場合、その本来の意味や土地の意味をある程度無視せざるを得ない。そして科学は、マナを一般的なカテゴリー として採用することができる。「20]: 99 メラネシアでは、アニマエは生きている人間の魂、亡くなった人間の幽霊、「幽霊のような外見をした」、あるいは生きている人間を模した霊である。霊は動物 や石など他の物体に宿ることもある[20]: 115-120 マナの最も重要な性質は、マナがその源から区別され、独立して存在することである。アニマはマナを通してのみ作用する。マナは非人間的で区別がなく、(エ ネルギーと同様に)対象物の間で伝達可能であり、対象物はマナを多く持つことも少なく持つこともできる。マナは知覚可能であり、(畏怖や驚嘆という意味 で)「畏怖の力」として現れる[20]: 12-13 マナを持つ物体は、マナの力から発せられる「尊敬、崇敬、鎮魂、奉仕」を観察者に印象づける。マレットは習慣的にマナを持つ対象として、「驚くべき自然の 現れ」、「不思議な石」、動物、「人間の遺体」、血液、[20]: 2 雷雨、日食、噴火、氷河、牛の鳴き声などを挙げている[20]: 14-17 マナが別個の力であるならば、それは別個に扱われるかもしれない。マレットは、マナを準客観的に扱う呪文と、(アニマに働きかける)祈りを区別している。 アニマは呪文という形でマナを残し、魔法で対処できるようになった。マレットはアニマ以前の段階、すなわちマナがアニマなしで登場する「初歩的宗教」ある いは「魔術的宗教」段階を仮定しているが、「純粋な『前アニミズム』の島は発見されていない」[20]: xxvi。タイロールと同様に、彼はアニミズムと前アニミズムの間に、超自然的なもの、つまり合理的なものとは対照的な「神秘的なもの」と同定される共通 性の糸を理論化している[20]: 22。 デュルケムのトーテミズム 1912年、フランスの社会学者エミール・デュルケームは、オーストラリアのアボリジニの宗教であるトーテミズムを社会学的・神学的観点から考察し、集団 の発揚はトーテム原理またはマナの思想に由来すると述べた[要出典]。 批判 1936年、イアン・ホグビンはマレットのプレアニミズムの普遍性を批判した:「マナは決して普遍的なものではなく、その結果、原始宗教の一般的な理論を 構築するための基礎としてそれを採用することは誤りであるだけでなく、実に誤りである」[21] しかしながら、マレットはこの概念を抽象的なものとして意図していた[20]: 55 20世紀初頭の学者たちもまた、マナを普遍的な概念とみなし、あらゆる人類の文化に見られ、神聖な生命エネルギーに対する人間の根源的な意識を表現してい ると考えた。マルセル・モースは1904年に発表したエッセイ「魔術の一般理論の概要」の中で、コドリントンらの著作を引用し、マナとは「卓越した力、物 事を消滅させることなく、その実際的な作用を裏付ける、物事の真の有効性」であるとした[22]: 111 モースはマナがイロコイ族のオレンダやアルゴンキン族のマニトゥーに類似していることを指摘し、「制度の普遍性」を確信した[22]: 116 「魔術的な力という概念を包含する概念は、かつてあらゆる場所で見出された」[22]: 117 モースと彼の共同研究者であるアンリ・ユベールは、1904年に『魔術の一般理論概論』が出版されたとき、この立場から批判を受けた。「マナの概念の存在 に疑問を抱く者はいなかったが、ユベールとモースはマナに普遍的な次元を与えたとして批判された」とモースの伝記作家マルセル・フルニエは書いている。ミ ルチェア・エリアーデによれば、マナの観念は普遍的なものではなく、マナが信じられている場所において、すべての人がマナを持っているわけではなく、「様 々な公式(マナ、ワカン、オレンダなど)の中にさえ、顕著な違いはないにせよ、初期の研究では十分に観察されなかったニュアンスが確かに存在する」 [24]。 ホルブラード[26]は「Thinking Through Things: Theorising Artefacts Ethnographically(人工物を民族誌的に理論化する)"に収録されている論文で、マナの概念は人類学における重要な理論的前提を浮き彫りに していると論じている。ホルブラードは、マナは社会調査において物質と意味の間に想定される区分を再評価する動機になると示唆している。彼の研究は、人類 学における存在論的転回、つまり他文化の存在論を真剣に受け止めることを目指すパラダイム・シフトの一環である[27]。 |
| Aṣẹ Barakah Chakra Charm The Force Guṇa Kami in Shinto Manitou Melanesian mythology Mysticism Occult Philippine shamans or Babaylan Prana Qi or Chi Quintessence or Aether Ritual Scientific skepticism Taboo Talisman Väki Wind Horse Yorishiro in Shinto |
|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Mana_(Oceanian_cultures) |
リンク
文献
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

Source: La Abeja Medica, Barcelona
++
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆