Maurice
Merleau-Ponty, 1908-1961

モーリス・メルロ=ポンティ
Maurice
Merleau-Ponty, 1908-1961

モーリス・ジャン・ジャック・メルロ=ポ ンティ[16](1908年3月14日 - 1961年5月3日)はフランスの現象学の哲学者で、エドマンド・フッサールやマルティン・ハイデガーから強い影響を受けた。人間の経験における意味の構 成に主な関心を寄せ、知覚、芸術、政治、宗教、生物学、心理学、精神分析、言語、自然、歴史について執筆した。1945年にジャン=ポール・サルトル、シ モーヌ・ド・ボーヴォワールとともに創刊した左翼雑誌『レ・タン・モダン』の主幹編集長を務めた。。科学哲学者ジャック・メルロ=ポンティの従兄弟にあた る。
1908 3月14日にロシュフォール・ シュル・メールで生まれる
1930 哲学のアグレガシオン取得
1931 ボーヴェ校(1931- 1933年)
1934 シャルトル校(1934- 1935年)
1935 パリ高等師範学校(1935- 1939年)
1939 歩兵第5連隊およ び第59軽歩兵師団(1939-1940年)
1940 リセ・カルノ校(1940- 1944年)
1942 La Structure
du comportement (1942)
1944 リセ・コンドルセ校(1944 -1945年)
1945 1945年、ソルボンヌ大学で La Structure du comportement (1942)とPhénoménologie de la perception (1945)により文学博士号を取得
1945 リヨン大学文学部哲学科講師、 1945年10月の雑誌『レ・タン・モダン』の創刊
1948 1月リヨン大学心理学の正教授
1949 パリ大学文学部教育心理学講師
1950 パリ大学無任所教授
1952 アンリ・ベルクソン、エドゥ アール・ルロワ、ルイ・ラヴェル2 が務めていたコレージュ・ド・フランスの哲学講座を受け持つ。12月とサルトルと絶縁。
1953 1月23日に行われた就任講演 「哲学を讃えて」
1958 1958年の立法選挙のために 設立された反ガウリスト、非共産主義左派を結集するカルテル「UFD(Union des forces démocratiques)」の全国事務局の一部を構成
1963 5月3日夜、53歳の若さで心
不全のため、デカルトの『ディオプトリク』を開いたままの机の前で亡くなった
| Maurice
Merleau-Ponty, né le 14 mars 1908 à Rochefort-sur-Mer, mort le 3
mai
1961 à Paris dans le 6e arrondissement1, est un philosophe français. Il
est le cousin du philosophe des sciences Jacques Merleau-Ponty. |
モーリス・メルロ=ポンティは1908年3月14日にロシュフォール・
シュル・メールで生まれ、1961年5月3日にパリ6区で没した1。科学哲学者ジャック・メルロ=ポンティの従兄弟にあたる。 |
| Biographie Famille et jeunesse Maurice Merleau-Ponty est né à Rochefort-sur-Mer en mars 19082,3. Son père, Bernard Jean Merleau-Ponty, capitaine d'artillerie coloniale bordelais4, meurt, en 1913, alors qu'il n'a que cinq ans5. Dans ses études, il se lie d'amitié pour Simone de Beauvoir et d'amour pour Élisabeth Lacoin, à qui il passe une bague au doigt quelques jours avant sa mort6. Élevé dans le catholicisme romain, il est ami avec l'auteur et philosophe existentialiste chrétien Gabriel Marcel, écrit des articles pour la revue chrétienne de gauche Esprit, mais quitte l'Église catholique en 1937. Au printemps 1939, il est le premier visiteur étranger des Archives Husserl, rencontre Eugen Fink et le Père Herman Léo Van Breda. À l'été 1939, alors que la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie, il sert en première ligne dans l'armée française, où il est blessé au combat en juin 1940. Sollicité par le résistant Pierre Grappin, un ami de Vladimir Jankélévitch qui le loge gracieusement, quai aux Fleurs, sous l'occupation allemande, il décline la proposition7 puis de retour à Paris à l'automne 1940, épouse Suzanne Jolibois8, psychanalyste lacanienne, décédée en 2010, à 96 ans. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise à Paris avec elle, sa mère Louise née Barthé et leur fille Marianne (1941-2019), épouse de Michel Butel. |
バイオグラフィー 家族と少年時代 モーリス・メルロ=ポンティは1908年3月、ロシュフォール・シュル・メールに生まれた3。父ベルナール・ジャン・メルロ=ポンティはボルドー出身の 植民地砲兵大尉であったが4、1913年、彼がわずか5歳の時に亡くなった5。在学中、シモーヌ・ド・ボーヴォワールと親交を深め、エリザベート・ラコワ ンと恋に落ち、彼女が亡くなる数日前に指輪をはめた6。 ローマ・カトリック教徒として育ち、キリスト教実存主義の作家で哲学者のガブリエル・マルセルと親しくなり、左翼キリスト教雑誌『エスプリ』に記事を書い たが、1937年にカトリック教会を離れた。1939年春、彼はフッサール文書館を訪れた最初の外国人訪問者となり、オイゲン・フィンクやヘルマン・レ オ・ヴァン・ブレダ神父に会った。1939年夏、フランスがナチス・ドイツに宣戦布告すると、彼はフランス軍の最前線に従軍し、1940年6月に戦闘で負 傷した。 1940年秋にパリに戻ると、ラカン派の精神分析家で2010年に96歳で亡くなったシュザンヌ・ジョリボワ8と結婚した。彼は彼女、母ルイーズ・旧姓バ ルテ、ミシェル・ビュテルの妻である娘マリアンヌ(1941-2019)とともにパリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬されている。 |
L'enseignant Tombe de Maurice Merleau-Ponty au cimetière du Père-Lachaise (division 52). Après des études secondaires terminées au lycée Louis-le-Grand à Paris, Maurice Merleau-Ponty devient élève de l'École normale supérieure de Paris, à la même époque que Jean-Paul Sartre (avec lequel il entretient des relations d'amitié), et est reçu deuxième à l'agrégation de philosophie en 1930. D’abord professeur à Beauvais (1931-1933), puis au lycée Marceau à Chartres (1934-1935), ensuite répétiteur («caïman») à l’École normale supérieure de Paris (1935-1939) et mobilisé au 5e régiment d'infanterie et à l’état-major de la 59e division légère d’infanterie (1939-1940), il enseigne aussi au lycée Carnot (1940-1944) et en première supérieure au lycée Condorcet (1944-1945). Enfin, il obtient un doctorat en lettres en 1945 avec La Structure du comportement (1942) et la Phénoménologie de la perception (1945) à la Sorbonne. Il est ensuite nommé maître de conférences de philosophie à la faculté des lettres de l'université de Lyon (1945), puis professeur titulaire de la chaire de psychologie (janvier 1948). À la rentrée 1949, il est nommé maître de conférences de psychologie pédagogique, à la faculté des lettres de l'université de Paris et obtient le titre de professeur sans chaire, en janvier 1950. Enfin, il devient titulaire à partir de 1952, jusqu'à sa mort en 1961 de la chaire de philosophie du Collège de France qu'avaient illustrée avant lui Henri Bergson, Édouard Le Roy ou Louis Lavelle2. Sa conférence inaugurale, le 23 janvier 1953 s'intitule « Éloge de la philosophie », et attire un public jeune, qui le connaît comme existentialiste2. Merleau-Ponty fut aussi membre du comité directeur de la revue Les Temps modernes en tant qu'éditorialiste politique, de la fondation de la revue en octobre 1945 jusqu'en décembre 1952, soit à l'époque de la rupture de son amitié avec Jean-Paul Sartre (la « rupture » eut lieu en juillet 1953)9. Merleau-Ponty s'engage aussi politiquement, faisant ainsi partie du bureau national du cartel de l'Union des forces démocratiques (UFD), mis sur pieds pour les élections législatives de 1958 et qui rassemblait la gauche non communiste et anti-gaulliste. À l'âge de cinquante-trois ans, il meurt d'un arrêt cardiaque le soir du 3 mai 19612, assis à son bureau, où la Dioptrique de Descartes était encore ouverte10. « Il laisse une œuvre considérable, inachevée, et singulièrement un livre auquel il travaillait et qui devait constituer son chef-d'œuvre : Le visible et l'invisible »11. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (52e division). Claude Lefort est l'exécuteur testamentaire de son œuvre12. |
教師 ペール・ラシェーズ墓地にあるモーリス・メルロ=ポンティの墓(52区画)。 モーリス・メルロ=ポンティは、パリのリセ・ルイ・ル・グランで中等教育を受けた後、パリの高等師範学校(École normale supérieure)でジャン=ポール・サルトル(サルトルとは親交があった)と同時期に学び、1930年に哲学のアグレガシオン (agrégation)で2位になった。 ボーヴェ校(1931-1933年)、シャルトル校(1934-1935年)、パリ高等師範学校(1935-1939年)で教鞭をとり、歩兵第5連隊およ び第59軽歩兵師団(1939-1940年)に動員された。 また、リセ・カルノ校(1940-1944年)、リセ・コンドルセ校(1944-1945年)で教鞭をとった。1945年、ソルボンヌ大学でLa Structure du comportement (1942)とPhénoménologie de la perception (1945)により文学博士号を取得。 その後、リヨン大学文学部哲学科講師に任命され(1945年)、心理学の正教授となる(1948年1月)。1949年、パリ大学文学部教育心理学講師とな り、1950年1月に無任所教授となる。1952年から1961年に亡くなるまで、それまでアンリ・ベルクソン、エドゥアール・ルロワ、ルイ・ラヴェル2 が務めていたコレージュ・ド・フランスの哲学講座を受け持った。1953年1月23日に行われた就任講演は、「哲学を讃えて」と題され、実存主義者として 彼を知る若い聴衆を魅了した2。 メルロ=ポンティはまた、1945年10月の雑誌『レ・タン・モダン』の創刊から1952年12月にジャン=ポール・サルトルとの友情を断ち切るまで (「決裂」は1953年7月に起こった)、政治コラムニストとして雑誌『レ・タン・モダン』の役員を務めていた9。 メルロ=ポンティは政治活動にも積極的で、1958年の立法選挙のために設立された反ガウリスト、非共産主義左派を結集するカルテル「UFD(Union des forces démocratiques)」の全国事務局の一部を構成していた。 1963年5月3日夜、53歳の若さで心不全のため、デカルトの『ディオプトリク』を開いたままの机の前で亡くなった10。「デカルトはかなりの未完の仕 事を残し、特に代表作となるはずだった本を書き上げた: 目に見えるものと見えないもの』11である。彼はペール・ラシェーズ墓地(第52師団)に埋葬されている。 クロード・ルフォールが遺言執行人である12。 |
| La rupture avec Sartre À l'époque de la guerre de Corée, Sartre s'était permis de publier son article « Les Communistes et la paix » (1952) sans prévenir quiconque à la revue des Temps modernes. Supportant difficilement l'attitude qu'avait prise Sartre, à partir de 1950, dans la direction de cette revue, Merleau-Ponty l'appela après que Sartre eut fait sauter sans l'avertir un texte qu'il avait rédigé pour coiffer un article marxiste (de Sartre), qu'il estimait ne pas être publiable sans ce texte préliminaire, dans le numéro de décembre 195213. La conversation téléphonique, tendue, dura deux heures14, puis fut suivie de trois longues lettres où s'expriment bien sûr leurs désaccords politiques ainsi que leurs désaccords sur le rôle de l'intellectuel et des divergences philosophiques, voire personnelles. Ces lettres marqueront la rupture de leur amitié qui datait de leurs années d'études à l'École normale supérieure – rupture qui semble ne jamais avoir été acceptée ni par l'un ni par l'autre, selon François Ewald15. |
サルトルとの決別 朝鮮戦争が勃発した頃、サルトルは雑誌『レ・タン・モダン』の編集部に内緒で論文『共産主義者と平和』(1952年)を発表した。1950年以降の同誌編 集者としてのサルトルの態度に不満を抱いていたメルロ=ポンティは、1952年12月号に掲載された(サルトルによる)マルクス主義的論考のキャップのた めに書いた文章を、サルトルが何の前触れもなく吹っ飛ばした後、彼に電話をかけた。緊迫した電話での会話は2時間に及び14、その後、政治的な意見の相 違、知識人の役割に関する意見の相違、哲学的、さらには個人的な相違を表す3通の長い手紙が続いた。フランソワ・エワルド15によれば、二人ともそれを受 け入れなかったようだ。 |
| Philosophie Article connexe : Phénoménologie (philosophie). L'Avant-Propos de la Phénoménologie de la perception Article connexe : Phénoménologie de la perception. Dans l'avant-propos de la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty tente de répondre à la question : « Qu’est-ce qu’est la phénoménologie ? »16. Il observe initialement que même un demi-siècle après les premiers écrits de Husserl, une définition univoque est loin de faire l’unanimité. De plus, beaucoup des propositions centrales semblent aller dans des directions différentes. Une première proposition soutient que la phénoménologie est caractérisée par un essentialisme, donc qu'elle ne s’intéresse pas à une interprétation empiriste des phénomènes, mais qu'elle veut éclairer les déterminations essentielles[Quoi ?] de la perception, de la conscience et de la corporéité. Elle est donc aussi une philosophie de la facticité. Une seconde proposition est que la phénoménologie se veut transcendantale, donc tente de réfléchir sur les conditions de possibilités de l’expérience et de la cognition en suspendant nos présupposés métaphysiques mondains, pour les évaluer de manière critique. Une troisième proposition explique que la phénoménologie se veut strictement scientifique, mais tente aussi de parler de l’expérience préscientifique du monde, du temps et de l’espace. Une quatrième proposition établit que souvent appréhendée comme une discipline purement descriptive, la phénoménologie vise à décrire l’expérience telle que donnée, elle ne s’intéresse pas à l’origine biologique ou neurobiologique, même si Husserl vers la fin de sa vie traite de l’importance du développement d’une phénoménologie génétique17. Ensuite, Merleau-Ponty explique qu’il semblerait tentant de simplement caser les travaux de Husserl et sa philosophie transcendantale comme étant une philosophie complètement à part de celle de Heidegger, qui lui traite plutôt de phénoménologie de l’existence et herméneutique. Cela est cependant trop simpliste pour Merleau-Ponty, ces points de vue ne s’opposent pas nécessairement, avec une analyse minutieuse ils peuvent s’incorporer18. C’est pourquoi dans la préface, Merleau-Ponty tente d’établir les points communs de la phénoménologie telle un tout et non spécifiquement la doctrine propre à chaque philosophe qui se dit de la tradition phénoménologique. Voici quelques concepts, notés par Merleau-Ponty, qui sont propres à la méthode phénoménologique. D’abord, l'invitation de Husserl : « il faut retourner aux choses mêmes » serait interprétée comme une critique du scientisme qui vise un retour au monde perçu tel qu’il est expérimenté avant toute théorisation scientifique18. Il est important de ne jamais oublier que ce savoir scientifique est ancré dans une perspective à la première personne. Ensuite, l’idéalisme et le réalisme ne sont que le revers d’une médaille et tous deux s’avèrent erronés. À l’aide d’une analyse phénoménologique précise, il est possible de s’apercevoir que le sujet n’existe pas uniquement pour lui-même, autrui est aussi présent et le savoir passe parfois par les autres, tout n’est pas accessible par son propre entendement. Aussi, la subjectivité est nécessairement implantée dans un contexte social, historique et naturel19. Le concept de l’intentionnalité est une des grandes réalisations de la phénoménologie. L’analyse de l’intentionnalité révèle que la conscience est toujours à propos de quelque chose. Peu importe si ce qui est évoqué est la perception, un jugement, une pensée, un doute, une fantaisie ou un souvenir, toutes ces formes de conscience sont caractérisées par un objet intentionnel et celui-ci ne peut pas être adéquatement compris sans une analyse de son corrélat objectif, soit ce qui est perçu, douté, rappelé. |
哲学 関連記事:現象学(哲学)。 知覚の現象学への序文 関連記事:知覚の現象学。 メルロ=ポンティは『知覚の現象学』の序文で、「現象学とは何か」という問いに答えようとしている16。彼はまず、フッサールの最初の著作から半世紀を経 てもなお、一義的な定義について一致した合意がないことを指摘する。さらに、中心的な命題の多くは異なる方向を向いているように見える。 第一の命題は、現象学は本質主義によって特徴づけられ、したがって現象の経験主義的解釈に関心があるのではなく、知覚、意識、身体性の本質的な決定 [What?]に光を当てたいと主張している。したがって、現象学は事実性の哲学でもある。 第二の命題は、現象学は超越論的であることを目指しており、それゆえ、経験や認識の可能性の条件を批判的に評価するために、私たちの世俗的な形而上学的前 提を保留することによって考察しようとする、というものである。 第三の命題は、現象学は厳密に科学的であることを目指すと同時に、世界、時間、空間についての科学以前の経験についても語ろうとするものであることを説明 する。 第4の命題は、純粋に記述的な学問として理解されることが多い現象学は、経験を所与のものとして記述することを目的としており、フッサールが晩年、遺伝的 現象学を発展させることの重要性を語っていたとしても、生物学的あるいは神経生物学的な起源には関心がないことを立証する17。 第二に、メルロ=ポンティは、フッサールの仕事と彼の超越論的哲学を、存在の現象学と解釈学をより多く扱うハイデガーのそれとは完全に別個のものとして単 純に分類したくなるようだと説明している。しかし、メルロ=ポンティにとって、これは単純すぎる。これらの視点は必ずしも対立するものではなく、注意深く 分析すれば組み入れることができる18。だからこそメルロ=ポンティは序文で、現象学の伝統に属すると主張する各哲学者の教義を具体的に示すのではなく、 現象学全体としての共通点を確立しようと試みているのである。 ここでは、メルロ=ポンティが指摘した、現象学的方法に特有の概念をいくつか紹介する。まず第一に、フッサールの「事物そのものに立ち戻れ」という誘い は、科学的理論化の前に経験されるような知覚された世界に立ち戻ることを目指す科学主義への批判として解釈されるだろう18。科学的知識が一人称の視点に 根ざしていることを決して忘れてはならない。第二に、観念論と実在論は同じコインの裏表に過ぎず、どちらも間違っている。正確な現象学的分析の助けを借り れば、主体は自分自身のためだけに存在するのではなく、他者もまた存在し、知識は時に他者を介してもたらされる。つまり、主体性は必然的に社会的、歴史 的、自然的文脈に組み込まれているのである19。意図性の概念は、現象学の偉大な成果のひとつである。意図性を分析することで、意識は常に何かに関連して いることが明らかになる。喚起されるものが知覚であれ、判断であれ、思考であれ、疑念であれ、空想であれ、記憶であれ、こうした意識の形態はすべて意図的 な対象によって特徴づけられる。 |
| Le primat de la perception Avec La Structure du comportement et la Phénoménologie de la perception (1944), Merleau-Ponty a voulu montrer que la perception n'était pas la résultante d'atomes causaux de sensations, contrairement à ce que véhiculait la tradition issue de John Locke dont la conception atomiste causale était perpétuée dans certains courants psychologiques de l'époque (par exemple le béhaviorisme). La perception a plutôt, selon Merleau-Ponty, une dimension active en tant qu'ouverture primordiale au monde vécu (au Lebenswelt)20. Cette ouverture primordiale est à la base de sa thèse du primat de la perception. Selon une formule de la phénoménologie d'Edmund Husserl, « toute conscience est conscience de quelque chose », ce qui implique une distinction entre « actes de pensée » (la noèse) et « objets intentionnels de la pensée » (le noème), faisant de la « corrélation » noético-noématique le premier socle de la constitution des analyses de la conscience. Or, en étudiant les manuscrits posthumes d'Edmund Husserl, qui demeure une de ses influences majeures, Merleau-Ponty remarque que dans leur évolution, ses travaux mettent eux-mêmes à jour des données qui ne sont pas assimilables à la corrélation noético-noématique21. C'est notamment le cas en ce qui a trait aux données sur le corps (qui est à la fois corps-sujet et corps-objet), sur le temps subjectif (la conscience du temps n'est ni un acte de conscience ni un objet de pensée) et sur autrui (les premières considérations d'autrui chez Husserl menaient au solipsisme). La distinction entre « actes de pensée » (noèse) et « objets intentionnels de la pensée » (noème) ne semble donc pas constituer une base irréductible, elle semble plutôt apparaître à un niveau supérieur de l'analyse. Ainsi, Merleau-Ponty ne postule pas que « toute conscience est conscience de quelque chose », ce qui suppose d'emblée un socle noético-noématique, il développe plutôt la thèse selon laquelle « toute conscience est conscience perceptive »22. Ce faisant, il instaure un tournant significatif23 dans le développement de la phénoménologie, indiquant que les conceptualisations doivent être réexaminées à l'aune du primat de la perception, en soupesant ses conséquences philosophiques. |
知覚の優位性 メルロ=ポンティは『行動の構造と知覚の現象学』(1944年)で、ジョン・ロックに始ま る伝統に反して、知覚は感覚の因果的な原子の結果ではないことを示そうとした。その代わりに、メルロ=ポンティによれば、知覚は、生かされている世界 (Lebenswelt)20 への根源的な開放として能動的な側面を持つ。 この根源的な開放性が、知覚の優位性という彼のテーゼの基礎となっている。エドムント・フッサールの現象学の定式によれば、「すべての意識は何かの意識で ある」。これは、「思考の行為」(ノエティック)と「思考の意図的対象」(ノエメ)の区別を意味し、ノエティックとノエメの「相関関係」が意識分析の構成 の主要な基礎となる。 しかし、メルロ=ポンティは、大きな影響を受けたエドムント・フッサールの遺稿を研究する中で、フッサールの研究そのものが、その発展の過程で、ノエ ティック-ノネマティック相関関係には同化できないデータを明るみに出したと指摘している21。特に、身体に関するデータ(身体-主体であると同時に身体 -客体でもある)、主観的時間に関するデータ(時間の意識は意識行為でも思考対象でもない)、他者に関するデータ(フッサールの他者に関する最初の考察は 独在論につながった)がそうである。 したがって、「思考行為」(ノエシス)と「意図的な思考対象」(ノエメ)の区別は、還元不可能な基礎を構成しているようには見えない。したがって、メルロ =ポンティは、「すべての意識は何かの意識である」と仮定するのではなく、むしろ「すべての意識は知覚的意識である」というテーゼを展開している22。そ うすることで、彼は現象学の発展において重要な転換点23を築き、知覚の優位性に照らして概念化を再検討し、その哲学的帰結を重く見なければならないこと を示したのである。 |
La corporéité René Descartes. En prenant comme point de départ l'étude de la perception, Merleau-Ponty est amené à reconnaître que le « corps propre » n'est pas seulement une chose, un objet potentiel d'étude pour la science, mais qu'il est aussi une condition permanente de l'expérience, qu'il est constituant de l'ouverture perceptive au monde et à son investissement. Il souligne alors qu'il y a une inhérence de la conscience et du corps dont l'analyse de la perception doit tenir compte. Pour ainsi dire, le primat de la perception signifie un primat de l'expérience, dans la mesure où la perception revêt une dimension active et constitutive24. Le développement de ses travaux instaure donc une analyse marquant la reconnaissance autant d'une corporalité de la conscience que d'une intentionnalité corporelle25, contrastant ainsi avec l'ontologie dualiste des catégories corps/esprit de René Descartes, un philosophe auquel Merleau-Ponty est demeuré attentif malgré les divergences importantes qui les séparent26. Il amorce alors une étude de l'incarnation de l'individu dans le monde, tentant de surmonter l'alternative entre une pure liberté et un pur déterminisme, tout comme le clivage entre le corps-pour-soi et le corps-pour-autrui. |
身体性 ルネ・デカルト 知覚の研究を出発点とすることで、メルロ=ポンティは、「適切な身体」は単なるモノ、科学の潜在的な研究対象ではなく、経験の永続的な条件でもあり、世界 に対する知覚的な開放性とそれへの投資の構成要素であることを認識するようになる。彼は、知覚の分析が考慮に入れなければならない、意識と身体との不可分 性が存在することを強調する。いわば、知覚の優位性とは、知覚が能動的で構成的な次元を持つ限りにおいて、経験の優位性を意味するのである24。 メルロ=ポンティは、ルネ・デカルトの心/身体の二元論的存在論とは対照的に、意識の身体性と身体的意図性の両方を認識する分析を確立した。メルロ=ポン ティは、純粋な自由と純粋な決定論との間の対立や、自己のための身体と他者のための身体との間の対立を乗り越えようと、世界における個人の身体化について の研究を始めた。 |
| Le langage Ferdinand de Saussure. Article connexe : philosophie du langage. La mise en lumière du fait que la corporéité a intrinsèquement une dimension d'expressivité qui s'avère fondamentale à la constitution de l'ego est l'une des conclusions de La Structure du comportement27 constamment réinvesties dans ses travaux ultérieurs. En suivant ce filon de l'expressivité, il va examiner comment un sujet incarné est en mesure de réaliser des activités qui dépassent le niveau organique du corps, tel que c'est le cas lors des opérations intellectuelles et en ce qui relève de la vie culturelle. Il considère alors attentivement le langage, en tant que noyau de la culture, en examinant notamment les liens entre le déploiement de la pensée et du sens, tout en enrichissant sa perspective non seulement par l'analyse de l'acquisition du langage et de l'expressivité du corps, mais aussi en prenant en compte les pathologies du langage, de même que la peinture, le cinéma, les usages littéraires du langage et la poésie. Tout comme, à la même époque, Gilbert Ryle, il rejette alors explicitement la conception cartésienne ou mentaliste du langage, qui en ferait la simple expression de représentations mentales. Les mots ne sont pas, pour Merleau-Ponty, le reflet de la pensée: « la parole n'est pas le « signe » de la pensée »28. On ne peut en effet dissocier la parole et la pensée : les deux sont « enveloppées l'une dans l'autre, le sens est pris dans la parole et la parole est l'existence extérieure du signe »28. Le langage implique d'abord une activité intentionnelle, qui passe par le corps propre. « La pensée n'est rien d'« intérieur », elle n'existe pas hors du monde et hors des mots. »28 Cette préoccupation pour le langage inclut dès le départ une considération des expressions relevant de la sphère artistique, comme en témoigne La Structure du comportement (1942) qui contient notamment un passage sur le Greco29 préfigurant les propos qu'il développe en 1945 dans Le Doute de Cézanne30, à la suite des considérations de la Phénoménologie de la perception31. Dans cette mesure, le travail qu'il réalise lorsqu'il occupe la Chaire de psychologie de l'enfant et de pédagogie à l'Université de La Sorbonne n'est pas un intermède à ses préoccupations philosophiques et phénoménologiques, il représente plutôt un moment significatif du développement de ses réflexions32. Tel que l'indiquent ses résumés de cours à l'Université de La Sorbonne, il maintient durant cette période un dialogue entre la phénoménologie et les divers travaux réalisés en psychologie, tout en revenant sur l'étude de l'acquisition du langage chez l'enfant, en plus d'être l'un des premiers philosophes à exploiter largement l'apport des travaux de linguistique de Ferdinand de Saussure et de travailler sur la notion de structure par l'entremise d'une discussion des travaux en psychologie, en linguistique et en anthropologie sociale33. |
言語 フェルディナン・ド・ソシュール 関連記事:言語哲学 行動の構造』27の結論のひとつで、その後の彼の著作に絶えず再投入されたのは、身体性は自我の構成にとって基本的な表現性の次元を本質的に持っていると いうことであった。この表現性という糸をたどりながら、知的活動や文化的生活においてそうであるように、身体化された主体がいかにして身体の有機的レベル を超えた活動を行うことができるかを考察する。 彼は、文化の核としての言語を綿密に観察し、特に思考の展開と意味との関連を検証しながら、言語の習得や身体の表現力を分析するだけでなく、言語の病理 学、絵画、映画、言語の文学的使用、詩なども考慮に入れることで、その視点を豊かにしていった。 同時代のギルバート・ライル同様、彼は、言語を単なる心的表象の表現とするデカルト的あるいは精神主義的な概念を明確に否定した。メルロ=ポンティにとっ て、言葉は思考の反映ではない。「発話は思考の『記号』ではない」28。発話と思考を切り離すことはできない。両者は「互いに包み込まれ、意味は発話に取 り込まれ、発話は記号の外的存在である」28。言語は何よりもまず、身体そのものを通過する意図的な活動を意味する。思考は 「内面的 」なものではなく、世界の外にも、言葉の外にも存在しない」28。 このような言語への関心には、当初から芸術領域における表現の考察も含まれていた。『行動の構造』(1942年)には、『知覚の現象学』31 での考察に続き、1945年に『セザンヌの疑惑』30 で展開した考えを予感させるエル・グレコ29 に関する一節がある。この意味で、彼がソルボンヌ大学で児童心理学・教育学の講座を開いていたときの仕事は、彼の哲学的・現象学的関心に対する幕間ではな く、むしろ彼の考察の発展における重要な瞬間であった32。 ソルボンヌ大学での講義概要が示すように、この時期、彼は現象学と心理学のさまざまな研究との対話を続けながら、子どもの言語習得の研究に立ち戻った。 彼はまた、フェルディナン・ド・ソシュールの言語学の研究を幅広く利用し、心理学、言語学、社会人類学の研究の議論を通じて構造の概念に取り組んだ最初の 哲学者の一人でもある33。 |
| Les arts Les Joueurs de cartes, Paul Cézanne. Il importe de préciser que l'attention que Merleau-Ponty porte aux diverses formes d'arts (visuels, plastiques, littéraires, poétiques, etc.) n'est pas tributaire d'un questionnement sur le beau, ni orientée en vue de l'élaboration de critères normatifs sur l'art. Ainsi, on ne retrouve pas dans ses travaux un effort de théorisation tentant de cerner ce qui constituerait un chef-d'œuvre, une œuvre d'art ou encore de l'artisanat. Son objectif est d'abord et avant tout d'analyser les structures à la base de l'expressivité, qui se révèlent invariantes, en enrichissant les considérations sur le langage par une attention au travail des artistes, poètes et écrivains34. Cependant, bien qu'il n'établisse pas de critères normatifs sur l'art en tant que tel, il y a néanmoins chez lui une distinction prévalant entre « expression première » et « expression seconde ». Cette distinction apparaît dans la Phénoménologie de la perception35 et est parfois reprise sous les termes de « langage parlé » et de « langage parlant »36. Le langage parlé (ou expression seconde) renvoie à notre bagage langagier, à l'héritage culturel que nous avons acquis, ainsi qu'à la masse brute de rapport de signes et de significations. Le langage parlant (ou expression première), quant à lui, c'est le langage en tant que mise en forme d'un sens, c'est le langage au moment où il procède à l'avènement d'une pensée, au moment où il se fait avènement de sens. C'est le langage parlant, c'est-à-dire l'expression première, qui intéresse Merleau-Ponty et qui retient son attention lorsqu'il traite de la nature de la production et de la réception des expressions, un sujet qui imbrique aussi une analyse de l'action, de l'intentionnalité, de la perception, ainsi que des rapports entre la liberté et les déterminants externes. Au sujet de l'œuvre peinte, Merleau-Ponty constate que lors de son travail de création, l'artiste peintre peut avoir au préalable une certaine idée et désirer la concrétiser, ou encore qu'il peut travailler d'abord le matériau en tentant d'en dégager une certaine idée ou émotion, mais que dans un cas comme dans l'autre, il y a dans l'activité du peintre une élaboration de l'expression qui se retrouve intimement en interaction avec le sens qui est mis en œuvre. C'est à partir de ce constat de base qu'il va tenter d'expliciter les structures invariantes caractérisant l'expressivité, en tentant de rendre compte de la surdétermination du sens qu'il a fait valoir dans Le doute de Cézanne30. Parmi les structures à considérer, l'étude de la notion de style occupera une place importante dans Le langage indirect et les voix du silence37. En dépit de certains accords avec André Malraux, il marquera ses distances par rapport à trois conceptions du style dont ce dernier fait usage dans Les Voix du silence (publié dans la collection La Pléiade et regroupant les quatre volumes de Psychologie de l'art publiés de 1947 à 1950). Merleau-Ponty considère que dans cet ouvrage, le style est employé par Malraux parfois dans une optique très subjective en étant assimilé à une projection de l'individualité de l'artiste, parfois dans une optique à l'inverse très métaphysique, voire mystique selon lui, où le style est alors lié à une conception de « surartiste » exprimant « L'Esprit de la peinture », et qu'enfin il est parfois réduit à simplement désigner une catégorisation d'école ou de mouvement artistique. Pour Merleau-Ponty, ce sont ces usages de la notion de style qui amènent André Malraux à postuler un clivage entre l'objectivité de la peinture de la Renaissance italienne et la subjectivité de la peinture de son époque, ce à quoi Merleau-Ponty s'oppose. Selon lui, il importe de considérer cette problématique à la base, en reconnaissant que le « style » est d'abord une exigence due au primat perceptif, ce qui implique aussi une prise en considération des dimensions de l'historicité et de l'intersubjectivité38. |
芸術 『カード・プレイヤー』ポール・セザンヌ メルロ=ポンティの芸術の諸形態(視覚的、造形的、文学的、詩的など)への注目は、美への問いかけに依存しているわけではなく、芸術の規範的な基準の開発 に向けられているわけでもないことを明記しておくことは重要である。その結果、彼の作品には、傑作、芸術作品、職人技を構成するものを理論化する試みはな い。彼の目的は何よりもまず、表現力の根底にある構造を分析することであり、その構造は不変であることが示され、芸術家、詩人、作家の作品に注目すること で言語についての考察を豊かにしている34。 しかし、彼は芸術の規範的な基準を確立しているわけではないが、「第一次的表現」と「第二次的表現」の区別は存在する。この区別は『知覚の現象学』35に 登場し、「話し言葉」と「話し言葉」と呼ばれることもある36。話し言葉(あるいは第二の表現)とは、私たちの言語的な荷物、私たちが獲得した文化的遺 産、そして記号と意味の間の関係の生の塊のことである。一方、「話す言語」(あるいは第一の表現)とは、意味の形成としての言語であり、思考を生み出す瞬 間、意味を生み出す瞬間の言語である。 メルロ=ポンティが、行為の分析、意図性、知覚、自由と外的な決定要因との関係も織り交ぜながら、表現の生成と受容の本質を扱うときに関心を寄せ、彼の注 意を引くのは、言語を語ること、つまり第一次的な表現である。 描かれた作品について、メルロ=ポンティは、画家が創作活動を行う過程で、あらかじめある考えを持ち、それを実現しようとする場合もあれば、ある考えや感 情を引き出そうとして、まず素材に手を加える場合もあるが、いずれにせよ、画家の活動には、持ち込まれた意味と密接に関わる表現の精緻化がある、と指摘す る。この基本的な観察に基づいて、セザンヌは『セザンヌの疑問』30で提唱した意味の過剰決定を説明するために、表現力を特徴づける不変の構造を説明しよ うと試みる。 『Le langage indirect et les voix du silence(間接的な言語と沈黙の声)』37では、考察すべき構造の中で、スタイルの概念の研究が重要な位置を占めることになる。メルロ=ポンティ は、アンドレ・マルローと一定の合意をしていたにもかかわらず、『沈黙の声』(1947年から1950年にかけて出版された『芸術心理学』全4巻からなる 『ラ・プレイヤード』集に収録)において、マルローの3つの文体概念から距離を置いている。メルロ=ポンティは、この作品において、マルローによってスタ イルが、時には非常に主観的な意味で、芸術家の個性の投影と同化して使われ、時には非常に形而上学的な、神秘主義的な意味でさえ使われ、そこではスタイル が「絵画の精神」を表現する「超芸術家」の概念と結びつけられ、最後には、スタイルが単に流派や芸術運動の分類に還元されることもあると考察している。 メルロ=ポンティにとって、アンドレ・マルローがイタリア・ルネサンス絵画の客観性と同時代の絵画の主観性との間に分裂を仮定したのは、こうした様式概念 の使用によるものであり、メルロ=ポンティはこれに反対している。メルロ=ポンティの見解では、この問題を最初から検討することが重要であり、「様式」と は何よりもまず知覚の優位性の要件であり、歴史性と間主観性の次元を考慮に入れることを意味している38。 |
| L'histoire et l'intersubjectivité Autant ses travaux sur la corporéité que ceux sur le langage révèlent l'importance, pour la compréhension de l'expressivité, de l'enracinement de l'individu au sein du monde vécu. Or, cet enracinement imbrique les dimensions de l'historicité et de l'intersubjectivité, qu'il s'efforce alors de rendre intelligibles39. Comme point de départ à la considération de l'histoire et de l'intersubjectivité, il remarque que l'individu n'en est ni le sujet, puisqu'il prend part à un univers socioculturel et langagier déjà structuré, mais qu'il n'en est pas non plus le produit, puisqu'il y prend part et influe sur les institutions par l'usage qu'il en fait, y compris en ce qui a trait au langage institué qui lui semble être un modèle d'étude pour la compréhension de ces phénomènes40, comme il le note dans le dossier qu'il remet en vue de sa nomination au Collège de France41. En ce sens, Merleau-Ponty est un contradicteur du sens de l'histoire, concept hégelien – quoique l'influence d'Hegel soit certes plus présente dans ses derniers travaux23. Par son traitement de l'intersubjectivité, Merleau-Ponty met en évidence aussi une aporie de la philosophie occidentale qui s'exprimait par le problème classique du solipsisme. Dans le sillage de Husserl mais davantage que ce dernier il insiste sur une sorte de primat de l'intersubjectivité qui révèle à quel point le point de départ cartésien dans le « je pense » était inducteur de difficultés exposant d'ailleurs la philosophie au ridicule d'un « solipsisme à plusieurs ». C'est sous l'effet de ce renversement qu'une réforme des catégories ontologiques se met en marche dans l'œuvre du philosophe français. |
歴史と間主観性 身体性についての彼の仕事も、言語についての彼の仕事も、表現性を理解するためには、個人が生きている世界の中に根ざしていることが重要であることを明ら かにしている。この根源性は、歴史性と間主観性の次元を織り成し、彼はそれを理解可能にしようと努めている39。歴史と相互主観性を考える出発点として、 彼は、個人はすでに構造化された社会文化的・言語的世界に参加しているため、その主体でもなければ、その産物でもないと指摘する、 彼は、コレージュ・ド・フランスに任命されるために提出した書類41 の中で、このような現象の理解を研究するためのモデルであるように思われる制度化された言語との関連も含めて、その使用を通じて、その現象に参加し、制度 に影響を与えるのである。 この意味で、メルロ=ポンティは、歴史の意味に関するヘーゲル的概念とは矛盾する存在である。 間主観性の扱いにおいて、メルロ=ポンティはまた、古典的な独在論の問題で表現された西洋哲学のアポリアに光を当てている。フッサールの足跡をたどりなが ら、しかしフッサールよりも大きな程度で、彼は間主観性の一種の優位性を主張し、「私は考える」というデカルト的出発点が、哲学を「多数の独在論」という 嘲笑にさらすような困難を生み出したことを明らかにしている。この逆転が、フランスの哲学者の仕事における存在論的カテゴリーの改革を動かしているのであ る。 |
| Les sciences La psychologie S'il est vrai que Merleau-Ponty s'est montré attentif aux travaux de la psychologie, la plupart des spécialistes de l'histoire de la discipline reconnaissent qu'il est tout aussi vrai que ses propres travaux ont eu un impact réel au niveau des recherches en psychologie42. La structure du comportement (1942) considère de front un large éventail des recherches expérimentales de l'époque tout en montrant plusieurs difficultés auxquelles sont confrontés certains de ces travaux, en particulier ceux du béhaviorisme, dû aux présupposés ontologiques sur lesquels ils s'appuient implicitement. Mais à l’inverse, il montre aussi que les données expérimentales de la psychologie mettent en évidence certains problèmes de l'épistémologie et de la philosophie des sciences de l'époque. On remarque par ailleurs que La structure du comportement contient de nombreuses références à des recherches telles que celles du neurologue Kurt Goldstein et de Frederik J. J. Buytendijk, et que, réciproquement, Buytendijk fait à son tour plusieurs fois référence à Merleau-Ponty dans son Traité de Psychologie animale (1952), en plus d'avoir publié un article intitulé « Toucher et être touché » (1953)43 qui n'est pas étranger aux thèses sur la réversibilité « touchant-touché » que l'on retrouve dans Le visible et l'invisible44. Merleau-Ponty a aussi été attentif aux travaux de la psychologie de la Gestalt45 et a tenté une interprétation des points de convergence et de divergence de la psychanalyse46 avec la phénoménologie, en plus de ses considérations sur la psychosociologie et sur les travaux de Jean Piaget47. |
科学 心理学 メルロ=ポンティが心理学の研究に注意を払っていたことは事実だが、心理学史の専門家の多くは、彼自身の研究が心理学研究に大きな影響を与えたことも同様 に事実だと認めている42。行動の構造』(1942年)は、当時の広範な実験的研究を正面から検討すると同時に、これらの研究の一部、特に行動主義の研究 が、暗黙のうちに拠って立つ存在論的前提のために直面した困難を示している。しかし逆に、心理学の実験データが、当時の認識論や科学哲学におけるある種の 問題を浮き彫りにしていることも示している。 また、『行動の構造』には神経学者クルト・ゴールドスタインとフレデリック・J・J・ブイテンダイクの研究への言及が数多く含まれていることも注目に値す る。Buytendijkが『動物心理学研究』(1952年)の中でメルロ=ポンティの研究に何度も言及していること、また逆にBuytendijkが 『触れることと触れられること』(1953年)という論文を発表していることも注目に値する43。 メルロ=ポンティはまた、ゲシュタルト心理学45の研究にも関心を寄せ、精神社会学やジャン・ピアジェ47の研究についての考察に加えて、精神分析46と 現象学の収束点と分岐点を解釈しようと試みた。 |
| La sociologie et l'anthropologie En faisant l'analyse de l'enracinement au monde vécu et, par extension, de l'intersubjectivité, Merleau-Ponty a été amené à prendre position sur la nature des recherches sociologiques et anthropologiques, notamment dans les articles Le philosophe et la sociologie48 et De Mauss à Claude Lévi-Strauss49. Ses thèses sur le primat de la perception et sur le corps vécu instaurent une compréhension novatrice de l'intersubjectivité et, pour cette raison, elles ont inspiré des recherches en sociologie. Ces travaux ont emprunté plusieurs directions, et notamment : 1) le thème du « corps propre » a joué un rôle dans la sociologie de l'habitus et de la pratique de Pierre Bourdieu50, qui a d'ailleurs hésité à la fin de ses études de philosophie entre s'inscrire en thèse avec Merleau-Ponty et devenir sociologue ; 2) une mise en perspective avec les travaux de phénoménologie sociologique d'Alfred Schütz sur les intentionnalités pratiques a été engagée51 ; 3) une confrontation avec la nouvelle sociologie pragmatique a été avancée52. |
社会学と人類学 メルロ=ポンティは、生活世界における根源性、ひいては間主観性についての分析から、社会学的・人類学的研究のあり方について、特に論文『哲学と社会学』 (Le philosophe et la sociologie)48や『モースとクロード=レヴィ=ストロース』(De Mauss à Claude Lévi-Strauss)49のような立場をとるようになった。知覚の優位性と生かされている身体に関する彼の論文は、間主観性についての革新的な理解 を確立し、そのために社会学の研究に刺激を与えた。1)「適切な身体」というテー マは、ピエール・ブルデュー50 のハビトゥスと実践の社会学に おいて役割を果たしたが、彼は哲学の研究の終わり に、メルロ=ポンティのもとで論文を書くか、社会学者になる かをためらっていた。 |
| La chair et le chiasme / Le
visible et l'invisible Les notions de chair et de chiasme, ainsi que les notions concomitantes de visible et d'invisible, apparaissent principalement dans Le visible et l'invisible et dans les Notes de travail qui l'accompagnent (rappelons qu'il s'agit d'un ouvrage posthume, demeuré en chantier53), ainsi que dans les notes de cours au Collège de France de la période 1959-196154 – et très brièvement dans la Préface de Signes55 et quelques autres endroits56. En raison de l'état d'inachèvement de l'articulation de ces notions, il n'est pas toujours évident de délimiter exactement ce que Merleau-Ponty voulait signifier par là, mais, sans entrer dans les questions d'interprétations, il y a néanmoins certaines indications généralement partagées par les spécialistes dans le domaine qui peuvent être relevées. On peut d'abord noter que l'introduction de ces notions vise à surmonter les clivages véhiculés par l'usage (de l'époque) de certaines notions. Ainsi, en postulant que « toute conscience est conscience perceptive », Merleau-Ponty a reconnu une prégnance primordiale du percevant et du perçu – ce qui est parfois indiqué par l'exemple de la réversibilité du touchant et du touché. De même, en traitant du corps propre, il a reconnu une corporalité de la conscience et une intentionnalité corporelle. Or, les catégories de sujet/monde, comme celles de corps/conscience ont souvent été articulées sur fond de dualisme des catégories. C'est en quelque sorte pour nommer ces prégnances et empiètements qu'apparaîtra la notion de chair, ainsi que les notions associées d'entrelacs et de chiasme57. Les notions de visible et d'invisible, quant à elles, sont liées à la question du sens. Selon les thèses de Merleau-Ponty, il n'y a pas de distinction catégorique entre être et manière d'apparaître. Ainsi, on remarquera que malgré son attention aux travaux de Heidegger, qu'il discute plus fréquemment dans cette période, Merleau-Ponty n'endosse pas les considérations de ce dernier sur le plan de la métaphysique58. Pour Merleau-Ponty, la question du sens ne s'inscrit pas dans une ontologie dualiste de l'apparence et de l'être, il y a plutôt une réversibilité des dimensions de visible et d’invisible qui doivent être comprises comme endroit et envers, l’invisible n'étant pas l'opposé du visible (Merleau-Ponty s'écarte ainsi de l'ontologie sartrienne de L'Être et le Néant), mais plutôt sa doublure, sa « profondeur charnelle ». Il s'agit là en quelque sorte pour lui de rendre justice à la prégnance des signes et du sens qui prévaut, selon ses travaux sur le langage et les arts. Ceci signifie qu'il n'y a pas subordination des signes au sens, ni l'inverse. Ainsi, la question du sens ne peut pas être ramenée à une pure idéalité, il y a aussi une matérialité inhérente au sens – par exemple, dans Phénoménologie de la perception Merleau-Ponty note qu'une œuvre peinte, si elle est déchirée, n'est plus sens, elle est ramenée à son état de lambeaux59. |
肉体とキアスム/見えるものと見えないもの 肉とキアスムの概念、そしてそれに付随する可視と不可視の概念は、主に『可視と不可視』(Le visible et l'invisible)とそれに付随する『作業ノート』(これは遺作であり、まだ進行中であることを忘れてはならない53)、1959年から 196154年までのコレージュ・ド・フランスでの講義ノート、そして『シグネス』(Signes)の序文55や他の数カ所56にごく簡単に登場する。メ ルロ=ポンティがこれらの概念で何を意味しているのかを正確に明らかにすることは、これらの概念の未完成な状態のために必ずしも容易ではないが、解釈の問 題に立ち入らない限り、この分野の専門家が一般的に共有している一定の兆候を指摘することはできる。 第一に、これらの概念の導入は、(当時の)ある概念の使用によって生み出された分断を克服することを意図している。メルロ=ポンティは、「すべての意識は 知覚する意識である」と仮定することで、知覚するものと知覚されるものの根源的な重要性を認識した。同様に、適切な身体を扱う際、彼は意識の身体性と身体 的意図性を認めた。しかし、主体/世界や身体/意識というカテゴリーは、しばしばカテゴリー二元論を背景に明確化されてきた。肉体の概念と、それに関連す る絡み合いやキアスムス57 の概念は、いわば、こうした含意や侵犯を名指しするために登場する。見えるものと見えないものという概念は、その部分において、意味の問題と結びついてい る。 メルロ=ポンティによれば、「存在すること」と「出現すること」の間に定型的な区別はない。したがって、この時期、ハイデガーの著作に注目し、より頻繁に 論じているにもかかわらず、メルロ=ポンティはハイデガーの形而上学的考察を支持していない58。メルロ=ポンティにとって、意味の問題は、外見と存在と いう二元論的存在論の一部ではなく、むしろ、見えるものと見えないものの次元の可逆性があり、それは正しい側と間違った側として理解されなければならず、 見えないものは見えるものの反対ではなく(メルロ=ポンティはこうして『存在と無』のサルトル的存在論から離れる)、むしろその裏地、その「肉欲的深さ」 である。メルロ=ポンティにとって、これは、言語と芸術に関する彼の仕事において優勢な、しるしと意味の普及を正当に評価するための方法である。つまり、 記号は意味に従属するものではなく、またその逆でもない。 したがって、意味の問題を純粋な観念性に還元することはできない。意味には物質性も内在している。例えば、『知覚の現象学』において、メルロ=ポンティ は、描かれた作品が破れれば、それはもはや意味ではなく、ズタズタの状態に還元されると述べている59。 |
| La politique La pensée politique de Merleau-Ponty ne se situe ni au niveau de l'élaboration théorique d'une philosophie politique proprement dite, ni au niveau d'une chronique de l'actualité et des événements politiques. L'élaboration de sa pensée politique procède d'un va-et-vient entre ces niveaux, il ne s'agit, du moins selon ses propres souhaits, ni de plaquer une théorie aux événements en faisant découler les actions à entreprendre à partir de principes politiques/moraux, ni de réagir à chaque événement comme s'il constituait à lui seul un tout sans dimension philosophique. Deux interlocuteurs de la tradition philosophique joueront un rôle particulier dans l'élaboration d'une esquisse de philosophie politique au risque des tumultes de l'histoire au sein desquels le penseur engagé a assumé son immersion : Machiavel60 et Marx61. Il publie Humanisme et terreur (1947) où il justifie les procès de Moscou au nom de la responsabilité « objective » des accusés ; puis Les Aventures de la dialectique (1955). Ces ouvrages, en plus de receler l'ébauche d'une philosophie de l'histoire, abordent l'interprétation du marxisme, sans pour autant adhérer à une quelconque doctrine. Il publie aussi maints articles à teneur politique dans divers journaux, ainsi que dans la revue Les Temps modernes dont il est éditorialiste politique jusqu'à son retrait, en décembre 1952, dû à des divergences d'opinion touchant à la fois aux perspectives d'engagement social des intellectuels et aux positions politiques de Sartre, tel qu'en témoigne le document Sartre, Merleau-Ponty : Les lettres d'une rupture62 . Dans le champ universitaire et du point de vue de leur actualité, les écrits de Merleau Ponty ont fait l'objet d'une controverse entre le sociologue et spécialiste de philosophie politique Philippe Corcuff et Vincent Peillon, comme philosophe63. À la suite de l'article de Philippe Corcuff intitulé « Actualité de la philosophie politique de Merleau-Ponty », publié en deux parties, à la suite des nombreux colloques qui se sont tenus pour le centenaire de la naissance de Merleau-Ponty, « (I)-Politique et raison critique »64 et «(II)-Politique et histoire»65, Vincent Peillon a souhaité répondre66, l'échange s'est ensuite poursuivi avec quelques éléments de réponse de Philippe Corcuff67. |
政治 メルロ=ポンティの政治思想は、いわゆる政治哲学の理論的推敲のレベルでもなければ、現在の政治的出来事の年代記のレベルでもない。彼の政治思想の展開 は、これらのレベルの間を行ったり来たりしながら進んでいく。少なくとも彼自身の希望によれば、政治的/道徳的原則からとるべき行動を導き出すことによっ て出来事に理論を適用することでもなければ、あたかもそれ自体が哲学的次元を持たない全体を構成しているかのように、それぞれの出来事に反応することでも ない。哲学の伝統に由来する二人の対話者は、献身的な思想家が没頭してきた歴史の騒乱の危険にさらされながら、政治哲学の輪郭を練り上げる上で特別な役割 を果たすことになる。 彼は、被告人の「客観的」責任という名目でモスクワ裁判を正当化した『ヒューマニズムとテロル』(1947年)を出版し、続いて『弁証法の冒険』 (1955年)を出版した。これらの著作は、歴史哲学の概要を含むと同時に、特定の教義に固執することなく、マルクス主義の解釈を扱った。サルトルはま た、さまざまな新聞や雑誌『レ・タン・モダン』にも政治的性格を帯びた記事を多数発表している。雑誌『レ・タン・モダン』では、1952年12月に政治担 当編集者を退任するまで、知識人の社会的コミットメントの展望やサルトルの政治的立場に関する意見の相違のために、政治担当編集者を務めていた。 学問的な分野とその時事性という点で、メルロ・ポンティの著作は、社会学者であり政治哲学の専門家であるフィリップ・コルキュフと、哲学者としてのヴァン サン・ペイヨンの間で論争の的となっている63。フィリップ・コルキュフの「メルロ=ポンティの政治哲学の妥当性」(Actualité de la philosophie politique de Merleau-Ponty)と題された論文に続き、メルロ=ポンティの生誕100周年を記念して開催された数々のコロキアム「(I)- Politique et raison critique」64 と「(II)-Politique et histoire」65 をきっかけに、ヴァンサン・ペイヨンが反論を希望し66 、フィリップ・コルキュフの反論の一部を交えながらやりとりが続いた67 。 |
| Merleau-Ponty romancier En octobre 2014, un article publié dans Le Monde a fait état de découvertes récentes au sujet d'un roman publié en 1928 chez Grasset (Nord. Récit de l'Arctique) et paru sous le nom de Jacques Heller dont des proches de Merleau-Ponty (Simone de Beauvoir, Elisabeth Lacoin…) semblent s'accorder à dire qu'il s'agit d'un roman écrit par Merleau-Ponty, alors étudiant à l'École normale supérieure68. En 2019, ces hypothèses ont été confirmées et étayées, grâce à des lettres inédites : Merleau-Ponty a rédigé l'essentiel de ce livre, qui évoque quatre années passées dans l'Arctique du Canada, en tant que « plume » pour son ami et explorateur Jacques Heller. À l'époque, le livre fut accueilli très favorablement par la critique littéraire. Simone de Beauvoir dit reconnaître dans la prose le style de Merleau-Ponty69. |
小説家メルロ=ポンティ 2014年10月、ル・モンド紙に掲載された記事は、1928年にグラッセによって出版され、ジャック・ヘラー名義で出版された小説(『北極圏の叙事 詩』)について最近の発見を報じたが、この小説はメルロ=ポンティに近い人々(シモーヌ・ド・ボーヴォワール、エリザベート・ラコアン...)が、当時高 等師範学校の学生だったメルロ=ポンティが書いたものだと同意しているようだ68。2019年、これらの仮説は未発表の書簡によって裏付けられ、確認され た: メルロ=ポンティは、カナダの北極圏で過ごした4年間を回想した本書の大半を、友人で探検家のジャック・ヘラーのための「ペン」として書いた。当時、この 本は文芸批評家から好意的に受け入れられた。シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、散文69の中にメルロ=ポンティの文体を認めたという。 |
| Publications Article détaillé : Liste des publications de Maurice Merleau-Ponty. La Structure du comportement, Paris, PUF, 1942 7e éd. en 1972 La Phénoménologie de la perception, Paris, NRF, Gallimard, 1945 Humanisme et terreur, Paris, Gallimard, 1947 L’Union de l’âme et du corps, chez Malebranche, Biran et Bergson, Vrin, 1968, cours présentés par J. Deprun Sens et non-sens, Paris, Nagel, 1948 Les Aventures de la dialectique, Gallimard, 1955 Les Sciences de l’homme et la phénoménologie, Centre de documentation universitaire, réédité en 1975 Les Relations avec autrui chez l’enfant, Paris, Centre de documentation universitaire, réédité en 1975 Éloge de la philosophie, leçon inaugurale faite au Collège de France, le jeudi 15 janvier 1953, NRF, Gallimard, 1953 Signes, NRF, Gallimard, 1960 Le Visible et l’invisible, publié par Cl. Lefort, Gallimard, 1964 L’Œil et l’esprit, Gallimard, 1960 Résumé de cours (1952-1960), Gallimard, 1968 La Prose du monde, Gallimard, 1969 Œuvres, édition établie et préfacée par Claude Lefort, Paris, Gallimard, 2010 Le monde sensible et le monde de l'expression : cours au Collège de France : notes, 1953, texte établi et annoté par Emmanuel de Saint-Aubert et Stefan Kristensen, Genève, Métis Presses, 2011 Recherches sur l'usage littéraire du langage : cours au Collège de France : notes, 1953, texte établi par Benedetta Zaccarello et Emmanuel de Saint-Aubert, annotations et avant-propos de Benedetta Zaccarello, Genève, Métis Presses, 2013 Entretiens avec Georges Charbonnier et autres dialogues, 1946-1959, transcription, avant-propos et annotations de Jérôme Melançon, Lagrasse, Verdier, 2016 Le Problème de la parole. Cours au Collège de France. Notes 1953-1954, édition par Lovisa Andén, Franck Robert et Emmanuel de Saint Aubert, Genève, MētisPresses, 2020, Simone de Beauvoir, Élisabeth Lacoin & Maurice Merleau-Ponty, Lettres d’amitié. 1920-1959, 2022, Paris, Gallimard, Blanche, 2022 Conférences en Europe et Premiers Cours à Lyon. Inédits I (1946-1947), édition par Michel Dalissier, avec la participation de Shôichi Matsuba, Paris & Milan, Mimésis, L’œil et l’esprit, 2022 Conférences en Amérique. Notes de cours et autres textes. Inédits II (1947-1949), édition par Michel Dalissier, avec la participation de Shôichi Matsuba, Paris & Milan, Mimésis, L’œil et l’esprit, 2022 |
出版物 詳細記事 モーリス・メルロ=ポンティの著書一覧。 La Structure du comportement, Paris, PUF, 1942 第七版は1972年に出版された。 知覚の現象学』パリ、NRF、ガリマール社、1945年 ヒューマニズムと宗教、パリ、ガリマール、1947年 マレブランシュ、ビラン、ベルクソンによる「肉体と肉体の統合」、ヴラン、1968年、J.デプランの講義による 感覚と非感覚、パリ、ナーゲル、1948年 弁証法の冒険』ガリマール社、1955年 Les Sciences de l'homme et la phénoménologie, Centre de documentation universitaire, reprinted in 1975. Les Relations avec autrui chez l'enfant, Paris, Centre de documentation universitaire, reprinted 1975 Éloge de la philosophie, Collège de Franceでの創立講義、1953年1月15日(木)、NRF、ガリマール、1953年 Signes, NRF, Gallimard, 1960年 見えるものと見えないもの』 Cl. ルフォール著、ガリマール社、1964年 L'Œil et l'esprit』 ガリマール社、1960年 Résumé de cours (1952-1960), Gallimard, 1968 世界の散文』 ガリマール社、1969年 クロード・ルフォール編著、前書き、パリ、ガリマール、2010年 Le monde sensible et le monde de l'expression: cours au Collège de France: notes, 1953, edited and annotated by Emmanuel de Saint-Aubert and Stefan Kristensen, Geneva, Métis Presses, 2011. Recherches sur l'usage littéraire du langage : cours au Collège de France : notes, 1953, edited by Benedetta Zaccarello and Emmanuel de Saint-Aubert, Benedetta Zaccarello, 注釈と序文, ジュネーブ, Métis Presses, 2013. Entretiens avec Georges Charbonnier et autres dialogues, 1946-1959, 書き起こし、序文、注釈(ジェローム・メルランソン), Lagrasse, Verdier, 2016 音声の問題 コレージュ・ド・フランスでの講義。ノート1953-1954年、ロヴィサ・アンデン、フランク・ロベール、エマニュエル・ド・サンオーベール編、ジュ ネーヴ、MētisPresses、2020年、 シモーヌ・ド・ボーヴォワール、エリザベス・ラコワン、モーリス・メルロ=ポンティ『レトル・ダミティエ』。1920-1959, 2022, パリ, ガリマール, ブランシュ, 2022 ヨーロッパでの講義とリヨンでの最初のコース。未刊行I(1946-1947)、ミシェル・ダリシエ編、松葉祥一参加、パリ&ミラノ、ミメシス、 L'œil et l'esprit, 2022 アメリカでの講義。講義ノートとその他のテキスト。Inédits II (1947-1949)、ミシェル・ダリシエ編、松葉昇一参加、パリ&ミラノ、ミメシス、L'œil et l'esprit, 2022 |
| Phénoménologie
de la perception Le Visible et l'Invisible Signes Corps propre Chair du monde Lexique de phénoménologie |
知覚の現象学 目に見えるものと見えないもの 兆し(シーニュ) 身体 世界の肉 現象学の用語集 |
Maurice Merleau-Ponty, 1908-1961、からの翻訳ならびに、加筆修正(中)です。関連ページに「メルロ=ポンティと『知覚の現象学』」 「現象学における時間概念」 「知 覚の現象学」などがあります。
****
| Maurice
Jean Jacques
Merleau-Ponty[16] (French: [mɔʁis mɛʁlo pɔ̃ti, moʁ-]; 14
March 1908 – 3
May 1961) was a French phenomenological philosopher, strongly
influenced by Edmund Husserl and Martin Heidegger. The constitution of
meaning in human experience was his main interest and he wrote on
perception, art, politics, religion, biology, psychology,
psychoanalysis, language, nature, and history. He was the lead editor
of Les Temps modernes, the leftist magazine he established with
Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir in 1945. |
モーリス・ジャン・ジャック・メルロ=ポンティ[16](フランス語:
[mɔʁis mɛ moʁ -
1961年5月3日)はフランスの現象学の哲学者で、エドマンド・フッサールやマルティン・ハイデガーから強い影響を受けた。人間の経験における意味の構
成に主な関心を寄せ、知覚、芸術、政治、宗教、生物学、心理学、精神分析、言語、自然、歴史について執筆した。1945年にジャン=ポール・サルトル、シ
モーヌ・ド・ボーヴォワールとともに創刊した左翼雑誌『レ・タン・モダン』の主幹編集長を務めた。 |
| At the core of Merleau-Ponty's
philosophy is a sustained argument for the foundational role that
perception plays in the human experience of the world. Merleau-Ponty
understands perception to be an
ongoing dialogue
between one's lived body and the world which it perceives, in which
perceivers passively and actively strive to express the perceived world
in concert with others. He was the only major phenomenologist of the
first half of the twentieth century to engage extensively with the
sciences. It is through this engagement that his writings became
influential in the project of naturalizing phenomenology, in which
phenomenologists use the results of psychology and cognitive science. |
メルロ=ポンティの哲学の核心は、知覚が人間の世界経験において果たす
基礎的な役割に対する持続的な議論である。メルロ=ポンティは、知覚を、生きている
自己の身体とそれが知覚する世界との間の継続的な対話であると理解し、そこでは知覚者は受動的にも能動的にも、他者と協調して知覚した世界を表現しようと
努力するのである。彼は、20世紀前半の主要な現象学者の中で唯一、科学と幅広く関わりを持った。現象学者が心理学や認知科学の成果を利用
する自然化現象学のプロジェクトにおいて、彼の著作が影響力を持ったのは、この関わりを通してである。 |
| Merleau-Ponty emphasized the
body as the primary site of knowing the world, a corrective to the long
philosophical tradition of placing consciousness as the source of
knowledge, and maintained that the perceiving body and its perceived
world could not be disentangled from each other. The articulation of
the primacy of embodiment (corporéité) led him away from phenomenology
towards what he was to call “indirect ontology” or the ontology of “the
flesh of the world” (la chair du monde), seen in his final and
incomplete work, The Visible and Invisible, and his last published
essay, “Eye and Mind”. |
メルロ=ポンティは、意識を知識の源泉とする長い哲学的伝統に対する修
正として、世界を知る第一の場として身体を強調し、知覚する身体とその知覚される世界とは、互いに切り離すことはできないと主張した。具現化の優位性を明
確にすることで、彼は現象学から「間接的存在論」あるいは「世界の肉体」(la chair du
monde)の存在論と呼ぶべきものへと向かい、それは彼の最後の不完全な著作『見えるものと見えないもの』や最後に出版されたエッセイ『眼と心』に見ら
れるものである。 |
| Merleau-Ponty engaged with
Marxism throughout his career. His 1947 book, Humanism and Terror, has
been widely misunderstood[17] as a defence of the Soviet farce trials.
In fact, this text avoids the definitive endorsement of a view on the
Soviet Union, but instead engages with the Marxist theory of history as
a critique of liberalism, in order to reveal an unresolved antinomy in
modern politics, between humanism and terror: if human values can only
be achieved through violent force, and if liberal ideas hide illiberal
realities, how is just political action to be decided?[18]
Merleau-Ponty maintained an engaged though critical relationship to the
Marxist left until the end of his life, particularly during his time as
the political editor of the journal Les Temps modernes. |
メルロ=ポンティはそのキャリアを通じてマルクス主義に関与していた。
彼の1947年の著書『ヒューマニズムとテロル』は、ソ連の茶番裁判を擁護するものであると広く誤解されている[17]。実際、このテキストはソ連に関す
る見解の決定的な支持を避ける代わりに、自
由主義への批判としてマルクス主義の歴史理論に関わり、近代政治におけるヒューマニズムと恐怖の間の未解決のアンチノミー、すなわち人間の価値が暴力に
よってのみ達成できるならば、そして自由主義の考えが非自由主義の現実を隠しているなら、公正な政治的行動はどのように決められるのだろうか、
ということを明らかにするために書かれたものである[18]。 メルロ=ポンティは、特に雑誌『Les Temps
Modernes』の政治編集者であった時期、マルクス主義左派と批判的ではあったが、その関係を最後まで維持した[18]。 |
| Maurice Merleau-Ponty was born
in 1908 in Rochefort-sur-Mer, Charente-Inférieure (now
Charente-Maritime), France. His father died in 1913 when Merleau-Ponty
was five years old.[19] After secondary schooling at the Lycée
Louis-le-Grand in Paris, Merleau-Ponty became a student at the École
Normale Supérieure, where he studied alongside Jean-Paul Sartre, Simone
de Beauvoir, Simone Weil, Jean Hyppolite, and Jean Wahl. As Beauvoir
recounts in her autobiography, she developed a close friendship with
Merleau-Ponty and became smitten with him, but ultimately found him too
well-adjusted to bourgeois life and values for her taste. He attended
Edmund Husserl's "Paris Lectures" in February 1929.[20] In 1929,
Merleau-Ponty received his DES degree (diplôme d'études supérieures
[fr], roughly equivalent to a M.A. thesis) from the University of
Paris, on the basis of the (now-lost) thesis La Notion de multiple
intelligible chez Plotin ("Plotinus's Notion of the Intelligible
Many"), directed by Émile Bréhier.[21] He passed the agrégation in
philosophy in 1930. Merleau-Ponty was raised as a Roman Catholic. He was friends with the Christian existentialist author and philosopher Gabriel Marcel and wrote articles for the Christian leftist journal Esprit, but he left the Catholic Church in 1937 because he felt his socialist politics were not compatible with the social and political doctrine of the Catholic Church.[22] An article published in the French newspaper Le Monde in October 2014 makes the case of recent discoveries about Merleau-Ponty's likely authorship of the novel Nord. Récit de l'arctique (Grasset, 1928). Convergent sources from close friends (Beauvoir, Elisabeth "Zaza" Lacoin) seem to leave little doubt that Jacques Heller was a pseudonym of the 20-year-old Merleau-Ponty.[23] Merleau-Ponty taught first at the Lycée de Beauvais (1931–33) and then got a fellowship to do research from the Caisse nationale de la recherche scientifique [fr]. From 1934 to 1935 he taught at the Lycée de Chartres. He then in 1935 became a tutor at the École Normale Supérieure, where he tutored a young Michel Foucault and Trần Đức Thảo and was awarded his doctorate on the basis of two important books: La structure du comportement (1942) and Phénoménologie de la Perception (1945). During this time, he attended Alexandre Kojeve's influential seminars on Hegel and Aron Gurwitsch's lectures on Gestalt psychology. |
1908年、フランスのシャラント=アンフェリユール県(現シャラント
=マリティム県)のロシュフォール=シュル=メールに生まれる。パリのリセ・ルイ・ル・グランで中等教育を受けた後、高等師範学校の学生となり、ジャン=
ポール・サルトル、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、シモーヌ・ヴァイル、ジャン・ヒポリット、ジャン・ヴァールらと共に学んだ[19]。ボーヴォワールが
自伝で語っているように、彼女はメルロ=ポンティと親しい友人関係を築き、彼に夢中になったが、結局、ブルジョワの生活と価値観に適応しすぎていて、自分
の趣味には合わないと感じた。1929年2月、エドムンド・フッサールの「パリ講演会」に参加[20] 、パリ大学でDES(diplôme
d'études supérieures [fr]
、ほぼ修士号と同等)の学位を取得。1929年、エミール・ブレヒエの指導による論文「プロティヌスの知性的多数概念」(La Notion de
multiple intelligible chez Plotin)に基づいて、パリ大学からDESの学位を取得した[21]。 メルロ=ポンティはローマ・カトリック教徒として育てられた。キリスト教実存主義の作家・哲学者であるガブリエル・マルセルと親交があり、キリスト教左派 の雑誌『エスプリ』に記事を書いていたが、社会主義的な政治がカトリック教会の社会・政治教義と相容れないと感じ、1937年にカトリック教会を脱退した [22]。 2014年10月にフランスの新聞『ル・モンド』に掲載された記事では、メルロ=ポンティが小説『ノルド』の作者である可能性が高いことが近年発見された ことを事例として挙げている。Récit de l'arctique (Grasset, 1928)のことである。親しい友人たち(ボーヴォワール、エリザベート・"ザザ"・ラコワン)からの収斂した情報源は、ジャック・ヘラーが20歳のメル ロ=ポンティの偽名であることをほとんど疑わないようである[23]。 メルロ=ポンティはまずボーヴェのリセで教え(1931-33)、その後、国立科学研究費補助金[fr]から研究のためのフェローシップを受ける。 1934年から1935年にかけては、シャルトルのリセで教鞭をとった。その後、1935年にエコール・ノルマル・シュペリウールの講師となり、若き日の ミシェル・フーコーやトタン・ドゥック・タオを指導し、2冊の重要な著書をもとに博士号を授与された。La structure du comportement (1942) とPhénoménologie de la Perception (1945) の2冊の重要な著書に基づいて博士号を授与された。この間、アレクサンドル・コジェーヴのヘーゲルに関する影響力のあるセミナーや、アロン・グルヴィッチ のゲシュタルト心理学に関する講義を受講した。 |
| In the spring of 1939, he was
the first foreign visitor to the newly established Husserl Archives,
where he consulted Husserl's unpublished manuscripts and met Eugen Fink
and Father Hermann Van Breda. In the summer of 1939, as France declared
war on Nazi Germany, he served on the frontlines in the French Army,
where he was wounded in battle in June 1940. Upon returning to Paris in
the fall of 1940, he married Suzanne Jolibois, a Lacanian
psychoanalyst, and founded an underground resistance group with
Jean-Paul Sartre called "Under the Boot". He participated in an armed
demonstration against the Nazi forces during the liberation of
Paris.[24] After teaching at the University of Lyon from 1945 to 1948,
Merleau-Ponty lectured on child psychology and education at the
Sorbonne from 1949 to 1952.[25] He was awarded the Chair of Philosophy
at the Collège de France from 1952 until his death in 1961, making him
the youngest person to have been elected to a chair. Besides his teaching, Merleau-Ponty was also political editor for the leftist journal Les Temps modernes from its founding in October 1945 until December 1952. In his youth, he had read Karl Marx's writings[26] and Sartre even claimed that Merleau-Ponty converted him to Marxism.[27] While he was not a member of the French Communist Party and did not identify as a Communist, he laid out an argument justifying the Soviet farce trials and political violence for progressive ends in general in the work Humanism and Terror in 1947. However, about three years later, he renounced his earlier support for political violence, rejected Marxism, and advocated a liberal left position in Adventures of the Dialectic (1955).[28] His friendship with Sartre and work with Les Temps modernes ended because of that, since Sartre still had a more favourable attitude towards Soviet communism. Merleau-Ponty was subsequently active in the French non-communist left and in particular in the Union of the Democratic Forces. Merleau-Ponty died suddenly of a stroke in 1961 at age 53, apparently while preparing for a class on René Descartes, leaving an unfinished manuscript which was posthumously published in 1964, along with a selection of Merleau-Ponty's working notes, by Claude Lefort as The Visible and the Invisible. He is buried in Père Lachaise Cemetery in Paris with his mother Louise, his wife Suzanne and their daughter Marianne. |
1939年春、新設されたフッサール資料館に外国人として初めて訪れ、
フッサールの未発表原稿を閲覧し、オイゲン・フィンクやヘルマン・ヴァン・ブレダ神父に会った。1939年夏、フランスがナチス・ドイツに宣戦布告する
と、フランス軍の最前線に従軍し、1940年6月に戦場で負傷する。1940年秋にパリに戻ると、ラカン派の精神分析医シュザンヌ・ジョリボワと結婚し、
ジャン=ポール・サルトルとともに地下抵抗組織「ブーツの下」を設立する。1945年から1948年までリヨン大学で教鞭をとった後、1949年から
1952年までソルボンヌ大学で児童心理と教育について講義した[25]。1952年から1961年に亡くなるまでコレージュ・ド・フランスの哲学講座を
受け、史上最年少で講座に選出された。 また、1945年10月の創刊から1952年12月まで、左翼系雑誌『レ・タン・モダン』の政治編集長を務めた。若い頃、カール・マルクスの著作を読んで おり[26]、サルトルはメルロ=ポンティが自分をマルクス主義に改宗させたとさえ主張している[27]。 フランス共産党員ではなく、共産主義者であることも認めなかったが、1947年に著作『人倫と恐怖』でソ連の茶番裁判や進歩的目的のための政治暴力一般を 正当とする論点を打ち立てている。しかし、約3年後、『弁証法の冒険』(1955年)において、それまでの政治的暴力への支持を放棄し、マルクス主義を否 定し、自由主義左派の立場を主張する[28]... サルトルがソ連共産主義に対してより好意的態度をとっていたので、そのためにサルトルとの友情とレスタンプ・モデルンの仕事は終了した。その後、メルロ= ポンティはフランスの非共産主義左派、特に民主勢力連合で活動することになる。 1961年、ルネ・デカルトの講義の準備中に脳卒中で53歳の若さで急死したが、未完の原稿を残し、1964年にクロード・ルフォールが『可視と不可視』 として、メルロ=ポンティの作業メモの一部を添えて出版した。母ルイーズ、妻シュザンヌ、娘マリアンヌとともにパリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬されて いる。 |
| Consciousness In his Phenomenology of Perception (first published in French in 1945), Merleau-Ponty develops the concept of the body-subject (le corps propre) as an alternative to the Cartesian "cogito".[citation needed] This distinction is especially important in that Merleau-Ponty perceives the essences of the world existentially. Consciousness, the world, and the human body as a perceiving thing are intricately intertwined and mutually "engaged". The phenomenal thing is not the unchanging object of the natural sciences, but a correlate of our body and its sensory-motor functions. Taking up and "communing with" (Merleau-Ponty's phrase) the sensible qualities it encounters, the body as incarnated subjectivity intentionally elaborates things within an ever-present world frame, through use of its pre-conscious, pre-predicative understanding of the world's makeup. The elaboration, however, is "inexhaustible" (the hallmark of any perception according to Merleau-Ponty). Things are that upon which our body has a "grip" (prise), while the grip itself is a function of our connaturality with the world's things. The world and the sense of self are emergent phenomena in an ongoing "becoming". The essential partiality of our view of things, their being given only in a certain perspective and at a certain moment in time does not diminish their reality, but on the contrary establishes it, as there is no other way for things to be copresent with us and with other things than through such "Abschattungen" (sketches, faint outlines, adumbrations). The thing transcends our view, but is manifest precisely by presenting itself to a range of possible views. The object of perception is immanently tied to its background—to the nexus of meaningful relations among objects within the world. Because the object is inextricably within the world of meaningful relations, each object reflects the other (much in the style of Leibniz's monads). Through involvement in the world – being-in-the-world – the perceiver tacitly experiences all the perspectives upon that object coming from all the surrounding things of its environment, as well as the potential perspectives that that object has upon the beings around it. Each object is a "mirror of all others". Our perception of the object through all perspectives is not that of a propositional, or clearly delineated, perception; rather, it is an ambiguous perception founded upon the body's primordial involvement and understanding of the world and of the meanings that constitute the landscape's perceptual Gestalt. Only after we have been integrated within the environment so as to perceive objects as such can we turn our attention toward particular objects within the landscape so as to define them more clearly. This attention, however, does not operate by clarifying what is already seen, but by constructing a new Gestalt oriented toward a particular object. Because our bodily involvement with things is always provisional and indeterminate, we encounter meaningful things in a unified though ever open-ended world. |
意識(コンシャスネス) メルロ=ポンティは『知覚の現象学』(1945年にフランス語で発表)の中で、デカルトの「コギト」に代わるものとして身体主体(le corps propre)の概念を展開している[citation needed] この区別は、メルロ=ポンティが世界の本質を実在的に知覚する上でとりわけ重要である。意識、世界、そして知覚するものとしての人間の身体は複雑に絡み 合っており、相互に「関与」している。現象的なものは、自然科学の不変の対象ではなく、私たちの身体とその感覚運動機能の相関関係である。受肉した主体と しての身体は、出会った感覚的な質を取り込み、「交感」(メルロ=ポンティの言葉)しながら、世界の構成に関する前意識的、予見的理解を用いて、常に存在 する世界の枠内で意図的に物事を精緻化する。しかし、その精緻化は「無尽蔵」である(メルロ=ポンティによれば、あらゆる知覚の特徴である)。物とは、私 たちの身体が「握る」(prise)ものであり、握ること自体は、世界の物に対する私たちの接続性の関数である。世界と自己の感覚は、現在進行中の「なり ゆき」において出現する現象である。 私たちのものの見方が本質的に偏向していること、ある視点とある瞬間にしか与えられないことは、ものの実在性を弱めるものではなく、逆にそれを確立するも のである。なぜなら、ものが私たちと他のものと共在するためには、このような「Abschattungen」(スケッチ、かすかな輪郭、装飾)を通して以 外に方法はないからである。事物は我々の視界を超越しているが、可能な視界の範囲に自らを提示することによって、まさに顕在化しているのである。知覚の対 象は、その背景である、世界の中の対象間の意味ある関係の結びつきに内在的に結びつけられている。対象は意味ある関係の世界と表裏一体であるため、それぞ れの対象は他を反映する(ライプニッツのモナドによく似たスタイル)。世界に関与すること、すなわち「世界に存在すること」を通して、知覚者は、その環境 の周囲のすべてのものから来るその対象へのすべての視点と、その対象が周囲の存在に持つ潜在的な視点を暗黙のうちに経験する。 それぞれの対象は、「他のすべての鏡」なのである。むしろそれは、世界と風景の知覚のゲシュタルトを構成する意味に対する身体の原初的な関与と理解に基づ く曖昧な知覚なのである。私たちは環境の中に統合され、物体をそのように認識できるようになって初めて、風景の中の特定の物体に注意を向け、それらをより 明確に定義することができるようになる。しかし、この注意は、すでに見えているものを明確にするのではなく、特定の対象に向かって新しいゲシュタルトを構 築することによって行われる。私たちの身体的な関わりは常に暫定的で不確定なものであるため、私たちは統一された、しかし常に開放的な世界の中で意味のあ るものに出会うのである。 |
| The primacy of perception From the time of writing Structure of Behavior and Phenomenology of Perception, Merleau-Ponty wanted to show, in opposition to the idea that drove the tradition beginning with John Locke, that perception was not the causal product of atomic sensations. This atomist-causal conception was being perpetuated in certain psychological currents of the time, particularly in behaviourism. According to Merleau-Ponty, perception has an active dimension, in that it is a primordial openness to the lifeworld (the "Lebenswelt"). This primordial openness is at the heart of his thesis of the primacy of perception. The slogan of Husserl's phenomenology is "all consciousness is consciousness of something", which implies a distinction between "acts of thought" (the noesis) and "intentional objects of thought" (the noema). Thus, the correlation between noesis and noema becomes the first step in the constitution of analyses of consciousness. However, in studying the posthumous manuscripts of Husserl, who remained one of his major influences, Merleau-Ponty remarked that, in their evolution, Husserl's work brings to light phenomena which are not assimilable to noesis–noema correlation. This is particularly the case when one attends to the phenomena of the body (which is at once body-subject and body-object), subjective time (the consciousness of time is neither an act of consciousness nor an object of thought) and the other (the first considerations of the other in Husserl led to solipsism). The distinction between "acts of thought" (noesis) and "intentional objects of thought" (noema) does not seem, therefore, to constitute an irreducible ground. It appears rather at a higher level of analysis. Thus, Merleau-Ponty does not postulate that "all consciousness is consciousness of something", which supposes at the outset a noetic-noematic ground. Instead, he develops the thesis according to which "all consciousness is perceptual consciousness". In doing so, he establishes a significant turn in the development of phenomenology, indicating that its conceptualisations should be re-examined in the light of the primacy of perception, in weighing up the philosophical consequences of this thesis. |
知覚の優位性 メルロ=ポンティは『行動の構造』と『知覚の現象学』を執筆しているときから、ジョン・ロックに始まる伝統を牽引してきた考えと対立して、知覚は原子的感 覚の因果的産物ではないことを示したいと考えていた。この原子論的因果概念は、当時のある種の心理学的潮流、特に行動主義において永続していた。メルロ= ポンティによれば、知覚は、生命界(「Lebenswelt」)に対する根源的な開放性という能動的な次元を持っている。 この原初的な開放性が、知覚の原初性という彼のテーゼの核心である。フッサールの現象学のスローガンは「すべての意識は何かの意識である」であり、これは 「思考の行為」(ノエシス)と「思考の意図的対象」(ノエマ)の区別を意味する。したがって、ノエシスとノエマの相関関係は、意識分析の構成の第一歩とな る。しかし、メルロ=ポンティは、大きな影響を受け続けたフッサールの遺稿を研究する中で、フッサールの研究は、その進化の過程で、ノエシス-ノエマ相関 とは同化できない現象を浮かび上がらせていると指摘する。特に、身体(身体-主体であると同時に身体-客体である)、主観的時間(時間の意識は意識行為で も思考対象でもない)、他者(フッサールにおける他者の最初の考察は独在論につながった)の現象に注目するとき、このことが言える。 したがって、「思考行為」(ノエシス)と「思考の意図的対象」(ノエマ)の区別は、還元不可能な根拠を構成しているようには思われない。それはむしろ、よ り高次の分析レベルに現れるものである。したがって、メルロ=ポンティは、「すべての意識は何かの意識である」という、ノエシス-ノエマ的な根拠を最初か ら前提とするような仮定はしていない。その代わりに、「すべての意識は知覚的な意識である」というテーゼを展開する。そして、このテーゼの哲学的帰結を検 討する際に、知覚の優位性に照らして、現象学の概念化を再検討する必要があることを示唆している。 |
| Corporeity Taking the study of perception as his point of departure, Merleau-Ponty was led to recognize that one's own body (le corps propre) is not only a thing, a potential object of study for science, but is also a permanent condition of experience, a constituent of the perceptual openness to the world. He therefore underlines the fact that there is an inherence of consciousness and of the body of which the analysis of perception should take account. The primacy of perception signifies a primacy of experience, so to speak, insofar as perception becomes an active and constitutive dimension. Merleau-Ponty demonstrates a corporeity of consciousness as much as an intentionality of the body, and so stands in contrast with the dualist ontology of mind and body in Descartes, a philosopher to whom Merleau-Ponty continually returned, despite the important differences that separate them. In the Phenomenology of Perception Merleau-Ponty wrote: “Insofar as I have hands, feet, a body, I sustain around me intentions which are not dependent on my decisions and which affect my surroundings in a way that I do not choose” (1962, p. 440). |
コーポラリティ(身体性) メルロ=ポンティは、知覚の研究を出発点として、自分自身の身体(le corps propre)が単にモノであり、科学の研究対象となりうるだけでなく、経験の永続的条件、世界に対する知覚的開放の構成要素であることを認識するように なる。したがって、知覚の分析が考慮すべきは、意識と身体の不可分性であることを強調している。知覚の優位性は、知覚が能動的かつ構成的な次元となる限 り、いわば経験の優位性を意味する。 メルロ=ポンティは、意識の身体性を身体の意図性と同様に示しており、デカルトにおける心と身体の二元論的存在論と対照的である。メルロ=ポンティは『知 覚の現象学』の中で、「私に手と足と身体がある限り、私は私の決断に依存しない意図を私の周りに維持し、私が選択しない方法で私の周囲に影響を与える」 (1962、440頁)と書いている。 |
| Spatiality The question concerning corporeity connects also with Merleau-Ponty's reflections on space (l'espace) and the primacy of the dimension of depth (la profondeur) as implied in the notion of being in the world (être au monde; to echo Heidegger's In-der-Welt-sein) and of one's own body (le corps propre).[29] Reflections on spatiality in phenomenology are also central to the advanced philosophical deliberations in architectural theory.[30] |
空間性 身体性に関する問題は、メルロ=ポンティの空間(l'espace)に関する考察や、世界における存在(être au monde;ハイデガーのIn-der-Welt-sein)と自分自身の身体(le corps propre)の概念に暗示される深さの次元の優先性とも結びついている[29] 。現象学における空間性に関する考察は、建築理論における高度な哲学的検討の中心でもある[30]。 |
| Language The highlighting of the fact that corporeity intrinsically has a dimension of expressivity which proves to be fundamental to the constitution of the ego is one of the conclusions of The Structure of Behavior that is constantly reiterated in Merleau-Ponty's later works. Following this theme of expressivity, he goes on to examine how an incarnate subject is in a position to undertake actions that transcend the organic level of the body, such as in intellectual operations and the products of one's cultural life. He carefully considers language, then, as the core of culture, by examining in particular the connections between the unfolding of thought and sense—enriching his perspective not only by an analysis of the acquisition of language and the expressivity of the body, but also by taking into account pathologies of language, painting, cinema, literature, poetry, and music. This work deals mainly with language, beginning with the reflection on artistic expression in The Structure of Behavior—which contains a passage on El Greco (p. 203ff) that prefigures the remarks that he develops in "Cézanne's Doubt" (1945) and follows the discussion in Phenomenology of Perception. The work, undertaken while serving as the Chair of Child Psychology and Pedagogy at the University of the Sorbonne, is not a departure from his philosophical and phenomenological works, but rather an important continuation in the development of his thought. As the course outlines of his Sorbonne lectures indicate, during this period he continues a dialogue between phenomenology and the diverse work carried out in psychology, all in order to return to the study of the acquisition of language in children, as well as to broadly take advantage of the contribution of Ferdinand de Saussure to linguistics, and to work on the notion of structure through a discussion of work in psychology, linguistics and social anthropology. |
言語 身体性が本質的に表現性の次元を持ち、それが自我の構成にとって基本的であることを強調したことは、『行動の構造』の結論の一つであり、その後のメルロ= ポンティの著作で常に繰り返される。この表現力のテーマに続いて、彼は、受肉した主体が、知的活動や文化的生活の産物など、身体の有機的なレベルを超えた 行為を行う立場にあることを検証していく。 そして、言語の獲得と身体の表現力の分析だけでなく、言語、絵画、映画、文学、詩、音楽などの病理を考慮しながら、特に思考の展開と感覚の関連性を検討 し、文化の核である言語を注意深く考察していくのである。 この著作は、主に言語を扱い、『行動の構造』の芸術表現に関する考察から始まる。この中にあるエル・グレコに関する一節(203ff)は、『セザンヌの疑 惑』(1945)で展開する発言の前触れであり、『知覚の現象学』の議論に続くものである。ソルボンヌ大学で児童心理学・教育学の講座を担当しながら取り 組んだこの作品は、彼の哲学的・現象学的著作からの逸脱ではなく、むしろ彼の思想展開における重要な継続である。 ソルボンヌ大学での講義の概要が示すように、この時期、彼は現象学と心理学における多様な研究との対話を続け、子どもの言語習得の研究に立ち戻るととも に、フェルディナン・ド・ソシュールの言語学への貢献を広く活用し、心理学、言語学、社会人類学の研究の議論を通じて構造という概念に取り組んでいるので ある。 |
| Art Merleau-Ponty distinguishes between primary and secondary modes of expression. This distinction appears in Phenomenology of Perception (p. 207, 2nd note [Fr. ed.]) and is sometimes repeated in terms of spoken and speaking language (le langage parlé et le langage parlant) (The Prose of the World, p. 10). Spoken language (le langage parlé), or secondary expression, returns to our linguistic baggage, to the cultural heritage that we have acquired, as well as the brute mass of relationships between signs and significations. Speaking language (le langage parlant), or primary expression, such as it is, is language in the production of a sense, language at the advent of a thought, at the moment where it makes itself an advent of sense. It is speaking language, that is to say, primary expression, that interests Merleau-Ponty and which keeps his attention through his treatment of the nature of production and the reception of expressions, a subject which also overlaps with an analysis of action, of intentionality, of perception, as well as the links between freedom and external conditions. The notion of style occupies an important place in "Indirect Language and the Voices of Silence". In spite of certain similarities with André Malraux, Merleau-Ponty distinguishes himself from Malraux in respect to three conceptions of style, the last of which is employed in Malraux's The Voices of Silence. Merleau-Ponty remarks that in this work "style" is sometimes used by Malraux in a highly subjective sense, understood as a projection of the artist's individuality. Sometimes it is used, on the contrary, in a very metaphysical sense (in Merleau-Ponty's opinion, a mystical sense), in which style is connected with a conception of an "über-artist" expressing "the Spirit of Painting". Finally, it sometimes is reduced to simply designating a categorization of an artistic school or movement. (However, this account of Malraux's notion of style—a key element in his thinking—is open to serious question.[31]) For Merleau-Ponty, it is these uses of the notion of style that lead Malraux to postulate a cleavage between the objectivity of Italian Renaissance painting and the subjectivity of painting in his own time, a conclusion that Merleau-Ponty disputes. According to Merleau-Ponty, it is important to consider the heart of this problematic, by recognizing that style is first of all a demand owed to the primacy of perception, which also implies taking into consideration the dimensions of historicity and intersubjectivity. (However, Merleau-Ponty's reading of Malraux has been questioned in a recent major study of Malraux's theory of art which argues that Merleau-Ponty seriously misunderstood Malraux.)[32] For Merleau-Ponty, style is born of the interaction between two or more fields of being. Rather than being exclusive to individual human consciousness, consciousness is born of the pre-conscious style of the world, of Nature. |
アート メルロ=ポンティは表現の様式を一次的なものと二次的なものに区別している。この区別は『知覚の現象学』(p. 207, 2nd note [Fr. ed.])に現れ、話し言葉と話し言葉(le langage parlé et le langage parlant)という言葉で繰り返されることもある(『世界の散文』p. 10)。話す言語(le langage parlé)、つまり二次的表現は、私たちの言語的荷物、私たちが獲得した文化的遺産、そして記号と意義の間の関係のブルートマスに立ち戻ることになる。 話す言語(le langage parlant)、つまり一次表現は、そのようなものであり、感覚の生産における言語、思考の到来における言語、それ自体が感覚の到来となる瞬間の言語で ある。 メルロ=ポンティが関心を寄せ、表現の生成と受容の本質を扱うことで注意を引きつけるのは、言葉を話すこと、つまり一次表現であり、このテーマは、行為、 意図性、知覚の分析、さらには自由と外部条件との関連にも重なるものである。 スタイルという概念は、「間接言語と沈黙の声」において重要な位置を占めている。メルロ=ポンティは、アンドレ・マルローとある種の共通点を持ちながら も、マルローの『沈黙の声』で採用されている3つのスタイル概念に関して、マルローと自らを区別している。メルロ=ポンティは、この作品において、マル ローが「スタイル」を極めて主観的な意味で使うことがあり、それは芸術家の個性の投影として理解されている、と指摘する。逆に、非常に形而上学的な意味 (メルロ=ポンティの考えでは、神秘的な意味)で使われることもあり、その場合、スタイルは「絵画の精神」を表現する「超芸術家」の概念と結びつけられて いる。また、芸術の流派や運動の分類を意味するものに還元されることもある。(しかし、マルローの思考の重要な要素であるスタイルについてのこの説明に は、重大な疑問がある[31]。 メルロ=ポンティは、マルローがイタリア・ルネサンス絵画の客観性と同時代の絵画の主観性の間に断絶があるとするのは、こうしたスタイル概念の使用による ものであり、この結論にメルロ=ポンティは異を唱えている。メルロ=ポンティによれば、様式とはまず知覚の優位に起因する要求であり、歴史性や間主観性の 次元を考慮することが重要であるとして、この問題の核心を考察している。(しかし、メルロ=ポンティのマルローに対する読みは、マルローの芸術論に関する 最近の主要な研究において、メルロ=ポンティがマルローを著しく誤解していると主張することによって疑問視されている)[32] メルロ=ポンティにとって、スタイルは2つ以上の存在の場の間の相互作用から生まれるものである。意識は人間の個人的な意識に独占されるのではなく、世界 や自然の前意識的なスタイルから生まれるのである。 |
| Science In his essay Cézanne's Doubt, in which he identifies Paul Cézanne's impressionistic theory of painting as analogous to his own concept of radical reflection, the attempt to return to, and reflect on, prereflective consciousness, Merleau-Ponty identifies science as the opposite of art. In Merleau-Ponty's account, whereas art is an attempt to capture an individual's perception, science is anti-individualistic. In the preface to his Phenomenology of Perception, Merleau-Ponty presents a phenomenological objection to positivism: that it can tell us nothing about human subjectivity. All that a scientific text can explain is the particular individual experience of that scientist, which cannot be transcended. For Merleau-Ponty, science neglects the depth and profundity of the phenomena that it endeavors to explain. Merleau-Ponty understood science to be an ex post facto abstraction. Causal and physiological accounts of perception, for example, explain perception in terms that are arrived at only after abstracting from the phenomenon itself. Merleau-Ponty chastised science for taking itself to be the area in which a complete account of nature may be given. The subjective depth of phenomena cannot be given in science as it is. This characterizes Merleau-Ponty's attempt to ground science in phenomenological objectivity and, in essence, to institute a "return to the phenomen |
科学 メルロ=ポンティは、ポール・セザンヌの印象派的な絵画理論を、彼自身のラディカル な反省、つまり反省以前の意識に戻り、反省しようとする概念と類似しているとした論文『セザンヌの疑惑』で、科学を芸術の対極にあるものと している。メルロ=ポンティの説明では、芸術が個人の知覚を捉えようとするものであ るのに対し、科学は反個人主義的である。メルロ=ポンティは『知覚の現象学』の序文で、実証主義に対する現象学的な反論として、実証主義は 人間の主観性について何も語ることができないと述べている。科学的な文章が説明できるのは、その科学者の個人的な経験だけであり、それを超越することはで きないのである。メルロ=ポンティにとって、科学は、説明しようとする現象の深さ、奥深さを無視するものである。 メルロ=ポンティは、科学が事後的な抽象化であると理解していた。例えば、知覚に関する因果的、生理学的な説明は、現象そのものを抽象化した後に初めて到 達する言葉で知覚を説明する。メルロ=ポンティは、科学が自らを自然を完全に説明できる領域だと考えていることを非難した。科学では、現象の主観的な深み をそのまま与えることはできない。このことは、科学を現象学的客観性に立脚させ、「現象への回帰」を実現しようとするメルロ=ポンティの試みを特徴づけて いる。 |
| Anticognitivist cognitive science Merleau-Ponty's critical position with respect to science was stated in his Preface to the Phenomenology: he described scientific points of view as "always both naive and at the same time dishonest". Despite, or perhaps because of, this view, his work influenced and anticipated the strands of modern psychology known as post-cognitivism. Hubert Dreyfus has been instrumental in emphasising the relevance of Merleau-Ponty's work to current post-cognitive research, and its criticism of the traditional view of cognitive science. Dreyfus's seminal critique of cognitivism (or the computational account of the mind), What Computers Can't Do, consciously replays Merleau-Ponty's critique of intellectualist psychology to argue for the irreducibility of corporeal know-how to discrete, syntactic processes. Through the influence of Dreyfus's critique and neurophysiological alternative, Merleau-Ponty became associated with neurophysiological, connectionist accounts of cognition. With the publication in 1991 of The Embodied Mind by Francisco Varela, Evan Thompson, and Eleanor Rosch, this association was extended, if only partially, to another strand of "anti-cognitivist" or post-representationalist cognitive science: embodied or enactive cognitive science, and later in the decade, to neurophenomenology. In addition, Merleau-Ponty's work has also influenced researchers trying to integrate neuroscience with the principles of chaos theory.[33] It was through this relationship with Merleau-Ponty's work that cognitive science's affair with phenomenology was born, which is represented by a growing number of works, including Ron McClamrock, Existential Cognition: Computational Minds in the World (1995) Andy Clark, Being There (1997) Jean Petitot et al. (eds.), Naturalizing Phenomenology (1999) Alva Noë, Action in Perception (2004) Shaun Gallagher, How the Body Shapes the Mind (2005) Franck Grammont, Dorothée Legrand, and Pierre Livet (eds.), Naturalizing Intention in Action (2010) The journal Phenomenology and the Cognitive Sciences. |
反認知主義的認知科学 メルロ=ポンティの科学に対する批判的な立場は、『現象学』序文に記されている。このような見解にもかかわらず、あるいはそれゆえに、彼の研究は、ポスト 認知主義と呼ばれる現代心理学の諸系統に影響を与え、先取りした。ドレフュスは、メルロ=ポンティの研究が現在のポスト認知研究との関連性を強調し、従来 の認知科学に対する批判に力を発揮している。 ドレフュスによる認知主義(あるいは心の計算論的説明)に対する代表的な批判である『コンピュータにできないこと』は、メルロ=ポンティの知的心理学に対 する批判を意識的に再現し、身体的ノウハウが個別の構文プロセスに対して還元不可能であることを主張している。ドレフュスの批判と神経生理学的な代替案の 影響により、メルロ=ポンティは神経生理学的な接続論的な認知の説明と関連づけられるようになった。 また、1991年に出版されたFrancisco Varela, Evan Thompson, Eleanor Roschによる『The Embodied Mind』によって、この関連は部分的ではあるが、「反認知主義」あるいはポスト表象主義の認知科学である身体的あるいは行動的認知科学、そして10年後 には神経現象学へと拡大されることになった。さらにメルロ=ポンティの作品は、神経科学をカオス理論の原理と統合しようとする研究者にも影響を与えている [33]。 認知科学の現象学との関わりはメルロ=ポンティの作品との関係を通じて生まれたものであり、それは以下のような作品に代表されるように増えている。 ロン・マクラムロック『実存的認知』。ロン・マクラムロック『実存的認知:世界の中の計算機的思考』(1995) アンディ・クラーク『そこにいること』(1997) ジャン・プティト他編『現象学の自然化』(1999年 アルヴァ・ノエ『知覚の中の行為』(2004年) ショーン・ギャラガー『身体はいかにして精神を形成するか』(2005年) フランク・グランモン、ドロテ・ルグラン、ピエール・リヴェ(編)『行為における意図の帰化』(2010年) 「現象学と認知科学」誌 |
| Feminist philosophy Merleau-Ponty has also been picked up by Australian and Nordic philosophers inspired by the French feminist tradition, including Rosalyn Diprose and Sara Heinämaa [fi]. Heinämaa has argued for a rereading of Merleau-Ponty's influence on Simone de Beauvoir. (She has also challenged Dreyfus's reading of Merleau-Ponty as behaviorist[citation needed], and as neglecting the importance of the phenomenological reduction to Merleau-Ponty's thought.) Merleau-Ponty's phenomenology of the body has also been taken up by Iris Young in her essay "Throwing Like a Girl," and its follow-up, "'Throwing Like a Girl': Twenty Years Later". Young analyzes the particular modalities of feminine bodily comportment as they differ from that of men. Young observes that while a man who throws a ball puts his whole body into the motion, a woman throwing a ball generally restricts her own movements as she makes them, and that, generally, in sports, women move in a more tentative, reactive way. Merleau-Ponty argues that we experience the world in terms of the "I can" – that is, oriented towards certain projects based on our capacity and habituality. Young's thesis is that in women, this intentionality is inhibited and ambivalent, rather than confident, experienced as an "I cannot". |
フェミニスト哲学 メルロ=ポンティは、ロザリン・ディプロスやサラ・ハイナマーなど、フランスのフェミニストの伝統に影響を受けたオーストラリアや北欧の哲学者たちにも取 り上げられている[fi]。 ハイナマーは、シモーヌ・ド・ボーヴォワールに対するメルロ=ポンティの影響の再読を主張している(彼女はまた、ドレフュールに対しても異議を唱えてい る)。(また、ドレフュスによるメルロ=ポンティの読解は行動主義的であり[citation needed]、メルロ=ポンティの思想における現象学的還元の重要性を無視しているとして異議を唱えている)。 メルロ=ポンティの身体の現象学は、アイリス・ヤングのエッセイ「Throwing Like a Girl」およびその続編「『Throwing Like a Girl』」でも取りあげられている。20年後)」である。ヤングは、男性とは異なる女性特有の身体的態様を分析している。ヤングは、ボールを投げる男性 が全身全霊でその動作に取り組むのに対し、女性がボールを投げる場合、一般的に自分の動きを制限しながら行うこと、また、一般的にスポーツにおいて、女性 はより暫定的で反応的な方法で動くことを観察している。メルロ=ポンティは、私たちは「できる」という観点から世界を経験する、つまり、私たちの能力と習 慣性に基づいて、ある特定のプロジェクトに向いていると論じている。ヤングの論文は、女性の場合、この意図性が抑制され、両義的であり、むしろ自信に満ち ており、「私にはできない」として経験されるというものである。 |
| Ecophenomenology Ecophenomenology can be described as the pursuit of the relationalities of worldly engagement, both human and those of other creatures (Brown & Toadvine 2003). This engagement is situated in a kind of middle ground of relationality, a space that is neither purely objective, because it is reciprocally constituted by a diversity of lived experiences motivating the movements of countless organisms, nor purely subjective, because it is nonetheless a field of material relationships between bodies. It is governed exclusively neither by causality, nor by intentionality. In this space of in-betweenness, phenomenology can overcome its inaugural opposition to naturalism.[34] David Abram explains Merleau-Ponty's concept of "flesh" (chair) as "the mysterious tissue or matrix that underlies and gives rise to both the perceiver and the perceived as interdependent aspects of its spontaneous activity", and he identifies this elemental matrix with the interdependent web of earthly life.[35] This concept unites subject and object dialectically as determinations within a more primordial reality, which Merleau-Ponty calls "the flesh" and which Abram refers to variously as "the animate earth", "the breathing biosphere" or "the more-than-human natural world". Yet this is not nature or the biosphere conceived as a complex set of objects and objective processes, but rather "the biosphere as it is experienced and lived from within by the intelligent body — by the attentive human animal who is entirely a part of the world that he or she experiences. Merleau-Ponty's ecophenemonology with its emphasis on holistic dialog within the larger-than-human world also has implications for the ontogenesis and phylogenesis of language; indeed he states that "language is the very voice of the trees, the waves and the forest".[36] Merleau-Ponty himself refers to "that primordial being which is not yet the subject-being nor the object-being and which in every respect baffles reflection. From this primordial being to us, there is no derivation, nor any break..."[37] Among the many working notes found on his desk at the time of his death, and published with the half-complete manuscript of The Visible and the Invisible, several make it evident that Merleau-Ponty himself recognized a deep affinity between his notion of a primordial "flesh" and a radically transformed understanding of "nature". Hence, in November 1960 he writes: "Do a psychoanalysis of Nature: it is the flesh, the mother."[38] And in the last published working note, written in March 1961, he writes: "Nature as the other side of humanity (as flesh, nowise as 'matter')."[39] This resonates with the conception of space, place, dwelling, and embodiment (in the flesh and physical, vs. virtual and cybernetic), especially as they are addressed against the background of the unfolding of the essence of modern technology. Such analytics figure in a Heideggerian take on “econtology” as an extension of Heidegger's consideration of the question of being (Seinsfrage) by way of the fourfold (Das Geviert) of earth-sky-mortals-divinities (Erde und Himmel, Sterblichen und Göttlichen). In this strand of “ecophenomenology”, ecology is co-entangled with ontology, whereby the worldly existential analytics are grounded in earthiness, and environmentalism is orientated by ontological thinking.[40] |
エコフェノメノロジー エコフェノメノロジーとは、人間や他の生き物の世界との関わりの関係性を追求することだといえる(Brown & Toadvine 2003)。 この関わりは、ある種の関係性の中間領域に位置している。この空間は、無数の生物の動きを動機づける多様な生活体験によって相互に構成されているため、純 粋に客観的でもなければ、それにもかかわらず身体間の物質的関係の場であるため、純粋に主観的にもなりえない。それは、因果関係にも意図性にも支配されて いない。この中間性の空間において、現象学は自然主義に対する発足以来の対立を克服することができる[34]。 デヴィッド・エイブラムはメルロ=ポンティの「肉」(椅子)の概念を「その自発的な活動の相互依存的な側面として知覚する者と知覚される者の両方を下支え し、生じさせる不思議な組織やマトリックス」として説明しており、この要素マトリックスを地上の生命の相互依存的な網と同定している[35]。 [この概念は、メルロ=ポンティが「肉」と呼び、アブラムが「生気ある地球」、「呼吸する生物圏」、「人間以上の自然界」と様々に呼ぶ、より根源的な現実 における決定として弁証法的に主体と客体を一体化させるものである。しかし、これは複雑な物体や客観的プロセスの集合として捉えられた自然や生物圏ではな く、「知的な身体によって、つまり、注意深い人間という動物によって内側から経験され、生きている生物圏であり、その動物が経験する世界の完全に一部であ る」。人間よりも大きな世界の中での全人的な対話を強調するメルロ=ポンティのエコフェネモロジーは言語の存在論と系統論にも含意を持っている。実際彼は 「言語は木々、波、森の声そのものである」と述べている[36]。 メルロ=ポンティ自身は「まだ主体的存在でもなく客体的存在でもない、あらゆる点で 内省を阻むその原初的存在」に言及している。この根源的な存在から我々への派生も断絶もない...」[37] 彼の死の際に机上で発見され、『見えるものと見えないもの』の半完成原稿とともに公表された多くの作業メモの中には、メルロ=ポンティ自身が根源的な「肉」の概念と「自然」の根本的に変換した理解の間の深い親和性を認めていたことが明 らかになるものがいくつかある。それゆえ、1960年11月に彼は「自 然の精神分析を行う:それは肉であり、母である」と書いている[38]。そして1961年3月に書かれた最後の出版された作業メモにおいて 彼は「人間の反対側としての自然(肉として、今や「物質」として)」と書いている[39]。 「これは、空間、場所、住居、身体性(肉体と物理的なもの、対仮想とサイバネティックなもの)の概念と共鳴し、特にそれらが近代技術の本質の展開を背景と して扱われるとき、共鳴する。このような分析は、ハイデガーが地球-空-死者-神 (Erde und Himmel, Sterblichen und Göttlichen)の4重(Das Geviert)を介して存在(Seinsfrage)の問題を考察した延長として、「生態学」をハイデガー的に捉えたものとして図式化さ れています。このような「エコ現象学」においては、生態学は存在論と共絡みしており、それによってこの世の実存的な分析が地球性に根ざし、環境主義が存在論的思考によって方向付けられる[40]。 |
| ・2つの対立概念、すなわち「主知主義(観念論)」と「経験主義(実在
論)」のそれぞれに内在的批判とその乗り越えをめざす。 |
|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Merleau-Ponty |
|
| Affordance Autopoiesis Body schema Difference (philosophy) Embodied cognition Embodied phenomenology Emergence Enactivism Gestalt psychology Habit Hylomorphism Incarnation Invagination (philosophy) Perspectivism Process philosophy Reflexivity Umwelt Virtuality (philosophy) |
アフォーダンス オートポイエーシス 身体スキーマ 差異(哲学) 身体化された認知 身体化された現象学 創発 エンアクティビズム ゲシュタルト心理学 習慣 物質形態論 受肉 内陥(哲学) 視点主義 プロセス哲学 反省性 ウンベルト 仮想性(哲学) |
英訳されている文献リスト
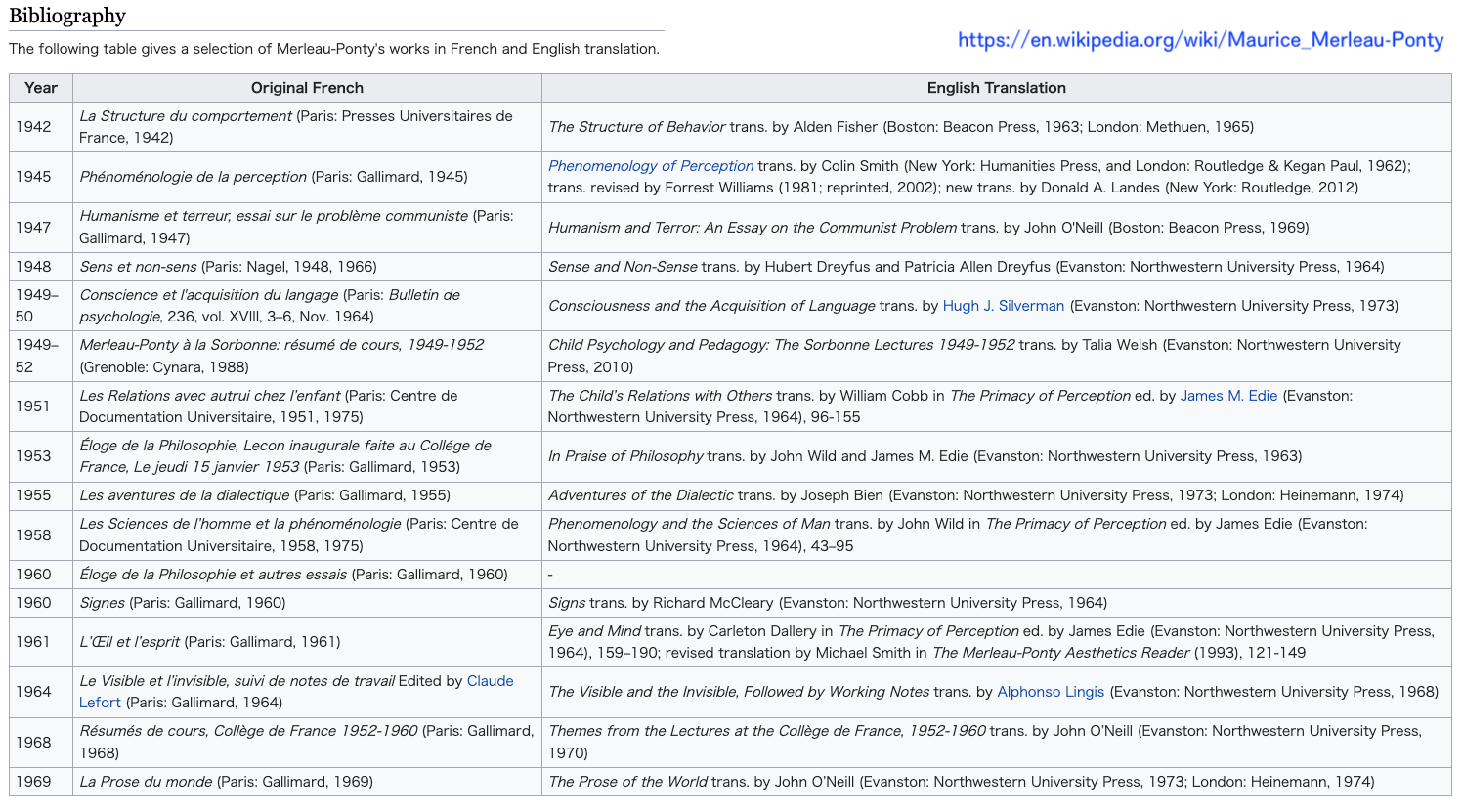
【知覚の現象学】からの引用
[足立和浩によるコトバンク解説より] 「フランスの哲学者モーリス・メル ロ=ポンティ(Maurice Jean Jacques Merleau-Ponty, 1908-1961)の初期の最重要著作。フッサール現象学の 諸成果を踏まえ、またそれを独創的に解釈し直しつつ、主として「身体」の問題に定位しながら、西欧の伝統的な二元論的発想――精神/身体、主観/客観、観 念論/実在論など――を克服しようとした。知覚についての伝統的な二つの考え方――主知主義と経験主義――が退けられたのちに「現象野」のうちに現れてく る「世界-内-存在」としての身体は、単なる物質的、物理的な客体なのではなく、まさしく人間と世界、主体と客体とが戯れ合う「両義性」の場である。身体 の両義性を強調することによって、デカルト以来の対自(精神)と即自 (身体・物体)との二元論的把握を転覆しようとの戦略である」
【世界-内-存在】[加國尚志によるコト バンク解説より]「世界-内-存在あるいは世界=内=存在は、ハイデガー(あるいはハイデッガー) の哲学用語である。マルティン・ハイデッガーは『存在と時間』で、存在の意味を問う 存在者を「現存在 Dasein」と呼び、その存在論的分析を 通じて、存在の問題を時間性から解釈することによって西洋の伝統的な存在論の解体を企てた。ここでの現存在はやはり人間の実存であるが、その際、現存在は、伝統的な主観性概念と 区別されて「世界-内-存在」と規定される。現存在はいつもすでに世界の内に投げ入れられて、気分づけられており、この世界の内から投企を行うのである。 もっともここで「世界」といっても、物理的客観の総体のことではないし、「内」といっても物理的空間内部にあるという意味ではない。ハイデッガーのいう「世界」とは意味や記号が連関している世界のことであり、たとえば道具が何らかの使用目的のために存在しているように(→本当か?池田)、現存在の配慮に応じて規定される世界のことである。したがって、世界内に存在す るということは、空間の中に事物のように位置づけられているということではなく、意 味連関の総体としての世界に慣れ親しんで内属しつつ、前学問的な存在了解を行いつつ実存しているということである。この意味で、存在を了解する可能性をもつ「世界-内-存在」と、この了解可能性を根拠として現存在が世界内部で出会わされる「世界内部的存在者」とは厳しく区別さ れねばならない。 現存在は、こうして世界-内-存在として、意味連関の総体としての 世界に、日常的に気分づけられて存在しながら、もっぱら誰でもない平均的な「ひと das Man」として非本来的に実存している。『存在と時間』の後半部は、このような世界-内-存在としての現存在が死への先駆的決意によって、不安の中で本来の有限な自己に立ち帰り、そこから本来的な時間性と して開示されてくるありさま(→所詮「ロマン主義」ではないか?池田)を描いている。世界-内-存在が本来的な時間性として開示されるに応じて、現存在の歴史性も自覚されることになる。世界-内-存在は歴史的に存在するのであり、『存在と時間』は、世界-内-存在の本来性と本来的な歴史の在り方の結びつきを、先駆的な決意によってもたらされる根源的な時間性 からとらえようとした著作なのである。 「世界-内-存在」の概念は、ジャン・ポール・サルトルが『存在と無』で、モーリス・メルロ・ポンティが『知覚の現象学』で用い、フランス実存主義哲学にも大きく影響した。 [加國尚志] 『マルティン・ハイデッガー著、細谷貞雄訳『存在と時間』(ちくま学芸文庫)』▽ 『木田元著『ハイデガー』(岩波現代文庫)』」
【章立て】中島盛夫訳に準拠(→「メルロ=ポンティと『知覚の現象学』」 「知覚の現象学」)
| 序文 緒論 古典的偏見と現象への復帰 0. 1. 「感覚」 0. 2. 「連合」と「追憶の投射」 0. 3. 「注意」と「判断」 0. 4. 現象の領野) 第1部 身体 1. 1. 客体としての身体と機械論的生理学 1. 2. 身体の経験と古典的心理学 1. 3. 自己の身体の空間性と運動機能 1. 4. 自己の身体の総合 1. 5. 性的存在としての身体 1. 6. 表現としての身体と言葉 第2部 知覚された世界 2. 1. 感覚すること 2. 2. 空間 2. 3. 物と自然的世界 2.4. 他人と人間的世界 第3部 対自存在と世界における(への)存在 3. 1. コギト 3. 2. 時間性 3. 3. 自由 |
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆