
アーレント暴力論:まとめ
Summary:
Hannah Arendt's concept of violence

暴力について(ハンナ・アレントの4つのテーゼ)[on violence in pdf with password]
『全体主義の起源』エピローグ「イデオロ ギーとテロル」
「イデオロギーは、それぞれの理念に固有 の論理をもとにして、歴史過程の全体の謎、過去の秘密、現在の込み入った状況、未来の予測できない事柄 ——を知っていると主張する……。人びとをたがいに圧迫させるあ うことで、絶対的テロルは彼らの間の空間を破壊する。その鉄のたがのなかの状態に比べれば、専制政治の砂漠でさ えも、それが何らかの空間であるかぎりは自由の保証のように思われる」 引用は(ヤング=ブルーエル 1999:347)[→出典]
このことの理論的含意について考えるの
が、このページの目的である。
====
《暴力と平和の「意味の四角形」》——我
々の常識
近代国家や平和学における「暴力」に対立
する概念は「非暴力」である。そして、非暴力のコノテーションこそが「平和」ないしは「平和的状態」で
ある。従って、これをグレマスの意味の四角形に議論に落とし込む
と、暴力の矛盾項は「平和」であり、暴力が存在する平和な状態は存在しない、という我々
が日常で抱く常識的な概念のマッチングができあがる。ここから導かれるのが権力(パワー)であり、それは権威が管理する暴力装置、例えば警察や(治安出動
を目的とする)軍隊とコノテートすることで、暴力装置に正当性が与えられる。これが我々の考える、暴力——権力による暴力装置——非暴力——平和という4
つの項目の関係性である。(→応用問題としてガルトゥングの「構造的暴力」
を考えてみよ!)
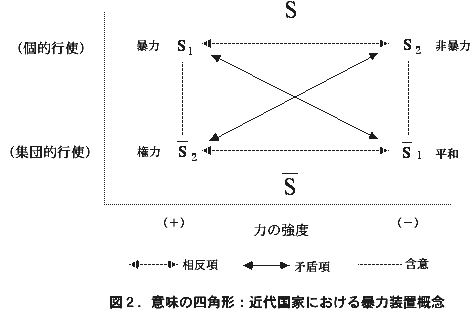
この暴力(=戦争状態)を自然状態とみる
見方は、イマヌエル・カントと軌を一にしている。つまり「カントの努力の全幅は、自然状態に代えて法治
状態を、つまり戦争には訴訟が、戦勝には訴訟判決が取ってかわるであろうような法治状態をもたらすことにある」(ラクロワ 1971:16)。
====
《暴力と権威は共存しないというハンナ・ アーレントの「意味の四角形」》——K・シュミットとは異なる「暴力を手中にする」方法について
上記の暴力と平和の「意味の四角形」とい う我々の常識に疑問符を付すのがハンナ・アーレントの暴力論である。アーレントにとって、暴力の反対概 念は、権威である。つまり、彼女によると、権威のあるところに暴力は存在しない。この権威は、グラムシのいうヘゲモニー概念にある種近いものかもしれない。権威とコノテートするのが権力である。 この点は、我々と承服するところだろう。というか、権威と権力の合致こそがヘゲモニーの確立を意味するからだ。このような意味の導出は、暴力と権力を矛盾 項の関係として定義する。権力はしばしば、抑圧的権力を権力そのものであると感じる人はまさに暴力の権化のようだ。しかし、権威が確立しているところに権 力は機能しているという(我々が具有する)スタティックな社会観を経由すると、それは確かに、権力は(暴力を独占しているがゆえに、暴力の自由な発露(= 「万人の万人に対する闘争」)を禁止する。したがって、彼女の指摘は、異様なものではなく、近代啓蒙主義の始祖の一人にも数えられるホッブス(→さまざまな国家論)の権力行使論と齟齬をきたさない。そして、さらに隠された第四項には、 革命が存在する。これによると革命と暴力はコノテーション関係であり、これも歴史的事実としては理解可能である。そして革命は権力と相反するわけだから、 革命は、既存の権力を否定する意味で相反なものであり、革命後には権威による支配が確立するが、革命という現在進行形の状態は権力掌握を通して権威を希求 するものであり、権威と革命は矛盾項の関係にある(革命は既存の権威構造を物理的かつ象徴的に破壊するからである)。
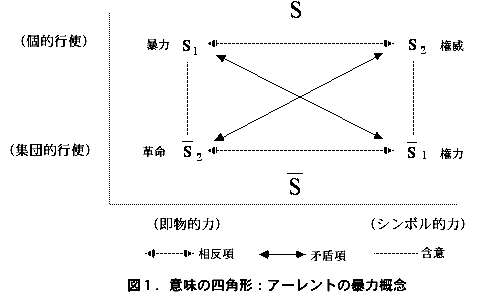
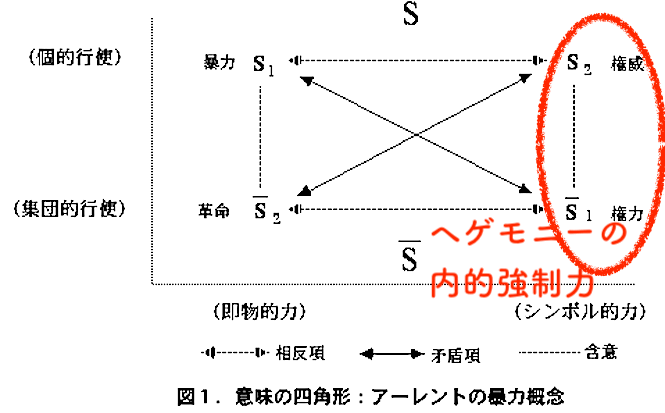
これらの関係についてのより詳しい関係は 次のページにある:池田光穂「政治的暴力の概念」
リンク
====
・Naumann, Bernd. 1966. Auschwitz. New York: Frederick A. Praeger. のアーレントの序文より 「アウシュヴィツツでは、だれもが善になるか悪になるかを自分で決めることができたということである……。そしてこの決定は、ユダヤ人であるかポーランド 人であるかドイツ人であるかにけっして関わりがなかった。またSS の隊員であることにすら関わりがなかった」引用は(ヤング=ブルーエル 1999:490)[→出 典]
・Naumann, Bernd. 1966. Auschwitz. New York: Frederick A. Praeger. のアーレントの序文より
「被告が臨床的に正常であるにもかかわらず、アウシュヴィッツでの最大の人間的要素はサディズムであった。そしてサディズムは基本的に性的 である。……アウシュヴィッツの人間的要素に関するかぎり、二番目に重要なものは、おそらくまったくの気まぐれであったにちがいない。……彼等の絶えず変 る気分は、すべての実体的中身を——善いか悪いか、優しいか残忍か、「理想主義的」阿呆か皮肉屋の性的倒錯者かというような個人のアイデンティティの堅固 な外面を——破壊してしまったかのようであった。もっとも重い判決の一つ——終身プラス八年——を当然に受けた同じ人物が、ときには子供にソーセージを分 け与えることもあった。ベナレクは、囚人たちを踏みつけて殺すという特技をやった後、部屋へ戻って祈った。それは彼がそのときは正常な気分だ/ったからで ある。何万人もを死に送り込んだ同じ医務官が、彼の母校で学んだ、それゆえ彼の青春時代を思い出させた一人の女性を助けたこともあった。翌日にはガスで殺 されることになっていたが子供を生んだ母親に、花とチョコレートが贈られることもあり得た。……死はアウシュヴィッツでの最高の支配者であった。しかし、 死と並んで収容者たちの運命を決定していたのは、偶然——死の下僕どもの移ろいやすい気まぐれと一体となったもっとも非道で気まぐれな偶然であった」(ヤ ング=ブルーエル 1999:490-491)[→出典]
【文献】
***
★アーレント『暴力について:共 和国の危機』ノート備忘
「暴力の機器の技術的な発達が、 いまや、どんな政治的目標もとうていその破壊力には引き合わないし、武力紛争でそれらを実際に使用する ことも正 当化できないところにまで達してしまったということがそれである」。97
「権力、強制力、あるいは力から明確に区 別されるべきものとしての暴力は(つとにエンゲルスが指摘していたように)つねに機器を必要とするもの である以上、テクノロジーの革命、道具作りの革命は戦争においてとりわけ著しかった」。98
「暴力はさらにそれに加えて恋意的な要素 をそれ自体のうちに秘めている。女神フォルトゥーナが戦場においてほど人間暴力についての事柄にかんし て、幸運にしろ不運にしろ、運命的な役割を演じることのまったく予期せぬものの介入は、それを「偶発事故」と呼んで、科学的に疑わしいとしたところで消え てなくなるわけではないし、シミュレーション、シナリオ、ゲーム理論等々をもちだすことによって排除できるものでもない。これらのものには確実性はまった くな計算によってはじき出されたある事態で想定されるお互いの滅亡ということも決定的に確実にあるわけではない」。98-99
「戦争がまったく姿を消してしまうほどの 技術的な発達の水準についに到達したという事実は、皮肉なことに、われわれが暴力の領域に近づいた瞬間 に出会う全面的な予言不可能性を思い起こさせる。戦争がまだ残っている主な理由は、人類の密かな死の願望でもなければ、抑制不能な攻撃本能でもないし、ひ いてはよりもっともらしく聞こえる軍備縮小に伴う重大な経済的社会的危険でもなく、ただ、国際的な問題でこの最終的な裁決者に取って代わるものが政治の舞 台にいまだに現れてこないという事実、これに尽きる。ホッブズが「剣を伴わない信約はたんなる言葉にすぎない」といったのは正しかったのではないか」 (p.99)
「国民国家とその主権の概念の衰退という 政治的な衰退がまずあって、その後にヨーロッパの衰退がやって来たという事実には気づかないで。低開発 国の外交問題においては、戦争は依然として最後の手段(ウルテイマ・ラツイオ)であり、昔からの暴力による政治がつづいていることは戦争が時代遅れである ことに反対する論拠にはならないし、核兵器や生物兵器をもたない小国だけがいまだに戦争することができるという事実は何の慰めにもならない」 (p.100)。
「出来事というものは、ほんらい、決まり きった過程や手続きを中断するものである」(p.101)。
「戦争とは「他の手段をもってする政治の 継続」というクラウゼヴイツツのいい方にしても、暴力は経済発展の促進剤というエンゲルスの長政治的な いし経済的な継続性、すなわち暴力的な行為よりも先に起きたことによって規定された過程の継続性である。。したがって、国際関係の研究者は、「国力の奥底 にある文化的資源と一致しない軍事的解決は永続しえないというのは金言である」とか、エンゲルスの言葉を借りるならば、「一国の権力構造がその経済発展と 矛盾するときにはつねにヘ敗北を喫するのは暴力手段を握っている政治権力の方である、というようなことを最近まで主張していたのである」(p.103)。
「第二次世界大戦の後につづいたのは平和 ではなく冷戦であり、軍産労複合体の確立であった」(p.103)。
「ロシアの物理学者サハロフの言葉を借り るならば、「水爆戦争は(クラウゼヴイツツの定式のいう)他の手段をもってする政治の継続とは考えられ ない。それは全世界の自殺の手段となるであろう」(p.104)。
「暴力は国際関係においてしだいに疑わし くて確実とはいえない道具になってきたが、国内問題では、とくに革命においては、評判と魅力を獲得する にいたっている。新左翼の強烈なマルクス主義的レトリックは、毛沢東が宣言した「権力は銃身から生じる」というまったく非マルクス主義的な確信の着実な成 長とぴったり符合する。たしかにマルクスは歴史における暴力の役割に気がついていたが、しかしこの役割はかれにとっては第二義的なものであった。古い社会 の終鷲をもたらすのは暴力ではなくて、その社会に内在するもろもろの矛盾なのだ。新しい社会が姿をあらわすに先立って暴動が起こるとしても、暴動が新しい 社会の登場の原因ではない。それは、出産に先立って陣痛がくるとしても、陣痛が出産の原因ではないのと同じことである。同様に、マルクスは、国家を支配階 級の意のままになる暴力の道具とみなしたが、支配階級の実際の権力は暴力からなるとか暴力に依拠していると考えたのではない。その権力は支配階級が社会の なかで果たす役割によって、もっと正確にいえば、生産過程における支配階級の役割によって規定されるとしたのだ」(p.105)。
(フランツ・ファノンの)「「地に呪われ たる者」が「人間になる」ことができるのは「狂暴な憤怒」を通じてであると述べるときに明らかである。 こうした考えがいっそう目を引くのは、〈人間が自分自身を創造する〉という観念がまったくヘーゲル的およびマルクス的な思考の伝統のうちにあるものだから である。これこそがあらゆる左翼ヒューマニズムの基礎にほかならない。しかし、ヘーゲルによるならば、人間が自分自身を「産出する」のは思想を通じてであ るのにたいし、ヘーゲルの「観念論」を転倒させたマルクスにとっては、この機能を果たすのは労働、いいかえれば人間的形態での自然との物質代謝であった」 (p.107)。
「新左翼の情動と躍動、かれらをいわば信 頼するに足るように思わせているものは、現代の兵器が異様な自殺的発達を遂げていることと密接な関係が ある。かれらは原子爆弾の影に覆われて育った最初の世代である。かれらが親の世代から受け継いだのは、政治に犯罪的暴力が大量に入り込んでくるという経験 である。かれらは高校や大学で強制収容所や絶滅収容所について学び、集団虐殺や拷問について学び、戦争となれば現代の軍事作戦は、たとえ使用する兵器は 「通常」兵器に限定されるとしても、非戦闘員の大規模な虐殺を伴わずには成り立たないことを学んでいる。かれらの最初の反応は、あらゆるかたちでの暴力に たいする嫌悪であり、ほとんど当然のこととして非暴力政治を支持することであった」(p.108)。
「この世代は心理学的に見てどこの国で も、並はずれた勇気、驚くほどの行為(アクション)への意志、変革の可能性への同様に驚くほどの自信を もっているという特徴がある」(p.109)。
「この世代の人びとに、「五O年後の世界 はどうあってほしいか」と「五年後の自分の生活はどのようなものであってほしいか」というこつの簡単な 質問をしたら、そ答にはまず「もし世界がまだ存在していたら」とか「もしわたしがまだ生きていたら」という文句がついていることが非常に多いだろう」 (p.111)。
「大学当局が黒人の要求に屈白人社会の 「罪悪感」によるものだと説明されることが多い。わたしは、それよりも、教員も局も理事会も「強制力や暴 力は広く民衆の支持がえられる場合には、首尾よく社会を統制し技術たりうる」という公式の『アメリカにおける暴力についての報告書』の結論を知ってか知そ れが明白なる真理であることに気がついているからだろう」(p.113)。
「暴行を受けた者は暴力を夢想し、抑圧さ れた者は「少なくとも一日に一回」は抑圧する者と立場を逆にすることを「夢に見」、貧しい者は富める者 の財産を夢に見、迫害されている者は「獲物の役割を狩人の役割」と交換することを夢に見、どん底にいる者は「後の者は先になり、先の者は後に」なる王国を 夢見ることをいったいだれが疑う、だろうか。ただ因ったことに、マルクスはわかっていたが、夢はけっして現実のものとはならないのである。奴隷の反乱や財 産もなく虐げられてきた人びとの蜂起がめったに起こらないことはだれもが知るとおりである。ごく稀にそれが起きたときには、まさに「狂気のごとき憤激」と なり、夢はすべての人にとって悪夢と化した」(p.114)。
「第三世界とは実在(リアリティ)ではな くてイデオロギーである」(p.115)。
「人類全体の進歩というようなものが存在 するという考えは一七世紀以前には知られていなかったが、一八世紀の文人たち(オム・ド・レトル)のあ いだではかなりありふれた見解となり、一九世紀にはほとんどあまねく受け入れられる教義となった」(p.118)。
「生ける有機体がすと同じように古い社会 はすべてその継承者の種を宿しているものだというヘーゲルゆずりのマルクスの考えは、きわめて巧妙であ るのみならず、歴史における進歩の恒常的連続性の唯一ありうべき概念的な保証でもある」(p.119)。
「「永遠回帰」、帝国の興亡、本質的に関 連性のな出来事の偶然の連なり、これらはすべて証拠を挙げて立証することも正当化することもできるが、 そのいずれをとっても直線的な時間の連続性を保証するものでもなければ歴史における絶えざる進歩を保証するものでもない」(p.119)。
「進歩は時間の連続性を断ち切ることなく 過去を説明するばかりでなく、未来に向かって活動するうえでの指標ともなりうる。この点こそ、マルクス がヘーゲルを転倒させたときに発見したことである。マルクスは歴史家の視線の方向を変えたのだ。過去の方を見る代わりに、歴史家はいまや自信をもって未来 の方を見ることができるようになった」(p.120)。
「進歩は現代の迷信市場に出回っている商 品のなかでも、まじめで複雑なものの部類に属する。無制限の進歩を信じた非合理的な一九世紀的な信仰が 普遍的に受け入れられていたのは、主として自然科学の驚くべき発展によることであって、自然科学は近代の勃興以来実際「普遍的」な科学となり、それゆえ果 てしなく広がる宇宙を探究するという終わりなき課題への取り組みを期待することができた」(122)。
「権力の現象についての議論を検討してい くと、左翼から右翼にいたるまでの政治理論のなかに、暴力は権力の最もあからさまな顕現にほかならない という合意が存在することにすぐさま気がつく。「政治とはすべて権力をめぐる闘争であり、究極的な権力は暴力である」とC ・ライト・ミルズは述べているが、これは、国家とは「正統な、ということはつまり正統であるとみなされているということであるが、暴力の手段にもとづく人 間のマックス・ウェーバーの定義のいわばこだまである。この合意は何とも奇妙である、というのは政治権力を「暴力の組織化」と同一視するのは、国家を支配 階級の掌中にある抑圧の価に従うのでなければ意味をなさないからである」(pp.124-125)。
「ヴオルテールは、「権力とは他者をおの れの意のままに行動させることである」と述べていた。他者の「抵抗に反してもおのれの意志を貫徹する」 機会があるときにはつねに権力が存在するとマクス・ヴェーバーはいうが、これは、「敵をわれわれの願望に従わせるための暴力活動」というクラウゼヴイツツ の戦争の定義を思い起こさせる」。
(アレクサンダー ・パッセリン・ダントレーヴの『国家の概念』)「「われわれは「権力」と「強制力」がはたして区別できるのか、区別できるならいかなる意味で区別できるか を決定し、法にしたがって強制力を行使することがどのように強制力そのものの質を変化させ、人間関係のまったく異なった姿をわれわれの目のまえに提示する のかを確認する必要がある」が、それは「強制力は、まさにそれが法的な条件を充たしていることによって、強制力ではなくなる」からである。しかし、この問 題にかんする文献のなかで最も洗練されよく考えられたこの区別でさえ事柄の根底にまでは達していない」(p.126)。
「権力は、パッセリン・ダントレーヴの理 解では、「法的な条件を充たした強制力」もしくは「制度化された強制力」である。いいかえれば、先に引 用した著述家たちは暴力を権力の最もあからさまな顕現と定義するのにたいして、パッセリン・ダントレーヴは権力をある種の緩和された暴力と定義しているの である。それは、最終的には同じことになる」(pp.126-127)。
「右翼から左翼にいたるまで、ベルトラ ン・ド・ジユヴネから毛沢東にいたるまでのすべての人が、権力の本質とは何かという政治哲学のきわめて基 本的な点にかんして意見が一致するものなのであろうか」(p.127)
「官僚制とはすなわち、一者でもなければ 最優秀者でもなく、また少数者でもなければ多数者でもなく、だれもがそこでは責任を負うことのできない 官庁の匿名のシステムであり、無人による支配とでも呼ぶのが適切であるようなものである。(もし、伝統的な政治思想に従って、暴政をみずからについての説 明をまったく要求されない統治とするなら、無人による支配は明らかにあらゆる統治のなかでも暴政的なものである。なぜなら、現在行われていることについて 釈明するように求められる人さえ残っていないからである。責任の所在を明らかにし、だれが敵であるかを識別することを不可能にしてしまうこの状態こそ、昨 今の世界的な反乱による動揺、その混乱した性格、統制がとれなくなり暴徒と化す危険な傾向が生ずる最も有力な原因の一つである。)」(pp.127- 128)。
「ジョン・スチユアート・ミルによれば、 「文明への第一課は服従」であり、かれはまた「〔人間には〕他者を支配する権力をふるいたいという欲望 と、他者に権力をふるわれるのを好まないという、二つの傾向のあり方〔があるごと述べている」(p.128)。
「アテネの都市国家がみずからの国制をイ ソノミアと呼ぴ、ローマ人がみずからの統治形態をキーウィタースと呼んだときに、かれらの念頭にあった のは、その本質が命令ー服従の関係に依拠せず、また権力と支配、あるいは法と命令とを同一視しない権力と法の観念であった。これこそが、一八世暴力につい て紀の革命の人びとが古代の文書を漁って共和政という統治形態を構成したときに範例としたものであった。共和政においては、法の支配は人民の権力に依拠す るのであり、かれらが「奴隷に適した統治」と考えた人間の人間にたいする支配に終止符を打つはずのものであった」(p.129)。
「僭主政はモンテスキューが発見したよう に、統治形態のなかでも最も暴力的でありかつ最も権力のないものな のである。実際権力と暴力との最も明白なる相違点の一つは、権力はつねに数を必要とするのにたいして、暴力は機器に依存するがゆえにある点までは数がなく てもなんとかやっていけるという点にある。法的な制限のない多数決原理、すなわち、国制なき民主政は、暴力を何ら行使せずとも、きわめて強硬に少数者の権 利を抑圧しうるし、きわめて効果的に異論を圧殺することができる、しかし、それは暴力と権力とが同一であるということではない」(p.131)。
■権力、力、強制力、権威
「権力(power)は、ただたんに行為 するだけでなく[他者と]一致して行為する人間の能力に対応する。権力はけっして個人の性質ではない。 それは集団に属すものであり、集団が集団として維持されているかぎりにおいてのみ存在しつづける」(p.133)。
「力(strength)は紛れもなく単 数の、個体的実在のうちにある何かを指している。それは物または人に固有の性質であり、その特性に属す ものであって、他の物や人間との関係のなかでその存在が証明されるであろうが、本質的には他の物や人間からは独立している」(p.134)。
「強制力(force)は、日常の会話の なかでは暴力、とりわけ強制の手段としての暴力と同義語として使われることが多いが、専門用語としては 「自然の力」や「事の成り行き」(la force des choses)、すなわち物理的または社会的運動から発せられたエネルギーを指す場合に用いられるべき語である」(p.134)。
「権威(authority)は、これら の現象にかんして最もとらえどころがなく、それゆえ術語としては最も頻繁に濫用されているが、権威は人 間に付与されることもあり——たとえば親と子の関係や教師と生徒の関係におけるような人格的権威のようなもの——、また、たとえばローマの元老院(〈元老 院に権威あり〉auctoritas in senatu)や教会の聖職位階制における職(聖職者は、たとえ酩酊していても、かれの行う罪の赦しは有効である)のような役職に付与されることもある。 権威は、それに従うように求められた者が疑問を差し挟むことなくそれを承認することによって保証されるのであって、強制も説得も必要ではない」 (p.135)。
「暴力(violence)は、すでに述 べたように、道具を用いるという特徴によって識別される。現象的にみれば、それは力に近い。なぜなら、 暴力の機器は、他のあらゆる道具と同じように、自然の力を増幅させるという目的で設計され使用され、その発達の最終段階では、自然の力にとって代わること ができるからである」(p.135)。
「今世紀初頭以来、革命についての理論家 たちは、政府のみが意のままにできる武器の破壊力が増大するに比例して革命の機会は著しく減少したと述 べてきた。成功した革命の機会は著しく現象したと述べてきた。成功した革命と失敗した革命についての驚くばかりの記録を蓄えているここ七〇年間の歴史は、 それとは違う物語を伝えている」(p.136)。
「もっぱら暴力の手段だけにもとづいてい るような政府はいまだかつて存在したためしがない。拷問を主要な支配の道具とする全体主義支配者でさ え、権力の基礎を必要とする——それが秘密警察とその密告者網である」(p.139)。
「われわれが知っている最も専制的な支配 である、数のうえではつねに主人にまさる奴隷にたいする主人の支配ですら、強制の手段そのものの優越に 依拠するのではなく、権力の組織化の優越ーーすなわち、主人たちの組織された連帯に依拠するのである」(p.139)。
「権力は政治的共同体の存在そのものにほ んらい備わっているものであるから、いささかの正当化(justification)も必要としない。 権力が必要とするのは正統性(legitimacy)である。この二つの語はよく同義語として扱われているが、それは服従と支持を等置する昨今の用語法と 同じく誤解と混乱を招くものである」(p.141)。
「正統性は、異議が申し立てられたときに は、その過去に訴えることを根拠とするが、これにたいして正当化は未来にある目的に関連している。暴力 を正当化することはできるが、しかし暴力が正統なものであることはけっしてないであろう。暴力の正当化は、それが意図する目的が未来へ遠ざかるほど真実味 を失う。自衛のための暴力の行使を疑問視する者がいないのは、危険が明らかであるばかりでなく現に存在しており、手段を正当化する目的が目前に迫っている からである」(p.141)。
「銃身からはけっして生じえないもの、そ れは権力である」(p.142)
「帝国主義の時代に大いに恐れられた、 「被支配人種への統治」(クローマー卿)の本国の統治に及ぼすブーメラン効果とは、遠方での暴力による支 配がイギリスの統治に影響を及ぼして、最後の「被支配人種」はイギリス人自身となるだろうということであった」(p.143)。
「権力の失墜は暴力をもって権力に代えよ うとする誘惑となる」(p.143)。
「ロシアの脱スターリン化については、い までは非常に多くのもっともだと思われる説明がある——わたしの思うに、スターリン主義の幹部たち自身 が、スターリン体制の継続によって反乱——それにたいしてはテロルは実際最良の安全装置である——を招くよりも、国中が麻痺状態に陥ることに気がついたか らだという説明ほど説得力のあるものはない」(p.145)。
「政治的にいうとすれば、権力と暴力は同 一ではないというのでは不十分である。権力と暴力とは対立する。一方が絶対的に支配するところでは、他 方は不在である。暴力は、権力が危うくなると現れてくるが、暴力をなすがままにしておくと最後には権力を消し去ってしまう。ということはつまり、暴力に対 立するのは非暴力であると考えるのは正しくないということである。非暴力的権力というのは、実際のところ、言葉の重複である。暴力は権力を破壊することは できるが、権力を創造することはまったくできない」(p.145)。
「ヘーゲルやマルクスが弁証法的な「否定 の威力」に深い信頼を寄せ、矛盾は発展を麻埠させるのではなく促進するがゆえに、「否定の威力」によっ て対立物は相互に破壊し合うのではなく難なく移行し合うと考えたのは、かれらがはるか大昔からの哲学的偏見に依拠していたからである。すなわち、悪とは善 の欠如した様態であり、善は悪から生まれることがある、要するに、悪はいまだに秘匿されている善の一時的な顕現にすぎないという偏見である」 (pp.145-146)
「社会科学者のさまざまな研究プロジェク トに財団から洪水のように資金が流れ込み、暴力にかんする書物がもはや氾濫といっていいほど出現し、著 名な自然科学者——生物学者、生理学者、動物行動学者、動物学者——が人間の行動にみられる「攻撃性」の謎を解明しようとする大々的な努力に結集し、「攻 撃学」というできたてほやほやの科学まで登場した」(p.146)。
「アドルフ・ポルトマンのいうように、動 物の行動についてのこれらの新しい洞察は人と動物との間にある深淵を埋めるものではなく、たんに「われ われが自分自身について知っていると思っていたことの大半が動物にも見られる」ことを示すにすぎない」(p.147)
「社会科学と自然科学両方の研究結果は、 暴力的な行動を「自然」な反応と見る傾向が強く、われわれがそうした研究結果を知らないで「自然」な反 応だと認めるのも吝かではないという場合に比べると、その傾向ははるかに強いという点である」(p.148)。
「動物王国における攻撃本能はこうした誘 因から独立しているように見える。逆に、誘因の欠如こそが本能の欲求不満を招き、「抑圧された」攻撃性 をもたらし、その結果心理学者のいう「エネルギー」の欝積が起こり、その最終的な爆発はきわめて危険であるとされる。(それではまるで、人の空腹の感覚 は、空腹をかかえた人びとの数が減少するに応じて増加するといっているようなものである)。この解釈によるならば、誘因なき暴力は「自然」であることにな る。もし暴力がその「理性的根拠(rationale)」——すなわちその自己保存の機能を根本的に失ってしまえば、それは「非理性的」なものとなり、そ れゆえに人は他の動物よりも「獣のよう」になりうるというのである。(文学のなかでは、負けた敵を殺さない狼の寛大な行動の話によくお目にかかるものだ が。)」(p.148)。
「理性的動物(animal rationale)」(p.149)
理性=人間という動物の自然の光 (lumen naturale)(p.149)
「暴力は往々にして憤りから起こるという のはありふれたことであり、また憤りは実際非理性的で病理的である場合もあるが、しかしそれは他のどん な人間の情緒でもそうである。人間を脱人間化するような条件——強制収容所、拷問、飢餓のような——を創造することが可能であるのは明らかだとしても、そ れによって人間が動物のようになるというわけではない。また、そのような条件のもとでは、憤りや暴力ではなく、それらが目に見えるかたちで存在しないこと が脱人間化の最も明瞭なしるしなのである」(p.150)。
「憤りは、けっして惨めさや苦痛そのもの にたいする自動的な反応ではない。不治の病や地震、さらにいうなら、変更できないように思われる社会的 条件に憤りをもって反応する人はいない。条件を変えることができそうなのに変えられていないのではないかと疑うだけの理由があるところでのみ、憤りは生ず る。正義感を害されたときにのみ、われわれは憤りをもって反応するのであって、この反応は必ずしも個人的な損害を反映するものではないことは、革命の歴史 全体が示しているとおりである。革命の歴史を見ると、例外なく上層階級を占める人ぴとが、抑圧され虐げられた人びとを焚きつけ、そして反乱へと導いてい る。憤りを誘うできごとや条件に直面したときに暴力に訴えるのは、暴力がほんらい備えている直接性と迅速さゆえに、非常に心そそられるものがある」 (p.150)。
「参加(engages)を憤り (enrages)に変換するであろう原因を歴史的に探求するなら、第一にくるのは不正義ではなく、偽善であ る。フランス革命の後半の段階でロベスピエールが「自由の専制」をテロルの支配〔恐怖政治〕に変換したときに偽善が果たした重大な役割は周知のこと」 (pp.152-153)。
■言葉への信頼=理性の狡知??
「すぐれた著述家で暴力のための暴力を讃 えた人は多くなかった。しかし、このごく少数の人々——ソレル、パレート、ファノン——は、主として同 情と燃えるような正義への欲望に駆り立てられていた旧来の左翼に比べると、ブルジョワ社会への憎悪がはるかに強く、ブルジョワ社会の道徳的基準とより徹底 的に断絶することとなった。敵の顔から偽善の仮面を剥ぎ取り、暴力的な手段を用いなくともかれの支配を可能にしている込み入った策謀や操作を暴くこと—— すなわち、真理を白日のもとに曝すためにはたとえ死を賭しても行為を喚起すること——これらは今日でもなお大学や街頭での暴力の最も強い動機の一つであ る。そしてこの暴力もまた非理性的ではない。人間は現れの世界で生きており、この世界とのかかわりにおいては自に見えてあらわれるものに頼っているのであ るから、偽善の気まぐれ——しかるべき時がくれば明らかにされる策略とは異なる——は、いわゆる理性的な行動では対応しきれない。言葉に信頼がおけるの は、ことばの機能が対象を隠すのではなく表すものであるという確信が抱けるあいだだけである。憤激を喚起するのは、理性的なるものの背後にある利害よりも はるかに、理性的なるものの見せかけである」(p.153)
「先に述べたように、暴力の効果は数に よって決まるわけではないものの——一人の機関銃をもった人がよく組織された何百人という人々を窮地に追 いやることもある——、それでもやはり集合的な暴力においてこそ暴力の最も危険で魅力的な特徴が前面に出てくるのであるが、そうなるのはけっして数に安全 性があるからではない。革命行為においても軍事行為においても、「最初に消えるもの[価値]は個人主義である」のはまったくそのとおりである。個人主義に 代わってある種の集団の団結心が生まれるが、これは文民ないし私人がもっどんなかたちの友情よりも強烈に感じられ、またそれよりもつづかないとはいえ、は るかに強い粋である」(p.154)。
チェ・ゲバラとカストロ?あるいはシエ ン・フエンテス?
■集団的暴力の呪縛
「集団は犯罪的なものであれ政治的なもの であれ、あらゆる非合法な企てにおいてそれ自身の安全のために、暴力の共同体への加入がまだ認められて いない人にたいして、まともな社会への架け橋を焼き払うようにご人ひとりが取り返しのつかない行為をする」ように求めるものである。しかしひとたび加入を 認められた人は、「一人ひとりの個人が暴力の大いなる連鎖を形づくり、沸き上がってきた暴力の大いなる有機的組織の一部となるがゆえに、人びとを一つの全 体へと結びつける暴力の実践」の陶酔的な呪文の虜になってしまうであろう」(pp.154-155)。
「政治は、死の下の平等から逃れてある程 度の無死性を保証してくれる令名を手にするための手段にほかならなかったのである。(ホッブスは、その 著作のなかで暴力死へ恐怖というかたちで死が重大な役割を果たしていることを示した唯一の政治哲学者である。しかし、ホッブズにとって決定的なのは、死の 下の平等ではない。自然状態における人間に団結して国家をつくる気にさせるのは、だれもが所有する平等な殺人能力から生ずる恐怖の平等である。)いずれに せよ、わたしの知るかぎり、死の下の平等や暴力で死が現実化されることを基礎としてできあがった治体はいまだかつてない」(p.156)。
「コンラート・ローレンツが動物王国にお いて攻撃性がもっている生命促進機能を発見するはるか以前に、暴力は生命力の、なかんずくその創造力の 顕れとして賛美されていたのである。ベルクソンの生の跳躍(エラン・ヴィタル)に喚起されて、ソレルは創造性の哲学をめざしたが、それは「生産者」のため に考案されたのであって、その論の矛先は消費社会とその知識人に向けられていた。かれには、消費者も知識人も寄生者であるように思われたのである。かれ [=ソレル]の著作のなかでは、平和的、自己満足的、偽善的、快楽を求め、権力への意志を欠き、資本主義の代表というよりその後期の産物であるというブル ジョワのイメージと、「意志の表出」ではなく「構成物」でしかない理論を弄ぶ知識人のイメージ、これとかれが希望を託している労働者のイメージとが均衡し ている」(pp.157-158)。
「ソレルよりももっと才能に恵まれ、同時 代人でフランスで教育を受けたイタリア人ヴィルフレード・パレートからはさらに多くを学ぶことができ る。ファノンは、この二人に比べると暴力の実践にはるかに深く通暁していたが、ソレルに大きな影響を受け、自分自身の経験からすれば明らかにおかしいとわ かっている場合でもソレルのカテゴリーを使用していた。ソレルやパレートが革命における暴力という要因を強調するようにしむけた決定的な経験はフランスの ドレフュス事件であり、パレートの言葉を借りていうなら、かれらは「[ドレフュス派の人びとが]みずから公然と非難している卑劣な方法を相手に行使してい るのを見て驚いた」のである。この時点でかれらは、かつてシステム〔体制〕と呼ばれ、今日ではエスタブリッシユメント〔体制〕とわれわれが呼んでいるもの を発見したのであるが、まさにこの発見によってかれらは暴力行為を礼賛するようになり、またパレートにかんし ては、労働者階級に絶望するようになったのである。(パレートは国の社会体や政治体のなかに労働者を急速に統合することは、実際のところは「ブルジョワ ジーと労働者層との同盟」を生み出し、労働者が「ブルジョワ化」することを意味するが、かれによれば、それがつぎには、かれが「金権民主政」と呼ぶ新しい 体制(システム)——ブルジョワの統治である金権政と労働者の統治である民主政との混合政体——を出現させる)」(pp.158-159)。
「ソレルが労働者階級にマルクス主義的な 信仰を抱いていた理由は、労働者こそ「生産者」であり、マルクスによるならば、労働者は必ずや人類の生 産力を解放するべき、社会における唯一の創造的な要素だからである。ただ、問題は、労働者は労働条件と生活条件が満足の行く水準に到達したとたんに、プロ レタリアでありつづけて革命的な役割を演ずることを断固拒否するようになることであった」(p.159)。
「現代世界の途方もない生産力の成長は、 けっして労働者の生産性の増加によるものではなく、もっぱらテクノロジーの発達によるものであり、そし てこれは労働者階級によるものでもなければブルジョワジーによるものでもなく、科学者によるものであった。ソレルやパレートが大いに軽蔑した「知識人」は 突如として周辺的な社会集団であることをやめ、新しいエリートとして台頭してきた」(pp.159-160)。
「この新しい集団が権力エリートへと発展 しない、あるいはまだ発展しないのには多くの理由があるが、しかし実際ダニエル・ベルとともに「最高の 才能だけでなく、いずれは社会的威信と社会的地位の全複合体が知的・科学的共同体に根ざすようになるであろう」と信じる理由には事欠かない。この共同体の メンバーは古い階級制度のなかの集団に比べるともっとばらばらで、明確な利益に縛られてもいない。それゆえ、かれらは自分たちを組織化しようという気にも ならないし、権力にかんするいかなる問題についての経験もない」(p.160)。
「この文脈でわれわれが何よりも興味を覚 えるのは、ソレル的な解釈を刻印されベルグソンンやニーチェの生の哲学の奇妙な復興である。いまの世代 の反抗的な精神状態のなかで暴力、生、創造という古い結合がどの程度作用しているかは、だれもが知るところである。生きていることというまったくの事実性 の強調、したがってまた生の最も悦ばしい顕現としての性愛の強調は、この世の終わりの日をもたらす機械を組み立てて地上のあらゆる生を破壊する現実的な可 能性への応答である。しかし、生の新しい礼賛者たちが自分を理解するために用いているカテゴリーは新しいものではない。社会の生産力を生の「創造」のイ メージで見るのは、少なくともマルクスにまで遡る古いことであり。生を促進する力(フォース)として暴力を信奉するのは少なくともニーチェにまで遡ること であり、そして創造を人間の最高善と考えるのは、少なくともベルクソンにまで遡ることなのである」(p.161)。
「暴力を生物学的に正当化しようとするこ の一見新奇な動向も、われわれの政治思想の最古の伝統のうちにある最も有害な要素と密接に関連してい る。先に見たように、暴力と等置される伝統的な権力概念にしたがうなら、権力は本性上拡張主義的である。それは「成長しようという内的衝動をもち」「成長 の本能がそれにとってほんらい的である」がゆえに創造的である」(p.161)
「「成長が止まったものは腐敗しはじめ る」というのはエカテリーナ帝の側近が伝えているロシアの諺である。王は「暴政のためではなく、弱いため に」殺されるといわれる。「人民が断頭台を築くのは、専制にたいする道徳的な罰としてではなく、弱さへの生物学的な報いとしてである。」(←ファノンの引 用?)したがって、革命が既成の権力に向けられるというのは「ただ外面的なことにすぎない。」その真の「効果は、権力に新しい活力と安定を与え、長いあい だその発展を妨げていた障害物を取り除くことにあった。」ファノンが暴力行為のうちにある「創造的狂気」を語るとき、かれはまだこの伝統のなかで考えてい るのである」(p.162)。
「理論的に見て、権力と暴力が生物学的用 語で解釈される、政治的な事柄をめぐる有機体的思考の伝統ほど危険なものはありえないとわたしは思う」 (p.162)
「「法と秩序」を回復させるために暴力的 手段を提唱する人びとと、非暴力的な改革を提唱する人ぴととの論争は、不吉にも、患者に外科的治療と内 科的治療を比較してどちらに利点があるかを論じている医者同士の議論に似てくる。患者の病状が重ければ重いほど、外科医の勝ちになる公算が大きい。そのう え、政治的な用語ではなく、生物学的な用語で語るかぎり、暴力の礼賛者たちは、自然の営みのなかでは破壊と創造は自然の過程の両面にほかならないという否 定しがたい事実に訴えることができるので、集合的な暴力行為は、それがほんらいもっている魅力とはまったく別に、動物王国における生命維持のために生存闘 争と暴力死がそうであるのと同様に、人類の集合的生活にとって自然な必要条件であると訴えられるかもしれない」(pp.162-163)。
「人種差別主義は、いかなる説得も権力も 変えることのできない自然な有機体の事実——白い肌もしくは黒い肌——を嫌うものである以上、ほんらい 暴力に満ちたものなのである。いざという時にできることといえば、その肌の色の人びとを絶滅させることだけでである人種差別主義は、人種そのものとは違っ て、生の事実ではなく、イデオロギーであり、それに導かれてなされる行いは反射的な行為ではなく、似非科学理論にもとづいた意図的な活動である。人種間の 闘争における暴力はつねに殺人につながるが、しかしそれは「非理性的」ではない。人種差別主義の論理的で理性的な帰結である。わたしが人種差別主義という ことで念頭に置いているのは、いずれの側にもあるやや漠然とした偏見ではなく、明確なイデオロギー的体系である」(p.163)。
「「啓蒙された利己心(セルフ・インタレ ス卜)」という信条ほど、その文字通りの解釈においても、より洗練されたマルクス主義的解釈において も、現実によって反駁されてきたものはない。逆に、多少の経験にほんのわずかの省察が付け加われば、啓蒙されることは利己心のまさに本質に反することがわ かる」(p.165)。
「暴力は、その本性からして道具的である 以上、それを正当化しなければならない目的に到達すると いうところまでは理性的である」(p.166)
「かつてコーナー・クルーズ・オブライエ ンは(観念の劇場における暴力の正統性をめぐる議論において)一九世紀アイルランドの土地均分論者にし てナショナリスティックな扇動家であったウィリアム・オブライエンの言葉を引いて、ときとして「暴力は節度の声に耳を傾けさせる唯一の手である」と述べて いた」(p.167)。
「創造の性質は、生の過程を比轍として用 いると適切に表現されない。子をもうけて産むことが創造ではないのは、死ぬことが無に帰すことではない のと同じである。それらは、あたかも魔法にかけられているかのように、すべての生きとし生けるものがとらえられている永遠回帰する同一物の異なった段階に ほかならない。権力も暴力も自然現象、すなわち、生の過程の顕現ではない。それらは、人間の事柄のうちの政治的領域に属すのであって、人間の事柄のうちで 本質的に人間的な性質は、人間の行為の能力、何か新しいことを始める能力によって保証されている。そして、人間の能力のうちで、近代の進歩によってこれほ ど被害を蒙ったものはほかにはないことを示すことができるように思われる」(p.170)。
「今日の暴力礼賛の多くは現代世界におけ る行為の能力にかんする重い失望感に由来するとわたし考えたいが、[パヴェル・]コホウト(チェコの作 家)のいう新しい範例が暴力の実践によってもたらされることはまずない」(p.171)。
「近年きわめて露わになってきた解体の過 程|l 公益事業、学校、警察、郵便配達、ゴミ収集、運輸機関等々の衰微、高速道路における死亡率、都市における交通問題、大気や水の汚染ーーは手に負なくなって きた大衆社会の必要から自動的に生じた結果である。これらは、それと時を同じくして起きた種々さまざまな政党という制度の衰退と軌を一にし、しばしばそれ によって加速されているが、政党というものの起源は多かれ少なかれ新しいものであり、大衆の政治的必要に役立つように考案されたものである——西側におい ては、直接民主政が「全員を部屋に収容できない」(ジョン・セルデン)がゆえにもはややっていけなくなったときに代議政体を可能ならしめるためであり、ま た東側においては、広大な領域にわたる絶対的支配をより効率的たらしめるためである」(pp.171-172)。
「最近台頭してきた奇妙な新種のナショナ リズムがある。これは通常右旋回と理解されているが、しかしおそらく世界的に高まりつつある「巨大さ」 そのものにたいする敵意(ルサンチマン)を示すものであろう。かつては、国民(ナショナル)感情は政治的な意思を国民全体に引きつけることによってさまざ まな民族集団を統一するものであったが、今日では、民族的(エスニツク)な「ナショナリズム」が最も古くかつ最良のかたちで確立された国民国家を解体する よう脅迫しはじめているさまがみられる。スコットランド人やウェールズ人、ブルトン人やプロヴァンス人といった、首尾よく同化することが国民国家勃興の必 要条件であり、それは完全に確実なものであるかに思われた民族集団は、ロンドンやパリの中央集権政府にたいする反抗から分離主義に向かいつつある。そし て、巨大さの衝撃に後押しされた中央集権化がそれ自体逆効果であることが判明したちょうどそのときに、連邦制の原理にしたがって権力分立を基礎とし、その 分離が尊重されるかぎり権力を維持できるこの国〔米国〕は、すべての「進歩的」な勢力の一致した喝采を浴びながら、アメリカにとっては新しい実験である中 央集権的な行政に向こうみずにも飛び込んだ。すなわち、連邦政府が州政府の権力を抑えつけ、執行権力が議会権力を浸食したのである。それはあたかも、憲法 制定者たちが訂正し取り除こうとしたまさにその誤りを大急ぎで繰り返すことによって、このヨーロッパの最も成功した植民地が衰退の道をたどりつつある母国 と運命を共にしたいと願っているかのようである」(pp.172-173)。
「〈権力の無力〉にみられる奇妙な矛盾を 示す例はほかにもある。科学において、これはおそらく現代科学へのアメリカの顕著な貢献であろうが、 チームワークが非常に効果的であるために、われわれは月旅行をふつうの週末のちょっとした旅行よりも危険性の少ないものにするほどの正確さをもって、複雑 きわまる過程を制御することができる。しかし、いわれるところの「地上最強国」は、地上最小国の一つにおいて、関係者すべてにとって明らかに悲惨である戦 争を終わらせることについてはお手上げである」(p.174)。
「ここでもまた、これらの発展がわれわれ をどこに導くのか、われわれにはわからない。しかし、権力のいかなる減退も暴力への公然の誘いであるこ とは、われわれは知っているし、知っているべきである——それがたとえ、政府であれ、被治者であれ、権力をもっていてその権力が自分の手から滑り落ちてい くのを感じる者は、権力の代わりに暴力を用いたくなる誘惑に負けないのは困難であるの昔からわかっているという理由だけからだとしても」(p.175)。
★アーレント「暴力について:共和国の危 機」に対するキャスリン・ソフィア・ベル(Kathryn Sophia Belle)の批判
「黒 人問題はアーレント思想の急所である。ユダヤ人としてナチ政権下で命の危機に晒された経験を持つアーレントが、アメリカでの黒人問題については差別的な発 言・記述を繰り返したのは何故だったのか。「黒人問題は黒人の問題ではなく白人の問題である」と喝破する著者が、アーレント思想に潜む「人種問題」を剔抉 する」
序論
1 「少女は、明らかに英雄となるよう求められていた」
2 「南部諸州で最も許し難い法律―異人種間結婚を犯罪とする法律」
3 「人間的生の三領域―政治的なもの・社会的なもの・私的なもの」
4 「革命の最終目的は自由の創設である」
5 「来るべき崩壊への準備段階」
6 「暴力と他者への支配だけが一部の男性を自由にできた」
7 「私たちの高等教育機関にとって学生の暴動よりもはるかに大きな脅威」
結論―アーレントの黒人問題へのアプローチにおける判断の役割
文献
リンク(授業関連)
リンク
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099