Explaining ethnography in five minutes!

5分でわかる民族誌研究の現状
Explaining ethnography in five minutes!

解説:池田光穂
民族誌と
は、 ethnos + -graphy つまりある特定の「民族集団(ethnos)」の「記述(-graphy)」のことをさし
ます。
しかし、この論理的前提には「民族」と「文化」と「言語」を同一のカテゴリーに包摂した
うえで、その〈社会の全体的表象〉が民族誌である、操作的理解が欠
かせません。
(第1段階)かつて、E.B. タイラーによる、文化の定義は、人間が後天的にもつ 文化項目の枚挙すればよいという話がありました。民族誌には、たしかにいろいろなことが書いてあります。でもこれはとても無謀な試みすぎませんでした。な ぜなら、それらには歴史的があり、絶対に枚挙が終わることがあり得ないからです。
(第2段階)文化のテーマによる民族誌的細部の整合性が試みられるようになり まし た。1922年のマリノフスキー『西 太平洋の遠洋航海者』やラドクリフ=ブラウン『アンダマン島民』は その最たるものでした。
(第3段階)表象記述の政治性 Writing Culture, 1985、ということで、民族誌は、人類学者と対象となった「民族」と、それらを支えているさまざまな外部の大きな勢力や文脈(例:植民地状況)の結果で あるという批判が浮上します。また、民族誌という記述体系における「修辞」ひらた く言えば表現の細部の戦術についても議論がおこるようになりました。
(第4段階)民族誌記述の細分化(連辞符人類学)が、その後ますます進むようになり、現在に至っています。
そこで検討されているのが、民族誌事実とはなにか?ということについてです。
でも、民族誌記述の古典的スタイルは、現在においてなお受け継がれているところが あります。
最初に、調査対象の集団的特性(民族、言語、生業等)が書かれます。
次に、先行研究とテーマの理論的素描がおこなわれます。
そして〈民族誌記述の本体部分〉です。具体的には、人類学者のスケッチ、観察、研 究対象の語り、観測可能なデータ、解釈のためのデータ、解釈(理論的抽象化)などが提示されます。
そして、最後に、地図、語彙、一日の生活、クロノロジー、注釈、文献、索引などで す。
【新しい考え方とさらなるジレンマ】
| この研究は、ニュージーランド・マオリの先住民思想家のリン
ダ・トゥヒワイ・スミス(1999)の言う「《研究》という言葉は、先住民の言語の中で最も汚れた言葉の一つである」という指摘の反省から出発する。つま
り先住民研究は誰がおこない誰のためにあるのか?ということである。 具体的には、ラテンアメリカの先住民文化が国民文化と混交融合をおこし先進国にもその影響が波及している文化現象に着目し3箇所の(メキシコ、コスタリ カ、チリ)の先住民社会がどのように「文化的脱植民地化(descolonización cultural)」を実践しているのかについて、インタビューと参与観察を通して民族誌的に記述する。そこで焦点化される文化的実践は、(i)伝統的知 識(TK)の習得と継承、(ii)外部からもたらされる資本主義との接続と介入過程、そして(iii)国内および国際的な先住民社会との文化や情報流通の 3つの諸相である。グローバルな資本・文化・知識の流通を追いかけるために言語・文化的な繋がりのある旧宗主国であるスペインが、この調査の対位法的なも うひとつの調査地になる。 トゥヒワイ・スミスの問いかけに答えるために、通常の研究倫理上の遵守に加えて、これまでの当該調査地域への文化人類学(民族学)研究のレビューと翻訳を 調査対象者とともにシェアし、我々の研究に興味をもつ若手の先住民への情報提供と現地社会への公開を試みる。またその民族誌過程 (ethnographic process)を記録するとともに、現地社会に方法論とともに資料をアーカイブ化し、具体的にはウェブページの公開を通して、これまでの民族誌情報が被 調査社会に還元できるように留意する。 だが、問題はそんな簡単なものではないだろう。「地域の慣習に詳しい部外者が田舎のとある村にたどり着き、そこで彼が地元の慣習をいかに深く「理解」し、またいかにそれに巧く従えるかをひけらかすぎこちない試みほどレイシスト的な ことはないだろう」(ジジェク 2005:29)ということである。また、研究対象としての〈他者〉が、研究者を受け入れてくれる寛容も、また、研究対象者にイラつくことなく、受けれ入 れて調査を「してやろう」という魂胆をもつ、研究者にも、寛容というものには、〈受け入れ可能な範疇〉というものがあるのである。「要するに寛容とは、こ の〈他者〉が「受け入れ難い原理主義者」でないという限りでの〈他 者〉すなわち本当の意味での〈他者〉ではないという限りでの〈他者〉へ与えられる寛容を意味するにすぎない」(ジジェク 2005:30) |
関連するリンク
文献
その他の情報
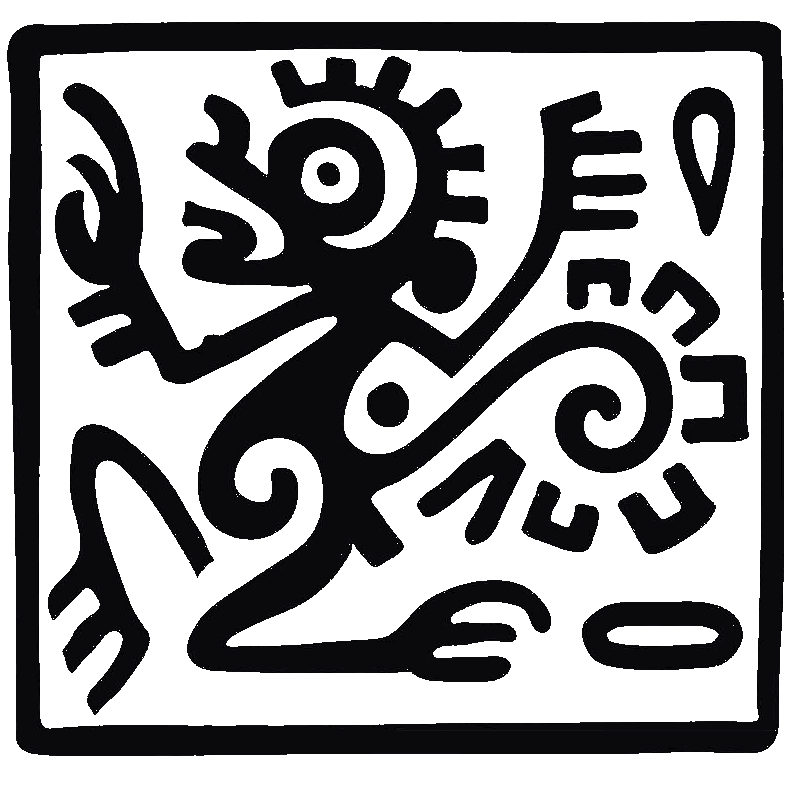
++
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆