Cultural relativism
Cultural relativism is an ethical attitude that accepts others as being different from oneself, questions what is not being questioned in one's own values and views (one's own culture), and aims for understanding and dialogue with others.
This definition was made with the view that we should accept cultural relativism as such an epistemological position or belief. Cultural relativism as an ethical attitude is also one that has traditionally been widely accepted within the field of cultural anthropology in the United States and Japan.
It must be stated honestly that the
definition of cultural relativism is inherently contradictory. In the
latter half of the twentieth century, there has been an increase in
criticism of cultural relativism, but much of this criticism has been
unwarranted, preempting the logical contradictions and limitations of
cultural relativism. These points were accompanied by an
overgeneralization of the problem.
| クリフォード・ギアツ(Clifford Geertz, 1926-2006) | フランツ・ボアズ(Franz Boas, 1858-1942) | ルース・ベネディクト(Ruth Fulton Benedict, 1887-1948) |
したがって文化相対主義を思想信条として採用する際に、正しい側面と誤った側面があることを理 解しなければならない。ギアツ(1926-2006)は次のように言う。
「文化の(あるいは歴史の、と言ってもよいが)相対主義の正しさは、われわれがけっして他の 民族や他の時代の想像力をあたかもわれわれ自身のものであるかのようにきちんと理解することはできないとするところにある。他方その誤りは、それゆえにわ れわれはけっして真にそれを理解することなどできないとすることにある。われわれは他の民族や他の時代の想像力を十分に、少なくともわれわれ自身のもので はない他のすべてのことを理解するのと同じくらいには理解することができるのだ。ただし、われわれとそれとの間に介在するおせっかいな解説 の背後からみる のではなく、それをとおして見ることによってそれは可能になる」(ギ アツ 1991:78)『ローカルノレッジ』)
上掲の〈ただし、われわれとそれとの間に介在するおせっかいな解説の背後からみるのではなく、そ れをとおして見ることによってそれは可能になる〉という表現を通して、ギアツは何を言いたいのだろうか?
文化相対主義が、「人間の心性 human nature 」という人間のもっともしぶとい正当化の呪文に対して、いまだに有効性をたもち続けることに関する有益な議論は、ギアツ[2002](Geertz 1984)を参考にして、どうか考えてください。
ボアズは直接、文化相対主義という用語を使ったことがないが、彼の死後、ボアズの弟子(学生)た ちにより使われ、その初出は1948年の『アメリカン・アンソロポロジスト』(ジュリアン・スチュアード「人権の表明へのコメント」)だと言われている が、私は未確認である。
"The subsequent refusals to own the
Universal Declaration, typically by the new political and military
elites in Asia and Africa, made Herskovits’s statement nothing short of
prescient. Much trouble may have been averted had the authors of the
Declaration attended to his concerns. Be that as it may, the lesson for
anthropology is to recognise how such reflections on the historically
contingent nature of so-called universal declarations do not
necessarily amount to cultural and moral relativism (Dembour 2001;
Goodale 2009b: 40-64). As an anthropologist associated with the
teachings of Franz Boas, an advocate of ‘cultural particularism’ in
American anthropology, Herskovits is too easily given the epithet
‘relativist’ (Simpson 1973). Would a relativist point out that cultural
differences actually became a means of governing colonised people, so
much so that ‘the hard core of similarities between cultures [were]
consistently overlooked’ (AAA 1947: 540, original emphasis)? This
acknowledgement that similarities across obvious differences carried
subversive potential hardly warrants a reputation for relativism.
Rather, the question posed by these early disciplinary reflections on
human rights is what anthropology’s sensibility to human diversity and
historical contingency amounts to when it is not dismissed as cultural
and moral relativism." - Human
Rights, the Cambridge Encyclopedia of Anthropology.
ルース・ベネディクトは、すでに1934年に、人びとが共有する「文化」概念がいかに異なり対比 的になるのか、ということを通して、ある社会の具体的な価値観を、別の社会の価値観でみることができないことを次のように示します。
「北西海岸がその文化の中で制度化するために選び出した人間行動の局面は、われわれの文明においては異常とみなされている局面である。しか
しながら、それはわれわれが理解できるほどわれわれ自身の文化のもつ態度にたいへん近いものであり、その上にわれわれはそれについて議論できうる明確な言
葉をもっている。われれわれの社会においては、誇大妄想的偏執狂的傾向はとても危険なものである。その傾向はわれわれのとりうる態度の中から、ひとつの選
択を行わしめるものである。ひとつは、その傾向を異常で非難されるべきものという烙印を押すことであり、これはわれわれが自らの文明の中で選択した態度で
ある。もうひとつの態度は、その傾向を理想的人間像の根本的特質とすることである。この態度が北西海岸地方の文化のとっている解決法である」(ベネディク
ト 2008[1934]:301)※字句は一部変えました。
他方、ベネディクトは、文化の相対性というものが、皆が共有する価値をずらすことによって、当該 の文化の中においても共有可能なものになることを『文化の型(文化の諸パターン)』で主張する。『文化の型』の最後の文章は次のようにしめくくられる。
"The recognition of cultural relativity
carries with it its own values, which need not be those of the
absolutist philosophies. It challenges customary opinions and causes
those who pave been bred to them acute discomfort. It rouses pessimism
because it throws old formulas into confusion, not because it contains
anything intrinsically difficult. As soon as the new opinion is
embraced as customary belief, it will be another trusted bulwark of the
good life. We shall arrive then at a more realistic social faith,
accepting as grounds of hope and as new bases for tolerance the
coexisting and equally valid patterns of life which mankind has created
for itself from the raw materials of existence"(Benedict
2005[1934]:278).
文化の相対性を認めることは、それ自体に価値をもつということであり、絶対主義的な哲学の価値というものを必ずしも必要としない。それは、これまで人がお
こなってきた慣習的な選択肢への挑戦と受け取られ、それによりこれまで育った人たちには性急な不快感をもたらすだろう。人が悲観的になるのは、それが古い
やり方を混乱に陥れるからであり、なにがなんでも難しいことがそこに含まれるからではない。新しい選択肢が慣習的な信条として受け入れられるならば、それ
はまた、すぐにでも別のよき生活の支え(bulwark)になるだろう。つまり、これまで共存してきたそして同時に価値あるものとしてきた、人類が生存
[のため]の生の素材から創造してきた生きた生活のパターンを、希望の地平として[そして]寛容の新しい基盤として受け入れることにより、私たちはより現
実的な社会的信念をもつようになるのだ。
さて、文化相対主義という発想の基本 的前提は、世界にさまざまな文化(複数の文化=cultures)があり、それらの間 に優劣のつけるということを留保しようという[倫理的]態度である。また、文化間の間の相対性のみならず、同一文化のなかにも多様性を認めて、また文化は 変化し、つねに固定化しているようにみえて、大きなうねりのように変化しているという考え方がある。このような考え方は、基本的に、西洋「文化」や西洋 「文明」の中心にいる、経済搾取や政治的抑圧の心配のない人たちからは大いに指示されてきた——あるいはそのように自分を西洋人に同化する現代日本の比較 的経済的にめぐまれた人たち=近代人からの支持のひとつの形態である。
しかし、自分たちの文化が、力のつよ い(=ヘゲモニックな)他者から、劣っていると見なされたり、自分たちのマイナーな文化を捨てて西洋の文化に同化せよと言われてきた地域や社会の人たちに は、自分たちの文化に対して、より複雑な態度をもつことが(皆さん自身の思考実験においてすら)容易に推測できる。そのような人たちにとって、文化の多元 性や、文化間に優劣をつけてはならない、ということは、これまでの歴史的な(=コロニアルな時代における)自文化や自己の属する集団(社会)に長い間否定 的評価がされてきた人たちには、都合のよい「支配者からの甘い懐柔のための言葉」に過ぎないという批判も、当然のことながら出てくる。これをポストコロニアル批判という。
ポストコロニアル批評家のガヤトリ・ スピバック(ないしはスピヴァック:Gayatri Chakravorty Spivak, 1942- )は、その代表格であろう。彼女は言う「多元論とは、中心的権威が反対意見を受け入れる かのよう に見せかけて実は骨抜きにするために用いる方法論のことである」と。
| ガヤトリ・スピバック | フランシス・フクヤマ | レオ・シュト
ラウス |
|
|
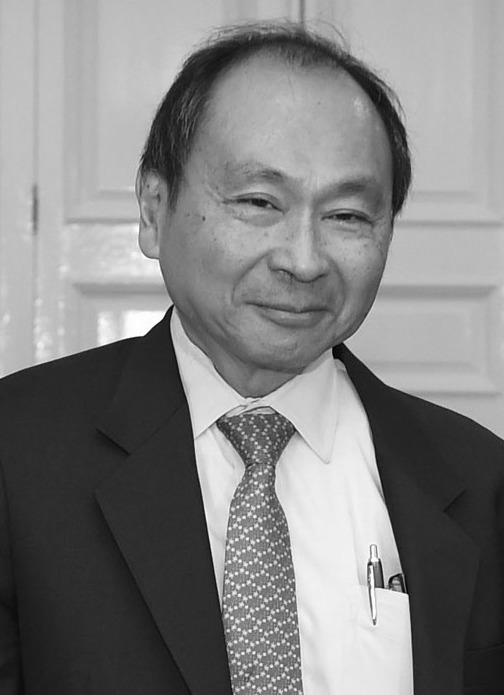 |
 |
「たとえばひとはそうですね、フラン スで産み出されている理論的な事柄の一部は、アフリカや、インドや、こうしたいわゆる自然な場所からきた人々には、自然に手に入ると言われています。もし ひとが啓蒙主義以後の理論の歴史を吟味してみれば、これまでの主要な問題は自伝の問題であったのです。つまり主体的構造が事実、客観的真実を与えることが できるのです。こうした同じ世紀の間、こうした他の場所に見いだされた「土着の情報提供者」の書いたものは、疑いもなく民族誌学、比較言語学、比較宗教学 など、いわゆる諸科学の創始のための客観的証拠として扱われました。だから再び、理論的問題は知識のある人にのみ関連してきます。知識のある人は自我にま つわるすべての問題を持っています。世間に知られている人は、どういうわけか問題性のある自我をもっていないように思われます」(スピヴァック, 1992:119-120)『ポスト植民地主義の思想』彩流社。
他方、文化相対主義は、新保守主義 (ネオコンサーバティブ、ネオコン)の陣営からも、批判にさらされている。
フランシス・フクヤマは冷戦の終焉後
に、東西のイデオロギー的対立が終わり、民主主義が勝利することを主張し、「歴史の終わり」がくると主張(予言?)していた。フクヤマによると、それまで
の、人類文化の理解は、文化の成熟度がばらばらであるゆえに、それらの社会へのより客観的な認識論的態度を担保するために文化相対主義が生まれたにすぎな
いという。最終的にはいくつかのタイプの先端社会のなかで、融合することで、文化相対主義は克服できるという(Fukuyama
1992:338/邦訳下、262頁)
これは、文化相対主義ならびに多文化共生社会(=日本語独特の用語)あるいは多文化主義に対する鋭い批判的論拠になっている。
それでもなお、文化相対主義を擁護す ると、2つの論法を我々は手にしていることがわかる。
まず最初の文化の多様性の概念におけ る重要な課題は、それがそれぞれの社会の価値概念の創出に役立っていることを再認識することである。そのために、それぞれの文化には、それぞれのメインス トリームの価値観に正/不正の概念があることがわかる。すなわち、あらゆる文化において、正/不正の概念が存在することは、 普遍的な正/不正の概念を否定するものではなく、むしろ、比較研究を通して普遍的な正/不正の概念の(我々の集合的な=自然権概念の)探究の出発点となる (シュトラウス 2013:26)(→「自然権」)。
そ して、その次には、ルース・ベネディクトやクリフォード・ギアーツは、文化相対主義にもとづく「異文化」の探究は、反響(エコー)のように、自文化の概念 の自明性を切り崩し、我々を反省へと誘うことを示唆する。つまり、ヘーゲルの弁証法に似て、文化相対主義にもとづく「異文化」の探究は、自文化への反省に 繋がることができれば、自文化の未来への「創造・修正・改造」に大いに役立つはずである。
【文献】
以上の説明がよくわからない人は、こちらへ進んでください。
以下は応用問題あるいは派生するテーマやトピックスです。
→(反対語)自民族中心主義
→(文化相対主義への異論)
| ミシェル・ド・モンテーニュ(Michel Eyquem de Montaigne, 1533-1592) | ノーム・チョムスキー(Avram Noam Chomsky, 1928- ) | マシュー・アーノルド(Matthew Arnold, 1822-1888) |
|
|
 |
 |
■ ギアツ(2002:88-90)の論文には、1982年当時に刊行されたホリスとルークスの 編纂した論集に出てくる、3名の反相対主義者の議論が紹介されている。その3名とは、アーネスト・ゲルナー、ロビン・ホートン、そしてダン・スペルベルで ある。
■ しかしながら、モンテーニュはそれ(=ゲルナー・ホートン・スペルベルの時代)よりもはるか以前に、人間のもっとも 普遍的な特質はその多 様性にあるということを主張しているために、啓蒙的理性がおしなべて文化現象に対して反相対的な普遍主義を専横に主張するという一般化はできない。
ミシェル・ド・モンテーニュ(Michel Eyquem de Montaigne, 1533-1592)
■ チョムスキーのように、諸言語の多様性という事実を認めることと、普遍的文法を信じることは 相矛盾しない。
ノーム・チョムス キー(Avram Noam Chomsky, 1928- )
■ 耕作することから自己陶冶としての文化への展開、そして高級文化と低級文化への分裂へ
文化(カルチャー)は、耕作すること(カルチャー)と同義であることから、努力して身に 付けるものという、高級な知識や身のこなしだという見方が、19世紀イギリスでは重要な位置を占めた。『教養と無秩序』(Culture and Anarchy, 1869)の作者であり、詩人で文化批評家(Cultural critic)のマシュー・アーノルド(Matthew Arnold, 1822-1888) 見解がそれである。岩波文庫の多田英次の翻訳からして、文化=カルチャーを「教養」と表現している。ここから、文化には、高邁な文化つまり、ハイカル チャーと、身分の低い人たち、大衆が身に付けているローカルチャーという分類ができる。ローカルチャーは文化(教養)には属さず、無秩序でアナーキーなも のなのである。この偏見は、身分の高いひとたちの教養=文化観が色濃くあらわれている。それに対して20世紀の後半から、レイモンド・ウィリアムズ(Raymond Henry Williams, 1921-1988)や、スチュアート・ホール(Stuart Hall, 1932-2014) のような、大衆文化論や、カルチュラル・スタディーズ(文化研究)という学派をつくりあげて、例えば英国の国民文化の中にもさまざまな階級や地域、あるい は時代により複数の文化がせめぎ合い、それぞれの社会のセグメント(部分的集団)のなかで、生まれ・再生産され・そして破棄されたり変形されたりすること で、多様性が継承されていくありさまに注意を促すようになった。カルチュラル・スタディーズ 派の人たちは、同一文化の中にも多様性と変化というダイナミズムがあり、ある特定の文化の中にも異文化と同文化(ないしは自文化としてふさわしいもの)と いうものがせめぎ合うことを明らかにした。これは、文化相対主義が前提とするような、社会は比較的均質で、自文化を再生産していくという単純な文化論では 理解が十分に不可能になるのではないかという警鐘と、自文化ですら、歴史的相対化や微細な差異への注目を通して、自文化そのものを自文化の中にいながら相 対化できるという道を切り開いたとも言えるのである。

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099