As a method of investigation and analysis of the political role of subaltern populations, Karl Marx's theory of history presents colonial history from the perspective of the proletariat; that the who? and the what? of social class are determined by the economic relations among the social classes of a society. Since the 1970s, the term subaltern has denoted the colonized peoples of the Indian subcontinent, imperial history told from below, from the perspective of the colonised peoples, rather than from the perspective of the colonisers from Western Europe. By the 1980s, the Subaltern Studies method of historical enquiry was applied to South Asian historiography. As a method of intellectual discourse, the concept of the subaltern originated as a Eurocentric method of historical enquiry for the study of non-Western peoples (of Africa, Asia, and the Middle East) and their relation to Western Europe as the centre of world history. Subaltern studies became the model for historical research of the subaltern's experience of colonialism in the Indian subcontinent.[2]
サバルタン階級の政治的役割の調査・分析の方法として、カール・マルクスの歴史理論では、プロレタリアートの視点から植民地史が提示されている。すなわ ち、社会階級の「誰が」と「何者か」は、社会階級間の経済関係によって決定されるというものである。1970年代以降、サバルタンという用語は、インド亜 大陸の植民地化された人々を指すようになり、西欧からの植民地支配者の視点ではなく、植民地化された人々の視点から語られる帝国の歴史を意味するように なった。1980年代には、サバルタン研究の歴史的調査手法が南アジアの歴史学に適用されるようになった。知的言説の方法論として、サバルタンという概念 は、非西洋諸国(アフリカ、アジア、中東)の研究と、それらの国々を世界史の中心である西欧との関係を考察するための、西欧中心主義的な歴史研究方法とし て生まれた。サバルタン研究は、インド亜大陸におけるサバルタンの植民地主義体験の歴史研究のモデルとなった。[2]
In postcolonial theory, the term subaltern describes the lower social classes and the Other social groups displaced to the margins of a society; in an imperial colony, a subaltern is a native man or woman without human agency, as defined by his and her social status.[3] Nonetheless, the feminist scholar Gayatri Chakravorty Spivak cautioned against an over-broad application of the term the subaltern, because the word:
subaltern is not just a classy word for "oppressed", for [the] Other, for somebody who's not getting a piece of the pie ... . In post-colonial terms, everything that has limited or no access to the cultural imperialism is subaltern—a space of difference. Now, who would say that's just the oppressed? The working class is oppressed. It's not subaltern ... .
Many people want to claim [the condition of] subalternity. They are the least interesting and the most dangerous. I mean, just by being a discriminated-against minority on the university campus; they don't need the word 'subaltern' ... . They should see what the mechanics of the discrimination are. They're within the hegemonic discourse, wanting a piece of the pie, and not being allowed, so let them speak, use the hegemonic discourse. They should not call themselves subaltern.[4]
In Marxist theory, the civil sense of the term subaltern was first used by Antonio Gramsci (1891–1937). In discussions of the meaning of the term subaltern in the work of Gramsci, Spivak said that he used the word as a synonym for the proletariat (a code word to deceive the prison censor to allow his manuscripts out the prison),[5] but contemporary evidence indicates that the term was a novel concept in Gramsci's political theory.[6] The postcolonial critic Homi K. Bhabha emphasized the importance of social power relations in defining subaltern social groups as oppressed, racial minorities whose social presence was crucial to the self-definition of the majority group; as such, subaltern social groups, nonetheless, also are in a position to subvert the authority of the social groups who hold hegemonic power.[7]
In Toward a New Legal Common Sense (2002), the sociologist Boaventura de Sousa Santos applied the term subaltern cosmopolitanism to describe the counter-hegemonic practice of social struggle against Neoliberalism and globalization, especially the struggle against social exclusion. Moreover, de Sousa Santos applied subaltern cosmopolitanism as interchangeable with the term cosmopolitan legality to describe the framework of diverse norms meant to realise an equality of differences, wherein the term subaltern identifies the oppressed peoples, at the margins of society, who are struggling against the hegemony of economic globalization. Context, time, and place determine who, among the marginalised peoples, is a subaltern; in India, women, Shudras and Dalits (also known as Untouchables), and rural migrant labourers are part of the subaltern social stratum.
ポストコロニアリズム理論において、「サバルタン」という用語は、社会の周縁に追いやられた下層階級や他者としての社会集団を指す。植民地においては、サ バルタンとは、その社会的地位によって定義される、人間としての主体性を持たない原住民の男女である。[3] しかし、フェミニストの学者であるガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァクは、サバルタンという用語の過度な適用に警告を発している。なぜなら、
サバルタンという言葉は、「抑圧された人々」、「他者」、「分け前にありつけない人々」を意味する上品な言葉ではない。ポストコロニアルの観点では、文化 帝国主義へのアクセスが限定的、あるいは全くないものはすべてサバルタン、つまり差異の空間である。では、それがただの抑圧された人々だと言う人がいるだ ろうか?労働者階級は抑圧されている。しかし、それはサバルタンではない。
多くの人々がサバルタンであることを主張したがっている。彼らは最も興味がなく、最も危険な存在である。つまり、大学キャンパスで差別されるマイノリティ であるというだけで、彼らには「サバルタン」という言葉は必要ないのだ。彼らは差別の力学がどのようなものか理解すべきである。彼らはヘゲモニック・ディ スコースの内部にいて、分け前を欲しがり、それを許されない。だから彼らに発言させ、ヘゲモニック・ディスコースを使わせよう。彼らは自らをサバルタンと 呼ぶべきではない。
マルクス主義理論において、「サバルタン」という言葉の市民的な意味を最初に用いたのは、アントニオ・グラムシ(1891-1937)である。グラムシの 著作におけるサバルタンという用語の意味についてスピヴァクは、グラムシはプロレタリアートの同義語としてこの語を使用したと述べている(これは、刑務所 の検閲官を欺いて原稿を刑務所外に出すための暗号のような言葉であった)[5]。しかし、現代の証拠は、この用語がグラムシの政治理論における新しい概念 であったことを示している[6]。ポストコロニアル批評家のホミ・K・バハーは、サバルタン的社会的集団を被抑圧的、人種的マイノリティとして定義するに あたり、社会的権力関係の重要性を強調した。サバルタン的社会的集団は、その社会的存在がマジョリティ集団の自己定義にとって不可欠である。しかし、それ にもかかわらず、サバルタン的社会的集団は、ヘゲモニー的権力を握る社会的集団の権威を覆す立場にもある。
社会学者のボアヴェンチュラ・デ・ソウザ・サントスは著書『新たな法の常識へ』(2002年)の中で、サバルタン・コスモポリタニズムという用語を、新自 由主義やグローバリゼーションに対する社会闘争、特に社会的排除に対する闘争という、ヘゲモニーに対抗する実践を表現するために用いた。さらに、デ・ソウ ザ・サントスは、サバルタン・コスモポリタニズムという用語を、コスモポリタン・レガリティ(Cosmopolitan Legality)という用語と交換可能なものとして適用し、差異の平等を実現するための多様な規範の枠組みを説明した。サバルタンという用語は、経済の グローバル化の覇権に抵抗する社会の周縁に位置する抑圧された人々を指す。誰が周縁化された人々の中でサバルタンとなるかは、その文脈、時代、場所によっ て決まる。インドでは、女性、シュードラ、ダリット(不可触民としても知られる)、そして農村からの出稼ぎ労働者がサバルタン層の一部である。
Postcolonial theory studies the power and the continued dominance of Western ways of intellectual enquiry, the methods of generating knowledge. In the book Orientalism (1978), Edward Said conceptually addresses the oppressed subaltern native to explain how the Eurocentric perspective of Orientalism produced the ideological foundations and justifications for the colonial domination of the Other. Before their actual explorations of The Orient, Europeans had invented imaginary geographies of the Orient; predefined images of the savage peoples and exotic places that lay beyond the horizon of the Western world. The mythologies of Orientalism were reinforced by travellers who returned from Asia to Europe with reports of monsters and savage lands, which were based upon the conceptual difference and strangeness of the Orient; such cultural discourses about the Oriental Other were perpetuated through the mass communications media of the time, and created an Us-and-Them binary social relation with which the Europeans defined themselves by defining the differences between the Orient and the Occident. As a foundation of colonialism, the Us-and-Them binary social relation misrepresented the Orient as backward and irrational lands, and, therefore, in need of the European civilizing mission, to help them become modern, in the Western sense; hence, the Eurocentric discourse of Orientalism excludes the voices of the subaltern natives, the Orientals, themselves.[8][9]
The cultural theorist Stuart Hall said that the power of cultural discourse created and reinforced Western dominance of the non-Western world. That the European discourses describing the differences between The West and The East, applied European cultural categories, languages, and ideas to represent the non-European Other. The knowledge produced by such discourses became social praxis, which then became reality; by producing a discourse of difference, Europe maintained Western dominance over the non-European Other, using a binary social relation that created and established the Subaltern native, realised by excluding The Other from the production of discourse, between the East and the West.[10]
ポストコロニアリズム理論では、西洋の知的探究の方法、すなわち知識を生み出す方法における権力と継続的な優位性について研究している。エドワード・サ イードは著書『オリエンタリズム』(1978年)で、抑圧されたサバルタン(被支配民)の視点から、オリエンタリズムにおけるヨーロッパ中心主義的な視点 が、他者に対する植民地支配のイデオロギー的基盤と正当性を生み出すに至った経緯を概念的に説明している。ヨーロッパ人が実際に東洋を探検する以前に、彼 らは東洋に関する想像上の地理を創り出していた。すなわち、西洋世界の地平線の彼方にある野蛮な民族やエキゾチックな場所という、あらかじめ決められたイ メージである。東洋学の神話は、アジアからヨーロッパに戻った旅行者たちが、怪物や未開の土地の報告とともに持ち帰ったことで強化された。こうした東洋の 他者に関する文化論は、当時のマスメディアを通じて広まり、西洋と東洋の違いを定義することで自らを定義する西洋と東洋の二元的な社会関係を生み出した。 植民地主義の基盤として、西洋と東洋という二項対立の社会関係は、東洋を後進的で非合理的な土地として誤って表現し、西洋的な意味での近代化を支援する欧 州の文明化の使命が必要であると主張した。そのため、オリエンタリズムの欧州中心主義的な言説は、サバルタンである原住民、すなわち東洋人自身の声を排除 したのである。
文化理論家のスチュアート・ホールは、文化論の力が西洋による非西洋世界の支配を生み出し、強化してきたと述べている。西洋と東洋の違いを説明するヨー ロッパの言説は、ヨーロッパの文化カテゴリー、言語、および考え方を適用し、非ヨーロッパの他者を表現した。このような言説によって生み出された知識は、 社会実践となり、現実となった。差異の言説を生み出すことで、ヨーロッパは非ヨーロッパの他者に対して西洋の優位性を維持し、二項対立的な社会関係を利用 してサバルタン(被支配的)な土着民を生み出し、確立した。これは、東と西の間の言説の生産から他者を排除することで実現した。[10]
In Geographies of Post colonialism (2008), Joanne Sharp developed Spivak's line of reasoning that Western intellectuals displace to the margin of intellectual discourse the non–Western forms of "knowing" by re-formulating, and thus intellectually diminishing, such forms of acquiring knowledge as myth and folklore. To be heard and to be known, the subaltern native must adopt Western ways of knowing (language, thought, reasoning); because of such Westernization, a subaltern people can never express their native ways of knowing, and, instead, must conform their native expression of knowledge to the Western, colonial ways of knowing the world.[11] The subordinated native can be heard by the colonisers only by speaking the language of their empire; thus, intellectual and cultural filters of conformity muddle the true voice of the subaltern native. For example, in Colonial Latin America, the subordinated natives conformed to the colonial culture, and used the linguistic filters of religion and servitude when addressing their Spanish imperial rulers. To make effective appeals to the Spanish Crown, slaves and natives would address the rulers in ways that masked their own, native ways of speaking.

Indian philosopher and theorist Gayatri Spivak, seen here giving a speech at the Internationaler Kongress in Berlin
The historian Fernando Coronil said that his goal as an investigator must be "to listen to the subaltern subjects, and to interpret what I hear, and to engage them and interact with their voices. We cannot ascend to a position of dominance over the voice, subjugating its words to the meanings we desire to attribute to them. That is simply another form of discrimination. The power to narrate somebody's story is a heavy task, and we must be cautious and aware of the complications involved."[12] Like Spivak, bell hooks questions the academic's engagement with the non–Western Other. That in order to truly communicate with the subaltern native, the academic would have to remove him or herself as "the expert" at the center of the Us-and-Them binary social relation. Traditionally, the academic wants to learn of the subaltern native's experiences of colonialism, but does not want to know the subaltern's (own) explanation of his or her experiences of colonial domination. In light of the mechanics of Western knowledge, hooks said that a true explanation can come only from the expertise of the Western academic, thus, the subaltern native surrenders knowledge of colonialism to the investigating academic. About the binary relationship of investigation, between the academic and the subaltern native, hooks said that:
[There is] no need to hear your [native] voice, when I can talk about you better than you can speak about yourself. No need to hear your voice. Only tell me about your pain. I want to know your story. And then I will tell it back to you in a new way. Tell it back to you in such a way that it has become mine, my own. Re-writing you, I write myself anew. I am still author, authority. I am still [the] colonizer, the speaking subject, and you are now at the center of my talk.[13]
As a means of constructing a great history of society, the story of the subaltern native is a revealing examination of the experience of colonialism from the perspective of the subaltern man and the subaltern woman, the most powerless people living within the socio-economic confines of imperialism; therefore, the academic investigator of post-colonialism must not assume cultural superiority when studying the voices of the subaltern natives.
ジョアン・シャープは著書『ポストコロニアリズムの地理学』(2008年)の中で、西洋の知識人が、神話や民間伝承といった非西洋的な「知」の形態を、再 定義することによって、知的な言説の周辺へと追いやっているというスピヴァクの論理展開を発展させた。サバルタンである原住民が聞き入れられ、知られるた めには、西洋の認識方法(言語、思考、推論)を採用しなければならない。このような西洋化により、サバルタンである原住民は自らの認識方法を表現すること ができず、代わりに、 従属的な先住民は、植民地支配者の帝国の言語を話すことによってのみ、彼らの声を聞いてもらうことができる。そのため、知的および文化的な同調のフィル ターが、サバルタン先住民の真の声を曇らせる。例えば、植民地時代のラテンアメリカでは、従属的な先住民は植民地文化に同調し、スペイン帝国の支配者と話 す際には、宗教と隷属という言語的フィルターを使用した。スペイン王家に効果的に訴えるために、奴隷や先住民は支配者に対して、自分たちの母国語の話し方 を隠すような話し方をする。

インドの哲学者であり理論家であるGayatri Spivak(写真)は、ベルリンで開催された国際会議でスピーチを行っている。
歴史学者のFernando Coronilは、研究者としての目標は「サバルタン(支配される人々)の声を聞き、それを解釈し、彼らと関わり、彼らの声と対話すること」であると述べ ている。私たちは、その声を支配する立場に上り詰めることはできないし、その言葉に私たちが与えたいと思う意味を押し付けることもできない。それは単に別 の形の差別である。誰かの物語を語ることは重い作業であり、私たちはその複雑さに注意深く、また自覚的でなければならない」[12] スピーヴァクと同様に、ベル・フックスも非西洋の他者と関わる学者の姿勢を疑問視している。真にサバルタン・ネイティブとコミュニケーションを取るために は、学者は「専門家」として、彼らと彼ら以外の二者択一の社会的関係の中心に立つことをやめなければならない、と。伝統的に、学者はサバルタン・ネイティ ブの植民地主義の経験について学びたいが、サバルタン(自身)による植民地支配の経験の説明を知ろうとはしない。西洋の知識の力学を踏まえて、フックスは 真の説明は西洋の学識者の専門知識からしか生まれないと述べ、サバルタンである先住民は植民地主義に関する知識を調査する学者に明け渡すことになる、と述 べた。学識者とサバルタンである先住民の二項関係について、フックスは次のように述べている。
「あなたが(先住民)の声を聞く必要はない。私があなたについて、あなたが自分自身について語るよりも上手に語ることができるのだから。あなたの声を聞く 必要はない。あなたの苦痛についてだけ話してほしい。私はあなたの物語を知りたい。そして、それを新しい方法であなたに伝える。それが私のもの、私自身の ものとなるように伝える。あなたを書き直すことで、私は自分自身を新たに書き直す。私は依然として著者であり、権威である。私は依然として植民地主義者で あり、話し手であり、そして、あなたは今、私の話の中心にいるのだ。
社会の偉大な歴史を構築する手段として、サバルタン(被支配者)の原住民の物語は、帝国主義の社会経済的枠組みの中で暮らす最も無力な人々であるサバルタ ン(被支配者)の男性とサバルタン(被支配者)の女性の視点から植民地主義の経験を明らかに検証するものである。したがって、ポストコロニアリズムの学術 研究者は、サバルタン(被支配者)の原住民の声を研究する際には、文化的優越性を前提にしてはならない。
Mainstream development discourse, which is based upon knowledge of colonialism and Orientalism, concentrates upon modernization theory, wherein the modernization of an underdeveloped country should follow the path to modernization taken (and established) by the developed countries of the West. As such, modernization is characterized by free trade, open markets, capitalist economic systems, and democratic systems of governance, as the means by which a nation should modernize their country en route to becoming a developed country in the Western style. Therefore, mainstream development discourse concentrates upon the application of universal social and political, economic and cultural policies that would nationally establish such modernization.[14]
In Making Development Geography (2007), Victoria Lawson presents a critique of mainstream development discourse as mere recreation of the Subaltern, which is effected by means of the subaltern being disengaged from other social scales, such as the locale and the community; not considering regional, social class, ethnic group, sexual- and gender-class differences among the peoples and countries being modernized; the continuation of the socio-cultural treatment of the subaltern as a subject of development, as a subordinate who is ignorant of what to do and how to do it; and by excluding the voices of the subject peoples from the formulations of policy and practice used to effect the modernization.[14]
As such, the subaltern are peoples who have been silenced in the administration of the colonial states they constitute, they can be heard by means of their political actions, effected in protest against the discourse of mainstream development, and, thereby, create their own, proper forms of modernization and development. Hence do subaltern social groups create social, political, and cultural movements that contest and disassemble the exclusive claims to power of the Western imperialist powers, and so establish the use and application of local knowledge to create new spaces of opposition and alternative, non-imperialist futures.[14]
植民地主義とオリエンタリズムの知識に基づく主流の開発論は、近代化理論に焦点を当てている。そこでは、発展途上国の近代化は、西洋の先進国がたどった近 代化の道筋(および確立)に従うべきであるとされている。 このように、近代化は自由貿易、開放市場、資本主義経済システム、民主的な統治システムによって特徴づけられる。したがって、主流派の開発論は、国家がそ のような近代化を確立するための普遍的な社会・政治、経済・文化政策の適用に重点を置いている。[14]
ヴィクトリア・ローソンは『Making Development Geography』(2007年)で、主流派の開発論を、サバルタンを単に再生産するものとして批判している。サバルタンは、地域やコミュニティなどの 他の社会的規模から切り離されることで、そのように再生産される。また、近代化される人々や国々の地域、社会階級、民族、性的・性別による違いを考慮しな いこと、 近代化される人々や国々の地域、社会階級、民族、性的・性別による違いを考慮しないこと、サバルタンを開発の主体として、何をどうすべきかを知らない従属 者として社会文化的に扱うことを継続すること、そして、近代化を推進するために用いられる政策や実践の策定から、対象となる人々の声を排除することであ る。
このように、サバルタンとは、彼ら自身が構成する植民地国家の行政において沈黙させられてきた人々である。彼らは、主流派の開発論に対する抗議として行う 政治的行動によって、その声を届けることができる。そして、それによって、彼ら自身にふさわしい近代化と開発の形を作り出すことができる。それゆえ、サバ ルタン社会集団は、西洋の帝国主義勢力の排他的な権力主張に異議を唱え、それを解体する社会、政治、文化運動を生み出し、それによって、新たな対抗勢力と 非帝国主義的未来の空間を創出するための地域的知識の利用と応用を確立する。[14]
Darder, Antonia: Decolonizing Interpretive Research: A Subaltern Methodology for Social Change, Routledge, London/New York 2019.
Santos, Boaventura de Sousa: Toward a New Legal Common Sense, 2nd ed. (London: LexisNexis Butterworths), particularly, 2002: 458–493.
Chakrabarty, Dipesh: Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies. University of Chicago Press 2002.
Rodríguez, Ileana: The Latin American subaltern studies reader. Duke University Press, North Carolina 2001.
Guha, Ranajit: Subaltern Studies Reader, 1986-1995. University of Minnesota Press 1997.
Bhabha, Homi K.: "Unsatisfied: notes on vernacular cosmopolitanism." In: Text and Nation: Cross-Disciplinary Essays on Cultural and National Identities. Ed. Laura Garcia-Moreno and Peter C. Pfeiffer. Columbia, SC: Camden House, 1996: 191-207.
Spivak, Gayatri Chakravorty: "Can the Subaltern Speak?". In: Marxism and the Interpretation of Culture. Eds. Cary Nelson and Lawrence Grossberg. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1988: 271-313.
Darder, Antonia: Decolonizing Interpretive Research: A Subaltern Methodology for Social Change, Routledge, London/New York 2019.
Santos, Boaventura de Sousa: Toward a New Legal Common Sense, 2nd ed. (London: LexisNexis Butterworths), 特に、2002: 458–493.
チャクラバーティ、ディペシュ著『モダニティの住みか:サバルタン研究の余波に関するエッセイ』シカゴ大学出版 2002年
ロドリゲス、イレアナ著『ラテンアメリカ・サバルタン研究読本』デューク大学出版、ノースカロライナ 2001年
グーハ、ラナジット著『サバルタン研究読本、1986-1995』ミネソタ大学出版 1997年
Bhabha, Homi K.: 「満たされない:土着の国際主義についての覚書」Laura Garcia-Moreno と Peter C. Pfeiffer 編『テキストと国家:文化と国家のアイデンティティに関する学際的研究論文』コロンビア、サウスカロライナ州:Camden House、1996年:191-207ページ。
スピヴァク、ガヤトリ・チャクラヴォルティ:「サバルタンは語ることができるか?」『マルクス主義と文化の解釈』編:キャリー・ネルソン、ローレンス・グ ロスバーグ。イリノイ州アーバナ:イリノイ大学出版、1988年:271-313ページ。
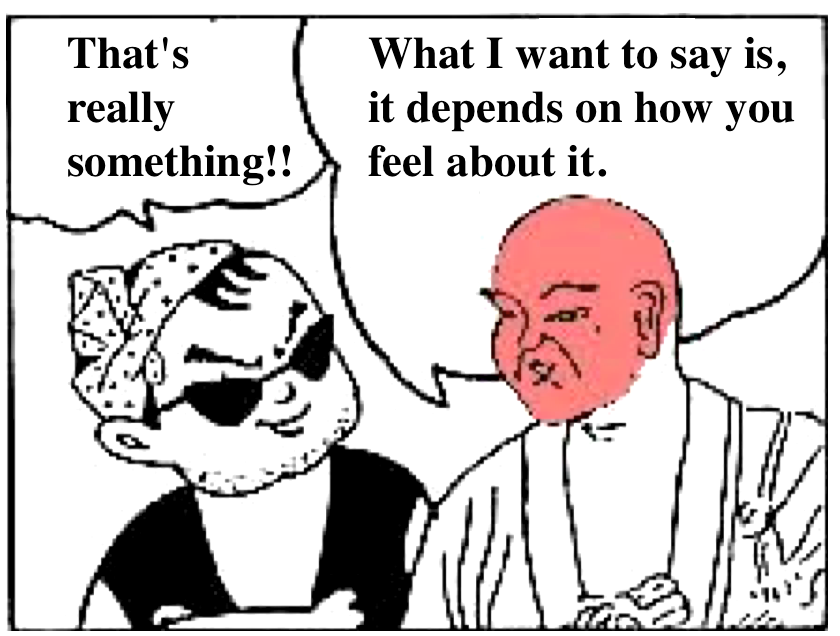

 ☆
☆