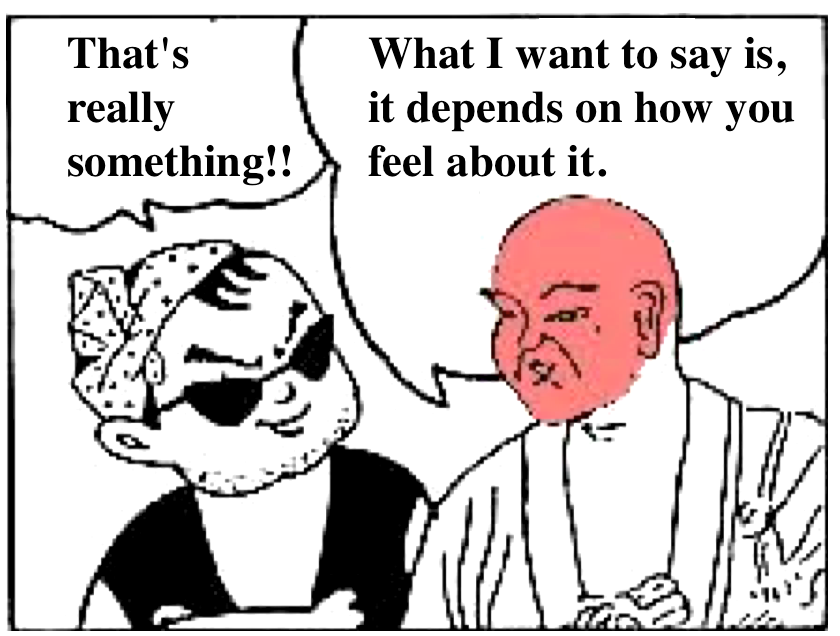
黒人研究リンク
Black Gold People
☆
黒人研究リンク(ベスト20)
| 黒人奴隷の歴史 |
現
在の北アメリカ大陸のアメリカ合衆国(がっしゅうこく、合州国と書く人もいます)が、まだ独立する前の
1619年ごろは、それはイギリスの植民地でした。そのころから、黒人(こくじん)の人がアメリカに移り住んでいました。黒人のひとたちは、アフリカ大陸
に多く住んでいたので、アメリカに住んでいる黒人の人たちを、現在では、
ご先祖さまが住んでいた土地の名前に由来してアフリカ系アメリカ人(アフロ・アメリカン/アフリカン・アメリカン)と言います。 |
| 「三つの人種——原住民・白人・黒人」に関する、現代コロンビア人歴史家サルセド・バスタルド(1986)の言及 |
「ボ
リーバルが生まれた植民地時代のベネズエラは混血社会であったが、原住民インディオ の割合はわずかであった。メキシコやベルーのように圧倒的な原住民
人口もなかったし、インディオが絶滅したため白人と黒人間の人種的混交だけが行なわれた地域のように、原住民がまったくいないといった状態も存在しなかっ
た」。 |
| 人種のステレオタイプ |
人
種とは、科学的に証明することが絶対にでき
ない人間を区分する分類概念です。つまり人種とはある考え方=見方であり事実ではない。しかしながら、人種主義(レイシズ ム)=人種差別思
想があるかぎり、人種の考え方がどのように生まれ、また「人種を信じて疑わない人」がどうしていなくならないのか?まだ人種差別という偏見がどのように維
持されているのかを知ることはとても重要になります!(→お子さまのページに もどります) |
| 奴隷は反抗できるのか? |
は
じめまして、幸村ともうします。最近映画『風と共に去りぬ』が大好きでよく見たり原作を読
んだりしています。そこでセンセイの「黒人奴隷の歴史について教えて!」につい
てウェブページを拝見しいろいろと勉強させていただきました。そこで質問なのですが、あの時代の奴隷制度の中、本当に黒人が(召使)があんなに反抗的で
あったり、意見を述べたりすることができたのでしょうか? |
| 人種 |
人
種とは、人間の種別的差異・種差(specific
difference)によって区分されたカテゴリー(分類範疇)のことである。つまり意味論的に言えば、人種とはある考え方や見方(=パースペクティ
ヴィズム)であり事実(=ホモ・サピエンスは同一種であり人
種なるものは存在しない)ではない。あるいは語用論的みれば人種は(人種差別を目的とする)「社会的構成概念」である。つまり人間のあいだの多様性のなか
を恣 意的にグルーピングして差別化を正当化する擬似科学の術語である(→人種理論)。よ
り平易に言えば、人の集団どおしを差別するためにフランシス・ゴルトンらにより主
張された。今日では非科学的な概念である(→科学的人種主義)(→「人種」概念の歴史)。 |
| 啓蒙思想の中に人種主義が潜んでいる |
「民
主主義の拡大と白人の形成の関連を、啓蒙思想 自体が内包する矛盾であるとする考え方がある。啓蒙思想が拠って立つ普遍主義のあり方そのものに、人種
主義が内在化されているというのである。この考えによると、黒人やその他の有色人種、女性が、一九世紀の政治的・経済的主体から排除されたのは、啓蒙思想
や平等主義が不徹底であったのではなく、啓蒙主義的普遍主義の実現がそのような事態を産んだのである」(藤川 2005:21)。 |
| どうして人には、はだの色にちがいがあるのですか? |
ど
うして人間には、はだや目の色、かみの毛がちがうひとがいるのでしょうか?、またそれはどうしてなので
しょうか?教えてください。→いまから約四万年ぐらい前に新人(しんじん)とよばれる人類があらわれました。わたしたちはその共通の祖
先をもつ、おなじ種類の人間なのです。 |
| カントとレイシズム |
マ
ヌエル・カントは、以下の著作について人 種についての議論をしている。だといっても、カントの『人間
学(アントロポロギー)』同様、カントは、近代文化
人類学いう学問の出発のはるか以前の人なので、いちおう、我々と同列に扱っては可哀想である。カントはカントなりに考えた点を考慮すべきである。 |
| イタリアのファシズムと人種差別 |
ファ
シストイタリアは、第二次世界大戦の枢軸国パートナーであるナチス ドイツとは異なり、当初は包括的な人種差別政策を持っていなかった。1938
年以降、差別と迫害は激化し、イタリアのファシストのイデオロギーと政策のますます重要な特徴となった[4]。それにもかかわらず、ムッソリーニとイタリ
ア 軍は人種宣言で採択された法律を一貫して適用しなかった[5] 1943
年、ムッソリーニは、この支持を避けられた可能性があったと述べ、遺憾の意を表明した[6]。最終的に、第二次イタリア・エチオピア戦争後,
イタリアのファシスト政府はエチオピアで白人と黒人の厳格な人種隔離を実施した。 |
| ラテンアメリカにおける人種概念 |
人
種主義は人間の種的分類概 念として19世紀を席
巻した生物学上の概念であり、20世紀にはその概念そのものが問題に伏されるものになり、21世紀には、人種が社会的構築物であるという合意であるという
認識にたどり着いた多様な変化の来歴がある。ラテンアメリカにおける人種(raza,
race)は、地理的変異、文化的変異、身体形質的変異を表現する用語として広く行き渡っている。その定義は曖昧で多様で、人種の概念がリジッドな北米に
比 べると、ラテンアメリカでは多様な人種的概念が横溢している。 |
| フランツ・ファノン『黒い肌・白い仮面』結論 |
『黒い肌、白い仮面』は、1952年に『Peau noire,
masques
blancs』としてフランス語で出版されたファノンの最も重要な作品のひとつである。黒い肌、白い仮面』の中でファノンは、抑圧された黒人が、自分たち
の住む白人の世界では劣った生き物でなければならないと認識されることを精神分析し、彼らが白人性のパフォーマンスを通してどのように世界をナビゲートす
るかを研究している。
[最終的に彼は、「白人として認識されるための(白人/植民者の)言語の習得は、黒人の人間性を従属させる依存を反映している」と結論付けている
[37]。
博士論文を含む彼の未発表の著作はほとんど注目されていない一方で、彼の著作の受容は、多くの脱落や誤りを含むと認識されている英訳によって影響を受けて
いる。その結果、ファノンはしばしば暴力の擁護者として描かれ(非暴力の弁証法的反対者というのがより正確だろう)、彼の思想は極端に単純化されすぎてい
ると論じられてきた。ファノンの著作に対するこのような還元主義的な見方は、植民地体制に対する彼の理解の繊細さを無視している。例えば、『黒い肌、白い
仮面』の第5章は、文字どおり「黒人の生きた経験」("L'expérience vécue du
Noir")と訳されているが、マークマンの訳は「黒人の事実」であり、ファノンの初期の仕事に現象学が与えた多大な影響を省いている[38]。
(出典:フランツ・ファノン) |
| 『ニグロの家族:国家行動のための事例研究』 |
『ニグロの家族』 一般に「モイニハン報告」として知られるThe
Negro Family: The Case For National Action, 1965.は、
リンドン・B・ジョンソン大統領の下で労働次官補を務め、後に上院議員になったアメリカの学者ダニエル・パトリック・モイニハンが1965年に書いた、ア
メリカにおける黒人の貧困に関する報告書である。モイニハンは、黒人の母子家庭の増加は、仕事の不足が原因ではなく、ゲットー文化の破壊的な脈絡が原因で
あると主張した。ダニエル・パトリック・モイニハン(Daniel Patrick Moynihan、1927年3月16日 -
2003年3月26日)は、アメリカの政治家、外交官。民主党に所属し、リチャード・ニクソン大統領の顧問を務めた後、1977年から2001年まで
ニューヨーク州選出の上院議員を務めた。 |
| アフリカ系プエルトリコ人 |
アフロ・プエルトリカンとは、アフリカ系黒人の血を引くプエルトリコ人 のことである[2][3]。 アフリカ系プエルトリコ人の歴史は、スペインのコンキスタドール(征服者)たちの島への侵攻に同行した、リベルトスと呼ばれる自由なアフリカ人男性から始ま る。 |
| 『ブラック・アトランティック』 |
『ブラック・アトランティック:モダニティと二重の意識』は、アフリ
カ、アメリカ、イギリス、カリブ海の文化の要素を取り入れた、独特なブラック・アトラ
ンティック文化に関する1993年の歴史書である。ポール・ギルロイ著、ハーバード大学出版局およびヴァーソ・ブックス刊。 |
| 奴隷状態への帰還あるいは啓蒙の逆説 |
「1838年、平和なバルバドス島(西インド諸島小アンティル列島中の
島。英領)で血みどろの暴動が起こっ た。
つい最近の三月の法令により、自由の身分に昇格したばかりの男女約二百名の黒人たちが、ある朝、かつての彼らの
主人であるグレネルグという者の家に、自分たちをふたたび元の奴隷の身分にしてくれと陳情しに来たのであ
る。陳情書を起草し、グレネルグの前でこれを読んだのは、仲間の一人である再洗礼派(アナバブティスト)の牧師であった。それか
ら議論が始まった。……」『O嬢の物語』 |
| カラー・ブラインドは本当に人種偏見から自由になれるか? |
カラー・ブラインド(color
blind)とは、色盲(しきもう=多色構成の人工物において色認識の峻別のタイプが多数派とは異なる人たち)のことである。このような人間の生理感覚の
多様性から、黒人と白人
が共存しながらも肌の色による峻別と差別や偏見が存在する社会状況において、カラー・ブラインドとは、肌の色で人びとを峻別しない態度、つまり人種偏見の
ないという表現が使われるようになった。OEDには、それが米語であることを示唆されており(生理感覚上の色盲の意味の次に)"Taking no
note of differences in racial colour, in sex,
etc."とその定義が記載されている。また、この意味での、カラーブラインド/カラー・ブ
ラインドの用法は、OEDによると、すでに19世紀後半にみとめられるという。 |
| 排除のためのコミュニケーションデザイン |
居住地などにおいて、新しい富裕層が入ってきて、利用料・使用料が上がるなどの旧住民にとっての排除につながる現象を「ジェントリフィケーション」と呼びます。 |
| コード・ノワール |
黒人法(Code noir; フ ランス語発音:[kɔd
nwaʁ]、Black
code)は、1685年にフランス王ルイ14世が発布した勅令であり、フランス植民地帝国における奴隷制の条件を規定した。この勅令は、フランス革命の
始まりを告げる年となった1789年まで、フランス植民地における奴隷制の行動規範として機能した。この法令は自由な有色人種の活動を制限し、帝国内の全
ての奴隷に対してカトリックへの改宗を義務付け、彼らに科される処罰を定め、フランスの植民地から全てのユダヤ人の追放を命じた。
この法典がフランス植民地帝国の奴隷人口に与えた影響は複雑かつ多面的であった。この法典により、所有者が奴隷に与えることのできる最悪の処罰が禁止さ
れ、自由民の人口が増加した。しかし、それでも奴隷は所有者の手による厳しい扱いを受けることには変わりなく、ユダヤ人の追放はフランス王国における反ユ
ダヤ主義の傾向の延長であった。
自由な有色人種は、黒人法によって依然として制限を受けていたが、それ以外では自由に自分のキャリアを追求することができた。アメリカ大陸における他の
ヨーロッパの植民地と比較すると、フランス植民地帝国における自由有色人種は、読み書きができる可能性が非常に高く、事業や不動産、さらには自分の奴隷を
所有する可能性も高かった。[1][2][3]
この法典は、近代フランス史の専門家であるタイラー・ストヴァル氏によって、「人種、奴隷制、自由に関する最も広範な公式文書であり、ヨーロッパで作成さ
れたものの中で最も広範な公式文書である」と評されている。[4] |
| W.E.B.デュボイス |
ウィリアム・エドワード・バーグハルト・デュボイス ( William Edward Burghardt Du Bois1868年2月23日 - 1963年8月27日)は、アメリカの社会学者、社会主義者、歴史学者、汎アフリカ主義者、公民権運動家である。 |
| アメリカ合州國は人種差別國家か? |
サウスカロライナ
州選出の共和党上院議員ティム・スコットが、ジョー・バイデン大統領の議会演説を受けて「アメリカは人種差別主義者の国ではない」と発言し、多くの人々に
衝撃を与えた。彼は自分自身が「差別の痛み」を経験したことがあることを認め、「理由もなく車を止められたり、買い物中に店内をつきまとわれたりするのが
どんな気分か、私にはわかる」と述べた。翌日、ABCの『グッド・モーニング・アメリカ』で質問されたカマラ・ハリス副大統領は、「アメリカは人種差別主
義者の国ではないと思う」と答え、スコット氏に同意しているように見えた。しかし、その直後に彼女は、"しかし、私たちはまた、私たちの国における人種差
別の歴史とその今日の存在について真実を語らなければなりません "と指摘した。 |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆