
先住民の脱植民地化
Indigenous decolonization
An example of a piece within the new Indigenous and Canadian Gallery at the National Art Gallery of Canada
☆先住民による脱植民地化(Indigenous decolonization) とは、先住民のコミュニティの歴史や、植民地拡大、文化同化、搾取的な西洋の研究、そして必ずしもアプリオリではないが、しばしばジェノサイド(大量虐殺)の 影響に関する物語を再構築し、論争することを目的とした、現在進行中の理論的・政治的プロセスを指す。脱植民地化に取り組む先住民は、西洋中心の研 究手法や言説に対して批判的な立場を取り、︎︎︎知識を先住民の文化的な慣習の中に再配置しようとしている。 西洋の政治思想の構造に依存する脱植民地化の取り組みは、逆説的に文化的な所有権の剥奪をさらに進めるものとして特徴づけられてきた。この文脈において、 たとえこれらの実践が政治的な承認に容易に結びつかないとしても、独立した知的、精神的、社会的、物理的な回復と再生の取り組みを行うべきであるという呼 びかけがなされてきた。学者たちは、先住民の脱植民地化を「人種差別と性差別への取り組みなしには、すべての人々を解放することはできない」交差する闘い として特徴づけることもある。 先住民の脱植民地化運動の理論的な側面を超えて、脱植民地化のための直接行動キャンペーン、ヒーリング・ジャーニー、身体を伴う社会闘争は、現在も続く先 住民の抵抗運動や、土地所有権、生態系の採取、政治的疎外、主権をめぐる論争と関連していることが多い。先住民の抵抗運動は何世紀にもわたって続いてきた が、先住民の活動が活発化したのは1960年代で、これはアフリカ、アジア、アメリカ大陸における国民解放運動と時を同じくしていた(→「脱植民地化の方法論」「植民地主義に対する先住民の反応」)。
| Indigenous
decolonization Indigenous decolonization describes ongoing theoretical and political processes whose goal is to contest and reframe narratives about indigenous community histories and the effects of colonial expansion, cultural assimilation, exploitative Western research, and often though not inherent, genocide.[1] Indigenous people engaged in decolonization work adopt a critical stance towards western-centric research practices and discourse and seek to reposition knowledge within Indigenous cultural practices.[1] |
先住民による脱植民地化 先住民による脱植民地化とは、先住民のコミュニティの歴史や、植民地拡 大、文化同化、搾取的な西洋の研究、そして必ずしも先天的ではないが、しばしばジェノサイド(大量虐殺)の影響に関する物語を再構築し、論争することを目 的とした、現在進行中の理論的・政治的プロセスを指す。脱植民地化に取り組む先住民は、西洋中心の研究手法や言説に対して批判的な立場を取り、知識を先住 民の文化的な慣習の中に再配置しようとしている。 |
| The decolonial work that relies on structures of western political thought has been characterized as paradoxically furthering cultural dispossession. In this context, there has been a call for the use of independent intellectual, spiritual, social, and physical reclamation and rejuvenation even if these practices do not translate readily into political recognition.[2] Scholars may also characterize indigenous decolonization as an intersectional struggle that "cannot liberate all people without first addressing racism and sexism."[1] | 西洋の政治思想の構造に依存する脱植民地化の取り組みは、逆説的に文化的な所有権の剥奪をさらに進めるものとして特徴づけられてきた。この文脈において、 たとえこれらの実践が政治的な承認に容易に結びつかないとしても、独立した知的、精神的、社会的、物理的な回復と再生の取り組みを行うべきであるという呼 びかけがなされてきた。[2] 学者たちは、先住民の脱植民地化を「人種差別と性差別への取り組みなしには、すべての人々を解放することはできない」[1] 交差する闘いとして特徴づけることもある。 |
| Beyond the theoretical dimensions of indigenous-decolonization work, direct action campaigns, healing journeys, and embodied social struggles for decolonization are frequently associated with ongoing native resistance struggles and disputes over land rights, ecological extraction, political marginalization, and sovereignty. While native resistance struggles have gone on for centuries, an upsurge of indigenous activism took place in the 1960s - coinciding with national liberation movements in Africa, Asia, and the Americas.[3] | 先住民の脱植民地化運動の理論的な側面を超えて、脱植民地化のための直接行動キャンペーン、ヒーリング・ジャーニー、身体を伴う社会闘争は、現在も続く先 住民の抵抗運動や、土地所有権、生態系の採取、政治的疎外、主権をめぐる論争と関連していることが多い。先住民の抵抗運動は何世紀にもわたって続いてきた が、先住民の活動が活発化したのは1960年代で、これはアフリカ、アジア、アメリカ大陸における国民解放運動と時を同じくしていた。[3] |
| Methods | 方法 |
|
Indigenous Postcolonial Theory Coined by Anna Lees, the methodology of "Indigenous Postcolonial Theory" builds upon and draws clear distinctions from other schools of postcolonial or decolonial thought.[4] First, the prefix post– doesn’t refer to a period of time, but rather a perpetual ambition of eradicating the political and social power imbalances and effects of colonization that manifest in efforts to culturally assimilate and stereotype Native Americans.[5] Secondly, Indigenous Postcolonial Theory was developed as an alternative method to exercising a broad, blanket critical theory to particularly center indigenous knowledge and values rather than applying a wholesale form of decolonization to Indigenous-specific trauma, strive, love, and joy.[4] Similarly, Marie Battiste posits that Indigenous Postcolonial Theory offers a method of deconstructing the layers and intricacies of colonization, its effect, and its underlying assumptions, in a way that Eurocentric theory is unable to do. She says, "[IPT] is based on our pain and our experiences, and it refuses to allow others to appropriate this pain and these experiences."[5] |
先住民ポストコロニアル理論 アンナ・リースが提唱した「先住民ポストコロニアル理論」の方法論は、他のポストコロニアル思想や脱植民地主義思想の学派を基盤とし、それらと明確な区別 を設けている。[4] まず、接頭辞「ポスト」は、特定の期間を指すのではなく、むしろ、ネイティブアメリカンを文化的に同化し固定観念化しようとする試みに現れる、植民地化に よる政治的・社会的権力の不均衡や影響を根絶するという永遠の志を意味する。[5] 第二に、先住民ポストコロニアル 理論は、植民地解放の画一的な形態を先住民特有のトラウマ、努力、愛、喜びなどに適用するのではなく、特に土着の知識や価値観に焦点を当てた広範かつ包括 的な批判理論の代替的手法として開発された。[4] 同様に、マリー・バティストは、先住民ポストコロニアル理論は、植民地化の層や複雑さ、その影響、その根底にある仮定を、脱構築する方法を提供しており、 それは欧州中心主義理論では不可能なことであると主張している。彼女は言う。「IPTは私たちの痛みと経験に基づいている。そして、この痛みと経験を他者 に利用されることを拒否する」[5] |
|
Survivance, sovereignty, and rhetorical sovereignty Gerald Vizenor coined the term survivance to characterize the struggle of colonized indigenous communities.[6] Combining the words "survival" and "resistance", he evokes "the duality of how Native Americans have survived brutal genocides and continue to resist white supremacist laws and culture that are designed to disenfranchise and assimilate". According to Vizenor, "Survivance is an active sense of presence, the continuance of native stories, not a mere reaction, or survivable name. Native survivance stories are renunciation of dominance, tragedy, and victimry." Thus, survivance is defined as "the resistance (of) colonial tendencies to resign indigeneity to the past by characterizing an ongoing state of being in response to colonizing efforts." According to King, Gubele, and Anderson, the study and "decolonization" of Native American Indigeneity "requires an understanding of the importance of sovereignty to American Indian nations…"[7] In this context, he defines sovereignty as including the localized self-determination of a people, as well as the political authority of nationhood and the recognition of equal-status with similarly sovereign international peers. King, Gubele, and Anderson believe that not only is this crucial for political purposes, but it's crucial for cultural and religious purposes, as well: "For Native nations, this kind of a nation is defined by a peoplehood, a concept that has its roots in the preservation and prospering of the community and binds its members together in cultural and often religious terms."[7] Citing the history of changes in US legislative terminology that sequentially redefined indigenous "nations" to "tribes" and "treaties" to "agreements", Stephen R. Lyons sought to generate a standard of "rhetorical sovereignty". Lyons looks at what he identifies as being "the communicative practices of the colonizer", and how consequently, indigenous representations and freedoms are constrained, as a result. He says, "Rhetorical sovereignty is the inherent right of peoples to determine their own communicative needs and desires in this pursuit, to decide for themselves the goals, modes, styles, and languages of public discourse."[8] In essence, the ambition of Indigenous rhetorical sovereignty is the desire to give rhetorical control, and thus representational control, to Indigenous ethnic groups. |
生存、主権、そして修辞的主権 ジェラルド・ヴィゼナーは、植民地化された先住民コミュニティの闘争を表現するために「サヴァイヴァンス」という言葉を造語した。[6] 「生存」と「抵抗」という言葉を組み合わせたこの言葉は、「ネイティブアメリカンが残虐な大量虐殺を生き延び、白人至上主義の法律や、市民権を剥奪し同化 を目的とした文化に抵抗し続けているという二面性」を想起させる。ヴィゼナーによれば、「サヴァイヴァンスとは、ネイティブの物語の継続であり、単なる反 応や生き残りの名ではない。ネイティブのサヴァイヴァンスの物語は、支配、悲劇、犠牲の放棄である」という。したがって、サヴァイヴァンスとは、「植民地 化の努力に対する継続中の存在状態を特徴づけることで、先住民性を過去のものとして諦める植民地化の傾向に対する抵抗」と定義される。 キング、グベレ、アンダーソンによると、ネイティブアメリカンの先住民性に関する研究と「脱植民地化」には、「アメリカンインディアン国家にとっての主権 の重要性を理解することが必要である」[7]。この文脈において、彼らは主権を、民族の地域的な自己決定、国家としての政治的権限、同等の主権を持つ国際 的な同輩との対等な地位の承認を含むものと定義している。キング、グビレ、アンダーソンは、これは政治的な目的だけでなく、文化や宗教的な目的においても 重要であると考えている。「先住民の国家にとって、この種の国家は民族性によって定義される。この概念は、コミュニティの維持と繁栄にそのルーツを持ち、 文化や宗教的な観点からそのメンバーを結びつけるものである」[7] スティーブン・R・ライオンズは、米国の立法用語の変遷の歴史を挙げ、先住民の「国家」を「部族」に、また「条約」を「合意」に順次再定義してきたことを 指摘し、「修辞的主権」の基準を確立しようとした。ライオンズは、彼が「植民地主義者のコミュニケーション慣行」と名付けたものに注目し、その結果として 先住民の表現や自由がどのように制約されているかを調べている。「修辞的主権とは、この追求において、自らのコミュニケーション上のニーズや欲求を決定 し、公共の議論の目標、様式、スタイル、言語を自ら決定する、人々の固有の権利である」と彼は言う。[8] 要するに、先住民の修辞的主権の野望とは、修辞的なコントロール、ひいては表現上のコントロールを先住民の民族集団に与えたいという願いである。 |
|
Narrative, counter-storytelling, and testimonies Thomas King states in his book The Truth about Stories: A Native Narrative that stories have a substantial impact on the human condition and humans’ constructed reality as a whole. They frame human relationships, perspectives, and moral codes.[9] As King, Gubele, and Anderson put it, "The stories we tell each other tell us who we are, locate us in time and space and history and land, and suggest who gets to speak and how."[7] Similarly, the stories that are widely disseminated or suppressed indicate similar societal expectations and limitations. Norman Denzin, Yvonna Lincoln, and Linda Smith, in their book titled "Handbook of Critical and Indigenous Methodologies", assert that "The Euro-American canon and its continuance of Greco-Roman traditions has deliberately marginalized indigenous stories that manifest in practices of theorizing, speaking, writing, and making", and that the telling of such stories would provide "alternatives to and challenge dominant narratives", thus becoming counter-narratives to them.[10] Linda Tuhiwai Smith writes that storytelling is a means of connecting past generations to the future ones and the land to the community by "passing down the beliefs and values of a culture in the hope that the new generations will treasure them and pass the story down further."[11] The themes and motifs of these stories pass down shared histories, knowledge, and cultural identity that can range from "humour and gossip and creativity… [to] love, sexual encounters, … [and] war and revenge."[12] Indigenous testimonies are a means and practice of pushing back against oppression and suppression by providing oral evidence about a painful experience or series of experiences. Linda Tuhiwai Smith writes that testimonies are contingent on a formal structure, a supportive atmosphere and audience, and upholding "a notion that truth is being revealed ‘under oath.’"[12] |
物語、反物語、証言 トーマス・キングは著書『物語の真実: 物語は人間の条件や人間が作り上げた現実全体に多大な影響を与えると述べている。物語は人間関係、視点、道徳規範を形作るのである。[9] キング、グベレ、アンダーソンが言うように、「私たちが互いに語る物語は、私たち自身について語り、私たちを時間と空間、歴史、土地の中に位置づけ、誰が 何を語るのかを示唆する」のである。[7] 同様に、広く普及したり、抑圧されたりする物語も、同様の社会的期待や限界を示している。ノーマン・デンジン、イヴォンナ・リンカーン、リンダ・スミス は、著書『批判的・土着的方法論ハンドブック』の中で、「ヨーロッパ・アメリカ的な正典と、そのギリシャ・ローマの伝統の継続は、理論化、発言、執筆、制 作の実践において、土着の物語を意図的に周辺化してきた」と主張している。また、そのような物語を語ることは、「支配的な物語に対する代替案と挑戦」とな り、それらに対するカウンター・ナラティブとなる、とも述べている。 リンダ・トゥヒワイ・スミスは、物語を語ることによって、過去の世代と未来の世代、そして土地とコミュニティを結びつけることができると述べている。「文 化の信念や価値観を語り継ぐことで、新しい世代がそれらを大切にし、さらにその物語を語り継いでくれることを願って 。これらの物語のテーマやモチーフは、共有された歴史、知識、文化的なアイデンティティを伝承するものであり、その範囲は「ユーモアやゴシップ、創造性… [から]愛、性的遭遇、…[そして]戦争や復讐」まで多岐にわたる。 先住民の証言は、苦痛を伴う経験や一連の経験に関する口頭による証拠を提供することで、抑圧や弾圧に抵抗する手段であり、実践である。リンダ・トゥヒワ イ・スミスは、証言は正式な構造、協力的な雰囲気、聴衆、そして「宣誓の下で真実が明らかになる」という概念に依存していると書いている。 |
|
Food sovereignty It has been speculated that food sovereignty is a means of providing a path towards decolonization. Its definition, in recent years, has been noted to be highly modifiable due to its dependency on the context of the circumstances to which it is applied.[13][14] In indigenous context, where sovereignty does not serve the right meaning and political intent,[13][15] the concept of food sovereignty sometimes does not follow the traditional meanings of each individual word.[13][15] It has been discussed and theorized in the indigenous context of the concept that food sovereignty is also an effort of reclaiming culture and former relationship to land;[13][15][14] it has also been noted that, as a situational concept, food sovereignty in the traditional sense may have underlying traces of capitalist or colonialist interests.[14] Food sovereignty's adaptable definition in the context of indigenous decolonization, in relation to the reclamation of culture, is then highly hypothesized to be a strong route towards decolonization.[13][14] |
食料主権 食料主権は脱植民地化への道筋を提供する手段であると推測されている。近年では、適用される状況の文脈に依存するため、その定義は極めて変更可能であるこ とが指摘されている。[13][14] 主権が正しい意味や政治的意図を果たさない先住民の文脈では、[13][15] 食料主権の概念は、個々の単語の伝統的な意味に従わないこともある。[13][15] 先住民の文脈において、食料主権は文化や土地との以前の関係を取り戻す取り組みでもあるという概念が議論され、理論化されてきた。[13][15] [14] また、状況に応じた概念として、伝統的な意味での食料主権には 資本主義や植民地主義の利害関係が根底にある可能性があるという指摘もある。[14] 食料主権の定義は、先住民の脱植民地化という文脈において、文化の再生と関連して適応可能なものであり、脱植民地化への強力な手段であるという仮説が有力 である。[13][14] |
| Challenges and initiatives This section is written like a personal reflection, personal essay, or argumentative essay that states a Wikipedia editor's personal feelings or presents an original argument about a topic. Please help improve it by rewriting it in an encyclopedic style. (August 2023) (Learn how and when to remove this message) |
課題と取り組み この節は、ウィキペディア編集者の個人的な感想や意見、あるいはトピックに関する独自の主張を述べた、個人的な考察、私的なエッセイ、論説のような書き方 をしている。百科事典的なスタイルに書き直して、改善にご協力ください。 (2023年8月) (このメッセージの削除方法とタイミングについてはこちらをご覧ください) |
|
Reclaiming indigenous knowledge and practices Indigenous knowledge and practices are deeply embedded in Indigenous cultures and encompass a wide array of systems, including traditional ecological knowledge, spiritual beliefs, healing practices, storytelling, and artistic expressions. However, the historical colonization of Indigenous communities has systematically devalued and suppressed these knowledge systems.[16] Colonial powers have imposed Western worldviews and systems on indigenous communities suppressing their cultures, languages, and spiritual beliefs. To address this, scholars like Winona LaDuke advocate for the reclamation and revitalization of Indigenous knowledge as an integral part of the decolonization process.[17] Organizations such as the First Peoples' Cultural Council in Canada and the Advocates for Indigenous California Language Survival in the United States actively work to revitalize Indigenous languages and support language revitalization initiatives.[18][19] The First Peoples' Cultural Council, in particular, prioritizes cultural revitalization and youth engagement within Canada. They offer funding, training, and resources for language programs, traditional arts, and cultural preservation projects and utilize digital platforms to make cultural knowledge accessible while respecting Indigenous protocols.[18] |
先住民の知識と慣習の回復 先住民の知識と慣習は、先住民の文化に深く根付いており、伝統的環境知識、精神的な信念、治療法、物語、芸術表現など、幅広い体系を包含している。しか し、先住民コミュニティに対する歴史的な植民地化は、これらの知識体系を体系的に軽視し、抑圧してきた。[16] 植民地支配国は、西洋的世界観やシステムを先住民コミュニティに押し付け、彼らの文化、言語、精神的な信念を抑制してきた。これに対処するために、ウィノ ナ・ラドルークのような学者は、脱植民地化プロセスの不可欠な一部として、先住民の知識の再生と活性化を提唱している。[17] カナダのファースト・ピープルズ・カルチュラル・カウンシルや米国の先住民カリフォルニア語存続の会などの組織は、先住民の言語の復興に積極的に取り組 み、言語復興の取り組みを支援している。[18][19] 特にファースト・ピープルズ・カルチュラル・カウンシルは、カナダ国内における文化復興と若者の参加を優先課題としている。 彼らは言語プログラム、伝統芸術、文化保存プロジェクトに資金援助、トレーニング、リソースを提供し、デジタルプラットフォームを活用して、先住民の慣習 を尊重しながら文化的な知識へのアクセスを可能にしている。[18] |
|
Overcoming symbolic and superficial decolonization Despite the abundance of decolonization efforts, many of them are symbolic and superficial and fail to address the underlying structures of power and inequality.[20] These approaches often create an illusion of progress without effectively addressing the systemic injustices faced by Indigenous communities. One such gesture is the renaming of a school after an Indigenous leader.[21] This tokenistic gesture is done in place of incorporating Indigenous knowledge systems into their curricula or providing substantial support to Indigenous students and communities. In response, scholars like Tuck and Yang criticize these gestures and emphasize the importance of challenging systems of colonization through the acknowledgment of Indigenous rights through substantive actions like land repatriation.[22] More recent efforts[when?] towards land repatriation come from The Indigenous Land Stewardship - an initiative led by Indigenous communities and organizations such as the Native Land Conservancy and the Cultural Conservancy. They prioritize land repatriation, ecological restoration, and the revitalization of traditional land management practices, ensuring that Indigenous peoples have control and decision-making power over their ancestral territories.[23] |
象徴的で表面的な脱植民地化の克服 脱植民地化の取り組みは数多くあるが、その多くは象徴的で表面的であり、権力や不平等性の根底にある構造に目を向けようとしていない。[20] こうしたアプローチは、先住民コミュニティが直面する構造的不正義に効果的に対処することなく、進歩の幻想を生み出すことが多い。その一例が、先住民の指 導者の名を冠した学校の名称変更である。[21] このような形だけの行為は、先住民の知識体系をカリキュラムに組み入れたり、先住民の学生やコミュニティに実質的な支援を提供したりすることの代わりに行 われる。これに対して、タックやヤンといった学者は、こうした行為を批判し、土地返還のような実質的な行動を通じて先住民の権利を認めることで、植民地化 のシステムに異議を唱えることの重要性を強調している。[22] 土地返還に向けたより最近の取り組み[いつ?]は、先住民土地管理(The Indigenous Land Stewardship)によるもので、ネイティブ・ランド・コンサーバンシー(Native Land Conservancy)や文化コンサーバンシー(Cultural Conservancy)などの先住民コミュニティや組織が主導している。彼らは土地返還、生態系の復元、伝統的土地管理手法の復活を優先し、先住民が先 祖伝来の領土を管理し、意思決定を行う力を確保することを目指している。 |
|
Sovereignty and borders Sovereignty and borders is also a contested issue in the decolonization process, particularly within the context of settler colonialism.[24] Reclaiming Indigenous lands and asserting political autonomy are key components of challenging the structures of settler governance. Sovereignty allows Indigenous peoples to govern themselves according to their own laws, traditions, and values, reinforcing their cultural identity and promoting the revitalization of Indigenous knowledge and practices. Recognizing the artificial nature of borders is crucial, as they often hinder Indigenous self-determination and governance.[25] A notable example comes from the lack of acknowledgment of the Mohawk people's sovereign right to cross the US-Canada border that predates Canada and the U.S.[24] Efforts led by organizations like the Native American Rights Fund (NARF) aim to defend tribal sovereignty, protect treaty rights, support land and resource reclamation, and address border-related issues impacting Indigenous communities. Through legal representation and advocacy, NARF defends tribal sovereignty, protects treaty rights, and supports efforts to reclaim ancestral lands and resources. They also address border-related issues impacting Indigenous communities and work towards the recognition of traditional border-crossing rights.[26] |
主権と国境 主権と国境もまた、脱植民地化の過程において、特に入植者による植民地主義の文脈において、論争の的となっている問題である。[24] 先住民の土地の回復と政治的自治の主張は、入植者による統治構造に異議を唱えるための重要な要素である。主権は、先住民が独自の法律、伝統、価値観に従っ て自らを統治することを可能にし、彼らの文化的アイデンティティを強化し、先住民の知識と慣習の再生を促進する。国境の人工的な性質を認識することは極め て重要である。なぜなら、国境はしばしば先住民の自己決定と統治を妨げるからである。[25] 注目すべき例として、カナダと米国に先立つ時代にモホーク族が有していた、米国とカナダの国境を越える主権的権利が認められていなかったことが挙げられ る。[24] ネイティブ・アメリカン・ライツ・ファンド(NARF)のような組織が主導する取り組みは、部族の主権を守り、条約上の権利を保護し、土地や資源の再生を 支援し、先住民コミュニティに影響を与える国境関連の問題に対処することを目的としている。NARFは、法的代理や擁護活動を通じて、部族の主権を守り、 条約上の権利を保護し、先祖伝来の土地や資源の再生に向けた取り組みを支援している。また、国境関連の問題が先住民コミュニティに与える影響に対処し、伝 統的な国境越えの権利の承認に向けた取り組みも行っている。 |
| contin. |
★次の項目に進む |
★先住民による脱植民地化(Indigenous decolonization)【続き】
|
Decolonizing education Decolonizing education aims to challenge and transform existing educational systems that have historically perpetuated colonization and marginalized Indigenous knowledge and ways of knowing. In particular, it aims to center Indigenous knowledge systems, languages, and cultural perspectives within educational institutions.[27] Battiste in particular emphasizes the importance of revitalizing Indigenous languages and traditions, promoting Indigenous ways of knowing.[28] She promotes Indigenous ways of knowing in education and fostering cultural pride and identity among Indigenous students. Organizations like the National Association for Indigenous Studies (NAISA) also advocate for decolonizing education through transforming curricula, promoting Indigenous methodologies, revitalizing languages and cultures, and supporting Indigenous teacher education. Their work aims to challenge colonial legacies and create culturally responsive and inclusive educational environments.[29] |
脱植民地化教育 脱植民地化教育は、歴史的に植民地化を永続させ、先住民の知識や認識の方法を疎外してきた既存の教育システムに異議を唱え、変革することを目的としてい る。特に、教育機関において、先住民の知識体系、言語、文化的な視点を中心とすることを目的としている。[27] バティストは特に、先住民の言語や伝統を活性化させ、先住民の認識方法を推進することの重要性を強調している。[28] 彼女は、教育において先住民の認識方法を推進し、先住民の学生たちの文化的誇りとアイデンティティの育成を促進している。 全米先住民研究協会(NAISA)のような組織も、カリキュラムの改革、先住民の方法論の推進、言語と文化の復興、先住民の教員教育の支援などを通じて脱 植民地化教育を提唱している。彼らの活動は、植民地時代の遺産に異議を唱え、文化的に適切な包括的な教育環境を作り出すことを目的としている。 |
| Indigenous research methods Prioritizing Indigenous research methodologies is also essential in decolonizing research practices and generating knowledge that serves Indigenous communities. Shawn Wilson's book "Research is Ceremony: Indigenous Research Methods" promotes the use of Indigenous research approaches rooted in Indigenous protocols, ethics, and knowledge systems.[30] It emphasizes community engagement, reciprocity, and the affirmation of Indigenous perspectives and voices. Similarly, Linda Tuhiwai Smith highlights the importance of centering Indigenous worldviews and methodologies while respecting cultural protocols, including obtaining free, prior, and informed consent.[31] NAISA also promotes Indigenous research methods through various initiatives including organizing research methodology workshops, developing Indigenous research ethics guidelines, and providing platforms for sharing Indigenous knowledge and research findings. They also support Indigenous researchers through mentorship programs, networking opportunities, and research funding emphasizing collaboration with Indigenous communities. They also encourage community-driven research that respects cultural protocols and community ownership.[29] |
先住民との研究方法 先住民の研究方法を優先することは、研究の実践を脱植民地化し、先住民のコミュニティに役立つ知識を生み出す上でも不可欠である。ショーン・ウィルソンの 著書『Research is Ceremony: Indigenous Research Methods [pdf] by Shawn Wilson, 2008』は、先住民の儀式、倫理、知識体系に根ざした先住民の研究アプローチの使用を推進している。[30] この本では、コミュニティの関与、相互性、先住民の視点や声の肯定が強調されている。同様に、リンダ・トゥヒワイ・スミスは、自由意思による事前の十分な 説明に基づく同意=インフォームド・コンセント(free, prior, and informed consent)の取得を含む文化的な儀式を尊重しながら、先住民の世界観と方法論を重視することの重要性を強調している。[31] NAISA(Native American and Indigenous Studies Association)も、研究方法ワークショップの開催、先住民研究倫理ガイドラインの策定、先住民の知識や研究結果を共有するためのプラットフォームの提供など、 さまざまな取り組みを通じて先住民研究法を推進している。また、先住民コミュニティとの協力を重視した指導プログラム、ネットワーキングの機会、研究資金 提供を通じて、先住民研究者を支援している。さらに、文化的な慣習やコミュニティの所有権を尊重したコミュニティ主導の研究も奨励している。[29] |
| Implications of Western knowledge production and epistemologies As Western scientists and academics have and continue to take advantage of knowledge from and about Indigenous communities (whether in publications[32][33] or through new pharmaceuticals[34][35]), those Indigenous communities are excluded from control over the nature and usage of the newly created knowledge. Thus, Indigenous communities are spoken for and become the indigenous "other" as those institutional systems and structures reproduce a knowledge that "becomes a commodity of colonial exploitation".[36] This continues to reinforce the privileging of Western knowledge and epistemologies over non-Western or Indigenous funds of knowledge (or traditional knowledge) in Western academia. This privilege manifests itself when, according to Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, "Indigenous knowledge systems are too frequently made into objects of study, treated as if they were instances of quaint folk theory held by the members of a primitive culture."[10] Indigenous decolonization seeks a dramatic shift in the subject of academic inquiry. Rather than comparing Indigenous knowledge systems in comparison to empirical Western values, Indigenous decolonization aims to reverse this perspective so that Western funds of knowledge are subjected to due examination and study en route to restoring Indigenous knowledge, traditions, and culture.[10] There are specific advantages to applying Indigenous decolonization to practices and situations involving Indigenous peoples over alternative critical lenses such as critical theory, or more specifically critical race theory. According to Denzin and Lincoln, critical theory’s broad tenets of liberation and sovereignty are far too generalized for this application: "Critical theory must be localized, grounded in the specific meanings, traditions, customs, and community relations that operate in each Indigenous setting."[10] Otherwise, a critical theory that disregards context and embraces ubiquitous characteristics of social movements cannot guide meaningful change when applied to a specific Indigenous context. |
西洋の知識生産と認識論が持つ意味 西洋の科学者や学者が、先住民コミュニティに関する知識を活用し、また活用し続けている(出版物[32][33] や新薬[34][35] を通じて)ため、それらの先住民コミュニティは、新たに生み出された知識の性質や利用法を管理する立場から排除されている。したがって、先住民コミュニ ティは代弁され、それらの制度システムや構造が「植民地搾取の商品となる」知識を再生産する中で、先住民の「他者」となる。[36] これは、西洋の学術界において西洋の知識や認識論が西洋以外の知識(または伝統的知識)よりも優位に立つことをさらに強化し続けている。この優位性は、 ノーマン・K・デンジンとイヴォンナ・S・リンカーンによると、「 「土着の知識体系はあまりにも頻繁に研究対象とされ、あたかも原始文化のメンバーが抱く古風な民間理論の事例であるかのように扱われている」[10] 土着の脱植民地化は、学術研究の主題に劇的な変化を求めている。先住民の知識体系を経験主義的な西洋の価値観と比較するのではなく、先住民の脱植民地化 は、この見方を覆し、西洋の知識体系を正当な検証と研究にさらすことで、先住民の知識、伝統、文化を復興させることを目的としている。 批判理論や、より具体的には批判的人種理論などの代替的な批判的レンズではなく、先住民の脱植民地化を先住民が関わる実践や状況に適用することには、特定 の利点がある。デニンとリンカーンによると、解放と主権という批判理論の広範な原則は、この適用にはあまりにも一般化されすぎている。「批判理論は、それ ぞれの先住民の環境で機能する特定の意味、伝統、習慣、地域社会の関係に根ざしたローカライズされたものでなければならない」[10]。そうでなければ、 文脈を無視し、社会運動の普遍的な特徴を受け入れる批判理論は、特定の先住民の文脈に適用された場合、有意義な変化をもたらすことはできない。 |
In art An example of a piece within the new Indigenous and Canadian Gallery at the National Art Gallery of Canada Indigenous artists have been using art as a form of activism for many years. Jarrett Martineau and Eric Ritskes say that art forms are never separate from our political forms and "Indigenous art thus occupies a unique space within settler colonialism: both as a site for articulating Indigenous resistance and resurgence, and also as a creative praxis that often reinscribes indigeneity within aesthetic and commodity forms that circulate in the capitalist art market".[37] Art can be used in political struggle to bring attention to important issues and to better convey the experiences of Indigenous peoples. Indigenous artists attempt to work outside of the binary of colonialism in their art. Martineau and Ritskes describe Indigenous art as "the generative expression of creativity, not the violence of colonial domination, and it is in Indigenous art's resistant motion to disavow the repetition of such violence that it recuperates the spirit of ancestral memory and place, and forges new pathways of re-emergence and References 1. Smith, L. T. (1999). Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. Zed Books. 2. Elliott, Michael. "Participatory parity and indigenous decolonization struggles." Constellations (2016): 1-12. 3. Hill, Gord. 500 years of Indigenous resistance. PM Press, 2010. 4. Lees, Anna (2016-09-27). "Roles of Urban Indigenous Community Members in Collaborative Field-Based Teacher Preparation". Journal of Teacher Education. 67 (5): 363–378. doi:10.1177/0022487116668018. ISSN 0022-4871. S2CID 152113071. 5. Battiste, Marie (2013-10-24). "Indigenous knowledge and indigenous peoples' education". doi:10.18356/aa0ced95-en. Retrieved 2021-03-09. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help) 6. LaGrand, James B.; Vizenor, Gerald (1996). "Manifest Manners: Postindian Warriors of Survivance". The Western Historical Quarterly. 27 (1): 87. doi:10.2307/969936. ISSN 0043-3810. JSTOR 969936. 7. King, Lisa; Gubele, Rose; Anderson, Joyce Rain, eds. (2015). Survivance, Sovereignty, and Story: Teaching American Indian Rhetorics. doi:10.7330/9780874219968. ISBN 9780874219968. 8. Lyons, Scott Richard (February 2000). "Rhetorical Sovereignty: What Do American Indians Want from Writing?". College Composition and Communication. 51 (3): 447–468. doi:10.2307/358744. ISSN 0010-096X. JSTOR 358744. 9. King, Thomas (2011). The Truth About Stories: a Native Narrative. House of Anansi Press. ISBN 978-0-88784-895-7. OCLC 746746794. 10. Denzin, Norman; Lincoln, Yvonna; Smith, Linda (2008). Handbook of Critical and Indigenous Methodologies. Thousand Oaks, California: Sage Publications. doi:10.4135/9781483385686. ISBN 978-1-4129-1803-9. 11. Cain, Tiffany (2013-11-25). "Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples, 2nd Edition by Linda Tuhiwai Smith. London and New York: Zed Books, 2012. 240 pp". Anthropology & Education Quarterly. 44 (4): 443–445. doi:10.1111/aeq.12032. ISSN 0161-7761. 12. McDonough, Sara (2013). "Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples by Linda Tuhiwai Smith". Collaborative Anthropologies. 6 (1): 458–464. doi:10.1353/cla.2013.0001. ISSN 2152-4009. S2CID 144079116. 13. Grey, Sam, Patel, Raj (2015). "Food sovereignty as decolonization: some contributions from indigenous movements to food system and development politics". Agriculture and Human Values. 32 (3): 431–444. doi:10.1007/s10460-014-9548-9. S2CID 55545504. 14. Figueroa-Helland, Leonardo; Thomas, Cassidy; Aguilera, Abigail (2018). "Decolonizing Food Systems: Food Sovereignty, Indigenous Revitalization, and Agroecology as Counter-Hegemonic Movements". Perspectives on Global Development and Technology. 17 (1–2): 173–201. doi:10.1163/15691497-12341473 – via Brill. 15. Asfia Gulrukh, Kamal; Dipple, Joseph; Linklater, Rene; Thompson, Shirley (2015). "Recipe for Change: Reclamation of Indigenous Food Sovereignty in O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation". Decolonization, Resource Sharing, and Cultural Restoration, Globalizations. 12: 559–575 – via Scholar's Portal. 16. Smith, Linda Tuhiwai, "Decolonizing knowledge", Research Justice, Bristol University Press, pp. 205–210, doi:10.2307/j.ctt1t89jrt.25, retrieved 2023-06-13 17. Grimshaw, Mike (2008-08-21). "Recovering the Sacred: The Power of Naming and Claiming by Winona LaDuke.Cambridge, MA: South End Press, 2005. ISBN 978-0-89608-712-5. 294 pp". Implicit Religion. 10 (3): 322–324. doi:10.1558/imre2007.v10i3.322. ISSN 1743-1697. 18. "Indigenous Languages Arts Cultures BC | First Peoples' Cultural Council". First Peoples Cultural Council. 2023-06-14. Retrieved 2023-06-14. 19. "Advocates for Indigenous California Language Survival – Helping Native communities create new speakers". Retrieved 2023-06-14. 20. Styres, Sandra (2018-06-14), "Literacies of Land", Indigenous and Decolonizing Studies in Education, Routledge, pp. 24–37, doi:10.4324/9780429505010-2, ISBN 978-0-429-50501-0, S2CID 197711037, retrieved 2023-06-14 21. Poitras Pratt, Yvonne; Louie, Dustin W.; Hanson, Aubrey Jean; Ottmann, Jacqueline (2018-01-24), "Indigenous Education and Decolonization", Oxford Research Encyclopedia of Education, Oxford University Press, doi:10.1093/acrefore/9780190264093.013.240, ISBN 978-0-19-026409-3, retrieved 2023-06-13 22. Tuck, Eve; Yang, K. Wayne (2012-09-08). "Decolonization is not a metaphor". Decolonization: Indigeneity, Education & Society. 1 (1). ISSN 1929-8692. 23. "The Cultural Conservancy". The Cultural Conservancy. Retrieved 2023-06-14. 24. "Conclusion Interruptus", Mohawk Interruptus, Duke University Press, pp. 177–194, 2020-12-31, doi:10.1515/9780822376781-008, ISBN 9780822376781, S2CID 241753567, retrieved 2023-06-14 25. Ashley, Jeffrey S. (2014-02-15). "The Rights of Indians and Tribes by Stephen L. Pevar". Human Rights Review. 15 (1): 103–104. doi:10.1007/s12142-014-0314-6. ISSN 1524-8879. S2CID 255518490. 26. "About Us". Native American Rights Fund. Retrieved 2023-06-14. 27. Brant, Jennifer (2014-10-09). "Decolonizing Education: Nourishing the Learning Spirit". Brock Education Journal. 23 (2). doi:10.26522/brocked.v23i2.398. ISSN 2371-7750. 28. Brant, Jennifer (2014). "Decolonizing Education: Nourishing the Learning Spirit". Brock Education Journal. 23 (2). doi:10.26522/brocked.v23i2.398. ISSN 2371-7750. 29. "About NAISA · Native American and Indigenous Studies Association". Native American and Indigenous Studies Association. Retrieved 2023-06-14. 30. Watson, Robert (2012-05-30). "Research is ceremony: Indigenous research methods by Shawn Wilson". The Canadian Geographer. 56 (2): 294–295. Bibcode:2012CGeog..56..294W. doi:10.1111/j.1541-0064.2012.00419.x. ISSN 0008-3658. 31. Tuhiwai Smith, Linda (2021). Decolonizing Methodologies. Zed Books. doi:10.5040/9781350225282. ISBN 978-1-78699-813-2. S2CID 241981019. 32. Barsh, Russel Lawrence (2001). "Who Steals Indigenous Knowledge?". Proceedings of the ASIL Annual Meeting. 95: 153–161. doi:10.1017/s0272503700056834. ISSN 0272-5037. S2CID 150738799. 33. Bhukta, Anindya (2020-06-18). Legal Protection for Knowledge. doi:10.1108/9781800430631. ISBN 978-1-80043-066-2. S2CID 219905931. 34. Pennacchio, Marcello; Ghisalberti, Emilio L (January 2000). "Indigenous knowledge and pharmaceuticals". Journal of Australian Studies. 24 (64): 173–175. doi:10.1080/14443050009387569. ISSN 1444-3058. S2CID 54745135. 35. Norchi, Charles H. (2001), Montgomery, John D.; Inkeles, Alex (eds.), "Indigenous knowledge as intellectual property", Social Capital as a Policy Resource, Boston, MA: Springer US, pp. 161–172, doi:10.1007/978-1-4757-6531-1_10, ISBN 978-1-4419-4871-7, S2CID 153825999, retrieved 2021-03-11 36. Akena, Francis Adyanga (September 2012). "Critical Analysis of the Production of Western Knowledge and Its Implications for Indigenous Knowledge and Decolonization". Journal of Black Studies. 43 (6): 599–619. doi:10.1177/0021934712440448. ISSN 0021-9347. S2CID 143709815. 37 Martineau, Jarrett; Ritskes, Eric (2014-05-20). "Fugitive indigeneity: Reclaiming the terrain of decolonial struggle through Indigenous art". Decolonization: Indigeneity, Education & Society. 3 (1). ISSN 1929-8692.[dead link] |
芸術において カナダ国立美術館の「先住民とカナダ人」ギャラリーに展示されている作品の一例 先住民のアーティストたちは、長年にわたり芸術を活動の一形態として活用してきた。ジャレット・マルティノーとエリック・リツケスは、芸術の形態は政治の 形態とは決して別個のものではないとし、「先住民の芸術は、入植者による植民地主義のなかで独特な位置を占めている。先住民の抵抗と再生を表明する場とし て、また 資本主義のアート市場で流通する美的・商品形態の中に先住民性を再定義する創造的な実践として」存在している。[37] アートは、重要な問題に注目を集め、先住民の経験をよりよく伝えるために、政治闘争に利用することができる。先住民のアーティストたちは、彼らの芸術にお いて、植民地主義の二元論の枠組みを超えた表現を試みている。マルティノーとリツケスは、先住民の芸術を「創造性の生成的な表現であり、植民地支配の暴力 ではない」と表現している。先住民の芸術は、そうした暴力の繰り返しを否定する抵抗運動であり、先祖代々受け継がれてきた記憶と土地の精神を回復し、新た な再生の道筋を切り開くものである。 参考文献 1. スミス、L. T. (1999). 『脱植民地化の方法論:研究と先住民』 Zed Books. 2. エリオット、マイケル. 「参加型平等と先住民の脱植民地化闘争」 『コンステレーションズ』 (2016): 1-12. 3. ヒル、ゴード. 『500年にわたる先住民の抵抗』 PM Press, 2010. 4. リーズ、アンナ (2016-09-27). 「共同フィールドベースの教師養成における都市先住民コミュニティメンバーの役割」. Journal of Teacher Education. 67 (5): 363–378. doi:10.1177/0022487116668018. ISSN 0022-4871. S2CID 152113071. 5. バティスト, マリー (2013-10-24). 「先住民の知識と先住民の教育」. doi:10.18356/aa0ced95-en. 2021-03-09 取得. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help) 6. ラグランド、ジェームズ B.、ヴィゼノール、ジェラルド (1996). 「マニフェスト・マナーズ:サバイバンスのポストインディアン戦士たち」. 『西部歴史季刊』. 27 (1): 87. doi:10.2307/969936. ISSN 0043-3810. JSTOR 969936. 7. キング、リサ; グベレ、ローズ; アンダーソン、ジョイス・レイン、編 (2015). 『サバイバンス、主権、そして物語:アメリカインディアンとヨーロッパインディアンとアフリカインディアンとアジアインディアンとオセアニアインディアン とオーストラリアインディアンとレズビアンとゲイとバイセクシュアルとトランスジェンダーのレトリックを教える』. doi:10.7330/97 8. ライアンズ、スコット・リチャード(2000年2月)。「修辞的主権:アメリカインディアンは文章から何を求めるのか?」。カレッジ・コンポジション・ア ンド・コミュニケーション。51 (3): 447–468. doi:10.2307/358744. ISSN 0010-096X. JSTOR 358744. 9. キング、トーマス (2011). 物語の真実:ネイティブの物語。アナンシ・プレス。ISBN 978-0-88784-895-7. OCLC 746746794. 10. デンジン、ノーマン、リンカーン、イヴォンナ、スミス、リンダ(2008)。『批判的かつ先住的な方法論のハンドブック』。カリフォルニア州サウザンド オークス:セージ出版。doi:10.4135/9781483385686。ISBN 978-1-4129-1803-9。 11. Cain, Tiffany (2013-11-25). 「脱植民地化の方法論:研究と先住民、第 2 版、Linda Tuhiwai Smith 著。ロンドンおよびニューヨーク:Zed Books、2012 年。240 ページ」。Anthropology & Education Quarterly. 44 (4): 443–445. doi:10.1111/aeq.12032. ISSN 0161-7761. 12. マクドノー、サラ(2013年)。「脱植民地化の方法論:リンダ・トゥヒワイ・スミス著『研究と先住民』」。『協働人類学』6巻1号:458–464頁。 doi:10.1353/cla.2013.0001. ISSN 2152-4009. S2CID 144079116. 13. グレイ、サム、パテル、ラジ(2015)。「脱植民地化としての食糧主権:先住民族運動が食糧システムと開発政治に与えた貢献」。農業と人間の価値観。 32 (3): 431–444. doi:10.1007/s10460-014-9548-9. S2CID 55545504. 14. フィゲロア=ヘランド、レオナルド; トーマス、キャシディ; アギレラ、アビゲイル (2018). 「食糧システムの脱植民地化:食糧主権、先住民の復興、そして反ヘゲモニー運動としての農業生態学」。『グローバル開発と技術に関する視点』。17 (1–2): 173–201. doi:10.1163/15691497-12341473 – Brill経由。 15. アスフィア・グルルク、カマル; ディプル、ジョセフ; リンクレイター、ルネ; トンプソン、シャーリー (2015). 「変革のレシピ:オ・ピポン・ナ・ピウィン・クリー・国民における先住民の食糧主権の回復」. 『脱植民地化、資源共有、文化復興』, グローバリゼーションズ. 12: 559–575 – Scholar's Portal経由. 16. スミス、リンダ・トゥヒワイ、「知識の脱植民地化」、『研究の正義』、ブリストル大学出版局、pp. 205–210、doi:10.2307/j.ctt1t89jrt.25、2023-06-13 取得 17. グリムショー、マイク (2008-08-21)。「聖なるものの回復:命名と主張の力」ウィノナ・ラデューク著。ケンブリッジ、マサチューセッツ州:サウスエンド出版、 2005年。ISBN 978-0-89608-712-5。294頁」。『インプリシット・レリジョン』10巻3号:322–324頁。doi: 10.1558/imre2007.v10i3.322. ISSN 1743-1697. 18. 「ブリティッシュコロンビア州先住民言語・芸術・文化 | ファースト・ピープルズ文化評議会」. ファースト・ピープルズ文化評議会. 2023-06-14. 2023-06-14 取得. 19. 「先住民カリフォルニア語存続支援団体 – 先住民コミュニティが新たな話者を創出する支援」. 2023-06-14 取得. 20. Styres, Sandra (2018-06-14), 「土地の識字能力」, 『先住民と脱植民地化教育研究』, Routledge, pp. 24–37, doi:10.4324/9780429505010-2, ISBN 978-0-429-50501-0, S2CID 197711037, 2023-06-14 取得 21. ポイトラス・プラット、イヴォンヌ; ルイ、ダスティン・W.; ハンソン、オーブリー・ジーン; オットマン、ジャクリーン (2018年1月24日), 「先住民教育と脱植民地化」, 『オックスフォード教育研究百科事典』, オックスフォード大学出版局, doi:10.1093/acrefore/9780190264093.013.240, ISBN 978-0-19-026409-3, 2023-06-13 取得 22. タック, イヴ; ヤン, K. ウェイン (2012-09-08). 「脱植民地化は隠喩ではない」. 『脱植民地化:先住性、教育、社会』. 1 (1). ISSN 1929-8692. 23. 「ザ・カルチュラル・コンサーバンシー」. ザ・カルチュラル・コンサーバンシー. 2023-06-14 閲覧. 24. 「中断された結論」, 『モホーク・インターラプトゥス』, デューク大学出版局, pp. 177–194, 2020-12-31, doi:10.1515/9780822376781-008, ISBN 9780822376781, S2CID 241753567, 2023年6月14日閲覧 25. Ashley, Jeffrey S. (2014-02-15). 「スティーブン・L・ペバー著『インディアンと部族の権利』」『人権レビュー』15巻1号: 103–104頁. doi:10.1007/s12142-014-0314-6. ISSN 1524-8879. S2CID 255518490. 26. 「当団体について」。ネイティブ・アメリカン権利基金。2023年6月14日閲覧。 27. ブラント、ジェニファー(2014年10月9日)。「教育の脱植民地化:学びの精神を育む」。ブロック教育ジャーナル。23巻2号。doi:10.26522/brocked.v23i2.398。ISSN 2371-7750. 28. Brant, Jennifer (2014). 「脱植民地化教育:学びの精神を育む」. Brock Education Journal. 23 (2). doi:10.26522/brocked.v23i2.398. ISSN 2371-7750. 29. 「NAISA について・ネイティブアメリカンおよび先住民研究協会」。ネイティブアメリカンおよび先住民研究協会。2023-06-14 取得。 30. ワトソン、ロバート (2012-05-30)。「研究は儀式である:ショーン・ウィルソンによる先住民の研究方法」。カナディアン・ジオグラファー。56 (2): 294–295。Bibcode:2012CGeog..56..294W. doi:10.1111/j.1541-0064.2012.00419.x. ISSN 0008-3658. 31. Tuhiwai Smith, Linda (2021). Decolonizing Methodologies. Zed Books. doi:10.5040/9781350225282。ISBN 978-1-78699-813-2。S2CID 241981019。 32. バーシュ、ラッセル・ローレンス(2001)。「誰が先住民の知識を盗むのか?」。ASIL年次総会議事録。95: 153–161. doi:10.1017/s0272503700056834. ISSN 0272-5037. S2CID 150738799. 33. ブクタ、アニンディヤ(2020-06-18)。知識の法的保護。doi:10.1108/9781800430631。ISBN 978-1-80043-066-2。S2CID 219905931。 34. Pennacchio, Marcello; Ghisalberti, Emilio L (2000年1月)。「先住民の知識と医薬品」。オーストラリア研究ジャーナル。24 (64): 173–175。doi:10.1080/14443050009387569。ISSN 1444-3058。S2CID 54745135。 35. Norchi, Charles H. (2001), Montgomery, John D.; Inkeles, Alex (eds.), 「知的財産としての先住民の知識」, 『政策資源としての社会資本』, ボストン, MA: Springer US, pp. 161–172, doi:10.1007/978-1-4757-6531-1_10, ISBN 978-1-4419-4871-7, S2CID 153825999, 2021-03-11 取得 36. Akena, Francis Adyanga (2012年9月). 「西洋知識の生産に関する批判的分析と、それが先住民の知識及び脱植民地化に与える影響」. Journal of Black Studies. 43 (6): 599–619. doi:10.1177/0021934712440448. ISSN 0021-9347. S2CID 143709815. 37 マーティノー、ジャレット、リトスケス、エリック (2014-05-20)。「逃亡する先住性:先住民の芸術を通じて脱植民地化闘争の領域を取り戻す」。脱植民地化:先住性、教育、社会。3 (1)。ISSN 1929-8692。[リンク切れ] |
| Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) Decolonize This Place Decolonization of knowledge Decolonization of museums Human migration Indigenous response to colonialism |
先住民の権利に関する宣言(2007) この場所の脱植民地化 知識の脱植民地化 博物館の脱植民地化 人間の移動 先住民による植民地主義への対応 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_decolonization |
|
| Food sovereignty
is a food system in which the people who produce, distribute, and
consume food also control the mechanisms and policies of food
production and distribution. This stands in contrast to the present
corporate food regime, in which corporations and market institutions
control the global food system. Food sovereignty emphasizes local food
economies, sustainable food availability, and centers culturally
appropriate foods and practices. Changing climates and disrupted
foodways disproportionately impact indigenous populations and their
access to traditional food sources while contributing to higher rates
of certain diseases; for this reason, food sovereignty centers
indigenous peoples. These needs have been addressed in recent years by
several international organizations, including the United Nations, with
several countries adopting food sovereignty policies into law. Critics
of food sovereignty activism believe that the system is founded on
inaccurate baseline assumptions; disregards the origins of the targeted
problems; and is plagued by a lack of consensus for proposed solutions. Definition The term "food sovereignty" was first coined in 1996 by members of Via Campesina, an international farmers' organisation, and later adopted by several international organisations, including the World Bank and United Nations. In 2007, the "Declaration of Nyéléni" provided a definition which was adopted by 80 countries; in 2011 it was further refined by countries in Europe. As of 2020, at least seven countries had integrated food sovereignty into their constitutions and laws.[1] History Aligned somewhat with the tenets of the Slow Food organization, the history of food sovereignty as a movement is relatively young. However, the movement is gaining traction as more countries take significant steps towards implementing food systems that address inequities.[2] Global gatherings At the 2007 Forum for Food Sovereignty in Sélingué, Mali, 500 delegates from more than 80 countries adopted the "Declaration of Nyéléni",[3] which says in part: Food sovereignty is the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through ecologically sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture systems. It puts those who produce, distribute and consume food at the heart of food systems and policies rather than the demands of markets and corporations. It defends the interests and inclusion of the next generation. It offers a strategy to resist and dismantle the current corporate trade and food regime, and directions for food, farming, pastoral and fisheries systems determined by local producers. Food sovereignty prioritises local and national economies and markets and empowers peasant and family farmer-driven agriculture, artisanal fishing, pastoralist-led grazing, and food production, distribution and consumption based on environmental, social and economic sustainability.[3] In April 2008 the International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD), an intergovernmental panel under the sponsorship of the United Nations and the World Bank, adopted the following definition: "Food sovereignty is defined as the right of peoples and sovereign states to democratically determine their own agricultural and food policies."[4] Government food sovereignty policy Issues of food production, distribution and access are seldom apolitical or without criticism. For example, the adoption of the Green Revolution in countries across the globe has increased world food production but has not "solved" the problem of world hunger. Food sovereignty advocates argue this is because the movement did not address access to land or distribution of economic power. Others argue that food sovereignty is based on incorrect baseline assumptions around the role of subsistence farming in government policy. Agrarian aspects of food sovereignty put the movement in conflict with globalisation, industrialisation, and urbanisation trends.[5] After Hugo Chávez was elected president of Venezuela in 1998, a new constitution was approved by the people of Venezuela which included the right to food as one of its basic civil rights. The government set up missions to deliver the various constitutional rights. Several missions related to food and farming were established by Chávez' government to provide equitable food access. Among these were the Misión Alimentación, Misión Vuelvan Caras, Misión Mercal and Misión Zamora. Later the Gran Misión AgroVenezuela was created to increase domestic agricultural production. Among the strategies used to increase food sovereignty for Venezuelans were land reform, agroecology, use of traditional crops and biological pest control and the establishment of subsidised food outlets such as Arepera Socialista, Café Venezuela and Cacao Venezuela.[6] In September 2008, Ecuador enshrined food sovereignty in its constitution. As of late 2008, a law is in the draft stages that is expected to expand upon this constitutional provision by banning genetically modified organisms, protecting many areas of the country from extraction of non-renewable resources, and to discourage monoculture. The law as drafted will also protect biodiversity as collective intellectual property and recognize the Rights of Nature.[7] Since then Mali, Bolivia, Nepal, Senegal and Egypt (2014 Constitution) have integrated food sovereignty into their national constitutions or laws.[1] Indigenous food sovereignty Global Issues Climate Climate change is impacting the food security of indigenous communities as well, including Pacific Islanders and those in the Circumpolar North, due to rising sea levels or erosion.[8] Cuisine Activists claim that native food sovereignty is also appropriated as a cuisine for mainstream dining because indigenous foods are framed to be culturally authentic, desired by those outside of these communities. Ingredients that are cultural staples, which are harder for these populations to find, are displaced due to a greater demand for access outside of indigenous populations.[9] Indigenous food sovereignty in the United States Further information: Contemporary Native American issues in the United States § Food insecurity Native Americans have been directly impacted in their ability to acquire and prepare their food and this disruption of traditional diets has resulted in health problems, including diabetes and heart disease.[10] Indigenous food sovereignty activists in the United States assert that the systematic displacement of indigenous communities has led to mass food insecurity. Activist groups advocate for revitalization of traditional practices, development of local food economies, the right to food, and seed sovereignty.[11] Indigenous people's food sovereignty and food security are closely related to their geographical location. Traditional indigenous foodways in the United States are tied to the ancestral homelands of Native American populations, especially for those with strong subsistence traditions. For instance, it is taught among the Muckleshoot that “the land that provides the foods and medicines we need are a part of who we are."[12][10] This image was taken from at the USDA Native American Heritage Month Observance event on Nov. 16, 2023. There were bags of white tepary beans (s-totoah bavī) from Romona Farms American Indian Foods were placed under each participants chairs to promote food sovereignty. The disruption of traditional foodways is described to be tied to the disruption of the connection between traditional Native land and their people, a change Rachel V. Vernon describes as being tied to “racism, colonialism, and the loss of autonomy and power.”[13] Pre-colonial lands were expansive and thriving with traditional foods. Because of disease and war, Native peoples in the early 20th century were directly impacted in their ability to acquire and prepare their food. In addition to this, relocation away from ancestral lands further limited traditional foodways. Many indigenous people in the United States now live in food deserts. Due to inadequate or inhibited access to food, indigenous peoples suffer disproportionately from food insecurity compared to the rest of the US population.[12] At reservations, the “‘highly processed, high sugar, high fat, and processed foods,’” further contributed to health issues in Native populations, leading to indigenous peoples in the United States having the highest rates of diabetes and heart disease in the nation.[14] In addition to this, a majority of Native peoples also live off-reservation, and so are even further removed from traditional foodways.[15] Because Native American nations are sovereign from the United States, they receive little help in rehabilitating traditional foodways. As defined by the National Congress of American Indians, tribal sovereignty ensures that any decisions about the tribes with regard to their property and citizens are made with their participation and consent.[16] The United States federal government recognizes Native American tribes as separate governments, opposed to “special interest groups, individuals, or ... other type of non-governmental entity.”[17] History Three sisters: maize, beans, and squash planted together. Prior to the colonization of the Americas, Native Americans had a diverse diet and food culture, procuring food in various ways across tribes. Depending on the region, Indigenous people sourced their food by hunting, fishing, gathering, and farming. Native food pathways revolved around the “three sisters,” or corn, beans, and squash, as staples in their diet. Hunting, gathering, and fishing were the primary means of collecting food. These balanced ecosystems were disrupted by European settler colonialism following Christopher Columbus’ “discovery” of America in 1492. Upon European arrival, the Indigenous peoples of America were stripped of their supplies and even starved out as a tactic for colonial control over Native lands. Domesticated animals were introduced into America by European settlers, bringing with them new diseases.[18] Colonizers targeted food stores specifically and drastically changed Native American diets, their ability to acquire resources, and produce food.[19] New food systems put in place by American settlers, have over time forced a dependency upon processed and mass-produced food on Indian reservations and indigenous communities at large. Native tribes have been forced into a position of food insecurity and put in a place in society where there is no ability to afford other sources of healthy or food that is organically farmed.[18] With a loss of food sovereignty, there was also a loss of land, as Indians were relocated and forcibly assimilated. Following Congress' passing of the Indian Appropriations Act in 1851, all Indigenous people were forced onto Indian reservations, losing the ability to cultivate the earth and rely on traditional means of living. Activism Native Americans today fight for food sovereignty as a means to address health, returning to culturally traditional foods for healing. Returning to traditional eating is challenging, considering an extensive history of relocation and cultural genocide. Many Native American histories of traditional culture foods have been lost or are now difficult to recreate.[20] Research assistant Kyle Kootswaytewa inspecting a corn crop in Santa Fe, NM. Directly connecting and caring for land/seeds in an important aspect of food sovereignty. Indigenous food sovereignty activists in the United States assert that indigenous communities have been systematically displaced from their traditional foodways, which has led to mass food insecurity.[11] It is argued that the most effective way to achieve food security for indigenous groups is to increase their agency in food production.[21] Some activists also argue for food sovereignty as a means of healing historical trauma and as a means of decolonizing their communities. In the United States the Indigenous Food Systems Network and the Native American Food Sovereignty Alliance work towards education and policy-making concerned with food and farming security. Another group focused on requiring food and energy sovereignty is the White Earth Anishnaabeg from Minnesota, who focus on a variety of foods, planting and harvesting them using traditional methods, a form of decolonization.[22] Such groups meet to establish policies for food sovereignty and to develop their local food economies at summits such as the Diné Bich’iiya’ Summit in Tsaile, Arizona, which focused on Navajo traditional foods.[23] Indigenous food sovereignty activists also often advocate for seed sovereignty, and more generally for plant breeders’ rights. Seed saving is important to indigenous communities in the United States because it provides those communities with a stable food source and holds cultural importance.[24] In addition, seed sovereignty advocates often argue that seed saving is an important mechanism in creating agricultural systems that can adapt to climate change.[25] Food sovereignty research and projects In 2021, a comprehensive literature review of IFS (Indigenous Food Sovereignty) and the effectiveness of food sovereignty principles concluded that Indigenous people in the United States and Canada have higher rates of obesity, food insecurity, and Type 2 diabetes than the general population.[26] Government projects supporting indigenous food systems are new attempts to uplift indigenous communities and are in amateur stages of development. Other countries adopted Indigenous food programs years before the U.S., including Canada. The Canadian Food Guide (CFG) was created in January 2019 as a means to include multicultural diets, instead of basing food standards on one or few cultures — the guide includes Indigenous diets and involved Indigenous populations in consultation.[27] A community member harvesting from a one-acre self-sustaining farm on an Indian reservation in South Dakota. In 2021, the United States' Department of Agriculture launched the Indigenous Food Sovereignty Initiative. This initiative is designed to "promote traditional food ways" as, similar to Canada, USDA programs have not historically encompassed Indigenous food pathways and diets.[28] The USDA has partnered with organizations already serving Indigenous tribes: The Indigenous Seed Keepers Network, Linda Black Elk & Lisa Iron Cloud, InterTribal Buffalo Council, North American Traditional Indigenous Food Systems, Intertribal Agriculture Council, and the University of Arkansas - Indigenous Food and Agriculture Initiative. Non-governmental projects, such as the “Good Life” project in Ecuador, are spearheaded by independent organizations and Indigenous community members. The "Good Life" suggests that there are alternative methods of action through Indigenous community development that do not involve governmental funding or state provisioning. In Ecuador, the Indigenous community has developed the “Good Life” project which drifts away from capitalist and western understandings of what a community needs, and rather focuses on cultivating community success through harmony with the people, nature, and defending their land — essentially working directly within an Indigenous community to reclaim food sovereignty.[29] Organizations in the United States have adopted similar models to Ecuador's "Good Life" project. In California, the UC Berkeley organization, CARES (the Community Assessment of Renewable Energy and Sustainability) works with the PPN (Pinoleville Pomo Nation) in Ukiah, California, to support their tribal sovereignty. This Indigenous community has been working with CARES over the years to design sustainable housing and energy that reflect its culture.[30] Narragansett people exercised their own food sovereignty initiative by reappropriating landscapes, seascapes, estuaries, spaces, and built places from a Rhode Island "Farm",[31] which had, in earnest after 1690, sustained southern New England proprietorship, land banks, and currency within a Greater Caribbean plantation complex. This carrying trade became a potential leg of the Triangular trade, although historians also argue that the self-contained carrying trade belied the triangle as a sequential circuit. By 1769, the woodlands and wetlands of the Narragansett tribal reserve near Charlestown, Rhode Island, had been reduced to less than five square miles, with multivalent consequences for resource allocation, survivance, religiosity, and race. Census and missionary records appraised the reserve population at approximately 600 tribal members, on the eve of Narragansett tribal veterans' return from the Seven Years' War.[32] But these same records did not address the seasonal fishing exodus and indicated that, for example, the Narragansett "have for ages been intermixing with Whites and Blacks...a number of others, of mixed nations, live among them, who, by their customs, are not of the tribe." One missionary later observed that less than a third of the reserve was available for tillage and sustenance, with the remainder devoted to tenancy and the maintenance of woodlands for timber (sales, etc.).[33] Previous debts to "Farmers", especially for gunpowder during hunting sojourns and for compensating "seasoned slaves" in assistance with fishing canoe transportation, had resulted in a mid-eighteenth-century emphasis on horticulture and agriculture, with limited animal husbandry. Historian Daniel Mandell argues that, compared to Eastern Woodland Algonquian communities in similar circumstances, "the Narragansetts had even less: in 1810, the tribe told [congregational missionary Curtis] Coe that they had no oxen to plow their fields or haul manure and held only about four cows; he had already noted that families on the reserve generally farmed only about an acre."[34] Despite the antebellum rise of "Greater Northeast" industrial agriculture,[35] the southern New England "Farms" and the carrying trade[36] in Caribbean sugar, molasses, rice, coffee, indigo, mahogany, and pre-1740 "seasoned slaves",[37] began to dissipate by the Election of 1800[38] and largely collapsed into agrarian ruins by the War of 1812.[39] The expansion of the Narragansett tribal project garnered media coverage and incited scholars to reevaluate a diminished focus on, or complete absence of, such "Farms", their proprietors, their multipurpose Pacers, seaport carriers, land banks, and Narragansett foodways in extant studies on Eastern Woodland Algonquian communities by both historians and anthropologists.[40] |
食
料主権とは、食料を生産、流通、消費する人々が、食料生産と流通の仕組みや政策も管理する食料システムである。これは、企業や市場機関がグローバルな食料
システムを管理する現在の企業食料体制とは対照的である。食料主権は、地域食料経済、持続可能な食料供給、そして文化的に適切な食料と慣習を重視する。気
候変動や食文化の崩壊は、先住民とその伝統的な食料源へのアクセスに不均衡な影響を与え、特定の病気の発生率を高める要因となる。このため、食料主権は先
住民を重視している。これらのニーズは近年、国連を含むいくつかの国際機関によって取り上げられ、いくつかの国では食料主権政策が法律として採択されてい
る。食糧主権の活動に批判的な人々は、このシステムは不正確な基本前提に基づいており、対象となる問題の起源を無視しており、提案された解決策のコンセン
サスが欠如していると主張している。 定義 「食糧主権」という用語は、1996年に国際的な農民組織であるビア・カンペシーナのメンバーによって初めて使用され、その後、世界銀行や国連を含むいく つかの国際機関によって採用された。2007年には「ニエレニ宣言」が定義を提示し、80カ国がこれを受け入れた。2011年にはヨーロッパ諸国によって さらに定義が洗練された。2020年現在、少なくとも7カ国が食料主権を憲法や法律に組み込んでいる。[1] 歴史 スローフード運動の理念と多少共通する部分はあるが、食料主権の運動としての歴史は比較的新しい。しかし、不平等に対処する食糧システムの実施に向けて重要な一歩を踏み出す国が増えるにつれ、この運動は勢いを増している。[2] 世界的な集会 2007年にマリのセリンゲで開催された食糧主権に関するフォーラムでは、80カ国以上から集まった500人の代表者が「ニェレニ宣言」を採択した。[3] 宣言の一部を以下に示す。 食料主権とは、生態学的に健全で持続可能な方法で生産された、健康的で文化的に適切な食料に対する人々の権利であり、食料および農業システムを自ら定義す る権利である。食料主権は、市場や企業の要求よりも、食料を生産、流通、消費する人々を食料システムおよび政策の中心に据える。次世代の利益と参加を擁護 する。また、現在の企業による貿易および食糧体制に抵抗し、それを解体するための戦略を提示し、地域生産者によって決定される食糧、農業、牧畜、漁業体制 の方向性を示す。食糧主権は、地域および国民経済と市場を優先し、小作農および家族経営の農業、手工漁業、牧畜民による放牧、環境、社会、経済の持続可能 性に基づく食糧生産、流通、消費を強化する。 2008年4月、国連と世界銀行の後援による政府間パネルである「開発のための農業科学と技術に関する国際評価(IAASTD)」は、以下の定義を採択した。「食料主権とは、人民および主権国家が自国の農業および食料政策を民主的に決定する権利である」[4] 政府による食料主権政策 食料生産、流通、入手の問題は、政治とは無関係であったり、批判を受けないことはほとんどない。例えば、世界中の国々で「緑の革命」が採用されたことによ り、世界の食料生産量は増加したが、世界の飢餓問題は「解決」されていない。食料主権の擁護者たちは、この理由は、この運動が土地へのアクセスや経済力の 分配に取り組んでいないためだと主張している。また、食料主権は、政府政策における自給自足農業の役割に関する誤った基本前提に基づいているという意見も ある。食料主権の農業的側面は、グローバリゼーション、工業化、都市化の傾向と対立するものである。 1998年にウゴ・チャベスがベネズエラの大統領に選出された後、ベネズエラ国民は食料に対する権利を基本的人権のひとつとして盛り込んだ新憲法を承認し た。政府は、さまざまな憲法上の権利を保障するためのミッションを設立した。チャベス政権は、公平な食料へのアクセスを確保するために、食料と農業に関す るいくつかのミッションを設立した。その中には、ミシオン・アレメンタシオン(Misión Alimentación)、ミシオン・ブエルバン・カラス(Misión Vuelvan Caras)、ミシオン・メルカル(Misión Mercal)、ミシオン・サモラ(Misión Zamora)などがある。その後、国内農業生産の増加を目的としたグラン・ミシオン・アグロベネズエラ(Gran Misión AgroVenezuela)が創設された。ベネズエラ国民の食料主権を強化するために用いられた戦略には、土地改革、アグロエコロジー、伝統的作物の利 用、生物学的害虫駆除、アレペラ・ソシスタ(Arepera Socialista)、カフェ・ベネズエラ(Café Venezuela)、カカオ・ベネズエラ(Cacao Venezuela)などの助成金付き食料販売店の設立などがある。 2008年9月、エクアドルは食料主権を憲法に盛り込んだ。2008年後半の時点で、遺伝子組み換え生物の禁止、国内の多くの地域を再生不能資源の採取か ら保護すること、単一栽培を抑制することを通じて、この憲法規定を拡大することが期待される法律が草案段階にある。草案の法律は、生物多様性を集合的知的 財産として保護し、自然の権利を認めることも想定されている。 それ以来、マリ、ボリビア、ネパール、セネガル、エジプト(2014年憲法)が、食料主権を自国の憲法または法律に盛り込んでいる。[1] 先住民の食料主権 世界的な問題 気候 気候変動は、海面上昇や浸食により、太平洋諸島や北極圏の住民を含む先住民コミュニティの食料安全保障にも影響を与えている。[8] 料理 活動家たちは、先住民の食料主権は、先住民の食料が文化的にも本物であると位置づけられ、これらのコミュニティの外にいる人々から求められているため、主 流の料理として流用されていると主張している。これらの人々にとって入手が困難な文化的な必需品である食材は、先住民以外の地域からの需要の高まりによ り、追い出されることとなった。[9] 米国における先住民の食料主権 さらに詳しい情報:米国における現代のネイティブアメリカンの問題 § 食料不安 アメリカ先住民は、食料の入手や調理能力に直接的な影響を受けており、伝統的な食生活の崩壊は、糖尿病や心臓病などの健康問題を引き起こしている。 [10] アメリカ先住民の食料主権活動家たちは、先住民コミュニティの組織的な排除が、食料不安の蔓延につながっていると主張している。 活動家グループは、伝統的慣習の復興、地域食料経済の発展、食料への権利、種子主権を提唱している。[11] 先住民の食料主権と食料安全保障は、彼らの地理的位置と密接な関係がある。米国における伝統的な先住民の食生活は、特に自給自足の伝統が強い人々にとって は、先祖代々の故郷と結びついている。例えば、マックルシュート族の間では、「我々が必要とする食料と薬を提供してくれる土地は、我々自身の一部である」 と教えられている。[12][10] この画像は、2023年11月16日に開催された米国農務省の「ネイティブ・アメリカン文化月間」記念イベントで撮影された。 ロモーナ・ファームズ・アメリカン・インディアン・フーズ社の白いテペリービーンズ(s-totoah bavī)の袋が、参加者の椅子の下に置かれていた。これは食料主権を推進するためのものだった。 伝統的な食文化の崩壊は、ネイティブアメリカンが伝統的に暮らしてきた土地と人々とのつながりの崩壊と関連していると説明されており、レイチェル・V・ ヴァーノンはこれを「人種差別、植民地主義、そして自立と権力の喪失」と表現している。[13] 植民地化以前の土地は広大で、伝統的な食文化が栄えていた。20世紀初頭、病気と戦争により、ネイティブアメリカンは食料の入手と調理能力に直接的な影響 を受けた。さらに、先祖伝来の土地から離れた移住により、伝統的な食生活はさらに制限された。現在、米国の多くの先住民はフードデザート(食の砂漠)と呼 ばれる地域に住んでいる。食料へのアクセスが不十分であったり、妨げられたりしているため、先住民は米国の他の人口層と比較して、不均衡に食料不安に苦し んでいる。[12] 保留地では、「高度に加工され、糖分や脂肪分が高い加工食品」が、さらに先住民の健康問題に拍車をかけた その結果、米国の先住民は糖尿病と心臓病の罹患率が国民の中で最も高いという結果を招いている。[14] さらに、先住民の大多数は居留地外に住んでいるため、伝統的な食生活からさらに遠ざかっている。[15] アメリカ先住民の国民は米国から主権を認められているため、伝統的な食生活の復興にはほとんど支援が得られていない。全米インディアン会議の定義による と、部族の主権は、部族の財産や市民に関するあらゆる決定が部族の参加と同意のもとに行われることを保証するものである。[16] 米国連邦政府は、アメリカ先住民の部族を「特定の利益団体、個人、またはその他の非政府組織」とは異なる政府として認めている。[17] 歴史 3種の姉妹:トウモロコシ、豆、カボチャを一緒に植える。 アメリカ大陸が植民地化される以前、アメリカ先住民は多様な食生活と食文化を持ち、部族間でさまざまな方法で食料を調達していた。地域によって、先住民は 狩猟、漁業、採集、農業によって食料を調達していた。先住民の食生活の中心は「3種の姉妹」、すなわちトウモロコシ、豆、カボチャであった。狩猟、採集、 漁撈が食料の収集の主な手段であった。 これらのバランスのとれた生態系は、1492年のクリストファー・コロンブスによる「アメリカ大陸発見」に続くヨーロッパ入植者による植民地主義によって 崩壊した。ヨーロッパ人が到着すると、アメリカ先住民は彼らの土地を植民地支配するための戦術として、彼らの供給源を奪われ、飢えに苦しむことさえあっ た。ヨーロッパからの入植者によって家畜がアメリカに持ち込まれたことで、新たな伝染病が持ち込まれた。[18] 植民地支配者は食料貯蔵庫を特に標的にし、ネイティブアメリカンの食生活、資源の入手能力、食料生産を大幅に変えた。[19] アメリカ人入植者によって新たに導入された食糧システムは、長い年月をかけて、インディアン居留地や先住民コミュニティ全体に加工食品や大量生産食品への 依存を強いることとなった。先住民部族は食糧不安に陥り、健康的な食品や有機農法による食品を入手する能力を持たない社会状況に置かれることとなった。 1851年に連邦議会がインディアン歳出法を可決した後、先住民は全員インディアン居留地に強制移住させられ、土地を耕す能力を失い、伝統的な生活手段に 頼ることができなくなった。 活動 今日、ネイティブアメリカンは健康問題に対処する手段として食料主権を求め、伝統的な癒しの食生活に戻ろうとしている。 移住と文化の大量虐殺という長い歴史を考えると、伝統的な食生活に戻ることは難しい。 伝統的な食文化を持つ多くのネイティブアメリカンの歴史は失われたり、再現が困難になっている。 ニューメキシコ州サンタフェでトウモロコシの収穫を検査する研究助手のカイル・クーツウェイテワ。食料主権の重要な側面として、土地と種を直接的に結びつけ、大切にしている。 米国の先住民による食料主権の活動家たちは、先住民のコミュニティが伝統的な食生活を組織的に失い、それが大量の食料不安につながっていると主張してい る。[11] 先住民グループの食料安全保障を達成する最も効果的な方法は、食料生産における彼らの権限を増大させることであると主張されている。[21] また、一部の活動家は、歴史的なトラウマを癒す手段として、また彼らのコミュニティの脱植民地化の手段として、食料主権を主張している。米国では、先住民 フードシステム・ネットワーク(Indigenous Food Systems Network)と先住民食料主権同盟(Native American Food Sovereignty Alliance)が、食料と農業の安全保障に関する教育と政策立案に取り組んでいる。食料主権とエネルギー主権の確立に焦点を当てている別のグループ は、ミネソタ州のホワイト・アース・アニシナベグ族で、さまざまな食料に焦点を当て、伝統的な方法でそれらを植え、収穫し、脱植民地化の一形態としてい る。[22] このようなグループは、食料主権のための政策を確立し、地元の食料経済を発展させるために、アリゾナ州ツァイレで開催されたナバホ族の伝統食に焦点を当て たディネ・ビチイヤ・サミットなどのサミットで会合を開いている。[23] 先住民の食料主権の活動家は、しばしば種子主権、さらに一般的に植物育種家権を提唱している。種子の保存は、米国の先住民コミュニティにとって重要なもの であり、それはコミュニティに安定した食料源を提供し、文化的にも重要な意味を持っているからである。[24] さらに、種子主権の擁護者たちは、種子の保存は気候変動に適応できる農業システムを構築する上で重要なメカニズムであると主張することが多い。[25] 食料主権に関する研究とプロジェクト 2021年、IFS(先住民の食料主権)と食料主権原則の有効性に関する包括的な文献レビューでは、米国とカナダの先住民は一般人口よりも肥満、食料不安、2型糖尿病の割合が高いという結論に達した。 先住民の食糧システムを支援する政府プロジェクトは、先住民コミュニティを向上させるための新たな試みであり、開発は素人段階にある。カナダを含む米国よ り何年も前に、他の国々は先住民の食糧プログラムを採用した。カナダのフードガイド(CFG)は、2019年1月に、食糧基準を1つまたは少数の文化に基 づいて定めるのではなく、多文化の食生活を取り入れる手段として作成された。このガイドには先住民の食生活が含まれており、先住民が協議に関与している。 サウスダコタ州のインディアン居留地にある1エーカーの自給自足農場で収穫するコミュニティのメンバー。 2021年、米国農務省は先住民食料主権イニシアティブを開始した。このイニシアティブは、カナダと同様に、米国農務省のプログラムは歴史的に先住民の食 生活や食事法を包含してこなかったため、「伝統的な食生活を促進する」ことを目的としている。[28] 米国農務省は、すでに先住民部族に奉仕している組織と提携している。先住民シードキーパーズ・ネットワーク、リンダ・ブラック・エルク&リサ・ア イアン・クラウド、インタートライバル・バッファロー協議会、北米伝統先住民食糧システム、インタートライバル農業協議会、アーカンソー大学先住民食糧農 業イニシアティブなどである。 エクアドルの「グッドライフ」プロジェクトのような非政府プロジェクトは、独立組織や先住民コミュニティのメンバーが主導している。「グッドライフ」は、 政府の資金援助や国家による供給を必要としない先住民コミュニティ開発による代替策を提案している。エクアドルでは、先住民コミュニティが「グッドライ フ」プロジェクトを立ち上げ、資本主義や西洋の考え方に基づくコミュニティに必要なものとは異なる、人々や自然との調和、そして土地を守ることでコミュニ ティの成功を育むことに焦点を当てている。本質的には、先住民コミュニティ内で直接的に働き、食料主権を回復することである。[29] 米国の団体もエクアドルの「グッドライフ」プロジェクトに似たモデルを採用している。カリフォルニア州では、カリフォルニア大学バークレー校の団体である CARES(再生可能エネルギーと持続可能性に関する地域評価)が、カリフォルニア州ウキアのPPN(ピノルビル・ポモ族)と協力し、同部族の主権を支援 している。この先住民コミュニティは、長年にわたりCARESと協力し、その文化を反映した持続可能な住宅とエネルギーの設計に取り組んでいる。 ナラガンセット族は、ロードアイランドの「農場」から景観、海景、河口、空間、建造物を再取得することで、独自の食料主権イニシアティブを実施した。この 農場は、1690年以降、本格的に南ニューイングランドの私有地、土地銀行、通貨を維持し、大カリブ海プランテーション複合施設内で活動していた。この運 搬貿易は三角貿易の潜在的な一翼を担うものとなったが、歴史家の中には、自己完結的な運搬貿易は順次循環する三角貿易とは異なるという見解もある。 1769年までに、ロードアイランド州チャールズタウン近郊のナラガンセット族保留地の森林地帯と湿地帯は、5平方マイル未満にまで縮小され、資源配分、 生存、宗教性、人種など、さまざまな影響をもたらした。国勢調査と宣教師の記録によると、ナラガンセット族の退役軍人が七年戦争から帰還する前夜、保留地 の人口は約600人の部族民であったと評価されている。[32] しかし、これらの記録は季節的な漁業のための出稼ぎについては触れておらず また、例えば、ナラガンセット族は「昔から白人や黒人と混血している...彼らの中には、習慣から見ても部族の一員ではない、混血の国民も多数住んでい る」と指摘している。ある宣教師は後に、耕作や自給自足に利用できる保留地は全体の3分の1以下であり、残りは借地や木材用林の維持(販売など)に充てら れていると観察している。 特に狩猟の間の火薬や、漁労用のカヌーの輸送を手伝う「熟練した奴隷」への報酬として、「農民」への負債が残っていたため、18世紀半ばには園芸や農業が 重視され、家畜の飼育は限定的であった。歴史家のダニエル・マンデルは、同様の状況にある東部森林アルゴンキン族のコミュニティと比較して、「ナラガン セット族はさらに劣っていた。1810年、部族は[会衆派宣教師のカーティス・]コーに、畑を耕したり肥料を運んだりする牛はおらず、牛は4頭ほどしか 飼っていないと伝えた。彼はすでに、居留地内の家族は通常、1エーカーほどの農地しか耕していないと指摘していた」と主張している。[34] 南北戦争前の「大北東部」の産業農業の隆盛にもかかわらず、[35] 「グレーター・ノースイースト」の産業農業が勃興したにもかかわらず[35]、ニューイングランド南部の「農場」やカリブ海の砂糖、糖蜜、米、コーヒー、 藍、マホガニー、1740年以前の「鍛えられた奴隷」[37]の運搬貿易[36]は、1800年の選挙[38]までに衰退し始め、1812年の戦争 [39]までにほぼ完全に農業の廃墟と化した。 ナラガンセット族の事業拡大はメディアの注目を集め、学者たちに、東部森林アルゴンキン族のコミュニティに関する既存の研究において、こうした「農場」、 その所有者、多目的のペースメーカー、海港の運送業者、土地銀行、ナラガンセット族の食文化に対する関心が薄れていた、あるいは完全に無視されていたこと を再評価するよう駆り立てた。[40] |
| Seed sovereignty Seed sovereignty can be defined as the right “to breed and exchange diverse open-sourced seeds."[41] It is closely connected to food sovereignty, as seed sovereignty activists argue for the practice of seed saving partly as a means of increasing food security.[42] These activists argue that seed saving allows for a closed food system that can help communities gain independence from major agricultural companies.[11] Seed sovereignty is distinct from food sovereignty in its emphasis on seed saving specifically, rather than food systems in their entirety. Seed sovereignty activists often argue for seed saving based on environmental reasoning, not just food justice ones.[24] They argue that seed saving fills an important role of restoring biodiversity to agriculture, and producing plant varieties that are more resilient to change climatic conditions in light of climate change.[25] |
種子の主権 種子の主権とは、「多様なオープンソースの種子を育種し、交換する権利」と定義することができる。[41] 種子の主権の活動家たちは、食糧安全保障を高める手段のひとつとして、種子を保存する慣行を主張しているため、種子の主権は食糧主権と密接に関連してい る。[ 42] これらの活動家は、種子を保存することで、地域社会が大手農業企業からの自立を達成できる閉鎖的な食糧システムが可能になるとしている。[11] 種子主権は、食糧システム全体ではなく、特に種子保存に重点を置いている点で、食糧主権とは異なる。種子主権の活動家は、食糧の公正さだけでなく、環境上 の理由から種子保存を主張することが多い。[24] 彼らは、種子保存は農業における生物多様性の回復という重要な役割を果たし、気候変動を踏まえて気候条件の変化に耐性のある植物品種を生産することになる と主張している。[25] |
| Food sovereignty versus food security Food sovereignty Movements to reclaim sovereignty over food have existed around the world for centuries; however, the concept of "food sovereignty" itself emerged in 1996.[43] Food sovereignty was initially defined by "small-scale producers [who] organized as the transnational social movement La Vía Campesina (LVC), and was launched globally at the 1996 United Nations World Food Summit."[44] It is a concept that explains how the industrialization of food pathways has decreased one's freedom to choose one's own food source.[45]"Food sovereignty movements work hard to increase local community control of the production, processing, and distribution of food, as this is seen as a necessary condition for liberating communities from oppression,"[46] which has transformed food movements toward building more overall security. In fall 2003, Peter Rosset argues in Food First's Backgrounder that "food sovereignty goes beyond the concept of food security... [Food security] means that... [everyone] must have the certainty of having enough to eat each day[,] ... but says nothing about where that food comes from or how it is produced."[47] Food sovereignty includes support for smallholders and for collectively owned farms, fisheries, etc., rather than industrializing these sectors in a minimally regulated global economy. In another publication, Food First describes "food sovereignty" as "a platform for rural revitalization at a global level based on equitable distribution of farmland and water, farmer control over seeds, and productive small-scale farms supplying consumers with healthy, locally grown food."[47] Food Security Main article: food security In the 90’s the Food and Agriculture Organization defined food security as “all people, at all times, hav[ing] physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life."[48] Despite the fact that food security has become more widely understood in the US as availability and access to nutritious foods all the time, this definition is not universally applicable. For instance, in the European Union, "the official food insecurity indicator includes the unaffordability of ‘a meal with meat, chicken or fish every second day'"[49] This definition differs greatly from food insecurity measurements of the US for instance.The existence of contradicting markers of food insecurity happening globally reflects different research and interpretations of that research.[50] Food security, emphasises access to adequate nutrition for all, which may be provided by food from one's own country or from global imports. In the name of efficiency and enhanced productivity, it has therefore served to promote what has been termed the "corporate food regime":[51] large-scale, industrialised corporate farming based on specialized production, land concentration and trade liberalisation. Critics of the food security movement claim that its inattention to the political economy of the corporate food regime blinds it to the adverse effects of that regime, notably the widespread dispossession of small producers and global ecological degradation.[52] Criticisms of the Green Revolution The Green Revolution, which refers to developments in plant breeding between the 1960s and 1980s that improved yields from major cereal crops, is upheld by some proponents of food security as a success story in increasing crop yields and combating world hunger. The policy focused primarily in research, development and transfer of agricultural technology, such as hybrid seeds and fertilisers, through massive private and public investment that went into transforming agriculture in a number of countries, starting in Mexico and India.[53] However, many in the food sovereignty movement are critical of the green revolution and accuse those who advocate it as following too much of a Western culture technocratic program that is out of touch with the needs of majority of small producers and peasants.[54] While the green revolution greatly increased food production and averted famine, world hunger continues because it did not address the problem of access.[55] Food sovereignty advocates argue that the green revolution failed to alter the highly concentrated distribution of economic power, particularly access to land and purchasing power.[56] Critics also argue that the green revolution's increased use of herbicides caused widespread environmental destruction and reduced biodiversity in many areas. [57] Academic perspectives Food Regime theory According to Philip McMichael, a "world agriculture" under the WTO Agreement on Agriculture ("food from nowhere") represents one pole of the "central contradiction" of the present regime. He is interested in the food sovereignty movement's potential to escalate the tension between this and its opposing pole, the agroecology-based localism ("food from somewhere") advocated by various grassroots food movements.[58] Offering slightly different conclusions, recent work by Harriet Friedmann suggests that "food from somewhere" is already being co-opted under an emergent "corporate-environmental" regime[59] (cf. Campbell 2009).[60] Criticisms Wrong baseline assumptions Some scholars argue that the Food Sovereignty movement follows wrong baseline assumptions, citing that small-scale farming is not necessarily a freely chosen lifestyle and farmers in least developed and highly developed countries do not face the same challenges. These critics claim the Food Sovereignty movement may be right about the mistakes of neoliberal economic ideology, but it is silent about the fact that many famines actually occurred under socialist and communist regimes that pursued the goal of food self-sufficiency (cf. Aerni 2011).[61] Political-jurisdictional model There is a lack of consensus within the food sovereignty movement regarding the political or jurisdictional community at which its calls for democratisation and renewed "agrarian citizenship" [62] are directed. In public statements, the food sovereignty movement urges strong action from both national governments and local communities (in the vein of the indigenous rights movement, Community-Based Natural Resource Management (CBNRM) . Elsewhere it has also appealed to global civil society to act as a check against abuses by national and supranational governing bodies.[63] Those who take a radically critical view on state sovereignty would argue against the possibility that national sovereignty can be reconciled with that of local communities[64] (see also the debate about multiculturalism and indigenous autonomy in Mexico[65][66][67] ). Crisis of the peasantry? In its strong reassertion of rural and peasant identities, the food sovereignty movement has been read as a challenge to modernist narratives of inexorable urbanisation, industrialisation of agriculture, and de-peasantisation. However, as part of ongoing debates over the contemporary relevance of agrarianism in classical Marxism,[68][69] Henry Bernstein is critical of these accounts. He claims that such analyses tend to present the agrarian population as a unified, singular and world-historical social category, failing to account for: a population's vast internal social differentiation (North/South, gender and class positionalities); the conservative, cultural survivalist tendencies of a movement that has emerged as part of a backlash against the perceived homogenising forces of globalisation[70] (Boyer discusses whether food sovereignty is a counter or anti-development narrative[71]) Berstein claims that these accounts cannot escape a certain agrarian populism (or agrarianism). For a response to Bernstein, see McMichael (2009).[72] |
食料主権と食料安全保障 食料主権 食料に対する主権を取り戻そうとする運動は、何世紀にもわたって世界中で存在してきたが、「食料主権」という概念自体は1996年に登場した。[43] 食料主権は当初、「小規模生産者たちが国際的な社会運動であるラ・ビア・カンペシーナ(LVC)として組織化し、1996年の国連世界食料サミットで世界 的に立ち上げられた」[44] ことで定義された。 4] これは、食料供給の工業化が、人々が食料源を自ら選択する自由をいかに減少させてきたかを説明する概念である。[45] 「食料主権運動は、地域社会が食料の生産、加工、流通を管理できるようにすることに力を注いでいる。なぜなら、これが地域社会を圧政から解放するための必 要条件と見なされているからだ」[46] 食料主権運動は、より包括的な安全保障の構築に向けた食料運動へと変貌を遂げた。 2003年秋、ピーター・ロセットは『フード・ファースト』の『バックグラウンダー』誌上で、「食糧主権は食糧安全保障の概念を超えるものである。食糧安 全保障とは、 誰もが毎日十分な食料を確保できるという確信を持たなければならない。しかし、その食料がどこから来るのか、どのように生産されるのかについては何も語っ ていない」[47] 食料主権には、小規模農家や共同所有の農場、漁場などへの支援が含まれ、最小限の規制しかないグローバル経済の中でこれらの部門を工業化することではな い。別の出版物では、フード・ファーストは「食糧主権」を「農地と水の公平な分配、種子の農家による管理、そして、地元で生産された健康的な食品を消費者 に供給する生産性の高い小規模農場を基盤とした、世界レベルでの農村活性化の基盤」と説明している。[47] 食糧安全保障 詳細は「食糧安全保障」を参照 90年代に、国連食糧農業機関(FAO)は食糧安全保障を「すべての人々が、活動的で健康的な生活を送るために必要な食糧を、身体的、社会的、経済的に入 手できること」と定義した。[48] 食糧安全保障は、栄養価の高い食糧が常に利用可能であり、入手できることを意味するものとして、米国ではより広く理解されるようになったが、この定義は普 遍的に適用できるものではない。例えば、欧州連合では、「公式の食料不安指標には、肉、鶏肉、魚を使った食事を2日に1度食べられないこと」も含まれてい る[49]。この定義は、例えば米国の食料不安の測定基準とは大きく異なる。世界中で食料不安の矛盾する指標が存在することは、その研究や解釈が異なるこ とを反映している[50]。 食料安全保障は、自国産の食料または世界からの輸入食料によって、すべての人々が適切な栄養を摂取できることを強調している。効率性と生産性の向上を理由 に、専門化された生産、土地の集中、貿易の自由化を基盤とする大規模な工業的企業農業、すなわち「企業による食料体制」と呼ばれるものを推進する役割を果 たしてきた。食料安全保障運動の批判者たちは、企業による食料体制の政治経済に目を向けないことで、その体制の悪影響、特に小規模生産者の土地収奪や地球 規模の生態系の劣化に気づかないと主張している。 緑の革命に対する批判 緑の革命とは、1960年代から1980年代にかけての主要穀物作物の収穫量を向上させた品種改良を指す言葉であるが、食糧安全保障の推進者の中には、作 物の収穫量を増加させ、世界の飢餓と闘う成功例としてこれを支持する者もいる。この政策は、ハイブリッド種子や肥料などの農業技術の研究、開発、移転に主 に焦点を当て、メキシコやインドをはじめとする多くの国々で農業の変革に投入された大規模な民間および公共投資を通じて実施された。[53] しかし、食料主権運動の多くの人々は、緑の革命を批判しており、それを擁護する人々を、大多数の小規模生産者や農民のニーズとはかけ離れた西欧の技術的プ ログラムに傾倒しすぎていると非難している。[54] 緑の革命は食糧生産を大幅に増加させ、飢饉を回避したが、アクセスという問題に対処できなかったため、世界の飢餓は続いている。[55] 食糧主権の擁護者たちは、緑の革命は経済力の集中した配分、特に土地や購買力へのアクセスを変化させることができなかったと主張している。[56] 批判者たちはまた、緑の革命による除草剤の使用増加が、広範囲にわたる環境破壊と多くの地域における生物多様性の減少を引き起こしたとも主張している。 [57] 学術的な視点 フード・レジーム理論 フィリップ・マクミランによると、WTO農業協定に基づく「世界農業」(「どこでもない場所からの食料」)は、現在の体制における「中心的な矛盾」の一方 の極を代表している。彼は、食料主権運動が、この極と対立する極である、さまざまな草の根の食料運動が提唱する農業生態学に基づく地域主義(「どこかから の食料」)との間の緊張を激化させる可能性に注目している。[58] ハロルド・フリードマンによる最近の研究では、やや異なる結論が示されている。それによると、「どこかからの食料」は、新たに台頭しつつある「企業・環 境」体制にすでに組み込まれているという。[59](キャンベル 2009年参照)[60] 批判 誤った基本前提 一部の学者は、食料主権運動は誤った基本前提に従っていると主張し、小規模農業が必ずしも自由に選択されたライフスタイルではないことや、後進国と先進国 の農家が同じ課題に直面しているわけではないことを挙げている。こうした批判者たちは、新自由主義経済イデオロギーの誤りについてはフード・ソブリンティ 運動が正しいかもしれないが、食料自給を目的とする社会主義や共産主義体制下で実際に多くの飢饉が発生しているという事実については沈黙していると主張し ている(Aerni 2011年参照)[61]。 政治的・管轄区域モデル 食料主権運動では、民主化と「農民の市民権」の再確立を求める声が向けられる政治的・管轄区域共同体に関して、コンセンサスが欠如している。食料主権運動 は公式声明において、各国政府と地域社会の両方に対して強力な行動を促している(先住民の権利運動や地域社会ベースの自然資源管理(CBNRM)の流れに 沿ったものである)。また、別の場面では、国家や超国家的な統治機関による濫用に対する牽制として、グローバルな市民社会に訴えかけている。[63] 国家主権に対して根本的に批判的な見解を持つ人々は、国家主権と地域社会の主権が調和しうるという可能性に反対するだろう。(メキシコにおける多文化主義と先住民の自治に関する議論も参照のこと。[65][66][67]) 農民の危機? 食料主権運動は農村や農民のアイデンティティを強く主張しているため、不可避な都市化、農業の工業化、脱農民化といった近代主義的な物語への挑戦と見なさ れている。しかし、古典的マルクス主義における現代の農本主義の妥当性に関する継続中の議論の一部として、[68][69] ヘンリー・バーンスタインはこれらの説明を批判している。彼は、このような分析は農村人口を単一で世界史的な社会カテゴリーとして統一的に捉えがちであ り、以下の点を説明できていないと主張している。 人口の広範な内部社会分化(南北、ジェンダー、階級の位置づけ) グローバル化の均質化の力に対する反動の一部として現れた運動の保守的で文化的な生存主義的傾向(Boyerは食料主権が開発促進論または開発反対論のど ちらに属するかを論じている[71])を説明できていない。バーンスタインは、これらの説明は特定の農本主義(または農本論)から逃れることができないと 主張している。バーンスタインへの反論については、McMichael(2009年)[72]を参照のこと。 |
| 2007–2008 world food price crisis Land grabbing Permaculture United Nations Decade of Family Farming United Nations Declaration on the Rights of Peasants |
2007年~2008年の世界的な食糧価格危機 土地収奪 パーマカルチャー 国連家族農業の10年 国連農民権利宣言 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Food_sovereignty |
|
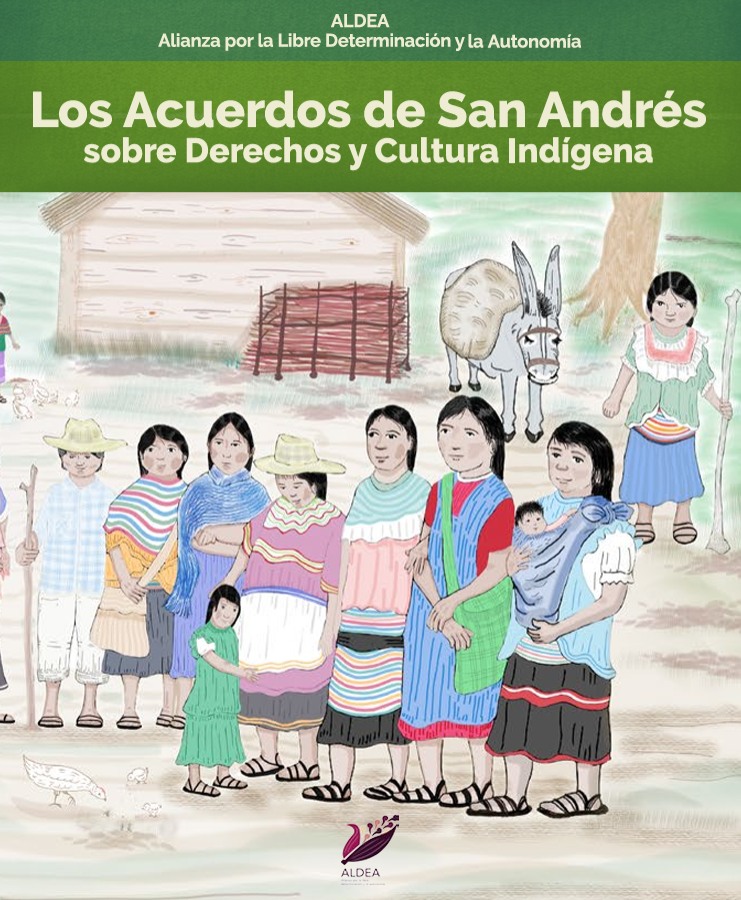 |
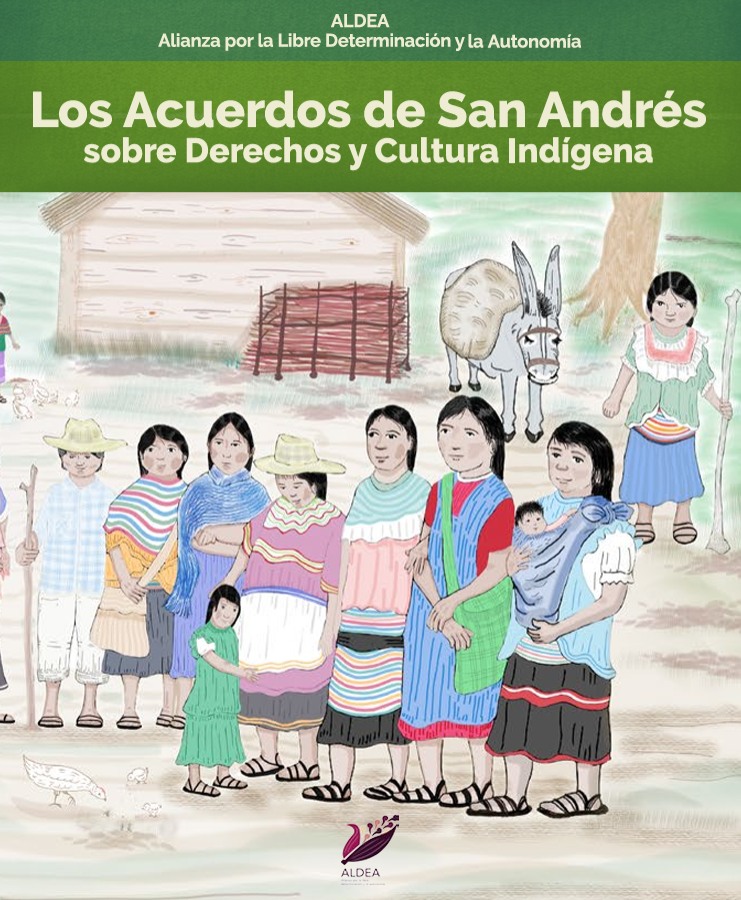
|
| LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS SOBRE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA, de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea). "A 29 años (hoy 30) de los Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) y Serapaz se pronunciaron por seguir luchando por su cumplimiento. "“Es una tarea no limitada sólo al conflicto armado en Chiapas, sino de todos los pueblos y organizaciones”, señalaron. "Como parte de la conmemoración, Aldea publicó un cuadernillo sobre este convenio, suscrito el 16 de febrero de 1996, en los que se establece la importancia de que los pueblos indígenas sean actores fundamentales de las decisiones que afectan su vida, que se les reconozca como sujetos de derecho, así como su libre determinación y autonomía. "También, la necesidad de ampliar la participación y representación política de los pueblos indígenas en el ámbito local y nacional, garantizar su pleno acceso a la justicia, admitir sus sistemas normativos internos para la solución de conflictos y garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas." |
サン・アンドレス協定における先住民の権利と文化について、自由決定と自治のための同盟(アルデア)より。 メキシコ連邦政府とサパティスタ民族解放軍(EZLN)が署名したサン・アンドレス協定から29年(現在は30年)が経過したが、自由決定と自治のための同盟(Aldea)とSerapazは、協定の履行に向けて引き続き闘うことを表明した。 「これは、チアパス州の武力紛争だけでなく、すべての民族と組織にとっての課題だ」と述べた。 記念行事の一環として、アルデアは1996年2月16日に調印されたこの協定に関する小冊子を発行した。そこでは、先住民族が自らの生活に影響を与える決定において重要な役割を担うこと、権利の主体として認められること、そして自己決定と自治の重要性が述べられている。 また、先住民族の地方および国家レベルでの政治参加と代表性を拡大し、司法への完全なアクセスを保証し、紛争解決のための先住民族の内部規範制度を認め、先住民族の基本的ニーズの充足を確保する必要性も述べられている。 |
| https://www.jornada.com.mx/2025/02/16/politica/007n3pol | https://www.jornada.com.mx/2025/02/16/politica/007n3pol |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099