
カント『純粋理性批判』ノート
Critique of Pure Reason, Kritik der reinen Vernunft; 1781; second edition 1787
Photography by Josef Sudek (Czech photographer, 1896–1976)
☆ 『純 粋理性批判』(じゅんすいりせいひはん、ドイツ語: Kritik der reinen Vernunft[pdf]、1781年、第2版1787年)は、ドイツの哲学者イマヌエル・カントによる著書。カントの「第一批判」とも呼ばれ、『実践理性批判』 (1788年)、『判断力批判』(1790年)と続 く。初版の序文でカントは、「純粋理性批判」とは「理性の能力一般について、それが あらゆる経験から独 立して努力しうるあらゆる知識について」の批判を意味し、「形而上学の可能性あるいは不可能性」についての結論に達することを目的としてい ると説明してい る。「批判」という用語は、口語的な意味ではなく、この文脈では体系的な分析を 意味すると理解されている(→黒崎政男「入門」ノート)。
★ウィキペディアの「純粋理性批判」解説・目次(左はCritique
of Pure Reason の章立て)
| 0. アウトライン 1. 背景 ・初期の合理主義
2. カントのアプローチ・カントによるヒュームの経験論の否定 ・合成的アプリオリ判断 ・超越論的観念論 ・エレメント(原理論と訳される)と、方法の教義
I. エレメントの超越論的教義(=超越論的原理論)・純粋理性批判の章別 ・超越論的美学(→超越論的感性論)
II. 方法の超越論的教義(→超越論的方法論)・空間と時間 ・超越論的論理学 ・第一部門 超越論的分析 ・形而上学的演繹(metaphysical deduction) ・超越論的演繹 ・図式論 ・観念論への反論 ・第二部門 超越論的弁証法 ・純粋理性のパラロギスム(誤った推理=誤謬推理) ・誤謬推理=魂は物質(サブスタンス)である ・誤謬推理=魂はシンプルである ・誤謬推理=魂は経験世界から分離している ・純粋理性のアンチノミー ・純粋理性の理想 ・カンタベリーのアンセルムの神の存在に関する存在論的証明に対する反論 ・神の存在に関する宇宙論的証明(「原動力」)に対する反論 ・神の存在に関する物理神学的証明 ・純粋理性の鍛錬
3. 用語とフレーズ・純粋理性の公準 ・純粋理性の建築学(熊野訳、p.791) ・純粋理性の歴史(p.808) 4. 受容 ・初期の反応 1781-1793 ・後の反応 |
The divisions of the Critique of Pure Reason Dedication 1. First and second Prefaces 2. Introduction 3. Transcendental Doctrine of Elements A. Transcendental Aesthetic
(1) On space
B. Transcendental Logic(2) On time (1) Transcendental Analytic
a. Analytic of Concepts
(2) Transcendental Dialectic: Transcendental Illusioni. Metaphysical Deduction ii. Transcendental Deduction b. Analytic of Principles i. Schematism (bridging chapter) ii. System of Principles of Pure Understanding a. Axioms of Intuition b. Anticipations of Perception c. Analogies of Experience d. Postulates of Empirical Thought (Refutation of Idealism) iii. Ground of Distinction of Objects into Phenomena and Noumena iv. Appendix on the Amphiboly of the Concepts of Reflection
a. Paralogisms of Pure Reason
4. Transcendental Doctrine of Methodb. Antinomy of Pure Reason c. Ideal of Pure Reason d. Appendix to Critique of Speculative Theology
A. Discipline of Pure Reason
B. Canon of Pure Reason C. Architectonic of Pure Reason D. History of Pure Reason |
★本文
☆形而上学の可能性とは、カントが「従来の」形而上学を革新できるという自負のことであり、形而上学の不可能性は「従来の」形而上学はそれを成し遂げられなかったという批判のことである。
1) 認識が対象に従うという考えを、対象が認識に従うという視点を確立した。→主観が世 界を成立させる(→バークリーの独我観念論とどう折り合いをつけ るか?)
2) 経験と対象は同時に存在する:「経験の可能性の条件が、同時に、経験の対象の可能性の条件である」(→概念と直観、悟性(理解)と感性の合一があって認識 が成立する)
3) 私たちの認識がかかわるのは物自体ではなく、わたしたちの感性と悟性が成立させる現象なのだ。→世界とは物自体の世界ではなく現象の世界である(→現象の認識は客観的である)
4)現象の認識は客観的だが、物自体についての認識は主観的なものにすぎない(黒崎 2000:25-30)
5)従来の形而上学のあり方を批判して、カントはその「来るべき形而上学」の用語に対して《超越論[的哲学]》という言葉を与える。
6)純粋理性批判は、綜合的学的な方法で書かれた。その後に現れた『プロレゴメナ』は分析的方法で書かれている(プロレゴメナ 篠田訳, p.28)
「ア・プリオリな総合判断はいかにして可能か?」がヘーゲルが考える『純粋理性批判』のテーゼ——(感性と悟性という)非同一なものがアプリオリに同一である理念を表現している。あるいは、構想力を理性とみる見方(黒崎 2000:166)(→「黒崎政男「カント純粋理性批判入門」ノート」)。
★ 『純粋理性批判』(じゅんすいりせいひはん、ドイツ語: Kritik der reinen Vernunft、1781年、第2版1787年)は、ドイツの哲学者イマヌエル・カントによる著書。カントの「第一批判」とも呼ばれ、『実践理性批判』 (1788年)、『判断力批判』(1790年)と続く。初版の序文でカントは、「純粋理性批判」とは「理性の能力一般について、それがあらゆる経験から独 立して努力しうるあらゆる知識について」の批判を意味し、「形而上学の可能性あるいは不可能性」についての結論に達することを目的としていると説明してい る。「批判」という用語は、口語的な意味ではなく、この文脈では体系的な分析を意味すると理解されている。 ︎
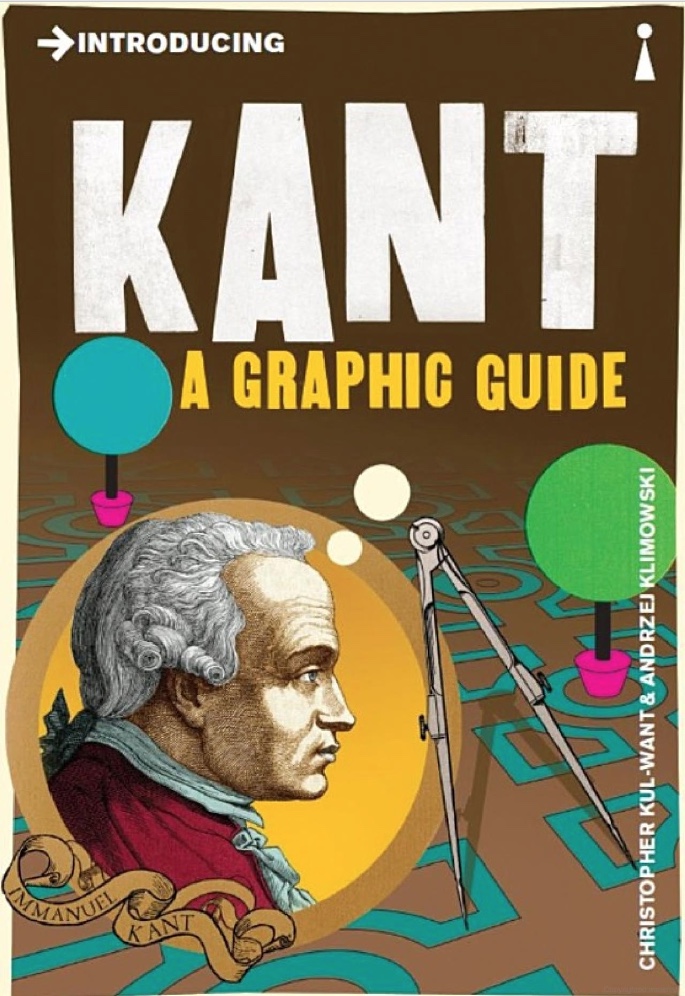


▶︎カントは、ジョン・ロックやデイヴィッド・ヒュームなどの経験主義哲学者や、ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツやクリスティアン・ヴォルフなどの合理主義哲学者の仕事を基礎としている。彼は、(1)空間と時間の本質に関する新しい考えを展開し、(2)原因と結果の関係に関する知識に関するヒュームの懐疑論や、(3)外界に関する知識に関するルネ・デカルトの懐疑論に解答を与えようとしている。 これは、(外見としての)物体とその外見の形式に関する超越論的観念論を通じて主張される。カントは、前者を「単なる表象であって、それ自体としては事物 ではない」とみなし、後者を「我々の直観の感覚的形態にすぎず、それ自体として与えられた決定や、それ自体としての事物の条件ではない」とみなす。これは 先験的知識の可能性を認めるものである。なぜなら、外見としての対象は「われわれの認識に適合しなければならない......それは、対象がわれわれに与 えられる前に、対象について何かを確定することである」。カントによれば、ある命題が必要かつ普遍的である場合、その命題はア・プリオリである。命題が必要 であるのは、それがどのような場合でも偽りでなく、したがって否定できない場合であり、否定は矛盾である。命題が普遍的であるのは、それがあらゆる場合に 真であり、したがっていかなる例外も認めない場合である。カントは、感覚を通じて事後的に得られる知識は、絶対的な必然性と普遍性を与えることはないと主 張する。
▶超越論的とは、我々が意識しないような、経験に先行する形式を明るみにだす方法のことである。
▶︎
カントはさらに「分析的」判断と「合成的=綜合的=総合的」判断の区別について詳しく述べている[4]。命題の述語概念の内容がその命題の主語概念の中に
すでに含まれている場合、その命題は分析的である[5]。例えば、カントは「すべての身体は拡張される」という命題を分析的であると考えるが、これは述語
概念(「拡張される」)が文の主語概念(「身体」)の中にすでに含まれている、つまり「思考されている」ためである。したがって、分析的判断の特徴は、そ
の中に含まれる概念を分析するだけで、それが真であることを知ることができるということである。一方、合成命題では、述語概念は主語概念の中にはすでに含
まれていない。例えば、カントは「すべての身体は重い」という命題を総合的命題とみなしているが、これは「身体」という概念が「重さ」という概念をすでに
含んでいないからである[6]。したがって、総合的判断は概念に何かを付加するのに対して、分析的判断は概念にすでに含まれているものを説明するだけであ
る。
▶︎ カント以前は、先験的知識はすべて分析的でなければならないと考えられていた。しかしカントは、数学、自然科学の第一原理、形而上学に関する知識は、アプ リオリであると同時に総合的であると主張する。このような知識の特異な性質は、説明が必要である。したがって、『批判』の中心的な問題は、次の問いに答え ることである: 「この種の知識の根拠が説明されることは、形而上学と人間の理性にとって「死活問題」であるとカントは主張する。
★カントの「超越論的方法論」——超越と批判——について
「カ ントは、理性が哲学的事業の中心にあると考えた。彼の考えでは、哲学の唯一の仕事は、理性に何ができ、何ができないかを決定することである。哲学とは「人 間の理性の本質的な目的に対するすべての知識の関係の科学」であり、その真の目的は建設的(「純粋な理性から生じるすべての知識の体系を概説すること」) であると同時に批判的(「その限界を忘れた理性の幻想を暴くこと」)である。哲学は、その目的が知恵であり、その実践者自身が 「理性の法学者 」であることから、偉大な尊厳のある職業である。しかし、哲学が「理性の最高格律の科学」であるためには、哲学者は人間の知識の源泉、範囲、妥当性、理性 の究極的限界を決定できなければならない。そして、これらの課題には特別な哲学的方法が必要となる。」
「カ ントはこれを「超越的方法」と呼ぶこともあったが、より多くは「批判的方法」と呼んでいた。彼の目的は、合理主義学派の独断的な仮定を否定することであ り、デカルトが独断的な確実性を主張するようになった以前の、半懐疑的な立場に戻りたいと願っていた。カントの方法は、ア・プリオリな理性の力を批判的に 検証すること、すなわち、すべての経験を取り除いた場合に理性が達成できることを探求することだった。彼の方法は、彼自身が「哲学におけるコペルニクス的 転回」(宇宙論における地動説から天動説への転換に喩えて)と呼んだ教義に基づいていた:対象が人間の知識——または人間の認識装置——に適合しなければ ならないという仮定だ。人間の知識が対象に適合しなければならないという仮定ではない。すると、問題は「この認識装置の正確な性質は何なのか」ということ になった。」
出典:https://www.britannica.com/topic/Western-philosophy/Professionalization-of-philosophy
▶︎
出版当初はほとんど注目されなかったが、後に経験主義者と合理主義者の両方からの攻撃を受け、論争の種となった。西洋哲学に永続的な影響を及ぼし、ドイツ
観念論の発展をもたらした。本書は、数世紀にわたる近世哲学の集大成であり、近代哲学の幕開けと考えられている。
★純粋理性批判に対する不本意な読解がカントをして『プロレゴメナ』の執筆に向かわせしめた
『学(Wissenshaft)として現れることのできるあらゆる将来の形而上学のための序説』
(独: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als
Wissenschaft wird auftreten
können)は、ドイツの哲学者イマヌエル・カントによる著作である。1783年に出版され、『純粋理性批判』初版から2年後のことである。カントの比
較的短い著作の一つであり、『純粋理性批判』の主要な結論を要約している。その中には『批判』では用いられなかった論証も含まれる。カントはここで、より
理解しやすいアプローチを「分析的」と特徴づけ、『批判』における「合成的」な方法、すなわち精神の諸能力とその原理を順次検討する手法と対比させてい
る。[1]本書は論争を意図したものでもある。カントは『純粋理性批判』の受けが思わしくなかったことに失望しており、ここでは批判的プロジェクトが形而
上学という 科学の存在そのものにとって重要だと繰り返し強調している。末尾の付録には『純粋理性批判』に対する否定的な書評への反論が収められている。
★︎「カント入門」▶黒崎政男「カント純粋理性批判入門」ノート︎▶ジル・ドゥルーズの『カントの批判哲学(La philosophie critique de Kant)』︎︎▶ドイツ観念論はやわかり︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎
★『純粋理性批判』アウトライン
| Kant's critical project See also: Critique of Pure Reason In the first Critique, and later on in other works as well, Kant frames the "general" and "real problem of pure reason" in terms of the following question: "How are synthetic judgments a priori possible?"[66][67] To parse this claim, it is necessary to define some terms. First, Kant makes a distinction in terms of the source of the content of knowledge: Cognitions a priori: "cognition independent of all experience and even of all the impressions of the senses". Cognitions a posteriori: cognitions that have their sources in experience—that is, which are empirical.[68] Second, he makes a distinction in terms of the form of knowledge: Analytic proposition: a proposition whose predicate concept is contained in its subject concept; e.g., "All bachelors are unmarried", or "All bodies take up space". These can also be called "judgments of clarification". Synthetic proposition: a proposition whose predicate concept is not contained in its subject concept; e.g., "All bachelors are alone", or "All bodies have weight". These can also be called "judgments of amplification".[69] An analytic proposition is true by nature of strictly conceptual relations. All analytic propositions are a priori (it is analytically true that no analytic proposition could be a posteriori). By contrast, a synthetic proposition is one the content of which includes something new. The truth or falsehood of a synthetic statement depends upon something more than what is contained in its concepts. The most obvious form of synthetic proposition is a simple empirical observation.[70] Philosophers such as David Hume believed that these were the only possible kinds of human reason and investigation, which he called "relations of ideas" and "matters of fact".[71] Establishing the synthetic a priori as a third mode of knowledge would allow Kant to push back against Hume's skepticism about such matters as causation and metaphysical knowledge more generally. This is because, unlike a posteriori cognition, a priori cognition has "true or strict...universality" and includes a claim of "necessity".[72][70] Kant himself regards it as uncontroversial that we do have synthetic a priori knowledge—most obviously, that of mathematics. That 7 + 5 = 12, he claims, is a result not contained in the concepts of seven, five, and the addition operation.[73] Yet, although he considers the possibility of such knowledge to be obvious, Kant nevertheless assumes the burden of providing a philosophical proof that we have a priori knowledge in mathematics, the natural sciences, and metaphysics. It is the twofold aim of the Critique both to prove and to explain the possibility of this knowledge.[74] |
カントの批判的プロジェクト こちらも参照のこと: 純粋理性批判 最初の『純粋理性批判』において、またその後の他の著作においても、カントは「純粋理性の一般的」かつ「現実的な問題」を次のような問いの観点から組み立てている: 「合成的判断はどのようにしてア・プリオリに可能なのか」[66][67]。 この主張を解析するためには、いくつかの用語を定義する必要がある。まず、カントは知識の内容の源泉という観点から区別を行っている: ア・プリオリに認識:「すべての経験、さらには感覚のすべての印象から独立した認識」。 ア・ポステリオリな認識:経験に源泉をもつ認識、すなわち経験的な認識である[68]。 第二に、彼は知識の形式という観点から区別している: 分析的命題:述語概念が主語概念に含まれている命題。例えば、「独身者はみな未婚である」、「すべての身体は空間を占める」などである。これらは「明確性の判断」とも呼ばれる。 合成命題:述語概念が主語概念に含まれない命題;例えば、「独身者はみな孤独である」、「すべての身体には重さがある」など。これらは「増幅の判断」とも呼ばれる[69]。 分析的命題は厳密に概念的な関係によって真である。分析的命題はすべてア・プリオリに真である(分析的命題がア・ポステリオリになることはありえない)。 対照的に、合成命題とは、その内容に新しいものが含まれる命題である。合成命題の真偽は、その概念に含まれるもの以上のものに依存する。合成命題の最も明 白な形式は、単純な経験的観察である[70]。 デイヴィッド・ヒュームのような哲学者たちは、人間の理性と調査にはこのようなものしかあり得ないと考えており、彼はこれを「観念の関係」と「事実の問 題」と呼んでいた[71]。第三の知の様式として合成的アプリオリを確立することで、カントは因果関係や形而上学的知識など一般的なものに対するヒューム の懐疑論に対抗することができるようになる。というのも、ア・ポステリオリな認識とは異なり、アプリオリな認識は「真または厳密な...普遍性」を有し、 「必然性」の主張を含むからである[72][70]。 カント自身は、我々が合成的なア・プリオリに知識を持っていることは議論の余地のないことだと考えている。7+5=12であることは、7、5、および加算 操作の概念に含まれない結果であるとカントは主張する[73]。しかし、そのような知識の可能性は自明であると考えてはいるものの、カントはそれにもかか わらず、数学、自然科学、および形而上学において、われわれがア・プリオリに知識を持っていることを哲学的に証明するという重責を負っている。この知識の 可能性を証明し説明することが『批判』の二重の目的である[74]。 |
| Before
turning to Kant's arguments in the body of the Critique, there are two
more distinctions from its introductory sections that must be
introduced. "There are", Kant says, "two stems of human cognition, which may perhaps arise from a common but to us unknown root, namely sensibility and understanding, through the first of which objects are given to us, but through the second of which they are thought."[75] Kant's term for the object of sensibility is intuition, and his term for the object of the understanding is concept. In general terms, the former is a non-discursive representation of a particular object, and the latter is a discursive (or mediate) representation of a general type of object.[76] The conditions of possible experience require both intuitions and concepts, that is, the affection of the receptive sensibility and the actively synthesizing power of the understanding.[77][e] Thus the statement: "Thoughts without content are empty, intuitions without concepts are blind."[79] Kant's basic strategy in the first half of his book will be to argue that some intuitions and concepts are pure—that is, are contributed entirely by the mind, independent of anything empirical. Knowledge generated on this basis, under certain conditions, can be synthetic a priori. This insight is known as Kant's "Copernican revolution", because, just as Copernicus advanced astronomy by way of a radical shift in perspective, so Kant here claims do the same for metaphysics.[80][81] The second half of the Critique is the explicitly critical part. In this "transcendental dialectic", Kant argues that many of the claims of traditional rationalist metaphysics violate the criteria he claims to establishing the first, "constructive" part of his book.[82][83] As Kant observes, "human reason, without being moved by the mere vanity of knowing it all, inexorably pushes on, driven by its own need to such questions that cannot be answered by any experiential use of reason".[84] It is the project of "the critique of pure reason" to establish the limits as to just how far reason may legitimately so proceed.[85] |
『純粋理性批判』の本文におけるカントの議論に目を向ける前に、その序論部分からさらに2つの区別を紹介しなければならない。 「カントは「人間の認識には二つの茎があり、それはおそらく共通の、しかしわれわれにとっては未知の根から生じるかもしれない、すなわち感性と理解である。 カントの言う感性の対象とは直観であり、彼の言う理解の対象とは概念で ある。一般的な用語では、前者は特定の対象についての非開示的な表象であり、後者は一般的な種類の対象についての開陳的な(あるいは媒介的な)表象である [76]。可能な経験の条件は、直観と概念の両方、すなわち受容的感性の情緒と理解の能動的な総合力を必要とする[77][e]: 「内容なき思考は空虚であり、概念なき直観は盲目である」[79]。 本書の前半におけるカントの基本的な戦略は、ある種の直観と概念は純粋であり、つまり経験的な何ものからも独立して、完全に心によってもたらされるもので あると主張することである。これに基づいて生成された知識は、一定の条件のもとでは、ア・プリオリに合成されうる。この洞察はカントの「コペルニクス的転 回」として知られているが、それはコペルニクスが視点の根本的な転換によって天文学を進歩させたように、カントもここで形而上学に対して同じことを主張す るからである[80][81]。 『純粋理性批判』の後半は明確に批判的な部分である。この「超越論的弁証法」においてカントは、伝統的な合理主義的形而上学の主張の多くが、彼の著作の最 初の「構成的」な部分を確立すると主張する基準に違反していると主張している。[82][83]カントが観察しているように、「人間の理性は、すべてを知 るという単なる虚栄心によって動かされることなく、理性のいかなる経験的な使用によっても答えることができないような疑問に対して、それ自身の必要性に よって駆り立てられながら、どうしようもなく突き進んでいく」[84]。理性がどこまで合法的にそのように突き進むことができるかについての限界を確立す ることが「純粋理性批判」のプロジェクトである[85]。 |
| The doctrine of transcendental idealism See also: Transcendental idealism The section of the Critique entitled "The transcendental aesthetic" advances Kant's famous thesis of transcendental idealism. Something is "transcendental" if it is a necessary condition for the possibility of experience, and "idealism" denotes some form of mind-dependence that must be further specified. (The correct interpretation of Kant's own specification remains controversial.)[86] The thesis, then, states that human beings only experience and know appearances, not things-in-themselves, because space and time are nothing but the subjective forms of intuition that we ourselves contribute to experience.[87][88] Nevertheless, although Kant says that space and time are "transcendentally ideal"—the pure forms of human sensibility, rather than part of nature or reality as it exists in-itself—he also claims that they are "empirically real", by which he means "that 'everything that can come before us externally as an object' is in both space and time, and that our internal intuitions of ourselves are in time".[89][87] However we may interpret Kant's doctrine, he clearly wishes to distinguish his position from the subjective idealism of Berkeley.[90] Paul Guyer, although critical of many of Kant's arguments in this section, nevertheless writes of the "Transcendental Aesthetic" that it "not only lays the first stone in Kant's constructive theory of knowledge; it also lays the foundation for both his critique and his reconstruction of traditional metaphysics. It argues that all genuine knowledge requires a sensory component, and thus that metaphysical claims that transcend the possibility of sensory confirmation can never amount to knowledge."[91] |
超越論的観念論の教義 以下も参照のこと: 超越論的観念論 『純粋理性批判』の「超越論的美学」と題された部分は、超越論的観念論というカントの有名なテーゼを進めている。何かが「超越論的」であるとは、それが経 験の可能性にとって必要な条件である場合であり、「観念論」とは、さらに特定されなければならない何らかの形の心依存性を示す。(カント自身の仕様の正し い解釈は依然として議論の的となっている)[86]。 空間と時間は私たち自身が経験に寄与する主観的な直観の形態に他ならないからである[87][88]。 とはいえ、カントは空間と時間は「超越的に理想的」なものであり、自然やそれ自体として存在する現実の一部ではなく、人間の感性の純粋な形態であるとして いるが、彼はまたそれらが「経験的に実在する」とも主張しており、その意味は「『対象として外的にわれわれの前に現れうるものすべて』は空間と時間の両方 にあり、われわれ自身の内的な直観は時間の中にある」ということである[89][87]。 カントの教義をどのように解釈しようとも、彼は自分の立場をバークレーの主観的観念論と明らかに区別したいと考えている[90]。 ポール・ガイヤーは、このセクションにおけるカントの主張の多くに批判的ではあるが、それでも『超越論的美学』について、「カントの知識の構成論における 最初の石を置いただけでなく、伝統的な形而上学に対する彼の批判と彼の再構築の両方の基礎を築いた」と書いている。それは、すべての真の知識は感覚的な要 素を必要とし、したがって感覚的な確認の可能性を超越した形而上学的な主張は決して知識にはなりえないという主張である」[91]。 |
| Interpretive disagreements One interpretation, known as the "two-world" interpretation, regards Kant's position as a statement of epistemological limitation, that we are not able to transcend the bounds of our own mind, meaning that we cannot access the "thing-in-itself". However, Kant also speaks of the thing in itself or transcendent object as a product of the (human) understanding as it attempts to conceive of objects in abstraction from the conditions of sensibility. Following this line of thought, some interpreters have argued that the thing in itself does not represent a separate ontological domain but simply a way of considering objects by means of the understanding alone; this is known as the "two-aspect" view.[92][93] |
解釈の相違 「二つの世界」解釈として知られる解釈の一つは、カントの立場を認識論的限界の表明とみなすもので、人間は自分の心の境界を超越することはできない、つま り「物自体」にアクセスすることはできないというものである。しかし、カントはまた、それ自体、あるいは超越的な対象というものを、感性の条件から対象を 抽象化して考えようとする(人間の)理解力の産物として語っている。このような思考の流れに従って、それ自体における事物は別の存在論的領域を表している のではなく、単に理解のみによって対象を考察する方法を表しているに過ぎないと主張する解釈者もいる[92][93]。 |
| Kant's theory of judgment See also: Category (Kant) Following the "Transcendental Analytic" is the "Transcendental Logic". Whereas the former was concerned with the contributions of the sensibility, the latter is concerned, first, with the contributions of the understanding ("Transcendental Analytic") and, second, with the faculty of reason as the source of both metaphysical errors and genuine regulatory principles ("Transcendental Dialectic"). The "Transcendental Analytic" is further divided into two sections. The first, "Analytic of Concepts", is concerned with establishing the universality and necessity of the pure concepts of the understanding (i.e., the categories). This section contains Kant's famous "transcendental deduction". The second, "Analytic of Principles", is concerned with the application of those pure concepts in empirical judgments. This second section is longer than the first and is further divided into many sub-sections.[94] |
カントの判断理論 参照のこと: カテゴリー(カント) 「超越論的分析」に続くのが「超越論的論理」である。前者が感性の貢献に関心を寄せていたのに対し、後者は、第一に理解の貢献(「超越論的分析」)、第二に形而上学的誤謬と真の規制原理の両方の源泉としての理性の能力(「超越論的弁証法」)に関心を寄せている。 「超越論的分析」はさらに2つのセクションに分かれている。最初の「概念の分析」は、理解の純粋概念(すなわちカテゴリー)の普遍性と必然性を確立するこ とに関係する。このセクションには、カントの有名な「超越論的演繹」が含まれている。第二の「原理の分析」は、経験的判断におけるそれらの純粋概念の適用 に関するものである。この第二節は第一節よりも長く、さらに多くの小節に分かれている[94]。 |
| Transcendental deduction of the categories of the understanding The "Analytic of Concepts" argues for the universal and necessary validity of the pure concepts of the understanding, or the categories, e.g., the concepts of substance and causation. These twelve basic categories define what it is to be a thing in general—that is, they articulate the necessary conditions according to which something is a possible object of experience. These, in conjunction with the a priori forms of intuition, are the basis of all synthetic a priori cognition. According to Guyer and Wood, "Kant's idea is that just as there are certain essential features of all judgments, so there must be certain corresponding ways in which we form the concepts of objects so that judgments may be about objects."[95] Kant provides two central lines of argumentation in support of his claims about the categories. The first, known as the "metaphysical deduction", proceeds analytically from a table of the Aristotelian logical functions of judgment. As Kant was aware, however, this assumes precisely what the skeptic rejects, namely, the existence of synthetic a priori cognition. For this reason, Kant also supplies a synthetic argument that does not depend upon the assumption in dispute.[96] This argument, provided under the heading "Transcendental Deduction of the Pure Concepts of the Understanding", is widely considered to be both the most important and the most difficult of Kant's arguments in the Critique. Kant himself said that it is the one that cost him the most labor.[97] Frustrated by its confused reception in the first edition of his book, he rewrote it entirely for the second edition.[98][99] The "Transcendental Deduction" gives Kant's argument that these pure concepts apply universally and necessarily to the objects that are given in experience. According to Guyer and Wood, "He centers his argument on the premise that our experience can be ascribed to a single identical subject, via what he calls the 'transcendental unity of apperception,' only if the elements of experience given in intuition are synthetically combined so as to present us with objects that are thought through the categories."[100] Kant's principle of apperception is that "The I think must be able to accompany all my representations; for otherwise something would be represented in me that could not be thought at all, which is as much as to say that the representation would either be impossible or else at least would be nothing for me."[101] The necessary possibility of the self-ascription of the representations of self-consciousness, identical to itself through time, is an a priori conceptual truth that cannot be based on experience.[102] This, however, is only a bare sketch of one of the arguments that Kant presents. |
理解のカテゴリーの超越論的演繹 概念の分析」は、理解の純粋概念、すなわちカテゴリー、例えば物質と因果の概念の普遍的かつ必要な妥当性を論証する。これらの12の基本的なカテゴリー は、一般的に事物とは何かを定義している-つまり、何かが経験の対象となりうる必要条件を明確にしているのである。これらは、直観のアプリオリな形式と結 びついて、すべての総合的アプリオリ認識の基礎となる。 ガイヤーとウッドによれば、「カントの考えは、すべての判断に一定の本質的な特徴があるのと同様に、判断が対象についてのものであることができるように、我々が対象の概念を形成する一定の対応する方法が存在しなければならないということである」[95]。 カントはカテゴリーについての彼の主張を支持するために2つの中心的な論証の筋道を提供している。第一は「形而上学的演繹」として知られるもので、アリス トテレス的な判断の論理的機能の表から分析的に進行する。しかし、カントも気づいていたように、これはまさに懐疑論者が否定するもの、すなわち、合成的 ア・プリオリに認識が存在することを前提としている。この理由から、カントは、論争中の仮定に依存しない合成的な議論も提供している[96]。 この論証は「理解の純粋概念の超越論的演繹」という見出しの下に提供されており、『批判』におけるカントの論証の中で最も重要であり、かつ最も困難なもの であると広く考えられている。カント自身、最も労力を費やしたのはこの論考であると述べている[97]。カントは、この論考の初版における混乱した受容に 不満を抱き、第二版のためにこの論考を全面的に書き直した[98][99]。 超越論的演繹」は、これらの純粋概念が経験において与えられる対象に対して普遍的かつ必然的に適用されるというカントの議論を与える。ガイヤーとウッドに よれば、「カントは、直観において与えられる経験の要素が、カテゴリーを通じて思考される対象を私たちに提示するように総合的に組み合わされる場合にの み、彼が『超越論的な認識の統一』と呼ぶものを介して、私たちの経験が単一の同一の主体に帰属することができるという前提を議論の中心としている」 [100]。 カントの認識の原理は、「私が考えることは、私のすべての表象を伴うことができなければならない。そうでなければ、私のうちに、まったく考えることができない何かが表象されることになる。 しかしながら、これはカントが提示する議論の一つの素描にすぎない。 |
| Principles of pure understanding Kant's deduction of the categories in the "Analytic of Concepts", if successful, demonstrates its claims about the categories only in an abstract way. The task of the "Analytic of Principles" is to show both that they must universally apply to objects given in actual experience (i.e., manifolds of intuition) and how it is they do so.[103] In the first book of this section on the "schematism", Kant connects each of the purely logical categories of the understanding to the temporality of intuition to show that, although non-empirical, they do have purchase upon the objects of experience. The second book continues this line of argument in four chapters, each associated with one of the category groupings. In some cases, it adds a connection to the spatial dimension of intuition to the categories it analyzes.[104] The fourth chapter of this section, "The Analogies of Experience", marks a shift from "mathematical" to "dynamical" principles, that is, to those that deal with relations among objects. Some commentators consider this the most significant section of the Critique.[105] The analogies are three in number: Principle of persistence of substance: Kant is here concerned with the general conditions of determining time-relations among the objects of experience. He argues that the unity of time implies that "all change must consist in the alteration of states in an underlying substance, whose existence and quantity must be unchangeable or conserved."[106] Principle of temporal succession according to the law of causality: Here Kant argues that "we can make determinate judgments about the objective succession of events, as contrasted to merely subjective successions of representations, only if every objective alteration follows a necessary rule of succession, or a causal law." This is Kant's most direct rejoinder to Hume's skepticism about causality.[107] Principle of simultaneity according to the law of reciprocity or community: The final analogy argues that "determinate judgments that objects (or states of substance) in different regions of space exists simultaneously are possible only if such objects stand in mutual causal relation of community or reciprocal interaction." (This is Kant's rejoinder to Leibniz's thesis in the Monadology.)[108][109] The fourth section of this chapter, which is not an analogy, deals with the empirical use of the modal categories. That was the end of the chapter in the A edition of the Critique. The B edition, however, includes one more short section, "The Refutation of Idealism". In this section, by analysis of the concept of self-consciousness, Kant argues that his transcendental idealism is a "critical" or "formal" idealism that does not deny the existence of reality apart from our subjective representations.[110] The final chapter of "The Analytic of Principles" distinguishes phenomena, of which we have can have genuine knowledge, from noumena, a term which refers to objects of pure thought that we cannot know, but to which we may still refer "in a negative sense".[111] An Appendix to the section further develops Kant's criticism of Leibnizian-Wolffian rationalism by arguing that its "dogmatic" metaphysics confuses the "mere features of concepts through which we think things...[with] features of the objects themselves". Against this, Kant reasserts his own insistence upon the necessity of a sensible component in all genuine knowledge.[112] |
純粋理解の原理 「概念の分析」におけるカントのカテゴリーの演繹は、もし成功したとしても、カテゴリーについての主張を抽象的にしか実証しない。諸原理の分析」の課題 は、諸原理が実際の経験において与えられる対象(すなわち直観の多様体)に対して普遍的に適用されなければならないということと、どのようにしてそうなる のかということの両方を示すことである[103]。 この「図式論」に関するセクションの第一の書において、カントは、理解の純粋に論理的な範疇のそれぞれを直観の時間性と結びつけて、非経験的ではあるが、 それらが経験の対象に対して購入を有することを示す。第2巻では、この論旨を4つの章に分け、各章を範疇のグループ分けに関連させている。場合によって は、分析するカテゴリーに直観の空間的次元との関連性を加えている[104]。 このセクションの第4章である「経験の類比」は、「数学的」原理から「力学的」原理、つまり対象間の関係を扱う原理への転換を意味している。ある論者は、この章が『批判』の最も重要な部分であると考えている[105]: 実体の持続性の原理: カントはここで、経験の対象間の時間的関係を決定する一般的な条件に関心を抱いている。彼は、時間の単一性は、「すべての変化は、根底にある物質における 状態の変化から成っていなければならず、その存在と量は不変であるか保存されていなければならない」ことを意味していると論じている[106]。 因果律に従った時間的継承の原理:ここでカントは、「すべての客観的変化が必然的な継承の規則、すなわち因果律に従う場合にのみ、われわれは、単に主観的 な表象の継承とは対照的に、出来事の客観的継承について確定的な判断を下すことができる」と主張している。これは因果性に関するヒュームの懐疑論に対する カントの最も直接的な反論である[107]。 互酬性または共同体の法則による同時性の原理: 最後の類比は、「空間の異なる領域にある物体(あるいは物質の状態)が同時に存在するという確定的判断は、そのような物体が共同体あるいは相互相互作用の 相互因果関係に立っている場合にのみ可能である」と主張する。(これは『モナドロジー』におけるライプニッツのテーゼに対するカントの再反論である) [108][109]。 この章の第4節は類比ではないが、様相範疇の経験的使用を扱っている。A版の『批評』ではこの章はここまでであった。 しかし、B版には、「観念論の反駁」という短い節がもう一つある。この章では、自己意識の概念の分析によって、カントは自分の超越論的観念論が、われわれの主観的表象から離れた現実の存在を否定しない「批判的」あるいは「形式的」観念論であると主張している[110]。 原理の分析』の最終章は、我々が真正な知識を持つことができる現象を、我々が知ることはできないが、それでも「否定的な意味で」言及することができる純粋思考の対象を指す用語であるヌーメナ(noumena)から区別している[111]。 このセクションの付録は、ライプニッツ=ヴォルフの合理主義に対するカントの批判をさらに発展させ、その「独断的な」形而上学が「われわれが物事を考える ための概念の単なる特徴と...(中略)対象それ自体の特徴」を混同していると論じている。これに対してカントは、すべての真の知識に感覚的な要素が必要 であるという彼自身の主張を再び主張する[112]。 |
| Critique of metaphysics The second of the two Divisions of "The Transcendental Logic", "The Transcendental Dialectic", contains the "negative" portion of Kant's Critique, which builds upon the "positive" arguments of the preceding "Transcendental Analytic" to expose the limits of metaphysical speculation. In particular, it is concerned to demonstrate as spurious the efforts of reason to arrive at knowledge independent of sensibility. This endeavor, Kant argues, is doomed to failure, which he claims to demonstrate by showing that reason, unbounded by sense, is always capable of generating opposing or otherwise incompatible conclusions. Like "the light dove, in free flight cutting through the air, the resistance of which it feels", reason "could get the idea that it could do even better in airless space".[113] Against this, Kant claims that, absent epistemic friction, there can be no knowledge. Nevertheless, Kant's critique is not entirely destructive. He presents the speculative excesses of traditional metaphysics as inherent in our very capacity of reason. Moreover, he argues that its products are not without some (carefully qualified) regulative value. |
形而上学批判 超越論的論理学』の2つの部分のうちの2つ目、『超越論的弁証法』には、カントの『批判』の「否定的」な部分が含まれており、先行する『超越論的分析』の 「肯定的」な議論を基礎として、形而上学的な思索の限界を明らかにする。特に、感性から独立した知識に到達しようとする理性の努力は偽りであることを明ら かにする。この試みは失敗に終わるとカントは主張し、感覚に束縛されない理性は、常に相反する結論や、そうでなければ相容れない結論を生み出す可能性があ ることを示すことによって、それを証明すると主張する。 光の鳩が、抵抗を感じながら空気を切り裂きながら自由に飛んでいる」ように、理性は「空気のない空間ではもっとうまくやれるという考えを得ることができる」[113]。 とはいえ、カントの批判は完全に破壊的なものではない。彼は伝統的な形而上学の思弁的な行き過ぎを、われわれの理性の能力そのものに内在するものとして提示している。さらに彼は、その産物が何らかの(注意深く修飾された)規制的価値を持たないわけではないと主張する。 |
| On the concepts of pure reason Kant calls the basic concepts of metaphysics "ideas". They are different from the concepts of understanding in that they are not limited by the critical stricture limiting knowledge to the conditions of possible experience and its objects. "Transcendental illusion" is Kant's term for the tendency of reason to produce such ideas.[114] Although reason has a "logical use" of simply drawing inferences from principles, in "The Transcendental Dialectic", Kant is concerned with its purportedly "real use" to arrive at conclusions by way of unchecked regressive syllogistic ratiocination.[115] The three categories of relation, pursued without regard to the limits of possible experience, yield the three central ideas of traditional metaphysics: The soul: the concept of substance as the ultimate subject; The world in its entirety: the concept of causation as a completed series; and God: the concept of community as the common ground of all possibilities.[115] Although Kant denies that these ideas can be objects of genuine cognition, he argues that they are the result of reason's inherent drive to unify cognition into a systematic whole.[114] Leibnizian-Wolffian metaphysics was divided into four parts: ontology, psychology, cosmology, and theology. Kant replaces the first with the positive results of the first part of the Critique. He proposes to replace the following three with his later doctrines of anthropology, the metaphysical foundations of natural science, and the critical postulation of human freedom and morality.[116] |
純粋理性の概念について カントは形而上学の基本概念を「イデア」と呼んでいる。それらは、知識を可能な経験とその対象の条件に限定するという批判的な厳格さによって制限されない という点で、理解の概念とは異なる。「超越論的幻想」とは、理性がそのような観念を生み出す傾向に対するカントの用語である[114]。 理性は単純に原理から推論を導くという「論理的な使用」を持っているが、『超越論的弁証法』においてカントは、抑制されない逆行的な音韻論的ラチオシオンによって結論に到達するという、「本当の使用」と称される理性に関心を抱いている[115]。 可能な経験の限界を無視して追求される関係の3つのカテゴリーは、伝統的な形而上学の3つの中心的な考え方をもたらす: 魂:究極的な主体としての実体概念; 世界全体:完成された系列としての因果の概念。 神:すべての可能性の共通基盤としての共同体の概念[115]。 カントはこれらの観念が真正な認識の対象でありうることを否定しているが、それらは認識を体系的な全体へと統一しようとする理性に固有の衝動の結果であると論じている[114]。 ライプニッツ=ヴォルフの形而上学は、存在論、心理学、宇宙論、神学の4つの部分に分かれていた。カントは最初の部分を『批判』の最初の部分の肯定的な結 果に置き換える。彼は次の3つを、人間学、自然科学の形而上学的基礎、人間の自由と道徳の批判的提起という後の教義に置き換えることを提案している [116]。 |
| The dialectical inferences of pure reason In the second of the two Books of "The Transcendental Dialectic", Kant undertakes to demonstrate the contradictory nature of unbounded reason. He does this by developing contradictions in each of the three metaphysical disciplines that he contends are, in fact, pseudo-sciences. This section of the Critique is long and Kant's arguments are extremely detailed. In this context, it not possible to do much more than enumerate the topics of discussion. The first chapter addresses what Kant terms the paralogisms—i.e., false inferences—that pure reason makes in the metaphysical discipline of rational psychology. He argues that one cannot take the mere thought of "I" in the proposition "I think" as the proper cognition of "I" as an object. In this way, he claims to debunk various metaphysical theses about the substantiality, unity, and self-identity of the soul.[117] The second chapter, which is the longest, takes up the topic Kant calls the antinomies of pure reason—that is, the contradictions of reason with itself—in the metaphysical discipline of rational cosmology. (Originally, Kant had thought that all transcendental illusion could be analyzed in antinomic terms.[118]) He presents four cases in which he claims reason is able to prove opposing theses with equal plausibility: That "reason seems to be able to prove that the universe is both finite and infinite in space and time"; that "reason seems to be able to prove that matter both is and is not infinitely divisible into ever smaller parts"; that "reason seems to be able to prove that free will cannot be a causally efficacious part of the world (because all of nature is deterministic) and yet that it must be such a cause"; and, that "reason seems to be able to prove that there is and there is not a necessary being (which some would identify with God)".[119][120] Kant further argues in each case that his doctrine of transcendental idealism is able to resolve the antinomy.[119] The third chapter examines fallacious arguments about God in rational theology under the heading of the "Ideal of Pure Reason". (Whereas an idea is a pure concept generated by reason, an ideal is the concept of an idea as an individual thing.[121]) Here Kant addresses and claims to refute three traditional arguments for the existence of God: the ontological argument, the cosmological argument, and the physio-theological argument (i.e., the argument from design).[122] The results of the transcendental dialectic so far appear to be entirely negative. In an Appendix to this section, however, Kant rejects such a conclusion. The ideas of pure reason, he argues, have an important regulatory function in directing and organizing our theoretical and practical inquiry. Kant's later works elaborate upon this function at length and in detail.[123] |
純粋理性の弁証法的推論 超越論的弁証法』の2冊のうちの2冊目では、カントは束縛されない理性の矛盾した性質を実証しようとする。これは、カントが実際には疑似科学であると主張 する3つの形而上学的学問のそれぞれにおける矛盾を展開することによって行われる。批判』のこの部分は長く、カントの議論は極めて詳細である。この文脈で は、論点を列挙する以上のことはできない。 第一章では、カントが合理的心理学という形而上学的学問において、純粋理性が行うパラロギスム、すなわち誤った推論を取り上げる。彼は、「私は考える」と いう命題における「私」の単なる思考を、対象としての「私」の適切な認識とみなすことはできないと主張する。このようにして彼は、魂の実体性、統一性、自 己同一性についてのさまざまな形而上学的テーゼを論破すると主張している[117]。 最も長い第二章では、カントが純粋理性の反知性、すなわち理性とそれ自身との矛盾と呼ぶトピックを、理性的宇宙論という形而上学的学問領域において取り上 げる。(もともとカントは、すべての超越論的幻想は反原理的な用語で分析できると考えていた[118])。彼は、理性が対立するテーゼを等しくもっともら しく証明できると主張する4つのケースを提示する: 理性は宇宙が空間と時間において有限であると同時に無限であることを証明できるようである」; 理性は、物質が無限に分割可能であると同時に、無限に分割不可能であることを証明できるようだ」; 理性は、自由意志が(自然のすべてが決定論的であるため)世界の因果的な部分であるはずがなく、しかしそのような原因でなければならないことを証明することができるようである、 理性は、必要な存在(これを神と同一視する者もいる)が存在することも存在しないことも証明できるように思われる」[119][120]。 カントはさらにそれぞれの場合において、超越論的観念論の教義がアンチノミーを解決することができると主張している[119]。 第3章では、「純粋理性のイデア」という見出しの下で、合理的神学における神についての誤った議論を検証している。(イデアとは理性によって生み出される 純粋な概念であるのに対して、イデアとは個別的なものとしてのイデアの概念である[121])。ここでカントは、神の存在についての伝統的な三つの議論、 すなわち存在論的議論、宇宙論的議論、および物理神学的議論(すなわち設計からの議論)を取り上げ、それに対する反論を主張している[122]。 ここまでの超越論的弁証法の結果は、完全に否定的であるように見える。しかし、この節の付録において、カントはそのような結論を否定している。純粋理性の 理念は、われわれの理論的・実践的探究を方向づけ、組織化するうえで重要な調節機能をもっている、と彼は主張している。カントの後期の著作は、この機能を 長く詳細に詳述している[123]。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant |
★ウィキペディアの「純粋理性批判」解説・目次(左はCritique of Pure Reason の章立て)→このページの冒頭に移転.
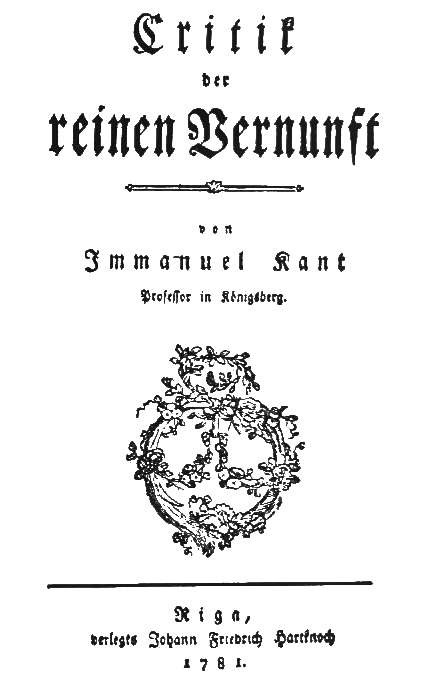 The
Critique of Pure
Reason (German: Kritik der reinen Vernunft; 1781; second
edition 1787)
is a book by the German philosopher Immanuel Kant, in which the author
seeks to determine the limits and scope of metaphysics. Also referred
to as Kant's "First Critique", it was followed by his Critique of
Practical Reason (1788) and Critique of Judgment (1790). In the preface
to the first edition, Kant explains that by a "critique of pure reason"
he means a critique "of the faculty of reason in general, in respect of
all knowledge after which it may strive independently of all
experience" and that he aims to reach a decision about "the possibility
or impossibility of metaphysics". The term "critique" is understood to
mean a systematic analysis in this context, rather than the colloquial
sense of the term. The
Critique of Pure
Reason (German: Kritik der reinen Vernunft; 1781; second
edition 1787)
is a book by the German philosopher Immanuel Kant, in which the author
seeks to determine the limits and scope of metaphysics. Also referred
to as Kant's "First Critique", it was followed by his Critique of
Practical Reason (1788) and Critique of Judgment (1790). In the preface
to the first edition, Kant explains that by a "critique of pure reason"
he means a critique "of the faculty of reason in general, in respect of
all knowledge after which it may strive independently of all
experience" and that he aims to reach a decision about "the possibility
or impossibility of metaphysics". The term "critique" is understood to
mean a systematic analysis in this context, rather than the colloquial
sense of the term.Kant builds on the work of empiricist philosophers such as John Locke and David Hume, as well as rationalist philosophers such as Gottfried Wilhelm Leibniz and Christian Wolff. He expounds new ideas on the nature of space and time, and tries to provide solutions to the skepticism of Hume regarding knowledge of the relation of cause and effect and that of René Descartes regarding knowledge of the external world. This is argued through the transcendental idealism of objects (as appearance) and their form of appearance. Kant regards the former "as mere representations and not as things in themselves", and the latter as "only sensible forms of our intuition, but not determinations given for themselves or conditions of objects as things in themselves". This grants the possibility of a priori knowledge, since objects as appearance "must conform to our cognition...which is to establish something about objects before they are given to us." Knowledge independent of experience Kant calls "a priori" knowledge, while knowledge obtained through experience is termed "a posteriori".[2] According to Kant, a proposition is a priori if it is necessary and universal. A proposition is necessary if it is not false in any case and so cannot be rejected; rejection is contradiction. A proposition is universal if it is true in all cases, and so does not admit of any exceptions. Knowledge gained a posteriori through the senses, Kant argues, never imparts absolute necessity and universality, because it is possible that we might encounter an exception.[3] Kant further elaborates on the distinction between "analytic" and "synthetic" judgments.[4] A proposition is analytic if the content of the predicate-concept of the proposition is already contained within the subject-concept of that proposition.[5] For example, Kant considers the proposition "All bodies are extended" analytic, since the predicate-concept ('extended') is already contained within—or "thought in"—the subject-concept of the sentence ('body'). The distinctive character of analytic judgments was therefore that they can be known to be true simply by an analysis of the concepts contained in them; they are true by definition. In synthetic propositions, on the other hand, the predicate-concept is not already contained within the subject-concept. For example, Kant considers the proposition "All bodies are heavy" synthetic, since the concept 'body' does not already contain within it the concept 'weight'.[6] Synthetic judgments therefore add something to a concept, whereas analytic judgments only explain what is already contained in the concept. Prior to Kant, it was thought that all a priori knowledge must be analytic. Kant, however, argues that our knowledge of mathematics, of the first principles of natural science, and of metaphysics, is both a priori and synthetic. The peculiar nature of this knowledge cries out for explanation. The central problem of the Critique is therefore to answer the question: "How are synthetic a priori judgments possible?"[7] It is a "matter of life and death" to metaphysics and to human reason, Kant argues, that the grounds of this kind of knowledge be explained.[7] Though it received little attention when it was first published, the Critique later attracted attacks from both empiricist and rationalist critics, and became a source of controversy. It has exerted an enduring influence on Western philosophy, and helped bring about the development of German idealism. The book is considered a culmination of several centuries of early modern philosophy and an inauguration of modern philosophy. |
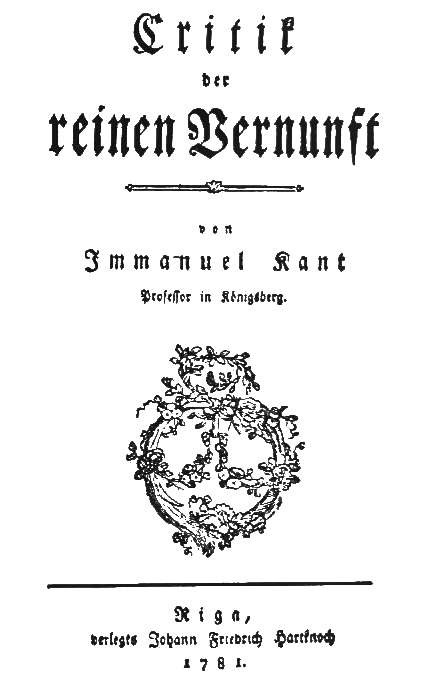 『純粋理性批判』(じゅんすいりせいひはん、ドイ
ツ語:
Kritik
der reinen
Vernunft、1781年、第2版1787年)は、ドイツの哲学者イマヌエル・カントに
よる著書。カントの「第一批判」とも呼ばれ、『実践理性批判』
(1788年)、『判断力批判』(1790年)と続
く。初版の序文でカントは、「純粋理性批判」とは「理性の能力一般について、それがあらゆる経験から独
立して努力しうるあらゆる知識について」の批判を意味し、「形而上学の可能性あるいは不可能性」についての結論に達することを目的としていると説明してい
る。「批判」
という用語は、口語的な意味ではなく、この文脈では体系的な分析を意味すると
理解されている。 『純粋理性批判』(じゅんすいりせいひはん、ドイ
ツ語:
Kritik
der reinen
Vernunft、1781年、第2版1787年)は、ドイツの哲学者イマヌエル・カントに
よる著書。カントの「第一批判」とも呼ばれ、『実践理性批判』
(1788年)、『判断力批判』(1790年)と続
く。初版の序文でカントは、「純粋理性批判」とは「理性の能力一般について、それがあらゆる経験から独
立して努力しうるあらゆる知識について」の批判を意味し、「形而上学の可能性あるいは不可能性」についての結論に達することを目的としていると説明してい
る。「批判」
という用語は、口語的な意味ではなく、この文脈では体系的な分析を意味すると
理解されている。カントは、ジョン・ロックやデイヴィッド・ヒュームなどの経験主義哲学者や、ゴットフリー ト・ヴィルヘルム・ライプニッツやクリスティアン・ヴォルフなど の合理主義哲学者の仕事を基礎としている。彼は、空間と時間の本質に関する新しい考えを展開し、原因と結果の関係に関する知識に関するヒュームの懐疑論 や、外界に関する知識に関するルネ・デカルトの懐疑論に解答を与えようとしている。これは、(外見としての)物体とその外見の形式に関する超越論的観念論 を通じて主張される。カントは、前者を「単なる表象であって、それ自体としては事物ではない」とみなし、後者を「我々の直観の感覚的形態にすぎず、それ自 体として与えられた決定や、それ自体としての事物の条件ではない」とみなす。これは先験的知識の可能性を認めるものである。なぜなら、外見としての対象は 「われわれの認識に適合しなければならない......それは、対象がわれわれに与えられる前に、対象について何かを確定することである」。カントによれ ば、ある命題が必要かつ普遍的である場合、その命題はアプリオリである。命題が必要であるのは、それがどのような場合でも偽りでなく、したがって否定でき ない場合であり、否定は矛盾である。命題が普遍的であるのは、それがあらゆる場合に真であり、したがっていかなる例外も認めない場合である。カントは、感 覚を通じて事後的に得られる知識は、絶対的な必然性と普遍性を与えることはないと主張する。 カントはさらに「分析的」判断と「合成的=綜合的=総合的」判断の区別について詳しく述べている[4]。命題の述語概念の内容がその命題の主語概念の中に すでに含まれてい る場合、その命題は分析的である[5]。例えば、カントは「すべての身体は拡張される」という命題を分析的であると考えるが、これは述語概念(「拡張され る」)が文の主語概念(「身体」)の中にすでに含まれている、つまり「思考されている」ためである。したがって、分析的判断の特徴は、その中に含まれる概 念を分析するだけで、それが真であることを知ることができるということである。一方、合成命題では、述語概念は主語概念の中にはすでに含まれていない。例 えば、カントは「すべての身体は重い」という命題を総合的命題とみなしているが、これは「身体」という概念が「重さ」という概念をすでに含んでいないから である[6]。したがって、総合的判断は概念に何かを付加するのに対して、分析的判断は概念にすでに含まれているものを説明するだけである。 カント以前は、先験的知識はすべて分析的でなければならないと考えられていた。しかしカントは、数学、自然科学の第一原理、形而上学に関する知識は、アプ リオリであると同時に総合的であると主張する。このような知識の特異な性質は、説明が必要である。したがって、『批判』の中心的な問題は、次の問いに答え ることである: 「この種の知識の根拠が説明されることは、形而上学と人間の理性にとって「死活問題」であるとカントは主張する。 出版当初はほとんど注目されなかったが、後に経験主義者と合理主義者の両方からの攻撃を受け、論争の種となった。西洋哲学に永続的な影響を及ぼし、ドイツ 観念論の発展をもたらした。本書は、数世紀にわたる近世哲学の集大成であり、近代哲学の幕開けと考えられている。 |
| Background Early rationalism Before Kant, it was generally held that truths of reason must be analytic, meaning that what is stated in the predicate must already be present in the subject (e.g., "An intelligent man is intelligent" or "An intelligent man is a man").[8] In either case, the judgment is analytic because it is ascertained by analyzing the subject. It was thought that all truths of reason, or necessary truths, are of this kind: that in all of them there is a predicate that is only part of the subject of which it is asserted.[8] If this were so, attempting to deny anything that could be known a priori (e.g., "An intelligent man is not intelligent" or "An intelligent man is not a man") would involve a contradiction. It was therefore thought that the law of contradiction is sufficient to establish all a priori knowledge.[9] David Hume at first accepted the general view of rationalism about a priori knowledge. However, upon closer examination of the subject, Hume discovered that some judgments thought to be analytic, especially those related to cause and effect, were actually synthetic (i.e., no analysis of the subject will reveal the predicate). They thus depend exclusively upon experience and are therefore a posteriori. Kant's rejection of Hume's empiricism Before Hume, rationalists had held that effect could be deduced from cause; Hume argued that it could not and from this inferred that nothing at all could be known a priori in relation to cause and effect. Kant, who was brought up under the auspices of rationalism, was deeply disturbed by Hume's skepticism. "I freely admit that it was the remembrance of David Hume which, many years ago, first interrupted my dogmatic slumber and gave my investigations in the field of speculative philosophy a completely different direction."[10] Kant decided to find an answer and spent at least twelve years thinking about the subject.[11] Although the Critique of Pure Reason was set down in written form in just four to five months, while Kant was also lecturing and teaching, the work is a summation of the development of Kant's philosophy throughout that twelve-year period.[12] Kant's work was stimulated by his decision to take seriously Hume's skeptical conclusions about such basic principles as cause and effect, which had implications for Kant's grounding in rationalism. In Kant's view, Hume's skepticism rested on the premise that all ideas are presentations of sensory experience. The problem that Hume identified was that basic principles such as causality cannot be derived from sense experience only: experience shows only that one event regularly succeeds another, not that it is caused by it. In section VI ("The General Problem of Pure Reason") of the introduction to the Critique of Pure Reason, Kant explains that Hume stopped short of considering that a synthetic judgment could be made 'a priori'. Kant's goal was to find some way to derive cause and effect without relying on empirical knowledge. Kant rejects analytical methods for this, arguing that analytic reasoning cannot tell us anything that is not already self-evident, so his goal was to find a way to demonstrate how the synthetic a priori is possible. To accomplish this goal, Kant argued that it would be necessary to use synthetic reasoning. However, this posed a new problem: how is it possible to have synthetic knowledge that is not based on empirical observation; that is, how are synthetic a priori truths possible? This question is exceedingly important, Kant maintains, because he contends that all important metaphysical knowledge is of synthetic a priori propositions. If it is impossible to determine which synthetic a priori propositions are true, he argues, then metaphysics as a discipline is impossible. The remainder of the Critique of Pure Reason is devoted to examining whether and how knowledge of synthetic a priori propositions is possible. Synthetic a priori judgments  Immanuel Kant, lecturing to Russian officers—by I. Soyockina / V. Gracov, the Kant Museum, Kaliningrad Kant argues that there are synthetic judgments such as the connection of cause and effect (e.g., "... Every effect has a cause.") where no analysis of the subject will produce the predicate. Kant reasons that statements such as those found in geometry and Newtonian physics are synthetic judgments. Kant uses the classical example of 7 + 5 = 12. No amount of analysis will find 12 in either 7 or 5 and vice versa, since an infinite number of two numbers exist that will give the sum 12. Thus Kant arrives at the conclusion that all pure mathematics is synthetic though a priori; the number 7 is seven and the number 5 is five and the number 12 is twelve and the same principle applies to other numerals; in other words, they are universal and necessary. For Kant then, mathematics is synthetic judgment a priori. Conventional reasoning would have regarded such an equation to be analytic a priori by considering both 7 and 5 to be part of one subject being analyzed, however Kant looked upon 7 and 5 as two separate values, with the value of five being applied to that of 7 and synthetically arriving at the logical conclusion that they equal 12. This conclusion led Kant into a new problem as he wanted to establish how this could be possible: How is pure mathematics possible?[11] This also led him to inquire whether it could be possible to ground synthetic a priori knowledge for a study of metaphysics, because most of the principles of metaphysics from Plato through to Kant's immediate predecessors made assertions about the world or about God or about the soul that were not self-evident but which could not be derived from empirical observation (B18-24). For Kant, all post-Cartesian metaphysics is mistaken from its very beginning: the empiricists are mistaken because they assert that it is not possible to go beyond experience and the dogmatists are mistaken because they assert that it is possible to go beyond experience through theoretical reason. Therefore, Kant proposes a new basis for a science of metaphysics, posing the question: how is a science of metaphysics possible, if at all? According to Kant, only practical reason, the faculty of moral consciousness, the moral law of which everyone is immediately aware, makes it possible to know things as they are.[13] This led to his most influential contribution to metaphysics: the abandonment of the quest to try to know the world as it is "in itself" independent of sense experience. He demonstrated this with a thought experiment, showing that it is not possible to meaningfully conceive of an object that exists outside of time and has no spatial components and is not structured in accordance with the categories of the understanding (Verstand), such as substance and causality. Although such an object cannot be conceived, Kant argues, there is no way of showing that such an object does not exist. Therefore, Kant says, the science of metaphysics must not attempt to reach beyond the limits of possible experience but must discuss only those limits, thus furthering the understanding of ourselves as thinking beings. The human mind is incapable of going beyond experience so as to obtain a knowledge of ultimate reality, because no direct advance can be made from pure ideas to objective existence.[14] Kant writes: "Since, then, the receptivity of the subject, its capacity to be affected by objects, must necessarily precede all intuitions of these objects, it can readily be understood how the form of all appearances can be given prior to all actual perceptions, and so exist in the mind a priori" (A26/B42). Appearance is then, via the faculty of transcendental imagination (Einbildungskraft), grounded systematically in accordance with the categories of the understanding. Kant's metaphysical system, which focuses on the operations of cognitive faculties (Erkenntnisvermögen), places substantial limits on knowledge not founded in the forms of sensibility (Sinnlichkeit). Thus it sees the error of metaphysical systems prior to the Critique as failing to first take into consideration the limitations of the human capacity for knowledge. Transcendental imagination is described in the first edition of the Critique of Pure Reason but Kant omits it from the second edition of 1787.[15] It is because he takes into account the role of people's cognitive faculties in structuring the known and knowable world that in the second preface to the Critique of Pure Reason Kant compares his critical philosophy to Copernicus' revolution in astronomy. Kant (Bxvi) writes: Hitherto it has been assumed that all our knowledge must conform to objects. But all attempts to extend our knowledge of objects by establishing something in regard to them a priori, by means of concepts, have, on this assumption, ended in failure. We must therefore make trial whether we may not have more success in the tasks of metaphysics, if we suppose that objects must conform to our knowledge. Just as Copernicus revolutionized astronomy by taking the position of the observer into account, Kant's critical philosophy takes into account the position of the knower of the world in general and reveals its impact on the structure of the known world. Kant's view is that in explaining the movement of celestial bodies, Copernicus rejected the idea that the movement is in the stars and accepted it as a part of the spectator. Knowledge does not depend so much on the object of knowledge as on the capacity of the knower.[16] Transcendental idealism Kant's transcendental idealism should be distinguished from idealistic systems such as that of George Berkeley. While Kant claimed that phenomena depend upon the conditions of sensibility, space and time, and on the synthesizing activity of the mind manifested in the rule-based structuring of perceptions into a world of objects, this thesis is not equivalent to mind-dependence in the sense of Berkeley's idealism. Kant defines transcendental idealism: I understand by the transcendental idealism of all appearances the doctrine that they are all together to be regarded as mere representations and not things in themselves, and accordingly that time and space are only sensible forms of our intuition, but not determinations given for themselves or conditions of objects as things in themselves. To this idealism is opposed transcendental realism, which regards space and time as something given in themselves (independent of our sensibility). — Critique of Pure Reason, A369 |
背景 初期の合理主義 カント以前は、理性の真理は分析的でなければならないと一般的に考えられていた。つまり、述語で述べられていることは、すでに主語の中に存在していなけれ ばならないということである(例えば、「知的な人間は知的である」または「知的な人間は人間である」)[8]。もしそうであれば、先験的に知ることができ るもの(例えば、「知的な人間は知的ではない」あるいは「知的な人間は人間ではない」)を否定しようとすることは矛盾を伴うことになる。したがって、矛盾 の法則はすべてのアプリオリな知識を立証するのに十分であると考えられていた[9]。 デイヴィッド・ヒュームは最初、先験的知識に関する合理主義の一般的見解を受 け入れていた。しかし、この主題を詳細に検討した結果、ヒュームは、分析的で あると考えられていたいくつかの判断、特に原因と結果に関する判断が、実際には合成的である(すなわち、主題を分析しても述語が明らかにならない)ことを 発見した。したがって、これらの判断は経験にのみ依存しており、したがって事後的である。 カントによるヒュームの経験論の否定 ヒューム以前の合理主義者たちは、結果は原因から推論できると考えていた。ヒュームはそうではないと主張し、そこから原因と結果に関して先験的に知ること ができるものは何もないと推論(主張)した。合理主義の下で育ったカントは、ヒュームの懐疑主義に深く心を痛めた。「何年も前に、私の独断的な眠りを妨げ、思弁哲 学の分野での私の研究をまったく違った方向に進ませたのは、デイヴィッド・ヒュームのことを思い出したからである」[10]。 カントはその答えを見つけることを決意し、少なくとも12年間このテーマについて考えることに費やした[11]。『純粋理性批判』は、カントが講義や教育 も行っている間に、わずか4~5ヶ月で文章化されたが、この著作はその12年間を通してのカント哲学の発展をまとめたものである[12]。 カントの仕事は、原因と結果のような基本原理に関するヒュームの懐疑的な結論を真剣に受け止めるという彼の決断によって刺激された。カントの考えでは、 ヒュームの懐疑主義は、すべての観念は感覚的経験の提示であるという前提の上に成り立っていた。ヒュームが指摘した問題は、因果関係などの基本原理は感覚 的経験のみから導き出すことができないということである。経験は、ある事象が他の事象に規則的に連続することを示すだけであって、それが他の事象によって 引き起こされることを示すのではない(→「経験論(Empiricism)」「経験論と主体性」)。 カントは『純粋理性批判』序章の第VI節(「純粋理性の一般的問題」)で、ヒュームは総合的判断が「アプリオリ」になされうると考えるに至らなかったと説 明している。カントの目標は、経験的知識に頼ることなく原因と結果を導き出す方法を見つけることであった。カントはこのために分析的方法を否定し、分析的 推論ではすでに自明でないことは何も語れないと主張する。したがって彼の目標は、合成的アプリオリがいかにして可能であるかを実証する方法を見つけること であった。 この目標を達成するために、カントは合成的推論を用いる必要があると主張した。しかし、これは新たな問題を提起した。すなわち、経験的観察に基づかない合 成的知識はどのようにして可能なのか、つまり、合成的アプリオリ真理はどのようにして可能なのか、という問題である。カントは、すべての重要な形而上学的 知識は合成的アプリオリ命題であると主張するので、この問題は非常に重要であると主張する。もし、どの構成的アプリオリ命題が真であるかを決定することが 不可能であるならば、学問としての形而上学は不可能であるとカントは主張する。純粋理性批判』の残りの部分は、構成的アプリオリ命題に関する知識が可能か どうか、またどのように可能かを検討することに費やされている。 合成的アプリオリ判断  イマヌエル・カント、ロシア将校への講義(I. ソヨッキナ/V. グラコフ、カリーニングラード、カント博物館蔵 カントは、原因と結果の関係(例えば、「...すべての結果には原因がある」)のような、主語を分析しても述語が得られないような総合的判断が存在すると 主張する。カントは、幾何学やニュートン物理学に見られるような記述は合成的判断であるとする。カントは7+5=12という古典的な例を用いる。どんなに 分析しても、7か5のどちらかに12を見出すことはできないし、その逆もできない。7は7であり、5は5であり、12は12であり、同じ原理が他の数字に も当てはまる。つまり、それらは普遍的かつ必然的なものなのである。カントにとって数学とは、先験的な総合的判断なのである。従来の推論であれば、このよ うな方程式は、7と5を一つの分析対象の一部とみなして、先験的に分析的であるとみなしただろうが、カントは、7と5を別々の値としてとらえ、7の値に5 の値を当てはめて、それらが12に等しいという論理的結論を総合的に導き出した。この結論は、カントを新たな問題へと導いた: プラトンからカントの直前の先達に至る形而上学の原理のほとんどが、世界について、あるいは神について、あるいは魂について、自明ではないが経験的観察か ら導き出すことのできない主張をしていたからである(B18-24)。カントにとって、カルテス以後の形而上学はすべてその最初から間違っている。経験主 義者は経験を超えることは不可能だと主張するから間違っているのであり、教条主義者は理論的理性によって経験を超えることが可能だと主張するから間違って いるのである。 そこでカントは、形而上学の科学が可能であるとすればどのように可能なのかという問いを投げかけながら、形而上学の科学の新しい基礎を提案する。カントに よれば、実践的理性、すなわち道徳的意識の能力、誰もが直ちに認識する道徳法則のみが、物事をあるがままに知ることを可能にする[13]。このことは、形 而上学に対する彼の最も影響力のある貢献、すなわち感覚的経験とは無関係に「それ自体」として世界を知ろうとする探求の放棄につながった。彼はこのことを 思考実験によって示し、時間の外に存在し、空間的な構成要素を持たず、実体や因果性といった理解(Verstand)の範疇に従って構造化されていない対 象を有意義に構想することは不可能であることを示した。そのような物体を考えることはできないが、そのような物体が存在しないことを示す方法はない、とカ ントは主張する。したがって、形而上学の科学は、可能な経験の限界を超えて到達しようとしてはならず、その限界のみを論じ、思考する存在としての我々自身 の理解を深めなければならないとカントは言う。なぜなら、純粋な観念から客観的存在へと直接的に前進することはできないからである[14]。 それゆえ、対象の受容性、つまり対象から影響を受ける能力は、必然的にこれらの対象に関するすべての直観に先行しなければならない。そして、超越論的想像 力(Einbildungskraft)を通じて、外見は理解の範疇に従って体系的に根拠づけられる。認識能力(Erkenntnisvermögen) の作用に焦点を当てるカントの形而上学体系は、感性(Sinnlichkeit)の形式に基づかない知識に実質的な限界を置く。このように、『批評』以前 の形而上学体系の誤りを、人間の知識能力の限界をまず考慮に入れなかったこととしている。超越論的想像力は『純粋理性批判』の第一版で記述されているが、 カントは1787年の第二版ではそれを省略している[15]。 カントが『純粋理性批判』の第二序文で、自身の批判哲学を天文学におけるコペルニクスの革命と比較しているのは、既知で知りうる世界の構造化における人々 の認識能力の役割を考慮しているからである。カント(Bxvi)はこう書いている: これまで、われわれの知識はすべて対象に適合しなければならないとされてきた。しかし、概念によって先験的に対象に関して何かを確立することによって、対 象に関する我々の知識を拡張しようとする試みはすべて、この前提のもとでは失敗に終わっている。したがって、形而上学の課題において、対象がわれわれの知 識に適合しなければならないと仮定するならば、われわれはより多くの成功を収めることができないかどうかを試さなければならない。 コペルニクスが観察者の立場を考慮に入れることによって天文学に革命をもたらしたように、カントの批判哲学は、世界を知る者の立場一般を考慮に入れ、それ が既知の世界の構造に及ぼす影響を明らかにする。カントの見解は、コペルニクスが天体の運動を説明する際に、運動が星の中にあるという考えを否定し、運動 を観者の一部として受け入れたというものである。知識は知識の対象というよりも、知る者の能力に依存する[16]。 超越論的観念論 カントの超越論的観念論は、ジョージ・バークレーのような観念論的体系とは区別されるべきである。カントは、現象は感性、空間、時間の条件と、知覚を対象 の世界へと規則に基づいて構造化することに現れる心の総合的な活動に依存していると主張しているが、このテーゼはバークレーの観念論の意味での心依存とは 等価ではない。カントは超越論的観念論を定義している: したがって、時間と空間はわれわれの直観の感覚的形態にすぎず、それ自体として与えられた決定でも、それ自体としての対象の条件でもない。この観念論に対 立するのが超越論的実在論であり、空間と時間をそれ自体として(われわれの感性とは無関係に)与えられたものとみなす。- 純粋理性批判』A369 【ノート】 ——そこから《空間はア・プリオリな人間の感覚能力》になる |
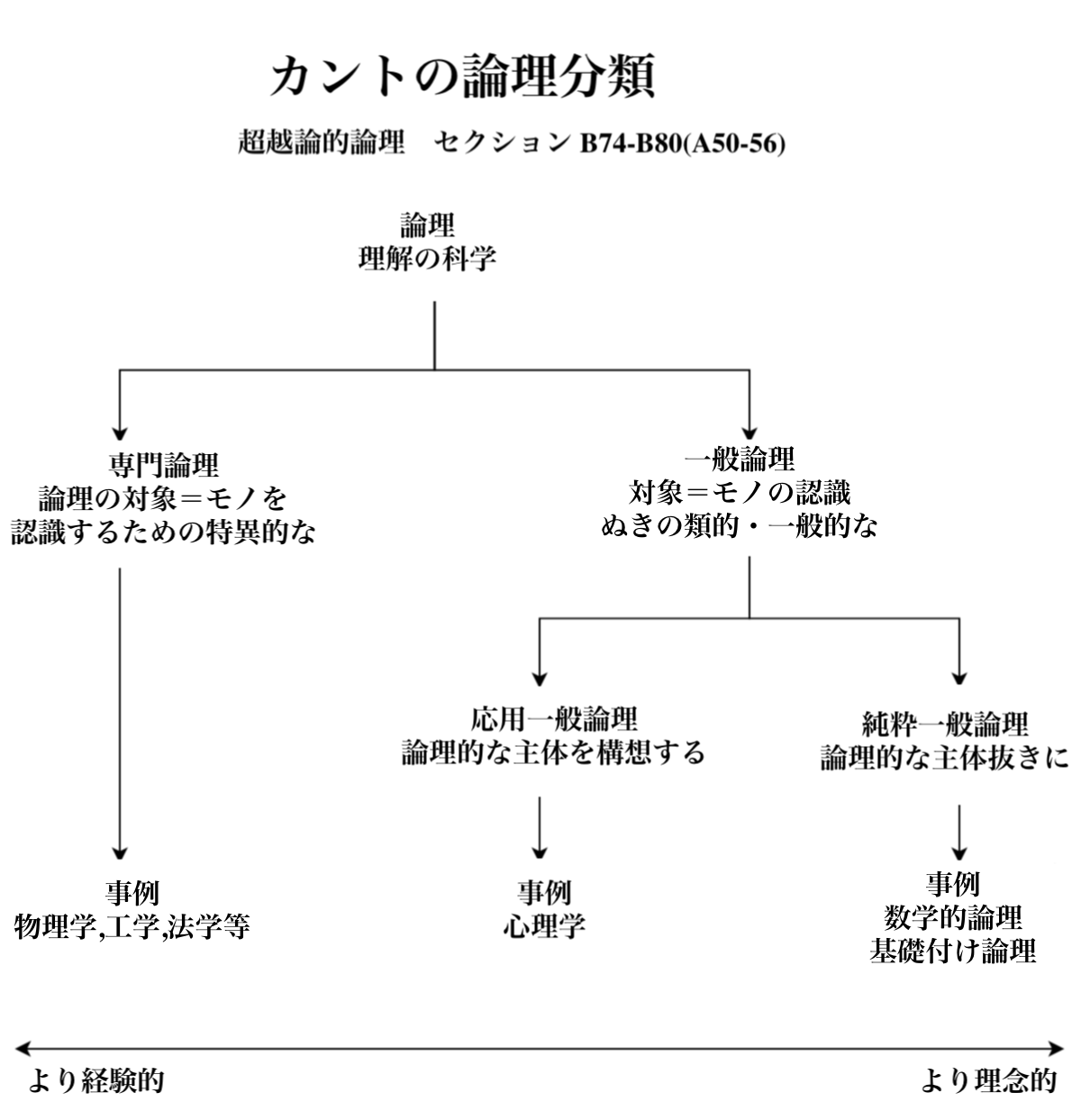 Kant's approach Kant's approachIn Kant's view, a priori intuitions and concepts provide some a priori knowledge, which also provides the framework for a posteriori knowledge. Kant also believed that causality is a conceptual organizing principle imposed upon nature, albeit nature understood as the sum of appearances that can be synthesized according to a priori concepts. In other words, space and time are a form of perceiving and causality is a form of knowing. Both space and time and conceptual principles and processes pre-structure experience. Things as they are "in themselves"—the thing in itself, or das Ding an sich—are unknowable. For something to become an object of knowledge, it must be experienced, and experience is structured by the mind—both space and time being the forms of intuition (Anschauung; for Kant, intuition is the process of sensing or the act of having a sensation)[17] or perception, and the unifying, structuring activity of concepts. These aspects of mind turn things-in-themselves into the world of experience. There is never passive observation or knowledge. According to Kant, the transcendental ego—the "Transcendental Unity of Apperception"—is similarly unknowable. Kant contrasts the transcendental ego to the empirical ego, the active individual self subject to immediate introspection. One is aware that there is an "I," a subject or self that accompanies one's experience and consciousness. Since one experiences it as it manifests itself in time, which Kant proposes is a subjective form of perception, one can know it only indirectly: as object, rather than subject. It is the empirical ego that distinguishes one person from another providing each with a definite character.[18] Contents The Critique of Pure Reason is arranged around several basic distinctions. After the two Prefaces (the A edition Preface of 1781 and the B edition Preface of 1787) and the Introduction, the book is divided into the Doctrine of Elements and the Doctrine of Method. Doctrine of Elements and of Method The Doctrine of Elements sets out the a priori products of the mind, and the correct and incorrect use of these presentations. Kant further divides the Doctrine of Elements into the Transcendental Aesthetic and the Transcendental Logic, reflecting his basic distinction between sensibility and the understanding. In the "Transcendental Aesthetic" he argues that space and time are pure forms of intuition inherent in our faculty of sense. The "Transcendental Logic" is separated into the Transcendental Analytic and the Transcendental Dialectic: The Transcendental Analytic sets forth the appropriate uses of a priori concepts, called the categories, and other principles of the understanding, as conditions of the possibility of a science of metaphysics. The section titled the "Metaphysical Deduction" considers the origin of the categories. In the "Transcendental Deduction", Kant then shows the application of the categories to experience. Next, the "Analytic of Principles" sets out arguments for the relation of the categories to metaphysical principles. This section begins with the "Schematism", which describes how the imagination can apply pure concepts to the object given in sense perception. Next are arguments relating the a priori principles with the schematized categories. The Transcendental Dialectic describes the transcendental illusion behind the misuse of these principles in attempts to apply them to realms beyond sense experience. Kant’s most significant arguments are the "Paralogisms of Pure Reason", the "Antinomy of Pure Reason", and the "Ideal of Pure Reason", aimed against, respectively, traditional theories of the soul, the universe as a whole, and the existence of God. In the Appendix to the "Critique of Speculative Theology" Kant describes the role of the transcendental ideas of reason. The Doctrine of Method contains four sections. The first section, "Discipline of Pure Reason", compares mathematical and logical methods of proof, and the second section, "Canon of Pure Reason", distinguishes theoretical from practical reason. The divisions of the Critique of Pure Reason Dedication 1. First and second Prefaces 2. Introduction 3. Transcendental Doctrine of Elements A. Transcendental Aesthetic (1) On space (2) On time B. Transcendental Logic (1) Transcendental Analytic a. Analytic of Concepts i. Metaphysical Deduction ii. Transcendental Deduction b. Analytic of Principles i. Schematism (bridging chapter) ii. System of Principles of Pure Understanding a. Axioms of Intuition b. Anticipations of Perception c. Analogies of Experience d. Postulates of Empirical Thought (Refutation of Idealism) iii. Ground of Distinction of Objects into Phenomena and Noumena iv. Appendix on the Amphiboly of the Concepts of Reflection (2) Transcendental Dialectic: Transcendental Illusion a. Paralogisms of Pure Reason b. Antinomy of Pure Reason c. Ideal of Pure Reason d. Appendix to Critique of Speculative Theology 4. Transcendental Doctrine of Method A. Discipline of Pure Reason B. Canon of Pure Reason C. Architectonic of Pure Reason D. History of Pure Reason 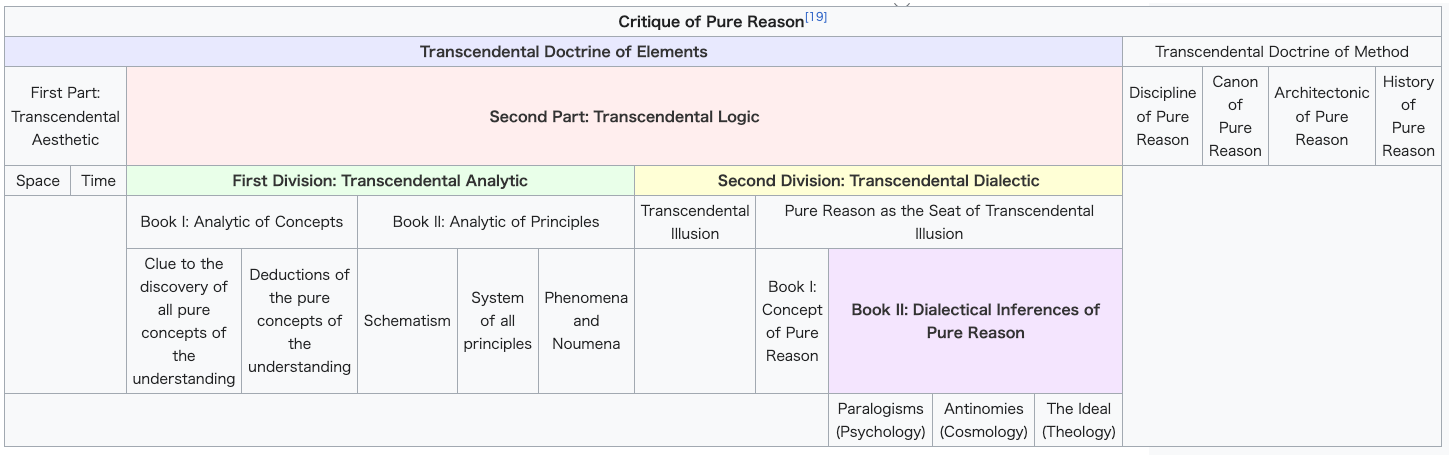 |
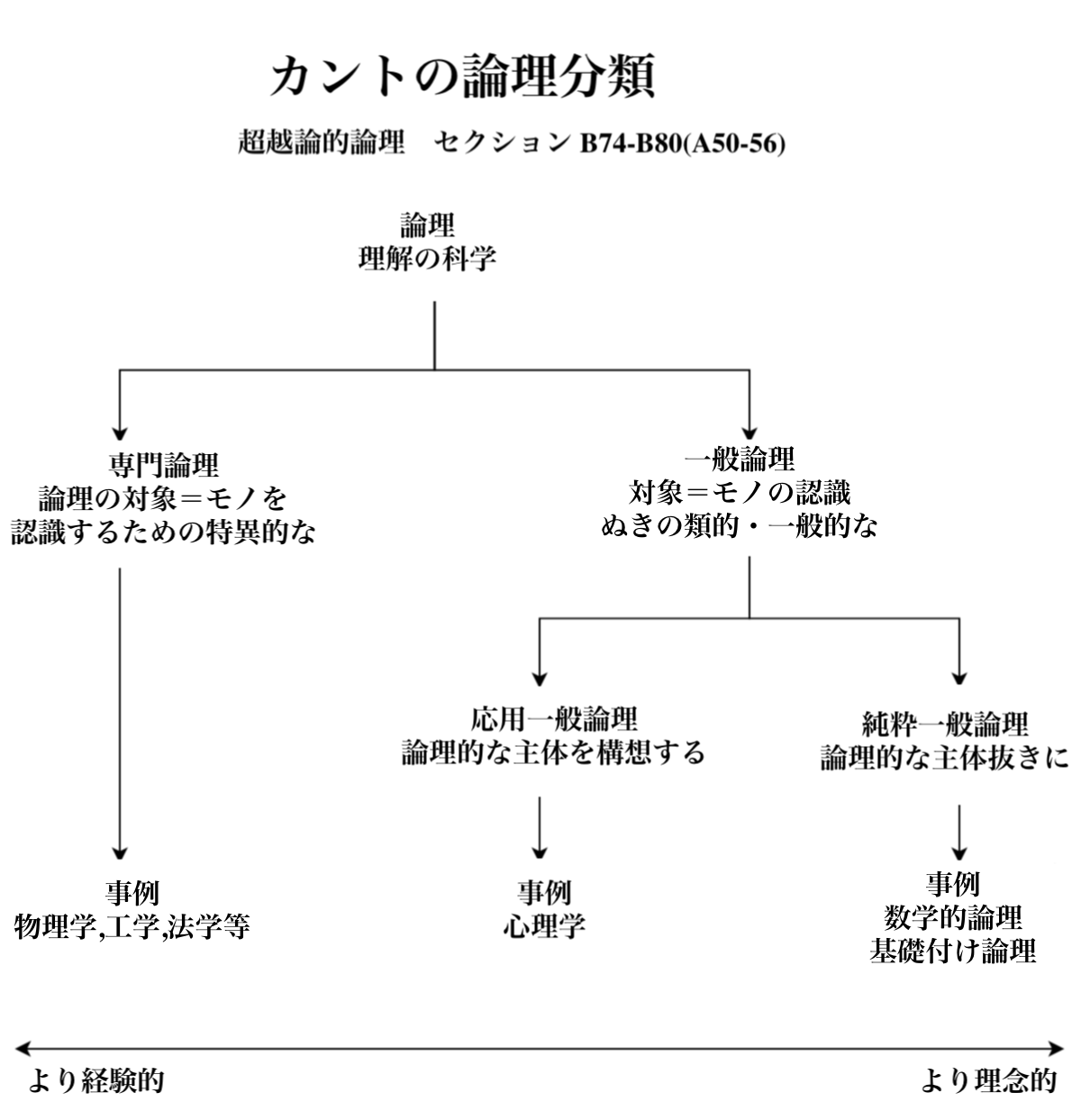 カントのアプローチ カントのアプローチカントの考えでは、先験的直観と概念は先験的知識を提供し、それはまた後験的知識の枠組みを提供する。カントはまた、因果性は自然に課せられた概念的な組 織原理であり、自然は先験的な概念に従って総合される出現の総体として理解されると考えた。 言い換えれば、空間と時間は知覚の一形態であり、因果性は知ることの一形態である。空間と時間、そして概念的な原理とプロセスの両方が、経験をあらかじめ 構造化している。それ自体」であるもの、すなわち「それ自体におけるもの」(das Ding an sich)は、知ることができない。何かが知識の対象となるためには、それは経験されなければならず、経験は心によって構造化される-空間と時間の両方が 直観(Anschauung;カントにとって直観とは、感覚するプロセス、あるいは感覚を持つ行為のこと)[17]や知覚の形態であり、概念の統一的、構 造化的な活動である。心のこれらの側面は、物事それ自体を経験の世界に変える。受動的な観察や知識は決して存在しない。 カントによれば、超越論的自我-「知覚の超越論的統一」-も同様に知ることができない。カントは超越論的自我を経験的自我、即座の内省に従う能動的な個人 的自我と対比している。人は「私」、つまり自分の経験と意識に付随する主体や自己が存在することを自覚している。カントが提唱する主観的な知覚形態である 「時間」に現れる「私」を経験することで、人は「私」を間接的にしか知ることができない。経験的自我は、ある人を別の人から区別し、それぞれに明確な性格 を与えるものである[18]。 内容 純粋理性批判』はいくつかの基本的な区別を中心に構成されている。2つの序文(1781年のA版序文と1787年のB版序文)と序論の後、本書は「要素の 教義」と「方法の教義」に分かれている。 元素の教義と方法の教義 要素の教義は、心のアプリオリな産物、およびこれらの提示の正しい使用と誤った使用を定めている。カントはさらに、「要素の教義」を「超越論的美学(感性論)」と 「超越論的論理学」に分け、感性と理解との基本的な区別を反映している。超越論的美学(感性論)」では、空間と時間は人間の感覚能力に内在する純粋な直観の形式であ ると主張する。超越論的論理学」は、超越論的分析学と超越論的弁証法に分かれている: 「超越論的分析」は、形而上学の科学の可能性の条件として、カテゴリーと呼ばれるアプリオリな概念と、理解の他の原理の適切な使用法を示している。形而上学 的演繹」と題されたセクションでは、カテゴリーの起源について考察している。次に「超越論的演繹」では、カントは経験へのカテゴリーの適用を示す。次に、 「原理の分析」では、カテゴリーの形而上学的原理への関係についての議論を示す。この節は「図式論」で始まり、想像力(→構想力)が純粋概念を感覚知覚で与えられる対 象にどのように適用できるかを説明する。次に、先験的原理と図式化されたカテゴリーとの関係を論証する。 「超越論的弁証法」は、感覚経験を超えた領域にこれらの原理を適用しようとする試みの誤用の背後にある超越論的錯覚(イリュージョン)について述べている。カントの最も重要な 主張は、「純粋理性のパラロギス」、「純粋理性のアンチノミー」、「純粋理性のイデア」であり、それぞれ魂、宇宙全体、神の存在に関する伝統的な理論に対 するものである。思弁的神学批判」の付録では、カントは理性の超越論的観念の役割について述べている。 方法の教義』には4つのセクションがある。第1部「純粋理性の規律」では、数学的証明方法と論理的証明方法を比較し、第2部「純粋理性の公準」では、理論 的理性と実践的理性を区別する。 純粋理性批判の区分 献辞 第一序文と第二序文 序論 I. 超越論的原理論 第一部門. 超越論的感性論(感性論は美学と同じ用語) (1) 空間について (2) 時間について 第二部門 超越論的論理学 (1) 超越論的分析論 (2) 超越論的弁証法 II 超越論的方法論 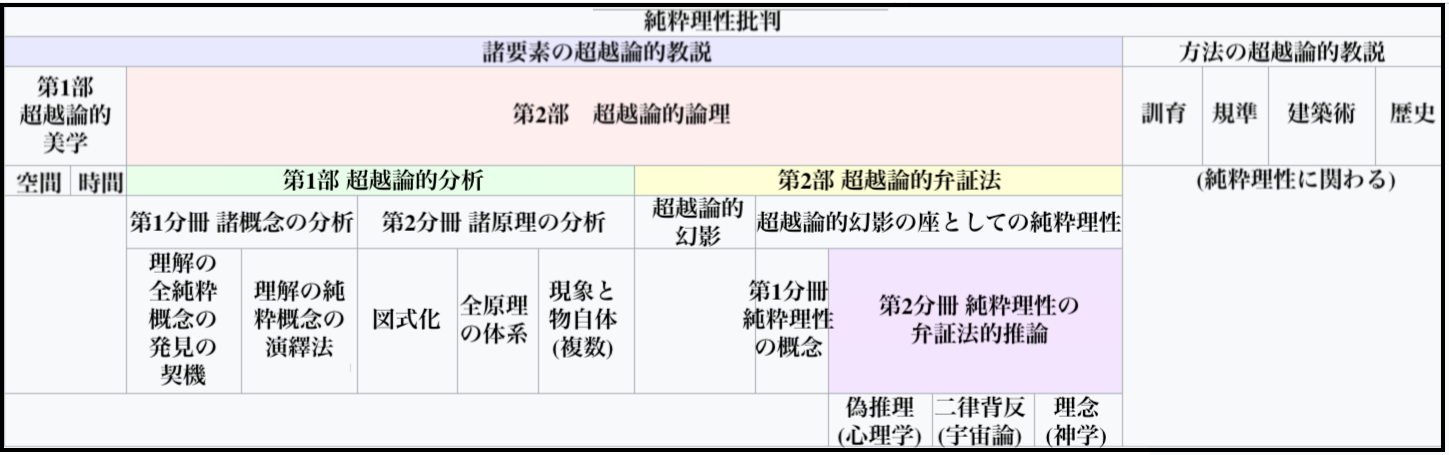 The divisions of the Critique of Pure Reason Dedication 1. First and second Prefaces 2. Introduction 3. Transcendental Doctrine of Elements A. Transcendental Aesthetic (1) On space (2) On time B. Transcendental Logic (1) Transcendental Analytic a. Analytic of Concepts i. Metaphysical Deduction ii. Transcendental Deduction b. Analytic of Principles i. Schematism (bridging chapter) ii. System of Principles of Pure Understanding a. Axioms of Intuition b. Anticipations of Perception c. Analogies of Experience d. Postulates of Empirical Thought (Refutation of Idealism) iii. Ground of Distinction of Objects into Phenomena and Noumena iv. Appendix on the Amphiboly of the Concepts of Reflection (2) Transcendental Dialectic: Transcendental Illusion a. Paralogisms of Pure Reason b. Antinomy of Pure Reason c. Ideal of Pure Reason d. Appendix to Critique of Speculative Theology 4. Transcendental Doctrine of Method A. Discipline of Pure Reason B. Canon of Pure Reason C. Architectonic of Pure Reason D. History of Pure Reason |
| I. Transcendental Doctrine of
Elements Transcendental Aesthetic The Transcendental Aesthetic, as the Critique notes, deals with "all principles of a priori sensibility."[20] As a further delimitation, it "constitutes the first part of the transcendental doctrine of elements, in contrast to that which contains the principles of pure thinking, and is named transcendental logic".[20] In it, what is aimed at is "pure intuition and the mere form of appearances, which is the only thing that sensibility can make available a priori."[21] It is thus an analytic of the a priori constitution of sensibility; through which "Objects are therefore given to us…, and it alone affords us intuitions."[22] This in itself is an explication of the "pure form of sensible intuitions in general [that] is to be encountered in the mind a priori."[23] Thus, pure form or intuition is the a priori "wherein all of the manifold of appearances is intuited in certain relations."[23] from this, "a science of all principles of a priori sensibility [is called] the transcendental aesthetic."[20] The above stems from the fact that "there are two stems of human cognition…namely sensibility and understanding."[24] This division, as the critique notes, comes "closer to the language and the sense of the ancients, among whom the division of cognition into αισθητα και νοητα is very well known."[25] An exposition on a priori intuitions is an analysis of the intentional constitution of sensibility. Since this lies a priori in the mind prior to actual object relation; "The transcendental doctrine of the senses will have to belong to the first part of the science of elements, since the conditions under which alone the objects of human cognition are given precede those under which those objects are thought".[26] Kant distinguishes between the matter and the form of appearances. The matter is "that in the appearance that corresponds to sensation" (A20/B34). The form is "that which so determines the manifold of appearance that it allows of being ordered in certain relations" (A20/B34). Kant's revolutionary claim is that the form of appearances—which he later identifies as space and time—is a contribution made by the faculty of sensation to cognition, rather than something that exists independently of the mind. This is the thrust of Kant's doctrine of the transcendental ideality of space and time. Kant's arguments for this conclusion are widely debated among Kant scholars. Some see the argument as based on Kant's conclusions that our representation (Vorstellung) of space and time is an a priori intuition. From here Kant is thought to argue that our representation of space and time as a priori intuitions entails that space and time are transcendentally ideal. It is undeniable from Kant's point of view that in Transcendental Philosophy, the difference of things as they appear and things as they are is a major philosophical discovery.[27] Others see the argument as based upon the question of whether synthetic a priori judgments are possible. Kant is taken to argue that the only way synthetic a priori judgments, such as those made in geometry, are possible is if space is transcendentally ideal. In Section I (Of Space) of Transcendental Aesthetic in the Critique of Pure Reason Kant poses the following questions: What then are time and space? Are they real existences? Or, are they merely relations or determinations of things, such, however, as would equally belong to these things in themselves, though they should never become objects of intuition; or, are they such as belong only to the form of intuition, and consequently to the subjective constitution of the mind, without which these predicates of time and space could not be attached to any object?[28] The answer that space and time are real existences belongs to Newton. The answer that space and time are relations or determinations of things even when they are not being sensed belongs to Leibniz. Both answers maintain that space and time exist independently of the subject's awareness. This is exactly what Kant denies in his answer that space and time belong to the subjective constitution of the mind.[29]: 87–88 Space and time Kant gives two expositions of space and time: metaphysical and transcendental. The metaphysical expositions of space and time are concerned with clarifying how those intuitions are known independently of experience. The transcendental expositions attempt to show how the metaphysical conclusions might be applied to enrich our understanding. In the transcendental exposition, Kant refers back to his metaphysical exposition in order to show that the sciences would be impossible if space and time were not kinds of pure a priori intuitions. He asks the reader to take the proposition, "two straight lines can neither contain any space nor, consequently, form a figure," and then to try to derive this proposition from the concepts of a straight line and the number two. He concludes that it is simply impossible (A47-48/B65). Thus, since this information cannot be obtained from analytic reasoning, it must be obtained through synthetic reasoning, i.e., a synthesis of concepts (in this case two and straightness) with the pure (a priori) intuition of space. In this case, however, it was not experience that furnished the third term; otherwise, the necessary and universal character of geometry would be lost. Only space, which is a pure a priori form of intuition, can make this synthetic judgment, thus it must then be a priori. If geometry does not serve this pure a priori intuition, it is empirical, and would be an experimental science, but geometry does not proceed by measurements—it proceeds by demonstrations. Kant rests his demonstration of the priority of space on the example of geometry. He reasons that therefore if something exists, it needs to be intelligible. If someone attacked this argument, he would doubt the universality of geometry (which Kant believes no honest person would do). The other part of the Transcendental Aesthetic argues that time is a pure a priori intuition that renders mathematics possible. Time is not a concept, since otherwise it would merely conform to formal logical analysis (and therefore, to the principle of non-contradiction). However, time makes it possible to deviate from the principle of non-contradiction: indeed, it is possible to say that A and non-A are in the same spatial location if one considers them in different times, and a sufficient alteration between states were to occur (A32/B48). Time and space cannot thus be regarded as existing in themselves. They are a priori forms of sensible intuition. The current interpretation of Kant states that the subject inherently possesses the underlying conditions to perceive spatial and temporal presentations. The Kantian thesis claims that in order for the subject to have any experience at all, then it must be bounded by these forms of presentations (Vorstellung). Some scholars have offered this position as an example of psychological nativism, as a rebuke to some aspects of classical empiricism. Kant's thesis concerning the transcendental ideality of space and time limits appearances to the forms of sensibility—indeed, they form the limits within which these appearances can count as sensible; and it necessarily implies that the thing-in-itself is neither limited by them nor can it take the form of an appearance within us apart from the bounds of sensibility (A48-49/B66). Yet the thing-in-itself is held by Kant to be the cause of that which appears, and this is where an apparent paradox of Kantian critique resides: while we are prohibited from absolute knowledge of the thing-in-itself, we can impute to it a cause beyond ourselves as a source of representations within us. Kant's view of space and time rejects both the space and time of Aristotelian physics and the space and time of Newtonian physics. |
I. 要素の超越論的教義 超越論的美学(感性論) 超越論的美学(感性論)は、『批判』が指摘するように、「先験的な感性のすべての原理」[20]を扱うものである。さらなる区切りとして、それは「純粋思考の原理を 含み、超越論的論理学と名づけられたそれとは対照的に、要素に関する超越論的教義の最初の部分を構成する」[20]。 [20]その中で目指されているのは、「純粋な直観と、出現の単なる形式であり、それは感性がアプリオリに利用できる唯一のものである」[21]。した がって、それは感性のアプリオリな構成の分析であり、それを通じて「対象はそれゆえわれわれに与えられ...それだけがわれわれに直観を与える」のであ る。 このこと自体が、「一般に、(先験的に)心において遭遇する感覚的直観の純粋形式」[23]の説明なのである。したがって、純粋形式あるいは直観とは、先 験的なものであり、「そこでは、出現の多様性のすべてが一定の関係において直観される」のである。 「このことから、「先験的な感性のすべての原理の科学は超越論的な美学(感性論)と呼ばれる」[20]。上記は、「人間の認識には、感性と理解という二つの系統があ る」[24]という事実から生じている。 この区分は、批評が指摘するように、「認識のαισθητα και νοηταへの区分が非常によく知られている古代人の言語と感覚に近い」[25]。なぜなら、人間の認識の対象だけが与えられる条件は、それらの対象が思 考される条件に先立つからである」[26]。 カントは出現の物質と形式を区別している。物質とは「感覚に対応する外見上のもの」(A20/B34)である。形とは、「ある関係において秩序づけられる ことを可能にするように、外観の多様体を決定するもの」である(A20/B34)。カントの画期的な主張は、出現の形式は、後に彼が空間と時間と特定する ものであり、心とは無関係に存在するものではなく、むしろ感覚という能力が認識に寄与するものであるということである。これが、空間と時間の超越論的イデ ア性というカントの教義の核心である。 この結論に対するカントの議論は、カント研究者の間で広く議論されている。ある者は、空間と時間の表象(Vorstellung)はアプリオリな直観であ るというカントの結論に基づく議論だと考える。ここからカントは、先験的直観としての空間と時間の表象は、空間と時間が超越的に理想的であることを含意し ていると主張すると考えられる。カントからすれば、超越論的哲学において、「見えるもの」と「あるもの」の差異が哲学上の大発見であることは否定できない [27]。カントは、幾何学でなされるような合成的な先験的判断が可能である唯一の方法は、空間が超越的に理想的である場合であると主張している。 純粋理性批判の超越論的美学(感性論)の第I節(空間について)で、カントは次のような問いを立てている: では、時間と空間とは何なのか?それらは実在するのか?それとも、時間と空間という述語がいかなる対象にも付されることなしに、時間と空間という述語がい かなる対象にも付されることができないような、直観の形式、ひいては心の主観的な構造にのみ属するものなのか?空間と時間は、それが知覚されていないとき でさえも、事物の関係あるいは決定であるという答えは、ライプニッツのものである。どちらの答えも、空間と時間は主体の認識とは無関係に存在すると主張し ている。これはまさに、空間と時間は心の主観的な構成に属するというカントの答えで否定されていることである[29]: 87-88 空間と時間 カントは空間と時間について、形而上学的な説明と超越論的な説明という二つの説明を与えている。空間と時間に関する形而上学的な説明は、それらの直観が経 験とは無関係にどのように知られるかを明らかにすることに関心がある。超越論的な説明では、形而上学的な結論をどのように応用すれば我々の理解を豊かにで きるかを示そうとする。 超越論的説明においてカントは、もし空間と時間が純粋な先験的直観の一種でなければ、諸科学は不可能であることを示すために、形而上学的説明に言及する。 カントは読者に、「2つの直線は空間を含まず、その結果図形を形成することもできない」という命題を取り上げ、直線と数字の2の概念からこの命題を導こう とする。彼は単純に不可能であると結論づける(A47-48/B65)。したがって、この情報は分析的推論からは得られないので、合成的推論、すなわち空 間に関する純粋な(アプリオリな)直観と概念(この場合は2と直線)の合成によって得なければならない。 しかし、この場合、第3項を与えるのは経験ではない。そうでなければ、幾何学の必要かつ普遍的な特徴が失われてしまうからである。純粋なアプリオリな直観 である空間だけが、この合成的判断を下すことができる。もし幾何学がこの純粋なアプリオリな直観を提供しないならば、それは経験的なものであり、実験科学 となる。 カントは、幾何学の例に基づいて空間の優先性を証明する。したがって、もし何かが存在するならば、それは理解可能でなければならない。もし誰かがこの議論 を攻撃すれば、その人は幾何学の普遍性を疑うことになる(正直な人はそんなことはしないとカントは考えている)。 超越論的美学(感性論)』のもう一つの部分は、時間とは数学を可能にする純粋な先験的直観であると主張する。時間は概念ではない。そうでなければ、形式的な論理分析 (したがって、無矛盾の原理)に従うだけだからである。しかし、時間は無矛盾の原理から逸脱することを可能にする。実際、Aと非Aを異なる時間に考えた場 合、Aは同じ空間的位置にあり、状態の間に十分な変化が起こると言うことが可能である(A32/B48)。このように、時間と空間はそれ自体で存在するも のとは見なされない。それらは感覚的直観のアプリオリな形態である。 現在のカント解釈は、主体は空間的・時間的提示を知覚するための基礎的条件を本来的に持っているとする。カントのテーゼは、主体が何らかの経験をするため には、これらの提示形態(Vorstellung)に束縛されなければならないと主張する。一部の学者は、この立場を心理学的ネイティビズムの一例とし て、古典的経験主義のいくつかの側面に対する反撃として提示した。 空間と時間の超越論的イデア性に関するカントのテーゼは、出現を感性の形式に限定している-実際、それらは、これらの出現が感性的なものとして数えられる 限界を形成しているのである。しかし、カントによって「自我に内在するもの」は、出現するものの原因であるとされ、ここにカント批判の明白な逆説が存在す る。カントの空間と時間についての見解は、アリストテレス物理学の空間と時間とニュートン物理学の空間と時間の両方を否定している。 |
Transcendental Logic Outline of Kant's division of the science of logic into special logic, general logic, and the pure and applied forms of general logic. In the Transcendental Logic, there is a section (titled The Refutation of Idealism) that is intended to free Kant's doctrine from any vestiges of subjective idealism, which would either doubt or deny the existence of external objects (B274-79).[30] Kant's distinction between the appearance and the thing-in-itself is not intended to imply that nothing knowable exists apart from consciousness, as with subjective idealism. Rather, it declares that knowledge is limited to phenomena as objects of a sensible intuition. In the Fourth Paralogism ("... A Paralogism is a logical fallacy"),[31] Kant further certifies his philosophy as separate from that of subjective idealism by defining his position as a transcendental idealism in accord with empirical realism (A366–80), a form of direct realism.[32][a] "The Paralogisms of Pure Reason" is the only chapter of the Dialectic that Kant rewrote for the second edition of the Critique of Pure Reason. In the first edition, the Fourth Paralogism offers a defence of transcendental idealism, which Kant reconsidered and relocated in the second edition.[35] Whereas the Transcendental Aesthetic was concerned with the role of the sensibility, the Transcendental Logic is concerned with the role of the understanding, which Kant defines as the faculty of the mind that deals with concepts.[36] Knowledge, Kant argued, contains two components: intuitions, through which an object is given to us in sensibility, and concepts, through which an object is thought in understanding. In the Transcendental Aesthetic, he attempted to show that the a priori forms of intuition were space and time, and that these forms were the conditions of all possible intuition. It should therefore be expected that we should find similar a priori concepts in the understanding, and that these pure concepts should be the conditions of all possible thought. The Logic is divided into two parts: the Transcendental Analytic and the Transcendental Dialectic. The Analytic Kant calls a "logic of truth";[37] in it he aims to discover these pure concepts which are the conditions of all thought, and are thus what makes knowledge possible. The Transcendental Dialectic Kant calls a "logic of illusion";[38] in it he aims to expose the illusions that we create when we attempt to apply reason beyond the limits of experience. The idea of a transcendental logic is that of a logic that gives an account of the origins of our knowledge as well as its relationship to objects. Kant contrasts this with the idea of a general logic, which abstracts from the conditions under which our knowledge is acquired, and from any relation that knowledge has to objects. According to Helge Svare, "It is important to keep in mind what Kant says here about logic in general, and transcendental logic in particular, being the product of abstraction, so that we are not misled when a few pages later he emphasizes the pure, non-empirical character of the transcendental concepts or the categories."[39] Kant's investigations in the Transcendental Logic lead him to conclude that the understanding and reason can only legitimately be applied to things as they appear phenomenally to us in experience. What things are in themselves as being noumenal, independent of our cognition, remains limited by what is known through phenomenal experience. First Division: Transcendental Analytic The Transcendental Analytic is divided into an Analytic of Concepts and an Analytic of Principles, as well as a third section concerned with the distinction between phenomena and noumena. In Chapter III (Of the ground of the division of all objects into phenomena and noumena) of the Transcendental Analytic, Kant generalizes the implications of the Analytic in regard to transcendent objects preparing the way for the explanation in the Transcendental Dialectic about thoughts of transcendent objects, Kant's detailed theory of the content (Inhalt) and origin of our thoughts about specific transcendent objects.[29]: 198–199 The main sections of the Analytic of Concepts are The Metaphysical Deduction and The Transcendental Deduction of the Categories. The main sections of the Analytic of Principles are the Schematism, Axioms of Intuition, Anticipations of Perception, Analogies of Experience, Postulates and follow the same recurring tabular form: 1. Quantity 2. Quality 3. Relation 4. Modality In the 2nd edition, these sections are followed by a section titled the Refutation of Idealism. The metaphysical deduction In the Metaphysical Deduction, Kant aims to derive twelve pure concepts of the understanding (which he calls "categories") from the logical forms of judgment. In the following section, he will go on to argue that these categories are conditions of all thought in general. Kant arranges the forms of judgment in a table of judgments, which he uses to guide the derivation of the table of categories.[40] The role of the understanding is to make judgments. In judgment, the understanding employs concepts which apply to the intuitions given to us in sensibility. Judgments can take different logical forms, with each form combining concepts in different ways. Kant claims that if we can identify all of the possible logical forms of judgment, this will serve as a "clue" to the discovery of the most basic and general concepts that are employed in making such judgments, and thus that are employed in all thought.[40] Logicians prior to Kant had concerned themselves to classify the various possible logical forms of judgment. Kant, with only minor modifications, accepts and adopts their work as correct and complete, and lays out all the logical forms of judgment in a table, reduced under four heads: 1. Quantity of Judgments 2. Quality 3. Relation 4. Modality Under each head, there corresponds three logical forms of judgment:[41] 1. Quantity of Judgments Universal Particular Singular 2. Quality Affirmative Negative Infinite 3. Relation Categorical Hypothetical Disjunctive 4. Modality Problematic Assertoric Apodeictic This Aristotelian method for classifying judgments is the basis for his own twelve corresponding concepts of the understanding. In deriving these concepts, he reasons roughly as follows. If we are to possess pure concepts of the understanding, they must relate to the logical forms of judgment. However, if these pure concepts are to be applied to intuition, they must have content. But the logical forms of judgment are by themselves abstract and contentless. Therefore, to determine the pure concepts of the understanding we must identify concepts which both correspond to the logical forms of judgment, and are able to play a role in organising intuition. Kant therefore attempts to extract from each of the logical forms of judgment a concept which relates to intuition. For example, corresponding to the logical form of hypothetical judgment ('If p, then q'), there corresponds the category of causality ('If one event, then another'). Kant calls these pure concepts 'categories', echoing the Aristotelian notion of a category as a concept which is not derived from any more general concept. He follows a similar method for the other eleven categories, then represents them in the following table:[42] 1. Categories of Quantity Unity Plurality Totality 2. Categories of Quality Reality Negation Limitation 3. Categories of Relation Inherence and Subsistence (substance and accident) Causality and Dependence (cause and effect) Community (reciprocity between agent and patient) 4. Categories of Modality Possibility—Impossibility Existence—Non-existence Necessity—Contingency These categories, then, are the fundamental, primary, or native concepts of the understanding. These flow from, or constitute the mechanism of understanding and its nature, and are inseparable from its activity. Therefore, for human thought, they are universal and necessary, or a priori. As categories they are not contingent states or images of sensuous consciousness, and hence not to be thence derived. Similarly, they are not known to us independently of such consciousness or of sensible experience. On the one hand, they are exclusively involved in, and hence come to our knowledge exclusively through, the spontaneous activity of the understanding. This understanding is never active, however, until sensible data are furnished as material for it to act upon, and so it may truly be said that they become known to us "only on the occasion of sensible experience". For Kant, in opposition to Christian Wolff and Thomas Hobbes, the categories exist only in the mind.[43] These categories are "pure" conceptions of the understanding, in as much as they are independent of all that is contingent in sense. They are not derived from what is called the matter of sense, or from particular, variable sensations. However, they are not independent of the universal and necessary form of sense. Again, Kant, in the "Transcendental Logic", is professedly engaged with the search for an answer to the second main question of the Critique: How is pure physical science, or sensible knowledge, possible? Kant, now, has said, and, with reference to the kind of knowledge mentioned in the foregoing question, has said truly, that thoughts, without the content which perception supplies, are empty. This is not less true of pure thoughts, than of any others. The content which the pure conceptions, as categories of pure physical science or sensible knowledge, cannot derive from the matter of sense, they must and do derive from its pure form. And in this relation between the pure conceptions of the understanding and their pure content there is involved, as we shall see, the most intimate community of nature and origin between sense, on its formal side (space and time), and the understanding itself. For Kant, space and time are a priori intuitions. Out of a total of six arguments in favor of space as a priori intuition, Kant presents four of them in the Metaphysical Exposition of space: two argue for space a priori and two for space as intuition.[29]: 75 |
超越論的論理学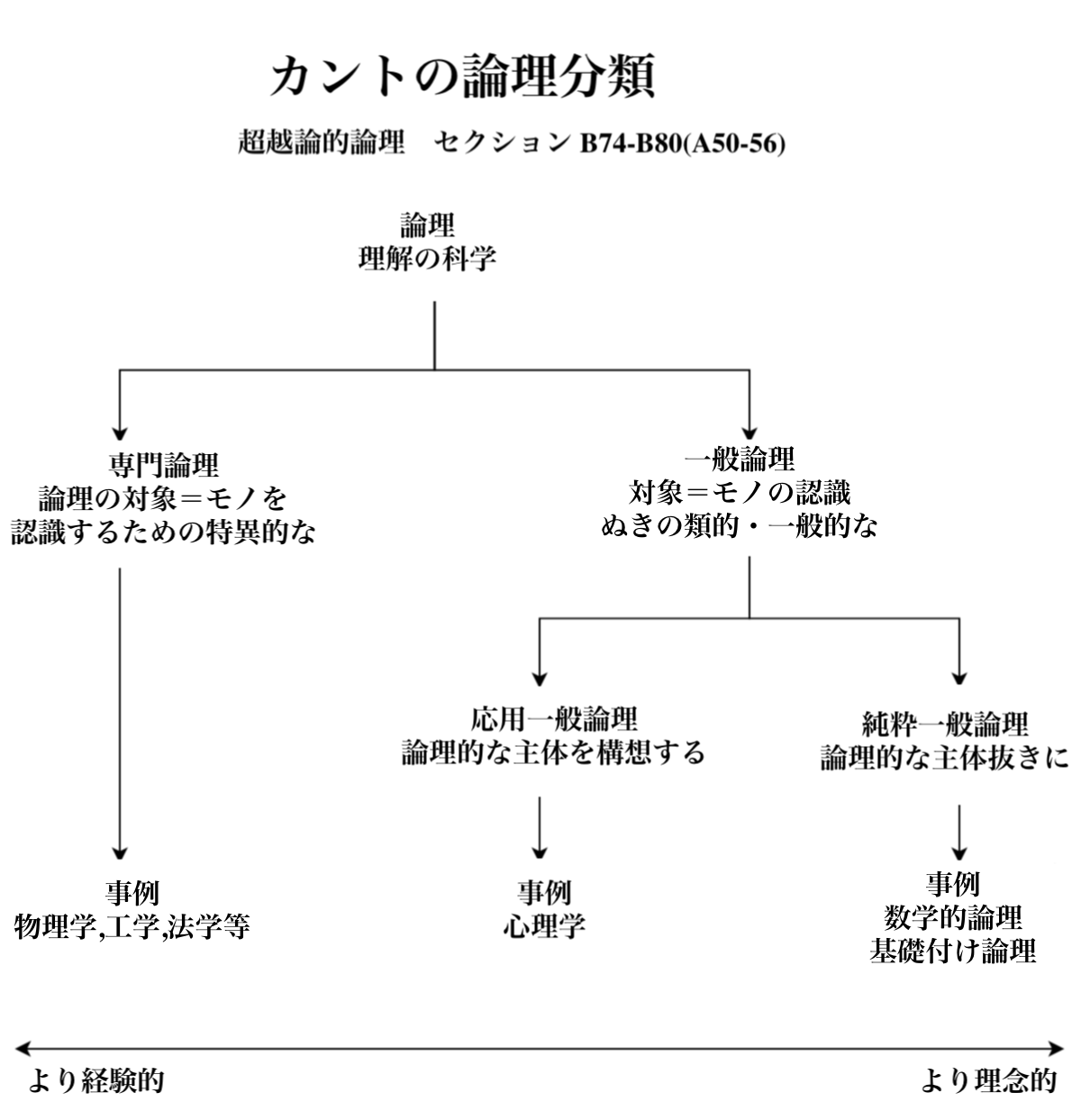 カントが論理学を特殊論理学、一般論理学、一般論理学の純粋形式と応用形式に分けた概要。 『超越論的論理学』には、外的対象の存在を疑ったり否定したりする主観的観念論の名残からカントの教義を解放することを意図した部分(『観念論の反駁』と い うタイトル)がある(B274-79)[30]。むしろ、知識は感覚的直観の対象としての現象に限定されると宣言しているのである。第四のパラロギズム (「...パラロギズムは論理的誤謬である」)において[31]、カントは自らの立場を直接実在論の一形態である経験的実在論(A366-80)と一致す る超越論的観念論として定義することによって、主観的観念論とは別個の哲学であることをさらに証明する[32][a]。第一版では、第四パラロギズムは超 越論的観念論の擁護を提示していたが、第二版ではカントが再考し、再配置した[35]。 『超越論的美学(感性論)』が感性の役割に関心を寄せていたのに対して、『超越論的論理学』は理解(カントは概念を扱う心の能力として定義している)の役割に関心を 寄 せている。超越論的美学(感性論)』において、彼は直観のアプリオリな形式が空間と時間であり、これらの形式がすべての可能な直観の条件であることを示そうとした。 したがって、理解においても同様のアプリオリな概念が見出されるはずであり、これらの純粋概念があらゆる可能な思考の条件となるはずである。論理学は超越 論的分析学と超越論的弁証法の二つの部分に分かれている。分析論においてカントは「真理の論理」[37]と呼び、すべての思考の条件であり、したがって知 識を可能にするものであるこれらの純粋概念を発見することを目指している。超越論的弁証法カントは「幻想の論理」[38]と呼び、その中で彼は、経験の限 界を超えて理性を適用しようとするときにわれわれが作り出す幻想を暴くことを目指している。 超越論的論理学の考え方は、我々の知識の起源と対象との関係について説明する論理学である。カントはこれを、私たちの知識が獲得される条件や、知識と対象 との関係から抽象化する一般論理の考え方と対比している。ヘルゲ・スヴァーレによれば、「一般的な論理学、特に超越論的論理学が抽象の産物であることにつ いてカントがここで述べていることを心に留めておくことは、数ページ後にカントが超越論的概念やカテゴリーの純粋で非経験的な性格を強調しているときに誤 解されないために重要である」[39]。 カントは『超越論的論理学』における研究によって、理解や理性は、経験において私たちに現象的に現れる事物に対してのみ正当に適用することができるという 結論に達する。物事がそれ自体としてどのようなものであるかは、私たちの認識とは無関係に、現象的経験を通じて知られるものによって制限されたままであ る。 第一部門 超越論的分析 超越論的分析』は、「概念の分析」と「原理の分析」に分けられ、さらに現象とヌーメナの区別に関する第三章がある。超越論的分析』の第三章(すべての対象 が現象とヌーメナに分割される根拠について)において、カントは超越的対象に関する『分析』の含意を一般化し、『超越論的弁証法』における超越的対象の思 考についての説明、すなわち特定の超越的対象についての思考の内容(Inhalt)と起源についてのカントの詳細な理論への道を準備する[29]: 198-199 『概念の分析』の主要な部分は、『形而上学的演繹』と『範疇の超越論的演繹』である。原理の分析」の主なセクションは、「図式論」、「直観の公理」、「知 覚の予期」、「経験の類推」、「定言」であり、同じ表形式が繰り返される: 1. 量 2. 質3. 関係 4. モダリティ 第2版では、これらの節に続いて「観念論の反駁」という節が設けられている。 形而上学的演繹 形而上学的演繹において、カントは判断の論理形式から12の純粋な理解概念(彼はこれを「カテゴリー」と呼ぶ)を導き出すことを目的とする。次の節では、 これらのカテゴリーがすべての思考一般の条件であることを論証する。カントは判断の形式を判断の表に整理し、それをカテゴリーの表の導出のために用いる [40]。 理解の役割は判断を下すことである。判断において、理解は、感性においてわれわれに与えられた直観に適用される概念を用いる。判断はさまざまな論理形式を とることができ、それぞれの形式はさまざまな方法で概念を組み合わせる。カントは、判断の可能な論理的形式をすべて特定することができれば、そのような判 断をする際に用いられる、したがってすべての思考において用いられる、最も基本的で一般的な概念を発見する「手がかり」になると主張している[40]。カ ント以前の論理学者たちは、さまざまな可能性のある論理的判断形式を分類することに関心を持っていた。カントは、わずかな修正を加えただけで、彼らの研究 を正しく完全なものとして受け入れ、採用し、すべての論理的判断形式を4つの見出しの下に縮小した表に整理した: 1. 判断の量 2. 判断の質 3. 関係 4. モダリティ 各ヘッドの下には、以下の3つの論理的な判断形式が対応する[41]。 1. 量的判断 普遍的 特殊 特異的 2. 質 肯定的 否定 無限 3. 関係 カテゴリー 仮説的 分離的 4. モダリティ 問題的 断定的 アポディクティック このようなアリストテレス流の判断の分類法が、理解に関する12の対応概念の基礎となっている。これらの概念を導き出すにあたって、彼はおおよそ次のよう な理由を述べている。もしわれわれが純粋な理解概念を持つとすれば、それは論理的な判断形態に関係するものでなければならない。しかし、これらの純粋概念 を直観に適用するのであれば、それは内容を持たなければならない。しかし、論理的な判断形式はそれ自体抽象的で内容がない。したがって、理解の純粋概念を 決定するためには、論理的判断形式に対応し、かつ直観を組織する役割を果たすことのできる概念を特定しなければならない。そこでカントは、論理的判断形式 のそれぞれから、直観に関係する概念を抽出しようとする。たとえば、仮言的判断の論理形式(「もしpならばq」)に対応するものとして、因果性のカテゴ リー(「もしある事象があれば別の事象もある」)がある。カントはこれらの純粋概念を「カテゴリー」と呼び、カテゴリーがより一般的な概念から派生しない 概念であるというアリストテレス的な概念を反響させている。彼は他の11のカテゴリーについても同様の方法に従って、それらを以下の表に表している [42]。 1. 量のカテゴリー 単一性 複数性 全体性 2. 質のカテゴリー 現実 否定 制限 3. 関係のカテゴリー 内在と存続(物質と偶然) 因果と依存(原因と結果) 共同体(代理人と患者の相互関係) 4. モダリティのカテゴリー 可能性-不可能性 存在-非存在 必要性-偶発性 これらの範疇は、理解における基本的な、第一の、あるいは固有の概念である。これらの概念は、理解のメカニズムやその性質に由来する、あるいはそれを構成 するものであり、その活動から切り離せないものである。したがって、人間の思考にとって、これらは普遍的で必要なもの、すなわちアプリオリなものである。 カテゴリーとして、それらは感覚的意識の偶発的な状態やイメージではなく、したがってそこから派生するものでもない。同様に、それらはそのような意識や感 覚的経験とは無関係に私たちに知られるものではない。一方では、それらは専ら理解の自発的な活動に関与しており、それゆえ、理解の自発的な活動を通じて専 ら私たちの知識となる。しかし、この理解は、それが作用する材料として感覚的なデータが提供されるまでは、決して活動しないのであり、したがって、それら は「感覚的な経験の機会においてのみ」私たちに知られるようになると言える。カントにとって、クリスチャン・ヴォルフやトマス・ホッブズとは反対に、カテ ゴリーは心の中にのみ存在する[43]。 これらのカテゴリーは、感覚において偶発的なものすべてから独立している限りにおいて、理解における「純粋な」概念である。範疇は感覚の物質と呼ばれるも の、あるいは特定の可変的な感覚に由来するものではない。しかし、感覚という普遍的で必要な形式から独立しているわけではない。再び、カントは『超越論的 論理学』において、『批判』の第二の主要な疑問、すなわち純粋な物理学、すなわち感覚的知識はいかにして可能なのか、に対する答えの探求に取り組んでいる ことを公言している。さて、カントは、前述の問いで言及した種類の知識について、「知覚が供給する内容を伴わない思考は空虚である」と述べた。このこと は、他のどのような思考にも劣らず、純粋な思考にも当てはまる。純粋な物理学や感覚的知識の範疇としての純粋な観念が、感覚という物質から導き出すことの できない内容は、その純粋な形から導き出されなければならないし、導き出されるのである。そして、理解力の純粋概念とその純粋な内容との間のこの関係に は、後述するように、感覚とその形式的側面(空間と時間)と理解力それ自体との間の性質と起源との最も密接な共同体が関与している。カントにとって、空間 と時間はアプリオリな直観である。空間がアプリオリな直観であることを支持する合計6つの議論のうち、カントは『形而上学的説明』の中で4つの議論を提示 している。 |
| The transcendental deduction In the Transcendental Deduction, Kant aims to show that the categories derived in the Metaphysical Deduction are conditions of all possible experience. He achieves this proof roughly by the following line of thought: all representations must have some common ground if they are to be the source of possible knowledge (because extracting knowledge from experience requires the ability to compare and contrast representations that may occur at different times or in different places). This ground of all experience is the self-consciousness of the experiencing subject, and the constitution of the subject is such that all thought is rule-governed in accordance with the categories. It follows that the categories feature as necessary components in any possible experience.[44] 1.Axioms of intuition 2.Anticipations of perception 3.Analogies of experience 4.Postulates of empirical thought in general The schematism In order for any concept to have meaning, it must be related to sense perception. The 12 categories, or a priori concepts, are related to phenomenal appearances through schemata. Each category has a schema. It is a connection through time between the category, which is an a priori concept of the understanding, and a phenomenal a posteriori appearance. These schemata are needed to link the pure category to sensed phenomenal appearances because the categories are, as Kant says, heterogeneous with sense intuition. Categories and sensed phenomena, however, do share one characteristic: time. Succession is the form of sense impressions and also of the Category of causality. Therefore, time can be said to be the schema of Categories or pure concepts of the understanding.[45] The refutation of idealism In order to answer criticisms of the Critique of Pure Reason that Transcendental Idealism denied the reality of external objects, Kant added a section to the second edition (1787) titled "The Refutation of Idealism" which turns the "game" of idealism against itself by arguing that self-consciousness presupposes external objects. Defining self-consciousness as a determination of the self in time, Kant argues that all determinations of time presuppose something permanent in perception and that this permanence cannot be in the self, since it is only through the permanence that one's existence in time can itself be determined. This argument inverted the supposed priority of inner over outer experience that had dominated philosophies of mind and knowledge since René Descartes. In Book II, chapter II, section III of the Transcendental Analytic, right under "The Postulates of Empirical Thought", Kant adds a "Refutation of Idealism (Widerlegung des Idealismus)", where he refutes both Descartes' problematic idealism and Berkeley's dogmatic idealism. According to Kant, in problematic idealism the existence of objects is doubtful or impossible to prove, while in dogmatic idealism the existence of space and therefore of spatial objects is impossible. In contradistinction, Kant holds that external objects may be directly perceived and that such experience is a necessary presupposition of self-consciousness.[46] Appendix: "Amphiboly of Concepts of Reflection" As an Appendix to the First Division of Transcendental Logic, Kant intends the "Amphiboly of the Conceptions of Reflection" to be a critique of Leibniz's metaphysics and a prelude to Transcendental Dialectic, the Second Division of Transcendental Logic. Kant introduces a whole set of new ideas called "concepts of reflection": identity/difference, agreement/opposition, inner/outer and matter/form. According to Kant, the categories do have but these concepts have no synthetic function in experience. These special concepts just help to make comparisons between concepts judging them either different or the same, compatible or incompatible. It is this particular action of making a judgment that Kant calls "logical reflection."[29]: 206 As Kant states: "Through observation and analysis of appearances we penetrate to nature's inner recesses, and no one can say how far this knowledge may in time extend. But with all this knowledge, and even if the whole of nature were revealed to us, we should still never be able to answer those transcendental questions which go beyond nature. The reason of this is that it is not given to us to observe our own mind with any other intuition than that of inner sense; and that it is yet precisely in the mind that the secret of the source of our sensibility is located. The relation of sensibility to an object and what the transcendental ground of this [objective] unity may be, are matters undoubtedly so deeply concealed that we, who after all know even ourselves only through inner sense and therefore as appearance, can never be justified in treating sensibility as being a suitable instrument of investigation for discovering anything save always still other appearances – eager as we yet are to explore their non-sensible cause." (A278/B334) Second Division: Transcendental Dialectic Following the systematic treatment of a priori knowledge given in the transcendental analytic, the transcendental dialectic seeks to dissect dialectical illusions. Its task is effectively to expose the fraudulence of the non-empirical employment of the understanding. The Transcendental Dialectic shows how pure reason should not be used. According to Kant, the rational faculty is plagued with dialectic illusions as man attempts to know what can never be known.[47] This longer but less dense section of the Critique is composed of five essential elements, including an Appendix, as follows: (a) Introduction (to Reason and the Transcendental Ideas), (b) Rational Psychology (the nature of the soul), (c) Rational Cosmology (the nature of the world), (d) Rational Theology (God), and (e) Appendix (on the constitutive and regulative uses of reason). In the introduction, Kant introduces a new faculty, human reason, positing that it is a unifying faculty that unifies the manifold of knowledge gained by the understanding. Another way of thinking of reason is to say that it searches for the 'unconditioned'; Kant had shown in the Second Analogy that every empirical event has a cause, and thus each event is conditioned by something antecedent to it, which itself has its own condition, and so forth. Reason seeks to find an intellectual resting place that may bring the series of empirical conditions to a close, to obtain knowledge of an 'absolute totality' of conditions, thus becoming unconditioned. All in all, Kant ascribes to reason the faculty to understand and at the same time criticize the illusions it is subject to.[48][verification needed] The paralogisms of pure reason One of the ways that pure reason erroneously tries to operate beyond the limits of possible experience is when it thinks that there is an immortal Soul in every person. Its proofs, however, are paralogisms, or the results of false reasoning. The soul is substance Every one of my thoughts and judgments is based on the presupposition "I think". "I" is the subject and thinking is the predicate. Yet the ever-present logical subject of every thought should not be confused with a permanent, immortal, real substance (soul). The logical subject is a mere idea, not a real substance. Unlike Descartes, who believes that the soul may be known directly through reason, Kant asserts that no such thing is possible. Descartes declares cogito ergo sum, but Kant denies that any knowledge of "I" may be possible. "I" is only the background of the field of apperception and as such lacks the experience of direct intuition that would make self-knowledge possible. This implies that the self in itself could never be known. Like Hume, Kant rejects knowledge of the "I" as substance. For Kant, the "I" that is taken to be the soul is purely logical and involves no intuitions. The "I" is the result of the a priori consciousness continuum, not of direct intuition a posteriori. It is apperception as the principle of unity in the consciousness continuum that dictates the presence of "I" as a singular logical subject of all the representations of a single consciousness. Although "I" seems to refer to the same "I" all the time, it is not really a permanent feature but only the logical characteristic of a unified consciousness.[49] The soul is simple The only use or advantage of asserting that the soul is simple is to differentiate it from matter and therefore prove that it is immortal, but the substratum of matter may also be simple. Since we know nothing of this substratum, both matter and soul may be fundamentally simple and therefore not different from each other. Then the soul may decay, as does matter. It makes no difference to say that the soul is simple and therefore immortal. Such a simple nature can never be known through experience. It has no objective validity. According to Descartes, the soul is indivisible. This paralogism mistakes the unity of apperception for the unity of an indivisible substance called the soul. It is a mistake that is the result of the first paralogism. It is impossible that thinking (Denken) could be composite for if the thought by a single consciousness were to be distributed piecemeal among different consciousnesses, the thought would be lost. According to Kant, the most important part of this proposition is that a multi-faceted presentation requires a single subject. This paralogism misinterprets the metaphysical oneness of the subject by interpreting the unity of apperception as being indivisible and the soul simple as a result. According to Kant, the simplicity of the soul as Descartes believed cannot be inferred from the "I think" as it is assumed to be there in the first place. Therefore, it is a tautology.[50] The soul is a person In order to have coherent thoughts, I must have an "I" that is not changing and that thinks the changing thoughts. Yet we cannot prove that there is a permanent soul or an undying "I" that constitutes my person. I only know that I am one person during the time that I am conscious. As a subject who observes my own experiences, I attribute a certain identity to myself, but, to another observing subject, I am an object of his experience. He may attribute a different persisting identity to me. In the third paralogism, the "I" is a self-conscious person in a time continuum, which is the same as saying that personal identity is the result of an immaterial soul. The third paralogism mistakes the "I", as unit of apperception being the same all the time, with the everlasting soul. According to Kant, the thought of "I" accompanies every personal thought and it is this that gives the illusion of a permanent I. However, the permanence of "I" in the unity of apperception is not the permanence of substance. For Kant, permanence is a schema, the conceptual means of bringing intuitions under a category. The paralogism confuses the permanence of an object seen from without with the permanence of the "I" in a unity of apperception seen from within. From the oneness of the apperceptive "I" nothing may be deduced. The "I" itself shall always remain unknown. The only ground for knowledge is the intuition, the basis of sense experience.[51] The soul is separated from the experienced world The soul is not separate from the world. They exist for us only in relation to each other. Whatever we know about the external world is only a direct, immediate, internal experience. The world appears, in the way that it appears, as a mental phenomenon. We cannot know the world as a thing-in-itself, that is, other than as an appearance within us. To think about the world as being totally separate from the soul is to think that a mere phenomenal appearance has independent existence outside of us. If we try to know an object as being other than an appearance, it can only be known as a phenomenal appearance, never otherwise. We cannot know a separate, thinking, non-material soul or a separate, non-thinking, material world because we cannot know things, as to what they may be by themselves, beyond being objects of our senses. The fourth paralogism is passed over lightly or not treated at all by commentators. In the first edition of the Critique of Pure Reason, the fourth paralogism is addressed to refuting the thesis that there is no certainty of the existence of the external world. In the second edition of the Critique of Pure Reason, the task at hand becomes the Refutation of Idealism. Sometimes, the fourth paralogism is taken as one of the most awkward of Kant's invented tetrads. Nevertheless, in the fourth paralogism, there is a great deal of philosophizing about the self that goes beyond the mere refutation of idealism. In both editions, Kant is trying to refute the same argument for the non-identity of mind and body.[52] In the first edition, Kant refutes the Cartesian doctrine that there is direct knowledge of inner states only and that knowledge of the external world is exclusively by inference. Kant claims mysticism is one of the characteristics of Platonism, the main source of dogmatic idealism. Kant explains skeptical idealism by developing a syllogism called "The Fourth Paralogism of the Ideality of Outer Relation:" That whose existence can be inferred only as a cause of given perceptions has only a doubtful existence. And the existence of outer appearances cannot be immediately perceived but can be inferred only as the cause of given perceptions. Then, the existence of all objects of outer sense is doubtful.[53] Kant may have had in mind an argument by Descartes: My own existence is not doubtful But the existence of physical things is doubtful Therefore, I am not a physical thing. It is questionable that the fourth paralogism should appear in a chapter on the soul. What Kant implies about Descartes' argument in favor of the immaterial soul is that the argument rests upon a mistake on the nature of objective judgment not on any misconceptions about the soul. The attack is mislocated.[54] These Paralogisms cannot be proven for speculative reason and therefore can give no certain knowledge about the Soul. However, they can be retained as a guide to human behavior. In this way, they are necessary and sufficient for practical purposes. In order for humans to behave properly, they can suppose that the soul is an imperishable substance, it is indestructibly simple, it stays the same forever, and it is separate from the decaying material world. On the other hand, anti-rationalist critics of Kant's ethics consider it too abstract, alienating, altruistic or detached from human concern to actually be able to guide human behavior. It is then that the Critique of Pure Reason offers the best defense, demonstrating that in human concern and behavior, the influence of rationality is preponderant.[55] The antinomy of pure reason Kant presents the four antinomies of reason in the Critique of Pure Reason as going beyond the rational intention of reaching a conclusion. For Kant, an antinomy is a pair of faultless arguments in favor of opposite conclusions. Historically, Leibniz and Samuel Clarke (Newton's spokesman) had just recently engaged in a titanic debate of unprecedented repercussions. Kant's formulation of the arguments was affected accordingly.[56] The Ideas of Rational Cosmology are dialectical. They result in four kinds of opposing assertions, each of which is logically valid. The antinomy, with its resolution, is as follows: Thesis: The world has, as to time and space, a beginning (limit). Antithesis: The world is, as to time and space, infinite. Both are false. The world is an object of experience. Neither statement is based on experience. Thesis: Everything in the world consists of elements that are simple. Antithesis: There is no simple thing, but everything is composite. Both are false. Things are objects of experience. Neither statement is based on experience. Thesis: There are in the world causes through freedom. Antithesis: There is no freedom, but all is nature. Both may be true. The thesis may be true of things-in-themselves (other than as they appear). The antithesis may be true of things as they appear. Thesis: In the series of the world-causes there is some necessary being. Antithesis: There is nothing necessary in the world, but in this series all is contingent. Both may be true. The thesis may be true of things-in-themselves (other than as they appear). The antithesis may be true of things as they appear. According to Kant, rationalism came to fruition by defending the thesis of each antinomy while empiricism evolved into new developments by working to better the arguments in favor of each antithesis.[57] The ideal of pure reason Pure reason mistakenly goes beyond its relation to possible experience when it concludes that there is a Being who is the most real thing (ens realissimum) conceivable. This ens realissimum is the philosophical origin of the idea of God. This personified object is postulated by Reason as the subject of all predicates, the sum total of all reality. Kant called this Supreme Being, or God, the Ideal of Pure Reason because it exists as the highest and most complete condition of the possibility of all objects, their original cause and their continual support.[58] Refutation of the ontological proof of God's existence of Anselm of Canterbury The ontological proof can be traced back to Anselm of Canterbury (1033–1109). Anselm presented the proof in chapter II of a short treatise titled "Discourse on the existence of God." It was not Kant but the monk Gaunilo and later the Scholastic Thomas Aquinas who first challenged the success of the proof. Aquinas went on to provide his own proofs for the existence of God in what are known as the Five Ways.[59] The ontological proof considers the concept of the most real Being (ens realissimum) and concludes that it is necessary. The ontological argument states that God exists because he is perfect. If he didn't exist, he would be less than perfect. Existence is assumed to be a predicate or attribute of the subject, God, but Kant asserted that existence is not a predicate. Existence or Being is merely the infinitive of the copula or linking, connecting verb "is" in a declarative sentence. It connects the subject to a predicate. "Existence is evidently not a real predicate ... The small word is, is not an additional predicate, but only serves to put the predicate in relation to the subject." (A599) Also, we cannot accept a mere concept or mental idea as being a real, external thing or object. The Ontological Argument starts with a mere mental concept of a perfect God and tries to end with a real, existing God. The argument is essentially deductive in nature. Given a certain fact, it proceeds to infer another from it. The method pursued, then, is that of deducing the fact of God's being from the a priori idea of him. If man finds that the idea of God is necessarily involved in his self-consciousness, it is legitimate for him to proceed from this notion to the actual existence of the divine being. In other words, the idea of God necessarily includes existence. It may include it in several ways. One may argue, for instance, according to the method of Descartes, and say that the conception of God could have originated only with the divine being himself, therefore the idea possessed by us is based on the prior existence of God himself. Or we may allege that we have the idea that God is the most necessary of all beings—that is to say, he belongs to the class of realities; consequently it cannot but be a fact that he exists. This is held to be proof per saltum. A leap takes place from the premise to the conclusion, and all intermediate steps are omitted. The implication is that premise and conclusion stand over against one another without any obvious, much less necessary, connection. A jump is made from thought to reality. Kant here objects that being or existence is not a mere attribute that may be added onto a subject, thereby increasing its qualitative content. The predicate, being, adds something to the subject that no mere quality can give. It informs us that the idea is not a mere conception, but is also an actually existing reality. Being, as Kant thinks, actually increases the concept itself in such a way as to transform it. You may attach as many attributes as you please to a concept; you do not thereby lift it out of the subjective sphere and render it actual. So you may pile attribute upon attribute on the conception of God, but at the end of the day you are not necessarily one step nearer his actual existence. So that when we say God exists, we do not simply attach a new attribute to our conception; we do far more than this implies. We pass our bare concept from the sphere of inner subjectivity to that of actuality. This is the great vice of the Ontological argument. The idea of ten dollars is different from the fact only in reality. In the same way the conception of God is different from the fact of his existence only in reality. When, accordingly, the Ontological proof declares that the latter is involved in the former, it puts forward nothing more than a mere statement. No proof is forthcoming precisely where proof is most required. We are not in a position to say that the idea of God includes existence, because it is of the very nature of ideas not to include existence. Kant explains that, being, not being a predicate, could not characterize a thing. Logically, it is the copula of a judgment. In the proposition, "God is almighty", the copula "is" does not add a new predicate; it only unites a predicate to a subject. To take God with all its predicates and say that "God is" is equivalent to "God exists" or that "There is a God" is to jump to a conclusion as no new predicate is being attached to God. The content of both subject and predicate is one and the same. According to Kant then, existence is not really a predicate. Therefore, there is really no connection between the idea of God and God's appearance or disappearance. No statement about God whatsoever may establish God's existence. Kant makes a distinction between "in intellectus" (in mind) and "in re" (in reality or in fact) so that questions of being are a priori and questions of existence are resolved a posteriori.[60] |
超越論的演繹 超越論的演繹において、カントは形而上学的演繹で導き出されたカテゴリーがすべての可能な経験の条件であることを示すことを目的としている。可能な知識の 源となるためには、すべての表象は何らかの共通の根拠を持たなければならない(経験から知識を引き出すには、異なる時間や場所で起こりうる表象を比較対照 する能力が必要だからである)。すべての経験のこの基盤は、経験する主体の自己意識であり、主体の構成は、すべての思考がカテゴリーに従って規則的に支配 されるようなものである。このことは、カテゴリーがあらゆる可能な経験において必要な構成要素として特徴づけられることを意味する[44]。 1.直観の公理 2.知覚の予期 3.経験の類推 4.経験的思考の一般的な仮定 図式論 どのような概念も意味を持つためには、感覚知覚に関連していなければならない。12のカテゴリー、すなわちアプリオリな概念は、スキーマを通して現象的現 われと関係づけられる。各カテゴリーにはスキーマがある。それは、理解の先験的概念であるカテゴリーと、現象的な事後的外観との間の、時間を通したつなが りである。これらのスキーマは、カントが言うように、カテゴリーが感覚的直観と異質であるために、純粋カテゴリーと感覚的現象的出現とを結びつけるために 必要とされる。しかし、カテゴリーと感覚現象は、時間という一つの特徴を共有している。連続は感覚的印象の形式であり、また因果性のカテゴリーの形式でも ある。したがって、時間はカテゴリーのスキーマ、あるいは理解の純粋概念であると言うことができる[45]。 観念論への反論 超越論的観念論が外的対象の実在を否定しているという『純粋理性批判』への批判に答えるために、カントは第2版(1787年)に「観念論の 反駁」という章を追加した。カントは、自己意識を時間における自己の決定と定義し、時間の決定はすべて知覚における永続的な何かを前提とし、この永続性は 自己にはあり得ないと主張する。この主張は、ルネ・デカルト以来、心や知識に関する哲学を支配してきた、外側の経験よりも内側の経験が優先されるという考 え方を覆すものであった。カントは『超越論的分析』の第二巻、第二章、第三節、「経験的思惟の定立」のすぐ下に、「観念論の反駁(Widerlegung des Idealismus)」を追加し、デカルトの問題的観念論とバークレーの独断的観念論に反論している。カントによれば、問題的観念論では物体の存在は疑 わしいか証明不可能であり、独断的観念論では空間の存在、したがって空間的物体の存在は不可能である。これとは対照的に、カントは外的な対象は直接知覚さ れることがあり、そのような経験は自己意識の必要な前提であるとする[46]。 付録"反射の概念の両義性" カントは『超越論的論理学』第一部の付録として、ライプニッツの形而上学に対する批判であり、『超越論的論理学』第二部である 『超越論的弁証法』への序章である「反省の概念の両義性」を意図している。カントは「反省の概念」と呼ばれる、同一性/差異、一致/対立、内面/外面、物 質/形態といった新しい概念を導入する。カントによれば、カテゴリーは存在するが、これらの概念は経験において合成的な機能を持たない。これらの特別な概 念は、概念間を比較し、異なるか同じか、適合するかしないかを判断するのに役立つだけである。カントが「論理的反省」[29]: 206と呼ぶのは、判断を下すこの特別な行為である: 「この知識がやがてどこまで広がるかは誰にもわからない。しかし、このような知識をもってしても、また、たとえ自然の全体がわれわれに明らかにされたとし ても、われわれは、自然を超えた超越論的な問いに答えることはできないであろう。その理由は、内的感覚以外の直観で自分の心を観察することは、私たちには 与えられていないからである。感覚と対象との関係や、この[客観的な]統一の超越論的な根拠が何であるかは、間違いなく深く隠されている事柄であり、結局 のところ、内的感覚を通してしか、したがって外見としてしか自分自身を知らない私たちが、感覚を、常に他の外見を除いて何かを発見するのに適した調査道具 として扱うことは決して正当化されない。(A278/B334) 第二部 超越論的弁証法 超越論的弁証法は、超越論的分析において与えられた先験的知識の体系的な取り扱いに続いて、弁証法的幻想を解体しようとする。超越論的弁証法は、弁証法的 幻想を解体しようとするものである。超越論的弁証法は、純粋理性がいかに利用されるべきではないかを示す。カントによれば、人間は決して知りえないことを 知ろうとするため、理性は弁証法的幻想に悩まされる[47]。 この『批判』の長いがそれほど密度の高くない部分は、付録を含めて以下の5つの本質的な要素から構成されている: (a)序論(理性と超越論的イデア)、(b)理性的心理学(魂の性質)、(c)理性的宇宙論(世界の性質)、(d)理性的神学(神)、(e)付録(理性の 構成的および調整的使用について)。 序論でカントは、人間の理性という新しい能力を導入し、それが理解によって得られる多様な知識を統一する統一的な能力であると仮定している。カントは『第 二の類比』において、経験的事象にはすべて原因があり、したがって各事象はそれ以前の何かによって条件づけられ、それ自体もまた条件づけられ、といったよ うに、理性は「無条件のもの」を探し求めると述べている。理性は、一連の経験的条件に終止符を打ち、条件の「絶対的全体性」についての知識を得て、無条件 になれるような知的な安息所を見つけようとする。全体として、カントは理性に、理性を理解し、同時に理性が受ける幻想を批判する能力を付与する[48] [要検証]。 純粋理性のパラロギスム 純粋理性が可能な経験の限界を超えて誤って活動しようとする方法の一つは、すべての人の中に不滅の魂があると考えるときである。し かし、その証明は類比論、すなわち誤った理性の結果である。 魂は実体である私の思考や判断はすべて、「私は考える」という前提に基づいている。「私」は主語であり、考えることは述語である。しかし、あらゆる思考に 常に存在する論理的主語を、永続的で不滅の実在する物質(魂)と混同してはならない。論理的主体は単なる考えであり、実在の物質ではない。魂は理性によっ て直接知ることができると考えるデカルトとは異なり、カントはそのようなことは不可能だと主張する。デカルトは「コギト・エルゴ・スム」を宣言したが、カ ントは「私」に関するいかなる知識もあり得ないと否定する。「私」は知覚の場の背景でしかなく、自己認識を可能にする直接的な直観の経験を欠いている。こ のことは、自己それ自体を知ることはできないということを意味している。ヒュームと同様、カントも実体としての「私」の知識を否定する。カントにとって、 魂とされる「私」は純粋に論理的であり、直観を伴わない。私」はアプリオリな意識連続体の結果であり、事後的な直接的直観の結果ではない。一つの意識のす べての表象の唯一の論理的主体としての「私」の存在を規定するのは、意識連続体における統一の原理としての知覚である。私」は常に同じ「私」を指している ように見えるが、それは実際には永続的な特徴ではなく、統一された意識の論理的特徴にすぎない[49]。 魂は物質(サブスタンス)である 魂が単純であると主張する唯一の用途や利点は、魂と物質とを区別し、したがって魂が不滅であることを証明することであるが、物質の基質も単純である可能性 がある。しかし、物質の基質も単純である可能性がある。この基質について私たちは何も知らないのだから、物質も魂も基本的には単純であり、したがって互い に違いはないのかもしれない。その場合、魂も物質と同じように朽ちるかもしれない。魂は単純であり、したがって不滅であると言っても違いはない。そのよう な単純な性質は、経験を通じて知ることはできない。客観的な妥当性はない。デカルトによれば、魂は不可分である。このパラロギズムは、知覚の単一性を魂と いう不可分の物質の単一性と取り違えている。これは最初のパラロギズムの結果としての間違いである。一つの意識による思考(Denken)が異なる意識に 断片的に分配されるなら、思考が失われるからである。カントによれば、この命題の最も重要な部分は、多面的な提示には単一の主体が必要だということであ る。このパラロギズムは、形而上学的な主体の一体性を誤って解釈し、知覚の一体性は不可分であり、その結果として魂は単純であると解釈する。カントによれ ば、デカルトが考えていたような魂の単純性は、そもそも「私が考える」ことから推測することはできない。したがって、それはトートロジーである[50]。 魂はシンプルである 首尾一貫した思考をするためには、変化せず、変化する思考をする「私」がいなければならない。しかし、永続的な魂や、私の人格を構成する不滅の「私」が存 在することを証明することはできない。私が知っているのは、私が意識している間、私が一人の人間であるということだけである。自分自身の経験を観察する主 体として、私はあるアイデンティティを自分自身に帰属させるが、他の観察主体にとっては、私は彼の経験の対象である。しかし、他の観察主体にとっては、私 は彼の経験の対象なのである。第三のパラロギズムでは、「私」は時間連続体における自意識の持ち主であり、これは個人のアイデンティティーが非物質的な魂 の結果であると言っているのと同じである。第三のパラロギズムは、知覚の単位が常に同じである「私」を、永遠の魂と取り違えている。カントによれば、 「私」の思考はすべての個人的思考に付随し、それが永続的な「私」の幻想を与える。しかし、「私」の知覚の統一における永続性は、物質の永続性ではない。 カントにとって、永続性とはスキーマであり、直観をカテゴリーの下に置くための概念的手段である。パラロギズムは、外から見た対象の永続性と、内から見た 統覚の統一における「私」の永続性とを混同している。知覚する「私」の一体性からは、何も推論できない。私」そのものは常に未知のままである。知識の唯一 の根拠は、感覚経験の基礎である直観である[51]。 魂は経験世界から分離している 魂は世界から切り離されてはいない。それらは私たちにとって、互いの関係においてのみ存在する。私たちが外界について知って いることはすべて、直接的で即時的な内的経験でしかない。世界は心的現象として、そのように見える。われわれは世界を、それ自体として、つまりわれわれの 内面に現れるものとしてしか知ることができない。世界が魂から完全に切り離されていると考えることは、単なる現象的な外観が私たちの外に独立した存在を 持っていると考えることである。ある物体が外見以外のものであると知ろうとすれば、それは現象的な外見としてしか知ることができず、そうでなければ決して 知ることはできない。私たちは、別個の、思考する、非物質的な魂や、別個の、思考しない、物質的な世界を知ることはできないのである。第四のパラロギズム は、解説者たちによって軽く流されるか、まったく扱われない。純粋理性批判』の第1版では、第4のパラロギズムは、外界の存在には確証がないというテーゼ に対する反論として扱われている。純粋理性批判』の第2版では、その課題は「観念論の反駁」となる。第4のパラロギズムは、カントが考案した四段論法の中 で最も厄介なもののひとつとみなされることもある。とはいえ、第四パラロギズムには、単なる観念論の反駁にとどまらない、自己についての哲学的考察が多く 含まれている。第1版では、カントは、内的状態についてのみ直接的な知識があり、外的世界についての知識はもっぱら推論による、というデカルトの教義に反 論している。カントは神秘主義がプラトン主義の特徴の一つであり、教条的観念論の主要な源であると主張する。カントは懐疑的観念論を、"外的関係の観念論 の第四パラロギズム "と呼ばれる三段論法を展開することによって説明する。 与えられた知覚の原因としてのみ存在を推論できるものは、疑わしい存在しか持たない。 そして、外界の外観の存在は、直ちに知覚することはできないが、与えられた知覚の原因としてのみ推論することができる。 そうすると、外界の感覚の対象はすべて存在が疑わしいことになる[53]。 カントはデカルトの議論を念頭に置いていたのかもしれない: 私自身の存在は疑わしくないが しかし物理的なものの存在は疑わしい したがって、私は物理的なものではない。 第四のパラロギズムが魂の章に登場するのは疑問である。非物質的な魂を支持するデカルトの議論についてカントが暗示しているのは、その議論は客観的判断の 本質についての誤りに基づいているのであって、魂についての誤認に基づくものではないということである。攻撃は誤った位置にある[54]。 これらのパラロギズムは思弁的な理由から証明することができず、したがって魂についての確かな知識を与えることはできない。しかし、人間の行動の指針とし て保持することはできる。このように、それらは実際的な目的にとっては必要かつ十分なものである。人間が適切に行動するためには、魂は不滅の物質であり、 破壊不可能なほど単純で、永遠に変わらず、朽ち果てる物質世界とは別物であると考えることができる。一方、カントの倫理を批判する反合理主義者は、倫理が 抽象的、疎外的、利他的、あるいは人間の関心から離れすぎていて、人間の行動を実際に導くことはできないと考える。純粋理性批判は、人間の関心と行動にお いて、合理性の影響が支配的であることを実証し、最善の弁護を提供するのである[55]。 純粋理性のアンチノミー カントは『純粋理性批判』において、結論に到達するという合理的な意図を超えるものとして理性の4つのアンチノミーを提示している。カントにとってアンチ ノミーとは、正反対の結論を支持する一対の欠点のない議論のことである。歴史的には、ライプニッツとサミュエル・クラーク(ニュートンの代弁者)はつい最 近、前代未聞の大激論を繰り広げたばかりであった。カントの論証の定式化はそれに応じて影響を受けた[56]。 合理的宇宙論のイデアは弁証法的である。その結果、4種類の対立する主張が生じ、それぞれが論理的に妥当である。その解決策を伴うアンチノミーは以下の通 りである: テーゼ テーゼ:世界には、時間と空間に関して、始まり(限界)がある。 アンチテーゼ: 世界は時間と空間に関して無限である。 どちらも誤りである。世界は経験の対象である。どちらの主張も経験に基 づいていない。 テーゼ 世界のすべては単純な要素で構成されている。 アンチテーゼ: 単純なものはなく、すべてが複合的である。 どちらも誤り。物事は経験の対象である。どちらの主張も経験に基づいて いない。 テーゼ 世界には自由による原因がある。 アンチテーゼ: 自由はないが、すべては自然である。 どちらも真実かもしれない。テーゼは、それ自体(外見上以外のもの)に おいて真であるかもしれない。アンチテーゼは、物事それ自体について真実であるかも しれない。 テーゼ: 世界原因の系列には、必要な存在がある。 アンチテーゼ: 世界には必要なものは何もないが、この系列においてはすべてが偶発的である。 どちらも真実かもしれない。テーゼは、それ自体(見かけ以外のもの)に対して真であるかもしれない。アンチテーゼは、物事それ自体について真であるかもし れない。 カントによれば、合理主義はそれぞれのアンチノミーのテーゼを擁護することによって結実し、一方経験主義はそれぞれのアンチテーゼを支持する論拠をより良 くすることに取り組むことによって新たな発展へと発展した[57]。 純粋理性の理想 純粋理性は、考え得る最も実在的なもの(ens realissimum)である存在が存在すると結論づけるとき、可能な経験との関係を誤って超えてしまう。このens realissimumこそ、神という観念の哲学的起源である。この人格化された対象は、理性によってすべての述語の主語、すべての現実の総体として仮定 される。カントはこの至高の存在、すなわち神を純粋理性の理想と呼んだが、それはすべての対象の可能性の最高で最も完全な条件として存在し、それらの原初 的な原因として存在し、それらの継続的な支えとして存在するからである[58]。 カンタベリーのアンセルムの神の存在に関する存在論的証明に対する反論 存在論的証明は、カンタベリーのアンセルム(1033-1109)まで遡ることができる。アンセルムは、"Discourse on the existence of God"(神の存在に関する論考)と題された短い論考の第二章で、その証明を提示した。この証明の成功に最初に異議を唱えたのはカントではなく、修道士ガ ウニロであり、後にスコラ学者トマス・アクィナスであった。アクィナスは、「五つの方法」として知られているもので、神の存在に対する彼自身の証明を提供 するようになった[59]。 存在論的証明は、最も実在的な存在(ens realissimum)の概念を考察し、それが必要であると結論づける。存在論的証明は、神は完全であるがゆえに存在すると述べている。もし神が存在し なければ、神は完全ではない。存在は主語である神の述語または属性であると仮定されるが、カントは存在は述語ではないと主張した。存在」あるいは「存在す ること」は、宣言文における連結動詞「である」の不定詞にすぎない。それは主語と述語を結びつける。「存在とは明らかに述語ではない。isという小単語 は、付加的な述語ではなく、述語を主語との関係に置く役割を果たすだけである。"(A599)。(A599)また、単なる概念や心的観念を、実在する外的 な事物や対象として受け入れることはできない。存在論的論証は、完全な神という単なる心的概念から出発し、実在する、現存する神で終わらせようとする。 論証は本質的に演繹的である。ある事実が与えられれば、そこから別の事実を推論する。そこで追求されるのは、先験的な神の観念から、神が存在するという事 実を推論する方法である。もし人間が、神という観念が自分の自己意識に必然的に含まれていることに気づけば、この観念から神の実在へと進むのは正当なこと である。言い換えれば、神の観念は必然的に存在を含む。神の観念が存在を含むには、いくつかの方法がある。たとえば、デカルトの方法に従って、神の観念は 神的存在自身によってのみ生じうるものであり、したがって、われわれの持つ観念は神そのものの事前の存在に基づいている、と主張することもできる。あるい は、神はあらゆる存在の中で最も必要な存在である、つまり実在の類に属する存在であり、したがって神が存在することは事実であると主張することもできる。 これは「塩による証明」である。前提から結論へと飛躍し、すべての中間段階が省略される。 その意味するところは、前提条件と結論は、明白な、ましてや必要な関連もなく、互いに重なり合っているということである。思考から現実へのジャンプが行わ れる。カントはここで、「存在」あるいは「存在」は、主題に付加され、それによってその質的な内容を増大させる単なる属性ではないことに異議を唱える。存 在という述語は、単なる性質では与えられない何かを対象に付加する。それは、理念が単なる観念ではなく、実際に存在する現実でもあることを教えてくれる。 カントが考えるように、存在とは、概念そのものを変容させるような形で、実際に増大させるものである。ある概念に好きなだけ属性を付けることはできるが、 それによってそれを主観的な領域から持ち出して現実のものとすることはできない。だから、神の概念に属性を積み重ねても、結局のところ、神の実際の存在に 一歩近づくとは限らない。つまり、私たちが「神は存在する」と言うとき、単に私たちの概念に新たな属性を付け加えるのではなく、それ以上のことをするので ある。私たちは裸の概念を内的主観性の領域から現実性の領域へと移行させるのである。これが存在論的議論の大きな悪弊である。10ドルという観念は、現実 においてのみ事実と異なる。同じように、神の観念は、現実においてのみ、神の存在の事実とは異なる。それゆえ、存在論的証明は、後者が前者に関与している と宣言するとき、それは単なる声明にすぎない。証明が最も必要とされるところで、証明は得られないのである。なぜなら、観念の本質として、存在を含まない からである。 カントは、存在とは述語ではなく、事物を特徴づけることはできないと説明する。論理的には、それは判断のコピュラである。神は全能である」という命題にお いて、「である」というコピュラは新たな述語を加えるのではなく、述語を主語に結びつけるだけである。神とその述語をすべてひっくるめて「神は存在する」 とか「神は存在する」と言うのは、神に新たな述語が付加されているわけではないので、結論を急ぐことになる。主語と述語の内容は同じである。カントによれ ば、存在は述語ではない。したがって、神という観念と神の出現や消失との間には、実際には何の関係もない。神についてのいかなる陳述も、神の存在を立証す ることはできない。カントは「知性において」(in intellectus)と「現実において」(in re)を区別し、存在の問題はアプリオリに、存在の問題は事後的に解決されるようにしている[60]。 |
| Refutation of the cosmological
("prime mover") proof of God's existence The cosmological proof considers the concept of an absolutely necessary Being and concludes that it has the most reality. In this way, the cosmological proof is merely the converse of the ontological proof. Yet the cosmological proof purports to start from sense experience. It says, "If anything exists in the cosmos, then there must be an absolutely necessary Being. " It then claims, on Kant's interpretation, that there is only one concept of an absolutely necessary object. That is the concept of a Supreme Being who has maximum reality. Only such a supremely real being would be necessary and independently existent, but, according to Kant, this is the Ontological Proof again, which was asserted a priori without sense experience. Summarizing the cosmological argument further, it may be stated as follows: "Contingent things exist—at least I exist; and as they are not self-caused, nor capable of explanation as an infinite series, it is requisite to infer that a necessary being, on whom they depend, exists." Seeing that this being exists, he belongs to the realm of reality. Seeing that all things issue from him, he is the most necessary of beings, for only a being who is self-dependent, who possesses all the conditions of reality within himself, could be the origin of contingent things. And such a being is God. Kant argues that this proof is invalid for three chief reasons. First, it makes use of a category, namely, Cause. And, as has been already pointed out, it is not possible to apply this, or any other, category except to the matter given by sense under the general conditions of space and time. If, then, we employ it in relation to Deity, we try to force its application in a sphere where it is useless, and incapable of affording any information. Once more, we are in the now familiar difficulty of the paralogism of Rational Psychology or of the Antinomies. The category has meaning only when applied to phenomena. Yet God is a noumenon. Second, it mistakes an idea of absolute necessity—an idea that is nothing more than an ideal—for a synthesis of elements in the phenomenal world or world of experience. This necessity is not an object of knowledge, derived from sensation and set in shape by the operation of categories. It cannot be regarded as more than an inference. Yet the cosmological argument treats it as if it were an object of knowledge exactly on the same level as perception of any thing or object in the course of experience. Thirdly, according to Kant, it presupposes the Ontological argument, already proved false. It does this, because it proceeds from the conception of the necessity of a certain being to the fact of his existence. Yet it is possible to take this course only if idea and fact are convertible with one another, and it has just been proved that they are not so convertible.[61] Physico-theological ("watch maker") proof of God's existence Main article: Teleological argument The physico-theological proof of God's existence is supposed to be based on a posteriori sensed experience of nature and not on mere a priori abstract concepts. It observes that the objects in the world have been intentionally arranged with great wisdom. The fitness of this arrangement could never have occurred randomly, without purpose. The world must have been caused by an intelligent power. The unity of the relation between all of the parts of the world leads us to infer that there is only one cause of everything. That one cause is a perfect, mighty, wise, and self-sufficient Being. This physico-theology does not, however, prove with certainty the existence of God. For this, we need something absolutely necessary that consequently has all-embracing reality, but this is the Cosmological Proof, which concludes that an all-encompassing real Being has absolutely necessary existence. All three proofs can be reduced to the Ontological Proof, which tried to make an objective reality out of a subjective concept. In abandoning any attempt to prove the existence of God, Kant declares the three proofs of rational theology known as the ontological, the cosmological and the physico-theological as quite untenable.[62] However, it is important to realize that while Kant intended to refute various purported proofs of the existence of God, he also intended to demonstrate the impossibility of proving the non-existence of God. Far from advocating for a rejection of religious belief, Kant rather hoped to demonstrate the impossibility of attaining the sort of substantive metaphysical knowledge (either proof or disproof) about God, free will, or the soul that many previous philosophers had pursued. |
神の存在に関する宇宙論的証明(「原動力」)に対する反論 宇宙論的証明 は、絶対的に必要な存在という概念を検討し、それが最も現実的であると結論づける。このように、宇宙論的証明は存在論的証明の逆である。しかし、宇宙論的 証明は、感覚的経験から出発すると称している。もし宇宙に何かが存在するなら、絶対に必要な存在が存在するはずだ。「そして、カントの解釈では、絶対必要 なものの概念は一つしかないと主張する。それは、最大の実在性を持つ至高の存在という概念である。そのような至高に実在する存在だけが必要であり、独立に 存在することになるが、カントによれば、これはまたもや存在論的証明であり、感覚的経験なしにアプリオリに主張されたものである。 宇宙論的証明をさらに要約すると、次のようになる: "偶発的なものは存在する-少なくとも私は存在する。" "それらは自己原因ではなく、無限系列として説明することもできないので、それらが依存する必要な存在が存在することを推論することが必要である。" この存在が存在することを見れば、その存在は現実の領域に属する。というのも、自己依存的で、現実の条件をすべて自分の中に持っている存在だけが、偶発的 なものの起源であり得るからである。そのような存在が神なのである。 カントは、この証明が3つの主な理由から無効であると主張する。第一に、この証明は「原因」というカテゴリーを用いている。そして、すでに指摘したよう に、空間と時間という一般的な条件のもとで、感覚によって与えられる事柄以外に、この、あるいは他のカテゴリーを適用することは不可能である。もし私たち がこの範疇を神との関係で用いるとすれば、私たちはこの範疇を、それが無用のものであり、いかなる情報も与えることのできない領域に無理矢理適用しようと することになる。理性的心理学や反知性主義のパラロギズムのような、今やお馴染みの難問に、私たちは今一度直面することになる。範疇は現象に適用されて初 めて意味を持つ。しかし、神は能現象である。第二に、現象界や経験界における諸要素の総合にとって、絶対的必然性の観念--理想にすぎない観念--を間違 えている。この必然性は、感覚から導かれ、カテゴリーの操作によって形づくられる、知識の対象ではない。推論以上のものとは見なされない。しかし、宇宙論 的議論は、経験の過程におけるあらゆる事物や物体の知覚とまったく同じレベルで、あたかもそれが知識の対象であるかのように扱う。第三に、カントによれ ば、宇宙論的議論は、すでに誤りであることが証明された存在論的議論を前提としている。それは、ある存在の必然性の概念から、その存在の事実へと進むから である。しかし、このような経過をたどることが可能なのは、観念と事実とが互いに変換可能である場合に限られるのであって、両者がそう変換可能でないこと が証明されたばかりである[61]。 神の存在に関する物理神学的証明 主な記事 目的論的証明 物理神学的な神の存在証明は、単なる先験的な抽象概念ではなく、自然に対する事後的な感覚的経験に基づくとされている。世界の物体は、偉大な知恵をもって 意図的に配置されている。このような配置の適性は、目的なしに無作為に生じることはあり得ない。世界は知的な力によって引き起こされたに違いない。世界の すべての部分間の関係が統一されていることから、すべての原因はただ一つであると推測される。その唯一の原因とは、完全で、強大で、賢明で、自己充足的な 存在である。しかし、この物理神学は神の存在を確実に証明するものではない。そのためには、絶対的に必要で、その結果としてすべてを包含する実在を持つ何 かが必要だが、これが宇宙論的証明であり、すべてを包含する実在が絶対的に必要な実在を持つと結論づけるものである。この3つの証明はすべて、主観的な概 念から客観的な実在を作り出そうとした存在論的証明に還元することができる。 カントは神の存在を証明する試みを放棄することで、存在論的証明、宇宙論的証明、物理神学的証明として知られる合理的神学の3つの証明は、まったく通用し ないものであると宣言している[62]。しかし、カントが神の存在に関するさまざまな証明と称されるものに反論することを意図していた一方で、神の非存在 を証明することの不可能性を示すことも意図していたことを理解することが重要である。カントはむしろ、宗教的信念の否定を主張するのではなく、それまでの 多くの哲学者たちが追求してきたような、神、自由意志、あるいは魂に関する実質的な形而上学的知識(証明であれ反証であれ)を得ることの不可能性を実証す ることを望んでいたのである。 |
| II. Transcendental Doctrine of
Method The second book in the Critique, and by far the shorter of the two, attempts to lay out the formal conditions of the complete system of pure reason. In the Transcendental Dialectic, Kant showed how pure reason is improperly used when it is not related to experience. In the Method of Transcendentalism, he explained the proper use of pure reason. The discipline of pure reason In section I, the discipline of pure reason in the sphere of dogmatism, of chapter I, the discipline of pure reason, of Part II, transcendental discipline of method, of the Critique of Pure Reason, Kant enters into the most extensive discussion of the relationship between mathematical theory and philosophy.[63] Discipline is the restraint, through caution and self-examination, that prevents philosophical pure reason from applying itself beyond the limits of possible sensual experience. Philosophy cannot possess dogmatic certainty. Philosophy, unlike mathematics, cannot have definitions, axioms or demonstrations. All philosophical concepts must be ultimately based on a posteriori, experienced intuition. This is different from algebra and geometry, which use concepts that are derived from a priori intuitions, such as symbolic equations and spatial figures. Kant's basic intention in this section of the text is to describe why reason should not go beyond its already well-established limits. In section I, the discipline of pure reason in the sphere of dogmatism, Kant clearly explains why philosophy cannot do what mathematics can do in spite of their similarities. Kant also explains that when reason goes beyond its own limits, it becomes dogmatic. For Kant, the limits of reason lie in the field of experience as, after all, all knowledge depends on experience. According to Kant, a dogmatic statement would be a statement that reason accepts as true even though it goes beyond the bounds of experience.[64] Restraint should be exercised in the polemical use of pure reason. Kant defined this polemical use as the defense against dogmatic negations. For example, if it is dogmatically affirmed that God exists or that the soul is immortal, a dogmatic negation could be made that God doesn't exist or that the soul is not immortal. Such dogmatic assertions can't be proved. The statements are not based on possible experience. In section II, the discipline of pure reason in polemics, Kant argues strongly against the polemical use of pure reason. The dogmatic use of reason would be the acceptance as true of a statement that goes beyond the bounds of reason while the polemic use of reason would be the defense of such statement against any attack that could be raised against it. For Kant, then, there cannot possibly be any polemic use of pure reason. Kant argues against the polemic use of pure reason and considers it improper on the grounds that opponents cannot engage in a rational dispute based on a question that goes beyond the bounds of experience.[64] Kant claimed that adversaries should be freely allowed to speak reason. In return, they should be opposed through reason. Dialectical strife leads to an increase of reason's knowledge. Yet there should be no dogmatic polemical use of reason. The critique of pure reason is the tribunal for all of reason's disputes. It determines the rights of reason in general. We should be able to openly express our thoughts and doubts. This leads to improved insight. We should eliminate polemic in the form of opposed dogmatic assertions that cannot be related to possible experience. According to Kant, the censorship of reason is the examination and possible rebuke of reason. Such censorship leads to doubt and skepticism. After dogmatism produces opposing assertions, skepticism usually occurs. The doubts of skepticism awaken reason from its dogmatism and bring about an examination of reason's rights and limits. It is necessary to take the next step after dogmatism and skepticism. This is the step to criticism. By criticism, the limits of our knowledge are proved from principles, not from mere personal experience. If criticism of reason teaches us that we can't know anything unrelated to experience, can we have hypotheses, guesses, or opinions about such matters? We can only imagine a thing that would be a possible object of experience. The hypotheses of God or a soul cannot be dogmatically affirmed or denied, but we have a practical interest in their existence. It is therefore up to an opponent to prove that they don't exist. Such hypotheses can be used to expose the pretensions of dogmatism. Kant explicitly praises Hume on his critique of religion for being beyond the field of natural science. However, Kant goes so far and not further in praising Hume basically because of Hume's skepticism. If only Hume would be critical rather than skeptical, Kant would be all-praises. In concluding that there is no polemical use of pure reason, Kant also concludes there is no skeptical use of pure reason. In section II, the discipline of pure reason in polemics, in a special section, skepticism not a permanent state for human reason, Kant mentions Hume but denies the possibility that skepticism could possibly be the final end of reason or could possibly serve its best interests.[65] Proofs of transcendental propositions about pure reason (God, soul, free will, causality, simplicity) must first prove whether the concept is valid. Reason should be moderated and not asked to perform beyond its power. The three rules of the proofs of pure reason are: (1) consider the legitimacy of your principles, (2) each proposition can have only one proof because it is based on one concept and its general object, and (3) only direct proofs can be used, never indirect proofs (e.g., a proposition is true because its opposite is false). By attempting to directly prove transcendental assertions, it will become clear that pure reason can gain no speculative knowledge and must restrict itself to practical, moral principles. The dogmatic use of reason is called into question by the skeptical use of reason but skepticism does not present a permanent state for human reason. Kant proposes instead a critique of pure reason by means of which the limitations of reason are clearly established and the field of knowledge is circumscribed by experience. According to the rationalists and skeptics, there are analytic judgments a priori and synthetic judgments a posteriori. Analytic judgments a posteriori do not really exist. Added to all these rational judgments is Kant's great discovery of the synthetic judgment a priori.[66] The canon of pure reason The canon of pure reason is a discipline for the limitation of pure reason. The analytic part of logic in general is a canon for the understanding and reason in general. However, the Transcendental Analytic is a canon of the pure understanding for only the pure understanding is able to judge synthetically a priori.[67] The speculative propositions of God, immortal soul, and free will have no cognitive use but are valuable to our moral interest. In pure philosophy, reason is morally (practically) concerned with what ought to be done if the will is free, if there is a God, and if there is a future world. Yet, in its actual practical employment and use, reason is only concerned with the existence of God and a future life. Basically, the canon of pure reason deals with two questions: Is there a God? Is there a future life? These questions are translated by the canon of pure reason into two criteria: What ought I to do? and What may I hope for? yielding the postulates of God's own existence and a future life, or life in the future.[68] The greatest advantage of the philosophy of pure reason is negative, the prevention of error. Yet moral reason can provide positive knowledge. There can't be a canon, or system of a priori principles, for the correct use of speculative reason. However, there can be a canon for the practical (moral) use of reason. Reason has three main questions and answers: What can I know? We cannot know, through reason, anything that can't be a possible sense experience; ("that all our knowledge begins with experience there can be no doubt") What should I do? Do that which will make you deserve happiness; What may I hope? We can hope to be happy as far as we have made ourselves deserving of it through our conduct. Reason tells us that there is a God, the supreme good, who arranges a future life in a moral world. If not, moral laws would be idle fantasies. Our happiness in that intelligible world will exactly depend on how we have made ourselves worthy of being happy. The union of speculative and practical reason occurs when we see God's reason and purpose in nature's unity of design or general system of ends. The speculative extension of reason is severely limited in the transcendental dialectics of the Critique of Pure Reason, which Kant would later fully explore in the Critique of Practical Reason.[69] In the transcendental use of reason, there can be neither opinion nor knowledge. Reason results in a strong belief in the unity of design and purpose in nature. This unity requires a wise God who provides a future life for the human soul. Such a strong belief rests on moral certainty, not logical certainty. Even if a person has no moral beliefs, the fear of God and a future life acts as a deterrent to evil acts, because no one can prove the non-existence of God and an afterlife. Does all of this philosophy merely lead to two articles of faith, namely, God and the immortal soul? With regard to these essential interests of human nature, the highest philosophy can achieve no more than the guidance, which belongs to the pure understanding. Some would even go so far as to interpret the Transcendental Analytic of the Critique of Pure Reason as a return to the Cartesian epistemological tradition and a search for truth through certainty.[70] The architectonic of pure reason All knowledge from pure reason is architectonic in that it is a systematic unity. The entire system of metaphysic consists of: (1.) Ontology—objects in general; (2.) Rational Physiology—given objects; (3.) Rational cosmology—the whole world; (4.) Rational Theology—God. Metaphysic supports religion and curbs the extravagant use of reason beyond possible experience. The components of metaphysic are criticism, metaphysic of nature, and metaphysic of morals. These constitute philosophy in the genuine sense of the word. It uses science to gain wisdom. Metaphysic investigates reason, which is the foundation of science. Its censorship of reason promotes order and harmony in science and maintains metaphysic's main purpose, which is general happiness. In chapter III, the architectonic of pure reason, Kant defines metaphysics as the critique of pure reason in relation to pure a priori knowledge. Morals, analytics and dialectics for Kant constitute metaphysics, which is philosophy and the highest achievement of human reason.[71] 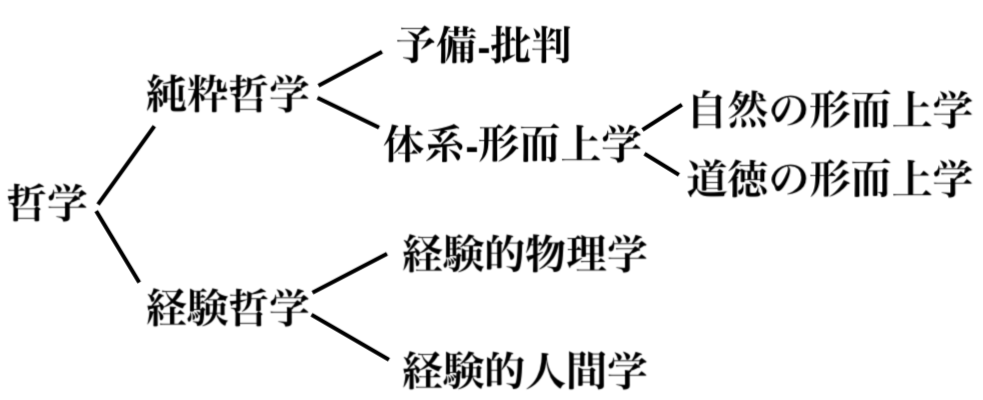 The history of pure reason Kant writes that metaphysics began with the study of the belief in God and the nature of a future world, beyond this immediate world as we know it, in our common sense. It was concluded early that good conduct would result in happiness in another world as arranged by God. The object of rational knowledge was investigated by sensualists (Epicurus), and intellectualists (Plato). Sensualists claimed that only the objects of the senses are real. Intellectualists asserted that true objects are known only by the understanding mind. Aristotle and Locke thought that the pure concepts of reason are derived only from experience. Plato and Leibniz contended that they come from reason, not sense experience, which is illusory. Epicurus never speculated beyond the limits of experience. Locke, however, said that the existence of God and the immortality of the soul could be proven. Those who follow the naturalistic method of studying the problems of pure reason use their common, sound, or healthy reason, not scientific speculation. Others, who use the scientific method, are either dogmatists (Wolff) or skeptics (Hume). In Kant's view, all of the above methods are faulty. The method of criticism remains as the path toward the completely satisfying answers to the metaphysical questions about God and the future life in another world. |
II. 方法の超越論的教義 批評』の第2巻は、純粋理性の完全な体系の形式的条件を明らかにしようとするもので、この2冊の中では圧倒的に短い。 超越論的弁証法』においてカントは、純粋理性が経験と関連していないときに、いかに不適切に使用されるかを示した。超越論の方法』では、純粋理性の適切な 使い方を説明した。 純粋理性の鍛錬 純粋理性批判』の第Ⅱ部「方法の超越論的規律」の第1章「教条主義の領域における純粋理性の規律」において、カントは数学理論と哲学の関係について最も広 範な議論に入る[63]。 規律とは、哲学的純粋理性が可能な感覚的経験の限界を超えて自らを適用することを防ぐための、注意と自己検討による抑制である。哲学は独断的な確信を持つ ことはできない。哲学は数学とは異なり、定義や公理や実証を持つことはできない。すべての哲学的概念は、最終的には事後的な経験的直観に基づかなければな らない。これは、代数学や幾何学が記号方程式や空間図形といったアプリオリな直観から導かれる概念を用いるのとは異なる。この節におけるカントの基本的な 意図は、理性がすでに確立された限界を超えてはならない理由を述べることである。第I章、教条主義の領域における純粋理性の規律において、カントは、数学 ができることを哲学ができない理由を、その類似性にもかかわらず明確に説明している。カントはまた、理性が自らの限界を超えると独断的になると説明する。 カントにとって、理性の限界は経験の分野にあり、結局のところ、すべての知識は経験に依存しているからである。カントによれば、独断的な言明とは、理性が 経験の限界を超えているにもかかわらず真であると認める言明のことである[64]。 純粋理性の極論的な使用には自制が必要である。カントはこの極論的使用を独断的否定に対する防御と定義した。例えば、神が存在することや魂が不滅であるこ とが独断的に肯定される場合、神は存在しないことや魂は不滅ではないという独断的な否定がなされる可能性がある。そのような独断的な主張は証明できない。 その発言は可能な経験に基づくものではない。第II部、極論における純粋理性の規律において、カントは純粋理性の極論的な使用に強く反対している。理性の 独断的な使用とは、理性の枠を超えた発言を真実として受け入れることであり、一方、理性の極論的な使用とは、そのような発言に対して提起されうるいかなる 攻撃に対しても、そのような発言を防衛することである。カントにとって、純粋理性の極論的使用はありえない。カントは純粋理性の極論的使用に反対し、対立 者が経験の境界を超えた問題に基づく合理的な論争を行うことはできないという理由で、それが不適切であると考える[64]。 カントは、敵対者は自由に理性を語ることを許されるべきであると主張した。その見返りとして、彼らは理性によって対抗されるべきである。弁証法的な争いは 理性の知識を増大させる。しかし、理性の独断的な極論的使用はあってはならない。純粋理性の批評は、理性のすべての論争の法廷である。それは理性の権利全 般を決定する。私たちは自分の考えや疑念を率直に述べることができるはずです。それが洞察力の向上につながる。私たちは、可能な経験と関連づけることので きない、対立する教条的な主張という形の極論を排除すべきである。 カントによれば、理性の検閲とは、理性を吟味し、叱責することである。このような検閲は疑念と懐疑につながる。独断論が対立する主張を生み出した後には、 通常懐疑論が生じる。懐疑主義による疑念は、理性を教条主義から目覚めさせ、理性の権利と限界の検証をもたらす。独断論と懐疑論の次のステップに進む必要 がある。それが批判へのステップである。批判によって、私たちの知識の限界は、単なる個人的な経験からではなく、原理から証明される。 もし理性批判が、経験と無関係なことは何も知ることができないと教えてくれるなら、そのような事柄について仮説や推測や意見を持つことができるだろうか。 私たちが想像できるのは、経験の対象となりうるものだけである。神や魂という仮説を教条的に肯定したり否定したりすることはできないが、私たちはその存在 に実際的な関心を持っている。したがって、それらが存在しないことを証明するのは相手次第である。このような仮説は、独断論の虚勢を暴くために利用でき る。カントは、ヒュームが宗教を自然科学の範疇を超えていると批判したことについて、明確に賞賛している。しかし、カントがヒュームを賞賛するのは、基本 的にヒュームの懐疑主義が原因である。ヒュームが懐疑的でなく批判的でありさえすれば、カントは全面的に賞賛しただろう。純粋理性の極論的な使用はないと 結論づけることで、カントは純粋理性の懐疑的な使用もないと結論づける。第II節、極論における純粋理性の規律、特別節、懐疑主義は人間の理性にとって永 続的な状態ではない、において、カントはヒュームに言及しているが、懐疑主義が理性の最終的な目的である可能性や、理性の最善の利益に役立つ可能性を否定 している[65]。 純粋理性に関する超越論的命題(神、魂、自由意志、因果性、単純性)の証明は、まずその概念が妥当かどうかを証明しなければならない。理性は節度あるもの であるべきであり、その力を超えた働きを求めてはならない。純粋理性の証明には3つのルールがある: (1) 原理の正当性を考慮する、(2) 一つの命題は一つの概念とその一般的な対象に基づいているため、一つの証明しかできない、(3) 直接的な証明しか使用できず、間接的な証明(例えば、ある命題はその反対が偽であるから真である)は決してできない。超越論的な主張を直接証明しようとす ることで、純粋理性は思弁的な知識を得ることができず、実践的で道徳的な原則に自らを限定しなければならないことが明らかになる。理性の独断的な使用は、 理性の懐疑的な使用によって疑問視されるが、懐疑主義は人間の理性にとって恒久的な状態を提示するものではない。カントは、理性の限界を明確にし、知識の 領域を経験によって限定することによって、純粋理性の批判を提案する。合理主義者と懐疑主義者によれば、先験的な分析的判断と事後的な総合的判断がある。 事後的な分析的判断は実際には存在しない。これらすべての合理的判断に加えられるのが、カントの偉大な発見である合成的判断のアプリオリである[66]。 純粋理性の公準 純粋理性の公準は、純粋理性の制限のための規律である。論理学全般の分析的な部分は、理解と理性全般のための公準である。しかしながら、超越論的分析法は 純粋理解の公準であり、純粋理解のみが先験的に総合的に判断することができるからである[67]。 神、不滅の魂、自由意志という思弁的命題は、認識的な用途は持たないが、我々の道徳的関心にとっては価値がある。純粋哲学において理性は、意志が自由であ るならば、神が存在するのならば、そして未来の世界が存在するのならば、何をなすべきかについて道徳的(実践的)に関心を抱いている。しかし、理性は、そ の実際の実践的な使用において、神と未来世の存在にしか関心を示さない。基本的に、純粋理性の公準は2つの問いを扱っている: 神は存在するか?神は存在するか?これらの疑問は、純粋理性の公準によって2つの基準に変換される: これらの問いは、純粋理性の公準によって、「私は何をなすべきか」と「私は何を望むべきか」という二つの基準に変換され、神自身の存在と未来の生、すなわ ち未来における生という仮定が導き出される[68]。 純粋理性の哲学の最大の利点は、誤りを防ぐという否定的なものである。しかし道徳的理性は肯定的な知識を提供することができる。思弁的理性を正しく使用す るための規範、すなわちアプリオリな原則の体系は存在しえない。しかし、理性の実際的な(道徳的な)使用のための規範は存在しうる。 理性には3つの主要な問いと答えがある: 何を知ることができるか?私たちは理性によって、感覚的経験であり得ないものを知ることはできない(「私たちの知識はすべて経験から始まることに疑いの余 地はない」)。 私は何をすべきでしょうか?幸福に値することをしなさい; 何を望むべきか?私たちは、自分の行いを通して自分自身を幸福に値するものにした限りにおいて、幸福になることを望むことができる。 理性は、至高の善である神が存在し、その神が道徳的な世界における未来の人生を手配していることを教えてくれる。もしそうでなければ、道徳律は空虚な空想 にすぎない。その理解可能な世界における私たちの幸福は、私たち自身がいかにして幸福であるにふさわしい存在となったかによって決まるのである。思弁的な 理性と実践的な理性の結合は、自然の統一的な設計や一般的な目的の体系に神の理性と目的を見出すときに起こる。理性の思弁的な拡張は、『純粋理性批判』の 超越論的弁証法においては厳しく制限されており、カントは後に『実践理性批判』においてそれを完全に探求することになる[69]。 理性の超越論的使用においては、意見も知識もありえない。理性は結果として、自然における設計と目的の統一性を強く信じることになる。この統一性は、人間 の魂に未来の生命を与える賢明な神を必要とする。このような強い信念は、論理的な確信ではなく、道徳的な確信に基づいている。たとえ道徳的な信念がなくて も、神と来世が存在しないことを証明することは誰にもできないからだ。この哲学はすべて、神と不滅の魂という2つの信仰につながるだけなのだろうか。人間 の本質的な関心事であるこれらについて、最高の哲学が達成できるのは、純粋な理解に属する導きだけである。純粋理性批判の超越論的分析は、デカルトの認識 論的伝統への回帰であり、確実性による真理の探求であると解釈する者さえいる[70]。 純粋理性の建築学 純粋理性からの知識はすべて、体系的な統一体であるという点で建築的である。形而上学の体系全体は以下からなる: (1.) 存在論-対象一般、(2.) 理性的生理学-与えられた対象、(3.) 理性的宇宙論-世界全体、(4.) 理性的神学-神。形而上学は宗教を支え、可能な経験を超えた理性の贅沢な使用を抑制する。形而上学の構成要素は、批評、自然の形而上学、道徳の形而上学で ある。これらが真の意味での哲学を構成している。哲学は科学を用いて知恵を得る。形而上学は科学の基礎である理性を調査する。理性の検閲は科学の秩序と調 和を促進し、形而上学の主目的である一般的な幸福を維持する。第III章「純粋理性の建築学」において、カントは形而上学を純粋な先験的知識との関係にお ける純粋理性の批評として定義している。カントにとっての道徳、分析学、弁証法は形而上学を構成し、それは哲学であり、人間の理性の最高の成果である [71]。 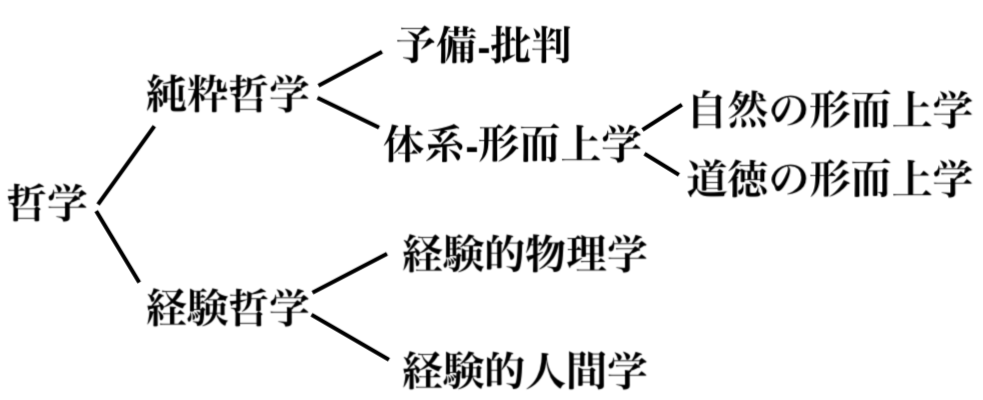 純粋理性の歴史 カントは、形而上学は、神への信仰と、私たちの常識の中で、私たちが知っているこの目の前の世界を超えた未来の世界の性質についての研究から始まったと書 いている。善い行いをすれば、神の定めた別の世界で幸福になるという結論が早くから得られていた。理性的知識の対象は、官能主義者(エピクロス)と知識主 義者(プラトン)によって研究された。官能主義者は、感覚の対象のみが実在すると主張した。知識主義者は、真の対象は理解する心によってのみ知ることがで きると主張した。アリストテレスとロックは、理性の純粋概念は経験にのみ由来すると考えた。プラトンとライプニッツは、理性は感覚から来るものであり、感 覚は幻想であると主張した。エピクロスは経験の限界を超えて思索することはなかった。しかしロックは、神の存在と魂の不滅性は証明できると述べた。純粋理 性の問題を研究する自然主義的手法に従う人々は、科学的推測ではなく、一般的で健全な理性を用いる。科学的方法を用いる者は、独断論者(ヴォルフ)か懐疑 論者(ヒューム)である。カントの考えでは、上記の方法はすべて誤りである。批評の方法は、神と別の世界での未来の生活についての形而上学的な疑問に対す る完全に満足のいく答えを得るための道として残っている。 |
| Terms and phrases a priori versus a posteriori Analytic versus synthetic Appearance Category concept versus object of sense perception Empirical versus pure intuition Manifold of the appearances Object Phenomena versus noumena Schema Transcendental idealism variant translations of Vorstellung: presentation or representation Intuition and concept Kant distinguishes between two different fundamental types of representation: intuitions and concepts: Concepts are "mediate representations" (see A68/B93). Mediate representations represent things by representing general characteristics of things. For example, consider a particular chair. The concepts "brown," "wooden," "chair," and so forth are, according to Kant, mediate representations of the chair. They can represent the chair by representing general characteristics of the chair: being brown, being wooden, being a chair, and so forth. Intuitions are "immediate representations" (see B41), that is, representations that represent things directly. One's perception of the chair is, according to Kant, an immediate representation. The perception represents the chair directly, and not by means of any general characteristics. 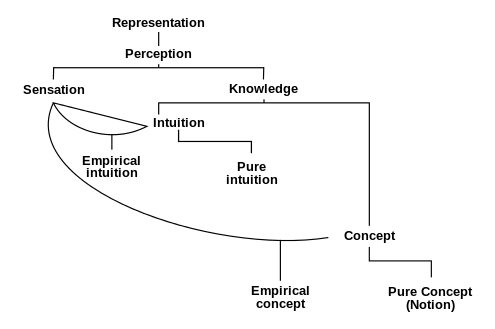 A diagram of Immanuel Kant's system of thought Kant divides intuitions in the following ways: Kant distinguishes intuitions into pure intuitions and empirical intuitions. Empirical intuitions are intuitions that contain sensation. Pure intuitions are intuitions that do not contain any sensation (A50/B74). An example of an empirical intuition would be one's perception of a chair or another physical object. All such intuitions are immediate representations that have sensation as part of the content of the representation. The pure intuitions are, according to Kant, those of space and time, which are our mind's subjective condition of coordinating sensibilia. Our representations of space and time are not objective and real, but immediate representations that do not include sensation within those representations. Thus both are pure intuitions. Kant also divides intuitions into two groups in another way. Some intuitions require the presence of their object, i.e. of the thing represented by the intuition. Other intuitions do not. (The best source for these distinctions is Kant's Lectures on Metaphysics.) We might think of these in non-Kantian terms as first, perceptions, and second, imaginations (see B151). An example of the former: one's perception of a chair. An example of the latter: one's memory (Gedachtnis/Erinnerung) of a chair that has subsequently been destroyed. Throughout the Transcendental Aesthetic, Kant seems to restrict his discussion to intuitions of the former type: intuitions that require the presence of their object. Kant also distinguished between a priori (pure) and a posteriori (empirical) concepts. Tables of principles and categories of understanding in the critique Kant borrowed the term categories from Aristotle, but with the concession that Aristotle's own categorizations were faulty. Aristotle's imperfection is apparent from his inclusion of "some modes of pure sensibility (quando, ubi, situs, also prius, simul), also an empirical concept (motus), none of which can belong to this genealogical register of the understanding." Kant's divisions, however, are guided by his search in the mind for what makes synthetic a priori judgments possible.[citation needed] |
用語とフレーズ アプリオリ対ポストステリオリ分析的対総合的 外観 カテゴリー 概念対感覚知覚の対象経験的対純粋 直観 外観の多様体 対象 現象対現象 シェーマ 超越論的観念論 Vorstellungの異訳:提示または表象 直観と概念 カントは、直観と概念という2つの異なる基本的な表象を区別している: 概念は「媒介表象」である(A68/B93参照)。媒介的表象は、事物の一般的な特徴を表象することによって事物を表象する。例えば、ある椅子を考えてみ よう。茶色」「木製」「椅子」などの概念は、カントによれば、椅子の媒介表象である。茶色であること、木製であること、椅子であることなど、椅子の一般的 な特徴を表すことによって、椅子を表象することができる。 直観は「即時表象」(B41 参照)であり、物事を直接的に表象するものである。カントによれば、椅子に対する知覚は即時表象である。知覚は椅子を直接的に表象するのであって、一般的 な特徴によって表象するのではない。 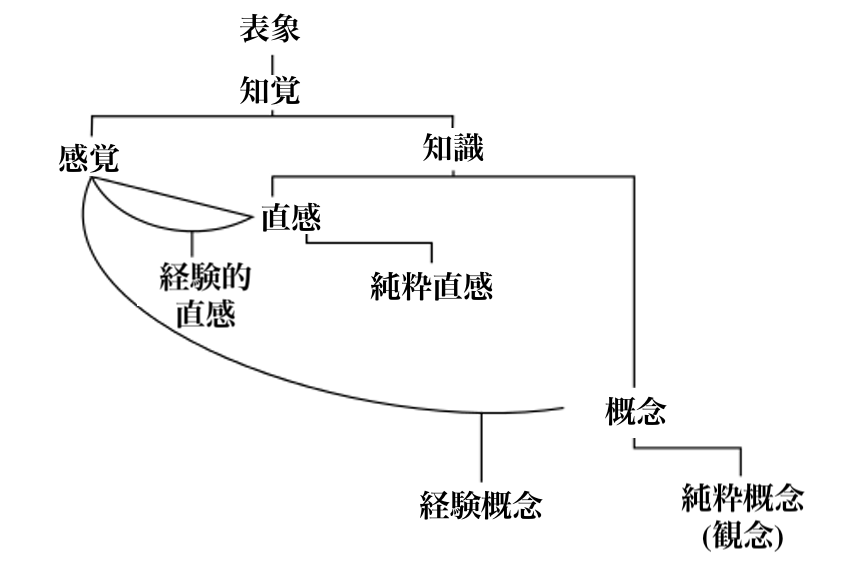 イマヌエル・カントの思考体系図 カントは直観を次のように分けている:カントは直観を純粋直観と経験的直観に区別する。経験的直観とは、感覚を含む直観である。純粋直観とは感覚を含まな い直観である(A50/B74)。経験的直観の例としては、椅子や他の物理的物体に対する知覚がある。このような直観はすべて、感覚を表象の内容の一部と する即時的表象である。カントによれば、純粋直観とは空間と時間の直観であり、感覚を調整する我々の心の主観的条件である。空間と時間の表象は、客観的で 実在的なものではなく、感覚を含まない即時的な表象である。したがって、どちらも純粋な直観である。 カントはまた別の方法で直観を2つのグループに分けている。ある直観はその対象、すなわち直観によって表象されるものの存在を必要とする。他の直観はそう ではない。(これらの区別をカント以外の用語で考えると、第一に知覚、第二に想像となる(B151参照)。前者の例:椅子の知覚。後者の例としては、破壊 された椅子の記憶(Gedachtnis/Erinnerung)が挙げられる。超越論的美学(感性論)』全体を通して、カントは前者のタイプの直観、つまり対象の 存在を必要とする直観に議論を限定しているようである。 カントはまた、アプリオリ(純粋)概念とポスト・プリオリ(経験的)概念を区別した。批評における原理と理解のカテゴリーの表 カントはアリストテレスからカテゴリーという用語を借用したが、アリストテレス自身のカテゴリー化が欠陥のあるものであったことを認めた。アリストテレス の不完全さは、彼が「純粋感覚のいくつかの様式(quando、ubi、situs、またprius、simul)、経験的概念(motus)を含んでい ることから明らかである。 しかし、カントの区分は、合成的アプリオリ判断を可能にするものを心の中で探求することによって導かれる[要出典]。 |
| Reception Early responses: 1781–1793 The Critique of Pure Reason was the first of Kant's works to become famous.[72] According to the philosopher Frederick C. Beiser, it helped to discredit rationalist metaphysics of the kind associated with Leibniz and Wolff which had appeared to provide a priori knowledge of the existence of God, although Beiser notes that this school of thought was already in decline by the time the Critique of Pure Reason was published. In his view, Kant's philosophy became successful in the early 1790s partly because Kant's doctrine of "practical faith" seemed to provide a justification for moral, religious, and political beliefs without an a priori knowledge of God.[73] However, the Critique of Pure Reason received little attention when it was first published. Kant did not expect reviews from anyone qualified to appraise the work, and initially heard only complaints about its obscurity. The theologian and philosopher Johann Friedrich Schultz wrote that the public saw the work as "a sealed book" consisting in nothing but "hieroglyphics". The first review appeared in the Zugaben zu den Göttinger gelehrte Anzeigen in 1782. The review, which denied that there is any distinction between Kant's idealism and that of Berkeley, was anonymous and became notorious. Kant reformulated his views because of it, redefining his transcendental idealism in the Prolegomena to Any Future Metaphysics (1783) and the second edition of the Critique of Pure Reason. The review was denounced by Kant, but defended by Kant's empiricist critics, and the resulting controversy drew attention to the Critique of Pure Reason.[74] Kant believed that the anonymous review was biased and deliberately misunderstood his views. He discussed it in an appendix of the Prolegomena, accusing its author of failing to understand or even address the main issue addressed in the Critique of Pure Reason, the possibility of synthetic a priori judgments, and insisting on the distinction between transcendental idealism and the idealism of Berkeley. In a letter to Kant, the philosopher Christian Garve admitted to having written the review, which he disowned due to editorial changes outside his control. Though Garve did not inform Kant of this, the changes were made by J. G. Feder. Following the controversy over Garve's review, there were no more reviews of the Critique of Pure Reason in 1782 except for a brief notice. The work received greater attention only in 1784, when Shultz's commentary was published and a review by the philosopher and historian of philosophy Dietrich Tiedemann was published in the Hessische Beyträge zur Gelehrsamkeit und Kunst. Tiedemann attacked the possibility of the synthetic a priori and defended the possibility of metaphysics. He denied the synthetic status of mathematical judgments, maintaining that they can be shown to be analytic if the subject term is analyzed in full detail, and criticized Kant's theory of the a priori nature of space, asking how it was possible to distinguish one place from another when the parts of absolute space are identical in themselves. Kant issued a hostile reaction. He maintained that Tiedemann did not understand the problems facing the critical philosophy.[75] Christian Gottlieb Selle, an empiricist critic of Kant influenced by Locke to whom Kant had sent one of the complimentary copies of the Critique of Pure Reason, was disappointed by the work, considering it a reversion to rationalism and scholasticism, and began a polemical campaign against Kant, arguing against the possibility of all a priori knowledge. His writings received widespread attention and created controversy. Though Kant was unable to write a reply to Selle, he did engage in a public dispute with Feder, after learning of Feder's role in the review published in Zugaben zu den Göttinger Gelehrten Anzeigen. In 1788, Feder published Ueber Raum und Causalität: Zur Prüfung der kantischen Philosophie, a polemic against the Critique of Pure Reason in which he argued that Kant employed a "dogmatic method" and was still employing the methodology of rationalist metaphysics, and that Kant's transcendental philosophy transcends the limits of possible experience. Feder believed that Kant's fundamental error was his contempt for "empirical philosophy", which explains the faculty of knowledge according to the laws of nature. With Christian Meiners, he edited a journal, the Philosophische Bibliothek, opposed to Kantianism.[76] Feder's campaign against Kant was unsuccessful and the Philosophische Bibliothek ceased publication after only a few issues. Other critics of Kant continued to argue against the Critique of Pure Reason, with Gottlob August Tittel, who was influenced by Locke, publishing several polemics against Kant, who, although worried by some of Tittel's criticisms, addressed him only in a footnote in the preface to the Critique of Practical Reason. Tittel was one of the first to make criticisms of Kant, such as those concerning Kant's table of categories, the categorical imperative, and the problem of applying the categories to experience, that have continued to be influential. The philosopher Adam Weishaupt, founder and leader of the secret society the Illuminati, and an ally of Feder, also published several polemics against Kant, which attracted controversy and generated excitement. Weishaupt charged that Kant's philosophy leads to complete subjectivism and the denial of all reality independent of passing states of consciousness, a view he considered self-refuting. Herman Andreas Pistorius was another empiricist critic of Kant. Kant took Pistorius more seriously than his other critics and believed that he had made some of the most important objections to the Critique of Pure Reason. Beiser writes that many sections of the Critique of Practical Reason are "disguised polemics against Pistorius". Pistorius argued that, if Kant were consistent, his form of idealism would not be an improvement over that of Berkeley, and that Kant's philosophy contains internal contradictions.[77] Though the followers of Wolff, such as J. G. E. Maass, J. F. Flatt, and J. A. Ulrich, initially ignored the Critique of Pure Reason, they began to publish polemics against Kant in 1788. The theologian Johann Augustus Eberhard began to publish the Philosophisches Magazin, which was dedicated to defending Wolff's philosophy. The Wolffian critics argued that Kant's philosophy inevitably ends in skepticism and the impossibility of knowledge, defending the possibility of rational knowledge of the supersensible world as the only way of avoiding solipsism. They maintained that the criterion Kant proposed to distinguish between analytic and synthetic judgments had been known to Leibniz and was useless, since it was too vague to determine which judgments are analytic or synthetic in specific cases.[citation needed] These arguments led to a controversy between the Wolffians and Kant's followers over the originality and adequacy of Kant's criterion. The Wolffian campaign against Kant was ultimately unsuccessful. Beiser argues that the decisive reason for Kant's victory over the Wolffians was the French Revolution, writing that, "The political revolution in France seemed to find its abstract formulation with the philosophical revolution in Germany." Specifically, he concludes that the principle of autonomy, which has an important role in Kant's ethics, appeared to express and justify the egalitarian demands behind the French Revolution.[78] Later responses The Critique of Pure Reason has exerted an enduring influence on Western philosophy.[79] The constructive aspect of the work, Kant's attempt to ground the conditions for the possibility of objects in the conditions of experience, helped bring about the development of German idealism. The work also influenced Young Hegelians such as Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach and Karl Marx, and also, Friedrich Nietzsche, whose philosophy has been seen as a form of "radical Kantianism" by Howard Caygill. Other interpretations of the Critique by philosophers and historians of philosophy have stressed different aspects of the work. The late 19th-century neo-Kantians Hermann Cohen and Heinrich Rickert focused on its philosophical justification of science, Martin Heidegger and Heinz Heimsoeth on aspects of ontology, and Peter Strawson on the limits of reason within the boundaries of sensory experience. Hannah Arendt and Jean-François Lyotard dealt with its work of orientation of a limited understanding in the field of world history.[80] According to Homer W. Smith, Kant's Critique of Pure Reason is important because it threw the philosophy of the nineteenth century into a state of temporary confusion. That it failed to prove its cardinal point, the existence of a priori truths, rapidly became clear. If there were no promises the fulfillment of which was to be expected, 'lying' would indeed be a universal law of action, and by Kant's own criterion lying would now be moral, and it would be truth that would be immoral.[81] |
受容 初期の反応 1781-1793 哲学者のフレデリック・C・バイザーによれば、『純粋理性批判』は、神の存在に関する先験的知識を提供するように思われたライプニッツやヴォルフに関連す る合理主義的形而上学を貶めるのに役立ったという。彼の見解によれば、カントの哲学が1790年代初頭に成功を収めたのは、カントの「実践的信仰」の教義 が、神についてのアプリオリな知識がなくても道徳的、宗教的、政治的信念を正当化できるように思われたからである。カントはこの著作を評価する資格のある 人からの批評を期待しておらず、当初はその不明瞭さについての苦情を聞くだけであった。神学者であり哲学者でもあったヨハン・フリードリヒ・シュルツは、 世間はこの著作を「象形文字」だけで構成された「封印された書物」と見ていると書いた。最初の書評は1782年の『Zugaben zu den Göttinger gelehrte Anzeigen』に掲載された。この書評は、カントの観念論とバークレーの観念論との間に区別があることを否定するもので、匿名で掲載され、悪名高いも のとなった。カントはこの批評によって自らの見解を改め、『未来の形而上学へのプロレゴメナ』(1783年)と『純粋理性批判』第2版で超越論的観念論を 再定義した。この批評はカントによって糾弾されたが、カントの経験主義批判者たちによって擁護され、その結果起こった論争は『純粋理性批判』に注目を集め ることになった[74]。 カントはこの匿名の批評が偏ったものであり、意図的に自分の見解を誤解していると考えた。彼は『プロレゴメナ』の付録でこの書評について論じ、その著者が 『純粋理性批判』で扱われている主要な問題、すなわち総合的アプリオリ判断の可能性を理解しておらず、またそれに言及すらしていないと非難し、超越論的観 念論とバークレーの観念論との区別を主張した。哲学者のクリスチャン・ガルヴェは、カント宛の手紙の中で、この書評を書いたことを認めたが、編集上の都合 により、彼はこの書評を否定した。ガルヴェはこのことをカントに知らせなかったが、その変更はJ.G.フェダーによって行われた。ガーヴェの批評をめぐる 論争の後、1782年には『純粋理性批判』に関する批評は、簡単な告知を除いては見られなくなった。シュルツの注釈書が出版され、哲学者・哲学史家である ディートリッヒ・ティーデマンによる書評が『ヘッシッシェ・バイ・トレーゲ・ツア・ゲレフラムケイト・ウント・クンスト』誌に掲載された1784年になっ て初めて、この作品は大きな注目を集めた。ティーデマンは合成的アプリオリの可能性を攻撃し、形而上学の可能性を擁護した。彼は数学的判断の合成的地位を 否定し、対象項を詳細に分析すれば解析的であることを示すことができると主張し、また空間のアプリオリな性質に関するカントの理論を批判し、絶対空間の部 分自体が同一であるのに、どうしてある場所と別の場所を区別することが可能なのかと問うた。カントは敵対的な反応を示した。彼は、ティーデマンは批判哲学 が直面している問題を理解していないと主張した[75]。 カントが『純粋理性批判』の副本を送ったロックの影響を受けた経験主義的なカント批判者であるクリスチャン・ゴットリープ・セーレは、この著作に失望し、 合理主義とスコラ主義への回帰であると考え、先験的知識の可能性に反対してカントに対する論争的なキャンペーンを開始した。彼の著作は広く注目され、論争 を巻き起こした。カントはセーレに返事を書くことはできなかったが、『ゲッティンガー・ゲレハルテン・アンツァイゲン』誌に掲載された批評でフェーダーが 果たした役割を知った後、フェーダーと公の場で論争を繰り広げた。1788年、フェーダーは『存在と因果』(Ueber Raum und Causalität)を出版した: 純粋理性批判』に対する極論で、カントは「教条主義的方法」を採用しており、合理主義的形而上学の方法論を依然として採用していること、カントの超越論的 哲学は可能な経験の限界を超越していることを主張した。フェダーは、カントの根本的な誤りは、自然の法則に従って知識の能力を説明する「経験哲学」を侮蔑 したことにあると考えた。彼はクリスチャン・マイナーズとともに、カント主義に反対する雑誌『哲学書誌』(Philosophische Bibliothek)を編集した[76]。 フェーダーのカント反対運動は失敗に終わり、『哲学書誌』はわずか数号で廃刊となった。ロックの影響を受けたゴットローブ・アウグスト・ティッテルは、カ ントに対するいくつかの論争を発表したが、ティッテルは、ティッテルのいくつかの批判に心を痛めながらも、『実践理性批判』の序文の脚注でカントに言及す るにとどまった。ティテルは、カントの範疇表、定言命法、範疇を経験に適用する問題など、カントに対する批判を最初に行った一人であり、その批判は現在も 影響力を持ち続けている。秘密結社イルミナティの創設者であり、フェーダーの盟友であった哲学者アダム・ヴァイスハウプトもまた、カントに対するいくつか の極論を発表し、論争を巻き起こした。ヴァイスハウプトは、カントの哲学は完全な主観主義につながり、通過する意識状態から独立したすべての現実を否定す るものだと主張した。ヘルマン・アンドレアス・ピストリウスもまた、カントを経験主義的に批判した一人である。カントはピストリウスを他の批判者よりも真 剣に受け止め、彼が『純粋理性批判』に対する最も重要な反論のいくつかを行ったと考えていた。バイザーは、『実践理性批判』の多くの部分は「ピストリウス に対する偽装された極論」であると書いている。ピストリウスは、もしカントが一貫していたとしても、彼の観念論の形式はバークレーの観念論を改善するもの ではなく、カントの哲学は内部矛盾を含んでいると主張した[77]。 J.G.E.マース、J.F.フラット、J.A.ウルリッヒといったヴォルフの信奉者たちは当初『純粋理性批判』を無視していたが、1788年にカントに 対する極論を発表し始めた。神学者ヨハン・アウグスト・エーベルハルトは、ヴォルフの哲学を擁護するための『哲学雑誌』の発行を始めた。ヴォルフ派の批判 者たちは、カントの哲学は必然的に懐疑主義と知の不可能性に帰結すると主張し、超感覚的世界の理性的知の可能性を、独在論を回避する唯一の方法として擁護 した。彼らは、分析的判断と合成的判断を区別するためにカントが提案した基準はライプニッツに知られていたものであり、具体的な場合においてどの判断が分 析的であるか合成的であるかを決定するにはあまりにも曖昧であるため、役に立たないと主張した[citation needed]。これらの議論は、カントの基準の独創性と妥当性をめぐってヴォルフ派とカントの信奉者の間で論争を引き起こした。カントに対するヴォルフ 派のキャンペーンは最終的に失敗に終わった。ベイザーは、カントがヴォルフ派に勝利した決定的な理由はフランス革命であったと主張し、「フランスにおける 政治革命は、ドイツにおける哲学革命によってその抽象的定式を見出したように思われる」と書いている。具体的には、カントの倫理学において重要な役割を持 つ自律性の原理が、フランス革命の背後にある平等主義的な要求を表現し、正当化するように見えたと結論付けている[78]。 後の反応 純粋理性批判』は西洋哲学に永続的な影響を及ぼした[79]。この作品の構成的な側面、すなわち経験の条件の中に対象の可能性の条件を根拠づけるカントの 試みは、ドイツ観念論の発展をもたらすのに役立った。この著作はブルーノ・バウアー、ルートヴィヒ・フォイエルバッハ、カール・マルクスといった若きヘー ゲル主義者たちにも影響を与え、またフリードリヒ・ニーチェにも影響を与えた。哲学者や哲学史家による『批判』のその他の解釈は、この作品のさまざまな側 面を強調してきた。19世紀末の新カント主義者ヘルマン・コーエンとハインリヒ・リッケルトは科学の哲学的正当化に、マルティン・ハイデガーとハインツ・ ハイムスースは存在論の側面に、ピーター・ストローソンは感覚経験の枠内での理性の限界に、それぞれ焦点を当てた。ハンナ・アーレントとジャン=フランソ ワ・リオタールは、世界史の分野における限定された理解の方向付けという仕事を扱った[80]、 カントの『純粋理性批判』が重要なのは、それが19世紀の哲学を一時的な混乱状態に陥れたからである。先験的真理の存在を証明することができなかったこと は、急速に明らかになった。もし期待される成就が約束されていないのであれば、「嘘をつく」ことは確かに行為の普遍的な法則であり、カント自身の基準で は、嘘をつくことは道徳的であり、不道徳であるのは真理であることになる[81]。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Critique_of_Pure_Reason |
|
| 黒崎政男, 2000. 『カント『純粋理性
批判』入門』講談社. プロローグ カントのプロフィール 序章 すべての哲学が失敗した理由 1章 『純粋理性批判』の建築現場 2章 『純粋理性批判』見学ツアー 3章 『純粋理性批判』の動揺 エピローグ カントの広さと深さ 索引 |
黒崎政男, 2000. 『カント『純粋理性 批判』入門』講談社.の読書ノートはこちらです!! |
| 黒崎政男, 2000. 『カント『純粋理性
批判』入門』講談社. プロローグ カントのプロフィール 序章 すべての哲学が失敗した理由 1. 「本当に在る」とはどういうことか 2. 存在するとは近くされることである(実在論と観念論) 3. 感覚のうちになければ知性のうちにない(経験論と合理主義) 1章 『純粋理性批判』の建築現場 1. 導きの糸としての現象 2. 沈黙の十年の苦闘(『批判』成立前後) 3. 伝統的な真理観(理性・知性の優位) 4. 形而上学のすべての秘密を解く鍵 2章 『純粋理性批判』見学ツアー 1. 形而上学とは何か(序文) 2. 時間と空間とは何か(超越論的感性論) 3. 真理とは何か(超越論的分析論) 3. カテゴリーこそ客観的認識の根拠である(超越論的演繹論) 4. 理性そのもののうちに潜む錯誤(超越論的弁証論) 3章 『純粋理性批判』の動揺 A. カントの不安 1. ハイデッガーのカント解釈 2. 感性と悟性の〈共通の根〉 3. イエナ期ヘーゲルの慧眼 B. 理性の深淵 4. 理性のダイナミックな性格 5. 『純粋理性批判』から最晩年『オプス・ポストゥムム』へ 6. 真理は本当に存在するか エピローグ カントの広さと深さ 索引 |
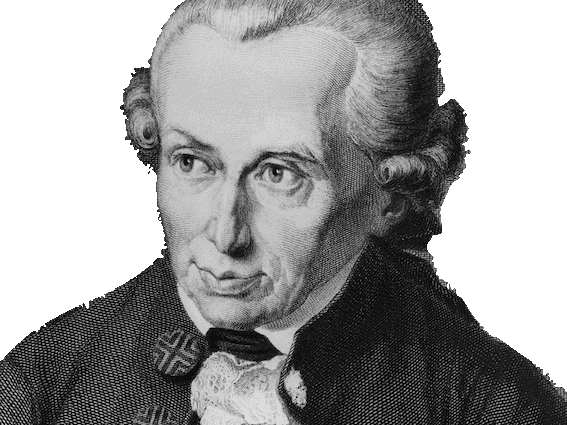 哲
学的実在論(てつがくてきじつざいろん)とは、ある種の事物(数字のような抽象的なものから道徳的な発言から物理的な世界そのものに至るまで幅広い)が
心とは無関係に存在する、つまり、それを知覚する心が存在しない場合でも存在する、あるいはその存在は見る者の目に映る単なる外見に過ぎないとする見解で
ある。実在論はリアリズム(realism)なので、哲学的現実主義、あるいは哲学的リアリズムとも呼ぶことが可能である。この用語は後期ラテン語の
realis「実在」に由来し、1781年にイマヌエル・カントによって抽象的な形而上学的な意味で初めて用いられた(CPR A 369)(だからこの挿絵の顔の人はイマヌエル・カントさんなのである!!)。 哲
学的実在論(てつがくてきじつざいろん)とは、ある種の事物(数字のような抽象的なものから道徳的な発言から物理的な世界そのものに至るまで幅広い)が
心とは無関係に存在する、つまり、それを知覚する心が存在しない場合でも存在する、あるいはその存在は見る者の目に映る単なる外見に過ぎないとする見解で
ある。実在論はリアリズム(realism)なので、哲学的現実主義、あるいは哲学的リアリズムとも呼ぶことが可能である。この用語は後期ラテン語の
realis「実在」に由来し、1781年にイマヌエル・カントによって抽象的な形而上学的な意味で初めて用いられた(CPR A 369)(だからこの挿絵の顔の人はイマヌエル・カントさんなのである!!)。 |

★スタンフォード哲学事典の「カント」のなかの「純粋理性批判」
| 2. 『純粋理性批判』におけるカントのプロジェクト 『純粋理性批判』の主題は、特定の意味で理解される形而上学の可能性である。カントは「経験とは無関係に理性が追求しうる認識」という観点から形而上学を 定義し、この著作における彼の目的は、「形而上学一般の可能性または不可能性についての決定、およびその源泉の決定、さらにその範囲と境界の決定を、すべ て原則から行うこと」(第3部第2章第2項)である。したがって、カントにとって形而上学とは、経験に依存しない知識、すなわち、その正当化が経験に依存 しない知識を意味する。そして、カントは、経験に依存しない知識を理性と関連付けている。『批判』の目的は、人間の理性が経験に依存しない知識をどの程度ま で、どのように、可能であるかを検証することである。 |
序言の見出し(石川文康訳) 1. 純粋な認識と経験論的認識の区別について 2. 我々はある種のア・プリオリな認識をもっており、常識でさえけっしてそれを欠いていない。 3. 哲学はすべてのア・プリオリな認識の可能性、原理、範囲を規定する学問を必要とする。 4. 分析判断と総合判断の区別について 5. 理性のすべての理論的な学問にはア・プリオリな総合判断が原理として含まれている。 6. 純粋理性の一般的な課題 7. 純粋理性批判という名の特殊な学問と区分 |
| 2.1 啓蒙主義の危機 『批判』のプロジェクトをより良く理解するために、この著作が書かれた歴史的および知的背景について考えてみよう。[5] カントは啓蒙主義の末期に『批判』を書いたが、当時、啓蒙主義は危機的状況にあった。 1780年代は、文化のバランスが啓蒙主義からロマン主義へと決定的に変化した過渡期の10年間であったことが、今では振り返って理解できるが、カントに はそのような後知恵はなかった。 啓蒙主義は、16世紀から17世紀にかけての近代科学の台頭と成功に対する反動であった。特にニュートンの目覚ましい功績は、自然を制御し、人間の生活を 向上させる人間の理性の力を広く信頼させ、楽観的な見通しを抱かせた。理性に対するこの新たな信頼のひとつの帰結として、伝統的な権威がますます疑問視さ れるようになった。 もし私たちひとりひとりが、これらのことを自分自身で理解する能力を持っているのであれば、なぜ政治的あるいは宗教的な権威が、私たちがどう生きるべき か、何を信じるべきかを私たちに教える必要があるのだろうか? カントは『批判』の中で、理性の主権に対する啓蒙主義のこの信念を次のように表現している。 我々の時代は批判の時代であり、あらゆるものはそれに従わなければならない。宗教は神聖さによって、立法は威厳によって、一般的にそれら自身をそこから免 除しようとする。しかし、この方法では、それら自身に対して正当な疑いを抱かせ、理性が自由で公の審査に耐えることのできたものだけに与える、偽りのない 敬意を主張することはできない。(Axi 啓蒙とは、他人に考えさせるのではなく、自分で考えることである。「啓蒙とは何か?」によると、 (8:35)。この論文でカントは、進歩の必然性に対する啓蒙思想の信念も表明している。少数の独立した思想家が徐々に幅広い文化運動に影響を与え、最終 的には行動の自由の拡大と政府の改革につながる。「あらゆる事柄において理性を公的に利用する自由」さえあれば、啓蒙文化は「ほぼ必然的」に生まれる (8:36)。 問題は、理性が伝統的な権威に対して完全な主権を享受した場合に、実際に進歩がもたらされるのかどうか、あるいは、理性のみでは唯物論、宿命論、無神論、 懐疑論(Bxxxiv)、さらには放縦主義や権威盲信主義(8:146)にまっしぐらに突き進むのではないか、ということである。啓蒙主義が理性の主権に 託した期待は、理性がこれらの結果を導くことはなく、むしろ伝統が常に是認してきた特定の主要な信念を支持するだろうというものであった。重要なのは、そ れらには神、魂、自由、そして科学と道徳および宗教の調和に対する信念が含まれていたことである。一部の知識人はこれらの信念の一部またはすべてを否定し たが、啓蒙主義の一般的な精神はそれほど急進的なものではなく、特にヨーロッパのドイツ語圏ではそうであった。啓蒙主義は、伝統的な権威を個々人の理性の 権威に置き換えるものではあったが、伝統的な道徳観や宗教観を覆すものではなかった。 しかし、啓蒙主義の原動力となったのは、機械論的な新しい物理学であった。自然が機械論的な因果律によって完全に支配されているとすれば、自由や魂、ある いは運動する物質以外のものは存在しないように思える。これは、道徳には自由が必要だという伝統的な見解を脅かすものであった。私たちは自由でなければ、 何が正しくて何が間違っているのかを選択することができない。そうでなければ、私たちは責任を負うことができないからだ。また、死後も生き続けたり、来世 で復活したりする魂という伝統的な宗教的信念も脅かされた。つまり、啓蒙主義の誇りであり、人間の理性の力を楽観視する源であった近代科学は、自由な理性 的思考が支えるはずであった伝統的な道徳的・宗教的信念を脅かすものとなったのだ。これが啓蒙主義の主な知的危機であった。 『純粋理性批判』は、この危機に対するカントの回答である。その主題は形而上学であり、カントにとって形而上学は理性の領域であり、「純粋理性によって我 々が所有するすべてのものの体系的な目録」である(Axx)。そして、理性の権威が問われていた。カントの主な目的は、伝統的な権威に頼らず、また抑制さ れることなく理性そのものによって理性を批判することが、ニュートン科学と伝統的な道徳および宗教の両方にとって、安全で一貫性のある基盤を確立すること を示すことである。言い換えれば、自由な理性的探究は、これらの人間にとって不可欠な関心事すべてを十分に裏付け、それらが相互に矛盾のないものであるこ とを示す。したがって、理性は啓蒙主義によって与えられた主権に値する。 |
|
| .2 カントの哲学におけるコペルニクス的転回 カントが『批判』においてこの目標を達成しようとした方法を知るには、彼が『初歩の論文』のプラトン主義を否定した根拠について考えることが役立つ。博士 論文もまた、ある意味ではニュートン科学と伝統的な道徳や宗教を調和させようとしているが、その戦略は『批判』とは異なっている。博士論文によれば、 ニュートン科学は、感性によってアクセス可能な感覚的世界において真である。そして、理解力は、神聖な道徳的完全性の原理を、感覚的世界におけるあらゆる ものを測定するための基準となる、明確な理解可能な世界において把握する。したがって、この見解では、感覚可能な世界に関する我々の知識は、感覚に依存し ないため、先験的である。そして、感覚可能な世界自体が、ある意味で感覚不可能な世界に適合または模倣しているため、この先験的知識は感覚可能な世界を判 断する原則となる。 しかし、カントは『序文』を書いた直後に、この見解に疑問を呈している。1772年2月21日付で、友人でありかつての教え子であったマルクス・ヘルツに宛てた手紙の中で、彼は次のように説明している。 私は論文の中で、知的表象の本質を単に否定的な方法で説明することに満足していた。すなわち、それらは対象によってもたらされた魂の変化ではないと述べる ことに満足していた。しかし、対象から何らかの影響を受けることなく対象を参照する表象がどのようにして可能であるかというさらなる疑問については、私は 沈黙していた。[B] それらが私たちに影響を与える方法によってではなく、どのような手段によって、これらの[知的表象]が私たちに与えられるのか?そして、もしこのような知 的表象が我々の内的活動に依存しているとすれば、それらが対象と一致しているはずだという合意はどこから来るのか。それにもかかわらず、それによって対象 が作り出されることはありえない。そして、理解がそのような概念の可能性に関する真の原理をどのように形成するのか、その原理は経験と完全に一致しなけれ ばならず、それにもかかわらず経験とは独立しているのか、というこの問いについては、理解の能力が事物そのものとどのように一致するのか、依然として不明 瞭なままである。(10:130-131) ここでカントは、理解可能な世界についての先験的知識がどのようにして可能なのかについて疑問を抱いている。『序文論文』の立場は、理解可能な世界は人間 の理解力や感覚世界とは独立しており、両者は(異なる方法で)理解可能な世界に適合しているというものである。しかし、感覚世界が理解可能な世界に適合す るとはどういう意味なのかという疑問はさておき、人間の理解力が理解可能な世界に適合したり把握したりすることはどのようにして可能なのか?もし理解可能 な世界が我々の理解とは独立しているとすれば、我々はそれを何らかの形で受動的に影響を受ける場合のみ、それを把握できるということになる。しかしカント にとって感性とは、我々とは独立した対象から受動的に影響を受ける我々の能力である(2:392、A51/B75)。したがって、私たちから独立した理解 可能な世界を把握できる唯一の方法は感性を通してであり、つまり、その世界に関する私たちの知識は先験的であるはずがないということになる。純粋理解のみ によって、せいぜい理解可能な世界の表象を形成できるだけである。しかし、こうした知的表象は完全に「私たちの内的活動に依存する」とカントがヘルツに 語っているように、それらが独立した理解可能な世界に一致するはずだという確かな根拠はない。このような先験的な知的表象は、人間の精神とは独立した何も のにも対応しない脳の産物である可能性もある。いずれにしても、純粋な知的表象と独立した理解可能な世界との間に、いかにして対応関係が生じるのかはまっ たく不可解である。 『批判』におけるカントの戦略は、学位論文における戦略と類似している。両作品とも、近代科学と伝統的な道徳や宗教を、それぞれ明確な感覚世界と理解可能 な世界へと追いやることによって、両者を調和させようとしている。しかし、『批判』では、先験的知識について、より控えめでありながらも革命的な説明がな されている。ヘルツ宛の手紙が示唆しているように、『序文』におけるカントの見解の主な問題点は、人間の精神とはまったく独立した世界に関する先験的知識 の可能性を説明しようとしていることである。これは行き詰まりとなり、カントは、理解可能な世界について先験的知識を持つことができると主張することは二 度となかった。しかし、カントの『批判』における革新的な立場は、感覚的世界は人間の精神から完全に独立しているわけではないため、その一般的な構造につ いて我々は先験的な知識を持つことができるというものである。感覚的世界、すなわち現象界は、受動的に受け取る感覚的事項と、認識能力によって与えられる 先験的な形相の組み合わせから人間の精神によって構成される。感覚的世界の側面について、私たちが先験的な知識を持つことができるのは、私たちの認識能力 によって供給される先験的な形を反映している場合のみである。カントの言葉によれば、「私たちは、自分自身がそれに与えたものだけを、先験的に認識するこ とができる」(Bxviii)。したがって、『批判』によれば、感覚的世界自体が人間の心が経験を構築する方法に依存している場合に限り、またその範囲に おいてのみ、先験的な知識は可能である。 |
|
| カントは『批判』において、この経験に関する新しい構成主義的見解を、天文学におけるコペルニクスの革命との類似性によって特徴づけている。 これまで、我々の認識はすべて対象に適合しなければならないとされてきた。しかし、認識を拡張する概念を通じて、対象について先験的に何かを見つけ出そう とする試みは、すべてこの前提のもとでは失敗に終わっている。それゆえ、対象が我々の認識に適合しなければならないと仮定することで、形而上学の問題から さらに遠くへ到達できるかどうかを一度試してみよう。これは、対象が我々に与えられる前に、対象について何かを確立するという、要求される先験的認識の可 能性によりよく一致するものである。これは、天体の動きの説明でなかなかうまくいかなかったコペルニクスが、天体全体が観察者の周りを回っていると仮定し たときに、観察者を回転させ、星を静止させたままにしておいた方がうまくいくのではないかと考えたときの最初の考え方に似ている。さて、形而上学におい て、我々は対象の直観について同様のことを試みることができる。もし直観が対象の性質に適合しなければならないのであれば、我々がそれらについて先験的に 何かを知ることができるとは思えない。しかし、対象(感覚の対象)が我々の直観の性質に適合するのであれば、私はこの可能性を自分自身に十分に表現するこ とができる。しかし、これらの直観に留まることはできず、もしそれらが認識となるためには、それらを何らかの対象として表象として参照し、それらを通して その対象を決定しなければならない。この決定をもたらす概念も対象に適合していると仮定すれば、再び、それらについてどのようにして先験的に知ることがで きるのかという同じ困難に陥る。あるいは、対象、つまり、それらを認識できる唯一の経験(与えられた対象)が それらを認識(与えられた対象として)できる唯一の経験が、それらの概念に適合していると仮定する。この場合、経験自体が理解を必要とする一種の認識であ るため、私はすぐにこの困難から抜け出す簡単な方法を見出す。なぜなら、経験のすべての対象は、必然的にこの概念に適合しなければならず、これに一致しな ければならないからだ。(Bxvi–xviii) この文章が示唆するように、カントが批判哲学で変更を加えたのは、主に理解の役割と能力に関する見解である。なぜなら、彼はすでに『序文』において、感性 は空間と時間の形式(彼はこれを純粋な(または先験的な)直観と呼ぶ)を感覚世界に対する認識に与えると主張していたからだ。しかし、『批判』は、純粋理 解もまた、理解可能な世界への洞察を与えるのではなく、感覚的世界の認識を構成する純粋概念または先験的概念と呼ばれる形式の提供に限定されると主張して いる。 したがって、感覚と理解の両方が協力して感覚的世界の認識を構成し、それゆえ、感覚の純粋直観と理解の先験的概念という認識能力によって供給される先験的 な形式に適合する。この説明は、天文学におけるコペルニクスの地動説に類似している。なぜなら、どちらも現象の説明に観察者の貢献を考慮する必要がある が、どちらも現象を観察者の貢献のみに還元するものではないからだ。[6] コペルニクスによると、天体現象が地球上でどのように見えるかは、天体の運動と地球の運動の両方に影響される。地球は、他のすべてのものが周回する静止し た天体ではない。カントにとって、同様に、人間の経験における現象は、感受性を通して受動的に受け取る感覚データと、人間の心がその先験的な規則に従って 能動的にデータを処理する方法の両方に依存している。これらの規則は、感覚世界と、その中のすべての対象(または現象)が私たちに現れる一般的な枠組みを 提供する。したがって、感覚世界とその現象は、人間の心から完全に独立しているわけではなく、その基本構造に寄与している。 カントの哲学におけるコペルニクス的転回は、近代科学と伝統的な道徳や宗教を調和させるための『学位論文』の戦略をどのように改善するのだろうか。まず、 カントは近代科学を先験的な基盤に置くための新しい独創的な方法を提示した。彼は、近代科学の基本法則は人間の心が経験を構造化することに寄与した結果で あるため、それらについて先験的な知識を持つことができると主張できる立場にある。言い換えれば、感覚的世界は、あらゆる出来事には原因があるというよう な、ある種の根本法則に必然的に従う。なぜなら、人間の精神がそれらの法則に従ってそれを構築しているからだ。さらに、経験可能な条件を振り返ることに よって、それらの法則を特定することができる。これにより、例えば、あらゆる出来事に原因がないような世界を経験することは不可能であることが明らかにな る。このことから、カントは、感覚可能な世界全体(私たちの実際の経験だけでなく、あらゆる人間の経験)が、必然的に特定の法則に従うという先験的な知識 を持つことができるという意味で、形而上学は確かに可能であると結論づけている。カントは、この形而上学を内在形而上学または経験形而上学と呼んでいる。 なぜなら、それは人間の経験に内在する本質的な原理を扱っているからである。 |
|
| しかし、第二に、「われわれが事物について先験的に認識できるのは、われわれ自身がその事物に与えたものだけである」とすれば、人間の精神とはまったく独 立した存在であり、その本質も独立している事物(カントはこれを「物自体」(Bxviii)と呼ぶ)について、われわれは先験的な知識を持つことはできな い。彼の言葉によれば、「この先験的に認識する能力の推論から、非常に奇妙な結果が導かれる。すなわち、この能力では、可能な経験の限界を越えることは決 してできないということである。また、このような認識は、現象にしか到達できず、物自体はそれ自体で実在するものとして残るが、我々には認識されない」 (Bxix–xx)。つまり、カントの構成主義的な科学的知識の基礎は、科学を現象の領域に制限し、超越論的形而上学、すなわち、人間の経験可能な範囲を 超える事物それ自体に関する先験的知識は不可能であることを意味する。批判』においてカントは、学位論文で擁護した理解可能な世界についての洞察を否定 し、事物それ自体についての知識を否定することが、科学と伝統的な道徳や宗教を調和させるために必要であると主張する。なぜなら、神、自由、不死に対する 信仰は厳密に道徳的な基盤を持つと主張するが、これらの信仰を道徳的な根拠に基づいて採用することは、それらが誤りであることが分かれば正当化されないか らである。「したがって、」とカントは言う。「私は信仰の余地を残すために知識を否定しなければならなかった」(Bxxx)。知識を外見に限定し、神と魂 を不可知な物自体の領域に追いやることによって、神や魂の自由、あるいは不滅性に関する主張を否定できないことが保証される。したがって、道徳的な議論に よって、私たちが信じることを正当化できる。さらに、現代科学の決定論はもはや伝統的な道徳が求める自由を脅かすものではない。なぜなら、科学、ひいては 決定論は外見のみに適用されるものであり、自己や魂が存在する事物そのものの領域には自由の余地があるからだ。私たちは、物自体について何も知ることがで きないため、理論的には、私たちが自由であることを知ることはできない。しかし、人間の自由を信じるには特に強力な道徳的根拠があり、それは他の道徳的根 拠に基づく信念を支える「要石」の役割を果たす(5:3-4)。このようにして、カントは超越形而上学を、彼が「道徳形而上学」と呼ぶ新しい実践科学に置 き換える。つまり、経験(または自然)の形而上学と道徳の形而上学という2種類の形而上学が可能であることが判明した。これらはどちらも、カントの哲学に おけるコペルニクス的転回に依存している。 | |
| https://plato.stanford.edu/entries/kant/#KanProThePurRea |
★カントの知識構成(ヴォルフ学派の影響のもとで——「純粋理性の建築術」『純粋理性批判』)
★想像力(→構想力)
「そ の語源であるドイツ語のEinbildungskraftは英語やフランス語のimaginationに相当し、本来なら「想像力」と訳されるべき言葉だ が、カント研究のコンテクストに限って「構想力」と訳される慣例がある。カントがバウムガルテンの『形而上学』から着想を得たという、人間の一認識能力を 「構想力」と訳す慣習がいつ、誰の手によって定着したのかは判然としないのだが、1929年刊行の岩波文庫版『純粋理性批判』(天野貞祐訳)には早くも 「構想力」という訳語が頻出し、この慣習が古くから存在したことを示している。もっとも、日本の思想史の文脈で言えば、「構想力」から真っ先に想起される のは三木清の『構想力の論理』(岩波書店、1939-1946)であろう。この未完の大作において、三木は「新しいタイプの人間」の創出や「人間再生」の 可能性を模索したが、その規範は最終的には「悟性と感性とを結合する」構想力の機能へと求められることとなった。そして近年、こうした三木のカント解釈は H・アーレントやM・メルロ=ポンティのそれとの類似が指摘されるに至っているが、従来日本のカント研究は圧倒的に『純粋理性批判』を対象とするのが主流 であったため、今後は『判断力批判』を軸とした「構想力」の美的考察が待望される。」→暮沢剛巳「構想力」
※純粋理性批判・第一版のアイディア(ハイデガー『カントと形而上学の問題』)(黒崎 2000:163)
☆冨田恭彦(Yasuhiko TOMITA b.1952)による『純粋理性批判』の批判的読解
| カント批判 : 『純粋理性批判』の論理を問う = Critique of Kant : the logic of the critique of pure reason, reconsidered / 冨田恭彦著, 勁草書房 , 2018 内容説明 「時代の子」としてのカント。その実像とは—カントの超越論的観念論を17〜18世紀の精神史の流れの中で捉え直し、明証必然的な理論を標榜しつつも、実は自然科学の知見を密かな基盤としていたことを明らかにする。 目次 第1章 「独断のまどろみ」からの不可解な「覚醒」—「唯一の原理」への奇妙な道筋 第2章 ロックの反生得説とカントの胚芽生得説—カントが言うほどカントとロックは違うのか? 第3章 カントはロックとヒュームを超えられたのか?—アプリオリ化の実像 第4章 そもそも「演繹」は必要だったのか?—自身の「経験」概念の絶対化 第5章 判断とカテゴリーの恣意的な扱い—カントの隠れ自然主義 第6章 空間の観念化とその代償—議論の浅さとその不整合の意味するもの |
|
| カント入門講義 : 超越論的観念論のロジック / 冨田恭彦著, 筑摩書房 , 2017 . - (ちくま学芸文庫, [ト-9-2]) 内容説明 我々が生きている世界は、心の中の世界=表象にすぎない。その一方で、しかし同時に「物自体」はある、とも言うカントの超越論的観念論。そのカラクリとし て、基本的なものの見方・考え方の枠組みが人間の心にはあらかじめセットされているとカントは強調したわけだが、この点を強調することによって、その哲学 は、後年の哲学者達の思想的転回に大きく貢献したと著者は説く。平明な筆致で知られる著者が、図解も交えてカント哲学の要点を一から説き、各ポイントが現 代の哲学者に至るまでどのような影響を与えてきたかを一望することのできる一冊。 目次 第1章 カント略伝 第2章 なぜ「物自体」vs「表象」なのか? 第3章 解かなければならない問題 第4章 コペルニクス的転回 第5章 「独断のまどろみ」から醒めて 第6章 主観的演繹と図式論 第7章 アプリオリな総合判断はいかにして可能か 第8章 魅力と謎 |
|
| カント哲学の奇妙な歪み : 『純粋理性批判』を読む / 冨田恭彦著, 岩波書店 , 2017 . - (岩波現代全書, 098) 内容説明 近代哲学はカントの認識論で素朴な経験主義を脱し、自然科学から自立したという理解は本当だろうか?哲学史的事情を踏まえるなら、カントの哲学は自然科学 を形而上学によって基礎づけたのではなく、自然科学を基盤としてそれに形而上学の装いを与えたのではなかったか。自然主義と全体論の視点から近世哲学史を 再検討する。 目次 第1章 論理空間が奇妙に歪んでいる—自然主義の伏流(『純粋理性批判』の初期の批評から;ロックとカントは相似形の枠組みの中で考えている ほか) 第2章 物自体はどこから来たのか—仮説的視点の劣化(なにごとも「体験」から?;デカルトの二元論に戻って ほか) 第3章 カントはいわゆる「一般観念」をこのように考えた—図式論の理解のために(英語の読めないカントはイギリス哲学をどのようにして読んだか;概念を直観化することとしての「構成」 ほか) 第4章 「無限判断」とは言うものの—伝統的論理学のよくない使い方(判断の量と質のおさらい;不確定言明とは ほか) 第5章 自然科学なのに無理に形而上学のふりをして—『純粋理性批判』の背面の論理(アプリオリな総合判断には二つの種類がある;「概念から」—形而上学(純粋哲学)の場合 ほか) |
|
| ニーチェによるカント批判——ニーチェ『善悪の彼岸』より |
https://x.gd/tbvQ1 |
| It
seems to me that there is everywhere an attempt at present to divert
attention from the actual influence which Kant exercised on German
philosophy, and especially to ignore prudently the value which he set
upon himself. Kant was first and foremost proud of his Table of
Categories; with it in his hand he said: “This is the most difficult
thing that could ever be undertaken on behalf of metaphysics.” Let us
only understand this “could be”! He was proud of having discovered a
new faculty in man, the faculty of synthetic judgment a priori.
Granting that he deceived himself in this matter; the development and
rapid flourishing of German philosophy depended nevertheless on his
pride, and on the eager rivalry of the younger generation to discover
if possible something—at all events “new faculties”—of which to be
still prouder!—But let us reflect for a moment—it is high time to do
so. “How are synthetic judgments a priori possible?” Kant asks
himself—and what is really his answer? “By means of a means
(faculty)”—but unfortunately not in five words, but so
circumstantially, imposingly, and with such display of German
profundity and verbal flourishes, that one altogether loses sight of
the comical niaiserie allemande involved in such an answer. People were
beside themselves with delight over this new faculty, and the
jubilation reached its climax when Kant further discovered a moral
faculty in man—for at that time Germans were still moral, not yet
dabbling in the “Politics of hard fact.” Then came the honeymoon of
German philosophy. All the young theologians of the Tubingen
institution went immediately into the groves—all seeking for
“faculties.” And what did they not find—in that innocent, rich, and
still youthful period of the German spirit, to which Romanticism, the
malicious fairy, piped and sang, when one could not yet distinguish
between “finding” and “inventing”! Above all a faculty for the
“transcendental”; Schelling christened it, intellectual intuition, and
thereby gratified the most earnest longings of the naturally
pious-inclined Germans. One can do no greater wrong to the whole of
this exuberant and eccentric movement (which was really youthfulness,
notwithstanding that it disguised itself so boldly, in hoary and senile
conceptions), than to take it seriously, or even treat it with moral
indignation. Enough, however—the world grew older, and the dream
vanished. A time came when people rubbed their foreheads, and they
still rub them today. People had been dreaming, and first and
foremost—old Kant. “By means of a means (faculty)”—he had said, or at
least meant to say. But, is that—an answer? An explanation? Or is it
not rather merely a repetition of the question? How does opium induce
sleep? “By means of a means (faculty),” namely the virtus dormitiva,
replies the doctor in Molière, Quia est in eo virtus dormitiva, Cujus est natura sensus assoupire. But such replies belong to the realm of comedy, and it is high time to replace the Kantian question, “How are synthetic judgments a priori possible?” by another question, “Why is belief in such judgments necessary?”—in effect, it is high time that we should understand that such judgments must be believed to be true, for the sake of the preservation of creatures like ourselves; though they still might naturally be false judgments! Or, more plainly spoken, and roughly and readily—synthetic judgments a priori should not “be possible” at all; we have no right to them; in our mouths they are nothing but false judgments. Only, of course, the belief in their truth is necessary, as plausible belief and ocular evidence belonging to the perspective view of life. And finally, to call to mind the enormous influence which “German philosophy”—I hope you understand its right to inverted commas (goosefeet)?—has exercised throughout the whole of Europe, there is no doubt that a certain virtus dormitiva had a share in it; thanks to German philosophy, it was a delight to the noble idlers, the virtuous, the mystics, the artiste, the three-fourths Christians, and the political obscurantists of all nations, to find an antidote to the still overwhelming sensualism which overflowed from the last century into this, in short—“sensus assoupire.” … https://x.gd/tbvQ1 |
私
には、現在、カントがドイツ哲学に与えた実際の影響から注意をそらそうとする試みが至る所で見られるように思える。特に、彼が自らに与えた価値を慎重に無
視しようとする試みだ。カントは、何よりもまず、カテゴリー表を誇りに思っていた。彼は、その表を手にしながら、「これは形而上学のためにこれまでになさ
れた中で最も困難なことだ」と言った。この「~できる」という部分だけを理解しよう。彼は、人間に備わる新しい能力、すなわち先験的総合判断能力を発見し
たことを誇りに思っていた。この点において彼が自らを欺いていたとしても、ドイツ哲学の発展と急速な隆盛は、彼の誇りと、より若い世代がさらに誇れる何か
(少なくとも「新しい能力」)を発見しようという熱心な競争心に依存していた。しかし、少し考えてみよう。今こそ、そうする時が来たのだ。「総合的判断は
どのようにして先験的に可能なのか?」とカントは自問する。そして、彼の答えは実際何なのか?「手段(能力)」によって、と彼は答える。しかし、残念なが
らそれは5つの単語で表現されたものではなく、状況に左右され、威圧的で、ドイツの深遠さと言葉の華麗さを誇示するようなものであり、そのような答えに含
まれるドイツ的な滑稽な気取りを完全に失わせるようなものだった。人々は、この新しい学問分野に狂喜乱舞し、カントがさらに人間に道徳的本能を発見したこ
とで、歓喜は頂点に達した。当時、ドイツ人はまだ道徳的であり、「事実に基づく政治」に手を染めてはいなかったからだ。そして、ドイツ哲学の蜜月時代が訪
れた。テュービンゲンの神学部の若き神学者たちは、すぐに「能力」を求めて森へと向かった。彼らは何を見つけられなかったのか。ロマン主義という悪意に満
ちた妖精が口ずさみ歌う、無邪気で豊かで、まだ若々しいドイツ精神の時代において、「発見」と「発明」の区別がつかない時代において!
とりわけ「超越論」のための能力。シェリングはそれを知的直観と名付け、生まれつき敬虔な傾向を持つドイツ人の最も切実な願いを満たした。この活気に満ち
た奇抜な運動全体(それは、老齢で偏屈な考えを大胆に隠していたにもかかわらず、実際には若々しいものだった)に対して、真剣に受け止めたり、道徳的な憤
りを覚えたりすることほど大きな過ちはない。しかし、もう十分だ。世界は老い、夢は消え去った。人々は額をこすり合わせ、そして今でもこすり合わせてい
る。人々は夢を見ていた。そして何よりもまず、老齢のカントが夢を見ていた。「手段(能力)によって」と彼は言った、あるいは少なくともそう言おうとし
た。しかし、それは答えなのか?説明なのか?それとも、単に質問を繰り返しているだけではないのか?アヘンはどのようにして眠りを誘うのか?「手段(能
力)によって」、すなわち「眠りの能力」によって、とモリエールの医師は答える。 なぜなら、そこには眠りの能力があるからだ。 その本質は感覚の眠りである。 しかし、このような答えは喜劇の領域に属するものであり、カントの「総合判断はどのようにして先験的に可能なのか?」という問いを「なぜそのような判断を 信じる必要があるのか?」という別の問いに置き換えるべき時が来ている。事実上、このような判断は真実であると信じなければならないことを理解すべき時が 来ている。なぜなら、私たちのような生き物を維持するためには、そうしなければならないからだ。しかし、それらの判断は依然として自然に誤った判断である 可能性がある!あるいは、もっとわかりやすく、乱暴に簡単に言えば、総合的判断は先験的には「ありえない」はずであり、我々にはそれらを正当化する権利は ない。我々の口からすれば、それは誤った判断でしかない。もちろん、人生観に属するもっともらしい信念や目撃証言のように、その真実性を信じることは必要 である。そして最後に、「ドイツ哲学」がヨーロッパ全体に多大な影響を与えてきたことを思い出すために、ある種の「潜在能力」がその一因であったことは疑 いようがない。ドイツ哲学のおかげで、それは 高貴な怠け者、高潔な人々、神秘主義者、芸術家、キリスト教徒の4分の3、そしてあらゆる国民の政治的蒙昧主義者にとって、前世紀から今世紀へと溢れ出た 圧倒的な官能主義に対する解毒剤を見つけることは、喜びであった。つまり、「感覚の沈静化」である。 |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099