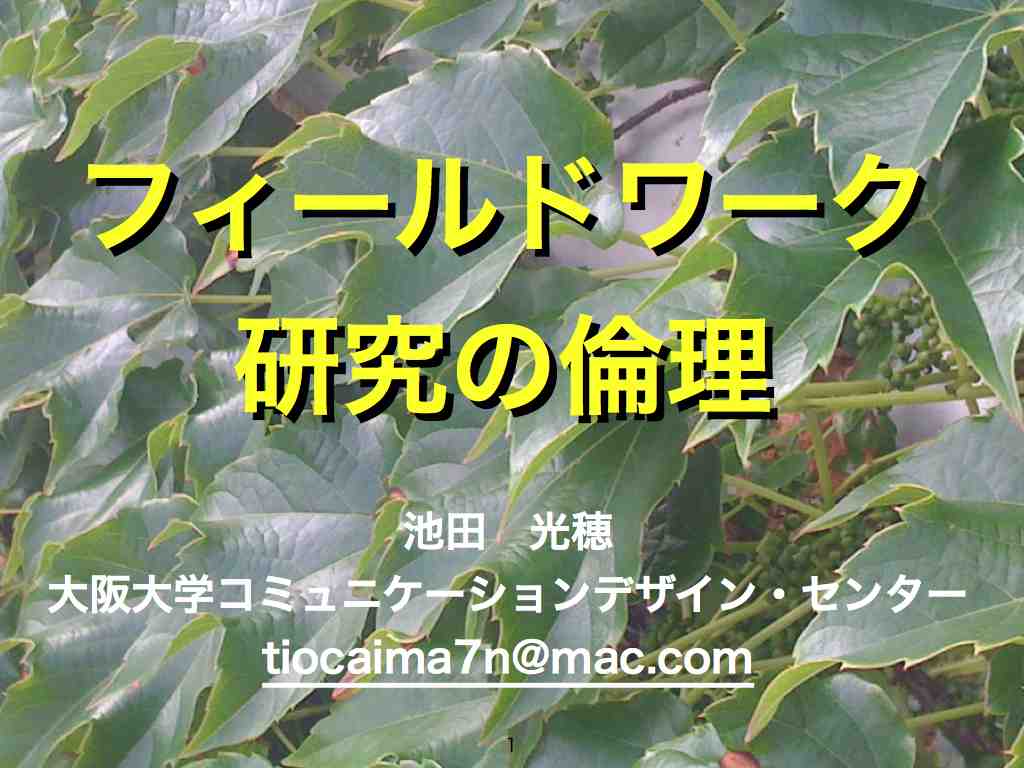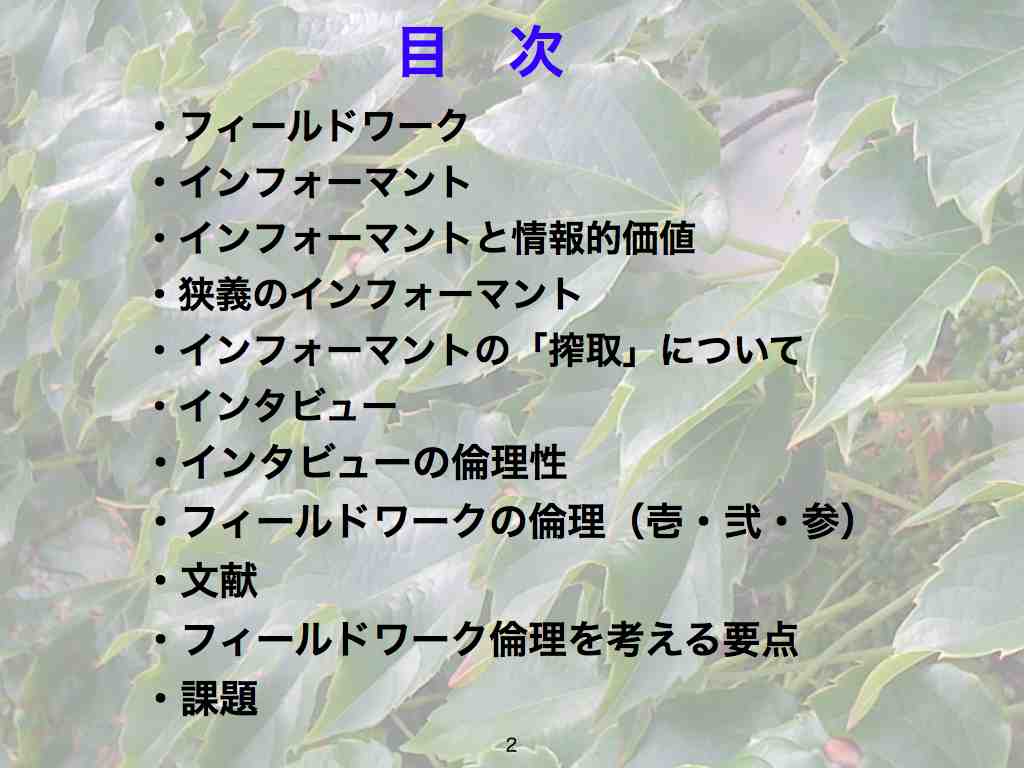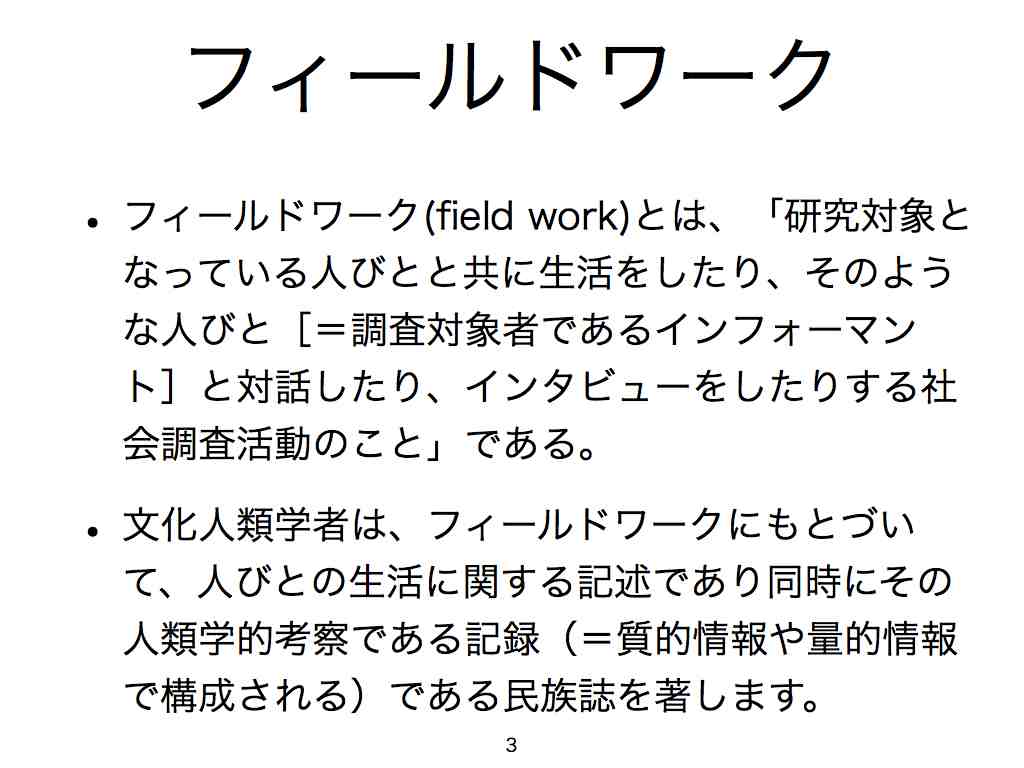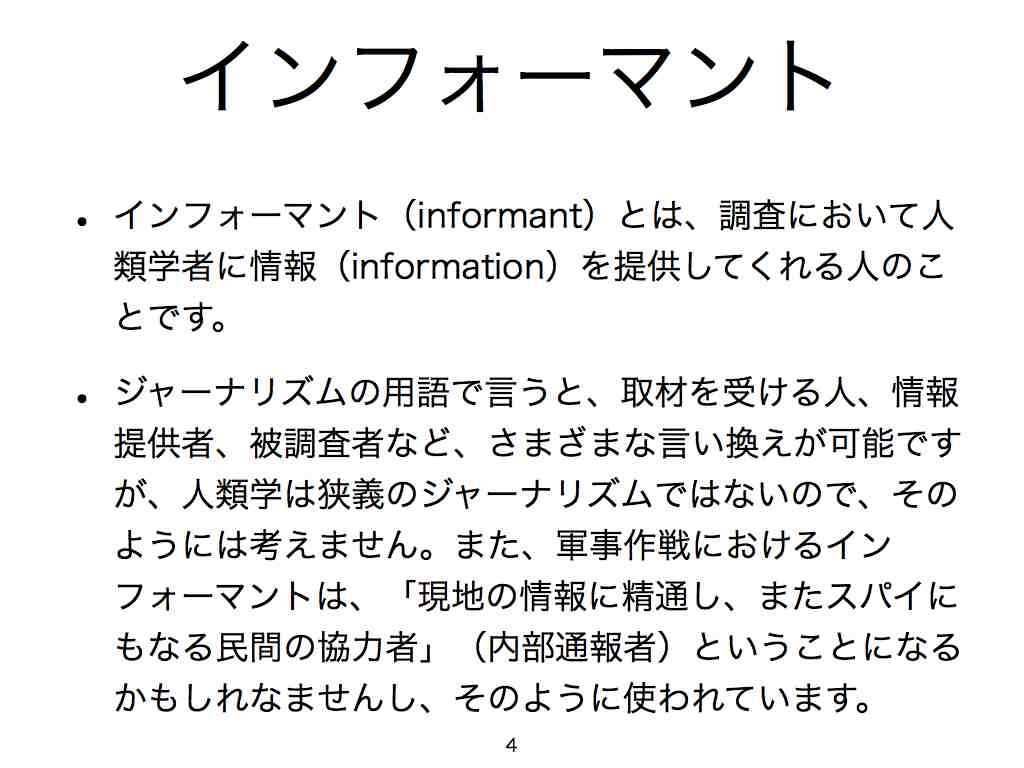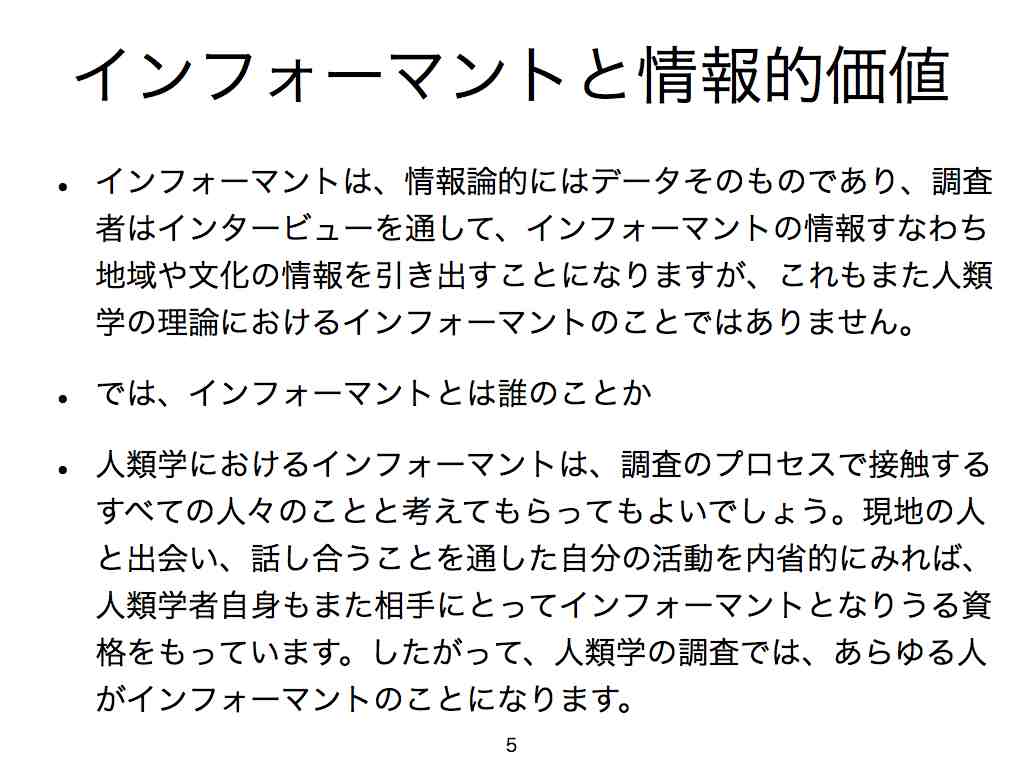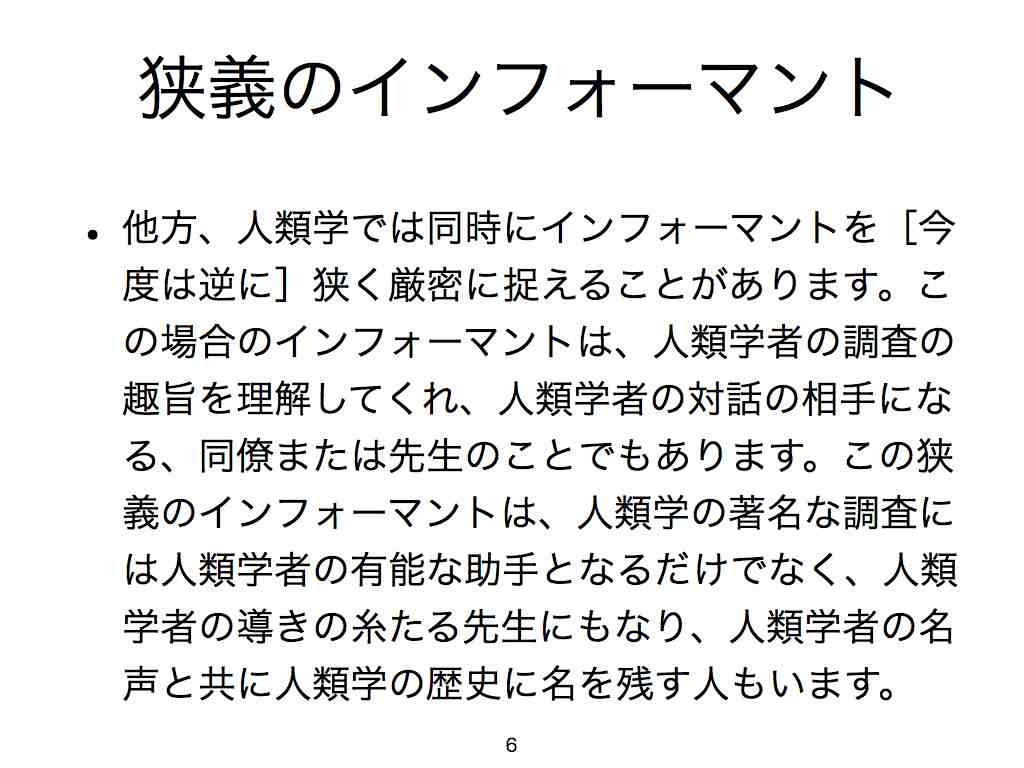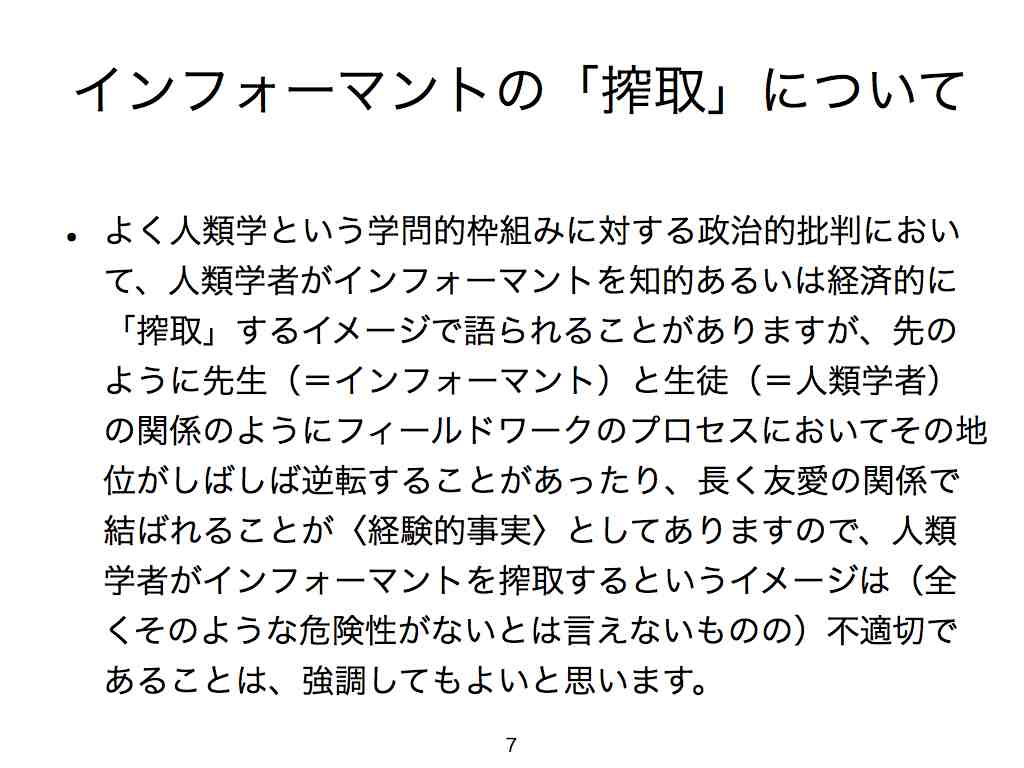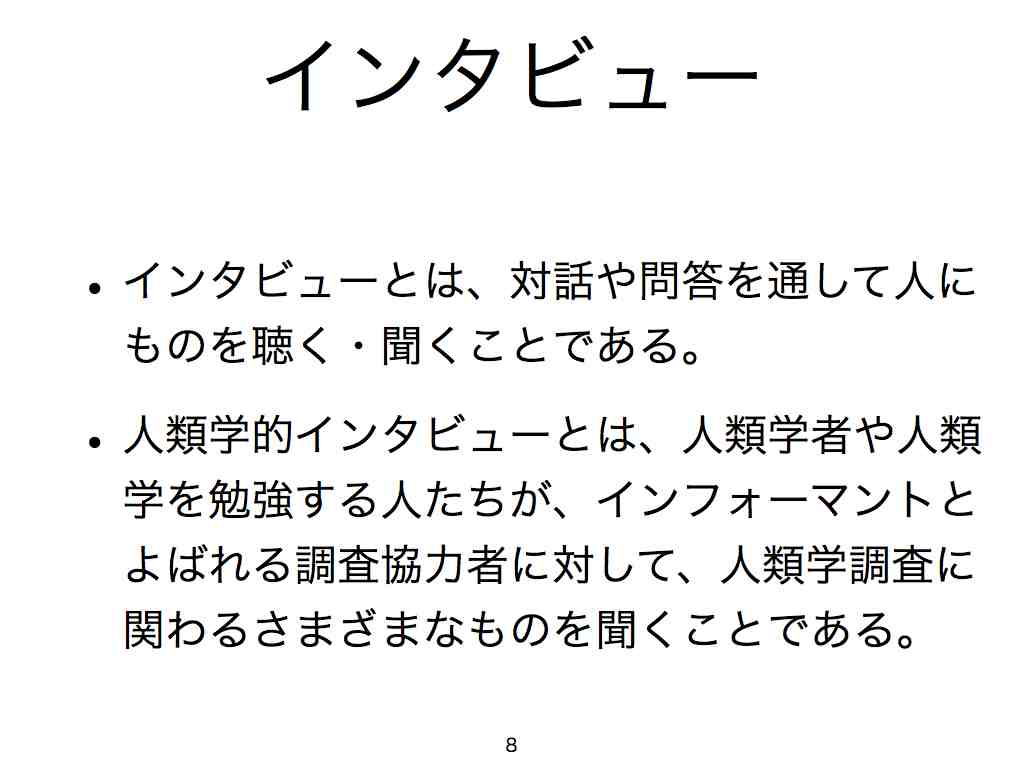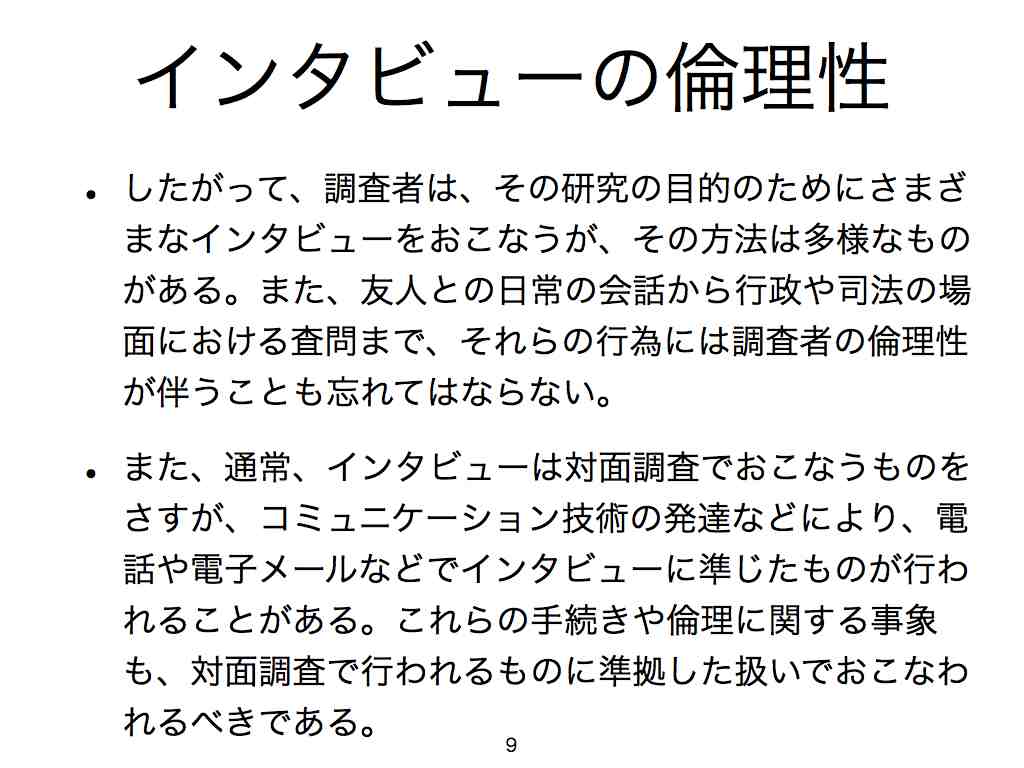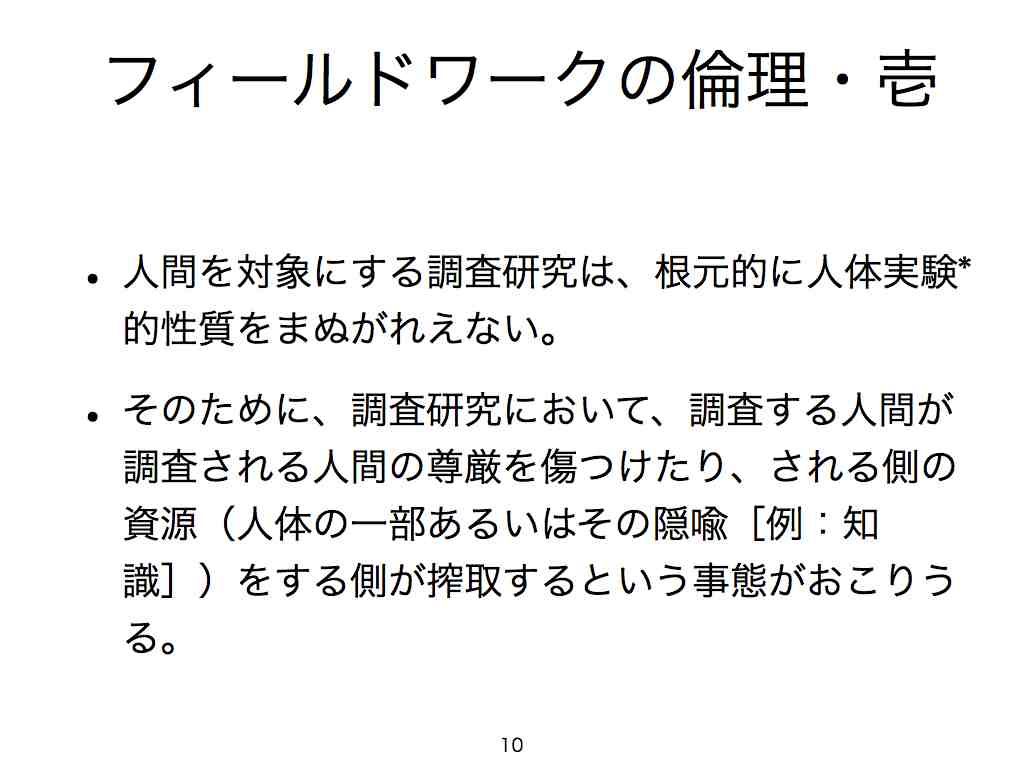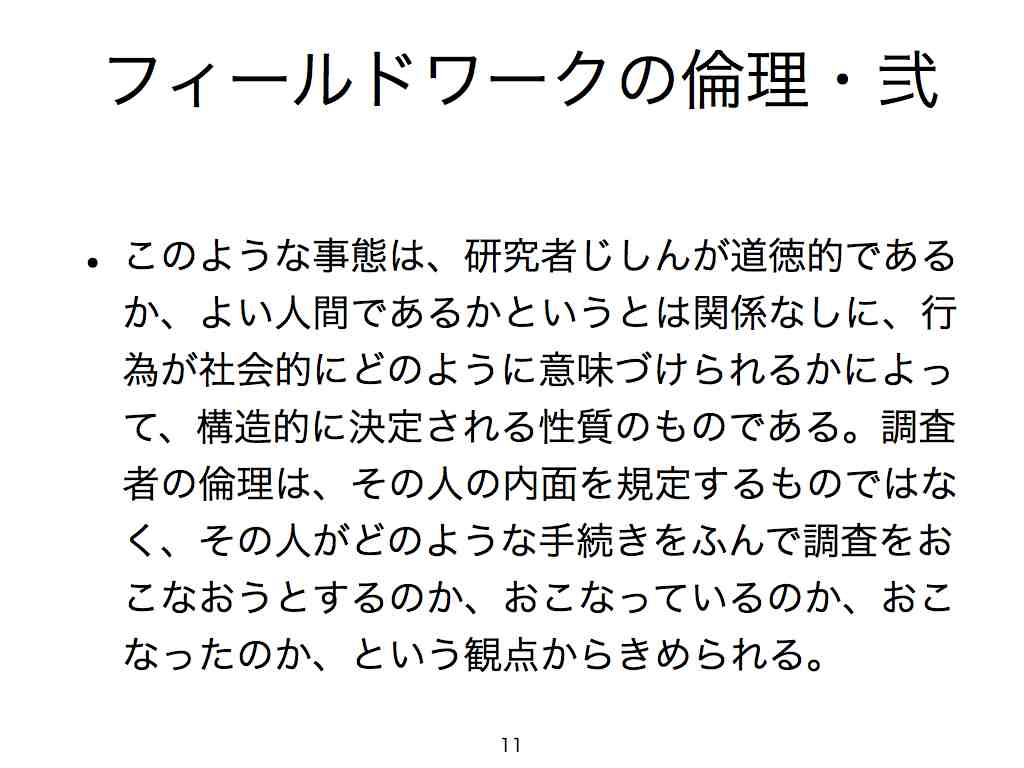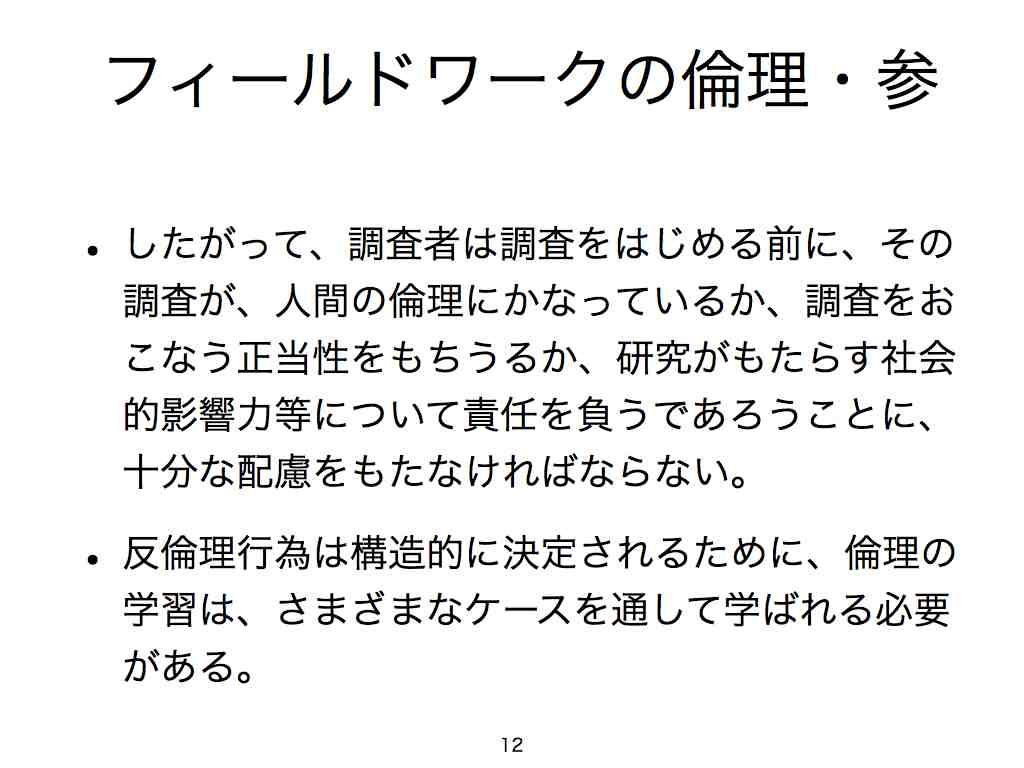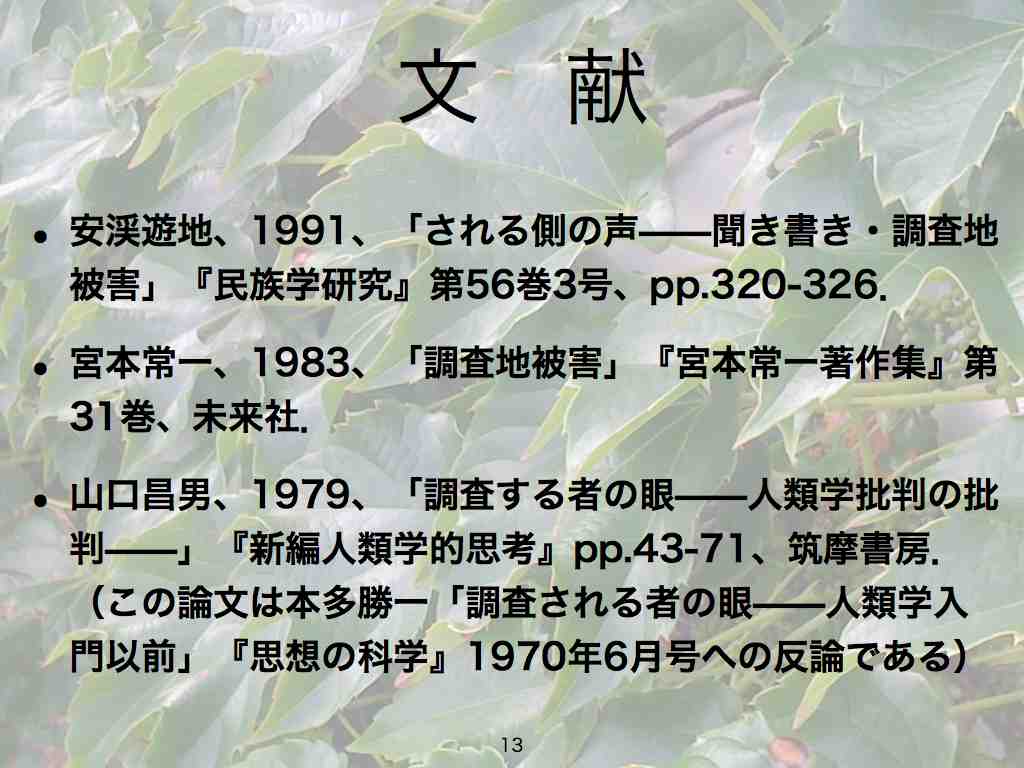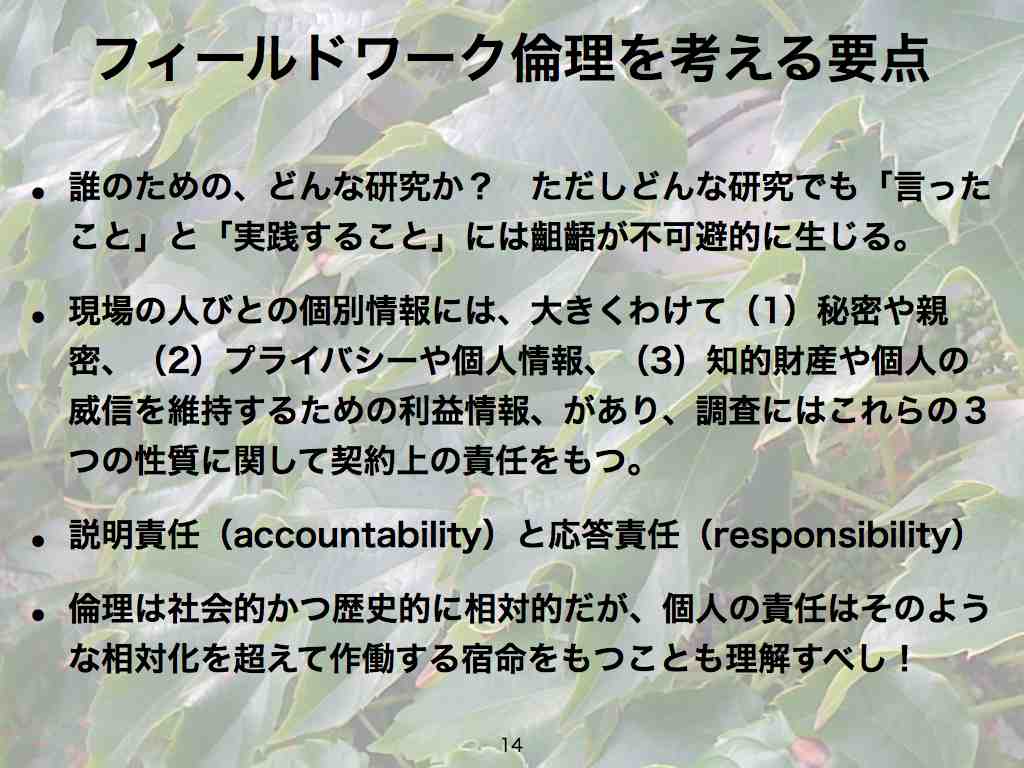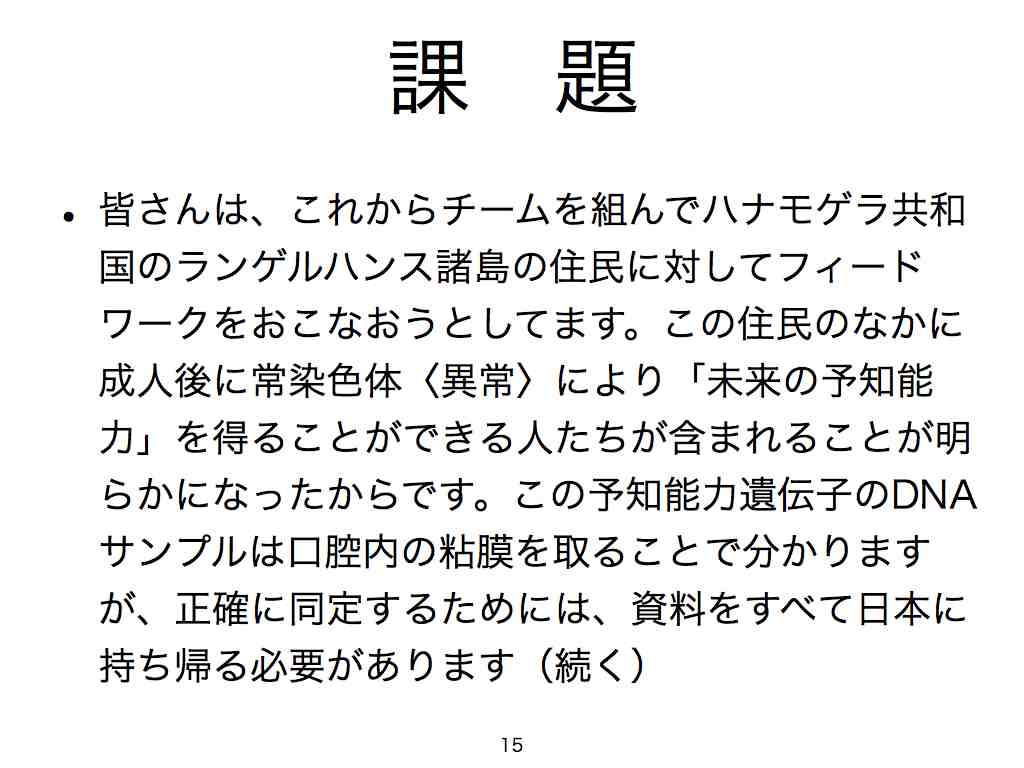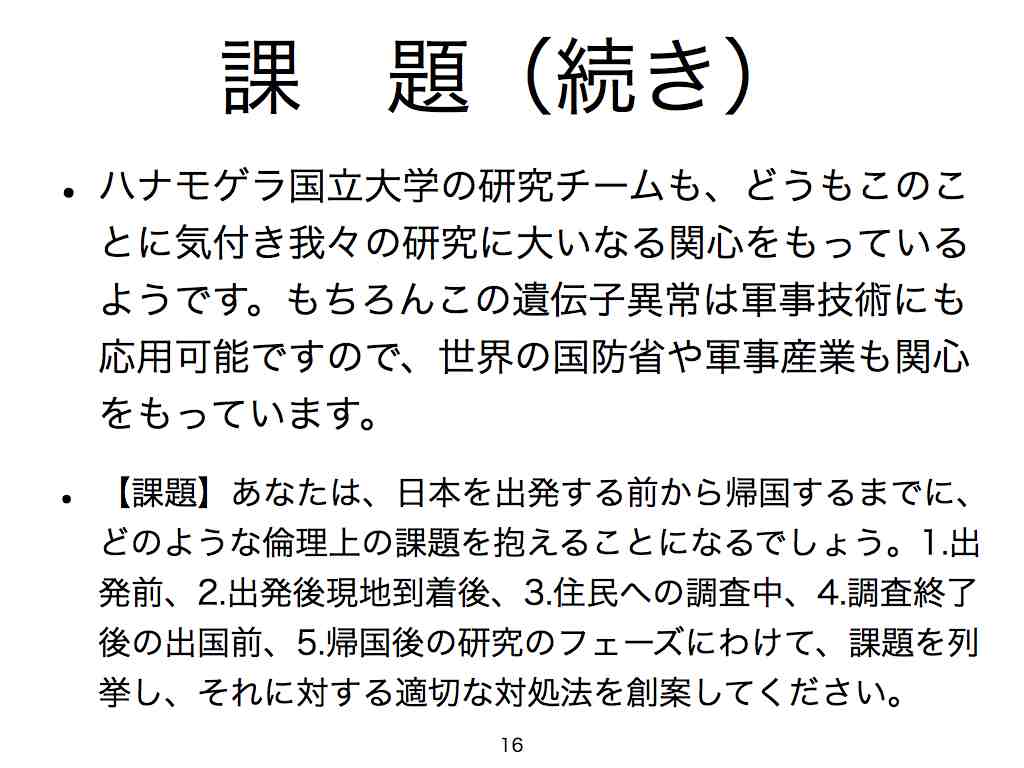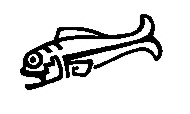スライドをクリックしますと単独で表示されます!(以下同様です)
現在の私の所属は、 大阪大学CO(こ)デザインセンターです。
現在の連絡先のメールアドレスは、
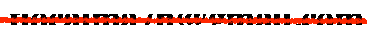

- ・フィールドワーク
- ・インフォーマント
- ・インフォーマントと情報的価値
- ・狭義のインフォーマント
- ・インフォーマントの「搾取」について
- ・インタビュー
- ・インタビューの倫理性
- ・フィールドワークの倫理(壱・弐・参)
- ・文献
- ・フィールドワーク倫理を考える要点
- ・課題
フィールドワーク(field work)とは、「研究対象となっている人びとと共に生活をしたり、そのような人びと[=調査対象者であるインフォーマント]と対話したり、インタビュー をしたりする社会調査活動のこと」である。
文化人類学者は、フィールドワークにもとづいて、人びとの生活に関する記述であり同時にその人類学的考察である記録(=質的情報や量的 情報 で構成される)である民族誌を著します。
インフォーマント(informant)とは、調査において人類学者に情報(information)を提供してくれる人のことです。
ジャーナリズムの用語で言うと、取材を受ける人、情報提供者、被調査者など、さまざまな言い換えが可能ですが、人類学は狭義のジャーナ リズ ムではないので、そのようには考えません。また、軍事作戦におけるインフォーマントは、「現地の情報に精通し、またスパイにもなる民間の協力者」(内部通 報者)ということになるかもしれなませんし、そのように使われています。
■インフォーマントとは?インフォーマントは、情報論的にはデータそのものであり、調査者はインタービューを通して、インフォーマントの情報すなわち地域や文化 の情 報を引き出すことになりますが、これもまた人類学の理論におけるインフォーマントのことではありません。
では、インフォーマントとは誰のことか
人類学におけるインフォーマントは、調査のプロセスで接触するすべての人々のことと考えてもらってもよいでしょう。現地の人と出会い、 話し 合うことを通した自分の活動を内省的にみれば、人類学者自身もまた相手にとってインフォーマントとなりうる資格をもっています。したがって、人類学の調査 では、あらゆる人がインフォーマントのことになります。
他方、人類学では同時にインフォーマントを[今度は逆に]狭く厳密に捉えることがあります。この場合のインフォーマントは、人類学者の調査 の趣旨を理解してくれ、人類学者の対話の相手になる、同僚または先生のことでもあります。この狭義のインフォーマントは、人類学の著名な調査には人類学者 の有能な助手となるだけでなく、人類学者の導きの糸たる先生にもなり、人類学者の名声と共に人類学の歴史に名を残す人もいます。
よく人類学という学問的枠組みに対する政治的批判において、人類学者がインフォーマントを知的あるいは経済的に「搾取」するイメージで語ら れることがありますが、先のように先生(=インフォーマント)と生徒(=人類学者)の関係のようにフィールドワークのプロセスにおいてその地位がしばしば 逆転することがあったり、長く友愛の関係で結ばれることが〈経験的事実〉としてありますので、人類学者がインフォーマントを搾取するというイメージは(全 くそのような危険性がないとは言えないものの)不適切であることは、強調してもよいと思います。
インタビューとは、対話や問答を通して人にものを聴く・聞くことである。
人類学的インタビューとは、人類学者や人類学を勉強する人たちが、インフォーマントとよばれる調査協力者に対して、人類学調査に関わる さま ざまなものを聞くことである。
したがって、調査者は、その研究の目的のためにさまざまなインタビューをおこなうが、その方法は多様なものがある。また、友人との日常 の会 話から行政や司法の場面における査問まで、それらの行為には調査者の倫理性が伴うことも忘れてはならない。
また、通常、インタビューは対面調査でおこなうものをさすが、コミュニケーション技術の発達などにより、電話や電子メールなどでインタ ビューに準じたものが行われることがある。これらの手続きや倫理に関する事象も、対面調査で行われるものに準拠した扱いでおこなわれるべきである。
人間を対象にする調査研究は、根元的に人体実験*的性質をまぬがれえない。
そのために、調査研究において、調査する人間が調査される人間の尊厳を傷つけたり、される側の資源(人体の一部あるいはその隠喩[例: 知 識])をする側が搾取するという事態がおこりうる。
このような事態は、研究者じしんが道徳的であるか、よい人間であるかというとは関係なしに、行為が社会的にどのように意味づけられるかに よって、構造的に決定される性質のものである。調査者の倫理は、その人の内面を規定するものではなく、その人がどのような手続きをふんで調査をおこなおう とするのか、おこなっているのか、おこなったのか、という観点からきめられる。
したがって、調査者は調査をはじめる前に、その調査が、人間の倫理にかなっているか、調査をおこなう正当性をもちうるか、研究がもたら す社 会的影響力等について責任を負うであろうことに、十分な配慮をもたなければならない。
反倫理行為は構造的に決定されるために、倫理の学習は、さまざまなケースを通して学ばれる必要がある。
- 安渓遊地、1991、「される側の声——聞き書き・調査地被害」『民族学研究』第56巻3号、pp.320-326.
- 宮本常一、1983、「調査地被害」『宮本常一著作集』第31巻、未来社.
- 山口昌男、1979、「調査する者の眼——人類学批判の批判——」『新編人類学的思考』pp.43-71、筑摩書房.(この論文 は本 多勝一「調査される者の眼——人類学入門以前」『思想の科学』1970年6月号への反論である)
- 本多勝一「調査される者の眼」
『思想の科学』1970年6月号、Pp.9-18, 1970年
・誰のための、どんな研究か? ただしどんな研究でも「言ったこと」と「実践すること」には齟齬が不可避的に生じる。
・現場の人びとの個別情報には、大きくわけて(1)秘密や親密、(2)プライバシーや個人情報、(3)知的財産や個人の威信を維持するた めの 利益情報、があり、調査にはこれらの3つの性質に関して契約上の責任をもつ。
・説明責任(accountability)と応答責任(responsibility)
・倫理は社会的かつ歴史的に相対的だが、個人の責任はそのような相対化を超えて作働する宿命をもつことも理解すべし!
【応用問題】問い:すばらしい学生の答案やレポートは無断で引用できる か?
【山口昌男と本多勝一 論争の〈深層〉について】
皆さんは、これからチームを組んでハナモゲラ共和国のランゲルハンス諸島の住民に対してフィードワークをおこなおうとしてます。この住民の なかに成人後に常染色体〈異常〉により「未来の予知能力」を得ることができる人たちが含まれることが明らかになったからです。この予知能力遺伝子のDNA サンプルは口腔内の粘膜を取ることで分かりますが、正確に同定するためには、資料をすべて日本に持ち帰る必要があります(続く)
ハナモゲラ国立大学の研究チームも、どうもこのことに気付き我々の研究に大いなる関心をもっているようです。もちろんこの遺伝子異常は 軍事 技術にも応用可能ですので、世界の国防省や軍事産業も関心をもっています。
【課題】あなたは、日本を出発する前から帰国するまでに、どのような倫理上の課題を抱えることになるでしょう。1.出発前、2.出発後 現地 到着後、3.住民への調査中、4.調査終了後の出国前、5.帰国後、という5つの研究のフェーズにわけて、課題を列挙し、それに対する適切な対処法を創案 してください。
当日配布したワークシートの構成は下記のとおりです。
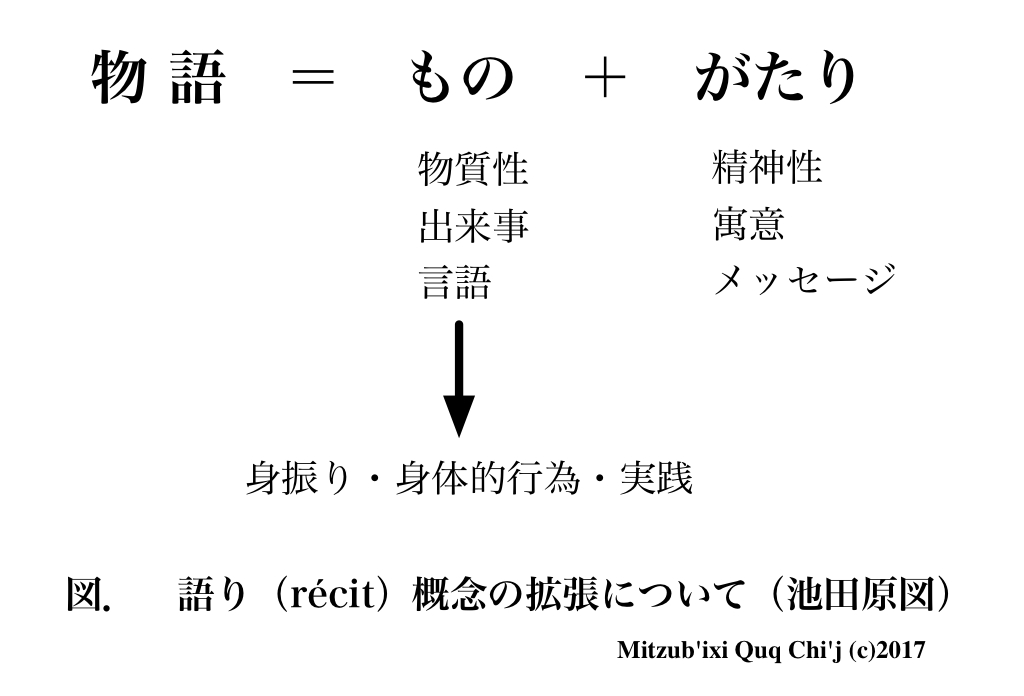

・調査参加への依頼・同意書(先住民/先住民族との研究の雛形の実例:hinagata_GSIND_2018.pdf)
英語
・Request for participation in Research and Survey : Consent form, participate_informed_consent2.pdf with password