シン「文化の否定性」ノート
On Nagativity (Nagative Aspects)
of Cuture, NS
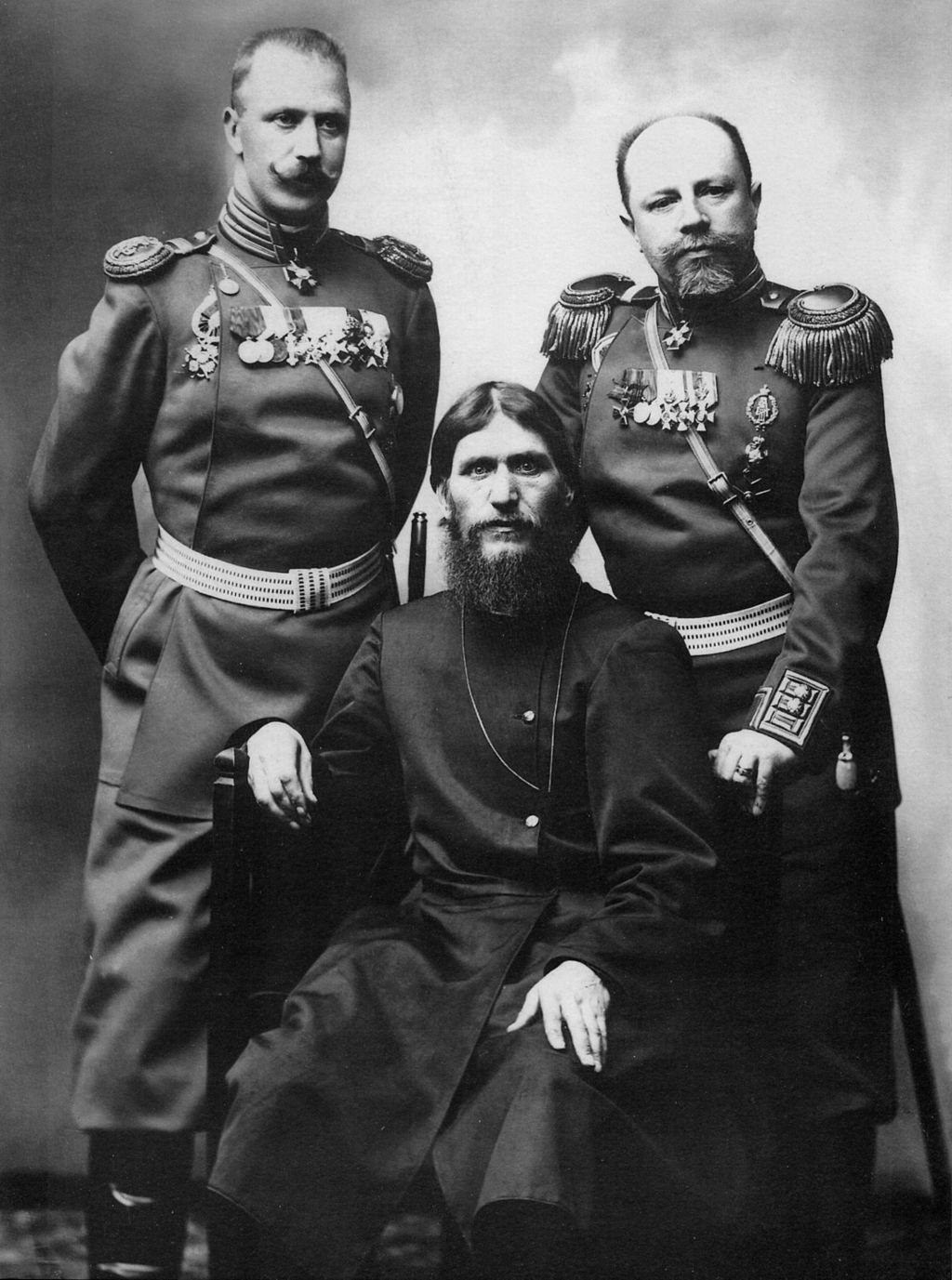
シン「文化の否定性」ノート
On Nagativity (Nagative Aspects)
of Cuture, NS
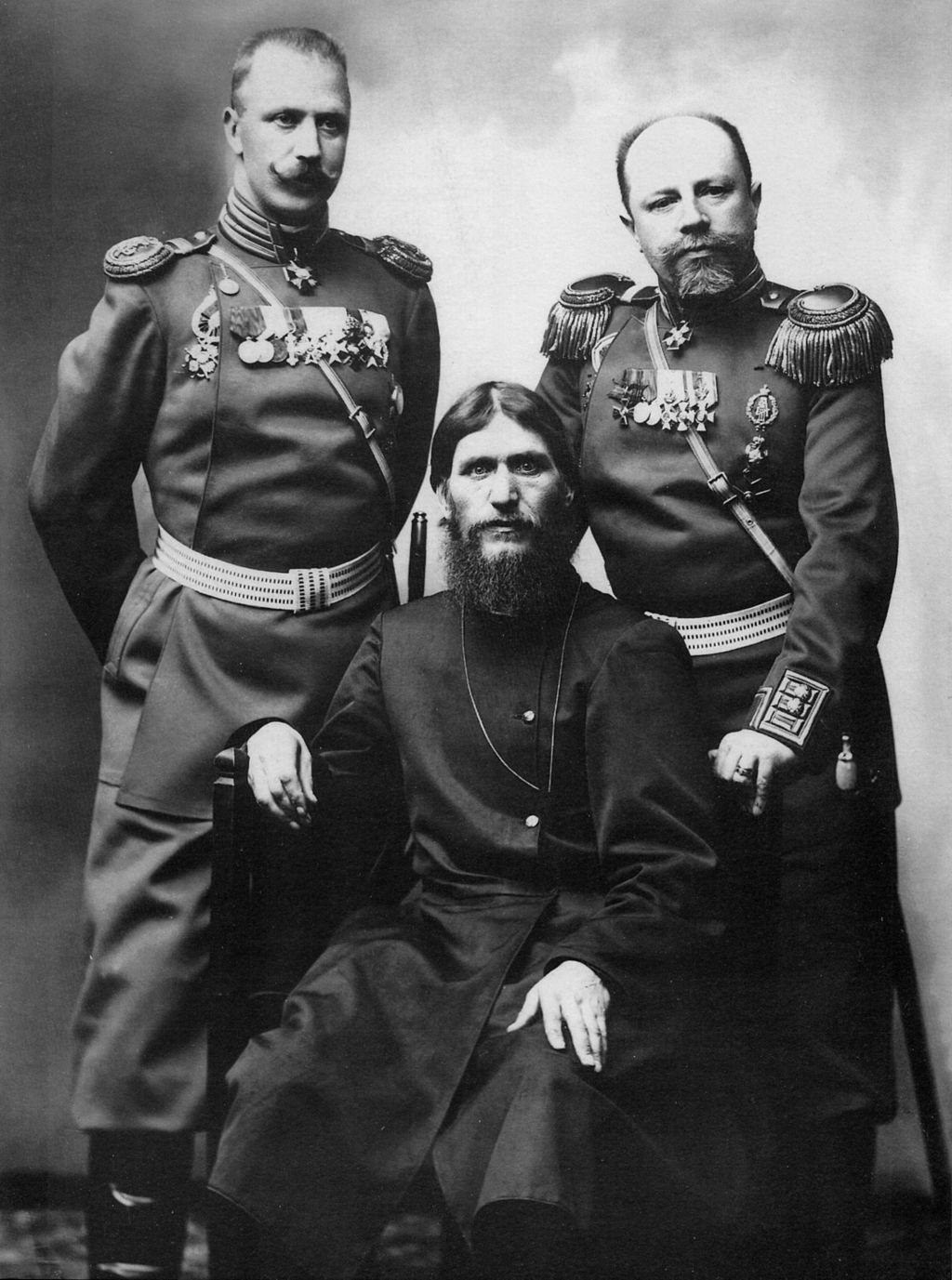
☆キックオフ:「「文 化の否定性」は1987年11月号の『中央公論』に掲載された、青木の論文である。正式な論題は「文化の否定性:反相対主義時代に見る」。平易な文章な がら、20世紀の最後の四半世紀における文化概念、とりわけ文化相対主義の衰退をとりあげてもなお、文 化相対主義の復権を唱える。ただし、その方法は、文 化の否定的な側面に着目して、「自文化」の過度な優越性を忘れる——青木の用語では「アムネジア(amnesia,記憶喪失)」——必要性があるのではな いかと締めくくる。/青木の心理主義的な「「自文化」の過度な優越性を忘れる」 ことで、青木が憂慮している、反文化相対主義のウェーブが、当時もそして今も——つまり、普遍的に——克服されるとは、思われないが、当時も今もつづく、 反文化相対主義の心理的錯乱を、フロイト的にコーピングするのは、ひとつの手立てだったのだろう。ちなみに、フロイ ト的忘却は、自分によって都合の悪いことや、超自我などによって「抑圧」されるものなので、「自文化」の過度な優越性を忘れることは、根本的な処方にはな らず、当時からも現在においても、まったく無効な処方 箋であることは言うまでもない。/こ の論文は、後に青木の単行本『文化の否定性』中央公論社、1988年に収載された。/各、 章立ては以下のとおり 1. 文化からの後退 2. 文化相対主義 3. 反文化相対主義 4. 文化の否定性」(→「青木保「文化の否定性」入門ノート」より)
★以下は、ウィキペディア(英語の)小項目 "Dialectics, speculation, idealism"からの引用である。
| Dialectics,
speculation, idealism Hegel is often credited with proceeding according to a "dialectical method"; in point of fact, however, Hegel characterizes his philosophy as "speculative" (spekulativ), rather than dialectical, and uses the term "dialectical" only "quite rarely".[258][ak] This is because, although "Dialektik sometimes stands for the entire movement of the self-articulation of meaning or thought, this term refers more specifically to the self-negation of the determinations of the understanding (Verstand), when they are thought through in their fixedness and opposition."[260] By contrast, "Hegel describes correct thinking as the methodical interplay of three moments[:] (a) abstract and intellectual (verständig), (b) dialectical or negatively rational (negativvernünftig), and (c) speculative or positively rational (positivvernünftig)."[261][262][263][al][am] For example, self-consciousness is "the concept that consciousness has of itself. Thus in this case concept and referent coincide:... 'self-consciousness' refers to mind's taking on the self-contradictory (and thus also self-negating) role of being subject and object of one and the same act of cognition – simultaneously and in the same respect."[267][268] Hence it is a speculative concept. According to Beiser, "if Hegel has any methodology at all, it appears to be an anti-methodology, a method to suspend all methods." Hegel's term "dialectic" must be understood with reference to the concept of the object of investigation. What must be grasped is "the 'self-organization' of the subject matter, its 'inner necessity' and 'inherent movement.'" Hegel renounces all external methods such as could be "applied" to some subject matter.[96] The dialectical character of Hegel's speculative procedure often makes his position on any given issue quite difficult to characterize. Instead of seeking to answer a question or solve a problem directly, he frequently recasts it by showing, for instance, "how the dichotomy underlying the dispute is false, and that it is therefore possible to integrate elements from both positions."[269] Speculative thought preserves what is true from apparently opposing theories in a process that Hegel terms "sublation". To "sublate" (aufheben) has three main senses:[an] 'to raise, to hold, lift up'; 'to annul, abolish, destroy, cancel, suspend'; and, 'to keep, save, preserve.'[272] Hegel generally uses the term in all three senses, with particular emphasis on the second and third, in which apparent contradictions are speculatively overcome.[272] His word for what is sublated is "moment" (das Moment, in the neuter), which denotes "an essential feature or aspect of a whole conceived as a static system, and an essential phase in a whole conceived as a dialectical movement or process."[273] (When Hegel describes something as "contradictory," what he means is that it is not independently self-sustaining on its own terms, and so it can only be comprehended [begreifen] as a moment of a larger whole.[274]) According to Hegel, to think of the finite as a moment of the whole, rather than an independently self-determined existent, is what it means to grasp it as idealized (das Ideelle).[275][276] Idealism, then, "is the doctrine that finite entities are ideal (ideell): they depend not on themselves for their existence but on some larger self-sustaining entity [i.e., the whole] that underlies or embraces them."[277] The pronoun-expressions – moment, sublate, and idealize – are characteristic of Hegel's account of idealism. They can be understood as stages of thought in which the "object is conceptually present first in mere adumbration, then according to circumstances both internal and external to it, and finally standing completely on its own."[278] This phenomenological and conceptual analysis distinguishes Hegel's idealism from Kant's transcendental idealism and Berkeley's mentalistic idealism.[279] In contrast to those positions, Hegel's idealism is entirely compatible with realism and non-mechanistic naturalism.[280] This position rejects empiricism as an a priori account of knowledge, but it is in no way opposed to the philosophical legitimacy of empirical knowledge.[281] Hegel's idealistic contention, which he claims to demonstrate, is that being itself is rational.[282] Although it is not incorrect to refer to Hegel's philosophy as "absolute idealism," this moniker was at the time more associated with Schelling, and Hegel himself is documented as employing it with reference to his own philosophy only three times.[283] According to Hegel, "every philosophy is essentially idealism."[284] This claim is based on the assumption, which Hegel claims to demonstrate, that conceptualization is present at all cognitive levels. For to completely deny this would undermine trust in the conceptual capacities necessary for objective knowledge – and so would lead to total skepticism.[285] Hence, according to Robert Stern, Hegel's idealism, "amounts to a form of conceptual realism, understood as 'the belief that concepts are part of the structure of reality.'"[286] |
弁証法、思弁、観念論 ヘーゲルはしばしば「弁証法的方法」に従って進んだとされるが、実際にはヘーゲルは自身の哲学を弁証法的なものではなく「思弁的」 (spekulativ)と特徴づけ、「弁証法」という用語は「ごくまれに」しか用いていない。[258][ak] これは、「Dialektik」という語が意味や思考の自己言及の全体的な運動を表すこともあるが、この用語は 理解(Verstand)の決定が固定性と対立の中で思考される際の自己否定を指す」からである。[260] これに対し、「ヘーゲルは正しい思考を、3つの要素の秩序だった相互作用として説明している[:] (a) 抽象的かつ知的(verständig)、 (b) 弁証法的または否定的に理性的(negativvernünftig)、および (c) 思弁的または肯定的理性的(positivvernünftig)」[261][262][263][al][am] 例えば、自己意識とは「意識がそれ自身について抱く概念」である。したがってこの場合、概念と対象は一致する。「自己意識」とは、心がある認識行為の主体 と対象という自己矛盾した(したがって自己否定的な)役割を同時に同じ観点で担うことを指す。[267][268] したがって、これは観念的な概念である。 ベイザーによると、「ヘーゲルに方法論があるとすれば、それは反方法論、すなわちあらゆる方法を停止させる方法であるように見える」という。ヘーゲルの用 語「弁証法」は、研究対象の概念を参照して理解されなければならない。把握されなければならないのは、「主題の『自己組織化』、その『内的必然性』と『内 在的運動』」である。ヘーゲルは、対象に「適用」できるような外部的な方法をすべて放棄している。[96] ヘーゲルの思弁的な手順の弁証法的な性格は、しばしば、彼のある問題に対する立場を特徴づけることを非常に困難にしている。ヘーゲルは、問題に直接的に答 えを求めたり、問題を解決しようとするのではなく、例えば「論争の根底にある二分法が誤りであり、それゆえ両方の立場からの要素を統合することが可能であ る」ことを示すことによって、問題を再定義することが多い。[269] 思弁的な思考は、ヘーゲルが「止揚」と呼ぶプロセスにおいて、一見対立する理論のなかに真実であるものを保存する。 止揚(aufheben)には主に3つの意味がある。[an] 「引き上げる、保持する、持ち上げる」; 「無効にする、廃止する、破壊する、取り消す、保留する」;そして、 「保持する、保存する、維持する」[272] ヘーゲルは一般的にこの用語を3つの意味すべてで使用しており、特に2番目と3番目の意味に重点を置いており、そこでは一見したところ矛盾するものが思索 的に克服されている。[272] 彼が「止揚」を意味する言葉として用いたのは「瞬間」(das Moment、中性形)であり、これは「静的なシステムとして考えられる全体の本質的な特徴または側面、および弁証法的な運動またはプロセスとして考えら れる全体の本質的な局面」を意味する。[273](ヘーゲルが何かを「矛盾する」と表現するとき、 「矛盾」という言葉で表現しているのは、それがそれ自身の条件において独立して自立しているわけではないということであり、したがって、それはより大きな 全体の一瞬としてのみ理解される[begreifen]ことができるということである。[274] ヘーゲルによれば、有限なものを独立して自己決定された存在ではなく、全体の一瞬として考えることが、それを理想(das Ideelle)として把握することである。[275][276] それゆえ、観念論とは「有限な存在は理想(ideell)であるという教義である。それらは、それらの存在をそれら自身に依存するのではなく、それらを根 底から支え、包含するより大きな自己維持的な存在(すなわち、全体)に依存する」ものである。」[277] 代名詞表現である「瞬間(moment)」、「超越(sublate)」、「理想化(idealize)」は、ヘーゲルの観念論の説明の特徴である。これ らは、「対象がまず概念的に単なる予兆として存在し、次にその対象の内外の状況に応じて存在し、最終的に完全に自立して存在する」という思考の段階として 理解することができる。[278] この現象学的かつ概念的分析により、ヘーゲルの観念論はカントの超越論的観念論やバークリーの心論的観念論とは区別される。[279] それらの立場とは対照的に、ヘーゲルの観念論は実在論や 。この立場は、経験論を知識のア・プリオリな説明として否定するが、経験的知識の哲学的正当性を否定するものではない。[281] ヘーゲルが主張する理想主義的な主張は、存在そのものが理性的であるというものである。[282] ヘーゲルの哲学を「絶対的観念論」と呼ぶのは間違いではないが、この呼び名は当時、シェリングとより関連付けられていた。ヘーゲル自身は、自身の哲学につ いてこの呼び名を3回しか使用していないことが記録されている。 ヘーゲルによれば、「あらゆる哲学は本質的に観念論である」[284]。この主張は、ヘーゲルが証明しようとした前提、すなわち、あらゆる認識レベルにお いて観念化が存在するという前提に基づいている。このことを完全に否定することは、客観的な知識に必要な概念化能力への信頼を損なうことになり、全面的な 懐疑論につながるだろう。[285] したがって、ロバート・スターンによると、ヘーゲルの観念論は、「概念は現実の構造の一部であるという信念」として理解される概念的リアリズムの一形態で ある。[286] |
| Thesis–antithesis–synthesis This terminology, largely developed earlier by Fichte, was spread by Heinrich Moritz Chalybäus in accounts of Hegel's philosophy that have since been broadly discredited.[287][288][289] Walter Kaufmann, for instance, reports: Fichte introduced into German philosophy the three-step of thesis, antithesis, and synthesis, using these three terms. Schelling took up this terminology. Hegel did not. He never once used these three terms together to designate three stages in an argument or account in any of his books. And they do not help us understand his Phenomenology, his Logic, or his philosophy of history; they impede any open-minded comprehension of what he does by forcing it into a scheme which was available to him and which he deliberately spurned.[290] More modestly, it has been said that this account is "only a partial comprehension that requires correction." What it gets right is that, according to Hegel, "truth emerges from error" in the course of historical development in a way that implies a "holism in which partial truths are progressively corrected so that their one-sidedness is overcome." What it distorts is that such a description is possible only after the process has unfolded. The "thesis" and "antithesis" are not "alien" to one another. Inasmuch as there can be said to be such a "dialectical method," it is not an external one such as could be "applied" to some subject matter.[291] Similarly, Stephen Houlgate argues that, in whatever limited sense Hegel might be said to have a "method," it is a strictly immanent method; that is, it emerges from thoughtful immersion in the subject-matter itself. If this leads to dialectics, that is only because there is a contradiction in the object itself, not because of any external methodological procedure.[292] |
テーゼ-アンチテーゼ-総合 この用語は、主にフィヒテによって以前に開発されたもので、ヘーゲルの哲学に関するハインリヒ・モーリッツ・シャリボーの著作によって広まったが、その後 広く否定されるようになった。[287][288][289] 例えば、ウォルター・カウフマンは次のように報告している。 フィヒテは、テーゼ、アンチテーゼ、総合という3段階を、これらの3つの用語を用いてドイツ哲学に導入した。シェリングは、この用語法を採用した。ヘーゲ ルはそうしなかった。彼は、どの著書においても、議論や説明の3つの段階を指し示すために、この3つの用語を一度も一緒に使っていない。そして、この3つ の用語は、彼の『現象学』、『論理学』、あるいは『歴史哲学』を理解する助けにはならない。むしろ、彼が意図的に拒絶した、彼にとって利用可能な枠組みに 無理やり当てはめようとするため、彼の業績に対する偏見のない理解を妨げることになる。 より控えめに言えば、この説明は「修正が必要な部分的な理解に過ぎない」とされている。ヘーゲルによれば、「歴史的発展の過程において、真実は誤りから生 まれる」という点が正しい。これは、「部分的な真実が徐々に修正され、その一面的な性質が克服される全体論」を暗示している。歪曲されているのは、そのよ うな説明はプロセスが展開された後にのみ可能であるという点である。「テーゼ」と「アンチテーゼ」は互いに「対立する」ものではない。このような「弁証法 的方法」が存在しうるとしても、それは何らかの主題に「適用」できるような外部的なものではない。 同様に、スティーブン・ホールゲートは、ヘーゲルが「方法」を有しているとされる場合、それはどのような限定的な意味においても、厳密に内在的な方法であ ると主張している。つまり、それは主題そのものへの熟考に満ちた没入から生じるのである。もしこれが弁証法につながるのであれば、それは対象そのものに矛 盾があるからであって、外部の方法論的プロセスによるものではない。[292] |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel |
|
リ ンク
文 献
そ
の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆