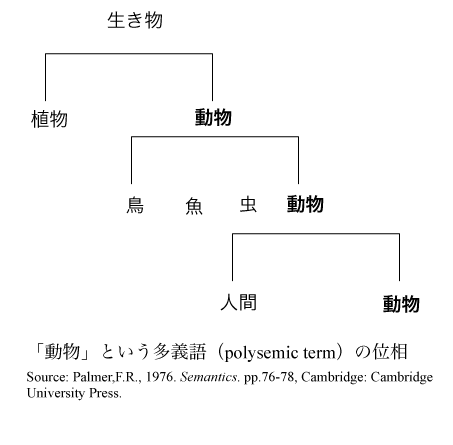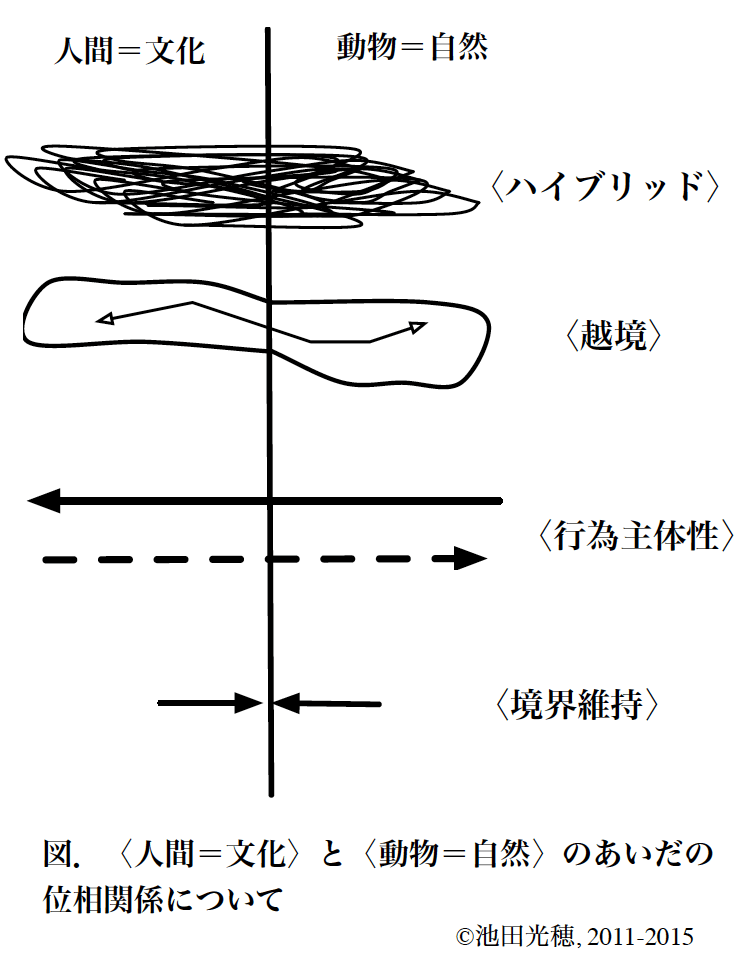「恩寵をラテン語ではグラーティア(gratia)というので、中世のトマス・アクィナス(Thomas Aquinas)の思想の要約として、しばしば "Gratia naturam non tollit, sed eam perficit"=恩寵は自然を破壊せずこれを完成する、という文章が引用される。これが神としての超自然と人間を含めての自然一般との関係をあらわし ている。動物はこのナトゥーラすなわち自然の世界にとどまるが、人間はとくに、それを超える営みをすることができる」(今道友信『自然哲学序説』 p.19, 講談社学術文庫、1993年)。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
旧版)人間と動物:自然と文化とそれらのハイブリッドに関する考察
- 1.自然と文化の働きかけ
- 2.文化に対立する一元的自然と多元的自然
- 3.実験室における自然
- 4.野生からみる自然
- 5.二元論を超えて
- 6. 結論
- bib. 文献
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1.自然と文化の働きかけ
新世界猿の研究者であり、長年、宮城県金華山をはじめとして長年にわたり野生のニホンザル調査に携わってきた伊沢紘生は、フィールドワークを基本とする
霊長類研究の神髄とも言える発言をおこなっている。彼は、自然=野生チンパンジーの観察には、観察者=人類学者(あるいは霊長類学者)が、自分のもつ文化
的背景を捨象し、ひたすら対象である自然と一体化することの重要性を説いている。
「私はこれまで、できるだけ人気[ひとけ]がなく、できるだけ人工物のない自然を選んで、おもにサルを対象に、半世紀にわたってフィールドワークを続けて きた。その中で私がいつも大切にしてきたこと、それは五感を研ぎ澄ますことと、観察力を養うことだ。……伊谷[純一郎]先生と半年間、東アフリカの無人の 原野で、ごく小さな二人用のテントに寝泊まりしながら、神出鬼没のチンパンジーに迫るという千載一遇の機会を得た。先生との原野での一日一日が私のフィー ルドワークのスタイルを決定づけたことは間違いない。私がアフリカで先生から学んだ最大のもの、それが五感を研ぎ澄ますことと観察力を養うことだったので ある」[伊沢 2009:412]
他方、西洋世界では、人間は動物に対する絶対的優位性をこれまで確保してきた。これは基本的には、人間を神から選ばれた恩寵の賜物として、そして動物を非 常に多義的な自然の概念[ラブジョイ 2003:59-65]に位置づけて区分してきた伝統の系譜の位置する。※ラブジョイ、アーサー『観念の歴史』鈴木信雄 他訳、名古屋大学出版会、 2003年
「恩寵をラテン語ではグラーティア(gratia)というので、中世のトマス・アクィナス(Thomas Aquinas)の思想の要約として、しばしば "Gratia naturam non tollit, sed eam perficit"=恩寵は自然を破壊せずこれを完成する、という文章が引用される。これが神としての超自然と人間を含めての自然一般との関係をあらわし ている。動物はこのナトゥーラすなわち自然の世界にとどまるが、人間はとくに、それを超える営みをすることができる」[今道 1993:19](今道友信『自然哲学序説』 p.19, 講談社学術文庫、1993年)。
動物の供儀のあり方について、パースペクティヴィズムという観点[VIVEIROS DE CASTRO
1998]からアイヌのイオマンテ(クマ送り・クマ祭り:カムイを御送りする儀礼)に関するともにアイヌ社会に溶け込んだ対照的な2人の異邦人の立場につ
いて考えてみよう(→「熊送りの諸相(1)」「熊送りの諸相(2)」)。
ここで取り扱われるものは1931年頃のアイヌのクマ送りである。英国のフィールド人類学ならびに医療人類学の歴史に名を残すアルフレッド・ ハッドン(Alfred C. Haddon, 1855-1940)が指揮したトレス海峡探検調査(1898年)に参加したチャールズ・セリグマン(Charles G. Seligman, 1873 - 1940)は1930年以来、二風谷においてアイヌに対して診療活動する傍ら民族誌調査をしていたニール・マンロー(Neil Munro, 1863 -1942)の研究の支援者と支えることになる。マンローはそれまでに自分の書物や論文をセリグマンに送付しており、それが彼の死の20年後に人類学者と して夫と共にスーダンでも調査経験のあるセリグマン夫人(Brenda Z. Seligman, 1882-1965)が編集した『アイヌの信仰とその儀式(Ainu Creed and Cult)』として出版されることになる。
しかし奇妙なことにアイヌの熊祭りに関しては、アイヌの伝統的な宗教実践としてこれまで数多くの民族誌家および民族史家によって記録・言及さ れてきた熊祭りについては、マンローは1931年に記録映画を撮影した以外にはまとまった記述を残していない。その直接の理由は明らかではないが、映画の 公開当時、聖公会宣教師で1877年からアイヌ地域の伝道に携わっていたジョン・バチェラー(John Batchelor, 1854-1944)が熊送りという「残酷野蛮な行事」映画の公開をアイヌの「一民族の恥」を晒すものと批判し、それに対してマンローがアイヌの信仰を擁 護して反論した経緯が背景にあった可能性があった。この確執はバチェラーが皮膚の腫瘍の切開のために1938年にマンローを訪れるまで続いたと言われてい る[桑原 1983:222-223]。(桑原千代子『わがマンロー伝』新宿書房、1983年)。次の記録は、マンローが先のセリグマンの論集の中に「追録」として 収載されている先に触れたセリグマン夫人が、マンローによる映画の説明部分から彼女自身が編集したものである。
「熊がしばらくの間みんなの前で引き廻されると、何人かの男たちが特別に作った飾り矢(花矢)を熊目がけて射かけます。この飾り矢は先端がとがっていない ので、熊を傷つけるようなことはありません。この後熊は、広場の中心に打ち込まれた杭につながれます。この行事が進められて行く中で、最後に選ばれた一人 の射手が、自分の放つ本当の矢が迅速に熊に命中してすぐに射斃(たお)すことができるように、と〈カムイ〉に向かって祈ります。竹の先端をとがらせて作っ た一本、時には二本の矢は、熊の身体からその霊魂を送り出してやるために適切なやり方であると考えられています。射た熊の身体から出る血を地面にこぼすこ とは禁じられており、またその血がほんのわずかな雪で汚れることも許されていません。一人の長老が、去り行く熊の霊魂の無事を祈ります。前に熊の遺体を安 置した祭壇を越えて何本かの霊力のある矢が空に放たれることで、熊の霊魂が去って行ったことが確認されます」[セリグマン 2002:242-243])[原文は英語でありこの書物の翻訳者はマンローの文章を常体、セリグマン夫人の文章を敬体と訳し分けている]。
日本語の翻訳にして二段組みでわずか4ページほどのテキストであるが、「北極圏から亜北極圏にかけて住む多くの民族と同じように、アイヌの人びとも仕留 めたあらゆる獣の身体に対しては大そう敬虔な態度で臨んで」いたことを示すことを簡潔ながら見事に表現するものとなっている。「仔熊は〈カムイ〉であるた めに檻の中で仔熊は崇められながら育てられ」「また優しく扱われて今でもかなり人に慣れて」いる。供儀にされる直前の熊に「一人の長老が祈りを唱えなが ら、この〈カムイ〉である熊の身体に酒のしずくを振りかけ」られ、「熊は唸り声をあげながら、それでも凶暴というよりはむしろ不意をつかれて驚いたような 表情を見せながら、自らの終焉の場所へと導かれて」ゆくわけだが供儀にする人たちはあまねく「こうすることで熊は幸せになれるだと信じ」ている[セリグマ ン 2002:241-242]。この熊に対する敬虔な態度は、熊の生物学的な生命が朽ち果てた後にも続く。
「雌の熊を送る儀式の場合には、その遺体に首飾りをかけて飾ってやります。熊の霊魂に向かっては、敬意をこめた挨拶の儀を行い、人ぴとに恵みを与えてくれ たことに讃辞を述べ、その霊魂を先祖のもとに送ってやる約束の言葉を唱えて捧酒を行います。こうすることで、その霊魂を満足させてやるのです。熊の毛皮を 紳いだり解体する作業は、伝統密な儀式の約束にもとづいて行われることになっています。人びとは敬虔な態度で熊の生き血を飲むことにしていますが、この生 き血は神聖な薬であるとされています(セリグマン 2002:243)。
もし民族誌家に学問的な感情移入という精神的性向というものがあり、その力能を我々が働かすことができれば、ここには動物の殺害に伴う凄惨な情景という ものが微塵もなく、むしろ美的なエロティシズムすら感じることができるかもしれない。「犠牲になった動物は聖なる存在になったが、しかし動物であるがゆえ に、その前からすでに聖なる存在だった。……原初の人間の眼には、動物は根本的な掟を知っているはずだと映っていた。そして動物は、自分を突き動かしてい る衝動、すなわち暴力が、この根本的な掟への侵犯であるということを知っているはずだと映っていた」[バタイユ 2004[1957]:132]。ジョルジュ・バタイユによる供儀論は、人間を供儀に使うようになった後で、時に動物がその代用として用いられるように なったが、それはそれまでも含めてもともと最古の供儀の対象は動物だったから代用できると考える。そして生命を絶つという暴力、それ自体は残虐ではない が、暴力を組織する者が登場することがそれを残虐にするという(「残虐さは、組織化された暴力の諸形態の一つ」)[バタイユ 2004[1957]:129; 131]。
このバタイユ的な残虐の概念が、アイヌという集合的な表象「(アイヌ)民族の恥」として独り歩きすることについて、キリスト教道徳の体現者で あったバチェラーは(その根源的な理解はともかくとして)十分に感じていたと思われる。ただしバチェラーは、多少なりとも父権主義的なところはあったが植 民地主義のメンタリティを完全に体現していたとは言いがたい。彼はクマ送りの記述を抹消すべきだとは考えず、欧米の読者に対しては少なくともアイヌの文化 のレパートリーとして詳細に記述している[Bachelor 1908:239-252, 1932]。マンローの上記の記述は、バチェラーの『宗教と倫理の百科事典』[1908]に収載されたアイヌの項目のなかの「熊祭り(The bear festival)」[Bachelor 1908:249-250]を踏襲したものと言えるほど共通性があり。つまりバチェラーのマンローの記録映画に対する反発は、クマ送りの表象が日本人にア イヌの偏見を助長することを危惧することが主目的であり、儀礼の存在的価値を過小評価するものではなかった可能性がある。他方、クマ送りの儀礼をアイヌ文 化の内面から理解しようとしていたマンローは、それが少数先住民の「野蛮な」表象として統治者の日本人にどのように映るのかということに関してじつはほと んど無理解であったように思われる。にもかかわらず日本の読者には疎遠な英語で記載についても行わなかったことは依然として謎のままである。それは日本に おけるアイヌ研究において膾炙している、クマ送りとアイヌの当事者性をめぐる両者の間の確執であれば、なぜバチェラーがクマ送りの記述を残し、儀礼に対し てアイヌの内面から理解しようとした——セリグマン夫人の語り口を通してではあるが——マンローがその記述を残さなかったことは疑問のまま残され、この事 実そのものは——古典的民族誌記述にはつきものではあるが——皮肉な結果と言わざるを得ない[Rosaldo 1993](Rosaldo, Renato. Culture & Truth: The Remaking of Social Analysis. Boston: Beacon Press. 1993)。
いずれにせよエキゾチックなイヨマンテの儀礼は、日本の社会においても歌謡曲の題名になり有名になればなるほど、アイヌと日本社会の差異性を 強調する文化表象として流通するようになる。しかし、他方、それは旧土人保護法以来、アイヌの同化をすすめる日本の統治者にとっては厄介な障壁として機能 する。またアイヌの観光化に伴いパフォーマンスとしての熊祭りの挙行に関して日本動物愛護協会からの抗議などが北海道に提出された。これを象徴する事件が 1955年におこる。同年(昭和30)年3月15日に田中敏文(当時)北海道県知事名で「生きた熊を公衆の面前に引き出して殺すことは信仰上相当な理由が あるにせよ同情博愛の精神にもとり野ばんな行為であるから廃止されなければならない」等を理由に「熊祭の行事中にある熊のさらし首についても廃止」も含め て北海道内の支庁長と市町村長に禁止の通達(文書名「昭和30年3月10日付け30畜第471号」)が送られた。
しかし、アイヌの民族に対する文化的な抑圧の象徴を示すこの事件の文書には次のような言葉も記載されている。「生きものを憐れみ殺すに忍びな い気持ちが熊祭の形式の上にも表れるよう指導して下さい」[この通達は後に『北海道公報』6638号82ページに収載される](北海道ウタリ協会 1989:955)。このような措置にもかかわらず少なくとも半世紀後になってこの通達が廃止されるまでにも、すくなくとも3度の儀礼が、それぞれ 1985(昭和60)年1月に旭川市近文で、1989(平成元)年1月と2月に白老町アイヌ民族博物館で実施され、詳細に記録に残されている(池田 2009:28)。前者では写真記録が、また後者では長老・日高善次郎の伝承による儀礼の再現が試みられた。これらはアイヌの代表的な儀礼への行政からの 禁止に対する、アイヌからの応答(あるいは抵抗)であることは言うまでもない。この当時1985年にいわゆるアイヌ肖像権裁判が始まり、1988年に和解 に到っている(現代企画室編集部 1988)。
そのような歴史的経緯もあり、北海道ウタリ協会(現、アイヌ協会)は2005年にこの儀礼禁止の通達の撤回を求めた。北海道は国に対して「動物の愛護及 び管理に関する法律」(1963(昭和48)年制定)との関連性について照会し、同年10月に環境省は動物を利用した祭式儀礼について「正当な理由をもっ て適切に行われる限り法律に抵触しない」ことを示し、道庁は2007年3月に環境省は「イヨマンテは祭式儀礼に該当する」と回答をした。それを受けて同年 4月2日付で先の通達の廃止を北海道に通知した。
つまりアイヌのクマ送りの近代化の歴史は、人類学者に対しては一種のメタ知識としてのアイヌのコスモロジーを理解するための儀礼装置を提示し てくれ、また儀礼に参加する当事者にとってはクマの〈カムイ〉と交流する始原的世界の体験とそれがもたらす感情の多声的空間からの後退を意味するもので あった。またアイヌ自身にとっては、道庁が禁止する以前は、観光化のなかでその始原的な意味が形骸断片化することで急速に生きた意味を失い、他方、禁止以 降は、抑圧されるアイヌ文化のよりどころ、あるいは民族文化のアイデンティティとして、急速にその文化の記録と再構成が「民族再生」のための喫緊の課題に なっていく。
したがってクマ送りの復元の政治化は、「クマ送りの儀礼は(もともと本来は)どのような意味をもっていたのか?」という本質主義的な人類学の
関心から遠ざけることになる。近代のクマ送りの文献を子細に検討した煎本孝は、このような状況に研究上の不足を覚え、次のように述べる。「昭和に入ってか
らの熊送り儀礼は、その詳細な記録にもかかわらず、狩猟採集生活の実際の経験の少ない、あるいは全くない参加者により行われたものであると考えられ、した
がって、これら熊送り儀礼が実際にはどの時代にまでさかのぼり得、またどのような歴史的脈絡の中で位置づけられるのかということを検討しなければならな
い」[煎本
1986:53]。煎本の主張を敷延すれば「採集狩猟生活の実際の経験」のない人たちが再演したクマ送りの記録や彼ら自身の体験は、アイヌが歴史的時間の
中で経験してきた儀礼の内容を反映しておらず、同じ儀礼手続きを執行しているとしても、儀礼の行為者や参加者に去来する感覚はそれぞれまったく別物である
ということになる。
2.文化に対立する一元的自然と多元的自然の問題
自然とは、西洋思想においては次のように位置づけられている。
「規範としての自然とは、「自然」(nature) および「自然な」 (natural) という言葉に含まれる多様な意味のなかの一つ以上が,個人にとっても社会にとっても好ましい生活の基準を与えるという考え方のことである。アーサー・ラヴ ジョイによれば,60を超える意味が区別され,それぞれが称讃と非難の根拠とされてきたという[ラブジョイ 2003:59-65;ボアズ 1990:266](※ボアズ、ジョージ「自然」フィリップ・P. ウィーナー編『西洋思想大事典』荒川幾男ほか訳、第2巻、Pp.266-271、平凡社、1990年)
他方、英語のニュアンスにおける自然とは、オックスフォード英語辞典(OED)では、自然(nature)の語義のもっとも最初の定義は次の ようなものである。
事物(モノ)の基本的な諸性質あるいは諸属性;あらゆるモノに基本的に一貫しており、かつその根本的特性を与える諸属性の、内的で不可分な組み合わせ (The essential qualities or properties of a thing; the inherent and inseparable combination of properties essentially pertaining to anything and giving it its fundamental character. )——OEDの冒頭[I.1.a.]の定義
ここでの自然の定義は要を得ていて、自然は事物(モノ)に内在するものであり、そのモノとは不可分ゆえにその性質もまた普遍で変化がないということであ る。ここからニュートン的な時間や空間概念に表現される近代の自然科学が前提にする自然のイメージを想起することは困難ではないだろう。しかしながら西洋 の自然概念は、生まれてから近代にいたるまで首尾一貫してきたようではないようだ。中世以降には、自然の事物を本質的に決定するすなわち「自然を支配する 力」として能動的な力(natura naturans, 能産的自然)と、その力の受動的な対象としての所産的自然(natura naturata)の区分があった。スピノザによれば、これらの2つの自然は神において融合し、神と自然は同一であり、かつ万物の内在的な原因であると見 なされた。これはデカルトによる心身二元論(他方でこれとは矛盾するがデカルトは『情念論』で心身の合一も唱える)に対比されて、心身並行論と呼ばれる ——これは今日では「性質二元論」というものに分類されジョン・サール[2006:68-71]により論難されている。
人類学のパラダイムでは自然はどのような観点から探究されてきたのであろうか。通常、人類学では、西洋啓蒙主義の伝統を「正しく」受け継い で、人間の文化を自然あるいは自然状態からの脱却を、人間社会が生み出した文化的諸力——力学として表象されているが——によるものであると理解するので ある。そこでは、〈自然〉と〈文化〉の二元論と呼ばれるように、自然と文化を対立的にとらえる見方が支配的である。これは自然の経済や家政学が語源となっ ている生態学(オイコスのエコノミー)あるいは人類生態学のように、環境(=自然)と社会(=文化)の関わりを研究する西洋近代科学における基本的な見方 であると同時に、さまざまな文化を超えて、環境と社会の関わりをもつ基本的な人間社会のあり方を分析する基本的な枠組みないしはモデルとして各社会・各文 化に備わっており、我々はその内容の豊かな多様性について調べるものとされている。
人類学では、このような西洋近代社会の認識論を広く受け継いでいるので、自然と文化の性質についてそれぞれまとめると次のごとくになる。
〈自然〉:観想の対象・受動的対象・必然性・普遍性の表象
〈文化〉:観察者が所有する能力・能動的主体・可変性・発展の表象
レヴィ=ストロースは『親族の基本構造』(原著は1949)の冒頭において、この自然と文化の結節点にインセスト・タブー(近親相姦禁忌)を位置づけて
彼の議論をはじめている。
「我々は文化と自然という相容れない次元に属す矛盾し合う属性を,規範および普遍性という二つの性格のなかに認めたわけだが、インセストはこれら二つの性
格を,いささかの曖昧さもなく,しかも不即不離のかたちで示すのである」[レヴィ=ストロース
2000:67]。※レヴィ=ストロース、クロード『親族の基本構造』福井和美訳、青弓社、2000年
人類学者にとって、近親相姦のタブーが自然から文化への移行を表象するものであるということが、あたり前のこととして受けいれられている。つまり近親相
姦のタブーこそが、文化をもつ人間の普遍性の証であると。しかし、晩年の彼は、日本の愛弟子に対して「普遍的なものは、近親相姦のタブーではなく、インセ
スト」の現実そのものだと述べている[川田
2008:9]。たしかに侵犯(=自然の現実)の発生は、その禁忌(=文化的規制)の認知に先立つ、言い方を変えるとタブーとタブー認知はトートロジーの
関係であり、禁忌の普遍性が重要なのではなく、禁忌のヴァラエティを明らかにすることが人類学者の仕事だからだ。この巧妙なレトリックは、トーテミズムや
カニバリズムという従来の人類学用語の適用をめぐる混乱から、その概念をめぐる一種の「幻想」産出と混乱した議論に対して鋭く批判してきた『親族の基本構
造』の著者らしい言挙げではある[cf. レヴィ=ストロース 1970, 2000:34-44, 2008:253; ニーダム 1977]。
人類学においては、ある種の常識化した自然のと文化の二元論であるが、西洋近代文化の末端に位置すると自任する我ら研究者は、実際に自分たち のフィールドにおいて我々および研究対象である「彼/彼女ら」と共に〈自然〉と〈文化〉の二分法を生きているのだろうかという疑問をもつのは当然である。 つまり、我々・人類学者は果たしてデカルトの嫡子つまり西洋近代の「正統な」遺産相続者なのだろうか。そして、フィールドの人たちは、西洋近代科学とは異 なる構成をもった自然と文化の二元論の世界を生きているのだろうか。
西洋近代の自然科学の認識論における自然と文化の二元論の代表はいうまでもなくルネ・デカルト(1596-1650)である。デカルトは心身 二元論の祖とされており、その主たる議論は当時のガリレオ宗教裁判を恐れて生前(1648)には準備されていたがデカルトの死後16年後に出版された『人 間論』(1664)のなかに表現されている。デカルトの二元論の基本的テーゼは、心と身体は、それぞれ物質性つまり実体(substance)をもちなが ら、異なった2つの性質をもちうるものだとうものである。彼は、それを心と身体、mind と body という二元的な対立で表現する。それぞれに対して、本質と属性が与えられている。心は思考や意識をもつものであり res cogitance (思惟する実体)といわれるが、二元論といわれるが、これは人間の人間たるゆえんであり、動物と人間を分かつ固有の性質である。それに対して、身体は、延 長をもつ実体すなわち res extensa と呼ばれる。なぜ延長かというと、それは意識(心)とはことなり、空間的に場を占めるような存在のことである。心は直感のように、直接的に知ることがで き、空間的条件に制限されない自由なものである。
このような二元論に彼がどのような発想法でたどりついたのかはさまざまな議論があるが、すくなくとも『人間論』には反射と並んで、視覚情報が 脳に伝達される経路や眼球運動や像の成立についての言及があることから、我々自身の身体(res extensa)を見る心、すなわち外部からの視覚表象が投影されてイメージを生む意識(res cogitance)にデカルトが強い関心をもっていたことは明らかである。
では、その心と身体は、どこで統一的な自己というものをもつのだろうか。ジョン・サールは次のように説明する。
「彼(デカルト:引用者)は解剖学を研究し、心と身体の結合点を探るために、少なくとも一度は死体解剖を観察した、最終的に彼は、それは松果体にあるにち がいないという仮説にいたった。……彼は脳内のすべてのものが左右対称に対をなしていることに気づいた。脳には二つの半球があるため、その組織は明らかに 対で存在する。しかし、心的な出来事は一体になっておこるのだから、脳には各半球の二つの流れを一つに統合する地点がなければならない。彼が脳内に見出す おとができた単体で存在する唯一の器官が松果体だった。だから彼は心的なものと身体的なものとの接点は松果体であるにちがいないと仮定した」(サール 2006:53-54)。
今日、松果体を意識の座と考える自然科学的根拠は全くないが、〈思惟する存在〉そのものをリフレクシブな観想の対象にするデカルトにおいてすら、対象と しての自己と意識する心を調停する統一的な地点=観点を必要としたことは興味深い。
もしデカルトの松果体の寓意を、人類学上の議論に当てはめるとするとレヴィ=ストロースもまた、人間を〈自然〉から分かつ〈文化〉の結節点を インセストに求めたと、言うことができるかもしれない。
『親族の基本構造』の初版の公刊(1949)から13年後のレヴィ=ストロース『今日のトーテミズム』において、自然と文化の二元論から、自 然から文化への移行に関する「人類学の中心問題」の検討にあたることになる[レヴィ=ストロース 1970:163]。フランス文献における「最初の一般人類学論」であるジャン=ジャック・ルソー『人間不平等起源論』(1775)をとりあげ、人間の自 然状態からの脱出が、人間集団の人口増加と多様化を生み不平等の起源になったというこの論文を意義をなぞらえながら、そこから得られる人類学上必要な推論 ——ルソーは論文の註10において類人猿はきちんとその行動を観察しない旅行者の間違いで獣に分類された可能性があることを示唆し、異なった民族に関して その人間の相違点について研究する必要性を説いている——についてレヴィ=ストロースは解説する。彼は、動物から人間へ、自然から文化へ、情調から知性へ という、このルソー的考えを、動物を含む世界の同一性の認識と、そこから自他を区別し、同類を相互に弁別する能力——トーテミズム的論理——を見るのであ る[レヴィ=ストロース 1970:165]。
レヴィ=ストロースのその後の思索を追いかけると、自然から文化への移行期に、生まれた分類の論理としてトーテミズムを彼は想定し、その小さ
な著作の末尾において、この思考を人間の「悟性」に属するものであると位置づけている。彼の人間の「自然への認識」への多様性とその基盤の認識論的論理の
探究は、同時期に公刊される『野生の思考』(1962)において余すところなく発揮される。
3.実験室における自然
視覚の神経生理学は、網膜レベルでの視覚情報処理に始まり、視神経交叉での左右の神経繊維の交差と同側への情報の流れ、外側膝状体(LGN)という神経
の中継経路を経て大脳皮質の第一次視覚野にいたる経路のほかに、さまざまな神経の経路があり、脊椎動物がもつきわめて洗練された視覚情報の処理を行ってい
る。このため歴史的に初期の神経生理学から今日における脳科学研究においても、視覚情報の処理に関する網膜細胞のユニークな振るまい、神経回路の配線や大
脳皮質における顕微鏡レベルでの解剖学的な知見と神経生理学で高度に発達した実験手法の組み合わせになどにより、きわめて広範囲で洗練された議論が展開し
てきたものであると言っても過言ではない。
そのような研究の蓄積を端的に表象するのが視覚系の「おそろしいマップ(scary map)」である。これは、網膜由来の神経情報と脳内のさまざま部位(中継する神経細胞の集まり)がさまざまな種類の神経細胞により、さまざまな情報様式 をもって連絡していることを示している。また視覚の神経生理学の実験手法は、視覚刺激の提示においてもユニークな方法を開発してきた。また微少イオン泳動 投与法(microiontophoresis)など、神経細胞にさまざまに作用する薬物の利用を使った実験により、複雑な神経細胞のふるまいを正確に把 握する手法も開発されている。このような洗練されたデータが得られるようになったのは、実験動物と実験機械のハイブリッドの様式が実験研究の歴史のなかで 洗練されてきたということもあげられる。
実験動物は、動物とは手をつけられていないインタクト(無傷な自然)な存在ではあるが、実験が行われる前から、人工的な環境のなかで育てら れ、統制された環境のなかで丁寧に育てられている。動物実験の流れを示すと次のようなものになる。
まず実験動物導入計画がなされ、必要な頭数や導入時期さらには実験までの期間の維持管理経費など予算の確保が講じられる。また、動物実験に は、施設内倫理委員会(IRB)への申請と承認が必要である。飼育(ケア)は施設により、管理要員を確保している場合でもそうでない場合でも、一定の管理 が求められる。次に実験の際には動物舎から実験棟や実験室のある場所まで搬送される。麻酔がなされ、実験室搬入される。眠らされた後に、気道確保および生 命維持のモニター装置などが装着される。視覚刺激が必要な動物では、苦痛の除去のために麻酔が必要になるが、同時に視覚情報を処理する脳の部位の生理学的 情報を入手するために、実験動物を「覚醒」した状態にするという技術が必要になる。ちょうど私たちが歯科治療を受ける際に歯の部分への麻酔が効いて感覚は 麻痺しており痛みは感じることはないが、意識は覚醒している状態である。
そのような前処置が終わると、次に頭蓋部に手術が行われ、実験装置への装着がなされる。それとほぼ同時に、筋弛緩剤投与による人工呼吸が開始 され、生命維持の監視装置が装着される。実験が行われている間は、実験動物に対する麻酔管理がなされる。苦痛の除去と「覚醒時」のデータ採集は実験にとっ ては、倫理的にもまた実験データにとっても必要不可欠な条件である。なぜなら麻酔のレベルが弱くなると痛みを感じることがあり、それが生命監視装置からモ ニターされる乱れ(例:心拍数が増加する)が観察されるが、そのようなストレス管理が、実験中に引き続いて最新の注意を払っておこなわれる。ただし生命監 視装置からモニターされる乱れがなければ(動物が本当に)苦痛を感じていないのかということには未知である。それは生命監視装置からモニターされる乱れが なければ「苦痛がない」と操作的に定義されているからである。人間の痛みの理解同様、動物の痛みもまた、その動物の感覚体験を共有することができない点 で、これまでも、またこれからもブラックボックスのままであろう。
実際、ここまでは実験ではなく「前処置」と呼ばれている一連の流れである。そこからは、実験動物に提示するスクリーン(モニタ)の管理や、脳 内の細胞内/外の記録などが、細心の注意をはらってデータがとられる。もちろん実験データをとるためには「急性実験」つまり実験動物を最終的に安楽殺する まで続けられるものと、電極などを埋め込んだり、さまざまな脳内の手術などをおこなって、麻酔から覚まして、経過を観察し、手術後に健康の回復をまってか ら、継続的にデータをとる「慢性実験」など、実験方法のやり方により、さまざまな管理手法がある。
必要な実験データが取れたり、実験動物の体力がなくなり、それ以上のデータ取得が認められなくなると、安楽殺の決定がなされる。実験は生理学 的データがとられれば終了というわけではなく、脳などの器官(臓器)摘出がとられたり、どの部位に電極が入っていたのかということを確認するために色素な どが注入して、のちほど標本固定したあと、適切な染色の方法をおこなったあと、解剖学的な部位とその実験データの照合が試みられる。後に解剖標本をつくっ て、実験データーの部位を特定するためである。
その標本は顕微鏡で調べるようにするために切片という薄く切られた標本が作成される。また細胞の種類を調べたり、電極を差し込んだ部分を特定 することを「検索する」という。
動物実験が終わったら動物の遺体はうち捨てられるのではなく、必要な部位が長く保存されたり、また決められた手続きにより処分される。一年に 一度は、動物慰霊碑への儀礼がおこなわれ、実験動物への「感謝」と動物霊への慰撫というものも行われる。
次に実験生理学者の日常とはどのようなものであろうか。動物実験をおこなう視覚の実験生理学者は(扱う動物の種類により変化があるが)実験動 物の経費、実験に投下する時間的精神的コストなど要因により、1年間に数回〜十数回の頻度でおこない、1回に最大数十時間の実験しか行えない。つまり実験 生理学者は一年を通して実験ばかりしているというわけではない。実験の頻度とそれに投入する時間は、それを可能にする研究費と、実験に関わる研究員などの スタッフや大学院生など研究室の規模(=ラボサイズ)に大きく依存することが大きい。つまり実験生理学者の時間のほとんどは(大学の授業を除けば)実験 データの整理や標本づくり、他のグループの論文検討、および学会発表用の資料作成等に費やされる。その点では、非実験系の研究者と同じような時間を過ごす という点で、実験以外では大学の研究者の生活スタイルには共通する部分も多い。
ただし、これはすべての実験系の自然科学者に当てはまることではなく。例えば、自動化が進みつつある遺伝子を扱う実験室の研究者などに比べる と、実験以外の時間を費やす時間は多いだろうと、当の神経生理学の研究者たちは、少なくともそのように述べた。
実験生理学者たちの間には、経験と「現場力」については、次のような関係が見られる。実験では生きた生物個体つまり生体という「なまもの」を 扱うので、どの研究室で修練を積んだかということが重要な要素となる。そのために研究室の院生などの教え子を関連する研究室に派遣したり留学させたりして その技術的伝承を維持することすらおこなう。なぜなら有効なデータ得るためには、現場力や暗黙知ような知識が必要で、それを。この部分による技術は、ある 種の秘義化する側面がある。
実験の秘義化には別の側面もある、技術や実験の内容を公開することに対するアニマルライツ派への脅威である。アニマルライツ派とは、この場合 実験動物の反対の立場をとり、場合によっては飼育舎に侵入して、動物の解放(リリース)をも辞さない行動主義をもつ人たちである。日本では欧米における過 激な行動主義をもつ人は「まだ少ない」が、そのような行動主義が今後はびこることを懸念し、またインターネットの書き込みなどで間接的に風評を立てられる ことを非常に警戒している。とりわけ大学は、学生・院生が学ぶ自由な環境を保証する場であり、そのようなアニマルライツ派の人たちをキャンパスに侵入する 危険性を排除できないと言われている。
また実験室では、研究室(ラボ)に所属している研究チームが分業体制を組んで一体になって実験をする。指導する教員や「先輩」は数少ない実験 の現場で、その適切な実験方法について伝授する場にもなっている。
では、実験室のメンバーたちは、実験動物に対して、どのような感情をもっているのであろうか。
実験動物の飼育(ケア)については、供給体制が分業化されているラボと「自前でなんでもやる」ラボとの違いはあるが、若手研究者は飼育場所の 清掃や餌やりなど、基本的な飼育を学ぶことが徒弟として重要なこととされている。
「飼育は注意深く観察し動物についてよく知ること」に寄与すると言われている。
私は、最終的には実験の犠牲になる実験動物には、常日ごろからモノを扱うような態度で接し、特定の実験動物に感情移入しないことつまり、実験 者による動物の非人称化という感情的手続きを無意識のうちにおこなっているという予見があった。これを非人称化仮説と呼ぶことしよう。非人称化によって、 モノのように扱えるから冷静に動物実験できるようになると私は考えたが、この仮説は実際には本事例研究ではあてはまらなかった。
実際には、非人称化どころか、実験前や後にも動物の個性や特徴について実験者は細かく記憶し、さまざまなエピソードで語ることが多い。つまり 非人称化どころか、人称化して、動物の心理的な個性について、擬人化という表現も含めて彼らは理解している。つまり、実験動物にも「心の存在」を認めてい るのである。それにも関わらず、それゆえにこそ、実験動物には神経学的特徴に個体差が反映されるとは決して考えない。すなわち個性は表面的なことであっ て、実験動物の神経学的深層は生物学的な普遍性にもとづく共通なものであることに些かの疑いももたない。
では、神経生理学の実験室における〈自然〉が具体的には何をあらわしているか整理してみよう。まず脊椎動物にある神経細胞の普遍的性質(膜電 位、神経スパイク、神経伝達物質など)がある。次に、生物種(species)に固有な神経回路や視覚情報処理における[説明や解釈の際の]合目的性があ る。また観察者の影響を完全に排除できると信じている観察対象の独自性ということも〈自然〉が内包する性質そのもである。このような自然の〈客観性〉を保 証するために人為的な影響(artifact)を除外する実践的な努力がおこなわれている。すなわち、〈自然〉は人為的影響という〈文化〉と境界を接して おり、実験室において自然科学者たちは、客観的な〈自然〉の領域をより広くとるために日夜努力しているさまが観察することができる。
このような自然科学者の努力は、〈客観性の保証〉のための努力ということができる。自然科学の歴史を紐解けば、この〈客観性の保証〉というこ との起源が、現在の彼/彼女たちの努力と驚くべき異なることをシェイピンは、ロバート・ボイルの実験を例にとって指摘している。真空ポンプ実験の客観性を 保証するためにロバート・ボイル(1627-1691)は紳士が立ち合い「ただ観察だけ」を求めた(ad hoc ergo propter hoc)(Shapin 1990)。この場合における真理の確認とは、「その場における確認こそがその場の適切さを保証する」かたちで証人によって確認されるという社会的な承認 を意味している。これに対して、現在の神経生理学者は、実験の追試験が高価な機械での高い技巧を要求するものであるために、実質的に実験者しか〈客観性が 担保〉できないものの保証について述べている。神経生理学の准教授は(二光子励起イメージング法=分子が光子を2個同時に吸収して励起される)「信じられ ない神業のような実験手法」が信憑性をもつのは、その後の研究の進展によりその実験結果と矛盾しない新事実が事後的に発見されることにのみよると主張した (post hoc ergo propter hoc)。
ボイルの真空ポンプ実験の客観性が社会的なものであるのに対して、この二光子励起イメージング法の客観性の保証とは、未来に起こるかもしれな い「事後的に証明されることによって、その場の適切さが保証される」という、我々がマートン流の科学の社会学において客観性を保証するような公準とは全く ことなる論理的な説明があることに驚かされる。実験室における〈自然〉という客観的データを保証するために人工物(=文化)すなわちアテーィファクトを極 小化するという行為から、〈自然〉を描出する方法がほかにもある。それは、〈文化〉によって〈自然〉が凌駕された状態、すなわち実験の失敗を、今日の自然 科学者たちはどのように説明し、その後の行為に対処するかということを調べることである。実際、動物実験の失敗にまつわるエピソードは多い。新しい赴任地 で動物実験を開始すると、それまでと全く同じ装置おなじ条件なのに半年間データがとれないことが、しばしば当事者たちから「動物実験はデリケート」である と言われる。その際の、対処法は、上手くできているラボとまったく同じセッティングにする。さらに出先のラボで実験を手伝ってもらい現場で学び、それを自 分たちにラボで再現する。ただしラボ間でラポールが確立されていないと、その伝授は容易ではないことは明らかである。これら一連の過程は、実験の失敗(= 自然)を人為的な操作(=文化)を通して克服することに他ならない。
実験室内で使われる現地語としての「自然」について考えてみよう。フィールドと実験室を往還する生態学者たちがしばしば「自然 (nature)」という用語を多用するのみならず自らの多くを自然主義者(naturalists)と呼ぶのに対して、神経生理学者たちの日常語彙の中 に「自然」が登場することは希である。この2つの研究領域における対比は、日本と欧米のそれぞれの文化(文明)がもたらす自然/Nature という語義の対立よりも強いコントラストがあるように思える。このことから、欧米語における nature/cuture の二元論の思想の翻訳語としての、それぞれの「自然」と「文化」についても現地語としての日本語の語用論(pragmatics)についても注意を払わね ばならないことを示している。語用論として、日本語の「自然」が意味するもの(=「人為的でないもの」)は自然環境により近い。実験室は「非自然的」環境 という意味づけがされており、そのような言語使用が認められるのか。また隠喩としての自然には、「外界的自然」を受容器(=眼)を通して見える(=情報処 理)というメカニズムの研究という神経生理学の独特の位置づけという理解は、自然と対比した人工物とそれに対する機械的反応の隠喩で捉えてしまう可能性が あるからだろうか。
他方「動物」と「実験」が組み合わさった「動物実験」という語彙がもつ、感情喚起力についても注意が必要である。実験動物の話をそれになじまない人に話 すと露骨な嫌悪や「非人道的行為」と非難される。この事態は、デカルトどころかアリストテレス的探究心からの現代人の知的荒廃あるいは科学の進歩からの後 退だろうか。他方でバイオフィリア(Wilson 1984,1993)つまり生命への志向性への関心や信条の一般化が進んでいる。そこでは、西洋文明が規定してきた観相や分析の対象としての自然、その表 象としての動物という観点から離脱が起こっているのだろうか。すなわち動物=文化、動物(生物)=自然という、これまでの西洋文明の見方とは真逆の現象に 向かっているのだろうか。
自然科学者の動物実験の洗練化と、バイオフィリア的エートスにみられるインタクトな自然としての動物を自然環境の文脈で全体論的に愛好するという現象 は、相反するものであり、現在その二極方向へと我々の文化は突き進んで進んでいるのだろうか。自然と文化の二元論が現実的にはうまく照合しないので、その 両者を扱うための別の思考実験をしてみよう。たとえば、自然と文化という二元論的要素を認めたうえで、それらが相互に浸透しハイブリッドを構成していた り、キメラを形作っていたり、また、場合によってはそのハイブリッドの中から二元論的要素を純化する(=二元論化する)動きがあるとみるのである。
このような観点に立てば、客観的にとらえうるものを自然とし、それを理解する人間の営為を文化と名付けるならば、自然科学者たちの活動は文化 的知恵(sapientia)を産出する重要なレパートリーのひとつである。しかし神経生理学者たちは、自分たちは文化的活動に与っていないと発言する。 いわゆる文化の違いが自然科学に反映したり影響を受けていることを自然科学者は一般的に否定する傾向にあると言える。欧米の自然科学に対して自分たちの科 学との差には違いがないと言いつつも、 文化、英語運用能力のハンディキャップ、学問層の厚み、ノーベル賞の受賞の量の違いなどにおいて、自然科学という営為の実態がどうやら文化的ないしは政治 経済的不均衡に晒されていることについては自覚している。ここでの文化の違いは、いわゆる表層的な(例えば洋の東西という)比較文化論に終始することが多 い。
自然科学者(ここでは神経生理学者)と文化人類学者が、心に抱く自然と文化は、二分法的な秩序によって区分[→近代西洋の存在論様式]されて
いるが、両者のインターフェイス(境界面)では、この二分法の関係が相互に押し合い引き合いしている。例えば、実験を文化的実践とみる文化人類学者の見
方、実験の失敗を克服しようとする神経生理学者の関係は図のような対立関係にある。これらは自然と文化のハイブリッドのなかにおける自然と文化を再び二元
論化する、いわば純化(purification)のプロセスであると言える。〈自然〉と〈文化〉の二分法を共有しているはずの神経生理学者と文化人類学
者には、それらの領域区分において境界面の位置は異なる。すなわちこの二分法の設定は自然と文化のハイブリッドが織りなす内実を表象するものである。
4.野生からみる自然
「オーストラリアと北米では、他所と同様に親近霊と守護霊とが動物の形をとるのが圧倒的である。それらはいわば、西アフリカの「叢林霊」や中米およびメキ シコのナグアル(nagual)とパラレルなものである」(上:171)※エリアーデ、ミルチア『シャーマニズム(上)』堀一郎訳、筑摩書房、2004年
「トゥングースのシャーマンは補助霊として蛇を持っているが、巫儀の間に爬虫類の運動をまねようとする。また補助霊としてつむじ風を持っているシヤーマン はつむじ風のように振る舞う。チュクチとエスキモーのシャーマンは狼に変身する。ラップ人のシャーマンは狼、熊、馴鹿[となかい]、魚になる。セマング族 のハラが虎に変わることができるのは、サカイ族のハラクラクやケランタン族のボモールと同様である。」(上:171)
「動物の形で補助霊があらわれること、それと秘密の言語で対話すること、シャーマンがかかる動物霊に化身すること(仮面、身振り、舞踊、など)は、シャー マンが人間の状態を放棄する——換言すれば、「死ぬ」ことができる——ことを別の方法で示しているという点である。悠遠の昔から、ほとんどすべての動物は 他界へ霊魂を伴い行く導き手として、または、死んだ人間の新しい形として考えられてきた。「祖先」であるにせよ、「イニシエーションの師匠」であるにせ よ、この動物は他界と真実にして直接的な関連を象徴している。おびただしい数の世界中の伝説や神話で英雄は動物によって他界に運ばれて行く。新加入者を背 中に乗せて叢林(地下界)に運んだり、顎にはさんだり呑み込んだりして「殺して復活させる」のは常に動物である。最後に古狩猟民の宗教の支配的特徴をなす 人間と動物との間の神秘的連帯性を考慮しなければならない。これによって、ある種の人間は動物に変形し得、その言語を解し、その予知力と神秘力とにあずか ることができる。シャーマンはいつでも動物の生活様式にあずかることができ、ある意味で人間界と動物界との離婚がまだ起こらなかった、かの神話時代に存在 した状況を再現するのである」(上:172)
「守護霊はシャーマンをして変身を可能ならしめるのみならず、シャーマンの「写し」でもあり、第二の自我(alter ego)でもあるわけだ。この第二の自我はシャーマンの「霊魂たち」の一つであり、「動物の形をした霊魂」——もっと正確には「生命霊」なのである。 シャーマンたちは互いに動物の形で対決し、もしその第二の自我が戦いで敗れると、シャーマンもやがて死んでしまう。」(上:173)
「未来のシャーマンはそのイニシエーションの過程で、巫儀の間に精霊たちや動物霊たちと交通するための秘密言語を習得しなければならない。彼はこの秘密言 語をその師匠からか、もしくは自分自身の努力——つまり精霊たちから直接に——よって習得する。……して用いられ到。どのシャーマンもそれぞれ自分に固有 の歌を持っていて、それを精霊に懇祷する際に詠唱する。秘密言語が直接問題にならぬ所でさえ、その痕跡は、例えばアルタイ語族におけるように、巫儀の間に 繰り返される理解し難いリフレインの文句のなかに見出される」(上:174)
「この秘密言語が実際に「動物言語」か、動物の啼き声に由来することが非常に多い。南米では、新米のシャーマンはそのイニシエーションで動物たちの声をま ねることを習得しなければならない。……カスタニェはキルギス・タタールのバクサがテントのまわりを走りまわり、跳ね、唸り、飛ぶ行事を記録している。バ クサは「犬のように吠え、参会者の臭いを嗅ぎ、牛のように吠え、羊のように唸り、叫び、メーメーと啼く。また、豚のようにブーブー言い、ヒヒンと言った り、クークー言ったり、驚くべき正確さで動物の啼き声や、鳥のさえずりや、その飛ぶ様子を真似し、そのすべてが聴衆に深い感銘を与える」と。」(上: 175)
「世界中どこででも、動物、とくに鳥の言葉を習得をすることは自然の秘密を知り、予言をすることができるのと同価値である。鳥の言葉は通常、蛇や呪的動物 と見做されている動物を食べることによって習得される。こうした動物は未来の秘密を啓示する。これらは死者の魂の容器、または神々の顕現と考えられている からである。だからその言葉を習い、その声をまねすることは、あの世や天上界と交通し得る能力に等しい。シャーマンの衣裳とその呪的飛翔とについて論ずる とき、この動物とくに鳥との同一視の問題に戻ってくるであろう。鳥は魂をあの世に導いてゆくものである。鳥そのものになること、鳥に伴われるということ は、生きているままで天界やあの世へのエクスタシーの旅を企てる能力を示すものなのである」(上:176-177)
「多くの伝承において、動物との親交や動物の言葉を理解する例のあることは、楽園的徴候を示している。初めのとき、すなわち神話時代には、人々は動物と平 和に暮らし、動物の言葉を解した。聖書の伝承の「人間の堕落」に比すべき原初的破局のときまでは——人間がこんにちそうであるように、死ぬべきものとな り、性を持つものとなり、自らを養うべく働かねばならなくなり、動物と敵対関係に入るまでは——、そうではなかったのである。」(上:177)
かつてツングースと呼ばれたエヴェンキとエヴェンの狩猟動物に対する取り扱い方とは、きわめて道徳的である。ツゴルコフ[1978]は、それをアニミズム の痕跡として次のように解説する。
「ツングース人の狩猟崇拝とは次のような前提の上に基礎づけられている:食糧、衣服、薪などを得るために、動物、鳥類、魚を殺したり、木を切り倒すこと は、自然に反しているのではないし、またそれを傷つけることでもない。自然に反することとは、必要もないのに傷つけ、自然の資源を無意味に浪費することで あり、それは天罰を受けるに価する悪行であると見なされている。ツングース人は、殺すことが目的となった殺害、必要のないものを得ること、そして動物を虐 待することを、まさしく反道徳的であると考えている。ツングースは、氏族のメンバーが鹿あるいは犬、あるいは他の動物を虐待したために氏族全体が滅んだと いう伝説を伝えている……。狩猟動物への崇拝は、狩人の獲物袋の取り扱いに関する詳細な規定にからも伺い知ることができる。狩人が獲物をもって集落に戻っ てくる時には、話してはならず、事物を叩いたり、咳払いをすることで、その帰還を知らせる。狩られたキツネやクロテンは目隠しされて家の中に持ち込まれ る。ジャコウジカを持ち帰る時には、間口の狭い入り口からは入れることができないくらいその獲物が大きいかのような振る舞いを行う。その間も、彼らは物音 をたてることは禁じられているのだ」[TUGOLUKOV 1978:420]。
Tugolukov, V. A., 1978. Some Aspects of the Beliefs of the Tingus
(Evenki and Evens)., In "Shamanism in Sibria." Dioszegi, V. and M.
Hoppal eds., Budapest: Akademiai Kiado.
人間と動物の共通の地平をもつのはただたんに〈道徳〉的な矜恃だけではない。性的な関係(=インターコース)という媒介によっても可能である。「動物に恋
をする」という動詞(ウァイ=ムラ・ガメタラーリ)において「表された観念は、自ら近づいて来て殺されるままになるように、動物を性的に誘いこむことであ
り、これ自体が性的な支配行為である」(p.277)
4.3 ディスコラの4つの存在論・再考
本研究における人間と動物の関係がどのような位相にあるのか、ここでフィリップ・ディスコラ(2006)に議論について考えてみよう。
ディスコラは、エトムント・フッサールの現象学のアイディアから、人間を人間自身がみる認識(=人間の人間についての存在論と言うことができ ないか?)には、内面性(interiority)と身体性(physicality)という二元論が抜き難くあり、それはまたポール・ブルームの所論を もちいて「生得的」であるという[Descola 2006:3; Bloom 2004:195]P. Bloom, Descartes’ Baby: How the Science of Child Development Explains What Makes Us Human (New York, Basic Books, 2004).
「根源的な構成が行なわれる領野、すなわち経験においては、時空内でさまざまに現出する多くの事物が根源的に与えられているだけではなく、生物も根源的に 与えられており、その中には人間(《理性的な》生物)も含まれている。とりわけ人間は二つの別個の所与の結合体ではなく、二重の統一体 (Doppeleinheiten)すなわち、それ自身の内部で二つの層を区別しうる統一体、つまり事物と心的生活をともなう主観との統一体である。人間 を統覚すれば、おのずから人と人との相互関係やコミュニケーションの可能性も与えられ、さらにすべての人間と動物にとって同一の本性(Natur)も与え られる。そのうえさらに、交友や結婚や団体などの社会的な結びつきも、比較的単純なものから複雑なものまで与えられる。これらは人間相互の間で創り出され る結びつきである(ただし、ごく低次の段階の結びつきはすでに動物たちの間にも見られる)」。フッサール『イデーン II-2』立松弘孝・別所良美訳、192ページ、みすず書房、2001年。
「さてそこでわれわれが共握(Komprehension)とその構成の諸能作をわれわれの諸考察の枠の中に引き入れると、それらの能作によって、以前は 個別的に思惟されていた自我が〈彼にとっての〉諸客観のうちにあるものを〈他者たちの身体〉として把握し、そしてそれらの身体と一緒に他の自我たちをも把 握するのである」フッサール『イデーン II-2』立松弘孝・別所良美訳、208ページ、みすず書房、2001年。
彼の議論によると、人間と他の種類の動物がどのような世界性——ディスコラは存在論(ontology)と呼ぶ——をもっているかで身体性と内面性から 考える必要性を強調する。
ディスコラの議論では、人間と動物の間の関係において、身体性の類似(+)と内面性の類似(+)に基調におくものはトーテミズムである。カン ガルーのトーテムに属する男を指し示し「彼はカンガルーである」と存在論的属性が完全に合致する。他方、日本の神経生理学における動物実験に動物は、同じ 中枢神経有して同じ神経情報処理をする点で身体性は合致(+)するが、デカルトと同様、我々には動物に洗練された心的メカニズムがあるとは考えない、つま り内面性は一致しない(−)。これは自然主義(naturalism)である。また、身体性は異なる(−)が、動物と内面性が繋がる(+)代表的な考えは アニミズムである。身体性(−)も内面性(−)繋がらない関係は、人間と動物のあいだに直接関係性はなく、それぞれの人間界と動物界の関係をつなぐもの は、たんなる類推的関係でしかない。その典型は中国の十二支における人間と干支の動物の関係のようなものである。
これらの4つの存在論はディスコラによれば、お互いに対比的な関係であるが、人間の思考においてそれらが相互に排除するような関係でもない。 それを表現して彼は次のように言う。
「私はこれらの同一化(同定化, identification)の4つの様式は相互に排除するものではないことを明確にしておきたい。各々の人間は、状況に合わせてそれらのどのような様 式を活性化するだろう、しかしながら、リアリティを感じまた解釈する主たる枠組みを通して、同じ実践コミュニティの中で技法と知識を得た人に与えられるあ る特異な時間と場所において、この4つの様式のどれかが優先するようになるのである。この(リアリティを与える)枠組みを存在論と呼ぼう」 [DESCOLA 2006:8]
実験動物を含めて、日本の社会における人間と動物の関係について、ディスコラの4つの象限にあてはまる動物の地位には、どんなものがあるのかについて考 えてみた。
まず身体性の類似(+)においても内面性の一致(+)において際立ったものは、例えば『ファインディング・ニモ』にみられる動物の社会をテー マにした子供向けのアニメーションである。クマノミの父親マリーンが人間に拉致されたニモを取り戻す話だが、海洋生物のしぐさやコミュニケーションから人 間と同等の世界がある。身体性の類似(+)をもちながらも内面性には共通性がない(−)ものが本研究でとりあげている動物実験の世界である。他方、身体性 にはまったく共通性をもたない(−)が、内面性には類似(+)のものを認めるのがペットである。そして、身体性(−)も内面性(−)をもちあわせないもの が食肉にされる動物である。
実験動物は、現代社会における動物のオントロジーの一角を占めるという点で、その存在論的価値が与えれている。現代社会のなかで動物は自然主 義、アニミズム、トーテミズム、そして類推主義としての存在様式をもっており。自然主義の観想の対象としての実験動物は自然科学という枠組み(= fictio)の中でのみ唯一〈自然〉としてのデータを産出できる条件を与えられているに過ぎない。そして、動物実験から〈自然〉を産出することができる 条件とはなんであろうか。実験動物から〈自然の真理〉を引き出すためには、真理を保証するための社会的なゲームの規約の手続き——倫理委員会、客観性の担 保、査読制度など——という社会性に根ざした正当化の文脈と条件が不可欠である。神経生理学者は、そのような真理ゲームのプレイヤーの一人である。
本研究における未解決の問題がある。それは自然を産出する際における人間の〈技術〉をどのように位置づけるかということである。真理探究の ゲームプレイヤーではなく、実際に〈自然の力〉を引き出そうとする非正統的科学者の存在——NPT非加盟国の科学者、ガレージサイエンティスト、麻薬カル テルに従事する化学者など——は自然/文化の二分法とは無縁の存在で、ひたすら自然から既存の文化の存在を脅かす破壊力や自己充足の知的満足や快楽を引き 出そうとしている。彼らは自然科学的精神の嫡子である実験生物学者と明らかに異なるが、はたして彼らはデカルトの庶子なのだろうか。あるいは、法的身分と しての嫡子と庶子をわけるという発想は、DNA判定により親子の本質的な鑑定が可能になった現在、そのような発想そのものがナンセンスなのだろうか。にも かかわらず、依然として私たちは技術という自然と文化がハイブリッドを起こした混成体を抜きに自然から恵みを得ることができない。文化の誕生の後以降、私 たちはすべからく技術に依存した生活を送っている。真理探究のゲームプレイヤーではなく、実際に〈自然の力〉を引き出そうとする非正統的科学者のみではな く(ill health からzero defaultを目論む)治療や治癒から、生命能力の増強(エンハンスメント)を目指す我々もまたデカルトの庶子である。この技術への信仰と日常世界への 浸食は、ハイデガーやハバーマスが批判した論点と軌を一にする。自然の虚構性あるいは徹頭徹尾、文化性に意味づけられる〈自然〉の中を我々は本当に生きて いるのだろうか。
●Do-it-yourself biology
DIYバイオとは「自己流生物学、またはDIY生物学、 DIYバイオ(英: Do-it-yourself biology, DIY biology, DIY bio)とは、バイオテクノロジー(生物工学)に関する拡大中の社会運動である。この運動では個人・共同体・小規模な組織が、伝統的な研究機関と同じ方法 で生物学や生命科学を学んでいる。DIYバイオは主に、学界や企業からの広範な研究訓練を受けた個々人によって行われており、正式訓練を受けたことが少な いかゼロである他のDIY生物学者(DIYバイオロジスト)を指導・監督している。これは趣味として、または地域教育や開放的科学イノベーションのための 非営利努力として行われ得る。同時に、利益やビジネス着手のためにも行われ得る。 他の関連用語も、DIYバイオの共同体に結びついている。バイオハッキングやウェットウェアハッキングといった用語は、ハッカー文化やハッカー倫理との繋 がりを強調している[1]。ハッカーという用語は本来の意味、すなわち物事を行うために新しくて賢い方法を見つけるという意味で使われている。バイオハッ キングという用語は、また、グラインダー達における身体改造の共同体によっても使われており、これはDIYバイオ運動と関連するが性質は異なると考えられ ている[2]。バイオパンクという用語は、この運動の技術進歩主義的・政治的・芸術的な要素を強調している。」日本語https://bit.ly/3fTe37u)
"Do-it-yourself biology
(DIY biology, DIY bio) is a growing biotechnological social movement in
which individuals, communities, and small organizations study biology
and life science using the same methods as traditional research
institutions. DIY biology is primarily undertaken by individuals with
extensive research training from academia or corporations, who then
mentor and oversee other DIY biologists with little or no formal
training.[citation needed] This may be done as a hobby, as a
not-for-profit endeavour for community learning and open-science
innovation, or for profit, to start a business.
Other terms are also associated with the do-it-yourself biology
community. The terms biohacking and wetware hacking emphasize the
connection to hacker culture and the hacker ethic.[1] The term hacker
is used in the original sense of finding new and clever ways to do
things. The term biohacking is also used by the grinder body
modification community, which is considered related but distinct from
the do-it-yourself biology movement.[2] The term biopunk emphasizes the
techno-progressive, political, and artistic elements of the movement."-
Do-it-yourself biology.
パースクティヴィズム(観点主義)とはヴィヴェイロ・デ・カストロ(Viveiro de Castro 1998)が主張する人間と動物の存在論についての見解あるいは解釈図式である。彼によるとアメリカ新大陸先住民とりわけアマゾンの先住民において、その 自然認識とりわけ人間と動物の間の関係について独自の視点(思考法)が存在する。それは一言でいうと、それぞれの動物たちには人間と同様なあるいは「対称 的」な生活世界があるという。
「動物は人びとである、あるいは、動物は自分たちを人として見ている。このような主張は、つねに次のような観念と仮想的に関連付けられている:各々の生き 物が指し示すかたちは、ちょうど外被(一種の「衣服」)であり、内部の人間のかたちを隠すかのごとくである、通常は、シャーマンのように生き物種類超えた ような存在か、特殊な種類の者の眼にだけに見えるのである」[VIVEIRO DE CASTRO 1998:470-471]。
ここには西洋の人間中心主義にみられる動物と人間が別々の存在があるという命題は存在しない。アメリインディアンの存在論では、人間と動物はともに「内 的存在形式としての人間」がその姿——それは衣服として表現される——を変えているに過ぎないという。もちろん、それは誰もがその「内的人間形態」を見る ことができず。シャーマンのような「種を超えた存在」の感覚能力によってのみ可視化されるのである。
もちろん内的な存在の形態についてのアメリインディアンの説明は非常に錯綜したものであり、リビエール(1994)を引用しつつ次のように解 説している。
「この「衣装」という主張は、変身(メタモルフォシス)——動物のかたちをとる諸精霊、屍体およびシャーマンたち、他の種類の獣に変身する獣たち、不注意 にも動物になってしまった人間——の特権的な表現のひとつであり、[RIVIERE 1994:256]によるとその変身とは「高度に形質転換のできる世界」においてどこにでも存在するプロセスなのである」[VIVEIRO DE CASTRO 1998:471]
このことは単純化すればヴィヴェイロ・デ・カストロのいうパースペクティヴィズムがしばしば「衣服の交換」という表現で語られるが、これが「アメリイン ディアンの存在論」(Viveiro de Castro 2004)とともに研究者の間で混乱と毀誉褒貶を産む原因になっていると思われる。だが彼の主張の焦点は、我々が表面的に騙されやすい——美女やイケメン の色香がどれだけ儚いものであるのかについて読者の多くは同意してもらえると思う——外見ではなく慣習的行動様式つまり彼の言葉を使うと「ハビトゥス」に よって存在が規定されることもきちんと指摘している。
「例えば、人間の姿をとることで、人を襲うジャガーの(ほんとうの)姿を隠してしまうという点で人を欺いてしまうにも関わらず、身体の見えるかたちはさま ざまな情動を違いの強力な徴(しるし)になる。つまり、私が「身体」と呼んでいるものは、明確な物質の同義語でも、固定的な姿のことでもない。すなわち、 ハビトゥスを構成するような、情動の一連の集合状態あるいは存在の方法なのである」[VIVEIRO DE CASTRO 1998:478]
このことは彼自身が「身体が衣服なのではなく、衣服が身体なのだ」と米国の象徴的相互作用論者顔負けの発言をしていることでもわかる。
「身体は衣装と言っているのではなく、衣装が身体なのである。まさに適切な儀礼的文脈が与えられたならば、皮膚の上に効果的な意味を刻印し、それらを着こ なすアイデンティティを形而上的に変形させる力を与えることができる動物の仮面を使う(あるいは少なくともその原理を知る)社会について私たちは議論して いるのである」[VIVEIRO DE CASTRO 1998:482]
我田引水を承知で私はこの文章から、ある操作——引用文では一例として「動物の仮面」をつけること——が、人間の世界と動物の世界を転移させる。つまり 2つの存在論で規定される世界を「移動」できる世界観をパースペクティヴィズムの重要な特徴として取り上げたい。
ではヴィヴェイロ・デ・カストロの観点主義(パースペクティヴィズム)でいったい人類学理論に対して何を伝えたいのであろうか。それはアメリ インディアンの存在論である観点主義を自然の複数性を表現する「多自然主義(multinaturalism)」と今日の西洋近代社会が用意する「多文化 主義(multiculturalism)」対比する。彼は言う。
「もし西洋の多文化主義は公的な政治としての相対主義であるならば、アメリカ先住民の観点主義者のシャーマニズムは宇宙論的な政治における多自然主義にな のである」[VIVEIRO DE CASTRO 1998:472]
西洋社会における文化と自然の対立は、言語学者のエミール・バンヴェニストを手がかりにして、主体の自然とモノとしての他者の身体の対比として表され る。
「もし「文化」が主体の内省的な観点であるならば、それは魂の概念を通して客観化され、「文化」は主体がとる他者から影響をうける身体という視点になると 言うことができる。つまり、もし(大文字で表記される)〈文化〉が〈主体〉の本質であるならば、〈自然〉は身体——つまり主体の対象(=客体)——として の〈他者〉の形態をとるだろう。〈文化〉は、「私(=一人称)」と発音する自己言及的な形態をとり、自然は非人格の形態か、対象[=客体]そのものになる が、この対象は「それ(=三人称)」と発音する非人称によって示されるのである[BENVENISTE 1966:256]」[VIVEIRO DE CASTRO 1998:478]
一般言語学あるいは記号論的な思考法をつかってパースペクティヴィズムの位置づけを、グレマスの四角形を手がかりに私は整理してみた。【図参照】
5.二元論を超えて
ジョン・サールは、内面的一元論あるいは一人称的知識の復権を唱えて次のように言う。
「要点は、知識が客観的・三人称的・物理的事実であるかぎりは、その知識およぶ範囲からは必然的にとりこぼされてしまう現実の現象がある、ということだ。 現実の現象とは、かたや色の経験であり、かたやコウモリの感覚である。これらは主観的・一人称的・意識的な現象だ。……私はある種の存在物(エンティ ティ)、つまり私の色の経験とある関係を結ぶ。コウモリはある種の存在物、つまりコウモリであるとはどのように感じることかという経験とある関係を結ぶ。 世界にかんする完全な三人称的な記述は、これらの存在物をとりこぼす。それゆえ、その記述は不完全である。メアリーとコウモリの専門家の例は、その不完全 さを示している」(サール 2006:133)[SEARLE 2004:67-68]。
※ここでのメアリーとは、哲学者フランク・ジャクソンの思考実験で、色の知覚について物理学と生物学に関する完璧な知識をもつ、架空の神経生物学者メア リーは、白と黒以外の色が存在しない環境で育ったと仮定して、色に関する知識がすべてあるにも関わらず彼女の経験には「色がどのように見えるかという知 識」は含まれていないという問題をもつ科学者(あるいは知識の寓意)のことである。
※またコウモリの専門家とは、哲学者トマス・ネーゲルによる思考実験で、コウモリの神経生理学について完璧な知識をもった研究者においても「こ うもりあるとはどんなことか?どんな感じがするのか?」ということが取りこぼされてしまう現象のことをさす。ネーゲルは「意識の本質」とは、客観的な説明 から抜け落ちる主観的な側面をも含むものであることをこの思考実験から指摘している。
※アレクサンダー・フォン・ユクスキュルが、それぞれの生物種には自分のとりまく環境に関する知覚から構成される環世界(Umbelt)があ り、種に固有の相対性をもつということをすでに指摘している。これらの思考実験は、環世界間の〈本質的な違い〉と、種間を横断した認知の不可能性について 表現しているが、このことははからずもこの種の議論をおこなう哲学者が、同一種内における主観的知識の本質性についてはなんら疑うことも、その必要性もな いことを前提にしていることがわかる。彼/彼女らは主観の本質主義を放棄しない懐疑論者である点で[デカルトをいかに批判しようとも]心=意識の本質を前 提にする二元論者である。他方、生物学者ユクスキュルは、そのような環世界間の〈本質的な違い〉を出発点にして、種間を横断した認知の可能性を具体的に模 索しようとする点では、今日の認知科学の祖の一人であると言える。
(先を続けよう)
サールにおいて重要なことは、因果論的還元(causal reduction)と存在論的還元(ontological reduction)の区分である[サール 2006:160-164]。
「タイプAの現象をタイプBの現象に因果論的還元できるというのは、タイプAの現象のふるまいが完全にタイプBの現象のふるまいによって因果的に説明さ れ、かつ、タイプのAの現象がタイプBの現象を引き起こすさまざまな力のほかに因果的な諸力をもたない場合に限られる」[サール 2006:160]。
「科学の歴史においてはしばしば存在論的な還元が因果的な還元に基づいて行われてきた。……意識の場合、因果的な還元を行うことはできるが、私たちが意識 という概念をもつというポイントを失うことなく存在論的な還元をおこなうことはできない。……意識とは、固体性や液体性のように表面的な性質を備えた他の 現象とは異なるのだ。……意識と志向性は、一人称の存在論を備えることにおいてのみ独特なのだ」[サール 2006:160-162]。
「現実の「物理的な」世界は、三人称の存在論を伴う実在(たとえば木やマッシュルーム)と一人称の存在論を伴う実在(たとえば痛みや色の経験)をともに含 んでいると認めていただきたい。一人称的な実在はすべてその三人称的な因果的基盤への因果的に還元できる。しかし、そこには非対称がある」[サール 2006:162]。
「(君は)意識を消去的に還元することはできない。なぜなら、意識は実際に存在するからだ。また、その現実の存在は通常の認識論的な疑いを免れる。なぜな ら、そうした疑いは見かけの現象と実在の区別に依存するからだ。そして、自分の意識状態がまさに存在するために、そうした区別をおこなうことはできない。 意識を神経的な基盤へと因果的に還元することはできる。だが、その還元は存在論的な還元を導くものではない。なぜなら、意識は一人称的な存在論を備えてお り、もし意識を三人称の用語で定義しなおせば、意識という概念をもつことの意義を失うことになるからだ」[サール 2006:164][SEARLE 2004:85-86]。
これについて、サイエンスフィクションがとる観点主義の角度から意識の問題を検討してみよう(サイバーパンクにおいて倫理は可能か?)
……
(SFの観点主義の説明)
……
ウォシャウスキー兄弟の監督になるいわゆる「マトリクス三部作」すなわち"The Matrix"(1998), "The Matrix Reloaded"(2003), "The Matrix Revolutions"(2003) は非常に奇妙な映画である。にもかかわらず多くのSF映画ファンを魅了してきており、金字塔と評する熱心なカルトファンも多い。その魅力はそれまでのSF 映画が自己主張していたエージェントやギミックの魅力よりも「現実」と「仮想現実」を対等に並置し、主人公がその往還をおこない自己探求するというダイナ ミズムにあるように思われる。人類学者にとって民話・神話・インフォーマントの語りなどのいわゆる口頭伝承が、当該文化や社会の分析にとって重要な資料と なったり、当の社会の人びとが「考えるのに適している」ためにこのような口頭伝承をさまざまな行動を誘発させる原動力としていることをみても、マトリクス 三部作についてそれを題材として取り上げることは僅かばかりでも意味のあることだと思われる。本節ではその梗概(シノプシス)を述べてみよう。
会社員のプログラマーであるトーマス・アンダーソンは天才ハッカー(クラッカー)「ネオ」の異名をもつ別の顔をもっているが、後に恋仲になるトリニティ の導きによりモーフィアスと出会う。モーフィアスやトリニティたちのよると、アンダーソンが生活している世界はコンピュータネットワークによって作られた 仮想現実の世界であり、「本当の現実世界」は機械が人間を支配下におきネットワークに繋げているという。その中で最後の抵抗をする「生身の人間たち」はザ イオンという地下世界の片隅で、船(シップ)と呼ぶ船を駆使してネットワークコンピュータを攻撃する遊撃戦下にあった。しかし機械世界はセンチネルという 蛸のようなロボットをザイオンに派兵して最後の殲滅戦を仕掛けていた。
ネオはトリニティらと共にモーフィアスの指揮のもとにある人間の遊撃隊に加わり、その抵抗運動に加わる。シップに乗り込み遊撃隊員たちは身体 の部分に埋め込まれたジャックに接続されてマトリクスの仮想現実の世界に潜り込む。そこではエージェント・スミスというプログラムが潜りこんだ人間のプロ グラムとマトリクス内で作動しているプログラムを恭順させ、反抗的なものに対しては同化するという支配を敢行していた。このような世界観と2つの世界の間 の移動について当初理解できなかったネオであるが、モーフィアスたちはネオが「救世主」であることを予感し、ネオを仮想世界に共に「連れ戻そう」とする。 逡巡しながらもネオは彼らとともにマトリクスの世界に「戻る」。
他方、マトリクスの世界はただひとつのコンピュータプログラムが一元的に支配する世界ではなく、さまざまな「人間=エージェント=プログラム」が住まう 世界でもある。そのマトリクス世界の中には、反抗勢力である「人間=エージェント=プログラム」が存在する。その中の中心的な存在であるオラクルは、マト リクス世界では普通のおばさんであるが、個々人の占いのみならず世界の未来の趨勢の予知能力をもつ。彼女はネオたちに、マトリクスの仮想現実の世界は機械 =コンピュータが作りかつ支配する世界だけではなく、より広大な精神世界の一部であることを告げる。そこで、ネオはモーフィアスが言う単なる予言者なので はなく、予めプログラムされ救世主になることを予定された「存在」であることを、オラクルの予言などから明らかにされる。
そこでは、またザイオンもマトリクス世界と敵対するだけの抵抗拠点=社会=コミュニティという実体ではなく、マトリクス世界を破局から救うた めに「アーキテクト」によって作られた存在であるというのだ。オラクルの予言によると、ネオもザイオンもアーキテクトによって予定されたプログラムだとい うのである。そこでネオは「現実世界」の親しい人たち(=ザイオンの住人)を武力闘争を通して共に闘うか、人類一般を救うためにマトリクス世界の改変にコ ミットするかの選択を迫られる。しかし「現実世界」では、無数のセンチネルがザイオンに向かいつつあった。
三部作目の"The Matrix Revolutions"(2003)のスートリーは複雑なので、ここでは私の議論に必要な内容の概要だけを要約する。ネオはネットに潜ったままだった が、その場所はマトリクス(ソフトウェアが走っている世界)とソース(メインフレーム)の境界上のであるモービル・アヴェーニューという地下鉄の駅にい る。そこでインド人風の夫婦と小さな女の子サティーに出会う。この境界世界はメロビンジアンとその従者トレインマンに支配されている。モーフィアス、トリ ニティらはネオを救済するために駅に侵入するがトレインマンに阻まれる。メロビンジアンはネオを幽閉しているが、モーフィアスらはネオの解放を要求する が、メロビンジアンは「予言者の眼」をかわりに要求する。他方、ネオは予知能力を獲得しつつあり、未来の幻影を観ることができるようになっていた。予言者 はネオに、そのような力の関係や複数のスタンドアローンになりより力をましたスミス(元のエージェント・スミス)について説明をした。
ネオがいなくなったところに闖入したスミスは、予言者と(プログラム的に)同化し予言者の能力もまた獲得するようになった。他方、現実世界に もどったネオはさまざまな交渉を経て、自分の予知能力に従って船に乗り込み「マシーン・シティ」にトリニティとともにのりこんでゆく。しかし船内にはすで にスミスに同化されていた乗組員ベインが潜んでおり、ベインはトリニティを人質にし、最終的にネオの眼を焼き彼は盲目になる。しかしながらさまざまな能力 をつけたネオは最終的にトリニティを解放し、ベイン(=スミスの代理・分身)を打倒することに成功する。彼らはマシーン・シティに向かう。
途中トリニティの死を経験するもようやくマシーン・シティに到着したネオはマトリクスの中枢にあるデウス・エクス・マシーナ——このジョーク としか思えない「存在の名前」は興ざめするめに当然のことながら映画のなかでは明示されない——と対話する。その中でネオはデウスと交渉し、スタンドア ローンになりマトリクスの意思とは関係なしに行動しはじめたスミスを打倒することを条件にデウスは機械と人間のあいだの和平すなわちザイオンへの侵攻を中 止する約束をとりつける。
しかしながら仮想世界と現実を往還する能力をもつようになり強力にパワーアップしたスミスの前にネオは倒されてしまう。驚喜するスミスであっ たがオラクルを同化した時に手に入れた予言者の眼で目の前に繰り広げられていることは、スミス自らがネオに対してオラクルの予言の言葉を掛ける「始まるあ るものには終焉あり、ネオ」と。その時にスミスはすべてがオラクルの罠であったあることに気づきつつ消滅(デバッグされて)してしまう。
仮想現実の世界にシーンが転回し[人格化された]アーキテクトと予言者が登場する。予言者はアーキテクトと対話し、マトリクスから人間が解放 されたことを宣言する。なぜならマトリクスはこの段階でヴァージョンアップを遂げることができ、人間だけが「唯一のエネルギー」ではないことが明らかにさ れる。サティとセラフ(「翼のない天使」)が予言者オラクルのもとに歩み寄る。そしてマトリクスは新しい夜明けを迎える。
アマゾン先住民のパースペクティヴィズムにおける多自然主義とは、複数の動物種からなる世界がそれぞれ独自の価値観をもって存在するというこ とであった。この発想を先に紹介した映画『マトリクス』に適用してみるとどうなるであろうか。
アマゾン先住民の世界は、人間が動物を眺めてそれを狩猟してたんぱく質資源として利用しているように、動物(例:ジャガー)もまた人間を対象 化する時に対称化した世界の住民であり、人間を食べたり相互作用をもつ独自の存在である。
他方、マトリクスの世界では、人間の対応物はネットワークに住まうコンピュータソフトウェアでありそれらは人格化されている。またコンピュー タソフトウェアはソースを媒介とするメインフレームコンピュータを必要とするために、ちょうど人間とコンピュータが接続するために脳=機械インターフェイ ス(Brain-Machine Interface, BMI)を媒介としてようやくシームレスな存在になるように、コンピュータもまたソフトマシーン(プログラム)とハードマシン(メインフレーム)は結びつ いている。
マトリクスが映像の消費者に見せる世界構造は多少複雑であり、そのことを理解するためには、人間が現実(ほんもの)だと思っている仮想現実 と、本当の真の現実がある。ちょうどティム・インゴルド(Ingold 1991,1996)が自然を「真の自然」と「文化的に構成された自然」と区分したように「世界の有り様」を2つに区分することが重要で、パースペクティ ヴィズムの観点から「現実の真の世界」の相対化の手続きが必要になる。
すなわち人間はマトリクスがつくった仮想現実の中で作動させられているコンピュータプログラムに他ならず、マトリクス世界では、エージェント という本物のプログラムが存在し、それらはまさに人間の姿の衣装を着ている存在に過ぎない。これが人間がほんものだとおもっている仮想世界すなわち「マト リクスによって構成された世界」がある。「ネオ」すなわちサラリーマンのアンダーソンは本物だと思っていた世界のなかでのアンダーグラウンドのハッキング の天才との呼ばれていたところに、「真の人間が住む世界」からやってきたモーフィアスやトリニティとの遭遇により「真の人間が住む世界」に引き戻される。 「真の人間が住む世界」では人間は機械=コンピュータプログラムによってネットワーク化されているので、身体のなかにさまざまな情報コンセントをもつこと で可視化されている。しかしながら「真の人間が住む世界」とは、マトリクスの支配から逃れ、ザイオンという地下世界に残された最後の抵抗拠点から、覚醒し た遊撃戦の戦士をジャックインすることで、マトリクス内に進入し、敵の背後から攪乱戦を挑んでいるのが現状なのである。
モーフィアスはマトリクス世界のアンダーソン(ネオ)は救世主であることを信じ、彼を「真の人間が住む世界」に引き戻し、マトリクス世界での 最終的な戦闘行為に付かせようとし、またネオ自身もそのことへの自覚をしてゆく物語である。
しかしこのような描写はマトリクスの2つの世界現実(worlds realities)からみると人間中心主義の見方にすぎない。もちろんマトリクス側(あるいはそこで世界を動かすエージェントたち)からみれば、現実に 覚醒して不要な遊撃戦を挑む「正規のマトリクスネットワーク」に接続されていないスタンドアローンの人間の遊撃戦兵士ならびにザイオンの人間はゆゆしき問 題であり、それゆえにマトリクス世界はセンチネルと削岩マシーンをザイオン世界に送りこんでスタンドアローンの人間の殲滅戦を挑む。つまり両者の間には戦 争状態が存在する。
覚醒した人間たちからみればマトリクス世界のコンピュータプログラムは人間の存在を脅かす存在であるが、逆の立場からみると、覚醒した人間た ちはマトリクス世界の安寧を脅かす存在すなわち反逆するパラサイトあるいはコンピュータウィルスのような存在である。それらがマトリクス世界では一見人畜 無害にみえる予言者オラクルらの助言にもとづいて不穏な動きをする。つまり、マトリクスという機械=プログラムの世界からみれば、抵抗する人間はマトリク ス世界の秩序を乱すだけではなく、その秩序そのものを転覆しようとする危険な存在なのである。
マトリクス世界からみるとその防御プログラム——生体であるなら免疫のような存在——であるエージェント・スミスは、ネオやモーフィアスを追 求するのみならず「マトリクス世界の秘密」を知る予言者オラクルなどを捜索取り調べをするうちに、システムの中で防御プログラムを適正に作動する存在から 次第にオートマトン的な暴走をしはじめる。
マトリクスの映画自体は、暴走したスミスをネオが最終的に破壊することで、最終的に機械が人間を必要としなくなり、すなわちザイオンの人間を 殲滅する必要がなくなり、マトリクスそのものがヴァージョンアップを遂げることで、急展開をとげて——文字通りデウス・エクス・マシーナの登場により—— 物語は終焉してしまう。つまりマトリクスの基本的モチーフである人間と機械(コンピュータプログラム)が相互にいがみ合い共存できず、お互いの片方が消滅 するまで闘う一種のマニ教的世界観に支えれていたので、その必要がなくなる時、和平が到来するという唐突な終わり方をする。
パースペクティヴィズムからみたマトリクスが私たちに与える第1の世界観は、人間にとって機械(コンピュータプログラム)はそれが融合する時 に機械は人間にとっての飼い慣らされ人間に有益性をもたらすものでなければならないというものである。他方、コンピュータプログラムはからみる第2の世界 観では、人間がマトリクスのシステムを維持永続させるために奉仕をつづける限り人間は機械にとって良い存在であるが、人間が自律性をもち人間中心主義を主 張するとそれはシステム全体にとっては脅威になることを意味する。つまり後者の世界観では、マトリクスの存在を自覚し、またシステム全体の根本的変革を野 望する者——「人間の救世主」と呼ばれる——ものは、システムにとって病気あるいはシステムに巣くい、かつシステムを利用しシステム全体を崩壊に至らしめ るウイルスにほかならない。
このように考えることはヴィヴェイロ・デ・カストロのパースペクティヴィズムに対する紋切り型の反論にあるように、それはただ単に認識論の相 違——つまりこちら側とあちら側からみれば善悪の基準が逆転している——のみを示唆し、存在論的な批判を持ち得ていないようにも覚える。
しかし、先に述べたように第1の存在論と第2の存在論は根本的に対立をなし、それぞれ人間と機械のエージェントが相互に浸透し、マニ教的世界 観のもとで両者は殲滅するまで侵入と攻撃を繰り返すための「生存競争(struggle for existance)」が永続するという点では、まさに生と死をかけた存在をめぐる闘いが繰り広げられており、認識の違いを理解するだけでは、和平などを 導くことは論理的に不可能な世界にほかならない。
マトリクス三部作の分析を通して私は、パースペクティヴィズムの観点を取れば機械=人間システム(Machine-Man System)の宿主である機械(コンピュータプログラム)にとって人間がそのシステムそのものへの脅威となるウイルスになるという視座であり存在の様式 をとることになる可能性について気づいた。たしかに機械のシステムに比べれば、人間は誤りを犯しやすく、また意志という余計なもの、つまり機械からみれば 「無用のノイズ」をもつことになり、それが宿主にとってダメージをもたらさないものあればまだしも、システムの致命傷になるように「進化」すれば非常に厄 介である。このシステム(機械)がもつ恐怖心——思考実験であるが未来の機械は恐怖をももつように「進化している」かもしれない——は、今日の人間どもが 経験している豚インフルエンザウィルスH1N1が「現在のところ弱毒化」のままだが、DNA/RNA——このウイルスは一本鎖RNAなので逆転写酵素を用 いて宿主(動物)の中でDNAを複製し、かつ増殖するプロセスの中で変異して強毒化する「可能性」をもつ——が突然変異を及ぼして、高病原性鳥インフルエ ンザ(H5N1亜型ウイルスはそのひとつ)のような高い致死率をもたらすかもしれないという影響力のある疫学者およびウィルス学者の発言と政策決定により パニックのにより、「こちらの世界」ではすでに経験済みのことである。つまりアマゾンの先住民のみならず、西洋近代社会のなかにもパースペクティヴィズム が生起している可能性はあるということだ。
にもかかわらず、マトリクスにおいても、豚インフルエンザの社会的パニックにおいても、このマニ教的世界観が支配しているが、なぜ西洋近代社 会のなかのパースペクティヴィズムは、このような恐怖のシステム——タウシグの言葉を借用すれば"Nervous System"(神経系の意味だが「いらいらや不安を生起させるシステム」とも受け取れる)——しか見えてこないのだろうか? そしてそれ以外の可能性は ないのだろうか? これらのことを検討するためには人間と人間にとって「融合」したり「寄生」しているものについての洞察が必要である。
……
※パラサイト・イブとミトコンドリアの想像力
……
日本住血吸虫症:症状が多様であるとか感染が日和見的におこる。その理由は宿主からの免疫抑制が効くからである。また、それ以上に自分の虫卵数を制御し て栄養源としての宿主の造血亢進など積極的な働きかけをやるという「共存」戦略をとる、ことが明らかになっている。
「大阪大学の朝長啓造准教授と国立遺伝学研究所などは、ヒトのゲノム(全遺伝情報)の中に、約4千万年前に感染したとみられる「ボルナウイルス」の痕跡 があるのを突き止めた。人やチンパンジーなどの共通祖先に感染したウイルスの遺伝子が、ヒトのゲノムに入り込み現在まで保存されていた。人類とウイルスの 共存関係を探る手掛かりになりそうだ。成果は英科学誌ネイチャーに7日掲載される。/人間などの生物は感染したウイルスの遺伝子を自らのゲノムに取り込 み、ゲノムを多様にしてきた。こうした遺伝子は「ウイルス化石」と呼ばれ、ヒトゲノム全体の約8%を占めるといわれている。/研究チームは馬や牛などに脳 炎を起こし、人にも感染する「ボルナウイルス」に着目。ヒトゲノムを調べたところ、ウイルスにある「ヌクレオたんぱく質」を作る遺伝子のDNA(デオキシ リボ核酸)配列がヒトゲノムにもあり、この遺伝子を「EBLN」と名付けた」(www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100107AT1G0601V06012010.html)。
図の出典は:Cedric Feschotte. Bornavirus enters the genome. Nature
463(7):39-40. January 2010
"A survey of mammalian genomes has unexpectedly unearthed DNA from
bornaviruses, leading to speculation about the role of these viruses
causing mutations with evolutionary and medical consequences".
注釈:ただしこのセクションが取り扱う生物における「宿主」とパラサイトとの共存に関する時間的尺度は一世代間(20年間)からSF的世界(サイボーグの
BMIからマトリクスができあがる50年〜100年間を想定すると)までの尺度に比べても10の6乗程度のスケールの違いがある。
『マトリクス』、サイボーグ的理性、寄生に関する生物学概念の存在論的考察などに関する「多自然主義」をめぐる存在論の間におけるインターフェイスの多
くは、競合や戦争の隠喩で表象されるようなテーマが多くみられる。しかしパースペクティヴィズムの可能性のなかには「多自然主義」の間のなかの共存や交渉
さらには対話という隠喩で検討しなければならないテーマが伏在していないだろうか。
このような検討を通して、デュルケーム=モースによるエスキモー社会が置かれた環境と社会形態——ひいては社会構成員が抱く観念形態——の考察に見られ
る古典的理論的布置を、ヴィヴェイロ・デ・カストロおよびディスコーラが開拓したパースペクティヴィズムと社会の存在論との関係を整理、照合させることに
より、後者の理論概念の批判継承してゆく。
……
(サイボーグ概論)
……
サイボーグ(cyborg)は、サイバネティック・オーガニズム(Cybernetic
Organism)の略で、人工臓器等の人工物を身体に埋め込む等、身体の機能を電子機器をはじめとした人工物に代替させることで、身体機能の補助や強化
を行った人間のこと(Wiki in
Japanese)。サイバネティックス(cybernetics)は、通信工学と制御工学を融合し、生理学、機械工学、システム工学を統一的に扱うこと
を意図して作られた学問。自動制御学(SF的に電脳工学と訳される場合もある)ともいう。その語源はギリシャ語で「(船の)舵を取る者」を意味するキベル
ネテスから来ている(by Wiki Japanese)。
補綴(ほてい・ほてつ):おぎなってつづりあわせること。不足を足すこと。 医学用語では「ほてつ」それ以外の分野では「ほてい」、補綴する(cosmetic)補綴(prosthesis)補綴の(prosthetic)補綴学 (prosthetics)補綴歯科医(prosth-odontics)などと使われる。
歯科学は補綴学が主要なもののひとつであるが、外科においてもProsthetics Mitral Valve Replacement(人工の僧帽弁置換術)などの用法がある。
W・ギブスン『ニューロマンサー』(1984)では補綴は重要な概念になる。[cyberpunk: A subgenre of science fiction typified by a bleak, high-tech setting in which a lawless subculture exists within an oppressive society dominated by computer technology. by OED]
英語では、a prosthesis is an artificial extension that replaces a missing body part(wiki/en).と説明される。だが期待される延長=エンハンスが意味するものが、構造なのか機能なのか、それともその両方なのかについて留 意することが、私のサイボーグ論では重要な概念になる。
足親指の切断による欠指者にとってサンダルを履くためには義足指と部分擬足は構造機能上重要な意味をもつ。
もし機能だけを追求していたらなぜ義足指には見事な——美学にも叶った——爪がついているのか?[永遠の美]
爪のついた義足指と部分擬足には、構造機能以上の美的機能あるいは両者の融合がある。
あるいは構造と機能を分ける近代的発想が誤謬で、補綴思考(prosthetic thinking)には両者の融合というユートピアがそもそも生まれた時から内包されている?[仮説]
失われた身体部分とその機能を取り戻すテクネー(作る知)の物象化としての補綴化実践がある。補綴物(=モノ)はすぐに身体と一体化する。あ るいは一体化しようとテクネーは人類によって進化させられる[例:免疫抑制剤と移植臓器の開発]。
機械と合体する身体のプログラムは人類の歴史と共にある。
サイボーグは人間の考える自然(フロネーシス)と文化(テクネー)の二分法思考を存在論的に解体する。
後期近代、ポストモダン、脱植民地化、近代の超克などの近代概念批判という議論における、共通の特徴として〈近代的なるもの〉の態勢の破綻・ 逆説・矛盾・異種混交などの指摘がある。
文明[概念]の終焉としての脱近代化を捉えるならば、構造と機能を峻別する主知主義的な分析理性(modernist analytic
reason)を批判し、モノ化した身体から照射するサイボーグ論も立派な脱近代化論の一部を構成する。
数々のサイボーグ論がポストモダン思想の特徴として取り上げられることが多いのも、このことから明白。
Homo-cyborg sapiens:人類の文明のレパートリーに多かれ少なかれ補綴概念(→脱自然化)が埋め込まれているとすると、我々の生後はサイボーグ化することが運命 づけられている[仮説]。
人間のサイボーグ化の批判の基本的基調は「自然な身体」であるが、それは近代が呪ってきた野蛮化(=非[西洋]人間化)の回帰であり前近代化 になる逆説をもつ。
のみならず、文化/自然の二分法(レヴィ=ストロース)における〈自然〉の概念は、文化によって修飾をうけた仮想的自然 (culturally constructed “virtual nature”)である。→「自然ー文化は文化以上でも文化以下でもない」(ラトゥール『虚構の「近代」』新評論,pp.20-21, 2008年)
サイボーグ理性(Cyborg Reason)とは、近代意識の中に住まう非サイボーグが、自らの身体の中のサイボーグ的属性に覚醒した時点以降に発見するさまざまな身体知の仕掛け(= 装置)のことである。言い換えると、意識をもつ装置そのものである。サイボーグ理性とは、サイボーグの心=マインドのことであると言ってもよい。
サイボーグ理性による批判とは、近代意識の中に住まう非サイボーグだと信じ込んでいる同胞に対し、自らの身体の中のサイボーグ的属性に覚醒自 覚することを促し、共にサイボーグとしての人類(Homo-Cyborg sapiens)同胞に目覚める社会運動のことである
この活動は、人類のサイボーグの心=マインドのことに対する自覚化とそれにともなう社会の再編運動を引き起こすだろう。
6. 結論
(未完)
bib.====================【文献】==========================
George Boas, 1973
レヴィ=ストロース、クロード『親族の基本構造』福井和美訳、青弓社、Pp.59-73, 2000年
リンク